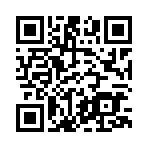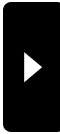2015年01月04日
小山街道コヤマカイドウ~(藤枝市~焼津市:旧大井川町)
著作権者:兵藤庄左衛門
~小山街道コヤマカイドウ~(藤枝市~焼津市:旧大井川町)
藤枝市の小山街道は、田沼街道の古形態とされる。確かに今の田沼街道の横を内陸側に寄って通じている。『定本 静岡県の街道』(郷土出版社)では藤枝市藤枝宿西入口瀬戸川西堤防で東海道から分かれ吉田町小山城下までの道である。古来は色尾越イロオゴエと云われた。中世頃に使われていたようだが開設時期は不明である。歴史に見えるのは戦国末期武田勝頼と徳川家康による田中城周辺の争奪に関して行き来されたことが分かっている。
田沼意次が相良城主になり、東海道藤枝宿から相良までの街道を整備した。これが通称「田沼街道」であるが、小山街道を整備して田沼街道になった部分と、田沼街道から外れた小山街道の部分もあった。それが藤枝市兵太夫新田以西である。
ちなみに大井川を渡った後、島田市中河に出て、吉田町小山城に向かうのだが、このルートが現在不明である。私見を述べると、おそらく中河は地名からみても、大井川の中州であるので、一刻も早く大井川の支流を含めて渡りきりたいだろうから、西岸の初倉の山麓に達したのではなかろうか。特に増水しているならなおさらである。ここから山麓の道をたどり、小山城に向かうのが水対策上は得策である。
この本文を読んでいくとき、ゼンリン等の住宅地図があると道筋が分かりやすいことを付け加えておく。筆者は古い住宅地図を古本屋で1冊千数百円で購入している。新品は1冊1~2万円しますから。或は図書館で見開きページの半分以下をコピーできます。田沼街道については「古街道を行く」等を参照してください。実地調査:’14 11月。
では道筋をたどるが、初めは田沼街道と同一であり、勝草橋周辺を含めて紹介する。
~旧東海道勝草橋周辺含む、瀬戸川東岸~
・出雲大社分院(藤枝市藤枝二丁目1番地)
・新:手洗石
・常夜灯、・石
・川除地蔵×2(藤枝市藤枝二丁目2番地 老人憩いの家)
・馬頭観音
・常夜灯、・石
~旧東海道勝草橋周辺含む、瀬戸川西岸~
・秋葉公園(藤枝市志太三丁目3番地)
・常夜灯
・地蔵、4~5基(志太三丁目13番地)瀬戸川土手沿い
・勝草橋、橋の袂に田沼街道由来版、他に勝草橋由来、
・田沼街道史蹟説明版:分岐点、(志太四丁目14番地)勝草橋西岸300m下る
ここから田沼街道分岐であり、小山街道でもある。
・周辺紹介
・龍王神社
・葦中観音堂
・塩取橋蹟(青木二丁目18番地)
・説明版:江戸時代田中藩では海岸方面から運ばれてくる塩に税金をかけ、青木地区周辺に住む元締めにその責務を負わせていた。そこに架かる橋の名が塩取橋といった。今は川筋も変わり橋もない。
*田中藩:藤枝市田中に田中城跡があり、現在は西益津小学校と中学校になっているが、一部家屋が再現されている。
・田沼街道説明版(青木二丁目1番地)
小山街道についても記載されている。この辺りは小山街道がそのまま田沼街道になった辺りで、どちらも同一路だ。
~ここで県道33号線:主要地方道藤枝大井川線:藤相田沼街道に合流する~
これが現在の田沼街道である。JR東海道本線のガード下道をくぐり、古道はまたしばらくすると分岐していくが、田沼街道は東側(左)、小山街道は反対の西側(右)である。
・稲荷:祠、・石製家型道祖神(田沼四丁目5番地)
この辺りで現在の県道:田沼街道から離れ1本西側の裏道に入っていく。
・馬頭観音 昭和十二年 大石次郎宅入口前(田沼四丁目7番地)
この辺りで馬頭観音に出くわし、古道の雰囲気を感じられる始まりである。
~新幹線ガードをくぐり150m南下する~
・八幡月夜見神社より北側 (田沼1丁目12~3丁目16~4丁目4~)
JR東海道本線南側手前で旧道の名残のような道筋の道は新たな都市計画区画整理で消失したようだ。ここから現在、田沼街道と呼ばれる県道の西側に沿って南下していく。ルートは田沼1丁目12~3丁目16~4丁目4~5丁目11~新幹線ガード下~高洲7である。
小山街道は八幡月夜見神社の横の道とされていて、ちょうどそこに出る。
・八幡月夜見神社(藤枝市高洲9)
・石鳥居:昭和三十八年、
・手洗石:文化十五
・常夜灯×2:明治四十四年
・御神前燈籠:安?
・表忠碑
・石:家:道祖神
・大嘗祭記念:平成二年
・小山街道碑:平成十年:説明
神社東側道を南下。高洲南幼稚園と高洲南小学校の間の道を南下。藤枝市上水道泉町配水場の東側を南下。栃山川土手に出て橋がないので迂回するが、川向うに道はない。大洲中学校東側の道が街道の系譜を引く道と推定する。弥左衛門と大東町の境の道である。基本的に古い街道は境界線になることが多い。焼津市(旧大井川町)に入ると、また道が消失する。少し南にある西進する道を通って大井川土手に到達して一旦終わり。
ただその道より北側の道を通って大井川土手に至る道の方が神社や寺がある。
栃山川に出ると橋がないので、200m下流の代官島橋を渡る。
・地蔵:明治四十四年(大洲四丁目2番地)代官島橋袂
大イチョウもある。隣は公園。
~公園横を100m上流へ道を進み左折し南下する。大洲中学校南の弥左衛門と大東町境の道を進む。~
・伝栄寺(大洲5丁目5番地13)
道が1~2本北にずれた位置だが周辺紹介する。おそらく伝栄寺や次項目の八幡宮前を通る道は藤枝市前島や青木方向へ進む道の古道
と思われる。
・六地蔵+1、・祠:・観音3:札所等拾五番、・地蔵4、・石燈籠4、・新:地蔵:ニコニコ、・地蔵:享保十九、・新:五重塔、・石:家:道祖神、・新:竣工記念碑2、・手洗石:穴がひょうたん型、・新:良徳観音、
・庚申塔 宝暦十(大洲五丁目15番地)
県道島田大井川線沿いにある。昔次項目の八幡宮から伝栄寺に向かう道沿いにあったようだ。
・八幡宮(焼津市上泉1403)
・説明版:14世紀中葉、川除の神として祀られた。
・石鳥居:昭和十五年、・石碑2:昭和四年:~工事、昭和十八年:□□八幡宮、・常夜灯2:昭和十五年、・コンクリ鳥居2、・石鳥居:慶應元年、・常夜灯2:昭和、・石柵:大正十五年、・狛犬2:昭和十六年、・鬼瓦、・手洗石2、明治(?三)年、天(?保)四、・祠:神6~7合祀、・手洗石:平成十三年、
・蓮性寺(上泉1199)
・近代:南無法蓮華経(?参)界萬霊、・墓石,観音,地蔵を合祀の中に「馬頭観音:昭和十三年 相草号」等が見つかる。
・板碑:老農山下幸五郎君碑銘、・石碑:父母~~昭和二十九年
寺前の通りの向こうにある。
・馬頭観音:昭和三十年代
2003年3月、大洲中学から蓮性寺辺りにかけての道沿いに昭和三十年代の高さ20~30㎝の小ぶりな馬頭観音があったが、2014年11月には見当たらなかった。
多分、'03には存在しなかった新しい道路:(東名吉田ICから直接大井川を渡り旧大井川町側の県道島田大井川線に出られる新道)が小山街道より道路1本南に作られたため、事前に移転したのではなかろうか。
ここより大井川土手近くは大規模工場等になり昔の道など存在しないし、土手沿いを見ても石仏等も見当たらない。
大井川向うの吉田町側の道は不明。
・吉田町
・小山城(吉田町片岡):(展望台として近世の天守閣:犬山城を模したといわれる)がある。戦国末期に武田・徳川両軍により激しい奪い合いが行われたことで知られる。中世山城で砦はあったろうが、近世の天守閣はまったくありえない。しかし付近の三日月堀等が残存していて中世末期の歴史資料として重要である。悲劇の城としての言い伝えもある。天守閣に歴史価値はないが、内部は吉田町資料館として一見の価値がある。
・能満寺(片岡)
・遠州七不思議に数えられる「大蘇鉄オオソテツ」が有名、吉田町きっての名刹。ちょうど小山城の麓にある。
・参考資料
「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ’90、¥16000→¥3500
「’93藤枝市 ゼンリン住宅地図」¥11500→¥1200
「’94大井川町 ゼンリン住宅地図」¥8000→¥900
「古街道を行く」鈴木茂伸、静岡新聞社、
~小山街道コヤマカイドウ~(藤枝市~焼津市:旧大井川町)
藤枝市の小山街道は、田沼街道の古形態とされる。確かに今の田沼街道の横を内陸側に寄って通じている。『定本 静岡県の街道』(郷土出版社)では藤枝市藤枝宿西入口瀬戸川西堤防で東海道から分かれ吉田町小山城下までの道である。古来は色尾越イロオゴエと云われた。中世頃に使われていたようだが開設時期は不明である。歴史に見えるのは戦国末期武田勝頼と徳川家康による田中城周辺の争奪に関して行き来されたことが分かっている。
田沼意次が相良城主になり、東海道藤枝宿から相良までの街道を整備した。これが通称「田沼街道」であるが、小山街道を整備して田沼街道になった部分と、田沼街道から外れた小山街道の部分もあった。それが藤枝市兵太夫新田以西である。
ちなみに大井川を渡った後、島田市中河に出て、吉田町小山城に向かうのだが、このルートが現在不明である。私見を述べると、おそらく中河は地名からみても、大井川の中州であるので、一刻も早く大井川の支流を含めて渡りきりたいだろうから、西岸の初倉の山麓に達したのではなかろうか。特に増水しているならなおさらである。ここから山麓の道をたどり、小山城に向かうのが水対策上は得策である。
この本文を読んでいくとき、ゼンリン等の住宅地図があると道筋が分かりやすいことを付け加えておく。筆者は古い住宅地図を古本屋で1冊千数百円で購入している。新品は1冊1~2万円しますから。或は図書館で見開きページの半分以下をコピーできます。田沼街道については「古街道を行く」等を参照してください。実地調査:’14 11月。
では道筋をたどるが、初めは田沼街道と同一であり、勝草橋周辺を含めて紹介する。
~旧東海道勝草橋周辺含む、瀬戸川東岸~
・出雲大社分院(藤枝市藤枝二丁目1番地)
・新:手洗石
・常夜灯、・石
・川除地蔵×2(藤枝市藤枝二丁目2番地 老人憩いの家)
・馬頭観音
・常夜灯、・石
~旧東海道勝草橋周辺含む、瀬戸川西岸~
・秋葉公園(藤枝市志太三丁目3番地)
・常夜灯
・地蔵、4~5基(志太三丁目13番地)瀬戸川土手沿い
・勝草橋、橋の袂に田沼街道由来版、他に勝草橋由来、
・田沼街道史蹟説明版:分岐点、(志太四丁目14番地)勝草橋西岸300m下る
ここから田沼街道分岐であり、小山街道でもある。
・周辺紹介
・龍王神社
・葦中観音堂
・塩取橋蹟(青木二丁目18番地)
・説明版:江戸時代田中藩では海岸方面から運ばれてくる塩に税金をかけ、青木地区周辺に住む元締めにその責務を負わせていた。そこに架かる橋の名が塩取橋といった。今は川筋も変わり橋もない。
*田中藩:藤枝市田中に田中城跡があり、現在は西益津小学校と中学校になっているが、一部家屋が再現されている。
・田沼街道説明版(青木二丁目1番地)
小山街道についても記載されている。この辺りは小山街道がそのまま田沼街道になった辺りで、どちらも同一路だ。
~ここで県道33号線:主要地方道藤枝大井川線:藤相田沼街道に合流する~
これが現在の田沼街道である。JR東海道本線のガード下道をくぐり、古道はまたしばらくすると分岐していくが、田沼街道は東側(左)、小山街道は反対の西側(右)である。
・稲荷:祠、・石製家型道祖神(田沼四丁目5番地)
この辺りで現在の県道:田沼街道から離れ1本西側の裏道に入っていく。
・馬頭観音 昭和十二年 大石次郎宅入口前(田沼四丁目7番地)
この辺りで馬頭観音に出くわし、古道の雰囲気を感じられる始まりである。
~新幹線ガードをくぐり150m南下する~
・八幡月夜見神社より北側 (田沼1丁目12~3丁目16~4丁目4~)
JR東海道本線南側手前で旧道の名残のような道筋の道は新たな都市計画区画整理で消失したようだ。ここから現在、田沼街道と呼ばれる県道の西側に沿って南下していく。ルートは田沼1丁目12~3丁目16~4丁目4~5丁目11~新幹線ガード下~高洲7である。
小山街道は八幡月夜見神社の横の道とされていて、ちょうどそこに出る。
・八幡月夜見神社(藤枝市高洲9)
・石鳥居:昭和三十八年、
・手洗石:文化十五
・常夜灯×2:明治四十四年
・御神前燈籠:安?
・表忠碑
・石:家:道祖神
・大嘗祭記念:平成二年
・小山街道碑:平成十年:説明
神社東側道を南下。高洲南幼稚園と高洲南小学校の間の道を南下。藤枝市上水道泉町配水場の東側を南下。栃山川土手に出て橋がないので迂回するが、川向うに道はない。大洲中学校東側の道が街道の系譜を引く道と推定する。弥左衛門と大東町の境の道である。基本的に古い街道は境界線になることが多い。焼津市(旧大井川町)に入ると、また道が消失する。少し南にある西進する道を通って大井川土手に到達して一旦終わり。
ただその道より北側の道を通って大井川土手に至る道の方が神社や寺がある。
栃山川に出ると橋がないので、200m下流の代官島橋を渡る。
・地蔵:明治四十四年(大洲四丁目2番地)代官島橋袂
大イチョウもある。隣は公園。
~公園横を100m上流へ道を進み左折し南下する。大洲中学校南の弥左衛門と大東町境の道を進む。~
・伝栄寺(大洲5丁目5番地13)
道が1~2本北にずれた位置だが周辺紹介する。おそらく伝栄寺や次項目の八幡宮前を通る道は藤枝市前島や青木方向へ進む道の古道
と思われる。
・六地蔵+1、・祠:・観音3:札所等拾五番、・地蔵4、・石燈籠4、・新:地蔵:ニコニコ、・地蔵:享保十九、・新:五重塔、・石:家:道祖神、・新:竣工記念碑2、・手洗石:穴がひょうたん型、・新:良徳観音、
・庚申塔 宝暦十(大洲五丁目15番地)
県道島田大井川線沿いにある。昔次項目の八幡宮から伝栄寺に向かう道沿いにあったようだ。
・八幡宮(焼津市上泉1403)
・説明版:14世紀中葉、川除の神として祀られた。
・石鳥居:昭和十五年、・石碑2:昭和四年:~工事、昭和十八年:□□八幡宮、・常夜灯2:昭和十五年、・コンクリ鳥居2、・石鳥居:慶應元年、・常夜灯2:昭和、・石柵:大正十五年、・狛犬2:昭和十六年、・鬼瓦、・手洗石2、明治(?三)年、天(?保)四、・祠:神6~7合祀、・手洗石:平成十三年、
・蓮性寺(上泉1199)
・近代:南無法蓮華経(?参)界萬霊、・墓石,観音,地蔵を合祀の中に「馬頭観音:昭和十三年 相草号」等が見つかる。
・板碑:老農山下幸五郎君碑銘、・石碑:父母~~昭和二十九年
寺前の通りの向こうにある。
・馬頭観音:昭和三十年代
2003年3月、大洲中学から蓮性寺辺りにかけての道沿いに昭和三十年代の高さ20~30㎝の小ぶりな馬頭観音があったが、2014年11月には見当たらなかった。
多分、'03には存在しなかった新しい道路:(東名吉田ICから直接大井川を渡り旧大井川町側の県道島田大井川線に出られる新道)が小山街道より道路1本南に作られたため、事前に移転したのではなかろうか。
ここより大井川土手近くは大規模工場等になり昔の道など存在しないし、土手沿いを見ても石仏等も見当たらない。
大井川向うの吉田町側の道は不明。
・吉田町
・小山城(吉田町片岡):(展望台として近世の天守閣:犬山城を模したといわれる)がある。戦国末期に武田・徳川両軍により激しい奪い合いが行われたことで知られる。中世山城で砦はあったろうが、近世の天守閣はまったくありえない。しかし付近の三日月堀等が残存していて中世末期の歴史資料として重要である。悲劇の城としての言い伝えもある。天守閣に歴史価値はないが、内部は吉田町資料館として一見の価値がある。
・能満寺(片岡)
・遠州七不思議に数えられる「大蘇鉄オオソテツ」が有名、吉田町きっての名刹。ちょうど小山城の麓にある。
・参考資料
「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ’90、¥16000→¥3500
「’93藤枝市 ゼンリン住宅地図」¥11500→¥1200
「’94大井川町 ゼンリン住宅地図」¥8000→¥900
「古街道を行く」鈴木茂伸、静岡新聞社、
2014年11月04日
安倍街道
○安倍街道
2014、3/2(日)、安倍街道についてあまりに部分的過ぎて、将来少しずつでも書き足していこうと思っておりました。今回少しは調べられたので内容をリニューアルします。まだ未調査はありますので、今後ものんびりではありますが、改定していくつもりです。少しほっとしました。
3/15に井川に行けたので井川部分も改訂します。3/21 調査:13年11~12月、14年2~3月を含む版
さらに14年10~11月調査、改定’14 11/3
・総説
一般的には静岡市中を安倍川沿いに遡り油島で安倍川支流の中河内川に沿い遡り、口坂本温泉を経由して大日峠を越えて井川に達する街道を本道とする。支線としては、先の油島でそのまま安倍川本流を遡り梅ヶ島温泉や安倍峠を越える梅ヶ島街道がある。また先の本道でも、玉川から口坂本側へ行かず、西河内川に沿い遡り大沢から笠張峠を越えて井川や大間に行く西河内川ルートもある。それらの本道や支線からさらに周辺へ分岐する峠道等は数多い。
一旦は2000年頃から12年まで少しずつ調べてはきたがあまりに部分的であった。そこで今回13年11~12月、14年2月
にかけ未調査だった主だったところだけでも一通り調査を試みた。すべてのルート及びその周辺地域の道路沿いとなると膨大すぎて手におえないのですべてのルートと遺物を調査紹介はできないが、調べられた範囲内でも発表し、今後の方たちへの調査研究への一助、および文化財や観光資源の発見につながれば幸いである。また間違いは多かろうが、今後ご指摘をお願いしたい。古街道研究が進むことを望む。
・用語説明
・国、県、市=国、県、市指定、・有、無=有形、無形、・登=登録、・文=文化財、・天=天然記念物、・重=重要、・民=民俗、・石=石製、・家=家型、・新=近代から現代にかけて作られた新しいものと推定されるもの、・古=新しくなく古そうなもの、・欠:破損欠落しているもの、・馬頭=馬頭観世音菩薩、・コンクリ=コンクリート製、(2)=2基、
・古い用語説明
廿=20、廿の縦線3本=30、等=塔、歳‣天‣月日=年、
美良または羊良=養(美や羊ではなく羊の下は大であり美ではなく横線3本である。狼という字に似ているが、その字がパソコンで出てこない。そういった字は多く他の現代的な字に切り替えたり注を施す)、クイズ:ちなみに養がなぜ美(横線3本)や羊(下は大)と良なのかはちょっと考えるとすぐ分かります。このように漢字の部分を上下左右に組み替えることは石塔への刻字ではよくあります。彫る時の字のバランスを考慮した石工さんたちの工夫です。ちなみにある石工さんはこういう字をお寺さんの字と言っていましたが寺院で使う字ではありません。この前見た字では政を上に正、下に政の正抜きの字を彫ったものを見ました。
*「石仏事典」類を参照してください。年号や干支もこれで分かります。
・住所について
なお住所は正確に分からないものは多く、隣や付近の住居の番地号を用いているものが多い。
○本街道:静岡市中~井川
安倍街道の一般的な出発点と思われていたのは井宮神社と薩摩土手のある所かららしい。しかし現代の安倍街道「県道井川湖御幸線」は国道1号線静岡駅前からであり、旧東海道からの分岐点は呉服町の札の辻からとなる。そこで今回はその付近の周辺遺物も含むこととした。
明治20年代の陸地測量部地図で確認すると、札の辻から北上し本通りで右折して、外堀からの通りと合流し安倍街道へつながっているので、外堀通り「県道井川湖御幸線」が安倍街道への直進路といえるのか。
~これより下 静岡市市街地内、静岡駅北西部を参照せよ~
*移動:
~~これより上、静岡市市街地内、静岡駅北西部を参照せよ
・賤機稲荷神社(宮ヶ崎町)
かつては忠正酒造裏と紹介できたが解体されたので、自動車販売店裏の山際にある。隣は片羽町公民館である。
・神社名石碑:新:賎機稲荷神社、・木鳥居:昭和六十年、・手洗石:奉納 片羽町婦人會
・忠正酒造(材木町6)
かつて存在した造り酒屋、今は跡形もない。忠正酒造ビルと昔ながらの建物を解体してしまった。
・泰雲山瑞龍寺(井宮町48)
・説明版:宗派:曹洞宗、寺系:静岡市葵区沓谷長源院末、開創:永禄3(1560)年室町戦国時代、本尊:聖観世音菩薩、開山:能屋梵藝大和尚のうおくぼんげい、開基:旭姫(徳川家康公夫人、豊臣秀吉公異父妹)、本山:大本山永平寺(福井県吉田郡永平寺町)、大本山総持寺(神奈川県横浜市鶴見区)、由来:永禄三年長源院第四世梵梅ぼんばい和尚の法嗣:能屋梵藝和尚が開山して旧寺址を広めた。当時は浅間山の西麓に位置し駿河七ヶ寺の一つであった。家康公は駿府在城の折度々住職を招集し曹洞の法門を聴聞された、当寺も七ヶ寺の一つとして家康公と深い縁に結ばれていた。天正十八(1590)年、旭姫没するや当寺に墓を建て、その時の法名「瑞龍院殿光室総旭大禅定尼」から当寺の名前が瑞龍寺となりました。この為豊臣家、徳川家両家より寺領を寄進せられた。戦災等で寺を消失し、のち昭和26年再建する。寺所有の重宝品:旭姫の小袖、秀吉公の朱印状、蝶足膳(桐紋蒔絵膳)、境内設置:旭姫の墓、切支丹灯篭、芭蕉の時雨塚、
開基は旭姫(豊臣秀吉妹で離婚させられ家康妻として嫁す)。
・観光案内版:しぐれ塚(芭蕉の句碑)
・キリシタン灯籠:竿石に舟形の囲みがあり、その中に浮き彫りされている。「1605年頃駿府城にフランシスコ会、イエズス会があって、城内、安倍川の2か所に南蛮寺があったといわれている。」
個人的には切支丹というより神仏関係と思われる。おそらく今後切支丹灯籠のいくつかは否定されると思われる。
’13年12月再見、案内表示の矢印や説明がなく、灯篭も各部がずれたまま中途半端に設置され一部損壊していて悲しくなった。私が否定したためだろうか。私見では否定したいが、だからといって灯篭をぞんざいに扱われることは悲しい。大切に保存し、説明版もつけ最後に一言否定説もあるとしてくれたらそれでよい。否定説も断定できないし、肯定説も断定できない。ただ今後否定説が有力になるだろうとは思います。
*私見の「キリシタン灯篭疑問説と保存活用」についてはブログ内の別項目を御参照ください。文章が長引くのでここでは簡単に済ませました。
・しぐれ塚:松尾芭蕉の句碑。安東村長安寺が廃寺になったので明治十二年頃材木町の大村青渓氏が移したもの。石の右側に「芭蕉桃青居士ばしょうとうせいこじ」、左側に芭蕉の命日「元禄七年十月十二日」が刻まれていた。「きょうばかり人も年よれ初しぐれ」から時雨塚という。
・旭姫の墓:朝日姫とも書く。正式な墓所は大阪。こちらは家康が建てた墓。「豊臣秀吉の妹で徳川家康の正室であった。家康と駿府城に住んでいたが、京都に行き48歳で亡くなった。家康が東福寺から分骨してここに墓を作った。戒名:瑞龍寺殿」
・説明版:豊臣秀吉公の異父妹で尾張の地士佐治日向守の妻、秀吉が小牧長久手の戦後家康と同盟関係を築くため妹を日向守と離別させ天正14(1586)年5月浜松城の家康の所へ嫁がせた。天正16年自分の母、大政所病気見舞いに上洛しそのまま天正18年1月自身も病気で没した。48歳。秀吉は京都東福寺に埋葬し「南明院殿光室総旭大姉」と諡(おくりな)し悲運な妹への供養を行った。家康と供に在った僅か2年、上洛後2年で病没し加えて前夫日向守は秀吉の仕打ちを憤り切腹し果てる誠に薄幸の身の上である。
一方家康は旭姫がしばし詣でていた当寺に墓を設け「瑞龍院殿光室総旭大禅定尼」と諡し祀った。
・新:燈籠(2)、・新:穏々の苑、・一石一字経寺塔、
・発掘された墓石:慶長十九甲寅~空風火水地本学~~~、・発掘された墓石:慶長十一丙午空風火水地笠岩~~~、
説明版:この2本の石塔は昭和57年9月12日台風で墓地の一部が崩れ落ちてしまいました。その場所から掘り出されたものです。どなたのものか分かりませんが、今から約327年前に亡くなられた方と思われます。
・句碑:?、・板碑:宗季山本翁碑、・新:六地蔵、・新:南無釈迦牟尼仏、・新:水子地蔵尊、
・安倍軽便鉄道旧井宮駅前(井宮町6-1) (株)赤石工場前
・工場横の塀に旧井宮駅と山岡鉄舟邸址を示す看板が掛かっている。
・説明版:安倍鉄道跡、大正5(1916)年4月15日井宮から牛妻までの10㎞の軽便鉄道として開通。福田ケ谷ですれ違う単線で平日乗客は150人位。昭和7(1932)年に廃止された。
*安倍鉄道路線跡については別項目「安倍鉄道跡」を参照ください。
・山岡鉄舟邸址(水道町1-5) 魚仲増田商店(魚屋)前、先ほどの(株)赤石工場前に説明版
・石碑:明治の初め徳川家について静岡に来て十分一の役人のいた家に住んだ、江戸城明け渡し等非常に功績のあった有名な人である。
十分一:安倍川からいかだで運んできた木材、炭、杉皮等を十分一という役所で荷物の十分の一を税金として納めさせた所であったので、広い敷地建物があった。
・説明版:山岡鐵舟:鐵舟は戊辰戦争時、徳川慶喜の意を受け、江戸に迫る東征軍の陣地を突破して、大総督府の参謀西郷隆盛と駿府で直談判、江戸城無血開城への道を開き江戸を戦火の災厄から救うと共に徳川家の存続もなさしめた。後に西郷は、この時の山岡を「命もいらず名もいらず官位も金も要らぬ始末に困る人」と評して感嘆した。明治元(1868)年、駿府藩若年寄格幹事役、明治2年、静岡藩権大参事としてこの地に住み旧幕臣の無禄移住者の生計確保のために奔走し、城下の治安維持にも努めるなど八面六臂の活躍をした。さらに殖産興業にも意を尽くし、牧之原大茶園の実現や清水次郎長の富士の裾野開墾事業推進に尽力した。明治5年、西郷隆盛等の強い要請を受け、十年間の期限を切って明治天皇の侍従となり、青年天皇の人格形成に大きな影響を与え皇后からも絶大な信頼を得ていた。明治16年、清水区の補陀洛山鐵舟禅寺(元久能寺)建立を発願、明治43年、多くの人たちの支援により完成した。 平成22年4月吉日、静岡・山岡鉄舟会 山岡鉄舟邸址の記念石碑をここから北寄りの歩道上に再建した。
・石碑:山岡鐵舟:通称、鐵太郎、剣、禅、書の奥義を極めた明治の英傑。戊辰戦争時には、東征軍の参謀西郷隆盛と駿府で直談判し江戸城無血開城の合意を成した。明治2年には静岡藩権大参事としてこの地に住まい、藩政に多大な功績を残した。明治21年没、享年53歳従三位勲二等子爵、静岡市は鐵舟住居跡の記念碑を建てたが破損して撤去されたままであったため「静岡・山岡鐵舟会」の協力を得てこの碑を再建した。平成22年四月吉日、静岡市葵区水道町 町内会、
・大応国師産湯の井(井宮町76)
1235年当地生まれ。1308年没。
・説明版:静岡市指定有形文化財(史跡) 、円通大応国師(南浦紹明なんぽじょうみょう)は1235年(嘉禎元年)旧駿河国安倍郡井宮村に生まれた。5歳の時服織村の建穂寺に入り、淨弁法師のもとで学び、鎌倉の蘭渓道隆禅師のもとでの修業を経て、中国(宋)に渡り臨済禅を修めた。帰国後は鎌倉の建長寺や九州大宰府の崇福寺等に住山し、大徳寺を開山した宗峰妙超や妙心寺を開山した法孫まごでしの関山慧玄かんざんえげんをはじめ、多くの弟子の育成に努めるなど、臨済宗の普及に功があった。この井戸は国師誕生のとき産湯の水を汲んだものと伝えられている。国師の遺跡として、郷土に残っている唯一のものである。平成13年8月、静岡市教育委員会、
・松樹院(井宮町248)(浄功院)
・おみたらしの石仏
・お薬師さん:薬師如来、善導大師作、
・浄功院:家康長女死去により乳母が供養建立。明治期に合併。
・燈籠、・祠石、・稲荷、・新:燈籠、・祠、・新:水子地蔵、・燈籠、・三界萬霊 元禄二己巳天、・新:燈籠、・新:永代供養塔、・常緑樹:大木1、中木1、
・松平忠明の墓(井宮町194-4)
松樹院の少し北側の住宅地の路地を抜けた山腹斜面にある。
・説明版:九州の大名の子として生まれ、信濃の松平家の養子となる。信濃守。1798年幕府の命で北海道の奥地まで調査した。函館山頂に信濃守の詩碑がある。1802年駿府の城代となる。火災で粗末な仮の宮であった浅間神社再建の途中死去。駿府の人はありがたいご城代さんと呼んでいた。自分が死んだら浅間神社の木遣りの音頭の聴こえる所に葬ってほしいとの言葉に従ってここに墓を作った。
隣は古墓地である。・古墓地、
・静岡ホーム(井宮町183)(社会福祉施設)、
かつては井宮監獄、その後駿府城内の市民文化会館付近に移転、現在は静岡刑務所(東千代田3丁目)
・井宮神社妙見宮(井宮町179)
一般的にはここからが安倍街道出発点となる。
・籠鼻砦跡:賤機山城西端出丸、標高123m。
・月承句碑、 ?句碑:辞世、
・保食稲荷:無実の女囚にまつわる悲しい物語が伝わる、井宮監獄が駿府公園に移転したためここに祀る、食べ物の神。、・祠:稲荷神社? ・稲荷(2):大正二年、
・木鳥居、
・石碑:村社井宮神社 昭和十四年、・石碑:奉納 宅地拾壱坪 町内一同 大正拾年、
・石塔:(梵字)阿闍梨日海 雄大 僧林、・忠魂碑:明治四十年、・石階段:奉納 大正十年、・手洗石:、・手洗石:天保十一年、・石燈籠(2):、・狛犬(2):昭和六十年、
・石碑:天保六 雲泉~~~、・手洗石:明治九年・常夜燈:文政二、
・燈籠:文化十三、・燈籠:明治九年、燈籠:奉、・常緑樹:大木、
・石柵:(奉)納松永~~~、
・説明版:妙見山井宮神社:現在の拝殿は安永5(1776)年に再建されました。徳川家康が妙見菩薩(北斗七星の一つ破軍星)を祀ったので、妙見山の名の方が有名である。昔から妙見さんと呼ばれている。開運の神また薩摩土手の守護神でもある。北斗七星を祀ってあるので8月に七夕まつりをしている。
・説明版:徳川家康公跡地、安倍川石合戦見学地:臨済寺に人質の頃、山伝えに当社妙見宮に参拝され石合戦見学地と伝えられている。
・薩摩土手(籠上3-48)
徳川家康の命により薩摩藩が作った。家康からの命令だったためかなり気合を入れて作ったようだ。外様大名の薩摩藩の財力をそぎ落とす目的もあったようだ。これにより藁科川と安倍川が西で合流し今の安倍川東岸市中が安定することになり、現在の静岡市街のもとができた。
・薩摩土手の碑
平成元年
・説明版:由来:薩摩土手は権現様堤つづみ、または一部ひやんどて火屋土手とも呼ばれ、江戸時代の始めに造られました。薩摩土手という呼び名が初めて記録に見えるのは、旧静岡市史に掲載の天保13(1842)年に描かれた地図「駿府独案内すんぷひとりあんない」と言われています。静岡市史によると、慶長11(1606)年薩摩藩主島津忠恒公が徳川家康公の命によりここ井宮妙見下から弥勒まで約4㎞にわたって築堤したのが薩摩土手と言われています。この堤は、江戸時代以来、市民の生命と財産を守ってきましたが、今日都市化の進展の中で現存しているのはこの辺りだけとなっています。平成元年4月、静岡市、
・六部尊
・堂、石塔、
・川除地蔵尊(水道町116)
・地蔵:宝永四、・手洗石:昭和十七年、・堂、
・説明版:由来:水道町の川除地蔵尊は、井宮町にある泰雲山瑞龍寺の所属仏堂でありますが、水道町の「しばきり」即ち、最初から居住者であるといわれる故小林京作翁から私が聞いた川除地蔵尊の由来は次のとおりであります。
今を去る780年前のこと、その年の9月9日(初9日)、19日(中の9日)、29日(弟9日)と3回にわたり、安倍川に大洪水がありました。その時はいわゆる「イノコナグラ」といわれる激浪が渦巻き、堅固であった一番水道の堤防も刻々危険に瀕しました。時の水利方役人松岡萬は、地蔵尊の仏体を菰に包んで堤防の上に安置し、治水を祈願しながら衆人を督励して、防水に専念していました。附近の住民はもとより、安倍川流域の、殊に一番水道より灌漑用水を取り入れている農民たちは非常に心配して地蔵堂に集まり、連日連夜の対策に協議を重ねました。しかしこの度重なる大出水に対しては施す術もなく、拱手傍観途方にくれておりました。そこへ一人の老僧(俗に六部さん)が現れ「この大難儀お察し申す。拙僧もはや老齢ゆえ、安倍川流域の人々のために人柱となってこの堤防を守り治水永久のご安泰を祈り申そう。」と申し出て、念仏を唱えながら従容として堤防の中に埋りました。その老僧が唱える念仏の鐘の音は、それから七日七夜、堤防の中から消えなかったといわれます。これに力を得た水利方を始め、衆人一体となっての防水作業が功を奏し、ついに事なきを得ました。この地蔵尊は、それまでは厄除地蔵尊として、地方の信仰が厚かったが、それ以来川除地蔵尊として衆人の信仰の的となったということです。現在の地蔵の尊体には、その背面に「宝永四(1707)年丁亥天二月吉日」と刻まれてあります。即ち今を去る277年前、中御門天皇の御代に再建されたものであります。昭和61年8月24日、水道町町内会、
・湯浅堤の碑(柳町161)
・板碑:大正十三年、湯浅県知事が音頭をとって築いた堤防なのでこの名がある。
・洋館(籠上1)
古橋氏邸宅、13年12月に見たところ、塗り直したばかりで新しく見える。
・安倍鉄道線路跡(籠上1と7)
井宮小学校と古橋氏邸宅の間の道がかつての安倍鉄道線路跡である。
・賤機山城
標高173m頂上本丸、土塁、堀切が残存。徳川家康支配後廃城。
・(周辺紹介)賎機温泉 美人の湯(籠上15)
近年採掘された温泉、日帰り温泉。賎機山山麓と平地の間に温泉が出ることを証明したといえる。理屈上は出やすいようですが、ただ温泉採掘は1回1億円で2回かかったので2億円経費がかかったということのようです。
・難波神社
明治以前、小字の難波(どうも円成寺の南側)にあったが、1909年白髭神社に合祀。
・円成寺(籠上18)
1720年頃創建。仏堂内成庵と種徳院が合併し臨済宗妙心寺派となる。本尊:薬師如来。
・新:狛犬(2対):、・庚申塔:□政十二年、・地蔵:法華一千部之塔 文政三歳庚辰、・新:子育水子地蔵尊、・新:福神堂(大黒様、布袋様コレクション200~250体):大黒様布袋様好きなら一見の価値あり、おもしろ~い、・句碑:、・庭に新諸石仏多数、
・地蔵堂(籠上21)
長栄寺参道入り口
・玉井山長栄寺(籠上24)
1597年開基。本尊:聖観音。
・説明版:宗派:曹洞宗(禅宗)、当山は慶長2(1597)年に開創され、禅宗三派中の曹洞宗み属し、御本山は福井県の永平寺と、横浜市鶴見区の総持寺の両大本山であります。寺名の由来は、開基甫庵長栄の法名により、長栄寺と称されました。当山、本堂に安置されるご本尊は、古来より信仰深く衆生済度の仏様であります聖観世音菩薩でございます。境内には本堂、位牌堂、庫裏、山門と、夢のお告げによる井戸の中より出現された千手観音様を祀る観音堂と、その井戸が山裾にあります。また駿河一国札所の地蔵様が祀られております。なお著名人の墓も数基あり、本堂前左側には珍しい菩提樹の木があります。
・井戸観音:伝説では今川義元が桶狭間で討ち死に後、婦人が家宝の千手観音を敵に渡さぬため、この井戸に沈めた。後に僧が夢のお告げにより拾い、堂を建てて祀った。
・説明版:井戸出現観音の由来(聖観音菩薩様):その昔、永禄十(1568)年武田信玄が駿河に侵攻し、今川家七代目氏親うじちかが滅ぼされた。その折賎機山の砦におられし姫君が重臣と供に狩野城麓の菩提寺慈悲山増善寺に庇護を頂くよう尾根伝いに当地へ降りられました。しかし昔は賎機山と対岸慈悲尾の間がすべて安倍川の河川敷であったため対岸まで家宝を持っては渡れなかった。そこで姫君は今川家の家宝、聖観音像を何人かに託したいとの思いで、この井戸に投入されました。後年幸いにもその観音様がこの井戸より発見され井戸出現観音様と称され、金色に輝くご本尊様として、深く信仰を頂き現在に至っております。平成22年12月吉日、玉井山長栄寺、
・玉の井:寺の裏にあり、伝説では弘法大師作の観音がこの井から出現した。出現井戸、
・(欠):馬頭11基以上すべて欠損、如来:けっか座位2、・コンクリ手洗石:、・玉井山長栄寺本堂建設記念碑 昭和四十九年、・石塔:△寛文十二ニ壬子 一郷心信(行人偏に奇の字)庚申~(1672)、・新:燈籠2、・石塔:観世音出現之井 西国三十三所 秩父三十三所 観世音菩薩 天明六、・新:家石道祖神、・新:厄除平和観音、・新:慰霊塔 永代供養の塔 安らぎの塔、・新:水子地蔵尊、・西国秩父供養塔 文化六己巳、・菩提樹、
・新:六地蔵:説明版:お地蔵様の信仰は、中国では1340年ほど前、日本ではおよそ1240年前のようです。その中で六地蔵様の信仰は約890年前に始まったとされております。お地蔵さまは、この世の中のすべての人を極楽に送り届けるということを請願されました。この世というものは、仏教では六道、つまり六通りの世界のことを言います。六通りの世界が色々組み合わされてできあがっているので、ある時は争い、ある時は苦しみ、ある時は笑いあって人々は生活しているのです。六地蔵様は、それぞれ六つの世界を、一つずつ分担して救い守って下さるのです。延命地蔵様、水子地蔵様、六地蔵様と、名前はそれぞれ異なっても、後生、現世、来世にわたり、長い間救い続けて下さる仏様です。一回でも多くの御縁を結び、お参り下さることをお勧めいたします。
・白髭神社(籠上28)
1812年再建。1846年白髭神社と改称。・コンクリ鳥居:昭和五十八年、・手洗石:昭和弐年、
・貴庵寺、地蔵尊堂(昭府町、昭府2丁目32)
寺山峰への登山口。・西国秩父壱国供養塔 施主勘四郎 □(長反)安□四月、・庚申供養 寛延四辛未、・石塔:?読、・奉巡礼西国秩父坂東南無観世音菩薩供養(羊良) 寛政九、・板碑:新:寄贈檀徒一同、・新:地蔵、・新:五輪塔:海野家遠祖各霊菩提、・馬頭観世音菩薩 籠上新田望月清作建之、・新:燈籠2、・六地蔵+地蔵 寛永五年?、・新:手洗石:、・新:合葬塔、
・菖蒲神社(昭府町、昭府2丁目32)
・コンクリ鳥居、・変形家コンクリ道祖神、
・白髭神社(新伝馬3丁目14)
・石鳥居:御大典記念 昭和三年、・手洗石:平成23年、
・説明:略記:祭神:建内宿弥命たてうちのすくねのみこと、八街比古命やちまたのひこのみこと、八街比賣命やちまたのひめのみこと、所在地:静岡市新伝馬3丁目14番3号、祭儀:元旦祭1月1日、茅の輪くぐり祭6月30日、例大祭(日待祭)10月中旬、七五三祭11月中旬、由緒:創建の年月は不明であるが駿河志料等によると伝馬町新田は宝永年間(1704~1711)に開村され、貴庵寺(現、昭府町)境内に鎮座する左口神社を氏神として奉祭してきた。弘化3(1846)年に現所在地に新殿を建て、建内宿弥命を奉祀し併せて従来信仰してきた左口神社の祭神、八街比古命、八街比賣命を祀って白髭神社と称して以来、一村の氏神として信仰した。明治8(1875)年伝馬町新田全域の氏神として村社に指定され県の神社明細帳に登載された。本殿、拝殿は昭和16年に改築され、現在のものは平成16年に町民、氏子の浄財寄進により再建したものである。祭神のご神徳:①建内宿弥命は国の政治に非常に功績があり日本の国で初めて大臣となされた方で出世の神、長寿の神、子孫繁栄の神、として信仰される。②八街比古命と八街比賣命は夫婦の神で共にこの町内に外部から悪い病気や災害が入ってくるのを防ぎ氏子の安全を守って下さる神様である。
・松富団地入口(松富上組、松富1丁目)
現街道(県道井川湖御幸線)より東の山側にほんの少し狭い道跡がある。これが近代の道だろう。再整備されつつあり近代あるいは街中に残る古街道の景色は消えうせるようだ。13年12月に山側の古く狭い道跡は道路拡幅工事により完全消滅した。
・石塔:天下泰平 宝暦八戌寅 駿州安倍郡松富村 ○日本廻国六十六部供養塔 国土安全十月吉祥日 願主 藤浪定右衛門
・石塔:△ □□□
・白髭神社(松富2丁目-8)
・手洗石:、・石鳥居:大正十年、・石碑:、・神社名碑:村社白髭神社、・石柱:明治四十二年八月指定神饌幣錦(金なし)料供進指定社
説明版:お祀りしてある神様:祭神名:武内宿祢命たけのうちすくねのみこと(長生の神様)、品陀和気命ほんだわけのみこと(武運の神様)、須佐之男命すさのおのみこと(農業の神様)、菅原道真公すがわらみちざねこう(学問の神様)、瀬織津姫命せおりつひめのみこと(水の神様)、例祭日:10月17日、由緒:創建年月は不詳であるが、慶長2(1597)年2月に再建された。
・板碑(松富3丁目2、町内公民館)
・板碑:合併記念碑 昭和七年、・板碑:耕地整理碑 昭和五年、
・富慶寺(松富3丁目7)
・新:永代供養塔、・石燈籠、・新:子持地蔵尊、・新:六地蔵、・新:延命地蔵尊、・不動明王堂、・五輪塔:土水火、・地蔵、・地蔵か墓石?
・地蔵堂、白髭神社(上伝馬26-10)
・地蔵堂裏に墓石4基、・石塔:七世父母六観音□為 正慎六亥辰七月(正徳六丙申七月なのか?)、・石塔:読?、・石塔、
・木鳥居、・石:家:道祖神:稲荷、
・白髭神社(与一6丁目13‐16)
・木鳥居:平成二十四年、・庚申塔:昭和五十五年、・小川地蔵尊 海蔵寺、・庚申塔:文政石?年、・手洗石2:明治三十一年十月、神木2:杉、
・與一右衛門新田開発人 與一右衛門碑 平成十二年:説明版:わが町与一は宝暦元(1751)年奥津与一右衛門の手により開基、以来250年間、度重なる安倍川水禍をも克服し、今や戸数1400、ますますの飛躍疑いなく、ここに与一開基250年を記念し、奥津家継嗣にして志太郡大井川町宗高より移り越したる池ヶ谷一門によりこの碑を建立するものなり。平成12年10月吉日、
・石仏(松富上組4‐3、運転免許試験場入口バス停近く、水神橋近く)
・馬頭:天保十二年、山際に祀られている。
・道祖神、水神宮(松富4丁目9)
・石:家:道祖神、・水神宮 松富講中 明治二拾七年、市立北部体育館方面入口手前
・恩愛の像(与一6丁目17 市立北部図書館)
・恩愛の像:元駿府公園内設置:説明版:この像は昭和37年児童会館の開館5周年を記念して建てられたものです。本文:しろがねもくがねもたまも なにせむに まされるたから こにしかめやも 銀母金母玉母 奈尓世武尓 麻佐礼留多可良 古尓斯迦米弥母 山上憶良「万葉集」より 意味:金や銀や宝石なんて何の役に立つのでしょう。それよりすぐれた宝としては、自分の子にかなうものはありません。」といった意味で、わが子を思う親の気持ちをみごとに歌い上げています。
・川除地蔵堂、石塔類(福田ヶ谷328)、福田ヶ谷公民館東側丘上
・川除地蔵堂、・地蔵、・庚申供養塔 安永三、・庚申塔 昭和五十五年、石塔?、・馬頭?、・地蔵?欠、・観音?欠、・観音?欠、・馬頭、・如来?座像、・妙法馬頭観音、・馬頭 昭和二年一月 川村浅左エ門、・馬頭:?天明二、馬頭:昭和二十二年二月建之 川村兼吉
・日枝神社(福田ヶ谷779)
・コンクリ鳥居、・手洗石、
説明版:鎮座地:静岡市葵区福田ケ谷779番地、神社名:日枝神社(宗教法人登記昭和27年元月)、創建不詳、安永七年四月二日再建、旧社格村社明治8年2月、現在の拝殿は昭和53年新築、祭神名:大山咋命おおやまくいのみこと(山を支配し平野の繁栄を守る大神)、御神徳:聡明長寿、家内安全、五穀豊穣、産業繁栄、例祭日:10月17日、神社有地1254平方m、工作物:本殿、拝殿、その他、
隣の大塚氏裏山畑で白ヤギ飼育中(13年12月)
・石仏(福田ケ谷52)
・六地蔵、・三界萬霊等 文化四年、
・諸岡山(下122)
・「有功堤之碑、明治26年(1893)」、
説明版: 有功堤之碑:この石碑は明治26(1893)年従一位勲一等近衛忠煕篆額このえただひろてんがく、権中教正祝部宿祢生源寺平格ごんのちゅうきょうはふりべすくねしょうげんじへいかく、撰文静岡県知事従四位勲四等小松原英太郎書による記念碑である。この有功堤というのは山脇から諸岡山に繋がる堤防の内、諸岡山の自然堤を利用して、仮定(ヒジマガリ)という堤防の作りによって、そこに一旦水を溜めて水流の勢いを弱めて下流に流す仕組みの堤防である。この仕組みの堤防が安政元(1854)年に駿河国に大地震が生じ大谷崩れが生じた上に翌年6月30日の大洪水によって堤防は決壊して流域の町村の人々と田畑に多大の損害を与えた。明治七年稲葉利平が中心となって工役を督し、元の堤防に復旧した。それ以来一度も水害がなくなった。明治26年11月にこの堤防と人々の功績を讃えて建立された。下郷土誌作成委員会、
・「文化五□□年 奉納百八十八番供養塔 □本清拾郎」、「文化二年十一月吉日 庚申塔」、「文政五歳□年 奉納百八十八番供養塔 七月吉日 願主幸四」、「紀元二千六百年記念 庚申供養塔 昭和十五庚辰年三月 上之谷講中」、「昭和五十五年 庚申塔」、文殊地蔵、三十三身観音、普賢菩薩、観音堂、「忠魂ノ碑」、「戦没者慰霊碑」、・地蔵?欠:寛政十二歳、
・養秀寺(下122)
・「東宮殿下御成婚奉祝記念、大正13年」(13年12月未発見)、・馬頭観音「」(13年12月未発見)、・庚申塔 文化二、・庚申供養塔 □□歳、・禁葷酒(埋設)、・新:地蔵:杉村隆風、・如来?観音?墓石?:寛政十二年、・新:水子地蔵、
養秀寺門前石垣は鯨陽学校跡の石垣である。この学校が賤機南小学校前身で、この地域の近代教育の礎である。鯨陽学校より前には積善舎という私塾があった。
・石碑(下134-2)
・石碑:幕末志士稲葉彦兵衛出生地 大正十三年、
・上之谷、堂の藪跡地(下77)
・「庚申塔 吉文政七(1824)歳□ 甲申二月二十六日」、・他墓石4基、
・三輪神社(下226)
・鰐口「永正3(1506)年」、・コンクリ鳥居:昭和八年、・石燈籠2、・手洗石、・狛犬2、
・福成神社(下)
賤機山最高地点、近世には神社が祀られていたようだ。近年整備され整っている。
・新:狛犬2:、
・南無観世音菩薩、馬頭観音(下1088)、安倍街道土手の切通し
観音「文政四(1821)」、馬頭観音「明和六(1769)年、九月建之」、「十一面 馬頭観音 供養塔」
・説明版:南無聖観世音菩薩(土手観音様)由来:昔旧安倍郡賎機村下字山脇地域において、流行病(悪熱)が発生したといわれている。それゆえ当地域では病を退治するため、文政4(1821)年巳七月、聖観音を土手の上に建立し祀り悪病を防いできた。それ以来当地域は健康で明るい地として栄え以来180余年にわたり土手の観音様と崇められ、皆に親しまれている。このたび第二東名工事が行われることから、やむなくこの地に観音様を移すこととした。
・鯨ヶ池(下)、御用水(下284)
鯨ヶ池八景(福成の秋月、鴻巣の夜雨、窪田の落雁、大平の暮雪、御殿場の晴嵐、山田の帰帆、和田の夕照、諸岡の晩鐘)
湧き水を元にする。戦前菱が生えていて食用にしていた。
安倍街道鯨ヶ池出入口前に鯨ヶ池から流れてきた用水がある。これが街道に沿って南下し駿府城堀の水になったので、御用水という。この地点から堤防が賤機中学校東側を通り南から諸岡山北につながっていた。これを「有功堤」という。
御用水
・弁財天、宗像神社(下544)、鯨ヶ池脇
弁天様「明治3年」
・桜峠、地蔵(下554、北)
地蔵「明和3(1766)年」
・昼井戸(下832)
稲葉家横、道路から見られる。単なる側溝として見落としてしまうほど、地味で目立たないが、ちょろちょろと今でも少しずつ透明な清水が湧くようだ。
・石碑(下714-4)
・石碑:大平農道完成記念碑 昭和五十六年、
門屋からの鼓平農道と山頂鼓平で合流して門屋までつながっている。13年12月俵峰までの林道開設中。
・水天神(門屋99、静岡市水道局門屋浄水場敷地内)
・鳥居、社、
・門屋番所関所(門屋387)
街道横の白鳥家の辺りがかつての関所番所らしい。
・宝寿院(門屋639)
曹洞宗、本尊:阿弥陀如来、かつては地蔵堂と大日堂もあった。本堂北側は改修されてしまったが、かつてここに勝海舟の別荘の海舟庵があった。
・内野紀伊守藤原宗重 寛政十戌午歳、・庚申供養塔 文政十三、・奉待庚申供養塔 享保五、・観音、・地蔵:文化□、・六地蔵、・燈籠、・石碑3、・新:百観音、・板碑:忠魂碑、・欠:宝篋印塔か五輪塔の相輪か空輪らしき?
・勝海舟屋敷跡:説明版:勝海舟(1823~1899)は、江戸末期の幕臣として生まれ、通称麟太郎といった。幕末の騒然とした時世にあって、蘭学、兵学に通じ、幕府海軍の育成に尽力した。万延元(1860)年咸臨丸艦長として、遣米使節を乗せ我が国で初めて太平洋を横断した。そして明治維新の際には、幕府の陸軍総裁として山岡鉄舟を使者に立て、官軍の参謀であった西郷隆盛と会見し、江戸城の無血入場、徳川家の家名存続、慶喜助命に成功したことはあまりにも有名である。明治維新後、多くの幕臣は、元将軍慶喜の後を追って静岡へ移り住んだが、海舟一家も静岡市鷹匠町に居を構えた。海舟は旧幕臣の面倒を見る傍ら新政府の仕事をするなど、多忙な日々を過ごしていた。この頃ここ門屋の名主、白鳥惣左衛門と親交が始まり、頻繁に門屋を訪れた海舟は、この地の美しい自然に強く心をひかれ、母信子の隠居所として白鳥家の一寓を借りて孝養をしたいと念願した。しかし母は息子の孝心にもかかわらず間もなく他界した。その後海舟は少しの暇を見つけてはここ門屋の家に来て、秘かに要人と会い、また村人と肩の凝らないひと時を楽しんだ。この家屋は、その後白鳥家の屋敷内に移されていたが、昭和32年宝寿院境内に再度移築され現存されている。昭和60年1月、静岡市、
*宝寿院和尚榑林雅雄氏によれば、その後息子夫婦の家として新築し直したそうだ。昔の家屋は消失したようだ。
・八幡神社(門屋542‐1)
創建不明、1713年再建、・コンクリ鳥居、・コンクリ燈籠2、・手洗石、・石:家:道祖神、
・石碑:鼓平農道完成記念 昭和51年7月(門屋)
門屋奥から鼓平山頂まで舗装され下の昼井戸からの大平農道とつながる。13年12月俵峰までの林道開設中。
・三味線滝、小僧沢、御殿場の御殿石、鼓平、ばんば、
滝や沢は門屋前を流れる沢を奥に詰めたところで途中まで農道で遡れる。皷平は農道を上り詰めて昼井戸との境の尾根の平らな茶畑の辺りで、かつて家康が鼓を打ったという伝説がある。
・三峯講(門屋390)
・祠:三峯講、・祠:地蔵2、
・天神(門屋381)
・観音、・天神之宮:祠、・新:燈籠、天神橋近く
・白澤神社(牛妻1139)
創建不明、1805年再建、付近に鉱泉、宝物跡、・石鳥居:大正五年、
・説明看板:延喜式内白澤神社 静岡市牛妻1139番地:鎮座、御祭神:伊邪那美命いざなみのみこと、建御名方命たけみなかたのみこと(諏訪神社)、大雀命おさざぎのみこと(若宮八幡)、木花佐久夜毘売命このはなのさくやひめのみこと(浅間神社)、例祭日:10月17日、御由緒:当神社創祀年月不詳。牛妻の開村と共に祀り始められたものと思われます。惣国風土記という古い書物に「白澤神社伊邪那美尊を祭る。和銅三(710)年元明天皇の御代に諏訪神社を添えて祭る。」という意味のことが書かれてあり、更に延喜五(905)年醍醐天皇の勅命に依り編纂された延喜式神名帳には「駿河国安倍郡白澤神社国幣小社。」と登載されています。これにより1200余年の昔には既に存在したことが証明され、また1090年の古より延喜式内の神社として、毎年の大祭に駿河の国府より国幣が献納された静岡市でも最も古い貴い神社であることが分かります。而して当神社は牛妻の氏神、産土神として村人を始め遠近の多くの人々の敬慕、信仰を集めて参りました。明治38年に牛妻地内の若宮八幡宮と浅間神社を合祀致しました。現在の社殿は昭和13年に改築したものであります。御神徳: 伊邪那美命=母性愛の神、安産の神、寿命を司る神、建御名方命=開拓の神、殖産興業の神、大雀命=富国救民の神、慈悲の神、木花佐久夜毘売命=美の神、婦徳の神、
・日陰山、観音滝
・牛妻原会館(牛妻625)
・祠、
・牛妻不動ノ滝、不動尊(牛妻丹野)、少女滝、聖滝、扇窪
・庚申供養塔 寛政十二年、丹野集落内、彫りが立派である。(牛妻1564‐1)
・丹野会館(牛妻1957):地蔵、
・不動の滝:不動堂、
・稲荷神社(牛妻)
・安倍鉄道旧牛妻駅跡(牛妻)
・県道沿い小萩橋より西の安倍川側の細い道で北へ向かうのが鉄道跡で牛妻保育園辺りが駅構内と思われる。小萩橋より南は県道より東側の道で門屋との境の天神橋辺りまでである。それより南は今の県道の西沿いを下の堤防(新東名)まで行くと思われる。
*詳細は別項目「安倍鉄道跡」を参照ください。
・牛妻水神社(牛妻2252)
・曙橋袂:東海自然歩道標識や説明版等、
・祠:地蔵(大2、小多数)三界萬霊、・馬頭:欠、・馬頭:昭和四年、・不動明王?、・馬頭:昭和四十四年、・地蔵、
・水神祠、・コンクリ鳥居、・石:家:道祖神2、
・板碑:東西両岸道路開通 静岡県知事斎藤滋与志
・福寿院(牛妻2233)
曹洞宗、1619年開基、かつては行翁山奥のごうりんにあったが移転したらしい。ごうりんから五輪塔を移したといわれる。寺門前に石塔がある。
・「葷酒不入寺内」、・石塔:東海自然歩道十二支観音 第一番札所龍爪山福寿院、・石塔、・石塔、・観音、・石仏:欠、・新:石仏、・句碑、・観音堂、・燈籠4、・新:六地蔵、・地蔵、
・津島神社(牛妻2233)
福寿院墓地横で祠3、祠手前に神木の杉大木2本。
・コンクリ鳥居:昭和三年、
・説明版掲示:国幣小社津島神社本社由緒略(田と各を上下に記述)記:所在地:愛知県海部郡津島町向島、名古屋より西へ五里、東海道線名古屋駅前柳橋より津島電車にて約40分、尾交一之宮駅より尾西電車にて約40分、関西線麗?富駅を電車にて約20分、御祭祀、御祭神:素鳶鳴尊すさのおのみこと、天照皇大御神の御弟袖にまします世俗□唱へ奉る大神なり、相殿 大冗牟遅命、またの御名大国主命と申し素鳶鳴尊の尚女神にまして世俗大国様と唱へ奉る大神なり、二柱の大神の御神秘の大要を称へ来れば武運長久勝利開運の神として
○方除厄除殊に悪病退治除去の守護神として
○縁結び及家庭円満の守護神として
○文学の祖神、特に歌道の守護神として
○造酒の守護神として偉大なる御神秘を題し給ふ
由緒:欽明天皇元年庚申六月朔日の御鎮座にして古来日本総社津島牛頭天王と称し皇室の崇敬は固より部門武将殊に織田信長豊臣秀吉徳川家康の崇敬最も厚く四条天皇の仁治年中本社造営遷宮の事あり、後亀山天皇の弘和元年辛酉冬大橋三河守貞省勅を奉じて本社を造営し永享九年丁巳十二月五日足利六代将軍義教続いて造営し文明四年壬辰六月六日足利八代将軍義政の命により又永禄八年乙丑十一月二十日足利十三代将軍義輝の命により造営遷宮の事あり天正の頃伊田信長殊に尊崇して本殿を始め楼門回廊に至るまで屡々修復を加え或は神領神器を寄付し奉れり文禄二年己巳豊臣秀吉又造営し慶長十年乙巳清州城主松平忠吉殿舎を修理し元和五年己来徳川二代将軍秀忠再び修理を加えらる慶安三年己丑尾張僕義直厠御神供所及橋等を造営し爾来必要に応じ修理材料及料銀等寄付あり、又尾張僕に祖先以来正月九日代参使を立てられ幣□料を奉納せらるるを恒例とせらる、亦者府よりは向島一園の地石一千二百九十三石九斗六合を寄付して神領に充て、其の他の待遇も熱田神宮眞清田神社と同格に受け給ひ後世に到り尾張五社の一つとして四氏の奉紫驚く神威林如として近きは関苅、遠きは樺太興料満州及宗邦人に並び参拝者は四対陸続として絶ゆることなし。
建物:本殿、渡殿、祭文殿、廻廊、拝殿、楼門、神庫、遂箱、絵馬堂、神水授与所、社務所、神水調整所、神苑亭等にして現在の本殿は特別保護建築物なり、其他の建物も本殿に準ずべき優秀な建築にて何れも朱塗宏麗を極む。
攝末社:約四十社ありて重なるは攝社居森社に御魂社と称し元此地に鎮り給ひしと云い傳ふ、攝社称五郎殿併堀田弥五郎正兼の建立にかかる故に此称あり。攝社八柱社、和御魂社、荒御魂社にして境内境外に奉斎す。
寶物:古鏡数十面、霊元天皇御直筆、後桃園天皇御□筆、織田信長書、国宝太刀大原真守作、国宝剣長船□党を初め多数の宝物、古文書を蔵す。
氏子:津島町約参千五百戸当社の氏子に属し殊に大宮向島に古来より神領として縁故最も多し。
附属講社:神社直轄の講社ありて太々講とす津島神社、宮司是が総理となり社殿一切を統括し神社を□□□の間に結社使ありて一カ事を称□を何人にても入社して社□たることと殊に神社は謙社の島の毎年一月十五日併に四月一日より三十一日間とに家運長久家内安全の□□を執行し四月中は毎日二回神□を勤行す。講社員は毎年金五拾銭を奉納し参拝なべる様に程々の待遇を受け現在□□は約参拾五□金に□□、益々隆昌に向ひつつあって菱大なる御神従に浴す。
附近名所:天王川、天王池とも称す。 有名なる銘祭は毎年陰暦六月十四日十五日此の池にて執り行はせらる車案の妙音は神入共に感動、万燈の蝋燭に天を発し地に転じて社麗□なし、遠近より宿でも拝観するも無慶数十等、名古屋鉄道社終夜間断なく運転池辺の公会堂には無料宿泊所を設け貧者に便宜を與ふ。 池の周囲の根上には桜楓満開春秋は美観を極め殊に或夏の候は納涼絶好の池なり。池の附設地に大スタンドあり。當に重要せらる。 昭和四年五月二十一日 本社参拝(参詣)記念 奉納 荻野力蔵
*撮影した写真の具合がよくなく読めない字があり、適当に字を当てたため意味不明な個所が多い。済みません。といってやり直す気にならないのでこのままです。
・石塔:?読、神社より北50m、
・石:家:道祖神2、集落内、
・石塔(牛妻公民館2215-2)
・馬頭:昭和五年六月、・有縁無縁□□等、・?馬頭:、・庚申塔:昭和五十五年、・石塔:?読、・庚申供養塔 大正九庚申年、・庚申供養塔 寛政十二年、
・森谷沢
・道路開通之碑 昭和二十七年、
・馬頭、・馬頭大正十年:、・石塔、
・火の見櫓
・地蔵:森谷沢公民館横(牛妻2694)
・えんま淵、鬼穴:現在「安倍ごころセンター」に改変され消失したろう。
・四足門
松永家、徳川家拝領の茶碗
・地蔵:旧街道道端側壁
・樽下滝、昇竜滝、
・石:家:道祖神(牛妻3108)
・泣姫、恋の淵、コンクリ家型道祖神、椿の木、(牛妻3108)
・付近に案内板:泣姫、鳴沢の滝、行翁山、案内板より右折50m、
・説明版:泣姫の由来についていくつかの話が伝わっている。漣昇山武昇院院主連昇氏が泣姫さんについて書いたものの中では、「武田勝頼公の奥方清州姫は慶長17年、子供と別れ別れになり行方を尋ね安倍奥地に向かう途中、勝頼公自害の報を聞き53歳で後を追った。」と記されています。いずれにしても泣姫伝説には子供を想う母の姿が語られており、それが夜泣きを治してくれるという信仰になっていったと思われます。
・説明版:泣き姫:樹齢数百年の椿の古木と大きな岩石、早春には見事な花が咲き満開となります。「小萩」は祖益の悶死後、その後を追い「恋の淵」に身を投げたので淵にその名がつけられ、また小萩を憐れんで「なきひめ」として祀ったといわれています。また武田の残党某が行翁山に逃れてきて、行者として仏門に入りましたが、後を追ってきた妻は夫に会えないため、恋の淵に身を投じ、里人は美人の人妻を憐れんで祀ったともいいます。また行方不明になった夫を探して行き倒れになった美人の人妻を祀ったともいいます。
このように三つの説がありますが、この世の離別の悲しみのあまり、無常をうらんで死んでいった同情すべき女性であったことは、三者共通しています。この泣き姫は夜泣きの児を治す霊験はあらたかで、遠くの静岡の方からも伝え聞いて参詣に来たといいます。願いが成就すると、そのおはたしとして人形やお菓子を供えて帰ります。今行っても必ず一つ二つの人形があげられています。泣きひめの 碑にしみとおる 春しぐれ 海哉、牛妻町内会
・鳴沢滝、行翁二の滝、行翁一の滝、垢離の淵、
・説明版:鳴沢は行翁山から沢を登った山腹にゴウリンと呼ばれる所が伝えられ、かつて寺があったといわれています。この寺の鐘が山津波によって押し出され鐘が鳴りながら下った沢が鳴沢といわれています。
・上記案内板より奥に直進100m、そこから更に奥に徒歩300m、
・行翁山、ごうりん
・案内板より泣姫過ぎて自動車道500m、そこから更に徒歩で登山道40分、
・説明版:昔この山に行翁という行者が住んでいました。行翁は第49代光仁天皇の宝亀9(778)年6月、京都の音羽の滝を出て衆生済度のため、この地にやって来たと伝えられています。洞窟に住み、その跡は現在もあり頂上の行翁堂には翁が履いていた鉄下駄と鉄の杖が残されており、山岳宗教修験道の場所と伝えられています。
行き方は、泣き姫前農道を上り農道終点に至る。そこから奥へ登山道を7分登って分岐点に最初の石仏がある。
・観音:「左ワ行園山」の文字が観音の左、見ている人からは右に記入されている、牛妻分岐点にある。更に山腹の斜面を左に横平行に20分歩くと二番目の石仏がある。
・地蔵:「左ワ行園山」の文字が観音の左、見ている人からは右に記入されている、牛妻分岐点から3分の2ほど行った尾根をまたぐ所にある。
そこから15分で沢場に到着するが、そこが頂上ではなく、もう3分登るとお堂があり頂上である。
・行翁山の碑:行翁山 弘化二乙巳(1845)年三月建立之府中安西□屋安全 南無阿弥陀佛 平森谷澤安全、 刻字が綺麗で四面とも書体を変え見事な彫りで美術的価値がある。
・石祠:家型道祖神:「阿弥陀佛」、
・地蔵:天明二年、
・石塔:開山行翁 明治十八年、本堂裏側安置、
・木祠:
牛見石、掛軸(望月家)、鉄下駄、鉄杖、
・行者穴:人為的に彫られた穴で堂の右崖下に横穴がある。穴を掘ること自体が修業だったのだろうか。この穴の大きさだと人が寝泊まり可能であろう。
・三界の滝:滝が3段に落ち見事である。・説明版:滝の悲話:武田の武人の妻が修業中の夫を尋ねて当山へ来たが落人狩りに襲われ死亡したと聞き、悲しみ入水したという。
・本堂裏に細い登山道が続き竜爪山に至るようだ。その途中にかつて寺のあったごうりんという場所もあるようだ(未調査)。寺のすぐ裏は切り立った崖上の細尾根登山道で、いかにも修験者の修験道という趣である。こういう切り立った細尾根道をよくきん冷やしとかきん縮みということがある。肝を冷やすと同意味であり、きんはきんたまの意である。行翁山周辺はいかにも修験場にふさわしい。
・庚申塔(森谷沢、平、丹野、中沢)?
・養福寺(油山1295)、
本尊:観世音菩薩、開山:1601年、・石塔、・石塔、・石燈籠、
・白髭神社(油山945)
寺の手前の尾根先端丘上にある。・板碑:耕地整理、・手洗石、・石鳥居、
・油山温泉
油山より奥へ1.5km。
*地名の「油山」の油等の「油~」は「湯」と同義である。つまり「油山」は「湯山」の意で湯のある山で、文字通り温泉のある山で油山温泉である。
・油山山日月龍神社(油山1836)
湯の島分岐点手前道路横の山腹斜面にある。・石塔3「龍爪安倍川 元主、龍爪油山之光、龍爪松野大怨霊」、木鳥居、
・栗島峠(湯の島峠)H450m
湯の島と栗島を結ぶ峠道で国土地理院地図上ではルートが示されているが、12年1月2日廃道、湯の島よりH300m辺りで倒木や道不明で通行不可。
この峠道を再生し使えるようになると、1本北側の峠道「油山峠(相沢峠)(東海自然歩道)」とともに使えるようになり、油山温泉やホテルりんどうを含み、油山温泉―油山峠―相沢―栗島―栗島峠―油山温泉という周回往復ルートになって同じ道をピストンせずに往復できてハイキングコースとしては使い勝手がよくなる。相沢や栗島の集落は古い石仏、お堂、優秀賞花壇、足様神社等があってそこもハイキングコースとしてよい。
・油山峠(相沢峠)(東海自然歩道)H400m
油山温泉より200m奥の沢を渡り(H180m)南西に進む。東海自然歩道なので標識、道の安全状態はよい。多分迷いにくい。一部急坂やガレ場はあるが登山初心者向き、家族向きハイキングコース。峠(H400m)は植林で展望なし、ベンチあり。油山峠からトワ山東ピークに尾根沿いに行けるはずだが不明。(’12 10/14 玉川トレイルレースコースとして復活。)相沢側はさらに補修された安全なコースだが、一部沢沿いのガレ場上コースなのでちょくちょくガレるのだろう。豪雨や地震直後はコースがガレやすいだろう。相沢のホテルりんどう前に出る。
・油山稲荷神社(松野30)、
・祠:平成24年、
・板碑:農道完成記念 平成8年竣工、
・石塔(松野187、県道側壁)
・馬頭:昭和三年、・?地蔵:□□□十年、・石塔:?大乗経典か庚申か
・薬師堂(松野813、阿弥陀仏像、木像、平安後期)
河段段丘の茶畑内墓地の横。河段段丘になっている茶畑の辺り一面は別所平遺跡という。この岡上の平地は河段段丘といって、かつての河原が隆起したものである。この仏像はかつて200m西の山に寺があり、そこにあったという。この河段段丘にかつて文化の華が開いたのだ。石塔:「瀬川氏之碑 松野区 昭和三年十一月」「信州善光寺 西国三十三所 四国八十八箇所 供養塔 安政三」「庚申供養等 安永五」、句碑。
・「やくさんの井戸」、地蔵。
・松源寺(松野148)
・板碑:西国三十三所観世音菩薩 大正十年、・地蔵、・地蔵、・(梵字)地神塔、新・六地蔵、・殉国英霊の碑、・新:永代供養塔、
・松野城跡(松野)
河段段丘の西の山で農道を詰めた所。
・石造物(松野1040‐1)
・石塔、・庚申供養塔 大正六庚申年、
・白髭神社(松野1350)
丘上、灯篭2、
・三島神社(津渡野198‐3)
蔵王権現も祀る、神社の裏山を津渡野遺跡といい、さらにその上が城跡である。
・石鳥居:、・石碑:竣工記念 昭和五十九年、
・石造物(津渡野248)
・庚申塔 安永十年、・欠:観音、・○三界萬霊等 文政三、
・寶津院(津渡野328)
臨済宗、・堂、・地蔵、・新:地蔵、・石仏、板碑:静霊、・燈籠、・六地蔵+1、・地蔵、・新:聖母観音、・首なし:地蔵、・?観音、・三界萬霊。
・近くに木の祠:稲荷、
・津渡野城跡(津渡野)
城跡の東側は津渡野遺跡といい、その下に三島神社がある。
・水除地蔵(津渡野)
かつての竜西橋北袂に安置。小川地蔵。
・新:地蔵(郷島1210-2)
郷島入口側壁安置。
・郷島浅間神社(郷島373)
・説明版:静岡市指定天然記念物(植物)郷島浅間神社の大クス:指定年月日平成七年一月二十三日、所在地静岡市郷島373番地、樹高43m、幹周(目通り)13m、枝張40m、樹齢約千年、この大クスは市内でも屈指の大きさ、樹齢を誇る巨樹です。樹勢も良好で、またクスノキに見られる美しい樹形を呈しています。クスノキは、各地の暖地に多く自生する常緑高木で、木全体に特有の良い香りがあります。静岡県では、伊豆をはじめとして駿遠地方の暖地に多くみられます。材は、建築、造船、楽器、彫刻など多様に使われます。以前は防虫剤の代表だった樟脳もクスノキ材から作られました。平成12年3月静岡市教育委員会。
・金属鳥居:昭和六十一年、
・秘在寺(郷島518)
13年12月、元は茶畑で次に薬師庵があった所に移転したばかりで新しい2階建てビルとなっているので寺院とは思われない。・新:永代供養墓、新:石碑数基、・新:句碑多数「しずおか句碑の郷サト」、
・元の秘在寺の場所(郷島506)
元寺があった所は空地だが手前に石塔類がある。・石碑:□□□□秘在禅寺 平成元年、・新:六地蔵、・?庚申供養塔、・庚申塔、
・古い酒屋の名残の建物(郷島246)
昭和の雰囲気のある建物だが、壊れそうなのでそのうち解体されるだろう。
・石仏(郷島5)、消防分団小屋横
道より低くなった畑の北端にある。・地蔵、・?観音、・地蔵:元禄六癸酉□月二十四日造□塔 文化□□?十十月~~~~~□天明、・石碑:土地改良記念碑 平成四年、
・石仏(郷島)
郷島出口県道右側壁安置。・?観音、
・釈迦堂(野田平242)
・鰐口、・石塔7(地蔵1、如来1、他不明)、これより奥へ上ると墓地でその手前で尾根に到達し俵沢方向へ下る登山道あり。そこに峠の石仏が安置されている。
・石仏(野田平242)
・地蔵:安倍郡野田平村善男善女□□亥四月吉祥日、・馬頭:明治三十一年四月、・地蔵:大正十三年七月建之、野田平と俵沢の境の峠に祀られていることになる。
尾根を登ると静清庵自然歩道の一本杉及び竜爪山穂積神社に至り、尾根を下るとすぐに墓地で、さらに下ると県道梅ヶ島線及び俵沢に出られたはずだ。13年12月現在一本杉のすぐ下には林道門屋俵峰線が通過していて、そこに野田平へ下る登山道と標識があり、おそらくこの石仏地点へ至ると思われる。
・神社(野田平242)
釈迦堂の少し横にある。・石鳥居:昭和二十九年、・石:家:道祖神、・杉:大木7、・常緑広葉樹:大木:1、
・石碑(野田平)
野田平から野田平公園へ降りる道沿い。・道路開通記念 静岡市長小島善吉、・野田平一号線開通記念、・石、
・石碑:野田平公園 平成7年、
・石造物(俵沢236)
賎機北小学校南口付近、・二宮金次郎像:薪を背負い読書、・板碑:併合碑、
・石塔(俵沢365)
賎機北小学校から俵峰に向かう道を進み、坂道の直登道と左に迂回しつつ登る道の分岐点に出る。そこを坂道直登道を進むと右にある。
・祠:・庚申供養塔:、・?墓石、・地蔵:弘化三、・?地蔵、・地蔵、・?地蔵、・墓石:□□□居士 文亀元 □□□大姉 永正二 □□□居士 憲徳(延徳か正徳の間違い?)元 □□□居士 文□二 □□□大姉 慶長四、・一字一石法華経塔 □□□居士 明和九、この祠の横は墓地で墓石の後方には三十三観音が墓石と同じように祀られている。
・神社(俵沢400-1)
先ほどの左の迂回道を進み、左にカーブしていた道が右カーブに変わる所で左の沢横の道を沢沿いに詰めていく。
・石鳥居:大東亜戦争講和調印記念昭和二十六年、・杉:大木2、・赤橋、
・石碑(俵沢334)
俵峰への道を進み俵沢集落を過ぎ、茶園ばかりになると道路脇にある。
・石碑:静岡県棚田等十選に認定する 静岡市俵沢のつづら折り茶園、
・石塔類(俵峰400-1)
俵峰集落へ入る道は直前で左への広めの新道迂回路と右への旧道となる。どちらを行っても集落の中央で合流する。その合流地点に石塔類がある。
・板碑:道路開通記念碑 昭和三十一年、・簡易水道通水記念碑 峰の水みち 平成十六年、・馬頭:大正十一年、・観世音、・?観音:天保十三、・庚申供養、・馬頭:欠、・その他5~6基、
・玉宝寺(俵峰625)
・?立像:半僧坊大権現、・地蔵、
・水月院(俵峰)
・石塔2、・石垣、
・白髭神社(俵峰)
・石鳥居:平成十八年、・手洗石:昭和十五年、・杉:巨木7~8、・祠2、・旗指石:昭和廿五年、
・農道和田線完成記念碑(水月院奥)
この農道を奥に進んでいくと林道俵峰門屋線終点に至る。
農道の反対側の道はすぐに真富士山登山口となって自動車道は行き止まりとなる。
・天神山△724.5m登山口(俵峰)
集落北にある山が天神山724.5mであるが、集落から直接登る登山口はなく、真富士山登山道を利用し、引き落とし峠で西尾根をたどると天神山に行けることになる。地図では集落から山の東側鞍部を越す道が記載されているが全くの廃道で道はない。
・竜爪山登山口、静清庵自然歩道(俵峰323)
穂積神社や一本杉に繋がっている。
・駒引(曳)峠への登山口(俵峰323)
先ほどの竜爪山登山口、静清庵自然歩道入り口に至る舗装された農道の1本手前に左折する舗装農道がある。これを100mも詰めると道は消失するが、その先に登山道がある。これがどうも駒引(曳)峠への登山口と推定される。広岡氏「東海道山筋紀行」にも記述されている道である。松浦武四郎も通過したのだろう。この登山道を登っていくと茶畑に出て、先ほどの農道和田線に出る。付近の茶畑2箇所には道祖神や石塔が祀られている。
・石:家:道祖神2、・石塔
道祖神がある辺りに松浦武四郎も通過した古い道があったのだろう。
更に先で林道俵峰門屋線終点看板があり、その横に石道標がある。
・石道標:右くろ川みち 左やまみち、 *刻字書体は楷書に近い少し崩しただけの行書で字の大きさも一定であることから、作られたのは近代の大正から昭和初期と推定したい。
農道和田線と林道俵峰門屋線終点脇に祀られるが、多少なりとも移転されてのことだろうから、こことは限らない。しかし300mほど林道を上ると小さな沢を渡った所で登山道が斜面を直登していく。これが現在の駒引峠への登り口で古道もこの付近を通過していたものと思われる。そこで先ほどの石道標も移転されたにせよ近い所にあったと思われる。
右の黒川道が駒引峠道であろうが、左の山道はどこの道か不明。
・駒引(曳)峠
・地蔵:「文政六未歳四月初八日 炭焼邑 俵峯 大平村」 *施主名略、1823年
・一本杉、 静清庵自然歩道、富士見峠の西側、一本杉の巨木
・地蔵:「文政六癸未年八月二十吉日 河内村」 1823年
~俵沢に戻る~
・常夜灯(俵沢28)
クリーニング屋の前にある。
・祠(俵沢25)
安倍街道新道と六番への旧道分岐点近く。
・石造物(油島22)
今の県道より上の集落内の旧道沿いに朽ち果てた石仏が設置されている。また油島公民館前にも石像物がある。よくぞ古びても安置してあるものだ。地元民の信仰心のあらわれだろう。
・石仏と石塔:欠:6、
安倍街道は玉機橋を渡り、梅が島街道(後述)は渡らず川沿いに北上する。
・菜流寺(油島122)
・石碑:菜流禅寺、・庚申塔 昭和五十五年、・庚申供養塔 文政六年、・燈籠4、・新:観音立像、・戦殉碑、・六地蔵 大正十辛酉年 延命地蔵尊、・三界萬霊塔、
・歯痛地蔵(中沢189-1)
玉機橋を渡ってすぐ左にある。右土手先に土手の神様(石仏)。その先を寺屋敷跡という。
県道は直進するがここで右の中沢集落、永倉栄太郎氏宅庭先の石は縄文石である。明治43年畑で見つけたものだそうだ。さらに奥の相淵集落を紹介する。
・白髭神社(中沢215)
杉の木は最高樹齢500年以上らしい。500年前に中沢には人が住んでいたらしい。神社裏山左斜面に穴がある。
・石鳥居、・杉:巨木、・社、
・白髭神社(相淵168-2)
・石鳥居、・杉:巨木、
・大志野山、中沢・池ヶ谷峠(中沢、池ヶ谷)
中沢からはかつての静清庵自然歩道コースとほぼ一緒であるが、峠付近で自然歩道コースは峠に向かわず、隣の鞍部の鉄塔のあるところを通る。つまり電線巡視路にそって自然歩道がついているので、昔の峠道とは違う。奥池ヶ谷へは昔の道は沢沿いに下るのに対し、電線巡視路コースは尾根沿いを下りまったく違うコースとなる。昔の道は今はおそらく廃道だろうし、静清庵自然歩道コースも今は使われず廃道寸前かもしれないが、電線巡視路なので通れるかもしれない。昔の道はかつての生活道路。なお石仏等昔のなごりは無いと思われる。大志野山へは峠や鞍部から稜線上を南に上ればよい。稜線上を北に上ると見月山に行けるはずだが、どれほどきれいか汚いかは不明。
中沢から県道に戻り西進する。県道北側尾根先端を中沢遺跡という。西山橋手前に馬頭観音。西山橋を渡った先、左にも石仏。
・新:地蔵(中沢27-1)
・石造物(金久保)
・?馬頭 明治□□、・庚申塔 萬延元年、・石塔:たぶん庚申系金剛像、七月吉日、・?馬頭:□□二、
・石碑(桂山649-1)
県道と集落内に入る道の分岐点にある。
・原の道 昭和四十二年 西一九六七年 お茶は本山桂山にかぎる 特に優れた味香り 玉川の流れの如く清らかに一致協力明日にそなえて 昭和四十二年一月開通 飛出すな一度とまって又あるけ、
・地蔵:山伏塚 昭和五十九年再建(桂山365-1)
・天桂山長光寺(佳山220)
・新:石:家:道祖神、・新:如来、・地蔵、・新:動物慰霊碑、・新:六地蔵、・鐘楼、・?青面金剛?不動、・新:水子地蔵、・公孫樹の木、・無縁萬霊等 寛政八丙辰天、・石塔、
・白髭神社、桂山神社、大吾上人、たんごさん(佳山56-2)
・石鳥居、・板碑:殉国英霊、・忠魂碑、
・板碑(佳山139)玉川公民館
・
・細木峠
桂山と湯の島を結ぶ峠で、それぞれの麓から車で林道をたどり、途中で登山道に切り替えて徒歩十数分の上りで到着できる。現在は杉檜の植林地で薄暗い。石仏があったかどうか覚えていない。
玉川橋を渡ると大日峠に行く旧街道と横沢経由で富士見峠に行く新街道に分岐する。
~落合経由大日峠、旧街道~
・石造物(佳山片瀬)
玉川中学手前左にある。 13年12月工事中で見つからない。下記石塔類と同一かもしれず、移転したのかもしれない。
・石塔類(奥ノ原737)
・燈籠、・△庚申 寛政八丙辰天、・?如来か観音、・常夜灯、
・石塔類(森越587)
・庚申塔、・□供養庚申文□、・石塔:無縁塔、
・旧道:596番地付近から奥の原に向けて山斜面中腹を回り込む登山道がある。墓地に向かう道で、多分奥の原と森越を結ぶ旧道と思われる。現在の県道より20mほど上である。
・潭月寺跡(森腰)
本尊:十一面観世音菩薩、
・石塔類(長熊上平700)
・?石塔3?墓石、
・白髭神社(長熊上平773)
・石鳥居:昭和十二年、・手洗石:昭和三年、・祠、・杉:巨木、・杉巨木切り株の中から樹齢50年ほどの杉が生えている。神社横は崖で崩れかかっている。
・普門寺跡
本尊:聖観世音菩薩、開山:1580年、
・林道栃木線、舗装されていて起点より1.4㎞先で行き止まり、
・祠:?馬頭:明和三丙戌□月吉日(堂原1998)
・堂原の長熊橋袂より2168番地に向かう歩道が山を回り込むように付いている。
・かつての静清庵自然歩道であり電線巡視路でもある登山道がある(長熊から奥池ヶ谷に至る手前)
現在自然歩道としては使われず、舗装県道を迂回して中沢から奥池ヶ谷に向かうよう標識が出ている。この電線巡視路が古道ではないが、その近くを通過できる道として参考になる。
・奥池ヶ谷城址(奥池ヶ谷54)
高圧鉄塔のある川に挟まれた丘上である。
・向陽寺跡(奥池ヶ谷)
本尊:阿弥陀如来、
・朝倉館跡(柿島)
かつて安倍七騎の一人、朝倉氏の出身地とされる。
・定林寺跡(柿島492)柿島公民館横
・お堂:本尊:瑠璃光薬師如来、 ・社、
・お堂(柿島530)
・地蔵:明治四十一年六月廿日
・曹源寺(長妻田25)
曹洞宗、本尊:聖観世音菩薩、開創:1508年、本寺:長源院(沓谷)。山門の仁王像はユーモアたっぷりなひょうきんな立像で独自の価値がある。
・新:観音像、・新:供養碑、・板碑?、・石塔?庚申塔?、・燈籠2:昭和十五年、・鐘楼、・新:石仏9、・石塔:曹洞宗松尾山曹源寺 平成二十年、・胸像:得仙大和尚、
・中平との峠道、旧道、古道(長妻田25)
曹源寺の裏の墓地上から電線巡視路が見月山稜線に向かい上っていく。かつて中平とを結ぶ峠道だった。中平から峠のある鉄塔までは行ける。稜線も歩いたという山行を聞くことはあるが、現在相当な藪と思われる。反対に柿島方面に行く道もある。
・祠(長妻田151‐1)
・地蔵、・六地蔵、・石仏、
・布沢滝
布張沢の奥にあるはずだが、直接行きやすい道がない。近くに高圧鉄塔があるので電線巡視路で近くまで行けるのではなかろうか。
・白髭神社(長妻田764)
・コンクリ鳥居:、
・養福寺跡(油野)
本尊:地蔵菩薩、
・白髭神社(上落合157)
・石鳥居:昭和八年、・手洗石:水の溜まる所の形が扇形である、・岩2、・祠2、・石柵:平成元年、
・石塔類(上落合149)
向坂橋袂。・地蔵、・庚申塔:明治三十八年、・岩、
~ここから仙俣、奥仙俣へ行く。~
・精進滝(口仙俣)
上落合から口仙俣への3分の2程の所の道路左沢崖上らしい。
・白髭神社(口仙俣)
仙俣川を渡った先で橋はなく丸太橋を通して渡るようだ。道路から川向こうの鳥居と石段が見える。
・涌泉寺跡(口仙俣256)
・お堂:本尊:薬師如来、市指文:鰐口:写真展示、・木魚、・鐘、
・分校跡(口仙俣)
口仙俣から奥仙俣方向へ向かってすぐ左、
・林道黒川線
・記念碑
奥仙俣の手前の吊り橋袂の岩上、
・祠2:水神(奥仙俣59)
仙俣川沿いの主要道から川を渡った向うの集落にある。10月7日が祭りだそうだ。
・石塔(奥仙俣180)
主要道沿いの集落入口、
・大石、・庚申塔 昭和五十年十月、
・白髭神社と記載されているが山神社(奥仙俣)
まだ再建間もない神社で本殿拝殿等新しい。10月7日祭り、ここに至る自動車道もできたばかりのようだ。
・祠2、・山神社参道開設記念碑 平成十六年九月吉日、・木鳥居、
・不動尊滝(奥仙俣)
奥に詰めていく林道とは別の北東に向かう沢奥にあるようだ。
~~~落合に戻る。~~~
・石仏(明ケ島76)
県道沿い民宿明ケ島への分岐点、
・石仏、・馬頭、・地蔵、・庚申塔、・馬頭、
・石:ペイントで記入:明ケ島、・石:ペイントで記入:♨口坂本温泉→ 民宿明ケ島、
・石仏(口坂本630)
口坂本温泉集落の橋手前分岐点に安置。
・口坂本温泉浴場:説明版:清らかに流れる渓流と緑まぶしい山々に囲まれ、市営浴場を中心に民宿、旅館が点在する静かな温泉地です。市営浴場には30人が入れる広い浴槽の他、日本庭園の中に露天風呂も整備され、日頃の疲れを癒す人たちが世間話に花を咲かせます。所在地:静岡市口坂本、利用時間:9:30~16:30(16:00札止め)、休館日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)年末年始12/29~1/2、料金:大人¥280、小人¥100、泉質:ナトリウム‐炭酸水素塩温泉(重曹泉)、
・八王子神社(口坂本527)
・説明版:鎮座地:静岡市口坂本527、御祭神:建速須佐之男命たけはやすさのをのみこと、例祭日:7月15日、由緒:創建不詳、元禄17(1704)年再建、更に寛政9(1797)年再建、昭和27年同地区鎮座の白髭神社を合併し現社殿の造営をした、元無格社、毎年7月15日安倍川まで神輿の渡御がある。安倍神楽の伝承がある。
・金属鳥居、・手洗石:大正十一年、・手洗石:苔むしている、・常夜灯2:御宝灯 慶應元年、
・宝積寺(口坂本53)
本尊:延命地蔵菩薩、開山:1347年、門前に地蔵祠ともう一つ祠がある。
・祠2:地蔵、・燈籠:元治二乙丑、・燈籠:道路改修 昭和四十二年 地蔵平より、・手洗石:水たまり扇形、・自然石石仏、・三界萬霊塔 昭和四十七壬子年、
~・口坂本から大日峠への旧道(大日古道)、稲荷神社祠及び井川本村まで~
・説明版:①歴史と文化の街道大日古道:大日古道は口坂本から井川に通ずる唯一の大切な昔の道でした。上り下り3里(12km)の細い山道で1町(109m)ごとに一尺三寸ほどの観音様が通行人の無事を願って立てられていた古い街道です。我々はこの先人たちの思いのこもった道を偲び、次世代へ伝えていきたいと願っています。
②井川に縄文人が住んでいたことは驚きだが、脈々と伝えられてきた多くの歴史がある。例えば中野の千手観音、田代の諏訪神社、薬師堂、小河内の金山、大井川の刎橋。そして数々の例祭、そこで舞われる神楽、暮らしの中の伝承から民話まで数えきれないほどです。たった半世紀前まで、こうした井川を支えた唯一の道が大日古道でした。
口坂本―十六番―水呑み跡―大日峠―一里塚―二本松―登山口―渡船・井川ダム湖―井川、
坂本から井川までの旧道にはかつて66の観音像(口坂本~大日峠33体、大日峠~井川33体、井川側33体は井川大日堂に全て安置保存。口坂本側は6体確認という。)が安置されていた。現在復活作業中で、この区間での旧道が通れる。この旧道は1958年に林道が作られるまで本道であった。口坂本村内に観音像1、庚申塔1、村入口の民宿明ヶ島前に石仏5(庚申塔、観音2、地蔵1、不明1、)、
入口は市営口坂本温泉前で先の歩道橋で川を渡り、民宿羽根田前を上り、人家はずれで左の畑に入る。
・一番観音跡:口坂本の人家のはずれから山に入る境目にある。石仏(観音、地蔵)が2つ安置されている。13年12月には石仏は移転した。多分明ケ島道路脇に移転合祀したものと思われる。
・二番~五番までは口坂本集落上に巻いて大日峠へ上る県道に寸断されるまでの500m区間にある。県道に出るとしばらく県道を歩き、この上の空人家の先で山に取り付き古道に入ることになるが、県道に出た所の延長線上に古道の跡は電柱と電線に沿い進んで行き、空人家手前の県道の辺りで消失する。なお県道に出た辺りの上に鳥居があり、稲荷神社の参道がある。やや古道からははずれている。
・人家の先で山に取り付く。ここから先にはまだ観音跡の標識は未設置。500m先でまた県道を横断し山に取り付く。しばらくすると十五番観音跡がある。この手前に左へ分岐し大草利に向かう山道が地図上ではあるはずだが不明。十五番を過ぎると植林地内に石垣がいくつか見られ、「十六番」である。老夫婦経営の茶店と田があった。うどんや惣菜を売っていた。700m進むと林道に出て、その先に石垣と水が湧き出る所がある。「水呑み茶屋跡」で確か二十三番?だったように思う。この先30番まである。林道右手裏はすぐに県道との合流点でゲートで閉じられている。湧き水横を上り、三十番までたどる。しばらく観音跡がないなと思えると、稜線に出て左(南)に「富士見峠、大日山ハイキングコース」と分岐し、それを過ぎるとすぐ先に、「お茶壷屋敷跡石碑」がある。
・大日峠、お茶壷屋敷跡、石造物
「富士見峠、大日山ハイキングコース」:富士見峠から大日峠までの稜線上の山道。途中三等三角点、大日山△1200.6mを通過する。またもう少し南の昔の大日峠跡も通過する。 「お茶壷屋敷跡」はかつて徳川家康が茶会用の茶を保存するために作らせた蔵である。実務を担当したのは柿島の庄屋、朝倉氏と井川の庄屋、海野氏である。この茶を駿府に運ぶための道中を再現したお茶壷道中が近年実施されている。なお蔵については再現か否か不明だが、このすぐ先のピクニック広場に近年蔵が建てられた。
ピクニック広場手前に「三十三番観音跡」、「大日如来堂跡」があり、石仏が祀られている。駐車場・公衆トイレ分岐にも「三十三番観音跡」がある。この33番は井川側の33番で大日如来堂側の33番は口坂本側のものだろう。
・井川側の大日古道~大日峠から井川渡船場~
ピクニック広場を下ると井川の三十二番、ピクニック広場入口で三十一番がある。舗装県道の大日峠から井川へのルートを横断する辺りが一里塚で二十五番となり地蔵が祀られている。さらに下の井川少年自然の家正門前の道を進んだ所は二本松という所でこの辺りに十七番と十六番があり、十八番観音が祀られている。この下は大日作業道に付かず離れずに古道は下っていく。大日作業道と数回交差して4番まで至る。この100m下が井川湖で渡船場になる。ここに一応1~3番標識があるが、説明看板には水没となっている。井川湖は井川ダムによりできた現代の人工湖なので、昔は存在しなかった。この湖の下に村が古道が遺跡が沈んでいる。井川側の古道は静清庵自然歩道、井川少年自然の家ウォークコース等に利用されているので道自体はほとんど利用されて残っている。すばらしいことだ。
かつて村の女たちも背負子や持ち子として30~50kgの荷物を背負って歩いた。
~井川近くの県道等主要道沿いを紹介し、井川につなげる~
・慰霊碑、地蔵(井川3179)
県道の富士見峠を井川ダムに向け下り、大沢度橋を約1㎞過ぎた道路脇。
・慰霊碑:地蔵:昭和41年4月1日 行年49才 故関谷正重霊(車需)之地 故森竹さわ江跋畢之地 行年17才
・井川五郎ダム(井川1955) 調査:’14 3/15
昭和32年完工、コンクリート代を節約するため、ダム内部は空洞で中空式と言われる。
・井川展示館:水力発電の仕組み、井川地区紹介、井川地域の筏流しや電源開発の歴史等紹介。展望もよい。ダムが昭和の資料といえる。
展示館内にパネル写真の展示あり。09年2月公開映画『ヘブンズ・ドア』監督:マイケル・アリアス、主演:長瀬智也、福田麻由子、106分、厳寒2月の3日間、井川ダムにてロケ、公開が2月なのでロケは多分08年2月と思われる。井川ダム内部が数分にせよ見られるようだ そのパネル写真展示。
・井川水神社{祠、鳥居}、・石碑:井川湖、・板碑:慰霊碑:昭和三十二年、
・井川遊歩道
井川ダム建設時に使われた線路跡を遊歩道として13年秋に再現開設された。井川ダムから井川本村堂平まで歩ける。距離800m。近くに夢の吊橋がある。
・井川駅(井川1959)
ダム建設のために作られた鉄道で、一回り小さなトロッコ機関車の終点駅、もはやこれも昭和の生き証人か。この駅の奥にはかつてトンネルがあり、トンネルを抜けた先が堂平への遊歩道となっている。
~川根路~
・大井神社(井川閑蔵2246⁻3)
かつての閑蔵林道今は県道を川根本町千頭方面へ下り閑蔵駅前で閑蔵の集落へ下っていくとある。
・金属鳥居:、・子安観世音:大正十五年七月、
・説明版:鎮座地:静岡市井川2246‐3、祭神:岡象女命みづはのめのみこと、例祭日:1月2日、由緒:元禄元年創建と伝えられる。
~井川に戻る~
・石仏(井川西山平1850)
・石仏:青面金剛?、丸石:道祖神?、休憩所の横の交差点にある。
・井川大仏(井川1551)
・井川大仏、・毘沙門天立像、・石碑:大仏開眼:油山寺貫主、・コンクリ石碑:昭和五十五年、
・説明版:一刀二礼仏の手法にならい一言一言唱えて作像された。一切如来、井川大仏は昭和55年11月1日湖畔の丘、金畑山公園望寿台標高772m、日本地図の中心部に誕生した。
毘沙門天は福の神として七福神に数えられまた四天王として仏法の守護神とされ古くより親しまれてきた神であり仏である幸運守護の御尊体であります。
・庚申塔:天明五 門間 青面金剛
井川大仏分岐点と門間の間の県道側壁にある。
・龍泉院(井川582)
・石碑:曹洞宗龍泉院:平成十四年、・燈籠、・板碑5、・新:葷酒山門に入るを許さず、・禁葷酒、・山門、・新:句碑:多数、・仁王像2、・故篠原荘夫翁記念碑、・・新:無縁菩提供養塔、・石家道祖神、・鐘楼、・新:常夜灯5、・新:六地蔵+1、・新:子育地蔵、・新:観音、・青面金剛、・新:地蔵、
・説明版:開基は1504年(永正元年)賢窓常俊禅師に依る。草創期の頃は現在地より約200m「薬澤」寺地の一角に建てられていたと言われる。崇信寺末寺の平僧寺として創建されたものだが、その後災禍等もあり、また適地として現在地に室町末期1544年(天文13年)頃移築された。長歳月の中では老朽化激しく、寺歴に残るような修復等を重ね現在のような姿で承継されている。開基禅僧の賢窓常俊は、怒忠天誾(信濃の人) 崇信寺。洞慶院の開山僧に得度し、後に石叟三派の名僧を育成されたといわれる大厳宗梅禅師(崇信寺3世、本院隠居寺の千光寺開山僧)に師事し後に宗派最高の総持寺貫主に昇り、その後崇信寺。洞慶院4世等の住職になった高僧である。かような高僧開基による本院も戦国末期から徳川初期にかけ代々受け継がれた高僧たちにより、大井川流域に本院の流れを汲む末寺九ヶ寺を有する(うち五ヶ寺は現在廃寺)格式の高い寺院にまで発展した。本院も、かつては信州今川氏に仕え後に井川領主となった安倍大蔵守一族の手厚い保護や檀徒(500有余)の貢献等によるものが大きく、今や草創期以来500年近い歳月を経て今日に至っている。
2002年2月吉日建立 龍泉院29世王竜徳潭比丘謹書
本寺院の概観
本尊:聖観世音菩薩 昭和53年修復、脇仏:地蔵菩薩 平成12年修復、大権修理菩薩
開山堂 当山開山賢窓常俊像、宗祖 道元禅師像 聖観世音菩薩像、達磨大使象、
大日如来像
建造物 山門 寛保3年建立、鐘楼堂 昭和30年3月建立。大鐘 昭和30年3月、
六地蔵菩薩像。堂。平成12年、無縁墓地造成 平成12年秋彼岸吉日、
・門間地蔵堂(井川門間557)
門間の集落内の旧道沿いにある。
・常夜灯、・常夜灯、・地蔵:元禄三、・地蔵、・二地蔵:六地蔵の一部?、・三地蔵:六地蔵の一部?、
・井川神社(井川1467)
・コンクリ鳥居2、・燈籠2、・燈籠2、・狛犬:立太子20年記念、・手洗石:嘉永六、
・説明版:鎮座地:静岡市井川1467⁻2、御祭神:瀬織津比(口偏に羊)神せおりつひめのかみ、外19柱、例祭日:1月3日、由緒:昭和33年4月14日井川ダム築造により、次の5社を合併して井川神社を設立した。①大井神社、嘉禎4年創建、②浅間神社、創建年不詳、③大頭龍神社、創建年不詳、④山神社、創建年不詳、元禄7年再建、⑤十二神社、創建年不詳、元禄13年12月再建。井川神楽の伝承あり。
・大日院、中野観音堂(井川1120)
大日古道の33観音が保存されている。
・金属鳥居、・祠:八幡宮:、・祠:秋葉大權現 神明大神宮 津嶌牛頭天王、・燈籠:秋葉大權現、・燈籠:津嶌牛頭天王、・地蔵5、・観音:約40(三十三観音とその他、大日古道の33観音?)、・石塔:欠:多数、
・中野観音堂:説明版:中野は、江戸時代には井川七ヶ村の一つに数えられ、古くから砂金の採取が盛んな集落として知られていた所です。この観音堂は別当、副別当の2軒を中心とした中野地区の人々によって大切に守られてきました。堂内にはご本尊である「千手観音立像」の他4体の仏像が安置されています。いずれも針葉樹による一木造りで、平安時代中期に制作されたものです。仏像の由来についてははっきりしたことが分かっていません。地元では先祖が井川まで背負って運んできたと伝えています。その際里芋を食べながら峠を越えたとも云われており、観音堂のお祭りでは今でも里芋に味噌をつけた芋田楽が参詣者に振舞われます。観音堂のお祭りは1月6日と2月7日の2晩行われます。かつては一晩中お堂で過ごしたことから、このお祭りのことを「お籠り:おこもり」と称しています。そのうち1月6日は1年に1度、ご本尊が御開帳される日です。今では6日の晩に御開帳が行われていますが、かつては一晩おこもりをしたのち、1月7日の早朝、太陽の光が射し込むわずかな時間だけご本尊を拝むことが許されたそうです。その他、中野観音堂に残る応永31年(1424)の鰐口も静岡市の有形文化財に指定されています。
静岡県指定有形文化財:「木造千手観音立像・木造伝十一面観音立像・木造伝十一面観音立像・木造菩薩立像・附木造菩薩立像」、指定年月日:平成17年11月29日、制作年代:平安時代中期(10世紀後半から11世紀前半)、指定理由:いずれも平安時代中期の作で、後補も見られるが、全体的に古い様式を残している。駿河山間部における古代の仏教文化を考える上でも貴重な彫刻である。
静岡市指定有形文化財「鰐口:わにぐち」、指定年月日:平成20年3月26日、内容:面径22.0㎝、厚さ9.5㎝、銘文によれば応永31年(1424)11月に中野観音堂に施入された。指定理由:現在所在が明らかで銘文に静岡市内の地名が見られるものとしては最も古く、静岡市の文化史上貴重なものであると共に、歴史的意義と価値を有するものと判断される。
平成23年3月 静岡市(文化財課)
・井川メンパ(井川971)
海野宅
・南アルプス絵本館(井川991)
新しい公共施設なのでそれ自体が古道と関係しているわけではないが、井川地区の資料が手に入る。
・交通事故供養塔(井川中野)
県道沿い中野、登沢橋より北へ500m。
・事故多発所 南無妙法蓮華経 交通事故 遭難者 供養塔 安全運轉 昭和四十年
・石碑(井川)
さらに北上すると県道沿い。
・石碑:滝浪兼政青山之地
・不動尊堂(井川岩崎中山680)
県道沿い、中山バス停近くの沢滝横にあり。
・お堂:不動尊
・地蔵堂(井川大島54)
大島バス停前県道沿い。
・地蔵4、・祠:不動明王、
・大島神社(井川・田代・割田原260)
割田原の井川湖湖底に縄文期の割田原遺跡がある。他にも遺跡跡がいくつかある。
大島橋を渡った先にある。現在の橋の隣に以前のコンクリ製橋脚が残っている。
・金属鳥居、・燈籠、・祠2、
・説明版:鎮座地:静岡市田代260、御祭神:素戔嗚命すさのおのみこと、例祭日:1月11日、由緒:通称お天王さん。慶長9年創建、元禄13年、宝永、嘉政、文政と再建造営のあと、現社殿は明治35年総欅材を以て造営された。元無格社。境内は「鎮守の森」に相応しく古木が生い茂っている。井川神楽が伝承されている。
・大井神社(井川・田代・割田原329⁻2)
県道沿い階段上にある。この上の台地にかつて井川北小学校があった。
・金属鳥居:平成三年、・燈籠1、・祠、
・説明版:鎮座地:静岡市田代329⁻2、御祭神:岡象女命みづはのめのみこと、瀬織津姫命せおりつひめのみこと、例祭日:1月15日、由緒:文禄元年勧請、同3年8月大井川大増水により流失し、寛永5年新社地に再建、宝永、明和と再建したるも、明治20年3月4日出火による類焼、仮社殿にて奉祀し、昭和35年4月26日井川ダム築造により湛水池に入り、本殿、拝殿、社務所造営の上現地に遷座した。元無格社。田代、岩崎両集落の産土神であり明治維新までは大村家が祠官職にあり、井川神楽発祥のお社である。
・田代集落内外の道(井川・田代)
オーミチ(大道)、梅の坂、堂の坂、南坂、別当坂、菅山街道、集落南旧道入口には秋葉常夜灯がある。集落西には天神2つあり。福寿院跡。手洗い井戸。旧道と新道北側出会いを薬師道。集落北東に共同墓地と水神。集落南端からの旧道は南坂で山へ続く。西の沢へ入る辺りに山神を祀る。
・秋葉常夜灯(井川田代762)
集落入口にある。形は常夜灯というより燈籠型だが常夜灯と刻まれている。
・常夜灯:大正十四年、
・石仏(井川田代681)
集落北端近くの辻
・二地蔵、・二地蔵か双体道祖神
・諏訪神社(井川田代855)
集落北端に鳥居と湧き水があって諏訪神社への参道入口となっている。また自動車道とは別に薬師堂に向かう歩道が延びている。この歩道は旧道(古道)と思われる。
小無間山登山口、県・無・ヤマメ祭り、神楽、雨乞い踊り。8km奥に普段禁猟区の明神谷があり、ヤマメ祭り用のヤマメを釣りに行く。市・建・田代の一間造りの民家、
・石鳥居:昭和四十八年、
・説明版:鎮座地:静岡市田代855、御祭神:建御名方命たけみなかたのみこと、八坂刀賣命やさかどめのみこと、例祭日:8月26・27日、由緒:信濃諏訪大社の御分社、嘉禎4年創建、神主諏訪權守が奉祀、享徳2年再建諏訪刑部奉祀、文禄、延享と再建、諏訪近江守が奉祀、現社殿は明治36年の造営総欅八棟造本格的神社建築である。閏年毎例祭日に神輿の渡御あり、特殊神饌魚釣祭、ヤマメ(魚に完)の粟漬、元郷社、明治維新までは海野家氏神であった。信州遠山より大井川支流信濃俣川を経て当地に来たと伝えられる。
・駿河田代諏訪の霊水:説明:この湧水は静岡市指定無形民俗文化財当社特殊神饌ヤマメの漁場明神澤水源御住池よりの伏流水にて4年に一度閏年毎8月26日神輿渡御の際右側の石積みは御旅所の台座であり、ここにて大神に霊水を献ずる。
昔からどのような渇水にもこの湧水は絶えたことはなく、里人はここにて若水を汲み年始となす貴重な生活用水でお井戸と称し親しまれ、また大小無間の登山者の必需水である。
水質検査の結果最優良水と確認されており、呑めばまろやか活力を生み、井川銘茶をこの水でたて、或は冷凍の上水割等に用ふれば、その味また格別なり。広く御愛用をお奨めします。
神社はここから徒歩にて約20分諏訪山頂にあり、この霊水にて身を浄め清々しいお気持ちにて御参詣下さい。
氏子は常に神社の護持運営に努めております。その費の一部として霊水御愛用の方々より何分の御奉賛を賜りますれば幸甚の至りに存じます。 諏訪神社社務所
・集落北端から山に向かって参道登山道が続くが、先ほどの常夜灯地点から林道で山上の諏訪神社本殿にも行ける。参道は一旦林道で断ち切られるが、林道を横断して又歩いて登れる。
・第二木鳥居:平成六年、・手洗石:一九二六年、・常夜灯2:大正十五年、・祠5、・杉巨木:御神木、・参道途中から大無間山、小無間山への登山道が分岐する。もしも車で来て登山するなら、神社本殿横の駐車場が広いので、そこに車を置くとよい。
・薬師堂(井川田代855)
集落北端より100m北。歩道もここに出る。
・常夜灯:昭和四年、・祠、
・外山沢山神社(井川田代)
県道南アルプス公園線沿い、畑薙6号トンネルと外山沢橋の間。
・石塔類(井川小河内)
小河内大橋を渡って小河内集落入口手前、
・地蔵2、・燈籠、・庚申塔:昭和五十五年、・道しるべ:静岡小河内雨畑線 山伏峠まで17㎞昭和55年、
・井川・小河内集落内外の道
堂の坂、井戸坂(井戸道)、イワン(ニワン)坂、上の道、下の道、コーギ道(ダシ山街道)、金山道(金沢金山道)などがある。南甲斐への道、南信濃への道、梅が島温泉への道がある。建正寺跡。
・井戸(井川・小河内)
湧き水、生活用水。
・阿弥陀堂(井川・小河内)、三十三観音、無縫塔
集落北端の共同墓地近く。三十三観音と無縫塔、他2体は埋もれていたのを掘り起こした。年号は「享保十年」「嘉永六年」「嘉永七寅」で1725、1853、1854年である。近くに八幡社。市・地登・小河内のヒヨンドリ、
・庚申塔、・燈籠、・地蔵2、・無縫塔、・三十三観音35、丘上で展望所。
・大井神社(井川・小河内32)
・石鳥居:昭和六十三年・平成元年、燈籠2:昭和十三年、
昭和46(1971)年遷座。
・説明版:鎮座地:静岡市小河内32、御祭神:弥都波能賣命みづはのめのみこと、例祭日:2月11日、由緒:創建不詳。棟札によれば、天正12年霜月火災により社殿焼失、87年後の寛文4年、宝暦3年、嘉永2年再建造営された。旧鎮座地井川ダム築造により、境内南側に崩潰を起こし危険な状態になり、昭和46年現地に移転した。元村社。閏年毎に例祭日に神輿渡御あり、井川神楽の伝承あり。
・小河内橋(井川・小河内)
現在の小河内大橋は昭和43(1968)年からでその少し下流に残る橋がこれで昭和28(1953)年から43年までとなる。その前は2つの橋の中間に昭和5(1930)年~28年まであったようだ。2014年3月この橋はない。この橋に行く袂付近に石塔類がある。
・石塔(井川・小河内)
・供養碑:昭和八年~昭和五十年、・板碑:遭難碑:明治四十年、・地蔵6:明治二十二・三十・三十九・四十二・昭和十二年・不明、
・地蔵:明治七□年弐月
集落奥はずれの林道井川雨畑線と林道小河内川線に分岐する手前の橋「小河内橋」(先ほどの橋と同名だが別橋)袂に安置。この背後の山上にも2通りの山道が分岐している。
・「林道井川雨畑線」の思い出
かつての静岡市の小中学校社会科用補助教材郷土資料冊子には林業や観光の為この林道を作った旨が記されている。それ相応の期待があって作られたようだ。
1980年代末、当時まだ舗装されていない頃、この林道をオフロードバイクで突破して山梨県側に抜けるのは至難の業というか、よほど運がよくないとできないことだった。四輪車では更にチャンスが減ってしまう。例えばこんな具合だった。林道に入って進んでいくと崩壊崩落していて道幅が1mしかない所がある。(だから四輪車ではチャンスが減るのです。)ある所では前方の道が島に見えた。どういうことかというと側壁上の崖が塊のまま崩落して道路上に塊のまま落ちているというか、樹木や草が生えたまま地面ごと道路上に載っているのでまるで道路上に島が浮かぶかのようだったのだ。数本の樹木は倒れていたが、数本は立ったままでいた。それをかいくぐるのが大変だった。それやこれやで県境の峠を越えて山梨県側に抜けてホッとしていたら、前方の橋手前の道路が、何か変なのだ。ブレーキをかけつつ進んで驚いた。橋手前の道路がすっぽり抜けて、道路や橋地面と同じ色の川水が流れているのが見えていて、何か道路の地面が波立つような乱反射するように見えたわけだ。それにしても道路の色と川水の色が全く同一に見えることも驚きである。橋の手前に河原に降りていく非常用道路が造られていて、川水のある所は土管を通して水を流し、その上を通過できるようになっていた。とても道路と言えた代物ではない状況が多かった。それがひとたび土建業者が入って道路整備すると、全く別物の道路のように快適に走れるのだ。ただそのように快適に整備されるのは少ない機会だし、ひとたび豪雨や台風が来ればあっさり半年や1年は通行不能の崩落崩壊である。近年静岡県側は舗装したが、だからと言って崩落崩壊が起きにくくなるとは思えないので大変なことだろう。山梨県側も大丈夫とは限らないのでいつ全線通行できるかははっきりしないだろう。県境の峠は大笹峠または山伏峠ヤンブシH1850mという。峠から山伏山頂△2013mへは徒歩20~30分であり最短時間登山路である。使用オートバイ:HONDA XL200R
・供養塔:昭和五十九年12月21日遭難 瀧浪武雄
林道小河内川線を1㎞進んだ所。
・雷神社(井川・上坂本239)いかづちじんじゃ
・金属鳥居、・祠2、・石家道祖神2、
・説明版:鎮座地:静岡市上坂本239、御祭神:別雷神わけいかづちのかみ、例祭日:1月7日、由緒:永政元年正月17日創建と伝えられる。元村社。江戸時代笹山金山の守護神として崇敬された。昭和36年11月27日同地区鎮座の山神社を法人合併されている。
・八幡神社(井川・岩崎)
・祠、・石碑:高祖王様:昭和三十□年、一王様は八幡神社に奉戴来~~~
14年3月岩崎地区には2軒家があるが住んでいる気配がない。
・井川峠(県民の森)
かつての生活道路。 現在ハイキングコース。
~横沢経由富士見峠、新街道~
・地蔵4(下平瀬)
下平瀬手前県道右上に安置。
・林道日蔭山線
・白髭神社(下平瀬)
・石鳥居:昭和四十八年、・岩、
・新:地蔵2(下平瀬1349)玉川園
・白髭神社(川島1434⁻2)
・石鳥居、・手洗石:明治十四年、・コンクリ燈籠、
・林道樫の木峠線(川島)
現在川島より起点となり、樫の木峠を越えて大川日向に至る。古道ルートについては下記の林道白石沢線を参照。
・玉川西公民館(大和8⁻5)
・二宮金次郎像(薪背負って読書)、・石碑:玉川西小学校跡、・卒業制作石膏像、
・?祠か社(大和951)
・石:家:道祖神(大和838)
・林道権七峠線(大和1037)起点
林道を300mも登ると愛宕神社がある。林道は3~4kmも進むと工事中で、その先を作っている最中だった。14年2月。
・愛宕神社(大和1037)
・手洗石:文政十二丑年(1829)五月吉日、・石鳥居、1829年、祠、
・馬頭(大和1037)
道路脇茶畑上に立つ。
・馬頭:明治十一年 岡田彦太夫建之、隣の家が岡田家である。1878年、
・庚申供養塔(大和1029)
・庚申供養塔 安永八巳年 亥十月吉日 安倍郡 寺尾邑中、1779年、
・石塔類(内匠256)
大和から内匠に進み、白石沢に架かる白石橋の手前県道左に安置。
・西国、・?、・庚申供養塔 安永七(1778)、・?馬頭、・?馬頭、・?観音:安政四(1857)、・?馬頭、・地蔵、・?観音:文政十弐(1829)、・奉巡礼、・南無阿弥陀佛、・馬頭、・石塔、
・林道白石沢線、樫の木峠(内匠256、白石沢)
県道の白石橋を渡るとすぐ左に林道白石沢線の道と標識があり、そこに海野家がある。
1980年代末、林道白石沢線を進み、行き止まりから徒歩で進み、丸彫りの石地蔵を右折し進み、沢へ出て地蔵(不明、海野家の老女が話していた、登山後私が見ていないというと、無くなったのかもしれないと言った、沢沿いにあったのなら流されたのかもしれない)を横目に渡り、斜面を上れば樫の木峠で、樫の木と石地蔵がある。現在林道樫の木峠線ができたのでこの旧登山道は使われずほぼ廃道と推定される。林道樫の木峠線は内匠手前の川島から上って峠を経て大川につながっているが、峠手前が厳しい斜面で崩れやすく車でいつも通れるとは限らない。なお峠から大川までには萩多和城址石碑、宝剣神社祠が見られる。林道なので旧登山道ではないが、峠よりかなり下の方の旧登山道は現在も使われている。かつては大川と内匠を結ぶ生活道だったろう。
上述は1980年代末の記述で2013年12月には現状が改変された。林道白石沢線は100mほど延長され、かつての石地蔵のあった分岐点が林道終点広場のようになった。ここに林道入口一軒家の海野氏により観音を幅50㎝の土管に入れ祀り直した。
20年以上前に見たのは確かに丸彫りの石地蔵もあったはずだが、今回観音(観音か馬頭)像しかないのはなぜなのか海野氏に聞くことができなかった。県道沿いの石塔類の中にもなかった。
・?観音か馬頭:□□□□(?右わらしな)ミち □□□□ミち:多分右左の行き先を明示していると思われるが判読不能、多分右が樫の木峠で大川日向村、藁科川、左は中村山、釜石峠、長嶋、栃沢、美和、足久保方面である。
このルートでの遡行を近年(2000年代)行ったものでは、広岡氏「東海道山筋紀行」に詳しい。峠直前は完全な薮だったようで大変苦労したようだ。帰路は二度と通過したくないのであえてこのコースをやめているほどだ。広岡氏が通過したのは松浦武四郎が通過しているからである。
樫の木峠より向うのコースは別項目「大川街道」を参照してください。
・白髭神社(内匠648)
・コンクリ鳥居、・手洗石、・公孫樹、
県道から東橋を渡ると下腰越集落である。
・馬頭(下腰越43)
・?馬頭、・?馬頭、
この馬頭の祀られている所から歩道が川沿いに延び吊り橋を渡って奥腰越につながっている。ちょうど県道とは反対岸である。このルートが古道と思われる。
・白髭神社(下腰越90)
・石鳥居:紀元二千六百年紀念 大正十五年、・燈籠:昭和十五年、常夜灯:安政四(1857)、・手洗石:文政六(1823)、・杉:巨木切株、
・神社(奥腰越639)
・お堂:地蔵、・常夜灯:安政五(1858)、・石塔、・供養□□、
・白髭神社(大沢259)
・石鳥居:平成十八年、・杉:大木数本、巨木ほどではない、
・寺院跡(大沢286)大沢公民館
・葷酒不入寺内、・四国西国秩父□□八十八所供養塔 明治二十亥(1887)年四月癸日、・?青面金剛か不動明王:文化二(1805)年丑二月吉日、・庚申供養塔 皇紀二千六百年記念、
・大沢縁側カフェマップ(大沢)
大沢ではおもてなしとして大沢縁側カフェを毎月第2,4日曜日に開催している。集落入口にそのマップが掲示されている。
・祠:馬頭(大沢)
・馬頭:明治四十四(1911)年十月、・馬頭:文化十弐(1829)年、・馬頭:明治三□□年十二月、
大沢集落を過ぎ茶畑農道を一番上の奥に詰めた所に祠と石仏がある。
かつてはここ大沢から上り大岳の鉱山や笠張峠に出ていた。今でも登山道はあるが、車では行けない。なお大岳へ直登する道は頂上間近でなくなり、あとは稜線を行く。
この馬頭観音がある所を直登するのが多分旧道古道と思われる。これより上には登山道が延びていて、登りきると笠張峠から伸びてくる林道大岳線に接続するかと思われる。そのルートが旧道と重なると思われる。
この馬頭観音こそが大沢から笠張峠を越えて馬で井川に通じていた証拠である。
・石造物(横沢61)横沢集会所、小学校跡地
・地蔵2、・石碑:静岡市在住横澤會、・大石3、
・御嶽神社(横沢156⁻1)
東側から上った所。
・石塔、・地蔵、・(梵字)庚申供養塔、
西側から上った所。
・馬頭、・馬頭:明治五年、・馬頭:辰八月、
手前は墓地で神社は本殿があるだけ。
・燈籠(横沢291)
以前の長倉商店前の5m丘の上、以前の横沢バス停前。
・臥龍(権現)滝
県道から見られる。水量が豊富である。臥龍滝と名づけたのはかつての県知事である。
・一本杉峠
県道をさらに上った左手に電線巡視路、一本杉峠線があり、大川諸子沢に出られる。かつての生活道であり、今は登山道、電線巡視路である。
・笠張峠
大日峠に変わって使われるようになった。今では大川大間への分岐点となっている。尾根を通って林道大岳線沿いに大沢に出るのが古道ルートである。明治以前にも使われていたようであるが、発祥や推移は不明で、笠張峠からいかにして井川に出たか不明? おそらく三ツ峰付近へ出て井川または梅地方向へ尾根伝いに下ったのだろうか。また三ツ峰付近から大日峠へ尾根伝いに行くルートもあったと思われる。笠張峠から三ツ峰を省略して大日峠に行こうとすると大体今の自動車道ルートと同一化するので旧道を改変することで今の自動車道ができているのではなかろうか。
地図上での記載は標高1057mだが、大間と横沢、富士見峠に県道が分岐する地点では標高1100m。かつては大沢、大間、井川への分岐点であったし、今も分岐点である。標高がずれるように今と昔では分岐地点が違っている。
・富士見峠(井川3115)
現在の県道の峠で、休憩所、トイレ、駐車場がある。現在はここから尾根上の遊歩道で大日峠に行けるし、少し西下に自動車道も通じている。ここから登山道で三ツ峰にも行くルートがある。三ツ峰から七つ峰にもルートが延びている。
笠張峠と大日峠を最短で結び三ツ峰を省略するとおよそこの富士見峠を経由することになるので、この辺りを旧道は通過していたのではないか。
県道「南アルプス公園線」沿い、標高1184m、駐車場とトイレがあり、展望所にシンボル碑あり。三ツ峰(H1350m)へのハイキングコース入口があり、ほどほどの登りなので自然散策を楽しみたい初心者向けである。ちなみに北方にある現在の大日峠(口坂本温泉から井川へ行く県道越え)は標高1150m。
~油島からの梅が島街道~
・旧県道舗装街道(油島と蕨野の間)
河原土手の今の県道右崖上に昭和期に使われていたアスファルト舗装県道が一部残存している。不動沢橋付近に道祖神が祀られている。
・本山茶の茶祖 聖一国師墓所(蕨野24)
説明版:聖一国師は藁科川の上流栃沢の米沢家に生まれ神童の誉れが高く、栃小僧(頓智)と呼ばれていました。五歳の時久能寺堯弁の弟子となってから、蕨野仲野播摩正の家にしばしは手習いに来ていました。嘉禎元(1235)年宋に渡り禅を究め、仁治元(1240)年帰国しました。その時茶の種を持ち帰り足久保や蕨野に植えました。当時僧の中には医療に携わる者もあって喫茶が養生法の一つにあげられ、茶は医薬としてたいへん珍重されました。江戸時代には将軍家の御用茶として、茶壺に納めて、お茶壺屋敷に保管し、お茶壺道中で警護されながら駿府や江戸に運ばれました。安倍川上流一帯は茶の適地として良質の茶を産するので、つくり初め本、味の本場であるということから「本山茶」の名が自然に生まれました。このように聖一国師は「本山茶」の種を安倍川筋にまいて、静岡茶を日本一にする基をつくったのです。国師墓所の寺号「医王山回春院」は茶の医療効果と結び付けて付けられたのでしょう。ここに「本山茶」の茶祖として聖一国師を讃え顕彰いたします。昭和54年4月、聖一国師顕彰会 平成21年1月改修、
・回春院(蕨野103)
無住、聖一国師墓。
・地蔵、・尼□□□申塔、・三界萬霊十方至、・當院開山救證(了不)聖一国師大和尚 弘安三庚辰(1280):この墓石が1280年のものではなく数回再建されてきたのだろう、
・城山(蕨野)
蕨野から吊り橋を渡った対岸の山は中世山城跡。
・大聖不動明王堂(横山)
八重沢川を500m遡ると左(南)岸にある。
・白髭神社(横山75⁻2)
・石鳥居:昭和五十八年、・手洗石:昭和十五年、・燈籠2:昭和十年、・燈籠:昭和十一年、・燈籠:昭和五年、・燈籠2:昭和十一年、・板碑、
・石塔、墓石(横山35⁻3)
・?墓石、・庚申供養塔 文政八(1825)、・祠、・地蔵、・?馬頭、
・小川地蔵(横山)
水難除けの地蔵で焼津市小川が発祥のものを分祀してある。
・馬頭観音(平野)
平野入口県道右側壁安置。今はない。引き揚げたようだ。下記観音堂入口に再設置。
・観音堂(平野)
原橋手前東側に近年設置された。
・馬頭:昭和十四年、・馬頭:昭和十八年、・燈籠、・紅葉、・樹木
・手作りの石灯籠:説明版:この石灯籠は長い歴史をもった由緒のあるものです。代々栄えた大家の庭にあったものです。石工がタガネを打って造形した手作りで見事な風格をたたえています。お堂との落ち着いた風情が庭園の見どころとなっています。
・観音堂:説明版:聖観音菩薩像:江戸初期1600年頃:堂の中央に安置するのは聖観世音菩薩の像です。眼光の鋭い目から放つ光は苦しみ悲しみ悩み事など苦労の様々を観音様自身が受け止めて下さり、慈悲に溢れたひとすじの光となって私たちの心の中に力強い力を与え下さるのです。観音様はいつまでも健康長寿、安らかな永遠の旅路まで加護下さいます。阿弥陀如来:室町1540年頃:堂の右側に安置する阿弥陀如来様は体長60㎝と小柄ですが、なんと重さは70㎏もある像です。この如来様は日頃の悩みや苦しみの一つ一つを重い体重で踏みつぶして取り去ってくれるのです。この如来様は踏みつぶし如来と呼ばれ穏やかに見守って下さっています。心からの礼拝で必ずや願い事が叶えられるでしょう。
・地蔵(平野164)
集落内分岐点の祠に安置。
・大村家住宅、カブト造り(平野1052)
・国登録有形文化財 文化庁、・景観重要建造物、茅葺屋根の一風変わった屋根の形をしている。兜に似ているのでカブト造りと言われるのだろう。カブト作りの屋根は見応えがある。
手前の道路脇に五輪塔2基の古い墓石がある。
・平野の盆踊り
平野の盆踊りは県指定無形文化財。
・石碑(平野481⁻2)
・石碑:礼場椿道 開通記念 平成元年、
・白髭神社(平野112)
・石鳥居:大正十五年、・角柱型燈籠3、・燈籠2:大正十年、・板碑、・社、・祠、・杉:巨木、
・少林院(平野504)
境内入口に石道標(再建)「右ひらの 左もろおかむら」とある。もろおかむらは末高山周辺の村岡村むらおかむらのことだろう。
・庚申供養塔、・庚申塔 昭和五十五年、・新:百度石、・新:経塚、・燈籠:大‣中、・燈籠4、
・仏足石、・真富士観音第一番、第二十九番、・不許葷酒入山門、・学校発祥地、・石道標:少林禅院 左もろおかむら 右よこやまむら、・その他、
・真富士三十三観音
少林院に第一番があり、第二真富士山山頂に第三十三番が安置されている。第一真富士山山頂に第三十一番で、第二真富士への途中に三十二番がある。第二番は寺を出てすぐに曲がった所にある。登山道沿いにあるため、林道だけを通過してもすべて見られるわけではない。戦後の昭和三十年代にハイキングコースが設置されたのを機に安置された。第一真富士山頂の手前に真富士神社がある。
14年10月現在、第一番は県道沿い平野バス停横に安置されていた。
ふりかけ食品メーカーに真富士屋があるが、経営者が当地出身だからである。
平野集落を出て真富士山方向へ林道を進むとすぐに左下に茶畑がある平坦地がある。黒部沢河口の平坦地でもともと集落はここにあったと言われているが、黒部沢に土石流が押し寄せたため上に集落を移したらしい。
・朝日滝(平野)
集落県道から対岸に見えるが、滝に行く道はない。
・不動滝、不動尊堂(平野)
中学校裏手にあり、歩道がついていたが、崖崩れ対策で不動滝周辺一帯を高いコンクリ壁で覆い尽くしたため、全く滝を見ることができなくなった。もはや見たり遊んだりすることは不可能である。よじ登りかいくぐれば可能ですが…
不動明王堂はコンクリ壁手前に再建されてある。
・?角柱型燈籠、・石:奉納、
・末高五輪塔、末高館跡(平野)
大河内小中学校右手(北側)の山上(末高山)の茶畑内にあり、歩道がついている。館跡という。末高氏は安倍七騎の一人。子孫は東京在住という。この下の県道カーブを地元民は末高山のカーブと呼ぶ。
・五輪塔2、その他の墓石多数、
・白髭神社(中平343)
中平の集落は現在の県道より上の旧道(通行不可)のそのまた旧旧道沿い及びそれより高所にあるため県道からは一部しか見られない。現在の県道がほぼ河原に作られたため人が居住できる場所ではないからだ。街道が新しくなるたびに下に移転したため街道のダウンムーブメント現象の好例として観察できる場所である。
・石鳥居、・白髭神社 紀元弐千六百年弐月、・手洗石:昭和十五年奉納、・板碑:頌徳碑しょうとくひ 立浪碑、・燈籠2:奉納弐千六百年、・祠、・社、・手洗石:明□奉納安倍郡中平村観音講中、・燈籠:大正十年、・杉:巨木、
・お堂、公民館(中平61)
かつて臨済宗の寺院で移転したがお堂は保存した。
・庚申塔 安政(併のイなし?)年如月吉日、お堂の門前にある。この上の斜面に切通しらしきがあり、かつての古道かと思われる。
・古い墓石群(中平23)
・三界萬霊無縁塔、・他墓石多数、江戸時代年号あり、
・学校跡地(下渡493)
・心の碑 昭和四十三年 大河内北小学校、・石碑、・コンクリ像、
・しだれ桜(上渡185)
県道沿いに咲き見事。
・全福寺(上渡4)
寺の参道入口にある。・水難除供養(美良)塔 地蔵3、
寺の門前墓地にある。・六地蔵、地蔵、
寺の上のお堂横にある。・庚申塔 享和二年(1802)、・?石塔?庚申 元禄二己巳幸(1689)、・庚申塔 大正九年、・庚申塔 昭和五十五、
・石造物(渡本5)
・記念碑:孝子白鳥文八居住之跡 東宮殿下御成婚奉祝記念 大正十三年一月二十六日建之 安倍郡、・燈籠:奉納、
・東雲寺(有東木776)uto-giうとうぎ
曹洞宗。子安観音、大日如来、山葵田がある。
・堂、・庚申塔、・石塔、・新:六地蔵、
・白髭神社(有東木597)
・祠、・新:燈籠2、・新:手洗石、・石:家:道祖神、・大杉10:高さ45m、隣に祠:仏像:天保三(1832)、
・有東木白髭神社の大スギ:説明版:樹高35m(新説明45m)、目通り周囲6.6m、枝張15m、この神社の境内には樹齢約720(新説明750)年にもなる樹勢の良好なスギが十本程あります。有東木に集落ができたのは500年ぐらい前といわれており、このスギはもともと天然林であったと思われます。静岡市。
・有東木の無形文化財
国・無・有東木の盆踊り、市・地登・有東木のギリッカケ、市・無・有東木の神楽、
・石塔(有東木267)
・馬頭、・祠、・?観音:天保四(1833)、
・辻の地蔵(有東木691)
寺の手前の住宅の辻。別名:しょんべん地蔵、長いいわれがある。
・分校跡(有東木751)
寺の裏の空き地で消防分団小屋の横。昭和44年廃校。
・ワサビ発祥の田(有東木734)
有東木公民館の先。
・地蔵:行山安全:えぼし岩(有東木734)
有東木公民館の先。
・火の見櫓(有東木767)
寺の裏の分校跡地横。
・たかんば:凧揚げ場がなまった、景色のよい所・山の神:山の神がくれた景色が見える所、・そらんだん:空の段がなまった、展望がよい。・山葵栽培発祥の碑、
・山葵高原(有東木)、正木峠、地蔵峠、成島峠、細島峠
有東木の奥に山葵(ワサビ)高原があり、山葵発祥の地という。さらに奥に正木峠があり、藤代への道である。また地蔵峠を越えると山梨県の月夜の段に出られる。他にも成島峠や細島峠を越えて山梨県側に出られる。特に細島峠や成島峠越えが使われていたようだ。地蔵峠越えは新しいようだ。主にかつての生活道路である。今はいくつかが登山コースとして歩けるが、廃道もある。
・石造物(大和田523⁻4)
かつては有東木園という蕎麦屋があり石造物を置いていた。蕎麦屋がなくなった後もしばらくは石造物があったが13年12月現在は何もない。
・コンクリ製橋桁(大和田、瀬戸橋手前)
かつての吊り橋用橋脚と思われる。
・(藤代)
かつては正木峠で有東木とつながっていた。川が増水したときの山越えコースになっていたようだ。この集落はかつて土石流により壊滅的打撃を受けたことがある。
集落入口手前に藤代の滝がある。
・庚申塔(藤代329)
集落入口手前の道路脇に新しい祠設置。
・庚申塔 寛文八(1668)、・庚申塔 天保十五(1844)、
・桜(入島・数珠窪)
今は県道から外れたが、かつては県道沿いに桜がかかり見事。
・石仏(入島)
2010年以前集落入口の県道沿いに安置されていたが、13年12月現在は入島公民館の下記地点に安置。
・指月院跡(入島220)入島公民館
草創:1506年、本尊:聖観世音菩薩、
・堂、・奉請庚申待一結之衆中敬為延宝八庚申(1680)、・地蔵2、・石塔2、・石塔の笠部分、・石破片、
・祠:地蔵(入島289)
農協の茶工場や茶畑のある辻に祀られている。
・土砂崩れで崩落した昭和期の県道(入島)
昭和期に使われていた県道は、入島から湯の森への長大なスロープ橋の左のがけの中腹に見える。一応崖は修復されているが、根本的に処置できないためこの長大な橋を通した。
・神社(湯の森1029⁻4)
・木鳥居、・常夜灯2:明治三歳、・燈籠2、・観音:延宝三(1675)、・石塔:見ざる言わざる系の浮彫りなので庚申塔系と思われる、神社の社殿は彫りが見事である。
・石碑(湯の森1029)
・忠魂碑、・大東亜戦争戦没者芳名、・御大典記念、・平和、
・石碑:渡辺柔郎 髯先生の碑(六郎木1327)
梅ヶ島小中学校前の校門橋を渡った公衆トイレ横。
・梅島山宝月院(関の沢、梅が島545)、
本尊:釈迦牟尼佛如来、開山:1968年、宝珠院と指月院が併合、
・新:不許葷酒入山門、・新:六地蔵、・新:地蔵、
・関の沢の水力発電所跡(関の沢)
静岡新聞13年12月に掲載。関の沢川沿いに水力発電所が戦前あったが戦後役目を終えた。取水口や発電施設跡が残る。
・(大代)
井川峠とつながっている。ハイキングコース通行可能。
・石塔類(大代3083)
大代集落内の峠越えのような高所にまとめて祀られている。おそらく近年移転合祀されたのではなかろうか。
・祠、・庚申供養塔、・石塔、・地蔵、・三地蔵、・石塔、・石塔、・石塔の笠部分、・丸石、・穴あき石、
・御巣鷹山853.8m、天神山826m (大代)
大代集落東側の双耳峰(山頂が二つある山)の名前は南の三角点のある高い山が御巣鷹山853.8m、北の低い山が天神山836mだそうだ。どうも登れるらしく、集落の山頂真下の森下(地名)716mに登山標識がある。標高差137mなので20~30分で登れて両山廻って1~2時間ではないでしょうか。
・(本村)
バス停のある家の裏から戸持集落に上れる。かつての古道で昭和期まで子供たちの通学路であった。下るときは約15分だったそうだ。またバス停横の川向こうの林道(この林道は500mも進むと行き止まり)入口から真上に向けて上る登山道も東峰に上る旧道(古道)であり、現在も大光山登山コースとして使われる。そしてこのコースも東峰の通学路だったのだろう。
「古道は通学路として近年まで残存しやすかった」といえる法則が成り立つ。そして古道は登山コースや自然歩道に選定されると残存しやすいともいえる。
・石塔類、神社(戸持3477)、兎作
集落内の戸持公会室横に祠や石塔が安置されている。
・祠、・稲荷神社、・?天神、・奉請庚申供養塔、・地蔵2、
戸持は急峻な山の斜面に茶畑が広がっていて、今は畑になっている所のいくつかで金の露天掘りがかつて行われていたという。今は茶畑ばかりだが焼畑農業との関係性もあるだろう。
戸持の一番北の高所の集落裏山に昭和40年代の地図上では鳥居マークがついているので、かつてはそこに神社があったと思われるが、現在は東峰に稲荷大明神があり、戸持の神社は湯の森の白髭神社に合祀された。かつての鳥居マークのあった所は調べたが何もない。
そこへ行く自動車道は裏山の下で舗装が終わるが、その奥には無舗装の道が続き、立ち入り禁止となっている。
・兎作 '14 11/3
その500m先にはかつて兎作という集落があった。兎作は廃村となっている。壊れかけた廃村の家の庭に、すり潰し用の自然石:30㎝四方で上部真ん中がへこんでいて、鉱石をすりつぶすのに用いたのかもしれない。他に15㎝四方と10㎝四方の丸石自然石が2つあった。
兎作の住人は最後3軒となり、大野木、古庄、末広町へ出ていったという。最後に残った2軒は、清水区の人が1軒を買い取り別荘にしているという。もう1軒はどうも吾作小屋というようで、大野木から戸持に来るとき通る舗装道から登山道が分岐しているようだ。
・神社、古道(東峰1959⁻2)
・赤祠、赤鳥居: 稲荷大明神、
神社横に標識:「日本一高い茶畑海抜1000m」、地図で確認すると標識のある神社前で標高900mで目の前の斜面の上に続く茶畑の最高所で1000mと推定される。その横を登山道は進むと思われる。登山標識「東峰←→大光山」があり、上る道は茶畑横を上り大光山に至り、ここから下山する道が本村バス停に続くことが分かる。
13年12月付近で飼われている犬が人懐こく近づいてきて癒された。
ただこの道がいつから使われているか証明がないので古道と言い切れるかは不明だが、旧道であることは言い切れる。もっと古い古道があるかないかは今後の調査研究を待つ。一応この旧道を古道と推定したい。
東峰も金の露天掘りとの関係がいわれる。焼畑農業とも関係あるだろう。
・(孫佐島)
井川峠とつながっている。ハイキングコース通行可能。現在市営キャンプ場。
孫佐島に渡る橋の手前に祠がある。橋を渡った所の山に取り付くと井川峠コースとなる。
・祠:金谷山神社、
・(大野木、戸持、東峰)
現在梅園、テニスコート、温泉民宿の地。この裏から戸持、東峰集落に行ける。この集落はかつて金の露天掘りをしていたと推定されている。なお六郎木集落の一つ上流の本村から徒歩で上って行ける。それが旧道(古道)である。
・刈安峠(草木)
東峰同様、刈安峠越えで山梨県につながっていたが、崩落だらけの危険なコースなので現在通行禁止となり廃道である。私も滑落しかかったことがあった。刈安峠そのものへは草木から大光山経由で稜線へ出て歩ける登山コースが設定されたので、稜線をたどり稜線上の鞍部として通過できる。なお山梨県側も廃道である。石仏やいわれのある樹木等はない。かつての生活道路。
・赤水の滝(赤水)
増水したとき水が赤く(赤茶色)濁るためである。この上流に大谷崩れがあるので土砂を含みやすかったのだろう。展望所が県道下にある。県道は滝の真上を通過する。自転車で上るとこの街道中もっともきつい上りである。
・(新田)
大谷崩れにより大量の土砂が集積し、金が取れなくなった日陰沢金山から鉱夫たちが移転し開拓した土地。市・無・梅が島の舞。
・稲荷大明神(新田5554)
この裏から登山すると、七人作りの尾根という安倍奥三大遭難地帯の稜線をたどれるようだが、すさまじい藪を通過する危険地帯なので素人は行かないように。
以前は小さな祠しかなかったが、13年11月現在、参道や社殿が新しくなっていた。
・赤鳥居:幾つか、・板碑、・新:燈籠2、・手洗石、・石碑:奉納正一位稲荷大明神百五十年祭記念碑、・石段、・燈籠2:昭和~、
・願勝寺分院(新田)
・大谷崩れ
日本三大崩れの一つ。扇の要から新窪乗っ越しを経て大谷嶺(三角点所在地△1997.7mだが三角点がすでにない、崩落したようだ)や山伏岳に上れる。一面のガレ場は見応え十分。
・日陰沢金山跡、奉行所跡、鉱夫たちの墓
魚魚(トト)の里の奥でハイキングコースになっている。入口の奉行所跡は休憩所になっている。近くには遊郭もあった。河原を数分歩くと集落跡の様子を石垣や段差等でつかむことができる。古い道もあり墓は山の稜線上にある。この街道中もっともスリリングなコース。一見の価値あり。墓石は小振りで甲州(山梨県)側で彫ってもらい鉱夫たちが背負って山越えしてきたものだ。もっとも新しいもので天保期(幕末)のものである。墓石が甲州のものということでいかに甲州とつながりがあるかが分かる。
入口周辺には市営黄金の湯、金山温泉、魚魚の里があり、レジャーに最適。
・宝珠院跡(梅が島本村)
本尊:釈迦牟尼佛、草創:1558年、
・市営温泉黄金の湯(新田)
日帰り温泉で土産物屋、公衆トイレ、無料駐車場がある。
温泉前の土手に梅ヶ島観光看板、砂防ダム説明版、三河内川床固め工群完成記念碑及びモニュメント付石庭がある。
川向うは魚魚の里と奉行所跡である。川の水量が少なければ靴や足がずぶ濡れになるのを覚悟すれば徒歩で渡河できる。ただし夏でも冷水で冷える。
・安倍の大滝(三河内)
最初の梅が島温泉民宿を右に入っていく。徒歩十数分。落差が多きく安倍川流域中最大の滝である。
・梅が島温泉
かつて市営温泉があった所は源泉取水場、湯之神社、公園になっていて、説明版等が多い。
・梅ヶ島温泉の歴史:説明看板:梅ヶ島温泉は、静岡市の北部、安倍川源流に近い安倍峠の麓に位置し標高1000m(級)の雄大な山々に囲まれた静寂な自然環境の中にあります。その歴史は古く、一説には約1700年前に遡るとも言われています。三人の狩人により発見された説、砂金採りにより発見された説、或は仙人が三匹の蛇が遊んでいる泉を見つけて発見された説など、梅ヶ島温泉にまつわる逸話が多数あります。
戦国期には信玄の隠し湯とも言われ、古くから美人づくりの湯と知られるこの温泉は、単純硫黄温泉で神経痛、関節痛、うちみ、痔、冷え性、疲労回復、皮膚病などに効能があり、ツルツルとした感触の良い温泉は清く澄み、時として黄金色に輝き、湯の花を浮かべ、長い間、湯治場として多くの人々に親しまれてきました。
昭和四年の大火、昭和四十一年の大水害等の苦難もありましたが、現在は旅館、民宿、土産物屋など十数軒が軒を連ね、その歴史を今なお継承しています。
この地、「おゆのふるさと」は、昭和四十五年に開設した市営浴場が平成十一年四月に梅ヶ島新田へ移転新築されたことに伴い、再整備したものです。梅ヶ島温泉の泉質を感じていただくお湯に触れる施設や湯之神社、岩風呂、湯滝等を回遊散策し、展望デッキからは梅ヶ島温泉街も一望でき、梅ヶ島の魅力を垣間見ることができます。
・湯之神社:猟師たちにより発見されたという。源泉上にある。・石塔:読めそうだが刻字不明、
・湯之神社の由来:説明版:正保二(1645)年初夏の頃、甲州天目山に治療中の良純親王は西方に霊泉ありとの夢のお告げを受け、それを尋ねて甲州路を安倍の峠へと辿られました。親王が重い足を引きずって頂上近い逆川のほとりで休息していますと赤い小蛇三匹が道に出て親王を導きました。(親王が持っていたお酒を盃につがれ差し出されると、それをなめられたといいます。)そして道なき道を西方に導かれ、やっとのこと温泉にお着きになりました。親王がこの温泉に入浴なさいますと三日で痛みもとれ、十数日で難病もすっかりご快癒になりました。
親王はこれを日頃崇拝する御仏が、権(かり)の姿でおいでになりお救いしてくれたものであると信じ、仏恩報謝の御心から持っていたお守り刀の備前長船祐定と紺紙金字の願経と水晶八房の御数珠を捧げられ三蛇大権現としておまつりしました。
しかるに、古来より「湯之宮三社(蛇)権現」と称されていましたが、明治に入り政府の神仏分離政策により湯之神社と改称、春秋年二回の祭典を行い現在に至っております。
・湯滝:説明版:湯之神社の脇にあるこの滝は、古くから人々の心を清め、和ませてくれる温泉の守り滝として奉られており、新緑青葉の時期に岩肌を滑り落ちる水しぶきは、昔と変わらぬ清涼感を今でも私たちに与え続けています。
・岩風呂:説明版:このお風呂が造られた時期は定かではありませんが、古くから美人づくり、子作り、長生き、健康づくりに御利益がある湯として人々に親しまれてきました。現在はここに湧き出ているお湯も含め、各旅館等に、源泉湯として供給されています。
・歌碑:あめつちの大き心にしたしむと駿河の山の湯どころに来し 勇
温泉旅館街から三段の滝へ行く道脇に慰霊碑がある。
・台風被害者慰霊碑:遭難者慰霊塔。慰霊碑、昭和41年9月25日台風26号による遭難者、遭難者個人名。水難地蔵慰霊菩薩 昭和四十一年九月二十五日水難犠牲者二十六名、増田。
・三段の滝:温泉街の上流、徒歩5分。
温泉街から安倍峠方向またはバス停のある方に向かうとバス停前にある。
・文学碑、吉井勇、あめつちの大きこころにしたしむと駿河の山の湯ところに来し、昭和十四年初夏。バス停前。
・摺石:武田信玄公の時代、新田部落付近に日影沢金山あり、其の当時金鉱を入れて摺り潰して□に流して金を得たものです。梅薫楼
・南無妙法蓮華経、昭和十四年、ひげ題目、
*山の中の地名になぜ「~島」が多いのか。島はシマで縄張り領分の意味があるようだが、一般的に島は水に囲まれた所である。この水は客観的に四方を囲まれた海(湖、池、沼、川)だけでなく、主観的に囲まれている、あるいは水のある所を渡って行く所も含むようだ。そうすると山の中でも川の向こうは「~島」である。
梅ヶ島温泉を三段の滝方向ではなく右折(東)してバス停方向へ行きさらに奥を目指すと、林道入り口ゲートと手前に八紘嶺安倍峠登山道入り口がある。古道は登山道であろう。ただし古式ゆかしいものは登山道沿いには見当たらない。以下は林道沿いのものも紹介する。林道豊岡梅ヶ島線は5月下旬開通、12月初め閉鎖となる。ただし林道が災害で通行不可能になることは多い。14年11月現在山梨県側は復旧工事中でここ3年ほど通行不可である。
・安倍の大滝の展望所、
梅ヶ島温泉より林道豊岡梅ヶ島線で1㎞進んだところ。標識「ここより安倍の大滝が見えます」、確かに滝の上部が見える。
・安倍の大滝への近道登山道、
梅ヶ島温泉より林道豊岡梅ヶ島線で1.5㎞進んだところ。標識「安倍の大滝入口、500m、安倍の大滝から民宿へ1.5㎞」
・鯉ヶ滝(恋仇)
梅ヶ島温泉より林道豊岡梅ヶ島線で1㎞進んだところ。看板標識がある。
「1、昔、安倍郡梅ヶ島村に住む百姓の三郎左衛門と湯治場の湯女(ゆな)のおよねとは、いいなずけの間柄だった。ある日、府中より馬場新之助という若侍がこの湯治場の腰痛の治療に来て、いつしかあ、およねと深い恋に落ちた。
2、二人の関係を知った三郎左衛門は、ショックの余り殺意を覚え、二人のいる湯治場に火を放ち山へ逃げ込んだ。そして、滝の上まで来た三郎左衛門は、湯治場にいるはずの二人の逢瀬の場を見つけ、逆上し背後から二人を滝下へ突き落してしまった。
3、住み慣れた村の空が湯治場の焼ける炎で赤く染まるのを見た三郎左衛門は、自戒の念にかられ、二人の後を追い滝下へ身を投げた。しかし、このとき彼が見た空は、火事の炎ではなく晩秋の美しい梅ヶ島の紅葉に彩られたものだった。
4、その後、三郎左衛門とおよねは緋鯉と真鯉に化身して結ばれ、仲良く滝に住んだという。爾来、この滝は「恋仇」(鯉ヶ滝)と呼ばれているが、事実は定かではない。」
滝は林道橋の上流側に見える。大岩の中を豪快に水が下っていく。
・八紘嶺登山口
温泉の林道ゲート付近からの登山道がまた林道と交差し、再び登山道に分岐する。付近に駐車場もある。
・安倍峠旧登山道
峠1㎞手前で林道からはずれた旧登山道入り口がある。沢沿いを進める。
・駐車場、公衆トイレ、富士見台の下
13年11月現在、梅ヶ島温泉よりここまで車で来られる。山梨県側が復旧工事中のためバリケードで車は進入できない。あと500mで安倍峠である。
・ハイキングコース案内標識:安倍峠~八紘嶺~梅ヶ島温泉 八紘嶺~安倍峠 八紘嶺~大谷崩、
・安倍峠、標高1488m、 '14 11/3
山梨県との生活道路で、かつては静岡市街側に行くより使われていた。川沿いまたは山また山を越えて歩く方が大変で、安倍峠等を越えて身延町側に出る方がましだった。オオイタヤメイゲツ等、秋に黄葉し更に紅葉する落葉樹が見事で、秋10月中旬に黄色というより午後の日差しを反射した黄金色の絶景は極楽のようだった。しかし地球温暖化の現在は10月下旬がピークである。14年10月25日はまだ緑、黄色、赤がぼちぼちでこれから1週間後がピークかと思われたが、11月3日に来たら紅葉を通り越し枯れ木となり葉は茶色く地面に積もって初冬景色となっていた。おそらく10月27~29日がピークで、あっという間に散ったようだ。
どうも地球温暖化で紅葉時期が遅れたが、終了は後ろにずれず、あっという間に散ることになったようだ。葉の紅葉の仕方は緑、黄色、赤、更には木についたままの葉が茶色く変色していくという、汚い紅葉いや紅葉しないで茶色く朽ち果てる葉がでる始末のようで、鮮やかな紅葉ではなくなっていくようだ。地球温暖化で夏が長期化したが、冬は例年通り来るので、秋が短期間化し、紅葉しきれず朽ち果てるという情けない紅葉になるようだ。
オオイタヤメイゲツ(カエデ科カエデ属):一般的には散生するが、このように群落をなすことが珍しいので学術参考林(昭和56年)となっている。そのため林道を峠から少し外れた箇所に作り県境を越すようにした。工事費がけた違いにはねあがったそうだ。
峠を旧道に沿って梅ヶ島方向に下ると500mほどで水が湧き出し川になるところを見られる。安倍川水源地の標識がある。まあ安倍川の最初の1滴といったところでしょうか。 更に1㎞沢沿いに下れる旧道がある。その先は林道に合流する。
林道合流をやめさらに道なき沢沿いを下ると、鯉が滝と安倍の大滝にはまることになり、落ちたら死にます。よく素人さんが、川沿いを下れば人が住む村や町に出られるから、遭難したら川を下ればよいと言いますが、それは平野を流れるゆったりした川が前提で、山の中の川は悪絶なる滝場、断崖絶壁の渓谷にはまるので、絶対川沿いを下ってはなりません。自殺行為です。
安倍峠にあるもの:
・馬頭観音?:コンクリート製、
・安倍峠から徒歩15分、シロヤシオ群生:開花5月下旬、トウゴクミツバツツジ:開5~6月、サラサドウダン:同6/下、チチブドウダン:同6/中、ブナ巨木、ミズナラ巨木、
・石碑:「開通記念 広域基幹林道豊岡梅ヶ島線」静岡県側7.4㎞、山梨県側14㎞
~参考文献~
・「井川村誌」井川村誌編集委員会、’74
自然、歴史、産業、交通・通信、発電、文化、民俗、方言という井川についての総覧であり、基礎資料である。
・「玉川村誌」、’64
1911年手書き版上梓、1964年写本プリント版発行である。自然、歴史、教化、兵事、衛生、警備、産業、交通、社寺、伝説、、伝記、言語、風俗、災害等について20世紀初頭においての観点でまとめられていて、今ではおやという部分もあるが、当時の基礎資料足りうるものである。
・「田代・小河内の民俗~静岡市井川~静岡県史民俗調査報告書第十四集」静岡県教育委員会文化課県史編さん室、’91
民俗調査報告書として一通り報告されているので便利。多分田代と小河内が取り上げられたのは、井川ダムの水没を免れた地域だからだろう。本地域の民俗資料決定版である。
・「美和郷土誌」美和郷土誌編集委員会、代表:小沢誠一、’85
自然、歴史、教育、生活文化、宗教、民俗、史料について、微に入り細に入りこれでもかというぐらい記述されていて、他の地誌に比べてもワンランク上の内容である。まさに美和を知るための一級資料で決定版である。
・「梅ヶ島物語 史話と伝説」志村孝一、’82
梅ヶ島にまつわる武将、豪族、庄屋、村々、温泉、偉人、産業について聞き書きしていて、よくここまで聞きまわったものだ。今では滅んだこともあろうから資料として残したことで、後世に価値が上がろう。
・「安倍川~その風土と文化~」富山昭・中村羊一郎、静岡新聞社、’80
堤防、水害、水神、交通、産業、伝説(金山、飢饉、白髭、七観音)、農耕信仰、祭、婚姻等について卓見多し。
・「安倍川流域の民俗」静岡県立静岡高等学校郷土研究部、’80
安倍川流域の歴史と産業、村の成り立ち、信仰、衣食住、人の一生の出来事、年中行事、諸芸能、伝説について、一通り概観し調査してある。70年代末によく高校生が調査研究できたものだ。
・「復刻版 大河内村誌、大河内村青年団、岩本利太郎:編、1913年」静岡市立大河内中学校、’89
1913年の大正期に出され、1953年に口語訳で一部抜粋にて再編纂され、さらに89年復刻された。内容は、自然、歴史、教育(学校、社会、宗教)、兵事、衛生、警備、産業、交通、名所旧跡、伝記、言語、風俗等である。簡略に知りえるのによい。
・「安倍川と安倍街道」海野實、明文出版社、’91
安倍川の成り立ち、安倍街道、水害、水神、筏流し、舟運、賃取橋、鉄道について分かりやすく、コンパクトに読ませる。
・「藁科路をたずねて」海野實、明文出版社、’84
藁科のお茶摘みさん、焼畑文化、藁科五街道についてコンパクトかつ分かりやすく説明している。
・「静岡市歴史散歩」川崎文昭(静岡新聞社)、’90
市内の数多い名所旧跡を手際よく簡潔にカラー写真付きで紹介している。
・「しずなか風土記 賤中ふどき」しずなか風土記編集委員会、静岡市立賤機中小学校、’68
伝説や民間伝承面が細かに採録されていて、今では語り伝えられないものがよく残せたものだ。この資料は助かった。
・「郷土史 私達の籠上」籠上町内会、’84
籠上単独でよく出したものだ。とりあえずコンパクトに知りえることができる。
・「静岡市 歴史の町 井宮町誌」静岡市井宮町町内会、’03
井宮周辺の歴史地理を細かにかつビジュアルに知りえる良い資料だ。
・「郷土誌 私達のふる里 下(しも)」下町内会、’08
静岡市葵区下地区(鯨ヶ池から諸岡山周辺地域)の主に近代以後の細かな情報が入手しやすい。
・「玉川新聞」
2014、3/2(日)、安倍街道についてあまりに部分的過ぎて、将来少しずつでも書き足していこうと思っておりました。今回少しは調べられたので内容をリニューアルします。まだ未調査はありますので、今後ものんびりではありますが、改定していくつもりです。少しほっとしました。
3/15に井川に行けたので井川部分も改訂します。3/21 調査:13年11~12月、14年2~3月を含む版
さらに14年10~11月調査、改定’14 11/3
・総説
一般的には静岡市中を安倍川沿いに遡り油島で安倍川支流の中河内川に沿い遡り、口坂本温泉を経由して大日峠を越えて井川に達する街道を本道とする。支線としては、先の油島でそのまま安倍川本流を遡り梅ヶ島温泉や安倍峠を越える梅ヶ島街道がある。また先の本道でも、玉川から口坂本側へ行かず、西河内川に沿い遡り大沢から笠張峠を越えて井川や大間に行く西河内川ルートもある。それらの本道や支線からさらに周辺へ分岐する峠道等は数多い。
一旦は2000年頃から12年まで少しずつ調べてはきたがあまりに部分的であった。そこで今回13年11~12月、14年2月
にかけ未調査だった主だったところだけでも一通り調査を試みた。すべてのルート及びその周辺地域の道路沿いとなると膨大すぎて手におえないのですべてのルートと遺物を調査紹介はできないが、調べられた範囲内でも発表し、今後の方たちへの調査研究への一助、および文化財や観光資源の発見につながれば幸いである。また間違いは多かろうが、今後ご指摘をお願いしたい。古街道研究が進むことを望む。
・用語説明
・国、県、市=国、県、市指定、・有、無=有形、無形、・登=登録、・文=文化財、・天=天然記念物、・重=重要、・民=民俗、・石=石製、・家=家型、・新=近代から現代にかけて作られた新しいものと推定されるもの、・古=新しくなく古そうなもの、・欠:破損欠落しているもの、・馬頭=馬頭観世音菩薩、・コンクリ=コンクリート製、(2)=2基、
・古い用語説明
廿=20、廿の縦線3本=30、等=塔、歳‣天‣月日=年、
美良または羊良=養(美や羊ではなく羊の下は大であり美ではなく横線3本である。狼という字に似ているが、その字がパソコンで出てこない。そういった字は多く他の現代的な字に切り替えたり注を施す)、クイズ:ちなみに養がなぜ美(横線3本)や羊(下は大)と良なのかはちょっと考えるとすぐ分かります。このように漢字の部分を上下左右に組み替えることは石塔への刻字ではよくあります。彫る時の字のバランスを考慮した石工さんたちの工夫です。ちなみにある石工さんはこういう字をお寺さんの字と言っていましたが寺院で使う字ではありません。この前見た字では政を上に正、下に政の正抜きの字を彫ったものを見ました。
*「石仏事典」類を参照してください。年号や干支もこれで分かります。
・住所について
なお住所は正確に分からないものは多く、隣や付近の住居の番地号を用いているものが多い。
○本街道:静岡市中~井川
安倍街道の一般的な出発点と思われていたのは井宮神社と薩摩土手のある所かららしい。しかし現代の安倍街道「県道井川湖御幸線」は国道1号線静岡駅前からであり、旧東海道からの分岐点は呉服町の札の辻からとなる。そこで今回はその付近の周辺遺物も含むこととした。
明治20年代の陸地測量部地図で確認すると、札の辻から北上し本通りで右折して、外堀からの通りと合流し安倍街道へつながっているので、外堀通り「県道井川湖御幸線」が安倍街道への直進路といえるのか。
~これより下 静岡市市街地内、静岡駅北西部を参照せよ~
*移動:
~~これより上、静岡市市街地内、静岡駅北西部を参照せよ
・賤機稲荷神社(宮ヶ崎町)
かつては忠正酒造裏と紹介できたが解体されたので、自動車販売店裏の山際にある。隣は片羽町公民館である。
・神社名石碑:新:賎機稲荷神社、・木鳥居:昭和六十年、・手洗石:奉納 片羽町婦人會
・忠正酒造(材木町6)
かつて存在した造り酒屋、今は跡形もない。忠正酒造ビルと昔ながらの建物を解体してしまった。
・泰雲山瑞龍寺(井宮町48)
・説明版:宗派:曹洞宗、寺系:静岡市葵区沓谷長源院末、開創:永禄3(1560)年室町戦国時代、本尊:聖観世音菩薩、開山:能屋梵藝大和尚のうおくぼんげい、開基:旭姫(徳川家康公夫人、豊臣秀吉公異父妹)、本山:大本山永平寺(福井県吉田郡永平寺町)、大本山総持寺(神奈川県横浜市鶴見区)、由来:永禄三年長源院第四世梵梅ぼんばい和尚の法嗣:能屋梵藝和尚が開山して旧寺址を広めた。当時は浅間山の西麓に位置し駿河七ヶ寺の一つであった。家康公は駿府在城の折度々住職を招集し曹洞の法門を聴聞された、当寺も七ヶ寺の一つとして家康公と深い縁に結ばれていた。天正十八(1590)年、旭姫没するや当寺に墓を建て、その時の法名「瑞龍院殿光室総旭大禅定尼」から当寺の名前が瑞龍寺となりました。この為豊臣家、徳川家両家より寺領を寄進せられた。戦災等で寺を消失し、のち昭和26年再建する。寺所有の重宝品:旭姫の小袖、秀吉公の朱印状、蝶足膳(桐紋蒔絵膳)、境内設置:旭姫の墓、切支丹灯篭、芭蕉の時雨塚、
開基は旭姫(豊臣秀吉妹で離婚させられ家康妻として嫁す)。
・観光案内版:しぐれ塚(芭蕉の句碑)
・キリシタン灯籠:竿石に舟形の囲みがあり、その中に浮き彫りされている。「1605年頃駿府城にフランシスコ会、イエズス会があって、城内、安倍川の2か所に南蛮寺があったといわれている。」
個人的には切支丹というより神仏関係と思われる。おそらく今後切支丹灯籠のいくつかは否定されると思われる。
’13年12月再見、案内表示の矢印や説明がなく、灯篭も各部がずれたまま中途半端に設置され一部損壊していて悲しくなった。私が否定したためだろうか。私見では否定したいが、だからといって灯篭をぞんざいに扱われることは悲しい。大切に保存し、説明版もつけ最後に一言否定説もあるとしてくれたらそれでよい。否定説も断定できないし、肯定説も断定できない。ただ今後否定説が有力になるだろうとは思います。
*私見の「キリシタン灯篭疑問説と保存活用」についてはブログ内の別項目を御参照ください。文章が長引くのでここでは簡単に済ませました。
・しぐれ塚:松尾芭蕉の句碑。安東村長安寺が廃寺になったので明治十二年頃材木町の大村青渓氏が移したもの。石の右側に「芭蕉桃青居士ばしょうとうせいこじ」、左側に芭蕉の命日「元禄七年十月十二日」が刻まれていた。「きょうばかり人も年よれ初しぐれ」から時雨塚という。
・旭姫の墓:朝日姫とも書く。正式な墓所は大阪。こちらは家康が建てた墓。「豊臣秀吉の妹で徳川家康の正室であった。家康と駿府城に住んでいたが、京都に行き48歳で亡くなった。家康が東福寺から分骨してここに墓を作った。戒名:瑞龍寺殿」
・説明版:豊臣秀吉公の異父妹で尾張の地士佐治日向守の妻、秀吉が小牧長久手の戦後家康と同盟関係を築くため妹を日向守と離別させ天正14(1586)年5月浜松城の家康の所へ嫁がせた。天正16年自分の母、大政所病気見舞いに上洛しそのまま天正18年1月自身も病気で没した。48歳。秀吉は京都東福寺に埋葬し「南明院殿光室総旭大姉」と諡(おくりな)し悲運な妹への供養を行った。家康と供に在った僅か2年、上洛後2年で病没し加えて前夫日向守は秀吉の仕打ちを憤り切腹し果てる誠に薄幸の身の上である。
一方家康は旭姫がしばし詣でていた当寺に墓を設け「瑞龍院殿光室総旭大禅定尼」と諡し祀った。
・新:燈籠(2)、・新:穏々の苑、・一石一字経寺塔、
・発掘された墓石:慶長十九甲寅~空風火水地本学~~~、・発掘された墓石:慶長十一丙午空風火水地笠岩~~~、
説明版:この2本の石塔は昭和57年9月12日台風で墓地の一部が崩れ落ちてしまいました。その場所から掘り出されたものです。どなたのものか分かりませんが、今から約327年前に亡くなられた方と思われます。
・句碑:?、・板碑:宗季山本翁碑、・新:六地蔵、・新:南無釈迦牟尼仏、・新:水子地蔵尊、
・安倍軽便鉄道旧井宮駅前(井宮町6-1) (株)赤石工場前
・工場横の塀に旧井宮駅と山岡鉄舟邸址を示す看板が掛かっている。
・説明版:安倍鉄道跡、大正5(1916)年4月15日井宮から牛妻までの10㎞の軽便鉄道として開通。福田ケ谷ですれ違う単線で平日乗客は150人位。昭和7(1932)年に廃止された。
*安倍鉄道路線跡については別項目「安倍鉄道跡」を参照ください。
・山岡鉄舟邸址(水道町1-5) 魚仲増田商店(魚屋)前、先ほどの(株)赤石工場前に説明版
・石碑:明治の初め徳川家について静岡に来て十分一の役人のいた家に住んだ、江戸城明け渡し等非常に功績のあった有名な人である。
十分一:安倍川からいかだで運んできた木材、炭、杉皮等を十分一という役所で荷物の十分の一を税金として納めさせた所であったので、広い敷地建物があった。
・説明版:山岡鐵舟:鐵舟は戊辰戦争時、徳川慶喜の意を受け、江戸に迫る東征軍の陣地を突破して、大総督府の参謀西郷隆盛と駿府で直談判、江戸城無血開城への道を開き江戸を戦火の災厄から救うと共に徳川家の存続もなさしめた。後に西郷は、この時の山岡を「命もいらず名もいらず官位も金も要らぬ始末に困る人」と評して感嘆した。明治元(1868)年、駿府藩若年寄格幹事役、明治2年、静岡藩権大参事としてこの地に住み旧幕臣の無禄移住者の生計確保のために奔走し、城下の治安維持にも努めるなど八面六臂の活躍をした。さらに殖産興業にも意を尽くし、牧之原大茶園の実現や清水次郎長の富士の裾野開墾事業推進に尽力した。明治5年、西郷隆盛等の強い要請を受け、十年間の期限を切って明治天皇の侍従となり、青年天皇の人格形成に大きな影響を与え皇后からも絶大な信頼を得ていた。明治16年、清水区の補陀洛山鐵舟禅寺(元久能寺)建立を発願、明治43年、多くの人たちの支援により完成した。 平成22年4月吉日、静岡・山岡鉄舟会 山岡鉄舟邸址の記念石碑をここから北寄りの歩道上に再建した。
・石碑:山岡鐵舟:通称、鐵太郎、剣、禅、書の奥義を極めた明治の英傑。戊辰戦争時には、東征軍の参謀西郷隆盛と駿府で直談判し江戸城無血開城の合意を成した。明治2年には静岡藩権大参事としてこの地に住まい、藩政に多大な功績を残した。明治21年没、享年53歳従三位勲二等子爵、静岡市は鐵舟住居跡の記念碑を建てたが破損して撤去されたままであったため「静岡・山岡鐵舟会」の協力を得てこの碑を再建した。平成22年四月吉日、静岡市葵区水道町 町内会、
・大応国師産湯の井(井宮町76)
1235年当地生まれ。1308年没。
・説明版:静岡市指定有形文化財(史跡) 、円通大応国師(南浦紹明なんぽじょうみょう)は1235年(嘉禎元年)旧駿河国安倍郡井宮村に生まれた。5歳の時服織村の建穂寺に入り、淨弁法師のもとで学び、鎌倉の蘭渓道隆禅師のもとでの修業を経て、中国(宋)に渡り臨済禅を修めた。帰国後は鎌倉の建長寺や九州大宰府の崇福寺等に住山し、大徳寺を開山した宗峰妙超や妙心寺を開山した法孫まごでしの関山慧玄かんざんえげんをはじめ、多くの弟子の育成に努めるなど、臨済宗の普及に功があった。この井戸は国師誕生のとき産湯の水を汲んだものと伝えられている。国師の遺跡として、郷土に残っている唯一のものである。平成13年8月、静岡市教育委員会、
・松樹院(井宮町248)(浄功院)
・おみたらしの石仏
・お薬師さん:薬師如来、善導大師作、
・浄功院:家康長女死去により乳母が供養建立。明治期に合併。
・燈籠、・祠石、・稲荷、・新:燈籠、・祠、・新:水子地蔵、・燈籠、・三界萬霊 元禄二己巳天、・新:燈籠、・新:永代供養塔、・常緑樹:大木1、中木1、
・松平忠明の墓(井宮町194-4)
松樹院の少し北側の住宅地の路地を抜けた山腹斜面にある。
・説明版:九州の大名の子として生まれ、信濃の松平家の養子となる。信濃守。1798年幕府の命で北海道の奥地まで調査した。函館山頂に信濃守の詩碑がある。1802年駿府の城代となる。火災で粗末な仮の宮であった浅間神社再建の途中死去。駿府の人はありがたいご城代さんと呼んでいた。自分が死んだら浅間神社の木遣りの音頭の聴こえる所に葬ってほしいとの言葉に従ってここに墓を作った。
隣は古墓地である。・古墓地、
・静岡ホーム(井宮町183)(社会福祉施設)、
かつては井宮監獄、その後駿府城内の市民文化会館付近に移転、現在は静岡刑務所(東千代田3丁目)
・井宮神社妙見宮(井宮町179)
一般的にはここからが安倍街道出発点となる。
・籠鼻砦跡:賤機山城西端出丸、標高123m。
・月承句碑、 ?句碑:辞世、
・保食稲荷:無実の女囚にまつわる悲しい物語が伝わる、井宮監獄が駿府公園に移転したためここに祀る、食べ物の神。、・祠:稲荷神社? ・稲荷(2):大正二年、
・木鳥居、
・石碑:村社井宮神社 昭和十四年、・石碑:奉納 宅地拾壱坪 町内一同 大正拾年、
・石塔:(梵字)阿闍梨日海 雄大 僧林、・忠魂碑:明治四十年、・石階段:奉納 大正十年、・手洗石:、・手洗石:天保十一年、・石燈籠(2):、・狛犬(2):昭和六十年、
・石碑:天保六 雲泉~~~、・手洗石:明治九年・常夜燈:文政二、
・燈籠:文化十三、・燈籠:明治九年、燈籠:奉、・常緑樹:大木、
・石柵:(奉)納松永~~~、
・説明版:妙見山井宮神社:現在の拝殿は安永5(1776)年に再建されました。徳川家康が妙見菩薩(北斗七星の一つ破軍星)を祀ったので、妙見山の名の方が有名である。昔から妙見さんと呼ばれている。開運の神また薩摩土手の守護神でもある。北斗七星を祀ってあるので8月に七夕まつりをしている。
・説明版:徳川家康公跡地、安倍川石合戦見学地:臨済寺に人質の頃、山伝えに当社妙見宮に参拝され石合戦見学地と伝えられている。
・薩摩土手(籠上3-48)
徳川家康の命により薩摩藩が作った。家康からの命令だったためかなり気合を入れて作ったようだ。外様大名の薩摩藩の財力をそぎ落とす目的もあったようだ。これにより藁科川と安倍川が西で合流し今の安倍川東岸市中が安定することになり、現在の静岡市街のもとができた。
・薩摩土手の碑
平成元年
・説明版:由来:薩摩土手は権現様堤つづみ、または一部ひやんどて火屋土手とも呼ばれ、江戸時代の始めに造られました。薩摩土手という呼び名が初めて記録に見えるのは、旧静岡市史に掲載の天保13(1842)年に描かれた地図「駿府独案内すんぷひとりあんない」と言われています。静岡市史によると、慶長11(1606)年薩摩藩主島津忠恒公が徳川家康公の命によりここ井宮妙見下から弥勒まで約4㎞にわたって築堤したのが薩摩土手と言われています。この堤は、江戸時代以来、市民の生命と財産を守ってきましたが、今日都市化の進展の中で現存しているのはこの辺りだけとなっています。平成元年4月、静岡市、
・六部尊
・堂、石塔、
・川除地蔵尊(水道町116)
・地蔵:宝永四、・手洗石:昭和十七年、・堂、
・説明版:由来:水道町の川除地蔵尊は、井宮町にある泰雲山瑞龍寺の所属仏堂でありますが、水道町の「しばきり」即ち、最初から居住者であるといわれる故小林京作翁から私が聞いた川除地蔵尊の由来は次のとおりであります。
今を去る780年前のこと、その年の9月9日(初9日)、19日(中の9日)、29日(弟9日)と3回にわたり、安倍川に大洪水がありました。その時はいわゆる「イノコナグラ」といわれる激浪が渦巻き、堅固であった一番水道の堤防も刻々危険に瀕しました。時の水利方役人松岡萬は、地蔵尊の仏体を菰に包んで堤防の上に安置し、治水を祈願しながら衆人を督励して、防水に専念していました。附近の住民はもとより、安倍川流域の、殊に一番水道より灌漑用水を取り入れている農民たちは非常に心配して地蔵堂に集まり、連日連夜の対策に協議を重ねました。しかしこの度重なる大出水に対しては施す術もなく、拱手傍観途方にくれておりました。そこへ一人の老僧(俗に六部さん)が現れ「この大難儀お察し申す。拙僧もはや老齢ゆえ、安倍川流域の人々のために人柱となってこの堤防を守り治水永久のご安泰を祈り申そう。」と申し出て、念仏を唱えながら従容として堤防の中に埋りました。その老僧が唱える念仏の鐘の音は、それから七日七夜、堤防の中から消えなかったといわれます。これに力を得た水利方を始め、衆人一体となっての防水作業が功を奏し、ついに事なきを得ました。この地蔵尊は、それまでは厄除地蔵尊として、地方の信仰が厚かったが、それ以来川除地蔵尊として衆人の信仰の的となったということです。現在の地蔵の尊体には、その背面に「宝永四(1707)年丁亥天二月吉日」と刻まれてあります。即ち今を去る277年前、中御門天皇の御代に再建されたものであります。昭和61年8月24日、水道町町内会、
・湯浅堤の碑(柳町161)
・板碑:大正十三年、湯浅県知事が音頭をとって築いた堤防なのでこの名がある。
・洋館(籠上1)
古橋氏邸宅、13年12月に見たところ、塗り直したばかりで新しく見える。
・安倍鉄道線路跡(籠上1と7)
井宮小学校と古橋氏邸宅の間の道がかつての安倍鉄道線路跡である。
・賤機山城
標高173m頂上本丸、土塁、堀切が残存。徳川家康支配後廃城。
・(周辺紹介)賎機温泉 美人の湯(籠上15)
近年採掘された温泉、日帰り温泉。賎機山山麓と平地の間に温泉が出ることを証明したといえる。理屈上は出やすいようですが、ただ温泉採掘は1回1億円で2回かかったので2億円経費がかかったということのようです。
・難波神社
明治以前、小字の難波(どうも円成寺の南側)にあったが、1909年白髭神社に合祀。
・円成寺(籠上18)
1720年頃創建。仏堂内成庵と種徳院が合併し臨済宗妙心寺派となる。本尊:薬師如来。
・新:狛犬(2対):、・庚申塔:□政十二年、・地蔵:法華一千部之塔 文政三歳庚辰、・新:子育水子地蔵尊、・新:福神堂(大黒様、布袋様コレクション200~250体):大黒様布袋様好きなら一見の価値あり、おもしろ~い、・句碑:、・庭に新諸石仏多数、
・地蔵堂(籠上21)
長栄寺参道入り口
・玉井山長栄寺(籠上24)
1597年開基。本尊:聖観音。
・説明版:宗派:曹洞宗(禅宗)、当山は慶長2(1597)年に開創され、禅宗三派中の曹洞宗み属し、御本山は福井県の永平寺と、横浜市鶴見区の総持寺の両大本山であります。寺名の由来は、開基甫庵長栄の法名により、長栄寺と称されました。当山、本堂に安置されるご本尊は、古来より信仰深く衆生済度の仏様であります聖観世音菩薩でございます。境内には本堂、位牌堂、庫裏、山門と、夢のお告げによる井戸の中より出現された千手観音様を祀る観音堂と、その井戸が山裾にあります。また駿河一国札所の地蔵様が祀られております。なお著名人の墓も数基あり、本堂前左側には珍しい菩提樹の木があります。
・井戸観音:伝説では今川義元が桶狭間で討ち死に後、婦人が家宝の千手観音を敵に渡さぬため、この井戸に沈めた。後に僧が夢のお告げにより拾い、堂を建てて祀った。
・説明版:井戸出現観音の由来(聖観音菩薩様):その昔、永禄十(1568)年武田信玄が駿河に侵攻し、今川家七代目氏親うじちかが滅ぼされた。その折賎機山の砦におられし姫君が重臣と供に狩野城麓の菩提寺慈悲山増善寺に庇護を頂くよう尾根伝いに当地へ降りられました。しかし昔は賎機山と対岸慈悲尾の間がすべて安倍川の河川敷であったため対岸まで家宝を持っては渡れなかった。そこで姫君は今川家の家宝、聖観音像を何人かに託したいとの思いで、この井戸に投入されました。後年幸いにもその観音様がこの井戸より発見され井戸出現観音様と称され、金色に輝くご本尊様として、深く信仰を頂き現在に至っております。平成22年12月吉日、玉井山長栄寺、
・玉の井:寺の裏にあり、伝説では弘法大師作の観音がこの井から出現した。出現井戸、
・(欠):馬頭11基以上すべて欠損、如来:けっか座位2、・コンクリ手洗石:、・玉井山長栄寺本堂建設記念碑 昭和四十九年、・石塔:△寛文十二ニ壬子 一郷心信(行人偏に奇の字)庚申~(1672)、・新:燈籠2、・石塔:観世音出現之井 西国三十三所 秩父三十三所 観世音菩薩 天明六、・新:家石道祖神、・新:厄除平和観音、・新:慰霊塔 永代供養の塔 安らぎの塔、・新:水子地蔵尊、・西国秩父供養塔 文化六己巳、・菩提樹、
・新:六地蔵:説明版:お地蔵様の信仰は、中国では1340年ほど前、日本ではおよそ1240年前のようです。その中で六地蔵様の信仰は約890年前に始まったとされております。お地蔵さまは、この世の中のすべての人を極楽に送り届けるということを請願されました。この世というものは、仏教では六道、つまり六通りの世界のことを言います。六通りの世界が色々組み合わされてできあがっているので、ある時は争い、ある時は苦しみ、ある時は笑いあって人々は生活しているのです。六地蔵様は、それぞれ六つの世界を、一つずつ分担して救い守って下さるのです。延命地蔵様、水子地蔵様、六地蔵様と、名前はそれぞれ異なっても、後生、現世、来世にわたり、長い間救い続けて下さる仏様です。一回でも多くの御縁を結び、お参り下さることをお勧めいたします。
・白髭神社(籠上28)
1812年再建。1846年白髭神社と改称。・コンクリ鳥居:昭和五十八年、・手洗石:昭和弐年、
・貴庵寺、地蔵尊堂(昭府町、昭府2丁目32)
寺山峰への登山口。・西国秩父壱国供養塔 施主勘四郎 □(長反)安□四月、・庚申供養 寛延四辛未、・石塔:?読、・奉巡礼西国秩父坂東南無観世音菩薩供養(羊良) 寛政九、・板碑:新:寄贈檀徒一同、・新:地蔵、・新:五輪塔:海野家遠祖各霊菩提、・馬頭観世音菩薩 籠上新田望月清作建之、・新:燈籠2、・六地蔵+地蔵 寛永五年?、・新:手洗石:、・新:合葬塔、
・菖蒲神社(昭府町、昭府2丁目32)
・コンクリ鳥居、・変形家コンクリ道祖神、
・白髭神社(新伝馬3丁目14)
・石鳥居:御大典記念 昭和三年、・手洗石:平成23年、
・説明:略記:祭神:建内宿弥命たてうちのすくねのみこと、八街比古命やちまたのひこのみこと、八街比賣命やちまたのひめのみこと、所在地:静岡市新伝馬3丁目14番3号、祭儀:元旦祭1月1日、茅の輪くぐり祭6月30日、例大祭(日待祭)10月中旬、七五三祭11月中旬、由緒:創建の年月は不明であるが駿河志料等によると伝馬町新田は宝永年間(1704~1711)に開村され、貴庵寺(現、昭府町)境内に鎮座する左口神社を氏神として奉祭してきた。弘化3(1846)年に現所在地に新殿を建て、建内宿弥命を奉祀し併せて従来信仰してきた左口神社の祭神、八街比古命、八街比賣命を祀って白髭神社と称して以来、一村の氏神として信仰した。明治8(1875)年伝馬町新田全域の氏神として村社に指定され県の神社明細帳に登載された。本殿、拝殿は昭和16年に改築され、現在のものは平成16年に町民、氏子の浄財寄進により再建したものである。祭神のご神徳:①建内宿弥命は国の政治に非常に功績があり日本の国で初めて大臣となされた方で出世の神、長寿の神、子孫繁栄の神、として信仰される。②八街比古命と八街比賣命は夫婦の神で共にこの町内に外部から悪い病気や災害が入ってくるのを防ぎ氏子の安全を守って下さる神様である。
・松富団地入口(松富上組、松富1丁目)
現街道(県道井川湖御幸線)より東の山側にほんの少し狭い道跡がある。これが近代の道だろう。再整備されつつあり近代あるいは街中に残る古街道の景色は消えうせるようだ。13年12月に山側の古く狭い道跡は道路拡幅工事により完全消滅した。
・石塔:天下泰平 宝暦八戌寅 駿州安倍郡松富村 ○日本廻国六十六部供養塔 国土安全十月吉祥日 願主 藤浪定右衛門
・石塔:△ □□□
・白髭神社(松富2丁目-8)
・手洗石:、・石鳥居:大正十年、・石碑:、・神社名碑:村社白髭神社、・石柱:明治四十二年八月指定神饌幣錦(金なし)料供進指定社
説明版:お祀りしてある神様:祭神名:武内宿祢命たけのうちすくねのみこと(長生の神様)、品陀和気命ほんだわけのみこと(武運の神様)、須佐之男命すさのおのみこと(農業の神様)、菅原道真公すがわらみちざねこう(学問の神様)、瀬織津姫命せおりつひめのみこと(水の神様)、例祭日:10月17日、由緒:創建年月は不詳であるが、慶長2(1597)年2月に再建された。
・板碑(松富3丁目2、町内公民館)
・板碑:合併記念碑 昭和七年、・板碑:耕地整理碑 昭和五年、
・富慶寺(松富3丁目7)
・新:永代供養塔、・石燈籠、・新:子持地蔵尊、・新:六地蔵、・新:延命地蔵尊、・不動明王堂、・五輪塔:土水火、・地蔵、・地蔵か墓石?
・地蔵堂、白髭神社(上伝馬26-10)
・地蔵堂裏に墓石4基、・石塔:七世父母六観音□為 正慎六亥辰七月(正徳六丙申七月なのか?)、・石塔:読?、・石塔、
・木鳥居、・石:家:道祖神:稲荷、
・白髭神社(与一6丁目13‐16)
・木鳥居:平成二十四年、・庚申塔:昭和五十五年、・小川地蔵尊 海蔵寺、・庚申塔:文政石?年、・手洗石2:明治三十一年十月、神木2:杉、
・與一右衛門新田開発人 與一右衛門碑 平成十二年:説明版:わが町与一は宝暦元(1751)年奥津与一右衛門の手により開基、以来250年間、度重なる安倍川水禍をも克服し、今や戸数1400、ますますの飛躍疑いなく、ここに与一開基250年を記念し、奥津家継嗣にして志太郡大井川町宗高より移り越したる池ヶ谷一門によりこの碑を建立するものなり。平成12年10月吉日、
・石仏(松富上組4‐3、運転免許試験場入口バス停近く、水神橋近く)
・馬頭:天保十二年、山際に祀られている。
・道祖神、水神宮(松富4丁目9)
・石:家:道祖神、・水神宮 松富講中 明治二拾七年、市立北部体育館方面入口手前
・恩愛の像(与一6丁目17 市立北部図書館)
・恩愛の像:元駿府公園内設置:説明版:この像は昭和37年児童会館の開館5周年を記念して建てられたものです。本文:しろがねもくがねもたまも なにせむに まされるたから こにしかめやも 銀母金母玉母 奈尓世武尓 麻佐礼留多可良 古尓斯迦米弥母 山上憶良「万葉集」より 意味:金や銀や宝石なんて何の役に立つのでしょう。それよりすぐれた宝としては、自分の子にかなうものはありません。」といった意味で、わが子を思う親の気持ちをみごとに歌い上げています。
・川除地蔵堂、石塔類(福田ヶ谷328)、福田ヶ谷公民館東側丘上
・川除地蔵堂、・地蔵、・庚申供養塔 安永三、・庚申塔 昭和五十五年、石塔?、・馬頭?、・地蔵?欠、・観音?欠、・観音?欠、・馬頭、・如来?座像、・妙法馬頭観音、・馬頭 昭和二年一月 川村浅左エ門、・馬頭:?天明二、馬頭:昭和二十二年二月建之 川村兼吉
・日枝神社(福田ヶ谷779)
・コンクリ鳥居、・手洗石、
説明版:鎮座地:静岡市葵区福田ケ谷779番地、神社名:日枝神社(宗教法人登記昭和27年元月)、創建不詳、安永七年四月二日再建、旧社格村社明治8年2月、現在の拝殿は昭和53年新築、祭神名:大山咋命おおやまくいのみこと(山を支配し平野の繁栄を守る大神)、御神徳:聡明長寿、家内安全、五穀豊穣、産業繁栄、例祭日:10月17日、神社有地1254平方m、工作物:本殿、拝殿、その他、
隣の大塚氏裏山畑で白ヤギ飼育中(13年12月)
・石仏(福田ケ谷52)
・六地蔵、・三界萬霊等 文化四年、
・諸岡山(下122)
・「有功堤之碑、明治26年(1893)」、
説明版: 有功堤之碑:この石碑は明治26(1893)年従一位勲一等近衛忠煕篆額このえただひろてんがく、権中教正祝部宿祢生源寺平格ごんのちゅうきょうはふりべすくねしょうげんじへいかく、撰文静岡県知事従四位勲四等小松原英太郎書による記念碑である。この有功堤というのは山脇から諸岡山に繋がる堤防の内、諸岡山の自然堤を利用して、仮定(ヒジマガリ)という堤防の作りによって、そこに一旦水を溜めて水流の勢いを弱めて下流に流す仕組みの堤防である。この仕組みの堤防が安政元(1854)年に駿河国に大地震が生じ大谷崩れが生じた上に翌年6月30日の大洪水によって堤防は決壊して流域の町村の人々と田畑に多大の損害を与えた。明治七年稲葉利平が中心となって工役を督し、元の堤防に復旧した。それ以来一度も水害がなくなった。明治26年11月にこの堤防と人々の功績を讃えて建立された。下郷土誌作成委員会、
・「文化五□□年 奉納百八十八番供養塔 □本清拾郎」、「文化二年十一月吉日 庚申塔」、「文政五歳□年 奉納百八十八番供養塔 七月吉日 願主幸四」、「紀元二千六百年記念 庚申供養塔 昭和十五庚辰年三月 上之谷講中」、「昭和五十五年 庚申塔」、文殊地蔵、三十三身観音、普賢菩薩、観音堂、「忠魂ノ碑」、「戦没者慰霊碑」、・地蔵?欠:寛政十二歳、
・養秀寺(下122)
・「東宮殿下御成婚奉祝記念、大正13年」(13年12月未発見)、・馬頭観音「」(13年12月未発見)、・庚申塔 文化二、・庚申供養塔 □□歳、・禁葷酒(埋設)、・新:地蔵:杉村隆風、・如来?観音?墓石?:寛政十二年、・新:水子地蔵、
養秀寺門前石垣は鯨陽学校跡の石垣である。この学校が賤機南小学校前身で、この地域の近代教育の礎である。鯨陽学校より前には積善舎という私塾があった。
・石碑(下134-2)
・石碑:幕末志士稲葉彦兵衛出生地 大正十三年、
・上之谷、堂の藪跡地(下77)
・「庚申塔 吉文政七(1824)歳□ 甲申二月二十六日」、・他墓石4基、
・三輪神社(下226)
・鰐口「永正3(1506)年」、・コンクリ鳥居:昭和八年、・石燈籠2、・手洗石、・狛犬2、
・福成神社(下)
賤機山最高地点、近世には神社が祀られていたようだ。近年整備され整っている。
・新:狛犬2:、
・南無観世音菩薩、馬頭観音(下1088)、安倍街道土手の切通し
観音「文政四(1821)」、馬頭観音「明和六(1769)年、九月建之」、「十一面 馬頭観音 供養塔」
・説明版:南無聖観世音菩薩(土手観音様)由来:昔旧安倍郡賎機村下字山脇地域において、流行病(悪熱)が発生したといわれている。それゆえ当地域では病を退治するため、文政4(1821)年巳七月、聖観音を土手の上に建立し祀り悪病を防いできた。それ以来当地域は健康で明るい地として栄え以来180余年にわたり土手の観音様と崇められ、皆に親しまれている。このたび第二東名工事が行われることから、やむなくこの地に観音様を移すこととした。
・鯨ヶ池(下)、御用水(下284)
鯨ヶ池八景(福成の秋月、鴻巣の夜雨、窪田の落雁、大平の暮雪、御殿場の晴嵐、山田の帰帆、和田の夕照、諸岡の晩鐘)
湧き水を元にする。戦前菱が生えていて食用にしていた。
安倍街道鯨ヶ池出入口前に鯨ヶ池から流れてきた用水がある。これが街道に沿って南下し駿府城堀の水になったので、御用水という。この地点から堤防が賤機中学校東側を通り南から諸岡山北につながっていた。これを「有功堤」という。
御用水
・弁財天、宗像神社(下544)、鯨ヶ池脇
弁天様「明治3年」
・桜峠、地蔵(下554、北)
地蔵「明和3(1766)年」
・昼井戸(下832)
稲葉家横、道路から見られる。単なる側溝として見落としてしまうほど、地味で目立たないが、ちょろちょろと今でも少しずつ透明な清水が湧くようだ。
・石碑(下714-4)
・石碑:大平農道完成記念碑 昭和五十六年、
門屋からの鼓平農道と山頂鼓平で合流して門屋までつながっている。13年12月俵峰までの林道開設中。
・水天神(門屋99、静岡市水道局門屋浄水場敷地内)
・鳥居、社、
・門屋番所関所(門屋387)
街道横の白鳥家の辺りがかつての関所番所らしい。
・宝寿院(門屋639)
曹洞宗、本尊:阿弥陀如来、かつては地蔵堂と大日堂もあった。本堂北側は改修されてしまったが、かつてここに勝海舟の別荘の海舟庵があった。
・内野紀伊守藤原宗重 寛政十戌午歳、・庚申供養塔 文政十三、・奉待庚申供養塔 享保五、・観音、・地蔵:文化□、・六地蔵、・燈籠、・石碑3、・新:百観音、・板碑:忠魂碑、・欠:宝篋印塔か五輪塔の相輪か空輪らしき?
・勝海舟屋敷跡:説明版:勝海舟(1823~1899)は、江戸末期の幕臣として生まれ、通称麟太郎といった。幕末の騒然とした時世にあって、蘭学、兵学に通じ、幕府海軍の育成に尽力した。万延元(1860)年咸臨丸艦長として、遣米使節を乗せ我が国で初めて太平洋を横断した。そして明治維新の際には、幕府の陸軍総裁として山岡鉄舟を使者に立て、官軍の参謀であった西郷隆盛と会見し、江戸城の無血入場、徳川家の家名存続、慶喜助命に成功したことはあまりにも有名である。明治維新後、多くの幕臣は、元将軍慶喜の後を追って静岡へ移り住んだが、海舟一家も静岡市鷹匠町に居を構えた。海舟は旧幕臣の面倒を見る傍ら新政府の仕事をするなど、多忙な日々を過ごしていた。この頃ここ門屋の名主、白鳥惣左衛門と親交が始まり、頻繁に門屋を訪れた海舟は、この地の美しい自然に強く心をひかれ、母信子の隠居所として白鳥家の一寓を借りて孝養をしたいと念願した。しかし母は息子の孝心にもかかわらず間もなく他界した。その後海舟は少しの暇を見つけてはここ門屋の家に来て、秘かに要人と会い、また村人と肩の凝らないひと時を楽しんだ。この家屋は、その後白鳥家の屋敷内に移されていたが、昭和32年宝寿院境内に再度移築され現存されている。昭和60年1月、静岡市、
*宝寿院和尚榑林雅雄氏によれば、その後息子夫婦の家として新築し直したそうだ。昔の家屋は消失したようだ。
・八幡神社(門屋542‐1)
創建不明、1713年再建、・コンクリ鳥居、・コンクリ燈籠2、・手洗石、・石:家:道祖神、
・石碑:鼓平農道完成記念 昭和51年7月(門屋)
門屋奥から鼓平山頂まで舗装され下の昼井戸からの大平農道とつながる。13年12月俵峰までの林道開設中。
・三味線滝、小僧沢、御殿場の御殿石、鼓平、ばんば、
滝や沢は門屋前を流れる沢を奥に詰めたところで途中まで農道で遡れる。皷平は農道を上り詰めて昼井戸との境の尾根の平らな茶畑の辺りで、かつて家康が鼓を打ったという伝説がある。
・三峯講(門屋390)
・祠:三峯講、・祠:地蔵2、
・天神(門屋381)
・観音、・天神之宮:祠、・新:燈籠、天神橋近く
・白澤神社(牛妻1139)
創建不明、1805年再建、付近に鉱泉、宝物跡、・石鳥居:大正五年、
・説明看板:延喜式内白澤神社 静岡市牛妻1139番地:鎮座、御祭神:伊邪那美命いざなみのみこと、建御名方命たけみなかたのみこと(諏訪神社)、大雀命おさざぎのみこと(若宮八幡)、木花佐久夜毘売命このはなのさくやひめのみこと(浅間神社)、例祭日:10月17日、御由緒:当神社創祀年月不詳。牛妻の開村と共に祀り始められたものと思われます。惣国風土記という古い書物に「白澤神社伊邪那美尊を祭る。和銅三(710)年元明天皇の御代に諏訪神社を添えて祭る。」という意味のことが書かれてあり、更に延喜五(905)年醍醐天皇の勅命に依り編纂された延喜式神名帳には「駿河国安倍郡白澤神社国幣小社。」と登載されています。これにより1200余年の昔には既に存在したことが証明され、また1090年の古より延喜式内の神社として、毎年の大祭に駿河の国府より国幣が献納された静岡市でも最も古い貴い神社であることが分かります。而して当神社は牛妻の氏神、産土神として村人を始め遠近の多くの人々の敬慕、信仰を集めて参りました。明治38年に牛妻地内の若宮八幡宮と浅間神社を合祀致しました。現在の社殿は昭和13年に改築したものであります。御神徳: 伊邪那美命=母性愛の神、安産の神、寿命を司る神、建御名方命=開拓の神、殖産興業の神、大雀命=富国救民の神、慈悲の神、木花佐久夜毘売命=美の神、婦徳の神、
・日陰山、観音滝
・牛妻原会館(牛妻625)
・祠、
・牛妻不動ノ滝、不動尊(牛妻丹野)、少女滝、聖滝、扇窪
・庚申供養塔 寛政十二年、丹野集落内、彫りが立派である。(牛妻1564‐1)
・丹野会館(牛妻1957):地蔵、
・不動の滝:不動堂、
・稲荷神社(牛妻)
・安倍鉄道旧牛妻駅跡(牛妻)
・県道沿い小萩橋より西の安倍川側の細い道で北へ向かうのが鉄道跡で牛妻保育園辺りが駅構内と思われる。小萩橋より南は県道より東側の道で門屋との境の天神橋辺りまでである。それより南は今の県道の西沿いを下の堤防(新東名)まで行くと思われる。
*詳細は別項目「安倍鉄道跡」を参照ください。
・牛妻水神社(牛妻2252)
・曙橋袂:東海自然歩道標識や説明版等、
・祠:地蔵(大2、小多数)三界萬霊、・馬頭:欠、・馬頭:昭和四年、・不動明王?、・馬頭:昭和四十四年、・地蔵、
・水神祠、・コンクリ鳥居、・石:家:道祖神2、
・板碑:東西両岸道路開通 静岡県知事斎藤滋与志
・福寿院(牛妻2233)
曹洞宗、1619年開基、かつては行翁山奥のごうりんにあったが移転したらしい。ごうりんから五輪塔を移したといわれる。寺門前に石塔がある。
・「葷酒不入寺内」、・石塔:東海自然歩道十二支観音 第一番札所龍爪山福寿院、・石塔、・石塔、・観音、・石仏:欠、・新:石仏、・句碑、・観音堂、・燈籠4、・新:六地蔵、・地蔵、
・津島神社(牛妻2233)
福寿院墓地横で祠3、祠手前に神木の杉大木2本。
・コンクリ鳥居:昭和三年、
・説明版掲示:国幣小社津島神社本社由緒略(田と各を上下に記述)記:所在地:愛知県海部郡津島町向島、名古屋より西へ五里、東海道線名古屋駅前柳橋より津島電車にて約40分、尾交一之宮駅より尾西電車にて約40分、関西線麗?富駅を電車にて約20分、御祭祀、御祭神:素鳶鳴尊すさのおのみこと、天照皇大御神の御弟袖にまします世俗□唱へ奉る大神なり、相殿 大冗牟遅命、またの御名大国主命と申し素鳶鳴尊の尚女神にまして世俗大国様と唱へ奉る大神なり、二柱の大神の御神秘の大要を称へ来れば武運長久勝利開運の神として
○方除厄除殊に悪病退治除去の守護神として
○縁結び及家庭円満の守護神として
○文学の祖神、特に歌道の守護神として
○造酒の守護神として偉大なる御神秘を題し給ふ
由緒:欽明天皇元年庚申六月朔日の御鎮座にして古来日本総社津島牛頭天王と称し皇室の崇敬は固より部門武将殊に織田信長豊臣秀吉徳川家康の崇敬最も厚く四条天皇の仁治年中本社造営遷宮の事あり、後亀山天皇の弘和元年辛酉冬大橋三河守貞省勅を奉じて本社を造営し永享九年丁巳十二月五日足利六代将軍義教続いて造営し文明四年壬辰六月六日足利八代将軍義政の命により又永禄八年乙丑十一月二十日足利十三代将軍義輝の命により造営遷宮の事あり天正の頃伊田信長殊に尊崇して本殿を始め楼門回廊に至るまで屡々修復を加え或は神領神器を寄付し奉れり文禄二年己巳豊臣秀吉又造営し慶長十年乙巳清州城主松平忠吉殿舎を修理し元和五年己来徳川二代将軍秀忠再び修理を加えらる慶安三年己丑尾張僕義直厠御神供所及橋等を造営し爾来必要に応じ修理材料及料銀等寄付あり、又尾張僕に祖先以来正月九日代参使を立てられ幣□料を奉納せらるるを恒例とせらる、亦者府よりは向島一園の地石一千二百九十三石九斗六合を寄付して神領に充て、其の他の待遇も熱田神宮眞清田神社と同格に受け給ひ後世に到り尾張五社の一つとして四氏の奉紫驚く神威林如として近きは関苅、遠きは樺太興料満州及宗邦人に並び参拝者は四対陸続として絶ゆることなし。
建物:本殿、渡殿、祭文殿、廻廊、拝殿、楼門、神庫、遂箱、絵馬堂、神水授与所、社務所、神水調整所、神苑亭等にして現在の本殿は特別保護建築物なり、其他の建物も本殿に準ずべき優秀な建築にて何れも朱塗宏麗を極む。
攝末社:約四十社ありて重なるは攝社居森社に御魂社と称し元此地に鎮り給ひしと云い傳ふ、攝社称五郎殿併堀田弥五郎正兼の建立にかかる故に此称あり。攝社八柱社、和御魂社、荒御魂社にして境内境外に奉斎す。
寶物:古鏡数十面、霊元天皇御直筆、後桃園天皇御□筆、織田信長書、国宝太刀大原真守作、国宝剣長船□党を初め多数の宝物、古文書を蔵す。
氏子:津島町約参千五百戸当社の氏子に属し殊に大宮向島に古来より神領として縁故最も多し。
附属講社:神社直轄の講社ありて太々講とす津島神社、宮司是が総理となり社殿一切を統括し神社を□□□の間に結社使ありて一カ事を称□を何人にても入社して社□たることと殊に神社は謙社の島の毎年一月十五日併に四月一日より三十一日間とに家運長久家内安全の□□を執行し四月中は毎日二回神□を勤行す。講社員は毎年金五拾銭を奉納し参拝なべる様に程々の待遇を受け現在□□は約参拾五□金に□□、益々隆昌に向ひつつあって菱大なる御神従に浴す。
附近名所:天王川、天王池とも称す。 有名なる銘祭は毎年陰暦六月十四日十五日此の池にて執り行はせらる車案の妙音は神入共に感動、万燈の蝋燭に天を発し地に転じて社麗□なし、遠近より宿でも拝観するも無慶数十等、名古屋鉄道社終夜間断なく運転池辺の公会堂には無料宿泊所を設け貧者に便宜を與ふ。 池の周囲の根上には桜楓満開春秋は美観を極め殊に或夏の候は納涼絶好の池なり。池の附設地に大スタンドあり。當に重要せらる。 昭和四年五月二十一日 本社参拝(参詣)記念 奉納 荻野力蔵
*撮影した写真の具合がよくなく読めない字があり、適当に字を当てたため意味不明な個所が多い。済みません。といってやり直す気にならないのでこのままです。
・石塔:?読、神社より北50m、
・石:家:道祖神2、集落内、
・石塔(牛妻公民館2215-2)
・馬頭:昭和五年六月、・有縁無縁□□等、・?馬頭:、・庚申塔:昭和五十五年、・石塔:?読、・庚申供養塔 大正九庚申年、・庚申供養塔 寛政十二年、
・森谷沢
・道路開通之碑 昭和二十七年、
・馬頭、・馬頭大正十年:、・石塔、
・火の見櫓
・地蔵:森谷沢公民館横(牛妻2694)
・えんま淵、鬼穴:現在「安倍ごころセンター」に改変され消失したろう。
・四足門
松永家、徳川家拝領の茶碗
・地蔵:旧街道道端側壁
・樽下滝、昇竜滝、
・石:家:道祖神(牛妻3108)
・泣姫、恋の淵、コンクリ家型道祖神、椿の木、(牛妻3108)
・付近に案内板:泣姫、鳴沢の滝、行翁山、案内板より右折50m、
・説明版:泣姫の由来についていくつかの話が伝わっている。漣昇山武昇院院主連昇氏が泣姫さんについて書いたものの中では、「武田勝頼公の奥方清州姫は慶長17年、子供と別れ別れになり行方を尋ね安倍奥地に向かう途中、勝頼公自害の報を聞き53歳で後を追った。」と記されています。いずれにしても泣姫伝説には子供を想う母の姿が語られており、それが夜泣きを治してくれるという信仰になっていったと思われます。
・説明版:泣き姫:樹齢数百年の椿の古木と大きな岩石、早春には見事な花が咲き満開となります。「小萩」は祖益の悶死後、その後を追い「恋の淵」に身を投げたので淵にその名がつけられ、また小萩を憐れんで「なきひめ」として祀ったといわれています。また武田の残党某が行翁山に逃れてきて、行者として仏門に入りましたが、後を追ってきた妻は夫に会えないため、恋の淵に身を投じ、里人は美人の人妻を憐れんで祀ったともいいます。また行方不明になった夫を探して行き倒れになった美人の人妻を祀ったともいいます。
このように三つの説がありますが、この世の離別の悲しみのあまり、無常をうらんで死んでいった同情すべき女性であったことは、三者共通しています。この泣き姫は夜泣きの児を治す霊験はあらたかで、遠くの静岡の方からも伝え聞いて参詣に来たといいます。願いが成就すると、そのおはたしとして人形やお菓子を供えて帰ります。今行っても必ず一つ二つの人形があげられています。泣きひめの 碑にしみとおる 春しぐれ 海哉、牛妻町内会
・鳴沢滝、行翁二の滝、行翁一の滝、垢離の淵、
・説明版:鳴沢は行翁山から沢を登った山腹にゴウリンと呼ばれる所が伝えられ、かつて寺があったといわれています。この寺の鐘が山津波によって押し出され鐘が鳴りながら下った沢が鳴沢といわれています。
・上記案内板より奥に直進100m、そこから更に奥に徒歩300m、
・行翁山、ごうりん
・案内板より泣姫過ぎて自動車道500m、そこから更に徒歩で登山道40分、
・説明版:昔この山に行翁という行者が住んでいました。行翁は第49代光仁天皇の宝亀9(778)年6月、京都の音羽の滝を出て衆生済度のため、この地にやって来たと伝えられています。洞窟に住み、その跡は現在もあり頂上の行翁堂には翁が履いていた鉄下駄と鉄の杖が残されており、山岳宗教修験道の場所と伝えられています。
行き方は、泣き姫前農道を上り農道終点に至る。そこから奥へ登山道を7分登って分岐点に最初の石仏がある。
・観音:「左ワ行園山」の文字が観音の左、見ている人からは右に記入されている、牛妻分岐点にある。更に山腹の斜面を左に横平行に20分歩くと二番目の石仏がある。
・地蔵:「左ワ行園山」の文字が観音の左、見ている人からは右に記入されている、牛妻分岐点から3分の2ほど行った尾根をまたぐ所にある。
そこから15分で沢場に到着するが、そこが頂上ではなく、もう3分登るとお堂があり頂上である。
・行翁山の碑:行翁山 弘化二乙巳(1845)年三月建立之府中安西□屋安全 南無阿弥陀佛 平森谷澤安全、 刻字が綺麗で四面とも書体を変え見事な彫りで美術的価値がある。
・石祠:家型道祖神:「阿弥陀佛」、
・地蔵:天明二年、
・石塔:開山行翁 明治十八年、本堂裏側安置、
・木祠:
牛見石、掛軸(望月家)、鉄下駄、鉄杖、
・行者穴:人為的に彫られた穴で堂の右崖下に横穴がある。穴を掘ること自体が修業だったのだろうか。この穴の大きさだと人が寝泊まり可能であろう。
・三界の滝:滝が3段に落ち見事である。・説明版:滝の悲話:武田の武人の妻が修業中の夫を尋ねて当山へ来たが落人狩りに襲われ死亡したと聞き、悲しみ入水したという。
・本堂裏に細い登山道が続き竜爪山に至るようだ。その途中にかつて寺のあったごうりんという場所もあるようだ(未調査)。寺のすぐ裏は切り立った崖上の細尾根登山道で、いかにも修験者の修験道という趣である。こういう切り立った細尾根道をよくきん冷やしとかきん縮みということがある。肝を冷やすと同意味であり、きんはきんたまの意である。行翁山周辺はいかにも修験場にふさわしい。
・庚申塔(森谷沢、平、丹野、中沢)?
・養福寺(油山1295)、
本尊:観世音菩薩、開山:1601年、・石塔、・石塔、・石燈籠、
・白髭神社(油山945)
寺の手前の尾根先端丘上にある。・板碑:耕地整理、・手洗石、・石鳥居、
・油山温泉
油山より奥へ1.5km。
*地名の「油山」の油等の「油~」は「湯」と同義である。つまり「油山」は「湯山」の意で湯のある山で、文字通り温泉のある山で油山温泉である。
・油山山日月龍神社(油山1836)
湯の島分岐点手前道路横の山腹斜面にある。・石塔3「龍爪安倍川 元主、龍爪油山之光、龍爪松野大怨霊」、木鳥居、
・栗島峠(湯の島峠)H450m
湯の島と栗島を結ぶ峠道で国土地理院地図上ではルートが示されているが、12年1月2日廃道、湯の島よりH300m辺りで倒木や道不明で通行不可。
この峠道を再生し使えるようになると、1本北側の峠道「油山峠(相沢峠)(東海自然歩道)」とともに使えるようになり、油山温泉やホテルりんどうを含み、油山温泉―油山峠―相沢―栗島―栗島峠―油山温泉という周回往復ルートになって同じ道をピストンせずに往復できてハイキングコースとしては使い勝手がよくなる。相沢や栗島の集落は古い石仏、お堂、優秀賞花壇、足様神社等があってそこもハイキングコースとしてよい。
・油山峠(相沢峠)(東海自然歩道)H400m
油山温泉より200m奥の沢を渡り(H180m)南西に進む。東海自然歩道なので標識、道の安全状態はよい。多分迷いにくい。一部急坂やガレ場はあるが登山初心者向き、家族向きハイキングコース。峠(H400m)は植林で展望なし、ベンチあり。油山峠からトワ山東ピークに尾根沿いに行けるはずだが不明。(’12 10/14 玉川トレイルレースコースとして復活。)相沢側はさらに補修された安全なコースだが、一部沢沿いのガレ場上コースなのでちょくちょくガレるのだろう。豪雨や地震直後はコースがガレやすいだろう。相沢のホテルりんどう前に出る。
・油山稲荷神社(松野30)、
・祠:平成24年、
・板碑:農道完成記念 平成8年竣工、
・石塔(松野187、県道側壁)
・馬頭:昭和三年、・?地蔵:□□□十年、・石塔:?大乗経典か庚申か
・薬師堂(松野813、阿弥陀仏像、木像、平安後期)
河段段丘の茶畑内墓地の横。河段段丘になっている茶畑の辺り一面は別所平遺跡という。この岡上の平地は河段段丘といって、かつての河原が隆起したものである。この仏像はかつて200m西の山に寺があり、そこにあったという。この河段段丘にかつて文化の華が開いたのだ。石塔:「瀬川氏之碑 松野区 昭和三年十一月」「信州善光寺 西国三十三所 四国八十八箇所 供養塔 安政三」「庚申供養等 安永五」、句碑。
・「やくさんの井戸」、地蔵。
・松源寺(松野148)
・板碑:西国三十三所観世音菩薩 大正十年、・地蔵、・地蔵、・(梵字)地神塔、新・六地蔵、・殉国英霊の碑、・新:永代供養塔、
・松野城跡(松野)
河段段丘の西の山で農道を詰めた所。
・石造物(松野1040‐1)
・石塔、・庚申供養塔 大正六庚申年、
・白髭神社(松野1350)
丘上、灯篭2、
・三島神社(津渡野198‐3)
蔵王権現も祀る、神社の裏山を津渡野遺跡といい、さらにその上が城跡である。
・石鳥居:、・石碑:竣工記念 昭和五十九年、
・石造物(津渡野248)
・庚申塔 安永十年、・欠:観音、・○三界萬霊等 文政三、
・寶津院(津渡野328)
臨済宗、・堂、・地蔵、・新:地蔵、・石仏、板碑:静霊、・燈籠、・六地蔵+1、・地蔵、・新:聖母観音、・首なし:地蔵、・?観音、・三界萬霊。
・近くに木の祠:稲荷、
・津渡野城跡(津渡野)
城跡の東側は津渡野遺跡といい、その下に三島神社がある。
・水除地蔵(津渡野)
かつての竜西橋北袂に安置。小川地蔵。
・新:地蔵(郷島1210-2)
郷島入口側壁安置。
・郷島浅間神社(郷島373)
・説明版:静岡市指定天然記念物(植物)郷島浅間神社の大クス:指定年月日平成七年一月二十三日、所在地静岡市郷島373番地、樹高43m、幹周(目通り)13m、枝張40m、樹齢約千年、この大クスは市内でも屈指の大きさ、樹齢を誇る巨樹です。樹勢も良好で、またクスノキに見られる美しい樹形を呈しています。クスノキは、各地の暖地に多く自生する常緑高木で、木全体に特有の良い香りがあります。静岡県では、伊豆をはじめとして駿遠地方の暖地に多くみられます。材は、建築、造船、楽器、彫刻など多様に使われます。以前は防虫剤の代表だった樟脳もクスノキ材から作られました。平成12年3月静岡市教育委員会。
・金属鳥居:昭和六十一年、
・秘在寺(郷島518)
13年12月、元は茶畑で次に薬師庵があった所に移転したばかりで新しい2階建てビルとなっているので寺院とは思われない。・新:永代供養墓、新:石碑数基、・新:句碑多数「しずおか句碑の郷サト」、
・元の秘在寺の場所(郷島506)
元寺があった所は空地だが手前に石塔類がある。・石碑:□□□□秘在禅寺 平成元年、・新:六地蔵、・?庚申供養塔、・庚申塔、
・古い酒屋の名残の建物(郷島246)
昭和の雰囲気のある建物だが、壊れそうなのでそのうち解体されるだろう。
・石仏(郷島5)、消防分団小屋横
道より低くなった畑の北端にある。・地蔵、・?観音、・地蔵:元禄六癸酉□月二十四日造□塔 文化□□?十十月~~~~~□天明、・石碑:土地改良記念碑 平成四年、
・石仏(郷島)
郷島出口県道右側壁安置。・?観音、
・釈迦堂(野田平242)
・鰐口、・石塔7(地蔵1、如来1、他不明)、これより奥へ上ると墓地でその手前で尾根に到達し俵沢方向へ下る登山道あり。そこに峠の石仏が安置されている。
・石仏(野田平242)
・地蔵:安倍郡野田平村善男善女□□亥四月吉祥日、・馬頭:明治三十一年四月、・地蔵:大正十三年七月建之、野田平と俵沢の境の峠に祀られていることになる。
尾根を登ると静清庵自然歩道の一本杉及び竜爪山穂積神社に至り、尾根を下るとすぐに墓地で、さらに下ると県道梅ヶ島線及び俵沢に出られたはずだ。13年12月現在一本杉のすぐ下には林道門屋俵峰線が通過していて、そこに野田平へ下る登山道と標識があり、おそらくこの石仏地点へ至ると思われる。
・神社(野田平242)
釈迦堂の少し横にある。・石鳥居:昭和二十九年、・石:家:道祖神、・杉:大木7、・常緑広葉樹:大木:1、
・石碑(野田平)
野田平から野田平公園へ降りる道沿い。・道路開通記念 静岡市長小島善吉、・野田平一号線開通記念、・石、
・石碑:野田平公園 平成7年、
・石造物(俵沢236)
賎機北小学校南口付近、・二宮金次郎像:薪を背負い読書、・板碑:併合碑、
・石塔(俵沢365)
賎機北小学校から俵峰に向かう道を進み、坂道の直登道と左に迂回しつつ登る道の分岐点に出る。そこを坂道直登道を進むと右にある。
・祠:・庚申供養塔:、・?墓石、・地蔵:弘化三、・?地蔵、・地蔵、・?地蔵、・墓石:□□□居士 文亀元 □□□大姉 永正二 □□□居士 憲徳(延徳か正徳の間違い?)元 □□□居士 文□二 □□□大姉 慶長四、・一字一石法華経塔 □□□居士 明和九、この祠の横は墓地で墓石の後方には三十三観音が墓石と同じように祀られている。
・神社(俵沢400-1)
先ほどの左の迂回道を進み、左にカーブしていた道が右カーブに変わる所で左の沢横の道を沢沿いに詰めていく。
・石鳥居:大東亜戦争講和調印記念昭和二十六年、・杉:大木2、・赤橋、
・石碑(俵沢334)
俵峰への道を進み俵沢集落を過ぎ、茶園ばかりになると道路脇にある。
・石碑:静岡県棚田等十選に認定する 静岡市俵沢のつづら折り茶園、
・石塔類(俵峰400-1)
俵峰集落へ入る道は直前で左への広めの新道迂回路と右への旧道となる。どちらを行っても集落の中央で合流する。その合流地点に石塔類がある。
・板碑:道路開通記念碑 昭和三十一年、・簡易水道通水記念碑 峰の水みち 平成十六年、・馬頭:大正十一年、・観世音、・?観音:天保十三、・庚申供養、・馬頭:欠、・その他5~6基、
・玉宝寺(俵峰625)
・?立像:半僧坊大権現、・地蔵、
・水月院(俵峰)
・石塔2、・石垣、
・白髭神社(俵峰)
・石鳥居:平成十八年、・手洗石:昭和十五年、・杉:巨木7~8、・祠2、・旗指石:昭和廿五年、
・農道和田線完成記念碑(水月院奥)
この農道を奥に進んでいくと林道俵峰門屋線終点に至る。
農道の反対側の道はすぐに真富士山登山口となって自動車道は行き止まりとなる。
・天神山△724.5m登山口(俵峰)
集落北にある山が天神山724.5mであるが、集落から直接登る登山口はなく、真富士山登山道を利用し、引き落とし峠で西尾根をたどると天神山に行けることになる。地図では集落から山の東側鞍部を越す道が記載されているが全くの廃道で道はない。
・竜爪山登山口、静清庵自然歩道(俵峰323)
穂積神社や一本杉に繋がっている。
・駒引(曳)峠への登山口(俵峰323)
先ほどの竜爪山登山口、静清庵自然歩道入り口に至る舗装された農道の1本手前に左折する舗装農道がある。これを100mも詰めると道は消失するが、その先に登山道がある。これがどうも駒引(曳)峠への登山口と推定される。広岡氏「東海道山筋紀行」にも記述されている道である。松浦武四郎も通過したのだろう。この登山道を登っていくと茶畑に出て、先ほどの農道和田線に出る。付近の茶畑2箇所には道祖神や石塔が祀られている。
・石:家:道祖神2、・石塔
道祖神がある辺りに松浦武四郎も通過した古い道があったのだろう。
更に先で林道俵峰門屋線終点看板があり、その横に石道標がある。
・石道標:右くろ川みち 左やまみち、 *刻字書体は楷書に近い少し崩しただけの行書で字の大きさも一定であることから、作られたのは近代の大正から昭和初期と推定したい。
農道和田線と林道俵峰門屋線終点脇に祀られるが、多少なりとも移転されてのことだろうから、こことは限らない。しかし300mほど林道を上ると小さな沢を渡った所で登山道が斜面を直登していく。これが現在の駒引峠への登り口で古道もこの付近を通過していたものと思われる。そこで先ほどの石道標も移転されたにせよ近い所にあったと思われる。
右の黒川道が駒引峠道であろうが、左の山道はどこの道か不明。
・駒引(曳)峠
・地蔵:「文政六未歳四月初八日 炭焼邑 俵峯 大平村」 *施主名略、1823年
・一本杉、 静清庵自然歩道、富士見峠の西側、一本杉の巨木
・地蔵:「文政六癸未年八月二十吉日 河内村」 1823年
~俵沢に戻る~
・常夜灯(俵沢28)
クリーニング屋の前にある。
・祠(俵沢25)
安倍街道新道と六番への旧道分岐点近く。
・石造物(油島22)
今の県道より上の集落内の旧道沿いに朽ち果てた石仏が設置されている。また油島公民館前にも石像物がある。よくぞ古びても安置してあるものだ。地元民の信仰心のあらわれだろう。
・石仏と石塔:欠:6、
安倍街道は玉機橋を渡り、梅が島街道(後述)は渡らず川沿いに北上する。
・菜流寺(油島122)
・石碑:菜流禅寺、・庚申塔 昭和五十五年、・庚申供養塔 文政六年、・燈籠4、・新:観音立像、・戦殉碑、・六地蔵 大正十辛酉年 延命地蔵尊、・三界萬霊塔、
・歯痛地蔵(中沢189-1)
玉機橋を渡ってすぐ左にある。右土手先に土手の神様(石仏)。その先を寺屋敷跡という。
県道は直進するがここで右の中沢集落、永倉栄太郎氏宅庭先の石は縄文石である。明治43年畑で見つけたものだそうだ。さらに奥の相淵集落を紹介する。
・白髭神社(中沢215)
杉の木は最高樹齢500年以上らしい。500年前に中沢には人が住んでいたらしい。神社裏山左斜面に穴がある。
・石鳥居、・杉:巨木、・社、
・白髭神社(相淵168-2)
・石鳥居、・杉:巨木、
・大志野山、中沢・池ヶ谷峠(中沢、池ヶ谷)
中沢からはかつての静清庵自然歩道コースとほぼ一緒であるが、峠付近で自然歩道コースは峠に向かわず、隣の鞍部の鉄塔のあるところを通る。つまり電線巡視路にそって自然歩道がついているので、昔の峠道とは違う。奥池ヶ谷へは昔の道は沢沿いに下るのに対し、電線巡視路コースは尾根沿いを下りまったく違うコースとなる。昔の道は今はおそらく廃道だろうし、静清庵自然歩道コースも今は使われず廃道寸前かもしれないが、電線巡視路なので通れるかもしれない。昔の道はかつての生活道路。なお石仏等昔のなごりは無いと思われる。大志野山へは峠や鞍部から稜線上を南に上ればよい。稜線上を北に上ると見月山に行けるはずだが、どれほどきれいか汚いかは不明。
中沢から県道に戻り西進する。県道北側尾根先端を中沢遺跡という。西山橋手前に馬頭観音。西山橋を渡った先、左にも石仏。
・新:地蔵(中沢27-1)
・石造物(金久保)
・?馬頭 明治□□、・庚申塔 萬延元年、・石塔:たぶん庚申系金剛像、七月吉日、・?馬頭:□□二、
・石碑(桂山649-1)
県道と集落内に入る道の分岐点にある。
・原の道 昭和四十二年 西一九六七年 お茶は本山桂山にかぎる 特に優れた味香り 玉川の流れの如く清らかに一致協力明日にそなえて 昭和四十二年一月開通 飛出すな一度とまって又あるけ、
・地蔵:山伏塚 昭和五十九年再建(桂山365-1)
・天桂山長光寺(佳山220)
・新:石:家:道祖神、・新:如来、・地蔵、・新:動物慰霊碑、・新:六地蔵、・鐘楼、・?青面金剛?不動、・新:水子地蔵、・公孫樹の木、・無縁萬霊等 寛政八丙辰天、・石塔、
・白髭神社、桂山神社、大吾上人、たんごさん(佳山56-2)
・石鳥居、・板碑:殉国英霊、・忠魂碑、
・板碑(佳山139)玉川公民館
・
・細木峠
桂山と湯の島を結ぶ峠で、それぞれの麓から車で林道をたどり、途中で登山道に切り替えて徒歩十数分の上りで到着できる。現在は杉檜の植林地で薄暗い。石仏があったかどうか覚えていない。
玉川橋を渡ると大日峠に行く旧街道と横沢経由で富士見峠に行く新街道に分岐する。
~落合経由大日峠、旧街道~
・石造物(佳山片瀬)
玉川中学手前左にある。 13年12月工事中で見つからない。下記石塔類と同一かもしれず、移転したのかもしれない。
・石塔類(奥ノ原737)
・燈籠、・△庚申 寛政八丙辰天、・?如来か観音、・常夜灯、
・石塔類(森越587)
・庚申塔、・□供養庚申文□、・石塔:無縁塔、
・旧道:596番地付近から奥の原に向けて山斜面中腹を回り込む登山道がある。墓地に向かう道で、多分奥の原と森越を結ぶ旧道と思われる。現在の県道より20mほど上である。
・潭月寺跡(森腰)
本尊:十一面観世音菩薩、
・石塔類(長熊上平700)
・?石塔3?墓石、
・白髭神社(長熊上平773)
・石鳥居:昭和十二年、・手洗石:昭和三年、・祠、・杉:巨木、・杉巨木切り株の中から樹齢50年ほどの杉が生えている。神社横は崖で崩れかかっている。
・普門寺跡
本尊:聖観世音菩薩、開山:1580年、
・林道栃木線、舗装されていて起点より1.4㎞先で行き止まり、
・祠:?馬頭:明和三丙戌□月吉日(堂原1998)
・堂原の長熊橋袂より2168番地に向かう歩道が山を回り込むように付いている。
・かつての静清庵自然歩道であり電線巡視路でもある登山道がある(長熊から奥池ヶ谷に至る手前)
現在自然歩道としては使われず、舗装県道を迂回して中沢から奥池ヶ谷に向かうよう標識が出ている。この電線巡視路が古道ではないが、その近くを通過できる道として参考になる。
・奥池ヶ谷城址(奥池ヶ谷54)
高圧鉄塔のある川に挟まれた丘上である。
・向陽寺跡(奥池ヶ谷)
本尊:阿弥陀如来、
・朝倉館跡(柿島)
かつて安倍七騎の一人、朝倉氏の出身地とされる。
・定林寺跡(柿島492)柿島公民館横
・お堂:本尊:瑠璃光薬師如来、 ・社、
・お堂(柿島530)
・地蔵:明治四十一年六月廿日
・曹源寺(長妻田25)
曹洞宗、本尊:聖観世音菩薩、開創:1508年、本寺:長源院(沓谷)。山門の仁王像はユーモアたっぷりなひょうきんな立像で独自の価値がある。
・新:観音像、・新:供養碑、・板碑?、・石塔?庚申塔?、・燈籠2:昭和十五年、・鐘楼、・新:石仏9、・石塔:曹洞宗松尾山曹源寺 平成二十年、・胸像:得仙大和尚、
・中平との峠道、旧道、古道(長妻田25)
曹源寺の裏の墓地上から電線巡視路が見月山稜線に向かい上っていく。かつて中平とを結ぶ峠道だった。中平から峠のある鉄塔までは行ける。稜線も歩いたという山行を聞くことはあるが、現在相当な藪と思われる。反対に柿島方面に行く道もある。
・祠(長妻田151‐1)
・地蔵、・六地蔵、・石仏、
・布沢滝
布張沢の奥にあるはずだが、直接行きやすい道がない。近くに高圧鉄塔があるので電線巡視路で近くまで行けるのではなかろうか。
・白髭神社(長妻田764)
・コンクリ鳥居:、
・養福寺跡(油野)
本尊:地蔵菩薩、
・白髭神社(上落合157)
・石鳥居:昭和八年、・手洗石:水の溜まる所の形が扇形である、・岩2、・祠2、・石柵:平成元年、
・石塔類(上落合149)
向坂橋袂。・地蔵、・庚申塔:明治三十八年、・岩、
~ここから仙俣、奥仙俣へ行く。~
・精進滝(口仙俣)
上落合から口仙俣への3分の2程の所の道路左沢崖上らしい。
・白髭神社(口仙俣)
仙俣川を渡った先で橋はなく丸太橋を通して渡るようだ。道路から川向こうの鳥居と石段が見える。
・涌泉寺跡(口仙俣256)
・お堂:本尊:薬師如来、市指文:鰐口:写真展示、・木魚、・鐘、
・分校跡(口仙俣)
口仙俣から奥仙俣方向へ向かってすぐ左、
・林道黒川線
・記念碑
奥仙俣の手前の吊り橋袂の岩上、
・祠2:水神(奥仙俣59)
仙俣川沿いの主要道から川を渡った向うの集落にある。10月7日が祭りだそうだ。
・石塔(奥仙俣180)
主要道沿いの集落入口、
・大石、・庚申塔 昭和五十年十月、
・白髭神社と記載されているが山神社(奥仙俣)
まだ再建間もない神社で本殿拝殿等新しい。10月7日祭り、ここに至る自動車道もできたばかりのようだ。
・祠2、・山神社参道開設記念碑 平成十六年九月吉日、・木鳥居、
・不動尊滝(奥仙俣)
奥に詰めていく林道とは別の北東に向かう沢奥にあるようだ。
~~~落合に戻る。~~~
・石仏(明ケ島76)
県道沿い民宿明ケ島への分岐点、
・石仏、・馬頭、・地蔵、・庚申塔、・馬頭、
・石:ペイントで記入:明ケ島、・石:ペイントで記入:♨口坂本温泉→ 民宿明ケ島、
・石仏(口坂本630)
口坂本温泉集落の橋手前分岐点に安置。
・口坂本温泉浴場:説明版:清らかに流れる渓流と緑まぶしい山々に囲まれ、市営浴場を中心に民宿、旅館が点在する静かな温泉地です。市営浴場には30人が入れる広い浴槽の他、日本庭園の中に露天風呂も整備され、日頃の疲れを癒す人たちが世間話に花を咲かせます。所在地:静岡市口坂本、利用時間:9:30~16:30(16:00札止め)、休館日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)年末年始12/29~1/2、料金:大人¥280、小人¥100、泉質:ナトリウム‐炭酸水素塩温泉(重曹泉)、
・八王子神社(口坂本527)
・説明版:鎮座地:静岡市口坂本527、御祭神:建速須佐之男命たけはやすさのをのみこと、例祭日:7月15日、由緒:創建不詳、元禄17(1704)年再建、更に寛政9(1797)年再建、昭和27年同地区鎮座の白髭神社を合併し現社殿の造営をした、元無格社、毎年7月15日安倍川まで神輿の渡御がある。安倍神楽の伝承がある。
・金属鳥居、・手洗石:大正十一年、・手洗石:苔むしている、・常夜灯2:御宝灯 慶應元年、
・宝積寺(口坂本53)
本尊:延命地蔵菩薩、開山:1347年、門前に地蔵祠ともう一つ祠がある。
・祠2:地蔵、・燈籠:元治二乙丑、・燈籠:道路改修 昭和四十二年 地蔵平より、・手洗石:水たまり扇形、・自然石石仏、・三界萬霊塔 昭和四十七壬子年、
~・口坂本から大日峠への旧道(大日古道)、稲荷神社祠及び井川本村まで~
・説明版:①歴史と文化の街道大日古道:大日古道は口坂本から井川に通ずる唯一の大切な昔の道でした。上り下り3里(12km)の細い山道で1町(109m)ごとに一尺三寸ほどの観音様が通行人の無事を願って立てられていた古い街道です。我々はこの先人たちの思いのこもった道を偲び、次世代へ伝えていきたいと願っています。
②井川に縄文人が住んでいたことは驚きだが、脈々と伝えられてきた多くの歴史がある。例えば中野の千手観音、田代の諏訪神社、薬師堂、小河内の金山、大井川の刎橋。そして数々の例祭、そこで舞われる神楽、暮らしの中の伝承から民話まで数えきれないほどです。たった半世紀前まで、こうした井川を支えた唯一の道が大日古道でした。
口坂本―十六番―水呑み跡―大日峠―一里塚―二本松―登山口―渡船・井川ダム湖―井川、
坂本から井川までの旧道にはかつて66の観音像(口坂本~大日峠33体、大日峠~井川33体、井川側33体は井川大日堂に全て安置保存。口坂本側は6体確認という。)が安置されていた。現在復活作業中で、この区間での旧道が通れる。この旧道は1958年に林道が作られるまで本道であった。口坂本村内に観音像1、庚申塔1、村入口の民宿明ヶ島前に石仏5(庚申塔、観音2、地蔵1、不明1、)、
入口は市営口坂本温泉前で先の歩道橋で川を渡り、民宿羽根田前を上り、人家はずれで左の畑に入る。
・一番観音跡:口坂本の人家のはずれから山に入る境目にある。石仏(観音、地蔵)が2つ安置されている。13年12月には石仏は移転した。多分明ケ島道路脇に移転合祀したものと思われる。
・二番~五番までは口坂本集落上に巻いて大日峠へ上る県道に寸断されるまでの500m区間にある。県道に出るとしばらく県道を歩き、この上の空人家の先で山に取り付き古道に入ることになるが、県道に出た所の延長線上に古道の跡は電柱と電線に沿い進んで行き、空人家手前の県道の辺りで消失する。なお県道に出た辺りの上に鳥居があり、稲荷神社の参道がある。やや古道からははずれている。
・人家の先で山に取り付く。ここから先にはまだ観音跡の標識は未設置。500m先でまた県道を横断し山に取り付く。しばらくすると十五番観音跡がある。この手前に左へ分岐し大草利に向かう山道が地図上ではあるはずだが不明。十五番を過ぎると植林地内に石垣がいくつか見られ、「十六番」である。老夫婦経営の茶店と田があった。うどんや惣菜を売っていた。700m進むと林道に出て、その先に石垣と水が湧き出る所がある。「水呑み茶屋跡」で確か二十三番?だったように思う。この先30番まである。林道右手裏はすぐに県道との合流点でゲートで閉じられている。湧き水横を上り、三十番までたどる。しばらく観音跡がないなと思えると、稜線に出て左(南)に「富士見峠、大日山ハイキングコース」と分岐し、それを過ぎるとすぐ先に、「お茶壷屋敷跡石碑」がある。
・大日峠、お茶壷屋敷跡、石造物
「富士見峠、大日山ハイキングコース」:富士見峠から大日峠までの稜線上の山道。途中三等三角点、大日山△1200.6mを通過する。またもう少し南の昔の大日峠跡も通過する。 「お茶壷屋敷跡」はかつて徳川家康が茶会用の茶を保存するために作らせた蔵である。実務を担当したのは柿島の庄屋、朝倉氏と井川の庄屋、海野氏である。この茶を駿府に運ぶための道中を再現したお茶壷道中が近年実施されている。なお蔵については再現か否か不明だが、このすぐ先のピクニック広場に近年蔵が建てられた。
ピクニック広場手前に「三十三番観音跡」、「大日如来堂跡」があり、石仏が祀られている。駐車場・公衆トイレ分岐にも「三十三番観音跡」がある。この33番は井川側の33番で大日如来堂側の33番は口坂本側のものだろう。
・井川側の大日古道~大日峠から井川渡船場~
ピクニック広場を下ると井川の三十二番、ピクニック広場入口で三十一番がある。舗装県道の大日峠から井川へのルートを横断する辺りが一里塚で二十五番となり地蔵が祀られている。さらに下の井川少年自然の家正門前の道を進んだ所は二本松という所でこの辺りに十七番と十六番があり、十八番観音が祀られている。この下は大日作業道に付かず離れずに古道は下っていく。大日作業道と数回交差して4番まで至る。この100m下が井川湖で渡船場になる。ここに一応1~3番標識があるが、説明看板には水没となっている。井川湖は井川ダムによりできた現代の人工湖なので、昔は存在しなかった。この湖の下に村が古道が遺跡が沈んでいる。井川側の古道は静清庵自然歩道、井川少年自然の家ウォークコース等に利用されているので道自体はほとんど利用されて残っている。すばらしいことだ。
かつて村の女たちも背負子や持ち子として30~50kgの荷物を背負って歩いた。
~井川近くの県道等主要道沿いを紹介し、井川につなげる~
・慰霊碑、地蔵(井川3179)
県道の富士見峠を井川ダムに向け下り、大沢度橋を約1㎞過ぎた道路脇。
・慰霊碑:地蔵:昭和41年4月1日 行年49才 故関谷正重霊(車需)之地 故森竹さわ江跋畢之地 行年17才
・井川五郎ダム(井川1955) 調査:’14 3/15
昭和32年完工、コンクリート代を節約するため、ダム内部は空洞で中空式と言われる。
・井川展示館:水力発電の仕組み、井川地区紹介、井川地域の筏流しや電源開発の歴史等紹介。展望もよい。ダムが昭和の資料といえる。
展示館内にパネル写真の展示あり。09年2月公開映画『ヘブンズ・ドア』監督:マイケル・アリアス、主演:長瀬智也、福田麻由子、106分、厳寒2月の3日間、井川ダムにてロケ、公開が2月なのでロケは多分08年2月と思われる。井川ダム内部が数分にせよ見られるようだ そのパネル写真展示。
・井川水神社{祠、鳥居}、・石碑:井川湖、・板碑:慰霊碑:昭和三十二年、
・井川遊歩道
井川ダム建設時に使われた線路跡を遊歩道として13年秋に再現開設された。井川ダムから井川本村堂平まで歩ける。距離800m。近くに夢の吊橋がある。
・井川駅(井川1959)
ダム建設のために作られた鉄道で、一回り小さなトロッコ機関車の終点駅、もはやこれも昭和の生き証人か。この駅の奥にはかつてトンネルがあり、トンネルを抜けた先が堂平への遊歩道となっている。
~川根路~
・大井神社(井川閑蔵2246⁻3)
かつての閑蔵林道今は県道を川根本町千頭方面へ下り閑蔵駅前で閑蔵の集落へ下っていくとある。
・金属鳥居:、・子安観世音:大正十五年七月、
・説明版:鎮座地:静岡市井川2246‐3、祭神:岡象女命みづはのめのみこと、例祭日:1月2日、由緒:元禄元年創建と伝えられる。
~井川に戻る~
・石仏(井川西山平1850)
・石仏:青面金剛?、丸石:道祖神?、休憩所の横の交差点にある。
・井川大仏(井川1551)
・井川大仏、・毘沙門天立像、・石碑:大仏開眼:油山寺貫主、・コンクリ石碑:昭和五十五年、
・説明版:一刀二礼仏の手法にならい一言一言唱えて作像された。一切如来、井川大仏は昭和55年11月1日湖畔の丘、金畑山公園望寿台標高772m、日本地図の中心部に誕生した。
毘沙門天は福の神として七福神に数えられまた四天王として仏法の守護神とされ古くより親しまれてきた神であり仏である幸運守護の御尊体であります。
・庚申塔:天明五 門間 青面金剛
井川大仏分岐点と門間の間の県道側壁にある。
・龍泉院(井川582)
・石碑:曹洞宗龍泉院:平成十四年、・燈籠、・板碑5、・新:葷酒山門に入るを許さず、・禁葷酒、・山門、・新:句碑:多数、・仁王像2、・故篠原荘夫翁記念碑、・・新:無縁菩提供養塔、・石家道祖神、・鐘楼、・新:常夜灯5、・新:六地蔵+1、・新:子育地蔵、・新:観音、・青面金剛、・新:地蔵、
・説明版:開基は1504年(永正元年)賢窓常俊禅師に依る。草創期の頃は現在地より約200m「薬澤」寺地の一角に建てられていたと言われる。崇信寺末寺の平僧寺として創建されたものだが、その後災禍等もあり、また適地として現在地に室町末期1544年(天文13年)頃移築された。長歳月の中では老朽化激しく、寺歴に残るような修復等を重ね現在のような姿で承継されている。開基禅僧の賢窓常俊は、怒忠天誾(信濃の人) 崇信寺。洞慶院の開山僧に得度し、後に石叟三派の名僧を育成されたといわれる大厳宗梅禅師(崇信寺3世、本院隠居寺の千光寺開山僧)に師事し後に宗派最高の総持寺貫主に昇り、その後崇信寺。洞慶院4世等の住職になった高僧である。かような高僧開基による本院も戦国末期から徳川初期にかけ代々受け継がれた高僧たちにより、大井川流域に本院の流れを汲む末寺九ヶ寺を有する(うち五ヶ寺は現在廃寺)格式の高い寺院にまで発展した。本院も、かつては信州今川氏に仕え後に井川領主となった安倍大蔵守一族の手厚い保護や檀徒(500有余)の貢献等によるものが大きく、今や草創期以来500年近い歳月を経て今日に至っている。
2002年2月吉日建立 龍泉院29世王竜徳潭比丘謹書
本寺院の概観
本尊:聖観世音菩薩 昭和53年修復、脇仏:地蔵菩薩 平成12年修復、大権修理菩薩
開山堂 当山開山賢窓常俊像、宗祖 道元禅師像 聖観世音菩薩像、達磨大使象、
大日如来像
建造物 山門 寛保3年建立、鐘楼堂 昭和30年3月建立。大鐘 昭和30年3月、
六地蔵菩薩像。堂。平成12年、無縁墓地造成 平成12年秋彼岸吉日、
・門間地蔵堂(井川門間557)
門間の集落内の旧道沿いにある。
・常夜灯、・常夜灯、・地蔵:元禄三、・地蔵、・二地蔵:六地蔵の一部?、・三地蔵:六地蔵の一部?、
・井川神社(井川1467)
・コンクリ鳥居2、・燈籠2、・燈籠2、・狛犬:立太子20年記念、・手洗石:嘉永六、
・説明版:鎮座地:静岡市井川1467⁻2、御祭神:瀬織津比(口偏に羊)神せおりつひめのかみ、外19柱、例祭日:1月3日、由緒:昭和33年4月14日井川ダム築造により、次の5社を合併して井川神社を設立した。①大井神社、嘉禎4年創建、②浅間神社、創建年不詳、③大頭龍神社、創建年不詳、④山神社、創建年不詳、元禄7年再建、⑤十二神社、創建年不詳、元禄13年12月再建。井川神楽の伝承あり。
・大日院、中野観音堂(井川1120)
大日古道の33観音が保存されている。
・金属鳥居、・祠:八幡宮:、・祠:秋葉大權現 神明大神宮 津嶌牛頭天王、・燈籠:秋葉大權現、・燈籠:津嶌牛頭天王、・地蔵5、・観音:約40(三十三観音とその他、大日古道の33観音?)、・石塔:欠:多数、
・中野観音堂:説明版:中野は、江戸時代には井川七ヶ村の一つに数えられ、古くから砂金の採取が盛んな集落として知られていた所です。この観音堂は別当、副別当の2軒を中心とした中野地区の人々によって大切に守られてきました。堂内にはご本尊である「千手観音立像」の他4体の仏像が安置されています。いずれも針葉樹による一木造りで、平安時代中期に制作されたものです。仏像の由来についてははっきりしたことが分かっていません。地元では先祖が井川まで背負って運んできたと伝えています。その際里芋を食べながら峠を越えたとも云われており、観音堂のお祭りでは今でも里芋に味噌をつけた芋田楽が参詣者に振舞われます。観音堂のお祭りは1月6日と2月7日の2晩行われます。かつては一晩中お堂で過ごしたことから、このお祭りのことを「お籠り:おこもり」と称しています。そのうち1月6日は1年に1度、ご本尊が御開帳される日です。今では6日の晩に御開帳が行われていますが、かつては一晩おこもりをしたのち、1月7日の早朝、太陽の光が射し込むわずかな時間だけご本尊を拝むことが許されたそうです。その他、中野観音堂に残る応永31年(1424)の鰐口も静岡市の有形文化財に指定されています。
静岡県指定有形文化財:「木造千手観音立像・木造伝十一面観音立像・木造伝十一面観音立像・木造菩薩立像・附木造菩薩立像」、指定年月日:平成17年11月29日、制作年代:平安時代中期(10世紀後半から11世紀前半)、指定理由:いずれも平安時代中期の作で、後補も見られるが、全体的に古い様式を残している。駿河山間部における古代の仏教文化を考える上でも貴重な彫刻である。
静岡市指定有形文化財「鰐口:わにぐち」、指定年月日:平成20年3月26日、内容:面径22.0㎝、厚さ9.5㎝、銘文によれば応永31年(1424)11月に中野観音堂に施入された。指定理由:現在所在が明らかで銘文に静岡市内の地名が見られるものとしては最も古く、静岡市の文化史上貴重なものであると共に、歴史的意義と価値を有するものと判断される。
平成23年3月 静岡市(文化財課)
・井川メンパ(井川971)
海野宅
・南アルプス絵本館(井川991)
新しい公共施設なのでそれ自体が古道と関係しているわけではないが、井川地区の資料が手に入る。
・交通事故供養塔(井川中野)
県道沿い中野、登沢橋より北へ500m。
・事故多発所 南無妙法蓮華経 交通事故 遭難者 供養塔 安全運轉 昭和四十年
・石碑(井川)
さらに北上すると県道沿い。
・石碑:滝浪兼政青山之地
・不動尊堂(井川岩崎中山680)
県道沿い、中山バス停近くの沢滝横にあり。
・お堂:不動尊
・地蔵堂(井川大島54)
大島バス停前県道沿い。
・地蔵4、・祠:不動明王、
・大島神社(井川・田代・割田原260)
割田原の井川湖湖底に縄文期の割田原遺跡がある。他にも遺跡跡がいくつかある。
大島橋を渡った先にある。現在の橋の隣に以前のコンクリ製橋脚が残っている。
・金属鳥居、・燈籠、・祠2、
・説明版:鎮座地:静岡市田代260、御祭神:素戔嗚命すさのおのみこと、例祭日:1月11日、由緒:通称お天王さん。慶長9年創建、元禄13年、宝永、嘉政、文政と再建造営のあと、現社殿は明治35年総欅材を以て造営された。元無格社。境内は「鎮守の森」に相応しく古木が生い茂っている。井川神楽が伝承されている。
・大井神社(井川・田代・割田原329⁻2)
県道沿い階段上にある。この上の台地にかつて井川北小学校があった。
・金属鳥居:平成三年、・燈籠1、・祠、
・説明版:鎮座地:静岡市田代329⁻2、御祭神:岡象女命みづはのめのみこと、瀬織津姫命せおりつひめのみこと、例祭日:1月15日、由緒:文禄元年勧請、同3年8月大井川大増水により流失し、寛永5年新社地に再建、宝永、明和と再建したるも、明治20年3月4日出火による類焼、仮社殿にて奉祀し、昭和35年4月26日井川ダム築造により湛水池に入り、本殿、拝殿、社務所造営の上現地に遷座した。元無格社。田代、岩崎両集落の産土神であり明治維新までは大村家が祠官職にあり、井川神楽発祥のお社である。
・田代集落内外の道(井川・田代)
オーミチ(大道)、梅の坂、堂の坂、南坂、別当坂、菅山街道、集落南旧道入口には秋葉常夜灯がある。集落西には天神2つあり。福寿院跡。手洗い井戸。旧道と新道北側出会いを薬師道。集落北東に共同墓地と水神。集落南端からの旧道は南坂で山へ続く。西の沢へ入る辺りに山神を祀る。
・秋葉常夜灯(井川田代762)
集落入口にある。形は常夜灯というより燈籠型だが常夜灯と刻まれている。
・常夜灯:大正十四年、
・石仏(井川田代681)
集落北端近くの辻
・二地蔵、・二地蔵か双体道祖神
・諏訪神社(井川田代855)
集落北端に鳥居と湧き水があって諏訪神社への参道入口となっている。また自動車道とは別に薬師堂に向かう歩道が延びている。この歩道は旧道(古道)と思われる。
小無間山登山口、県・無・ヤマメ祭り、神楽、雨乞い踊り。8km奥に普段禁猟区の明神谷があり、ヤマメ祭り用のヤマメを釣りに行く。市・建・田代の一間造りの民家、
・石鳥居:昭和四十八年、
・説明版:鎮座地:静岡市田代855、御祭神:建御名方命たけみなかたのみこと、八坂刀賣命やさかどめのみこと、例祭日:8月26・27日、由緒:信濃諏訪大社の御分社、嘉禎4年創建、神主諏訪權守が奉祀、享徳2年再建諏訪刑部奉祀、文禄、延享と再建、諏訪近江守が奉祀、現社殿は明治36年の造営総欅八棟造本格的神社建築である。閏年毎例祭日に神輿の渡御あり、特殊神饌魚釣祭、ヤマメ(魚に完)の粟漬、元郷社、明治維新までは海野家氏神であった。信州遠山より大井川支流信濃俣川を経て当地に来たと伝えられる。
・駿河田代諏訪の霊水:説明:この湧水は静岡市指定無形民俗文化財当社特殊神饌ヤマメの漁場明神澤水源御住池よりの伏流水にて4年に一度閏年毎8月26日神輿渡御の際右側の石積みは御旅所の台座であり、ここにて大神に霊水を献ずる。
昔からどのような渇水にもこの湧水は絶えたことはなく、里人はここにて若水を汲み年始となす貴重な生活用水でお井戸と称し親しまれ、また大小無間の登山者の必需水である。
水質検査の結果最優良水と確認されており、呑めばまろやか活力を生み、井川銘茶をこの水でたて、或は冷凍の上水割等に用ふれば、その味また格別なり。広く御愛用をお奨めします。
神社はここから徒歩にて約20分諏訪山頂にあり、この霊水にて身を浄め清々しいお気持ちにて御参詣下さい。
氏子は常に神社の護持運営に努めております。その費の一部として霊水御愛用の方々より何分の御奉賛を賜りますれば幸甚の至りに存じます。 諏訪神社社務所
・集落北端から山に向かって参道登山道が続くが、先ほどの常夜灯地点から林道で山上の諏訪神社本殿にも行ける。参道は一旦林道で断ち切られるが、林道を横断して又歩いて登れる。
・第二木鳥居:平成六年、・手洗石:一九二六年、・常夜灯2:大正十五年、・祠5、・杉巨木:御神木、・参道途中から大無間山、小無間山への登山道が分岐する。もしも車で来て登山するなら、神社本殿横の駐車場が広いので、そこに車を置くとよい。
・薬師堂(井川田代855)
集落北端より100m北。歩道もここに出る。
・常夜灯:昭和四年、・祠、
・外山沢山神社(井川田代)
県道南アルプス公園線沿い、畑薙6号トンネルと外山沢橋の間。
・石塔類(井川小河内)
小河内大橋を渡って小河内集落入口手前、
・地蔵2、・燈籠、・庚申塔:昭和五十五年、・道しるべ:静岡小河内雨畑線 山伏峠まで17㎞昭和55年、
・井川・小河内集落内外の道
堂の坂、井戸坂(井戸道)、イワン(ニワン)坂、上の道、下の道、コーギ道(ダシ山街道)、金山道(金沢金山道)などがある。南甲斐への道、南信濃への道、梅が島温泉への道がある。建正寺跡。
・井戸(井川・小河内)
湧き水、生活用水。
・阿弥陀堂(井川・小河内)、三十三観音、無縫塔
集落北端の共同墓地近く。三十三観音と無縫塔、他2体は埋もれていたのを掘り起こした。年号は「享保十年」「嘉永六年」「嘉永七寅」で1725、1853、1854年である。近くに八幡社。市・地登・小河内のヒヨンドリ、
・庚申塔、・燈籠、・地蔵2、・無縫塔、・三十三観音35、丘上で展望所。
・大井神社(井川・小河内32)
・石鳥居:昭和六十三年・平成元年、燈籠2:昭和十三年、
昭和46(1971)年遷座。
・説明版:鎮座地:静岡市小河内32、御祭神:弥都波能賣命みづはのめのみこと、例祭日:2月11日、由緒:創建不詳。棟札によれば、天正12年霜月火災により社殿焼失、87年後の寛文4年、宝暦3年、嘉永2年再建造営された。旧鎮座地井川ダム築造により、境内南側に崩潰を起こし危険な状態になり、昭和46年現地に移転した。元村社。閏年毎に例祭日に神輿渡御あり、井川神楽の伝承あり。
・小河内橋(井川・小河内)
現在の小河内大橋は昭和43(1968)年からでその少し下流に残る橋がこれで昭和28(1953)年から43年までとなる。その前は2つの橋の中間に昭和5(1930)年~28年まであったようだ。2014年3月この橋はない。この橋に行く袂付近に石塔類がある。
・石塔(井川・小河内)
・供養碑:昭和八年~昭和五十年、・板碑:遭難碑:明治四十年、・地蔵6:明治二十二・三十・三十九・四十二・昭和十二年・不明、
・地蔵:明治七□年弐月
集落奥はずれの林道井川雨畑線と林道小河内川線に分岐する手前の橋「小河内橋」(先ほどの橋と同名だが別橋)袂に安置。この背後の山上にも2通りの山道が分岐している。
・「林道井川雨畑線」の思い出
かつての静岡市の小中学校社会科用補助教材郷土資料冊子には林業や観光の為この林道を作った旨が記されている。それ相応の期待があって作られたようだ。
1980年代末、当時まだ舗装されていない頃、この林道をオフロードバイクで突破して山梨県側に抜けるのは至難の業というか、よほど運がよくないとできないことだった。四輪車では更にチャンスが減ってしまう。例えばこんな具合だった。林道に入って進んでいくと崩壊崩落していて道幅が1mしかない所がある。(だから四輪車ではチャンスが減るのです。)ある所では前方の道が島に見えた。どういうことかというと側壁上の崖が塊のまま崩落して道路上に塊のまま落ちているというか、樹木や草が生えたまま地面ごと道路上に載っているのでまるで道路上に島が浮かぶかのようだったのだ。数本の樹木は倒れていたが、数本は立ったままでいた。それをかいくぐるのが大変だった。それやこれやで県境の峠を越えて山梨県側に抜けてホッとしていたら、前方の橋手前の道路が、何か変なのだ。ブレーキをかけつつ進んで驚いた。橋手前の道路がすっぽり抜けて、道路や橋地面と同じ色の川水が流れているのが見えていて、何か道路の地面が波立つような乱反射するように見えたわけだ。それにしても道路の色と川水の色が全く同一に見えることも驚きである。橋の手前に河原に降りていく非常用道路が造られていて、川水のある所は土管を通して水を流し、その上を通過できるようになっていた。とても道路と言えた代物ではない状況が多かった。それがひとたび土建業者が入って道路整備すると、全く別物の道路のように快適に走れるのだ。ただそのように快適に整備されるのは少ない機会だし、ひとたび豪雨や台風が来ればあっさり半年や1年は通行不能の崩落崩壊である。近年静岡県側は舗装したが、だからと言って崩落崩壊が起きにくくなるとは思えないので大変なことだろう。山梨県側も大丈夫とは限らないのでいつ全線通行できるかははっきりしないだろう。県境の峠は大笹峠または山伏峠ヤンブシH1850mという。峠から山伏山頂△2013mへは徒歩20~30分であり最短時間登山路である。使用オートバイ:HONDA XL200R
・供養塔:昭和五十九年12月21日遭難 瀧浪武雄
林道小河内川線を1㎞進んだ所。
・雷神社(井川・上坂本239)いかづちじんじゃ
・金属鳥居、・祠2、・石家道祖神2、
・説明版:鎮座地:静岡市上坂本239、御祭神:別雷神わけいかづちのかみ、例祭日:1月7日、由緒:永政元年正月17日創建と伝えられる。元村社。江戸時代笹山金山の守護神として崇敬された。昭和36年11月27日同地区鎮座の山神社を法人合併されている。
・八幡神社(井川・岩崎)
・祠、・石碑:高祖王様:昭和三十□年、一王様は八幡神社に奉戴来~~~
14年3月岩崎地区には2軒家があるが住んでいる気配がない。
・井川峠(県民の森)
かつての生活道路。 現在ハイキングコース。
~横沢経由富士見峠、新街道~
・地蔵4(下平瀬)
下平瀬手前県道右上に安置。
・林道日蔭山線
・白髭神社(下平瀬)
・石鳥居:昭和四十八年、・岩、
・新:地蔵2(下平瀬1349)玉川園
・白髭神社(川島1434⁻2)
・石鳥居、・手洗石:明治十四年、・コンクリ燈籠、
・林道樫の木峠線(川島)
現在川島より起点となり、樫の木峠を越えて大川日向に至る。古道ルートについては下記の林道白石沢線を参照。
・玉川西公民館(大和8⁻5)
・二宮金次郎像(薪背負って読書)、・石碑:玉川西小学校跡、・卒業制作石膏像、
・?祠か社(大和951)
・石:家:道祖神(大和838)
・林道権七峠線(大和1037)起点
林道を300mも登ると愛宕神社がある。林道は3~4kmも進むと工事中で、その先を作っている最中だった。14年2月。
・愛宕神社(大和1037)
・手洗石:文政十二丑年(1829)五月吉日、・石鳥居、1829年、祠、
・馬頭(大和1037)
道路脇茶畑上に立つ。
・馬頭:明治十一年 岡田彦太夫建之、隣の家が岡田家である。1878年、
・庚申供養塔(大和1029)
・庚申供養塔 安永八巳年 亥十月吉日 安倍郡 寺尾邑中、1779年、
・石塔類(内匠256)
大和から内匠に進み、白石沢に架かる白石橋の手前県道左に安置。
・西国、・?、・庚申供養塔 安永七(1778)、・?馬頭、・?馬頭、・?観音:安政四(1857)、・?馬頭、・地蔵、・?観音:文政十弐(1829)、・奉巡礼、・南無阿弥陀佛、・馬頭、・石塔、
・林道白石沢線、樫の木峠(内匠256、白石沢)
県道の白石橋を渡るとすぐ左に林道白石沢線の道と標識があり、そこに海野家がある。
1980年代末、林道白石沢線を進み、行き止まりから徒歩で進み、丸彫りの石地蔵を右折し進み、沢へ出て地蔵(不明、海野家の老女が話していた、登山後私が見ていないというと、無くなったのかもしれないと言った、沢沿いにあったのなら流されたのかもしれない)を横目に渡り、斜面を上れば樫の木峠で、樫の木と石地蔵がある。現在林道樫の木峠線ができたのでこの旧登山道は使われずほぼ廃道と推定される。林道樫の木峠線は内匠手前の川島から上って峠を経て大川につながっているが、峠手前が厳しい斜面で崩れやすく車でいつも通れるとは限らない。なお峠から大川までには萩多和城址石碑、宝剣神社祠が見られる。林道なので旧登山道ではないが、峠よりかなり下の方の旧登山道は現在も使われている。かつては大川と内匠を結ぶ生活道だったろう。
上述は1980年代末の記述で2013年12月には現状が改変された。林道白石沢線は100mほど延長され、かつての石地蔵のあった分岐点が林道終点広場のようになった。ここに林道入口一軒家の海野氏により観音を幅50㎝の土管に入れ祀り直した。
20年以上前に見たのは確かに丸彫りの石地蔵もあったはずだが、今回観音(観音か馬頭)像しかないのはなぜなのか海野氏に聞くことができなかった。県道沿いの石塔類の中にもなかった。
・?観音か馬頭:□□□□(?右わらしな)ミち □□□□ミち:多分右左の行き先を明示していると思われるが判読不能、多分右が樫の木峠で大川日向村、藁科川、左は中村山、釜石峠、長嶋、栃沢、美和、足久保方面である。
このルートでの遡行を近年(2000年代)行ったものでは、広岡氏「東海道山筋紀行」に詳しい。峠直前は完全な薮だったようで大変苦労したようだ。帰路は二度と通過したくないのであえてこのコースをやめているほどだ。広岡氏が通過したのは松浦武四郎が通過しているからである。
樫の木峠より向うのコースは別項目「大川街道」を参照してください。
・白髭神社(内匠648)
・コンクリ鳥居、・手洗石、・公孫樹、
県道から東橋を渡ると下腰越集落である。
・馬頭(下腰越43)
・?馬頭、・?馬頭、
この馬頭の祀られている所から歩道が川沿いに延び吊り橋を渡って奥腰越につながっている。ちょうど県道とは反対岸である。このルートが古道と思われる。
・白髭神社(下腰越90)
・石鳥居:紀元二千六百年紀念 大正十五年、・燈籠:昭和十五年、常夜灯:安政四(1857)、・手洗石:文政六(1823)、・杉:巨木切株、
・神社(奥腰越639)
・お堂:地蔵、・常夜灯:安政五(1858)、・石塔、・供養□□、
・白髭神社(大沢259)
・石鳥居:平成十八年、・杉:大木数本、巨木ほどではない、
・寺院跡(大沢286)大沢公民館
・葷酒不入寺内、・四国西国秩父□□八十八所供養塔 明治二十亥(1887)年四月癸日、・?青面金剛か不動明王:文化二(1805)年丑二月吉日、・庚申供養塔 皇紀二千六百年記念、
・大沢縁側カフェマップ(大沢)
大沢ではおもてなしとして大沢縁側カフェを毎月第2,4日曜日に開催している。集落入口にそのマップが掲示されている。
・祠:馬頭(大沢)
・馬頭:明治四十四(1911)年十月、・馬頭:文化十弐(1829)年、・馬頭:明治三□□年十二月、
大沢集落を過ぎ茶畑農道を一番上の奥に詰めた所に祠と石仏がある。
かつてはここ大沢から上り大岳の鉱山や笠張峠に出ていた。今でも登山道はあるが、車では行けない。なお大岳へ直登する道は頂上間近でなくなり、あとは稜線を行く。
この馬頭観音がある所を直登するのが多分旧道古道と思われる。これより上には登山道が延びていて、登りきると笠張峠から伸びてくる林道大岳線に接続するかと思われる。そのルートが旧道と重なると思われる。
この馬頭観音こそが大沢から笠張峠を越えて馬で井川に通じていた証拠である。
・石造物(横沢61)横沢集会所、小学校跡地
・地蔵2、・石碑:静岡市在住横澤會、・大石3、
・御嶽神社(横沢156⁻1)
東側から上った所。
・石塔、・地蔵、・(梵字)庚申供養塔、
西側から上った所。
・馬頭、・馬頭:明治五年、・馬頭:辰八月、
手前は墓地で神社は本殿があるだけ。
・燈籠(横沢291)
以前の長倉商店前の5m丘の上、以前の横沢バス停前。
・臥龍(権現)滝
県道から見られる。水量が豊富である。臥龍滝と名づけたのはかつての県知事である。
・一本杉峠
県道をさらに上った左手に電線巡視路、一本杉峠線があり、大川諸子沢に出られる。かつての生活道であり、今は登山道、電線巡視路である。
・笠張峠
大日峠に変わって使われるようになった。今では大川大間への分岐点となっている。尾根を通って林道大岳線沿いに大沢に出るのが古道ルートである。明治以前にも使われていたようであるが、発祥や推移は不明で、笠張峠からいかにして井川に出たか不明? おそらく三ツ峰付近へ出て井川または梅地方向へ尾根伝いに下ったのだろうか。また三ツ峰付近から大日峠へ尾根伝いに行くルートもあったと思われる。笠張峠から三ツ峰を省略して大日峠に行こうとすると大体今の自動車道ルートと同一化するので旧道を改変することで今の自動車道ができているのではなかろうか。
地図上での記載は標高1057mだが、大間と横沢、富士見峠に県道が分岐する地点では標高1100m。かつては大沢、大間、井川への分岐点であったし、今も分岐点である。標高がずれるように今と昔では分岐地点が違っている。
・富士見峠(井川3115)
現在の県道の峠で、休憩所、トイレ、駐車場がある。現在はここから尾根上の遊歩道で大日峠に行けるし、少し西下に自動車道も通じている。ここから登山道で三ツ峰にも行くルートがある。三ツ峰から七つ峰にもルートが延びている。
笠張峠と大日峠を最短で結び三ツ峰を省略するとおよそこの富士見峠を経由することになるので、この辺りを旧道は通過していたのではないか。
県道「南アルプス公園線」沿い、標高1184m、駐車場とトイレがあり、展望所にシンボル碑あり。三ツ峰(H1350m)へのハイキングコース入口があり、ほどほどの登りなので自然散策を楽しみたい初心者向けである。ちなみに北方にある現在の大日峠(口坂本温泉から井川へ行く県道越え)は標高1150m。
~油島からの梅が島街道~
・旧県道舗装街道(油島と蕨野の間)
河原土手の今の県道右崖上に昭和期に使われていたアスファルト舗装県道が一部残存している。不動沢橋付近に道祖神が祀られている。
・本山茶の茶祖 聖一国師墓所(蕨野24)
説明版:聖一国師は藁科川の上流栃沢の米沢家に生まれ神童の誉れが高く、栃小僧(頓智)と呼ばれていました。五歳の時久能寺堯弁の弟子となってから、蕨野仲野播摩正の家にしばしは手習いに来ていました。嘉禎元(1235)年宋に渡り禅を究め、仁治元(1240)年帰国しました。その時茶の種を持ち帰り足久保や蕨野に植えました。当時僧の中には医療に携わる者もあって喫茶が養生法の一つにあげられ、茶は医薬としてたいへん珍重されました。江戸時代には将軍家の御用茶として、茶壺に納めて、お茶壺屋敷に保管し、お茶壺道中で警護されながら駿府や江戸に運ばれました。安倍川上流一帯は茶の適地として良質の茶を産するので、つくり初め本、味の本場であるということから「本山茶」の名が自然に生まれました。このように聖一国師は「本山茶」の種を安倍川筋にまいて、静岡茶を日本一にする基をつくったのです。国師墓所の寺号「医王山回春院」は茶の医療効果と結び付けて付けられたのでしょう。ここに「本山茶」の茶祖として聖一国師を讃え顕彰いたします。昭和54年4月、聖一国師顕彰会 平成21年1月改修、
・回春院(蕨野103)
無住、聖一国師墓。
・地蔵、・尼□□□申塔、・三界萬霊十方至、・當院開山救證(了不)聖一国師大和尚 弘安三庚辰(1280):この墓石が1280年のものではなく数回再建されてきたのだろう、
・城山(蕨野)
蕨野から吊り橋を渡った対岸の山は中世山城跡。
・大聖不動明王堂(横山)
八重沢川を500m遡ると左(南)岸にある。
・白髭神社(横山75⁻2)
・石鳥居:昭和五十八年、・手洗石:昭和十五年、・燈籠2:昭和十年、・燈籠:昭和十一年、・燈籠:昭和五年、・燈籠2:昭和十一年、・板碑、
・石塔、墓石(横山35⁻3)
・?墓石、・庚申供養塔 文政八(1825)、・祠、・地蔵、・?馬頭、
・小川地蔵(横山)
水難除けの地蔵で焼津市小川が発祥のものを分祀してある。
・馬頭観音(平野)
平野入口県道右側壁安置。今はない。引き揚げたようだ。下記観音堂入口に再設置。
・観音堂(平野)
原橋手前東側に近年設置された。
・馬頭:昭和十四年、・馬頭:昭和十八年、・燈籠、・紅葉、・樹木
・手作りの石灯籠:説明版:この石灯籠は長い歴史をもった由緒のあるものです。代々栄えた大家の庭にあったものです。石工がタガネを打って造形した手作りで見事な風格をたたえています。お堂との落ち着いた風情が庭園の見どころとなっています。
・観音堂:説明版:聖観音菩薩像:江戸初期1600年頃:堂の中央に安置するのは聖観世音菩薩の像です。眼光の鋭い目から放つ光は苦しみ悲しみ悩み事など苦労の様々を観音様自身が受け止めて下さり、慈悲に溢れたひとすじの光となって私たちの心の中に力強い力を与え下さるのです。観音様はいつまでも健康長寿、安らかな永遠の旅路まで加護下さいます。阿弥陀如来:室町1540年頃:堂の右側に安置する阿弥陀如来様は体長60㎝と小柄ですが、なんと重さは70㎏もある像です。この如来様は日頃の悩みや苦しみの一つ一つを重い体重で踏みつぶして取り去ってくれるのです。この如来様は踏みつぶし如来と呼ばれ穏やかに見守って下さっています。心からの礼拝で必ずや願い事が叶えられるでしょう。
・地蔵(平野164)
集落内分岐点の祠に安置。
・大村家住宅、カブト造り(平野1052)
・国登録有形文化財 文化庁、・景観重要建造物、茅葺屋根の一風変わった屋根の形をしている。兜に似ているのでカブト造りと言われるのだろう。カブト作りの屋根は見応えがある。
手前の道路脇に五輪塔2基の古い墓石がある。
・平野の盆踊り
平野の盆踊りは県指定無形文化財。
・石碑(平野481⁻2)
・石碑:礼場椿道 開通記念 平成元年、
・白髭神社(平野112)
・石鳥居:大正十五年、・角柱型燈籠3、・燈籠2:大正十年、・板碑、・社、・祠、・杉:巨木、
・少林院(平野504)
境内入口に石道標(再建)「右ひらの 左もろおかむら」とある。もろおかむらは末高山周辺の村岡村むらおかむらのことだろう。
・庚申供養塔、・庚申塔 昭和五十五年、・新:百度石、・新:経塚、・燈籠:大‣中、・燈籠4、
・仏足石、・真富士観音第一番、第二十九番、・不許葷酒入山門、・学校発祥地、・石道標:少林禅院 左もろおかむら 右よこやまむら、・その他、
・真富士三十三観音
少林院に第一番があり、第二真富士山山頂に第三十三番が安置されている。第一真富士山山頂に第三十一番で、第二真富士への途中に三十二番がある。第二番は寺を出てすぐに曲がった所にある。登山道沿いにあるため、林道だけを通過してもすべて見られるわけではない。戦後の昭和三十年代にハイキングコースが設置されたのを機に安置された。第一真富士山頂の手前に真富士神社がある。
14年10月現在、第一番は県道沿い平野バス停横に安置されていた。
ふりかけ食品メーカーに真富士屋があるが、経営者が当地出身だからである。
平野集落を出て真富士山方向へ林道を進むとすぐに左下に茶畑がある平坦地がある。黒部沢河口の平坦地でもともと集落はここにあったと言われているが、黒部沢に土石流が押し寄せたため上に集落を移したらしい。
・朝日滝(平野)
集落県道から対岸に見えるが、滝に行く道はない。
・不動滝、不動尊堂(平野)
中学校裏手にあり、歩道がついていたが、崖崩れ対策で不動滝周辺一帯を高いコンクリ壁で覆い尽くしたため、全く滝を見ることができなくなった。もはや見たり遊んだりすることは不可能である。よじ登りかいくぐれば可能ですが…
不動明王堂はコンクリ壁手前に再建されてある。
・?角柱型燈籠、・石:奉納、
・末高五輪塔、末高館跡(平野)
大河内小中学校右手(北側)の山上(末高山)の茶畑内にあり、歩道がついている。館跡という。末高氏は安倍七騎の一人。子孫は東京在住という。この下の県道カーブを地元民は末高山のカーブと呼ぶ。
・五輪塔2、その他の墓石多数、
・白髭神社(中平343)
中平の集落は現在の県道より上の旧道(通行不可)のそのまた旧旧道沿い及びそれより高所にあるため県道からは一部しか見られない。現在の県道がほぼ河原に作られたため人が居住できる場所ではないからだ。街道が新しくなるたびに下に移転したため街道のダウンムーブメント現象の好例として観察できる場所である。
・石鳥居、・白髭神社 紀元弐千六百年弐月、・手洗石:昭和十五年奉納、・板碑:頌徳碑しょうとくひ 立浪碑、・燈籠2:奉納弐千六百年、・祠、・社、・手洗石:明□奉納安倍郡中平村観音講中、・燈籠:大正十年、・杉:巨木、
・お堂、公民館(中平61)
かつて臨済宗の寺院で移転したがお堂は保存した。
・庚申塔 安政(併のイなし?)年如月吉日、お堂の門前にある。この上の斜面に切通しらしきがあり、かつての古道かと思われる。
・古い墓石群(中平23)
・三界萬霊無縁塔、・他墓石多数、江戸時代年号あり、
・学校跡地(下渡493)
・心の碑 昭和四十三年 大河内北小学校、・石碑、・コンクリ像、
・しだれ桜(上渡185)
県道沿いに咲き見事。
・全福寺(上渡4)
寺の参道入口にある。・水難除供養(美良)塔 地蔵3、
寺の門前墓地にある。・六地蔵、地蔵、
寺の上のお堂横にある。・庚申塔 享和二年(1802)、・?石塔?庚申 元禄二己巳幸(1689)、・庚申塔 大正九年、・庚申塔 昭和五十五、
・石造物(渡本5)
・記念碑:孝子白鳥文八居住之跡 東宮殿下御成婚奉祝記念 大正十三年一月二十六日建之 安倍郡、・燈籠:奉納、
・東雲寺(有東木776)uto-giうとうぎ
曹洞宗。子安観音、大日如来、山葵田がある。
・堂、・庚申塔、・石塔、・新:六地蔵、
・白髭神社(有東木597)
・祠、・新:燈籠2、・新:手洗石、・石:家:道祖神、・大杉10:高さ45m、隣に祠:仏像:天保三(1832)、
・有東木白髭神社の大スギ:説明版:樹高35m(新説明45m)、目通り周囲6.6m、枝張15m、この神社の境内には樹齢約720(新説明750)年にもなる樹勢の良好なスギが十本程あります。有東木に集落ができたのは500年ぐらい前といわれており、このスギはもともと天然林であったと思われます。静岡市。
・有東木の無形文化財
国・無・有東木の盆踊り、市・地登・有東木のギリッカケ、市・無・有東木の神楽、
・石塔(有東木267)
・馬頭、・祠、・?観音:天保四(1833)、
・辻の地蔵(有東木691)
寺の手前の住宅の辻。別名:しょんべん地蔵、長いいわれがある。
・分校跡(有東木751)
寺の裏の空き地で消防分団小屋の横。昭和44年廃校。
・ワサビ発祥の田(有東木734)
有東木公民館の先。
・地蔵:行山安全:えぼし岩(有東木734)
有東木公民館の先。
・火の見櫓(有東木767)
寺の裏の分校跡地横。
・たかんば:凧揚げ場がなまった、景色のよい所・山の神:山の神がくれた景色が見える所、・そらんだん:空の段がなまった、展望がよい。・山葵栽培発祥の碑、
・山葵高原(有東木)、正木峠、地蔵峠、成島峠、細島峠
有東木の奥に山葵(ワサビ)高原があり、山葵発祥の地という。さらに奥に正木峠があり、藤代への道である。また地蔵峠を越えると山梨県の月夜の段に出られる。他にも成島峠や細島峠を越えて山梨県側に出られる。特に細島峠や成島峠越えが使われていたようだ。地蔵峠越えは新しいようだ。主にかつての生活道路である。今はいくつかが登山コースとして歩けるが、廃道もある。
・石造物(大和田523⁻4)
かつては有東木園という蕎麦屋があり石造物を置いていた。蕎麦屋がなくなった後もしばらくは石造物があったが13年12月現在は何もない。
・コンクリ製橋桁(大和田、瀬戸橋手前)
かつての吊り橋用橋脚と思われる。
・(藤代)
かつては正木峠で有東木とつながっていた。川が増水したときの山越えコースになっていたようだ。この集落はかつて土石流により壊滅的打撃を受けたことがある。
集落入口手前に藤代の滝がある。
・庚申塔(藤代329)
集落入口手前の道路脇に新しい祠設置。
・庚申塔 寛文八(1668)、・庚申塔 天保十五(1844)、
・桜(入島・数珠窪)
今は県道から外れたが、かつては県道沿いに桜がかかり見事。
・石仏(入島)
2010年以前集落入口の県道沿いに安置されていたが、13年12月現在は入島公民館の下記地点に安置。
・指月院跡(入島220)入島公民館
草創:1506年、本尊:聖観世音菩薩、
・堂、・奉請庚申待一結之衆中敬為延宝八庚申(1680)、・地蔵2、・石塔2、・石塔の笠部分、・石破片、
・祠:地蔵(入島289)
農協の茶工場や茶畑のある辻に祀られている。
・土砂崩れで崩落した昭和期の県道(入島)
昭和期に使われていた県道は、入島から湯の森への長大なスロープ橋の左のがけの中腹に見える。一応崖は修復されているが、根本的に処置できないためこの長大な橋を通した。
・神社(湯の森1029⁻4)
・木鳥居、・常夜灯2:明治三歳、・燈籠2、・観音:延宝三(1675)、・石塔:見ざる言わざる系の浮彫りなので庚申塔系と思われる、神社の社殿は彫りが見事である。
・石碑(湯の森1029)
・忠魂碑、・大東亜戦争戦没者芳名、・御大典記念、・平和、
・石碑:渡辺柔郎 髯先生の碑(六郎木1327)
梅ヶ島小中学校前の校門橋を渡った公衆トイレ横。
・梅島山宝月院(関の沢、梅が島545)、
本尊:釈迦牟尼佛如来、開山:1968年、宝珠院と指月院が併合、
・新:不許葷酒入山門、・新:六地蔵、・新:地蔵、
・関の沢の水力発電所跡(関の沢)
静岡新聞13年12月に掲載。関の沢川沿いに水力発電所が戦前あったが戦後役目を終えた。取水口や発電施設跡が残る。
・(大代)
井川峠とつながっている。ハイキングコース通行可能。
・石塔類(大代3083)
大代集落内の峠越えのような高所にまとめて祀られている。おそらく近年移転合祀されたのではなかろうか。
・祠、・庚申供養塔、・石塔、・地蔵、・三地蔵、・石塔、・石塔、・石塔の笠部分、・丸石、・穴あき石、
・御巣鷹山853.8m、天神山826m (大代)
大代集落東側の双耳峰(山頂が二つある山)の名前は南の三角点のある高い山が御巣鷹山853.8m、北の低い山が天神山836mだそうだ。どうも登れるらしく、集落の山頂真下の森下(地名)716mに登山標識がある。標高差137mなので20~30分で登れて両山廻って1~2時間ではないでしょうか。
・(本村)
バス停のある家の裏から戸持集落に上れる。かつての古道で昭和期まで子供たちの通学路であった。下るときは約15分だったそうだ。またバス停横の川向こうの林道(この林道は500mも進むと行き止まり)入口から真上に向けて上る登山道も東峰に上る旧道(古道)であり、現在も大光山登山コースとして使われる。そしてこのコースも東峰の通学路だったのだろう。
「古道は通学路として近年まで残存しやすかった」といえる法則が成り立つ。そして古道は登山コースや自然歩道に選定されると残存しやすいともいえる。
・石塔類、神社(戸持3477)、兎作
集落内の戸持公会室横に祠や石塔が安置されている。
・祠、・稲荷神社、・?天神、・奉請庚申供養塔、・地蔵2、
戸持は急峻な山の斜面に茶畑が広がっていて、今は畑になっている所のいくつかで金の露天掘りがかつて行われていたという。今は茶畑ばかりだが焼畑農業との関係性もあるだろう。
戸持の一番北の高所の集落裏山に昭和40年代の地図上では鳥居マークがついているので、かつてはそこに神社があったと思われるが、現在は東峰に稲荷大明神があり、戸持の神社は湯の森の白髭神社に合祀された。かつての鳥居マークのあった所は調べたが何もない。
そこへ行く自動車道は裏山の下で舗装が終わるが、その奥には無舗装の道が続き、立ち入り禁止となっている。
・兎作 '14 11/3
その500m先にはかつて兎作という集落があった。兎作は廃村となっている。壊れかけた廃村の家の庭に、すり潰し用の自然石:30㎝四方で上部真ん中がへこんでいて、鉱石をすりつぶすのに用いたのかもしれない。他に15㎝四方と10㎝四方の丸石自然石が2つあった。
兎作の住人は最後3軒となり、大野木、古庄、末広町へ出ていったという。最後に残った2軒は、清水区の人が1軒を買い取り別荘にしているという。もう1軒はどうも吾作小屋というようで、大野木から戸持に来るとき通る舗装道から登山道が分岐しているようだ。
・神社、古道(東峰1959⁻2)
・赤祠、赤鳥居: 稲荷大明神、
神社横に標識:「日本一高い茶畑海抜1000m」、地図で確認すると標識のある神社前で標高900mで目の前の斜面の上に続く茶畑の最高所で1000mと推定される。その横を登山道は進むと思われる。登山標識「東峰←→大光山」があり、上る道は茶畑横を上り大光山に至り、ここから下山する道が本村バス停に続くことが分かる。
13年12月付近で飼われている犬が人懐こく近づいてきて癒された。
ただこの道がいつから使われているか証明がないので古道と言い切れるかは不明だが、旧道であることは言い切れる。もっと古い古道があるかないかは今後の調査研究を待つ。一応この旧道を古道と推定したい。
東峰も金の露天掘りとの関係がいわれる。焼畑農業とも関係あるだろう。
・(孫佐島)
井川峠とつながっている。ハイキングコース通行可能。現在市営キャンプ場。
孫佐島に渡る橋の手前に祠がある。橋を渡った所の山に取り付くと井川峠コースとなる。
・祠:金谷山神社、
・(大野木、戸持、東峰)
現在梅園、テニスコート、温泉民宿の地。この裏から戸持、東峰集落に行ける。この集落はかつて金の露天掘りをしていたと推定されている。なお六郎木集落の一つ上流の本村から徒歩で上って行ける。それが旧道(古道)である。
・刈安峠(草木)
東峰同様、刈安峠越えで山梨県につながっていたが、崩落だらけの危険なコースなので現在通行禁止となり廃道である。私も滑落しかかったことがあった。刈安峠そのものへは草木から大光山経由で稜線へ出て歩ける登山コースが設定されたので、稜線をたどり稜線上の鞍部として通過できる。なお山梨県側も廃道である。石仏やいわれのある樹木等はない。かつての生活道路。
・赤水の滝(赤水)
増水したとき水が赤く(赤茶色)濁るためである。この上流に大谷崩れがあるので土砂を含みやすかったのだろう。展望所が県道下にある。県道は滝の真上を通過する。自転車で上るとこの街道中もっともきつい上りである。
・(新田)
大谷崩れにより大量の土砂が集積し、金が取れなくなった日陰沢金山から鉱夫たちが移転し開拓した土地。市・無・梅が島の舞。
・稲荷大明神(新田5554)
この裏から登山すると、七人作りの尾根という安倍奥三大遭難地帯の稜線をたどれるようだが、すさまじい藪を通過する危険地帯なので素人は行かないように。
以前は小さな祠しかなかったが、13年11月現在、参道や社殿が新しくなっていた。
・赤鳥居:幾つか、・板碑、・新:燈籠2、・手洗石、・石碑:奉納正一位稲荷大明神百五十年祭記念碑、・石段、・燈籠2:昭和~、
・願勝寺分院(新田)
・大谷崩れ
日本三大崩れの一つ。扇の要から新窪乗っ越しを経て大谷嶺(三角点所在地△1997.7mだが三角点がすでにない、崩落したようだ)や山伏岳に上れる。一面のガレ場は見応え十分。
・日陰沢金山跡、奉行所跡、鉱夫たちの墓
魚魚(トト)の里の奥でハイキングコースになっている。入口の奉行所跡は休憩所になっている。近くには遊郭もあった。河原を数分歩くと集落跡の様子を石垣や段差等でつかむことができる。古い道もあり墓は山の稜線上にある。この街道中もっともスリリングなコース。一見の価値あり。墓石は小振りで甲州(山梨県)側で彫ってもらい鉱夫たちが背負って山越えしてきたものだ。もっとも新しいもので天保期(幕末)のものである。墓石が甲州のものということでいかに甲州とつながりがあるかが分かる。
入口周辺には市営黄金の湯、金山温泉、魚魚の里があり、レジャーに最適。
・宝珠院跡(梅が島本村)
本尊:釈迦牟尼佛、草創:1558年、
・市営温泉黄金の湯(新田)
日帰り温泉で土産物屋、公衆トイレ、無料駐車場がある。
温泉前の土手に梅ヶ島観光看板、砂防ダム説明版、三河内川床固め工群完成記念碑及びモニュメント付石庭がある。
川向うは魚魚の里と奉行所跡である。川の水量が少なければ靴や足がずぶ濡れになるのを覚悟すれば徒歩で渡河できる。ただし夏でも冷水で冷える。
・安倍の大滝(三河内)
最初の梅が島温泉民宿を右に入っていく。徒歩十数分。落差が多きく安倍川流域中最大の滝である。
・梅が島温泉
かつて市営温泉があった所は源泉取水場、湯之神社、公園になっていて、説明版等が多い。
・梅ヶ島温泉の歴史:説明看板:梅ヶ島温泉は、静岡市の北部、安倍川源流に近い安倍峠の麓に位置し標高1000m(級)の雄大な山々に囲まれた静寂な自然環境の中にあります。その歴史は古く、一説には約1700年前に遡るとも言われています。三人の狩人により発見された説、砂金採りにより発見された説、或は仙人が三匹の蛇が遊んでいる泉を見つけて発見された説など、梅ヶ島温泉にまつわる逸話が多数あります。
戦国期には信玄の隠し湯とも言われ、古くから美人づくりの湯と知られるこの温泉は、単純硫黄温泉で神経痛、関節痛、うちみ、痔、冷え性、疲労回復、皮膚病などに効能があり、ツルツルとした感触の良い温泉は清く澄み、時として黄金色に輝き、湯の花を浮かべ、長い間、湯治場として多くの人々に親しまれてきました。
昭和四年の大火、昭和四十一年の大水害等の苦難もありましたが、現在は旅館、民宿、土産物屋など十数軒が軒を連ね、その歴史を今なお継承しています。
この地、「おゆのふるさと」は、昭和四十五年に開設した市営浴場が平成十一年四月に梅ヶ島新田へ移転新築されたことに伴い、再整備したものです。梅ヶ島温泉の泉質を感じていただくお湯に触れる施設や湯之神社、岩風呂、湯滝等を回遊散策し、展望デッキからは梅ヶ島温泉街も一望でき、梅ヶ島の魅力を垣間見ることができます。
・湯之神社:猟師たちにより発見されたという。源泉上にある。・石塔:読めそうだが刻字不明、
・湯之神社の由来:説明版:正保二(1645)年初夏の頃、甲州天目山に治療中の良純親王は西方に霊泉ありとの夢のお告げを受け、それを尋ねて甲州路を安倍の峠へと辿られました。親王が重い足を引きずって頂上近い逆川のほとりで休息していますと赤い小蛇三匹が道に出て親王を導きました。(親王が持っていたお酒を盃につがれ差し出されると、それをなめられたといいます。)そして道なき道を西方に導かれ、やっとのこと温泉にお着きになりました。親王がこの温泉に入浴なさいますと三日で痛みもとれ、十数日で難病もすっかりご快癒になりました。
親王はこれを日頃崇拝する御仏が、権(かり)の姿でおいでになりお救いしてくれたものであると信じ、仏恩報謝の御心から持っていたお守り刀の備前長船祐定と紺紙金字の願経と水晶八房の御数珠を捧げられ三蛇大権現としておまつりしました。
しかるに、古来より「湯之宮三社(蛇)権現」と称されていましたが、明治に入り政府の神仏分離政策により湯之神社と改称、春秋年二回の祭典を行い現在に至っております。
・湯滝:説明版:湯之神社の脇にあるこの滝は、古くから人々の心を清め、和ませてくれる温泉の守り滝として奉られており、新緑青葉の時期に岩肌を滑り落ちる水しぶきは、昔と変わらぬ清涼感を今でも私たちに与え続けています。
・岩風呂:説明版:このお風呂が造られた時期は定かではありませんが、古くから美人づくり、子作り、長生き、健康づくりに御利益がある湯として人々に親しまれてきました。現在はここに湧き出ているお湯も含め、各旅館等に、源泉湯として供給されています。
・歌碑:あめつちの大き心にしたしむと駿河の山の湯どころに来し 勇
温泉旅館街から三段の滝へ行く道脇に慰霊碑がある。
・台風被害者慰霊碑:遭難者慰霊塔。慰霊碑、昭和41年9月25日台風26号による遭難者、遭難者個人名。水難地蔵慰霊菩薩 昭和四十一年九月二十五日水難犠牲者二十六名、増田。
・三段の滝:温泉街の上流、徒歩5分。
温泉街から安倍峠方向またはバス停のある方に向かうとバス停前にある。
・文学碑、吉井勇、あめつちの大きこころにしたしむと駿河の山の湯ところに来し、昭和十四年初夏。バス停前。
・摺石:武田信玄公の時代、新田部落付近に日影沢金山あり、其の当時金鉱を入れて摺り潰して□に流して金を得たものです。梅薫楼
・南無妙法蓮華経、昭和十四年、ひげ題目、
*山の中の地名になぜ「~島」が多いのか。島はシマで縄張り領分の意味があるようだが、一般的に島は水に囲まれた所である。この水は客観的に四方を囲まれた海(湖、池、沼、川)だけでなく、主観的に囲まれている、あるいは水のある所を渡って行く所も含むようだ。そうすると山の中でも川の向こうは「~島」である。
梅ヶ島温泉を三段の滝方向ではなく右折(東)してバス停方向へ行きさらに奥を目指すと、林道入り口ゲートと手前に八紘嶺安倍峠登山道入り口がある。古道は登山道であろう。ただし古式ゆかしいものは登山道沿いには見当たらない。以下は林道沿いのものも紹介する。林道豊岡梅ヶ島線は5月下旬開通、12月初め閉鎖となる。ただし林道が災害で通行不可能になることは多い。14年11月現在山梨県側は復旧工事中でここ3年ほど通行不可である。
・安倍の大滝の展望所、
梅ヶ島温泉より林道豊岡梅ヶ島線で1㎞進んだところ。標識「ここより安倍の大滝が見えます」、確かに滝の上部が見える。
・安倍の大滝への近道登山道、
梅ヶ島温泉より林道豊岡梅ヶ島線で1.5㎞進んだところ。標識「安倍の大滝入口、500m、安倍の大滝から民宿へ1.5㎞」
・鯉ヶ滝(恋仇)
梅ヶ島温泉より林道豊岡梅ヶ島線で1㎞進んだところ。看板標識がある。
「1、昔、安倍郡梅ヶ島村に住む百姓の三郎左衛門と湯治場の湯女(ゆな)のおよねとは、いいなずけの間柄だった。ある日、府中より馬場新之助という若侍がこの湯治場の腰痛の治療に来て、いつしかあ、およねと深い恋に落ちた。
2、二人の関係を知った三郎左衛門は、ショックの余り殺意を覚え、二人のいる湯治場に火を放ち山へ逃げ込んだ。そして、滝の上まで来た三郎左衛門は、湯治場にいるはずの二人の逢瀬の場を見つけ、逆上し背後から二人を滝下へ突き落してしまった。
3、住み慣れた村の空が湯治場の焼ける炎で赤く染まるのを見た三郎左衛門は、自戒の念にかられ、二人の後を追い滝下へ身を投げた。しかし、このとき彼が見た空は、火事の炎ではなく晩秋の美しい梅ヶ島の紅葉に彩られたものだった。
4、その後、三郎左衛門とおよねは緋鯉と真鯉に化身して結ばれ、仲良く滝に住んだという。爾来、この滝は「恋仇」(鯉ヶ滝)と呼ばれているが、事実は定かではない。」
滝は林道橋の上流側に見える。大岩の中を豪快に水が下っていく。
・八紘嶺登山口
温泉の林道ゲート付近からの登山道がまた林道と交差し、再び登山道に分岐する。付近に駐車場もある。
・安倍峠旧登山道
峠1㎞手前で林道からはずれた旧登山道入り口がある。沢沿いを進める。
・駐車場、公衆トイレ、富士見台の下
13年11月現在、梅ヶ島温泉よりここまで車で来られる。山梨県側が復旧工事中のためバリケードで車は進入できない。あと500mで安倍峠である。
・ハイキングコース案内標識:安倍峠~八紘嶺~梅ヶ島温泉 八紘嶺~安倍峠 八紘嶺~大谷崩、
・安倍峠、標高1488m、 '14 11/3
山梨県との生活道路で、かつては静岡市街側に行くより使われていた。川沿いまたは山また山を越えて歩く方が大変で、安倍峠等を越えて身延町側に出る方がましだった。オオイタヤメイゲツ等、秋に黄葉し更に紅葉する落葉樹が見事で、秋10月中旬に黄色というより午後の日差しを反射した黄金色の絶景は極楽のようだった。しかし地球温暖化の現在は10月下旬がピークである。14年10月25日はまだ緑、黄色、赤がぼちぼちでこれから1週間後がピークかと思われたが、11月3日に来たら紅葉を通り越し枯れ木となり葉は茶色く地面に積もって初冬景色となっていた。おそらく10月27~29日がピークで、あっという間に散ったようだ。
どうも地球温暖化で紅葉時期が遅れたが、終了は後ろにずれず、あっという間に散ることになったようだ。葉の紅葉の仕方は緑、黄色、赤、更には木についたままの葉が茶色く変色していくという、汚い紅葉いや紅葉しないで茶色く朽ち果てる葉がでる始末のようで、鮮やかな紅葉ではなくなっていくようだ。地球温暖化で夏が長期化したが、冬は例年通り来るので、秋が短期間化し、紅葉しきれず朽ち果てるという情けない紅葉になるようだ。
オオイタヤメイゲツ(カエデ科カエデ属):一般的には散生するが、このように群落をなすことが珍しいので学術参考林(昭和56年)となっている。そのため林道を峠から少し外れた箇所に作り県境を越すようにした。工事費がけた違いにはねあがったそうだ。
峠を旧道に沿って梅ヶ島方向に下ると500mほどで水が湧き出し川になるところを見られる。安倍川水源地の標識がある。まあ安倍川の最初の1滴といったところでしょうか。 更に1㎞沢沿いに下れる旧道がある。その先は林道に合流する。
林道合流をやめさらに道なき沢沿いを下ると、鯉が滝と安倍の大滝にはまることになり、落ちたら死にます。よく素人さんが、川沿いを下れば人が住む村や町に出られるから、遭難したら川を下ればよいと言いますが、それは平野を流れるゆったりした川が前提で、山の中の川は悪絶なる滝場、断崖絶壁の渓谷にはまるので、絶対川沿いを下ってはなりません。自殺行為です。
安倍峠にあるもの:
・馬頭観音?:コンクリート製、
・安倍峠から徒歩15分、シロヤシオ群生:開花5月下旬、トウゴクミツバツツジ:開5~6月、サラサドウダン:同6/下、チチブドウダン:同6/中、ブナ巨木、ミズナラ巨木、
・石碑:「開通記念 広域基幹林道豊岡梅ヶ島線」静岡県側7.4㎞、山梨県側14㎞
~参考文献~
・「井川村誌」井川村誌編集委員会、’74
自然、歴史、産業、交通・通信、発電、文化、民俗、方言という井川についての総覧であり、基礎資料である。
・「玉川村誌」、’64
1911年手書き版上梓、1964年写本プリント版発行である。自然、歴史、教化、兵事、衛生、警備、産業、交通、社寺、伝説、、伝記、言語、風俗、災害等について20世紀初頭においての観点でまとめられていて、今ではおやという部分もあるが、当時の基礎資料足りうるものである。
・「田代・小河内の民俗~静岡市井川~静岡県史民俗調査報告書第十四集」静岡県教育委員会文化課県史編さん室、’91
民俗調査報告書として一通り報告されているので便利。多分田代と小河内が取り上げられたのは、井川ダムの水没を免れた地域だからだろう。本地域の民俗資料決定版である。
・「美和郷土誌」美和郷土誌編集委員会、代表:小沢誠一、’85
自然、歴史、教育、生活文化、宗教、民俗、史料について、微に入り細に入りこれでもかというぐらい記述されていて、他の地誌に比べてもワンランク上の内容である。まさに美和を知るための一級資料で決定版である。
・「梅ヶ島物語 史話と伝説」志村孝一、’82
梅ヶ島にまつわる武将、豪族、庄屋、村々、温泉、偉人、産業について聞き書きしていて、よくここまで聞きまわったものだ。今では滅んだこともあろうから資料として残したことで、後世に価値が上がろう。
・「安倍川~その風土と文化~」富山昭・中村羊一郎、静岡新聞社、’80
堤防、水害、水神、交通、産業、伝説(金山、飢饉、白髭、七観音)、農耕信仰、祭、婚姻等について卓見多し。
・「安倍川流域の民俗」静岡県立静岡高等学校郷土研究部、’80
安倍川流域の歴史と産業、村の成り立ち、信仰、衣食住、人の一生の出来事、年中行事、諸芸能、伝説について、一通り概観し調査してある。70年代末によく高校生が調査研究できたものだ。
・「復刻版 大河内村誌、大河内村青年団、岩本利太郎:編、1913年」静岡市立大河内中学校、’89
1913年の大正期に出され、1953年に口語訳で一部抜粋にて再編纂され、さらに89年復刻された。内容は、自然、歴史、教育(学校、社会、宗教)、兵事、衛生、警備、産業、交通、名所旧跡、伝記、言語、風俗等である。簡略に知りえるのによい。
・「安倍川と安倍街道」海野實、明文出版社、’91
安倍川の成り立ち、安倍街道、水害、水神、筏流し、舟運、賃取橋、鉄道について分かりやすく、コンパクトに読ませる。
・「藁科路をたずねて」海野實、明文出版社、’84
藁科のお茶摘みさん、焼畑文化、藁科五街道についてコンパクトかつ分かりやすく説明している。
・「静岡市歴史散歩」川崎文昭(静岡新聞社)、’90
市内の数多い名所旧跡を手際よく簡潔にカラー写真付きで紹介している。
・「しずなか風土記 賤中ふどき」しずなか風土記編集委員会、静岡市立賤機中小学校、’68
伝説や民間伝承面が細かに採録されていて、今では語り伝えられないものがよく残せたものだ。この資料は助かった。
・「郷土史 私達の籠上」籠上町内会、’84
籠上単独でよく出したものだ。とりあえずコンパクトに知りえることができる。
・「静岡市 歴史の町 井宮町誌」静岡市井宮町町内会、’03
井宮周辺の歴史地理を細かにかつビジュアルに知りえる良い資料だ。
・「郷土誌 私達のふる里 下(しも)」下町内会、’08
静岡市葵区下地区(鯨ヶ池から諸岡山周辺地域)の主に近代以後の細かな情報が入手しやすい。
・「玉川新聞」
2014年03月22日
静岡市市街地内、静岡駅北西部
○静岡市市街地内、静岡駅北西部
調査 ’13 11~12月を含む版
まだ未調査地や不十分な個所が多いですが、いったん公開します。将来のんびりと改訂していきます。
・用語説明
・国、県、市=国、県、市指定、・有、無=有形、無形、・登=登録、・文=文化財、・天=天然記念物、・重=重要、・民=民俗、・石=石製、・家=家型、・新=近代から現代にかけて作られた新しいものと推定されるもの、・古=新しくなく古そうなもの、・欠:破損欠落しているもの、・馬頭=馬頭観世音菩薩、・コンクリ=コンクリート製、(2)=2基、
・古い用語説明
廿=20、廿の縦線3本=30、等=塔、歳‣天‣月日=年、
美良または羊良=養(美や羊ではなく羊の下は大であり美ではなく横線3本である。狼という字に似ているが、その字がパソコンで出てこない。そういった字は多く他の現代的な字に切り替えたり注を施す)、クイズ:ちなみに養がなぜ美(横線3本)や羊(下は大)と良なのかはちょっと考えるとすぐ分かります。このように漢字の部分を上下左右に組み替えることは石塔への刻字ではよくあります。彫る時の字のバランスを考慮した石工さんたちの工夫です。ちなみにある石工さんはこういう字をお寺さんの字と言っていましたが寺院で使う字ではありません。この前見た字では政を上に正、下に政の正抜きの字を彫ったものを見ました。
*「石仏事典」類を参照してください。年号や干支もこれで分かります。
・住所について
なお住所は正確に分からないものは多く、隣や付近の住居の番地号を用いているものが多い。
○静岡市市街地内、静岡駅北西部
・宝台院(常盤町2丁目13‐2)
・宝台院ほうだいいん、金米山宝台院:説明版:宝台院は、徳川家康の側室で二代将軍秀忠の生母西郷の局サイゴウノツボネ(お愛の方)の菩提寺である。西郷の局は27歳で家康に仕え、翌天正7年(1579)4月、家康の第3子秀忠を生んだ。家康38歳の時である。この頃家康にとっては、浜松城にあって、三方原の合戦、設楽原合戦、小牧長久手の合戦と、戦に明け暮れたもっとも苦難な時代であった。西郷の局は、家康の浜松城時代に仕え、苦しい浜松城の台所を仕切った文字通り糟糠ソウコウの妻であったということができる。天正14年12月、西郷の局は、長かった苦難の浜松時代を終え、名実共に東海一の実力者となった家康と共に駿府入りした。家康の陰の立役者として、献身的に仕えた西郷の局は、駿府入りと共に浜松時代の疲れが出て、天正17年5月19日、38歳の短い生涯を終わった。後年、将軍職に就いた秀忠は、母のために盛大な法要を営み、その霊を慰めた。以来、徳川300年の間、この宝台院は、徳川家の厚い保護を受けたのである。
寺宝:白本尊如来像:重要文化財、他多数。静岡市。
・徳川慶喜公謹慎之地:宝台院と徳川慶喜公:説明版:明治元年七月、第十五代将軍慶喜公、御謹慎の身となり、同月十九日水戸を出発して銚子港に到着し、同月二十一日蟠龍艦に乗船し、同月二十三日に清水港に到着しました。海路にて移動したのは、上野彰義隊の戦いの興奮も冷めない江戸を通ることが、極めて危険なことだったからでしょう。この時目付の中台信太郎(のち駿府藩町奉行)がこれを出迎え、また精鋭隊頭松岡万以下五十名の厳重な護衛がついて駿府に向かいました。慶喜公が討幕派、旧幕臣の双方から命を狙われる重要人物であった事情に加えて、無政府状態とも言うべき当時の駿府の町の状況がこのような物々しい警護体制を必要としていました。一行は当日夕刻には宝台院に入りましたが慶喜公の駿府移住は秘密裏に行われ町民には一切知らされていませんでした。慶喜公の駿府入りが町触れで知らされたのは、その五日後の二十八日のことでした。尚、宝台院を慶喜公謹慎の場所に選んだのは元若年寄大久保一翁でした。彼は駿府町奉行の経験もあってこの町を熟知しており、徳川第二代将軍秀忠公の生母西郷局が葬られた宝台院こそ慶喜公が落ち着いて過ごせる場所と考えたのでしょう。以来、精神誠意慎をされ翌明治二年九月二十八日、謹慎が解け十月五日紺屋町の元代官屋敷(現在の浮月楼)に移転されるまで、約一年余りを当山で起居されました。この謹慎の部屋は十畳と六畳の二室で、十畳の間を居間、六畳の間を次の間として使用し、当時渋沢栄一や勝海舟と面会されたのもこの六畳間でした。明治元年八月十五日、藩主亀之助(家達公)が駿府に到着した時も、先ず宝台院に参上し御霊屋に参礼の後、やはりこの部屋で対面したということです。家達公は七間町三丁目を曲がり、御輿で大手門より入城されましたが、当時まだ七歳というお年でした。現在の宝台院には、慶喜公の遺品として、キセル、カミソリ箱、急須、火鉢、本人直筆の掛軸、居間安置の観音像が残っております。静岡市。
・西郷の局供養塔、・キリシタン灯篭、・百度石、・尺八碑:明治二十三年、・板碑:燈臺寄附連名:明治三十二年、・板碑:潮田良一之碑:昭和二十二年、・板碑:俳諧師かしく坊の辞世、・新:延命地蔵尊:駿河一国百地蔵尊第三十一番、祠:稲荷大明神、・新:西国九番札所:観世音菩薩安置成田山不動尊、手洗石:長野縣信濃国諏訪郡冨士見□、・狛犬2、・地蔵、・観音、・不動明王、・新:地蔵2、・石:三○:?石垣用石、・新:狛犬2:大正十三年、・新:観音:レリーフ、・石碑:アソカ幼稚園園歌:平成二十一年、
・家康の身代わり観音:阿弥陀如来立像のこと、かつては像に傷がついていたが現代に修理したため傷は消失した。家康は本像を合戦に持って行き安置しており、自分の近くに置いた像に矢が刺さり身代わりになったと考えたというが、伝説なのか史実なのかは不明。しかも傷がなくなったそうなので、いかなる傷だったのかもなおさら不明。
ちなみに静岡市葵区、宝台院のホームページを調べると、徳川家康関係の宝物(阿弥陀如来立像、家康公の自画像、真の太刀、家康公筆「安元御賀記手習」)、三代将軍家光公筆「遠山月」二代将軍秀忠の生母・西郷の局の墓、徳川慶喜公謹慎之地、かくし坊の辞世があり、その中にキリシタン灯篭もある。説明文:「キリシタン灯篭:茶人として有名な古田織部が制作し駿府城へ奉納、徳川家康公の侍女・ジュリアおたあが信拝したという灯篭です。この灯篭は城内より静岡奉行所を経て宝台院へ移されました。」とある。
ジュリアおたあをウィキペディアで調べると生涯概略の他、文章末に「~なお、駿府時代には灯篭を作らせ瞑想していたと言い伝えられており、そのキリシタン灯篭は、現在は宝台院に移されている。」と書かれている。
これらはいかなることでしょう。日本最初のキリシタン灯篭発見が宝台院で1923(対象12)年とすると、ジュリアおたあ信拝説はそれ以後と思われますが、いったいどういう証拠があるのでしょうか。分かりません。
*私見での「キリシタン灯篭の疑問点と保存」については別項目を参照してください。文章が長くなるのでここでは割愛します。
・鎮火稲荷神社(本通5丁目1‐5)
・稲荷(2):昭和廿三年、・鳥居:コンクリ、
・津島神社(梅屋町4‐1)
・鳥居:コンクリ、・狛犬(2):昭和54年、
・説明版:津島神社:祭神:当神社の御祭神:素戔嗚尊は日本神話の中で伊弉諾尊、イザナミノミコトの御子で天照大神の□神に当たられ、荒々しい剛直な性格の神で、天照大神を天の岩戸に~~させ給われ、高天原から地上に追放されました。出雲で八岐のおろちを退治されて奇稲田姫と結婚され大蛇の尾から出た天叢雲剣~~し献上されました。また新羅に渡られ船材の樹木を持ち帰り~植林の道を教えられたと伝えられております。また、大国主命は素戔嗚尊の御愛婿であられ、出雲の地で親子二代に亘って国土の経営、産業開発にお力をいたされ、災厄と疫病を除く御徳と受福の神様として世に知られております。神話では暴風神、英雄神、農業神として語られ、氷川神社、八坂神社、熊野大社などの御祭神でもあります。
天王さん:津島神社は古くは津島牛頭天王社と言い、今日でも一般に「お天王さん」と尊称されております。これは日本には上古から民俗宗教としての祖神信仰がありましたが、仏教が伝来して次第に日本化して、その結果崇神、崇仏思想が接近し、後年明治政府が神仏分離令を発布するまで、神宮寺、寺院鎮守など神社とお寺が同居していたことと関係があるように思われますが、インドの祇園精舎の守護神であるとか、新羅の牛頭山に留まっていた素戔嗚尊の御神霊を勧請してお祀りしたとか諸説があってはっきりしません。
由緒:神社年鑑によれば天明5年(1785)創建、明治11年公称を許可とあります。古老からの言い伝えで、昔疫病が流行り疫病除けの神として勧請したと言われておりますが、歴史年表を見ると。天明3年の頃には、「7月浅間山噴火、死者2万人に及ぶ。この年未曽有の凶作、奥羽の死者数十万人に達する」 天明4年は「この年夏、秋、米価騰□して諸民飢餓し、秋よりは疫病流行して死者が多い。」 天明5年「奥州三春、凶作、琉球凶作」 天明6年「江戸開府以来の大水で死者、家屋破損が多い。この年大凶作、収穫三分の一」などとあり、疫病除けの神として素戔嗚尊を勧請したものであろうと推測されます。
沿革:天明5年 創建、明治11年 公称許可、昭和9年 本殿、拝殿、社務所等造営、昭和15年1月15日静岡大火にて焼失、昭和15年仮社殿造営、昭和30年 空襲の罹災を免れる。その後現在地に移転。昭和44年 新社殿造営、現在に至る。平成11年6月吉日。
・八朔神社(本通2丁目1‐3)
・木鳥居、・手洗石、
・静岡神明宮(屋形町13)
・石鳥居:大正十五年、・常夜灯(2):大正十五年、・石柵:大正十二年、・狛犬:大正十四年、・神社名碑:昭和八年、・道路開鑿碑:明治四拾年、
・東本願寺静岡別院(屋形町10)
・新:堂、・新:木石堂、
・大林寺(安西4丁目93)
・梶原景季と景嘉の墓:五輪塔:土水火風空、・祠:白山妙理大権現、・祠、・山門:仁王像(阿吽)、裏に風神と雷神像、・新:水子地蔵、・新:六地蔵、・石燈籠、・観音、・中世末墓石、江戸初期墓石(2)、観音風墓石(2)、・青面金剛供養塔:天明二、・法華千部塔:文政二、
・説明版:縁起:古記録によると当山は今から約800年前、鎌倉時代初期当國庵原郡高部村大内にあり、大淋寺(天台宗)といい大林寺殿贈四品榮昌福寿桑道場妙開大禅定門、姓平氏葛原親王第十四代梶原信濃守従四位少将景義四男刑部少輔朝景卿建仁元辛酉(1201)年5月3日卒を最初の開基としている。文永元(1264)年12月18日仏殿を今の柚木町に建立している(駿河記)。時移り戦国争乱期、北条早雲殿(1459)の命により、武田、今川の動静を探るため旧東海道の見張所としての城塞の寺を現在の場所に草創したのである。七堂伽藍は一万の大軍を収容でき、山門が柚木町の堤上にあり、その下に尼寺と墓地があった。寺格は法地寺中5反6畝3歩安西内新田、除地5反3畝3歩安西外新田、雑地10反あり(駿河志料)。
その後曹洞宗通幻派最乗寺門下総世寺末となり同寺五世天祐宗根和尚に嗣法する鳥道長鯨和尚天文12(1532)年癸卯12月10日寂を開山としている。三世好山宗禅和尚は慶長年間(1596)徳川家康より法門の聴聞あり。四世明室温察和尚(1624)は梶原源太景季、景嘉の墳墓を改築し、六世揚山和尚(1704)は末寺龍津の中興で、七世大鳳和尚(1688)貞享3年梵鐘鋳造の功をなし良富院の開山となる。九世槐國萬貞和尚(1716)は最勝、定林に歴住し海松、円城、雨林の3か所の開山であり、卍山道白禅師の法嗣で、徳川吉宗の釣命により、官刹長崎の皎台寺に転住し、大同庵、金泉寺を開き語録二巻を著している。十世古岳日峻、十四世一了玄画和尚も皎台寺に当寺から普住した。特に日峻は書物に参同契測海があり、海門及び月舟宗胡、独庵玄光、(辟と水で上下)山の高泉、黒瀧の潮音、槐國と共に参じた中世稀にみる高僧である。二十九世祖鳳光禅和尚は洗耳寺に歴住し明治40年七堂を再建したが、昭和20年6月19日戦火により焼失している。昭和34年三十一世光雄和尚が本堂、位牌堂、庫裏を再築している。尚開基より光雄和尚まで5回兵火に遭っている。また寺の所在は大内→安西→柚木→安西(正保元(1644)年町奉行落合氏により)に戻っている(寛政寺記及び駿河記) 昭和60年12月18日 大林寺 三十一世大鑑光雄記
・説明版:大林寺墓塔群:○梶原源太景季・景嘉の墓:源頼家(1182)の母政子の父北条時政の家来家来梶原景時(1200)が滅ぼされ、その門葉景嘉が駿河殿(徳川忠長1602)に仕え寛永9年(1632)壬申1月21日歿した。本府古図の安西4丁目南にその姓名がある。大内梶原堂の条によれば太田美濃守入道資正二男が梶原の養子となり源太政景といった。景嘉はこの後葉である。(駿河志料他)
○落合能登守小平次道次の墓(1652):長篠城攻防戦の勇者鳥居強右衛門の磔に感動した落合佐平次道久は、自分の指物に磔の図を描いて出陣し、家康に見出され、後に徳川頼宜に従って駿河衆となり、養子の道次は江戸幕府に出府し駿河奉行として由比正雪を召し捕り功あり。寛永17年より承応元年まで13年奉行として活躍した。慶安5年8月9日寂。
○安鶴の墓(1872):『諸国畸人傳』(石川淳)『駿府の安鶴』(江崎惇)により全国的に有名。
○舟川斎寺西源正勝の墓:幕府旗本天神真陽流柔術指南医士。
○小沢久七の墓:長崎で勉強し漆器界の発展に尽力した。
○小出東嶂の墓(1823~1889)画家福田半香の弟子であり書画に通じ明治6年静岡新聞を刊行す。
協力者:~略~、昭和60年12月18日、大林寺31世大鑑光雄代
・延命地蔵堂(安西5丁目114)
・堂、・秋葉山常夜灯、
ここから川根筋に抜ける川根(秋葉)街道の起点と考えられている。
*「川根(秋葉)街道」については、『古街道を行く』鈴木茂伸(静岡新聞社)をご覧ください。ただこの本すでに絶版ですので、静岡県内図書館にあるので検索するか、静岡県内の古本屋にもないので、古本屋にリクエストしていって取り扱ってもらえるとよいでしょう。
・柳町水神社(柳町135)
・木鳥居、・手洗石、・社、
・曙稲荷神社(若松町15)
・石柵:昭和十年、・石鳥居:昭和十年、・石燈籠(2):昭和十年、・石燈籠(2):昭和四十年、・稲荷(2)、・稲荷(2)、・祠、・手洗石、
・八雲神社(北番町84)
・神社名碑:昭和四十六年、・八雲神社碑、・新:狛犬(2)、・石鳥居:明治三十四年、・手洗石、・石燈籠(2):明治三十年、・北番町公園碑:昭和46年、・石塔:庚申、・石塔?、・石塔?:文政六癸未年、・若松町制四十周年:昭和三十九年、
・八雲神社御由緒:鎮座地:静岡市□番町八雲~、祭神:~~~、祭□:例祭、~~~~、創立年月日:口伝によれば応永3年創立と伝承。
往古は牛頭天王という。当国総社浅間神社に祀られていたが、戦禍に遭い別当職が簑に納め安倍郡大岩村に遷し大岩村村民の氏神として祭祀を引き継ぎたり。その後寛永の頃駿府城北番詰所の番士この地に居住し牛頭天王を崇敬し為に寛永3年大岩村よりこの地に勧請し宝永3年真言宗建穂寺末寺別当牛頭山宝積寺中興願成院智寂法印氏神として祭祀を承継す。明治3年神仏混淆廃止令により八雲神社と改称、同8年2月村社に列格、同43年6月18日神饌幣帛供進指定を受く。敗戦により国家の庇護を離れ、神社本庁設立に伴い、静岡県神社庁所属となり、氏子により祭祀を継承、現在に至る。350年を記念して建立。~以下略~
・桜森稲荷神社(土太夫町7)
・鳥居:コンクリ、・新:燈籠、・古:燈籠、・手洗石、・石:家:道祖神、
・二十六番札所、水月院(安西1丁目24)
十一面観音菩薩、
・説明版:水月堂御縁起:水月堂(通称おはつかさん)は静岡市安西1丁目南裏に位置し十一面観世音菩薩を安置し、新選府辺観音霊場(新西国)三十三か所巡礼札所中第26番にして本尊は鎌倉初期の名匠運慶の作と伝えられ国宝的存在でありました。しかし戦災(昭和20年6月20日)で焼失してしまいました。元亀年間、今を去ること400有余(405)年前、安倍郡籠鼻(今の井宮町西北部)の圓皆寺(現在は廃寺)の住僧宗文の創建で今川家の臣福島淡路守の夫人然正院智現妙本大姉の開基と伝えられています。毎月20日を以て御縁日と定め毎年3月には僧侶も招き特別大法要を続けております。 平成18年3月20日、水月堂奉賛会
・住吉神社(一番町25)
・手洗石:奉献願主府内(絞?)仲間、常夜灯:昭和六年、・石鳥居:昭和五十年、・石燈籠(2):住吉大神宮御宝前 文化十年と大正四年、・石碑:神饌幣帛供進指定中津神社 昭和十六年、
中津神社とは何? 昭和16年号なので静岡空襲か大火で消失し、戦後住吉神社と併合され、たのか?
・顕光院(研屋町45)
・馬頭(3):馬頭観音建立由来碑:昭和13年1(6)月15日正午過ぎ新富町、~~~不明
*撮影した写真不鮮明で判読困難、再度やり直す気がないのでこのままです。ごめんなさい。
おそらく内容は静岡大火と静岡空襲による戦火の災害供養のため馬頭観音を設置したと言いたいようです。
・地蔵、・南無阿弥陀仏:昭和二十六年、・地蔵(3)、・板碑:大正九年、・新:六地蔵、・三界萬霊等、・無縁堂、・平和観音堂、・庚申:文化四、・庚申:寛政二、・新観音、・新:灯篭(3)、・新:駿河一国百地蔵第一番開運成就地蔵尊、・奉納弘法大師四国八十八所 国々諸々神社供養 秩父三十三所 一国三十三所 坂東三十三所 文政四、
・くがたか橋の碑(追手町12)
かつての外堀沿いの橋の欄干だったのか。
・石塔(城内町1‐2)静岡聖母幼稚園前
全く刻字等有無不明
・石碑:青葉小(追手町4)
廃校になった青葉小学校の記念碑。
・校址碑:静岡第二尋常小學校 明治34年新設、静岡城内東小學校 大正2年 校名変更、静岡城内東尋常高等小學校 大正13年 校名変更、静岡城内東尋常小學校 昭和8年 校名変更、城内東國民學校 昭和16年校名変更 昭和20年9月5日廃校、青葉小学校 昭和29年4月設立、平成19年3月閉校、
・石碑:城濠用水 土地改良区記念碑(追手町4)
・説明版:城濠用水由来:城濠の誕生は慶長12年
~写真不鮮明で判読あきらめ~
昭和53年5月、城濠用水土地改良区
・石碑:葵文庫跡(追手町4)
・説明石碑:由来:葵文庫は大正8年静岡に縁の深い徳川家の記念事業として計画され、同14年3月28日徳川家の家紋を館名としてこの地に開館した。その特色は、江戸幕府旧蔵書の一部である「葵文庫」と3代県令関口隆吉収集にかかる「久能文庫」にあった。以来県立葵文庫は県民の図書館として、また全国的にも貴重書の宝庫として注目されその発展をみた。昭和44年市内谷田に新館が建設され、静岡県立中央図書館として移転すると、葵文庫は新たに静岡市立図書館として再出発した。しかし施設の老朽化により、昭和59年市内大岩に新築移転したため、県民に親しまれた建物は取り壊された。~~~不明
*撮影した写真に石碑終盤の文字が写っていなかったので不明としました。撮影し直すなりもう一度見に行って判読するなりの気にならないので一旦終了します。ごめんなさい。
・駿府城(駿府城公園)
・説明版:駿府城は外堀、中堀、内堀の三重の堀を持つ輪郭式の平城です。本丸を中心に回字形に本丸、二の丸、三の丸と順に配置され、中央の本丸の北西角には、五層七階(外観五層内部七階)の天守閣がありましたが、寛永十二年(1635)に焼失しています。駿府城が城郭としてその姿を見せるのは天正十三年(1585)に徳川家康が築城を開始したことに始まります。この天正期の駿府城は現在の城跡に比べると一回り小さいと考えられますが、詳細は不明です。この後江戸幕府を開いた家康が慶長十二年(1607)将軍を退き、駿府に移り住むために天正期の駿府城を「天下普請」として拡張、修築しました。当時の駿府は江戸と並ぶ政治の中心地として重要な役割を果たしていました。 平成8年3月 静岡市
・巽櫓(駿府城公園)内堀沿い たつみやぐら
巽櫓は駿府城二の丸の南東に位置する木造矩折三層二重の建物です。この巽櫓は寛永十二年(1635)城下から出た火によって延焼焼失し、寛永十五年に新たに建設されたといわれています。巽とは十二支で表した方位で辰と巳の間、即ち南東の方角をいいます。また櫓とは、一、武器を納めておくため、一、四方を展望するために設けた高楼、の役割をしたものです。巽櫓の復元は、「駿府城内外覚書」や「駿府御城惣指図」の資料をもとにしており、3年の歳月をかけ、平成元年3月に完成しました。 静岡市
・東御門(駿府城公園)ひがしごもん
東御門は駿府城二ノ丸の東に位置する主要な出入口でした。この門は二ノ丸堀(中堀)に架かる東御門橋と高麗門、櫓門、南・西の多門櫓で構成される枡形門です。東御門の前が安藤帯刀タテワキの屋敷だったことから「帯刀前御門」また、台所奉行の松下淨慶にちなんで「淨慶御門」とも呼ばれ、主に重臣たちの出入口として利用されました。東御門は寛永十二年(1635)に天守閣、御殿、巽櫓等と共に焼失し、同十五年に再建されました。復元工事は、この寛永年間の再建時の姿をめざし、復元したものです。 平成八年三月 静岡市
・坤櫓(駿府城公園)内堀沿い ひつじさるやぐら
木造二層三階。家康築城時に武器庫として利用される。寛永12年(1635)の火災で焼失。2014年4月に復元工事完了し1階は公開される。2階は非公開。
・駿府城公園内:発掘された石垣、公園内地面下には戦国期の今川館跡遺跡
駿府城は古くは今川館があったと推定される。その後徳川家康により隠居城となり、一時は大名が治めたこともあるが、長くは代官の行政所となり一部を使用したようだ。使わない部分はかなり荒廃した箇所もあるようだ。江戸時代中期以降は狐が住んでいたほど荒れていたようだ。明治期に内堀を埋立て軍隊駐屯地になった。今は公園。発掘で徳川期の石垣や使用道具類、今川氏館跡等が出土している。しかも焼かれた物が出土している。武田氏により滅ぼされ今川館は焼失したと思われるが、そのとき焼かれた物かどうかは不明。
天守閣は家康が建造したが女中の不手際で失火焼失、再建されたがまた焼失。代官時代には天守閣はなかったようだ。またそれ以外の建物や施設も代官時代に使用が縮小していったようだ。
現在みられる駿府城外側の石垣は近代以降、幾たびも修復されているので全てが江戸時代のものというわけではない。ただ一部残存しているのも確かで、家康が築城する際には全国の大名を動員したので、石垣に各大名のしるしがつけられているものがある。また各時代により石垣の積み方に特徴が出ている。
*石垣の積み方についてはネットや図書で検索してください。
・家康お手植えの蜜柑ミカンの木、
・家康銅像、
・東海道中膝栗毛弥次喜多像(追手町)内堀沿い
・説明版:十返舎一九と「東海道中膝栗毛」: 「東海道中膝栗毛」の作者十返舎一九(1765~1831)は、ここ駿河の府中(静岡市)出身で江戸文学における戯作者の第一人者であり、日本最初の本格的な職業作家といえます。1765年駿府町奉行同心、重田与八郎の長男として両替町で生まれました。本名は重田貞一、幼名を市九といいます。1783年大阪へ行き、一時は近松余七の名で浄瑠璃作家としても活躍しましたが、その後士分を捨て1794年再び庶民文化華やかな江戸に戻って戯作に道に専念し、多くの黄表紙や洒落本などを書きました。
「東海道中膝栗毛」は1802年初編(初編は「浮世道中膝栗毛」のち改題)以降毎年一編ずつ8年にわたって書き続け、1809年全8編を完結しました。この膝栗毛は爆発的人気を呼び、休む間もなく「続膝栗毛」の執筆にとりかかり、1822年の最終編までに実に21年間に及ぶ長旅の物語として空前の大ロングセラーとなりました。
物語は江戸神田の八丁堀に住む府中生まれの弥次郎兵衛(左の像)と、元役者で江尻(現清水市)出身の喜多八(右の像)という無邪気でひょうきんな主人公二人が江戸を出発して東海道を西へ向かい伊勢を経て京都、大坂へと滑稽な旅を続ける道中記で、今でも弥次喜多道中といえば楽しい旅の代名詞となっています。
当地の名物として安倍川餅やとろろ汁も登場。また府中では夜は弥勒手前の安倍川町(二丁町といった)の遊郭へ出かけたり、鞠子(現丸子)では、とびこんだ茶屋の夫婦喧嘩に巻き込まれ、名物とろろ汁を食べるどころか早々に退散したといった話が語られています。
一九は1831年没、享年67歳。墓所は東陽院(現東京都中央区勝どき)にあります。ここ府中は江戸から44里24町45間(約175㎞)19番目の宿です。
2002年2月、静岡市
・甘夏みかんの木(追手町)内堀沿い
・わさび像「わさび漬発祥の地」(追手町)内堀沿い
・説明版:わさびは370年前わが国で初めて安倍川上流有東木で栽培された。わさび漬けは今から200余年前駿府のわさび商人によってはじめて考案され幾多の人に受け継がれて改良進歩した。特に明治以後交通機関の発達により長足の発展を遂げたのである。ここに明治百年を期し先覚者の偉業を偲び感謝の誠を捧げて、この碑を建つ。昭和43年5月23日、静岡県山葵漬工業協同組合
・このわさびの像はコンクリ製で芋虫に似ていて一種のゆるキャラっぽい。あるいはシュールというべきか。宇都宮市に餃子像があるのならば静岡市にはわさび像です。
・現代アート像:指人形(追手町)内堀沿い
指人形 The fingerdoll 制作:細谷泰玆 Yasuji Hosoya 1983年
・石碑:静岡学問所跡(追手町)内堀沿い
・説明版:静岡学問所は明治維新後駿府に移ってきた徳川家(府中藩)により、藩の人材育成を目的として駿府城四ツ足御門にあった元定番屋敷内(現静岡地方合同庁舎付近)に明治元(1868)年府中学問所として創設されました。学問所には翌2年駿府が静岡に改められたことにより静岡学問所となりましたが、明治5年8月学制の施行とともに閉鎖されました。この学問所には向学心に燃える者は身分を問わず入学が許可され向山黄村、津田真一郎(真道)、中村正直(敬宇)、外山捨八(正一)など当代一流の学者により国学、漢学とともにイギリス、フランス、オランダ、ドイツの洋学も教授されました。またアメリカ人教授E.W.クラークは専門の理化学の他哲学や法学なども教えました。廃校後洋学系の教授の多くは明治政府に登用され開成学校(現東京大学の母体)の教授など学界や官界で活躍しました。静岡学問所の歴史は短期間でしたが、日本の近代教育の先駆けをなし、明治初期の中等、高等教育の最高水準の学府でありました。 静岡市教育委員会、平成元年12月
・石碑:戸田茂睡生誕之地(追手町100)とだもすい
1629~1706年、江戸時代前期の歌学者。父は徳川忠長(徳川3代将軍家光の弟、駿府城主、改易され謹慎の後自害)の付け人で、駿府城内で生まれた。
・駿府城四足御門跡(追手町)よつあしごもん
・説明版:駿府城南辺の西寄りの箇所に設けられた出入口で、東側の大手御門オオテゴモンと並び、東海道筋から城へ入る重要な出入口の一つです。三の丸堀を土橋で渡って、左手へ直角に曲がり渡櫓門ワタリヤグラモンから城内へ入る構造になっていました。 静岡市教育委員会
・大手‣追手門(追手町)
・説明版:駿府城大手御門:駿府城内に入る正面出入り口です。三の丸堀を土橋で渡って、右手へ直角に曲がり渡櫓門ワタリヤグラモンから城内へ入る構造になっていました。歩道には渡櫓門の柱礎石の位置が記されています。 静岡市教育委員会
・石垣修復説明版(追手町)
・説明版:駿府公園二の丸堀(中堀)石垣災害復旧工事完了のお知らせ:平成21年8月11日駿河湾で発生した震度6弱の地震により、駿府公園二の丸堀(中堀)の石垣が崩落しました。平成22年1月6日工事着手、平成23年3月15日工事完了、石垣の構造を説明した「石垣モデル」が駿府公園内、富士見芝生広場に設けてありますのでぜひ一度ご覧ください。静岡市。
崩落前と崩落直後、復旧後の3つの写真が並置されているので、見た目では一目で分かるようになっている。なお石垣は見えない内部構造も重要なので石垣モデルを見てください。
・静岡県庁本館(追手町9)
登録有形文化財、
・静岡市役所本館ドーム(追手町5)
登録有形文化財、
・教導石(追手町)県庁市役所前バス停
・説明版:静岡市指定有形文化財(歴史資料) 教導石きょうどうせき、指定年月日:昭和59年7月17日、所在地:静岡市追手町、所有者:静岡市、「教導石」は、明治という新しい時代を迎え、「富や知識の有無、身分の垣根を越えて互いに助け合う社会を目指す」との趣旨に賛同をした各界各層の人たちの善意をもって明治19(1885)年7月に建立されました。正面の「教導石」の文字は、旧幕臣山岡鉄太郎(鉄舟)の筆になり、本市の明治時代の数少ない歴史遺産の一つとなっています。碑の正面上部には、静岡の里程元票(札の辻)から県内各地、及び東京の日本橋や京都三条大橋までの距離を刻んであります。教導石建立の趣旨に従って碑の右側面を「尋ル方」とし、住民の相談事や何か知りたいこと、また苦情等がある人はその内容を貼り付けておくと、物事をよく知っている人や心ある人が左側面の「教ル方」に答えを寄せる、というものでした。尋ね事などのほか、店の開業広告、発明品や演説会の広告から遺失物や迷子をさがす広告なども掲示してよいことになっていました。全体の高さ:207㎝、台石の幅:107㎝、本体:高さ:177㎝、正面幅:44㎝、側面幅:38㎝、静岡市‣静岡市教育委員会
・正面:「教導石、里程(?田谷、略を上下に書く)表、駿河國沼津宿拾五里拾町余、同吉原宿拾里拾九町余、 同大宮町拾壹里拾六町、同興津宿四里拾貮町余、同清水町三里六町余、同根古屋村貮里拾九町余、同藤枝宿五里拾町余、遠江國静波町拾里貮拾九兆余、同相良町拾貮里貮拾町余、同掛川宿拾貮里拾七町余、同森町村拾六里三町余、同横須賀町拾六里三拾町」
右:「尋ル方、静岡里程元票 各地距離、東京日本橋四拾六里拾町余、神奈川縣廰三拾九里廿六町余、山梨縣廰貮拾七里拾七町、伊豆相模國堺貮拾里壹町余、伊豆國下田町三拾五里拾五町、同熱海村貮拾三里四町余、同修善寺村拾壹里二拾町、同韮山町拾九里三町余、同三島宿拾六里三拾町余」
*撮影写真不鮮明で判読困難、やり直す気がないので間違ったままですが掲載します。
左:「教ル方、同見附宿拾六里貮拾七町、同中泉村拾七里九町余、同掛塚村拾九里拾壹町、同濱松宿貮拾里拾七町余、同二俣村廿壹里廿七町余、同気賀村廿四里拾八町余、同新居宿廿四里二拾町余、遠江三河國堺廿六里(十十十)五町余、愛知縣廰四拾八里拾七町余、西京三条大橋八拾四里拾四町」
・街道研究としては近代の石道標の価値がある。
・札の辻(呉服町1丁目と2丁目の境)伊勢丹前
静岡市街の中心地は呉服町で、旧東海道も呉服町の札の辻を通過し本通り乃至は新通りに向かい直進するか曲がる交差点であり、高札等のお触書も建てられた府中宿中心の場所である。
・国・登・静岡銀行本店(旧三十五銀行)(呉服町1-10 )
国登録有形文化財、第22-0010号、この建造物は貴重な国民的財産です、文化庁。
景観重要建造物、静岡銀行本店(旧静岡三十五銀行本店) 静岡市葵区呉服町、指定第3号、平成23年9月30日、静岡市。
・静岡天満宮(中町1‐3)
・石鳥居:昭和三十一年、・神社名碑:昭和五十二年、・手洗石、・牛像、・石碑:川中天神伝説之地、黒い直径15~20㎝溶岩多数(富士山溶岩か?)、
・稲荷社祠:、・説明版:静岡天満宮末社、静銀稲荷社、御由緒:御祭神:稲荷大神、昭和20年終戦後、進駐軍が静岡に入り、大企業に立入調査を行った折、(株)静岡銀行の守護神として、社内に祀っておりました稲荷社を、直ちに撤去廃棄すべしと命ぜられ、銀行側は検討の結果、御神体を隣接する静岡天満宮(当時は天満天神社)に保管祭祀を依頼し、神社側もこれに応じて静岡天満宮末社「静銀稲荷社」として現在の場所に鎮座奉斎したのです。以来初午祭には静銀本店営業部の責任者が参拝する習わしとなったのです。御神祠:この御神祠は明治初年から昭和3年まで静岡天満宮(当時は天満天神社)の御本殿として鎮座しておりましたが、昭和4年新たに御本殿を造営するにあたり市内宮本町山下家に譲渡し同家にて同家の守護神として奉斎されていました。しかし同家の事情により、この神祠を処分することになりましたので、昭和54年2月同家より静岡天満宮の地に還御しました。これと同時に従来静岡天満宮の本殿に合祀しておりました、静銀稲荷社の御神体をこの神祠に奉斎して、今日に及んでいるのです。(昭和4年竣工の御本殿は、昭和20年6月戦災にて焼失)
・景行社祠:、・説明版:静岡天満宮攝社景行社御由緒:昌泰4年(901)1月25日菅原道真公が、無き罪により大宰府に流された。翌々日公の子息達も夫々別々の地に流され、次男景行も駿河権介に左降され、この駿河の地に流され、ここ駿河の国府に居住した。この国府は現在の静岡天満宮を中心とした一帯の地域である。その後景行の記録が定かでなく、今日に至ったので、道真公を祀る静岡天満宮を崇敬する有志が景行を祀ろうということになった。その折り、大阪市天王寺区の一行者(鎌原氏)や清水区三保の行者(日蓮宗)に「景行を祀れ」との道真公の託宣があったとのことで、平成元年春に景行社を創祀したのである。(平成20年6月25日再記)
・銅鐸:説明版:県指定文化財、奈良県北葛城郡上牧村観音山から出土したもので、銅製で耳がなくたすき形の模様がある。高さ19.7㎝、底の長径15.1㎝、短径11.5㎝、保管:登呂考古館、明治百年紀念、静岡県文化財保存協会、
・尼ヶ崎稲荷神社(中町37‐1)
・石柵、・手洗石:昭和六十年、・石燈籠(2):平成十九年、・稲荷(2)、
・説明版:尼ヶ崎稲荷神社の由来:元尼崎又右衛門という富商邸内にありました。家康に召されて駿府に移り、はじめ本通り五丁目に宅地を賜りそこを十軒町と言ったが、慶長14年四ツ足御門町(現中町)に替地を賜ったと言われています。尚金座町稲荷神社(後藤稲荷神社)がこのすぐ裏手にあり慶長の頃、駿府上魚町(現金座町日銀)で小判を鋳造した後藤庄三郎光次邸があった所でもあります。又銀座町は現在の東京銀座にお移されております。
・説明版:四ツ足御門と中町の由来:四ツ足御門町の町名は非常に地位の高い町名でありました。今の中町の所から駿府城に入ったあたりに駿府城の四ツ足御門がありましたので、この町名となったのです。さらにこれを遡れば、その昔、大化の改新に伴い今の長谷町付近に国府が置かれた頃、この中町付近に国庁の四ツ足御門があったからという説があります。その説によれば四ツ足の名は千数百年の歴史を飾る由緒ある町名であります。現在、中町という町名になったのは、四ツ足といえば獣類に通じ快い町名とは聞こえないということで、大正4年11月10日「静岡市の中心」ということで中町と改称されたのであります。 平成23年3月15日 春季大祭
・上魚町碑(金座町1)かみうおちょう
・説明版:上魚町は徳川家康の大御所時代には、中央の通りを挟んで南側を後藤庄三郎光次が拝領し、光次が江戸に移るまではここを金座として「駿河小判」と呼ばれる金貨を鋳造していました。また北側は駿府城築城の作事方中井正清が拝領していました。「駿国雑誌」によれば、家康の在城の時、下魚町から魚商人を移住させたとされ、町の南側には魚問屋、北側には青物問屋が軒を連ね、さながら「流通センター」のような役割を果たしていました。元禄5(1692)年の「駿府町数・家数・人数覚帳」によると、当時の上魚町は、南側が家数38軒、人数203人、北側が家数4軒、人数70人でした。上魚町は昭和3年に金座町となりましたが、それ以後も「かみんだな(上の店)」と呼ばれていました。
・金座稲荷神社(金座町49)
・手洗石:昭和六十二年、・常夜灯:昭和六十二年、・金座碑:昭和三十年:
日本銀行静岡支店からこの金座神社界隈はかつての金座で小判等を鋳造していた。
・説明版:お金の神様、金座稲荷神社御由緒、創建:慶長11(1606)年、御祭神:稲荷大神、秋葉大神、当神社は後藤庄三郎光次が徳川家康公の命を奉じ駿府、上魚町(現在の金座町)に金座を開設し小判の鋳造を始めるに際し金座の守護神として御二柱を祀ったのが起源であります。以来400年、上魚町の産土神として祀られ、その霊験洵にあらたかなる為、「お金の神、金運の神様」として広く崇敬を集め、通称「後藤稲荷」として親しまれてまいりました。その後幾多の変遷を経て、昭和62年5月23日、当所へ遷座致しました。尚金座町という町名は、歴史的事実にもとづいた町名としては全国で唯一のものであります。昭和63年11月吉日、金座稲荷神社。
・戸塚歯科医院跡(本通1丁目3‐2)
かつて戸塚氏は郷土史家として静岡近辺の野仏や民間習俗の研究で知られていた。氏の本は私にとっても貴重な資料である。
・奥津宮神社(車町26)
・新:石灯篭、・庚申供養塔:文政三庚辰年、・石鳥居:昭和二十六年、・石柵:平成四年、・欠:庚申:安政七、・欠:庚申供養塔:文政五壬午年、・観音堂、・欠:奉寄進石燈:寛文(?政)九年
・石碑:説明:奥津彦神社、静岡市葵区車町26鎮座、祭神:火産霊神、奥津彦神、奥津媛神。由緒:神社の創立年月不明。社伝に駿河国の守護今川範国の子今川了俊深くこの神々を崇敬して邸内に奉祀してあったが、その子今川仲秋に政治の要諦を教えると共に「よくこの神を信仰せよ」と御神体を授ける。仲秋はよく父の教えを守り身を慎み祭祀を怠けたらず善政を行いやがて立身して遠江守護、尾張守護等を歴任した。仲秋は一の世を去るに臨みてその家臣に命じて御神体をこの地に祀らしめ三宝荒神社と称したと伝えられている。三宝荒神社は明治元年の神仏分離令に依り奥津彦神社と改称された。又三宝荒神社の別当用触山守源寺は昔から駿府の会所に使用され町々へのお触れ通達はここから出したので用触山の名がつけられた。御神徳:火の神様である炊事キッチンの守り神である。火の神信仰は火難を免れ病難を防ぐ。祭日:2月28日、9月28日、12月28日
・願勝寺(車町50)
・新:双体道祖神
・金剛院(八千代町17)
・石:家:道祖神
・秋葉山常夜灯(馬場町)
中町交差点に市・有民・中町秋葉山常夜灯、上部は木造で彫りが見事、下部は石造、・赤鳥居:コンクリート製、
・山田長政像(宮ケ崎町100)
馬場町は伝山田長政屋敷跡といわれる。
・二瀬川神社(馬場町65)
・石灯籠(2基):明治四年、・手洗石:古そうで年号等もありそうだが見えない位置に安置されていて判読不能。
・説明版:二瀬川神社、静岡市葵区馬場町65番地、祭神名:保食神うけもちの神、多紀理比賣神たぎりひめの神、例祭日:9月15日、社殿工作物:本殿3.3平方m、拝殿6.6平方m、境内地:132平方m、氏子戸数297戸、神職名:宮司:鈴木巌夫、禰宜:鈴木哲夫、責任役員名:小川保、鍋田治夫、由緒:創建年月不詳、昭和20年6月の戦災により焼失、昭和25年9月都市計画区画整理により現在地に移転し、以前120坪の地が40坪に削減され、その境内地に町内会館を建設したため実質は更に三分の一となって、極めて不遇な道を経過した神社といえる。静岡県神社庁神社等級規定13等級社である。年間スケジュール:祭旦祭:1月1日、初午祭:2月2の午の日(二の午祭)、夏祭:5月15日、例祭:9月15日、神輿清祓祭:例祭前後の土曜又は日曜日、
・報土寺(宮ケ崎町110)
・石塔:新:南無阿弥陀仏、・新:六地蔵(杉村隆風)、・新:無縁萬霊之塔、
・石碑:新:養国寺慰霊之碑 平成十九年、説明版:報土寺の末寺で安翁山丹龍院養国寺という浄土宗の寺が本通7丁目74番地にありました。開基は寛正6年(1466)で開山は松漣社貞誉王山上人還阿和尚であります。その後は報土寺の末寺となり歴代の当山住職が兼務住職となり、本通りの人たちと供に養国寺を護持してきましたが、昭和20年6月19日の静岡大空襲により堂宇すべて廃墟と期しました。その後、報土寺が戦後復興を進めていく中、昭和27年、養国寺は本寺である報土寺に合併されることとなりました。開基よりおよそ550年、養国寺の歴代住職をはじめ信徒の方々、本通り7丁目の方々、その他養国寺の護持の為にご協力を頂いた多くの善男善女の方々に心より御礼申し上げ、ここに慰霊の碑を建立致します。
平成19年8月、報土寺住職 泰誉博隆
・石碑:新:南無阿弥陀仏 大正十余年、説明版:経に曰く至心信楽即得往生~~~以下略~~~
~~~大正十余年
・新:冷泉為和の歌碑:冷泉為和の歌碑についての由来:報土寺の本堂前に戦国時代宮廷歌壇の第一人者冷泉為和の歌碑が建てられた。為和は歌聖藤原定家の直系冷泉家第7代の当主である。当時応仁の乱(1467~77)後の荒廃した京都を逃れて駿府に流寓した公家殿上人はかなりの数にのぼっていた。権大納言冷泉為和もそうした中の一人であった。その為和が駿府滞在中我が報土寺において歌会を催すこと9回、11首の和歌を詠んでいる。それは、「今川為和集」の中に歴然としるされている。報土寺境内にある歌碑に彫られた和歌はその中の天文12年(1543)5月2日の歌会の折りのもので、
松契還年
代々かけて 軒のかわらに むす苔も 緑あらそふ 松の気だかさ (為和)
この歌の題の「還年」は長寿をいうので軒の瓦が苔むすといえば1年や2年のことではない。何代という長い年月を栄え続けてきた証で、それと競うように枝を伸ばした松の緑の気品のある美しさを讃えて長寿を祝う歌とした手腕はさすがである。(文責 長倉智恵雄)
・一加番稲荷神社(鷹匠1丁目8)
・石鳥居:昭和三十七年五月、・石稲荷2:昭和五十一年、石柵:昭和五十八年、・手洗石:昭和五十六年、・コンクリ石塔:昭和壬子二月、・石碑:神社名:新、
・説明版:当神社の御祭神は、保食大神ウケモモノオオカミ、御別名を豊宇気比売神トヨウケヒメノカミ、また食稲霊神ウカノタマノカミと申し上げ、稲、五穀の御霊神と尊まれ、衣食住の神、商売繁盛、厄除開運、無病息災、延命長寿の守護神として広く信仰されている神である。
当社鎮座の由来は寛永八年(1631)駿府城主駿河大納言忠長卿(二代将軍秀忠公の第3子)が三代将軍家光(兄)の勘気を受けて甲斐に蟄居の後は、幕府は駿河を直轄領とし、城主を置かず重臣の内から駿府城代を任命して庶政を綜理せしめ、城代を輔けて城外の守衛に当たらせるために在番一年の役として加番を勤番させることとし、紺屋町に一加番屋敷を設けた。(これを紺屋町加番或は町口加番屋敷という)初代一加番に信州飯田城主五万五千石脇坂淡路守安元が寛永九年(1632)12月に仰せ付けられ着任した。この加番開設にあたり3200余坪の屋敷内の浄地を選び社殿を建て寛永十年(1633)山城国伏見稲荷神社の分霊を勧請し、駿府一加番の守護神として鎮斎したのが当神社の創祀と伝えられている。慶安四年(1651)由井正雪の乱があり、一加番は府城に近い横内御門前(現在の鷹匠一丁目)に移され、これに伴い当稲荷神社も新屋敷内に遷宮された。斯くて創祀以来文久元年(1861)に至る迄約230年間歴代の加番は折々に鳥居、燈籠等を献納し、年々の祭祀を厳修して、崇敬の誠をつくしてきた。
明治維新に至り加番屋敷廃邸後は、鷹匠町一丁目の産土神として、明治11年政府より存置が許可されて、一般市民の崇敬の神社となった。昭和20年6月戦災により社殿、工作物悉く焼失した。戦後氏子の奉賛により復興し、地域の区画も整理されて面目を一新し、当神社の信仰は市の内外に広まるに至った。
祭典:例祭5月5日、歳旦祭:1月1日、節分会:2月3日、秋祭:11月25日。
昭和63年5月 奉納:松浦元男
・二加番稲荷神社(西草深町4)
もとは駿府城の警護用番所でもっと敷地も広く馬場等もあったが、今はそこの祠があった部分のみに神社がある。周辺は住宅地でキリスト教会やNHKビルがある。そこもかつては敷地内だったはず。
・村本喜代作先生明徳碑文:翁は西草深町520世帯の町内会長として20年にわたる長き間、社会公共のため奉仕せられた功績は甚大である。当二加番稲荷神社は戦災により灰燼化し瓦礫の中に樹木を植え社殿を再建し自ら責任役員となり神社を中心に民福をはかり明朗な社会環境造成に盡くす。又政教社雨声会を起し政治経済文学史話等の講演を行うこと実に250余回、其の間先生の薫陶を受けた方の中には名政治家も現はる。ここに村本喜代作先生を後世に伝えるため西草深町内会神社総代会雨声会の有志相謀り明徳碑を建立する。昭和55年3月、~以下略~
・手洗石:文化(五)九年(戌辰)壬申歳、・神社名石碑:昭和四十三年、・石灯籠:天保十五甲辰、・石鳥居:昭和四十六年、・石柵:昭和四十八年、・?石灯籠の一部:元文四巳未、・?石塔:崩れて成れの果て、
・説明版:二加番稲荷神社:祭神三社:豊受毘賣命トヨウケヒメノミコト穀物の神 商業あきないの神、猿田彦命サルタヒコノミコトお祓いの神、天鈿女命アメノウヅメノミコト神楽の創始芸能の神、由緒:駿府城は寛永8年以後は城主を置かず「城代」によって統治され、城外守衛のため「加番」という役が置かれた。当所は二加番屋敷の跡で、その守護神として稲荷神社が祀られた。当社を鷹森稲荷と称されたのは、この附近を流れた安倍川のほとりに鷹が集った森があった故という。一加番(鷹匠1丁目)三加番にも夫々稲荷神社が奉祭されている。明治維新後は西草深町の産土神として遠近より崇敬されて今日に至った。加番屋敷には馬場、的場、火の見櫓などがあり、その略図を裏面に記した。歳旦祭 1月1日 春祭 初午 春分の日 秋祭 秋分の日
・裏面:二加番屋敷略図:外堀に面した現在はNHK静岡放送局から付近一帯の住宅地も含む広大な屋敷であることが分かる。外堀側77間(138.6m)、奥行き42間(75.6m)、面積10478.16平方m、3175坪。
・三加番稲荷神社(東草深町11)
・石碑:神社名:昭和三十八年九月、・石柵:平成九年、・石鳥居:安政六巳未二月初午、旗指石:奉献安藤杢(木の下は工ではなく立つ)之助源有(有るの下は月ではなく且つ)剛、・手洗石:安政(正の下に久)□□□二月、・手洗石:?、・石塔:寄進~~~、・石(埋)、・礎石2?、・石燈籠2:、・倒れた石燈籠:稲荷大明神 廣舟(止の下は舟) 文化三丙寅三月初午、
・説明版:祭神:保食大神ウケモチノオオカミ、祭日:春祭:春分の日、秋祭:秋分の日、由緒:寛永八年(1631)に駿府城主徳川忠長が将軍の勘気に触れ蟄居を命ぜられての後は駿河国は幕府の直轄領となり、駿府城には城主を置かず城代定番が勤める番城となり定番の下に小大名または旗本の中から加番を勤番せしめ城外の警備に当たらしめた。慶安四年(1651)に由井正雪の反乱があっての後は、従来の一、二加番に加えて三加番が増設され、東草深にその屋敷を設けると共に邸内の守護神として、この三加番稲荷神社を鎮祭した。代々の加番は深く崇敬して毎年二月初午に盛大な祭典を行い、また石燈籠鳥居等も数多く奉納された。
明治維新に至り加番屋敷廃邸後は、東草深三ヶ町の鎮守となり、明治11年3月政府公認の神社として存置を許可された。後に水落町二丁目も氏子に加わり一般町家、遠近の人々から深く信仰されるに至った。
御神徳:保食大神は伊勢の外宮に奉祀する豊受大神と御同神で人間生活に一番必要な食糧と衣料をお恵み下さる神である。古歌に「朝夕の箸とるごとに保食の神の恵みを思え世の人とあう」また福徳円満の神、商売繁盛の神として最も信仰される神である。
・草深界隈の古い洋館類、キリスト教会等(西草深町、東草深町)
‘13現在、(西草深町15番)西草深眼科(かつての中島医院)が洋館の趣をとどめている。他にもあったのだがだいぶ減少した。教会も現代建築のビルに改築され古式ゆかしさは消失した。
静岡英和女学院(西草深町8)はねむの木学園創設者:宮城まり子出身校である。
クラシック音楽愛好家には一時期全国的に知られていたのが青島ホール(西草深町16‐3) である。
・西草深公園(西草深町27)
・説明版:西草深と徳川慶喜公:草深町は駿府九十六ヶ町の一つで、現在の西草深公園の東側に、二筋の通りに面して一画を占めていました。明治6年(1873)に一帯の武家屋敷を含めて西草深町となり、昭和44年に御器屋町ゴキヤチョウなどを併せて現在に至っています。駿府城に近い草深町の近辺には慶安4年(1651)に駿府城の警護や城下の治安維持にあたった加番の一つ二加番や与力、同心などの武家屋敷が配置されていました。草深地区には江戸時代初期に徳川家康公に仕えた儒者、林羅山の屋敷があり、また明治維新期には静岡学問所頭ガクモンジョガシラであった向山黄村ムコウヤマコウソンをはじめとする学問所の著名な学者が多数居住していました。西草深公園には浅間神社の社家シャケの屋敷があり、明治2年(1869)6月に静岡藩主となった徳川家達イエサト公が社家新宮兵部シングウヒョウブの屋敷に移り住みました。
徳川幕府第15代将軍徳川慶喜公は、大政奉還の後、慶應4年(1868)2月から謹慎生活に入り、同年7月に駿府の宝台院に移り住みました。宝台院での謹慎生活が解かれた慶喜公は、明治2年(1869)に紺屋町コウヤマチの元駿府代官屋敷に移り、更に明治21年には西草深町に屋敷を構えましたが、東京に戻る明治30年まで政治の世界を離れ、一市民として過ごしました。静岡での慶喜公は、狩りや写真を好み、油絵をたしなみ、明治10年代から自転車を購入して市内を乗り回って市民の話題になるなど、多種多様な趣味と共に西洋的な生活を謳歌した当時の最先端を行く文化人でもありました。中でも静岡で修得した写真撮影の技術から生まれた作品は、各地の風景、生活ぶりを伝える貴重な歴史資料ともなっています。慶喜公が、東京に戻った後の徳川邸は葵ホテルとなり、更に明治37年には日露戦争の捕虜収容所の一つとして使われましたが、同38年に施設内から出火し焼失してしまいました。
・説明版:万葉歌碑:焼津邊 吾去鹿歯 駿河奈流 阿倍乃市道尓 相之兒等羽裳
春日蔵首老 焼き津辺にわが行きしかば駿河なる安倍の市道に逢いし児らはも
万葉集は日本最古の歌集で奈良時代
~~~不明、
昭和36年
*写真不鮮明で判読困難
以下は、インターネット検索「万葉集巻3、れんだいこ」より引用
「万葉集、巻3、No.284、春日蔵首老かすがのくらびとおゆ、作歌
焼き津辺=静岡県焼津市辺り、阿倍=静岡市安倍、安倍川の安倍、市道=イチジ、市場が開かれていた道、焼津方面に赴いた際、安倍の市で出会った娘たちを思い出して懐かしがっている歌。これを男女が市に集まって乱舞した、いわゆる歌垣の際の思い出ととってもよかろうが、そうとらなくても単純に美しく楽しげだった娘らを思い出しての歌として一向に差支えない。」
私見:この短歌から静岡市(安倍の市)がすでに奈良時代に賑わっていたことが分かる。
・石鳥居
浅間神社前、麻機街道と長谷通りの分岐点
・浅間神社(静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町102-1)
・交番裏の賤機山を上るとすぐ賤機山古墳がある。もう少し上に麓山神社がある。さらに上に一本松・5世紀の古墳がある。さらに上ると浅間山山頂(△140m)で舗装路はなくなり、あとは山道となる。その先に空堀(地獄谷)があり、さらに先に賤機山城址(△173m)と光明地蔵となる。
浅間神社境内遺跡跡。国・重文・浅間神社社殿。石造物でも石灯籠等、市内最古級のものが多い。
国・登・遍界山不去来庵本堂。
・西蔵寺(片羽町79)
・三界萬霊等、・庚申塔、・地蔵、・新:観音、・手洗い石、・新:灯篭、
・元三大師延命地蔵(安倍町23)
・地蔵:
・瑞光寺(安西1丁目100‐1)
・石塔:文正夂(政)十三年庚寅八月、・?観音:元文五庚申、・板碑:山梨易司翁彰功碑 大正八年、・板碑:佐久間翁叟先生碑、・新:有縁無縁三界萬霊、・お花塚 石州流生花家元~~昭和十三年、・如来(4):片足膝立ち座位、・地蔵(4)、・地蔵、・同一様式の観音約80基(三十三所観音3つ分で不足分は消失か、いくつかには二十六番等の番号が読み取れる)、
*文政の政を正夂と刻字してあるのか?
・然正院(安西1丁目103)
・新:六地蔵、・新:水子供養塔(2)、
・末広中(末広町)
かつて高等女学校があった。
・神明宮(神明町54)
・木鳥居、・常夜灯(2):昭和十五年、・石柵:昭和十五年、・狛犬(2):昭和十五年、・神社名碑:平成二年、
調査 ’13 11~12月を含む版
まだ未調査地や不十分な個所が多いですが、いったん公開します。将来のんびりと改訂していきます。
・用語説明
・国、県、市=国、県、市指定、・有、無=有形、無形、・登=登録、・文=文化財、・天=天然記念物、・重=重要、・民=民俗、・石=石製、・家=家型、・新=近代から現代にかけて作られた新しいものと推定されるもの、・古=新しくなく古そうなもの、・欠:破損欠落しているもの、・馬頭=馬頭観世音菩薩、・コンクリ=コンクリート製、(2)=2基、
・古い用語説明
廿=20、廿の縦線3本=30、等=塔、歳‣天‣月日=年、
美良または羊良=養(美や羊ではなく羊の下は大であり美ではなく横線3本である。狼という字に似ているが、その字がパソコンで出てこない。そういった字は多く他の現代的な字に切り替えたり注を施す)、クイズ:ちなみに養がなぜ美(横線3本)や羊(下は大)と良なのかはちょっと考えるとすぐ分かります。このように漢字の部分を上下左右に組み替えることは石塔への刻字ではよくあります。彫る時の字のバランスを考慮した石工さんたちの工夫です。ちなみにある石工さんはこういう字をお寺さんの字と言っていましたが寺院で使う字ではありません。この前見た字では政を上に正、下に政の正抜きの字を彫ったものを見ました。
*「石仏事典」類を参照してください。年号や干支もこれで分かります。
・住所について
なお住所は正確に分からないものは多く、隣や付近の住居の番地号を用いているものが多い。
○静岡市市街地内、静岡駅北西部
・宝台院(常盤町2丁目13‐2)
・宝台院ほうだいいん、金米山宝台院:説明版:宝台院は、徳川家康の側室で二代将軍秀忠の生母西郷の局サイゴウノツボネ(お愛の方)の菩提寺である。西郷の局は27歳で家康に仕え、翌天正7年(1579)4月、家康の第3子秀忠を生んだ。家康38歳の時である。この頃家康にとっては、浜松城にあって、三方原の合戦、設楽原合戦、小牧長久手の合戦と、戦に明け暮れたもっとも苦難な時代であった。西郷の局は、家康の浜松城時代に仕え、苦しい浜松城の台所を仕切った文字通り糟糠ソウコウの妻であったということができる。天正14年12月、西郷の局は、長かった苦難の浜松時代を終え、名実共に東海一の実力者となった家康と共に駿府入りした。家康の陰の立役者として、献身的に仕えた西郷の局は、駿府入りと共に浜松時代の疲れが出て、天正17年5月19日、38歳の短い生涯を終わった。後年、将軍職に就いた秀忠は、母のために盛大な法要を営み、その霊を慰めた。以来、徳川300年の間、この宝台院は、徳川家の厚い保護を受けたのである。
寺宝:白本尊如来像:重要文化財、他多数。静岡市。
・徳川慶喜公謹慎之地:宝台院と徳川慶喜公:説明版:明治元年七月、第十五代将軍慶喜公、御謹慎の身となり、同月十九日水戸を出発して銚子港に到着し、同月二十一日蟠龍艦に乗船し、同月二十三日に清水港に到着しました。海路にて移動したのは、上野彰義隊の戦いの興奮も冷めない江戸を通ることが、極めて危険なことだったからでしょう。この時目付の中台信太郎(のち駿府藩町奉行)がこれを出迎え、また精鋭隊頭松岡万以下五十名の厳重な護衛がついて駿府に向かいました。慶喜公が討幕派、旧幕臣の双方から命を狙われる重要人物であった事情に加えて、無政府状態とも言うべき当時の駿府の町の状況がこのような物々しい警護体制を必要としていました。一行は当日夕刻には宝台院に入りましたが慶喜公の駿府移住は秘密裏に行われ町民には一切知らされていませんでした。慶喜公の駿府入りが町触れで知らされたのは、その五日後の二十八日のことでした。尚、宝台院を慶喜公謹慎の場所に選んだのは元若年寄大久保一翁でした。彼は駿府町奉行の経験もあってこの町を熟知しており、徳川第二代将軍秀忠公の生母西郷局が葬られた宝台院こそ慶喜公が落ち着いて過ごせる場所と考えたのでしょう。以来、精神誠意慎をされ翌明治二年九月二十八日、謹慎が解け十月五日紺屋町の元代官屋敷(現在の浮月楼)に移転されるまで、約一年余りを当山で起居されました。この謹慎の部屋は十畳と六畳の二室で、十畳の間を居間、六畳の間を次の間として使用し、当時渋沢栄一や勝海舟と面会されたのもこの六畳間でした。明治元年八月十五日、藩主亀之助(家達公)が駿府に到着した時も、先ず宝台院に参上し御霊屋に参礼の後、やはりこの部屋で対面したということです。家達公は七間町三丁目を曲がり、御輿で大手門より入城されましたが、当時まだ七歳というお年でした。現在の宝台院には、慶喜公の遺品として、キセル、カミソリ箱、急須、火鉢、本人直筆の掛軸、居間安置の観音像が残っております。静岡市。
・西郷の局供養塔、・キリシタン灯篭、・百度石、・尺八碑:明治二十三年、・板碑:燈臺寄附連名:明治三十二年、・板碑:潮田良一之碑:昭和二十二年、・板碑:俳諧師かしく坊の辞世、・新:延命地蔵尊:駿河一国百地蔵尊第三十一番、祠:稲荷大明神、・新:西国九番札所:観世音菩薩安置成田山不動尊、手洗石:長野縣信濃国諏訪郡冨士見□、・狛犬2、・地蔵、・観音、・不動明王、・新:地蔵2、・石:三○:?石垣用石、・新:狛犬2:大正十三年、・新:観音:レリーフ、・石碑:アソカ幼稚園園歌:平成二十一年、
・家康の身代わり観音:阿弥陀如来立像のこと、かつては像に傷がついていたが現代に修理したため傷は消失した。家康は本像を合戦に持って行き安置しており、自分の近くに置いた像に矢が刺さり身代わりになったと考えたというが、伝説なのか史実なのかは不明。しかも傷がなくなったそうなので、いかなる傷だったのかもなおさら不明。
ちなみに静岡市葵区、宝台院のホームページを調べると、徳川家康関係の宝物(阿弥陀如来立像、家康公の自画像、真の太刀、家康公筆「安元御賀記手習」)、三代将軍家光公筆「遠山月」二代将軍秀忠の生母・西郷の局の墓、徳川慶喜公謹慎之地、かくし坊の辞世があり、その中にキリシタン灯篭もある。説明文:「キリシタン灯篭:茶人として有名な古田織部が制作し駿府城へ奉納、徳川家康公の侍女・ジュリアおたあが信拝したという灯篭です。この灯篭は城内より静岡奉行所を経て宝台院へ移されました。」とある。
ジュリアおたあをウィキペディアで調べると生涯概略の他、文章末に「~なお、駿府時代には灯篭を作らせ瞑想していたと言い伝えられており、そのキリシタン灯篭は、現在は宝台院に移されている。」と書かれている。
これらはいかなることでしょう。日本最初のキリシタン灯篭発見が宝台院で1923(対象12)年とすると、ジュリアおたあ信拝説はそれ以後と思われますが、いったいどういう証拠があるのでしょうか。分かりません。
*私見での「キリシタン灯篭の疑問点と保存」については別項目を参照してください。文章が長くなるのでここでは割愛します。
・鎮火稲荷神社(本通5丁目1‐5)
・稲荷(2):昭和廿三年、・鳥居:コンクリ、
・津島神社(梅屋町4‐1)
・鳥居:コンクリ、・狛犬(2):昭和54年、
・説明版:津島神社:祭神:当神社の御祭神:素戔嗚尊は日本神話の中で伊弉諾尊、イザナミノミコトの御子で天照大神の□神に当たられ、荒々しい剛直な性格の神で、天照大神を天の岩戸に~~させ給われ、高天原から地上に追放されました。出雲で八岐のおろちを退治されて奇稲田姫と結婚され大蛇の尾から出た天叢雲剣~~し献上されました。また新羅に渡られ船材の樹木を持ち帰り~植林の道を教えられたと伝えられております。また、大国主命は素戔嗚尊の御愛婿であられ、出雲の地で親子二代に亘って国土の経営、産業開発にお力をいたされ、災厄と疫病を除く御徳と受福の神様として世に知られております。神話では暴風神、英雄神、農業神として語られ、氷川神社、八坂神社、熊野大社などの御祭神でもあります。
天王さん:津島神社は古くは津島牛頭天王社と言い、今日でも一般に「お天王さん」と尊称されております。これは日本には上古から民俗宗教としての祖神信仰がありましたが、仏教が伝来して次第に日本化して、その結果崇神、崇仏思想が接近し、後年明治政府が神仏分離令を発布するまで、神宮寺、寺院鎮守など神社とお寺が同居していたことと関係があるように思われますが、インドの祇園精舎の守護神であるとか、新羅の牛頭山に留まっていた素戔嗚尊の御神霊を勧請してお祀りしたとか諸説があってはっきりしません。
由緒:神社年鑑によれば天明5年(1785)創建、明治11年公称を許可とあります。古老からの言い伝えで、昔疫病が流行り疫病除けの神として勧請したと言われておりますが、歴史年表を見ると。天明3年の頃には、「7月浅間山噴火、死者2万人に及ぶ。この年未曽有の凶作、奥羽の死者数十万人に達する」 天明4年は「この年夏、秋、米価騰□して諸民飢餓し、秋よりは疫病流行して死者が多い。」 天明5年「奥州三春、凶作、琉球凶作」 天明6年「江戸開府以来の大水で死者、家屋破損が多い。この年大凶作、収穫三分の一」などとあり、疫病除けの神として素戔嗚尊を勧請したものであろうと推測されます。
沿革:天明5年 創建、明治11年 公称許可、昭和9年 本殿、拝殿、社務所等造営、昭和15年1月15日静岡大火にて焼失、昭和15年仮社殿造営、昭和30年 空襲の罹災を免れる。その後現在地に移転。昭和44年 新社殿造営、現在に至る。平成11年6月吉日。
・八朔神社(本通2丁目1‐3)
・木鳥居、・手洗石、
・静岡神明宮(屋形町13)
・石鳥居:大正十五年、・常夜灯(2):大正十五年、・石柵:大正十二年、・狛犬:大正十四年、・神社名碑:昭和八年、・道路開鑿碑:明治四拾年、
・東本願寺静岡別院(屋形町10)
・新:堂、・新:木石堂、
・大林寺(安西4丁目93)
・梶原景季と景嘉の墓:五輪塔:土水火風空、・祠:白山妙理大権現、・祠、・山門:仁王像(阿吽)、裏に風神と雷神像、・新:水子地蔵、・新:六地蔵、・石燈籠、・観音、・中世末墓石、江戸初期墓石(2)、観音風墓石(2)、・青面金剛供養塔:天明二、・法華千部塔:文政二、
・説明版:縁起:古記録によると当山は今から約800年前、鎌倉時代初期当國庵原郡高部村大内にあり、大淋寺(天台宗)といい大林寺殿贈四品榮昌福寿桑道場妙開大禅定門、姓平氏葛原親王第十四代梶原信濃守従四位少将景義四男刑部少輔朝景卿建仁元辛酉(1201)年5月3日卒を最初の開基としている。文永元(1264)年12月18日仏殿を今の柚木町に建立している(駿河記)。時移り戦国争乱期、北条早雲殿(1459)の命により、武田、今川の動静を探るため旧東海道の見張所としての城塞の寺を現在の場所に草創したのである。七堂伽藍は一万の大軍を収容でき、山門が柚木町の堤上にあり、その下に尼寺と墓地があった。寺格は法地寺中5反6畝3歩安西内新田、除地5反3畝3歩安西外新田、雑地10反あり(駿河志料)。
その後曹洞宗通幻派最乗寺門下総世寺末となり同寺五世天祐宗根和尚に嗣法する鳥道長鯨和尚天文12(1532)年癸卯12月10日寂を開山としている。三世好山宗禅和尚は慶長年間(1596)徳川家康より法門の聴聞あり。四世明室温察和尚(1624)は梶原源太景季、景嘉の墳墓を改築し、六世揚山和尚(1704)は末寺龍津の中興で、七世大鳳和尚(1688)貞享3年梵鐘鋳造の功をなし良富院の開山となる。九世槐國萬貞和尚(1716)は最勝、定林に歴住し海松、円城、雨林の3か所の開山であり、卍山道白禅師の法嗣で、徳川吉宗の釣命により、官刹長崎の皎台寺に転住し、大同庵、金泉寺を開き語録二巻を著している。十世古岳日峻、十四世一了玄画和尚も皎台寺に当寺から普住した。特に日峻は書物に参同契測海があり、海門及び月舟宗胡、独庵玄光、(辟と水で上下)山の高泉、黒瀧の潮音、槐國と共に参じた中世稀にみる高僧である。二十九世祖鳳光禅和尚は洗耳寺に歴住し明治40年七堂を再建したが、昭和20年6月19日戦火により焼失している。昭和34年三十一世光雄和尚が本堂、位牌堂、庫裏を再築している。尚開基より光雄和尚まで5回兵火に遭っている。また寺の所在は大内→安西→柚木→安西(正保元(1644)年町奉行落合氏により)に戻っている(寛政寺記及び駿河記) 昭和60年12月18日 大林寺 三十一世大鑑光雄記
・説明版:大林寺墓塔群:○梶原源太景季・景嘉の墓:源頼家(1182)の母政子の父北条時政の家来家来梶原景時(1200)が滅ぼされ、その門葉景嘉が駿河殿(徳川忠長1602)に仕え寛永9年(1632)壬申1月21日歿した。本府古図の安西4丁目南にその姓名がある。大内梶原堂の条によれば太田美濃守入道資正二男が梶原の養子となり源太政景といった。景嘉はこの後葉である。(駿河志料他)
○落合能登守小平次道次の墓(1652):長篠城攻防戦の勇者鳥居強右衛門の磔に感動した落合佐平次道久は、自分の指物に磔の図を描いて出陣し、家康に見出され、後に徳川頼宜に従って駿河衆となり、養子の道次は江戸幕府に出府し駿河奉行として由比正雪を召し捕り功あり。寛永17年より承応元年まで13年奉行として活躍した。慶安5年8月9日寂。
○安鶴の墓(1872):『諸国畸人傳』(石川淳)『駿府の安鶴』(江崎惇)により全国的に有名。
○舟川斎寺西源正勝の墓:幕府旗本天神真陽流柔術指南医士。
○小沢久七の墓:長崎で勉強し漆器界の発展に尽力した。
○小出東嶂の墓(1823~1889)画家福田半香の弟子であり書画に通じ明治6年静岡新聞を刊行す。
協力者:~略~、昭和60年12月18日、大林寺31世大鑑光雄代
・延命地蔵堂(安西5丁目114)
・堂、・秋葉山常夜灯、
ここから川根筋に抜ける川根(秋葉)街道の起点と考えられている。
*「川根(秋葉)街道」については、『古街道を行く』鈴木茂伸(静岡新聞社)をご覧ください。ただこの本すでに絶版ですので、静岡県内図書館にあるので検索するか、静岡県内の古本屋にもないので、古本屋にリクエストしていって取り扱ってもらえるとよいでしょう。
・柳町水神社(柳町135)
・木鳥居、・手洗石、・社、
・曙稲荷神社(若松町15)
・石柵:昭和十年、・石鳥居:昭和十年、・石燈籠(2):昭和十年、・石燈籠(2):昭和四十年、・稲荷(2)、・稲荷(2)、・祠、・手洗石、
・八雲神社(北番町84)
・神社名碑:昭和四十六年、・八雲神社碑、・新:狛犬(2)、・石鳥居:明治三十四年、・手洗石、・石燈籠(2):明治三十年、・北番町公園碑:昭和46年、・石塔:庚申、・石塔?、・石塔?:文政六癸未年、・若松町制四十周年:昭和三十九年、
・八雲神社御由緒:鎮座地:静岡市□番町八雲~、祭神:~~~、祭□:例祭、~~~~、創立年月日:口伝によれば応永3年創立と伝承。
往古は牛頭天王という。当国総社浅間神社に祀られていたが、戦禍に遭い別当職が簑に納め安倍郡大岩村に遷し大岩村村民の氏神として祭祀を引き継ぎたり。その後寛永の頃駿府城北番詰所の番士この地に居住し牛頭天王を崇敬し為に寛永3年大岩村よりこの地に勧請し宝永3年真言宗建穂寺末寺別当牛頭山宝積寺中興願成院智寂法印氏神として祭祀を承継す。明治3年神仏混淆廃止令により八雲神社と改称、同8年2月村社に列格、同43年6月18日神饌幣帛供進指定を受く。敗戦により国家の庇護を離れ、神社本庁設立に伴い、静岡県神社庁所属となり、氏子により祭祀を継承、現在に至る。350年を記念して建立。~以下略~
・桜森稲荷神社(土太夫町7)
・鳥居:コンクリ、・新:燈籠、・古:燈籠、・手洗石、・石:家:道祖神、
・二十六番札所、水月院(安西1丁目24)
十一面観音菩薩、
・説明版:水月堂御縁起:水月堂(通称おはつかさん)は静岡市安西1丁目南裏に位置し十一面観世音菩薩を安置し、新選府辺観音霊場(新西国)三十三か所巡礼札所中第26番にして本尊は鎌倉初期の名匠運慶の作と伝えられ国宝的存在でありました。しかし戦災(昭和20年6月20日)で焼失してしまいました。元亀年間、今を去ること400有余(405)年前、安倍郡籠鼻(今の井宮町西北部)の圓皆寺(現在は廃寺)の住僧宗文の創建で今川家の臣福島淡路守の夫人然正院智現妙本大姉の開基と伝えられています。毎月20日を以て御縁日と定め毎年3月には僧侶も招き特別大法要を続けております。 平成18年3月20日、水月堂奉賛会
・住吉神社(一番町25)
・手洗石:奉献願主府内(絞?)仲間、常夜灯:昭和六年、・石鳥居:昭和五十年、・石燈籠(2):住吉大神宮御宝前 文化十年と大正四年、・石碑:神饌幣帛供進指定中津神社 昭和十六年、
中津神社とは何? 昭和16年号なので静岡空襲か大火で消失し、戦後住吉神社と併合され、たのか?
・顕光院(研屋町45)
・馬頭(3):馬頭観音建立由来碑:昭和13年1(6)月15日正午過ぎ新富町、~~~不明
*撮影した写真不鮮明で判読困難、再度やり直す気がないのでこのままです。ごめんなさい。
おそらく内容は静岡大火と静岡空襲による戦火の災害供養のため馬頭観音を設置したと言いたいようです。
・地蔵、・南無阿弥陀仏:昭和二十六年、・地蔵(3)、・板碑:大正九年、・新:六地蔵、・三界萬霊等、・無縁堂、・平和観音堂、・庚申:文化四、・庚申:寛政二、・新観音、・新:灯篭(3)、・新:駿河一国百地蔵第一番開運成就地蔵尊、・奉納弘法大師四国八十八所 国々諸々神社供養 秩父三十三所 一国三十三所 坂東三十三所 文政四、
・くがたか橋の碑(追手町12)
かつての外堀沿いの橋の欄干だったのか。
・石塔(城内町1‐2)静岡聖母幼稚園前
全く刻字等有無不明
・石碑:青葉小(追手町4)
廃校になった青葉小学校の記念碑。
・校址碑:静岡第二尋常小學校 明治34年新設、静岡城内東小學校 大正2年 校名変更、静岡城内東尋常高等小學校 大正13年 校名変更、静岡城内東尋常小學校 昭和8年 校名変更、城内東國民學校 昭和16年校名変更 昭和20年9月5日廃校、青葉小学校 昭和29年4月設立、平成19年3月閉校、
・石碑:城濠用水 土地改良区記念碑(追手町4)
・説明版:城濠用水由来:城濠の誕生は慶長12年
~写真不鮮明で判読あきらめ~
昭和53年5月、城濠用水土地改良区
・石碑:葵文庫跡(追手町4)
・説明石碑:由来:葵文庫は大正8年静岡に縁の深い徳川家の記念事業として計画され、同14年3月28日徳川家の家紋を館名としてこの地に開館した。その特色は、江戸幕府旧蔵書の一部である「葵文庫」と3代県令関口隆吉収集にかかる「久能文庫」にあった。以来県立葵文庫は県民の図書館として、また全国的にも貴重書の宝庫として注目されその発展をみた。昭和44年市内谷田に新館が建設され、静岡県立中央図書館として移転すると、葵文庫は新たに静岡市立図書館として再出発した。しかし施設の老朽化により、昭和59年市内大岩に新築移転したため、県民に親しまれた建物は取り壊された。~~~不明
*撮影した写真に石碑終盤の文字が写っていなかったので不明としました。撮影し直すなりもう一度見に行って判読するなりの気にならないので一旦終了します。ごめんなさい。
・駿府城(駿府城公園)
・説明版:駿府城は外堀、中堀、内堀の三重の堀を持つ輪郭式の平城です。本丸を中心に回字形に本丸、二の丸、三の丸と順に配置され、中央の本丸の北西角には、五層七階(外観五層内部七階)の天守閣がありましたが、寛永十二年(1635)に焼失しています。駿府城が城郭としてその姿を見せるのは天正十三年(1585)に徳川家康が築城を開始したことに始まります。この天正期の駿府城は現在の城跡に比べると一回り小さいと考えられますが、詳細は不明です。この後江戸幕府を開いた家康が慶長十二年(1607)将軍を退き、駿府に移り住むために天正期の駿府城を「天下普請」として拡張、修築しました。当時の駿府は江戸と並ぶ政治の中心地として重要な役割を果たしていました。 平成8年3月 静岡市
・巽櫓(駿府城公園)内堀沿い たつみやぐら
巽櫓は駿府城二の丸の南東に位置する木造矩折三層二重の建物です。この巽櫓は寛永十二年(1635)城下から出た火によって延焼焼失し、寛永十五年に新たに建設されたといわれています。巽とは十二支で表した方位で辰と巳の間、即ち南東の方角をいいます。また櫓とは、一、武器を納めておくため、一、四方を展望するために設けた高楼、の役割をしたものです。巽櫓の復元は、「駿府城内外覚書」や「駿府御城惣指図」の資料をもとにしており、3年の歳月をかけ、平成元年3月に完成しました。 静岡市
・東御門(駿府城公園)ひがしごもん
東御門は駿府城二ノ丸の東に位置する主要な出入口でした。この門は二ノ丸堀(中堀)に架かる東御門橋と高麗門、櫓門、南・西の多門櫓で構成される枡形門です。東御門の前が安藤帯刀タテワキの屋敷だったことから「帯刀前御門」また、台所奉行の松下淨慶にちなんで「淨慶御門」とも呼ばれ、主に重臣たちの出入口として利用されました。東御門は寛永十二年(1635)に天守閣、御殿、巽櫓等と共に焼失し、同十五年に再建されました。復元工事は、この寛永年間の再建時の姿をめざし、復元したものです。 平成八年三月 静岡市
・坤櫓(駿府城公園)内堀沿い ひつじさるやぐら
木造二層三階。家康築城時に武器庫として利用される。寛永12年(1635)の火災で焼失。2014年4月に復元工事完了し1階は公開される。2階は非公開。
・駿府城公園内:発掘された石垣、公園内地面下には戦国期の今川館跡遺跡
駿府城は古くは今川館があったと推定される。その後徳川家康により隠居城となり、一時は大名が治めたこともあるが、長くは代官の行政所となり一部を使用したようだ。使わない部分はかなり荒廃した箇所もあるようだ。江戸時代中期以降は狐が住んでいたほど荒れていたようだ。明治期に内堀を埋立て軍隊駐屯地になった。今は公園。発掘で徳川期の石垣や使用道具類、今川氏館跡等が出土している。しかも焼かれた物が出土している。武田氏により滅ぼされ今川館は焼失したと思われるが、そのとき焼かれた物かどうかは不明。
天守閣は家康が建造したが女中の不手際で失火焼失、再建されたがまた焼失。代官時代には天守閣はなかったようだ。またそれ以外の建物や施設も代官時代に使用が縮小していったようだ。
現在みられる駿府城外側の石垣は近代以降、幾たびも修復されているので全てが江戸時代のものというわけではない。ただ一部残存しているのも確かで、家康が築城する際には全国の大名を動員したので、石垣に各大名のしるしがつけられているものがある。また各時代により石垣の積み方に特徴が出ている。
*石垣の積み方についてはネットや図書で検索してください。
・家康お手植えの蜜柑ミカンの木、
・家康銅像、
・東海道中膝栗毛弥次喜多像(追手町)内堀沿い
・説明版:十返舎一九と「東海道中膝栗毛」: 「東海道中膝栗毛」の作者十返舎一九(1765~1831)は、ここ駿河の府中(静岡市)出身で江戸文学における戯作者の第一人者であり、日本最初の本格的な職業作家といえます。1765年駿府町奉行同心、重田与八郎の長男として両替町で生まれました。本名は重田貞一、幼名を市九といいます。1783年大阪へ行き、一時は近松余七の名で浄瑠璃作家としても活躍しましたが、その後士分を捨て1794年再び庶民文化華やかな江戸に戻って戯作に道に専念し、多くの黄表紙や洒落本などを書きました。
「東海道中膝栗毛」は1802年初編(初編は「浮世道中膝栗毛」のち改題)以降毎年一編ずつ8年にわたって書き続け、1809年全8編を完結しました。この膝栗毛は爆発的人気を呼び、休む間もなく「続膝栗毛」の執筆にとりかかり、1822年の最終編までに実に21年間に及ぶ長旅の物語として空前の大ロングセラーとなりました。
物語は江戸神田の八丁堀に住む府中生まれの弥次郎兵衛(左の像)と、元役者で江尻(現清水市)出身の喜多八(右の像)という無邪気でひょうきんな主人公二人が江戸を出発して東海道を西へ向かい伊勢を経て京都、大坂へと滑稽な旅を続ける道中記で、今でも弥次喜多道中といえば楽しい旅の代名詞となっています。
当地の名物として安倍川餅やとろろ汁も登場。また府中では夜は弥勒手前の安倍川町(二丁町といった)の遊郭へ出かけたり、鞠子(現丸子)では、とびこんだ茶屋の夫婦喧嘩に巻き込まれ、名物とろろ汁を食べるどころか早々に退散したといった話が語られています。
一九は1831年没、享年67歳。墓所は東陽院(現東京都中央区勝どき)にあります。ここ府中は江戸から44里24町45間(約175㎞)19番目の宿です。
2002年2月、静岡市
・甘夏みかんの木(追手町)内堀沿い
・わさび像「わさび漬発祥の地」(追手町)内堀沿い
・説明版:わさびは370年前わが国で初めて安倍川上流有東木で栽培された。わさび漬けは今から200余年前駿府のわさび商人によってはじめて考案され幾多の人に受け継がれて改良進歩した。特に明治以後交通機関の発達により長足の発展を遂げたのである。ここに明治百年を期し先覚者の偉業を偲び感謝の誠を捧げて、この碑を建つ。昭和43年5月23日、静岡県山葵漬工業協同組合
・このわさびの像はコンクリ製で芋虫に似ていて一種のゆるキャラっぽい。あるいはシュールというべきか。宇都宮市に餃子像があるのならば静岡市にはわさび像です。
・現代アート像:指人形(追手町)内堀沿い
指人形 The fingerdoll 制作:細谷泰玆 Yasuji Hosoya 1983年
・石碑:静岡学問所跡(追手町)内堀沿い
・説明版:静岡学問所は明治維新後駿府に移ってきた徳川家(府中藩)により、藩の人材育成を目的として駿府城四ツ足御門にあった元定番屋敷内(現静岡地方合同庁舎付近)に明治元(1868)年府中学問所として創設されました。学問所には翌2年駿府が静岡に改められたことにより静岡学問所となりましたが、明治5年8月学制の施行とともに閉鎖されました。この学問所には向学心に燃える者は身分を問わず入学が許可され向山黄村、津田真一郎(真道)、中村正直(敬宇)、外山捨八(正一)など当代一流の学者により国学、漢学とともにイギリス、フランス、オランダ、ドイツの洋学も教授されました。またアメリカ人教授E.W.クラークは専門の理化学の他哲学や法学なども教えました。廃校後洋学系の教授の多くは明治政府に登用され開成学校(現東京大学の母体)の教授など学界や官界で活躍しました。静岡学問所の歴史は短期間でしたが、日本の近代教育の先駆けをなし、明治初期の中等、高等教育の最高水準の学府でありました。 静岡市教育委員会、平成元年12月
・石碑:戸田茂睡生誕之地(追手町100)とだもすい
1629~1706年、江戸時代前期の歌学者。父は徳川忠長(徳川3代将軍家光の弟、駿府城主、改易され謹慎の後自害)の付け人で、駿府城内で生まれた。
・駿府城四足御門跡(追手町)よつあしごもん
・説明版:駿府城南辺の西寄りの箇所に設けられた出入口で、東側の大手御門オオテゴモンと並び、東海道筋から城へ入る重要な出入口の一つです。三の丸堀を土橋で渡って、左手へ直角に曲がり渡櫓門ワタリヤグラモンから城内へ入る構造になっていました。 静岡市教育委員会
・大手‣追手門(追手町)
・説明版:駿府城大手御門:駿府城内に入る正面出入り口です。三の丸堀を土橋で渡って、右手へ直角に曲がり渡櫓門ワタリヤグラモンから城内へ入る構造になっていました。歩道には渡櫓門の柱礎石の位置が記されています。 静岡市教育委員会
・石垣修復説明版(追手町)
・説明版:駿府公園二の丸堀(中堀)石垣災害復旧工事完了のお知らせ:平成21年8月11日駿河湾で発生した震度6弱の地震により、駿府公園二の丸堀(中堀)の石垣が崩落しました。平成22年1月6日工事着手、平成23年3月15日工事完了、石垣の構造を説明した「石垣モデル」が駿府公園内、富士見芝生広場に設けてありますのでぜひ一度ご覧ください。静岡市。
崩落前と崩落直後、復旧後の3つの写真が並置されているので、見た目では一目で分かるようになっている。なお石垣は見えない内部構造も重要なので石垣モデルを見てください。
・静岡県庁本館(追手町9)
登録有形文化財、
・静岡市役所本館ドーム(追手町5)
登録有形文化財、
・教導石(追手町)県庁市役所前バス停
・説明版:静岡市指定有形文化財(歴史資料) 教導石きょうどうせき、指定年月日:昭和59年7月17日、所在地:静岡市追手町、所有者:静岡市、「教導石」は、明治という新しい時代を迎え、「富や知識の有無、身分の垣根を越えて互いに助け合う社会を目指す」との趣旨に賛同をした各界各層の人たちの善意をもって明治19(1885)年7月に建立されました。正面の「教導石」の文字は、旧幕臣山岡鉄太郎(鉄舟)の筆になり、本市の明治時代の数少ない歴史遺産の一つとなっています。碑の正面上部には、静岡の里程元票(札の辻)から県内各地、及び東京の日本橋や京都三条大橋までの距離を刻んであります。教導石建立の趣旨に従って碑の右側面を「尋ル方」とし、住民の相談事や何か知りたいこと、また苦情等がある人はその内容を貼り付けておくと、物事をよく知っている人や心ある人が左側面の「教ル方」に答えを寄せる、というものでした。尋ね事などのほか、店の開業広告、発明品や演説会の広告から遺失物や迷子をさがす広告なども掲示してよいことになっていました。全体の高さ:207㎝、台石の幅:107㎝、本体:高さ:177㎝、正面幅:44㎝、側面幅:38㎝、静岡市‣静岡市教育委員会
・正面:「教導石、里程(?田谷、略を上下に書く)表、駿河國沼津宿拾五里拾町余、同吉原宿拾里拾九町余、 同大宮町拾壹里拾六町、同興津宿四里拾貮町余、同清水町三里六町余、同根古屋村貮里拾九町余、同藤枝宿五里拾町余、遠江國静波町拾里貮拾九兆余、同相良町拾貮里貮拾町余、同掛川宿拾貮里拾七町余、同森町村拾六里三町余、同横須賀町拾六里三拾町」
右:「尋ル方、静岡里程元票 各地距離、東京日本橋四拾六里拾町余、神奈川縣廰三拾九里廿六町余、山梨縣廰貮拾七里拾七町、伊豆相模國堺貮拾里壹町余、伊豆國下田町三拾五里拾五町、同熱海村貮拾三里四町余、同修善寺村拾壹里二拾町、同韮山町拾九里三町余、同三島宿拾六里三拾町余」
*撮影写真不鮮明で判読困難、やり直す気がないので間違ったままですが掲載します。
左:「教ル方、同見附宿拾六里貮拾七町、同中泉村拾七里九町余、同掛塚村拾九里拾壹町、同濱松宿貮拾里拾七町余、同二俣村廿壹里廿七町余、同気賀村廿四里拾八町余、同新居宿廿四里二拾町余、遠江三河國堺廿六里(十十十)五町余、愛知縣廰四拾八里拾七町余、西京三条大橋八拾四里拾四町」
・街道研究としては近代の石道標の価値がある。
・札の辻(呉服町1丁目と2丁目の境)伊勢丹前
静岡市街の中心地は呉服町で、旧東海道も呉服町の札の辻を通過し本通り乃至は新通りに向かい直進するか曲がる交差点であり、高札等のお触書も建てられた府中宿中心の場所である。
・国・登・静岡銀行本店(旧三十五銀行)(呉服町1-10 )
国登録有形文化財、第22-0010号、この建造物は貴重な国民的財産です、文化庁。
景観重要建造物、静岡銀行本店(旧静岡三十五銀行本店) 静岡市葵区呉服町、指定第3号、平成23年9月30日、静岡市。
・静岡天満宮(中町1‐3)
・石鳥居:昭和三十一年、・神社名碑:昭和五十二年、・手洗石、・牛像、・石碑:川中天神伝説之地、黒い直径15~20㎝溶岩多数(富士山溶岩か?)、
・稲荷社祠:、・説明版:静岡天満宮末社、静銀稲荷社、御由緒:御祭神:稲荷大神、昭和20年終戦後、進駐軍が静岡に入り、大企業に立入調査を行った折、(株)静岡銀行の守護神として、社内に祀っておりました稲荷社を、直ちに撤去廃棄すべしと命ぜられ、銀行側は検討の結果、御神体を隣接する静岡天満宮(当時は天満天神社)に保管祭祀を依頼し、神社側もこれに応じて静岡天満宮末社「静銀稲荷社」として現在の場所に鎮座奉斎したのです。以来初午祭には静銀本店営業部の責任者が参拝する習わしとなったのです。御神祠:この御神祠は明治初年から昭和3年まで静岡天満宮(当時は天満天神社)の御本殿として鎮座しておりましたが、昭和4年新たに御本殿を造営するにあたり市内宮本町山下家に譲渡し同家にて同家の守護神として奉斎されていました。しかし同家の事情により、この神祠を処分することになりましたので、昭和54年2月同家より静岡天満宮の地に還御しました。これと同時に従来静岡天満宮の本殿に合祀しておりました、静銀稲荷社の御神体をこの神祠に奉斎して、今日に及んでいるのです。(昭和4年竣工の御本殿は、昭和20年6月戦災にて焼失)
・景行社祠:、・説明版:静岡天満宮攝社景行社御由緒:昌泰4年(901)1月25日菅原道真公が、無き罪により大宰府に流された。翌々日公の子息達も夫々別々の地に流され、次男景行も駿河権介に左降され、この駿河の地に流され、ここ駿河の国府に居住した。この国府は現在の静岡天満宮を中心とした一帯の地域である。その後景行の記録が定かでなく、今日に至ったので、道真公を祀る静岡天満宮を崇敬する有志が景行を祀ろうということになった。その折り、大阪市天王寺区の一行者(鎌原氏)や清水区三保の行者(日蓮宗)に「景行を祀れ」との道真公の託宣があったとのことで、平成元年春に景行社を創祀したのである。(平成20年6月25日再記)
・銅鐸:説明版:県指定文化財、奈良県北葛城郡上牧村観音山から出土したもので、銅製で耳がなくたすき形の模様がある。高さ19.7㎝、底の長径15.1㎝、短径11.5㎝、保管:登呂考古館、明治百年紀念、静岡県文化財保存協会、
・尼ヶ崎稲荷神社(中町37‐1)
・石柵、・手洗石:昭和六十年、・石燈籠(2):平成十九年、・稲荷(2)、
・説明版:尼ヶ崎稲荷神社の由来:元尼崎又右衛門という富商邸内にありました。家康に召されて駿府に移り、はじめ本通り五丁目に宅地を賜りそこを十軒町と言ったが、慶長14年四ツ足御門町(現中町)に替地を賜ったと言われています。尚金座町稲荷神社(後藤稲荷神社)がこのすぐ裏手にあり慶長の頃、駿府上魚町(現金座町日銀)で小判を鋳造した後藤庄三郎光次邸があった所でもあります。又銀座町は現在の東京銀座にお移されております。
・説明版:四ツ足御門と中町の由来:四ツ足御門町の町名は非常に地位の高い町名でありました。今の中町の所から駿府城に入ったあたりに駿府城の四ツ足御門がありましたので、この町名となったのです。さらにこれを遡れば、その昔、大化の改新に伴い今の長谷町付近に国府が置かれた頃、この中町付近に国庁の四ツ足御門があったからという説があります。その説によれば四ツ足の名は千数百年の歴史を飾る由緒ある町名であります。現在、中町という町名になったのは、四ツ足といえば獣類に通じ快い町名とは聞こえないということで、大正4年11月10日「静岡市の中心」ということで中町と改称されたのであります。 平成23年3月15日 春季大祭
・上魚町碑(金座町1)かみうおちょう
・説明版:上魚町は徳川家康の大御所時代には、中央の通りを挟んで南側を後藤庄三郎光次が拝領し、光次が江戸に移るまではここを金座として「駿河小判」と呼ばれる金貨を鋳造していました。また北側は駿府城築城の作事方中井正清が拝領していました。「駿国雑誌」によれば、家康の在城の時、下魚町から魚商人を移住させたとされ、町の南側には魚問屋、北側には青物問屋が軒を連ね、さながら「流通センター」のような役割を果たしていました。元禄5(1692)年の「駿府町数・家数・人数覚帳」によると、当時の上魚町は、南側が家数38軒、人数203人、北側が家数4軒、人数70人でした。上魚町は昭和3年に金座町となりましたが、それ以後も「かみんだな(上の店)」と呼ばれていました。
・金座稲荷神社(金座町49)
・手洗石:昭和六十二年、・常夜灯:昭和六十二年、・金座碑:昭和三十年:
日本銀行静岡支店からこの金座神社界隈はかつての金座で小判等を鋳造していた。
・説明版:お金の神様、金座稲荷神社御由緒、創建:慶長11(1606)年、御祭神:稲荷大神、秋葉大神、当神社は後藤庄三郎光次が徳川家康公の命を奉じ駿府、上魚町(現在の金座町)に金座を開設し小判の鋳造を始めるに際し金座の守護神として御二柱を祀ったのが起源であります。以来400年、上魚町の産土神として祀られ、その霊験洵にあらたかなる為、「お金の神、金運の神様」として広く崇敬を集め、通称「後藤稲荷」として親しまれてまいりました。その後幾多の変遷を経て、昭和62年5月23日、当所へ遷座致しました。尚金座町という町名は、歴史的事実にもとづいた町名としては全国で唯一のものであります。昭和63年11月吉日、金座稲荷神社。
・戸塚歯科医院跡(本通1丁目3‐2)
かつて戸塚氏は郷土史家として静岡近辺の野仏や民間習俗の研究で知られていた。氏の本は私にとっても貴重な資料である。
・奥津宮神社(車町26)
・新:石灯篭、・庚申供養塔:文政三庚辰年、・石鳥居:昭和二十六年、・石柵:平成四年、・欠:庚申:安政七、・欠:庚申供養塔:文政五壬午年、・観音堂、・欠:奉寄進石燈:寛文(?政)九年
・石碑:説明:奥津彦神社、静岡市葵区車町26鎮座、祭神:火産霊神、奥津彦神、奥津媛神。由緒:神社の創立年月不明。社伝に駿河国の守護今川範国の子今川了俊深くこの神々を崇敬して邸内に奉祀してあったが、その子今川仲秋に政治の要諦を教えると共に「よくこの神を信仰せよ」と御神体を授ける。仲秋はよく父の教えを守り身を慎み祭祀を怠けたらず善政を行いやがて立身して遠江守護、尾張守護等を歴任した。仲秋は一の世を去るに臨みてその家臣に命じて御神体をこの地に祀らしめ三宝荒神社と称したと伝えられている。三宝荒神社は明治元年の神仏分離令に依り奥津彦神社と改称された。又三宝荒神社の別当用触山守源寺は昔から駿府の会所に使用され町々へのお触れ通達はここから出したので用触山の名がつけられた。御神徳:火の神様である炊事キッチンの守り神である。火の神信仰は火難を免れ病難を防ぐ。祭日:2月28日、9月28日、12月28日
・願勝寺(車町50)
・新:双体道祖神
・金剛院(八千代町17)
・石:家:道祖神
・秋葉山常夜灯(馬場町)
中町交差点に市・有民・中町秋葉山常夜灯、上部は木造で彫りが見事、下部は石造、・赤鳥居:コンクリート製、
・山田長政像(宮ケ崎町100)
馬場町は伝山田長政屋敷跡といわれる。
・二瀬川神社(馬場町65)
・石灯籠(2基):明治四年、・手洗石:古そうで年号等もありそうだが見えない位置に安置されていて判読不能。
・説明版:二瀬川神社、静岡市葵区馬場町65番地、祭神名:保食神うけもちの神、多紀理比賣神たぎりひめの神、例祭日:9月15日、社殿工作物:本殿3.3平方m、拝殿6.6平方m、境内地:132平方m、氏子戸数297戸、神職名:宮司:鈴木巌夫、禰宜:鈴木哲夫、責任役員名:小川保、鍋田治夫、由緒:創建年月不詳、昭和20年6月の戦災により焼失、昭和25年9月都市計画区画整理により現在地に移転し、以前120坪の地が40坪に削減され、その境内地に町内会館を建設したため実質は更に三分の一となって、極めて不遇な道を経過した神社といえる。静岡県神社庁神社等級規定13等級社である。年間スケジュール:祭旦祭:1月1日、初午祭:2月2の午の日(二の午祭)、夏祭:5月15日、例祭:9月15日、神輿清祓祭:例祭前後の土曜又は日曜日、
・報土寺(宮ケ崎町110)
・石塔:新:南無阿弥陀仏、・新:六地蔵(杉村隆風)、・新:無縁萬霊之塔、
・石碑:新:養国寺慰霊之碑 平成十九年、説明版:報土寺の末寺で安翁山丹龍院養国寺という浄土宗の寺が本通7丁目74番地にありました。開基は寛正6年(1466)で開山は松漣社貞誉王山上人還阿和尚であります。その後は報土寺の末寺となり歴代の当山住職が兼務住職となり、本通りの人たちと供に養国寺を護持してきましたが、昭和20年6月19日の静岡大空襲により堂宇すべて廃墟と期しました。その後、報土寺が戦後復興を進めていく中、昭和27年、養国寺は本寺である報土寺に合併されることとなりました。開基よりおよそ550年、養国寺の歴代住職をはじめ信徒の方々、本通り7丁目の方々、その他養国寺の護持の為にご協力を頂いた多くの善男善女の方々に心より御礼申し上げ、ここに慰霊の碑を建立致します。
平成19年8月、報土寺住職 泰誉博隆
・石碑:新:南無阿弥陀仏 大正十余年、説明版:経に曰く至心信楽即得往生~~~以下略~~~
~~~大正十余年
・新:冷泉為和の歌碑:冷泉為和の歌碑についての由来:報土寺の本堂前に戦国時代宮廷歌壇の第一人者冷泉為和の歌碑が建てられた。為和は歌聖藤原定家の直系冷泉家第7代の当主である。当時応仁の乱(1467~77)後の荒廃した京都を逃れて駿府に流寓した公家殿上人はかなりの数にのぼっていた。権大納言冷泉為和もそうした中の一人であった。その為和が駿府滞在中我が報土寺において歌会を催すこと9回、11首の和歌を詠んでいる。それは、「今川為和集」の中に歴然としるされている。報土寺境内にある歌碑に彫られた和歌はその中の天文12年(1543)5月2日の歌会の折りのもので、
松契還年
代々かけて 軒のかわらに むす苔も 緑あらそふ 松の気だかさ (為和)
この歌の題の「還年」は長寿をいうので軒の瓦が苔むすといえば1年や2年のことではない。何代という長い年月を栄え続けてきた証で、それと競うように枝を伸ばした松の緑の気品のある美しさを讃えて長寿を祝う歌とした手腕はさすがである。(文責 長倉智恵雄)
・一加番稲荷神社(鷹匠1丁目8)
・石鳥居:昭和三十七年五月、・石稲荷2:昭和五十一年、石柵:昭和五十八年、・手洗石:昭和五十六年、・コンクリ石塔:昭和壬子二月、・石碑:神社名:新、
・説明版:当神社の御祭神は、保食大神ウケモモノオオカミ、御別名を豊宇気比売神トヨウケヒメノカミ、また食稲霊神ウカノタマノカミと申し上げ、稲、五穀の御霊神と尊まれ、衣食住の神、商売繁盛、厄除開運、無病息災、延命長寿の守護神として広く信仰されている神である。
当社鎮座の由来は寛永八年(1631)駿府城主駿河大納言忠長卿(二代将軍秀忠公の第3子)が三代将軍家光(兄)の勘気を受けて甲斐に蟄居の後は、幕府は駿河を直轄領とし、城主を置かず重臣の内から駿府城代を任命して庶政を綜理せしめ、城代を輔けて城外の守衛に当たらせるために在番一年の役として加番を勤番させることとし、紺屋町に一加番屋敷を設けた。(これを紺屋町加番或は町口加番屋敷という)初代一加番に信州飯田城主五万五千石脇坂淡路守安元が寛永九年(1632)12月に仰せ付けられ着任した。この加番開設にあたり3200余坪の屋敷内の浄地を選び社殿を建て寛永十年(1633)山城国伏見稲荷神社の分霊を勧請し、駿府一加番の守護神として鎮斎したのが当神社の創祀と伝えられている。慶安四年(1651)由井正雪の乱があり、一加番は府城に近い横内御門前(現在の鷹匠一丁目)に移され、これに伴い当稲荷神社も新屋敷内に遷宮された。斯くて創祀以来文久元年(1861)に至る迄約230年間歴代の加番は折々に鳥居、燈籠等を献納し、年々の祭祀を厳修して、崇敬の誠をつくしてきた。
明治維新に至り加番屋敷廃邸後は、鷹匠町一丁目の産土神として、明治11年政府より存置が許可されて、一般市民の崇敬の神社となった。昭和20年6月戦災により社殿、工作物悉く焼失した。戦後氏子の奉賛により復興し、地域の区画も整理されて面目を一新し、当神社の信仰は市の内外に広まるに至った。
祭典:例祭5月5日、歳旦祭:1月1日、節分会:2月3日、秋祭:11月25日。
昭和63年5月 奉納:松浦元男
・二加番稲荷神社(西草深町4)
もとは駿府城の警護用番所でもっと敷地も広く馬場等もあったが、今はそこの祠があった部分のみに神社がある。周辺は住宅地でキリスト教会やNHKビルがある。そこもかつては敷地内だったはず。
・村本喜代作先生明徳碑文:翁は西草深町520世帯の町内会長として20年にわたる長き間、社会公共のため奉仕せられた功績は甚大である。当二加番稲荷神社は戦災により灰燼化し瓦礫の中に樹木を植え社殿を再建し自ら責任役員となり神社を中心に民福をはかり明朗な社会環境造成に盡くす。又政教社雨声会を起し政治経済文学史話等の講演を行うこと実に250余回、其の間先生の薫陶を受けた方の中には名政治家も現はる。ここに村本喜代作先生を後世に伝えるため西草深町内会神社総代会雨声会の有志相謀り明徳碑を建立する。昭和55年3月、~以下略~
・手洗石:文化(五)九年(戌辰)壬申歳、・神社名石碑:昭和四十三年、・石灯籠:天保十五甲辰、・石鳥居:昭和四十六年、・石柵:昭和四十八年、・?石灯籠の一部:元文四巳未、・?石塔:崩れて成れの果て、
・説明版:二加番稲荷神社:祭神三社:豊受毘賣命トヨウケヒメノミコト穀物の神 商業あきないの神、猿田彦命サルタヒコノミコトお祓いの神、天鈿女命アメノウヅメノミコト神楽の創始芸能の神、由緒:駿府城は寛永8年以後は城主を置かず「城代」によって統治され、城外守衛のため「加番」という役が置かれた。当所は二加番屋敷の跡で、その守護神として稲荷神社が祀られた。当社を鷹森稲荷と称されたのは、この附近を流れた安倍川のほとりに鷹が集った森があった故という。一加番(鷹匠1丁目)三加番にも夫々稲荷神社が奉祭されている。明治維新後は西草深町の産土神として遠近より崇敬されて今日に至った。加番屋敷には馬場、的場、火の見櫓などがあり、その略図を裏面に記した。歳旦祭 1月1日 春祭 初午 春分の日 秋祭 秋分の日
・裏面:二加番屋敷略図:外堀に面した現在はNHK静岡放送局から付近一帯の住宅地も含む広大な屋敷であることが分かる。外堀側77間(138.6m)、奥行き42間(75.6m)、面積10478.16平方m、3175坪。
・三加番稲荷神社(東草深町11)
・石碑:神社名:昭和三十八年九月、・石柵:平成九年、・石鳥居:安政六巳未二月初午、旗指石:奉献安藤杢(木の下は工ではなく立つ)之助源有(有るの下は月ではなく且つ)剛、・手洗石:安政(正の下に久)□□□二月、・手洗石:?、・石塔:寄進~~~、・石(埋)、・礎石2?、・石燈籠2:、・倒れた石燈籠:稲荷大明神 廣舟(止の下は舟) 文化三丙寅三月初午、
・説明版:祭神:保食大神ウケモチノオオカミ、祭日:春祭:春分の日、秋祭:秋分の日、由緒:寛永八年(1631)に駿府城主徳川忠長が将軍の勘気に触れ蟄居を命ぜられての後は駿河国は幕府の直轄領となり、駿府城には城主を置かず城代定番が勤める番城となり定番の下に小大名または旗本の中から加番を勤番せしめ城外の警備に当たらしめた。慶安四年(1651)に由井正雪の反乱があっての後は、従来の一、二加番に加えて三加番が増設され、東草深にその屋敷を設けると共に邸内の守護神として、この三加番稲荷神社を鎮祭した。代々の加番は深く崇敬して毎年二月初午に盛大な祭典を行い、また石燈籠鳥居等も数多く奉納された。
明治維新に至り加番屋敷廃邸後は、東草深三ヶ町の鎮守となり、明治11年3月政府公認の神社として存置を許可された。後に水落町二丁目も氏子に加わり一般町家、遠近の人々から深く信仰されるに至った。
御神徳:保食大神は伊勢の外宮に奉祀する豊受大神と御同神で人間生活に一番必要な食糧と衣料をお恵み下さる神である。古歌に「朝夕の箸とるごとに保食の神の恵みを思え世の人とあう」また福徳円満の神、商売繁盛の神として最も信仰される神である。
・草深界隈の古い洋館類、キリスト教会等(西草深町、東草深町)
‘13現在、(西草深町15番)西草深眼科(かつての中島医院)が洋館の趣をとどめている。他にもあったのだがだいぶ減少した。教会も現代建築のビルに改築され古式ゆかしさは消失した。
静岡英和女学院(西草深町8)はねむの木学園創設者:宮城まり子出身校である。
クラシック音楽愛好家には一時期全国的に知られていたのが青島ホール(西草深町16‐3) である。
・西草深公園(西草深町27)
・説明版:西草深と徳川慶喜公:草深町は駿府九十六ヶ町の一つで、現在の西草深公園の東側に、二筋の通りに面して一画を占めていました。明治6年(1873)に一帯の武家屋敷を含めて西草深町となり、昭和44年に御器屋町ゴキヤチョウなどを併せて現在に至っています。駿府城に近い草深町の近辺には慶安4年(1651)に駿府城の警護や城下の治安維持にあたった加番の一つ二加番や与力、同心などの武家屋敷が配置されていました。草深地区には江戸時代初期に徳川家康公に仕えた儒者、林羅山の屋敷があり、また明治維新期には静岡学問所頭ガクモンジョガシラであった向山黄村ムコウヤマコウソンをはじめとする学問所の著名な学者が多数居住していました。西草深公園には浅間神社の社家シャケの屋敷があり、明治2年(1869)6月に静岡藩主となった徳川家達イエサト公が社家新宮兵部シングウヒョウブの屋敷に移り住みました。
徳川幕府第15代将軍徳川慶喜公は、大政奉還の後、慶應4年(1868)2月から謹慎生活に入り、同年7月に駿府の宝台院に移り住みました。宝台院での謹慎生活が解かれた慶喜公は、明治2年(1869)に紺屋町コウヤマチの元駿府代官屋敷に移り、更に明治21年には西草深町に屋敷を構えましたが、東京に戻る明治30年まで政治の世界を離れ、一市民として過ごしました。静岡での慶喜公は、狩りや写真を好み、油絵をたしなみ、明治10年代から自転車を購入して市内を乗り回って市民の話題になるなど、多種多様な趣味と共に西洋的な生活を謳歌した当時の最先端を行く文化人でもありました。中でも静岡で修得した写真撮影の技術から生まれた作品は、各地の風景、生活ぶりを伝える貴重な歴史資料ともなっています。慶喜公が、東京に戻った後の徳川邸は葵ホテルとなり、更に明治37年には日露戦争の捕虜収容所の一つとして使われましたが、同38年に施設内から出火し焼失してしまいました。
・説明版:万葉歌碑:焼津邊 吾去鹿歯 駿河奈流 阿倍乃市道尓 相之兒等羽裳
春日蔵首老 焼き津辺にわが行きしかば駿河なる安倍の市道に逢いし児らはも
万葉集は日本最古の歌集で奈良時代
~~~不明、
昭和36年
*写真不鮮明で判読困難
以下は、インターネット検索「万葉集巻3、れんだいこ」より引用
「万葉集、巻3、No.284、春日蔵首老かすがのくらびとおゆ、作歌
焼き津辺=静岡県焼津市辺り、阿倍=静岡市安倍、安倍川の安倍、市道=イチジ、市場が開かれていた道、焼津方面に赴いた際、安倍の市で出会った娘たちを思い出して懐かしがっている歌。これを男女が市に集まって乱舞した、いわゆる歌垣の際の思い出ととってもよかろうが、そうとらなくても単純に美しく楽しげだった娘らを思い出しての歌として一向に差支えない。」
私見:この短歌から静岡市(安倍の市)がすでに奈良時代に賑わっていたことが分かる。
・石鳥居
浅間神社前、麻機街道と長谷通りの分岐点
・浅間神社(静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町102-1)
・交番裏の賤機山を上るとすぐ賤機山古墳がある。もう少し上に麓山神社がある。さらに上に一本松・5世紀の古墳がある。さらに上ると浅間山山頂(△140m)で舗装路はなくなり、あとは山道となる。その先に空堀(地獄谷)があり、さらに先に賤機山城址(△173m)と光明地蔵となる。
浅間神社境内遺跡跡。国・重文・浅間神社社殿。石造物でも石灯籠等、市内最古級のものが多い。
国・登・遍界山不去来庵本堂。
・西蔵寺(片羽町79)
・三界萬霊等、・庚申塔、・地蔵、・新:観音、・手洗い石、・新:灯篭、
・元三大師延命地蔵(安倍町23)
・地蔵:
・瑞光寺(安西1丁目100‐1)
・石塔:文正夂(政)十三年庚寅八月、・?観音:元文五庚申、・板碑:山梨易司翁彰功碑 大正八年、・板碑:佐久間翁叟先生碑、・新:有縁無縁三界萬霊、・お花塚 石州流生花家元~~昭和十三年、・如来(4):片足膝立ち座位、・地蔵(4)、・地蔵、・同一様式の観音約80基(三十三所観音3つ分で不足分は消失か、いくつかには二十六番等の番号が読み取れる)、
*文政の政を正夂と刻字してあるのか?
・然正院(安西1丁目103)
・新:六地蔵、・新:水子供養塔(2)、
・末広中(末広町)
かつて高等女学校があった。
・神明宮(神明町54)
・木鳥居、・常夜灯(2):昭和十五年、・石柵:昭和十五年、・狛犬(2):昭和十五年、・神社名碑:平成二年、
2014年03月22日
キリシタン燈籠疑問説、しかし保存してほしい
・キリシタン灯籠説について疑問を呈したいが、その灯籠は文化財として大切に保存してほしい
2014 2/8
キリシタン灯籠は織部型灯籠の竿部分に描かれたキリスト者または十字架を隠れキリシタンが信仰していたという。ただこの説は大正時代から昭和初期にブームを起こしたもので、なぜ禁教を解かれた明治期に全く存在が知られなかったか不思議です。
例えば京都桂離宮には7つ存在するという。これらは桂離宮を作った者の知り合いのキリスト者を供養するために作ったという。まあそれはそれで、キリスト教信仰者への供養があったのかもしれないという説もあるとうかがっておきましょう。
日本全国にはかなりの数のキリシタン灯籠があるらしい。ためしにネットで調べただけでも次々出てくる。桂離宮もそうだ。いったいいくつあるのだろう。数百単位ではなく、もしかすると千単位あるのかもしれない。これだけ作られたなら相当な数の隠れキリシタンがいたはずです。または本人が信仰者でなくとも、信仰者を供養する人が後を絶たなかったことになります。信仰の自由が認められた現代日本でのキリスト教徒は人口の0.6%だそうだ。ましてや江戸時代の禁教化の中でどれだけの信者がいたのだろうか。その人たちが明治期、いや大正期に入って、あの灯篭を先祖伝来拝んできたとでもいう話が起こったのなら肯定しますが、そのような信者側からの報告はないようで、以下の話を見つけました。
*ネットサイト「街道ひとり歩る記-楽しんでこそ人生!!」より、(そのまま引用)
以下は、日本キリスト教大辞典「織部灯篭とキリシタン宗門」松田毅一より
「~大正12(1923)年頃からで、静岡の某氏が宝台院の一基の下部に人物像があることに注目して、同地の教会のフランス人司祭に見せたところ、カトリックの聖人像で、服装はローマの法服であると認定したと言う。」
以下は簡単にまとめて引用します。
「これ以後キリシタン灯籠ブームが起きたらしい。昭和23(1948)年に西村貞は「キリシタンと茶道」で織部灯篭の一部をキリシタン宗門と関係づけようと論証に努めた。しかし今日に至るも立証したものはいない。古田織部もキリシタンではない。灯篭のデザインは中世以前からの仏教関係の古い石造文化財の影響を受けている。記入されている記号は供養塔、墓標、庚申塔に刻まれているものが刻印されているようだ。」以上といったところです。
日本のキリスト教関係者が否定するのだから、日本の隠れキリシタン、または近代のキリスト教徒もキリシタン灯篭を信仰の対象にしていないようです。ということはキリシタン灯篭を発見しては騒いでいた人たちは、まったくキリスト教とは関係ない人たちだったのかな、なんとなくデザインがキリスト教っぽいからということですか? 隠れキリシタンが信仰していたという話は、いったい誰が言い出したのでしょうか? 分かりませんが、なぜその当人は地元のキリスト教徒を調査しなかったのでしょうか。キリシタン灯篭を、信仰してきたという信者またはその子孫の話を見つけられない限り、肯定しようがありません。といって、100%否定しきることもできませんので、否定傾向にあるあいまいな不明なままです。なお隠れキリシタンが伝えてきた信仰対象物はあるようですが、灯篭とは全く関係ないようです。
キャッチコピー「信者もいないのにキリシタン灯篭とはこれいかに?」
ただ別の視点で考えると、歴史学や考古学って、けっこうあいまいに進むんだなあと思います。以前、考古学においてゴッドハンド神の手と称される天才民間考古学者が一躍注目を浴び、彼の手による発掘でいくつもの石器遺跡が文化財として認定されましたが、いんちきだったことがわかり、あっさり、いくつもの指定遺跡が解除されるという、嘘みたいな本当の話がありました。また欧州では100年ほど前の話かなもっと前かもしれませんが、類人猿や原人の人骨を巡ってのいんちきか生物学的一大発見か争われ、いんちきだったことが証明されるという大失態があったそうです。
そうそう私がこの文章を書いたわけは、単に否定したいからではなく、その後のことを悲しく思うからです。
私がブログで静岡市の「安倍街道」を書いてアップさせたのですが、その中で「井宮町、瑞龍寺のキリシタン灯篭」の項目でキリシタン灯篭を否定する旨まで記入しました。ただこの「安倍街道」記事の内容は不十分で中途半端なまま、いつか調べるための調査地点や概要程度の下書きのままアップしてありました。そこで今回安倍街道を再調査し、ブログ内容の充実を図ることにしました。そこで2013年12月に瑞龍寺に再度行ったらば悲しくなりました。
寺の前には、井宮や寺についてのハイキングコース標識、案内看板があり、瑞龍寺では3つ紹介されていました。1、旭(朝日)姫の墓、2、時雨塚の碑、3、キリシタン灯篭、です。1,2の2つについては説明版と矢印の行き先表示がありましたが、3は矢印が見つからないので、自力で、キリシタン灯篭を探しました。
多分これがキリシタン灯篭だったはずのものに行き当たりました。説明版もありません。しかし灯篭は各部がずれていて一部破損している始末。
私がこの灯篭を矢面に立たせて否定したからこんな姿になったのかもしれないと思うと、悲しかったです。私としてはキリシタン灯篭説には疑問を呈し半ば否定したいですが、破壊したり撤去してほしいと言ったつもりはありません。キリシタン灯篭といわれているものは今まで通り説明版もつけて大切に保存されるべきです。説明版に一言最後に否定説もある旨を記入すればよいでしょう。全国にある指定文化財になっているものは、今後の歴史学界の動向を注目し、あまりに否定説が強まれば、検討対象にして、指定解除されればよいでしょう。ただし解除されたから、粗末に扱われ破損撤去されることは悲しいことです。その後も所有者等が大切に保存に努めてもらいたいし、かつてキリシタン灯篭と呼ばれていた織部型灯篭だという説明板ぐらいつけておくとよいでしょう。それはそれで歴史観光資料としての価値があるでしょう。
なお隠れキリシタンが実在していた長崎県の各地方には、彼らが信仰対象物にしていたものが残っているようです。長崎県にも織部型灯篭はあると思うのですが、この形式の灯篭を信仰対象物にしていたというものはないようです。
ちなみにマリア観音も否定されるでしょう。静岡市内では用宗の用舟城跡の観音堂にマリア観音がありますが、隠れキリシタンの信者の子孫の証言といったものはあるのでしょうか。地域住民の観音様信仰はあるのでしょうが、キリスト教関係の信仰として明治時代以前からあるという口承等がなければ否定に傾くでしょう。新聞報道された内容では、地元民から観音信仰はあって日常お参りしているがマリア信仰といったものは聞いたことがないという話だそうです。マリア観音と断定?または推定した方々は、マリアとして信仰している人たちを探したのでしょうか?これもキリスト教徒とは関係なくても、地域の文化財で民間信仰の対象物として末永く大切に保存されることを望みます。説明板もついているとありがたいです。なお長崎県には隠れキリシタンが信仰していたマリア観音が実在しているそうですが、こちらは隠れキリシタンの存在は確実で、きっと信者や子孫の口承等もあるのでしょう。
キリシタン灯篭を認定するには、織部型灯篭のデザインだけではなく、地域周辺にかつて存在していたはずの隠れキリシタンの存在を突き止め、その子孫からの口承証言等を取らねばならないはずです。それがないことに驚きます。
ちなみに静岡市葵区、宝台院のホームページを調べると、徳川家康関係の宝物(阿弥陀如来立像、家康公の自画像、真の太刀、家康公筆「安元御賀記手習」)、三代将軍家光公筆「遠山月」二代将軍秀忠の生母・西郷の局の墓、徳川慶喜公謹慎之地、かくし坊の辞世があり、その中にキリシタン灯篭もある。説明文:「キリシタン灯篭:茶人として有名な古田織部が制作し駿府城へ奉納、徳川家康公の侍女・ジュリアおたあが信拝したという灯篭です。この灯篭は城内より静岡奉行所を経て宝台院へ移されました。」とある。
ジュリアおたあをウィキペディアで調べると生涯概略の他、文章末に「~なお、駿府時代には灯篭を作らせ瞑想していたと言い伝えられており、そのキリシタン灯篭は、現在は宝台院に移されている。」と書かれている。
これらはいかなることでしょう。日本最初のキリシタン灯篭発見が1923(大正12)年とすると、ジュリアおたあ信拝説はそれ以後と思われますが、いったいどういう証拠があるのでしょうか。分かりません。ただジュリアおたあや宝台院の業績は素晴らしいものと思いますので、そこは肯定します。また宝台院の織部型灯篭も価値あるものと思います。それが本当にキリシタンが信仰対象にしたものか証拠を出してほしいのです。それはキリシタン燈籠説を出した人たちの責任であって、宝台院やジュリアおたあ、瑞龍寺や織部型燈籠の責任ではないのですが。
2014 2/8
キリシタン灯籠は織部型灯籠の竿部分に描かれたキリスト者または十字架を隠れキリシタンが信仰していたという。ただこの説は大正時代から昭和初期にブームを起こしたもので、なぜ禁教を解かれた明治期に全く存在が知られなかったか不思議です。
例えば京都桂離宮には7つ存在するという。これらは桂離宮を作った者の知り合いのキリスト者を供養するために作ったという。まあそれはそれで、キリスト教信仰者への供養があったのかもしれないという説もあるとうかがっておきましょう。
日本全国にはかなりの数のキリシタン灯籠があるらしい。ためしにネットで調べただけでも次々出てくる。桂離宮もそうだ。いったいいくつあるのだろう。数百単位ではなく、もしかすると千単位あるのかもしれない。これだけ作られたなら相当な数の隠れキリシタンがいたはずです。または本人が信仰者でなくとも、信仰者を供養する人が後を絶たなかったことになります。信仰の自由が認められた現代日本でのキリスト教徒は人口の0.6%だそうだ。ましてや江戸時代の禁教化の中でどれだけの信者がいたのだろうか。その人たちが明治期、いや大正期に入って、あの灯篭を先祖伝来拝んできたとでもいう話が起こったのなら肯定しますが、そのような信者側からの報告はないようで、以下の話を見つけました。
*ネットサイト「街道ひとり歩る記-楽しんでこそ人生!!」より、(そのまま引用)
以下は、日本キリスト教大辞典「織部灯篭とキリシタン宗門」松田毅一より
「~大正12(1923)年頃からで、静岡の某氏が宝台院の一基の下部に人物像があることに注目して、同地の教会のフランス人司祭に見せたところ、カトリックの聖人像で、服装はローマの法服であると認定したと言う。」
以下は簡単にまとめて引用します。
「これ以後キリシタン灯籠ブームが起きたらしい。昭和23(1948)年に西村貞は「キリシタンと茶道」で織部灯篭の一部をキリシタン宗門と関係づけようと論証に努めた。しかし今日に至るも立証したものはいない。古田織部もキリシタンではない。灯篭のデザインは中世以前からの仏教関係の古い石造文化財の影響を受けている。記入されている記号は供養塔、墓標、庚申塔に刻まれているものが刻印されているようだ。」以上といったところです。
日本のキリスト教関係者が否定するのだから、日本の隠れキリシタン、または近代のキリスト教徒もキリシタン灯篭を信仰の対象にしていないようです。ということはキリシタン灯篭を発見しては騒いでいた人たちは、まったくキリスト教とは関係ない人たちだったのかな、なんとなくデザインがキリスト教っぽいからということですか? 隠れキリシタンが信仰していたという話は、いったい誰が言い出したのでしょうか? 分かりませんが、なぜその当人は地元のキリスト教徒を調査しなかったのでしょうか。キリシタン灯篭を、信仰してきたという信者またはその子孫の話を見つけられない限り、肯定しようがありません。といって、100%否定しきることもできませんので、否定傾向にあるあいまいな不明なままです。なお隠れキリシタンが伝えてきた信仰対象物はあるようですが、灯篭とは全く関係ないようです。
キャッチコピー「信者もいないのにキリシタン灯篭とはこれいかに?」
ただ別の視点で考えると、歴史学や考古学って、けっこうあいまいに進むんだなあと思います。以前、考古学においてゴッドハンド神の手と称される天才民間考古学者が一躍注目を浴び、彼の手による発掘でいくつもの石器遺跡が文化財として認定されましたが、いんちきだったことがわかり、あっさり、いくつもの指定遺跡が解除されるという、嘘みたいな本当の話がありました。また欧州では100年ほど前の話かなもっと前かもしれませんが、類人猿や原人の人骨を巡ってのいんちきか生物学的一大発見か争われ、いんちきだったことが証明されるという大失態があったそうです。
そうそう私がこの文章を書いたわけは、単に否定したいからではなく、その後のことを悲しく思うからです。
私がブログで静岡市の「安倍街道」を書いてアップさせたのですが、その中で「井宮町、瑞龍寺のキリシタン灯篭」の項目でキリシタン灯篭を否定する旨まで記入しました。ただこの「安倍街道」記事の内容は不十分で中途半端なまま、いつか調べるための調査地点や概要程度の下書きのままアップしてありました。そこで今回安倍街道を再調査し、ブログ内容の充実を図ることにしました。そこで2013年12月に瑞龍寺に再度行ったらば悲しくなりました。
寺の前には、井宮や寺についてのハイキングコース標識、案内看板があり、瑞龍寺では3つ紹介されていました。1、旭(朝日)姫の墓、2、時雨塚の碑、3、キリシタン灯篭、です。1,2の2つについては説明版と矢印の行き先表示がありましたが、3は矢印が見つからないので、自力で、キリシタン灯篭を探しました。
多分これがキリシタン灯篭だったはずのものに行き当たりました。説明版もありません。しかし灯篭は各部がずれていて一部破損している始末。
私がこの灯篭を矢面に立たせて否定したからこんな姿になったのかもしれないと思うと、悲しかったです。私としてはキリシタン灯篭説には疑問を呈し半ば否定したいですが、破壊したり撤去してほしいと言ったつもりはありません。キリシタン灯篭といわれているものは今まで通り説明版もつけて大切に保存されるべきです。説明版に一言最後に否定説もある旨を記入すればよいでしょう。全国にある指定文化財になっているものは、今後の歴史学界の動向を注目し、あまりに否定説が強まれば、検討対象にして、指定解除されればよいでしょう。ただし解除されたから、粗末に扱われ破損撤去されることは悲しいことです。その後も所有者等が大切に保存に努めてもらいたいし、かつてキリシタン灯篭と呼ばれていた織部型灯篭だという説明板ぐらいつけておくとよいでしょう。それはそれで歴史観光資料としての価値があるでしょう。
なお隠れキリシタンが実在していた長崎県の各地方には、彼らが信仰対象物にしていたものが残っているようです。長崎県にも織部型灯篭はあると思うのですが、この形式の灯篭を信仰対象物にしていたというものはないようです。
ちなみにマリア観音も否定されるでしょう。静岡市内では用宗の用舟城跡の観音堂にマリア観音がありますが、隠れキリシタンの信者の子孫の証言といったものはあるのでしょうか。地域住民の観音様信仰はあるのでしょうが、キリスト教関係の信仰として明治時代以前からあるという口承等がなければ否定に傾くでしょう。新聞報道された内容では、地元民から観音信仰はあって日常お参りしているがマリア信仰といったものは聞いたことがないという話だそうです。マリア観音と断定?または推定した方々は、マリアとして信仰している人たちを探したのでしょうか?これもキリスト教徒とは関係なくても、地域の文化財で民間信仰の対象物として末永く大切に保存されることを望みます。説明板もついているとありがたいです。なお長崎県には隠れキリシタンが信仰していたマリア観音が実在しているそうですが、こちらは隠れキリシタンの存在は確実で、きっと信者や子孫の口承等もあるのでしょう。
キリシタン灯篭を認定するには、織部型灯篭のデザインだけではなく、地域周辺にかつて存在していたはずの隠れキリシタンの存在を突き止め、その子孫からの口承証言等を取らねばならないはずです。それがないことに驚きます。
ちなみに静岡市葵区、宝台院のホームページを調べると、徳川家康関係の宝物(阿弥陀如来立像、家康公の自画像、真の太刀、家康公筆「安元御賀記手習」)、三代将軍家光公筆「遠山月」二代将軍秀忠の生母・西郷の局の墓、徳川慶喜公謹慎之地、かくし坊の辞世があり、その中にキリシタン灯篭もある。説明文:「キリシタン灯篭:茶人として有名な古田織部が制作し駿府城へ奉納、徳川家康公の侍女・ジュリアおたあが信拝したという灯篭です。この灯篭は城内より静岡奉行所を経て宝台院へ移されました。」とある。
ジュリアおたあをウィキペディアで調べると生涯概略の他、文章末に「~なお、駿府時代には灯篭を作らせ瞑想していたと言い伝えられており、そのキリシタン灯篭は、現在は宝台院に移されている。」と書かれている。
これらはいかなることでしょう。日本最初のキリシタン灯篭発見が1923(大正12)年とすると、ジュリアおたあ信拝説はそれ以後と思われますが、いったいどういう証拠があるのでしょうか。分かりません。ただジュリアおたあや宝台院の業績は素晴らしいものと思いますので、そこは肯定します。また宝台院の織部型灯篭も価値あるものと思います。それが本当にキリシタンが信仰対象にしたものか証拠を出してほしいのです。それはキリシタン燈籠説を出した人たちの責任であって、宝台院やジュリアおたあ、瑞龍寺や織部型燈籠の責任ではないのですが。
2014年03月02日
古代官道:東海道、静岡市街
古代官道:東海道、静岡市街
(佐渡交差点または手越原交差点から清見寺へ)
・前説明
古代東海道は、静岡市駿河区手越の佐渡交差点、西之宮神社から東へまっすぐ清水区興津清見寺方向へ伸びるものと推定されている。なお静岡市教育委員会『曲金北遺跡調査報告書』では西宮神社ではなく、もっと南の的山を名の通りマトとしたと考えている。現実にそのライン上のJR東静岡駅と隣のグランシップの間の歩道地面下に古代の官道:東海道が出現した。なぜ東西をまっすぐ貫くかというと、古代の条里制により、東西南北に区画がなされ、その延長線上に官道も敷かれていたようだ。静岡市の地図で確認するならば、西は佐渡交差点の西之宮神社で、東は興津手前の盧崎神社(横砂本町29)イホサキ辺りに定規を当てるとよいだろう。無論JR東静岡駅とグランシップを通過するようにする。また曲金の軍神社や矢倉町の矢倉神社付近も通るだろう。ちなみに現在、古代の官道に沿って通れるわけではないので、現地を通りたい場合は付近を迂回することが多いはずである。
もう少し詳しく見るなら、手越の佐渡交差点または手越原交差点から今の国1に沿い東進し、安倍川で線路をクロスし駅南の南安倍三丁目に渡る。ここで線路に並行して通る道を東進する。途中宮本町の神明神社横を通過し、稲川の浅間神社横を通る。もしかするともう少し南の伊河麻神社の境内地が北に広ければ隣接していたかもしれない。曲金の軍神社の北辺をかすめグランシップと線路の間を東進する。線路沿いに東進し、栗原の神明神社北を通り草薙駅西の熊野神社南に達する。ここから直線道路を東へ進み草薙駅前を通過し七つ新屋の春日神社までまっすぐ東に進める。もしかするとこの東西直線道路は古代条里制の名残を残した道だろうか。ということは古代官道:東海道残存部の可能性がある。しかしこの道は明治期の地図には存在していないので、後世の近代に鉄道線路に平行するよう作られたようだ。期せずして古代の道路設計者と近代の鉄道や道路の設計者の思惑が偶然一致したようだ。しかしそういう風に作るのが合理的だという証拠なのだろう。
ここから東への道はないが、およそ新幹線ガードと一定の距離で並行するように東に向かい国1を渡り渋川に達すると、ここで新幹線に並行する道路が出現する。これも官道の名残か。はじめ狭かった道は新たに拡幅された広い東進する道になり、巴川を渡り清水東高前で道はなくなる。地図上ではここからさらに東進すると矢倉神社横の矢倉の辻に達し、神社北の中世北街道とされる庵原川に達する道に接続したはずである。中世北街道が古代官道東海道残存部と推定される。中世北街道も直進道路であり、庵原川に達する部分のみ現在曲線になるが、古代は直進すれば盧崎神社により近かったであろう。ここが曲線なのは土手が作られたためだろう。
・的山マトウヤマ、的山峠マトウトウゲ、マトヤマトウゲ
名のように的山を目指したという考えもあるようだ。
芹が谷から井尻へ山越えしていける道があり、この峠を的山峠という。
やなぎだ眼科医院(丸子芹が谷町9-1)を目指し、やなぎだ眼科医院から南の山あいの谷地に入っていく。谷地の農地に入っていくところに朽ちかけた「谷津峠↓←→的山峠」標識がある。谷地に入っていいのだが、この先の谷地の農地から峠のある山腹に取り付く所には標識はないので、住民に聞くしかない。最後の住宅も過ぎ農地だけになって川が広がって水を溜めている池みたいなところの2箇所過ぎたところを左に曲がり、川に架かる板橋を渡る。草刈もしていないので草だらけの斜面をモノラックのレール(索道)を横目に見つつ、「もとは道だなあ」と思いつつ約5分上ると、頂上に「井尻←的山峠→芹が谷」標識がある。頂上部の尾根は歩きやすく眺めもよい。井尻への下り道は草もなく快適である。5分下ると平坦な車道に接続する。ここに「井尻峠←→的山峠」標識がある。車道へ出ず細い野良道をさらに行くと井尻の集落内に出る。ここにも「井尻峠←→的山峠」標識がある。
・佐渡交差点、西之宮神社(丸子)サワタリ
古代官道はこの西之宮神社から東は清見寺方向、横砂の盧崎神社イホサキにまっすぐ突き当たるようだ。佐渡山は古墳群で、縄文や弥生期からの遺跡が出土する。
創建不詳、再建明和三年。「遷宮記念碑 昭和60年」、石鳥居「明治22年」、石灯籠、「庚申塔」3「大正九」「昭和55」、今の国1と近世東海道が丸子方面へ分岐する所。
・福泉寺(手越14)
石塔類。徳川秀忠の付き人の墓もあるなど由緒がある。
・手越原交差点
長田西中学校のある今の国1と近世東海道が手越及び市中へ向かう分岐点
・国1:佐渡交差点、手越原交差点から安倍川を渡る駿河大橋手前まで
国1は直線状に西から東にむかっており、もしかすると古代東海道に一致するのではと思う。駿河大橋で安倍川を渡るとき道がやや北向きになるので、古代東海道は安倍川で南のJR線路をまたぎ駅南の南安倍3丁目に至るようだ。ただし安倍川がここを通るようになったのは、家康が駿府に隠居し、薩摩土手を築いてからなので、中世までは藁科川が流れていたし、安倍川はこれより東を幾筋かの分流になって流れていたはずである。
・南安倍3丁目、八幡神社(南安倍1丁目8)
ここからJR線路と南のカネボウ通りの間を東に向かえばよいが、正確なルートは不明だし、この辺りで古代東海道をしのべるものはない。
ただ線路北にすぐ見える1丁目の八幡神社がある。(古代とは関係なさそうだが周辺紹介として取り上げる。これからもそうしていく。)中世の源氏関係者により創建されたと推定される。地蔵堂:地蔵「昭和二十八年」、祠、板碑、石塔、与九郎稲荷の由来、義僕八助施義の碑:八助は暇を出されても主家に使え再興に尽くし評判を呼んだ。
線路南を東へ向かう。
・神明神社(宮本町9)
この神明神社の付近を東西に官道は貫いていたと思われる。
創建不詳だが延暦三(784)年再建で1200年以上続くと思われる。手洗石「文化十一」、庚申塔2基「明治十三」「天保十一」、板碑、石塔類。
・聞信寺(宮本町11) (周辺紹介)
山門、庭、石塔、墓といったものはなく、モダンなというかビルそのものである。寺とは思えない。
・蓮久寺(南安倍1丁目8) (周辺紹介)
山門、庭、墓といったものはなく、街中の狭い1軒屋に見えるが、寺名の石碑が出ていて判別できる。
・兵庫浜地蔵尊(黒金町29) (周辺紹介)
元は南安東にあったがここに移転された。悲しい母子伝説がある。川を汚してはならぬ決まりだが、汚している妊婦がいて、とがめられ切り殺された。その妊婦とお腹の子を供養したものである。句碑、板碑、地蔵10基。
・山王寺(馬淵3丁目17) (周辺紹介)
石塔8基:江戸期、地蔵。道元と老翁の問答像。
・津島神社(馬淵3丁目15) (周辺紹介)
創建不詳、再建文化二年、樹木:樹齢300年以上、手洗石・石鳥居・石灯籠:近代。
・伊河麻神社(稲川1丁目10)
創建:白鳳四年、手洗石「寛政十二」、樹木:1本、800年以上?。北辺りを官道が通っていたかも。
・崇福寺鯖大師(稲川1丁目3) (周辺紹介)
古い石塔類。
・千勝浅間神社(稲川1丁目2)
創建不詳。狛犬(市指定文化財)「正和二」:直接見られない、境内にある狛犬は近代の物。手洗石:さざれ石で平安鎌倉期推定。この神社の北か南を官道は通っていたはず。
・軍神社(曲金2丁目7)
日本武尊伝説があり、ここで東征のおり戦勝祈願したという。樹木:樹齢800年以上?。石塔類:近代、板碑。
もしかすると北を通る線路南の江戸時代東海道は官道と一致するのかも。神社は古代官道の脇にあり、東征軍の陣か休憩地か。横田駅家との関連性だ取沙汰される。横田駅家だったかもしれない。
・法蔵寺(曲金2丁目7) (周辺紹介)
石塔類多し、「背くらべ」作詞者海野厚墓、千日地蔵、他いくつか、平澤観音道道標。近くに梶原一族の馬頭観音。
・龍泉寺(曲金2丁目8) (周辺紹介)
石塔。
・曲金北遺跡、JR東静岡駅・グランシップ間歩道、古代の官道:東海道(曲金6丁目8)
JR東静岡駅南口からグランシップに向かう歩道に説明看板あり。道幅9mの歩道が古代官道の幅を示し、周囲の植え込みが側溝を表すよう、分かりやすく歩道が作られている。官道は地下に保存されている。道はほぼ東西にまっすぐで歴史学者等の推定どおり発掘された。官道はまっすぐ東に向かうようだが、そのものずばりの道が現在無いので付近を東進する。
・神明神社(栗原276) (周辺紹介)
手洗石「萬延元年」、石鳥居・狛犬・祠:近代。
・江戸時代の東海道記念標識(栗原38) (周辺紹介)
線路の地下ガード手前にある。本来は踏み切りで向こうへ越すのが正しいのだろうが、少し位置を変えて地下ガードでくぐれるようにした。
・津島神社(中吉田41-10) (周辺紹介)
創建不詳、修造文政六(1823)、樹木1本:樹齢200年、手洗石「天保六」、常夜灯の脚「文政六」、石鳥居「」平成七」、「東源台小学校開校記念 平成七」、「やぶきた茶発祥地記念碑」。石灯籠:近代。
・普済寺(中吉田33) (周辺紹介)
石塔類:「庚申塔」など。
・東光寺(清水区谷田9) (周辺紹介)
石塔類、江戸期東海道に面する。
・谷田宮の後公園、熊野三柱神社、古墳(谷田26)
円墳がいくつかある。古代官道を見下ろす、または道から見上げられる位置にあったはず。
・鳳林寺(中之郷101) (周辺紹介)
石塔類:江戸期。
・桜井戸、桜井戸灸(中之郷425) (周辺紹介)
庚申塔4基、水神、板碑。桜井戸は清泉湧出していたが安政地震で減水、周辺開墾で枯渇し消滅したが記念碑を建立。桜井戸灸は倒れた行者を介抱しお礼に灸を教えてもらい人気になった話である。
・熊野神社(中之郷430) (周辺紹介)
手洗石「弘化五」、市指定保存樹木:楠:樹齢700年以上。薬師如来、新駿河十二薬師第八番札所、閻魔大王。稲荷・祠・手洗石・石灯籠:近代。この神社南の道が官道残存部と考えられ、この道をまっすぐ東に向かう。
・ひょうたん塚公園、前方後円墳(草薙20)
古代官道を見下ろす、または道から見上げられる位置にあったはず。
・冷泉寺(草薙175-1) (周辺紹介)
石塔類:江戸期。
・草薙神社(草薙349)
日本武尊伝説。日本平で火責めに遭うが、草薙の剣で薙ぎ払い難を逃れたという。その草薙剣を納めたという。道からは数km離れている。
・妙盛寺(草薙1973) (周辺紹介)
石塔類。
・春日神社、八幡神社(七つ新屋一丁目7) (周辺紹介)
春日神社:創建慶長期、八幡神社:創建安土~江戸初期、市指定保存樹木:楠。板碑・石灯籠・手洗石:近代。
草薙の熊野神社前からこの神社までの東西を貫く道は官道残存部なのだろう。文化財級の道である。この先、東にはまっすぐ進む道はなくなるので、紆余曲折しながらも矢倉神社をめざす。ガイドにはこの北に見える新幹線高架ガードである。一定の距離で東に進めば間違いはない。
・八幡神社(吉川43) (周辺紹介)
本来は吉川館にあった氏神だが、当地に移転した。創建不詳、市指定保存樹林、石灯籠「文化三」、日待ち太鼓保存会、板碑、境内の2/3は線路で消失。市地域登録文化財(石造物)第1号・旧鳥居・寛政元(1789)吉川氏の由来等のことを書き付ける。昭和59年に書写された石鳥居が現在建つ。
静鉄線狐ヶ崎駅裏にある。駅前が江戸期東海道であり、吉川という地名がいかに南北に長いか分かる。ここが吉川の南端である。岩国城主の大名吉川氏は参勤交代の度にこの神社に参詣し寄付をしていったといわれる。かつては境内はもっと広かったが、線路や駅舎にとられたという。かつて吉川氏というスポンサーがいたからなのか羽振りがよかったのだろう。地域が広いのもそのためか。
・達磨寺(追分四丁目273) (周辺紹介)
達磨を陳列してある。
・乳母が池、一本松、延寿院(追分四丁目2311) (周辺紹介)
伝説の残る池と石塔、お堂がある。追分と国1を結ぶ広い新道脇に見える。延寿院管轄のお堂になるらしい。
・春日神社(追分三丁目5) (周辺紹介)
創建:伝鎌倉期、手洗石・祠・石灯籠:近代。隣は近世東海道に面する延寿院である。ここから近世東海道の追分羊羹本店の赤のれんが見える。
・珠林禅寺(渋川544) (周辺紹介)
ショッテケ地蔵:狐にだまされた愉快な伝説である。馬頭観音「明治十七」、六地蔵・新。
・国1を渡る官道
新幹線高架ガードと国1がクロスするすぐ東の北脇交差点を北に渡り東に曲がる道がある。これが官道残存部ではなかろうか。ちょうど新幹線高架ガードと並行していて今の都市計画の区画整理の思惑と一致し拡幅され、東に延伸することになり、結果として官道を甦らせることになったようだ。
・三島神社(馬淵3丁目15) (周辺紹介)
創建不詳、再建宝暦十三(1763)、伊豆一ノ宮三島大明神を遷した。石鳥居・石灯籠・狛犬・手洗石:近代。
・金剛法寺(渋川2丁目16) (周辺紹介)
石塔類:江戸期。寺の南を東西に通過する道路がたまたま官道残存部になるようだ。
・渋川館(渋川1丁目10) (周辺紹介)
中世豪族で梶原一族を討った駿河地侍一派の渋川氏の館の土塀の一部が残存している。 なんてことないちょいとした高さ5mの丘で茶畑になっているのだが、これは人為的に積み上げた土塀の跡のごく一部が残存したのである。説明看板はあるが、古びてまったく読めなくなっている。
・官道ルートを矢倉神社へ
官道は東に進みつつも徐々に北方向へ向かうというより、今の道が東に進むようでやや南へ曲がるというべきか。北脇新田から渋川にかけて新幹線ガードのすぐ南を平行して東をめざすのが、官道ルートに近いのだろう。金剛法寺のすぐ南の道を東に目指す。清水インター取り付け道路に出て清水東高前で直進不能となる。やや北の北街道へ出れば矢倉神社はすぐだ。ちなみに地図で確認すると、東高を貫いて直進すると矢倉神社にヒットするようだ。新幹線南の平行道路は官道ルートと一致するような気がする。高橋の辺りは以前この東西向きの道はまったく無かった。巴川河口付近の氾濫源のため、もっとも早く条里制が崩れ、官道も消失したのだろうか。
・矢倉神社(矢倉町5)
古くから神社があったことは確実である。日本武尊東征に関する伝説がある。軍の兵営地か武器庫だったという。この神社はこの周辺の要であった。
手洗石「文化五」、猿田彦大神、手洗石「紀元2600(昭和15)年」、石灯籠「大正九」「紀元2600年」、板碑多し、合祀される神多し。祠多し。
・矢倉の辻、古代官道、中世北街道(矢倉町6-1)
神社のすぐ北の路地前に「矢倉の辻」の標識が出ている。この路地はいかにも古道ぽく、いつもなら古道だと喜ぶが、今回の官道は幅広で直進という近代的道路と共通項がある。そうなると中世北街道とされる、その北の五差路の右(東)、一方通行の出口になっている道がやはり官道ルートに似つかわしいのではなかろうか。この道はまた新幹線ガードと一定距離で並行して東進する。新幹線ルートを決める人の決断ともたまたま一致したようだ。
この古い道が現代によく残っていたものだ。文化財級であろう。しかしこの道も古代道路とは一致しないらしく、別の道があったらしい。
・墓地(西久保345) (周辺紹介)
ひげ題目「法界 弘化二年」、石塔2基、地蔵、祠。
・子育観音(天王さん) (袖師町365-3)
祠、石仏。
・真如寺(袖師町365-3) (周辺紹介)
地蔵、金比羅宮、「庚申塔」、「金光明一千部供養塔」、岩松地蔵。
・旧北街道と国道1号線合流点(横砂西町11、12)
庵原川手前で国1に出て、北街道は終点となる。川に出る直前で道は曲がるが土手ができたため直線道路を曲げたのだろう。古代・中世には直線だったろう。
庵原川手前で近世東海道(今の国1)に合流する。横砂や興津でも近世と中世や古代の東海道は微妙に違うのだろうが、今のところはっきりしたルートが分からない。
・尾羽廃寺跡、庵原郡郡衙関連
かつて廃寺周辺は郡衙だったかもしれない。
・東光寺(横砂本町20) (周辺紹介)
東進すると寺がある。ここからは近世東海道紹介ともなる。
六地蔵、手洗石、「青面金剛童子 嘉永七」、「萬霊塔」、石塔2基。ウスカンザクラ、新・観音多し。
・盧崎神社(横砂本町29)イホサキ
創建不詳だが天慶(平安期)にあったという。古くは八王子大明神で明治に今の名になる。石灯籠2基「嘉永五」。石灯籠2、石鳥居、狛犬、手洗石:近代。祠多数。
おそらくこの神社を西の西ノ宮神社から目指して古代官道は達したのだろう。
「盧」の字はイホと読むが漢和辞典ではロと読む。
・延命地蔵堂、秋葉山常夜燈(横砂東町24) (周辺紹介)
近世東海道紹介。風情がよい。隣のコンクリート製建物も近代初期建築風でレトロ。近世東海道はここから近代の国1を離れより海岸線に近い細い道に入る。前方にJR東海道線の踏切があり渡る。ここから左を見ると国1のある所は丘上になるので、平坦な下の道が東海道なのが分かる。川を渡ると興津である。
・清見神社(興津清見寺町428) (周辺紹介)キヨミ
創建不詳、再建:文化三(1806)年、元は浅間神社と称していた。手洗石2・石灯籠2・石鳥居・狛犬:近代。板碑。祠。力石。
・瑞雲院(興津清見寺町420)
805年本尊如意輪観世音菩薩。性海庵の湧水ショウカイヤ。石塔多し。ウスカンザクラ。句碑、板碑。新・石仏。
・清見寺(興津清見寺町418-1)
奈良期に関所が作られそれを守護する仏堂から寺に発展した。鎌倉期1264年に足利尊氏が再興した。朝鮮通信使関連史蹟。家康手植えの臥竜梅、五百羅漢、石塔類多し。
*参考文献
・「曲金北遺跡跡 第2・3・5・9次発掘調査報告書 静岡市埋蔵文化財調査報告」2008
静岡市教育委員会
(佐渡交差点または手越原交差点から清見寺へ)
・前説明
古代東海道は、静岡市駿河区手越の佐渡交差点、西之宮神社から東へまっすぐ清水区興津清見寺方向へ伸びるものと推定されている。なお静岡市教育委員会『曲金北遺跡調査報告書』では西宮神社ではなく、もっと南の的山を名の通りマトとしたと考えている。現実にそのライン上のJR東静岡駅と隣のグランシップの間の歩道地面下に古代の官道:東海道が出現した。なぜ東西をまっすぐ貫くかというと、古代の条里制により、東西南北に区画がなされ、その延長線上に官道も敷かれていたようだ。静岡市の地図で確認するならば、西は佐渡交差点の西之宮神社で、東は興津手前の盧崎神社(横砂本町29)イホサキ辺りに定規を当てるとよいだろう。無論JR東静岡駅とグランシップを通過するようにする。また曲金の軍神社や矢倉町の矢倉神社付近も通るだろう。ちなみに現在、古代の官道に沿って通れるわけではないので、現地を通りたい場合は付近を迂回することが多いはずである。
もう少し詳しく見るなら、手越の佐渡交差点または手越原交差点から今の国1に沿い東進し、安倍川で線路をクロスし駅南の南安倍三丁目に渡る。ここで線路に並行して通る道を東進する。途中宮本町の神明神社横を通過し、稲川の浅間神社横を通る。もしかするともう少し南の伊河麻神社の境内地が北に広ければ隣接していたかもしれない。曲金の軍神社の北辺をかすめグランシップと線路の間を東進する。線路沿いに東進し、栗原の神明神社北を通り草薙駅西の熊野神社南に達する。ここから直線道路を東へ進み草薙駅前を通過し七つ新屋の春日神社までまっすぐ東に進める。もしかするとこの東西直線道路は古代条里制の名残を残した道だろうか。ということは古代官道:東海道残存部の可能性がある。しかしこの道は明治期の地図には存在していないので、後世の近代に鉄道線路に平行するよう作られたようだ。期せずして古代の道路設計者と近代の鉄道や道路の設計者の思惑が偶然一致したようだ。しかしそういう風に作るのが合理的だという証拠なのだろう。
ここから東への道はないが、およそ新幹線ガードと一定の距離で並行するように東に向かい国1を渡り渋川に達すると、ここで新幹線に並行する道路が出現する。これも官道の名残か。はじめ狭かった道は新たに拡幅された広い東進する道になり、巴川を渡り清水東高前で道はなくなる。地図上ではここからさらに東進すると矢倉神社横の矢倉の辻に達し、神社北の中世北街道とされる庵原川に達する道に接続したはずである。中世北街道が古代官道東海道残存部と推定される。中世北街道も直進道路であり、庵原川に達する部分のみ現在曲線になるが、古代は直進すれば盧崎神社により近かったであろう。ここが曲線なのは土手が作られたためだろう。
・的山マトウヤマ、的山峠マトウトウゲ、マトヤマトウゲ
名のように的山を目指したという考えもあるようだ。
芹が谷から井尻へ山越えしていける道があり、この峠を的山峠という。
やなぎだ眼科医院(丸子芹が谷町9-1)を目指し、やなぎだ眼科医院から南の山あいの谷地に入っていく。谷地の農地に入っていくところに朽ちかけた「谷津峠↓←→的山峠」標識がある。谷地に入っていいのだが、この先の谷地の農地から峠のある山腹に取り付く所には標識はないので、住民に聞くしかない。最後の住宅も過ぎ農地だけになって川が広がって水を溜めている池みたいなところの2箇所過ぎたところを左に曲がり、川に架かる板橋を渡る。草刈もしていないので草だらけの斜面をモノラックのレール(索道)を横目に見つつ、「もとは道だなあ」と思いつつ約5分上ると、頂上に「井尻←的山峠→芹が谷」標識がある。頂上部の尾根は歩きやすく眺めもよい。井尻への下り道は草もなく快適である。5分下ると平坦な車道に接続する。ここに「井尻峠←→的山峠」標識がある。車道へ出ず細い野良道をさらに行くと井尻の集落内に出る。ここにも「井尻峠←→的山峠」標識がある。
・佐渡交差点、西之宮神社(丸子)サワタリ
古代官道はこの西之宮神社から東は清見寺方向、横砂の盧崎神社イホサキにまっすぐ突き当たるようだ。佐渡山は古墳群で、縄文や弥生期からの遺跡が出土する。
創建不詳、再建明和三年。「遷宮記念碑 昭和60年」、石鳥居「明治22年」、石灯籠、「庚申塔」3「大正九」「昭和55」、今の国1と近世東海道が丸子方面へ分岐する所。
・福泉寺(手越14)
石塔類。徳川秀忠の付き人の墓もあるなど由緒がある。
・手越原交差点
長田西中学校のある今の国1と近世東海道が手越及び市中へ向かう分岐点
・国1:佐渡交差点、手越原交差点から安倍川を渡る駿河大橋手前まで
国1は直線状に西から東にむかっており、もしかすると古代東海道に一致するのではと思う。駿河大橋で安倍川を渡るとき道がやや北向きになるので、古代東海道は安倍川で南のJR線路をまたぎ駅南の南安倍3丁目に至るようだ。ただし安倍川がここを通るようになったのは、家康が駿府に隠居し、薩摩土手を築いてからなので、中世までは藁科川が流れていたし、安倍川はこれより東を幾筋かの分流になって流れていたはずである。
・南安倍3丁目、八幡神社(南安倍1丁目8)
ここからJR線路と南のカネボウ通りの間を東に向かえばよいが、正確なルートは不明だし、この辺りで古代東海道をしのべるものはない。
ただ線路北にすぐ見える1丁目の八幡神社がある。(古代とは関係なさそうだが周辺紹介として取り上げる。これからもそうしていく。)中世の源氏関係者により創建されたと推定される。地蔵堂:地蔵「昭和二十八年」、祠、板碑、石塔、与九郎稲荷の由来、義僕八助施義の碑:八助は暇を出されても主家に使え再興に尽くし評判を呼んだ。
線路南を東へ向かう。
・神明神社(宮本町9)
この神明神社の付近を東西に官道は貫いていたと思われる。
創建不詳だが延暦三(784)年再建で1200年以上続くと思われる。手洗石「文化十一」、庚申塔2基「明治十三」「天保十一」、板碑、石塔類。
・聞信寺(宮本町11) (周辺紹介)
山門、庭、石塔、墓といったものはなく、モダンなというかビルそのものである。寺とは思えない。
・蓮久寺(南安倍1丁目8) (周辺紹介)
山門、庭、墓といったものはなく、街中の狭い1軒屋に見えるが、寺名の石碑が出ていて判別できる。
・兵庫浜地蔵尊(黒金町29) (周辺紹介)
元は南安東にあったがここに移転された。悲しい母子伝説がある。川を汚してはならぬ決まりだが、汚している妊婦がいて、とがめられ切り殺された。その妊婦とお腹の子を供養したものである。句碑、板碑、地蔵10基。
・山王寺(馬淵3丁目17) (周辺紹介)
石塔8基:江戸期、地蔵。道元と老翁の問答像。
・津島神社(馬淵3丁目15) (周辺紹介)
創建不詳、再建文化二年、樹木:樹齢300年以上、手洗石・石鳥居・石灯籠:近代。
・伊河麻神社(稲川1丁目10)
創建:白鳳四年、手洗石「寛政十二」、樹木:1本、800年以上?。北辺りを官道が通っていたかも。
・崇福寺鯖大師(稲川1丁目3) (周辺紹介)
古い石塔類。
・千勝浅間神社(稲川1丁目2)
創建不詳。狛犬(市指定文化財)「正和二」:直接見られない、境内にある狛犬は近代の物。手洗石:さざれ石で平安鎌倉期推定。この神社の北か南を官道は通っていたはず。
・軍神社(曲金2丁目7)
日本武尊伝説があり、ここで東征のおり戦勝祈願したという。樹木:樹齢800年以上?。石塔類:近代、板碑。
もしかすると北を通る線路南の江戸時代東海道は官道と一致するのかも。神社は古代官道の脇にあり、東征軍の陣か休憩地か。横田駅家との関連性だ取沙汰される。横田駅家だったかもしれない。
・法蔵寺(曲金2丁目7) (周辺紹介)
石塔類多し、「背くらべ」作詞者海野厚墓、千日地蔵、他いくつか、平澤観音道道標。近くに梶原一族の馬頭観音。
・龍泉寺(曲金2丁目8) (周辺紹介)
石塔。
・曲金北遺跡、JR東静岡駅・グランシップ間歩道、古代の官道:東海道(曲金6丁目8)
JR東静岡駅南口からグランシップに向かう歩道に説明看板あり。道幅9mの歩道が古代官道の幅を示し、周囲の植え込みが側溝を表すよう、分かりやすく歩道が作られている。官道は地下に保存されている。道はほぼ東西にまっすぐで歴史学者等の推定どおり発掘された。官道はまっすぐ東に向かうようだが、そのものずばりの道が現在無いので付近を東進する。
・神明神社(栗原276) (周辺紹介)
手洗石「萬延元年」、石鳥居・狛犬・祠:近代。
・江戸時代の東海道記念標識(栗原38) (周辺紹介)
線路の地下ガード手前にある。本来は踏み切りで向こうへ越すのが正しいのだろうが、少し位置を変えて地下ガードでくぐれるようにした。
・津島神社(中吉田41-10) (周辺紹介)
創建不詳、修造文政六(1823)、樹木1本:樹齢200年、手洗石「天保六」、常夜灯の脚「文政六」、石鳥居「」平成七」、「東源台小学校開校記念 平成七」、「やぶきた茶発祥地記念碑」。石灯籠:近代。
・普済寺(中吉田33) (周辺紹介)
石塔類:「庚申塔」など。
・東光寺(清水区谷田9) (周辺紹介)
石塔類、江戸期東海道に面する。
・谷田宮の後公園、熊野三柱神社、古墳(谷田26)
円墳がいくつかある。古代官道を見下ろす、または道から見上げられる位置にあったはず。
・鳳林寺(中之郷101) (周辺紹介)
石塔類:江戸期。
・桜井戸、桜井戸灸(中之郷425) (周辺紹介)
庚申塔4基、水神、板碑。桜井戸は清泉湧出していたが安政地震で減水、周辺開墾で枯渇し消滅したが記念碑を建立。桜井戸灸は倒れた行者を介抱しお礼に灸を教えてもらい人気になった話である。
・熊野神社(中之郷430) (周辺紹介)
手洗石「弘化五」、市指定保存樹木:楠:樹齢700年以上。薬師如来、新駿河十二薬師第八番札所、閻魔大王。稲荷・祠・手洗石・石灯籠:近代。この神社南の道が官道残存部と考えられ、この道をまっすぐ東に向かう。
・ひょうたん塚公園、前方後円墳(草薙20)
古代官道を見下ろす、または道から見上げられる位置にあったはず。
・冷泉寺(草薙175-1) (周辺紹介)
石塔類:江戸期。
・草薙神社(草薙349)
日本武尊伝説。日本平で火責めに遭うが、草薙の剣で薙ぎ払い難を逃れたという。その草薙剣を納めたという。道からは数km離れている。
・妙盛寺(草薙1973) (周辺紹介)
石塔類。
・春日神社、八幡神社(七つ新屋一丁目7) (周辺紹介)
春日神社:創建慶長期、八幡神社:創建安土~江戸初期、市指定保存樹木:楠。板碑・石灯籠・手洗石:近代。
草薙の熊野神社前からこの神社までの東西を貫く道は官道残存部なのだろう。文化財級の道である。この先、東にはまっすぐ進む道はなくなるので、紆余曲折しながらも矢倉神社をめざす。ガイドにはこの北に見える新幹線高架ガードである。一定の距離で東に進めば間違いはない。
・八幡神社(吉川43) (周辺紹介)
本来は吉川館にあった氏神だが、当地に移転した。創建不詳、市指定保存樹林、石灯籠「文化三」、日待ち太鼓保存会、板碑、境内の2/3は線路で消失。市地域登録文化財(石造物)第1号・旧鳥居・寛政元(1789)吉川氏の由来等のことを書き付ける。昭和59年に書写された石鳥居が現在建つ。
静鉄線狐ヶ崎駅裏にある。駅前が江戸期東海道であり、吉川という地名がいかに南北に長いか分かる。ここが吉川の南端である。岩国城主の大名吉川氏は参勤交代の度にこの神社に参詣し寄付をしていったといわれる。かつては境内はもっと広かったが、線路や駅舎にとられたという。かつて吉川氏というスポンサーがいたからなのか羽振りがよかったのだろう。地域が広いのもそのためか。
・達磨寺(追分四丁目273) (周辺紹介)
達磨を陳列してある。
・乳母が池、一本松、延寿院(追分四丁目2311) (周辺紹介)
伝説の残る池と石塔、お堂がある。追分と国1を結ぶ広い新道脇に見える。延寿院管轄のお堂になるらしい。
・春日神社(追分三丁目5) (周辺紹介)
創建:伝鎌倉期、手洗石・祠・石灯籠:近代。隣は近世東海道に面する延寿院である。ここから近世東海道の追分羊羹本店の赤のれんが見える。
・珠林禅寺(渋川544) (周辺紹介)
ショッテケ地蔵:狐にだまされた愉快な伝説である。馬頭観音「明治十七」、六地蔵・新。
・国1を渡る官道
新幹線高架ガードと国1がクロスするすぐ東の北脇交差点を北に渡り東に曲がる道がある。これが官道残存部ではなかろうか。ちょうど新幹線高架ガードと並行していて今の都市計画の区画整理の思惑と一致し拡幅され、東に延伸することになり、結果として官道を甦らせることになったようだ。
・三島神社(馬淵3丁目15) (周辺紹介)
創建不詳、再建宝暦十三(1763)、伊豆一ノ宮三島大明神を遷した。石鳥居・石灯籠・狛犬・手洗石:近代。
・金剛法寺(渋川2丁目16) (周辺紹介)
石塔類:江戸期。寺の南を東西に通過する道路がたまたま官道残存部になるようだ。
・渋川館(渋川1丁目10) (周辺紹介)
中世豪族で梶原一族を討った駿河地侍一派の渋川氏の館の土塀の一部が残存している。 なんてことないちょいとした高さ5mの丘で茶畑になっているのだが、これは人為的に積み上げた土塀の跡のごく一部が残存したのである。説明看板はあるが、古びてまったく読めなくなっている。
・官道ルートを矢倉神社へ
官道は東に進みつつも徐々に北方向へ向かうというより、今の道が東に進むようでやや南へ曲がるというべきか。北脇新田から渋川にかけて新幹線ガードのすぐ南を平行して東をめざすのが、官道ルートに近いのだろう。金剛法寺のすぐ南の道を東に目指す。清水インター取り付け道路に出て清水東高前で直進不能となる。やや北の北街道へ出れば矢倉神社はすぐだ。ちなみに地図で確認すると、東高を貫いて直進すると矢倉神社にヒットするようだ。新幹線南の平行道路は官道ルートと一致するような気がする。高橋の辺りは以前この東西向きの道はまったく無かった。巴川河口付近の氾濫源のため、もっとも早く条里制が崩れ、官道も消失したのだろうか。
・矢倉神社(矢倉町5)
古くから神社があったことは確実である。日本武尊東征に関する伝説がある。軍の兵営地か武器庫だったという。この神社はこの周辺の要であった。
手洗石「文化五」、猿田彦大神、手洗石「紀元2600(昭和15)年」、石灯籠「大正九」「紀元2600年」、板碑多し、合祀される神多し。祠多し。
・矢倉の辻、古代官道、中世北街道(矢倉町6-1)
神社のすぐ北の路地前に「矢倉の辻」の標識が出ている。この路地はいかにも古道ぽく、いつもなら古道だと喜ぶが、今回の官道は幅広で直進という近代的道路と共通項がある。そうなると中世北街道とされる、その北の五差路の右(東)、一方通行の出口になっている道がやはり官道ルートに似つかわしいのではなかろうか。この道はまた新幹線ガードと一定距離で並行して東進する。新幹線ルートを決める人の決断ともたまたま一致したようだ。
この古い道が現代によく残っていたものだ。文化財級であろう。しかしこの道も古代道路とは一致しないらしく、別の道があったらしい。
・墓地(西久保345) (周辺紹介)
ひげ題目「法界 弘化二年」、石塔2基、地蔵、祠。
・子育観音(天王さん) (袖師町365-3)
祠、石仏。
・真如寺(袖師町365-3) (周辺紹介)
地蔵、金比羅宮、「庚申塔」、「金光明一千部供養塔」、岩松地蔵。
・旧北街道と国道1号線合流点(横砂西町11、12)
庵原川手前で国1に出て、北街道は終点となる。川に出る直前で道は曲がるが土手ができたため直線道路を曲げたのだろう。古代・中世には直線だったろう。
庵原川手前で近世東海道(今の国1)に合流する。横砂や興津でも近世と中世や古代の東海道は微妙に違うのだろうが、今のところはっきりしたルートが分からない。
・尾羽廃寺跡、庵原郡郡衙関連
かつて廃寺周辺は郡衙だったかもしれない。
・東光寺(横砂本町20) (周辺紹介)
東進すると寺がある。ここからは近世東海道紹介ともなる。
六地蔵、手洗石、「青面金剛童子 嘉永七」、「萬霊塔」、石塔2基。ウスカンザクラ、新・観音多し。
・盧崎神社(横砂本町29)イホサキ
創建不詳だが天慶(平安期)にあったという。古くは八王子大明神で明治に今の名になる。石灯籠2基「嘉永五」。石灯籠2、石鳥居、狛犬、手洗石:近代。祠多数。
おそらくこの神社を西の西ノ宮神社から目指して古代官道は達したのだろう。
「盧」の字はイホと読むが漢和辞典ではロと読む。
・延命地蔵堂、秋葉山常夜燈(横砂東町24) (周辺紹介)
近世東海道紹介。風情がよい。隣のコンクリート製建物も近代初期建築風でレトロ。近世東海道はここから近代の国1を離れより海岸線に近い細い道に入る。前方にJR東海道線の踏切があり渡る。ここから左を見ると国1のある所は丘上になるので、平坦な下の道が東海道なのが分かる。川を渡ると興津である。
・清見神社(興津清見寺町428) (周辺紹介)キヨミ
創建不詳、再建:文化三(1806)年、元は浅間神社と称していた。手洗石2・石灯籠2・石鳥居・狛犬:近代。板碑。祠。力石。
・瑞雲院(興津清見寺町420)
805年本尊如意輪観世音菩薩。性海庵の湧水ショウカイヤ。石塔多し。ウスカンザクラ。句碑、板碑。新・石仏。
・清見寺(興津清見寺町418-1)
奈良期に関所が作られそれを守護する仏堂から寺に発展した。鎌倉期1264年に足利尊氏が再興した。朝鮮通信使関連史蹟。家康手植えの臥竜梅、五百羅漢、石塔類多し。
*参考文献
・「曲金北遺跡跡 第2・3・5・9次発掘調査報告書 静岡市埋蔵文化財調査報告」2008
静岡市教育委員会
2014年03月02日
林道、農道の費用について
☆林道、農道の費用について
’13 12/31
・1 林道、農道への関心
私は林道や農道を通行することが好きで趣味と言ってよい。かつてはオフロードバイクに乗っていて、わざと林道を見つけては走行したものだ。今はオフロードバイクに乗っていないが、自動車や自転車で走行するのも好きだ。山登りが好きなので、林道や農道に乗り入れて、登山道への接続点の登山口まで行くこともよくある。古街道にも興味があり、古街道のルートや周辺遺物を調べてはブログに発表している。マイナーな古街道の中には山中を抜けるものがあり、これまた林道や農道を通行する場合がある。というわけでもともと林道や農道には興味があった。
今回気になったのは、2013年秋10~11月に静岡新聞に掲載されていた記事だ。安倍峠を越える林道開設(林道:豊岡梅ヶ島線)の折り、静岡大学の近田教授が安倍峠の樹木:オオイタヤメイゲツ(カエデの仲間で安倍峠で群落していることが珍しい)を残すため林道を峠に通させず、峠より上の斜面に迂回させたという話があった。その時迂回した林道を1m作るのに500万円かかったという。この金額に驚いてしまった。今まで林道走行は好きだが、費用について気にしたことはなかった。
ただ農道で地元の農家の人が「あそこの人が金を払って作ってもらった道だから。……」とか「うちが100万円も払い道路用地もただで取られた道なのに、金払ってない人がただで通るんだよね。」というグチや、よそ者に通行してほしくないという気持ちを表す場面に遭遇することはあった。
・2 今までの林道や農道との付き合い方
林道や農道は入口に「林業(農業)関係者のための道路であり立ち入り禁止」または「立ち入りを制限し、林業(農業)関係者を優先すること」、「道路の安全性を確保できないので通行禁止」となっていることが多い。時には頑丈なゲートが作られ、鍵がかかっていて車両が全く入れない入口もある。
たいていのオフロード好きは見つからないようにそっと進入し、作業している関係者がいる時だけは迷惑をかけないように遠慮がちに通行し、あとは自分なりにマイペース走行でしょうか。マイペースということは飛ばし屋は飛ばし、ゆっくり屋はゆっくりということでしょう。
農道・林道で関係者の作業の邪魔をすると威力業務妨害になるかもしれないそうです。私有地内であれば不法侵入ですが、農道・林道も公道に準ずると考えると、立ち入り禁止でも不法侵入罪を問えるかは疑問です。全国には3千か所以上の施錠か所があるそうです。このうち千数百か所で施錠を壊される事態が発生しています。これは明らかに器物損壊罪です。ただ私もオフロードバイクに乗っている頃、手慣れたオフロード連中は施錠を壊す各種道具を持っていましたね。これは犯罪です。やめましょう。
林道オモシロ小噺というか、林道の入口には不思議なことがあります。全国的に通用することなのかどうかは知りませんが、静岡県辺りでは林道での当り前なことです。どういうことかというと、まず1~2年前の静岡新聞の読者投稿欄から始めましょう。投稿内容は、静岡市の竜爪山での林道は全面舗装されて通行できるようになっているのに、なぜか林道開始点から間もない旧登山口のすぐ先の数m区間地点のみ全く舗装されず、ずっと未舗装のデコボコ道のままなので、その理由と改修を希望するものでした。私は笑いました。おそらく林道マニアなら当然じゃんと思ったはず。後日市役所の林道担当からの読者投稿欄への回答が掲載されていた。これまたしらばっくれた内容で吹き出しました。内容は、工事業者にはしっかり作るように指導してきたはずなのに、なぜこのような個所があるのか分からない。後日改修をしたい旨でした。
それから1~2年経過しますが、全く改修される気配もありません。林道担当どころか誰でもそこを通過すればここだけが悪路で絶対気付くはずですが、放置しているのですというか、わざとです。一般的に静岡の林道マニアの間では林道開始点付近にわざと一部分だけ悪路にして、一般の人たちが進入する気をなくさせるためだといわれています。つまり故意にわざと一部悪路なのです。施錠等して通行禁止にしにくいので、一部悪路にしてでも立ち入る車を減らしたいのでしょう。
申し訳ない話ですが、立ち入り禁止の道を奥に向かって入っていくと、ちょうど工事中で道をさらに奥へ奥へと伸ばしている光景もあります。あのう知らぬ間にどんどん工事して道を伸ばしていることもあるということです。
すべての農道・林道が閉鎖的かというとそういうわけではなく、一部の道路は一般国民に開放されていて、地域住民のほとんどにとって県道や市道と同じように便利な道として使われているものもあります。これならOKでしょう。
農道・林道とは別に幅の狭い悪路になりがちな作業道というものが、近年作られてきました。かなりな悪路になりがちで民間所有者等が作る私道になりがちなようですが、公的機関も作るのかを知りません。私道なら立ち入り禁止は当たり前でしょう。
林道、農道の目的は林業や農業の関係者のための道であるというのが一般的な認識でしょうし、私もそう思っていました。自己負担金を取られ用地も取られているなら、なおさらそれでよいのだろうと思っていました。しかしほとんど多額な国税を投入して作っていることを知り愕然としたわけです。
農道・林道はこのままでいいの?
・3 林道、農道のお値段
林道、農道の値段を知るため、農林省の地域部署の総務課に問い合わせをしましたところ、市役所に問い合わせると値段が分かるだろうとのことでした。
静岡市役所に問い合わせました。
・静岡市役所、農林水産部、治山林道課-林道担当の説明 tel:054-354-2166
一概に言えない。安倍峠迂回路に1m=500万円は破格の高値で高額すぎて具体的には分からない(困惑しているようです)。ごく一般的に1m=20万円。
地元負担金は取っていない。用地についてはたいてい無償で提供してもらっている。
静岡市内全域の林道の日常管理年間費用は3千万円。(改修費は別立てのようです。)
・静岡市役所、農林水産部、農地整備課-農道水路担当の説明 tel:054-354-2067
現場の状況により千差万別、一概に言った数字だけで判断されても困るとのこと。
平地で水路等付加設備設置がなく最低の4m幅だけを設置するならば1m=20万円。崖に作れば1m=100万円。もっと高いこともあるが、現場の状況を鑑みずに言えばそのようなところである。地元負担金は今は取っていない。昔、土地改良事業を伴うということでとっていたことがあるのかもしれないが分からない。用地はたいてい無償提供が多い。
そこで私なりにひっくるめて単純解釈すると、平地で20万なので林道の1m=20万は最低価格と思えばよいのかも。たいてい林道は崖に作られるので、100万前後程度かかるのではないでしょうか。道路脇に水路や、土留ブロック、えぐれている部分に土を入れて平らにする盛土、斜面を切り崩す切土等を施すほど、道路は1mしか作れず進まなくても崖等の左右両端で道路を保持するためのいろいろな設備が増して、単価が跳ね上がるようです。道路の距離は1mでも左右を見れば10mや20mもの幅でいろいろ作られていることはあります。
*林道、農道ではないが、国道「三遠南信道」費用についての記事
・’13 12/27金、静岡新聞、夕刊、「三遠南信ルート固まる」より
対象区間:21㎞(14㎞:時速80km制限の自動車専用道、7㎞:現道の国道152号線を改良して時速50㎞)
総事業費:約740億円
以上です。21㎞のうち3分の2は自動車専用道で、残りは既存国道の拡幅付け直しということのようです。そこで道路としては全く違う種類を2つになるので、一緒くたにするのは無理ですが、2種類個々の費用が分かりませんので、あっさり740億を21㎞のうちの1mで算出すると1m=325万円。(憶測だと、多分、自動車専用道が500万程度で、既存国道改良が150~200万程度かなと勝手に…、具体的には分かりません)
ただここで国道費用を出した理由は、道路建設には莫大な費用が必要だということが分かるということです。決して道路は安く作れない。莫大な税金が使われるということです。私は驚きました。
では近頃新東名高速ができて便利でいいねと私は言っていましたが、あれは片側3車線の上、トンネルとバカ高い高架橋だらけなので、1m単価はいくら? もしかしたら1000万円? きっと破格の高額でしょうが、一般国民にとって利便性があり、将来の東海地震後の災害復旧用の必要性があるそうなので、地震があっても役に立つならokでしょう。
・4 法律における林道、農道とは何?
日本国内での道路としては、国道(国土交通省:管理)、都道府県道(各都道府県)、市町村道(各市町村)があり、たいてい人の住居があるところまでは以上3つの道路があるようになっている。これらの道路を管轄する法律もある。だがこれらと全く別の道路がある。まあ私道もそうであるが、これは基本的に私有地に作られるもので道路として直接管轄する法律はないはずである。
では何かというと、農林水産省が補助金(税金、国家予算)をもって作る林道や農道である。先ほど自己負担金があると書いたが、自己負担金だけで作るなら私道や作業道であり、林道や農道にはならない。あくまで補助金を使った道路である。以前一部費用を地元が負担していたこともあるようだが、今はほぼないようだ。また費用を一部負担するにせよ、百万、二百万といったところで、農家にしてみれば大変な金額だが、前述する値段を見れば道路のたった数m分に過ぎず、ほとんどは税金だ。林道や農道は道路だが、管轄は国土交通省ではなく農林省であり、管轄する法律も全く別である。
日本全国の林道や農道の道路距離㎞や舗装率、トンネルや橋梁部の距離といった数字は、農林省の「農道・林道整備状況調査」が公開されている。ちなみに最新版で平成17年度版である。ただこれには費用(事業費)はまったくないし、各路線ごとの距離や、舗装率等もまったく分からない。
農林省にしてみれば日本全国や各地域でのまとめた数字が大切なのでしょう。年間いくら補助金を投入しているのか知りたいものです。また各路線の距離と総事業費も知りたいものです。
以下に法律上の説明をします。
・用語の説明、「農道・林道整備状況調査の概要」よりコピー
農道
調査期日現在で、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業で造成され、農道として管理されている幅員1.8m以上の道路、独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)に基づく農用地総合整備事業、特定中山間保全整備事業又はふるさと農道緊急整備事業により造成された幅員1.8m以上の道路をいい、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路、林道、漁港関連道路及び農道として造成された道路であっても、既に都道府県道、市町村道に認定されている道路は含まない。
一定要件農道
市町村が管理している幅員4m以上の農道のうち、農道の両端(起点及び終点)が道路法に基づく道路又は農道台帳に記載されている全区間において4m以上である農道に接続し、かつ、農道台帳作成済みの道路をいう。
林道
調査期日現在で、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく国庫補助により造成し、民有林林道として管理されている幅員1.8m以上の道路(自動車道のみ)及び独立行政法人緑資源機構法に基づく大規模林業圏開発林道事業又はふるさと林道緊急整備事業等(県単林道、融資林道・自力施行林道を含む。)により造成された幅員1.8m以上の道路(自動車道のみ)をいい、道路法に基づく道路、農道、漁港関連道路及び林道として造成された道路であっても、既に都道府県道、市町村道に認定されている道路は含まない。
一定要件林道
市町村が管理している幅員4m以上の林道のうち、林道の両端(起点及び終点)が道路法に基づく道路に接続(一定要件林道又は一定要件農道等を介して接続する場合を含む。)し、かつ林道台帳作成済みの道路をいう。
舗装済
農道及び林道延長距離のうち、アスファルト及びコンクリートによる本舗装又は簡易舗装の延長距離を対象とし、砂利道は含めていない。
トンネル部
農道及び林道に係るトンネル部をいう。
橋梁部
農道及び林道に係る橋梁部で、農道については橋長15m以上のもの、林道については橋長4m以上のものをいう。
管理主体
農道及び林道を実質的に維持・管理しているものをいう。
また、「土地改良区等」には、農協、農業集落等を含み、「森林組合等」には、生産森林組合、森林組合連合会等を含む。
以上です。法律言葉はややこしい。法律では農道・林道の順番です。そして一定要件農道・林道という種類も区分してます。林道には融資林道や自力施工林道というものもあり、自己負担でも作ってよいということなのでしょうか。
・調査事項は
1.管理主体別幅員別農道及び林道延長距離
2.管理主体別幅員別舗装済農道及び舗装済林道延長距離
3.管理主体別幅員別農道及び林道内トンネル部延長距離
4.管理主体別幅員別農道及び林道内トンネル個数
5.管理主体別幅員別農道及び林道内橋梁部延長距離
6.管理主体別幅員別農道及び林道内橋梁個数
以上で、これらのことが分かります。以下にその数字の一端を掲載します。単位はkm、m、%が入り混じるのでご注意ください。トンネルや橋梁部は単位がmで、()内は%です。
平成17年度版 : 8月1日現在の状況を11月に調査
農道:全国:総距離:180792km、舗装延長:60866km(舗装率33.7%)、幅員:1.8~4.0m:106492km(割合58.9%)、4.0m以上:74301㎞(41.1%)、トンネル部:総延長:53798m、か所数:230、平均:234m、橋梁部:総延長:131408m、か所数:2986、平均:44m、
都道府県管理:359km、市町村が管理:122353km、土地改良区等が管理:58080㎞、
*土地改良区は土地改良法第3条に規定された土地改良事業に参加する資格を有する土地の使用者や小作人・養畜を行う者など使用収益者等15人以上の者が、その地域において同様の資格を有する耕作者などの有資格者の3分の2以上の同意をえて、都道府県に申請を行い、その認可を受けることによって設立される(土地改良法第5条~第10条)。都道府県知事の認可を受けて設立された土地改良区は法人とし(土地改良法第13条)、土地改良区でないものはその名称を使用することができない(土地改良法第14条)。
ウィキペディアをコピペしたら以上の文になった。難解な法律言葉だ。その土地の改良にかかわる多数の人による組合でいいのかな。
林道:全国:総距離:88478km、舗装延長:36411km(舗装率41.2%)、幅員:1.8~4.0m:33820km(割合38.2%)、4.0m以上:54658㎞(61.8%)、トンネル部:総延長:90383m、か所数:533、平均:170m、橋梁部:総延長:230818m、か所数:17054、平均:14m、
都道府県管理:6992km、市町村が管理:78238km、森林組合が管理:3248㎞、
*森林組合は林業者の組合
ぶっちゃけて分かりやすく言えば平成17年は以下です。
農道は18万km、うち舗装は6万kmで3分の1、幅1,8m~4mが6割、4m以上が4割、トンネル部が50㎞、橋部が130㎞、市町村管理が67%、都道府県が0.2%、土地改良区等が32%です。
林道は9万㎞、うち舗装は4割、幅1,8m~4,mが4割、4m以上が6割、トンネル部が90㎞、橋部が230㎞、市町村管理が88%、都道府県が8%、森林組合等が4%です。
・農道・林道に多額の補助金はなぜ?
農道・林道に多額の補助金を使うわけは、日本の農業・林業を守るため、山村活性化策、食料の自給率確保のため、雇用確保のため等いろいろ理由はつけられそうです。一部の農道・林道は自由通行で、実際に地域住民の生活、通勤、通学、買い物、便利な近道、観光利用といった用途に使われていて、これなら国民も納得でしょう。しかし一部の農道・林道は立ち入り禁止で施錠されているものもあります。安全性の問題で通行禁止にしているというなら、国民の税金を億単位で使って、安全性が不十分な欠陥道路を作り、一部の人の利便にのみ供与しているわけなので、そこまでして一部の人に供与される必要性を説明してもらってもよいのかもしれません。費用対効果として、一部の人の利便性がこれほどあるので間接的に国民に還元されるはずだといったことを説明してもらいたいです。費用対効果は10億円で作った道路で、年間3千3百万円ほど利益が出るので、30年で元が取れるといったことでもよいと思います。もっとシビアなら道路ができる以前の生産性と道路開通後の生産性を比較し、その差額が費用対効果と言えます。開通以前年間100万円の収益が、開通後200万円になれば100万円の効果といえるのですが、そこまで求めると多分、100年かかってももとがとれなさそうな気がしますが、いったいどうなのでしょうか。
元林業従事者の奥さん(老女)から聞いた話なのでぼけた時代錯誤の話かもしれませんが、一応載せます。昔は林道などないから、歩いて這いつくばって山を登り、沢を渡り、ひどい思いをしながら山に入って、木の世話をし、人足を雇って木を刈ってワイヤーを張り、すべて手作業で木を出したものだ。しかしオイルショック以後、安い外来材が輸入され、とても手作業で木を出したら、人足代にもならない。林道ができて車で取り出せても、下手すれば赤字かもしれない。よほどうまくやらねばもうけを出せないだろう、という話でした。
林業経営は林道があってもきつい状態だろうとは察せられます。だからこそ林業を守るため億単位でもなんでも税金をつぎ込んで守りたいという人もいれば、ものには限度があってそこにばかり多額の税金を投入しても効果が限定的ならば、それなりの税金投入は当たり前としても、億単位は多すぎるという人もいることでしょう。
何せ国家財政の累積赤字は1000兆円を超え、’13年度国家予算が補正予算込みで230兆円、税収40兆円、税収以外の収入20兆円、収入合計60兆円で、不足分170兆円という、すさまじい超赤字だらけなのです。国民に支払う年金代だけでも30兆円必要だというのに、
どうしましょう。公務員の給与も退職金も減額し、その他もろもろけちってます。農道・林道もかつての日本土建屋国家と言われた高度成長期に比べたら、縮小の一途をたどったことでしょう。今は最低ラインと言えるでしょうから、道路作りに情熱のある輩からは、これ以上道路建設費を削るなと言われそうです。しかし必要なものまで削っている今、効果が限定的な農道や林道に回す税金があるのでしょうか。特に立ち入り禁止でどれほどの利用価値があるのかと思える道路、行き止まりで道路周辺の山林や畑に作業する人が時々使う程度の道路など、そこまでして億単位の税金を投入しなければいけないのでしょうか。
もしも10億円で作った林道で施錠されていて、鍵を持っている使用者が民間管理者5人と森林事務所職員5人で計10人だとしたら、1人当たり1億円も利便性のために補助してもらったことになるのでしょうか。実際何人位が使用しているか全く知りませんのであてずっぽうな数字で申し訳ありませんが、そんなに多くの人が施錠を開ける鍵を持っているとは思えません。ごく少数の人の利便性のため億単位も税金つぎ込むんですか。ここまでしてでも高い効果があるとか、道路が危険だとか、何らかの納得できる説明はできるのでしょうか。
一般の人も補助金の効果に預かることはあるでしょう。例えばCO2削減効果のある自動車を購入すると一時期補助金が出ていました。こうしたことで自動車産業関係者は新車売上効果があったでしょうから、儲かったといえるでしょう。しかしこの効果に預かった人は新車製造、販売、部品関連産業等多岐にわたり、一人当たりにしたら高額にはならないでしょう。
農道・林道はなぜに一部の人だけの利便性のために多額の税金を投入することをよしとしてしまったのでしょうか。高度成長期に都市部だけでなく農山村部でも人間の必要とするところすべてに自動車道があることが平等を旨とする公共の福利にかなうと思われたのでしょうか。都市部には道路がいっぱいあるのに農山村部にはろくな道路がない。畑や森に行くのにも歩いていくしかないとなれば、不公平ではありますね。財政黒字で羽振りのよいときならそれでよかったのでしょうが、この財政赤字の中ではきついですね。
・農道・林道こうしてほしい
・農道・林道は存在していない:多くの一般国民は、そこに農道・林道が存在することさえ知らないという事実があります。それは農道や林道が道路工事のたび、開設されて距離を伸ばしていっても、国土地理院の地形図に開設されて25年程度経過しないと、掲載されないことが多いからです。たいていの民間地図会社の地図やナビは国土地理院の地図を許可を受け無料でコピーしているので、国土地理院の地図に掲載されない限り、日本の地図に農道・林道は掲載されません。そうすると多くの人々はそこに道があることさえ知らないわけです。そこで登山者がよく経験する話を一つ、山を歩いて登っていたら、上に車がいてハイヒールを履いた人たちがいたということになるわけです。地図に載らないので登山者は知らずに登って当惑するのです。国土地理院にすれば一部利用者のための農道や林道を調査する費用や手間暇まで手が回らないということだとは思います。しかし国民の多額の税金を使って作った道を掲載しないというのは、ひどい言い方をすれば、税金の使途を国民に知らせることを怠っている、もっと悪辣に言えば隠ぺいする工作と言われるかもしれません。農林省側も国土地理院に地図に記入するためのデータを送るなんてことはしていないでしょう。農道・林道は関係者の利便のためにあり、関係者だけ知っていれば十分という意識なのでしょう。そこで関係者以外に周知しようという気もないのでしょう。しかし補助金(税金)で作っているのですから、費用、距離、ルート等は周知努力をすべきでしょう。
・農道・林道の看板標識について:農道の看板や標識、石碑には、開通記念、農業関係者優先、立ち入り禁止、といった内容です。林道では開通記念、開通日、立ち入り禁止、安全確保不十分、林業関係者優先、距離、幅員、閉鎖期間といった内容です。今後こうなってほしいという看板標識についいて記述します。一般国民(納税者)にしてみたら、距離、幅員、閉鎖期間の表示は絶対必要です。その他必要なのは、ルート図です。どういうルートなのか分からないのです。なにせ現状では上記のように地図に掲載されていないのでどこへ向かうかさっぱり分からないのです。距離、幅員の他、総事業費か補助金の額を記入したほうがよいでしょう。いったいいくらかかった道路か分かります。本路線の農業、林業への有効性について簡略に説明する。またあるならば本路線の一般国民への有効性:例えば観光、登山、リクレーション利用等について簡略に説明する。
・すべてではないが、各路線による立ち入り禁止措置について、道路の安全性が確保できないならやむをえぬと思いますが、一部の人だけが使える現状において、それでも道路が必要であるという説明責任をはたすべきでしょう。道路の安全性、利用効果、費用対効果、利用人数、年間利用日数、道路建設の総事業費及びそのうちの補助金額、年間管理費用等ですね。これらを農林省、農林事務所、森林事務所、地方公共団体の農林部課署、土地改良組合、森林組合等は説明できるようにすべきです。施錠等がなされているならなおさら施錠ゲート前に上記に記述したような看板標識により、説明責任を果たしていただきたいです。一納税者よりのお願いです。また何せ施錠されていて中がのぞけないのに、道路はどんどん工事されて現在も距離を伸ばしていることがあり、まさに知らぬ間にどんどん税金使っていることもありますのでなおさらです。
・へそ曲がりな展望、拡散希望
施錠箇所を壊すようなまねはやめるべきです。それより別の手段、例えば長期間かかりそうですが、今私が行っているブログへの投書、この農道・林道への税金投与を不合理だとして訴えるアピールに賛同、または別の意見をお持ちでしたら、その意見をブログやツイッター、新聞への投書等で表明していくことにしませんか。私のつたないこのブログの意見の拡散でも、あるいはあなたなりの意見でもよいので拡散していただき、ぜひ多くの国民に知らせたいと思っています。道路を作るためにこんなに税金がかかるとは知りませんでした。
拡散してもらうには、刺激的で強烈なキャッチコピーなんぞ必要でしょうか。農林省、農林事務所、森林事務所、地方公共団体の農林部課署、土地改良組合、森林組合等にケンカを売るつもりは全くなく、それより一般国民が知らないうちに納税者の知らない道路を着々と作られているという事実を知ってもらいたいのです。
キャッチコピー:「あなたが知らぬ間に税金道路着々と、できあがっても見えないところにあるから大丈夫、知らなくていいのよ、どうせ立ち入り禁止」
「税金のむだづかい、農道・林道は税金泥棒道路」
以上2つご用意しましたが、むちゃくちゃな内容ですよね。この言葉だけであまり本気にしてもらっては困るのですが。
2014年03月02日
石塔や石仏といった石造物が危機に瀕している
・石塔や石仏といった石造物が危機に瀕している
2013 12/31
1990年代あるいは2002,3年頃までは、石仏等の年号や保存状態に関して経年劣化が少しずつ進むなと思っていたが、ここ数年2010年代に入り、急速に劣化が速まっている気がする。なぜなのかは明確な証拠はないが、憶測で言わせてもらえば、この異常気象や大気汚染が拍車をかけているのかもしれないという気がする。2000年代以降、真夏の暑さは尋常ではなく、しかも長期間化してきた。冬も低温傾向が強まるなど地球温暖化の影響が石造物に来るのかもしれない。大気もpm2.5とやらで野外にある石塔、石仏に汚染された雨風がじわじわ影響していくのかもしれない。大気汚染に関しては公害全盛の1960~70年代に一旦悪化したのだろうが、今回は異常高温と低温も束になり、さらに雨は降れば降ったで今までに経験したことのない100年に一度の1時間に100㎜雨量が降る場合もあるという状態です。これって石仏にしても難儀なことでしょうね。真夏に人々が脱水症でバタバタ倒れるこのご時世、石仏もかつてない経験に脱水症になりそうなのかも。真冬は地域によっては自宅からわずか100m先でホワイトアウトで遭難凍死するご時世、石仏も凍死してるのかも。
ここ数年、石造物に刻まれた文字がどんどん判読不能になり、石本体もボロボロになるスピードが速すぎる気がする。こうなると屋根のある下に保存しなおすしかないのだろうか。神社仏閣の軒先や、地区集会所の軒先、物置内の土間等に保管しないと、古い石造物はどんどん崩れて、ただの石ころや砂粒になってしまう。もう江戸時代の石造物は古いものや希少価値があるものから各市町村の有形文化財として年々徐々に登録されていってよいと思っているが、これでは文化財になる前に全滅しかねない状態だ。こりゃえらいこっちゃ、文化財候補がなくなるう。
2013 12/31
1990年代あるいは2002,3年頃までは、石仏等の年号や保存状態に関して経年劣化が少しずつ進むなと思っていたが、ここ数年2010年代に入り、急速に劣化が速まっている気がする。なぜなのかは明確な証拠はないが、憶測で言わせてもらえば、この異常気象や大気汚染が拍車をかけているのかもしれないという気がする。2000年代以降、真夏の暑さは尋常ではなく、しかも長期間化してきた。冬も低温傾向が強まるなど地球温暖化の影響が石造物に来るのかもしれない。大気もpm2.5とやらで野外にある石塔、石仏に汚染された雨風がじわじわ影響していくのかもしれない。大気汚染に関しては公害全盛の1960~70年代に一旦悪化したのだろうが、今回は異常高温と低温も束になり、さらに雨は降れば降ったで今までに経験したことのない100年に一度の1時間に100㎜雨量が降る場合もあるという状態です。これって石仏にしても難儀なことでしょうね。真夏に人々が脱水症でバタバタ倒れるこのご時世、石仏もかつてない経験に脱水症になりそうなのかも。真冬は地域によっては自宅からわずか100m先でホワイトアウトで遭難凍死するご時世、石仏も凍死してるのかも。
ここ数年、石造物に刻まれた文字がどんどん判読不能になり、石本体もボロボロになるスピードが速すぎる気がする。こうなると屋根のある下に保存しなおすしかないのだろうか。神社仏閣の軒先や、地区集会所の軒先、物置内の土間等に保管しないと、古い石造物はどんどん崩れて、ただの石ころや砂粒になってしまう。もう江戸時代の石造物は古いものや希少価値があるものから各市町村の有形文化財として年々徐々に登録されていってよいと思っているが、これでは文化財になる前に全滅しかねない状態だ。こりゃえらいこっちゃ、文化財候補がなくなるう。
2013年05月03日
大川街道、静岡県道南アルプス公園線
大川街道(静岡市八幡~湯ノ島、大間、笠張峠)県道60号線南アルプス公園線
調査:2013年2/24~4月
静岡市羽鳥で国道362号線を上り昼居渡八幡で国道362号線から右分岐し、県道南アルプス公園線を遡上し、笠張峠までの区間とする。八幡から湯の島の近代道路は1916年開通。
*なお静岡市安西・羽鳥から昼居渡八幡までの区間(この区間の近代道路は1903年開通)は、『古街道を行く』(静岡新聞社)の川根街道を参照してください。
・(八幡)
70m進むと道は右カーブになる。そこの岩上に石塔あり。
・馬頭観音:明治四十五年六月廿二日
・庚申塔 大正九庚申年
・石灯篭:大正十二年
・(赤沢)
赤沢の休憩所を過ぎ、集落右上に神社がある。上っていく途中の家の石垣庭先に石塔あり。
・農道建設碑 昭和三十二年
???・対岸の峠は櫛筐峠クシゲ(クシバコ)トウゲというそうだが、具体的にどこなのかわからない。わかる方お知らせください。
集落左手上に神社あり。
・山神神社(赤沢)
神社拝殿の額には山之神社と書かれている。
・手洗石:昭和三十四年
・鳥居・金属製
県道に戻り北上。のがたけへの分岐より手前に祠があり、祠内に3つのものが祀られている。
・弘法大師
・観世音菩薩
・黒田渕稲荷
ここの渕を黒田渕というようだ。
・(のがたけ)
のがたけへの分岐には東海自然歩道標識あり。吊り橋で藁科川を渡り、標識に従い山に取り付けば尾根まで行ける。尾根上の道は古い川根街道であり今の東海自然歩道である。ちょうどのがたけからの上り口は裏川根街道上り口のようだ。
のがたけの集落の庭先に石塔あり。
・石塔?:摩滅して刻字等不明、細長い60~70×20cm、庚申供養塔?か
・石塔?:摩滅して刻字等不明、背が低く幅広40~50×30cm、
集落を上がっていくと分岐点あり。東海自然歩道標識と石道標あり。
・石道標:従是 右 相又 左 村中 道:行書で書かれており幕末から明治初期のものか。摩滅していて判読しにくい。右が東海自然歩道・川根街道方向で相又である。左は集落で吊り橋を渡れば赤沢や寺島に行ける。
また県道に戻り北上。
・(寺島 市ノ瀬)
寺島中心集落手前カーブ地点上に神社あり。
・行春社(市ノ瀬)
・石鳥居:刻字?だいぶ摩滅しているものばかりで判読不能。
・手洗石2:刻字?
・石燈篭:?
・地蔵:?
・馬頭:?
・石仏:?
・如来:?
・祠:
・石塔:生祠
この上に神社あり。
・白髭神社
・鳥居:木製
・手洗石:明治十四年
・石製家型道祖神:
・奉供養庚申之塔 文政九丙戌年
県道に戻り北上。寺島集落で右折して坂本へ行くルートがある。東海自然歩道も同じく右折である。
・弥助桜、伝説「約250年前村が貧しく年貢を払えないとき、山杢弥助は役人とトラブルを起し桜の大木に上って隠れていたが役人に見つかり、富沢の六郎兵衛が鉄砲で撃ち落とした。そのとき弥助は六郎兵衛を七代祟ってやると叫んだ。その通り六郎兵衛の子孫は肉体的不具合が多かった。また弥助には二人子供がいたが賢かったので弥助のようになることを案じ殺してしまった。桜の木は弥助桜と呼ばれた。昔子供を祀ったものが田の中にあったという。」
???弥助桜はどこにあったのか?
・弥助観音、伝説「寺島新宮にあり、山杢弥助にまつわるものである。形は直径約15cmの円盤状の石で割れたものを継ぎ直したようになっている。昔弥助観音がある辻の辺りが子供の遊び場で、子供が弥助観音を割ってしまったので、武士が子供をたしなめていると、観音がせっかく子供と楽しく遊んでいたのにと武士に注意したといわれる。」、子供と遊ぶ地蔵伝説は各所にある。
???弥助観音はどこにあるのか?
○~寺島で坂本(東海自然歩道)への分岐。~
200m進むと右に石仏あり。
・地蔵
さらに進むと坂本集落が見えてくる。
・坂本
坂本集落橋手前の右民家前に石仏あり。
・庚申塔 大正九年
・南無馬頭観世音 大正六年
清沢本橋を渡ると集落中心部だ。すぐ橋周辺が坂本川砂防公園で右に看板あり。
・看板説明版:河原施餓鬼:鎮魂の碑:大昔に遡る約三百年前享保六丑(1721)年閏七月十六日異常な大雨が降り続き、字姉山沢の奥が山崩れとなり、人家へ押し寄せる土石流に、一瞬にして泥中に埋没した家屋数三戸、五郎兵衛方男女四人、助蔵方男女二人、権四郎方男女三人が、家と共に山なす泥土の下深く埋まる大惨事となった。また周囲の屋敷、田畑、山林も埋め尽くし、大きな爪跡を残した。
それより百三十三年後の安政大地震により、再び山崩れを起こし、家屋敷に被害が発生したが、人的災害がなく、不幸中の幸いであった。
貴い人命と共に被害、損傷を受けた我々の先祖の苦難の歴史をたどる時、霊の鎮魂の為、三年に一度、この地で川原施餓鬼を行い、犠牲になられた緒人をはじめ、受難の時代を乗り越えた古人の冥福を祈り、祈願を続けている。
*注釈:閏ウルウ七月とは、七月の翌月が閏七月となり、七月を2回行ってから、その翌月が八月であり、1年が13ヶ月になることもある旧暦のシステムである。約3年に一度13ヶ月になる。以下の崩野の延命地蔵箇所で旧暦一口メモとして簡単に紹介する。
メインストリートの林道坂本線に沿い上っていくと公園内に祀られているものに出会う。
・地蔵:光背付き
・句碑:とつさきに山霊導くわか泉 昭山
公園を過ぎ茶畑右に石碑あり。
・句碑:
更に進み左が崖になると、その崖に祀られている。
・馬頭観音:
メインストリートを清沢本橋手前まで戻り、集落内旧道を上る。すぐ左に石仏あり。
・馬頭観音 昭和十四年:朝風という馬を祀っている。
寺に向かう。
○清源寺
・大カヤ:説明版:樹高30m、目通り周囲3.7m、枝張18m、このカヤの木は樹勢が良好で樹齢約450年にも達する巨樹である。カヤの木は山地に自生しているが、庭樹としても植えられている常緑の高木である。種の胚乳は食用になりまた油を採る。材は基盤、将棋盤として有名である。
・馬頭:明治六年
・石仏:他2つ付き
・西国三十三所:他に馬頭と如来付き
・地蔵:
・西国三十三所
・西国三十三所 寛政戌辰年
・庚申供養塔 文政七年
・八幢しょう:
・地蔵:祠
もう少し山上に神社あり。
○清沢神社
・石鳥居:大正十三年
・石灯籠:
・石灯籠:
・石灯籠:
・石灯籠:昭和十二年
・手洗石:慶応四年
・石塔:奉献 伊津奈大権現 寛政八丙辰歳九月吉祥日
・奉献 御神燈 寛政八辰年九月□
・かまど
奥に奥宮がある。
・石灯籠:
・結界石
・祠
・石塔
・鳥居:金属製
元来た道を戻り下ると途中に四十一坂(肘打峠)上り口表示がある。
・四十一坂(肘打峠、肘打嶺)、静岡市駿河区坂本、国土地理院2万5千分1地図「牛妻」
’13 3/17 坂本より二十数年振りに登った。登山道は整備され標識も多い。集落上はずれから畑次いで森を通り峠まで15分。道は狭いところもあるがかつては道幅1間1.8mあったと思われる。一部崩壊していて道の付け直しがされている。集落はずれと畑の境辺りに石ころの道祖神がある。かつて登ったとき峠は平坦な茶畑でそのときはちょうどおじさんとおばさんが茶畑の世話をしていたが、今は植林と雑木が一面を覆っている。峠には石仏の観音2基と説明看板がある。
・西国一国三十三所 萬延元年
・□国一国三十三所 宝暦四年
・説明看板:肘打峠は大昔より藁科街道往来の道として栄えてきた。峠にはかつて大樫の大木が繁り峠越えの旅人の休息の場所となっていた。また鎌倉時代源頼朝の希望により栃沢の米沢家の老女が永年手塩にかけた愛馬:摺墨(磨墨)の手綱を頼朝の家来赤沢入道、小島三郎、日向太郎の高名な三勇士に名馬摺墨の手綱を手渡し、しばしの別れを惜しんだ峠と伝えられる。坂道の曲がり多く狭く険しく肘を突く峠の道、坂道を上りきるとそこに石仏二体苔むした観音菩薩が静かに時の流れを見守っている。(清沢村誌引用)
峠から更に坂の上に向かい下る。初めは見事な切通しで道幅1.8mが確保されていたことがよく分かる。ただしこの道を見ていきなり近世の古道をイメージしてはいけないのだろう。たいていの古道が、少なくとも昭和の戦後期まで現役の道として使われ補修を受けてきたのだろうから、戦後期の姿と受け止めたほうがいいのだろう。ニホンカモシカに会った。体長1.5m以上で立派な体格だ。このところ里山でも数多く見受けられる。天然記念物がこんなに人里にいていいのかと思う。被害は出ているのだろうか。逃げていくとき「キー」という甲高い声で鳴いていた。見受けることはしばしばあるが声を聞いたのは初めてだ。周囲に知らせるかのように鳴いていたので付近に仲間がいたのだろうか。しばらく下るとガレているところがあり道は崩壊していくようだ。15分で下りきり茶畑の農道終点に出る。ここから坂の上に出られる。なお農道は低いところを通って坂の神に出るが古道はもっと高いところを通過していたのだろう。
以下に以前の文章を載せる。
静岡市羽鳥で藁科川を遡る国道362号線を北上、八幡にて県道で藁科川を北上、市ノ瀬で東海自然歩道の標識あり、750m北上で寺島集落に出る。東海自然歩道標識は県道を右折し坂本集落に向かう。1kmで坂本へ、集落西端の家から裏山に登る登山道あり。分からなければ地元の人に聞くべし。道はやぶっていてよくないが、何とか通れる。標高差70mで尾根の峠到着、石造物が2体あったはず。昔は茶畑などでもっと通りやすかっただろう。確認89年頃なのでいつか再確認をしたい。ルートと名称は国土地理院2万5千分1地図に記載があるが、下り道未確認。西に下れば藁科川沿いに坂の上集落から延びる農道に出られるようだ。農道から登山道に入る付近に架かる吊り橋手前県道に「古道、四十一坂、肘打峠」の標識あり。農道からの標高差150m。坂本集落内にも標識あり。この道はかつての藁科街道のはずである。
~坂本から寺島の藁科川沿いへ戻り県道を北上する。~
鍵穴バス停付近で鍵穴橋を渡り、向こう岸の本村へ行く。
集会所のある墓地はおそらくかつての寺院跡だろう。
・奉一国三十三所供養塔 天保五申午年
・庚申塔 天保五年
・石塔2基
集会所裏手に神社がある。
・八幡神社(鍵穴本村)
石鳥居:大正十四年
・手洗石:大正十四年
・石灯籠2基:
~県道に戻り北上する。~
○大瀬戸
大瀬戸の県道カーブ地点上の山にお堂がある。かつての寺だ。
参道入口は集落内である。
・門柱:コンクリ製:昭和拾壱年 鍵穴同志會
・石灯籠:剥離ひどし
・手洗石:明治□二年
・手洗石:文久二歳正月
大瀬戸の県道より川に下っていくと道祖神と桜がある。
・石製家型道祖神:隣は枝垂桜である。
~県道に戻り北上する。~
県道沿いに祠がある。
・地蔵(新)
・天満宮(小島)
・石鳥居:昭和五十一年
・石灯籠:明治二十七八年
・石灯籠:昭和54年
・手洗石:
・五輪塔:4基、古い、壊れている、
小島橋を渡った向こうの集落はじめの家先に石塔がある。
・庚申塔 大正十四年
その上の方に小島の墓地がある。
・地蔵
・西国三十三所供養塔
・庚申供養塔
・地蔵
・奉西国三十三所
・?西国三十三所
~県道に戻り北上する。~
・木製標識:交通安全供養塔
・山王峠
休憩所:「樅の樹」前の道を上って曲がると坂の上方向が見える。ちなみに曲がるところで川に向かって降りていくと大川自然広場でキャンプ場。
・四十一坂
上り口標識
・唐沢橋を渡ったところに観光案内図看板と記念碑「大川 在来そばの里 大川100年そばの会」がある。その先の川の右崖淵カーブ上に石仏がある。
・馬頭観世音 昭和十五年
その先右カーブ左崖下に祠がある。
・地蔵
~坂の上集落に入る。
・石塔(坂ノ上 東)さかのかみ
・庚申塔:天保五年
・庚申塔:大正九年
・薬師堂(坂ノ上 東)
近くの墓地前に石塔が3つある。堂内には木製仏像群、建穂寺に次ぐ規模、:本尊薬師如来等:推定平安期。五智如来、観音菩薩、十一面観音、天部七体、僧形、神像。
眼病に効くそうだ。
この裏山を上っていった先を兜巾山というようだ。
・右:地蔵
・中:有縁無縁三界萬霊等
・左:葷酒不入門内月向山主□國□□
・坂ノ上神社(坂ノ上 東)
石造物
・石灯籠:安永九年×2
・狛犬:平成三年×2
・石鳥居:昭和六十三年
・手洗石:明治二十九年
・句碑:昭和三年
・割れ目のある石
・御即位紀念:大正四年
・天盃拝領 御即位記念 昭和三年
・改修道路 昭和三年
~ 町内の裏を藁科川が流れ宅地と畑の境の土手際に耳地蔵がある。
・耳地蔵、田の中にあるという。お果たしは穴の開いた石を祀る。今は藁科川の土手際に祀られている。3基石塔が祀られ、
・右が地蔵で穴あき石を首にかけているので、これが耳地蔵だろう。
・中央は「有縁無縁三界萬霊塔」、
・左は地蔵。
???・清名塚、戦で死んだ武者を埋葬したところに五輪塔を祀ったというが不明。分かる方お知らせください。
・陣場河原:かつて戦があったところで、町内を流れる藁科川の河原のこと。
・机平ツクエダイラ:平和協定を結んだところをいい藁科川の向こう側で、吊り橋を渡った先の左上の平坦な大地である(平原氏談)。今は廃棄茶畑と建築業の資材置き場、携帯電話の電波塔らしきがある。おそらく古道は机平上端を水平に通過し、坂の上集落と四十一坂を下った先の茶畑を結んでいたのだろう。
~坂の上集落で公民館横の道を進み、橋を渡り向こう岸へ出て、四十一坂入口方向を目指す。
途中左民家裏に屋敷墓があり、庚申塔もある。(道からは見えない。)
・庚申塔:大正九年
~一旦集落北に向かい、大川保育園横を通過したカーブに石塔がある。小字の南と高沢の境あたりなのか。
・庚申塔:昭和三年
・庚申塔:昭和十年九月宗野ひさ
・庚申塔:大正九年
・石塔?:昭和三年□月吉日
・手洗石:
・花挿し用の石3:中村辰也
~方向を変えて南に向かう。集落南はずれの民家に地蔵がある。
・地蔵
・丸石:道祖神か?
古道はもっと高いところを通っていたのだろうが、自動車道は中腹を通過し途中机平の平坦地を抜け、河原に広がる畑に向かい降りて行き、方向を下流の四十一坂入口方向に変える。ちょうどそこに13基の石仏が合祀されている。ちなみに畑や道ごと金属ネットの檻のような柵で囲われ中へ入れない。平原氏の地所だそうである。
・地蔵:
・奉納 一国三十三所 西国三十三所 文政六年
・西国一国善光寺三十三所供養塔
・庚申供養塔 天明ニ壬寅年
・?観音
・?西国三十三所
・西国三十三所 天明二年
・西国一国三十三所 文政
・西国一国三拾三所供養塔
・?石塔
・?石塔
・?観音
・三拾三所供養塔
~県道に戻り北上する。~
坂ノ上神社山下の道を抜けると宇山集落である。ここからも坂ノ上神社の裏から上る道がある。
・坂ノ上神社への参道(坂ノ上 宇山)
古かった参道は新たにコンクリート舗装され神社まで車で行けるようになったが、古道の赴きは消失。神社のある尾根付近で畑色へ向かいさらに洗沢峠を目指す古道(秋葉街道の枝道)があるはずだが、新しい参道から分岐点目視判別不能なので、よじ登ってみたが、新道から尾根に上がったところは炭焼き小屋跡で尾根上に踏み跡はあるが、特に分岐点を示す石道標や歴史遺物は見られない。
~県道に戻り、宇山集落、宇山バス停付近、「八幡まで8.5km 笠張峠まで24.0km」標識のある所に石塔物がある。
・奉
・庚申塔
・奉納 森藤□□蔵
・馬頭
・石塔
・手洗石:奉納 永野
・地蔵
???・平石:バス停より徒歩2分上に、名馬摺墨と老婆の足跡がついているという。かつてあったようだが今はない。分かる方お知らせください。
・この先「巽荘」という看板の?元酒屋がありその先は茶畑で、その茶畑を上っていき北の尾根を目指す登山道がある。かつては畑色や上杉尾を経て洗沢峠にいけたようなので
秋葉街道の枝道として登山口を調べてみた。登山道入口付近に石道標や遺物は見られない。
○~坂の上から県道北上し、この先で立石橋を渡ると左川沿い道が本道で右上に上る道が栃沢への道~ この道は県道大川静岡線。
かつては奥長島から栃沢に抜け坂ノ上等に出るのが本道だったようだが、自動車道が川沿いに作られて一変した。
この分岐点のカーブミラーの真下の暗がりに石造物がある。
・石道標:とちさわみち
・馬頭:
・□□□観世音:壊れて横倒し
~栃沢を目指し上っていく。~
○栃沢
左が山の崖になると石仏がある。
・庚申供養塔 大正九年
栃沢の家が見え出すと神社入口がある。
・子安神社(栃沢)
・祝大正十五年車道改鑿
・火坊鎮守
・板碑:
・石灯籠2:昭和三十(廿の三本)七年
・鳥居:金属製
・石鳥居:?
・板碑:
・石灯籠2:弘化四年
・狛犬2:昭和四十二年
・手洗石:明治三十二年
・手洗石:慶応四戌辰
・手洗石:
・祠2
主要道を奥へ進むと米沢家で聖一国師碑がある。
・米沢家(栃沢)
???聖一国師生家、摺墨の馬蹄石(見られない)、
・聖一神光国師誕生地 昭和七年
・句碑:昭和三十八年
・三夜燈 安政四年
・三夜燈 寛政十一年
・庚申塔 大正九年
・?庚申塔
・石塔:家の門前
・石灯籠2:弘化四年:家の裏
・祠
・五輪塔
・墓石2
裏に自宅墓地がある。
手前のお宅の庭にも石塔がある。
・石塔:記念
更に主要道を奥に進むと寺がある。
・竜珠院(栃沢)
木像:薬師如来
・六地蔵:?
・手洗石:
・有縁無縁三界萬霊等
・三界萬霊塔
・有縁無縁先祖代々精霊等三界萬霊
・祠、小さい地蔵多数
・割れ石
・□神山
・鎮守
・割れ石
・祠:弘法大師
・観世音
・水差し石
・花挿し石2:
・如意輪観世音 大正十二年
寺を過ぎもう少し進むと岩の上に石仏がある。
・馬頭観世音
更に奥に進むと突先山ハイキングコース、ティーロード入口標識となる。この道が釜石峠を経て足久保に至る古道といえる。釜石峠には通称:歯痛地蔵といわれる如来(石道標にもなっている)が祀られる。
3月にはこの入口付近に淡い黄色あるいはカスタードクリーム色といった色合いの花が冬枯れした野に咲いている。近づくとほんのり上品な花の香りが漂ってくる。枝先が3つに分かれていてミツマタの花だ。枯れ枝に似たような色合いのため地味で目立たず、遠目にはあまり綺麗とは感じられないが、香りはよく春を感じさせる。この時期各所で遅咲きの梅の花や桃花、早咲き桜とともに遭遇した。
○釜石峠 (*美和街道を参照)
奥長島と栃沢の峠。歯痛地蔵と呼ばれる大日如来が祀られる。かつてはお堂もあったようだ。大川から静岡市街に出るにはこの道を通った。
峠から南尾根を通ると突先山に至り、さらに大山を経て坂本に出られた。
峠から北尾根を通ると中村山△1007.0mを経て樫の木峠に出られ、玉川または大川に下れた。現在樫の木峠から中村山方向への尾根道は、一見すると藪道のように見受けられる。
釜石峠H820m。以前と峠の位置が変わったような気がする。この峠、平で広く東西50m幅ある。以前標識や歯痛地蔵は東端だったと思うが、今は西端である。歯痛地蔵(大日如来像)「是より 右ハ美和村あしくぼ 左ハ玉川村たくみ」となっていて、東の足久保奥長島と北の中村山・樫の木峠経由内匠へのコースを示す。西へ下る道は栃沢へである。
・歯痛地蔵:大日如来「是より 右ハ美和村あしくぼ 左ハ玉川村たくみ」
この先は美和街道・足久保街道である。*玉川村は安倍街道を参照。釜石峠や突先山周辺に関しては兵藤庄左衛門・Seeesaブログ・スポーツ・玉川トレイルレースを参照。
~県道の栃沢分岐点に戻り日向に遡上する~
バス停「森林組合前」の日向集落手前に橋がある。この辺りを森の腰というらしく、人家や石垣がある。かつて日向の白髭神社ははじめ松の平にあったが、次に森の腰に遷座した。その後今の場所に移転したようだ。石垣は近代のものだろうが人が生活していた家や畑の証拠とも言える。橋があり対岸に渡ると切杭である。橋を渡った正面に小長井宅(屋号ヨコベエ)があり、このお宅に許可をもらい家の横から裏山に上らせてもらう。家のすぐ裏には屋敷神の祠があり、裏山急斜面を3分も登ると祠がある。
・切杭天神が祀られている。さらに裏山を上っていき畑色に至るだろう切通しの旧道が伸びている。きっと途中で廃道だろう。ただ地図上ではそれほどの距離ではなく上の畑色の舗装道路に至れるようだ。上に道があるだけでなく、今の舗装された平地の道より上の山斜面上の今の道より20mほど上の植林地内を等高線に並行した旧道が付いていることも確認できた。 またこの上の方に池の段という昔の池の跡があるようだ。伝説ではこの池から土石流が流れ地形を変えたようだ。池の主の蛇が出て行ったというのは土石流の流れ跡をさすようだ。切杭には土石流が流れる前まで生えていた大木の根株が時々露出することがあり、まさに切杭である。
もう少し切杭側の藁科川を上流側に畑に沿い舗装道路をつめていくと行き止まりとなる。行き止まりの10m手前から山に取り付く登山道があるので上っていくと5分で、切り立った細尾根先端部に出られ向こうはフドウボツの沢である。細尾根先端部山頂には祠がある。
・不動明王(石仏)が祀られている。藁科川対岸はちょうど福田寺のある丘が正面に見える。
・伝説「切杭本社の木魂明神」
日向に原坂宅に美しい娘がいた。ここに毎夜美少年が通ってくるようになった。どこの少年か不明で、母は娘に少年の袴の裾に針で糸を縫いつけるよう指示し、そうしたところ、糸は大木まで続いていた。少年は大木の精だった。大木を切ることにしたが、切っても切っても翌日元通りになっていた。そこで切った屑をすぐ焼き捨てては切っていったところ、木はキリクイという異様な音を立て倒れた。ここをキリクイという。
その大木で空船ウツロブネを作り、娘を乗せ川に流した。安倍川の舟山で船が転覆したので、そこを舟山という。途中赤沢の対岸に娘の櫛が落ちたのでそこを櫛筐峠クシゲ(クシバコ)トウゲというそうだ。
この大木は高さが33間、梢を杉尾村で望めたので、そこで杉尾という名になった。原坂家では麻を作らないようになった。またこの家で生まれる女子は美人だといわれる。この大木老杉を木魂明神という。
~ 集落入口の県道に戻る。
日向 小向の集落入口に達する。崖上の2箇所に石仏を祀っている。日向の地名は日当たりがよい東または南向きの場所を指すそうだ。ここの地形は古くからのものではなく川の流れの変容により変化したと考えられている。
またこの藁科川と籠沢が合流する辺りには大木の根元の株が出現することが近年まであり、キリクイ切杭の伝説となっている。イケノダンが決壊しマコモノハラを押し流したという。その土地には大木の切り株(切杭)が今でも出るというので切杭という。
・マコモノ原:日向字堂上で大川小学校前の平坦地を指すようだ。
・小長井家屋敷跡:大川小学校の辺りのようだ。
○石塔(日向 小向)
○馬頭観音8基
・大正十五年
・大正十年
・大正十三年
・大正十三年
・為紀念征露
・明治二廿一年
・明治四十年
・明治二十一年
かつて字(アザ)チャアラと字ヤスミイシの境である。ここに馬頭観音を祀ってあるのは、昔から急カーブ地点で馬がよく落ちたからだそうである。
○庚申塔7基
年号は明治38(1905)年から昭和12(1937)年まで。
・昭和十年
・明治四十二年
・
・
・昭和十二年
・昭和十□年
・明治
川沿いに通過するのが新県道であるが、集落内に入る道が旧道であり、旧道に沿い進む。
集落内に張り出した舌状大地の上が神社と寺である。そしてそこへ上って向こうの小学校に下る道が古道である。
ちなみに手前右に林道起点ある。
○~林道:樫の木峠線、この龍沢を奥に詰めて行くと樫の木峠に至り玉川内匠に昔は出られた。幕末明治期探検家:松浦武四郎「東海道山すじ日記」はこのルートを通過している。~
・樫の木峠
途中、祠(剣宝社、けんぷん様)、萩多和城跡石碑通過。峠には幕末期石地蔵1基。そこから林道で川島に出られる。地蔵近くから旧登山道を下り白石沢沿いに内匠に出られたが、おそらく廃道同然か。
・飛神天神:日向集落出口から樫の木峠へ向かう旧道付近を指すようだ。今の林道より20mほど上になる。集落上部から山の中に入る旧道と推定される人為的平坦地の幅1~1.5mが部分的に残存しているので、これが旧道(古道)と推定される。この道を松浦武四郎も通ったはずだ。かつては何かが祀られていたのかもしれない。ただ地元でもトビガミテンジンといっても不明で、集落と山の境付近の上(林道出入り口より真上)の天神テンジンといえばわかる人がいる。ただテンジンと言うと、けんぷん様の先にある天神を示されることが多いので混同注意である。集落の人への言い方としては、昔山の畑に行く時に通った村集落と山の境の天神はどこかと聞いたほうがいいかも。
このトビカミテンジンの旧道(藪で道とは思えないが、人為的平坦地なので、かつての古道と判断できる)を奥に10mも進むと開墾された茶畑上部南端に出る。ここで一旦旧道は消失するが、茶畑を北へ水平移動していくと、北端の動物用罠の檻上部に平坦地があり、奥に進める。すぐに建物の後背部に到達し後背部に沿って平坦地が続いている。更に進めそうだがここでやめた。地図上ではあと数十mで沢に達するのでそこで道は消失するだろう。
・祠(剣宝社、けんぷん様):昔女性の修験者(巫女)が、この先、於万津ケ淵の滝壺で亡くなり、里人がここに祀ったという。歯の神(山里に多い)・山の神と里人に祈願崇拝された。歯の痛いとき、けんぷん様を拝むと治ると昔から言われている。治ったお礼として剣を奉納した。~「野山の仏」戸塚孝一郎より、取付:城北、坂本~
現在林道脇に祠と説明書きが見られる。
・お松が淵:けんぷん様の先にあるらしい。於万津ケ淵。
・天神:けんぷん様より更に先で旧道が籠沢沿いから尾根道に移る辺りで、林道が籠沢からヘアピンカーブして沢をまたぐ橋を渡り沢から離れ山斜面に急激に登り出すところで、ちょうど「夕暮れ山・樫の木峠登山道」が山斜面に取り付くところで登山標識がある。林道より高いところを通っていた旧道が一旦沢に降り沢を渡る辺りを指すようで、林道をまたぐ橋のすぐ横の茶畑付近を天神というようだ。かつては何かが祀られていたのかもしれない。
*以下に、樫の木峠や一本杉峠の参照用に、兵藤庄左衛門、Seeesaブログ、「夕暮山、中保津山、樫の木峠」を全文掲載する。
・夕暮山、標高1,026m(静岡市葵区内匠と大川の境、樫の木峠の北1km、一本杉峠・天狗岳の南2km)及び、中保津山、樫の木峠
夕暮山への場所は上記の通り。登るには林道樫の木峠線を使い樫の木峠を目指すか、一本杉峠を目指すかである。大川・日向で林道樫の木峠線へ入り3km進むと大きく広く右カーブする所がある。ここに標識「樫の木峠、夕暮山」がある。徒歩ならここから登るのがよいが、道の状態は知らない。植林内で踏み跡はし
っかりしているかもしれないが、雑草はあるだろう。車なら林道を詰めたほうがよい。登山道もこの上で林道に合流し林道歩きになるので。
林道をさらに2kmも行くと先ほどの登山道と合流する。林道をなお進み夕暮山の南西尾根の△769.3mより上の辺りで「萩田和城址記念碑」と説明版がある。これを過ぎて0.5kmで切通しをくぐる。ここの左(北東)尾根に標識「夕暮山→」がある。ここから登るのが最短なようだが、いきなり雑草だらけなのでやめたほうがよいかも。この上で林道一本杉線も横切っているので、その林道を行ってからこの尾根に取り付く手があるかも。林道樫の木峠線をさらに200mも進むと左に林道一本杉線があり、工事中となっている。上を仰ぐと先ほどの尾根を上で横切っている。ここを通って上で尾根に取り付けそうだが、未実施。林道樫の木峠線をさらに進む。10年9月林道が急に荒れギャップがひどい所があったが、500mで樫の木峠へ出た。ここに石仏一つと樫の木がある。ここから北西尾根へ標識「夕暮山・造林展示林→」があり、もっとも無難な尾根コースだろう。夕暮山からさらに北へだらだらの平坦尾根を通って天狗岳や一本杉峠へ縦走できる。展示林となっているから少しは道が整備されているかもしれないが、未確認。樫の木峠から南へ尾根を伝うと中村山へ通じるが、峠から南へは雑草だらけで、踏み跡をたどるのはきつそうだ。標識も無い。
一本杉峠・天狗岳へは玉川・横沢から井川・富士見峠への県道を行き、権現(臥竜)の滝を過ぎ500mで一本杉峠登山道がある。これを詰めるか、反対側の大川・諸子沢を詰めるかである。しかし一本杉峠の南西尾根を詰めることもできる。横沢から井川・富士見峠への県道を富士見峠手前の笠張峠で大間へ曲がるか、大川・湯島から大間を経て笠張峠方向に行く。切通しの分水嶺を横切ると、林道一本杉線の看板があり、南東尾根に沿い林道が延びている。左に別の作業道も分岐している。林道はそれほどアップダウンはないが、ギャップなどが多く荒れている。3km進み△1013.3mのピーク(中保津山)手前500mで林道が2つに分岐する。
右は別の林道で4.5km尾根を進んだ諸子沢の上辺りで行き止まりである。が、工事中で延伸するのかもしれない。
左の林道を進む。中保津山を右へ巻くようにして平坦な尾根に出る。ここも道が分岐し左は私有地でチェーンが張られている。右にまたピークを巻き尾根道が下りだす。この下に一本杉峠があると思われるが、夕方で引き返す。後日再調査予定。峠までは林道はあると思われる。
先ほど樫の木峠の近くにも林道一本杉線の看板があったので、そことつながるはずだ。10年10月、大間の県道から一本杉峠辺りまで林道はついているようだ。この先天狗岳や夕暮山の尾根の西を通過してつながるものと思われる。
△1013.3mのピーク(中保津山)へは林道の雑草の切れた辺りからピークを目指せばよいと思われる。諸子沢上への林道しか無い頃は林道がピークを巻く辺りから踏み跡をたどって登れた。今も草を掻き分ければ標高差わずか30mほどで登れるだろう。
樫の木峠へ話を戻す。樫の木峠の石仏の左横に下る踏み跡がある。かつての「白石沢ルート」である。林道が開通した今となっては使う人はまれだろう。80年代末に通ったことを報告する。内匠の白石沢の横を通る林道白石沢線を2.5km詰めると行き止まりで堰堤となるが、登山道は奥に続くので徒歩で沢沿いを行くとすぐに石仏がある。自分では道なりに進んだつもりが、この石仏の所で道は分岐していて本当は右に行くのだが、間違って直進した。樫の木峠への沢より1本南の沢を詰めてしまった。沢沿いにきれいな林業用作業歩道が付いていてそれをひたすら詰めたが、何か変なので引き返し地元の人に話を聞いたところ、石仏のところで間違ったことを知った。
後日再アタック。今度は石仏で右折し沢横を詰めていく。峠直下と思われるところで、沢を渡る。ここにも石仏があるとのことだったが見ていない。渡ってしばらくすると急斜面を巻いて登りだす。登りきると峠である。
これらのコースは、登るなら雑草や蜘蛛の巣が少ない11月下旬から6月初旬までが最適だろう。
~日向集落内旧道を進むと右上に寺と神社がある。
ちなみに樫の木峠・籠沢から来た秋葉道(樫の木峠林道より20m上で集落最上部の家の裏山を下ってくる感じである)は今の集落や畑と裏山の境の辺りを回りこみ白髭神社・福田寺に上ったようだ。
付近のお宅には屋敷墓があり、その中に供養塔が混じっていることもある。
付近の屋敷墓で
・先祖代々有縁無縁三界萬霊等 明治十九年七月日
上記を発見したが、まだまだ他のものはあろう。
○白髭神社、朝旭山福田寺観音堂(日向 千田)
白髭神社はもとは能又川と藁科川が合流する手前の松ノ平にあったと伝えられる。松ノ平は下湯島手前から下に降りる林道を下ってすぐの茶畑のところである。本社白髭大明神、藁科八社ともいわれた。
・DVD「日向の七草祭(静岡市) 静岡県指定無形民俗文化財」静岡市教育委員会、ふるさと民俗芸能'ビデオNo.5、'93、27分
安倍川支流の藁科川を車で40分遡ると静岡市(旧大川村)日向集落で、日向は静岡市山間部の旧秋葉街道沿いで中世に城もあった大川地区の中心地で戸数88戸である。産業は水田、林業、茶、椎茸である。七草祭は旧暦1月7日の七草の夜に行われるための呼称である。場所は朝旭山福田寺観音堂境内の仮設舞台である。フクデンジ。
川根本町田代・大井神社の神楽との類似性が指摘される。かつての領主土岐氏の勢力範囲に重なる。西遠州の猿楽・田楽の流れを汲む稲の豊作を祈願する田遊びである。付近には大間(福養)の滝(大間)、聖一国師の生家(栃沢)、(日向)陽明じには「木霊明神の縁起書」:切杭本社は川底に水没したが、庄屋の娘と木の精の大蛇との悲しい物語、大蛇の子を孕んだ娘は空ろ船で川に流され、あとを追った母が娘をこいこがれた場所が木枯らしの森という。藁科川流域には建穂寺(観音堂)という巨大寺院がかつてあり、福田寺とも関係していたと考えられる。
祭りに先立ち毎年持ち回りの8軒の当番は様々な行事を行う。大浜海岸、潮花汲み:海水で祭りの場や家々を清める。浜石も採る。柳採り:柳の枝を切り取る。陽明寺和尚が絵馬札刷り「牛王法印」を行い、その紙を柳に挟む、札は祭り当日村人に配布される、札は豊作願い田の水口に挿す、舞練習は日向町内会集会所、大人に混じり子供たちも熱心に笛太鼓を行う。旧暦正月6日(この年は1月28日)、大日待頭屋:会食料理、床の間に浜石と潮花、境内では清掃と舞台作り、大日待の料理作り、各家々へ潮花配り:仏壇や家屋内を清める、頭屋では餅つき:丸餅とのし餅、水に漬けておいた米で「はたき餅(シットギ)」、大川地区連合町内会集会所:大日待行事、日向地区各家代表集まり会食、浜石、潮花、はたき餅、今は料理一部仕出しだがかつては割り子に詰められたもの、舞揃え:舞練習総仕上げ、旧暦正月7日(この年は1月29日)七草祭当日、町内会長が観音堂の厨子を開き掃き清める、福の種、お供物、万延の詞章本、寛永の詞章本、翁面箱、笹竹13本、3本使って舞台中央に組む、重しに浜石使う、舞台が神聖な場であることを示す結界、日の出祈祷、御詠歌、抹香を酒で溶いたものにネッキという棒で牛王の印をつき札作り、ネッキの一方「牛王」反対側「仏法僧」というが定かでない、参拝者の額にも押す、一年の無病息災、36本の御幣、小豆入り餓鬼の飯を境内各所に供える、境内清め、大地の神を鎮める、施餓鬼:観音堂裏山宝篋印塔、水垢離:一日7回水清め、今でも1回は藁科川で清める、夕方7回目の水垢離代わりに笹垢離をとり舞台に向かう、見物人いっぱい、
構成は1、歳徳神礼拝トシトクシン、2、大拍子、3、申(猿)田楽:舞手6人輪、中に笹竹、幣の色で役割、笹持って回る、扇子で胸当て袖持って足挙げ、体を回す、拍子が速くなり扇子打って回る、笹竹13本舞台上げ、4、駒んず:笹竹根元足で固定し揺らし打ち合わせ詞章を囃す、春駒、繭豊作、馬と山鳥、馬は蚕の始まり伝説由来、山鳥は蚕のはきたてに羽を使うため取り入れたらしい、5、浜行:背負う桶に海の幸、潮花を神前に供え、滑稽に海幸配り、・若魚ワカイオ:近隣の神楽「オオスケ」と同じく神の一種、神聖な海水を祀り神々の祝福によりて五穀豊穣を約す、・(近年付加)女の子の舞、・順の舞、2回繰り返し、初めは試し上演と考えられる、浜行若魚2回目、滑稽バチ男根見立て、潮花振り掛け清め、(休憩)、後半が本上演と考えられる、翁面と詞章本を舞台上に出す、6、歳徳神礼拝、7、大拍子、8、駒んず、9、数え文カゾエモン:太鼓に米撒き田に見立てて、神歌、稲草、福の種、鳥追、田植、穂孕み、取り入れの内容で村の歴史とかかわるのだろう、福の種と鳥追に所作あり他は詞章のみ、、10、猿田楽、このあと一同本尊礼拝終了、
このあと今は福引。
旧暦1月15日(この年2月6日)、鈎取の佐藤家、太鼓の田に撒かれた米で粥作り、家屋内に供え、福田寺にも供え、粥を食べ、村人への活力を分け与える。
・朝旭山福田寺:建穂寺の奥の院。以下木製、千手観音坐像:推定江戸期前半、彩色なし菩薩像:推定平安期:欠損している、二天像:東方天・西方天:江戸期前半17世紀後期~18世紀初期、
・白髭神社:春祭り4月第1日曜日、秋祭り10月第3または第4日曜日、男女神像:江戸期後期、保存状態よくない、木製、
・石鳥居:大正十四年
・石鳥居:平成八年
・手洗石3:
・石灯籠5:昭和九年…2、□永九年、
・石碑:昭和十二年
○庚申塔38基、割れ石 (44基?)
年号は宝暦二(1752)年から昭和三十(1955)年まで。日向では個人的に病気平癒の願果しとして建てることがあった。個人名を刻んだものも多い。造立数の多いのは大正九(1920)年の7基である。
*一般的には庚申塔は、更新講中により庚申縁年(60年に1回巡ってくる庚申年)に建てることが多く、他にも合力祈願や供養として建てることも多い。
庚申講は、庚申の日が60日に1回巡ってくるので1年で6回は行った。庚申講は床の間に青面金剛の掛軸を掛け、全員で唱えごとを21回繰り返してから拝む。その後飲食をするのが楽しみであったようで、信仰心と、娯楽としての宴会、世間づきあいの世間話で盛り上がり、庶民の楽しみだったようだ。当番は輪番制であった。(「日向の七草祭」より引用を含む。)
・大正五年:後列右より
・大正八年
・
・
・明治三十(廿の3本)六年
・大正八年
・
・大正四年
・昭和十一年
・明治三十(廿の3本)八年:後列2列目右より
・
・明治十八年
・明治三十(廿の3本)三年
・大正元年
・昭和四年
・
・明治四十四年:後ろ3列目右より
・明治四十年
・大正九庚申年
・大正九庚申年
・大正九庚申年
・大正九年
・
・大正九年
・昭和四十四年
・割れ石
・昭和十七年:最前列右より
・昭和七年
・大正九年
・大正十二年
・昭和八年
・昭和十九年
・昭和三十七年
・昭和九年
・昭和三年
・□□□年
・昭和十四年
・大正十二年
・昭和□□
裏山に上っていくと
・祠:弘法大師
・秋葉山三夜燈 寛政十一年
裏山の頂に立派な宝篋印塔がある。
・宝篋印塔
またここは萩多和城の南朝方支城の一谷城跡である。尾根伝いに上っていくと萩多和城跡に行くし、夕暮れ山や樫の木峠にも行ける。尾根より下の神社から中腹を通っても行ける歩道がついている。一谷城用水路跡で樋道という。突き当りは樋口という。現在、尾根道には夕暮れ山ハイキングコースの標識がついている。
先ほどの尾根コースと反対に福田寺西側の丘上は畑と墓がある。どうもこの墓のことを
・ネギヤの屋敷墓というようだ。
尾根と西側丘の間に空堀のような切通しの道が下っていく。
・古道
小学校方向へ下る古道をとる。御堂坂という。学校手前で旧道舗装路に出る。わずかな距離だが古道残存部である。学校前の平地の辺りをマコモノハラというらしい。学校前の旧道をたどると学校向こうで立派な門が見える。その先に寺がある。ちなみに古い秋葉街道は旧道より1本川寄り(新県道寄り)の狭い道である。
・農家の茅葺の門
○陽明寺(日向 中村)
開基:雲叟、1510年、日向村に一草庵、
・六地蔵(新)
・石製家型道祖神
・石造物(古)
・地蔵
・地蔵
・□□巡霊等
・地蔵(新)
・板碑
・忠魂碑
○1列に並ぶ石仏
・地蔵:明治二十七年
・?馬頭:明和七庚寅天
・?馬頭:明治二十四年
・?如来
・?馬頭:法傳 諸子沢村
・如来:
・西国三十三所
・十一面観音:諸子沢村 送精
・馬頭:八手、?阿弥陀、大きい:大正十五年
・馬頭:大正十年 佐藤善作
・西国三十三所供養塔 明治十九年
・馬頭:明治五□
・馬頭:八手、
・?馬頭:
・?馬頭:森下常吉立
・観音:
・馬頭:昭和十三年
・地蔵:
・地蔵:
陽明寺前の旧道を下るとすぐに今の(新)県道に出る。その県道向こうの河原に向かうとすぐに石道標がある。掛川市在住の広谷氏の報告及び「日向の七草祭」所収されたものである。
・石道標:右湯島諸子沢 左洗沢秋葉山 道
近代のものであろうがルートとしては近世に準じたところにある。ただこの下につり橋があって渡れるがそこから先に道は消失している。この上の茶畑の石道標につながる道は新たに舗装路を作った際消失したようだ。広谷氏によれば東海道山筋日記コースを東京から西に向かってきて、初めて目にした秋葉山の道標だそうである。
~県道に戻り奥へ進む。~
・新しい地蔵(日向 中村)
八幡へ11.5km表示近く県道沿い。
○~この先、城山橋のところで右折で諸子沢、左折で城山橋渡ると畑色・杉尾に至る。いったん諸子沢に向かう。~
○諸子沢 モロコザワ ・大道島
・白髭神社、大日堂
右折してすぐに白髭神社、大日堂の標識がある。100m上ると境内である。神社の祭りは2月建国記念の日、10月第2日曜日。
・石鳥居:昭和二十七年
・手洗石:寛政十戌午十二月吉日
・奉納大日如来 寛政十年
・石灯籠:奉納白髭大権現 寛政十年
・石製家型道祖神
・馬頭観音 昭和廿二年
・馬頭:享保二十年
隣にお堂がある。
・大日堂:木製:大日如来、薬師如来、弥勒如来:江戸期
~更に諸子沢を進むと時計台(新)や花壇を通過する。次に平の尾や地蔵堂への分岐点が上を目指すので地蔵堂へ行く。
○地蔵堂
前に石仏が合祀されている。じぞう祭りが8月24日にある。
・手洗石:三角形
・庚申塔
・庚申塔 昭和十二年
・庚申塔
・庚申塔 昭和十五年
・庚申塔
・庚申供養等
・庚申塔 大正九庚申年
・?石仏:
・?馬頭観世音:
・西国三十三所 文久二壬戌七月
・奉納西国三十三所 明治拾八戌年
・石仏:□□二十二年十二月建
・石仏:割れている
・ほていさん(新)
・西国三拾三所
・?石仏:転倒
・?石仏:割れている
・西国三十三所 明和
・?石仏:割れ
・西国三拾三所 天保三壬辰
他にも割れたり崩れたりしていていくつあるか正確には不明。お堂の前を旧道(古道)が下っていくのが分かる。一部古道残存。
~また舗装路を戻り奥に進む。舗装路の上に寺が見える。日陰橋手前道沿いに石塔がある。
・庚申塔
・庚申塔 明治四十二年
・庚申塔
地蔵堂の上を目指すと平の尾集落である。
・平の尾:急斜面沿いに集落が展開している。この更に上に向かい林道が続いている。
・雨降松開拓地:林道が尾根に到達した所の平坦地で茶畑が続いている。無人だが家が1軒ある。かつて雨降り松なるものがあったようだが、今はない。そこはちょっとした空き地というか公園みたいな休憩所になっている。
*この上の平の尾と大間方面は山越えの林道でつながっているが、そのことは「インターネット、兵藤庄左衛門、さぽろぐ、林道一本杉線」を参照してください。一応全文掲載します。
・林道一本杉峠線(静岡市葵区、大間~一本杉峠~天狗岳~夕暮山~樫の木峠~大川)まだ工事中でつながっていない、林道川久保線、林道峯諸子沢線、林道八重枯線、林道京塚線、及び付近の作業道
実は(静岡市葵区、大間~△1013m「中保津山」~諸子沢平の尾~川久保)
2010年10月、天狗岳から夕暮山区間は工事中で、一本杉峠付近はまったく手付かずであるらしい。
大間の南アルプス公園線県道分岐から一本杉峠の1km手前の△1013m「中保津山」までは林道になっているが路面はギャップ(クレバス、えぐれた溝)があり、通行しにくい。樫の木峠近くの林道樫の木峠線からの林道一本杉線への分岐は工事中通行止めである。おそらく夕暮山付近で工事中と思われる。
大間の県道分岐へは藁科街道を上り、湯の島や大間集落を通過し福養の滝レストハウスを抜け、笠張峠方向へ県道を進む。地すべり箇所の赤い回転灯の1km手前の切り通し箇所で東に分岐する「林道一本杉峠線」標識がある。すぐ左に林道「京塚線」があり道も開いているが、どうも行き止まりらしい。途中いくつかの林業用の作業道も横切っていくが、多分どれも行き止まりだろう。直進で2km進むと右へ下る「林道八重枯線」がある。多分「国土地理院、地形図」の・1037mから・878m付近の尾根をたどる道と想定される(が間違っているかもしれない)。
もう1km進むと道が平坦でY字に分岐する所に出る。分岐点の中央奥にあるピークが三角点所在地△1013.3m「中保津山」である。ただ山名が本当にこの名前なのかは不明である。十数年前に上ったときにこの山名のプレートがあった。ここから尾根沿いを歩いて上っても10分足らずだ。今回2度目に上ってみて三角点はあったが標識はなく、付近の様子も植林の暗い中でそのことは前回同様だが、測量されたらしき雰囲気がない。測量すると付近の樹木や草を刈り払い標識を立てるように見受けられるが、そういう痕跡がない。国土地理院は4等以下の三角点をあまり用いなくなってきているのか。登山道は送電線巡視路になっているので踏み跡はしっかりしていて草刈が行われているので信用度は高い歩道だ。中保津山を越えて尾根をさらに東へ1km歩けば一本杉峠に至るはずだが、今回は時間が無くあきらめた。
話をY字路に戻す。左の道は「私有地で立ち入り禁止」とあり、チェーンが張られている。この道は作業道で1km先の送電線まで進み下り出し、臥龍(権現)の滝のある井川へ行く県道方面へ下りかかって行き止まりになっている。
Y字路を右にとる。500mも進むと道が下りだし、道がひどく荒れギャップ(クレバス、えぐれた溝)が多く、ダイハツ・ハイゼット660cc では道幅全体の中の通りやすい所を選んでゆっくり通過したが、たまに車底をこすった。オフロード車はがんがん通ったがこちらはまねできない厳しい道だった。4WDスイッチがあって助かった。この部分の道を上ることもしたが4WDでないと上れないだろう。1km下ると平坦になりついでに舗装までされている。見晴らしがよく送電線高圧鉄塔に沿って道は南南西に進む。舗装が切れるが道は直進している。そこの右から「川久保林道」が合流してくる。
「川久保林道」は藁科川沿いの県道を湯の島から大間に向かい2km上って行くと、右に「川久保林道」の標識と上る道が見える。この林道は一応コンクリート舗装がだいぶされているが、クラック(割れ目)だらけででこぼこといっていい。しかし土道に比べればはるかに通行しやすい。4~5km上ると尾根の林道に合流する。途中幾度か作業道が分岐するが、そちらは通行禁止の標識があるので道を間違えにくいとは思う。(13年3月林道入口改修工事中で出入り不能。)
話を尾根の林道の川久保林道合流点に戻す。さらに直進していくと送電線付近は眺めがよく高原の草原のようだ。草原を過ぎると道は下りだす。しばらく行くと「林道峯諸子沢線」の看板がある。しばらく下ると茶畑と人家のある所に出る。「雨降り松」の休憩所もある。ただ松の木は見当たらなかった。人家はあっても現在休憩作業用らしく無人である。ただここからの林道は道の状態がよくなる。普段から人が使っているからだろう。2~3km下ると平の尾集落に出る。ここからは急坂で狭いが舗装路となり、諸子沢の主要道に出て、藁科川沿いの県道に戻れる。
「平の尾」集落を下っていき大道島へ行く諸子沢本道に出る手前に「地蔵堂」があり、石仏も多数あり、古色が漂う。他にも藁科川沿いや諸子沢川沿いの道に石仏が見られ古色ゆかしい。
・吉祥寺(柿の平)
・石塔(新)
・石塔(新)
・地蔵(新)
・臼
大道島を目指す。自動車道の終点で堰堤の向こう岸がどうも峠入口らしい。
・一本杉峠上り口:はっきりしない
???・頼朝石:未確認
この奥?に頼朝石があるらしいが、20年以上前に上ったときもはっきりせず、堰堤工事が進み川岸がだいぶ削られ登山道もはっきりしない。わかる方お知らせください。
○~県道に戻り、城山橋を渡り、畑色方向に進む。~
城山橋を渡ったところですぐ右(北)に歩道を探す。畑色と能又川(よきまたがわ)の中腹にあった集落「藁山わらやま」、「道光どうこう」に向かう道であり洗沢峠に至るルートでもあるので、一応秋葉街道の枝道として何か道標等歴史遺物はないかということで探してみる。山尾根に向かう登山道の切通しを発見するが道標等はない。この登山道が今は廃村になった集落「道光」を通過しさらに畑色の別荘地奥の養鶏場に出られる道のはずであるが、今は手前集落「藁山」はなく、奥側集落「道光」も1軒と少しの畑だけが残っているようだ。
さて畑色方向へ舗装路を進む。さて藁科川に突き出すように丘がある。
・城山:藁科川に突き出す小山、城を築こうとしたが矢が対岸から行ききってしまうので築城をあきらめたという伝説がある。
・石道標(日向)
掛川市在住の広谷氏や「日向の七草祭」で報告されているものである。対岸の中村の秋葉山道標と川を挟み対のようになっている。
城山橋より200m進み茶畑のある両側山のある城山の小さな峠を越えるところの右茶畑にある。
「従是 右往還 左秋葉道 天保五年甲午正月」。幕末明治期探検家:松浦武四郎「東海道山筋日記」はこのルートを通過している。この茶畑から尾根に取り付くが道は部分的にしか残存しておらず、強引に上る。途中滝を巻きその上部で沢を渡り上に上る。茶畑最上部の左下から作業道が伸びるのでそれを上る。そのうち作業道が下るので、尾根の旧道切り通しらしきを上る。廃屋小屋を通過すると上り道消失するので尾根を強引に上ると畑に出る。畑の左に上っていく道があるので行く。すぐ道は消失するが尾根を強引上りすると、畑色のメインストリート(主要道)舗装路に出る。10m先で舗装路は左に折れるが、尾根は正面なので正面上りの廃屋別荘地廃道に取り付く。右下に分岐する道もある。廃屋別荘地廃道を上って行くと新しい別荘地の道に出た。別荘地の道を上ると舗装路「林道畑色支線」に合流し、右(東)に養鶏場、左(西)に行くと山賊鍋ウッドカッター店前で主要道舗装路に出られる。どうも古道はこの合流点辺りで尾根に上っていったものと思われるが、現在まったくなし。山賊鍋店に行き舗装路に出て舗装主要道を東へ。尾根横に並行に進む。おそらく古道と同じルートではなかろうか。
話は変わるが、先ほどの養鶏場の下方向に行く道がかつてはあり、能又ヨキマタ川まで出られて途中に集落「道光」があった。昭和53年修正測量・国土地理院地図には人家があることが確認できる。現在、道は廃道か。
・蓄魂碑(日向 畑色)
別荘地の陽光台付近の尾根で別荘地入口横にある。かつては山神が祀られていたか。現在新しい「蓄魂碑」がある。隣に壊れた石があり山神なのか。もう1km尾根を進むと洗沢峠であるが、尾根下を通る舗装路があるので、尾根は廃道同然だが、私を含め物好きは強引に突っ切って峠に至れる。部分的には旧道切り通し残存。
この先で尾根に出て尾根左へ主要道、右に私有地林道、尾根の植林地内に取り付く。はじめは旧道切り通しがあるがそのうち消失、峠には1km。途中茶畑がある。
・大黒様、茶畑の神様(上杉尾)
尾根が茶畑になる箇所がある。真下に上杉尾の人家(おそらく上仲家、佐藤家)がある。茶畑に現代の大黒様があり、祀られたあとがある。設置は新しいが、祀られる行為は古くからあるのではなかろうか。あと500m強引にくぐっていくと、峠に茶畑、人家、お堂がある。
・洗沢峠(杉尾 洗沢)
犬2匹にさんざん吠えられあとを付けられたが噛んでは来なかった。頂上にはお堂、三角点。北側の景色がよく見える。上ってきたのと反対方向の人家3軒(かつて2軒でもう1軒増えたという記事が東海道山すじ日記1869年に見えるので140年以上同一戸数ということか、現在住んでいるのは1軒だけらしい。1990年頃ここに住んでいる人と話をしたことがある。そのときは家の近くに地蔵が祀られていた。そのときは3軒とも住んでいたようだ。また2000年頃も話をしたことがあり、川根街道を調べるため茶畑から南の藪に入っていたことを思い出す。そのときは1~2軒住んでいたのかも。)の前を降りていくと峠の茶屋前に出て、国道362号線。国道を渡るとお堂があり、地蔵や秋葉山石道標が設置されている。ここからは川根街道主要ルートとなる。今までがサブルートといってよい。
*川根街道主要ルート近辺の歴史遺物紹介は「古街道を行く」鈴木茂伸(静岡新聞社)の川根街道を参照してほしい。
~上杉尾~
先ほどの上仲家、佐藤家の下の方にお堂がある。
○観世音堂
堂内に多数の石仏が祀られており、境内に西国三十三所観音があるところをみると、三十三体の観音石仏ではなかろうかと思う。
・手洗石:佐藤
・奉西国三十三所観世音菩薩 文化十□正大二月
近くに火の見櫓もある。
~下杉尾~
坂の上の県道から下杉尾に向かう舗装林道を2km進む。坂の上から杉尾を経て洗沢峠を目指す古いルートでもある。杉尾川を渡る橋と「杉尾川起点ここより300m上流」標識、この付近ヘアピンカーブにもなるところである。橋手前に川沿いに歩ける登山道が川に沿って上流を目指していく。これが下杉尾から上杉尾更には洗沢峠を越えて秋葉山に行けるルートの古道残存部である、そこで秋葉街道枝道の歴史遺物はないか入口付近を探すが何もない。すぐ奥は倒木で通行困難。引き返す。
舗装林道を1.5km進むと下杉尾に出る。その手前に古道から舗装路に出る登山道取り付き点らしきもあったが、特に道標等は見当たらない。橋手前右に高橋宅がある。ここに地蔵と七人塚がある。集落近辺の舗装路下に神社がある。
・地蔵:高橋宅前茶畑端にある。
・七人塚:高橋宅前茶畑に上るとすぐに屋敷墓4基があり、その近くに高さ70cmの石垣が縦50cm、横1.2m積まれている。上は小木が繁っているがかつては更地でその上にお供え物をしてお祀りをしたようだ。年2回春秋に行ったようだ。いわれは伝説「落武者七人が杉尾に落ち延び弓の稽古をしていたが切腹した。彼らを祀った所だと言う。みさきがりという。」、下の神社向こうは武者が弓の稽古をした的当て場という。
・子神社
・石鳥居:
・手洗石:昭和十八年
・神社用地設置記念 昭和二十六年
神社前の道が旧道(古道)で川沿いを上りこの先の髙橋宅の裏に進み川沿いに上ると、この上の上杉尾に至るようだ。
???・池城、昔水があり池の主も住んでいたが、女性が汚れ物を洗い、大蛇と共に怒って流れ出ていった。どこか分かる方お知らせください。
・寺屋敷、小字マイガイト、278番地、畑の片隅に3つの石碑と一体の観音様があるそうだ。この近くに大きな杉の木があったそうで、安倍川から見ると尻尾のように見えたので、ここを杉尾という。坂の上の薬師様はこの木で彫ったという。杉尾集会所・火の見櫓より2箇所カーブを上ったところのカーブとカーブに挟まれた狭い所にありカーブ道の上下から見える。樹木の根元付近に石塔5基他破片がいくつかある。
・如来:文政三
・石塔:安永五
・石塔:元文五
・石塔:
・石塔:
・石塔破片いくつか
・道光 ドウコウ、藁山 ワラヤマ
~城山橋まで戻り県道を遡上する。~
・松の平
下湯ノ島手前で林道入口が左にある。能又川(よきまたがわ)沿いの林道である。丸山橋を渡り進む。この辺はかつて日向の白髭神社(藁科八社、本社白髭大明神)があった松の平というところらしい。付近に地蔵型の墓石と四角柱型の墓がある。ここは能又川と藁科川が合流するところであることが河原に下りると一目瞭然である。
1.3km進むと右(北)の湯の島側の山に向かい上る林道がある。上っていくと、中腹の茶畑を経由しつつ行き止まりで、更に先を工事中である。ここで対岸(南)の日向・畑色の方を見ると昭和53年の地形図に載っている中腹の集落跡が分かる。東側集落「藁山」はすでになく植林ではないが枯草色で藪らしいことが分かり、*(これは間違いで藁山も家一軒と茶畑が健在である。)西側集落跡「道光」は家と畑がはっきりしていてまだ人の手が入っているらしい。では林道を下り能又川沿いの分岐地点へ戻り、奥を目指す。1km進むと橋を渡り家畜用飼料小屋があり、右へ本道で、左に作業道で関係者以外立ち入り制限になっている。
・道光
元来た道を戻り、先ほどの林道分岐100m手前に川に降りていく歩道がある。これが西側集落跡に行く登山道で集落を越えて畑色の別荘地奥の養鶏場に至る道のはずであるということは、秋葉街道枝道でもあるので、何か歴史遺物はないか調べてみる。特に石道標等は見当たらないが、切通しだけははっきりついている。集落直前で竹林が繁りかいくぐることになる。1軒の家は閉まっているが作業小屋として常時使われているようだ。周辺の畑の一部も整備されている。まず集落西を確認する。城山橋から伸びてくるルートの確認である。はっきりしない。
茶畑の上に旧道登山道があるはずなので上ってみると切通しがついている。ここから上の畑色の養鶏場につながるはずだ。すぐに廃屋があり、それより上部は草木がかぶさるようになる。だいぶ廃道が進んでいるようだ。切通し以外遺物もないので引き返すことにする。
今度は先ほどの家の西側が道も広々して歩きやすそうなのでそちらに降りていくことにする。それにしても自動車が通る道だ。
広い道に近づいて更にギョッ、すごい驚いた!!! 家の前にイノシシがいる。後ろ左足を縛られているが、道をほじくりやたらと動き回っている。なんとそいつが私に気付いた。私の方を見て私に近づこうと縛られた足でもがいている。ドキドキである。あいつに噛まれたりぶつけられたりしたら重症だ。でも顔をよく見ていると牙はなく、メスかな? 鼻がやけに大きい、イノシシってもっと鼻が細長いと違うんか? もしかしたら、イノブタか?イノシシと豚の合いの子?あいつジーと私を見てロープ目いっぱい伸ばし私に近づいてる。あのロープほどけませんように。おそるおそるかつ足早にあいつを無視するかのようにして家の反対側に回った。ほっとした。さっさと元来た道を早く戻ろう。きっとあいつこの家の番犬ならぬ番イノブタなのだろう。今思うと近づいたところで写真撮影しとけばよかった。このところニホンカモシカ、キジ、猿は見かけるがイノブタには驚いた。
ちなみに猿は川沿いの椎茸ホダギにかぶせてある金属ネットを器用に取り払い、中の椎茸を食いまくっていた。ホダギはすべて金属ネットがかぶせてあるにもかかわらず意に介してないというか、このネット代金とかぶせる手間ひまは大変だろうに、こりゃ農家はたまらん。ニホンカモシカは人と出会うととりあえずジーと見つめてきますので、動きを止めすばやくかつおどさぬようにカメラ等を準備し望遠で撮影しましょう。うまく行けば2~3m距離で出会うこともあります。ただ逃げるときはすばやいというか、あとでカモシカがいたところに自分で行ってどう動いて逃げたか同一ルートを少し試せたら試してみましょう。何を言いたいかというと、人が歩いたり立ったりするのも困難なところを平気で走っていくので、その能力の高さに驚きます。追いかけることは不可能です。あなたが転落死亡します。キジはとっとと逃げるので撮影できませんでした。猿もすばしっこいです。ただこのところカモシカとの出会いが多いですね。天然記念物こんなに増えて大丈夫なのでしょうか。今のところ熊との遭遇はありません。そのうちあるかな……。
ちなみに後日ここでの茶園等畑の管理をしている湯の島の小沢氏に出会って道光と藁山を案内していただき、このイノシシ一件も聞いた。
あのときの動物間違いなく野生のオスイノシシだそうで、ちょうどこのときわなに掛かったイノシシを撃ちとめてもらうためハンターを呼びに行っていたそうである。夕方ハンターにより撃ちとめたそうで、肉はかたいので捨てたそうである。牙は小さいながらも確かにあったそうでオスである。イノシシに襲われていたら、今頃ここに私はいないかな…。
藁山と道光間のルートは沢の辺りで道はないそうである。どうしても沢で道は崩壊してしまう。
小沢氏の案内で道光の石造物所在地を確認できた。集落西側の作業道すぐ上であった。ここに隣り合った平地が2箇所あり、神明社と曹洞宗学恩寺があったところのようだ。その平地の上の隅に石塔が祀られている。(『日向の七草祭』p3「3 道光に残る石造物」と同じである。)ちなみにp2「2 道光の景観」に写っている小屋は小沢氏の休憩所で電気も通っている。茶園は同氏の管理であり、その中に墓石もある。
・地蔵:貞享五辰年十二月廿三日 □□村 佐藤、1688年元禄元年
・不動明王:享保二十□□、 1735年
・馬頭観音:
・壊れかけた石:おそらく五輪塔か宝篋印塔と思われる。
他に茶畑内にも墓がある。
・墓石:明治廿七年 徳巌良禅□ 徳應貞壽□
他の墓石は子孫が移転したそうで主に日向陽明寺だそうである。ちなみにこの石造物後ろに立てられている卒塔婆は小沢氏が陽明寺からもらってくるそうだ。
道光は天明八(1788)年の文書によれば家数15戸(一説に20余戸)とある。山田長政の母の出生地という伝承もある。宝暦六(1756)年、奉公人として落ちぶれた主家に尽くしたことで町内の推薦で駿府町奉行所から褒美をもらった忠僕八助も出身者である。(忠僕八助の碑はJR線隣の南安倍の八幡宮にある。)陽明寺の開山の雲叟も出身者である。しかし文化年間(1804~17)には滝右衛門一人在住で、その直後無住。明治初年日向村合併。昭和22(1947)年開拓入植開始、しかし以後無住で現在小沢氏が通いで管理。
・藁山
この後、小沢氏に車で道案内してもらい藁山へ行く。途中城山から洗沢峠へ徒歩で上ったときに横断した林道がこの道であることを知った。藁山は現在無住だが1軒だけ残っていて、某氏息子が通いで茶畑等管理しているとのことだった。昔は20軒ほどあったが生活困窮で天明年間に6~7軒に減少し、以後無住。明治初年日向村合併。神明神社がある。
『駿河国新風土記』著者新庄道雄は萩多和城の藁科氏の居所が藁山だという説を述べている。
藁山には墓石や地蔵、祠が残されている。車を駐車した藁山西側入口近くにある墓石から紹介する。これは『日向の七草祭』p16「1-2 藁山に残る墓石群である。
・宝篋印塔?
・石塔
・墓石:江戸期風
そこから東に5mでまた墓石がある。
・墓石:小永井 明治廿二四月、四角柱連立式の近現代の墓石、
・墓:小長井
・墓:地蔵:童子
そこから東10mで地蔵と祠がある。
・祠
・日切地蔵 大正五年十一月:歯痛地蔵:あごなし地蔵
・地蔵:右の日切り地蔵の左にもう1体安置されている。
・手洗石:
・焼香台のようなもの?
そこより30m上
・祠:多分、神明社
神明社のすぐ手前を横切りアカミチが上の畑色に上っていく。しかしすぐ上で崩壊している。アカミチを下にたどっていくと植林内に入っていく。そこも平坦地がありかつての人家の跡である。ただその下へは道は不明である。横へ行く道も細い。
~林道から県道に戻り湯の島を目指す。~
○下湯ノ島 ゆのしま
13年3月に県道集落手前に石塔類合祀場所が作られた。
○石塔類24基
・庚申塔 昭和五年
・庚申供養塔 天保四癸巳年
・庚申塔 昭和参年
・庚申塔 昭和三年
・庚申塔 昭和二年
・庚申塔 昭和八年
・庚申塔 昭和四十四年
・庚申供養塔 大正九年
・庚申塔 明治四十一年
・庚申塔 大正九庚申年
・庚申塔 昭和十七年
・馬頭:昭和十四年
・馬頭観世音 大正十三年
・庚申塔 昭和廿一年
・庚申塔 昭和十七年
・庚申塔 昭和二年
・庚申塔 昭和三十九年
・西国 奉納経 四国 安政(正が上、マイが下)
・石灯籠:昭和五年
・手洗石:昭和四年
・地蔵:虫歯守護あごなし地蔵大菩薩:、子供の歯痛を治してもらった願果しに建立したもので、藁山のものの方が古い。
・?馬頭:明治廿一年
・?馬頭:湯本小太郎
・馬頭観世音 昭和三年
湯島橋を渡り左に石仏がある。
・馬頭観世音 昭和十二年
道を上っていくとお堂がある。
・琴比羅神社:金比羅堂
その先に墓地とお堂がある。
・玄国堂 宝積寺
虚空蔵菩薩:木製:江戸期、
・手洗石:明治廿一年
・玄国堂紹介説明版:玄国和尚は明和安永の頃(1764~1780年)の湯島村宝積寺の住僧なり。生国は甲斐の国西八代郡大島村(身延町、JR身延線甲斐大島駅)なり。出家して晩年衆生済度のため諸国行脚の旅に出でたり。途中湯島村佐藤彦右衛門宅に止宿す。「やんれやんれ」と声をかけて歩く程なればこの時相当高齢なるべし。
和尚の徳声まことに高く時には近縁の者集まりて法話を聞き、ますます信仰の念を深める者多し。和尚は又この里の人情厚きを喜びて静かに老後を宝積寺にて養い居たり。当主彦右衛門は和尚に随喜すること特に厚く風呂の沸く毎に請して優遇したり。又ある時は和尚自らそばを作付けしてその収穫を彦右衛門に依頼せり。「彦右衛門そば拾いに来たれり」と言いしに和尚は「そばを拾うと言わずそばを刈ると改むべし」と笑いて語りしとか。現在この土地にそば拾いの呼称あるを思えば他国より来たれる和尚にはこの方言奇異に感ぜられたるべし。和尚は一朝翻然として悟道するところあり。即ち信徒を集めて後事を託し「吾れ滅後に於いて浄心を専らにして吾名を唱うる衆生あらばもろもろの苦悩を解脱し必ず安心を得せしめんとの遺書を残して入定せり。(生きながら身を棺に入りて土中に埋葬すること)老若男女泣きて和尚の入定を止むれど決意の程固く如何とも止め難く如何とも止め難し。時に安永四(1754)年二月二十七日行年八十三歳なり。その後七日七夜墓の中より念仏唱名の鐘の音聞こえたりと。
彦右衛門の悲嘆見るもあわれなり。終生只管和尚の意を守り供養を怠らざりき。嘉永元(1848)年七月二十日行年九十六歳を一期として逝く彦右衛門の法名潤屋百歳信士と号す。
和尚の生前「彦右衛門よ、死後は吾傍に来たれ」と言われしとて和尚の墓近くに自ら墓所を定め家人に吾れ死後はここに埋葬することを話せり。現に和尚の墓近くに彦右衛門の墓あり。如何に追慕の情深きを知るべく吾里の信仰美談なり。
玄国堂は和尚の祠堂にして現在の建物は明治三十五(1902)年の建立にしてもと宝積寺境内に在りしを遷せるものなり。此の祠堂に安置せる和尚の尊像は当村孫右衛門村民に謀り当時鍵穴村喜左衛門方に逗留せる仏師某に依頼彫刻せるものなり。明治初年に一度修理せしことなるものなり。
往時病難災厄ありし時村民此の堂に参集し尊前にて光明真言を唱え一心に祈念せり。心願成就霊験あらたかなりと。
今日尚玄国堂に香華の絶ゆることなきは昔より如何に栄誉の的なりしか推して知るべし。二月二十七日は毎年祥月供養せしが後に春彼岸中日に変更し今日に至る。当日は本寺陽明寺住職来堂し法要を営み併せて無縁仏の施餓鬼供養を行う。因みに当日信者に配る玄国和尚尊像のお札版は当村庄右衛門の作なりと。
・和尚たちの墓:「潤屋百歳信士」墓石が右端にある。
・墓地やお堂前の歩道が旧道(古道)残存部である。上湯の島に続いていて、約600mである。
はじめ200mは石垣で道の崩壊を防ぎ快適な道だが、それを過ぎると道が崩壊しかかっている沢を渡り、ガレかかったところを通過することになる。今のところは通過可能だが整備しないと徐々に崩壊が進むだろう。上湯の島の市営温泉駐車場の真上に出る。ここは峠みたいで急に上湯の島集落が見え、枝尾根をまたぐ形になる。炭焼き小屋跡の石垣を組んだ穴が見られる。標高はこの先の飯綱神社と同じぐらいの高さだ。集落に降りていくには林道の作業道に下りればよいが、かつては茶畑に付いている石垣のある道が本道だったのではなかろうかと思う。集落自体がかつては川や県道より離れたもう少し上にあったのだろう。裏山の飯綱神社程度の高さに村があったのかもしれない。今は川沿いの県道周辺に集落が移動したと考えたほうがよかろう。
○上湯ノ島
市営湯の島会館前の民家に地蔵がある。
・地蔵:
民家裏山に神社がある。
・飯綱神社
・石段:安政七年
・石鳥居:□□□十三□□□
・手洗石:慶応戌辰
・祠
・五輪塔:宝篋印塔、これは古そうです。神社裏の周辺は畑でやや平坦で、ここに集落があったのかも。
近くの墓地に石灯籠がある。
・石灯籠2:
県道川沿いの川に下る道があるところに石塔がある。
・庚申塔 昭和五年
・渡河地点:上湯島と大間:なぜここに庚申塔があり、川に下る道があるかと考えると、ここで川に下り、ちょうどこの辺りの水流が弱く、渡りやすく、渡った先の対岸には茶畑があり、上って行ける歩道がついている。おそらくここがかつての渡河地点だったのだろう。今はここより100m上流に大間に行く湯島大橋がある。まあ庚申塔は川に下る道の横が空いていたのでたまたま祀っただけのことかもしれない。
・湯の島温泉の由来:大間に信州高遠から来た武士が住み着いた。藁科の村は羽鳥しかなく大間までは大きな距離があり大間ということになった。その弟が大間を訪ねる途中湯が湧くのを発見し温泉にした。江戸期繁盛したが、あるとき武士が遊女を切って首を温泉に投げ入れてから湯が止まった。地名は昔湯島だったが、同じ地名があることから、湯の島とした。
~県道はこの先湯島大橋手前で右:大間・笠張峠と左:楢尾・崩野・八草に分岐する。
左:楢尾・崩野・八草方面をとる。最初のカーブで石塔がある。
・庚申塔 道路開鑿記念 大正十三年
すぐ次に右:楢尾への分岐があるが直進し崩野・八草方面をとる。
○崩野 くずれの
崩野への中間辺りの沢横の道路沿いに石塔がある。
・弘法大師 道路開鑿記念 大正十五年
集落への一つ手前の泉沢橋のその手前のカーブ地点に祠がある。
・地蔵:
崩野 登り尾集落直前の尾根途中にお堂があり、地蔵が祀られている。
・地蔵堂:延命地蔵:説明看板:昔、子供に幸せ薄い村人が、別の場所で朽ち果てていた地蔵を、この地に移し供養したところ、子宝に恵まれたといわれる。以来子供を守る地蔵と敬われている。縁日旧暦12月24日(現在の暦だと1月末から2月初め頃)
*旧暦について一口メモ
旧暦の日にちを今の暦に直すと毎年日付がずれるので毎年違う日になるはずです。単純に計算できません。およそ40日ずれるといわれますが、これもおよそで毎年こうとはいえません。旧暦は19年に7回、1年が12ヶ月ではなく、13ヶ月になるという大胆な暦で、こうでもしないと、真夏に冬のはずの正月になりかねないからです。旧暦は月の満ち欠けで数えていて、一ヶ月は平均29.5日で一ヶ月は29日か30日なのです。12か月分だと、今の暦より11日少ないので、これで15年も続ければ真夏が正月です。そこで19年に7回13ヶ月になる閏月という制度があり、季節と日付がずれないようにしてます。約3年に一度といえます。例えば七月が終わると閏七月になり、それが終わるとやっと八月になるわけです。この閏月も法則がありますが、例年同じ月ではなくもう少し複雑なのでややこしいです。詳しく知りたい方は。他を調べてください。ネットでも図書館でもどうぞ。ちなみに1年が13ヶ月だと月給取りのサラリーマンは1回得しますね、だからこそ明治5年明治新政府は財政難で、公務員への13回目の給料支払いをやめるために今の暦にしたといわれます。
~崩野の中心集落に入る。集会所先のカーブ崖上に石塔がある。
・庚申塔 大正九庚申年
・奉納 庚申供養塔 明治五年
・庚申供養塔 昭和□年
更に道を上っていくと
○宝光寺跡
・(三)界萬霊塔 大正十四年
・三夜燈 安政四年
・石塔:
・六地蔵:六体
・地蔵:
・五輪塔
・馬頭:
・石段改設 明治拾七年
○観音堂
金属製:千手観音像:江戸期:擬古作、
かつて月小屋(女性が生理中こもる家)も付近にあったそうだ。
・手洗石:
・石灯籠:
○白髭神社
・石鳥居:氏子安全 御大典記念 昭和三年
・氏子安全
・石鳥居の根元片側が埋もれている
・石段:昭和五年
・手洗石:祈皇軍健捷 昭和十九年
・石灯籠2:奉納 白髭神社 御宝前 明治廿七年
・祠2:
・手洗石:明治十一年
この裏山を登っていくと智者山・天狗石山に至る。
崩野集落を下っていき、かつて楢尾に渡っていた所、今は朽ち果てた吊り橋の残骸があるところから上流を登っていくと、「崩野川右岸支流に朝日滝:落差30m、3段、別名:崩野滝」(ネットのサイト「静岡県の滝」より)というものがあるようだ。吊り橋のところから右岸の登山歩道は砂防ダムがいくつもできて消滅しているようだが、左岸に林道が出来ているので1kmほど遡行できる。林道1kmで終点でとくに標識等がないのでどこが朝日滝方向か不明。しかしその辺りから沢が3つに分かれているのが分かり、林道は左岸の支流砂防ダム前で終点であるが、対岸の右岸に流れ込む支流が3段ほどに分かれ滝状に落ちている様子が木の間がくれに見える。落差は合計30mほどかなと思える。もしかしたらあれが朝日滝かな。吊り橋残骸から1kmほど上流の右岸支流である。
またここからさらに1km沢奥を詰めると大野滝というものがあるように地形図では記入されているが、ネットのサイト「静岡県の滝」では消滅と記入されている。
○八草 やくさ
現在無住、かつて7軒あった。無人の民家が4軒ある。もう1軒はお堂である。集落手前に智者山登山口を示す標識があり、集落奥を指しているが、その前に自動車道舗装路終点地(未舗装道路は更に50m奥に進む。)の右上が山斜面で上って行く登山道がある。1分上ると杉桧植林地内に集落墓地があり、真下が自動車道舗装路終点地である。
・墓地:上湯ノ島の玄国茶屋に勤めている八草出身のご婦人の話によると、60基ほど墓石はあり、石碑を根元に抱えた栂の木があり、近くに女杉もあるとのことだ。しかし墓地は改変されていて、だいぶ空き地になっていてまとめて積まれた墓石や破片を含めて30基ほどと思われる。おそらく大半を移転したと思われる。しかも墓地周辺の古い樹木はことごとく伐採され、残っているのは植林ばかりである。
無論根元に石碑を抱えた栂の木は不明であるというか、おそらく伐採されたものと思う。
女杉であるが、付近には植林された杉ばかりでいわれのありそうな木はないので、伐採されたものと思う。
????・女杉、池の段:杉と池の中に女の大蛇が住んでいたが、暴風雨か女が洗濯したため出て行ったという。どこ?池の段は裏山というか智者山登山口付近の平坦地のことか?女杉は墓の付近らしいが不明。
・旧道(古道):墓地の下で自動車道より上に道幅30cm~1mの登山道が水平についている。自動車道より10m上を水平についている。おそらく登り尾集落に向かう旧道であろう。自動車道ができる前の生活道路、旧道(古道)であろう。今は植林地内の作業道であろう。使われなくなり徐々に崩壊していくだろう。
~一旦墓地から無住集落に向かい進んでいく。
途中建物がありお堂である。
・神明神社:お堂
・手洗石:
この裏山の尾根先端頭頂部に神社があることに地形図ではなっているので行ってみると、参道は道がはっきりあり、頭頂部は平坦で建物跡が見られる。ちなみにこの尾根頭頂部と先ほどの崩野延命地蔵堂のある所は同一線上(東西方向)の尾根である。かつては尾根道でつながっていたのではなかろうか。この尾根を2~3分東に下ると先ほどの墓地に出ることができる。
・石段跡:
・建物跡の礎石か周辺をかためた配列石:
この裏山尾根を西に登っていくと尾根を一旦北に回り込むが、その先で尾根に取り付き西に上る道があり、そちらへ智者山登山用矢印が出ている。
ちなみにそこから杉桧の植林された尾根を下に下る切通しがついていて、多分下の登り尾の集落につながっている旧道と思われる。
八草内の植林地で智者山、崩野、八草民家の分岐点近くに植林より低い火の見櫓が見つかる。
・火の見櫓:今は周辺の杉植林より低い。かつてここが見晴らしよく周辺が畑か人家だったという証拠だろう。
八草から智者山を目指すと直接智者山山頂ではなく、一旦智者山林道が通過する尾根に出るはずだ。そこから尾根を詰めるか、林道を少し詰めてから標識に従い尾根に取り付くかだと思う。そして林道に出る辺りに、四角柱の石道標があるはずだ。林道工事中に一旦不明となり、新聞記事まで出て所在確認が行われ、どなたかが預かっていたことが判明したそうだ。今はもとの場所にあるのだろうか。
八草無住民家を詰めていくと最後の民家の奥は大きく崩壊していてもう進めない。最後の民家前も地滑りで地面に段差がいくつか生じている。さも地滑りの見本のようだ。
無住民家の庭先に布団類を敷き並べて土に戻そうとしてある。子供用ビニールプールの破片もころがっている。別の植林内の家は開けっ放しで家屋内に古い大型のアナログテレビがぽつんとある。周辺には洗濯機やバケツがころがっている。かつてここに人々が生活し人の生活の営み、家庭の団らん、幸福が、子育てが、悲しみがあったのだろうに、こうして廃墟と化すと、寒々とした悲哀感が押し寄せてくる。
遠い未来、東京や静岡といった都市が廃墟と化したとき、それを探索する人は20世紀から21世紀の人々の営みの痕跡に人生の悲哀を感じるのだろうか。
*無住集落を訪ね歩くのはあなたの自由でしょうが、今でも所有者や管理者はきちんとあり、そこで生まれ育った人にとってはかけがえのないふるさとでしょうから、現状を改変したり汚したりする行為は一切しないようにしましょう。
無住集落内を一本の沢が流れ下っていくが、途中明らかに沢を付け替えてあり、本来の沢には石垣があり水が流れていない。おそらくわさび田として利用したため水量調節のため古タイヤを積み重ねて沢をせき止め、横に水路を掘り流れを変えたものと思う。
・昔髙橋家は井川金山の関所と智者山神社の別当(禰宜ネギ、神主)だったという。
八草から ~楢尾、川合、川合坂、本村への分岐に戻る~
○楢尾、川合、川合坂、本村
分岐を過ぎ楢尾への橋を渡る。橋の位置は改定されている。渡るとすぐに祠がある。
・地蔵:明治七戌年
~道を上っていくと最初の集落:川合であり道端に石塔がある。
・石?
・地蔵:
・墓石:
~茶畑の上に石祠がある。
・石祠:
・石柱:奉納 稲荷神社之元屋敷 明治四十年
ここに稲荷神社があったということか、住民に聞いてみると、
???・住民によれば神社は林道をもっと上った山の中腹にあるそうだ。未確認。
~次の集落:川合坂の上に神社がある。神社に上る道の近くに石塔がある。
・庚申塔 昭和七年
~上っていくと尾根付近に神社がある。
・稲荷大神
・石鳥居:明治百年記念
・手洗石:明治十五年
・石灯籠2:昭和五十一丙辰年
・祠:稲荷
~楢尾への舗装路を進む。
・海前寺
・地蔵:
・板碑:この寺に学びし頃の思い出の歌
~大間への舗装林道を進む。
・楢尾の石仏、ならおのいしぼとけ
舗装林道を尾根辺りまで出て尾根に杉巨木が見える所、大間や益田山への分岐200m手前である。林道は尾根より5m下を通過しているため、尾根伝いの旧道(古道)上の丸石を手向ける杉巨木のあるこの場所はそのままである。祠も祀られている。峠の語源には峠越えの安全祈願を手向ける→手向け→たうけ→たうげ→とうげ峠になったという説もある。柴を手向けることが多かろうが丸石を手向けることもある。この舗装林道が開通したことでかなり旧道は消失したようだ。丸石は願掛けやお果たしでもある。
もう200m進むと分岐点がある。直進で益田山、七つ峰方向へのダートの楢尾智者山林道、右折で大間である。大間へは部分的に旧道が残存している。
・石道標:「これよりみぎ大まみち」四角柱で頭頂部は四角錐である。
???・益田山:どこの山? 七つ峰への前衛峰?
○大間
・大間の石仏、おおまのいしぼとけ、大間の古道(旧道)
石道標のある分岐点から、しばらく林道を下ると大間との境らしい。この辺り林道より5m上に丸石が見られたようで大間の石仏だそうだが、探しても一つも丸石は見つからなかった。意図的に移動されたものと思う。ただ林道より上部を探すと旧道(古道)残存部はあり、しっかりした道も部分的にある。その中に楢尾の石仏を彷彿とさせるような峠のような境目のような大きい木が4本ある場所があったので、私としてはそこを推定地としたい。先ほどの分岐点より700m進んだ林道地点の20mほど上の尾根である。旧道は上り下りの境目で道の左右に杉2本、モミかツガが2本で計4本大木である。祠や丸石は一つもないが、楢尾の石仏と風情は似ている箇所である。この近辺に古道らしさがよく残存している。ただ20~30年前まで子供が楢尾小学校に通う通学路として安全に整備されていたのだろうから、昭和期終わり頃の姿をとどめているという思いも必要だろう。
大間に向かい旧道切通しをたどると数回林道と交錯し断ち切られるが沢を2回またぎ林道と違う箇所へ向かうのが分かる。その先急斜面の尾根に出て真下に砂防ダムが見えるところで、旧道は崩壊していた。この急斜面では致し方ない。おそらくここで七曲りの巻き道になり急斜面尾根を下っていったのだろう。ちなみに大間の林道出口には砂防ダムがあるところは見当たらないが、1本北の沢は砂防ダムがあり、急斜面の尾根があるので、おそらくここの真上であろう。付近を探したが旧道出口らしきは不明である。崩壊しているのか、私の探し方がまずいのか。
大間集落直前の福養橋手前に石塔がある。
・庚申塔 昭和九年
大間集落に神社がある。
・白髭神社
不動堂:木製:二体不動明王、
・石鳥居:昭和五十五年
・祠2:
・石製家型道祖神:明治□年
・石灯籠:慶応四年
・庚申供養□ 元治二□
・庚申供養塔 大正九庚申□年
まあ慶応四年(明治元年)も元治二年(慶応元年)も公式にはないが、石屋が彫ってしまってから年号が変化したと思えばよいのだろう。まあ昭和元年は1週間で終わり、昭和64年は1週間しかなかったしね。こういう年号違いは時々見られるが一つところで二つも見られるというのは初めてだ。ここではないが他には萬延二年(文久元年)もよくある。
・火の見櫓
○福養の滝
大間集落左上の沢というか先ほどの福養橋上流にある。安置されている石塔は2基である。
・大滝不動
・不動明王
・説明看板:昔、信州高遠乾の町(伊那市高遠町)から三人の落武者が逃れ、この地に住み着いたのが大間である。この地には滝があり高さ100m、幅4m(現在では高さ135m、幅3.3mとされる)の滝の水は滑らかに岩を這うように流れ飛び散る水玉は陽光に映えて、宝石を散りばめたように美しい。またこの辺りは不動尊が祀る神池とも伝えられる。この滝に毎年五月五日の午前十時頃一頭の馬が滝つぼに漬かり毛並みを整えていた。この馬はのちに栃沢の米沢家で飼われて宇治川の先陣争いをした俊馬「磨墨するすみ」となった。村人はそのためこの滝を「お馬が滝」と呼んだ。1909年当時の安倍郡長、田沢義鋪よしすけが井川村から郡内調査に来たとき、滝の確かな名称のないことを残念に思い、岐阜県養老町の養老の滝に似ているので「福養の滝」と名付けられた。(現在は似ていないといわれる)
名馬「磨墨」伝説とも重なる伝説の滝であり、静岡市内では有名な滝である。
~湯島から大間に上る県道沿いにも石仏がある。
・?馬頭:古びていて判読不能。
・川久保林道分岐点:13年3月工事中、出入り不能。
・地蔵:おおはたけ橋袂にある。「大正十五丙寅年 霊峯山人建之」
・林道野田平線分岐点:先ほどの楢尾大間の林道である。これより上はすでに記入済み。
~大間を越えて、この先、県道南アルプス公園線は、尾根を越していく。その尾根を右に進めば一本杉峠や諸子沢・平の尾方向に下っていける。その先で地すべり地帯を通過し笠張峠で県道井川湖御幸線に合流する~
*林道一本杉線に関しては、諸子沢の平の尾・地蔵堂辺りを参照してください。
・参考文献
・「静岡県指定無形民俗文化財調査報告書 日向の七草祭」静岡市教育委員会 ‘06
かなりの部分を引用させていただいた。
・「駿河の伝説」小山枯柴:編著、宮本勉:校訂 旧版:‘43 新版:‘94
・「藁科物語 第3号 ~藁科の地名特集~」静岡市立藁科図書館 ‘94
・「藁科物語 第4号 ~藁科の史話と伝説~」静岡市立藁科図書館 ‘00
調査:2013年2/24~4月
静岡市羽鳥で国道362号線を上り昼居渡八幡で国道362号線から右分岐し、県道南アルプス公園線を遡上し、笠張峠までの区間とする。八幡から湯の島の近代道路は1916年開通。
*なお静岡市安西・羽鳥から昼居渡八幡までの区間(この区間の近代道路は1903年開通)は、『古街道を行く』(静岡新聞社)の川根街道を参照してください。
・(八幡)
70m進むと道は右カーブになる。そこの岩上に石塔あり。
・馬頭観音:明治四十五年六月廿二日
・庚申塔 大正九庚申年
・石灯篭:大正十二年
・(赤沢)
赤沢の休憩所を過ぎ、集落右上に神社がある。上っていく途中の家の石垣庭先に石塔あり。
・農道建設碑 昭和三十二年
???・対岸の峠は櫛筐峠クシゲ(クシバコ)トウゲというそうだが、具体的にどこなのかわからない。わかる方お知らせください。
集落左手上に神社あり。
・山神神社(赤沢)
神社拝殿の額には山之神社と書かれている。
・手洗石:昭和三十四年
・鳥居・金属製
県道に戻り北上。のがたけへの分岐より手前に祠があり、祠内に3つのものが祀られている。
・弘法大師
・観世音菩薩
・黒田渕稲荷
ここの渕を黒田渕というようだ。
・(のがたけ)
のがたけへの分岐には東海自然歩道標識あり。吊り橋で藁科川を渡り、標識に従い山に取り付けば尾根まで行ける。尾根上の道は古い川根街道であり今の東海自然歩道である。ちょうどのがたけからの上り口は裏川根街道上り口のようだ。
のがたけの集落の庭先に石塔あり。
・石塔?:摩滅して刻字等不明、細長い60~70×20cm、庚申供養塔?か
・石塔?:摩滅して刻字等不明、背が低く幅広40~50×30cm、
集落を上がっていくと分岐点あり。東海自然歩道標識と石道標あり。
・石道標:従是 右 相又 左 村中 道:行書で書かれており幕末から明治初期のものか。摩滅していて判読しにくい。右が東海自然歩道・川根街道方向で相又である。左は集落で吊り橋を渡れば赤沢や寺島に行ける。
また県道に戻り北上。
・(寺島 市ノ瀬)
寺島中心集落手前カーブ地点上に神社あり。
・行春社(市ノ瀬)
・石鳥居:刻字?だいぶ摩滅しているものばかりで判読不能。
・手洗石2:刻字?
・石燈篭:?
・地蔵:?
・馬頭:?
・石仏:?
・如来:?
・祠:
・石塔:生祠
この上に神社あり。
・白髭神社
・鳥居:木製
・手洗石:明治十四年
・石製家型道祖神:
・奉供養庚申之塔 文政九丙戌年
県道に戻り北上。寺島集落で右折して坂本へ行くルートがある。東海自然歩道も同じく右折である。
・弥助桜、伝説「約250年前村が貧しく年貢を払えないとき、山杢弥助は役人とトラブルを起し桜の大木に上って隠れていたが役人に見つかり、富沢の六郎兵衛が鉄砲で撃ち落とした。そのとき弥助は六郎兵衛を七代祟ってやると叫んだ。その通り六郎兵衛の子孫は肉体的不具合が多かった。また弥助には二人子供がいたが賢かったので弥助のようになることを案じ殺してしまった。桜の木は弥助桜と呼ばれた。昔子供を祀ったものが田の中にあったという。」
???弥助桜はどこにあったのか?
・弥助観音、伝説「寺島新宮にあり、山杢弥助にまつわるものである。形は直径約15cmの円盤状の石で割れたものを継ぎ直したようになっている。昔弥助観音がある辻の辺りが子供の遊び場で、子供が弥助観音を割ってしまったので、武士が子供をたしなめていると、観音がせっかく子供と楽しく遊んでいたのにと武士に注意したといわれる。」、子供と遊ぶ地蔵伝説は各所にある。
???弥助観音はどこにあるのか?
○~寺島で坂本(東海自然歩道)への分岐。~
200m進むと右に石仏あり。
・地蔵
さらに進むと坂本集落が見えてくる。
・坂本
坂本集落橋手前の右民家前に石仏あり。
・庚申塔 大正九年
・南無馬頭観世音 大正六年
清沢本橋を渡ると集落中心部だ。すぐ橋周辺が坂本川砂防公園で右に看板あり。
・看板説明版:河原施餓鬼:鎮魂の碑:大昔に遡る約三百年前享保六丑(1721)年閏七月十六日異常な大雨が降り続き、字姉山沢の奥が山崩れとなり、人家へ押し寄せる土石流に、一瞬にして泥中に埋没した家屋数三戸、五郎兵衛方男女四人、助蔵方男女二人、権四郎方男女三人が、家と共に山なす泥土の下深く埋まる大惨事となった。また周囲の屋敷、田畑、山林も埋め尽くし、大きな爪跡を残した。
それより百三十三年後の安政大地震により、再び山崩れを起こし、家屋敷に被害が発生したが、人的災害がなく、不幸中の幸いであった。
貴い人命と共に被害、損傷を受けた我々の先祖の苦難の歴史をたどる時、霊の鎮魂の為、三年に一度、この地で川原施餓鬼を行い、犠牲になられた緒人をはじめ、受難の時代を乗り越えた古人の冥福を祈り、祈願を続けている。
*注釈:閏ウルウ七月とは、七月の翌月が閏七月となり、七月を2回行ってから、その翌月が八月であり、1年が13ヶ月になることもある旧暦のシステムである。約3年に一度13ヶ月になる。以下の崩野の延命地蔵箇所で旧暦一口メモとして簡単に紹介する。
メインストリートの林道坂本線に沿い上っていくと公園内に祀られているものに出会う。
・地蔵:光背付き
・句碑:とつさきに山霊導くわか泉 昭山
公園を過ぎ茶畑右に石碑あり。
・句碑:
更に進み左が崖になると、その崖に祀られている。
・馬頭観音:
メインストリートを清沢本橋手前まで戻り、集落内旧道を上る。すぐ左に石仏あり。
・馬頭観音 昭和十四年:朝風という馬を祀っている。
寺に向かう。
○清源寺
・大カヤ:説明版:樹高30m、目通り周囲3.7m、枝張18m、このカヤの木は樹勢が良好で樹齢約450年にも達する巨樹である。カヤの木は山地に自生しているが、庭樹としても植えられている常緑の高木である。種の胚乳は食用になりまた油を採る。材は基盤、将棋盤として有名である。
・馬頭:明治六年
・石仏:他2つ付き
・西国三十三所:他に馬頭と如来付き
・地蔵:
・西国三十三所
・西国三十三所 寛政戌辰年
・庚申供養塔 文政七年
・八幢しょう:
・地蔵:祠
もう少し山上に神社あり。
○清沢神社
・石鳥居:大正十三年
・石灯籠:
・石灯籠:
・石灯籠:
・石灯籠:昭和十二年
・手洗石:慶応四年
・石塔:奉献 伊津奈大権現 寛政八丙辰歳九月吉祥日
・奉献 御神燈 寛政八辰年九月□
・かまど
奥に奥宮がある。
・石灯籠:
・結界石
・祠
・石塔
・鳥居:金属製
元来た道を戻り下ると途中に四十一坂(肘打峠)上り口表示がある。
・四十一坂(肘打峠、肘打嶺)、静岡市駿河区坂本、国土地理院2万5千分1地図「牛妻」
’13 3/17 坂本より二十数年振りに登った。登山道は整備され標識も多い。集落上はずれから畑次いで森を通り峠まで15分。道は狭いところもあるがかつては道幅1間1.8mあったと思われる。一部崩壊していて道の付け直しがされている。集落はずれと畑の境辺りに石ころの道祖神がある。かつて登ったとき峠は平坦な茶畑でそのときはちょうどおじさんとおばさんが茶畑の世話をしていたが、今は植林と雑木が一面を覆っている。峠には石仏の観音2基と説明看板がある。
・西国一国三十三所 萬延元年
・□国一国三十三所 宝暦四年
・説明看板:肘打峠は大昔より藁科街道往来の道として栄えてきた。峠にはかつて大樫の大木が繁り峠越えの旅人の休息の場所となっていた。また鎌倉時代源頼朝の希望により栃沢の米沢家の老女が永年手塩にかけた愛馬:摺墨(磨墨)の手綱を頼朝の家来赤沢入道、小島三郎、日向太郎の高名な三勇士に名馬摺墨の手綱を手渡し、しばしの別れを惜しんだ峠と伝えられる。坂道の曲がり多く狭く険しく肘を突く峠の道、坂道を上りきるとそこに石仏二体苔むした観音菩薩が静かに時の流れを見守っている。(清沢村誌引用)
峠から更に坂の上に向かい下る。初めは見事な切通しで道幅1.8mが確保されていたことがよく分かる。ただしこの道を見ていきなり近世の古道をイメージしてはいけないのだろう。たいていの古道が、少なくとも昭和の戦後期まで現役の道として使われ補修を受けてきたのだろうから、戦後期の姿と受け止めたほうがいいのだろう。ニホンカモシカに会った。体長1.5m以上で立派な体格だ。このところ里山でも数多く見受けられる。天然記念物がこんなに人里にいていいのかと思う。被害は出ているのだろうか。逃げていくとき「キー」という甲高い声で鳴いていた。見受けることはしばしばあるが声を聞いたのは初めてだ。周囲に知らせるかのように鳴いていたので付近に仲間がいたのだろうか。しばらく下るとガレているところがあり道は崩壊していくようだ。15分で下りきり茶畑の農道終点に出る。ここから坂の上に出られる。なお農道は低いところを通って坂の神に出るが古道はもっと高いところを通過していたのだろう。
以下に以前の文章を載せる。
静岡市羽鳥で藁科川を遡る国道362号線を北上、八幡にて県道で藁科川を北上、市ノ瀬で東海自然歩道の標識あり、750m北上で寺島集落に出る。東海自然歩道標識は県道を右折し坂本集落に向かう。1kmで坂本へ、集落西端の家から裏山に登る登山道あり。分からなければ地元の人に聞くべし。道はやぶっていてよくないが、何とか通れる。標高差70mで尾根の峠到着、石造物が2体あったはず。昔は茶畑などでもっと通りやすかっただろう。確認89年頃なのでいつか再確認をしたい。ルートと名称は国土地理院2万5千分1地図に記載があるが、下り道未確認。西に下れば藁科川沿いに坂の上集落から延びる農道に出られるようだ。農道から登山道に入る付近に架かる吊り橋手前県道に「古道、四十一坂、肘打峠」の標識あり。農道からの標高差150m。坂本集落内にも標識あり。この道はかつての藁科街道のはずである。
~坂本から寺島の藁科川沿いへ戻り県道を北上する。~
鍵穴バス停付近で鍵穴橋を渡り、向こう岸の本村へ行く。
集会所のある墓地はおそらくかつての寺院跡だろう。
・奉一国三十三所供養塔 天保五申午年
・庚申塔 天保五年
・石塔2基
集会所裏手に神社がある。
・八幡神社(鍵穴本村)
石鳥居:大正十四年
・手洗石:大正十四年
・石灯籠2基:
~県道に戻り北上する。~
○大瀬戸
大瀬戸の県道カーブ地点上の山にお堂がある。かつての寺だ。
参道入口は集落内である。
・門柱:コンクリ製:昭和拾壱年 鍵穴同志會
・石灯籠:剥離ひどし
・手洗石:明治□二年
・手洗石:文久二歳正月
大瀬戸の県道より川に下っていくと道祖神と桜がある。
・石製家型道祖神:隣は枝垂桜である。
~県道に戻り北上する。~
県道沿いに祠がある。
・地蔵(新)
・天満宮(小島)
・石鳥居:昭和五十一年
・石灯籠:明治二十七八年
・石灯籠:昭和54年
・手洗石:
・五輪塔:4基、古い、壊れている、
小島橋を渡った向こうの集落はじめの家先に石塔がある。
・庚申塔 大正十四年
その上の方に小島の墓地がある。
・地蔵
・西国三十三所供養塔
・庚申供養塔
・地蔵
・奉西国三十三所
・?西国三十三所
~県道に戻り北上する。~
・木製標識:交通安全供養塔
・山王峠
休憩所:「樅の樹」前の道を上って曲がると坂の上方向が見える。ちなみに曲がるところで川に向かって降りていくと大川自然広場でキャンプ場。
・四十一坂
上り口標識
・唐沢橋を渡ったところに観光案内図看板と記念碑「大川 在来そばの里 大川100年そばの会」がある。その先の川の右崖淵カーブ上に石仏がある。
・馬頭観世音 昭和十五年
その先右カーブ左崖下に祠がある。
・地蔵
~坂の上集落に入る。
・石塔(坂ノ上 東)さかのかみ
・庚申塔:天保五年
・庚申塔:大正九年
・薬師堂(坂ノ上 東)
近くの墓地前に石塔が3つある。堂内には木製仏像群、建穂寺に次ぐ規模、:本尊薬師如来等:推定平安期。五智如来、観音菩薩、十一面観音、天部七体、僧形、神像。
眼病に効くそうだ。
この裏山を上っていった先を兜巾山というようだ。
・右:地蔵
・中:有縁無縁三界萬霊等
・左:葷酒不入門内月向山主□國□□
・坂ノ上神社(坂ノ上 東)
石造物
・石灯籠:安永九年×2
・狛犬:平成三年×2
・石鳥居:昭和六十三年
・手洗石:明治二十九年
・句碑:昭和三年
・割れ目のある石
・御即位紀念:大正四年
・天盃拝領 御即位記念 昭和三年
・改修道路 昭和三年
~ 町内の裏を藁科川が流れ宅地と畑の境の土手際に耳地蔵がある。
・耳地蔵、田の中にあるという。お果たしは穴の開いた石を祀る。今は藁科川の土手際に祀られている。3基石塔が祀られ、
・右が地蔵で穴あき石を首にかけているので、これが耳地蔵だろう。
・中央は「有縁無縁三界萬霊塔」、
・左は地蔵。
???・清名塚、戦で死んだ武者を埋葬したところに五輪塔を祀ったというが不明。分かる方お知らせください。
・陣場河原:かつて戦があったところで、町内を流れる藁科川の河原のこと。
・机平ツクエダイラ:平和協定を結んだところをいい藁科川の向こう側で、吊り橋を渡った先の左上の平坦な大地である(平原氏談)。今は廃棄茶畑と建築業の資材置き場、携帯電話の電波塔らしきがある。おそらく古道は机平上端を水平に通過し、坂の上集落と四十一坂を下った先の茶畑を結んでいたのだろう。
~坂の上集落で公民館横の道を進み、橋を渡り向こう岸へ出て、四十一坂入口方向を目指す。
途中左民家裏に屋敷墓があり、庚申塔もある。(道からは見えない。)
・庚申塔:大正九年
~一旦集落北に向かい、大川保育園横を通過したカーブに石塔がある。小字の南と高沢の境あたりなのか。
・庚申塔:昭和三年
・庚申塔:昭和十年九月宗野ひさ
・庚申塔:大正九年
・石塔?:昭和三年□月吉日
・手洗石:
・花挿し用の石3:中村辰也
~方向を変えて南に向かう。集落南はずれの民家に地蔵がある。
・地蔵
・丸石:道祖神か?
古道はもっと高いところを通っていたのだろうが、自動車道は中腹を通過し途中机平の平坦地を抜け、河原に広がる畑に向かい降りて行き、方向を下流の四十一坂入口方向に変える。ちょうどそこに13基の石仏が合祀されている。ちなみに畑や道ごと金属ネットの檻のような柵で囲われ中へ入れない。平原氏の地所だそうである。
・地蔵:
・奉納 一国三十三所 西国三十三所 文政六年
・西国一国善光寺三十三所供養塔
・庚申供養塔 天明ニ壬寅年
・?観音
・?西国三十三所
・西国三十三所 天明二年
・西国一国三十三所 文政
・西国一国三拾三所供養塔
・?石塔
・?石塔
・?観音
・三拾三所供養塔
~県道に戻り北上する。~
坂ノ上神社山下の道を抜けると宇山集落である。ここからも坂ノ上神社の裏から上る道がある。
・坂ノ上神社への参道(坂ノ上 宇山)
古かった参道は新たにコンクリート舗装され神社まで車で行けるようになったが、古道の赴きは消失。神社のある尾根付近で畑色へ向かいさらに洗沢峠を目指す古道(秋葉街道の枝道)があるはずだが、新しい参道から分岐点目視判別不能なので、よじ登ってみたが、新道から尾根に上がったところは炭焼き小屋跡で尾根上に踏み跡はあるが、特に分岐点を示す石道標や歴史遺物は見られない。
~県道に戻り、宇山集落、宇山バス停付近、「八幡まで8.5km 笠張峠まで24.0km」標識のある所に石塔物がある。
・奉
・庚申塔
・奉納 森藤□□蔵
・馬頭
・石塔
・手洗石:奉納 永野
・地蔵
???・平石:バス停より徒歩2分上に、名馬摺墨と老婆の足跡がついているという。かつてあったようだが今はない。分かる方お知らせください。
・この先「巽荘」という看板の?元酒屋がありその先は茶畑で、その茶畑を上っていき北の尾根を目指す登山道がある。かつては畑色や上杉尾を経て洗沢峠にいけたようなので
秋葉街道の枝道として登山口を調べてみた。登山道入口付近に石道標や遺物は見られない。
○~坂の上から県道北上し、この先で立石橋を渡ると左川沿い道が本道で右上に上る道が栃沢への道~ この道は県道大川静岡線。
かつては奥長島から栃沢に抜け坂ノ上等に出るのが本道だったようだが、自動車道が川沿いに作られて一変した。
この分岐点のカーブミラーの真下の暗がりに石造物がある。
・石道標:とちさわみち
・馬頭:
・□□□観世音:壊れて横倒し
~栃沢を目指し上っていく。~
○栃沢
左が山の崖になると石仏がある。
・庚申供養塔 大正九年
栃沢の家が見え出すと神社入口がある。
・子安神社(栃沢)
・祝大正十五年車道改鑿
・火坊鎮守
・板碑:
・石灯籠2:昭和三十(廿の三本)七年
・鳥居:金属製
・石鳥居:?
・板碑:
・石灯籠2:弘化四年
・狛犬2:昭和四十二年
・手洗石:明治三十二年
・手洗石:慶応四戌辰
・手洗石:
・祠2
主要道を奥へ進むと米沢家で聖一国師碑がある。
・米沢家(栃沢)
???聖一国師生家、摺墨の馬蹄石(見られない)、
・聖一神光国師誕生地 昭和七年
・句碑:昭和三十八年
・三夜燈 安政四年
・三夜燈 寛政十一年
・庚申塔 大正九年
・?庚申塔
・石塔:家の門前
・石灯籠2:弘化四年:家の裏
・祠
・五輪塔
・墓石2
裏に自宅墓地がある。
手前のお宅の庭にも石塔がある。
・石塔:記念
更に主要道を奥に進むと寺がある。
・竜珠院(栃沢)
木像:薬師如来
・六地蔵:?
・手洗石:
・有縁無縁三界萬霊等
・三界萬霊塔
・有縁無縁先祖代々精霊等三界萬霊
・祠、小さい地蔵多数
・割れ石
・□神山
・鎮守
・割れ石
・祠:弘法大師
・観世音
・水差し石
・花挿し石2:
・如意輪観世音 大正十二年
寺を過ぎもう少し進むと岩の上に石仏がある。
・馬頭観世音
更に奥に進むと突先山ハイキングコース、ティーロード入口標識となる。この道が釜石峠を経て足久保に至る古道といえる。釜石峠には通称:歯痛地蔵といわれる如来(石道標にもなっている)が祀られる。
3月にはこの入口付近に淡い黄色あるいはカスタードクリーム色といった色合いの花が冬枯れした野に咲いている。近づくとほんのり上品な花の香りが漂ってくる。枝先が3つに分かれていてミツマタの花だ。枯れ枝に似たような色合いのため地味で目立たず、遠目にはあまり綺麗とは感じられないが、香りはよく春を感じさせる。この時期各所で遅咲きの梅の花や桃花、早咲き桜とともに遭遇した。
○釜石峠 (*美和街道を参照)
奥長島と栃沢の峠。歯痛地蔵と呼ばれる大日如来が祀られる。かつてはお堂もあったようだ。大川から静岡市街に出るにはこの道を通った。
峠から南尾根を通ると突先山に至り、さらに大山を経て坂本に出られた。
峠から北尾根を通ると中村山△1007.0mを経て樫の木峠に出られ、玉川または大川に下れた。現在樫の木峠から中村山方向への尾根道は、一見すると藪道のように見受けられる。
釜石峠H820m。以前と峠の位置が変わったような気がする。この峠、平で広く東西50m幅ある。以前標識や歯痛地蔵は東端だったと思うが、今は西端である。歯痛地蔵(大日如来像)「是より 右ハ美和村あしくぼ 左ハ玉川村たくみ」となっていて、東の足久保奥長島と北の中村山・樫の木峠経由内匠へのコースを示す。西へ下る道は栃沢へである。
・歯痛地蔵:大日如来「是より 右ハ美和村あしくぼ 左ハ玉川村たくみ」
この先は美和街道・足久保街道である。*玉川村は安倍街道を参照。釜石峠や突先山周辺に関しては兵藤庄左衛門・Seeesaブログ・スポーツ・玉川トレイルレースを参照。
~県道の栃沢分岐点に戻り日向に遡上する~
バス停「森林組合前」の日向集落手前に橋がある。この辺りを森の腰というらしく、人家や石垣がある。かつて日向の白髭神社ははじめ松の平にあったが、次に森の腰に遷座した。その後今の場所に移転したようだ。石垣は近代のものだろうが人が生活していた家や畑の証拠とも言える。橋があり対岸に渡ると切杭である。橋を渡った正面に小長井宅(屋号ヨコベエ)があり、このお宅に許可をもらい家の横から裏山に上らせてもらう。家のすぐ裏には屋敷神の祠があり、裏山急斜面を3分も登ると祠がある。
・切杭天神が祀られている。さらに裏山を上っていき畑色に至るだろう切通しの旧道が伸びている。きっと途中で廃道だろう。ただ地図上ではそれほどの距離ではなく上の畑色の舗装道路に至れるようだ。上に道があるだけでなく、今の舗装された平地の道より上の山斜面上の今の道より20mほど上の植林地内を等高線に並行した旧道が付いていることも確認できた。 またこの上の方に池の段という昔の池の跡があるようだ。伝説ではこの池から土石流が流れ地形を変えたようだ。池の主の蛇が出て行ったというのは土石流の流れ跡をさすようだ。切杭には土石流が流れる前まで生えていた大木の根株が時々露出することがあり、まさに切杭である。
もう少し切杭側の藁科川を上流側に畑に沿い舗装道路をつめていくと行き止まりとなる。行き止まりの10m手前から山に取り付く登山道があるので上っていくと5分で、切り立った細尾根先端部に出られ向こうはフドウボツの沢である。細尾根先端部山頂には祠がある。
・不動明王(石仏)が祀られている。藁科川対岸はちょうど福田寺のある丘が正面に見える。
・伝説「切杭本社の木魂明神」
日向に原坂宅に美しい娘がいた。ここに毎夜美少年が通ってくるようになった。どこの少年か不明で、母は娘に少年の袴の裾に針で糸を縫いつけるよう指示し、そうしたところ、糸は大木まで続いていた。少年は大木の精だった。大木を切ることにしたが、切っても切っても翌日元通りになっていた。そこで切った屑をすぐ焼き捨てては切っていったところ、木はキリクイという異様な音を立て倒れた。ここをキリクイという。
その大木で空船ウツロブネを作り、娘を乗せ川に流した。安倍川の舟山で船が転覆したので、そこを舟山という。途中赤沢の対岸に娘の櫛が落ちたのでそこを櫛筐峠クシゲ(クシバコ)トウゲというそうだ。
この大木は高さが33間、梢を杉尾村で望めたので、そこで杉尾という名になった。原坂家では麻を作らないようになった。またこの家で生まれる女子は美人だといわれる。この大木老杉を木魂明神という。
~ 集落入口の県道に戻る。
日向 小向の集落入口に達する。崖上の2箇所に石仏を祀っている。日向の地名は日当たりがよい東または南向きの場所を指すそうだ。ここの地形は古くからのものではなく川の流れの変容により変化したと考えられている。
またこの藁科川と籠沢が合流する辺りには大木の根元の株が出現することが近年まであり、キリクイ切杭の伝説となっている。イケノダンが決壊しマコモノハラを押し流したという。その土地には大木の切り株(切杭)が今でも出るというので切杭という。
・マコモノ原:日向字堂上で大川小学校前の平坦地を指すようだ。
・小長井家屋敷跡:大川小学校の辺りのようだ。
○石塔(日向 小向)
○馬頭観音8基
・大正十五年
・大正十年
・大正十三年
・大正十三年
・為紀念征露
・明治二廿一年
・明治四十年
・明治二十一年
かつて字(アザ)チャアラと字ヤスミイシの境である。ここに馬頭観音を祀ってあるのは、昔から急カーブ地点で馬がよく落ちたからだそうである。
○庚申塔7基
年号は明治38(1905)年から昭和12(1937)年まで。
・昭和十年
・明治四十二年
・
・
・昭和十二年
・昭和十□年
・明治
川沿いに通過するのが新県道であるが、集落内に入る道が旧道であり、旧道に沿い進む。
集落内に張り出した舌状大地の上が神社と寺である。そしてそこへ上って向こうの小学校に下る道が古道である。
ちなみに手前右に林道起点ある。
○~林道:樫の木峠線、この龍沢を奥に詰めて行くと樫の木峠に至り玉川内匠に昔は出られた。幕末明治期探検家:松浦武四郎「東海道山すじ日記」はこのルートを通過している。~
・樫の木峠
途中、祠(剣宝社、けんぷん様)、萩多和城跡石碑通過。峠には幕末期石地蔵1基。そこから林道で川島に出られる。地蔵近くから旧登山道を下り白石沢沿いに内匠に出られたが、おそらく廃道同然か。
・飛神天神:日向集落出口から樫の木峠へ向かう旧道付近を指すようだ。今の林道より20mほど上になる。集落上部から山の中に入る旧道と推定される人為的平坦地の幅1~1.5mが部分的に残存しているので、これが旧道(古道)と推定される。この道を松浦武四郎も通ったはずだ。かつては何かが祀られていたのかもしれない。ただ地元でもトビガミテンジンといっても不明で、集落と山の境付近の上(林道出入り口より真上)の天神テンジンといえばわかる人がいる。ただテンジンと言うと、けんぷん様の先にある天神を示されることが多いので混同注意である。集落の人への言い方としては、昔山の畑に行く時に通った村集落と山の境の天神はどこかと聞いたほうがいいかも。
このトビカミテンジンの旧道(藪で道とは思えないが、人為的平坦地なので、かつての古道と判断できる)を奥に10mも進むと開墾された茶畑上部南端に出る。ここで一旦旧道は消失するが、茶畑を北へ水平移動していくと、北端の動物用罠の檻上部に平坦地があり、奥に進める。すぐに建物の後背部に到達し後背部に沿って平坦地が続いている。更に進めそうだがここでやめた。地図上ではあと数十mで沢に達するのでそこで道は消失するだろう。
・祠(剣宝社、けんぷん様):昔女性の修験者(巫女)が、この先、於万津ケ淵の滝壺で亡くなり、里人がここに祀ったという。歯の神(山里に多い)・山の神と里人に祈願崇拝された。歯の痛いとき、けんぷん様を拝むと治ると昔から言われている。治ったお礼として剣を奉納した。~「野山の仏」戸塚孝一郎より、取付:城北、坂本~
現在林道脇に祠と説明書きが見られる。
・お松が淵:けんぷん様の先にあるらしい。於万津ケ淵。
・天神:けんぷん様より更に先で旧道が籠沢沿いから尾根道に移る辺りで、林道が籠沢からヘアピンカーブして沢をまたぐ橋を渡り沢から離れ山斜面に急激に登り出すところで、ちょうど「夕暮れ山・樫の木峠登山道」が山斜面に取り付くところで登山標識がある。林道より高いところを通っていた旧道が一旦沢に降り沢を渡る辺りを指すようで、林道をまたぐ橋のすぐ横の茶畑付近を天神というようだ。かつては何かが祀られていたのかもしれない。
*以下に、樫の木峠や一本杉峠の参照用に、兵藤庄左衛門、Seeesaブログ、「夕暮山、中保津山、樫の木峠」を全文掲載する。
・夕暮山、標高1,026m(静岡市葵区内匠と大川の境、樫の木峠の北1km、一本杉峠・天狗岳の南2km)及び、中保津山、樫の木峠
夕暮山への場所は上記の通り。登るには林道樫の木峠線を使い樫の木峠を目指すか、一本杉峠を目指すかである。大川・日向で林道樫の木峠線へ入り3km進むと大きく広く右カーブする所がある。ここに標識「樫の木峠、夕暮山」がある。徒歩ならここから登るのがよいが、道の状態は知らない。植林内で踏み跡はし
っかりしているかもしれないが、雑草はあるだろう。車なら林道を詰めたほうがよい。登山道もこの上で林道に合流し林道歩きになるので。
林道をさらに2kmも行くと先ほどの登山道と合流する。林道をなお進み夕暮山の南西尾根の△769.3mより上の辺りで「萩田和城址記念碑」と説明版がある。これを過ぎて0.5kmで切通しをくぐる。ここの左(北東)尾根に標識「夕暮山→」がある。ここから登るのが最短なようだが、いきなり雑草だらけなのでやめたほうがよいかも。この上で林道一本杉線も横切っているので、その林道を行ってからこの尾根に取り付く手があるかも。林道樫の木峠線をさらに200mも進むと左に林道一本杉線があり、工事中となっている。上を仰ぐと先ほどの尾根を上で横切っている。ここを通って上で尾根に取り付けそうだが、未実施。林道樫の木峠線をさらに進む。10年9月林道が急に荒れギャップがひどい所があったが、500mで樫の木峠へ出た。ここに石仏一つと樫の木がある。ここから北西尾根へ標識「夕暮山・造林展示林→」があり、もっとも無難な尾根コースだろう。夕暮山からさらに北へだらだらの平坦尾根を通って天狗岳や一本杉峠へ縦走できる。展示林となっているから少しは道が整備されているかもしれないが、未確認。樫の木峠から南へ尾根を伝うと中村山へ通じるが、峠から南へは雑草だらけで、踏み跡をたどるのはきつそうだ。標識も無い。
一本杉峠・天狗岳へは玉川・横沢から井川・富士見峠への県道を行き、権現(臥竜)の滝を過ぎ500mで一本杉峠登山道がある。これを詰めるか、反対側の大川・諸子沢を詰めるかである。しかし一本杉峠の南西尾根を詰めることもできる。横沢から井川・富士見峠への県道を富士見峠手前の笠張峠で大間へ曲がるか、大川・湯島から大間を経て笠張峠方向に行く。切通しの分水嶺を横切ると、林道一本杉線の看板があり、南東尾根に沿い林道が延びている。左に別の作業道も分岐している。林道はそれほどアップダウンはないが、ギャップなどが多く荒れている。3km進み△1013.3mのピーク(中保津山)手前500mで林道が2つに分岐する。
右は別の林道で4.5km尾根を進んだ諸子沢の上辺りで行き止まりである。が、工事中で延伸するのかもしれない。
左の林道を進む。中保津山を右へ巻くようにして平坦な尾根に出る。ここも道が分岐し左は私有地でチェーンが張られている。右にまたピークを巻き尾根道が下りだす。この下に一本杉峠があると思われるが、夕方で引き返す。後日再調査予定。峠までは林道はあると思われる。
先ほど樫の木峠の近くにも林道一本杉線の看板があったので、そことつながるはずだ。10年10月、大間の県道から一本杉峠辺りまで林道はついているようだ。この先天狗岳や夕暮山の尾根の西を通過してつながるものと思われる。
△1013.3mのピーク(中保津山)へは林道の雑草の切れた辺りからピークを目指せばよいと思われる。諸子沢上への林道しか無い頃は林道がピークを巻く辺りから踏み跡をたどって登れた。今も草を掻き分ければ標高差わずか30mほどで登れるだろう。
樫の木峠へ話を戻す。樫の木峠の石仏の左横に下る踏み跡がある。かつての「白石沢ルート」である。林道が開通した今となっては使う人はまれだろう。80年代末に通ったことを報告する。内匠の白石沢の横を通る林道白石沢線を2.5km詰めると行き止まりで堰堤となるが、登山道は奥に続くので徒歩で沢沿いを行くとすぐに石仏がある。自分では道なりに進んだつもりが、この石仏の所で道は分岐していて本当は右に行くのだが、間違って直進した。樫の木峠への沢より1本南の沢を詰めてしまった。沢沿いにきれいな林業用作業歩道が付いていてそれをひたすら詰めたが、何か変なので引き返し地元の人に話を聞いたところ、石仏のところで間違ったことを知った。
後日再アタック。今度は石仏で右折し沢横を詰めていく。峠直下と思われるところで、沢を渡る。ここにも石仏があるとのことだったが見ていない。渡ってしばらくすると急斜面を巻いて登りだす。登りきると峠である。
これらのコースは、登るなら雑草や蜘蛛の巣が少ない11月下旬から6月初旬までが最適だろう。
~日向集落内旧道を進むと右上に寺と神社がある。
ちなみに樫の木峠・籠沢から来た秋葉道(樫の木峠林道より20m上で集落最上部の家の裏山を下ってくる感じである)は今の集落や畑と裏山の境の辺りを回りこみ白髭神社・福田寺に上ったようだ。
付近のお宅には屋敷墓があり、その中に供養塔が混じっていることもある。
付近の屋敷墓で
・先祖代々有縁無縁三界萬霊等 明治十九年七月日
上記を発見したが、まだまだ他のものはあろう。
○白髭神社、朝旭山福田寺観音堂(日向 千田)
白髭神社はもとは能又川と藁科川が合流する手前の松ノ平にあったと伝えられる。松ノ平は下湯島手前から下に降りる林道を下ってすぐの茶畑のところである。本社白髭大明神、藁科八社ともいわれた。
・DVD「日向の七草祭(静岡市) 静岡県指定無形民俗文化財」静岡市教育委員会、ふるさと民俗芸能'ビデオNo.5、'93、27分
安倍川支流の藁科川を車で40分遡ると静岡市(旧大川村)日向集落で、日向は静岡市山間部の旧秋葉街道沿いで中世に城もあった大川地区の中心地で戸数88戸である。産業は水田、林業、茶、椎茸である。七草祭は旧暦1月7日の七草の夜に行われるための呼称である。場所は朝旭山福田寺観音堂境内の仮設舞台である。フクデンジ。
川根本町田代・大井神社の神楽との類似性が指摘される。かつての領主土岐氏の勢力範囲に重なる。西遠州の猿楽・田楽の流れを汲む稲の豊作を祈願する田遊びである。付近には大間(福養)の滝(大間)、聖一国師の生家(栃沢)、(日向)陽明じには「木霊明神の縁起書」:切杭本社は川底に水没したが、庄屋の娘と木の精の大蛇との悲しい物語、大蛇の子を孕んだ娘は空ろ船で川に流され、あとを追った母が娘をこいこがれた場所が木枯らしの森という。藁科川流域には建穂寺(観音堂)という巨大寺院がかつてあり、福田寺とも関係していたと考えられる。
祭りに先立ち毎年持ち回りの8軒の当番は様々な行事を行う。大浜海岸、潮花汲み:海水で祭りの場や家々を清める。浜石も採る。柳採り:柳の枝を切り取る。陽明寺和尚が絵馬札刷り「牛王法印」を行い、その紙を柳に挟む、札は祭り当日村人に配布される、札は豊作願い田の水口に挿す、舞練習は日向町内会集会所、大人に混じり子供たちも熱心に笛太鼓を行う。旧暦正月6日(この年は1月28日)、大日待頭屋:会食料理、床の間に浜石と潮花、境内では清掃と舞台作り、大日待の料理作り、各家々へ潮花配り:仏壇や家屋内を清める、頭屋では餅つき:丸餅とのし餅、水に漬けておいた米で「はたき餅(シットギ)」、大川地区連合町内会集会所:大日待行事、日向地区各家代表集まり会食、浜石、潮花、はたき餅、今は料理一部仕出しだがかつては割り子に詰められたもの、舞揃え:舞練習総仕上げ、旧暦正月7日(この年は1月29日)七草祭当日、町内会長が観音堂の厨子を開き掃き清める、福の種、お供物、万延の詞章本、寛永の詞章本、翁面箱、笹竹13本、3本使って舞台中央に組む、重しに浜石使う、舞台が神聖な場であることを示す結界、日の出祈祷、御詠歌、抹香を酒で溶いたものにネッキという棒で牛王の印をつき札作り、ネッキの一方「牛王」反対側「仏法僧」というが定かでない、参拝者の額にも押す、一年の無病息災、36本の御幣、小豆入り餓鬼の飯を境内各所に供える、境内清め、大地の神を鎮める、施餓鬼:観音堂裏山宝篋印塔、水垢離:一日7回水清め、今でも1回は藁科川で清める、夕方7回目の水垢離代わりに笹垢離をとり舞台に向かう、見物人いっぱい、
構成は1、歳徳神礼拝トシトクシン、2、大拍子、3、申(猿)田楽:舞手6人輪、中に笹竹、幣の色で役割、笹持って回る、扇子で胸当て袖持って足挙げ、体を回す、拍子が速くなり扇子打って回る、笹竹13本舞台上げ、4、駒んず:笹竹根元足で固定し揺らし打ち合わせ詞章を囃す、春駒、繭豊作、馬と山鳥、馬は蚕の始まり伝説由来、山鳥は蚕のはきたてに羽を使うため取り入れたらしい、5、浜行:背負う桶に海の幸、潮花を神前に供え、滑稽に海幸配り、・若魚ワカイオ:近隣の神楽「オオスケ」と同じく神の一種、神聖な海水を祀り神々の祝福によりて五穀豊穣を約す、・(近年付加)女の子の舞、・順の舞、2回繰り返し、初めは試し上演と考えられる、浜行若魚2回目、滑稽バチ男根見立て、潮花振り掛け清め、(休憩)、後半が本上演と考えられる、翁面と詞章本を舞台上に出す、6、歳徳神礼拝、7、大拍子、8、駒んず、9、数え文カゾエモン:太鼓に米撒き田に見立てて、神歌、稲草、福の種、鳥追、田植、穂孕み、取り入れの内容で村の歴史とかかわるのだろう、福の種と鳥追に所作あり他は詞章のみ、、10、猿田楽、このあと一同本尊礼拝終了、
このあと今は福引。
旧暦1月15日(この年2月6日)、鈎取の佐藤家、太鼓の田に撒かれた米で粥作り、家屋内に供え、福田寺にも供え、粥を食べ、村人への活力を分け与える。
・朝旭山福田寺:建穂寺の奥の院。以下木製、千手観音坐像:推定江戸期前半、彩色なし菩薩像:推定平安期:欠損している、二天像:東方天・西方天:江戸期前半17世紀後期~18世紀初期、
・白髭神社:春祭り4月第1日曜日、秋祭り10月第3または第4日曜日、男女神像:江戸期後期、保存状態よくない、木製、
・石鳥居:大正十四年
・石鳥居:平成八年
・手洗石3:
・石灯籠5:昭和九年…2、□永九年、
・石碑:昭和十二年
○庚申塔38基、割れ石 (44基?)
年号は宝暦二(1752)年から昭和三十(1955)年まで。日向では個人的に病気平癒の願果しとして建てることがあった。個人名を刻んだものも多い。造立数の多いのは大正九(1920)年の7基である。
*一般的には庚申塔は、更新講中により庚申縁年(60年に1回巡ってくる庚申年)に建てることが多く、他にも合力祈願や供養として建てることも多い。
庚申講は、庚申の日が60日に1回巡ってくるので1年で6回は行った。庚申講は床の間に青面金剛の掛軸を掛け、全員で唱えごとを21回繰り返してから拝む。その後飲食をするのが楽しみであったようで、信仰心と、娯楽としての宴会、世間づきあいの世間話で盛り上がり、庶民の楽しみだったようだ。当番は輪番制であった。(「日向の七草祭」より引用を含む。)
・大正五年:後列右より
・大正八年
・
・
・明治三十(廿の3本)六年
・大正八年
・
・大正四年
・昭和十一年
・明治三十(廿の3本)八年:後列2列目右より
・
・明治十八年
・明治三十(廿の3本)三年
・大正元年
・昭和四年
・
・明治四十四年:後ろ3列目右より
・明治四十年
・大正九庚申年
・大正九庚申年
・大正九庚申年
・大正九年
・
・大正九年
・昭和四十四年
・割れ石
・昭和十七年:最前列右より
・昭和七年
・大正九年
・大正十二年
・昭和八年
・昭和十九年
・昭和三十七年
・昭和九年
・昭和三年
・□□□年
・昭和十四年
・大正十二年
・昭和□□
裏山に上っていくと
・祠:弘法大師
・秋葉山三夜燈 寛政十一年
裏山の頂に立派な宝篋印塔がある。
・宝篋印塔
またここは萩多和城の南朝方支城の一谷城跡である。尾根伝いに上っていくと萩多和城跡に行くし、夕暮れ山や樫の木峠にも行ける。尾根より下の神社から中腹を通っても行ける歩道がついている。一谷城用水路跡で樋道という。突き当りは樋口という。現在、尾根道には夕暮れ山ハイキングコースの標識がついている。
先ほどの尾根コースと反対に福田寺西側の丘上は畑と墓がある。どうもこの墓のことを
・ネギヤの屋敷墓というようだ。
尾根と西側丘の間に空堀のような切通しの道が下っていく。
・古道
小学校方向へ下る古道をとる。御堂坂という。学校手前で旧道舗装路に出る。わずかな距離だが古道残存部である。学校前の平地の辺りをマコモノハラというらしい。学校前の旧道をたどると学校向こうで立派な門が見える。その先に寺がある。ちなみに古い秋葉街道は旧道より1本川寄り(新県道寄り)の狭い道である。
・農家の茅葺の門
○陽明寺(日向 中村)
開基:雲叟、1510年、日向村に一草庵、
・六地蔵(新)
・石製家型道祖神
・石造物(古)
・地蔵
・地蔵
・□□巡霊等
・地蔵(新)
・板碑
・忠魂碑
○1列に並ぶ石仏
・地蔵:明治二十七年
・?馬頭:明和七庚寅天
・?馬頭:明治二十四年
・?如来
・?馬頭:法傳 諸子沢村
・如来:
・西国三十三所
・十一面観音:諸子沢村 送精
・馬頭:八手、?阿弥陀、大きい:大正十五年
・馬頭:大正十年 佐藤善作
・西国三十三所供養塔 明治十九年
・馬頭:明治五□
・馬頭:八手、
・?馬頭:
・?馬頭:森下常吉立
・観音:
・馬頭:昭和十三年
・地蔵:
・地蔵:
陽明寺前の旧道を下るとすぐに今の(新)県道に出る。その県道向こうの河原に向かうとすぐに石道標がある。掛川市在住の広谷氏の報告及び「日向の七草祭」所収されたものである。
・石道標:右湯島諸子沢 左洗沢秋葉山 道
近代のものであろうがルートとしては近世に準じたところにある。ただこの下につり橋があって渡れるがそこから先に道は消失している。この上の茶畑の石道標につながる道は新たに舗装路を作った際消失したようだ。広谷氏によれば東海道山筋日記コースを東京から西に向かってきて、初めて目にした秋葉山の道標だそうである。
~県道に戻り奥へ進む。~
・新しい地蔵(日向 中村)
八幡へ11.5km表示近く県道沿い。
○~この先、城山橋のところで右折で諸子沢、左折で城山橋渡ると畑色・杉尾に至る。いったん諸子沢に向かう。~
○諸子沢 モロコザワ ・大道島
・白髭神社、大日堂
右折してすぐに白髭神社、大日堂の標識がある。100m上ると境内である。神社の祭りは2月建国記念の日、10月第2日曜日。
・石鳥居:昭和二十七年
・手洗石:寛政十戌午十二月吉日
・奉納大日如来 寛政十年
・石灯籠:奉納白髭大権現 寛政十年
・石製家型道祖神
・馬頭観音 昭和廿二年
・馬頭:享保二十年
隣にお堂がある。
・大日堂:木製:大日如来、薬師如来、弥勒如来:江戸期
~更に諸子沢を進むと時計台(新)や花壇を通過する。次に平の尾や地蔵堂への分岐点が上を目指すので地蔵堂へ行く。
○地蔵堂
前に石仏が合祀されている。じぞう祭りが8月24日にある。
・手洗石:三角形
・庚申塔
・庚申塔 昭和十二年
・庚申塔
・庚申塔 昭和十五年
・庚申塔
・庚申供養等
・庚申塔 大正九庚申年
・?石仏:
・?馬頭観世音:
・西国三十三所 文久二壬戌七月
・奉納西国三十三所 明治拾八戌年
・石仏:□□二十二年十二月建
・石仏:割れている
・ほていさん(新)
・西国三拾三所
・?石仏:転倒
・?石仏:割れている
・西国三十三所 明和
・?石仏:割れ
・西国三拾三所 天保三壬辰
他にも割れたり崩れたりしていていくつあるか正確には不明。お堂の前を旧道(古道)が下っていくのが分かる。一部古道残存。
~また舗装路を戻り奥に進む。舗装路の上に寺が見える。日陰橋手前道沿いに石塔がある。
・庚申塔
・庚申塔 明治四十二年
・庚申塔
地蔵堂の上を目指すと平の尾集落である。
・平の尾:急斜面沿いに集落が展開している。この更に上に向かい林道が続いている。
・雨降松開拓地:林道が尾根に到達した所の平坦地で茶畑が続いている。無人だが家が1軒ある。かつて雨降り松なるものがあったようだが、今はない。そこはちょっとした空き地というか公園みたいな休憩所になっている。
*この上の平の尾と大間方面は山越えの林道でつながっているが、そのことは「インターネット、兵藤庄左衛門、さぽろぐ、林道一本杉線」を参照してください。一応全文掲載します。
・林道一本杉峠線(静岡市葵区、大間~一本杉峠~天狗岳~夕暮山~樫の木峠~大川)まだ工事中でつながっていない、林道川久保線、林道峯諸子沢線、林道八重枯線、林道京塚線、及び付近の作業道
実は(静岡市葵区、大間~△1013m「中保津山」~諸子沢平の尾~川久保)
2010年10月、天狗岳から夕暮山区間は工事中で、一本杉峠付近はまったく手付かずであるらしい。
大間の南アルプス公園線県道分岐から一本杉峠の1km手前の△1013m「中保津山」までは林道になっているが路面はギャップ(クレバス、えぐれた溝)があり、通行しにくい。樫の木峠近くの林道樫の木峠線からの林道一本杉線への分岐は工事中通行止めである。おそらく夕暮山付近で工事中と思われる。
大間の県道分岐へは藁科街道を上り、湯の島や大間集落を通過し福養の滝レストハウスを抜け、笠張峠方向へ県道を進む。地すべり箇所の赤い回転灯の1km手前の切り通し箇所で東に分岐する「林道一本杉峠線」標識がある。すぐ左に林道「京塚線」があり道も開いているが、どうも行き止まりらしい。途中いくつかの林業用の作業道も横切っていくが、多分どれも行き止まりだろう。直進で2km進むと右へ下る「林道八重枯線」がある。多分「国土地理院、地形図」の・1037mから・878m付近の尾根をたどる道と想定される(が間違っているかもしれない)。
もう1km進むと道が平坦でY字に分岐する所に出る。分岐点の中央奥にあるピークが三角点所在地△1013.3m「中保津山」である。ただ山名が本当にこの名前なのかは不明である。十数年前に上ったときにこの山名のプレートがあった。ここから尾根沿いを歩いて上っても10分足らずだ。今回2度目に上ってみて三角点はあったが標識はなく、付近の様子も植林の暗い中でそのことは前回同様だが、測量されたらしき雰囲気がない。測量すると付近の樹木や草を刈り払い標識を立てるように見受けられるが、そういう痕跡がない。国土地理院は4等以下の三角点をあまり用いなくなってきているのか。登山道は送電線巡視路になっているので踏み跡はしっかりしていて草刈が行われているので信用度は高い歩道だ。中保津山を越えて尾根をさらに東へ1km歩けば一本杉峠に至るはずだが、今回は時間が無くあきらめた。
話をY字路に戻す。左の道は「私有地で立ち入り禁止」とあり、チェーンが張られている。この道は作業道で1km先の送電線まで進み下り出し、臥龍(権現)の滝のある井川へ行く県道方面へ下りかかって行き止まりになっている。
Y字路を右にとる。500mも進むと道が下りだし、道がひどく荒れギャップ(クレバス、えぐれた溝)が多く、ダイハツ・ハイゼット660cc では道幅全体の中の通りやすい所を選んでゆっくり通過したが、たまに車底をこすった。オフロード車はがんがん通ったがこちらはまねできない厳しい道だった。4WDスイッチがあって助かった。この部分の道を上ることもしたが4WDでないと上れないだろう。1km下ると平坦になりついでに舗装までされている。見晴らしがよく送電線高圧鉄塔に沿って道は南南西に進む。舗装が切れるが道は直進している。そこの右から「川久保林道」が合流してくる。
「川久保林道」は藁科川沿いの県道を湯の島から大間に向かい2km上って行くと、右に「川久保林道」の標識と上る道が見える。この林道は一応コンクリート舗装がだいぶされているが、クラック(割れ目)だらけででこぼこといっていい。しかし土道に比べればはるかに通行しやすい。4~5km上ると尾根の林道に合流する。途中幾度か作業道が分岐するが、そちらは通行禁止の標識があるので道を間違えにくいとは思う。(13年3月林道入口改修工事中で出入り不能。)
話を尾根の林道の川久保林道合流点に戻す。さらに直進していくと送電線付近は眺めがよく高原の草原のようだ。草原を過ぎると道は下りだす。しばらく行くと「林道峯諸子沢線」の看板がある。しばらく下ると茶畑と人家のある所に出る。「雨降り松」の休憩所もある。ただ松の木は見当たらなかった。人家はあっても現在休憩作業用らしく無人である。ただここからの林道は道の状態がよくなる。普段から人が使っているからだろう。2~3km下ると平の尾集落に出る。ここからは急坂で狭いが舗装路となり、諸子沢の主要道に出て、藁科川沿いの県道に戻れる。
「平の尾」集落を下っていき大道島へ行く諸子沢本道に出る手前に「地蔵堂」があり、石仏も多数あり、古色が漂う。他にも藁科川沿いや諸子沢川沿いの道に石仏が見られ古色ゆかしい。
・吉祥寺(柿の平)
・石塔(新)
・石塔(新)
・地蔵(新)
・臼
大道島を目指す。自動車道の終点で堰堤の向こう岸がどうも峠入口らしい。
・一本杉峠上り口:はっきりしない
???・頼朝石:未確認
この奥?に頼朝石があるらしいが、20年以上前に上ったときもはっきりせず、堰堤工事が進み川岸がだいぶ削られ登山道もはっきりしない。わかる方お知らせください。
○~県道に戻り、城山橋を渡り、畑色方向に進む。~
城山橋を渡ったところですぐ右(北)に歩道を探す。畑色と能又川(よきまたがわ)の中腹にあった集落「藁山わらやま」、「道光どうこう」に向かう道であり洗沢峠に至るルートでもあるので、一応秋葉街道の枝道として何か道標等歴史遺物はないかということで探してみる。山尾根に向かう登山道の切通しを発見するが道標等はない。この登山道が今は廃村になった集落「道光」を通過しさらに畑色の別荘地奥の養鶏場に出られる道のはずであるが、今は手前集落「藁山」はなく、奥側集落「道光」も1軒と少しの畑だけが残っているようだ。
さて畑色方向へ舗装路を進む。さて藁科川に突き出すように丘がある。
・城山:藁科川に突き出す小山、城を築こうとしたが矢が対岸から行ききってしまうので築城をあきらめたという伝説がある。
・石道標(日向)
掛川市在住の広谷氏や「日向の七草祭」で報告されているものである。対岸の中村の秋葉山道標と川を挟み対のようになっている。
城山橋より200m進み茶畑のある両側山のある城山の小さな峠を越えるところの右茶畑にある。
「従是 右往還 左秋葉道 天保五年甲午正月」。幕末明治期探検家:松浦武四郎「東海道山筋日記」はこのルートを通過している。この茶畑から尾根に取り付くが道は部分的にしか残存しておらず、強引に上る。途中滝を巻きその上部で沢を渡り上に上る。茶畑最上部の左下から作業道が伸びるのでそれを上る。そのうち作業道が下るので、尾根の旧道切り通しらしきを上る。廃屋小屋を通過すると上り道消失するので尾根を強引に上ると畑に出る。畑の左に上っていく道があるので行く。すぐ道は消失するが尾根を強引上りすると、畑色のメインストリート(主要道)舗装路に出る。10m先で舗装路は左に折れるが、尾根は正面なので正面上りの廃屋別荘地廃道に取り付く。右下に分岐する道もある。廃屋別荘地廃道を上って行くと新しい別荘地の道に出た。別荘地の道を上ると舗装路「林道畑色支線」に合流し、右(東)に養鶏場、左(西)に行くと山賊鍋ウッドカッター店前で主要道舗装路に出られる。どうも古道はこの合流点辺りで尾根に上っていったものと思われるが、現在まったくなし。山賊鍋店に行き舗装路に出て舗装主要道を東へ。尾根横に並行に進む。おそらく古道と同じルートではなかろうか。
話は変わるが、先ほどの養鶏場の下方向に行く道がかつてはあり、能又ヨキマタ川まで出られて途中に集落「道光」があった。昭和53年修正測量・国土地理院地図には人家があることが確認できる。現在、道は廃道か。
・蓄魂碑(日向 畑色)
別荘地の陽光台付近の尾根で別荘地入口横にある。かつては山神が祀られていたか。現在新しい「蓄魂碑」がある。隣に壊れた石があり山神なのか。もう1km尾根を進むと洗沢峠であるが、尾根下を通る舗装路があるので、尾根は廃道同然だが、私を含め物好きは強引に突っ切って峠に至れる。部分的には旧道切り通し残存。
この先で尾根に出て尾根左へ主要道、右に私有地林道、尾根の植林地内に取り付く。はじめは旧道切り通しがあるがそのうち消失、峠には1km。途中茶畑がある。
・大黒様、茶畑の神様(上杉尾)
尾根が茶畑になる箇所がある。真下に上杉尾の人家(おそらく上仲家、佐藤家)がある。茶畑に現代の大黒様があり、祀られたあとがある。設置は新しいが、祀られる行為は古くからあるのではなかろうか。あと500m強引にくぐっていくと、峠に茶畑、人家、お堂がある。
・洗沢峠(杉尾 洗沢)
犬2匹にさんざん吠えられあとを付けられたが噛んでは来なかった。頂上にはお堂、三角点。北側の景色がよく見える。上ってきたのと反対方向の人家3軒(かつて2軒でもう1軒増えたという記事が東海道山すじ日記1869年に見えるので140年以上同一戸数ということか、現在住んでいるのは1軒だけらしい。1990年頃ここに住んでいる人と話をしたことがある。そのときは家の近くに地蔵が祀られていた。そのときは3軒とも住んでいたようだ。また2000年頃も話をしたことがあり、川根街道を調べるため茶畑から南の藪に入っていたことを思い出す。そのときは1~2軒住んでいたのかも。)の前を降りていくと峠の茶屋前に出て、国道362号線。国道を渡るとお堂があり、地蔵や秋葉山石道標が設置されている。ここからは川根街道主要ルートとなる。今までがサブルートといってよい。
*川根街道主要ルート近辺の歴史遺物紹介は「古街道を行く」鈴木茂伸(静岡新聞社)の川根街道を参照してほしい。
~上杉尾~
先ほどの上仲家、佐藤家の下の方にお堂がある。
○観世音堂
堂内に多数の石仏が祀られており、境内に西国三十三所観音があるところをみると、三十三体の観音石仏ではなかろうかと思う。
・手洗石:佐藤
・奉西国三十三所観世音菩薩 文化十□正大二月
近くに火の見櫓もある。
~下杉尾~
坂の上の県道から下杉尾に向かう舗装林道を2km進む。坂の上から杉尾を経て洗沢峠を目指す古いルートでもある。杉尾川を渡る橋と「杉尾川起点ここより300m上流」標識、この付近ヘアピンカーブにもなるところである。橋手前に川沿いに歩ける登山道が川に沿って上流を目指していく。これが下杉尾から上杉尾更には洗沢峠を越えて秋葉山に行けるルートの古道残存部である、そこで秋葉街道枝道の歴史遺物はないか入口付近を探すが何もない。すぐ奥は倒木で通行困難。引き返す。
舗装林道を1.5km進むと下杉尾に出る。その手前に古道から舗装路に出る登山道取り付き点らしきもあったが、特に道標等は見当たらない。橋手前右に高橋宅がある。ここに地蔵と七人塚がある。集落近辺の舗装路下に神社がある。
・地蔵:高橋宅前茶畑端にある。
・七人塚:高橋宅前茶畑に上るとすぐに屋敷墓4基があり、その近くに高さ70cmの石垣が縦50cm、横1.2m積まれている。上は小木が繁っているがかつては更地でその上にお供え物をしてお祀りをしたようだ。年2回春秋に行ったようだ。いわれは伝説「落武者七人が杉尾に落ち延び弓の稽古をしていたが切腹した。彼らを祀った所だと言う。みさきがりという。」、下の神社向こうは武者が弓の稽古をした的当て場という。
・子神社
・石鳥居:
・手洗石:昭和十八年
・神社用地設置記念 昭和二十六年
神社前の道が旧道(古道)で川沿いを上りこの先の髙橋宅の裏に進み川沿いに上ると、この上の上杉尾に至るようだ。
???・池城、昔水があり池の主も住んでいたが、女性が汚れ物を洗い、大蛇と共に怒って流れ出ていった。どこか分かる方お知らせください。
・寺屋敷、小字マイガイト、278番地、畑の片隅に3つの石碑と一体の観音様があるそうだ。この近くに大きな杉の木があったそうで、安倍川から見ると尻尾のように見えたので、ここを杉尾という。坂の上の薬師様はこの木で彫ったという。杉尾集会所・火の見櫓より2箇所カーブを上ったところのカーブとカーブに挟まれた狭い所にありカーブ道の上下から見える。樹木の根元付近に石塔5基他破片がいくつかある。
・如来:文政三
・石塔:安永五
・石塔:元文五
・石塔:
・石塔:
・石塔破片いくつか
・道光 ドウコウ、藁山 ワラヤマ
~城山橋まで戻り県道を遡上する。~
・松の平
下湯ノ島手前で林道入口が左にある。能又川(よきまたがわ)沿いの林道である。丸山橋を渡り進む。この辺はかつて日向の白髭神社(藁科八社、本社白髭大明神)があった松の平というところらしい。付近に地蔵型の墓石と四角柱型の墓がある。ここは能又川と藁科川が合流するところであることが河原に下りると一目瞭然である。
1.3km進むと右(北)の湯の島側の山に向かい上る林道がある。上っていくと、中腹の茶畑を経由しつつ行き止まりで、更に先を工事中である。ここで対岸(南)の日向・畑色の方を見ると昭和53年の地形図に載っている中腹の集落跡が分かる。東側集落「藁山」はすでになく植林ではないが枯草色で藪らしいことが分かり、*(これは間違いで藁山も家一軒と茶畑が健在である。)西側集落跡「道光」は家と畑がはっきりしていてまだ人の手が入っているらしい。では林道を下り能又川沿いの分岐地点へ戻り、奥を目指す。1km進むと橋を渡り家畜用飼料小屋があり、右へ本道で、左に作業道で関係者以外立ち入り制限になっている。
・道光
元来た道を戻り、先ほどの林道分岐100m手前に川に降りていく歩道がある。これが西側集落跡に行く登山道で集落を越えて畑色の別荘地奥の養鶏場に至る道のはずであるということは、秋葉街道枝道でもあるので、何か歴史遺物はないか調べてみる。特に石道標等は見当たらないが、切通しだけははっきりついている。集落直前で竹林が繁りかいくぐることになる。1軒の家は閉まっているが作業小屋として常時使われているようだ。周辺の畑の一部も整備されている。まず集落西を確認する。城山橋から伸びてくるルートの確認である。はっきりしない。
茶畑の上に旧道登山道があるはずなので上ってみると切通しがついている。ここから上の畑色の養鶏場につながるはずだ。すぐに廃屋があり、それより上部は草木がかぶさるようになる。だいぶ廃道が進んでいるようだ。切通し以外遺物もないので引き返すことにする。
今度は先ほどの家の西側が道も広々して歩きやすそうなのでそちらに降りていくことにする。それにしても自動車が通る道だ。
広い道に近づいて更にギョッ、すごい驚いた!!! 家の前にイノシシがいる。後ろ左足を縛られているが、道をほじくりやたらと動き回っている。なんとそいつが私に気付いた。私の方を見て私に近づこうと縛られた足でもがいている。ドキドキである。あいつに噛まれたりぶつけられたりしたら重症だ。でも顔をよく見ていると牙はなく、メスかな? 鼻がやけに大きい、イノシシってもっと鼻が細長いと違うんか? もしかしたら、イノブタか?イノシシと豚の合いの子?あいつジーと私を見てロープ目いっぱい伸ばし私に近づいてる。あのロープほどけませんように。おそるおそるかつ足早にあいつを無視するかのようにして家の反対側に回った。ほっとした。さっさと元来た道を早く戻ろう。きっとあいつこの家の番犬ならぬ番イノブタなのだろう。今思うと近づいたところで写真撮影しとけばよかった。このところニホンカモシカ、キジ、猿は見かけるがイノブタには驚いた。
ちなみに猿は川沿いの椎茸ホダギにかぶせてある金属ネットを器用に取り払い、中の椎茸を食いまくっていた。ホダギはすべて金属ネットがかぶせてあるにもかかわらず意に介してないというか、このネット代金とかぶせる手間ひまは大変だろうに、こりゃ農家はたまらん。ニホンカモシカは人と出会うととりあえずジーと見つめてきますので、動きを止めすばやくかつおどさぬようにカメラ等を準備し望遠で撮影しましょう。うまく行けば2~3m距離で出会うこともあります。ただ逃げるときはすばやいというか、あとでカモシカがいたところに自分で行ってどう動いて逃げたか同一ルートを少し試せたら試してみましょう。何を言いたいかというと、人が歩いたり立ったりするのも困難なところを平気で走っていくので、その能力の高さに驚きます。追いかけることは不可能です。あなたが転落死亡します。キジはとっとと逃げるので撮影できませんでした。猿もすばしっこいです。ただこのところカモシカとの出会いが多いですね。天然記念物こんなに増えて大丈夫なのでしょうか。今のところ熊との遭遇はありません。そのうちあるかな……。
ちなみに後日ここでの茶園等畑の管理をしている湯の島の小沢氏に出会って道光と藁山を案内していただき、このイノシシ一件も聞いた。
あのときの動物間違いなく野生のオスイノシシだそうで、ちょうどこのときわなに掛かったイノシシを撃ちとめてもらうためハンターを呼びに行っていたそうである。夕方ハンターにより撃ちとめたそうで、肉はかたいので捨てたそうである。牙は小さいながらも確かにあったそうでオスである。イノシシに襲われていたら、今頃ここに私はいないかな…。
藁山と道光間のルートは沢の辺りで道はないそうである。どうしても沢で道は崩壊してしまう。
小沢氏の案内で道光の石造物所在地を確認できた。集落西側の作業道すぐ上であった。ここに隣り合った平地が2箇所あり、神明社と曹洞宗学恩寺があったところのようだ。その平地の上の隅に石塔が祀られている。(『日向の七草祭』p3「3 道光に残る石造物」と同じである。)ちなみにp2「2 道光の景観」に写っている小屋は小沢氏の休憩所で電気も通っている。茶園は同氏の管理であり、その中に墓石もある。
・地蔵:貞享五辰年十二月廿三日 □□村 佐藤、1688年元禄元年
・不動明王:享保二十□□、 1735年
・馬頭観音:
・壊れかけた石:おそらく五輪塔か宝篋印塔と思われる。
他に茶畑内にも墓がある。
・墓石:明治廿七年 徳巌良禅□ 徳應貞壽□
他の墓石は子孫が移転したそうで主に日向陽明寺だそうである。ちなみにこの石造物後ろに立てられている卒塔婆は小沢氏が陽明寺からもらってくるそうだ。
道光は天明八(1788)年の文書によれば家数15戸(一説に20余戸)とある。山田長政の母の出生地という伝承もある。宝暦六(1756)年、奉公人として落ちぶれた主家に尽くしたことで町内の推薦で駿府町奉行所から褒美をもらった忠僕八助も出身者である。(忠僕八助の碑はJR線隣の南安倍の八幡宮にある。)陽明寺の開山の雲叟も出身者である。しかし文化年間(1804~17)には滝右衛門一人在住で、その直後無住。明治初年日向村合併。昭和22(1947)年開拓入植開始、しかし以後無住で現在小沢氏が通いで管理。
・藁山
この後、小沢氏に車で道案内してもらい藁山へ行く。途中城山から洗沢峠へ徒歩で上ったときに横断した林道がこの道であることを知った。藁山は現在無住だが1軒だけ残っていて、某氏息子が通いで茶畑等管理しているとのことだった。昔は20軒ほどあったが生活困窮で天明年間に6~7軒に減少し、以後無住。明治初年日向村合併。神明神社がある。
『駿河国新風土記』著者新庄道雄は萩多和城の藁科氏の居所が藁山だという説を述べている。
藁山には墓石や地蔵、祠が残されている。車を駐車した藁山西側入口近くにある墓石から紹介する。これは『日向の七草祭』p16「1-2 藁山に残る墓石群である。
・宝篋印塔?
・石塔
・墓石:江戸期風
そこから東に5mでまた墓石がある。
・墓石:小永井 明治廿二四月、四角柱連立式の近現代の墓石、
・墓:小長井
・墓:地蔵:童子
そこから東10mで地蔵と祠がある。
・祠
・日切地蔵 大正五年十一月:歯痛地蔵:あごなし地蔵
・地蔵:右の日切り地蔵の左にもう1体安置されている。
・手洗石:
・焼香台のようなもの?
そこより30m上
・祠:多分、神明社
神明社のすぐ手前を横切りアカミチが上の畑色に上っていく。しかしすぐ上で崩壊している。アカミチを下にたどっていくと植林内に入っていく。そこも平坦地がありかつての人家の跡である。ただその下へは道は不明である。横へ行く道も細い。
~林道から県道に戻り湯の島を目指す。~
○下湯ノ島 ゆのしま
13年3月に県道集落手前に石塔類合祀場所が作られた。
○石塔類24基
・庚申塔 昭和五年
・庚申供養塔 天保四癸巳年
・庚申塔 昭和参年
・庚申塔 昭和三年
・庚申塔 昭和二年
・庚申塔 昭和八年
・庚申塔 昭和四十四年
・庚申供養塔 大正九年
・庚申塔 明治四十一年
・庚申塔 大正九庚申年
・庚申塔 昭和十七年
・馬頭:昭和十四年
・馬頭観世音 大正十三年
・庚申塔 昭和廿一年
・庚申塔 昭和十七年
・庚申塔 昭和二年
・庚申塔 昭和三十九年
・西国 奉納経 四国 安政(正が上、マイが下)
・石灯籠:昭和五年
・手洗石:昭和四年
・地蔵:虫歯守護あごなし地蔵大菩薩:、子供の歯痛を治してもらった願果しに建立したもので、藁山のものの方が古い。
・?馬頭:明治廿一年
・?馬頭:湯本小太郎
・馬頭観世音 昭和三年
湯島橋を渡り左に石仏がある。
・馬頭観世音 昭和十二年
道を上っていくとお堂がある。
・琴比羅神社:金比羅堂
その先に墓地とお堂がある。
・玄国堂 宝積寺
虚空蔵菩薩:木製:江戸期、
・手洗石:明治廿一年
・玄国堂紹介説明版:玄国和尚は明和安永の頃(1764~1780年)の湯島村宝積寺の住僧なり。生国は甲斐の国西八代郡大島村(身延町、JR身延線甲斐大島駅)なり。出家して晩年衆生済度のため諸国行脚の旅に出でたり。途中湯島村佐藤彦右衛門宅に止宿す。「やんれやんれ」と声をかけて歩く程なればこの時相当高齢なるべし。
和尚の徳声まことに高く時には近縁の者集まりて法話を聞き、ますます信仰の念を深める者多し。和尚は又この里の人情厚きを喜びて静かに老後を宝積寺にて養い居たり。当主彦右衛門は和尚に随喜すること特に厚く風呂の沸く毎に請して優遇したり。又ある時は和尚自らそばを作付けしてその収穫を彦右衛門に依頼せり。「彦右衛門そば拾いに来たれり」と言いしに和尚は「そばを拾うと言わずそばを刈ると改むべし」と笑いて語りしとか。現在この土地にそば拾いの呼称あるを思えば他国より来たれる和尚にはこの方言奇異に感ぜられたるべし。和尚は一朝翻然として悟道するところあり。即ち信徒を集めて後事を託し「吾れ滅後に於いて浄心を専らにして吾名を唱うる衆生あらばもろもろの苦悩を解脱し必ず安心を得せしめんとの遺書を残して入定せり。(生きながら身を棺に入りて土中に埋葬すること)老若男女泣きて和尚の入定を止むれど決意の程固く如何とも止め難く如何とも止め難し。時に安永四(1754)年二月二十七日行年八十三歳なり。その後七日七夜墓の中より念仏唱名の鐘の音聞こえたりと。
彦右衛門の悲嘆見るもあわれなり。終生只管和尚の意を守り供養を怠らざりき。嘉永元(1848)年七月二十日行年九十六歳を一期として逝く彦右衛門の法名潤屋百歳信士と号す。
和尚の生前「彦右衛門よ、死後は吾傍に来たれ」と言われしとて和尚の墓近くに自ら墓所を定め家人に吾れ死後はここに埋葬することを話せり。現に和尚の墓近くに彦右衛門の墓あり。如何に追慕の情深きを知るべく吾里の信仰美談なり。
玄国堂は和尚の祠堂にして現在の建物は明治三十五(1902)年の建立にしてもと宝積寺境内に在りしを遷せるものなり。此の祠堂に安置せる和尚の尊像は当村孫右衛門村民に謀り当時鍵穴村喜左衛門方に逗留せる仏師某に依頼彫刻せるものなり。明治初年に一度修理せしことなるものなり。
往時病難災厄ありし時村民此の堂に参集し尊前にて光明真言を唱え一心に祈念せり。心願成就霊験あらたかなりと。
今日尚玄国堂に香華の絶ゆることなきは昔より如何に栄誉の的なりしか推して知るべし。二月二十七日は毎年祥月供養せしが後に春彼岸中日に変更し今日に至る。当日は本寺陽明寺住職来堂し法要を営み併せて無縁仏の施餓鬼供養を行う。因みに当日信者に配る玄国和尚尊像のお札版は当村庄右衛門の作なりと。
・和尚たちの墓:「潤屋百歳信士」墓石が右端にある。
・墓地やお堂前の歩道が旧道(古道)残存部である。上湯の島に続いていて、約600mである。
はじめ200mは石垣で道の崩壊を防ぎ快適な道だが、それを過ぎると道が崩壊しかかっている沢を渡り、ガレかかったところを通過することになる。今のところは通過可能だが整備しないと徐々に崩壊が進むだろう。上湯の島の市営温泉駐車場の真上に出る。ここは峠みたいで急に上湯の島集落が見え、枝尾根をまたぐ形になる。炭焼き小屋跡の石垣を組んだ穴が見られる。標高はこの先の飯綱神社と同じぐらいの高さだ。集落に降りていくには林道の作業道に下りればよいが、かつては茶畑に付いている石垣のある道が本道だったのではなかろうかと思う。集落自体がかつては川や県道より離れたもう少し上にあったのだろう。裏山の飯綱神社程度の高さに村があったのかもしれない。今は川沿いの県道周辺に集落が移動したと考えたほうがよかろう。
○上湯ノ島
市営湯の島会館前の民家に地蔵がある。
・地蔵:
民家裏山に神社がある。
・飯綱神社
・石段:安政七年
・石鳥居:□□□十三□□□
・手洗石:慶応戌辰
・祠
・五輪塔:宝篋印塔、これは古そうです。神社裏の周辺は畑でやや平坦で、ここに集落があったのかも。
近くの墓地に石灯籠がある。
・石灯籠2:
県道川沿いの川に下る道があるところに石塔がある。
・庚申塔 昭和五年
・渡河地点:上湯島と大間:なぜここに庚申塔があり、川に下る道があるかと考えると、ここで川に下り、ちょうどこの辺りの水流が弱く、渡りやすく、渡った先の対岸には茶畑があり、上って行ける歩道がついている。おそらくここがかつての渡河地点だったのだろう。今はここより100m上流に大間に行く湯島大橋がある。まあ庚申塔は川に下る道の横が空いていたのでたまたま祀っただけのことかもしれない。
・湯の島温泉の由来:大間に信州高遠から来た武士が住み着いた。藁科の村は羽鳥しかなく大間までは大きな距離があり大間ということになった。その弟が大間を訪ねる途中湯が湧くのを発見し温泉にした。江戸期繁盛したが、あるとき武士が遊女を切って首を温泉に投げ入れてから湯が止まった。地名は昔湯島だったが、同じ地名があることから、湯の島とした。
~県道はこの先湯島大橋手前で右:大間・笠張峠と左:楢尾・崩野・八草に分岐する。
左:楢尾・崩野・八草方面をとる。最初のカーブで石塔がある。
・庚申塔 道路開鑿記念 大正十三年
すぐ次に右:楢尾への分岐があるが直進し崩野・八草方面をとる。
○崩野 くずれの
崩野への中間辺りの沢横の道路沿いに石塔がある。
・弘法大師 道路開鑿記念 大正十五年
集落への一つ手前の泉沢橋のその手前のカーブ地点に祠がある。
・地蔵:
崩野 登り尾集落直前の尾根途中にお堂があり、地蔵が祀られている。
・地蔵堂:延命地蔵:説明看板:昔、子供に幸せ薄い村人が、別の場所で朽ち果てていた地蔵を、この地に移し供養したところ、子宝に恵まれたといわれる。以来子供を守る地蔵と敬われている。縁日旧暦12月24日(現在の暦だと1月末から2月初め頃)
*旧暦について一口メモ
旧暦の日にちを今の暦に直すと毎年日付がずれるので毎年違う日になるはずです。単純に計算できません。およそ40日ずれるといわれますが、これもおよそで毎年こうとはいえません。旧暦は19年に7回、1年が12ヶ月ではなく、13ヶ月になるという大胆な暦で、こうでもしないと、真夏に冬のはずの正月になりかねないからです。旧暦は月の満ち欠けで数えていて、一ヶ月は平均29.5日で一ヶ月は29日か30日なのです。12か月分だと、今の暦より11日少ないので、これで15年も続ければ真夏が正月です。そこで19年に7回13ヶ月になる閏月という制度があり、季節と日付がずれないようにしてます。約3年に一度といえます。例えば七月が終わると閏七月になり、それが終わるとやっと八月になるわけです。この閏月も法則がありますが、例年同じ月ではなくもう少し複雑なのでややこしいです。詳しく知りたい方は。他を調べてください。ネットでも図書館でもどうぞ。ちなみに1年が13ヶ月だと月給取りのサラリーマンは1回得しますね、だからこそ明治5年明治新政府は財政難で、公務員への13回目の給料支払いをやめるために今の暦にしたといわれます。
~崩野の中心集落に入る。集会所先のカーブ崖上に石塔がある。
・庚申塔 大正九庚申年
・奉納 庚申供養塔 明治五年
・庚申供養塔 昭和□年
更に道を上っていくと
○宝光寺跡
・(三)界萬霊塔 大正十四年
・三夜燈 安政四年
・石塔:
・六地蔵:六体
・地蔵:
・五輪塔
・馬頭:
・石段改設 明治拾七年
○観音堂
金属製:千手観音像:江戸期:擬古作、
かつて月小屋(女性が生理中こもる家)も付近にあったそうだ。
・手洗石:
・石灯籠:
○白髭神社
・石鳥居:氏子安全 御大典記念 昭和三年
・氏子安全
・石鳥居の根元片側が埋もれている
・石段:昭和五年
・手洗石:祈皇軍健捷 昭和十九年
・石灯籠2:奉納 白髭神社 御宝前 明治廿七年
・祠2:
・手洗石:明治十一年
この裏山を登っていくと智者山・天狗石山に至る。
崩野集落を下っていき、かつて楢尾に渡っていた所、今は朽ち果てた吊り橋の残骸があるところから上流を登っていくと、「崩野川右岸支流に朝日滝:落差30m、3段、別名:崩野滝」(ネットのサイト「静岡県の滝」より)というものがあるようだ。吊り橋のところから右岸の登山歩道は砂防ダムがいくつもできて消滅しているようだが、左岸に林道が出来ているので1kmほど遡行できる。林道1kmで終点でとくに標識等がないのでどこが朝日滝方向か不明。しかしその辺りから沢が3つに分かれているのが分かり、林道は左岸の支流砂防ダム前で終点であるが、対岸の右岸に流れ込む支流が3段ほどに分かれ滝状に落ちている様子が木の間がくれに見える。落差は合計30mほどかなと思える。もしかしたらあれが朝日滝かな。吊り橋残骸から1kmほど上流の右岸支流である。
またここからさらに1km沢奥を詰めると大野滝というものがあるように地形図では記入されているが、ネットのサイト「静岡県の滝」では消滅と記入されている。
○八草 やくさ
現在無住、かつて7軒あった。無人の民家が4軒ある。もう1軒はお堂である。集落手前に智者山登山口を示す標識があり、集落奥を指しているが、その前に自動車道舗装路終点地(未舗装道路は更に50m奥に進む。)の右上が山斜面で上って行く登山道がある。1分上ると杉桧植林地内に集落墓地があり、真下が自動車道舗装路終点地である。
・墓地:上湯ノ島の玄国茶屋に勤めている八草出身のご婦人の話によると、60基ほど墓石はあり、石碑を根元に抱えた栂の木があり、近くに女杉もあるとのことだ。しかし墓地は改変されていて、だいぶ空き地になっていてまとめて積まれた墓石や破片を含めて30基ほどと思われる。おそらく大半を移転したと思われる。しかも墓地周辺の古い樹木はことごとく伐採され、残っているのは植林ばかりである。
無論根元に石碑を抱えた栂の木は不明であるというか、おそらく伐採されたものと思う。
女杉であるが、付近には植林された杉ばかりでいわれのありそうな木はないので、伐採されたものと思う。
????・女杉、池の段:杉と池の中に女の大蛇が住んでいたが、暴風雨か女が洗濯したため出て行ったという。どこ?池の段は裏山というか智者山登山口付近の平坦地のことか?女杉は墓の付近らしいが不明。
・旧道(古道):墓地の下で自動車道より上に道幅30cm~1mの登山道が水平についている。自動車道より10m上を水平についている。おそらく登り尾集落に向かう旧道であろう。自動車道ができる前の生活道路、旧道(古道)であろう。今は植林地内の作業道であろう。使われなくなり徐々に崩壊していくだろう。
~一旦墓地から無住集落に向かい進んでいく。
途中建物がありお堂である。
・神明神社:お堂
・手洗石:
この裏山の尾根先端頭頂部に神社があることに地形図ではなっているので行ってみると、参道は道がはっきりあり、頭頂部は平坦で建物跡が見られる。ちなみにこの尾根頭頂部と先ほどの崩野延命地蔵堂のある所は同一線上(東西方向)の尾根である。かつては尾根道でつながっていたのではなかろうか。この尾根を2~3分東に下ると先ほどの墓地に出ることができる。
・石段跡:
・建物跡の礎石か周辺をかためた配列石:
この裏山尾根を西に登っていくと尾根を一旦北に回り込むが、その先で尾根に取り付き西に上る道があり、そちらへ智者山登山用矢印が出ている。
ちなみにそこから杉桧の植林された尾根を下に下る切通しがついていて、多分下の登り尾の集落につながっている旧道と思われる。
八草内の植林地で智者山、崩野、八草民家の分岐点近くに植林より低い火の見櫓が見つかる。
・火の見櫓:今は周辺の杉植林より低い。かつてここが見晴らしよく周辺が畑か人家だったという証拠だろう。
八草から智者山を目指すと直接智者山山頂ではなく、一旦智者山林道が通過する尾根に出るはずだ。そこから尾根を詰めるか、林道を少し詰めてから標識に従い尾根に取り付くかだと思う。そして林道に出る辺りに、四角柱の石道標があるはずだ。林道工事中に一旦不明となり、新聞記事まで出て所在確認が行われ、どなたかが預かっていたことが判明したそうだ。今はもとの場所にあるのだろうか。
八草無住民家を詰めていくと最後の民家の奥は大きく崩壊していてもう進めない。最後の民家前も地滑りで地面に段差がいくつか生じている。さも地滑りの見本のようだ。
無住民家の庭先に布団類を敷き並べて土に戻そうとしてある。子供用ビニールプールの破片もころがっている。別の植林内の家は開けっ放しで家屋内に古い大型のアナログテレビがぽつんとある。周辺には洗濯機やバケツがころがっている。かつてここに人々が生活し人の生活の営み、家庭の団らん、幸福が、子育てが、悲しみがあったのだろうに、こうして廃墟と化すと、寒々とした悲哀感が押し寄せてくる。
遠い未来、東京や静岡といった都市が廃墟と化したとき、それを探索する人は20世紀から21世紀の人々の営みの痕跡に人生の悲哀を感じるのだろうか。
*無住集落を訪ね歩くのはあなたの自由でしょうが、今でも所有者や管理者はきちんとあり、そこで生まれ育った人にとってはかけがえのないふるさとでしょうから、現状を改変したり汚したりする行為は一切しないようにしましょう。
無住集落内を一本の沢が流れ下っていくが、途中明らかに沢を付け替えてあり、本来の沢には石垣があり水が流れていない。おそらくわさび田として利用したため水量調節のため古タイヤを積み重ねて沢をせき止め、横に水路を掘り流れを変えたものと思う。
・昔髙橋家は井川金山の関所と智者山神社の別当(禰宜ネギ、神主)だったという。
八草から ~楢尾、川合、川合坂、本村への分岐に戻る~
○楢尾、川合、川合坂、本村
分岐を過ぎ楢尾への橋を渡る。橋の位置は改定されている。渡るとすぐに祠がある。
・地蔵:明治七戌年
~道を上っていくと最初の集落:川合であり道端に石塔がある。
・石?
・地蔵:
・墓石:
~茶畑の上に石祠がある。
・石祠:
・石柱:奉納 稲荷神社之元屋敷 明治四十年
ここに稲荷神社があったということか、住民に聞いてみると、
???・住民によれば神社は林道をもっと上った山の中腹にあるそうだ。未確認。
~次の集落:川合坂の上に神社がある。神社に上る道の近くに石塔がある。
・庚申塔 昭和七年
~上っていくと尾根付近に神社がある。
・稲荷大神
・石鳥居:明治百年記念
・手洗石:明治十五年
・石灯籠2:昭和五十一丙辰年
・祠:稲荷
~楢尾への舗装路を進む。
・海前寺
・地蔵:
・板碑:この寺に学びし頃の思い出の歌
~大間への舗装林道を進む。
・楢尾の石仏、ならおのいしぼとけ
舗装林道を尾根辺りまで出て尾根に杉巨木が見える所、大間や益田山への分岐200m手前である。林道は尾根より5m下を通過しているため、尾根伝いの旧道(古道)上の丸石を手向ける杉巨木のあるこの場所はそのままである。祠も祀られている。峠の語源には峠越えの安全祈願を手向ける→手向け→たうけ→たうげ→とうげ峠になったという説もある。柴を手向けることが多かろうが丸石を手向けることもある。この舗装林道が開通したことでかなり旧道は消失したようだ。丸石は願掛けやお果たしでもある。
もう200m進むと分岐点がある。直進で益田山、七つ峰方向へのダートの楢尾智者山林道、右折で大間である。大間へは部分的に旧道が残存している。
・石道標:「これよりみぎ大まみち」四角柱で頭頂部は四角錐である。
???・益田山:どこの山? 七つ峰への前衛峰?
○大間
・大間の石仏、おおまのいしぼとけ、大間の古道(旧道)
石道標のある分岐点から、しばらく林道を下ると大間との境らしい。この辺り林道より5m上に丸石が見られたようで大間の石仏だそうだが、探しても一つも丸石は見つからなかった。意図的に移動されたものと思う。ただ林道より上部を探すと旧道(古道)残存部はあり、しっかりした道も部分的にある。その中に楢尾の石仏を彷彿とさせるような峠のような境目のような大きい木が4本ある場所があったので、私としてはそこを推定地としたい。先ほどの分岐点より700m進んだ林道地点の20mほど上の尾根である。旧道は上り下りの境目で道の左右に杉2本、モミかツガが2本で計4本大木である。祠や丸石は一つもないが、楢尾の石仏と風情は似ている箇所である。この近辺に古道らしさがよく残存している。ただ20~30年前まで子供が楢尾小学校に通う通学路として安全に整備されていたのだろうから、昭和期終わり頃の姿をとどめているという思いも必要だろう。
大間に向かい旧道切通しをたどると数回林道と交錯し断ち切られるが沢を2回またぎ林道と違う箇所へ向かうのが分かる。その先急斜面の尾根に出て真下に砂防ダムが見えるところで、旧道は崩壊していた。この急斜面では致し方ない。おそらくここで七曲りの巻き道になり急斜面尾根を下っていったのだろう。ちなみに大間の林道出口には砂防ダムがあるところは見当たらないが、1本北の沢は砂防ダムがあり、急斜面の尾根があるので、おそらくここの真上であろう。付近を探したが旧道出口らしきは不明である。崩壊しているのか、私の探し方がまずいのか。
大間集落直前の福養橋手前に石塔がある。
・庚申塔 昭和九年
大間集落に神社がある。
・白髭神社
不動堂:木製:二体不動明王、
・石鳥居:昭和五十五年
・祠2:
・石製家型道祖神:明治□年
・石灯籠:慶応四年
・庚申供養□ 元治二□
・庚申供養塔 大正九庚申□年
まあ慶応四年(明治元年)も元治二年(慶応元年)も公式にはないが、石屋が彫ってしまってから年号が変化したと思えばよいのだろう。まあ昭和元年は1週間で終わり、昭和64年は1週間しかなかったしね。こういう年号違いは時々見られるが一つところで二つも見られるというのは初めてだ。ここではないが他には萬延二年(文久元年)もよくある。
・火の見櫓
○福養の滝
大間集落左上の沢というか先ほどの福養橋上流にある。安置されている石塔は2基である。
・大滝不動
・不動明王
・説明看板:昔、信州高遠乾の町(伊那市高遠町)から三人の落武者が逃れ、この地に住み着いたのが大間である。この地には滝があり高さ100m、幅4m(現在では高さ135m、幅3.3mとされる)の滝の水は滑らかに岩を這うように流れ飛び散る水玉は陽光に映えて、宝石を散りばめたように美しい。またこの辺りは不動尊が祀る神池とも伝えられる。この滝に毎年五月五日の午前十時頃一頭の馬が滝つぼに漬かり毛並みを整えていた。この馬はのちに栃沢の米沢家で飼われて宇治川の先陣争いをした俊馬「磨墨するすみ」となった。村人はそのためこの滝を「お馬が滝」と呼んだ。1909年当時の安倍郡長、田沢義鋪よしすけが井川村から郡内調査に来たとき、滝の確かな名称のないことを残念に思い、岐阜県養老町の養老の滝に似ているので「福養の滝」と名付けられた。(現在は似ていないといわれる)
名馬「磨墨」伝説とも重なる伝説の滝であり、静岡市内では有名な滝である。
~湯島から大間に上る県道沿いにも石仏がある。
・?馬頭:古びていて判読不能。
・川久保林道分岐点:13年3月工事中、出入り不能。
・地蔵:おおはたけ橋袂にある。「大正十五丙寅年 霊峯山人建之」
・林道野田平線分岐点:先ほどの楢尾大間の林道である。これより上はすでに記入済み。
~大間を越えて、この先、県道南アルプス公園線は、尾根を越していく。その尾根を右に進めば一本杉峠や諸子沢・平の尾方向に下っていける。その先で地すべり地帯を通過し笠張峠で県道井川湖御幸線に合流する~
*林道一本杉線に関しては、諸子沢の平の尾・地蔵堂辺りを参照してください。
・参考文献
・「静岡県指定無形民俗文化財調査報告書 日向の七草祭」静岡市教育委員会 ‘06
かなりの部分を引用させていただいた。
・「駿河の伝説」小山枯柴:編著、宮本勉:校訂 旧版:‘43 新版:‘94
・「藁科物語 第3号 ~藁科の地名特集~」静岡市立藁科図書館 ‘94
・「藁科物語 第4号 ~藁科の史話と伝説~」静岡市立藁科図書館 ‘00
2012年07月10日
☆VHS『歴史の道』日本通信教育連盟 全10巻
☆VHS『歴史の道』日本通信教育連盟 全10巻
私も『古道を行く』という本を出版し、古道マニアの一人として、このようなビデオがあることはうれしい。とりあえず北海道から沖縄までにある古道をビジュアルに紹介した功績はあろう。この目で古道の一端を見られてうれしい。そしていつの日にかそこに自分がいることを念じていた。今後さらに古道はメジャーになっていくだろう。
映像内の浮世絵や写真が3D画像になり立体感が得られる。「アバター」より古いものなので、多少立体感は落ちるが、ごく初期の試験作品として、技術開発途上のものとして楽しめる。
○・VHS『歴史の道 第1巻 北海道・東北』55分
・旧福山街道:松前町(福山)から松前半島の日本海沿岸沿い北上檜山郡上ノ国町に通ずる。中世北海道歴史資料勝山館遺構等残る。上ノ国~赤坂~虎ノ沢~松前(福山)~函館。
虎ノ沢:昔はヒグマが見られた、幕府の巡検使が羆を見て騒ぎヒグマが虎の如く速く逃げたためといわれる、伝説:十兵衛石:彼が戦って勝てなかった相手。15世紀に和人ともめる、八幡牧野:八幡菩薩祈る、1457年アイヌのコシャマイン軍と武田信広の戦い、コシャマイン優勢だったが最終的に和人勝つ。赤坂:赤土はこの戦いの名残という、足洗川:旅人わらじ洗う、勝山館跡(武田信広館跡)、和人館12、客殿跡、館神八幡宮跡、鳥居跡、空堀、沢から用水でため池へ、3万点陶磁器かなり高い文明、数万点金属品木製品、夷王山、夷王山墳墓群:武田氏柿崎氏墓、大きな和人社会、武士中心、海産物本州必要で和人増加、上国寺: 武田信広菩提寺、上ノ国八幡宮、
・奥州街道:みちのくに通じる重要街道、簑ヶ坂の急坂は明治天皇行幸時近在青年が馬車押し上げたという。54宿。盛岡~簑ヶ坂~三戸~高山峠~五戸~青森~三厩。蝦夷地に通ずる。
大蛇が簑に化け旅人を引きずり込んだという伝説。標高180m籠立場:岩手青森県境まで100m急坂、明治天皇巡幸記念碑、緩やか下り坂200m一里塚、三戸:南部藩発祥地のち盛岡へ、三戸城復元、宮坂、なだらか単調に続く長坂、一里塚残存多し:所有者不変でそのまま、高山峠H277m、展望名久井岳、長い下り坂、2km先で赤松古木、浅水城跡:南部氏、宝福寺、鳥内坂トリナイ、五戸町:宿場町・代官所、江渡家住宅:寄棟作り・国重要文化財・代官下役、追分石、
・羽州街道:~矢立峠越え~、秋田青森県境の矢立峠(杉峠:天然秋田杉)は急勾配、吉田松陰もその険しさを詩に詠む、碇ヶ関関所では米や物資の移動を厳しく検査した。秋田~能代~大館~矢立峠~碇ヶ関~弘前~青森。
長走の風穴:気孔冷風真夏10度高山植物H165m、矢立峠H258m難所、矢立温泉、吉田松陰「漢詩」、相馬大作跡地:南部騒動、急な下り坂参勤交代有名人通過、碇ヶ関関所:口留番所:物資監視、遠見番所、下番所・上番所、碇ヶ関温泉入湯規則、
・秋田街道:~国見峠越え~、盛岡城下から雫石、仙岩峠、国見峠を越え秋田城下を最短で結んでいた。平泉藤原氏全盛時代は生活密着重要道。盛岡~雫石~仙岩峠センガン~田沢湖町~秋田、
橋場宿(雫石町):番所、坂本川沿いに西、南部藩は馬名産地で藩直営牧場、馬買い衆往来、人馬通行為道整備、難所は南部領と秋田領境の南に仙岩峠:「是より南西秋田領」、北に国見峠:「是より北東南部領」で二つは国境山道でつながる、助小屋跡地:相互の荷物を信頼して預ける、盛岡城跡、仙北町、六枚野一里塚(田沢湖町)、田沢湖、
・北国街道:~三崎山越え~、山形県酒田から庄内地方の日本海沿岸沿いに秋田県象潟に通じる街道、県境の三崎山越えは芭蕉他多くの文人墨客が日本海の潮騒を聞きつつたどった峠道。酒田~遊佐~三崎山~象潟~秋田。
最上川、酒田市、出羽随一港、吹浦海岸、十六羅漢岩:明治初期22体石仏刻む、奥の細道三崎峠、駒泣かせ、坂道、石畳、大師堂1493年建立、有耶無耶の関跡、タブの木、供養塔:領土争い死者、一里塚、象潟:天下の絶景:遠浅海に小島多数、向こうに鳥海山だが1804年海底隆起で陸地、カンマンジ(虫甘)満寺、「象潟や雨に西施がねぶの花」芭蕉、
○・VHS『歴史の道 第2巻 東北』60分
・出羽・仙台街道:~中山越え・山刀伐峠越えナタギリ~、宮城県鳴子町から山形県最上町・尾花沢市に至る街道、奥の細道での通行している、中山越の先に山刀伐峠越えという難所、最上街道とも、仙台~鳴子~尿前~中山峠~最上~酒田
↘山刀伐峠~尾花沢~山形へ
鳴子温泉:こけし、尿前の関、松尾芭蕉「此道旅人稀なる所なれば関守にあやしめられて漸として関をこす」奥の細道、源義経を藤原秀平が迎えに来た伝説、コブカザワからオオブカザワへ、境田村、「大山のぼって日既暮れければ封人の家を見かけて舎を求む」芭蕉、封人の家(旧有路家住宅):国境守る役人:土間に三つ厩:「蚤虱馬の尿する枕もと」芭蕉、山刀伐峠:ハケゴという籠を二つに切った形の峠、10km、「高山森々として一鳥声きかず木の下閤茂りあひて夜る行がごとし」奥の細道、27曲がり、子持ち杉、子宝地蔵堂、代官領境、
・米沢・福島街道:~板谷峠越え~、米沢から板谷峠越えで福島につながる街道、米沢藩専用の参勤交代道として利用、板谷峠から李平の旧街道の石畳、米沢~板谷峠~李平~福島、
米沢城跡、上杉家墓所、御霊屋:国史跡、米沢城下絵図、普門院、上杉鷹山:藩財政建て直し、板谷宿、本陣代わり板谷御殿、大野九郎兵衛の墓:伝説:赤穂浪士が上杉家に逃げる吉良を討つため待ち構えたが来なかったので死んだ、板谷峠H760m、米沢藩だけ参勤交代ここ通過、物資輸送、旧米沢街道石畳、李平宿場跡、李平村絵図、あべ家中心に40戸、人馬栄えたが今草むら、泉安寺跡の墓:森林内廃墟墓地・明治4年廃寺、明治32年鉄道開通・3年後大火で廃村、庭坂宿から先奥州街道合流。
・会津街道:~束松峠・滝沢峠越え~、会津若松から越後新発田へ至る道、海路佐渡に続く、会津若松では滝沢峠・戸ノ口原古戦場、戊辰戦争舞台:白川街道筋にもつながる。
会津若松、鶴ヶ城、
新発田~束松峠~会津若松~滝沢峠~(白河街道~)白河
↘三春
会津坂下アイズバンゲ、恵隆寺:仏像・立木観音:千手観音、天屋本名テンヤホンナ:道の左右別名、ホンナには肝煎斉藤家:肝煎は庄屋のこと、上り坂にかつて敷石だったが馬車邪魔で剥ぎ取られてない、地蔵の茶屋跡、石仏、石水槽、三本松、一里塚、束松:天然記念物、先300m束松峠、展望台:会津盆地、
白河街道、会津若松、旧滝沢本陣、戊辰戦争弾痕跡、滝沢峠道昭和40年代復元、石畳、参勤交代、佐渡金山運搬道、十八人之墓、戸ノ口原古戦場、白虎隊、
・八十里越え:越後吉ヶ平と会津、福島県只見町を結ぶ街道。平家追討失敗:以仁王、官軍に追われた長岡藩家老:河井継之助も通った。長岡~吉ヶ平ヨシガヒラ~鞍掛峠~木ノ根峠(八十里峠)~入叶津、26km、一里が10里に相当するといわれた、
以仁王流浪伝説(富士川戦死)、源仲綱墓:伝説(富士川戦死)、吉ヶ平山荘:かつて庄屋椿屋敷、河井継之助:武装中立主張するが賊軍として敗走、長岡城攻防絵図、守門川、八十里越え入る、2時間6.7kmで番屋乗越H895m:番屋は源仲綱設置伝説、空堀小屋跡:宿泊休憩食事、眺望・烏帽子山・岩肌剥き出し、鞍掛峠、小松峰・眺望、「八十里こしぬけ武士の越す峠」河井継之助、木ノ根峠(八十里峠)、庶民交流・生活道、入叶津(只見町):越後交流・越後弁、口留番所跡:会津藩監視用、医王寺(只見町塩沢:、河井継之助墓:北越の蒼き竜
・下野街道:会津若松から田島・山王峠越えで下野・今市へ向かう道、参勤交代や東照宮参詣道としてにぎわった。大内宿は名高い。会津若松~栃沢~大内峠~大内宿~田島~糸沢~山王峠~今市へ、会津西街道ともいう、
栃沢、栃沢一里塚、大内峠、大内ダム:大内沼、地蔵「右若松」石仏、大内宿・本陣跡・参勤交代・回米(扶持米)運搬用・高倉神社、田島・宿駅、糸沢宿・口留番所・戊辰戦争の図・龍福寺:襖逆さ芸州弐番隊、山王茶屋(峠中腹)、日吉神社、山王峠:馬頭観音:H903m、
○・VHS『歴史の道 第3巻 関東』58分
・陸前浜街道:~十王坂越え~、江戸と水戸を結ぶ実と街道の延長、陸前・岩沼で奥州街道と合流、伊能忠敬も歩いた道の十王町から高萩を行く。水戸~日立~十王坂~十王~伊師~高萩、磐城相馬街道とも、
鵜の岬:ここで捕れた鵜を岐阜県長良川で使う、十王台遺跡:縄文弥生、十王台式土器:十王町民俗資料館:北関東弥生様式稲作文化、海岸段丘上通過、北方軍用道路の面、奥州街道脇往還、高萩の海見える、(十王町)伊師、一里塚、愛宕神社、馬頭観音:台座「右いぶき山 左いわき道」、長久保赤水:江戸中期地理測量学者・長久保赤水旧宅、伊能忠敬到着10日前亡くなる、
・日光杉並木街道:日光街道・会津西街道・例幣使街道は世界最長杉並木道、砲弾撃ち込み杉・からかさ杉等ある。特別史跡・天然記念物。古くは樹齢350年、日光街道:宇都宮~大沢~今市~日光、例幣使街道:小倉~今市~日光~大 ~会津西街道、総延長37km、
日光街道、並木寄進碑:1648年、日光東照宮、大沢御殿跡、今市宿、芋の木杉、砲弾打ち込み杉、神橋、並木寄進碑、
例幣使街道、並木寄進碑、
会津西街道、からかさ杉、
・中山道:~碓氷峠越え~、上州から信州に向かう道に難所:碓氷峠があり境に熊野神社社殿がまたがっている、妙義山・浅間山の展望がよい。碓氷峠関所跡(横川)、坂本~碓氷峠~軽井沢~追分~塩尻、
坂本宿、「木曽街道69次・坂本宿:英泉」:本陣・脇本陣、碓氷峠、安政遠足トオアシ:安中城から碓氷峠、堂峰番所跡:遠見番所、覗ノゾキ:坂本宿見下ろせる・一茶「坂本や袂の下の夕ひばり」、馬頭観音、はね石坂、なだらか、唐松林、山中茶屋:峠真ん中・寺・13軒、H956m群馬長野県境、石風車、見晴台・眺望・浅間山、遊覧歩道軽井沢、碓氷峠越えは江戸防衛のため、二手橋、軽井沢・沓掛・追分宿、旅籠油屋、分(か)去れの石道標:中山道と北国街道分岐点、
・見沼通船堀:(浦和市)さいたま市、水運の堀、1721年開通、パナマ運河より183年前同一「閘門式コウモンシキ: 水のエレベーター」。見沼代用水路~東縁と西縁を結ぶ水路、下山口新田、芝川、浦和、見沼は広大沼地で干拓で新田、利根川取水口、西縁代用水路、東縁代用水路、4つの水門、江戸との物資輸送、
東縁仮締め切り、今は隣にふるさと歩道、東縁第二の関、東縁一の関、距離390m、芝川、水位差3m、、水門高さ九尺2.7m・板塀・鳥居柱・各落板、八丁橋、大正時代の八丁橋・写真、おやつもらって船通す、水神社、鈴木家:通船業務、西縁代用水路、654m、西縁第二の関:今ない、
・鎌倉街道:~上総道~、関東周辺から鎌倉に至る道を一般に鎌倉街道という。房総半島にも海路越しの道があり市原市・袖ヶ浦市を訪ねる。鎌倉~(海路)~木更津~三ツ作~立野~袖ヶ浦~市原~千葉、古代の官道、上総国分寺・国分尼寺、源頼朝、竜島(鋸南町):頼朝上陸地、飯香岡八幡宮、切替家:旗印を頼朝のものに切り替えたため、御所覧塚H3m:頼朝築かせた、須軽田坂、おみかり様:首狩の意、三ツ作神社、石道標「南たかくら道」・「北ちば道」、木更津たかくら観音霊場道、
○・VHS『歴史の道 第4巻 関東・北信越』60分
・浜街道:~鑓水峠越え・絹の道~、幕末から明治初期に桑都といわれた八王子から横浜まで、八王子と鑓水の商人が生糸や絹織物を運んだ道で絹の道とも浜街道ともいわれる。鑓水周辺は貴重な歴史の道として残存している。明治期写真「鑓水の風景」フェリックス・ベアト:撮影、八王子~大塚山~鑓水峠~(絹の道)~横浜へ、浜街道40km起点八王子は関東周辺生糸集散地で桑都といわれた、「新編武蔵風土記・八王子宿」、h213m大塚山周辺残存、八王子市、鑓水峠、絹の道→横浜、明治8年建立の大塚道了堂跡(大塚山公園)、「大塚山道了堂之図」、写真「八王子に向かう道」ベアト撮影、鑓水峠、江戸期・絹運送規制、明治開放、「神奈川横浜新開港図」、かつて裕福だった鑓水商人がたてた石塔多し、絹の道資料館:八木下要右衛門屋敷跡、旧小泉家:典型的なこの地域の農家の建て方、永泉寺、鑓水商人菩提寺、芭蕉像、慈眠寺、諏訪神社、彫刻見事、鑓水商人寄進、石灯籠、明治41年八王子~横浜鉄道開通により旧街道衰退。
・箱根旧街道:箱根山:関東と東海を分割する所、天下の険、沼津~三島~箱根峠・関所~湯本~小田原、箱根湯本温泉、早雲寺:北条氏菩提寺、一里塚:江戸から22番目、箱根旧街道入る、石畳、大澤坂、畑宿、駕籠かき中継地、寄木細工、茗荷屋跡:庭園、西海子坂(さいかちざか)、甘酒茶屋、赤穂浪士・神崎与五郎侘び証文、白水坂:進軍する豊臣方に北条側が攻撃し豊臣方が城を見ずに撤退したため、石畳残る、泥にすねまで漬かる坂を改良、斜めの排水路、箱根馬子唄の碑、二子山、権現坂(下り)、芦ノ湖・富士山、「東海道五十三次・箱根」広重画、箱根古道:鎌倉古道・湯坂道、浅間山・鷹巣山・精進ヶ池から芦ノ湖に下りる、杉並木、箱根関所跡、250年間、入り鉄砲出女改め、芦川の石仏群、向坂、兜石:秀吉が兜を置いて休んだという、
・松本・千国街道チクニ:上杉謙信が武田信玄に塩を送った話で有名な塩の道として知られる。ボッカ道であった。
~塩の道~、ボッカ:険しい山道の運搬人、松本~大町~白馬~千国~大網峠~大野~糸魚川120km、糸魚川市姫川上流に縄文期遡る、小滝川ヒスイ峡:ヒスイ原石:糸魚川・奴奈川姫伝説・古墳発掘品装身具、姫川氾濫考慮し東側高い所通る、大賽の神、道は急、角間の道標「右松本街道 大網 左中谷道 横川」、ウトウの道:ウトウはわらじ等で踏みつけU字型に窪んだ所、角間池、ブナ・ナラ・トチの原生林、大網峠h850m越後信州国境、ボッカの立ち休み:杖を背負子に当てる、牛方、牛の水飲み場、大日如来、横川の吊橋、小谷村大網、塩蔵:釘不使用・腐食防止、粗塩:水分多くニガリ、千国宿チクニ、千国番所、親坂:岩多い、牛つなぎ石:岩に穴、弘法清水:水飲み場が二段で上人・下牛用、小谷村沓掛、牛方宿:土間2階牛方・1階牛、白馬村・落倉の道標「右ゑちご 左やまみち」、信州越後物資運搬、参勤交代なし、
・臼ヶ峰往来:越中の氷見から臼ヶ峰を経て能登の志雄町を結ぶ。大伴家持が通行したことでも有名。氷見市日名田、臼ヶ峰往来、御上使往来、氷見~日名田~臼ヶ峰~下石~羽昨~金沢、岩盤露出しているところもある、杉や雑木の林の中、床鍋:小さな山間集落、かつては和紙作りだったが衰退し竹細工、竹林多し、臼ヶ峰h266m、奈良時代大伴家持(国司として29歳から5年間越中で暮らした)や御上使が通った。能登巡行で通過、万葉期には道があった、志雄路という、1250年前、「志雄路から直越え来れば羽昨の海朝なぎしたり船舵もがな」家持、富山県氷見市と石川県志雄町境、富山湾眺め、5年任期220首作る、親鸞聖人像、1207年流罪で通過、太子堂:親鸞が太子見たという伝説、中世合戦場1183年、江戸期流通道、
・白山禅定道:日本有数の山岳信仰の一つ、白山への登山道である。御前峰・大汝峰・剣ヶ峰の3つ合わせた山名、
石川県尾口~尾添~(加賀禅定道)~白山・室堂~石撒白~(美濃禅定道)~岐阜県白鳥・馬場・白山中居神社、 ↖~(越前禅定道)~福井県勝山
白鳥・馬場・白山中居神社、石撒白の大杉イトシロ、泰澄タイチョウ:白山に「上れとお告げ、千日白山で修行、その後一般修行僧も修験さらに一般人も、修験の山から禅定の山、禅定道:足跡をたどる道、石撒白・ちょうしが峰・さんが峰を越えると別山見える、別山平→別山山頂:別山社、おしゃり山、油坂、高山植物、畜生谷:この水飲むと苦しむ伝説、南竜ヶ馬場バンバ、御前坂、ハイマツの中、室堂、トンビ岩、室堂:3つの禅定道合流点、御前峰h2702m、十一面観音祀る、御来光、翠ヶ池: 泰澄が池のほとりで見た夢で神と仏を結びつける神仏混淆、大汝峰:阿弥陀如来祀る、千蛇ヶ池:千匹蛇が雪に閉ざされた伝説、ハイマツの中の道、御手水鉢の池オチョウズバチ:水量一定、加賀禅定道は石川県に伸びる、高山植物花々、
○・VHS『歴史の道 第5巻 中部』59分
・棒道:甲斐の武田信玄が北信濃攻略のため八ヶ岳山麓に造った上中下3本の道筋をもち棒のようにまっすぐ伸びた最短距離の軍用道路だが、昇仙峡の御岳詣でや富士山詣でに使われた。甲府~韮崎~穴山~(下の棒道)~諏訪へ
↘若神子~~~(中の棒道)~~~湯川~大門峠~松本・長野へ
↘城南~小荒間~(上の棒道)~↗、 一般的には上の棒道が有名、
山梨県須玉町:若神子ワカミコ城跡狼煙台、上棒道起点、小荒間古戦場跡:村上氏との戦い、御座石、遠見石、馬蹄石、日本名水百選・八ヶ岳湧水群の一つ:三分一湧水:三角形の石柱を使う、小荒間口留番所跡、石道標「右すわ左むら」、直線に伸びる、石仏:坂東一番十一面観音立像:嘉永元年、道幅狭い、尾根道けもの道を発見されにくいように活用、川中島攻める前年に造る、武田氏が信州獲得後物資輸送路、石仏多し、坂東三番:千手観音立像、修行僧、御岳参り、生活道、道幅広い所あり防火帯16mとして、坂東七番:聖観世音文字塔、小淵沢、坂東十六番千手観音坐像、その後中山道甲州街道発達で使われなくなる、
・中山道・信濃路:中山道・信州芦田宿から和田峠を越え木曽路に至る部分を紹介する。江戸へ~芦田(江戸から27番目宿)~笠取峠~和田~下諏訪~塩尻~奈良井~鳥居峠~野尻~三留野~妻籠~馬籠峠~馬籠、笠取峠:松並木700本松、馬頭観音、和田峠:唐松・モミ・険しいというが谷沿い緩やかな道、春から秋は快適・冬雪で困難、和田施行所:焚き火・おかゆ一杯・馬にはかいば一杯恵む、木曽の木は尾張藩管轄・生一本首一つ、地元木曾の収入源ならず、近畿特に近江から人足雇い、収入源少ないので木曽の人は何でも食べた、木曽路十一宿、奈良井、杉並木、二百体地蔵、奈良井宿、2km保存、越後屋:旅籠、中村屋:櫛問屋、お六櫛:髪を梳くと頭痛治るといわれた、黄泉画:木曽街道六十九次、鳥居峠h1197m、鎮神社、石畳200m、峰の茶屋:馬方茶屋・句碑、円山公園、石碑多し、薮原宿、与川道:バイパス・野尻~上野原・三留野、妻籠宿:もっとも小さい宿・街並み保存、妻籠宿本陣:南木曾町博物館、中山道・飯田道分岐点、馬籠峠:木曽御木の原生林、「夜明け前」藤村、男滝・女滝、馬籠峠h801m、馬籠宿:藤村出生地、
・野麦道:信州松本と飛騨高山をつなぎ、乗鞍岳南の野麦峠を越える道、近代製糸工場に働きに行く飛騨の娘たちが通ったことで有名。奈川村川浦、石室:復元:文政8年、ボッカ・牛方避難所、松本~川浦~野麦峠~野麦~高山へ90km・野麦街道ともいう、岡船:牛:信州で活躍・飛騨には行かない、信州雪深いため牛がだめでボッカ活躍、最大50貫190kg、たいてい150kg、飛騨ブリ:富山のブリを飛騨高山から信州へ、h1500m越えるとモミ・ツガ等針葉樹林帯を折り返す、熊笹=野麦=ダンゴにして飢えしのぐ、飛騨郡代の江戸往来道で信仰の道、野麦峠、展望・乗鞍岳、飛騨の貧しい少女たち・明治期・信州の製糸工場へ、政井みなの碑:百円工女、当時日本の生糸生産量世界一、お助け小屋:復元、冬の野麦峠越え命がけ、雪道を歩くのは大変・滑落すると止まらない、地蔵堂、野麦:飛騨高根村
・本坂通:~姫街道~ともいわれ江戸幕府が東海道の脇街道として整備した。浜松で東海道から離れ浜名湖北を通過し御油宿で東海道に合流した。浜松~気賀~引佐峠~三ケ日~本坂峠~当古~御油、脇街道、浜名湖北岸、姫街道、気賀一里塚:江戸から69里、引佐峠h200m、時々石畳敷いて安全対策、コスモス、平石御休憩所、姫岩:湯茶接待用、浜名湖展望よし、「姫君様行列之図」、今切関:今切渡船、バイパス、姫街道由来:①姫通った・②ひねた・ひなびた、象鳴き坂:吉宗献上象通過、石投げ岩:岩に石投げすると峠越えが無事という、一里塚:江戸から72里、本坂峠へ、大師堂→山道・石畳、橘逸勢:伊豆流罪途中当地で没す、鏡岩:高さ3m・幅10m・昔は光って姿が映ったという、本坂峠h328m、林間下り坂、嵩山宿スセ:本陣・脇本陣、嵩山の蛇穴遺跡:縄文前期住居跡、豊川市当古豊川・渡船、
・下田街道:~天城越え~、東海道三島宿から天城峠を越え下田に至る道。幕末下田が開港されて重要となる。天城越えともいい、伊豆の踊り子等で有名。~天城越え~、天城峠、「伊豆の踊り子」、旧天城トンネル、三島~韮山~修善寺~湯ヶ島~天城峠(二本杉峠)~小鍋~下田、天城湯ヶ島町大川端・紀州尾鷲の炭焼き市兵衛の墓:石道標「右ハやまみち左ハ下田道」、二本杉峠40分、炭焼き技法を教えた、産業の道でもある、ワサビ田、天城峠頂上:広場・二本大杉、この道1819年私財を投じて完成、幕末外国人も通行、1853年黒船翌年下田函館開港、吉田松陰下田で密航企て捕縛遠丸籠で通過、宋太郎林道、タウンゼント・ハリス下田から江戸へ、釜滝カマダル、川横:川合野、慈眼院、小鍋峠への山道、小鍋峠:河津町と下田市境、「伊豆の踊り子」川端康成の一節朗読、
○・VHS『歴史の道 第6巻 近畿』62分
・東海道:~鈴鹿峠越え~、伊勢と近江を分ける鈴鹿山脈の南に関町セキチョウ、古くは鈴鹿の関があった、伊勢神宮一の鳥居:東の追分、東海道と伊勢別街道分岐点、江戸から106里2丁、江戸時代宿場町街並み:江戸後期、中町:本陣・脇本陣・大旅籠、脇本陣:千鳥破風、関の地蔵院:建立・行基伝、中興・一休伝、門前町、つし二階建て:屋根裏を物置にし軒低い、西の追分:刑場・供養塔は石道標「左伊賀大和道」、関:47番目宿~坂下~鈴鹿峠~土山、転び石、筆捨山:安藤広重「東海道五十三次」にも描かれる、黄色い奇岩、狩野元信が山を描きえず筆を捨てた伝説、坂下宿、法安寺、庫裏は本陣移築、本陣3、脇本陣1、旅籠48、峠まで1里半、岩屋観音:江戸初期石仏、清滝、片山神社、ここから8丁27曲がり峠越え、燈籠坂、夜の旅人用に常夜灯、石畳、難儀、峠を境に天候も違うほどきつい、東の箱根に西の鈴鹿、鈴鹿山の鏡岩:三重県指定天然記念物、山賊は鏡岩に隠れ岩に映った旅人を襲ったという、東海自然歩道、峠は国境で近江側は緩やか下り坂、万人講常夜灯、土山宿、本陣跡、連子格子、二階の塗り込め壁、東海道反野畷タンノナワテ、松並木、
・熊野参詣道:伊勢路、紀伊路、和歌山-(紀伊路)-田辺-滝尻-(中辺路)-本宮-那智勝浦-新宮-(伊勢路)-熊野-八鬼山-尾鷲-馬越峠-海山、馬越峠道マゴセ、西国三十三所巡り第1番札所青岸渡寺巡礼道、八鬼山道ヤキヤマ、難所、石仏、滝尻王子、数多くの王子あり、王子ごと禊をして熊野に詣でる、熊野三山知られたは平安期、上皇たちが熊野詣をするようになってから、果無山脈ハテナシ(大和と紀伊を分ける)熊野山塊、花山上皇が木の枝を折って箸に使ったという箸折峠、牛馬童子像:19歳で譲位させられた花山上皇の姿伝、箸折峠下の近露集落の日置川ヒキ、かつては旅籠30軒一日800人宿泊したことあるという、近露王子、継桜王子・野中の清水、伏拝王子・小さな祠だけ、ここからかつて伏して熊野大社を拝めた・麓の窪地に明治22年まで社があったが洪水で移転、、熊野本宮大社、やた烏、山伏修験場、熊野にいます神社、熊野の本山、熊野川、上皇たちは船で熊野川を下り新宮目指した、新宮・熊野速玉大社、補陀洛渡海、夫婦杉:那智大社への入口、大門坂、那智の滝:落差133m日本一、滝をご神体にした原始信仰から始まる、熊野那智大社、社殿熊野作り権現作り構造、北に大雲取越・小雲取越の2つの道、上皇たちは京に帰るため通った、
・宮津街道:普甲峠越え、大江山越え、丹後の天橋立、宮津市、古い港町、京極氏、宮津城跡、京口橋:京に向かう宮津街道起点、石道標:観音霊場案内「左なりあい観音」、京極氏が参勤交代用に整備した道、ちりめん街道、糸の道・絹の道、石畳が道の半分、峠の茶屋跡、峠の石塔「ちとせ山」: 普甲峠はフコウに通じるのでちとせ山と呼ばせたことがある、天台密教の普甲寺跡、今は寺屋敷集落、普賢堂、最盛期一山百か寺、織田信長により焦土、峠の南側は緩やかで中茶屋集落ナカノチャヤ、昭和30年代まで小中学生登校路、峠越え最短路、二瀬川渓谷、鬼ヶ茶屋の石畳(復元)、遊歩道、大江山鬼退治伝説関連、鬼の足跡、大江山、頼光の腰掛岩、石仏「南無阿弥陀仏 文政六年六月」:道普請犠牲者出た、毛原の道標「右ふげん左なりあい」普甲寺道と宮津なりあい観音道分岐点、南に丹波の山々で京、
・竹内街道:二上山ニジョウサン、大阪と奈良境、竹内峠タケノウチ、最古の国道、613年「難波より京に至る大道を置く」日本書紀、難波-堺-太子-竹内峠-当麻-飛鳥、大阪府太子町「近つ飛鳥」、推古天皇陵、叡福寺「上の太子」推古天皇摂政聖徳太子祀る、聖徳太子廟、太子町・春日、白い塗り壁・板壁、大和川水運に使われた船の板、太子町・大道、餅屋橋の道標「左幸徳天皇御陵」名所旧跡案内、伊勢灯篭、大和棟、西国三十三所巡礼道・5番藤井寺・叡福寺・當麻寺・6番壷坂寺に向かう道、さらにお伊勢参り・長谷寺詣で、道端の地蔵堂「右大阪さかい」、役行者像、岩屋越との分岐点、地蔵「右つぼさか 左岩屋當麻の口」、岩屋越道、当麻寺タイマジ:聖徳太子弟創建、中将姫伝説、河内名所図会、遣隋使派遣で隋の使者を迎える外交路としての必要性、河内細見図、国道166号線、峠の手前草の道少し残る、十一面観音、宝篋印塔、「大峯山三十三度」、竹内峠:国境石「従是東 奈良縣管轄」
・山陰道:~蒲生峠越え~、鳥取県東部と兵庫県北部県境の山々、蒲生峠、鳥取-岩美-岩井温泉-塩谷-蒲生峠(蒲生トンネル)-温泉町・湯村温泉-春来峠-京都、山陰道は律令時代に定められた官道、岩井温泉・蒲生峠まで8km、塩谷、地蔵堂、因幡商人塩運送・但馬商人受け継ぐので塩谷、明治初年まで蒲生川の一番奥の沢が入口、羽柴秀吉も鳥取城攻撃に使った道、あまりに険しいので鳥取藩は参勤交代道からはずす、今は一番奥で崖になり不通、明治初期にその上に大八車用の国道できる、文化庁歴史の道百選指定、上り口から3km頂上見える、蒲生峠h356mには延命地蔵、国道9号線真下トンネル、旧国道通過、鳥取・兵庫県境、温泉町・千石チタニ宿場町、こうじ屋旅館「昭和八年四月宿泊人名簿」出稼ぎ商人・職人・馬喰、生業の道、千原の名号石「南無阿弥陀仏」、伊勢神宮常夜灯「大神宮 秋葉山 愛宕山 天保十四」、温泉町湯村温泉、慈覚大師:平安期発見伝、夢千代日記、春来川、春来峠・今は下をトンネル、榜示石「従是西豊岡藩」、因幡から蒲生峠を越えて但馬に入った山陰道は春来峠を越えて幾重にも連なる山々の先の京を目指す。
○・VHS『歴史の道 第7巻 近畿・中国』61分
・柳生街道:奈良市北部を東の柳生まで結ぶ道、剣豪の道といわれるが信仰や奈良市内の大寺院とその荘園だった柳生周辺を結ぶ道。興福寺から見た奈良北部、春日山と高円山の窪みを越える道、奈良春日山南麓~石切峠~大柳生~柳生:5里20km、能登川、滝坂道、葬送の道、修行の道、大寺院の荘園への道(物資)、轍の跡:石畳、寝仏:崖上の大日如来の摩崖仏が落ちたもの、夕日観音:摩崖仏:弥勒菩薩、朝日観音: 摩崖仏:弥勒・地蔵、首切り地蔵:地獄谷と柳生への分岐点、石切峠:奈良大仏春日石切り出し、春日山石窟仏: 摩崖仏:平安後期:春日石切り出し、地獄谷石窟仏:線を刻んで彩色:薬師・る遮那仏・十一面観音:奈良期昨、峠の茶屋:武芸者の代金代わりの武具、誓多林、忍辱山円成寺:文化財・春日堂・白山堂:日本最古の春日造り、庭園:平安期の姿残す:国の名勝、大柳生への下り、大柳生集落内を街道通過、阪原峠:石畳残る、柳生:家老屋敷跡:小山田しゅれい:資料館、柳生陣屋跡、1万石、正木道場:復元:柳生新陰流、芳徳禅寺:沢庵和尚・柳生宗矩・柳生家菩提寺、
・大山道:中国地方屈指の名山で信仰の山、大山ダイセン。その麓の大山寺を目指す道。大山h1729m、伯耆富士、関金~(川床道)~大山寺・大山~(横手道)~釘貫小川~岡山へ、
大山道:大山寺目指す・大山参り:農業神、「六十余州名所図会・大山遠望」、瀬戸内からの横手道大山西側を南北に通過、ブナ林内古道、横手地蔵:18番1丁ごと置かれた、南からは荒々しい姿で西からは優しい姿、一の沢、大山は死霊のおもむく山:備中の人々は道に石仏祀る、川床道:風情残る・7km古道残る、地蔵峠:地蔵「萬延元年」、道は川沿い緩やか、大山滝、大休峠:急坂道1km、h1000m、川床まで4km:石畳、(岡山県:牛つなぎ石:穴あき石)、大山での牛馬市のため牛馬連れて行った、大山寺:宝牛像、
・智頭往来:~志戸坂峠越え~、平安期から因幡と上方を結ぶ道、参勤交代も使った。因幡→上方へ、平安期都からの国司往来・江戸期鳥取藩参勤交代、鳥取~市瀬~智頭チズ~志戸坂峠~京都へ、鳥取から智頭で一泊、鳥取から志戸坂峠越えで1日半40km、平時範「時範記」:旅日記、参勤交代用道178回、鳥取城、「鳥取城攻めの陣営図」:秀吉は堅固な鳥取城落とすため街道通過、千代川沿いに智頭往来あり、篠ヶホキ:山間の険しい所難所、六地蔵「寛政十二年」、(京・上方・馬方)(街道・往来)、智頭宿:石道標・備前街道分岐点、魚の棚、志戸坂峠:2km・積雪通行不可・「けふいなばそふの瀧山こえるなり都にかけよ夢のうきはし」、明治20年大改修・馬車道・改修碑、
・広瀬清水街道:山陰の鎌倉といわれる島根県広瀬と山陰道をつなぐ道、尼子一族ゆかりの地や安来の清水寺への参詣道。島根県広瀬町・山陰の鎌倉・富田トダ・月山ガッサン:尼子氏居城、尼子氏利用道、広瀬~鍵尾峠~清水峠~門生~(山陰道)~安来~松江
↘京へ(山陰道)
「出雲国風土記」、月山:富田城跡1397年尼子氏入城11カ国領有・1566年毛利氏により陥落、意多岐神社オダキ:古代出雲四大社の一つ・能義神社…中心地、古道は草生し通う人なし、尼子時代の軍用道、鍵尾峠:石塔、能登?集落:竹やぶ、出雲巡礼21番札所11番清水寺巡礼道:信仰道、石道標「右きよみず左ひろせ」、弁慶坂:弁慶が釣鐘を担ぎ上ったという伝説、仁王門・清水寺キヨミズサン・尼子一族菩提寺・本堂:観音33図・尼子拾勇士絵:山中鹿之助等・弁慶絵図・三重塔1859年建立山陰唯一、追分:六地蔵・山陰道と合流、
・山陽道:~大山峠越え・玖波~、京都と九州大宰府を結ぶ最も重要な官道で、宮島厳島神社周辺に残存している箇所を紹介する。大化の改新以降、七つの道を官道:大中小区分:中国行程路:唯一の大路:都と大宰府を結ぶ道:大宰府は遠の朝廷ミカド:政治文化外交上重要な道、「中国行程図」、京~東広島市西条町~大山峠~広島~~~~大野町~玖波~大竹~大宰府
宮島厳島神社
安芸の国中心地:西条町:広島大学中心:四日市次郎丸という宿場町:西条駅北側:国分寺跡:仁王門・七重塔礎石・レンガ造り・煙突・白壁・造り酒屋・本陣跡:部屋数29、海岸に出た山陽道は展望よし、大野町:厳島神社展望よい、室町期今川貞世通行:幕府勢力権力拡大のため、宮島厳島神社:平安末期平清盛造営・塔の岡:五重塔・戦国期毛利が陶晴賢を破る1555年、毛利:要害山山頂のおとりの城、鼓ヶ浦、大野:四十八坂:49よりまし、つづらおり長洲戦争激戦地、残念神社:長洲戦争戦没者祀る、
○・VHS『歴史の道 第8巻 中国・四国』60分
・萩往還:江戸期毛利氏が治めた長洲藩府・萩と瀬戸内の三田尻を結び参勤交代や多くのし志士達が通った道。
萩城跡、「中国行程記」江戸中期宝暦・萩から京都伏見まで・第1巻は萩から三田尻まで、萩~明木アキラギ~一ノ坂~山口~防府(三田尻)、松下村塾・吉田松陰像・維新の志士輩出、涙松の遺址「帰らじと思ひさだめし旅なればひとしほぬるる涙松かな」松陰、萩から一里のオオヤ竹やぶ・首切り地蔵:刑場跡・石碑「栗山孝庵女刑屍体臓分之跡」日本で初めて女性遺体解剖、萩から五里・一升谷:石畳:一升の豆を食べつくすほど長い坂という、国境の碑「北長門國阿武郡 南周防國吉敷郡」、一ノ坂h差260m、曲がり角40以上、三田尻御船倉跡:参勤交代や旅人によっては船移動・毛利水軍、
・赤間関街道:~中道筋~、長洲藩府・萩と赤間関:下関を結ぶ3つの街道、その中でも美東・吉田を経て赤間関に至る中道筋は公用路として重視された。
萩市、高杉晋作の生家:彼がよく通った道、
萩~明木~一ノ坂~(萩往還)~山口~防府(三田尻)
↘美東~絵堂~秋吉~(中道筋)~吉田~赤間関(下関):19里
↘~(北浦筋)~ ↗
↘~(北浦道筋)~ ↗
下ノ峠タオ、美東町、絵堂戦跡記念碑、長州藩政府軍本陣跡、戸に弾痕、大田・絵堂戦に使われた鉄砲、金麗社、「四境の役」、燈籠:小倉城のもの略奪、カルスト、大久保台、石畳、秋芳洞:滝穴32間、吉田宰判勘場跡:自治体の区役所、しみずやま:高杉晋作の墓「東行の墓」29歳、「六十余州名所図会・下の関」、壇ノ浦、赤間神宮、長洲砲、
・讃岐街道:~大坂峠越え~、讃岐高松から讃岐山脈越えで阿波徳島に至る道。鳴門市四国遍路一番札所霊山寺に向かう信仰の道で義経が屋島に駆け抜けた道でもある。
讃岐山脈、讃岐街道:琴平へ~高松・屋島~引田~大坂峠~板野~徳島~勝浦~土佐へ
伊予へ↙ ↘鳴門
引田町ヒケタ、落ち着いたたたずまい、引田廻船、寿可多美の地蔵「右大坂道 左なる戸 文化十四年」、「六十余州名所図会・象頭山遠望」、信仰の地、阿波鳴門一番札所霊山寺、二番札所極楽寺、三番札所金泉寺、四国八十八箇所巡りの一番に行くため大坂峠は最初の難所、大坂峠への丁石、借耕牛、5丁目過ぎると急坂、800年前源義経一行通過:屋島の合戦、豆茶屋跡石垣、豆茶:半つき米と豆を一晩つけてから蒸して白湯をかけたもの、徳島城跡、蜂須賀氏、番所・村瀬家・大坂御番所跡:明治初期までの230年間・武具、遍路の通行手形「遍路」、近代大正昭和初期にトンネル・鉄道開通により大坂峠いなくなる、
・土佐北街道:~笹ヶ峰越え~、土佐高知を峻険な四国山地越えで瀬戸内と結んだ道。参勤交代120年ほど2000人ほど・信仰・物資輸送路として利用された道。土佐藩二十四万石山之内一豊:高知城、四国山地、高知~大豊~笹ヶ峰h1015m~新宮~川之江、はじめ参勤交代路は海路で20日ほどだが、潮待ちで50日、江戸中期に期日厳守となり陸路開発。碁石茶:発酵茶・筵に干した様子が碁石に似ている、笹ヶ峰、国境標:土佐伊予、しばらく尾根通し、杖立て地蔵・弘法大師像・安政九年1858・杖を立てて感謝、腹包丁h差400mで距離1500m続く急坂:腰にさした刀が地面につかえるので腹に抱えた、オハツキイチョウ樹齢300年・安産祈る・柱瘤、平安期:熊野神社信仰の道・参勤交代以前から、
・檮原街道ユスハラ:(檮トウ)、~韮ヶ峠越え~、高知城下から伊予の境・檮原を経て大洲城下を結ぶ道。坂本龍馬等勤皇志士脱藩して通ったことから(勤皇・脱藩)(街道・道)ともいう。
高知~須崎~檮原~韮ヶ峠~大野ヶ原~泉ヶ峠~宿間~大洲・長浜、勤皇街道、坂本龍馬、高知城、桂浜・坂本龍馬像、1862年脱藩、澤村惣之丞:海援隊前身亀山社中、檮原:千枚田・那須俊平信吾・掛橋和泉邸:神官・勤皇志士かくまう、宮野々番所跡、韮ヶ峠:舗装道路・土佐伊予境、大野ヶ原・激戦地、男水:龍馬が水を飲んだという、榎ヶ峠、御幸の橋:屋根付き橋江戸中期休憩用に付けた、泉ヶ峠:かつて旅館や運送業でにぎわう・石垣跡、宿間、肱川、船で長浜へ下れる、
○・VHS『歴史の道 第9巻 九州』62分
・長崎街道Ⅰ:~冷水峠越え~、鎖国の中唯一開かれていた天領・長崎と筑前小倉を結ぶ道。著名人が往来し海外文明を伝えた道。小倉~黒崎~木屋瀬~飯塚~内野~冷水峠h283m~山家ヤマエ~原田~長崎へ、筑前六宿チクゼンムシュク、エンゲルベルト・ケンペル1691年江戸旅行・「江戸参府道中の画」・オランダ商館長(カピタン)の駕籠、山家宿、「筑前六宿・山家宿」、追分石「右肥前大宰府長嵜原田 左肥後久留米柳川松崎」、西構口跡、恵比寿石神:江戸初期寛永年間建立:1611年山家宿開設理由記入され貴重、郡屋土蔵:参勤交代用品置いた、郡屋は近代取り壊し、冷水峠:九州の箱根、黒田長政整備・博多を通らせない、首無し地蔵堂:旅人の身代わり伝説、石畳、「南蛮屏風」:象通過、山間の低地伝いに内野宿へ、「筑前名所図会・往来の図」、「寂寥の山駅にして海遠く山深し」松陰、内野宿三叉路石道標「大宰府天満宮米山越道」:米山官道、老松神社、正円寺、長崎屋:脇本陣、小倉屋:脇本陣・荷物輸送中継の問屋場・両替商、
・肥前・筑前街道:~背振坂越えセフリ~、全長6里24km、肥前・佐賀県と筑前・福岡県を結ぶ道。平安末期平家の財源佐賀県神崎の年貢米を博多港へ運ぶ道。脊振坂越えは博多への最短ルート。吉野ヶ里遺跡、神埼宿:長崎街道合流、櫛田宮・肥前鳥居:複数の石組み合わせ、
佐賀~神埼~(坂本峠)~脊振坂~亀ノ尾峠~山田(那珂川)~博多、
脊振山
脊振山地、脊振山頂・脊振神社:修験一大聖地・脊振千坊・修学院:脊振山下宮:鍋島家祈願所、一町宮:地蔵「右ちくぜん道 左山」、五町石、平安末期平家により信仰道から年貢米を運ぶ流通道へ発展、霊仙寺跡・石道標「右とうりみち 左坊中」、左へ行くと茶の木:栄西禅師が中国から持ち帰り植えた茶の木という、茶園上りきると乙護法堂、水上坊跡、千坊ほとんど消失、霊水石、自生白サザンカ名所、坂本峠の馬頭観世音、国境石:江戸期元禄1600年代末、那珂川中州石垣:國領示し石に触ること禁止旨刻む、南畑ダム、亀ノ尾峠:石畳残る、石垣:山城の家来屋敷跡、山田(那珂川町):農耕で栄える、裂田溝:用水路、那珂川、川港、
・太閤道:肥前・佐賀県唐津から鎮西町名護屋までの16kmの道。秀吉朝鮮出兵では名護屋城建築資材運搬や軍勢移動用に整備した道。
唐津城「舞鶴城」:桃山様式模した昭和の復元、松浦潟、虹の松原:5km長さ・防風防砂林・国天然記念物、かつて遣唐使派遣港で唐の津、佐賀~(唐津街道)~佐志ノ辻~馬部~鎮西・名護屋城跡、1591年朝鮮出兵、近松寺キンショウジ:名護屋城一の門、浄泰寺前道通過、林の中、観音:道標、佐志ノ辻:太閤道一里塚、そば畑内一里塚石、石垣残存、西進むと野元神社、農道として北進む、名護屋城跡:大阪城に次ぐ規模で桃山様式五層天守閣・30万将兵、陣屋跡大小260箇所以上、草庵茶室の遺構、草庵茶室想像図:四畳半、「太閤が睨みし海の霞かな」青木月斗、
・長崎街道Ⅱ:~日見峠・井桶ノ尾峠越えイビノオ~、文明の道、異国情緒溢れる長崎から大村間に古道の面影多く残る。海外文明を伝播した道でシーボルトも通った。長崎市、孔子廟、オランダ坂、メガネ橋、出島(復元模型)、平戸オランダ商館を長崎出島移転、長崎~日見峠~矢上ヤガミ~井桶ノ尾峠~諫早~破籠井ワリゴイ~鈴田峠~大村~小倉へ、蛍茶屋、一瀬橋、「長崎近郊の貴族的な茶屋」F・ベアト撮影:幕末の蛍茶屋と一瀬橋写る、近くに鳴滝塾跡:医院・塾(現シーボルト記念館):医師・博物学者、アジサイをお滝さんからオタクサと命名、シーボルト旅日記、日見峠:由来:火見:戦でかがり火が見えた、日見峠の切通し、下りは通称七曲、芒塚:向井去来の句碑、長崎街道矢上宿跡、教宗寺・庭園、井桶ノ尾峠手前に天領と肥前佐賀藩領境石、井桶ノ尾峠:h100mほどの丘の連なり、長崎街道御籠立場、眼下に大村湾、諫早、破籠井:旅人がここで弁当箱を開けて食べた所なので、鈴田峠:深い山の中通過、大村の町眼下に見える、
・豊後街道:熊本市、熊本城、肥後・熊本城下から阿蘇外輪山北部通過し豊後・大分県鶴崎港に至る道。31里、加藤清正によって整備が始められた。左右を堤にし一段掘り下げて造られた清正公道セイショウコウドウが残る。熊本~大津オオヅ~二重峠~内牧~一の宮~滝室坂~大利~山鹿~鶴崎へ、 阿蘇山
整然と石垣、武蔵塚:宮本武蔵:細川氏庇護、大津街道杉並木:屋久杉、大津宿:熊本から五里、清正公道、路面土粘って滑る、二里半、二重峠、健磐龍命伝説:カルデラに水溜まる削ったが水抜けず見ると二重だった、大津から望む外輪山、上りきると石畳の下り坂、天草展望、阿蘇五岳展望、車帰坂クルマガエシ、牛王水ゴオウスイ・石畳斜め排水工夫、阿蘇谷、1km先・的石御茶屋跡、内牧ウチノマキ、一の宮、阿蘇神社、坂梨・大坂に坂無し坂梨に坂有り、滝室坂、乙護法堂オトゴホウ: 乙護法:子供姿の神:仏法守護、この先草地で一旦道消失、坂の上、大利の石畳、山鹿の石畳、坂上で国境、鶴崎から船で大坂へ、
○・VHS『歴史の道 第10巻 九州・沖縄』56分
・日田・中津街道:江戸期西国郡代が置かれた天領日田と周防灘に面する中津藩十万石中津城下を結ぶ道。周防国・山口県から呼び寄せた石工が敷いた石畳が残る。日田~市ノ瀬~伏木峠~中津、日田市:天領九州政治経済金融中心地、永山布政所(郡代屋敷):西国郡代、豆田町・古い商家残る、掛屋:両替商:日田金、咸宜園跡カンギ:すべてよろしいの意で誰でも入門できた:広瀬淡窓: 掛屋:塾生:高野長英・大村益次郎・「休道他郷多辛苦 同胞有友自相親 柴扉暁出霜如雪 君汲川流我拾薪」、中津街道北東へ・石坂石畳道・1.3km・嘉永三年・信仰道・周防から石工呼ぶ・坂に石敷くのは高度技術、道の中央に滑りにくい石で両端は違う、石阪修治碑:石坂完成記念・碑文:淡窓、茶屋跡:石垣、物資輸送路、
・日田・竹田街道:滝廉太郎「荒城の月」の豊後・大分県竹田の岡城の城下町から久住高原南部を通過し、天領日田に至る道。九十九折の石畳を通って大量に物資が運搬された。岡城跡:鎌倉期・国史跡、久住高原クジュウ、日田往還、大分~竹田~曽田ノ台~出口イデグチ~台下~日田、 久住山
湯見岳ユノミh740mの麓で肥後方面の道と日田往還出合う、石道標「右つ 左小国 」その横にかつての旧道痕跡わずかに残る、曽田ノ池、曽田ノ台、下る石畳九十九折700~800m、物資輸送路、「五馬駄賃取り唄」、浄念寺(北平)、中村(出口駅):石垣、日田屋旅館「店」:茅葺、出口庄屋屋敷跡、文化九年:伊能忠敬宿泊記念碑、伊能忠敬、玉来神社・五馬媛イツマヒメ:土蜘蛛の意・老杉、薹(台)神社:江戸中期・前の坂道は舗装石畳、
・飫肥街道オビ:(飫ヨ・オ) 飫肥藩の日南市飫肥オビから北の宮崎や、南は薩摩や大隈へ通じた道。花立山近くに旧街道が残る。日南市飫肥オビ、飫肥城:伊東氏、鹿児島へ~都城~日南・飫肥~花立山~山仮屋~清武~宮崎、殿様街道:参勤交代用、「元禄十四年飫肥領国絵図」、伊東家邸宅:江戸期270年間伊東氏治める、本町通り、酒谷川、唐人、物資流通盛ん、振徳堂:藩の塾・儒学幕末には蘭学医学も、旧道は花立山を越えた辺りから山仮屋関所跡まで1.6km残存、桜名所、石仏、町指定史跡:山仮屋関所跡h400m、「山仮屋関所跡見取図」、汗道:険しい飫肥街道・佐々助三郎スケサン通過、安井息軒旧宅(復元・清武町)、
・東目筋・大口筋:薩摩藩城下町鹿児島を起点に宮崎に向かう道を東目筋、肥後・熊本に向かう道を大口筋という。勢力のある薩摩藩の道なので見事な整備がされている。錦江湾・桜島・鹿児島市、鹿児島~白銀坂~加治木~竜門司坂~(大口筋)~大口~熊本へ
桜島 ↘(東目筋)~宮崎へ
↘宮崎へ
鶴丸城:館作り・櫓や天守閣なし:島津氏、白銀坂:錦江湾絶壁に道できず山坂道となる:石畳道幅広し・急勾配では段差設ける、布引(白銀)の滝:落差20m、展望よい、1km石畳国道合流、姶良町アイラ(姶オウ)、加治木町:隈姫神社クマヒメ:悲劇の姫祀る、田の神、龍門滝:落差46m、竜門司坂タツモンジ(ダシモン坂):酒樽等だしもんを運ぶ、長さ464m元文6年石畳敷く、加治木:焼き物・龍門司焼(黒もん)、明治5年国道10号線・明治34年鉄道近代開通旧道通らない、
・国頭・中頭方西海道クニガミ・ナカガミホウサイカイドウ:首里から座喜味城へ向かう中頭方西海道、さらに北の今帰仁城へ向かう国頭方西海道、首里城を出た道は琉球王朝時代の面影残す石畳道となって北へ延びる。
琉球王朝時代の石畳道、守礼門、首里城、各城グスクからの道、歓會門、金城の石畳道カナジョウ、宿道シュクミチ:公用、那覇・首里~浦添~座喜味城跡~仲泊~恩納オンナ~名護~今帰仁ナキジン、中頭方西海道:安波茶橋アハチャ:500年前建造、浦添城跡:切石積石垣残存・薩摩藩征服により、史跡当山の石畳道:17世紀半ば作られる:馬転ばし、国頭方西海道:読谷山の道、宿道は間切マギリ:いくつかの集落を集めたもの:に行く道、多幸山のフェーレー岩:フェーレー=山賊、サトウキビ畑、海展望、本部半島: 今帰仁城、山田谷川矼: 矼コウ=石橋・かつて6枚の石橋・今4枚で復元、久良波の道:断崖の上道・下草刈ってもすぐ草むら、比屋根ヒヤネ坂:石畳、ペリーは浦賀来る前琉球国頭方西海道通る、「夕暮れの恩納番所:ハイネ画」、史跡仲泊遺跡:第三貝塚:沖縄海洋博国道拡張工事発見、海沿い道、今帰仁城跡:石垣、行程80km、
私も『古道を行く』という本を出版し、古道マニアの一人として、このようなビデオがあることはうれしい。とりあえず北海道から沖縄までにある古道をビジュアルに紹介した功績はあろう。この目で古道の一端を見られてうれしい。そしていつの日にかそこに自分がいることを念じていた。今後さらに古道はメジャーになっていくだろう。
映像内の浮世絵や写真が3D画像になり立体感が得られる。「アバター」より古いものなので、多少立体感は落ちるが、ごく初期の試験作品として、技術開発途上のものとして楽しめる。
○・VHS『歴史の道 第1巻 北海道・東北』55分
・旧福山街道:松前町(福山)から松前半島の日本海沿岸沿い北上檜山郡上ノ国町に通ずる。中世北海道歴史資料勝山館遺構等残る。上ノ国~赤坂~虎ノ沢~松前(福山)~函館。
虎ノ沢:昔はヒグマが見られた、幕府の巡検使が羆を見て騒ぎヒグマが虎の如く速く逃げたためといわれる、伝説:十兵衛石:彼が戦って勝てなかった相手。15世紀に和人ともめる、八幡牧野:八幡菩薩祈る、1457年アイヌのコシャマイン軍と武田信広の戦い、コシャマイン優勢だったが最終的に和人勝つ。赤坂:赤土はこの戦いの名残という、足洗川:旅人わらじ洗う、勝山館跡(武田信広館跡)、和人館12、客殿跡、館神八幡宮跡、鳥居跡、空堀、沢から用水でため池へ、3万点陶磁器かなり高い文明、数万点金属品木製品、夷王山、夷王山墳墓群:武田氏柿崎氏墓、大きな和人社会、武士中心、海産物本州必要で和人増加、上国寺: 武田信広菩提寺、上ノ国八幡宮、
・奥州街道:みちのくに通じる重要街道、簑ヶ坂の急坂は明治天皇行幸時近在青年が馬車押し上げたという。54宿。盛岡~簑ヶ坂~三戸~高山峠~五戸~青森~三厩。蝦夷地に通ずる。
大蛇が簑に化け旅人を引きずり込んだという伝説。標高180m籠立場:岩手青森県境まで100m急坂、明治天皇巡幸記念碑、緩やか下り坂200m一里塚、三戸:南部藩発祥地のち盛岡へ、三戸城復元、宮坂、なだらか単調に続く長坂、一里塚残存多し:所有者不変でそのまま、高山峠H277m、展望名久井岳、長い下り坂、2km先で赤松古木、浅水城跡:南部氏、宝福寺、鳥内坂トリナイ、五戸町:宿場町・代官所、江渡家住宅:寄棟作り・国重要文化財・代官下役、追分石、
・羽州街道:~矢立峠越え~、秋田青森県境の矢立峠(杉峠:天然秋田杉)は急勾配、吉田松陰もその険しさを詩に詠む、碇ヶ関関所では米や物資の移動を厳しく検査した。秋田~能代~大館~矢立峠~碇ヶ関~弘前~青森。
長走の風穴:気孔冷風真夏10度高山植物H165m、矢立峠H258m難所、矢立温泉、吉田松陰「漢詩」、相馬大作跡地:南部騒動、急な下り坂参勤交代有名人通過、碇ヶ関関所:口留番所:物資監視、遠見番所、下番所・上番所、碇ヶ関温泉入湯規則、
・秋田街道:~国見峠越え~、盛岡城下から雫石、仙岩峠、国見峠を越え秋田城下を最短で結んでいた。平泉藤原氏全盛時代は生活密着重要道。盛岡~雫石~仙岩峠センガン~田沢湖町~秋田、
橋場宿(雫石町):番所、坂本川沿いに西、南部藩は馬名産地で藩直営牧場、馬買い衆往来、人馬通行為道整備、難所は南部領と秋田領境の南に仙岩峠:「是より南西秋田領」、北に国見峠:「是より北東南部領」で二つは国境山道でつながる、助小屋跡地:相互の荷物を信頼して預ける、盛岡城跡、仙北町、六枚野一里塚(田沢湖町)、田沢湖、
・北国街道:~三崎山越え~、山形県酒田から庄内地方の日本海沿岸沿いに秋田県象潟に通じる街道、県境の三崎山越えは芭蕉他多くの文人墨客が日本海の潮騒を聞きつつたどった峠道。酒田~遊佐~三崎山~象潟~秋田。
最上川、酒田市、出羽随一港、吹浦海岸、十六羅漢岩:明治初期22体石仏刻む、奥の細道三崎峠、駒泣かせ、坂道、石畳、大師堂1493年建立、有耶無耶の関跡、タブの木、供養塔:領土争い死者、一里塚、象潟:天下の絶景:遠浅海に小島多数、向こうに鳥海山だが1804年海底隆起で陸地、カンマンジ(虫甘)満寺、「象潟や雨に西施がねぶの花」芭蕉、
○・VHS『歴史の道 第2巻 東北』60分
・出羽・仙台街道:~中山越え・山刀伐峠越えナタギリ~、宮城県鳴子町から山形県最上町・尾花沢市に至る街道、奥の細道での通行している、中山越の先に山刀伐峠越えという難所、最上街道とも、仙台~鳴子~尿前~中山峠~最上~酒田
↘山刀伐峠~尾花沢~山形へ
鳴子温泉:こけし、尿前の関、松尾芭蕉「此道旅人稀なる所なれば関守にあやしめられて漸として関をこす」奥の細道、源義経を藤原秀平が迎えに来た伝説、コブカザワからオオブカザワへ、境田村、「大山のぼって日既暮れければ封人の家を見かけて舎を求む」芭蕉、封人の家(旧有路家住宅):国境守る役人:土間に三つ厩:「蚤虱馬の尿する枕もと」芭蕉、山刀伐峠:ハケゴという籠を二つに切った形の峠、10km、「高山森々として一鳥声きかず木の下閤茂りあひて夜る行がごとし」奥の細道、27曲がり、子持ち杉、子宝地蔵堂、代官領境、
・米沢・福島街道:~板谷峠越え~、米沢から板谷峠越えで福島につながる街道、米沢藩専用の参勤交代道として利用、板谷峠から李平の旧街道の石畳、米沢~板谷峠~李平~福島、
米沢城跡、上杉家墓所、御霊屋:国史跡、米沢城下絵図、普門院、上杉鷹山:藩財政建て直し、板谷宿、本陣代わり板谷御殿、大野九郎兵衛の墓:伝説:赤穂浪士が上杉家に逃げる吉良を討つため待ち構えたが来なかったので死んだ、板谷峠H760m、米沢藩だけ参勤交代ここ通過、物資輸送、旧米沢街道石畳、李平宿場跡、李平村絵図、あべ家中心に40戸、人馬栄えたが今草むら、泉安寺跡の墓:森林内廃墟墓地・明治4年廃寺、明治32年鉄道開通・3年後大火で廃村、庭坂宿から先奥州街道合流。
・会津街道:~束松峠・滝沢峠越え~、会津若松から越後新発田へ至る道、海路佐渡に続く、会津若松では滝沢峠・戸ノ口原古戦場、戊辰戦争舞台:白川街道筋にもつながる。
会津若松、鶴ヶ城、
新発田~束松峠~会津若松~滝沢峠~(白河街道~)白河
↘三春
会津坂下アイズバンゲ、恵隆寺:仏像・立木観音:千手観音、天屋本名テンヤホンナ:道の左右別名、ホンナには肝煎斉藤家:肝煎は庄屋のこと、上り坂にかつて敷石だったが馬車邪魔で剥ぎ取られてない、地蔵の茶屋跡、石仏、石水槽、三本松、一里塚、束松:天然記念物、先300m束松峠、展望台:会津盆地、
白河街道、会津若松、旧滝沢本陣、戊辰戦争弾痕跡、滝沢峠道昭和40年代復元、石畳、参勤交代、佐渡金山運搬道、十八人之墓、戸ノ口原古戦場、白虎隊、
・八十里越え:越後吉ヶ平と会津、福島県只見町を結ぶ街道。平家追討失敗:以仁王、官軍に追われた長岡藩家老:河井継之助も通った。長岡~吉ヶ平ヨシガヒラ~鞍掛峠~木ノ根峠(八十里峠)~入叶津、26km、一里が10里に相当するといわれた、
以仁王流浪伝説(富士川戦死)、源仲綱墓:伝説(富士川戦死)、吉ヶ平山荘:かつて庄屋椿屋敷、河井継之助:武装中立主張するが賊軍として敗走、長岡城攻防絵図、守門川、八十里越え入る、2時間6.7kmで番屋乗越H895m:番屋は源仲綱設置伝説、空堀小屋跡:宿泊休憩食事、眺望・烏帽子山・岩肌剥き出し、鞍掛峠、小松峰・眺望、「八十里こしぬけ武士の越す峠」河井継之助、木ノ根峠(八十里峠)、庶民交流・生活道、入叶津(只見町):越後交流・越後弁、口留番所跡:会津藩監視用、医王寺(只見町塩沢:、河井継之助墓:北越の蒼き竜
・下野街道:会津若松から田島・山王峠越えで下野・今市へ向かう道、参勤交代や東照宮参詣道としてにぎわった。大内宿は名高い。会津若松~栃沢~大内峠~大内宿~田島~糸沢~山王峠~今市へ、会津西街道ともいう、
栃沢、栃沢一里塚、大内峠、大内ダム:大内沼、地蔵「右若松」石仏、大内宿・本陣跡・参勤交代・回米(扶持米)運搬用・高倉神社、田島・宿駅、糸沢宿・口留番所・戊辰戦争の図・龍福寺:襖逆さ芸州弐番隊、山王茶屋(峠中腹)、日吉神社、山王峠:馬頭観音:H903m、
○・VHS『歴史の道 第3巻 関東』58分
・陸前浜街道:~十王坂越え~、江戸と水戸を結ぶ実と街道の延長、陸前・岩沼で奥州街道と合流、伊能忠敬も歩いた道の十王町から高萩を行く。水戸~日立~十王坂~十王~伊師~高萩、磐城相馬街道とも、
鵜の岬:ここで捕れた鵜を岐阜県長良川で使う、十王台遺跡:縄文弥生、十王台式土器:十王町民俗資料館:北関東弥生様式稲作文化、海岸段丘上通過、北方軍用道路の面、奥州街道脇往還、高萩の海見える、(十王町)伊師、一里塚、愛宕神社、馬頭観音:台座「右いぶき山 左いわき道」、長久保赤水:江戸中期地理測量学者・長久保赤水旧宅、伊能忠敬到着10日前亡くなる、
・日光杉並木街道:日光街道・会津西街道・例幣使街道は世界最長杉並木道、砲弾撃ち込み杉・からかさ杉等ある。特別史跡・天然記念物。古くは樹齢350年、日光街道:宇都宮~大沢~今市~日光、例幣使街道:小倉~今市~日光~大 ~会津西街道、総延長37km、
日光街道、並木寄進碑:1648年、日光東照宮、大沢御殿跡、今市宿、芋の木杉、砲弾打ち込み杉、神橋、並木寄進碑、
例幣使街道、並木寄進碑、
会津西街道、からかさ杉、
・中山道:~碓氷峠越え~、上州から信州に向かう道に難所:碓氷峠があり境に熊野神社社殿がまたがっている、妙義山・浅間山の展望がよい。碓氷峠関所跡(横川)、坂本~碓氷峠~軽井沢~追分~塩尻、
坂本宿、「木曽街道69次・坂本宿:英泉」:本陣・脇本陣、碓氷峠、安政遠足トオアシ:安中城から碓氷峠、堂峰番所跡:遠見番所、覗ノゾキ:坂本宿見下ろせる・一茶「坂本や袂の下の夕ひばり」、馬頭観音、はね石坂、なだらか、唐松林、山中茶屋:峠真ん中・寺・13軒、H956m群馬長野県境、石風車、見晴台・眺望・浅間山、遊覧歩道軽井沢、碓氷峠越えは江戸防衛のため、二手橋、軽井沢・沓掛・追分宿、旅籠油屋、分(か)去れの石道標:中山道と北国街道分岐点、
・見沼通船堀:(浦和市)さいたま市、水運の堀、1721年開通、パナマ運河より183年前同一「閘門式コウモンシキ: 水のエレベーター」。見沼代用水路~東縁と西縁を結ぶ水路、下山口新田、芝川、浦和、見沼は広大沼地で干拓で新田、利根川取水口、西縁代用水路、東縁代用水路、4つの水門、江戸との物資輸送、
東縁仮締め切り、今は隣にふるさと歩道、東縁第二の関、東縁一の関、距離390m、芝川、水位差3m、、水門高さ九尺2.7m・板塀・鳥居柱・各落板、八丁橋、大正時代の八丁橋・写真、おやつもらって船通す、水神社、鈴木家:通船業務、西縁代用水路、654m、西縁第二の関:今ない、
・鎌倉街道:~上総道~、関東周辺から鎌倉に至る道を一般に鎌倉街道という。房総半島にも海路越しの道があり市原市・袖ヶ浦市を訪ねる。鎌倉~(海路)~木更津~三ツ作~立野~袖ヶ浦~市原~千葉、古代の官道、上総国分寺・国分尼寺、源頼朝、竜島(鋸南町):頼朝上陸地、飯香岡八幡宮、切替家:旗印を頼朝のものに切り替えたため、御所覧塚H3m:頼朝築かせた、須軽田坂、おみかり様:首狩の意、三ツ作神社、石道標「南たかくら道」・「北ちば道」、木更津たかくら観音霊場道、
○・VHS『歴史の道 第4巻 関東・北信越』60分
・浜街道:~鑓水峠越え・絹の道~、幕末から明治初期に桑都といわれた八王子から横浜まで、八王子と鑓水の商人が生糸や絹織物を運んだ道で絹の道とも浜街道ともいわれる。鑓水周辺は貴重な歴史の道として残存している。明治期写真「鑓水の風景」フェリックス・ベアト:撮影、八王子~大塚山~鑓水峠~(絹の道)~横浜へ、浜街道40km起点八王子は関東周辺生糸集散地で桑都といわれた、「新編武蔵風土記・八王子宿」、h213m大塚山周辺残存、八王子市、鑓水峠、絹の道→横浜、明治8年建立の大塚道了堂跡(大塚山公園)、「大塚山道了堂之図」、写真「八王子に向かう道」ベアト撮影、鑓水峠、江戸期・絹運送規制、明治開放、「神奈川横浜新開港図」、かつて裕福だった鑓水商人がたてた石塔多し、絹の道資料館:八木下要右衛門屋敷跡、旧小泉家:典型的なこの地域の農家の建て方、永泉寺、鑓水商人菩提寺、芭蕉像、慈眠寺、諏訪神社、彫刻見事、鑓水商人寄進、石灯籠、明治41年八王子~横浜鉄道開通により旧街道衰退。
・箱根旧街道:箱根山:関東と東海を分割する所、天下の険、沼津~三島~箱根峠・関所~湯本~小田原、箱根湯本温泉、早雲寺:北条氏菩提寺、一里塚:江戸から22番目、箱根旧街道入る、石畳、大澤坂、畑宿、駕籠かき中継地、寄木細工、茗荷屋跡:庭園、西海子坂(さいかちざか)、甘酒茶屋、赤穂浪士・神崎与五郎侘び証文、白水坂:進軍する豊臣方に北条側が攻撃し豊臣方が城を見ずに撤退したため、石畳残る、泥にすねまで漬かる坂を改良、斜めの排水路、箱根馬子唄の碑、二子山、権現坂(下り)、芦ノ湖・富士山、「東海道五十三次・箱根」広重画、箱根古道:鎌倉古道・湯坂道、浅間山・鷹巣山・精進ヶ池から芦ノ湖に下りる、杉並木、箱根関所跡、250年間、入り鉄砲出女改め、芦川の石仏群、向坂、兜石:秀吉が兜を置いて休んだという、
・松本・千国街道チクニ:上杉謙信が武田信玄に塩を送った話で有名な塩の道として知られる。ボッカ道であった。
~塩の道~、ボッカ:険しい山道の運搬人、松本~大町~白馬~千国~大網峠~大野~糸魚川120km、糸魚川市姫川上流に縄文期遡る、小滝川ヒスイ峡:ヒスイ原石:糸魚川・奴奈川姫伝説・古墳発掘品装身具、姫川氾濫考慮し東側高い所通る、大賽の神、道は急、角間の道標「右松本街道 大網 左中谷道 横川」、ウトウの道:ウトウはわらじ等で踏みつけU字型に窪んだ所、角間池、ブナ・ナラ・トチの原生林、大網峠h850m越後信州国境、ボッカの立ち休み:杖を背負子に当てる、牛方、牛の水飲み場、大日如来、横川の吊橋、小谷村大網、塩蔵:釘不使用・腐食防止、粗塩:水分多くニガリ、千国宿チクニ、千国番所、親坂:岩多い、牛つなぎ石:岩に穴、弘法清水:水飲み場が二段で上人・下牛用、小谷村沓掛、牛方宿:土間2階牛方・1階牛、白馬村・落倉の道標「右ゑちご 左やまみち」、信州越後物資運搬、参勤交代なし、
・臼ヶ峰往来:越中の氷見から臼ヶ峰を経て能登の志雄町を結ぶ。大伴家持が通行したことでも有名。氷見市日名田、臼ヶ峰往来、御上使往来、氷見~日名田~臼ヶ峰~下石~羽昨~金沢、岩盤露出しているところもある、杉や雑木の林の中、床鍋:小さな山間集落、かつては和紙作りだったが衰退し竹細工、竹林多し、臼ヶ峰h266m、奈良時代大伴家持(国司として29歳から5年間越中で暮らした)や御上使が通った。能登巡行で通過、万葉期には道があった、志雄路という、1250年前、「志雄路から直越え来れば羽昨の海朝なぎしたり船舵もがな」家持、富山県氷見市と石川県志雄町境、富山湾眺め、5年任期220首作る、親鸞聖人像、1207年流罪で通過、太子堂:親鸞が太子見たという伝説、中世合戦場1183年、江戸期流通道、
・白山禅定道:日本有数の山岳信仰の一つ、白山への登山道である。御前峰・大汝峰・剣ヶ峰の3つ合わせた山名、
石川県尾口~尾添~(加賀禅定道)~白山・室堂~石撒白~(美濃禅定道)~岐阜県白鳥・馬場・白山中居神社、 ↖~(越前禅定道)~福井県勝山
白鳥・馬場・白山中居神社、石撒白の大杉イトシロ、泰澄タイチョウ:白山に「上れとお告げ、千日白山で修行、その後一般修行僧も修験さらに一般人も、修験の山から禅定の山、禅定道:足跡をたどる道、石撒白・ちょうしが峰・さんが峰を越えると別山見える、別山平→別山山頂:別山社、おしゃり山、油坂、高山植物、畜生谷:この水飲むと苦しむ伝説、南竜ヶ馬場バンバ、御前坂、ハイマツの中、室堂、トンビ岩、室堂:3つの禅定道合流点、御前峰h2702m、十一面観音祀る、御来光、翠ヶ池: 泰澄が池のほとりで見た夢で神と仏を結びつける神仏混淆、大汝峰:阿弥陀如来祀る、千蛇ヶ池:千匹蛇が雪に閉ざされた伝説、ハイマツの中の道、御手水鉢の池オチョウズバチ:水量一定、加賀禅定道は石川県に伸びる、高山植物花々、
○・VHS『歴史の道 第5巻 中部』59分
・棒道:甲斐の武田信玄が北信濃攻略のため八ヶ岳山麓に造った上中下3本の道筋をもち棒のようにまっすぐ伸びた最短距離の軍用道路だが、昇仙峡の御岳詣でや富士山詣でに使われた。甲府~韮崎~穴山~(下の棒道)~諏訪へ
↘若神子~~~(中の棒道)~~~湯川~大門峠~松本・長野へ
↘城南~小荒間~(上の棒道)~↗、 一般的には上の棒道が有名、
山梨県須玉町:若神子ワカミコ城跡狼煙台、上棒道起点、小荒間古戦場跡:村上氏との戦い、御座石、遠見石、馬蹄石、日本名水百選・八ヶ岳湧水群の一つ:三分一湧水:三角形の石柱を使う、小荒間口留番所跡、石道標「右すわ左むら」、直線に伸びる、石仏:坂東一番十一面観音立像:嘉永元年、道幅狭い、尾根道けもの道を発見されにくいように活用、川中島攻める前年に造る、武田氏が信州獲得後物資輸送路、石仏多し、坂東三番:千手観音立像、修行僧、御岳参り、生活道、道幅広い所あり防火帯16mとして、坂東七番:聖観世音文字塔、小淵沢、坂東十六番千手観音坐像、その後中山道甲州街道発達で使われなくなる、
・中山道・信濃路:中山道・信州芦田宿から和田峠を越え木曽路に至る部分を紹介する。江戸へ~芦田(江戸から27番目宿)~笠取峠~和田~下諏訪~塩尻~奈良井~鳥居峠~野尻~三留野~妻籠~馬籠峠~馬籠、笠取峠:松並木700本松、馬頭観音、和田峠:唐松・モミ・険しいというが谷沿い緩やかな道、春から秋は快適・冬雪で困難、和田施行所:焚き火・おかゆ一杯・馬にはかいば一杯恵む、木曽の木は尾張藩管轄・生一本首一つ、地元木曾の収入源ならず、近畿特に近江から人足雇い、収入源少ないので木曽の人は何でも食べた、木曽路十一宿、奈良井、杉並木、二百体地蔵、奈良井宿、2km保存、越後屋:旅籠、中村屋:櫛問屋、お六櫛:髪を梳くと頭痛治るといわれた、黄泉画:木曽街道六十九次、鳥居峠h1197m、鎮神社、石畳200m、峰の茶屋:馬方茶屋・句碑、円山公園、石碑多し、薮原宿、与川道:バイパス・野尻~上野原・三留野、妻籠宿:もっとも小さい宿・街並み保存、妻籠宿本陣:南木曾町博物館、中山道・飯田道分岐点、馬籠峠:木曽御木の原生林、「夜明け前」藤村、男滝・女滝、馬籠峠h801m、馬籠宿:藤村出生地、
・野麦道:信州松本と飛騨高山をつなぎ、乗鞍岳南の野麦峠を越える道、近代製糸工場に働きに行く飛騨の娘たちが通ったことで有名。奈川村川浦、石室:復元:文政8年、ボッカ・牛方避難所、松本~川浦~野麦峠~野麦~高山へ90km・野麦街道ともいう、岡船:牛:信州で活躍・飛騨には行かない、信州雪深いため牛がだめでボッカ活躍、最大50貫190kg、たいてい150kg、飛騨ブリ:富山のブリを飛騨高山から信州へ、h1500m越えるとモミ・ツガ等針葉樹林帯を折り返す、熊笹=野麦=ダンゴにして飢えしのぐ、飛騨郡代の江戸往来道で信仰の道、野麦峠、展望・乗鞍岳、飛騨の貧しい少女たち・明治期・信州の製糸工場へ、政井みなの碑:百円工女、当時日本の生糸生産量世界一、お助け小屋:復元、冬の野麦峠越え命がけ、雪道を歩くのは大変・滑落すると止まらない、地蔵堂、野麦:飛騨高根村
・本坂通:~姫街道~ともいわれ江戸幕府が東海道の脇街道として整備した。浜松で東海道から離れ浜名湖北を通過し御油宿で東海道に合流した。浜松~気賀~引佐峠~三ケ日~本坂峠~当古~御油、脇街道、浜名湖北岸、姫街道、気賀一里塚:江戸から69里、引佐峠h200m、時々石畳敷いて安全対策、コスモス、平石御休憩所、姫岩:湯茶接待用、浜名湖展望よし、「姫君様行列之図」、今切関:今切渡船、バイパス、姫街道由来:①姫通った・②ひねた・ひなびた、象鳴き坂:吉宗献上象通過、石投げ岩:岩に石投げすると峠越えが無事という、一里塚:江戸から72里、本坂峠へ、大師堂→山道・石畳、橘逸勢:伊豆流罪途中当地で没す、鏡岩:高さ3m・幅10m・昔は光って姿が映ったという、本坂峠h328m、林間下り坂、嵩山宿スセ:本陣・脇本陣、嵩山の蛇穴遺跡:縄文前期住居跡、豊川市当古豊川・渡船、
・下田街道:~天城越え~、東海道三島宿から天城峠を越え下田に至る道。幕末下田が開港されて重要となる。天城越えともいい、伊豆の踊り子等で有名。~天城越え~、天城峠、「伊豆の踊り子」、旧天城トンネル、三島~韮山~修善寺~湯ヶ島~天城峠(二本杉峠)~小鍋~下田、天城湯ヶ島町大川端・紀州尾鷲の炭焼き市兵衛の墓:石道標「右ハやまみち左ハ下田道」、二本杉峠40分、炭焼き技法を教えた、産業の道でもある、ワサビ田、天城峠頂上:広場・二本大杉、この道1819年私財を投じて完成、幕末外国人も通行、1853年黒船翌年下田函館開港、吉田松陰下田で密航企て捕縛遠丸籠で通過、宋太郎林道、タウンゼント・ハリス下田から江戸へ、釜滝カマダル、川横:川合野、慈眼院、小鍋峠への山道、小鍋峠:河津町と下田市境、「伊豆の踊り子」川端康成の一節朗読、
○・VHS『歴史の道 第6巻 近畿』62分
・東海道:~鈴鹿峠越え~、伊勢と近江を分ける鈴鹿山脈の南に関町セキチョウ、古くは鈴鹿の関があった、伊勢神宮一の鳥居:東の追分、東海道と伊勢別街道分岐点、江戸から106里2丁、江戸時代宿場町街並み:江戸後期、中町:本陣・脇本陣・大旅籠、脇本陣:千鳥破風、関の地蔵院:建立・行基伝、中興・一休伝、門前町、つし二階建て:屋根裏を物置にし軒低い、西の追分:刑場・供養塔は石道標「左伊賀大和道」、関:47番目宿~坂下~鈴鹿峠~土山、転び石、筆捨山:安藤広重「東海道五十三次」にも描かれる、黄色い奇岩、狩野元信が山を描きえず筆を捨てた伝説、坂下宿、法安寺、庫裏は本陣移築、本陣3、脇本陣1、旅籠48、峠まで1里半、岩屋観音:江戸初期石仏、清滝、片山神社、ここから8丁27曲がり峠越え、燈籠坂、夜の旅人用に常夜灯、石畳、難儀、峠を境に天候も違うほどきつい、東の箱根に西の鈴鹿、鈴鹿山の鏡岩:三重県指定天然記念物、山賊は鏡岩に隠れ岩に映った旅人を襲ったという、東海自然歩道、峠は国境で近江側は緩やか下り坂、万人講常夜灯、土山宿、本陣跡、連子格子、二階の塗り込め壁、東海道反野畷タンノナワテ、松並木、
・熊野参詣道:伊勢路、紀伊路、和歌山-(紀伊路)-田辺-滝尻-(中辺路)-本宮-那智勝浦-新宮-(伊勢路)-熊野-八鬼山-尾鷲-馬越峠-海山、馬越峠道マゴセ、西国三十三所巡り第1番札所青岸渡寺巡礼道、八鬼山道ヤキヤマ、難所、石仏、滝尻王子、数多くの王子あり、王子ごと禊をして熊野に詣でる、熊野三山知られたは平安期、上皇たちが熊野詣をするようになってから、果無山脈ハテナシ(大和と紀伊を分ける)熊野山塊、花山上皇が木の枝を折って箸に使ったという箸折峠、牛馬童子像:19歳で譲位させられた花山上皇の姿伝、箸折峠下の近露集落の日置川ヒキ、かつては旅籠30軒一日800人宿泊したことあるという、近露王子、継桜王子・野中の清水、伏拝王子・小さな祠だけ、ここからかつて伏して熊野大社を拝めた・麓の窪地に明治22年まで社があったが洪水で移転、、熊野本宮大社、やた烏、山伏修験場、熊野にいます神社、熊野の本山、熊野川、上皇たちは船で熊野川を下り新宮目指した、新宮・熊野速玉大社、補陀洛渡海、夫婦杉:那智大社への入口、大門坂、那智の滝:落差133m日本一、滝をご神体にした原始信仰から始まる、熊野那智大社、社殿熊野作り権現作り構造、北に大雲取越・小雲取越の2つの道、上皇たちは京に帰るため通った、
・宮津街道:普甲峠越え、大江山越え、丹後の天橋立、宮津市、古い港町、京極氏、宮津城跡、京口橋:京に向かう宮津街道起点、石道標:観音霊場案内「左なりあい観音」、京極氏が参勤交代用に整備した道、ちりめん街道、糸の道・絹の道、石畳が道の半分、峠の茶屋跡、峠の石塔「ちとせ山」: 普甲峠はフコウに通じるのでちとせ山と呼ばせたことがある、天台密教の普甲寺跡、今は寺屋敷集落、普賢堂、最盛期一山百か寺、織田信長により焦土、峠の南側は緩やかで中茶屋集落ナカノチャヤ、昭和30年代まで小中学生登校路、峠越え最短路、二瀬川渓谷、鬼ヶ茶屋の石畳(復元)、遊歩道、大江山鬼退治伝説関連、鬼の足跡、大江山、頼光の腰掛岩、石仏「南無阿弥陀仏 文政六年六月」:道普請犠牲者出た、毛原の道標「右ふげん左なりあい」普甲寺道と宮津なりあい観音道分岐点、南に丹波の山々で京、
・竹内街道:二上山ニジョウサン、大阪と奈良境、竹内峠タケノウチ、最古の国道、613年「難波より京に至る大道を置く」日本書紀、難波-堺-太子-竹内峠-当麻-飛鳥、大阪府太子町「近つ飛鳥」、推古天皇陵、叡福寺「上の太子」推古天皇摂政聖徳太子祀る、聖徳太子廟、太子町・春日、白い塗り壁・板壁、大和川水運に使われた船の板、太子町・大道、餅屋橋の道標「左幸徳天皇御陵」名所旧跡案内、伊勢灯篭、大和棟、西国三十三所巡礼道・5番藤井寺・叡福寺・當麻寺・6番壷坂寺に向かう道、さらにお伊勢参り・長谷寺詣で、道端の地蔵堂「右大阪さかい」、役行者像、岩屋越との分岐点、地蔵「右つぼさか 左岩屋當麻の口」、岩屋越道、当麻寺タイマジ:聖徳太子弟創建、中将姫伝説、河内名所図会、遣隋使派遣で隋の使者を迎える外交路としての必要性、河内細見図、国道166号線、峠の手前草の道少し残る、十一面観音、宝篋印塔、「大峯山三十三度」、竹内峠:国境石「従是東 奈良縣管轄」
・山陰道:~蒲生峠越え~、鳥取県東部と兵庫県北部県境の山々、蒲生峠、鳥取-岩美-岩井温泉-塩谷-蒲生峠(蒲生トンネル)-温泉町・湯村温泉-春来峠-京都、山陰道は律令時代に定められた官道、岩井温泉・蒲生峠まで8km、塩谷、地蔵堂、因幡商人塩運送・但馬商人受け継ぐので塩谷、明治初年まで蒲生川の一番奥の沢が入口、羽柴秀吉も鳥取城攻撃に使った道、あまりに険しいので鳥取藩は参勤交代道からはずす、今は一番奥で崖になり不通、明治初期にその上に大八車用の国道できる、文化庁歴史の道百選指定、上り口から3km頂上見える、蒲生峠h356mには延命地蔵、国道9号線真下トンネル、旧国道通過、鳥取・兵庫県境、温泉町・千石チタニ宿場町、こうじ屋旅館「昭和八年四月宿泊人名簿」出稼ぎ商人・職人・馬喰、生業の道、千原の名号石「南無阿弥陀仏」、伊勢神宮常夜灯「大神宮 秋葉山 愛宕山 天保十四」、温泉町湯村温泉、慈覚大師:平安期発見伝、夢千代日記、春来川、春来峠・今は下をトンネル、榜示石「従是西豊岡藩」、因幡から蒲生峠を越えて但馬に入った山陰道は春来峠を越えて幾重にも連なる山々の先の京を目指す。
○・VHS『歴史の道 第7巻 近畿・中国』61分
・柳生街道:奈良市北部を東の柳生まで結ぶ道、剣豪の道といわれるが信仰や奈良市内の大寺院とその荘園だった柳生周辺を結ぶ道。興福寺から見た奈良北部、春日山と高円山の窪みを越える道、奈良春日山南麓~石切峠~大柳生~柳生:5里20km、能登川、滝坂道、葬送の道、修行の道、大寺院の荘園への道(物資)、轍の跡:石畳、寝仏:崖上の大日如来の摩崖仏が落ちたもの、夕日観音:摩崖仏:弥勒菩薩、朝日観音: 摩崖仏:弥勒・地蔵、首切り地蔵:地獄谷と柳生への分岐点、石切峠:奈良大仏春日石切り出し、春日山石窟仏: 摩崖仏:平安後期:春日石切り出し、地獄谷石窟仏:線を刻んで彩色:薬師・る遮那仏・十一面観音:奈良期昨、峠の茶屋:武芸者の代金代わりの武具、誓多林、忍辱山円成寺:文化財・春日堂・白山堂:日本最古の春日造り、庭園:平安期の姿残す:国の名勝、大柳生への下り、大柳生集落内を街道通過、阪原峠:石畳残る、柳生:家老屋敷跡:小山田しゅれい:資料館、柳生陣屋跡、1万石、正木道場:復元:柳生新陰流、芳徳禅寺:沢庵和尚・柳生宗矩・柳生家菩提寺、
・大山道:中国地方屈指の名山で信仰の山、大山ダイセン。その麓の大山寺を目指す道。大山h1729m、伯耆富士、関金~(川床道)~大山寺・大山~(横手道)~釘貫小川~岡山へ、
大山道:大山寺目指す・大山参り:農業神、「六十余州名所図会・大山遠望」、瀬戸内からの横手道大山西側を南北に通過、ブナ林内古道、横手地蔵:18番1丁ごと置かれた、南からは荒々しい姿で西からは優しい姿、一の沢、大山は死霊のおもむく山:備中の人々は道に石仏祀る、川床道:風情残る・7km古道残る、地蔵峠:地蔵「萬延元年」、道は川沿い緩やか、大山滝、大休峠:急坂道1km、h1000m、川床まで4km:石畳、(岡山県:牛つなぎ石:穴あき石)、大山での牛馬市のため牛馬連れて行った、大山寺:宝牛像、
・智頭往来:~志戸坂峠越え~、平安期から因幡と上方を結ぶ道、参勤交代も使った。因幡→上方へ、平安期都からの国司往来・江戸期鳥取藩参勤交代、鳥取~市瀬~智頭チズ~志戸坂峠~京都へ、鳥取から智頭で一泊、鳥取から志戸坂峠越えで1日半40km、平時範「時範記」:旅日記、参勤交代用道178回、鳥取城、「鳥取城攻めの陣営図」:秀吉は堅固な鳥取城落とすため街道通過、千代川沿いに智頭往来あり、篠ヶホキ:山間の険しい所難所、六地蔵「寛政十二年」、(京・上方・馬方)(街道・往来)、智頭宿:石道標・備前街道分岐点、魚の棚、志戸坂峠:2km・積雪通行不可・「けふいなばそふの瀧山こえるなり都にかけよ夢のうきはし」、明治20年大改修・馬車道・改修碑、
・広瀬清水街道:山陰の鎌倉といわれる島根県広瀬と山陰道をつなぐ道、尼子一族ゆかりの地や安来の清水寺への参詣道。島根県広瀬町・山陰の鎌倉・富田トダ・月山ガッサン:尼子氏居城、尼子氏利用道、広瀬~鍵尾峠~清水峠~門生~(山陰道)~安来~松江
↘京へ(山陰道)
「出雲国風土記」、月山:富田城跡1397年尼子氏入城11カ国領有・1566年毛利氏により陥落、意多岐神社オダキ:古代出雲四大社の一つ・能義神社…中心地、古道は草生し通う人なし、尼子時代の軍用道、鍵尾峠:石塔、能登?集落:竹やぶ、出雲巡礼21番札所11番清水寺巡礼道:信仰道、石道標「右きよみず左ひろせ」、弁慶坂:弁慶が釣鐘を担ぎ上ったという伝説、仁王門・清水寺キヨミズサン・尼子一族菩提寺・本堂:観音33図・尼子拾勇士絵:山中鹿之助等・弁慶絵図・三重塔1859年建立山陰唯一、追分:六地蔵・山陰道と合流、
・山陽道:~大山峠越え・玖波~、京都と九州大宰府を結ぶ最も重要な官道で、宮島厳島神社周辺に残存している箇所を紹介する。大化の改新以降、七つの道を官道:大中小区分:中国行程路:唯一の大路:都と大宰府を結ぶ道:大宰府は遠の朝廷ミカド:政治文化外交上重要な道、「中国行程図」、京~東広島市西条町~大山峠~広島~~~~大野町~玖波~大竹~大宰府
宮島厳島神社
安芸の国中心地:西条町:広島大学中心:四日市次郎丸という宿場町:西条駅北側:国分寺跡:仁王門・七重塔礎石・レンガ造り・煙突・白壁・造り酒屋・本陣跡:部屋数29、海岸に出た山陽道は展望よし、大野町:厳島神社展望よい、室町期今川貞世通行:幕府勢力権力拡大のため、宮島厳島神社:平安末期平清盛造営・塔の岡:五重塔・戦国期毛利が陶晴賢を破る1555年、毛利:要害山山頂のおとりの城、鼓ヶ浦、大野:四十八坂:49よりまし、つづらおり長洲戦争激戦地、残念神社:長洲戦争戦没者祀る、
○・VHS『歴史の道 第8巻 中国・四国』60分
・萩往還:江戸期毛利氏が治めた長洲藩府・萩と瀬戸内の三田尻を結び参勤交代や多くのし志士達が通った道。
萩城跡、「中国行程記」江戸中期宝暦・萩から京都伏見まで・第1巻は萩から三田尻まで、萩~明木アキラギ~一ノ坂~山口~防府(三田尻)、松下村塾・吉田松陰像・維新の志士輩出、涙松の遺址「帰らじと思ひさだめし旅なればひとしほぬるる涙松かな」松陰、萩から一里のオオヤ竹やぶ・首切り地蔵:刑場跡・石碑「栗山孝庵女刑屍体臓分之跡」日本で初めて女性遺体解剖、萩から五里・一升谷:石畳:一升の豆を食べつくすほど長い坂という、国境の碑「北長門國阿武郡 南周防國吉敷郡」、一ノ坂h差260m、曲がり角40以上、三田尻御船倉跡:参勤交代や旅人によっては船移動・毛利水軍、
・赤間関街道:~中道筋~、長洲藩府・萩と赤間関:下関を結ぶ3つの街道、その中でも美東・吉田を経て赤間関に至る中道筋は公用路として重視された。
萩市、高杉晋作の生家:彼がよく通った道、
萩~明木~一ノ坂~(萩往還)~山口~防府(三田尻)
↘美東~絵堂~秋吉~(中道筋)~吉田~赤間関(下関):19里
↘~(北浦筋)~ ↗
↘~(北浦道筋)~ ↗
下ノ峠タオ、美東町、絵堂戦跡記念碑、長州藩政府軍本陣跡、戸に弾痕、大田・絵堂戦に使われた鉄砲、金麗社、「四境の役」、燈籠:小倉城のもの略奪、カルスト、大久保台、石畳、秋芳洞:滝穴32間、吉田宰判勘場跡:自治体の区役所、しみずやま:高杉晋作の墓「東行の墓」29歳、「六十余州名所図会・下の関」、壇ノ浦、赤間神宮、長洲砲、
・讃岐街道:~大坂峠越え~、讃岐高松から讃岐山脈越えで阿波徳島に至る道。鳴門市四国遍路一番札所霊山寺に向かう信仰の道で義経が屋島に駆け抜けた道でもある。
讃岐山脈、讃岐街道:琴平へ~高松・屋島~引田~大坂峠~板野~徳島~勝浦~土佐へ
伊予へ↙ ↘鳴門
引田町ヒケタ、落ち着いたたたずまい、引田廻船、寿可多美の地蔵「右大坂道 左なる戸 文化十四年」、「六十余州名所図会・象頭山遠望」、信仰の地、阿波鳴門一番札所霊山寺、二番札所極楽寺、三番札所金泉寺、四国八十八箇所巡りの一番に行くため大坂峠は最初の難所、大坂峠への丁石、借耕牛、5丁目過ぎると急坂、800年前源義経一行通過:屋島の合戦、豆茶屋跡石垣、豆茶:半つき米と豆を一晩つけてから蒸して白湯をかけたもの、徳島城跡、蜂須賀氏、番所・村瀬家・大坂御番所跡:明治初期までの230年間・武具、遍路の通行手形「遍路」、近代大正昭和初期にトンネル・鉄道開通により大坂峠いなくなる、
・土佐北街道:~笹ヶ峰越え~、土佐高知を峻険な四国山地越えで瀬戸内と結んだ道。参勤交代120年ほど2000人ほど・信仰・物資輸送路として利用された道。土佐藩二十四万石山之内一豊:高知城、四国山地、高知~大豊~笹ヶ峰h1015m~新宮~川之江、はじめ参勤交代路は海路で20日ほどだが、潮待ちで50日、江戸中期に期日厳守となり陸路開発。碁石茶:発酵茶・筵に干した様子が碁石に似ている、笹ヶ峰、国境標:土佐伊予、しばらく尾根通し、杖立て地蔵・弘法大師像・安政九年1858・杖を立てて感謝、腹包丁h差400mで距離1500m続く急坂:腰にさした刀が地面につかえるので腹に抱えた、オハツキイチョウ樹齢300年・安産祈る・柱瘤、平安期:熊野神社信仰の道・参勤交代以前から、
・檮原街道ユスハラ:(檮トウ)、~韮ヶ峠越え~、高知城下から伊予の境・檮原を経て大洲城下を結ぶ道。坂本龍馬等勤皇志士脱藩して通ったことから(勤皇・脱藩)(街道・道)ともいう。
高知~須崎~檮原~韮ヶ峠~大野ヶ原~泉ヶ峠~宿間~大洲・長浜、勤皇街道、坂本龍馬、高知城、桂浜・坂本龍馬像、1862年脱藩、澤村惣之丞:海援隊前身亀山社中、檮原:千枚田・那須俊平信吾・掛橋和泉邸:神官・勤皇志士かくまう、宮野々番所跡、韮ヶ峠:舗装道路・土佐伊予境、大野ヶ原・激戦地、男水:龍馬が水を飲んだという、榎ヶ峠、御幸の橋:屋根付き橋江戸中期休憩用に付けた、泉ヶ峠:かつて旅館や運送業でにぎわう・石垣跡、宿間、肱川、船で長浜へ下れる、
○・VHS『歴史の道 第9巻 九州』62分
・長崎街道Ⅰ:~冷水峠越え~、鎖国の中唯一開かれていた天領・長崎と筑前小倉を結ぶ道。著名人が往来し海外文明を伝えた道。小倉~黒崎~木屋瀬~飯塚~内野~冷水峠h283m~山家ヤマエ~原田~長崎へ、筑前六宿チクゼンムシュク、エンゲルベルト・ケンペル1691年江戸旅行・「江戸参府道中の画」・オランダ商館長(カピタン)の駕籠、山家宿、「筑前六宿・山家宿」、追分石「右肥前大宰府長嵜原田 左肥後久留米柳川松崎」、西構口跡、恵比寿石神:江戸初期寛永年間建立:1611年山家宿開設理由記入され貴重、郡屋土蔵:参勤交代用品置いた、郡屋は近代取り壊し、冷水峠:九州の箱根、黒田長政整備・博多を通らせない、首無し地蔵堂:旅人の身代わり伝説、石畳、「南蛮屏風」:象通過、山間の低地伝いに内野宿へ、「筑前名所図会・往来の図」、「寂寥の山駅にして海遠く山深し」松陰、内野宿三叉路石道標「大宰府天満宮米山越道」:米山官道、老松神社、正円寺、長崎屋:脇本陣、小倉屋:脇本陣・荷物輸送中継の問屋場・両替商、
・肥前・筑前街道:~背振坂越えセフリ~、全長6里24km、肥前・佐賀県と筑前・福岡県を結ぶ道。平安末期平家の財源佐賀県神崎の年貢米を博多港へ運ぶ道。脊振坂越えは博多への最短ルート。吉野ヶ里遺跡、神埼宿:長崎街道合流、櫛田宮・肥前鳥居:複数の石組み合わせ、
佐賀~神埼~(坂本峠)~脊振坂~亀ノ尾峠~山田(那珂川)~博多、
脊振山
脊振山地、脊振山頂・脊振神社:修験一大聖地・脊振千坊・修学院:脊振山下宮:鍋島家祈願所、一町宮:地蔵「右ちくぜん道 左山」、五町石、平安末期平家により信仰道から年貢米を運ぶ流通道へ発展、霊仙寺跡・石道標「右とうりみち 左坊中」、左へ行くと茶の木:栄西禅師が中国から持ち帰り植えた茶の木という、茶園上りきると乙護法堂、水上坊跡、千坊ほとんど消失、霊水石、自生白サザンカ名所、坂本峠の馬頭観世音、国境石:江戸期元禄1600年代末、那珂川中州石垣:國領示し石に触ること禁止旨刻む、南畑ダム、亀ノ尾峠:石畳残る、石垣:山城の家来屋敷跡、山田(那珂川町):農耕で栄える、裂田溝:用水路、那珂川、川港、
・太閤道:肥前・佐賀県唐津から鎮西町名護屋までの16kmの道。秀吉朝鮮出兵では名護屋城建築資材運搬や軍勢移動用に整備した道。
唐津城「舞鶴城」:桃山様式模した昭和の復元、松浦潟、虹の松原:5km長さ・防風防砂林・国天然記念物、かつて遣唐使派遣港で唐の津、佐賀~(唐津街道)~佐志ノ辻~馬部~鎮西・名護屋城跡、1591年朝鮮出兵、近松寺キンショウジ:名護屋城一の門、浄泰寺前道通過、林の中、観音:道標、佐志ノ辻:太閤道一里塚、そば畑内一里塚石、石垣残存、西進むと野元神社、農道として北進む、名護屋城跡:大阪城に次ぐ規模で桃山様式五層天守閣・30万将兵、陣屋跡大小260箇所以上、草庵茶室の遺構、草庵茶室想像図:四畳半、「太閤が睨みし海の霞かな」青木月斗、
・長崎街道Ⅱ:~日見峠・井桶ノ尾峠越えイビノオ~、文明の道、異国情緒溢れる長崎から大村間に古道の面影多く残る。海外文明を伝播した道でシーボルトも通った。長崎市、孔子廟、オランダ坂、メガネ橋、出島(復元模型)、平戸オランダ商館を長崎出島移転、長崎~日見峠~矢上ヤガミ~井桶ノ尾峠~諫早~破籠井ワリゴイ~鈴田峠~大村~小倉へ、蛍茶屋、一瀬橋、「長崎近郊の貴族的な茶屋」F・ベアト撮影:幕末の蛍茶屋と一瀬橋写る、近くに鳴滝塾跡:医院・塾(現シーボルト記念館):医師・博物学者、アジサイをお滝さんからオタクサと命名、シーボルト旅日記、日見峠:由来:火見:戦でかがり火が見えた、日見峠の切通し、下りは通称七曲、芒塚:向井去来の句碑、長崎街道矢上宿跡、教宗寺・庭園、井桶ノ尾峠手前に天領と肥前佐賀藩領境石、井桶ノ尾峠:h100mほどの丘の連なり、長崎街道御籠立場、眼下に大村湾、諫早、破籠井:旅人がここで弁当箱を開けて食べた所なので、鈴田峠:深い山の中通過、大村の町眼下に見える、
・豊後街道:熊本市、熊本城、肥後・熊本城下から阿蘇外輪山北部通過し豊後・大分県鶴崎港に至る道。31里、加藤清正によって整備が始められた。左右を堤にし一段掘り下げて造られた清正公道セイショウコウドウが残る。熊本~大津オオヅ~二重峠~内牧~一の宮~滝室坂~大利~山鹿~鶴崎へ、 阿蘇山
整然と石垣、武蔵塚:宮本武蔵:細川氏庇護、大津街道杉並木:屋久杉、大津宿:熊本から五里、清正公道、路面土粘って滑る、二里半、二重峠、健磐龍命伝説:カルデラに水溜まる削ったが水抜けず見ると二重だった、大津から望む外輪山、上りきると石畳の下り坂、天草展望、阿蘇五岳展望、車帰坂クルマガエシ、牛王水ゴオウスイ・石畳斜め排水工夫、阿蘇谷、1km先・的石御茶屋跡、内牧ウチノマキ、一の宮、阿蘇神社、坂梨・大坂に坂無し坂梨に坂有り、滝室坂、乙護法堂オトゴホウ: 乙護法:子供姿の神:仏法守護、この先草地で一旦道消失、坂の上、大利の石畳、山鹿の石畳、坂上で国境、鶴崎から船で大坂へ、
○・VHS『歴史の道 第10巻 九州・沖縄』56分
・日田・中津街道:江戸期西国郡代が置かれた天領日田と周防灘に面する中津藩十万石中津城下を結ぶ道。周防国・山口県から呼び寄せた石工が敷いた石畳が残る。日田~市ノ瀬~伏木峠~中津、日田市:天領九州政治経済金融中心地、永山布政所(郡代屋敷):西国郡代、豆田町・古い商家残る、掛屋:両替商:日田金、咸宜園跡カンギ:すべてよろしいの意で誰でも入門できた:広瀬淡窓: 掛屋:塾生:高野長英・大村益次郎・「休道他郷多辛苦 同胞有友自相親 柴扉暁出霜如雪 君汲川流我拾薪」、中津街道北東へ・石坂石畳道・1.3km・嘉永三年・信仰道・周防から石工呼ぶ・坂に石敷くのは高度技術、道の中央に滑りにくい石で両端は違う、石阪修治碑:石坂完成記念・碑文:淡窓、茶屋跡:石垣、物資輸送路、
・日田・竹田街道:滝廉太郎「荒城の月」の豊後・大分県竹田の岡城の城下町から久住高原南部を通過し、天領日田に至る道。九十九折の石畳を通って大量に物資が運搬された。岡城跡:鎌倉期・国史跡、久住高原クジュウ、日田往還、大分~竹田~曽田ノ台~出口イデグチ~台下~日田、 久住山
湯見岳ユノミh740mの麓で肥後方面の道と日田往還出合う、石道標「右つ 左小国 」その横にかつての旧道痕跡わずかに残る、曽田ノ池、曽田ノ台、下る石畳九十九折700~800m、物資輸送路、「五馬駄賃取り唄」、浄念寺(北平)、中村(出口駅):石垣、日田屋旅館「店」:茅葺、出口庄屋屋敷跡、文化九年:伊能忠敬宿泊記念碑、伊能忠敬、玉来神社・五馬媛イツマヒメ:土蜘蛛の意・老杉、薹(台)神社:江戸中期・前の坂道は舗装石畳、
・飫肥街道オビ:(飫ヨ・オ) 飫肥藩の日南市飫肥オビから北の宮崎や、南は薩摩や大隈へ通じた道。花立山近くに旧街道が残る。日南市飫肥オビ、飫肥城:伊東氏、鹿児島へ~都城~日南・飫肥~花立山~山仮屋~清武~宮崎、殿様街道:参勤交代用、「元禄十四年飫肥領国絵図」、伊東家邸宅:江戸期270年間伊東氏治める、本町通り、酒谷川、唐人、物資流通盛ん、振徳堂:藩の塾・儒学幕末には蘭学医学も、旧道は花立山を越えた辺りから山仮屋関所跡まで1.6km残存、桜名所、石仏、町指定史跡:山仮屋関所跡h400m、「山仮屋関所跡見取図」、汗道:険しい飫肥街道・佐々助三郎スケサン通過、安井息軒旧宅(復元・清武町)、
・東目筋・大口筋:薩摩藩城下町鹿児島を起点に宮崎に向かう道を東目筋、肥後・熊本に向かう道を大口筋という。勢力のある薩摩藩の道なので見事な整備がされている。錦江湾・桜島・鹿児島市、鹿児島~白銀坂~加治木~竜門司坂~(大口筋)~大口~熊本へ
桜島 ↘(東目筋)~宮崎へ
↘宮崎へ
鶴丸城:館作り・櫓や天守閣なし:島津氏、白銀坂:錦江湾絶壁に道できず山坂道となる:石畳道幅広し・急勾配では段差設ける、布引(白銀)の滝:落差20m、展望よい、1km石畳国道合流、姶良町アイラ(姶オウ)、加治木町:隈姫神社クマヒメ:悲劇の姫祀る、田の神、龍門滝:落差46m、竜門司坂タツモンジ(ダシモン坂):酒樽等だしもんを運ぶ、長さ464m元文6年石畳敷く、加治木:焼き物・龍門司焼(黒もん)、明治5年国道10号線・明治34年鉄道近代開通旧道通らない、
・国頭・中頭方西海道クニガミ・ナカガミホウサイカイドウ:首里から座喜味城へ向かう中頭方西海道、さらに北の今帰仁城へ向かう国頭方西海道、首里城を出た道は琉球王朝時代の面影残す石畳道となって北へ延びる。
琉球王朝時代の石畳道、守礼門、首里城、各城グスクからの道、歓會門、金城の石畳道カナジョウ、宿道シュクミチ:公用、那覇・首里~浦添~座喜味城跡~仲泊~恩納オンナ~名護~今帰仁ナキジン、中頭方西海道:安波茶橋アハチャ:500年前建造、浦添城跡:切石積石垣残存・薩摩藩征服により、史跡当山の石畳道:17世紀半ば作られる:馬転ばし、国頭方西海道:読谷山の道、宿道は間切マギリ:いくつかの集落を集めたもの:に行く道、多幸山のフェーレー岩:フェーレー=山賊、サトウキビ畑、海展望、本部半島: 今帰仁城、山田谷川矼: 矼コウ=石橋・かつて6枚の石橋・今4枚で復元、久良波の道:断崖の上道・下草刈ってもすぐ草むら、比屋根ヒヤネ坂:石畳、ペリーは浦賀来る前琉球国頭方西海道通る、「夕暮れの恩納番所:ハイネ画」、史跡仲泊遺跡:第三貝塚:沖縄海洋博国道拡張工事発見、海沿い道、今帰仁城跡:石垣、行程80km、
2012年05月04日
ビデオ『奈良大和路古道紀行』全3巻 各52分 アートデイズ
☆ビデオ『奈良大和路古道紀行』全3巻 各52分 アートデイズ
○・『斑鳩いかるがの道 聖徳太子栄光の足跡を訪ねて』52分 歴史ロマンの旅
昔斑鳩は政治・文化の中心地で多くの王宮も造られたし、聖徳太子ゆかりの地でもある。要衝の地。
1.城の町大和郡山から大和民俗公園
奈良盆地北の2つの河川に挟まれ発達した城下町、豊臣秀長等が治める、郡山城跡、今桜名所、追手門前に本家「菊屋」:和菓子屋、春岳院: 豊臣秀長菩提寺、郡山城下町:築地塀・東屋・水路端等復元、富雄川、矢田丘陵、県立大和民俗公園、博物館、里山の麓、18~19世紀の大和の古民家9棟、町屋集落より、国中集落より、宇陀・東山集落より、吉野集落より、道は上り坂、東明寺:、本堂、山門、舎人親王、山腹歩き、奈良盆地、
2.地蔵信仰とあじさいの矢田寺
金剛山寺(矢田寺):かつての本尊は違うが今は地蔵、東明寺への道:、出迎え地蔵、地蔵信仰、弘法大師の石仏、左手に法杖・右手は阿弥陀印の矢田型、見送り地蔵、味噌なめ地蔵、大門坊、末法思想、千仏堂、鐘楼、あじさい60種8000株、矢田丘陵、
3.松尾寺を経て石州流侘び茶の慈光院へ
松尾寺:本尊・千手観音、厄除け観音、慈光院、一之門、茨木城楼門、中庭、書院、片桐さだまさ、石州流茶道、上之間、
~旅の栞~東大寺散策、南大門:重層入母屋作り、中門、大仏殿:びる遮那仏、幾たびも再建、世界最大木造建築物、
4.悲劇の舞台 法起寺
大和畝屋根、岡本宮跡:法起寺、三重塔、聖天堂、講堂、道を西にたどる、
5.太子が愛した膳(かしわで)夫人の住居跡
法輪寺: 膳夫人の住居跡、三重塔、
6.「弥勒」の名刹 中宮寺
中宮寺:皇子の御所跡で荒廃、観世音弥勒菩薩半か像:国宝、天寿国曼荼羅繡帳、
~旅の栞~聖徳太子が眠る寺・叡福寺、多宝塔、太子道、金堂、結界石、
7.太子の夢の跡 法隆寺
重要文化財多し、世界最古の木造建築物、夢殿、法隆寺は再建されていた、南大門、美術史上重要、飛鳥様式、中門、金剛力士像、廻廊、五重塔、上層ほど屋根小さくして安定感、金堂、大講堂、薬師如来・月光・日光菩薩、西円堂、西室・三経院、地蔵堂、宝珠院、東院伽藍「四脚門」、絵殿・舎利殿、東大門、
○・『山の辺の道 万葉と神話の故郷を行く』52分 歴史ロマンの旅
日本最古の道といわれる。大和の古道、三輪山麓から若草山に並ぶ春日山麓まで、奈良盆地東端の山裾を縫うように通っている。弥生時代後期には布留遺跡と纏向遺跡を結ぶ道と推測される。東海自然歩道。正確にはたどれない。
1.万葉に歌われた石神(いそのかみ)神社と神の剣
石上神宮、「石上布留の神杉神さびし恋をもわれは更にするかも」万葉集、神剣、楼門、神杉、山之辺の道がすぐ脇を通る。摂社出雲健雄神社拝殿、拝殿、瑞垣に囲まれたところから遺物発掘、七支刀、「乙女らが袖振る山の瑞垣の久しき時ゆ思いきわれは」万葉集:柿本人麻呂、萱御所跡:後醍醐天皇行幸、その近くに本堂池だけ残存、永久寺跡: 石上神宮神宮寺:大寺院、芭蕉句碑「内山やとざましらずの花盛り」、峠の茶屋、乙木集落、夜都伎神社、「山之辺の道はるけく野路の上に乙木の鳥居朱に立つ見ゆ」東歌、拝殿萱拭屋根、
2.環濠集落竹ノ内と萱生(かよう)
竹ノ内環濠集落、展望ひらけ畑続く、萱生環濠集落、西山塚古墳、古墳多し、西殿塚古墳、継体天皇皇后手白香皇女衾田陵、展望よし、念佛寺:衾寺、「衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし」柿ノ本人麻呂・万葉集、
3.大寺院の名残り長岳寺
長岳寺:弘法大師伝開基・かつて大寺院、楼門、本堂、阿弥陀如来三尊像、
無料休憩所:東海自然歩道トレイルセンター、茶サービス、周辺観光情報、
4.観音信仰と牡丹の長谷寺
~旅の栞~長谷寺を訪ねて、長谷観音霊場、徳願上人勅願により楠彫った観音祀る、中世文学にも多い長谷寺参り、五重塔、「春の夜や篭りびゆかし堂の隅」芭蕉、400段登廊、きざはしのぼり現世の不浄を清める、牡丹、梅、桜、雪柳、山吹、しゃくなげ、あじさい、もみじ、
5.柿本人麻呂ゆかりの穴師の里
第十代崇神天皇陵、前方後円墳、外堀は灌漑用池として改修、景行天皇陵、春は桜、大和三山見える、三輪山、「三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなむ隠さふべしや」額田王・万葉集、穴師坐兵主神社、相撲神社、カタヤケシ、祠前に歴代横綱名前刻む石碑、車谷、巻向川、「ぬばたまの夜さり来れば巻向の川音高しもあらしかも疾き」柿ノ本人麻呂・万葉集、
水車、「あしひきの山川の瀬の鳴るなへに弓月が岳に雲立ち渡る」柿ノ本人麻呂・万葉集、車谷の里、生駒山地、展望よし、矢田丘陵、桧原ヒバラ神社:本殿・拝殿なく背後の三輪山を拝する、三輪鳥居(三ツ鳥居)、ここから二上山見え展望最高、井寺池に映る三輪山、
6.大物主神(おおものぬしのみこと)の伝説と箸墓(はしはか)古墳
箸墓古墳(倭述述日百襲姫命墓)姫は大物主神と結婚したが、本当の姿を見てはいけないといわれたが、蛇の姿を見てしまい、腰を下ろしたとき箸で突いて死んだという、古墳は昼は人が作り、夜は神が作ったという、「いにしへにありけむ人もわが如か三輪の桧原にかざし折りけむ」「古の人の植ゑけむ杉が枝に霞たなびく春は来ぬらし」柿ノ本人麻呂・万葉集、玄賓ゲンピン谷、玄賓ゲンピ庵、はじめ桧原谷にあったが明治期移転、謡曲「三輪」舞台、この坂上ると狭井神社:疫病の神、拝殿、4月の祭は薬草添えられる、狭井の御神水、大美和の社展望台より天の香具山、畝傍山、耳成山、門前町の桜井市三輪の地が広がる展望、坂下ると久延彦神社、おだまさ杉、
7.大神(おおみわ)神社から古代の市場・海柘榴市(つばいち)へ
大神神社:大和一ノ宮:三輪明神、二の鳥居、参道、祓戸社、大鳥居、拝殿、巳の神杉、金屋の石仏:弥勒如来像・釈迦如来像・国重要文化財、海柘榴市:日本最初の市、海柘榴市跡、竹ノ内街道、
○・『柳生の道 』52分 歴史ロマンの旅
剣豪の道と呼ばれるが、多数の石仏があることから振興の道であり、生活道であることが分かる。奈良市春日山の新薬師寺から柳生の里への道。東海自然歩道。
1.萩が咲く天平の名刹 新薬師寺
春日山は伐採禁止で太古の原生林が残る。鶯の滝:昔水滴が氷を叩き鶯のようだったといわれる。コスモス。稲穂。新薬師寺、天平期古寺、萩、本堂:屋根裏なく天井見せる国宝、747年光明皇后建立、鐘楼、落雷多く立ち枯れる木多し、薬師如来像、十二神将、地蔵堂、十一面観世音菩薩、
2.石畳と石仏の滝坂道
新薬師寺から春日山へ伸びる道、能登川、石畳、滝坂道、寝仏:だ尾に地如来像、夕日観音、三体地蔵:弥勒菩薩像、朝日観音:弥勒菩薩像、首切り地蔵:荒木又衛門試し斬り伝、
3.春日山石窟仏と地獄谷石窟
春日山石窟仏(穴仏)、地獄谷石窟(聖人窟)、石切峠、峠の茶屋:鉄砲・槍・酒徳利、上誓多林集落、茶畑、五尺地蔵尊、
4.忍辱山(にんにくせん)円成寺と平安朝の余韻
地蔵多数、北大和五山(鹿野苑、菩提山、忍辱山、大慈山、誓多林)、忍辱山円成寺、浄土式庭園、楼門、本堂:重要文化財、阿弥陀如来、多宝塔、大日如来像:若い運慶作伝、十一面観音像、扉絵、白山堂・春日堂:国宝、キキョウ、カエデ、
5.大柳生から阪原(かえりばさ)の集落へ
白砂川、夜支布(ヤギュウ)山口神社、拝殿、太鼓踊り:雨乞いの名残→現在大柳生神社でのみ残る、立磐神社、大柳生の集落、阪原の集落、南明寺、十三重石塔、宝経印塔、阿弥陀如来坐像、おふじの井戸:柳生但馬守とおふじの出会いのとんち話、柳生と大柳生の分岐、阪原峠、疱瘡地蔵、
6.剣豪一族の夢の跡「柳生の里」
柳生の里、柳生宗矩、沢庵和尚、柳生陣屋跡、石垣再現、公園、八坂神社、旧柳生藩家老屋敷:小山田主鈴→のち山岡荘八購入→奈良市寄贈・一般公開、
7.沢庵和尚の芳徳禅寺
今川、もみじ橋、霊験坂、正木坂剣道場、ふくろ刀、柳生新陰流、芳徳禅寺:1638年建立、資料館、兵法書、柳生家墓所、まんねんけい、天乃石立神社、一刀石:伝柳生宗厳石舟斎が天狗を切ると巨岩が割れていたという、
○・『斑鳩いかるがの道 聖徳太子栄光の足跡を訪ねて』52分 歴史ロマンの旅
昔斑鳩は政治・文化の中心地で多くの王宮も造られたし、聖徳太子ゆかりの地でもある。要衝の地。
1.城の町大和郡山から大和民俗公園
奈良盆地北の2つの河川に挟まれ発達した城下町、豊臣秀長等が治める、郡山城跡、今桜名所、追手門前に本家「菊屋」:和菓子屋、春岳院: 豊臣秀長菩提寺、郡山城下町:築地塀・東屋・水路端等復元、富雄川、矢田丘陵、県立大和民俗公園、博物館、里山の麓、18~19世紀の大和の古民家9棟、町屋集落より、国中集落より、宇陀・東山集落より、吉野集落より、道は上り坂、東明寺:、本堂、山門、舎人親王、山腹歩き、奈良盆地、
2.地蔵信仰とあじさいの矢田寺
金剛山寺(矢田寺):かつての本尊は違うが今は地蔵、東明寺への道:、出迎え地蔵、地蔵信仰、弘法大師の石仏、左手に法杖・右手は阿弥陀印の矢田型、見送り地蔵、味噌なめ地蔵、大門坊、末法思想、千仏堂、鐘楼、あじさい60種8000株、矢田丘陵、
3.松尾寺を経て石州流侘び茶の慈光院へ
松尾寺:本尊・千手観音、厄除け観音、慈光院、一之門、茨木城楼門、中庭、書院、片桐さだまさ、石州流茶道、上之間、
~旅の栞~東大寺散策、南大門:重層入母屋作り、中門、大仏殿:びる遮那仏、幾たびも再建、世界最大木造建築物、
4.悲劇の舞台 法起寺
大和畝屋根、岡本宮跡:法起寺、三重塔、聖天堂、講堂、道を西にたどる、
5.太子が愛した膳(かしわで)夫人の住居跡
法輪寺: 膳夫人の住居跡、三重塔、
6.「弥勒」の名刹 中宮寺
中宮寺:皇子の御所跡で荒廃、観世音弥勒菩薩半か像:国宝、天寿国曼荼羅繡帳、
~旅の栞~聖徳太子が眠る寺・叡福寺、多宝塔、太子道、金堂、結界石、
7.太子の夢の跡 法隆寺
重要文化財多し、世界最古の木造建築物、夢殿、法隆寺は再建されていた、南大門、美術史上重要、飛鳥様式、中門、金剛力士像、廻廊、五重塔、上層ほど屋根小さくして安定感、金堂、大講堂、薬師如来・月光・日光菩薩、西円堂、西室・三経院、地蔵堂、宝珠院、東院伽藍「四脚門」、絵殿・舎利殿、東大門、
○・『山の辺の道 万葉と神話の故郷を行く』52分 歴史ロマンの旅
日本最古の道といわれる。大和の古道、三輪山麓から若草山に並ぶ春日山麓まで、奈良盆地東端の山裾を縫うように通っている。弥生時代後期には布留遺跡と纏向遺跡を結ぶ道と推測される。東海自然歩道。正確にはたどれない。
1.万葉に歌われた石神(いそのかみ)神社と神の剣
石上神宮、「石上布留の神杉神さびし恋をもわれは更にするかも」万葉集、神剣、楼門、神杉、山之辺の道がすぐ脇を通る。摂社出雲健雄神社拝殿、拝殿、瑞垣に囲まれたところから遺物発掘、七支刀、「乙女らが袖振る山の瑞垣の久しき時ゆ思いきわれは」万葉集:柿本人麻呂、萱御所跡:後醍醐天皇行幸、その近くに本堂池だけ残存、永久寺跡: 石上神宮神宮寺:大寺院、芭蕉句碑「内山やとざましらずの花盛り」、峠の茶屋、乙木集落、夜都伎神社、「山之辺の道はるけく野路の上に乙木の鳥居朱に立つ見ゆ」東歌、拝殿萱拭屋根、
2.環濠集落竹ノ内と萱生(かよう)
竹ノ内環濠集落、展望ひらけ畑続く、萱生環濠集落、西山塚古墳、古墳多し、西殿塚古墳、継体天皇皇后手白香皇女衾田陵、展望よし、念佛寺:衾寺、「衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし」柿ノ本人麻呂・万葉集、
3.大寺院の名残り長岳寺
長岳寺:弘法大師伝開基・かつて大寺院、楼門、本堂、阿弥陀如来三尊像、
無料休憩所:東海自然歩道トレイルセンター、茶サービス、周辺観光情報、
4.観音信仰と牡丹の長谷寺
~旅の栞~長谷寺を訪ねて、長谷観音霊場、徳願上人勅願により楠彫った観音祀る、中世文学にも多い長谷寺参り、五重塔、「春の夜や篭りびゆかし堂の隅」芭蕉、400段登廊、きざはしのぼり現世の不浄を清める、牡丹、梅、桜、雪柳、山吹、しゃくなげ、あじさい、もみじ、
5.柿本人麻呂ゆかりの穴師の里
第十代崇神天皇陵、前方後円墳、外堀は灌漑用池として改修、景行天皇陵、春は桜、大和三山見える、三輪山、「三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなむ隠さふべしや」額田王・万葉集、穴師坐兵主神社、相撲神社、カタヤケシ、祠前に歴代横綱名前刻む石碑、車谷、巻向川、「ぬばたまの夜さり来れば巻向の川音高しもあらしかも疾き」柿ノ本人麻呂・万葉集、
水車、「あしひきの山川の瀬の鳴るなへに弓月が岳に雲立ち渡る」柿ノ本人麻呂・万葉集、車谷の里、生駒山地、展望よし、矢田丘陵、桧原ヒバラ神社:本殿・拝殿なく背後の三輪山を拝する、三輪鳥居(三ツ鳥居)、ここから二上山見え展望最高、井寺池に映る三輪山、
6.大物主神(おおものぬしのみこと)の伝説と箸墓(はしはか)古墳
箸墓古墳(倭述述日百襲姫命墓)姫は大物主神と結婚したが、本当の姿を見てはいけないといわれたが、蛇の姿を見てしまい、腰を下ろしたとき箸で突いて死んだという、古墳は昼は人が作り、夜は神が作ったという、「いにしへにありけむ人もわが如か三輪の桧原にかざし折りけむ」「古の人の植ゑけむ杉が枝に霞たなびく春は来ぬらし」柿ノ本人麻呂・万葉集、玄賓ゲンピン谷、玄賓ゲンピ庵、はじめ桧原谷にあったが明治期移転、謡曲「三輪」舞台、この坂上ると狭井神社:疫病の神、拝殿、4月の祭は薬草添えられる、狭井の御神水、大美和の社展望台より天の香具山、畝傍山、耳成山、門前町の桜井市三輪の地が広がる展望、坂下ると久延彦神社、おだまさ杉、
7.大神(おおみわ)神社から古代の市場・海柘榴市(つばいち)へ
大神神社:大和一ノ宮:三輪明神、二の鳥居、参道、祓戸社、大鳥居、拝殿、巳の神杉、金屋の石仏:弥勒如来像・釈迦如来像・国重要文化財、海柘榴市:日本最初の市、海柘榴市跡、竹ノ内街道、
○・『柳生の道 』52分 歴史ロマンの旅
剣豪の道と呼ばれるが、多数の石仏があることから振興の道であり、生活道であることが分かる。奈良市春日山の新薬師寺から柳生の里への道。東海自然歩道。
1.萩が咲く天平の名刹 新薬師寺
春日山は伐採禁止で太古の原生林が残る。鶯の滝:昔水滴が氷を叩き鶯のようだったといわれる。コスモス。稲穂。新薬師寺、天平期古寺、萩、本堂:屋根裏なく天井見せる国宝、747年光明皇后建立、鐘楼、落雷多く立ち枯れる木多し、薬師如来像、十二神将、地蔵堂、十一面観世音菩薩、
2.石畳と石仏の滝坂道
新薬師寺から春日山へ伸びる道、能登川、石畳、滝坂道、寝仏:だ尾に地如来像、夕日観音、三体地蔵:弥勒菩薩像、朝日観音:弥勒菩薩像、首切り地蔵:荒木又衛門試し斬り伝、
3.春日山石窟仏と地獄谷石窟
春日山石窟仏(穴仏)、地獄谷石窟(聖人窟)、石切峠、峠の茶屋:鉄砲・槍・酒徳利、上誓多林集落、茶畑、五尺地蔵尊、
4.忍辱山(にんにくせん)円成寺と平安朝の余韻
地蔵多数、北大和五山(鹿野苑、菩提山、忍辱山、大慈山、誓多林)、忍辱山円成寺、浄土式庭園、楼門、本堂:重要文化財、阿弥陀如来、多宝塔、大日如来像:若い運慶作伝、十一面観音像、扉絵、白山堂・春日堂:国宝、キキョウ、カエデ、
5.大柳生から阪原(かえりばさ)の集落へ
白砂川、夜支布(ヤギュウ)山口神社、拝殿、太鼓踊り:雨乞いの名残→現在大柳生神社でのみ残る、立磐神社、大柳生の集落、阪原の集落、南明寺、十三重石塔、宝経印塔、阿弥陀如来坐像、おふじの井戸:柳生但馬守とおふじの出会いのとんち話、柳生と大柳生の分岐、阪原峠、疱瘡地蔵、
6.剣豪一族の夢の跡「柳生の里」
柳生の里、柳生宗矩、沢庵和尚、柳生陣屋跡、石垣再現、公園、八坂神社、旧柳生藩家老屋敷:小山田主鈴→のち山岡荘八購入→奈良市寄贈・一般公開、
7.沢庵和尚の芳徳禅寺
今川、もみじ橋、霊験坂、正木坂剣道場、ふくろ刀、柳生新陰流、芳徳禅寺:1638年建立、資料館、兵法書、柳生家墓所、まんねんけい、天乃石立神社、一刀石:伝柳生宗厳石舟斎が天狗を切ると巨岩が割れていたという、
Posted by 兵藤庄左衛門 at
15:03
│Comments(0)
2012年05月04日
VHS『歴史の道百選 中山道』全4巻 TDKコア
☆VHS『歴史の道百選 中山道』全4巻 TDKコア
・『歴史の道百選 中山道 第1巻 碓氷峠越え』(坂本宿~碓氷峠~追分宿)約37分
全行程12km、緑豊かな古街道、
碓氷関所跡、おじぎ石。四大関所の一つ、資料館、松井田町、石垣、総欅作り、唯一現存復元門、御関所廃止届、 1’07”経過開始
坂本宿~五料の茶屋本陣、五料村、上段の間、青面金剛塔1740年建立、夜泣き地蔵、茶釜石(叩くと金属的な音)、中山道540km、69宿、間口の狭い家、千本格子、江戸から17番目、旅籠や多い、3’24”
堂峰番所跡、かつては見晴らしよく関所破りを見張っていた遠見番所、門の土台石、ヒメジョオン~刎石ハネイシ坂、柱状節理、石仏群~上り地蔵・下り地蔵、常夜灯~三枚石、8’06”
覗のぞき~風穴~ 坂本宿を見下ろせる、12’05”
刎石茶屋跡、h793m 刎石山山頂の四軒の茶屋跡石垣、~弘法の井戸~座頭ころばし、湿った土と石ころ~ 13’38”
山中茶屋跡、峠の真ん中で13軒立場茶屋、安政遠足トオアシ(安中藩、日本最初のマラソン)、17’37”
碓氷峠~熊野(皇大)神社、狛犬、風車石像1688年、本殿3つ。上州・信州国境、古鐘(鎌倉期)、シナの木御神木~金原やぶ(金原忠魂碑)~思婦石(ヤマトタケル伝説)~一つ家の歌碑~碓氷川水源、ワサビ田~碓氷峠見晴台、狼煙台、浅間山、万葉集の歌碑~碓氷峠遊覧歩道、ミツバウツギ、クワガタソウ~二手橋にて~ h1200m 、18’58”
軽井沢宿~追分の一里塚、江戸から40番目~ つるや旅館と周辺土産物屋に古い面影、29’37”
追分宿、本陣跡、本陣石垣~追分の分去れワカサレ、石道標、常夜灯、歌碑、石造物群、追分節発祥地、~浅間神社、枡形の茶屋~ 31’09”
陽春から秋の歴史と叙情、きつい坂のトオアシハイキング。
・『歴史の道百選 中山道 第2巻 鳥居峠越え』(奈良井宿~鳥居峠~薮原宿)約34分
中仙道、石畳、
贄川ニエカワ関所、曲物や漆器取り締まり、白木改め、女改め、口留番所、1’18”経過開始
八幡神社、奈良井宿手前で二百地蔵、杉並木、2’25”
奈良井宿~奈良井五カ寺(大宝寺、専念寺、法然寺、長泉寺、浄龍寺)庭園~水場~鍵の手(敵への防御、火災防止)~中村邸(櫛問屋、間口狭い、出し張り作り、小屋根、鎧庇、吊り金具で吊る当宿場のみ、看板吊る飾り屋根、袖壁、くぐり戸、通り土間・店・勝手・中の間・座敷・裏庭)~高札場~、天保から弘化年間の建物多い、国の重要伝統的建造物群保存地区、奈良井千軒、漆器・曲物、楢川村、漆塗り材料の錆び土産出、 3’28”
鎮神社、奈良井村鎮守、峠越え安全祈願、石仏群、 15’10”
中の茶屋、 石畳復元、18’07”
葬ホウムリ沢、木曾氏と武田氏の古戦場で敗れた武田武将500人の亡骸を葬ったという、木曽路一の難所、旧国道合流、18’36”
子産みの栃、頂上手前、子宝に恵まれない人が木の穴に捨てられた子を育てて幸せになったという伝説があり、この栃の実を煎じて飲むと子宝に恵まれるという。 23’45”
鳥居峠、h1192m、戦国期、木曾氏が戦勝祈願を峠で行い勝利したので鳥居を建立したことに由来する。御岳遥拝所、石碑、 24’22”
丸山公園、峠を薮原側に少し下ったところにあり、芭蕉句碑もある。25’36”
薮原宿、江戸から36番目、タガソデソウ、つげのお六櫛、木祖村、 29’24”
春夏秋最適な歴史と自然のハイキングコース。
・『歴史の道百選 中山道 第3巻 馬籠峠越え』(妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿)約34分
羅天、野尻と三留野の迂回路の古道:与川道から妻籠宿を経て馬籠宿(島崎藤村の故郷)への馬籠峠越え、木曽川、木曽名所図会、木曽の桟カケハシ、国道19号線(旧中仙道)、
与川道、~ウツギ、阿弥陀堂、竜のひげ(ジャノヒゲ)~松原御小休所マツバラゴコヤスミジョ、ヤマサギゴケ、ツルキンバイ、キバナノヤマオダマキ、中山道に合流、3’03”経過開始
三留野宿:江戸から41番目・長さ2丁15間230m余594人77軒旅籠32本陣脇本陣各1、~本陣跡、枝垂れ梅~等覚寺、円空仏:弁財天十五童子像・韋駄天~、9’40”
上久保の一里塚、妻籠宿手前、江戸から78番目、11’15”
妻籠宿ツマゴ:南木曾町:江戸から42番目、~口留番所跡近く、鯉岩、木曽名所図会~妻籠宿本陣(復元、上段の間、)~脇本陣奥谷~歴史資料館、和宮から拝領した車付長持~ギンモクセイの大木:長野県指定天然記念物、だし張り作り~上了子屋、牛つなぎの鉄環~松代屋、御嶽講のまねき板、厩ウマヤ~上嵯峨屋:木賃宿~下嵯峨屋・板葺き・石置屋根~、重要伝統的建造物群保存地区、 12’42”
男滝オダル・女滝メダル、~石畳道、さわらの大木:樹齢300年、神居木カモイギ・神居座~、20’29”
白木改番所跡シラキアラタメバンショ、一石栃イチコクトチの番所跡、木曾五木(ひのき、さわら、あすなろ、こうやまき、ねずこ)伐採禁止の木材取り締まり、~立場茶屋、茶屋の人たちの墓所~、22’48”
馬籠峠マゴメh801m、~正岡子規句碑、コアジサイ、熊野神社~峠集落、十返舎一九歌碑~、 24’18”
馬籠宿714人、島崎藤村実家は本陣・問屋・庄屋、~藤村記念館(本陣跡)、馬籠本陣礎石~、28’14”
新茶屋、立場茶屋、江戸から83番目一里塚、~一里塚~藤村碑「是より北木曽路」信濃美濃国境~芭蕉句碑、落合の石畳~、30’35”
・『歴史の道百選 中山道 第4巻 東美濃路』(落合宿~三城峠~御嵩宿)約35分
岐阜県中津川市の落合宿から中津川宿、大井宿、大湫宿オオクテ、細久手宿、御嵩宿ミタケまで。国道19号線、21号線沿いで、中津川市、恵那市、瑞浪市、御嵩町。緑豊かな歴史の道。
「是より北、木曽路」藤村石碑、新茶屋、木曽(長野県)と美濃(岐阜県)境、
落合の石畳、十曲峠、ヒトツバタコの木(ナンジャモンジャ)、1’52”経過開始
医王寺、山中薬師、十返舎一九「木曽街道続膝栗毛」、きつねこうやく:看板、版木、効能書き、落合川、~下桁橋:木曽街道六十九次・広重画~、4’35”
落合宿、江戸から44番目で美濃国最初の宿、本陣の井口家の門は加賀藩より贈られた物、6’15”
大井宿、江戸から46番目宿、本陣内樹齢300年以上松老木、7’21”
西行苑、西行亡くなるまでの3年間過ごす、~西行塚、七本松坂~槙が根~一里塚~西行の森、恵那山展望、百種類桜~槙が根追分、石道標「右西京大阪 左伊勢名古屋(下街道) 道」~下街道:幕府から通行禁止令~乱れ坂~乱れ橋~紅坂ベニ~深萱フカガヤの立場跡、立場本陣~、8’09”
三城峠ミツジロh382m、展望よく近くの三つの城(権現・奥の権現・藤城)が見えたので、~樫の木坂~権現山~一里塚~阿波屋の茶屋跡~三十三観音~尻冷し地蔵、しゃれこ坂、やまなみ坂、寺坂、十三峠越え終わり~、14’27”
大湫宿おおくて、天保期人口338人、家66軒、本陣・脇本陣各1、旅籠30軒、格子戸・虫籠窓・土塀、~大湫宿脇本陣~神明神社、神木樹齢1200年杉~観音堂~、 18’23”
琵琶峠、石畳、頂上から伊吹山・鈴鹿山脈・加賀の白山展望、~弁財天の池~、21’18”
細久手宿:256人65軒本陣脇本陣各1旅籠24、尾張藩本陣・大黒屋は昔からの旅籠・箱階段、~鴨之巣一里塚コウノス、ドクダミ、ウツボグサ、ノアザミ~謡坂うとうざか御殿場:皇女和宮休憩所、ラベンダー~一呑の清水ヒトノミ~耳神社、願成就で年齢分のキリをすだれに編む~、さいと坂下る、和泉式部廟所~、24’08”
御嵩宿、大寺山願興寺(開創平安時代)に江戸期初期領地が与えられ門前町として栄えた、~御嵩宿本陣~願興寺:国重要文化財~、31’12”
・『歴史の道百選 中山道 第1巻 碓氷峠越え』(坂本宿~碓氷峠~追分宿)約37分
全行程12km、緑豊かな古街道、
碓氷関所跡、おじぎ石。四大関所の一つ、資料館、松井田町、石垣、総欅作り、唯一現存復元門、御関所廃止届、 1’07”経過開始
坂本宿~五料の茶屋本陣、五料村、上段の間、青面金剛塔1740年建立、夜泣き地蔵、茶釜石(叩くと金属的な音)、中山道540km、69宿、間口の狭い家、千本格子、江戸から17番目、旅籠や多い、3’24”
堂峰番所跡、かつては見晴らしよく関所破りを見張っていた遠見番所、門の土台石、ヒメジョオン~刎石ハネイシ坂、柱状節理、石仏群~上り地蔵・下り地蔵、常夜灯~三枚石、8’06”
覗のぞき~風穴~ 坂本宿を見下ろせる、12’05”
刎石茶屋跡、h793m 刎石山山頂の四軒の茶屋跡石垣、~弘法の井戸~座頭ころばし、湿った土と石ころ~ 13’38”
山中茶屋跡、峠の真ん中で13軒立場茶屋、安政遠足トオアシ(安中藩、日本最初のマラソン)、17’37”
碓氷峠~熊野(皇大)神社、狛犬、風車石像1688年、本殿3つ。上州・信州国境、古鐘(鎌倉期)、シナの木御神木~金原やぶ(金原忠魂碑)~思婦石(ヤマトタケル伝説)~一つ家の歌碑~碓氷川水源、ワサビ田~碓氷峠見晴台、狼煙台、浅間山、万葉集の歌碑~碓氷峠遊覧歩道、ミツバウツギ、クワガタソウ~二手橋にて~ h1200m 、18’58”
軽井沢宿~追分の一里塚、江戸から40番目~ つるや旅館と周辺土産物屋に古い面影、29’37”
追分宿、本陣跡、本陣石垣~追分の分去れワカサレ、石道標、常夜灯、歌碑、石造物群、追分節発祥地、~浅間神社、枡形の茶屋~ 31’09”
陽春から秋の歴史と叙情、きつい坂のトオアシハイキング。
・『歴史の道百選 中山道 第2巻 鳥居峠越え』(奈良井宿~鳥居峠~薮原宿)約34分
中仙道、石畳、
贄川ニエカワ関所、曲物や漆器取り締まり、白木改め、女改め、口留番所、1’18”経過開始
八幡神社、奈良井宿手前で二百地蔵、杉並木、2’25”
奈良井宿~奈良井五カ寺(大宝寺、専念寺、法然寺、長泉寺、浄龍寺)庭園~水場~鍵の手(敵への防御、火災防止)~中村邸(櫛問屋、間口狭い、出し張り作り、小屋根、鎧庇、吊り金具で吊る当宿場のみ、看板吊る飾り屋根、袖壁、くぐり戸、通り土間・店・勝手・中の間・座敷・裏庭)~高札場~、天保から弘化年間の建物多い、国の重要伝統的建造物群保存地区、奈良井千軒、漆器・曲物、楢川村、漆塗り材料の錆び土産出、 3’28”
鎮神社、奈良井村鎮守、峠越え安全祈願、石仏群、 15’10”
中の茶屋、 石畳復元、18’07”
葬ホウムリ沢、木曾氏と武田氏の古戦場で敗れた武田武将500人の亡骸を葬ったという、木曽路一の難所、旧国道合流、18’36”
子産みの栃、頂上手前、子宝に恵まれない人が木の穴に捨てられた子を育てて幸せになったという伝説があり、この栃の実を煎じて飲むと子宝に恵まれるという。 23’45”
鳥居峠、h1192m、戦国期、木曾氏が戦勝祈願を峠で行い勝利したので鳥居を建立したことに由来する。御岳遥拝所、石碑、 24’22”
丸山公園、峠を薮原側に少し下ったところにあり、芭蕉句碑もある。25’36”
薮原宿、江戸から36番目、タガソデソウ、つげのお六櫛、木祖村、 29’24”
春夏秋最適な歴史と自然のハイキングコース。
・『歴史の道百選 中山道 第3巻 馬籠峠越え』(妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿)約34分
羅天、野尻と三留野の迂回路の古道:与川道から妻籠宿を経て馬籠宿(島崎藤村の故郷)への馬籠峠越え、木曽川、木曽名所図会、木曽の桟カケハシ、国道19号線(旧中仙道)、
与川道、~ウツギ、阿弥陀堂、竜のひげ(ジャノヒゲ)~松原御小休所マツバラゴコヤスミジョ、ヤマサギゴケ、ツルキンバイ、キバナノヤマオダマキ、中山道に合流、3’03”経過開始
三留野宿:江戸から41番目・長さ2丁15間230m余594人77軒旅籠32本陣脇本陣各1、~本陣跡、枝垂れ梅~等覚寺、円空仏:弁財天十五童子像・韋駄天~、9’40”
上久保の一里塚、妻籠宿手前、江戸から78番目、11’15”
妻籠宿ツマゴ:南木曾町:江戸から42番目、~口留番所跡近く、鯉岩、木曽名所図会~妻籠宿本陣(復元、上段の間、)~脇本陣奥谷~歴史資料館、和宮から拝領した車付長持~ギンモクセイの大木:長野県指定天然記念物、だし張り作り~上了子屋、牛つなぎの鉄環~松代屋、御嶽講のまねき板、厩ウマヤ~上嵯峨屋:木賃宿~下嵯峨屋・板葺き・石置屋根~、重要伝統的建造物群保存地区、 12’42”
男滝オダル・女滝メダル、~石畳道、さわらの大木:樹齢300年、神居木カモイギ・神居座~、20’29”
白木改番所跡シラキアラタメバンショ、一石栃イチコクトチの番所跡、木曾五木(ひのき、さわら、あすなろ、こうやまき、ねずこ)伐採禁止の木材取り締まり、~立場茶屋、茶屋の人たちの墓所~、22’48”
馬籠峠マゴメh801m、~正岡子規句碑、コアジサイ、熊野神社~峠集落、十返舎一九歌碑~、 24’18”
馬籠宿714人、島崎藤村実家は本陣・問屋・庄屋、~藤村記念館(本陣跡)、馬籠本陣礎石~、28’14”
新茶屋、立場茶屋、江戸から83番目一里塚、~一里塚~藤村碑「是より北木曽路」信濃美濃国境~芭蕉句碑、落合の石畳~、30’35”
・『歴史の道百選 中山道 第4巻 東美濃路』(落合宿~三城峠~御嵩宿)約35分
岐阜県中津川市の落合宿から中津川宿、大井宿、大湫宿オオクテ、細久手宿、御嵩宿ミタケまで。国道19号線、21号線沿いで、中津川市、恵那市、瑞浪市、御嵩町。緑豊かな歴史の道。
「是より北、木曽路」藤村石碑、新茶屋、木曽(長野県)と美濃(岐阜県)境、
落合の石畳、十曲峠、ヒトツバタコの木(ナンジャモンジャ)、1’52”経過開始
医王寺、山中薬師、十返舎一九「木曽街道続膝栗毛」、きつねこうやく:看板、版木、効能書き、落合川、~下桁橋:木曽街道六十九次・広重画~、4’35”
落合宿、江戸から44番目で美濃国最初の宿、本陣の井口家の門は加賀藩より贈られた物、6’15”
大井宿、江戸から46番目宿、本陣内樹齢300年以上松老木、7’21”
西行苑、西行亡くなるまでの3年間過ごす、~西行塚、七本松坂~槙が根~一里塚~西行の森、恵那山展望、百種類桜~槙が根追分、石道標「右西京大阪 左伊勢名古屋(下街道) 道」~下街道:幕府から通行禁止令~乱れ坂~乱れ橋~紅坂ベニ~深萱フカガヤの立場跡、立場本陣~、8’09”
三城峠ミツジロh382m、展望よく近くの三つの城(権現・奥の権現・藤城)が見えたので、~樫の木坂~権現山~一里塚~阿波屋の茶屋跡~三十三観音~尻冷し地蔵、しゃれこ坂、やまなみ坂、寺坂、十三峠越え終わり~、14’27”
大湫宿おおくて、天保期人口338人、家66軒、本陣・脇本陣各1、旅籠30軒、格子戸・虫籠窓・土塀、~大湫宿脇本陣~神明神社、神木樹齢1200年杉~観音堂~、 18’23”
琵琶峠、石畳、頂上から伊吹山・鈴鹿山脈・加賀の白山展望、~弁財天の池~、21’18”
細久手宿:256人65軒本陣脇本陣各1旅籠24、尾張藩本陣・大黒屋は昔からの旅籠・箱階段、~鴨之巣一里塚コウノス、ドクダミ、ウツボグサ、ノアザミ~謡坂うとうざか御殿場:皇女和宮休憩所、ラベンダー~一呑の清水ヒトノミ~耳神社、願成就で年齢分のキリをすだれに編む~、さいと坂下る、和泉式部廟所~、24’08”
御嵩宿、大寺山願興寺(開創平安時代)に江戸期初期領地が与えられ門前町として栄えた、~御嵩宿本陣~願興寺:国重要文化財~、31’12”
2012年05月04日
ビデオ『歴史の道百選 東海道』全3巻 TDKコア
☆ビデオ『歴史の道百選 東海道』全3巻 TDKコア
箱根、小夜の中山、鈴鹿峠を紹介している。いつか行ってみたくなる光景だ。もっとも古道らしいところをうまく見せている。歴史的紹介も手際よい。
○・『歴史の道百選 東海道 第1巻 箱根路』(箱根湯元~箱根峠~三島宿)約35分
箱根旧街道は小田原宿から芦ノ湖畔、箱根宿を経て箱根峠を越えた三島宿までの八里30kmで、遺跡や石畳が多く歴史の面影が色濃く残る古街道である。
箱根湯本、小田原から4km、早川に架かる三枚橋からはじまる。~早雲寺:北条早雲遺言で作られた、北条文化、北条五代の墓、北条早雲像、枯山水香爐峰(北条幻庵作)、鳴き方独特ヒメハルゼミ~正眼ショウゲン寺、地蔵信仰、石仏石塔、曽我堂、曽我五郎槍突石、箱根旧街道、ハコネサンショウウオ~大沢坂、石畳、江戸期のもの~、 1’18”経過開始
畑宿、箱根寄木細工発祥地、シーボルト絶賛、間の宿 ~畑宿の一里塚、23里目、石畳、排水路の石畳~甘酒茶屋~お玉坂、1702年処刑~、6’32”
お玉ヶ池、那津奈可池なづながいけと言われていたが関所破りで処刑されたお玉にちなんで名がついた~白水坂(城見ず坂)秀吉軍勢が北条軍から攻撃受け城を見ずに退却したため伝~天ヶ石坂~休憩広場:二子山展望、♫箱根馬子唄♬~権現坂、ここから下り坂、芦ノ湖~湯坂道(鎌倉古道)、アジサイ、芦ノ湖~、11’06”
箱根神社、もとは箱根権現、関東の鎮護神、山岳信仰、18’19”
箱根杉並木、650m区間残存、樹齢350年の杉は生育に適さない松から植え替えられたと推定される、 19’17”
箱根関所跡、昔山裾が芦ノ湖に最も迫っていた場所に設置、箱根関所資料館、20’37”
箱根宿、幕府が小田原と三島から50戸ずつ移住させて開設、今も町名に小田原町、三島町が残るが往時の面影はない、本陣跡:箱根ホテル前の楓の木:樹齢400年~芦川の石仏~向坂~ 、21’47”
箱根峠、西坂、箱根竹、元はキセルの原料で箱根峠道に敷いていたが労力が大変なので石畳にしたという~兜石坂~施行平、ウツボグサ、ホタルブクロ~念仏石、自然石に南無阿弥陀仏と刻む~願合寺の石畳、ニホンミツバチの巣~雲助徳利の墓~、23’01”
山中城跡、畝堀、北条氏築造、秀吉小田原征伐落城、障子堀、本丸跡、矢立の杉~宗閑寺、豊臣と北条武将の墓~富士見平、「霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き」芭蕉~上長坂地区の石畳~こわめし坂、馬頭観世音~錦田の一里塚、約1km松並木~ 28’06”
三島宿、江戸から12番目、旅籠屋多く70~80軒、樋口本陣門(円明寺)、世古本陣門(長園寺)、三島宿風俗絵屏風:三島信用金庫蔵~三島御殿神社:御殿の屋敷神~三嶋大社~ 31’43”
○・『歴史の道百選 東海道 第2巻 小夜の中山道』(島田宿~大井川~日坂宿)約34分
川留めでも賑わった島田宿から越すに越されぬ大井川を渡り金谷宿を経て小夜の中山峠越えで日坂宿への行程。徳川幕府政策により大井川には徒歩渡りしか許可しなかった。
島田宿、最大28日間の川留め記録がある。松尾芭蕉も4日間川留めされた。~大井川川越遺跡:川会所(川越業務を管理運営した所)・蓮台・~塚本家跡:松尾芭蕉逗留・連歌「やわらかにたけよことしの手作麦」如舟「田植とともにたびの朝起」芭蕉~朝顔の松:「朝顔日記」近松門左衛門作~ 1’18”経過開始
大井神社、島田宿氏神、川越安全祈願、土手石垣・平石橋・川越制度廃止後失業した人足や幕府役人は牧之原開墾茶農家 5’09”
大井川、川越人足、川越し制度1696年、~蓬莱橋:1879年完成の木橋~ 6’14”
金谷宿、東橋、川留めでも栄える、川を渡ると水祝いと称して酒を酌み交わしたという、佐塚本陣跡、~不動橋:宿西木戸~金谷坂:平成石畳復元、すべらず地蔵:平成~牧之原公園:周辺茶畑~ 8’12”
諏訪原城跡、1569年信玄砦築く、甲州流築城術、1575年家康によって落城、本丸跡~菊川坂(菊坂):石畳復元~ 13’29”
菊川の里:間の宿、頼朝・藤原宗行・日野俊基等が通った、詩碑、石道標:遠江三十三箇所観音霊場巡り、 14’52”
久延寺、山内一豊が境内に茶室を設け関が原に向かう家康を接待したという、そのとき利用した御上井戸、家康手植え五葉松、 19’05”
小夜の中山公園、歌枕名所:「年たけてまた越ゆべしとおもひきやいのちなりけり小夜の中山」西行・「旅寝するさよの中山さよ中に鹿ぞなくなる妻や恋しき」橘為仲朝臣、狭い谷さやが語源、~小夜鹿サヤカの一里塚~涼み松:「命なりわずかの笠の下涼み」芭蕉~夜泣き石跡:安藤広重「東海道五十三次日坂夜泣き石図」レリーフ、2つの夜泣き石:小泉屋裏と久延寺、夜泣き石伝説・山賊に殺された妊婦の子が飴で育ち仇を取った等~扇屋:子育て飴・川島ちとせ~沓掛七曲り:急坂~ 20’58”
日坂宿、旅籠屋33軒の小さい宿場、本陣扇屋跡、1852年大火、~相伝寺:秋葉山常夜灯:天保十・槙の木~旅籠:川坂屋:大火直後建物で江戸期唯一残る~常現寺:1501年創建・旅人の無縁仏多し~ 28’41”
○・『歴史の道百選 東海道 第3巻 鈴鹿峠越え』(関宿~鈴鹿峠~土山宿)約35分
三重県と滋賀県境の鈴鹿峠、東の箱根と並び難所、
関宿、関町、日本書紀にも名がある関、47番目宿、東の追分:伊勢神宮一の鳥居、伊勢別街道分岐15里、20年に一度のせき年新宮、石道標、建立・行基伝:地蔵院・愛染堂:重要文化財、地蔵院庭園、瑞光院、権現柿、ご馳走場:地元役人等出迎え用、東西1.8km宿場町歴史的景観保存、むくり屋根:楕円形屋根、塗籠(ぬりごめ):土蔵風漆喰塗り、環金具、揚げ店(ばったり)、関まちなみ資料館、町屋建築、箱階段、部屋三間、裏庭、土蔵、関宿旅籠玉屋歴史資料館:玉屋は今なら高級旅館・安藤広重「東海道五十三次」にも描かれる・広い土間は台所・離れは欄間等高級特別室、深川屋ふかわや寛永年間創業和菓子屋・和三盆:こしあんをぎゅうひで包み白くまぶし鈴鹿の峯に積もる雪に見立てた、関の戸:荷担箱、西の追分:左大和街道・右東海道鈴鹿、
沓掛の集落、のどかな田園風景、
坂下宿、街道有数の宿場、大竹屋本陣跡:大本陣、岩屋観音:高さ18m巨岩に掘られた穴に3体石仏安置、古町(旧坂下宿):1650年代洪水壊滅、サツキ、
片山神社、鈴鹿権現・鈴鹿明神・峠越え安全祈願、3常夜灯:享保・文化・延享、ここから鈴鹿峠越え急坂八丁27曲がり約1km、「ほっしんの初にこゆる鈴鹿山」松尾芭蕉、「憂き世をよそにふり捨てていかになりゆくわが身ならなむ」西行、頂上手前広場は茶屋跡、寛永期8軒茶屋、
鏡岩、茶屋跡から脇道進むと鏡岩:姿見伝説・盗賊見張り場伝、田村神社跡:征夷大将軍坂之上田村麻呂鬼女または山賊退治伝説、
鈴鹿峠、茶畑、土山町立歴史民俗資料館、茶壷、一大産地、
万人講常夜灯:巨石3千人奉仕造った、穏やか坂道、鈴鹿馬子唄、一里塚緑地、のどかな田園風景、
田村神社:土山宿入口:坂之上田村麻呂鬼女退治伝説:厄除け、
土山宿:あいの土山のあいは坂下と相対するか間の宿からという、古代から近江と伊勢を結ぶ交通の要衝、土山本陣、関札多数保存、宿帳、上段の間、街道分岐点多し、石道標、御代参街道は伊勢参拝後の多賀大社参詣利用・あんらく峠・豊臣秀吉も通行、
箱根、小夜の中山、鈴鹿峠を紹介している。いつか行ってみたくなる光景だ。もっとも古道らしいところをうまく見せている。歴史的紹介も手際よい。
○・『歴史の道百選 東海道 第1巻 箱根路』(箱根湯元~箱根峠~三島宿)約35分
箱根旧街道は小田原宿から芦ノ湖畔、箱根宿を経て箱根峠を越えた三島宿までの八里30kmで、遺跡や石畳が多く歴史の面影が色濃く残る古街道である。
箱根湯本、小田原から4km、早川に架かる三枚橋からはじまる。~早雲寺:北条早雲遺言で作られた、北条文化、北条五代の墓、北条早雲像、枯山水香爐峰(北条幻庵作)、鳴き方独特ヒメハルゼミ~正眼ショウゲン寺、地蔵信仰、石仏石塔、曽我堂、曽我五郎槍突石、箱根旧街道、ハコネサンショウウオ~大沢坂、石畳、江戸期のもの~、 1’18”経過開始
畑宿、箱根寄木細工発祥地、シーボルト絶賛、間の宿 ~畑宿の一里塚、23里目、石畳、排水路の石畳~甘酒茶屋~お玉坂、1702年処刑~、6’32”
お玉ヶ池、那津奈可池なづながいけと言われていたが関所破りで処刑されたお玉にちなんで名がついた~白水坂(城見ず坂)秀吉軍勢が北条軍から攻撃受け城を見ずに退却したため伝~天ヶ石坂~休憩広場:二子山展望、♫箱根馬子唄♬~権現坂、ここから下り坂、芦ノ湖~湯坂道(鎌倉古道)、アジサイ、芦ノ湖~、11’06”
箱根神社、もとは箱根権現、関東の鎮護神、山岳信仰、18’19”
箱根杉並木、650m区間残存、樹齢350年の杉は生育に適さない松から植え替えられたと推定される、 19’17”
箱根関所跡、昔山裾が芦ノ湖に最も迫っていた場所に設置、箱根関所資料館、20’37”
箱根宿、幕府が小田原と三島から50戸ずつ移住させて開設、今も町名に小田原町、三島町が残るが往時の面影はない、本陣跡:箱根ホテル前の楓の木:樹齢400年~芦川の石仏~向坂~ 、21’47”
箱根峠、西坂、箱根竹、元はキセルの原料で箱根峠道に敷いていたが労力が大変なので石畳にしたという~兜石坂~施行平、ウツボグサ、ホタルブクロ~念仏石、自然石に南無阿弥陀仏と刻む~願合寺の石畳、ニホンミツバチの巣~雲助徳利の墓~、23’01”
山中城跡、畝堀、北条氏築造、秀吉小田原征伐落城、障子堀、本丸跡、矢立の杉~宗閑寺、豊臣と北条武将の墓~富士見平、「霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き」芭蕉~上長坂地区の石畳~こわめし坂、馬頭観世音~錦田の一里塚、約1km松並木~ 28’06”
三島宿、江戸から12番目、旅籠屋多く70~80軒、樋口本陣門(円明寺)、世古本陣門(長園寺)、三島宿風俗絵屏風:三島信用金庫蔵~三島御殿神社:御殿の屋敷神~三嶋大社~ 31’43”
○・『歴史の道百選 東海道 第2巻 小夜の中山道』(島田宿~大井川~日坂宿)約34分
川留めでも賑わった島田宿から越すに越されぬ大井川を渡り金谷宿を経て小夜の中山峠越えで日坂宿への行程。徳川幕府政策により大井川には徒歩渡りしか許可しなかった。
島田宿、最大28日間の川留め記録がある。松尾芭蕉も4日間川留めされた。~大井川川越遺跡:川会所(川越業務を管理運営した所)・蓮台・~塚本家跡:松尾芭蕉逗留・連歌「やわらかにたけよことしの手作麦」如舟「田植とともにたびの朝起」芭蕉~朝顔の松:「朝顔日記」近松門左衛門作~ 1’18”経過開始
大井神社、島田宿氏神、川越安全祈願、土手石垣・平石橋・川越制度廃止後失業した人足や幕府役人は牧之原開墾茶農家 5’09”
大井川、川越人足、川越し制度1696年、~蓬莱橋:1879年完成の木橋~ 6’14”
金谷宿、東橋、川留めでも栄える、川を渡ると水祝いと称して酒を酌み交わしたという、佐塚本陣跡、~不動橋:宿西木戸~金谷坂:平成石畳復元、すべらず地蔵:平成~牧之原公園:周辺茶畑~ 8’12”
諏訪原城跡、1569年信玄砦築く、甲州流築城術、1575年家康によって落城、本丸跡~菊川坂(菊坂):石畳復元~ 13’29”
菊川の里:間の宿、頼朝・藤原宗行・日野俊基等が通った、詩碑、石道標:遠江三十三箇所観音霊場巡り、 14’52”
久延寺、山内一豊が境内に茶室を設け関が原に向かう家康を接待したという、そのとき利用した御上井戸、家康手植え五葉松、 19’05”
小夜の中山公園、歌枕名所:「年たけてまた越ゆべしとおもひきやいのちなりけり小夜の中山」西行・「旅寝するさよの中山さよ中に鹿ぞなくなる妻や恋しき」橘為仲朝臣、狭い谷さやが語源、~小夜鹿サヤカの一里塚~涼み松:「命なりわずかの笠の下涼み」芭蕉~夜泣き石跡:安藤広重「東海道五十三次日坂夜泣き石図」レリーフ、2つの夜泣き石:小泉屋裏と久延寺、夜泣き石伝説・山賊に殺された妊婦の子が飴で育ち仇を取った等~扇屋:子育て飴・川島ちとせ~沓掛七曲り:急坂~ 20’58”
日坂宿、旅籠屋33軒の小さい宿場、本陣扇屋跡、1852年大火、~相伝寺:秋葉山常夜灯:天保十・槙の木~旅籠:川坂屋:大火直後建物で江戸期唯一残る~常現寺:1501年創建・旅人の無縁仏多し~ 28’41”
○・『歴史の道百選 東海道 第3巻 鈴鹿峠越え』(関宿~鈴鹿峠~土山宿)約35分
三重県と滋賀県境の鈴鹿峠、東の箱根と並び難所、
関宿、関町、日本書紀にも名がある関、47番目宿、東の追分:伊勢神宮一の鳥居、伊勢別街道分岐15里、20年に一度のせき年新宮、石道標、建立・行基伝:地蔵院・愛染堂:重要文化財、地蔵院庭園、瑞光院、権現柿、ご馳走場:地元役人等出迎え用、東西1.8km宿場町歴史的景観保存、むくり屋根:楕円形屋根、塗籠(ぬりごめ):土蔵風漆喰塗り、環金具、揚げ店(ばったり)、関まちなみ資料館、町屋建築、箱階段、部屋三間、裏庭、土蔵、関宿旅籠玉屋歴史資料館:玉屋は今なら高級旅館・安藤広重「東海道五十三次」にも描かれる・広い土間は台所・離れは欄間等高級特別室、深川屋ふかわや寛永年間創業和菓子屋・和三盆:こしあんをぎゅうひで包み白くまぶし鈴鹿の峯に積もる雪に見立てた、関の戸:荷担箱、西の追分:左大和街道・右東海道鈴鹿、
沓掛の集落、のどかな田園風景、
坂下宿、街道有数の宿場、大竹屋本陣跡:大本陣、岩屋観音:高さ18m巨岩に掘られた穴に3体石仏安置、古町(旧坂下宿):1650年代洪水壊滅、サツキ、
片山神社、鈴鹿権現・鈴鹿明神・峠越え安全祈願、3常夜灯:享保・文化・延享、ここから鈴鹿峠越え急坂八丁27曲がり約1km、「ほっしんの初にこゆる鈴鹿山」松尾芭蕉、「憂き世をよそにふり捨てていかになりゆくわが身ならなむ」西行、頂上手前広場は茶屋跡、寛永期8軒茶屋、
鏡岩、茶屋跡から脇道進むと鏡岩:姿見伝説・盗賊見張り場伝、田村神社跡:征夷大将軍坂之上田村麻呂鬼女または山賊退治伝説、
鈴鹿峠、茶畑、土山町立歴史民俗資料館、茶壷、一大産地、
万人講常夜灯:巨石3千人奉仕造った、穏やか坂道、鈴鹿馬子唄、一里塚緑地、のどかな田園風景、
田村神社:土山宿入口:坂之上田村麻呂鬼女退治伝説:厄除け、
土山宿:あいの土山のあいは坂下と相対するか間の宿からという、古代から近江と伊勢を結ぶ交通の要衝、土山本陣、関札多数保存、宿帳、上段の間、街道分岐点多し、石道標、御代参街道は伊勢参拝後の多賀大社参詣利用・あんらく峠・豊臣秀吉も通行、
2012年02月05日
久能街道(大谷←→駒越←→鉄舟寺)
久能街道(大谷←→駒越←→鉄舟寺)
・序文
久能山東照宮道の後半部分である。前半は近世東海道伝馬町の西之宮神社や伝馬町小学校近くの石碑辺りから南下し高松交番までである。消失したところもあるが、残存部らしきもある。
後半は高松交番で東に向きを変える。ここから東大谷や西平松バス停辺りまで区画整理され直し旧道は消滅した。久能山東照宮入口まで旧道は一定の幅(車が通れる広さ)でまっすぐではないが、それでも曲がりを抑えたストレートな通りといえる。
この道はいつ作られたのだろう。明治20年代にはすでに旧道がメインストリートとして使われていたことは分かる。旧道より北に時々路地が現れるが、だいぶ狭く紆余曲折している。江戸時代初期に家康の葬儀が通過し石蔵院前で舎人が殉死したことは知られている。おそらくこの葬儀の列は旧道を通ったのではなかろうか。もしかするとこの葬儀のために拡幅工事をしたのかもしれない。
東照宮入口より東へは一旦東照宮鳥居前参道に入ってから東に向きを変え狭い道を上り勾配で東に進む。この道は先ほどの道より曲折し狭く勾配もきつい、古道の趣がある。おそらく東照宮より先の道なので葬儀に関係ないので拡幅等を行わなかったためなのか。
久能山東照宮道が高松の交番にて東に経路を変える。
・薬師堂(高松公会堂裏)
高松交番の西南にある。鳥居、石塔:「奉納大乗妙典六十六部…文化五戌…」、他全4基、手水鉢:「大正十三」、地蔵2基、大日如来、社、祠、「庚申塔文政十三年…」。
広い車道は東に直角に曲がるが、旧道は車道の南裏にあり、南裏路地として東進する。大谷から久能、駒越、さらに鉄舟寺までの歴史遺産と道を紹介したい。
大谷川橋を渡り、南6軒先に格好屋商店がある。
・格好屋商店(大谷2265)
元回漕問屋で大谷港からの物資を配送していた。東京から格好良い物を仕入れていたので屋号になった。岩崎氏宅。11年4月周辺は区画整理され直し西側角の大村酒店は営業しているが、格好屋や他の店は見当たらず、新しい家ばかりである。
付近には西から「格好屋橋」「隠居橋」「郷蔵橋」の橋があった。川は暗渠で道となり橋の面影もない。東大谷あたりまで区画整理され直し旧態はない。
旧道は広くなった大谷街道交差点で消失する。ここから八坂神社に向かう旧道辻の地蔵祠前に出る。旧道より古い道は車道より北を通っていたかもしれないと思う。
・八坂神社(大谷)
創建不詳、棟札1672,1854年、元牛頭天王社、樹木100~300年、石鳥居:明治二十九年建造昭和六十二年再建、石灯籠:元和三1617年、慶安元1648年、手水舎:文化三1806年。
・海岸山大谷不動明王、加羅倶利堂(大谷)
地蔵祠東先を左折するとアスレチック広場のある大谷不動の山に行ける。参道途中に庚申塔等の石塔14基、地蔵7基が安置されている。大谷不動の由来は漁師が漁をしていて網にかかったのが石仏で、それを祀ったものだという。大谷不動の西側には地蔵堂(地蔵、大日如来)がある。歯痛封じの地蔵である。倶利伽羅堂という。石灯籠:元和二年、六地蔵、80cm×1.5mの台石。
・東大谷地蔵尊、祠(大谷25611→移転、東200m)
『久能山東照宮道』や『大谷街道』参照。2011年4月細かった道は広く付け直され、旧道のルートも付け直され周辺も区画整理されて新しい家ばかりで、旧態がほぼない。地蔵は東に移転した。
説明版「宝永六巳丑(1709)年より宮小路入口、行部沢家の屋敷内に祀られていましたが東大谷・西大谷の区画整理に伴い東大谷山田喜代司様こう様の御寄進により土地を譲り受け移転安置し供養する。大正寺 平成二十一巳丑(2009)年三月吉日」
この2年前1707年に宝永地震があり、それへの供養の意味があったのだろうか。
・祠、お堂(東大谷)
山際にある。かつては各個人宅の裏で祀られていたものであろうが、区画整理で山際に新道ができ見つけやすくなったというものか。
・かわなび、静岡市治水交流資料館
大谷川放水路(後久川)河口の東側で東西大谷公民館隣で放水路の操作場にある。七夕豪雨等について知ることができる。現代の施設だが、歴史資料に触れられる。
・釜屋、篠田氏宅(大谷2726)
東大谷バス停を通過した先、篠田氏宅がかつての田中助右衛門鋳物工場:釜屋跡である。区画整理で旧態がない。
・大谷港跡(大谷2508)、浜橋付近
大谷境バス停を南へ行くと浜橋になる。この付近がかつて駿府への荷をあげ降ろしていた港で、格好屋が問屋だった。区画整理で旧態がない。
・慈恵院慈恵観音教(西平松63)
西平松バス停前。この付近から旧態をたどれる。
・西平松閻魔堂、西平松公民館・老人つどいの家
説明版「久能街道沿いに江戸時代からあり、通行人の休憩所と安全を願う場所。毎年8月14日祭り。閻魔大王坐像中心、十王坐像、脱衣婆坐像、地蔵菩薩立像、司命立像、司録立像、計15像。」
・たい泉寺(西平松183)、(たいは小偏に台つくり、小台)
久能街道から左折(北)し山に向かう。山すそにある。
・天羽衣神社(西平松175)
久能街道を横切る橋を渡り山に向かい北に進むと山すそにある。三保とは違う伝説をもつ神社である。説明看板、伝説:「中平松に住む男が仕事帰りに駒越の浜の松に掛かる羽衣を見つけ家に持ち帰った。天女は取り返すため素性を隠しその男の許に行き仕えた。三年後隙を見て羽衣を取り返したが霊力が尽きていたのでお清めをしているところを見つかった。天女は事情を語り氏神として祀れば永く守護すると誓い天に帰った。そこで村人は氏神として祀ったという。」石灯籠、狛犬:近代。
・江雲寺(西平松170)
石塔26:「奉納 観 供養 安政五 七月壱日」「奉納 善光寺如来 明治三 三月」「奉巡拝 善光寺如来 一国三十三所 當村 明治十八年三月吉日」「奉順禮一国三十三所観 信州善光寺 天保六 七月七日」「奉順拝 一国三十三 信州善光 天保十五 七月」「奉順禮一国三拾三所供養 明治三 七月」「奉納 本州三拾三所観世音 信州善光寺 供養 文政十三寅年 七月上」「奉順拝 西国三拾 天保十五 七月」「奉納西国三十三所観世音菩薩供養 寛政四子年 五月十七日」「奉順拝 本州三十三所観世音 信州善光寺 供養塔 文政元」「奉納西国三拾三所 文政十一子年」「 寛 」「三十三所」「三界萬霊 文政六」「前住貞岳 」「詳鶴祖瑞□肴 寛保二」「三界萬霊」「圓寫稍瑞岳□ 文化十三」「――女 明治十――」「西国三十三所 安永」「西国秩父坂東供養塔 安永四」、比丘尼の墓?:「 五 」「 天保五 」
「奉納壱國三十三所」「奉納壱國三十三所」「奉順拝西国三十三所 天保十五 七月」「三十三所」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺 」「奉順禮一国三十三所 信州善光寺」「奉順拝一国三十三所」。
六地蔵:「文政十三」
・道祖神(中平松)
石造り道祖神。消防第13分団小屋隣。
・龍珠院(青沢39)青沢公民館、青沢老人つどいの家
久能街道を東進し殿谷川を渡ると青沢であり、北側2~3番目の路地を北に進むとある。記念碑もある。
青面金剛祠、地蔵、庚申塔3:「卍庚申供養塔 萬延」石塔、手洗石、板碑、石塔12?:「――三拾――等」「西国三拾三処」「奉□□□三拾」「奉順礼一国三十三」「――三十三所」「西国三十三所供養」「一国三十三所供養」
・八幡宮(古宿14)
久能幼稚園前を過ぎ、川も過ぎると古宿であり、すぐ山側に左折し北進するとある。石灯籠「弘化」。手洗石「明治十八年」。すぐ横を「すんぷゆめひろば」へ行く新道が通り周辺の様子は変貌している。
・継全寺(古宿29)
古宿バス停を過ぎ左折し進むと山すそにある。石塔3:「大乗妙典供養」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺 明治三拾□ □月吉日」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺 供養塔 七月吉日」、石塔9:「奉納西国三十三所霊場供養塔 寛政六寅 四月吉翔日」「奉順禮一国三十三所霊場供養塔 寛政六卯寅八月吉日」「奉順―――供養」「奉順拝信州善光寺如来
―――三十三所供養塔」「奉順禮一国三十三所」「奉納西国三拾三所観世音供養塔 天保十二 七月」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺 供養塔 明治三十九」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺」
この辺りの人々は西国三十三所や一国三十三所を回り、お礼参りに信州善光寺に行くことが一般化していたようだ。
・地蔵堂
地蔵2、庚申供養塔3、継全寺門前の古い生活道路沿い(おそらく江戸期初期以前の旧道)の分岐点にある。
・阿弥陀堂(安居55)
石塔3:「宝暦」、どうも墓石らしい。
・安居山石蔵院(安居272)
久能小や久能JAを過ぎ古安川を渡り、安居バス停をも過ぎると、左にある。お葉付き公孫樹(葉がついたまま結実することが珍しい)が有名。家康が崩御したとき慕う武士が門前で殉死したことでも知られる。
井出八郎右エ門墓(殉死した舎人、下級武士)、顕彰碑、地蔵堂
その先に神社がある。
・安居神社(安居288)
街道を左折するとすぐ参道でその先に拝殿がある。創建不詳、再建文化元年(1875)、句碑?:判読不能、石灯籠:「安古大明神 元和二」2、立派な物で刻字もはっきり読める。徳川家康が死んだ年で江戸期初期の物がいまだに健在であることから、しっかり保存されたか、それなりの高級品であると推察される。江戸幕府が家康死去に際し高級品を奉納したのか。ソテツ2、
隣は寺である。
・宝台院別院(安居291)
宝台院自体は静岡駅前、常盤町2丁目にある静岡市を代表する古刹にして名刹である。本院は家康の守り本尊を祀ってあり、家康の変わりに矢を受けた傷もかつてはあったが、修理してしまい矢傷はなくなってしまったという。家人の野上氏より聞いた話である。他にも家康の妻で秀忠の母の西郷の局の墓もあるなど、寺宝は貴重だ。
ここはその別院である。
柳沢川を渡ると、左の山に東照宮が見える。
・柳澤橋:石碑
橋の袂に古い石碑がある。
・廃道のかつての日本平ハイキングコースだった所、一応立ち入り禁止
柳沢川に沿って上っていく林道があり、林道がなくなってからは、歩けそうな所を行くと、入り込んだ人たちによりかすかなコースが設定?されている。一種の裏本のような裏コース登山報告や知っている人たちの道案内で登山可能である。建前上、一応危険なため立ち入り禁止である。1970年代の豪雨により、日本平ロープウェイ駅前から久能へのハイキングコースががけ崩れで歩行禁止となった。その他にも多くの日本平周辺コースが廃道となっていて、冒険好きは冬に入り込むチャンスではある。ただし自己責任です。
・久能山東照宮(根古屋390)
家康が崩御して最初に埋葬されたところである。日光にはのちに祀り直された。しかし全国的には日光は知られていても、静岡市にあることはほとんど知られていない。石段で行くもよし、日本平からロープウェイで行くもよしである。かつては武田氏の久能山城があり、勘助井戸が残る。それ以前は名刹古刹の久能寺(現鉄舟寺)があった。現在東照宮、博物館があり、家康権現を祀った石造物もある。神社は国指定重要文化財になった。
麓には梅園、売店など門前町の風情が漂う。
・徳音院(根古屋392)
東照宮参道石段入口前にあり、かつての東照宮の別院寺院だったが、寺院は明治になり廃止されお堂(一聖天堂、他一堂)だけが残った。石灯籠「両大師」
・八幡宮(根古屋318)
参道途中の売店「かどや」で東に曲がり進むのが、かつての旧道ルートである。老人ホーム(かつての保養所久能荘)の裏にある。石灯籠:「元和二」2、立派な物で刻字もはっきり読める。先ほどの安居神社の物と同類と推察される。これも高級品の奉納物か。
旧道はホテル横の滝が原川を渡り住宅のある所を少し上り、また下って現在の旧国道に合流する。ここまでが古街道らしさが残っている。
・白髭大明神神社(清水区蛇塚120、中組)
さらに東進すると久能街道と旧国道150号線が合流し、その先で清水区となる。さきの八幡宮からの道も滝ヶ原川を渡り清水区に入る。唐津川手前の道を北に進むと神社がある。
なお現在の国道150号線バイパスは海岸沿い堤防上のサイクリングロード上になっている。
祠、鳥居「明治元年」
・お堂、蛇塚公会堂(清水区蛇塚221、中組)
石塔類12:「文政八年 奉納西国三十三所供養塔」「文政九年 蛇塚 奉納西国三十三所供養塔 七月吉日」「元禄十七甲申天 奉納西国三十三所供養塔 願主蛇塚村」「宝暦十二壬 ――助譽是心大徳 三月二 」「奉納當国三十三所蛇塚村 元文元辰七月朔日 同行」「奉順禮當国三十三所観世音」「□奉禮念大悲観世音――西国三十三所」「圓寂全得――」(墓?)「――供養塔 蛇塚」「奉順禮當国三十三所観世音」「宝暦三 禅□信士心 十二月三――」(墓?)等
・龍宮神社(清水区蛇塚382、新田原)
さらに400m東進すると神社というかお堂がある。説明板碑の概略:「明治4年、古老の古記書による。正安元(1299)年五月中頃、海を漂流してきたものが漁網にかかる。木像あり。社建て祀る。信心すると御利益が増したので、社を造営すること数度に及んだ。古記書は先年の大時化で消失した。」
・龍源寺(清水区増114)
濁沢川を渡りしばらくすると増集落となる。やや山沿いに古い道が曲がりくねりながら通っている。そこに寺がある。石造物:地蔵2。
いったん国150号に戻り進むと左山手に神社がある。
・伊勢神明社(増206)
人家の出入り口付近から左への山道を歩いて上る。
・石塔(増259)
国道沿い人家の石垣壁沿いに安置されている。
石塔3:「奉請庚申供養寶塔敬白」「□百所之観世音菩薩 宝永三丙戌歳□秋廿日 増村居住同行 笏(竹冠なし)現 伊右門 忠右衛門 太郎兵衛 忠三郎」「奉納西国三十三所 」
・清苺神社、記念碑「石垣いちご発祥の地」(増260)
新しい神社なのだろうか。これまた人家の横から「ヘレン・ケラー来園」の看板に沿って農道を上る。横に記念碑「石垣いちご発祥の地」がある。
・萬象寺(駒越西二丁目9)
かつてはこの地ではなく、もっと東の駒越中1~2丁目辺りの古びた五輪塔が多くある所であった。移転したためか常夜灯が古いくらいで他の石造物で古い物が少ない。
・鉄砲道(駒越西二丁目17)
萬象寺前の国150号線向かい裏に舗装のない歩道というかあぜ道がある。これがかつての鉄砲道といわれる。久能街道の古道残存部とも考えられる。
幕末から明治初期の海岸警備隊や軍隊が鉄砲練習の行き帰りに使った道という。
鉄砲道から駒越神社の南に出る道がかつての久能道古道であろうか。
* 駒越神社、延命地蔵堂、大公孫樹、その先の久能街道駒越出発点については、「久能街道駒越ルート」を参照されたい。ここで駒越ルートに接続した。
ここから先は萬象寺辺りから北進して鉄舟寺に至る「久能寺観音道ルート」への接続ルートを紹介していく。
萬象寺の西の柑橘試験場や清水社会福祉事業団前を通過する道は山すそを掘って水平直線にした道で明らかに新道だが、かつては山すそに沿って曲がりくねる細い道があったはずだ。また萬象寺の東のもう少し低い所を通る道もあったと思う。両方とも開発され古い道はなく直線化した車道となっている。どのみちこの先の忠霊塔公園東入口または西に向かうだろう。
・忠霊塔公園(迎山町1)
・殿沢の古墳
殿沢から清水病院前辺りに抜けるのだろうが、ルートをたどることはできない。この辺り旧道が分からない。
・天王山神社、筆塚、天王山公園、古墳(宮加三789)
古墳で神社で目印になるランドマークだ。
ここから古い観音道は左斜め上(北西)に進んでいく。東邸の西から旧日本平道路(日本平アウスタ道路)を横切り、北進する。このルートが旧観音道と思われる。
・龍華寺(村松2085)
庭がきれいで有名。高山樗牛の墓もある。
門前を南北に通過する道が観音道である。ここから鉄舟寺に至るのだが、道に沿っていったん広い新道に出て鉄舟寺に至るのか、もう少し山際を通って鉄舟寺に至るのかが分からないが、どちらかあるいは両方がルートだったと思われる。山際ルートは幾分たどれるが鉄舟寺までは通れない。
・鉄舟寺(村松2188)
* 「久能寺観音道」、「安倍七観音霊場巡り」を参照。
・序文
久能山東照宮道の後半部分である。前半は近世東海道伝馬町の西之宮神社や伝馬町小学校近くの石碑辺りから南下し高松交番までである。消失したところもあるが、残存部らしきもある。
後半は高松交番で東に向きを変える。ここから東大谷や西平松バス停辺りまで区画整理され直し旧道は消滅した。久能山東照宮入口まで旧道は一定の幅(車が通れる広さ)でまっすぐではないが、それでも曲がりを抑えたストレートな通りといえる。
この道はいつ作られたのだろう。明治20年代にはすでに旧道がメインストリートとして使われていたことは分かる。旧道より北に時々路地が現れるが、だいぶ狭く紆余曲折している。江戸時代初期に家康の葬儀が通過し石蔵院前で舎人が殉死したことは知られている。おそらくこの葬儀の列は旧道を通ったのではなかろうか。もしかするとこの葬儀のために拡幅工事をしたのかもしれない。
東照宮入口より東へは一旦東照宮鳥居前参道に入ってから東に向きを変え狭い道を上り勾配で東に進む。この道は先ほどの道より曲折し狭く勾配もきつい、古道の趣がある。おそらく東照宮より先の道なので葬儀に関係ないので拡幅等を行わなかったためなのか。
久能山東照宮道が高松の交番にて東に経路を変える。
・薬師堂(高松公会堂裏)
高松交番の西南にある。鳥居、石塔:「奉納大乗妙典六十六部…文化五戌…」、他全4基、手水鉢:「大正十三」、地蔵2基、大日如来、社、祠、「庚申塔文政十三年…」。
広い車道は東に直角に曲がるが、旧道は車道の南裏にあり、南裏路地として東進する。大谷から久能、駒越、さらに鉄舟寺までの歴史遺産と道を紹介したい。
大谷川橋を渡り、南6軒先に格好屋商店がある。
・格好屋商店(大谷2265)
元回漕問屋で大谷港からの物資を配送していた。東京から格好良い物を仕入れていたので屋号になった。岩崎氏宅。11年4月周辺は区画整理され直し西側角の大村酒店は営業しているが、格好屋や他の店は見当たらず、新しい家ばかりである。
付近には西から「格好屋橋」「隠居橋」「郷蔵橋」の橋があった。川は暗渠で道となり橋の面影もない。東大谷あたりまで区画整理され直し旧態はない。
旧道は広くなった大谷街道交差点で消失する。ここから八坂神社に向かう旧道辻の地蔵祠前に出る。旧道より古い道は車道より北を通っていたかもしれないと思う。
・八坂神社(大谷)
創建不詳、棟札1672,1854年、元牛頭天王社、樹木100~300年、石鳥居:明治二十九年建造昭和六十二年再建、石灯籠:元和三1617年、慶安元1648年、手水舎:文化三1806年。
・海岸山大谷不動明王、加羅倶利堂(大谷)
地蔵祠東先を左折するとアスレチック広場のある大谷不動の山に行ける。参道途中に庚申塔等の石塔14基、地蔵7基が安置されている。大谷不動の由来は漁師が漁をしていて網にかかったのが石仏で、それを祀ったものだという。大谷不動の西側には地蔵堂(地蔵、大日如来)がある。歯痛封じの地蔵である。倶利伽羅堂という。石灯籠:元和二年、六地蔵、80cm×1.5mの台石。
・東大谷地蔵尊、祠(大谷25611→移転、東200m)
『久能山東照宮道』や『大谷街道』参照。2011年4月細かった道は広く付け直され、旧道のルートも付け直され周辺も区画整理されて新しい家ばかりで、旧態がほぼない。地蔵は東に移転した。
説明版「宝永六巳丑(1709)年より宮小路入口、行部沢家の屋敷内に祀られていましたが東大谷・西大谷の区画整理に伴い東大谷山田喜代司様こう様の御寄進により土地を譲り受け移転安置し供養する。大正寺 平成二十一巳丑(2009)年三月吉日」
この2年前1707年に宝永地震があり、それへの供養の意味があったのだろうか。
・祠、お堂(東大谷)
山際にある。かつては各個人宅の裏で祀られていたものであろうが、区画整理で山際に新道ができ見つけやすくなったというものか。
・かわなび、静岡市治水交流資料館
大谷川放水路(後久川)河口の東側で東西大谷公民館隣で放水路の操作場にある。七夕豪雨等について知ることができる。現代の施設だが、歴史資料に触れられる。
・釜屋、篠田氏宅(大谷2726)
東大谷バス停を通過した先、篠田氏宅がかつての田中助右衛門鋳物工場:釜屋跡である。区画整理で旧態がない。
・大谷港跡(大谷2508)、浜橋付近
大谷境バス停を南へ行くと浜橋になる。この付近がかつて駿府への荷をあげ降ろしていた港で、格好屋が問屋だった。区画整理で旧態がない。
・慈恵院慈恵観音教(西平松63)
西平松バス停前。この付近から旧態をたどれる。
・西平松閻魔堂、西平松公民館・老人つどいの家
説明版「久能街道沿いに江戸時代からあり、通行人の休憩所と安全を願う場所。毎年8月14日祭り。閻魔大王坐像中心、十王坐像、脱衣婆坐像、地蔵菩薩立像、司命立像、司録立像、計15像。」
・たい泉寺(西平松183)、(たいは小偏に台つくり、小台)
久能街道から左折(北)し山に向かう。山すそにある。
・天羽衣神社(西平松175)
久能街道を横切る橋を渡り山に向かい北に進むと山すそにある。三保とは違う伝説をもつ神社である。説明看板、伝説:「中平松に住む男が仕事帰りに駒越の浜の松に掛かる羽衣を見つけ家に持ち帰った。天女は取り返すため素性を隠しその男の許に行き仕えた。三年後隙を見て羽衣を取り返したが霊力が尽きていたのでお清めをしているところを見つかった。天女は事情を語り氏神として祀れば永く守護すると誓い天に帰った。そこで村人は氏神として祀ったという。」石灯籠、狛犬:近代。
・江雲寺(西平松170)
石塔26:「奉納 観 供養 安政五 七月壱日」「奉納 善光寺如来 明治三 三月」「奉巡拝 善光寺如来 一国三十三所 當村 明治十八年三月吉日」「奉順禮一国三十三所観 信州善光寺 天保六 七月七日」「奉順拝 一国三十三 信州善光 天保十五 七月」「奉順禮一国三拾三所供養 明治三 七月」「奉納 本州三拾三所観世音 信州善光寺 供養 文政十三寅年 七月上」「奉順拝 西国三拾 天保十五 七月」「奉納西国三十三所観世音菩薩供養 寛政四子年 五月十七日」「奉順拝 本州三十三所観世音 信州善光寺 供養塔 文政元」「奉納西国三拾三所 文政十一子年」「 寛 」「三十三所」「三界萬霊 文政六」「前住貞岳 」「詳鶴祖瑞□肴 寛保二」「三界萬霊」「圓寫稍瑞岳□ 文化十三」「――女 明治十――」「西国三十三所 安永」「西国秩父坂東供養塔 安永四」、比丘尼の墓?:「 五 」「 天保五 」
「奉納壱國三十三所」「奉納壱國三十三所」「奉順拝西国三十三所 天保十五 七月」「三十三所」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺 」「奉順禮一国三十三所 信州善光寺」「奉順拝一国三十三所」。
六地蔵:「文政十三」
・道祖神(中平松)
石造り道祖神。消防第13分団小屋隣。
・龍珠院(青沢39)青沢公民館、青沢老人つどいの家
久能街道を東進し殿谷川を渡ると青沢であり、北側2~3番目の路地を北に進むとある。記念碑もある。
青面金剛祠、地蔵、庚申塔3:「卍庚申供養塔 萬延」石塔、手洗石、板碑、石塔12?:「――三拾――等」「西国三拾三処」「奉□□□三拾」「奉順礼一国三十三」「――三十三所」「西国三十三所供養」「一国三十三所供養」
・八幡宮(古宿14)
久能幼稚園前を過ぎ、川も過ぎると古宿であり、すぐ山側に左折し北進するとある。石灯籠「弘化」。手洗石「明治十八年」。すぐ横を「すんぷゆめひろば」へ行く新道が通り周辺の様子は変貌している。
・継全寺(古宿29)
古宿バス停を過ぎ左折し進むと山すそにある。石塔3:「大乗妙典供養」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺 明治三拾□ □月吉日」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺 供養塔 七月吉日」、石塔9:「奉納西国三十三所霊場供養塔 寛政六寅 四月吉翔日」「奉順禮一国三十三所霊場供養塔 寛政六卯寅八月吉日」「奉順―――供養」「奉順拝信州善光寺如来
―――三十三所供養塔」「奉順禮一国三十三所」「奉納西国三拾三所観世音供養塔 天保十二 七月」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺 供養塔 明治三十九」「奉順拝一国三十三所 信州善光寺」
この辺りの人々は西国三十三所や一国三十三所を回り、お礼参りに信州善光寺に行くことが一般化していたようだ。
・地蔵堂
地蔵2、庚申供養塔3、継全寺門前の古い生活道路沿い(おそらく江戸期初期以前の旧道)の分岐点にある。
・阿弥陀堂(安居55)
石塔3:「宝暦」、どうも墓石らしい。
・安居山石蔵院(安居272)
久能小や久能JAを過ぎ古安川を渡り、安居バス停をも過ぎると、左にある。お葉付き公孫樹(葉がついたまま結実することが珍しい)が有名。家康が崩御したとき慕う武士が門前で殉死したことでも知られる。
井出八郎右エ門墓(殉死した舎人、下級武士)、顕彰碑、地蔵堂
その先に神社がある。
・安居神社(安居288)
街道を左折するとすぐ参道でその先に拝殿がある。創建不詳、再建文化元年(1875)、句碑?:判読不能、石灯籠:「安古大明神 元和二」2、立派な物で刻字もはっきり読める。徳川家康が死んだ年で江戸期初期の物がいまだに健在であることから、しっかり保存されたか、それなりの高級品であると推察される。江戸幕府が家康死去に際し高級品を奉納したのか。ソテツ2、
隣は寺である。
・宝台院別院(安居291)
宝台院自体は静岡駅前、常盤町2丁目にある静岡市を代表する古刹にして名刹である。本院は家康の守り本尊を祀ってあり、家康の変わりに矢を受けた傷もかつてはあったが、修理してしまい矢傷はなくなってしまったという。家人の野上氏より聞いた話である。他にも家康の妻で秀忠の母の西郷の局の墓もあるなど、寺宝は貴重だ。
ここはその別院である。
柳沢川を渡ると、左の山に東照宮が見える。
・柳澤橋:石碑
橋の袂に古い石碑がある。
・廃道のかつての日本平ハイキングコースだった所、一応立ち入り禁止
柳沢川に沿って上っていく林道があり、林道がなくなってからは、歩けそうな所を行くと、入り込んだ人たちによりかすかなコースが設定?されている。一種の裏本のような裏コース登山報告や知っている人たちの道案内で登山可能である。建前上、一応危険なため立ち入り禁止である。1970年代の豪雨により、日本平ロープウェイ駅前から久能へのハイキングコースががけ崩れで歩行禁止となった。その他にも多くの日本平周辺コースが廃道となっていて、冒険好きは冬に入り込むチャンスではある。ただし自己責任です。
・久能山東照宮(根古屋390)
家康が崩御して最初に埋葬されたところである。日光にはのちに祀り直された。しかし全国的には日光は知られていても、静岡市にあることはほとんど知られていない。石段で行くもよし、日本平からロープウェイで行くもよしである。かつては武田氏の久能山城があり、勘助井戸が残る。それ以前は名刹古刹の久能寺(現鉄舟寺)があった。現在東照宮、博物館があり、家康権現を祀った石造物もある。神社は国指定重要文化財になった。
麓には梅園、売店など門前町の風情が漂う。
・徳音院(根古屋392)
東照宮参道石段入口前にあり、かつての東照宮の別院寺院だったが、寺院は明治になり廃止されお堂(一聖天堂、他一堂)だけが残った。石灯籠「両大師」
・八幡宮(根古屋318)
参道途中の売店「かどや」で東に曲がり進むのが、かつての旧道ルートである。老人ホーム(かつての保養所久能荘)の裏にある。石灯籠:「元和二」2、立派な物で刻字もはっきり読める。先ほどの安居神社の物と同類と推察される。これも高級品の奉納物か。
旧道はホテル横の滝が原川を渡り住宅のある所を少し上り、また下って現在の旧国道に合流する。ここまでが古街道らしさが残っている。
・白髭大明神神社(清水区蛇塚120、中組)
さらに東進すると久能街道と旧国道150号線が合流し、その先で清水区となる。さきの八幡宮からの道も滝ヶ原川を渡り清水区に入る。唐津川手前の道を北に進むと神社がある。
なお現在の国道150号線バイパスは海岸沿い堤防上のサイクリングロード上になっている。
祠、鳥居「明治元年」
・お堂、蛇塚公会堂(清水区蛇塚221、中組)
石塔類12:「文政八年 奉納西国三十三所供養塔」「文政九年 蛇塚 奉納西国三十三所供養塔 七月吉日」「元禄十七甲申天 奉納西国三十三所供養塔 願主蛇塚村」「宝暦十二壬 ――助譽是心大徳 三月二 」「奉納當国三十三所蛇塚村 元文元辰七月朔日 同行」「奉順禮當国三十三所観世音」「□奉禮念大悲観世音――西国三十三所」「圓寂全得――」(墓?)「――供養塔 蛇塚」「奉順禮當国三十三所観世音」「宝暦三 禅□信士心 十二月三――」(墓?)等
・龍宮神社(清水区蛇塚382、新田原)
さらに400m東進すると神社というかお堂がある。説明板碑の概略:「明治4年、古老の古記書による。正安元(1299)年五月中頃、海を漂流してきたものが漁網にかかる。木像あり。社建て祀る。信心すると御利益が増したので、社を造営すること数度に及んだ。古記書は先年の大時化で消失した。」
・龍源寺(清水区増114)
濁沢川を渡りしばらくすると増集落となる。やや山沿いに古い道が曲がりくねりながら通っている。そこに寺がある。石造物:地蔵2。
いったん国150号に戻り進むと左山手に神社がある。
・伊勢神明社(増206)
人家の出入り口付近から左への山道を歩いて上る。
・石塔(増259)
国道沿い人家の石垣壁沿いに安置されている。
石塔3:「奉請庚申供養寶塔敬白」「□百所之観世音菩薩 宝永三丙戌歳□秋廿日 増村居住同行 笏(竹冠なし)現 伊右門 忠右衛門 太郎兵衛 忠三郎」「奉納西国三十三所 」
・清苺神社、記念碑「石垣いちご発祥の地」(増260)
新しい神社なのだろうか。これまた人家の横から「ヘレン・ケラー来園」の看板に沿って農道を上る。横に記念碑「石垣いちご発祥の地」がある。
・萬象寺(駒越西二丁目9)
かつてはこの地ではなく、もっと東の駒越中1~2丁目辺りの古びた五輪塔が多くある所であった。移転したためか常夜灯が古いくらいで他の石造物で古い物が少ない。
・鉄砲道(駒越西二丁目17)
萬象寺前の国150号線向かい裏に舗装のない歩道というかあぜ道がある。これがかつての鉄砲道といわれる。久能街道の古道残存部とも考えられる。
幕末から明治初期の海岸警備隊や軍隊が鉄砲練習の行き帰りに使った道という。
鉄砲道から駒越神社の南に出る道がかつての久能道古道であろうか。
* 駒越神社、延命地蔵堂、大公孫樹、その先の久能街道駒越出発点については、「久能街道駒越ルート」を参照されたい。ここで駒越ルートに接続した。
ここから先は萬象寺辺りから北進して鉄舟寺に至る「久能寺観音道ルート」への接続ルートを紹介していく。
萬象寺の西の柑橘試験場や清水社会福祉事業団前を通過する道は山すそを掘って水平直線にした道で明らかに新道だが、かつては山すそに沿って曲がりくねる細い道があったはずだ。また萬象寺の東のもう少し低い所を通る道もあったと思う。両方とも開発され古い道はなく直線化した車道となっている。どのみちこの先の忠霊塔公園東入口または西に向かうだろう。
・忠霊塔公園(迎山町1)
・殿沢の古墳
殿沢から清水病院前辺りに抜けるのだろうが、ルートをたどることはできない。この辺り旧道が分からない。
・天王山神社、筆塚、天王山公園、古墳(宮加三789)
古墳で神社で目印になるランドマークだ。
ここから古い観音道は左斜め上(北西)に進んでいく。東邸の西から旧日本平道路(日本平アウスタ道路)を横切り、北進する。このルートが旧観音道と思われる。
・龍華寺(村松2085)
庭がきれいで有名。高山樗牛の墓もある。
門前を南北に通過する道が観音道である。ここから鉄舟寺に至るのだが、道に沿っていったん広い新道に出て鉄舟寺に至るのか、もう少し山際を通って鉄舟寺に至るのかが分からないが、どちらかあるいは両方がルートだったと思われる。山際ルートは幾分たどれるが鉄舟寺までは通れない。
・鉄舟寺(村松2188)
* 「久能寺観音道」、「安倍七観音霊場巡り」を参照。
2011年10月22日
富士山表口村山登山道(村山古道)
1.松岡筋(富士市松岡~富士宮浅間大社~村山浅間神社)
2.吉原筋(富士市鈴川~吉原宿~村山浅間神社)
3.村山筋(村山浅間神社~中宮八幡堂跡~富士宮口新六合目~山頂)
以上3つのコースに分けて説明していく。
1.西から来た人は富士川を渡ったあと北に方向を変え、富士宮浅間大社(大宮)に参詣した後、村山浅間神社に向かった。
2.東から来た人は吉原宿から村山浅間神社に向かった。その前に田子の浦の水につかり、海岸の石を1個、富士塚に供えたという。大宮側からは大宮に寄らず登っていくので幾度も禁制の触れを出している。(おそらく有名無実)
3.以上1と2のコースが村山浅間神社で合流し、ここから本格的な登山がはじまった。というわけで本当は1と2のコースがあったというべきだが、ここでは便宜的に3つに分けた。これらの道を「道者(ドウシャ)道」という。
復活した村山古道は部分的に道というより野渓や廃道であるが、歴史文化財として指定し保存すべきである。
登山道区間は数年がかりで2006年に地元有志と畠堀操八氏はじめ登山仲間等の大変な努力によって再発見され整備され通行可能になった。まだ整備されきったわけではなくやっと人が通れる状態である。
*(付近)というのは、村山古道と直接関連がなくとも、通過する地域に関する地理歴史情報を提供する項目である。
1.松岡筋(富士市松岡~富士宮浅間大社~村山浅間神社)
この区間は「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八にも記述がなく、大まかなルート図が「富士山村山口登山道跡調査報告書」にあっただけで、私が推論してコースを立てたので正確ではないでしょう。しかしとにかくこの区間に切り込めたことが収穫でしょう。あとは後続の調査研究で直されればよいでしょう。
・水神社、石道標「冨士山道」 (富士市松岡)
東海道筋の富士川渡船場横にある。東海道に関する標識や看板があり歴史散策の地。昔は橋がなく松岡と岩淵の間は船で渡っていた。富士川本流がここを通るようになったのは近世以後で、神社北背後の雁堤(カリガネツヅミ)ができたことで、今の富士市街への流れをカットできたからである。石道標「冨士山道」が安置されている。昔はもっと東の分岐点にあったがここに移された。富士山道はここから東海道(県道、旧国道1号)を東進する。
しかし一旦南下し別の歴史物を見に行く。
・(付近)帰郷堤(キキョウツヅミ)、三重稲荷利神社(松岡四丁河原西、富士川堤防東岸)
水神社前の信号を南に向かい狭い道を富士川緑地方向に400m行くと、小さな神社と看板がある。ここの堤防の名と御利益豊富な神社の謂われが記入されている。この地が水害に悩まされていたことが分かる。
・石道標、秋葉山常夜灯(松岡)
あらためて水神社前を800m東進する。
東海道の標識と看板がある。本当はここまで来ると来過ぎで、もう1本50m手前の道を北に曲がる。
・雁堤(カリガネツヅミ)、護所(人柱)神社(松岡)
150m北進し道が合流分岐する手前左(西)の堤防上に護所(人柱)神社がある。上ってみれば堤防が見渡せ、晴れていれば富士山もよく見える。日本三代急流の一つ富士川の激流を止めるために水をソフトに受け止める工夫が、この雁堤(カリガネツヅミ)である。またこの工事を成功させるため人柱の犠牲があったことが記されている。歴史的事実かどうかは証明されないようだ。しかし幾度も失敗を重ねての困難な工事であったことが分かる。ここから2km北の山際突端の河原に一番ダシ、二番ダシ、三番ダシという真っ先に水を受け止める堤防に行くこともできる。祠が祀られている。雑草だらけかもしれず、歩くと遠い。
・石仏、石塔(松岡)
道がいくつも分岐するが、水路脇の北東に進む道を選び北進する。北の岩本山右(東)中腹を目指す。岐流橋を渡ると水路は左に離れる。道なりに直進する。
途中石仏(馬頭観音、供養塔かと思われるが丸石を載せ地蔵のよう)や石塔(実相寺の題目塔で参詣道を示す)に出会う。
・稲荷神社、山神社(松岡)
護所神社から北進1kmで、東名高速ガード下左に2つの神社が隣接してある。
・上堀橋(岩本)
東名高速ガード下から600mで道は直進不能で左右に曲がる。ここからどちらが古道か迷うので両方紹介する。
・右折し150mで左折すると橋を渡り、岩本山に登る道が正面にある。正面の上り道(車で登れる旧道)ではなく更に右の狭い道が古道らしい。上っていくと石仏がある。
・左折し上堀橋を渡ったらすぐ右折し川沿いを上っていく。150mで右折ルートと合流し、北東方向への住宅地の中の狭い道を上り、石仏に出会う。
古道を登ると広い新道と車で登れる旧道とに合流する。本当の古道は旧道側の左に入ってすぐ山上に上る狭い道かもしれない。また永源寺西の山に登る道かもしれない。車で通れる道のようなので車で通行するのが手っ取り早い。明治20年代の地図ではほぼ新道に沿って道がついているので、新道を北上すればよいようだ。旧道も新道も最終的には山本で合流する。
旧道未調査。
・(付近) 岩本山実相寺、永源寺、八面神社、琴平神社、岩本山公園
岩本山実相寺…
永源寺…
八面神社…巨樹
琴平神社…
岩本山公園…
・第六天神社(富士宮市山本)
ちょうど富士市岩本と富士宮市山本の境界線で新道と旧道は合流する。その先150m左(西)に神社がある。
・(付近)山本勘助所縁の地(山本)
山本勘助は武田信玄の軍師として知られる。出生地には異説(愛知県豊川市、豊橋市、豊田市)はあるが、この地、山本が有力である。その後三河で養子になったという。ただ初出の『甲陽軍艦』からして後世のものなのでどこまで信じていいのか。同時代の文書で「山本菅助」名がいくつか発見されているが、なぜ「菅」なのか、出生地の証明はとなると?である。
第六天神社を新道北40mで勘助史蹟の標識があり、双体道祖神もある。右折(東)し下っていくと勘助坂標識がある。勘助が子供の頃この坂で遊んだという。
第六天神社を北200mで右折(東)し500m下っていくと勘助母の墓、その先に勘助子孫の吉野家がある。長屋門は見事である。
・石仏(山本か黒田)
馬頭観音と他一基。新道沿いにある。
・石仏、石塔(黒田)
新道に戻り北進する。明星山入口(旧星陵高前)交差点バス停より200m先左(西)石塔類(単体道祖神、甲子神、馬頭観音、大日)がある。標識もあるので分かりやすい。昔はここから明星山に登ったようだ。
この先250mで黒田小学校に達し道は右カーブし富士宮市中心街に向かう。おそらくここにも昔は道標があったのだろうが、まったくそういう雰囲気はない。
・題目塔(黒田)
本光寺参道を示す。古い題目塔と新造の寺の名を示す石塔がある。
・題目塔、双体道祖神(田中町)
金谷橋で潤井川を渡ると左にある。
・常泉寺(東町)
門前石塔類。
・平等寺(東町)
山門、石塔類、鐘楼。
・大頂寺(東町)
虚空蔵堂(かつて富士山頂にあった仏像が廃仏毀釈で麓に預けられさらにこの寺に寄贈された。) 仏像がすべて破壊されたのではなく、このようにひそかに降ろされ寺に預けられたものもあるようだ。六地蔵。
・宗心寺(東町)
門前石塔類。
大頂寺方向へ西進し浅間大社まで行く。
・富士山本宮浅間大社(宮町)
湧玉池で禊をするのが正式であるが、触れればよいでしょう。背後が山でここが窪地となっているので、湧水するようだ。夏でも冷たく澄んだ水で水量が多い。この水が湧き出すからここに神社があり、町が発展したのだろう。
本殿(国重文)、信玄櫻、御神幸道道標、鳥居、石灯籠、赤心隊石碑、火山弾、鉾立石、桜の馬場。富士山頂8合目より上は当神社所有。全国の浅間神社の総本山。石碑「天然記念物 湧玉池」。
・福石神社(元城町)
湧玉池のある浅間大社東側道向かいにある。この神社前を東進する。道端の角に双体道祖神がある。
・萬松院(元城町)
大宮小学校を過ぎると北に寺が見える。門前に石仏も祀られている。
平等寺裏を過ぎた所で左折し北進する。
・山神社(若の宮町)
北進200m左に鳥居。
・石仏(舞々木町、市営舞々木墓地)
北進1.1kmで市営墓地を通過し、道沿いに新造の大黒のような布袋のような石仏。(無論古い村山古道とは直接関係ないですが、現代の村山古道周辺での石造物状況を知るためのよい参考資料でしょう。又後世への参考資料にしたいからです。例えば百年後にこの通りの石造物を調べたい人がいた場合、この資料はほぼ残らないでしょうが、万一にでも残存して、この平成期に作られた石造物を調べていて、ここに存在したことを証明する記事があれば、2011年に確かに存在したと証明できるではありませんか。これらの記述は遠い後世における歴史資料にしたいので載せています。)
・石道標「右 富士山道」(舞々木町)
墓地より北進300m、Y字路に石道標。
・石仏、「富士登山 満行供養塔」(大岩)
石道標より北進250mで舞々木橋を渡り今の広い道を北進せず、その1本左の川沿いの狭い道を北へ上がる。これが旧道と思われる。すぐ左に石仏がある。
「富士登山 満行供養塔」、地蔵、六地蔵、供養塔があり、富士登山との関連性を物語っている。北進してすぐ新道と合流。
・重林寺、石仏(大岩)
北進200mで広い道と合流。右に石仏(地蔵、題目塔)、その向こうに寺と門前の石塔類がある。
・大岩堤自然歩道、ビオトープ大岩(大岩)
北東進400m。右に以上のタイトルの歩道入口表示があった。未調査。大岩堤という池がありビオトープになっているようだ。(無論古い村山古道とは直接関係ないですが、大岩周辺の当たり前の自然環境がいかなるものだったのか知るにはよい参考資料でしょう。)
北東進600mで古い街道は二又という交差点に向かうため左斜めに上って行く(北進)。
・二又石塔(粟倉)
700m行って二又で右折を2回連続行い、東進する。ここに新造の石塔がある。昔から要衝の地だからかここで遠回りだが曲がっていく。
ドウシャ道は妙心寺入口で左折し狭い舗装路を北東に登っていく。
・妙心寺、石仏(粟倉)
当地に移転したばかりの寺のようだ。妙心寺門前で左折し狭い舗装路を北東に登っていく。道端途中石仏が祀られている。道なりに上に行く要領で進むとよい。
・粟倉観音堂、石仏、石塔・墓石?(粟倉)
旧国道469号線(新国道は別で今は県道か市道)沿い、富士根北公民館より北東へ400m左、堂内に石仏三体。敷地に10体の石仏石塔を祀り、懇切丁寧な説明版もある。
ここからさらに北東150mの交差点角に石塔か江戸時代中期頃の墓石かと思われるものが祀られているが、詳細?。
・「山辻の石畳」、「道者道ドウシャミチ」案内板(粟倉、村山)
妙心寺から人家を過ぎ配水池のある所の右に「山辻の石畳」の標識がある。コンクリ舗装路はこの先行き止まりである。右の「山辻の石畳」を歩く。地元の子供たちが石を埋めるなど整備して10年とたっていないがもはや廃道である。300m倒木・雑草・浮石・蜘蛛の巣のめちゃくちゃな中やっと通り過ぎると旧国道の舗装路、そのすぐ先に階段があり、上ると現国道469号線である。階段下に「道者道ドウシャミチ」案内板がある。階段を上り、国道をまたげば西見付への寸断された旧道である。元は幅一間(1.8m)の石畳道だったのだろう。石畳にしたのは後世だろう。ここが西見付に至る道者道で住民の主要生活道路だったのだろう。
ここにいるだけで廃道の古道、使われなくなり汚れていく狭い旧国道469号線の舗装路、車がビュンビュン走り抜ける広い現国道469号線の3つの道の栄枯盛衰を一目で見られる。それにしても石畳道はどうにかできないのだろうか。歴史文化財の価値は十分である。
・道者ドウシャ道の近道はないのか?
先ほど二又まで行って曲がってきた。正式にはそれがルートだろうが、明らかに遠回りである。歩くドウシャの中には近道する者はなかっただろうか。
私の勝手な推定路2パターン。
1.妙心寺前交差点から南西の丘向こうの墓地へ、墓地の南下の氏神神社前に出て、旧国469号へ西で合流しさらに南下の粟倉南町、舟久保町、粟倉境の五差路に合流する。
2.妙心寺前交差点から南西の真下に下りる道を進み下粟倉のT字路にぶつかり直進できないので、右折(西)し舟久保町の新興住宅地(もはや古道はないだろう)を何とか抜けて旧国469号へ出る。途中複数の石仏に出会える。
・西見付(村山)
石仏、西の番所と木戸の跡である。
・村山浅間神社(村山)
もとは神仏混合の修験道による興法寺であり、大日堂にその名残をとどめる。明治の廃仏毀釈により神社となる。もとは神主ではなく山伏の僧侶により運営されていたのだ。巨樹も多い。石仏も多い。護摩壇。水垢離跡。詳細は「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八:著を参照。
*この松岡筋に関しては岩本山山麓の山本を通らず東端の龍巌淵を通り天間から杉田へそして石原に向かうルートがあったようだ。
2.吉原筋(富士市鈴川~吉原宿~村山浅間神社)
このコースについては以下の3.村山筋同様、村山古道コースマップ(畠堀操八:著) ¥1000が必要です。しかもそれを持っていても初めてなのに下るということをやると、道迷いします。それは私です。初めて挑戦したとき富士市松岡に車を置き、自転車で岩本、山本、富士宮浅間大社、粟倉、村山浅間神社まで上り、そこから横沢、石原、大渕、伝法、吉原宿、鈴川へ下りました。下りは楽だと思いきや、いくつかの目印が探せず、付近で3人に聞いて市の境界線の「道しるべの5左村山道」の石道標を見つけ、又、迷った所(石原の「左の急坂を上る」)の坂上まで上り直すはめになるなど、相当体力と時間、気力をそぎました。それは登山道区間でなお顕著ですが、あくまでも上ることを念頭に作られているので、コースを知らず下ると目印を発見できません。人里なので迷うと思ってなかった私がバカです。特に分かりにくいのが、横沢から石原、次郎長町にかけてでしょう。「道しるべ6」から「左の急坂を上る」の上りきった所、「自販機の向こうを右へ」の辺りです。「道しるべの5左村山道」または「道しるべの4左村山道」を発見できればそこからはコースマップを見直せば正しいルートにすぐ復帰できます。付近の住民に「村山古道はどこ?」と聞いてもまったく通用しません。コースマップの写真を見せて「ここに行きたい」という方がよいでしょう。ちなみに自転車で鈴川に達し、さらに松岡まで戻ったら7時間かかりました。このときは粟倉の「山辻の石畳道」は歩いてなかったのですけど。
記事は下った道を上りに再構成しました。
*一部吉原宿辺りで近世東海道を通過するため、東海道のガイドブックを参照してもらってもよいです。
・浅間宮、富士塚(富士市鈴川)
富士登山をする者が海水で水垢離した後海岸の石を一つ置いていったものが積み重なって塚になったという。別説には、津波後の施し米のお礼として積み上げた。北条・武田・今川が対峙したときの天の香久山砦の跡。などの説もある。
鳥居前を直進して突き当たると石碑「皇太子殿下御散策之蹟」があり、左に元吉原中学校がある。戻るなら左折だが、海に行くなら右折する。
ここから海水に触れるには堤防の出入り口を越し、左折(東)していくとテトラポッドが切れて砂浜が少し見える。反対に西へ行くと田子の浦港の岸壁で立入不可となるのでむだである。
・閻魔堂、地蔵堂、石塔、黒露の墓(鈴川)
閻魔堂…閻魔像、地蔵
地蔵堂…地蔵
石塔…17基、観音、六地蔵、燈籠、
黒露の墓…黒露は江戸時代中期の俳人。
地蔵堂前の階段が古くは海に出る道で、南進して一度曲がって先の皇太子碑に出ればよい。
・木之元神社、古東海道(鈴川)
戻りは地蔵堂から東進60mで右の路地に入ると古東海道であり、木之元神社前に出る。御神水の碑、六角井戸、神木がある。神社上側の道を行く。近世東海道に出るにはその先を左折し広い道に出るが、おそらく古東海道は右折した路地のように少し高いところを東進していたのだろう。近世東海道側へ進む。広い道に出たらすぐにある踏切を越え線路に沿い西進し、JR吉原駅前で北西進していく。*(ここからは近世東海道に出たので、近世東海道のガイドブックと同一内容になる。) 河合橋を渡り国道1号線と新幹線のガードを斜め左に横断する。その先に静かな街並みがある。左富士神社のある中吉原宿跡である。
・(付近)阿字神社、妙法寺、富士と港の見える公園、三本松、毘沙門天妙法寺(鈴川)
阿字神社…近世以前の東海道は田子の浦を船で渡っていた。そのとき東岸側で安全祈願をした所の名残である。相当古い神社と考えられるが、これだけ海に近い所にあるためか古い物はない。(多分地震や津波で遺物は残りにくい) 里宮の裏の奥宮横に見付の井戸(ばば井戸)や見付宿跡説明板がある。かつていけにえの場所だったことがわかる。付近に仏舎利塔がある。
妙法寺…題目塔、石塔、日蓮像、ガンジー像、
富士と港の見える公園…現代の公園、展望台があり眺めは抜群。トイレや駐車場数台分ある。
三本松…元吉原中学校向かいにある。何の謂れか?
毘沙門天妙法寺…だるま市で有名、近世東海道筋にあるので歩くとちょっと遠い。
・中吉原宿跡、左富士神社(依田橋町)~近世東海道~
先ほどの鈴川や毘沙門天の辺りが元吉原宿であるが、津波で破壊され、この左富士神社から西の辺りに移転した。しかしここも津波で破壊され今の吉原本町の吉原宿に再々度移転した。(中吉原宿をはじめ元吉原宿、吉原宿の資料は富士市立博物館にある。)
*ここ以後しばらく近世東海道ルートなのでもっと詳しく知りたい方は東海道吉原宿近辺のガイドブックを読んでください。
・左富士(依田橋町)
東海道を東から西に行けば富士山は右に見えるのだが、この地だけは左に見えるので「左富士」と称され珍しがられた。東海道が一旦北北東を向くからである。左富士神社先の交差点に史蹟看板があり、松が植えられている。左富士の浮世絵レリーフもある。
・石仏(依田橋町)
左富士史蹟を過ぎて北進すると左に祠が見える。
・平家越し(新橋町)
橋を渡る所にある。平家が富士川沿いに陣取り羽音を源氏の攻撃かと驚き逃げ出したという伝説の地である。平家は羽音だけに驚いたのではなく、その前から源氏の陽動作戦で疑心暗鬼になっていたという説もある。ここはいまでは富士川ではないが、雁堤設定以前はここまで富士川が幾本かに分流して流れていたようだ。
・吉原宿、東木戸(吉原宝町)
近世に三度も宿替えをした宿場の最終地、現在も繁華街。
吉原本町駅…レトロな電車が走っていてマニアに受けるそうだ。
百地蔵尊…吉原本町駅目の前
鯛屋旅館…旅籠や、
下本陣跡…コンドウ薬局、上本陣…富士見会館、
脇本陣跡…ノグチカメラ、おもちゃのキムラ、オオイカメラ、岳南堂菓子舗、
問屋跡…メガネヤナセ、
長さん小路…この地で小青年期を過ごしたドリフターズいかりや長助を記念した通り。
・妙祥寺前題目塔、宿場の鍵の手(中央町一丁目)
ここで宿場通りは左折し妙祥寺に南下する。そこに題目塔がある。ここでまた右折し南西に向かう。
・(付近)日吉浅間神社、富知六所浅間神社
・日吉浅間神社…東泉院ははじめ浄土院といい、頼尊に属した僧によって創建。元は吉原公園にあり、移転を繰り返し現在地となる。西隣は六所氏屋敷跡地でさらに西に吉原公園となる。六所氏は近在の有力者で神社移転を行ったのも六所氏である。旧東海道の吉原宿から北進し出すとすぐ左に「旧順天堂田中歯科医院診療所兼主屋」(国登録有形文化財)の洋館と和館がある。その先の川を渡った所に「大日如来」がある。正面の「上和田子安地蔵尊」の左に神社がある。
富知六所浅間神社…大楠、東泉院の別当が管掌。楠(県指定天然記念物) 、火山弾。付近にカンカン堂がある。
・西木戸跡(中央町三丁目)~近世東海道~
ここで近世東海道から離れ右折し北西進する。
・馬頭観音、道祖神(伝法)
県道富士インター線の富士インター南の長者町西交差点より50m南の道路東側にある。新造のようだ。文字碑。付近の地下道入口花壇に道祖神2体(文字碑)がある。
ここから先の道路を横断し酒のアルコの北裏に北西進する。
・(付近)伊勢塚古墳(伝法)
付近の玄龍寺には「伊勢塚古墳」(円墳)がある。墓地上の丘にお堂があり眺めがよい。周辺は環濠で南側が広がった独自の形だったようだが、墓地に改変され様子は分からない。古墳があることでこの付近が古くから開けた地であることを証左している。
・広見公園、富士市立博物館(伝法)
この公園の南西角を掠めて北西進する。公園内に富士市立博物館があり、村山古道や村山修験、富士山、吉原宿、東海道、富士市の歴史関連の資料があるので、一見の価値がある。屋外には古民家や遺跡が展示されている。
・石道標 道しるべ1「東三ツ倉 左むら山道」(大渕)
伝法沢川西岸沿い道は西側に工場や倉庫、東側に住宅地を見つつ北進して交差点に至る。
石道標に刻まれた「三ツ倉」は東南500mの現在、法蔵寺周辺の中野・三ツ倉町を指す。なおこの石道標は仁藤春耕の作製したものと考えられている。
主要地方道一色・久沢線に出て、左折し80m右折し左斜め北進する。まもなく第二東名富士インター線の高架橋を渡る。畑と住宅地の混在地を抜けて行く。
・釈迦堂(大渕・穴原町)
石塔類5基。釈迦堂橋を渡って北西進する。
・(付近)不動穴、八幡穴(大渕、久沢)
釈迦堂より北東500m不動穴。西1km八幡穴。どちらも溶岩風穴。多分立ち入り禁止。この村山古道は風穴類に立ち寄らないとみられるので偶然近くを通っただけだろう。別の登山道の精進口登山道はわざと風穴を通るようになっている。洞窟で修行せよということである。またこの近辺には天満宮や八幡宮等神社も多く昔の風景が残っている。
・婦夫地蔵(大渕・穴原町)
釈迦堂橋を過ぎて100mほど右道端にある。500m北西進する。
・石道標 道しるべ2「左むら山道」(大渕・境町)
畑地内に石垣を築いたちょっとした墓地の交差点角にある。題目塔。
・三社氏神社(大渕・大峯町)
250m北西進すると交差点。県道富士・富士宮・由比線に出て左にコンビニ店、道向こうに神社がある。古道沿い最後のコンビニ店。
・石道標 道しるべ3「左むら山道」(大渕・大富町)
交差点より北進300m・この道が富士市と富士宮市の境界線となり、これから境界線沿いに北上していく。しばらく北上するとラーメンみゆき食堂がある。このあと古道沿いには食堂はない。
・石仏(大渕・大富町)
右に馬頭観音らしきが2基。あるいは童子の地蔵か。別の左に石塔「右 杉田 左吉原」らしきがある。
・石道標 道しるべ4「左村山道」(大渕・大富町)
題目塔。
・石道標 道しるべ5「左村山道」、道祖神(大渕・次郎長町)
北進900m。道の反対側に石道標「右ぼんぶ川 左よし原」もある。もはや刻字を読み取れない。参考資料があるから読める。村山道はこの境界線の道をさらに450m北西進する。
個人的な話だが村山浅間から自転車で下ってきて石原の急下り坂を発見できず、三人に市の境界線を聞き、三人目の次郎長町のコンビニ店(山田商店)の方から聞いてやっとこの場所に来られて正しいルートに復帰できた。ここからまた石原の急坂に戻った。コンビニ店から下るとき、ちょうど次郎長を顕彰する白髭神社前を通ったはずだがそんなことかまっていられなかった。この道しるべから北に外れて650mでコンビニ店がある。その途中に白髭神社(次郎長碑)もある。
・自販機の向こうを右へ(大渕・次郎長町)
昔ここにも石道標があったが付近の畑に埋められたそうだ。右折する。狭い道だが舗装されているしかつての主要道で村山道である。交差点に出ると両市の看板が出ていて境界線であることが分かる。その先で鞍骨橋で日沢を渡り、境界線からしばらく離れる。道なりに上っていくと右の畑に背中を向けた石仏がある。
・石仏(富士宮市粟倉・石原)
背中を向け(東)畑を向いている。馬頭観音、地蔵。すぐに広い道に出て左折(西) 100m弱で右に石仏、左に電波塔と三角点のある丘がある。
・石仏(富士宮市粟倉・石原)
馬頭観音、家型道祖神2基、石柱:石道標?「左よし(原) 右ぼんぶ(川)」が道路に面している。南の丘上には三角点がある。50m東には丸石の石塔「甲子」と家型道祖神が祀られている。道はここで右折する。
さっきから出てくる「吉原、ぼんぶ川」を示す石道標は下る人のためであり、村山道を示す道標の反対に置かれるとよいのだろう。
・左の急坂を上る(富士宮市粟倉・石原)
狭い舗装路を道なりに250m上っていくとそのまま道なりに上っていく道とすぐ左横に急勾配で上る狭い道がある。この滑り止め用円形型押しのあるコンクリート製急上り坂を登り、上で合流したら右方向に上っていく。あとは道なりに上っていく。途中右や左に分岐する道があるが、とにかく道なりに上っていく。
個人的にはこの急坂の上で急坂を発見できず別の道を下ってしまい、その後紆余曲折した。
・石道標 道しるべ6「左村山道」のレリーフ(横沢)
人家が出てくるとX字型四つ角がある。その正面に壁にレリーフされた道しるべが見える。左先を進む。かつてのバス通りに出る所に石道標?らしきがある。
・石塔?石道標か?(横沢)
道が分岐する所に何かの目印になる石が安置されているがまったく判読不能。さらに北に100m進む。
・石道標 道しるべ7「左むら山道」 (村山・横沢)
旧横沢バス停跡(バス廃止)に出る。「道しるべ7 左むら山道」四角い石道標があり、標識もある。
村山道は左に直角に曲がり、家一軒ない寂しい道を上って行く。このときは台風直撃すぐ後だったので倒木で車通行不可。自転車なので担いで越す。
・東見付、末代上人の墓(村山)
すぐ左に牛舎があり、もう少し広い舗装路に出る。目の前に標識がある。石仏、東の番所と木戸の跡である。すぐ近くに別の馬頭観音もある。またこのすぐ上の墓地に開祖:末代上人の墓もある。
この先は村山浅間神社だ。神社門前の山本商店が最後の店で、神社への問い合わせ先で、この村山古道復活活動の有志でもある。
3.村山筋(村山浅間神社~中宮八幡堂跡~富士宮口新六合目~山頂)
村山古道登山区間(距離、時間、標高)コースタイム案内
*注意点
¥1000で売られているコースマップ(畠堀操八:著)は絶対必要です。あと磁石かGPSハンディナビを持参してください。もしくは村山古道を通過した経験者が必要です。できれば「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八:著の本を読んでいくか、持参すると迷ったとき役に立つでしょう。
上ったことがないのにいきなり下るとテーピングを発見できず幾度も道迷いをします。私は山の村から札打場、発心門にかけて下ったのですが、3回道迷いし引き返しては正しいルートを探す手間ひまがかかりました。上る分には最低限のテーピングはありますが、下る方向に見やすいテーピングはありません。下る人への考慮はありません。別種類のテーピングは至る所あるので間違わないよう、正しいテーピングを追うようにしてください。(11年9月には幅3cm赤いテープが正しいルートを示していたが、今後変わるでしょう。)迷うと深さ3~5mのV字谷の野渓にはまりますが、こんな深い所は必ず迂回道にテーピングがあるので、深い野渓にはまったら間違いかもと思い引き返してください。迷いやすい所は五辻から発心門、林道富士裾野線交差点及び北井久保林道交差点、札打場、天照教社までの区間です。この区間どうしても迷ったまま元へ戻れなければ、その野渓を高巻くなどして身の安全を確保しつつ下山すれば、林道に必ず出るはずです。周囲はすべて植林地ですので見通しがきき作業道も一杯付いていますので、作業道を下っても林道へ出るでしょう。ただその作業道や踏み跡、涸れ沢が錯綜していて道迷いしやすいのですが。
なお他に野渓化した所は山の村から二番目の馬頭観音までの1kmですが、ここはすぐ横を迂回するなど(草や倒木で歩きにくいですが)すればよいでしょう。天照教社から少し上も野渓化していますが、すぐ横を迂回できます。
村山古道も他の山の中の古道同様、野渓化を免れません。野渓を歩くと割り切りましょう。先ほど挙げた所が標高の低い植林地内で道迷いしやすい悲惨なコース部分です。中宮八幡堂付近は家族連れ子供向けのハイキングコースに絶好です。それより上も歩きよい登山道に整備されつつあります。
なお天照教社より上には一切の村山古道を示す文字標識はなく(11年9月)テーピングと地図・磁石を頼りに歩きました。例外は高鉢駐車場を示す標識と宝永遊歩道の標識はありました。そして宝永遊歩道付近で突然多数のハイカーと行きかいました。それまでまったく人に会わない登山道でしたから驚きました。向こうのハイカーも変な所から人が出てきたので驚いてました。このとき村山古道を歩いていたのは私一人だったようです。村山古道で動けなくなっても誰も通らないでしょう。まったく静かなコースで誰もいません。あとこんなに静かなコースは、精進口登山道、大沢崩れ左右の登山道ぐらいでしょう。
*村山古道は富士宮口新六合目で富士宮口登山道となるというより、歴史的にはその逆でしょうが、今は富士宮口といいます。そこで六合目より上は一般の富士登山ガイドブックを参照してください。ちなみに山頂には破壊された石仏がいくつもあるようです。廃仏毀釈による破壊についても「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八:著を参照してください。なお破壊されず難を逃れた物もあるようです。
コースタイムの距離はキルビメーターで測りましたが、どうも実際より30%ほど短い気がします。実際歩くと表示距離より30%増しにして下さい。つまり表示1.5kmなら2kmです。時間はややゆっくりめにしたつもりですので、健脚者はもっと速く、初心者はもっとゆっくりかもしれません。休憩時間は入れませんし、道迷いの時間も含んでいません。
村山古道は日沢に沿うように道がつけられています。普段は涸れ沢ですが、雨が降ると濁流が流れます。ちょうど山の村の富士市と富士宮市の境界標識がある川です。11年9月17日、下界は雨がやんでいるのに山の村は土砂降りで緑陰広場横の日沢も深さ20cmの濁流でした。翌日は沢には水一滴もありませんでした。9月23日に行くと沢は涸れていましたが、2日前に台風15号直撃を受け、山の村すぐ下の吉原林道と交差する箇所が破壊され通行不能でした。緑陰広場横の日沢の枯葉の堆積から深さ50cmの濁流が流れたと推定されます。駿河湾の湿った空気が富士山麓南面の地に当たり村山周辺にすさまじい降雨量となって降るためのようです。地元ではベタベタだかベトベトと言うようです。その雨水が片っ端から地面をえぐるため、道も広場もガタガタになります。村山古道の野渓化やむなしです。雨のあとどの道の状態も悪化します。通行不能もありえます。樹木にしても地面が溶岩でやせているのか風が強いのか、倒木になり道をふさぐのは日常茶飯事かもしれません。下界は降って無くても当地で土砂降りのとき、沢や野渓化した道は通行不能でしょう。
・コースタイム
富士宮口新六合目、宝永山荘、H2490m ←→宝永第一火口手前
↓↑ 0.5km 30分 ↑↓ 20分 ↓↑
富士宮口五合目←→ 宝永遊歩道分岐点、H2350m ←→宝永第二火口手前
(二合目、三合目石室跡…石垣、便所穴跡)
0.7km 40分 ↑↓ 30分 一合目小屋跡ともう一つ平坦地がある。
一ノ木戸跡(石段、石垣、やかん) H2150m
0.6km 30分 ↑↓ 20分
横渡(日沢を渡る) H2000m
0.6km 30分 ↑↓ 20分
笹垢離跡(石仏) H1870m
0.3km 10分↑↓ 7分
岩屋不動への分岐点、H1800m ←0.7km、30分→ 岩屋不動跡、H1870m
0.5km 20分 ↑↓ 15分
高鉢駐車場←→ 「高鉢駐車場~御殿庭コース散策道」分岐点、H1720m ←→御殿庭
0.7km 25分 ↓↑ 20分
富士山スカイライン152号線(180号線分岐~富士山五合目)「10.8km」標識、H1600m
1.5km 50分 ↑↓ 40分
富士山スカイライン180号線(山宮~御殿場)「7.8km」標識、H1340m
1km 30分 ↑↓ 20分
中宮八幡堂跡、 H1250m
2km 50分 ↑↓ 40分
富士山麓山の村(緑陰広場)、 H1090m
1km 30分 ↑↓ 20分
天照教社、 H1000m
1km 30分 ↑↓ 20分
林道富士裾野線交差点、 H740m
2km 50分 ↑↓ 40分 上ってすぐに札打場ケヤキがある。
北井久保林道交差点、 H800m
1km 30分 ↑↓ 20分 途中、発心門跡を通過するが単なる平坦地で痕跡なし。
五辻(林道から登山道へ)、 H650m
0.5km 15分 ↑↓ 10分
最初の馬頭観音(チェーンが張られこの先自動車通行不可)、 H590m
1.5km 45分 ↑↓ 30分徒歩
村山浅間神社、標高H490m
・解説
・ 村山浅間神社西横から部分的に石畳道があり、途切れたところは集落内の舗装された生活道路を通行するので安心して通れる。村山集落の北に向かい最後の人家:鯛津氏宅(この村山古道復活活動の地元有志)を過ぎると寂しい道になる。
・ チェーンが張られた林道の横に最初の馬頭観音がある。車を置くなら左折してもう50mも奥に行けば平坦な所がある。よくよく見るとこの平坦な所やこの下の涸れ沢が本来の村山道ではないかという気がする。林道歩きは500mで終わり登山道に取り付く。
・ 五辻から登山道区間に入ると途端にV字谷のような野渓化した道に出くわす。そしてそれを迂回するかのようにすぐ横に別の切通しが通っていくのが分かる。それがしょっちゅうであり、これは他の古道でもよくある例である。ただ県内の他の古道よりえぐれ方が激しいのは、さすが富士山という高山にして溶岩の山で降雨量の多い地であるためだろう。もはやファミリー向けハイキングコースではない。
・ 発心門の辺りはなんとなく平坦な植林地である。かつては礎石があったらしいが今は痕跡もない。発心門推定地に標識があるといいですね。このあとコースは上へ上らず、ひたすら横へ水平移動し、林道へ出てそこから又上り、札打場ケヤキに至る。それにしてもなぜここで上らず水平移動するのか? 日沢との関連か? 札打場ケヤキに行きたいのか? 札打場を過ぎるとまたいくつも野渓のような道を通過する。天照教社に近づくと道がよくなってくる。
・ 天照教社前で舗装された林道に出て標識も多い。11年9月村山古道の文字標識はこれより上にはなかった。ここからしばらく野渓のような道もあるが平坦に近くすぐ横を迂回しやすい。山の村に近づくと平坦な森林散策路となる。一旦吉原林道を横断して山の村敷地に入る。吊り橋の下は金属パイプもくぐるため狭いが道はよい。このあとすぐ道はえぐれたオーバーハングの下となる。昔は左に上ったようだが今は無理なので、右から上る。そのように標識やロープが張られている。進むとすぐ山の村の車道と緑陰広場に出る。休憩によい。
・ 山の村緑陰広場で交差する箇所には11年9月にはまったく標識はなく、ガイドマップを持っている人にしか分からないようになっている。下りはいきなりオーバーハングの崖を避けて上り下りするところがあり、注意書きと黄色いロープがある。緑陰広場の右奥からの上りは野渓が1km続き、このままでは家族や子供用のハイキングコースにはなりにくい。2番目の馬頭観音より先は森の散策コースになり快適に大淵林道を横断し涸れた日沢も越えて、中宮八幡堂跡を目指せる。中宮八幡堂跡付近は地元の人が使うのできれいな道でありハイキングコースになる。富士山スカイライン「7.8km」標識までは道迷いなく快適に歩けると思われる。
・ 「7.8km」標識近くに登山道は開けているがテーピングがあるだけで、何の道かは知っている人にしか分からない。ここからもしばらく歩きやすい道だが周辺のコケだらけなのを見ても分かるとおり、夏は湿度が高く蒸し暑い。緑のコケの絨毯はしっとりした日本庭園のようで美しい。「10.8km」標識手前に一箇所岩むき出しの急坂があるが慎重に通過すればよいでしょう。これも野渓化ですね。
・ 「10.8km」標識近くのテーピングの切り開けから入山。高鉢駐車場分岐点では文字標識がある。これより上の古道では宝永遊歩道までエスケープ不能となる。この先ちょいとした人工的広場があり、「大樅」という修験場跡がある。この先へつりになっているところがあるので注意。
・ 岩屋不動への道はくたびれ果てた白テープとかすかな踏み跡を頼りにたどり、渓谷辺りで黄色いロープがいくつも張られていてやっと分かった次第。一応「危険なので注意して参拝してください」との注意書き。洞窟というほどではないが、岩の割れ目の暗黒世界が拝める。なかなかの巨岩の涸れ滝世界。山岳修験に似つかわしく行者が修行するにはよい所でしょう。
・ 笹垢離跡の石仏はかつて3体、ガイドブックでは4体、そしてこのときは5体だったと思う。? だんだん地中から出土してくるのでしょうか。晴れていれば絶景。ちょいと草と倒木は多いが野渓よりまし。
・ 横渡も晴れていれば絶景で、涸れ沢の日沢も安心して渡れるが、テーピングが失われるときつかろう。
・ 一ノ木戸跡にあるやかんは薄手で近代以後の産物と思われる。おそらく昭和期のものか。ただ畠堀操八氏が言うようにこのまま安置すべきだろう。村山古道自体が文化財であり保存できるとよいという意識で通行しよう。その後一合目小屋跡ともう一箇所小さな平坦地がある。この付近倒木が多いが切断され踏み跡がたどれるようになっている。
・ 二合目、三合目石室跡の石垣や便所穴跡は宝永遊歩道のすぐ近くであるがそこを通る誰もが気付かないようだ。まあその方がよいだろう。二合目と三合目の石室はすぐ近くだが、この辺りがかつての森林限界だったため、すぐ近くに2つ建てざるをえなかったのか?
・ 岩室跡より上では樹木が低く明るくなる。すぐに樹木がなくなり、ガラガラの溶岩石帯になる。テーピングではなく、石に付けられた水色マーキングをたどる。晴れていると絶景で振り返れば愛鷹山から海まで見え、この上の6合目山荘も見える。そこで富士宮口登山道と合流する。
・推論
笹垢離跡(石仏)H1870mは特段、道の状況が変わるわけでもない坂の途中に唐突にある感じがする。普通石仏等を祀り垢離を行う場所はそれなりの雰囲気のある所なので不思議な気がする。その手前に岩屋不動への分岐点、H1800mがあり、木馬道をたどって岩屋不動跡、H1870mへ達するのだが、岩屋不動跡、H1870mと同じ標高なのだ。多分昔はこの二箇所が同一標高のまま平坦な道で結ばれていたのではなかろうか。あるいは同一標高の笹垢離で禊をすれば岩屋不動まで行かなくとも同じご利益があるとでも考えたのだろうか。
・参考資料
・「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八:著、風濤社、’06
・「富士山村山口登山道跡調査報告書」富士宮市立郷土資料館、’93
・「本山修験宗聖護院富士山入峯修行復活 富士山表口登山道全図 富士山村山古道を歩く」畠堀操八、NPO法人シニア大樂山樂カレッジ、’09、¥1000
2.吉原筋(富士市鈴川~吉原宿~村山浅間神社)
3.村山筋(村山浅間神社~中宮八幡堂跡~富士宮口新六合目~山頂)
以上3つのコースに分けて説明していく。
1.西から来た人は富士川を渡ったあと北に方向を変え、富士宮浅間大社(大宮)に参詣した後、村山浅間神社に向かった。
2.東から来た人は吉原宿から村山浅間神社に向かった。その前に田子の浦の水につかり、海岸の石を1個、富士塚に供えたという。大宮側からは大宮に寄らず登っていくので幾度も禁制の触れを出している。(おそらく有名無実)
3.以上1と2のコースが村山浅間神社で合流し、ここから本格的な登山がはじまった。というわけで本当は1と2のコースがあったというべきだが、ここでは便宜的に3つに分けた。これらの道を「道者(ドウシャ)道」という。
復活した村山古道は部分的に道というより野渓や廃道であるが、歴史文化財として指定し保存すべきである。
登山道区間は数年がかりで2006年に地元有志と畠堀操八氏はじめ登山仲間等の大変な努力によって再発見され整備され通行可能になった。まだ整備されきったわけではなくやっと人が通れる状態である。
*(付近)というのは、村山古道と直接関連がなくとも、通過する地域に関する地理歴史情報を提供する項目である。
1.松岡筋(富士市松岡~富士宮浅間大社~村山浅間神社)
この区間は「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八にも記述がなく、大まかなルート図が「富士山村山口登山道跡調査報告書」にあっただけで、私が推論してコースを立てたので正確ではないでしょう。しかしとにかくこの区間に切り込めたことが収穫でしょう。あとは後続の調査研究で直されればよいでしょう。
・水神社、石道標「冨士山道」 (富士市松岡)
東海道筋の富士川渡船場横にある。東海道に関する標識や看板があり歴史散策の地。昔は橋がなく松岡と岩淵の間は船で渡っていた。富士川本流がここを通るようになったのは近世以後で、神社北背後の雁堤(カリガネツヅミ)ができたことで、今の富士市街への流れをカットできたからである。石道標「冨士山道」が安置されている。昔はもっと東の分岐点にあったがここに移された。富士山道はここから東海道(県道、旧国道1号)を東進する。
しかし一旦南下し別の歴史物を見に行く。
・(付近)帰郷堤(キキョウツヅミ)、三重稲荷利神社(松岡四丁河原西、富士川堤防東岸)
水神社前の信号を南に向かい狭い道を富士川緑地方向に400m行くと、小さな神社と看板がある。ここの堤防の名と御利益豊富な神社の謂われが記入されている。この地が水害に悩まされていたことが分かる。
・石道標、秋葉山常夜灯(松岡)
あらためて水神社前を800m東進する。
東海道の標識と看板がある。本当はここまで来ると来過ぎで、もう1本50m手前の道を北に曲がる。
・雁堤(カリガネツヅミ)、護所(人柱)神社(松岡)
150m北進し道が合流分岐する手前左(西)の堤防上に護所(人柱)神社がある。上ってみれば堤防が見渡せ、晴れていれば富士山もよく見える。日本三代急流の一つ富士川の激流を止めるために水をソフトに受け止める工夫が、この雁堤(カリガネツヅミ)である。またこの工事を成功させるため人柱の犠牲があったことが記されている。歴史的事実かどうかは証明されないようだ。しかし幾度も失敗を重ねての困難な工事であったことが分かる。ここから2km北の山際突端の河原に一番ダシ、二番ダシ、三番ダシという真っ先に水を受け止める堤防に行くこともできる。祠が祀られている。雑草だらけかもしれず、歩くと遠い。
・石仏、石塔(松岡)
道がいくつも分岐するが、水路脇の北東に進む道を選び北進する。北の岩本山右(東)中腹を目指す。岐流橋を渡ると水路は左に離れる。道なりに直進する。
途中石仏(馬頭観音、供養塔かと思われるが丸石を載せ地蔵のよう)や石塔(実相寺の題目塔で参詣道を示す)に出会う。
・稲荷神社、山神社(松岡)
護所神社から北進1kmで、東名高速ガード下左に2つの神社が隣接してある。
・上堀橋(岩本)
東名高速ガード下から600mで道は直進不能で左右に曲がる。ここからどちらが古道か迷うので両方紹介する。
・右折し150mで左折すると橋を渡り、岩本山に登る道が正面にある。正面の上り道(車で登れる旧道)ではなく更に右の狭い道が古道らしい。上っていくと石仏がある。
・左折し上堀橋を渡ったらすぐ右折し川沿いを上っていく。150mで右折ルートと合流し、北東方向への住宅地の中の狭い道を上り、石仏に出会う。
古道を登ると広い新道と車で登れる旧道とに合流する。本当の古道は旧道側の左に入ってすぐ山上に上る狭い道かもしれない。また永源寺西の山に登る道かもしれない。車で通れる道のようなので車で通行するのが手っ取り早い。明治20年代の地図ではほぼ新道に沿って道がついているので、新道を北上すればよいようだ。旧道も新道も最終的には山本で合流する。
旧道未調査。
・(付近) 岩本山実相寺、永源寺、八面神社、琴平神社、岩本山公園
岩本山実相寺…
永源寺…
八面神社…巨樹
琴平神社…
岩本山公園…
・第六天神社(富士宮市山本)
ちょうど富士市岩本と富士宮市山本の境界線で新道と旧道は合流する。その先150m左(西)に神社がある。
・(付近)山本勘助所縁の地(山本)
山本勘助は武田信玄の軍師として知られる。出生地には異説(愛知県豊川市、豊橋市、豊田市)はあるが、この地、山本が有力である。その後三河で養子になったという。ただ初出の『甲陽軍艦』からして後世のものなのでどこまで信じていいのか。同時代の文書で「山本菅助」名がいくつか発見されているが、なぜ「菅」なのか、出生地の証明はとなると?である。
第六天神社を新道北40mで勘助史蹟の標識があり、双体道祖神もある。右折(東)し下っていくと勘助坂標識がある。勘助が子供の頃この坂で遊んだという。
第六天神社を北200mで右折(東)し500m下っていくと勘助母の墓、その先に勘助子孫の吉野家がある。長屋門は見事である。
・石仏(山本か黒田)
馬頭観音と他一基。新道沿いにある。
・石仏、石塔(黒田)
新道に戻り北進する。明星山入口(旧星陵高前)交差点バス停より200m先左(西)石塔類(単体道祖神、甲子神、馬頭観音、大日)がある。標識もあるので分かりやすい。昔はここから明星山に登ったようだ。
この先250mで黒田小学校に達し道は右カーブし富士宮市中心街に向かう。おそらくここにも昔は道標があったのだろうが、まったくそういう雰囲気はない。
・題目塔(黒田)
本光寺参道を示す。古い題目塔と新造の寺の名を示す石塔がある。
・題目塔、双体道祖神(田中町)
金谷橋で潤井川を渡ると左にある。
・常泉寺(東町)
門前石塔類。
・平等寺(東町)
山門、石塔類、鐘楼。
・大頂寺(東町)
虚空蔵堂(かつて富士山頂にあった仏像が廃仏毀釈で麓に預けられさらにこの寺に寄贈された。) 仏像がすべて破壊されたのではなく、このようにひそかに降ろされ寺に預けられたものもあるようだ。六地蔵。
・宗心寺(東町)
門前石塔類。
大頂寺方向へ西進し浅間大社まで行く。
・富士山本宮浅間大社(宮町)
湧玉池で禊をするのが正式であるが、触れればよいでしょう。背後が山でここが窪地となっているので、湧水するようだ。夏でも冷たく澄んだ水で水量が多い。この水が湧き出すからここに神社があり、町が発展したのだろう。
本殿(国重文)、信玄櫻、御神幸道道標、鳥居、石灯籠、赤心隊石碑、火山弾、鉾立石、桜の馬場。富士山頂8合目より上は当神社所有。全国の浅間神社の総本山。石碑「天然記念物 湧玉池」。
・福石神社(元城町)
湧玉池のある浅間大社東側道向かいにある。この神社前を東進する。道端の角に双体道祖神がある。
・萬松院(元城町)
大宮小学校を過ぎると北に寺が見える。門前に石仏も祀られている。
平等寺裏を過ぎた所で左折し北進する。
・山神社(若の宮町)
北進200m左に鳥居。
・石仏(舞々木町、市営舞々木墓地)
北進1.1kmで市営墓地を通過し、道沿いに新造の大黒のような布袋のような石仏。(無論古い村山古道とは直接関係ないですが、現代の村山古道周辺での石造物状況を知るためのよい参考資料でしょう。又後世への参考資料にしたいからです。例えば百年後にこの通りの石造物を調べたい人がいた場合、この資料はほぼ残らないでしょうが、万一にでも残存して、この平成期に作られた石造物を調べていて、ここに存在したことを証明する記事があれば、2011年に確かに存在したと証明できるではありませんか。これらの記述は遠い後世における歴史資料にしたいので載せています。)
・石道標「右 富士山道」(舞々木町)
墓地より北進300m、Y字路に石道標。
・石仏、「富士登山 満行供養塔」(大岩)
石道標より北進250mで舞々木橋を渡り今の広い道を北進せず、その1本左の川沿いの狭い道を北へ上がる。これが旧道と思われる。すぐ左に石仏がある。
「富士登山 満行供養塔」、地蔵、六地蔵、供養塔があり、富士登山との関連性を物語っている。北進してすぐ新道と合流。
・重林寺、石仏(大岩)
北進200mで広い道と合流。右に石仏(地蔵、題目塔)、その向こうに寺と門前の石塔類がある。
・大岩堤自然歩道、ビオトープ大岩(大岩)
北東進400m。右に以上のタイトルの歩道入口表示があった。未調査。大岩堤という池がありビオトープになっているようだ。(無論古い村山古道とは直接関係ないですが、大岩周辺の当たり前の自然環境がいかなるものだったのか知るにはよい参考資料でしょう。)
北東進600mで古い街道は二又という交差点に向かうため左斜めに上って行く(北進)。
・二又石塔(粟倉)
700m行って二又で右折を2回連続行い、東進する。ここに新造の石塔がある。昔から要衝の地だからかここで遠回りだが曲がっていく。
ドウシャ道は妙心寺入口で左折し狭い舗装路を北東に登っていく。
・妙心寺、石仏(粟倉)
当地に移転したばかりの寺のようだ。妙心寺門前で左折し狭い舗装路を北東に登っていく。道端途中石仏が祀られている。道なりに上に行く要領で進むとよい。
・粟倉観音堂、石仏、石塔・墓石?(粟倉)
旧国道469号線(新国道は別で今は県道か市道)沿い、富士根北公民館より北東へ400m左、堂内に石仏三体。敷地に10体の石仏石塔を祀り、懇切丁寧な説明版もある。
ここからさらに北東150mの交差点角に石塔か江戸時代中期頃の墓石かと思われるものが祀られているが、詳細?。
・「山辻の石畳」、「道者道ドウシャミチ」案内板(粟倉、村山)
妙心寺から人家を過ぎ配水池のある所の右に「山辻の石畳」の標識がある。コンクリ舗装路はこの先行き止まりである。右の「山辻の石畳」を歩く。地元の子供たちが石を埋めるなど整備して10年とたっていないがもはや廃道である。300m倒木・雑草・浮石・蜘蛛の巣のめちゃくちゃな中やっと通り過ぎると旧国道の舗装路、そのすぐ先に階段があり、上ると現国道469号線である。階段下に「道者道ドウシャミチ」案内板がある。階段を上り、国道をまたげば西見付への寸断された旧道である。元は幅一間(1.8m)の石畳道だったのだろう。石畳にしたのは後世だろう。ここが西見付に至る道者道で住民の主要生活道路だったのだろう。
ここにいるだけで廃道の古道、使われなくなり汚れていく狭い旧国道469号線の舗装路、車がビュンビュン走り抜ける広い現国道469号線の3つの道の栄枯盛衰を一目で見られる。それにしても石畳道はどうにかできないのだろうか。歴史文化財の価値は十分である。
・道者ドウシャ道の近道はないのか?
先ほど二又まで行って曲がってきた。正式にはそれがルートだろうが、明らかに遠回りである。歩くドウシャの中には近道する者はなかっただろうか。
私の勝手な推定路2パターン。
1.妙心寺前交差点から南西の丘向こうの墓地へ、墓地の南下の氏神神社前に出て、旧国469号へ西で合流しさらに南下の粟倉南町、舟久保町、粟倉境の五差路に合流する。
2.妙心寺前交差点から南西の真下に下りる道を進み下粟倉のT字路にぶつかり直進できないので、右折(西)し舟久保町の新興住宅地(もはや古道はないだろう)を何とか抜けて旧国469号へ出る。途中複数の石仏に出会える。
・西見付(村山)
石仏、西の番所と木戸の跡である。
・村山浅間神社(村山)
もとは神仏混合の修験道による興法寺であり、大日堂にその名残をとどめる。明治の廃仏毀釈により神社となる。もとは神主ではなく山伏の僧侶により運営されていたのだ。巨樹も多い。石仏も多い。護摩壇。水垢離跡。詳細は「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八:著を参照。
*この松岡筋に関しては岩本山山麓の山本を通らず東端の龍巌淵を通り天間から杉田へそして石原に向かうルートがあったようだ。
2.吉原筋(富士市鈴川~吉原宿~村山浅間神社)
このコースについては以下の3.村山筋同様、村山古道コースマップ(畠堀操八:著) ¥1000が必要です。しかもそれを持っていても初めてなのに下るということをやると、道迷いします。それは私です。初めて挑戦したとき富士市松岡に車を置き、自転車で岩本、山本、富士宮浅間大社、粟倉、村山浅間神社まで上り、そこから横沢、石原、大渕、伝法、吉原宿、鈴川へ下りました。下りは楽だと思いきや、いくつかの目印が探せず、付近で3人に聞いて市の境界線の「道しるべの5左村山道」の石道標を見つけ、又、迷った所(石原の「左の急坂を上る」)の坂上まで上り直すはめになるなど、相当体力と時間、気力をそぎました。それは登山道区間でなお顕著ですが、あくまでも上ることを念頭に作られているので、コースを知らず下ると目印を発見できません。人里なので迷うと思ってなかった私がバカです。特に分かりにくいのが、横沢から石原、次郎長町にかけてでしょう。「道しるべ6」から「左の急坂を上る」の上りきった所、「自販機の向こうを右へ」の辺りです。「道しるべの5左村山道」または「道しるべの4左村山道」を発見できればそこからはコースマップを見直せば正しいルートにすぐ復帰できます。付近の住民に「村山古道はどこ?」と聞いてもまったく通用しません。コースマップの写真を見せて「ここに行きたい」という方がよいでしょう。ちなみに自転車で鈴川に達し、さらに松岡まで戻ったら7時間かかりました。このときは粟倉の「山辻の石畳道」は歩いてなかったのですけど。
記事は下った道を上りに再構成しました。
*一部吉原宿辺りで近世東海道を通過するため、東海道のガイドブックを参照してもらってもよいです。
・浅間宮、富士塚(富士市鈴川)
富士登山をする者が海水で水垢離した後海岸の石を一つ置いていったものが積み重なって塚になったという。別説には、津波後の施し米のお礼として積み上げた。北条・武田・今川が対峙したときの天の香久山砦の跡。などの説もある。
鳥居前を直進して突き当たると石碑「皇太子殿下御散策之蹟」があり、左に元吉原中学校がある。戻るなら左折だが、海に行くなら右折する。
ここから海水に触れるには堤防の出入り口を越し、左折(東)していくとテトラポッドが切れて砂浜が少し見える。反対に西へ行くと田子の浦港の岸壁で立入不可となるのでむだである。
・閻魔堂、地蔵堂、石塔、黒露の墓(鈴川)
閻魔堂…閻魔像、地蔵
地蔵堂…地蔵
石塔…17基、観音、六地蔵、燈籠、
黒露の墓…黒露は江戸時代中期の俳人。
地蔵堂前の階段が古くは海に出る道で、南進して一度曲がって先の皇太子碑に出ればよい。
・木之元神社、古東海道(鈴川)
戻りは地蔵堂から東進60mで右の路地に入ると古東海道であり、木之元神社前に出る。御神水の碑、六角井戸、神木がある。神社上側の道を行く。近世東海道に出るにはその先を左折し広い道に出るが、おそらく古東海道は右折した路地のように少し高いところを東進していたのだろう。近世東海道側へ進む。広い道に出たらすぐにある踏切を越え線路に沿い西進し、JR吉原駅前で北西進していく。*(ここからは近世東海道に出たので、近世東海道のガイドブックと同一内容になる。) 河合橋を渡り国道1号線と新幹線のガードを斜め左に横断する。その先に静かな街並みがある。左富士神社のある中吉原宿跡である。
・(付近)阿字神社、妙法寺、富士と港の見える公園、三本松、毘沙門天妙法寺(鈴川)
阿字神社…近世以前の東海道は田子の浦を船で渡っていた。そのとき東岸側で安全祈願をした所の名残である。相当古い神社と考えられるが、これだけ海に近い所にあるためか古い物はない。(多分地震や津波で遺物は残りにくい) 里宮の裏の奥宮横に見付の井戸(ばば井戸)や見付宿跡説明板がある。かつていけにえの場所だったことがわかる。付近に仏舎利塔がある。
妙法寺…題目塔、石塔、日蓮像、ガンジー像、
富士と港の見える公園…現代の公園、展望台があり眺めは抜群。トイレや駐車場数台分ある。
三本松…元吉原中学校向かいにある。何の謂れか?
毘沙門天妙法寺…だるま市で有名、近世東海道筋にあるので歩くとちょっと遠い。
・中吉原宿跡、左富士神社(依田橋町)~近世東海道~
先ほどの鈴川や毘沙門天の辺りが元吉原宿であるが、津波で破壊され、この左富士神社から西の辺りに移転した。しかしここも津波で破壊され今の吉原本町の吉原宿に再々度移転した。(中吉原宿をはじめ元吉原宿、吉原宿の資料は富士市立博物館にある。)
*ここ以後しばらく近世東海道ルートなのでもっと詳しく知りたい方は東海道吉原宿近辺のガイドブックを読んでください。
・左富士(依田橋町)
東海道を東から西に行けば富士山は右に見えるのだが、この地だけは左に見えるので「左富士」と称され珍しがられた。東海道が一旦北北東を向くからである。左富士神社先の交差点に史蹟看板があり、松が植えられている。左富士の浮世絵レリーフもある。
・石仏(依田橋町)
左富士史蹟を過ぎて北進すると左に祠が見える。
・平家越し(新橋町)
橋を渡る所にある。平家が富士川沿いに陣取り羽音を源氏の攻撃かと驚き逃げ出したという伝説の地である。平家は羽音だけに驚いたのではなく、その前から源氏の陽動作戦で疑心暗鬼になっていたという説もある。ここはいまでは富士川ではないが、雁堤設定以前はここまで富士川が幾本かに分流して流れていたようだ。
・吉原宿、東木戸(吉原宝町)
近世に三度も宿替えをした宿場の最終地、現在も繁華街。
吉原本町駅…レトロな電車が走っていてマニアに受けるそうだ。
百地蔵尊…吉原本町駅目の前
鯛屋旅館…旅籠や、
下本陣跡…コンドウ薬局、上本陣…富士見会館、
脇本陣跡…ノグチカメラ、おもちゃのキムラ、オオイカメラ、岳南堂菓子舗、
問屋跡…メガネヤナセ、
長さん小路…この地で小青年期を過ごしたドリフターズいかりや長助を記念した通り。
・妙祥寺前題目塔、宿場の鍵の手(中央町一丁目)
ここで宿場通りは左折し妙祥寺に南下する。そこに題目塔がある。ここでまた右折し南西に向かう。
・(付近)日吉浅間神社、富知六所浅間神社
・日吉浅間神社…東泉院ははじめ浄土院といい、頼尊に属した僧によって創建。元は吉原公園にあり、移転を繰り返し現在地となる。西隣は六所氏屋敷跡地でさらに西に吉原公園となる。六所氏は近在の有力者で神社移転を行ったのも六所氏である。旧東海道の吉原宿から北進し出すとすぐ左に「旧順天堂田中歯科医院診療所兼主屋」(国登録有形文化財)の洋館と和館がある。その先の川を渡った所に「大日如来」がある。正面の「上和田子安地蔵尊」の左に神社がある。
富知六所浅間神社…大楠、東泉院の別当が管掌。楠(県指定天然記念物) 、火山弾。付近にカンカン堂がある。
・西木戸跡(中央町三丁目)~近世東海道~
ここで近世東海道から離れ右折し北西進する。
・馬頭観音、道祖神(伝法)
県道富士インター線の富士インター南の長者町西交差点より50m南の道路東側にある。新造のようだ。文字碑。付近の地下道入口花壇に道祖神2体(文字碑)がある。
ここから先の道路を横断し酒のアルコの北裏に北西進する。
・(付近)伊勢塚古墳(伝法)
付近の玄龍寺には「伊勢塚古墳」(円墳)がある。墓地上の丘にお堂があり眺めがよい。周辺は環濠で南側が広がった独自の形だったようだが、墓地に改変され様子は分からない。古墳があることでこの付近が古くから開けた地であることを証左している。
・広見公園、富士市立博物館(伝法)
この公園の南西角を掠めて北西進する。公園内に富士市立博物館があり、村山古道や村山修験、富士山、吉原宿、東海道、富士市の歴史関連の資料があるので、一見の価値がある。屋外には古民家や遺跡が展示されている。
・石道標 道しるべ1「東三ツ倉 左むら山道」(大渕)
伝法沢川西岸沿い道は西側に工場や倉庫、東側に住宅地を見つつ北進して交差点に至る。
石道標に刻まれた「三ツ倉」は東南500mの現在、法蔵寺周辺の中野・三ツ倉町を指す。なおこの石道標は仁藤春耕の作製したものと考えられている。
主要地方道一色・久沢線に出て、左折し80m右折し左斜め北進する。まもなく第二東名富士インター線の高架橋を渡る。畑と住宅地の混在地を抜けて行く。
・釈迦堂(大渕・穴原町)
石塔類5基。釈迦堂橋を渡って北西進する。
・(付近)不動穴、八幡穴(大渕、久沢)
釈迦堂より北東500m不動穴。西1km八幡穴。どちらも溶岩風穴。多分立ち入り禁止。この村山古道は風穴類に立ち寄らないとみられるので偶然近くを通っただけだろう。別の登山道の精進口登山道はわざと風穴を通るようになっている。洞窟で修行せよということである。またこの近辺には天満宮や八幡宮等神社も多く昔の風景が残っている。
・婦夫地蔵(大渕・穴原町)
釈迦堂橋を過ぎて100mほど右道端にある。500m北西進する。
・石道標 道しるべ2「左むら山道」(大渕・境町)
畑地内に石垣を築いたちょっとした墓地の交差点角にある。題目塔。
・三社氏神社(大渕・大峯町)
250m北西進すると交差点。県道富士・富士宮・由比線に出て左にコンビニ店、道向こうに神社がある。古道沿い最後のコンビニ店。
・石道標 道しるべ3「左むら山道」(大渕・大富町)
交差点より北進300m・この道が富士市と富士宮市の境界線となり、これから境界線沿いに北上していく。しばらく北上するとラーメンみゆき食堂がある。このあと古道沿いには食堂はない。
・石仏(大渕・大富町)
右に馬頭観音らしきが2基。あるいは童子の地蔵か。別の左に石塔「右 杉田 左吉原」らしきがある。
・石道標 道しるべ4「左村山道」(大渕・大富町)
題目塔。
・石道標 道しるべ5「左村山道」、道祖神(大渕・次郎長町)
北進900m。道の反対側に石道標「右ぼんぶ川 左よし原」もある。もはや刻字を読み取れない。参考資料があるから読める。村山道はこの境界線の道をさらに450m北西進する。
個人的な話だが村山浅間から自転車で下ってきて石原の急下り坂を発見できず、三人に市の境界線を聞き、三人目の次郎長町のコンビニ店(山田商店)の方から聞いてやっとこの場所に来られて正しいルートに復帰できた。ここからまた石原の急坂に戻った。コンビニ店から下るとき、ちょうど次郎長を顕彰する白髭神社前を通ったはずだがそんなことかまっていられなかった。この道しるべから北に外れて650mでコンビニ店がある。その途中に白髭神社(次郎長碑)もある。
・自販機の向こうを右へ(大渕・次郎長町)
昔ここにも石道標があったが付近の畑に埋められたそうだ。右折する。狭い道だが舗装されているしかつての主要道で村山道である。交差点に出ると両市の看板が出ていて境界線であることが分かる。その先で鞍骨橋で日沢を渡り、境界線からしばらく離れる。道なりに上っていくと右の畑に背中を向けた石仏がある。
・石仏(富士宮市粟倉・石原)
背中を向け(東)畑を向いている。馬頭観音、地蔵。すぐに広い道に出て左折(西) 100m弱で右に石仏、左に電波塔と三角点のある丘がある。
・石仏(富士宮市粟倉・石原)
馬頭観音、家型道祖神2基、石柱:石道標?「左よし(原) 右ぼんぶ(川)」が道路に面している。南の丘上には三角点がある。50m東には丸石の石塔「甲子」と家型道祖神が祀られている。道はここで右折する。
さっきから出てくる「吉原、ぼんぶ川」を示す石道標は下る人のためであり、村山道を示す道標の反対に置かれるとよいのだろう。
・左の急坂を上る(富士宮市粟倉・石原)
狭い舗装路を道なりに250m上っていくとそのまま道なりに上っていく道とすぐ左横に急勾配で上る狭い道がある。この滑り止め用円形型押しのあるコンクリート製急上り坂を登り、上で合流したら右方向に上っていく。あとは道なりに上っていく。途中右や左に分岐する道があるが、とにかく道なりに上っていく。
個人的にはこの急坂の上で急坂を発見できず別の道を下ってしまい、その後紆余曲折した。
・石道標 道しるべ6「左村山道」のレリーフ(横沢)
人家が出てくるとX字型四つ角がある。その正面に壁にレリーフされた道しるべが見える。左先を進む。かつてのバス通りに出る所に石道標?らしきがある。
・石塔?石道標か?(横沢)
道が分岐する所に何かの目印になる石が安置されているがまったく判読不能。さらに北に100m進む。
・石道標 道しるべ7「左むら山道」 (村山・横沢)
旧横沢バス停跡(バス廃止)に出る。「道しるべ7 左むら山道」四角い石道標があり、標識もある。
村山道は左に直角に曲がり、家一軒ない寂しい道を上って行く。このときは台風直撃すぐ後だったので倒木で車通行不可。自転車なので担いで越す。
・東見付、末代上人の墓(村山)
すぐ左に牛舎があり、もう少し広い舗装路に出る。目の前に標識がある。石仏、東の番所と木戸の跡である。すぐ近くに別の馬頭観音もある。またこのすぐ上の墓地に開祖:末代上人の墓もある。
この先は村山浅間神社だ。神社門前の山本商店が最後の店で、神社への問い合わせ先で、この村山古道復活活動の有志でもある。
3.村山筋(村山浅間神社~中宮八幡堂跡~富士宮口新六合目~山頂)
村山古道登山区間(距離、時間、標高)コースタイム案内
*注意点
¥1000で売られているコースマップ(畠堀操八:著)は絶対必要です。あと磁石かGPSハンディナビを持参してください。もしくは村山古道を通過した経験者が必要です。できれば「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八:著の本を読んでいくか、持参すると迷ったとき役に立つでしょう。
上ったことがないのにいきなり下るとテーピングを発見できず幾度も道迷いをします。私は山の村から札打場、発心門にかけて下ったのですが、3回道迷いし引き返しては正しいルートを探す手間ひまがかかりました。上る分には最低限のテーピングはありますが、下る方向に見やすいテーピングはありません。下る人への考慮はありません。別種類のテーピングは至る所あるので間違わないよう、正しいテーピングを追うようにしてください。(11年9月には幅3cm赤いテープが正しいルートを示していたが、今後変わるでしょう。)迷うと深さ3~5mのV字谷の野渓にはまりますが、こんな深い所は必ず迂回道にテーピングがあるので、深い野渓にはまったら間違いかもと思い引き返してください。迷いやすい所は五辻から発心門、林道富士裾野線交差点及び北井久保林道交差点、札打場、天照教社までの区間です。この区間どうしても迷ったまま元へ戻れなければ、その野渓を高巻くなどして身の安全を確保しつつ下山すれば、林道に必ず出るはずです。周囲はすべて植林地ですので見通しがきき作業道も一杯付いていますので、作業道を下っても林道へ出るでしょう。ただその作業道や踏み跡、涸れ沢が錯綜していて道迷いしやすいのですが。
なお他に野渓化した所は山の村から二番目の馬頭観音までの1kmですが、ここはすぐ横を迂回するなど(草や倒木で歩きにくいですが)すればよいでしょう。天照教社から少し上も野渓化していますが、すぐ横を迂回できます。
村山古道も他の山の中の古道同様、野渓化を免れません。野渓を歩くと割り切りましょう。先ほど挙げた所が標高の低い植林地内で道迷いしやすい悲惨なコース部分です。中宮八幡堂付近は家族連れ子供向けのハイキングコースに絶好です。それより上も歩きよい登山道に整備されつつあります。
なお天照教社より上には一切の村山古道を示す文字標識はなく(11年9月)テーピングと地図・磁石を頼りに歩きました。例外は高鉢駐車場を示す標識と宝永遊歩道の標識はありました。そして宝永遊歩道付近で突然多数のハイカーと行きかいました。それまでまったく人に会わない登山道でしたから驚きました。向こうのハイカーも変な所から人が出てきたので驚いてました。このとき村山古道を歩いていたのは私一人だったようです。村山古道で動けなくなっても誰も通らないでしょう。まったく静かなコースで誰もいません。あとこんなに静かなコースは、精進口登山道、大沢崩れ左右の登山道ぐらいでしょう。
*村山古道は富士宮口新六合目で富士宮口登山道となるというより、歴史的にはその逆でしょうが、今は富士宮口といいます。そこで六合目より上は一般の富士登山ガイドブックを参照してください。ちなみに山頂には破壊された石仏がいくつもあるようです。廃仏毀釈による破壊についても「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八:著を参照してください。なお破壊されず難を逃れた物もあるようです。
コースタイムの距離はキルビメーターで測りましたが、どうも実際より30%ほど短い気がします。実際歩くと表示距離より30%増しにして下さい。つまり表示1.5kmなら2kmです。時間はややゆっくりめにしたつもりですので、健脚者はもっと速く、初心者はもっとゆっくりかもしれません。休憩時間は入れませんし、道迷いの時間も含んでいません。
村山古道は日沢に沿うように道がつけられています。普段は涸れ沢ですが、雨が降ると濁流が流れます。ちょうど山の村の富士市と富士宮市の境界標識がある川です。11年9月17日、下界は雨がやんでいるのに山の村は土砂降りで緑陰広場横の日沢も深さ20cmの濁流でした。翌日は沢には水一滴もありませんでした。9月23日に行くと沢は涸れていましたが、2日前に台風15号直撃を受け、山の村すぐ下の吉原林道と交差する箇所が破壊され通行不能でした。緑陰広場横の日沢の枯葉の堆積から深さ50cmの濁流が流れたと推定されます。駿河湾の湿った空気が富士山麓南面の地に当たり村山周辺にすさまじい降雨量となって降るためのようです。地元ではベタベタだかベトベトと言うようです。その雨水が片っ端から地面をえぐるため、道も広場もガタガタになります。村山古道の野渓化やむなしです。雨のあとどの道の状態も悪化します。通行不能もありえます。樹木にしても地面が溶岩でやせているのか風が強いのか、倒木になり道をふさぐのは日常茶飯事かもしれません。下界は降って無くても当地で土砂降りのとき、沢や野渓化した道は通行不能でしょう。
・コースタイム
富士宮口新六合目、宝永山荘、H2490m ←→宝永第一火口手前
↓↑ 0.5km 30分 ↑↓ 20分 ↓↑
富士宮口五合目←→ 宝永遊歩道分岐点、H2350m ←→宝永第二火口手前
(二合目、三合目石室跡…石垣、便所穴跡)
0.7km 40分 ↑↓ 30分 一合目小屋跡ともう一つ平坦地がある。
一ノ木戸跡(石段、石垣、やかん) H2150m
0.6km 30分 ↑↓ 20分
横渡(日沢を渡る) H2000m
0.6km 30分 ↑↓ 20分
笹垢離跡(石仏) H1870m
0.3km 10分↑↓ 7分
岩屋不動への分岐点、H1800m ←0.7km、30分→ 岩屋不動跡、H1870m
0.5km 20分 ↑↓ 15分
高鉢駐車場←→ 「高鉢駐車場~御殿庭コース散策道」分岐点、H1720m ←→御殿庭
0.7km 25分 ↓↑ 20分
富士山スカイライン152号線(180号線分岐~富士山五合目)「10.8km」標識、H1600m
1.5km 50分 ↑↓ 40分
富士山スカイライン180号線(山宮~御殿場)「7.8km」標識、H1340m
1km 30分 ↑↓ 20分
中宮八幡堂跡、 H1250m
2km 50分 ↑↓ 40分
富士山麓山の村(緑陰広場)、 H1090m
1km 30分 ↑↓ 20分
天照教社、 H1000m
1km 30分 ↑↓ 20分
林道富士裾野線交差点、 H740m
2km 50分 ↑↓ 40分 上ってすぐに札打場ケヤキがある。
北井久保林道交差点、 H800m
1km 30分 ↑↓ 20分 途中、発心門跡を通過するが単なる平坦地で痕跡なし。
五辻(林道から登山道へ)、 H650m
0.5km 15分 ↑↓ 10分
最初の馬頭観音(チェーンが張られこの先自動車通行不可)、 H590m
1.5km 45分 ↑↓ 30分徒歩
村山浅間神社、標高H490m
・解説
・ 村山浅間神社西横から部分的に石畳道があり、途切れたところは集落内の舗装された生活道路を通行するので安心して通れる。村山集落の北に向かい最後の人家:鯛津氏宅(この村山古道復活活動の地元有志)を過ぎると寂しい道になる。
・ チェーンが張られた林道の横に最初の馬頭観音がある。車を置くなら左折してもう50mも奥に行けば平坦な所がある。よくよく見るとこの平坦な所やこの下の涸れ沢が本来の村山道ではないかという気がする。林道歩きは500mで終わり登山道に取り付く。
・ 五辻から登山道区間に入ると途端にV字谷のような野渓化した道に出くわす。そしてそれを迂回するかのようにすぐ横に別の切通しが通っていくのが分かる。それがしょっちゅうであり、これは他の古道でもよくある例である。ただ県内の他の古道よりえぐれ方が激しいのは、さすが富士山という高山にして溶岩の山で降雨量の多い地であるためだろう。もはやファミリー向けハイキングコースではない。
・ 発心門の辺りはなんとなく平坦な植林地である。かつては礎石があったらしいが今は痕跡もない。発心門推定地に標識があるといいですね。このあとコースは上へ上らず、ひたすら横へ水平移動し、林道へ出てそこから又上り、札打場ケヤキに至る。それにしてもなぜここで上らず水平移動するのか? 日沢との関連か? 札打場ケヤキに行きたいのか? 札打場を過ぎるとまたいくつも野渓のような道を通過する。天照教社に近づくと道がよくなってくる。
・ 天照教社前で舗装された林道に出て標識も多い。11年9月村山古道の文字標識はこれより上にはなかった。ここからしばらく野渓のような道もあるが平坦に近くすぐ横を迂回しやすい。山の村に近づくと平坦な森林散策路となる。一旦吉原林道を横断して山の村敷地に入る。吊り橋の下は金属パイプもくぐるため狭いが道はよい。このあとすぐ道はえぐれたオーバーハングの下となる。昔は左に上ったようだが今は無理なので、右から上る。そのように標識やロープが張られている。進むとすぐ山の村の車道と緑陰広場に出る。休憩によい。
・ 山の村緑陰広場で交差する箇所には11年9月にはまったく標識はなく、ガイドマップを持っている人にしか分からないようになっている。下りはいきなりオーバーハングの崖を避けて上り下りするところがあり、注意書きと黄色いロープがある。緑陰広場の右奥からの上りは野渓が1km続き、このままでは家族や子供用のハイキングコースにはなりにくい。2番目の馬頭観音より先は森の散策コースになり快適に大淵林道を横断し涸れた日沢も越えて、中宮八幡堂跡を目指せる。中宮八幡堂跡付近は地元の人が使うのできれいな道でありハイキングコースになる。富士山スカイライン「7.8km」標識までは道迷いなく快適に歩けると思われる。
・ 「7.8km」標識近くに登山道は開けているがテーピングがあるだけで、何の道かは知っている人にしか分からない。ここからもしばらく歩きやすい道だが周辺のコケだらけなのを見ても分かるとおり、夏は湿度が高く蒸し暑い。緑のコケの絨毯はしっとりした日本庭園のようで美しい。「10.8km」標識手前に一箇所岩むき出しの急坂があるが慎重に通過すればよいでしょう。これも野渓化ですね。
・ 「10.8km」標識近くのテーピングの切り開けから入山。高鉢駐車場分岐点では文字標識がある。これより上の古道では宝永遊歩道までエスケープ不能となる。この先ちょいとした人工的広場があり、「大樅」という修験場跡がある。この先へつりになっているところがあるので注意。
・ 岩屋不動への道はくたびれ果てた白テープとかすかな踏み跡を頼りにたどり、渓谷辺りで黄色いロープがいくつも張られていてやっと分かった次第。一応「危険なので注意して参拝してください」との注意書き。洞窟というほどではないが、岩の割れ目の暗黒世界が拝める。なかなかの巨岩の涸れ滝世界。山岳修験に似つかわしく行者が修行するにはよい所でしょう。
・ 笹垢離跡の石仏はかつて3体、ガイドブックでは4体、そしてこのときは5体だったと思う。? だんだん地中から出土してくるのでしょうか。晴れていれば絶景。ちょいと草と倒木は多いが野渓よりまし。
・ 横渡も晴れていれば絶景で、涸れ沢の日沢も安心して渡れるが、テーピングが失われるときつかろう。
・ 一ノ木戸跡にあるやかんは薄手で近代以後の産物と思われる。おそらく昭和期のものか。ただ畠堀操八氏が言うようにこのまま安置すべきだろう。村山古道自体が文化財であり保存できるとよいという意識で通行しよう。その後一合目小屋跡ともう一箇所小さな平坦地がある。この付近倒木が多いが切断され踏み跡がたどれるようになっている。
・ 二合目、三合目石室跡の石垣や便所穴跡は宝永遊歩道のすぐ近くであるがそこを通る誰もが気付かないようだ。まあその方がよいだろう。二合目と三合目の石室はすぐ近くだが、この辺りがかつての森林限界だったため、すぐ近くに2つ建てざるをえなかったのか?
・ 岩室跡より上では樹木が低く明るくなる。すぐに樹木がなくなり、ガラガラの溶岩石帯になる。テーピングではなく、石に付けられた水色マーキングをたどる。晴れていると絶景で振り返れば愛鷹山から海まで見え、この上の6合目山荘も見える。そこで富士宮口登山道と合流する。
・推論
笹垢離跡(石仏)H1870mは特段、道の状況が変わるわけでもない坂の途中に唐突にある感じがする。普通石仏等を祀り垢離を行う場所はそれなりの雰囲気のある所なので不思議な気がする。その手前に岩屋不動への分岐点、H1800mがあり、木馬道をたどって岩屋不動跡、H1870mへ達するのだが、岩屋不動跡、H1870mと同じ標高なのだ。多分昔はこの二箇所が同一標高のまま平坦な道で結ばれていたのではなかろうか。あるいは同一標高の笹垢離で禊をすれば岩屋不動まで行かなくとも同じご利益があるとでも考えたのだろうか。
・参考資料
・「富士山・村山古道を歩く」畠堀操八:著、風濤社、’06
・「富士山村山口登山道跡調査報告書」富士宮市立郷土資料館、’93
・「本山修験宗聖護院富士山入峯修行復活 富士山表口登山道全図 富士山村山古道を歩く」畠堀操八、NPO法人シニア大樂山樂カレッジ、’09、¥1000
2011年10月02日
古代の東海道(静岡市→焼津市)、万葉の東路
古代の東海道(静岡市→焼津市)、万葉の東路
静岡市から西の日本坂峠を越え焼津市の花沢の里へ向かう古代の道が推定されているので紹介する。推定ルートは以下である。
駿河国府→舟山→猿郷→手児の呼坂→宗小路→細工所→谷津神社→谷津峠→的山峠→井尻峠→大和田→小坂→日本坂峠
このコースは丸子の下流平野部を避けて山際を通るようになっていて、増水したときや古代以前の弥生期にも使われていたのではないかとさえ思われる。古代以前には丸子下流平野は入り江だったかもしれない。
・駿河国府→舟山
実は駿河国府は確定地がない。推定では長谷通りの静岡高校辺り(国府跡の石碑があるが、あくまで推定地の一つ)、あるいは横内・横田辺りだろうとされている。まあ広く見て浅間神社から駿府城跡周辺だろう。しかし片山廃寺の件から駅南の小鹿辺りという説まである。ここでは浅間神社から駿府城跡周辺として舟山に出る。現在の本通りと安西通りの間を通り、田町で現在の安倍川を渡ると途中の中洲に舟山がある。確たる道筋は不明だ。ここに安倍川があるのは、江戸時代初期に家康が薩摩土手を作らせたからで、それまでは藁科川下流だったはずで、安東と安西の間を安倍川は幾筋かに分流して流れていたろう。舟山までに安倍川分流を数本渡るはずだろう。なおさら道筋は分からない。
・舟山→猿郷
多分ここで藁科川を渡ったのだろう。舟山には現在舟山神社がある。80年代には祠が一つあるだけだった。なお舟山に行くには安倍川を徒歩で渡るしかないので、水が減ったときを見て渡るしかない。増水時は渡渉不可能。猿郷からは陸路となる。
・猿郷→手児の呼坂
猿郷から山際を南下していく。昔の道らしきは、山際をたどれば概ねよいようだ。ただし通れないところもあり、古道は消失していく。
底本とした「ふるさとの東路 知られざる万葉の道」滝本雄士と「古街道を行く」鈴木茂伸の南藁科街道に詳しい説明があるので参照するとよい。
徳願寺前を通過してしばらくすると手児の呼坂の入口となる。
・手児の呼坂
入口に西国順礼塔や他の石塔が立つ。道は舗装された農道となっている。最後は歩道を歩き峠となる。記念碑等がある。下ればまた農道となり、宗小路という辺りになる。
・宗小路→細工所
古く狭い道が山ろくにあったようだが、不明なので、平野の北丸子工業団地に出る。大きな工場敷地が四角く区分されていて、新道を通る。
・(周辺紹介)龍国寺(戸斗ノ谷、北丸子二丁目27)
駿河一国百地蔵第十二番、「南無観世音」、庚申塔、「三界萬霊」、菩薩、石灯籠、六地蔵3×2、石塔、地蔵4、馬頭観音、鐘楼、
・(周辺紹介) 戸斗ノ谷公民館(戸斗ノ谷、北丸子二丁目26)
古い墓石が多数集まっている。
・津島神社(戸斗ノ谷、北丸子二丁目10)
北丸子工業団地の大きな工場を過ぎた直後山際に神社への参道入口となる。
創建不詳、再建天正二年。手洗石、石段「昭和9」、狛犬「昭和46」、石灯籠「寛政五」。
津島神社参道入口から丸子の平野部を南へ渡る。現在の国道1号線や江戸期旧東海道(県道)も渡る。古道ははっきりしないが、ここから丸子幼稚園に行く道と考えると割合古道らしいところを通れる。新興住宅地内の新しい道をそれなりに曲がっては丸子幼稚園方向を目指す。戸斗前公園の東を通過し橋を渡り南下する。国1手前でアパート西の道らしくない道で空き地のようなところ(多分古道)を通過すると国1向かいに丸子幼稚園がある。
・丸子幼稚園東側の古道(丸子六丁目7)
丸子幼稚園東の路地が古道らしい。多分この道は丸子幼稚園園長:野上氏(宝台院別院)の善意で残されているのだろう。この路地を抜けると旧東海道に出る。2軒分東に行きそこの路地を南に進むと丸子川の土手に出て、川向こうに谷津神社がある。
・(周辺紹介)丸子一里塚(丸子六丁目6)
旧東海道をもう数十m東に進むと一里塚跡になる。
・(周辺紹介)地蔵堂(丸子六丁目13)
駿河一国百地蔵第十一番、石地蔵3、庚申塔3「昭和55」「大正9」、
・(周辺紹介)文殊堂(丸子)
智恵文殊菩薩、石塔。丸子川沿い谷津神社少し南。
・谷津神社(丸子4970、芹ヶ谷)
創建不詳、再建永禄九年。静岡市指定天然記念物:クスノキ(幹直径1.9m、樹齢約千年)、手洗石「明治30」、石鳥居「明治39」。
・谷津峠 谷津神社から芹が谷に山越えする峠を谷津峠という。標識は一切ないので周辺住民に聞いてから上ったほうがよい。しかし住民にもあまり周知されていないので情報は得にくいだろう。谷津神社前の道を左の畑に沿って山奥に入っていく。距離300m約5分も上れば切通しの峠である。11年5月現在ここに朽ちかけた「谷津峠 標高71.9m」の標識があり、間違いなく峠であることが分かるが、将来はやめに朽ち果てるだろう。さてここから杉檜の植林が数十m下り続けてからみかん畑になっているが、植林地内は道が分からない。適当に下ってみかん畑に降り、あとは歩きやすいところを下った。山を降り切る手前に階段になり、平野部には芹が谷の住宅地が広がっていた。下りも約5分。左に2階建てアパート(丸子芹が谷町5)があるところに出て町となる。ここにも標識はない。
・的山峠マトウトウゲ、マトヤマトウゲ
芹が谷から井尻へ山越えしていける道があり、この峠を的山峠という。
やなぎだ眼科医院(丸子芹が谷町9-1)を目指し、やなぎだ眼科医院から南の山あいの谷地に入っていく。谷地の農地に入っていくところに朽ちかけた「谷津峠↓←→的山峠」標識がある。谷地に入っていいのだが、この先の谷地の農地から峠のある山腹に取り付く所には標識はないので、住民に聞くしかない。最後の住宅も過ぎ農地だけになって川が広がって水を溜めている池みたいなところの2箇所過ぎたところを左に曲がり、川に架かる板橋を渡る。草刈もしていないので草だらけの斜面をモノラックのレール(索道)を横目に見つつ、「もとは道だなあ」と思いつつ約5分上ると、頂上に「井尻←的山峠→芹が谷」標識がある。頂上部の尾根は歩きやすく眺めもよい。井尻への下り道は草もなく快適である。5分下ると平坦な車道に接続する。ここに「井尻峠←→的山峠」標識がある。車道へ出ず細い野良道をさらに行くと井尻の集落内に出る。ここにも「井尻峠←→的山峠」標識がある。いったん集落内の小野寺参道の車道に出て小野寺方向を目指す。すぐに神社がある。
・八幡神社(丸子井尻)
手洗石、石灯籠「昭和18」「大正3」、小野寺への丁石「一丁目」が横倒し。
小野寺参道麓に位置する。ここから裏山の井尻峠を越え向こうの大和田に行くことができる。この神社の左手(南)に小野寺とは別方向に上る道がある。左手奥の低い所が井尻峠で向こうは大和田である。神社手前を左に上る。
・(周辺紹介)小野寺(丸子3877)
この山腹に古い五輪塔が散在し、手越河原の戦いの死者を弔うものといわれている。石塔類多数。丁石は八丁目まである。寺から西尾根を進めば朝鮮岩である。
・井尻峠
井尻と大和田を結ぶ古道で、万葉の東路として紹介されている。井尻と大和田を最短で結ぶ道である。上り下りにきつくない峠なので生活道路としても便がよかったろう。尾根を西に上れば小野寺で東に進めば渭川寺裏山イセンジである。八幡神社から約5分で峠である。下りも約5分で農道に出る。農道の分岐点に「井尻峠←→大和田」標識がある。
ただ大和田から上る場合、畑内で2~3箇所山道が分岐するが標識が無いので2~3回道迷いして約10~15分かけて上ったので、住民に聞いてから上ったほうがよい。ヒントは大和田の農道から山の畑に入る標識のある所のやや左上の低い所が峠であるので、そちらを目指すと思えばよい。
農道を下って行けば大和田集落である。途中農道は左右に分岐するが、左は神社経由で下り、右は直接下る道で、どちらも麓で合流する。
・大和田神社(大和田101)
農道の途中、集落よりやや上にある。創建不詳、再建文化十一年。手洗石、石鳥居「昭和60」、樹木:200~500年。大和田の地名は水が淀むまたは溜まる所を意味し、地形からも古くは入り江の内浦だったと推定されている。集落を下りきり麓の山際道に出るとお堂がある。
・馬頭観音堂、地蔵(大和田204)
双体馬頭観音、地蔵3、庚申塔3「昭和55」「大正9」、標識「万葉の東路 大和田→井尻峠」。
・墓地(大和田78)
馬頭観音堂を山際に沿い東に70m進むと、朽ち欠けた約50の墓石が道路から見える。またお堂のほうに戻り、西の小坂方面に進む。
はじめ「この先行き止まり」と標識のある山際の未舗装路を西に進むが、そのうち城山中学前辺りで山際の古い道が遮断されるので、いったんまっすぐで広い道路に迂回する。しばらく古道は通れない。
・板碑4(小坂橋南たもと)
耕地整理等記念碑。
・庚申塔(小坂JA支店前バス停)
「庚申供養塔 昭和55」、「庚申供養塔大正九年 右用宗停車場十三丁 左静岡縣廰二里 西花澤一里五丁」。
・御所の前(小坂1424) 石碑「御所の前」。日本武尊伝説の地で、ここで休憩したという。用宗・石部からの古道もここで合流した。ここから古道である。
・ 神社、地蔵(小坂1280)
御所の前の北東にある。手前に地蔵もある。
・満願寺(小坂1336)
建武五年国宣状を賜う、曹洞宗、本尊:千手観音。「三界萬霊等」、近くに「一宮随波斎供養塔」があるらしい。寺は無住らしい。
御所の前から安養寺前を目指すと、途中左に石塔あり。瑞應寺を示す。
・地蔵、新・石道標「南無延命地蔵菩薩 雲梯山瑞應禅寺」。
・瑞應寺(小坂1076)
開山行基、開基日本武尊、臨済宗、子安観音地蔵堂、手洗石、観音、地蔵、石灯籠、新・地蔵:多数、金比羅宮。
寺の裏(南)を通っていくと熊野神社、さらには峠越えで石部に通じていた。
・熊野神社(小坂赤坂)
創建天正年中。巨木。石塔類。石部から峠越えで行ける。そして御所の前に出られる。
・安養寺(小坂1426)
安養寺前バス停に戻る。参道入口に石塔がある。自然石2、庚申塔2「昭和55」、庚申像、新・地蔵・馬頭観音。
建立文治三年、本尊:阿弥陀如来、家康お手植えの蜜柑の樹がある。「不許葷酒入山門」、「下馬」石、新・地蔵、句碑:多数、板碑、土肥7騎の墓、鐘楼、水琴窟、榧の巨木、半僧坊社、
・日枝神社(小坂1433-2)
元山王社、明治5年日枝神社。手洗石、石灯籠2、石鳥居:近代、堂、樹木:900年?
安養寺の隣にある。
・祠(小坂1407)
街道沿いにある。
・日本坂の磐座イワクラ(小坂1673)
祠の向かい側の道を入る。もと日本坂にあった磐座だが崩落したので所有者の自宅に展示した。
・石塔、土蔵(小坂公民館前バス停)
庚申供養塔「昭和55」「大正9」、「奉納大乗妙典経日本回□供養塔 天明二」、新・地蔵3、老人つどいの家の横に土蔵がある。
・石造物(小坂2149)
秋葉山常夜燈、地蔵堂:地蔵3.
・山ノ神(小坂2176)
祠2、石灯籠「安政三」。
・花立観音
座っている地蔵像である。
・「庚申供養塔」(日本坂と満願峰の分岐点)
「庚申供養塔 右十一番観世音二丁半 左日本坂頂上迠十二丁」、他には破損した石塔類。
・観音堂(分岐点より満願峰方向へ250m)
観音堂、三十三観音(破損したもの含め約26体)、堂5、石塔「安政六」、祠、不動尊、ひすいの滝、
・庚申塔(分岐点より日本坂方向へ300m)
「庚申塔」、「庚申供養塔 右日本坂道 左小坂道」。
・蛙石、子持石、小滝(日本坂への途中)
自然石、滝。
・日本坂峠(静岡市小坂、焼津市花沢)
古代東海道の峠道。穴地蔵。
・(周辺紹介)渭川寺裏山→井尻峠→小野寺→→朝鮮岩→→丸子富士(高山、蔵王権現)→水来頭峠→満願峰→小布川峠→雨乞神→日本坂峠(尾根道縦走路)
渭川寺裏山や井尻小野寺から尾根伝いに満願峰を経由し日本坂に行くことができる。今はハイキングコースであるが、昔も使われたと思われる。
新考察・古代官道(佐渡交差点、西之宮神社→大和田)
* ここまで万葉の東路を紹介してきたが、近年の研究で古代の官道:東海道が、JR東静岡駅・グランシップ(曲金北遺跡)で発見される等、古代官道を訂正する方向に動かざるをえなくなってきている。この考え方では西は佐渡交差点、西之宮神社から東は横砂の盧崎神社までを直線で結ぶ古代条里制による道である。途中で曲金北遺跡の官道を通過することになる。
丸子側は佐渡交差点、西之宮神社を起点にして大和田までのルートを考えることになる。大和田から日本坂峠までは同一と考える。西之宮神社から大和田に行くルートは2つ、1つ目は、西之宮神社から近世東海道筋を通過し、井尻に出て井尻峠を越えて大和田に出る山越えコースである。2つ目は、西之宮神社から長田・鎌田方向を南下し渭川寺・巴川製紙工場で西に曲がり大和田に出る平野コースである。2つとも記述する。
1、佐渡交差点、西之宮神社→井尻峠→大和田
・佐渡交差点、西之宮神社(丸子)サワタリ
古代官道はこの西之宮神社から東は清見寺方向、横砂の盧崎神社イヲサキにまっすぐ突き当たるようだ。佐渡山は古墳群で、縄文や弥生期からの遺跡が出土する。
創建不詳、再建明和三年。「遷宮記念碑 昭和60年」、石鳥居「明治22年」、石灯籠、「庚申塔」3「大正九」「昭和55」、
・福泉寺(手越14)
石塔類。徳川秀忠の付き人の墓もあるなど由緒がある。
・佐渡の子授地蔵堂(丸子一丁目10)、「佐渡の手児万葉歌碑」(丸子一丁目8)
近世東海道のコースと一緒である。駿河一国百地蔵尊第十番。
この先の小豆川を渡ったところで近世東海道を左折し西の井尻を目指す。丸子川に架かる井尻橋を渡ると井尻地区である。小野寺のある山を目指すと麓に八幡神社がある。
堂の向かい側が佐渡公民館で「佐渡の手児万葉歌碑 昭和57」がある。
・石塔、石道標(昔は近世東海道の小野寺への分岐点にあったが今は丸子4丁目にある)
・八幡神社(丸子井尻)
手洗石、石灯籠「昭和18」「大正3」、小野寺への丁石「一丁目」が横倒し。
小野寺参道麓に位置する。ここから裏山の井尻峠を越え向こうの大和田に行くことができる。この神社の左手(南)に小野寺とは別方向に上る道がある。左手奥の低い所が井尻峠で向こうは大和田である。神社手前を左に上る。
・(周辺紹介)小野寺(丸子3877)
この山腹に古い五輪塔が散在し、手越河原の戦いの死者を弔うものといわれている。石塔類多数。丁石は八丁目まである。寺から西尾根を進めば朝鮮岩である。
・井尻峠
井尻と大和田を結ぶ古道で、万葉の東路として紹介されている。井尻と大和田を最短で結ぶ道である。上り下りにきつくない峠なので生活道路としても便がよかったろう。尾根を西に上れば小野寺で東に進めば渭川寺裏山イセンジである。八幡神社から約5分で峠である。下りも約5分で農道に出る。農道の分岐点に「井尻峠←→大和田」標識がある。
ただ大和田から上る場合、畑内で2~3箇所山道が分岐するが標識が無いので2~3回道迷いして約10~15分かけて上ったので、住民に聞いてから上ったほうがよい。ヒントは大和田の農道から山の畑に入る標識のある所のやや左上の低い所が峠であるので、そちらを目指すと思えばよい。
農道を下って行けば大和田集落である。途中農道は左右に分岐するが、左は神社経由で下り、右は直接下る道で、どちらも麓で合流する。
2、長田街道(手越原→鎌田→大和田)
佐渡交差点の西之宮神社(佐渡山あるいは徳願寺山南端で近世東海道と近代国道1号線の通過する要衝の地)から手越原交差点方向へ東に向かい進み、手越原交差点で南下する道をたどる平野部コースである。長田街道とも鎌田街道とも言う。
・佐渡交差点、西之宮神社(丸子)サワタリ
古代官道はこの西之宮神社から東は清見寺方向、横砂の盧崎神社にまっすぐ突き当たるようだ。佐渡山は古墳群で、縄文や弥生期からの遺跡が出土する。
創建不詳、再建明和三年。「遷宮記念碑 昭和60年」、石鳥居「明治22年」、石灯籠、「庚申塔」3「大正九」「昭和55」、
・福泉寺(手越14)
石塔類。徳川秀忠の付き人の墓もあるなど由緒がある。
・白髭神社(手越239)
創建不詳、伝創建永禄元年、再建寛保二年。石造物:石鳥居、手洗石、古代官道に面していたと思われる。
・手越原交差点
江戸期東海道と旧国道1号線及び、ここで取り上げる長田街道(県道用宗停車場・丸子線、鎌田街道)と、その向かい側で北進する南藁科街道(県道奈良間・手越線)が交差する。
手越は手越少将や手越河原の戦いで有名である。手越少将を祀った少将井神社は江戸期東海道に沿い、東進するとある。手越河原の戦いの記念碑はこの先紹介する。
古い街道はこの交差点より少し東から南に入る路地ではないかと推定される。170m南進すると道が途絶える。おそらくこの先に流れていく水路に沿って昔は道もあったのだろう。次に道が現れるのは無量寺横である。
・中央消防署鎌田出張所(鎌田54)
長田村役場跡。長田村の中心地だった。
・無量寺(鎌田56)
本尊:阿弥陀如来、創立天正年間、地蔵堂、板碑、新・石仏。
寺の東から南へ300m進む。この先未舗装の路地裏が現れたら、道を右折(西) し2軒分進んだらまた左折(南)し50m進む。左に神社がある。この道は寺田と鎌田の境界線になっている。
・八幡宮(寺田79)
創建不詳、伝創建元亀元年、再建天保十一年。祠。
鎌田と寺田の地区境がかつての旧道ではないかと推定される。この境に沿って南下する。途中で道ではなく家境が境界線となるので付近を迂回する。丸子川手前で広い通りに出る。公園の横で丸子川に出る。川向こうに青木天満宮が見える。今の化粧橋はもっと西なのでいったんそちらに迂回する。
・八幡神社(寺田74)
創建天正元(1573)年。手洗石「文化二」、他石造物:近代。樹木:300~600年?
・明光寺(寺田61)
創立永禄十二年、本尊:阿弥陀如来、駿河一国百地蔵第八番、地蔵堂、「庚申塔」、「西国三十三所供養塔」。
・化粧橋(寺田)
昔の橋はもう少し東の青木天満宮のところだったろう。
・化粧坂(寺田)
手越河原の戦いのとき、この坂に陣を敷いたという。寺田と青木の境の丘らしい。化粧橋近辺と思われるが詳細不明。
・青木天満宮(青木227)
創建不詳、再建天保十三年。手洗石「文化貳」、石造物:近代。元は青木270番台の地にあったそうなので、新幹線で用地を取られたのだろうか。今は移転して当地である。
かつての旧道はこの天満宮(当時はない)の横を通過したのではなかろうか。このまま南下すると道は西を向き、今の長田街道に出て向こうに渭川寺が見える。
・渭川寺イセンジ(青木435)
開礎天正十五年、「庚申供養塔」2、「一国三十三所」、新・石仏。
裏山は遺跡である。南の巴川製紙工場敷地内からも遺跡が発掘された。
・渭川寺裏山、神社(青木626)
裏山南側のお宅横から登れる。石仏:三面八手、台石「第二十二番」、手洗石:近代、石鳥居「昭和10」、本殿祠、道祖神、祠。遺跡でもあり、南の巴川製紙工場敷地内も遺跡が出土した。
道をここで西に変え、山際に沿い進む。ここからは長田(鎌田)街道をはずれる。
・みずほ公園(みずほ5丁目12)
手越河原の戦いの記念碑。
・墓地(大和田78)
大和田を山際に沿い進むと、朽ち欠けた約50の墓石が道路から見える。70m進むとお堂がある。
・馬頭観音堂、地蔵(大和田204)
双体馬頭観音、地蔵3、庚申塔3「昭和55」「大正9」、標識「万葉の東路 大和田→井尻峠」。
静岡市から西の日本坂峠を越え焼津市の花沢の里へ向かう古代の道が推定されているので紹介する。推定ルートは以下である。
駿河国府→舟山→猿郷→手児の呼坂→宗小路→細工所→谷津神社→谷津峠→的山峠→井尻峠→大和田→小坂→日本坂峠
このコースは丸子の下流平野部を避けて山際を通るようになっていて、増水したときや古代以前の弥生期にも使われていたのではないかとさえ思われる。古代以前には丸子下流平野は入り江だったかもしれない。
・駿河国府→舟山
実は駿河国府は確定地がない。推定では長谷通りの静岡高校辺り(国府跡の石碑があるが、あくまで推定地の一つ)、あるいは横内・横田辺りだろうとされている。まあ広く見て浅間神社から駿府城跡周辺だろう。しかし片山廃寺の件から駅南の小鹿辺りという説まである。ここでは浅間神社から駿府城跡周辺として舟山に出る。現在の本通りと安西通りの間を通り、田町で現在の安倍川を渡ると途中の中洲に舟山がある。確たる道筋は不明だ。ここに安倍川があるのは、江戸時代初期に家康が薩摩土手を作らせたからで、それまでは藁科川下流だったはずで、安東と安西の間を安倍川は幾筋かに分流して流れていたろう。舟山までに安倍川分流を数本渡るはずだろう。なおさら道筋は分からない。
・舟山→猿郷
多分ここで藁科川を渡ったのだろう。舟山には現在舟山神社がある。80年代には祠が一つあるだけだった。なお舟山に行くには安倍川を徒歩で渡るしかないので、水が減ったときを見て渡るしかない。増水時は渡渉不可能。猿郷からは陸路となる。
・猿郷→手児の呼坂
猿郷から山際を南下していく。昔の道らしきは、山際をたどれば概ねよいようだ。ただし通れないところもあり、古道は消失していく。
底本とした「ふるさとの東路 知られざる万葉の道」滝本雄士と「古街道を行く」鈴木茂伸の南藁科街道に詳しい説明があるので参照するとよい。
徳願寺前を通過してしばらくすると手児の呼坂の入口となる。
・手児の呼坂
入口に西国順礼塔や他の石塔が立つ。道は舗装された農道となっている。最後は歩道を歩き峠となる。記念碑等がある。下ればまた農道となり、宗小路という辺りになる。
・宗小路→細工所
古く狭い道が山ろくにあったようだが、不明なので、平野の北丸子工業団地に出る。大きな工場敷地が四角く区分されていて、新道を通る。
・(周辺紹介)龍国寺(戸斗ノ谷、北丸子二丁目27)
駿河一国百地蔵第十二番、「南無観世音」、庚申塔、「三界萬霊」、菩薩、石灯籠、六地蔵3×2、石塔、地蔵4、馬頭観音、鐘楼、
・(周辺紹介) 戸斗ノ谷公民館(戸斗ノ谷、北丸子二丁目26)
古い墓石が多数集まっている。
・津島神社(戸斗ノ谷、北丸子二丁目10)
北丸子工業団地の大きな工場を過ぎた直後山際に神社への参道入口となる。
創建不詳、再建天正二年。手洗石、石段「昭和9」、狛犬「昭和46」、石灯籠「寛政五」。
津島神社参道入口から丸子の平野部を南へ渡る。現在の国道1号線や江戸期旧東海道(県道)も渡る。古道ははっきりしないが、ここから丸子幼稚園に行く道と考えると割合古道らしいところを通れる。新興住宅地内の新しい道をそれなりに曲がっては丸子幼稚園方向を目指す。戸斗前公園の東を通過し橋を渡り南下する。国1手前でアパート西の道らしくない道で空き地のようなところ(多分古道)を通過すると国1向かいに丸子幼稚園がある。
・丸子幼稚園東側の古道(丸子六丁目7)
丸子幼稚園東の路地が古道らしい。多分この道は丸子幼稚園園長:野上氏(宝台院別院)の善意で残されているのだろう。この路地を抜けると旧東海道に出る。2軒分東に行きそこの路地を南に進むと丸子川の土手に出て、川向こうに谷津神社がある。
・(周辺紹介)丸子一里塚(丸子六丁目6)
旧東海道をもう数十m東に進むと一里塚跡になる。
・(周辺紹介)地蔵堂(丸子六丁目13)
駿河一国百地蔵第十一番、石地蔵3、庚申塔3「昭和55」「大正9」、
・(周辺紹介)文殊堂(丸子)
智恵文殊菩薩、石塔。丸子川沿い谷津神社少し南。
・谷津神社(丸子4970、芹ヶ谷)
創建不詳、再建永禄九年。静岡市指定天然記念物:クスノキ(幹直径1.9m、樹齢約千年)、手洗石「明治30」、石鳥居「明治39」。
・谷津峠 谷津神社から芹が谷に山越えする峠を谷津峠という。標識は一切ないので周辺住民に聞いてから上ったほうがよい。しかし住民にもあまり周知されていないので情報は得にくいだろう。谷津神社前の道を左の畑に沿って山奥に入っていく。距離300m約5分も上れば切通しの峠である。11年5月現在ここに朽ちかけた「谷津峠 標高71.9m」の標識があり、間違いなく峠であることが分かるが、将来はやめに朽ち果てるだろう。さてここから杉檜の植林が数十m下り続けてからみかん畑になっているが、植林地内は道が分からない。適当に下ってみかん畑に降り、あとは歩きやすいところを下った。山を降り切る手前に階段になり、平野部には芹が谷の住宅地が広がっていた。下りも約5分。左に2階建てアパート(丸子芹が谷町5)があるところに出て町となる。ここにも標識はない。
・的山峠マトウトウゲ、マトヤマトウゲ
芹が谷から井尻へ山越えしていける道があり、この峠を的山峠という。
やなぎだ眼科医院(丸子芹が谷町9-1)を目指し、やなぎだ眼科医院から南の山あいの谷地に入っていく。谷地の農地に入っていくところに朽ちかけた「谷津峠↓←→的山峠」標識がある。谷地に入っていいのだが、この先の谷地の農地から峠のある山腹に取り付く所には標識はないので、住民に聞くしかない。最後の住宅も過ぎ農地だけになって川が広がって水を溜めている池みたいなところの2箇所過ぎたところを左に曲がり、川に架かる板橋を渡る。草刈もしていないので草だらけの斜面をモノラックのレール(索道)を横目に見つつ、「もとは道だなあ」と思いつつ約5分上ると、頂上に「井尻←的山峠→芹が谷」標識がある。頂上部の尾根は歩きやすく眺めもよい。井尻への下り道は草もなく快適である。5分下ると平坦な車道に接続する。ここに「井尻峠←→的山峠」標識がある。車道へ出ず細い野良道をさらに行くと井尻の集落内に出る。ここにも「井尻峠←→的山峠」標識がある。いったん集落内の小野寺参道の車道に出て小野寺方向を目指す。すぐに神社がある。
・八幡神社(丸子井尻)
手洗石、石灯籠「昭和18」「大正3」、小野寺への丁石「一丁目」が横倒し。
小野寺参道麓に位置する。ここから裏山の井尻峠を越え向こうの大和田に行くことができる。この神社の左手(南)に小野寺とは別方向に上る道がある。左手奥の低い所が井尻峠で向こうは大和田である。神社手前を左に上る。
・(周辺紹介)小野寺(丸子3877)
この山腹に古い五輪塔が散在し、手越河原の戦いの死者を弔うものといわれている。石塔類多数。丁石は八丁目まである。寺から西尾根を進めば朝鮮岩である。
・井尻峠
井尻と大和田を結ぶ古道で、万葉の東路として紹介されている。井尻と大和田を最短で結ぶ道である。上り下りにきつくない峠なので生活道路としても便がよかったろう。尾根を西に上れば小野寺で東に進めば渭川寺裏山イセンジである。八幡神社から約5分で峠である。下りも約5分で農道に出る。農道の分岐点に「井尻峠←→大和田」標識がある。
ただ大和田から上る場合、畑内で2~3箇所山道が分岐するが標識が無いので2~3回道迷いして約10~15分かけて上ったので、住民に聞いてから上ったほうがよい。ヒントは大和田の農道から山の畑に入る標識のある所のやや左上の低い所が峠であるので、そちらを目指すと思えばよい。
農道を下って行けば大和田集落である。途中農道は左右に分岐するが、左は神社経由で下り、右は直接下る道で、どちらも麓で合流する。
・大和田神社(大和田101)
農道の途中、集落よりやや上にある。創建不詳、再建文化十一年。手洗石、石鳥居「昭和60」、樹木:200~500年。大和田の地名は水が淀むまたは溜まる所を意味し、地形からも古くは入り江の内浦だったと推定されている。集落を下りきり麓の山際道に出るとお堂がある。
・馬頭観音堂、地蔵(大和田204)
双体馬頭観音、地蔵3、庚申塔3「昭和55」「大正9」、標識「万葉の東路 大和田→井尻峠」。
・墓地(大和田78)
馬頭観音堂を山際に沿い東に70m進むと、朽ち欠けた約50の墓石が道路から見える。またお堂のほうに戻り、西の小坂方面に進む。
はじめ「この先行き止まり」と標識のある山際の未舗装路を西に進むが、そのうち城山中学前辺りで山際の古い道が遮断されるので、いったんまっすぐで広い道路に迂回する。しばらく古道は通れない。
・板碑4(小坂橋南たもと)
耕地整理等記念碑。
・庚申塔(小坂JA支店前バス停)
「庚申供養塔 昭和55」、「庚申供養塔大正九年 右用宗停車場十三丁 左静岡縣廰二里 西花澤一里五丁」。
・御所の前(小坂1424) 石碑「御所の前」。日本武尊伝説の地で、ここで休憩したという。用宗・石部からの古道もここで合流した。ここから古道である。
・ 神社、地蔵(小坂1280)
御所の前の北東にある。手前に地蔵もある。
・満願寺(小坂1336)
建武五年国宣状を賜う、曹洞宗、本尊:千手観音。「三界萬霊等」、近くに「一宮随波斎供養塔」があるらしい。寺は無住らしい。
御所の前から安養寺前を目指すと、途中左に石塔あり。瑞應寺を示す。
・地蔵、新・石道標「南無延命地蔵菩薩 雲梯山瑞應禅寺」。
・瑞應寺(小坂1076)
開山行基、開基日本武尊、臨済宗、子安観音地蔵堂、手洗石、観音、地蔵、石灯籠、新・地蔵:多数、金比羅宮。
寺の裏(南)を通っていくと熊野神社、さらには峠越えで石部に通じていた。
・熊野神社(小坂赤坂)
創建天正年中。巨木。石塔類。石部から峠越えで行ける。そして御所の前に出られる。
・安養寺(小坂1426)
安養寺前バス停に戻る。参道入口に石塔がある。自然石2、庚申塔2「昭和55」、庚申像、新・地蔵・馬頭観音。
建立文治三年、本尊:阿弥陀如来、家康お手植えの蜜柑の樹がある。「不許葷酒入山門」、「下馬」石、新・地蔵、句碑:多数、板碑、土肥7騎の墓、鐘楼、水琴窟、榧の巨木、半僧坊社、
・日枝神社(小坂1433-2)
元山王社、明治5年日枝神社。手洗石、石灯籠2、石鳥居:近代、堂、樹木:900年?
安養寺の隣にある。
・祠(小坂1407)
街道沿いにある。
・日本坂の磐座イワクラ(小坂1673)
祠の向かい側の道を入る。もと日本坂にあった磐座だが崩落したので所有者の自宅に展示した。
・石塔、土蔵(小坂公民館前バス停)
庚申供養塔「昭和55」「大正9」、「奉納大乗妙典経日本回□供養塔 天明二」、新・地蔵3、老人つどいの家の横に土蔵がある。
・石造物(小坂2149)
秋葉山常夜燈、地蔵堂:地蔵3.
・山ノ神(小坂2176)
祠2、石灯籠「安政三」。
・花立観音
座っている地蔵像である。
・「庚申供養塔」(日本坂と満願峰の分岐点)
「庚申供養塔 右十一番観世音二丁半 左日本坂頂上迠十二丁」、他には破損した石塔類。
・観音堂(分岐点より満願峰方向へ250m)
観音堂、三十三観音(破損したもの含め約26体)、堂5、石塔「安政六」、祠、不動尊、ひすいの滝、
・庚申塔(分岐点より日本坂方向へ300m)
「庚申塔」、「庚申供養塔 右日本坂道 左小坂道」。
・蛙石、子持石、小滝(日本坂への途中)
自然石、滝。
・日本坂峠(静岡市小坂、焼津市花沢)
古代東海道の峠道。穴地蔵。
・(周辺紹介)渭川寺裏山→井尻峠→小野寺→→朝鮮岩→→丸子富士(高山、蔵王権現)→水来頭峠→満願峰→小布川峠→雨乞神→日本坂峠(尾根道縦走路)
渭川寺裏山や井尻小野寺から尾根伝いに満願峰を経由し日本坂に行くことができる。今はハイキングコースであるが、昔も使われたと思われる。
新考察・古代官道(佐渡交差点、西之宮神社→大和田)
* ここまで万葉の東路を紹介してきたが、近年の研究で古代の官道:東海道が、JR東静岡駅・グランシップ(曲金北遺跡)で発見される等、古代官道を訂正する方向に動かざるをえなくなってきている。この考え方では西は佐渡交差点、西之宮神社から東は横砂の盧崎神社までを直線で結ぶ古代条里制による道である。途中で曲金北遺跡の官道を通過することになる。
丸子側は佐渡交差点、西之宮神社を起点にして大和田までのルートを考えることになる。大和田から日本坂峠までは同一と考える。西之宮神社から大和田に行くルートは2つ、1つ目は、西之宮神社から近世東海道筋を通過し、井尻に出て井尻峠を越えて大和田に出る山越えコースである。2つ目は、西之宮神社から長田・鎌田方向を南下し渭川寺・巴川製紙工場で西に曲がり大和田に出る平野コースである。2つとも記述する。
1、佐渡交差点、西之宮神社→井尻峠→大和田
・佐渡交差点、西之宮神社(丸子)サワタリ
古代官道はこの西之宮神社から東は清見寺方向、横砂の盧崎神社イヲサキにまっすぐ突き当たるようだ。佐渡山は古墳群で、縄文や弥生期からの遺跡が出土する。
創建不詳、再建明和三年。「遷宮記念碑 昭和60年」、石鳥居「明治22年」、石灯籠、「庚申塔」3「大正九」「昭和55」、
・福泉寺(手越14)
石塔類。徳川秀忠の付き人の墓もあるなど由緒がある。
・佐渡の子授地蔵堂(丸子一丁目10)、「佐渡の手児万葉歌碑」(丸子一丁目8)
近世東海道のコースと一緒である。駿河一国百地蔵尊第十番。
この先の小豆川を渡ったところで近世東海道を左折し西の井尻を目指す。丸子川に架かる井尻橋を渡ると井尻地区である。小野寺のある山を目指すと麓に八幡神社がある。
堂の向かい側が佐渡公民館で「佐渡の手児万葉歌碑 昭和57」がある。
・石塔、石道標(昔は近世東海道の小野寺への分岐点にあったが今は丸子4丁目にある)
・八幡神社(丸子井尻)
手洗石、石灯籠「昭和18」「大正3」、小野寺への丁石「一丁目」が横倒し。
小野寺参道麓に位置する。ここから裏山の井尻峠を越え向こうの大和田に行くことができる。この神社の左手(南)に小野寺とは別方向に上る道がある。左手奥の低い所が井尻峠で向こうは大和田である。神社手前を左に上る。
・(周辺紹介)小野寺(丸子3877)
この山腹に古い五輪塔が散在し、手越河原の戦いの死者を弔うものといわれている。石塔類多数。丁石は八丁目まである。寺から西尾根を進めば朝鮮岩である。
・井尻峠
井尻と大和田を結ぶ古道で、万葉の東路として紹介されている。井尻と大和田を最短で結ぶ道である。上り下りにきつくない峠なので生活道路としても便がよかったろう。尾根を西に上れば小野寺で東に進めば渭川寺裏山イセンジである。八幡神社から約5分で峠である。下りも約5分で農道に出る。農道の分岐点に「井尻峠←→大和田」標識がある。
ただ大和田から上る場合、畑内で2~3箇所山道が分岐するが標識が無いので2~3回道迷いして約10~15分かけて上ったので、住民に聞いてから上ったほうがよい。ヒントは大和田の農道から山の畑に入る標識のある所のやや左上の低い所が峠であるので、そちらを目指すと思えばよい。
農道を下って行けば大和田集落である。途中農道は左右に分岐するが、左は神社経由で下り、右は直接下る道で、どちらも麓で合流する。
2、長田街道(手越原→鎌田→大和田)
佐渡交差点の西之宮神社(佐渡山あるいは徳願寺山南端で近世東海道と近代国道1号線の通過する要衝の地)から手越原交差点方向へ東に向かい進み、手越原交差点で南下する道をたどる平野部コースである。長田街道とも鎌田街道とも言う。
・佐渡交差点、西之宮神社(丸子)サワタリ
古代官道はこの西之宮神社から東は清見寺方向、横砂の盧崎神社にまっすぐ突き当たるようだ。佐渡山は古墳群で、縄文や弥生期からの遺跡が出土する。
創建不詳、再建明和三年。「遷宮記念碑 昭和60年」、石鳥居「明治22年」、石灯籠、「庚申塔」3「大正九」「昭和55」、
・福泉寺(手越14)
石塔類。徳川秀忠の付き人の墓もあるなど由緒がある。
・白髭神社(手越239)
創建不詳、伝創建永禄元年、再建寛保二年。石造物:石鳥居、手洗石、古代官道に面していたと思われる。
・手越原交差点
江戸期東海道と旧国道1号線及び、ここで取り上げる長田街道(県道用宗停車場・丸子線、鎌田街道)と、その向かい側で北進する南藁科街道(県道奈良間・手越線)が交差する。
手越は手越少将や手越河原の戦いで有名である。手越少将を祀った少将井神社は江戸期東海道に沿い、東進するとある。手越河原の戦いの記念碑はこの先紹介する。
古い街道はこの交差点より少し東から南に入る路地ではないかと推定される。170m南進すると道が途絶える。おそらくこの先に流れていく水路に沿って昔は道もあったのだろう。次に道が現れるのは無量寺横である。
・中央消防署鎌田出張所(鎌田54)
長田村役場跡。長田村の中心地だった。
・無量寺(鎌田56)
本尊:阿弥陀如来、創立天正年間、地蔵堂、板碑、新・石仏。
寺の東から南へ300m進む。この先未舗装の路地裏が現れたら、道を右折(西) し2軒分進んだらまた左折(南)し50m進む。左に神社がある。この道は寺田と鎌田の境界線になっている。
・八幡宮(寺田79)
創建不詳、伝創建元亀元年、再建天保十一年。祠。
鎌田と寺田の地区境がかつての旧道ではないかと推定される。この境に沿って南下する。途中で道ではなく家境が境界線となるので付近を迂回する。丸子川手前で広い通りに出る。公園の横で丸子川に出る。川向こうに青木天満宮が見える。今の化粧橋はもっと西なのでいったんそちらに迂回する。
・八幡神社(寺田74)
創建天正元(1573)年。手洗石「文化二」、他石造物:近代。樹木:300~600年?
・明光寺(寺田61)
創立永禄十二年、本尊:阿弥陀如来、駿河一国百地蔵第八番、地蔵堂、「庚申塔」、「西国三十三所供養塔」。
・化粧橋(寺田)
昔の橋はもう少し東の青木天満宮のところだったろう。
・化粧坂(寺田)
手越河原の戦いのとき、この坂に陣を敷いたという。寺田と青木の境の丘らしい。化粧橋近辺と思われるが詳細不明。
・青木天満宮(青木227)
創建不詳、再建天保十三年。手洗石「文化貳」、石造物:近代。元は青木270番台の地にあったそうなので、新幹線で用地を取られたのだろうか。今は移転して当地である。
かつての旧道はこの天満宮(当時はない)の横を通過したのではなかろうか。このまま南下すると道は西を向き、今の長田街道に出て向こうに渭川寺が見える。
・渭川寺イセンジ(青木435)
開礎天正十五年、「庚申供養塔」2、「一国三十三所」、新・石仏。
裏山は遺跡である。南の巴川製紙工場敷地内からも遺跡が発掘された。
・渭川寺裏山、神社(青木626)
裏山南側のお宅横から登れる。石仏:三面八手、台石「第二十二番」、手洗石:近代、石鳥居「昭和10」、本殿祠、道祖神、祠。遺跡でもあり、南の巴川製紙工場敷地内も遺跡が出土した。
道をここで西に変え、山際に沿い進む。ここからは長田(鎌田)街道をはずれる。
・みずほ公園(みずほ5丁目12)
手越河原の戦いの記念碑。
・墓地(大和田78)
大和田を山際に沿い進むと、朽ち欠けた約50の墓石が道路から見える。70m進むとお堂がある。
・馬頭観音堂、地蔵(大和田204)
双体馬頭観音、地蔵3、庚申塔3「昭和55」「大正9」、標識「万葉の東路 大和田→井尻峠」。
2011年10月02日
「東海道山すじ日記」の通行ルート
・「東海道山すじ日記」、著:松浦武四郎、翻字・解説:宮本勉、羽衣出版、’01 原文、翻字、口語訳、原図付きで読みやすい。急いでいる人は口語訳だけでもよいし、他の部分も目を通すと、彼の時代にタイムスリップできる。生活事情がある程度分かる。ただもう少しエピソードがあると分かりやすいし、道の行程ももう少し記入されていると分かりやすいのだが、明治のごく初期にこのような山間部を通行したことで、歴史上に峠道のいくつかの状態を証明したことになり、私にとってなぞ貴重である。清水区宍原の椿峠、竜爪山北の駒曳き峠、樫の木峠、洗沢峠を通過している。そして珍しいのは権現峠という場所を通るのだ。その場所は、静岡新聞などで特定された。
それにしても彼はこのような山間地を通りつつ地元の純朴な人たちと関わっていくのだが、決して彼らを見下さず、彼らの人情に敬意をもちつつ付き合っていけることがすばらしい。アイヌ人にも敬意をもって接することができる人で大きい心の持ち主といえよう。
・「東海道山すじ日記」通行ルート
彼の通行ルートだけを取り出して一覧してみたい。
・江戸下谷三枚橋、青山通り→世田谷街道ニ里→宮益→一里→原口→世田谷(馬継場) →一里半→二子渡(六郷の川上舟渡) →18丁→溝の口(日本橋から四里)(世田谷廻りで太子堂経由で半里近くなる) →48坂→左右蠏(木ヘンに解、こく)柏(コクビャク)山、下にはツツジ、大山参詣頃人通り多し→二里→窪田→長津田→原道一里八丁→鶴間→細川渡り八丁→相模鶴間→二里→国部村(国分尼寺) →28~9丁→柏が谷村→馬入川の舟渡→→8丁→厚木宿→田んぼ道→上岡田、下岡田、酒井、小柳村→一里→愛甲(高麗寺山近く見えた){厚木から槽谷に行くにはここまで下らず、まっすぐに船子村を横切れば近かろう}、石田村→一里→糠谷→伊勢原村→一里→神渡→城の内村→18丁→前波マエナミ(善波?) →切通上り10丁→下る一里→十日市場→
増屋→上の道近道→沢間→畑道一里→千村チムラ→半里下る→川筋、48瀬→一里→
↘下の道山坂ない遠い
神山村(向かい松田村) →十文字川(仮橋、酒匂川上流)越して→町屋、吉田島、延沢村
→坂道下る二里→関本→片上里、雨坪村、弘西寺村、苅岩村、一色村→一里八丁→矢倉沢
(関所)→20丁上り→16~7丁下り→地蔵堂村→険路上り一里→足柄峠(地蔵堂) →一里八丁下る→
一里で竹の下→4~5丁上り→並木通り、厩や村→一里→御殿場
→埃沢エンザワ通り→印野(光徳寺) →独鈷沢→須山口の鳥居→半里→印野から二里半で
↘本道は左:茱□(草カンムリに叟、ミ)原グミハラ、芹沢原、菱刈原、二里半遠い
十里木(9軒)→一里下り→世古(勢子)辻→上の道→大宮道
→中道、大淵村→原まま沢に下り、十里木より
→下道→吉原道
三里、大淵村→杉谷村→甲州路二里半→大宮町
↘半里→万農原
・大宮(富士宮浅間大社)から野中村、治窪村を過ぎ、峠一つ越えて羽鮒村に下る。
治窪村は沼久保のことか? だとすると野中町から沼久保へ出て、安居山越えで羽鮒に至ったようだが、正確にはどこを越えたか不明。地元の人なら分かるのかもしれない。羽鮒山にはハイキングコースがあり、展望台もある。もしかするとそのハイキングコースの一部にも重なっているかもしれない。
・次に鮒川(芝川)の急流では藤縄を張った刳船で渡って、長貫村に出ている。釜口峡の藤縄の吊り橋に度肝を抜かれている。
・内房村、塩出組、境川村を通り宍原道、これは洪水のときに使う道で、または爪生島を通りしし原道となる。水廻り通りを行くとなっているので爪生島を通り途中で山に取り付き、今はゴルフ場となっている山を越して宍原に至ったのか。細谷川とは稲瀬川のことか。
・宍原から椿峠へ登る。峠からは大所へ下りている。今は大所入口に供養塔がある。桑又川に沿い下って小川村に出る。
・小川村から山を上って板峠(榎峠のことか?) 和田嶌に下る。しけの島村(茂野島)、とつら沢村(葛沢) 、土村、(布沢村)、黒川村、(河内村、大平村)、(竜爪山)、駒曳峠、
黒川から駒曳峠へはおぼつかない危険な道だったようで、今ではさらに廃道化しているようだ。よほどの山慣れた人しか歩けないだろう。
・駒曳峠、俵峰村、俵沢村、油島村、安倍川、中沢村、桂山村、只間(唯間)村、落合村、寺尾村、内匠村、樫の木峠、
峠から俵峰へは今も道がある。俵沢へは舗装された新道となる。その付近に昔の廃道があるのだろう。中沢から安倍川や中河内川、西河内川沿いに歩いているが、河原道を通ったのか、古道があったかは不明。おそらく内匠村から白石沢に沿いに上って樫の木峠に出ている。1990年ごろこのルートは通れたが今通れるか不明。川島から林道で峠に出られるようになったため。樫の木峠直下から日向村に出る古道は林道により消失している。ただ林道の途中から古道登山ルートが一部残存している。
・日向村、藁科川、洗沢峠、峯(富士城?、平栗の枝村)、(榊尾峠?、高山・無双連山方向のことか)、真瀬マセの大橋(馬路マジ橋)、
日向で藁科川を越え、後の開拓地:畑色(この時代は未開拓)付近を通り上杉尾を通過し洗沢峠に出たと思われる。
・藤川村、小永井村(小長井)、小長井神社(城)、岸村、田代村、坂本尾沢、青部村、沢間村、堀の内村(徳山)、庄島(正島)村、田の口(田野口)村、梅島、下長尾村、麦代村(向井、原山、久保尾?)、
この辺り川根沿いの秋葉街道に当たり、そのルートそのままに通行している。(*川根沿いの秋葉街道については、「古街道を行く」鈴木茂伸、静岡新聞社、参照)
麦代村はどこの村なのだろうか?
・麦代村(向井、原山、久保尾?)、権現峠(川根本町原山と浜松市田河内水舟、家山林道)、田河内村、越木平、花島村、
権現峠(川根本町原山と浜松市田河内水舟)家山林道
権現峠は先の静岡新聞記事の推定で間違いなかろう。今は家山林道が尾根通しに通過していて峠という印象すらなかろうが、向井や田河内村に下る古道は残存している。
・越木平→花島村→右:春埜山道五十丁、杉野村
↘左:秋葉道→いさ川村(砂川) →半里→和泉平→半里→中谷→半里→平生
*なお上記の右左は私なりに考えてみると変な気がする。なぜなら村の名の順序からして南西方向に進行している(または西ないしは南向きと考えてもよい)はずだが、そうすると左に春埜山道、右に秋葉道になると思うのだが、私が変?
→半里→若之平→十丁→犬居村→左:和田ヶ谷→中沢、領家村→32丁→峯小屋、中小屋(横川
↘右:坂本道 ↘18丁→光明山
村) →只来村→50丁→山東村→48瀬→25~6丁18瀬越→二股村→小峠一つ越え→東鹿島村、船渡し場→西鹿島村→岩水村、岩水寺→宮の口→味方が原→右:都田村、初山鮭院寺、この上の山蓮華峯、前:瀬戸村、瀬戸ヶ淵→右:金指宿→気賀→引佐峠→二里→三ケ火→本坂越二里半→嵩山すせ→一里→長柄→三里→御油
*以下は松浦武四郎が考えたより合理的なルートの案として掲載されているものである。
・(案1)大井川梅島→篠原、平木□□、黒原→犬居
・(案2)上長尾→越木平、気田村、窪田村→秋葉の後山→雲名村の渡し→石打村→熊村→嶺→神沢→鳳来寺、新城
それにしても彼はこのような山間地を通りつつ地元の純朴な人たちと関わっていくのだが、決して彼らを見下さず、彼らの人情に敬意をもちつつ付き合っていけることがすばらしい。アイヌ人にも敬意をもって接することができる人で大きい心の持ち主といえよう。
・「東海道山すじ日記」通行ルート
彼の通行ルートだけを取り出して一覧してみたい。
・江戸下谷三枚橋、青山通り→世田谷街道ニ里→宮益→一里→原口→世田谷(馬継場) →一里半→二子渡(六郷の川上舟渡) →18丁→溝の口(日本橋から四里)(世田谷廻りで太子堂経由で半里近くなる) →48坂→左右蠏(木ヘンに解、こく)柏(コクビャク)山、下にはツツジ、大山参詣頃人通り多し→二里→窪田→長津田→原道一里八丁→鶴間→細川渡り八丁→相模鶴間→二里→国部村(国分尼寺) →28~9丁→柏が谷村→馬入川の舟渡→→8丁→厚木宿→田んぼ道→上岡田、下岡田、酒井、小柳村→一里→愛甲(高麗寺山近く見えた){厚木から槽谷に行くにはここまで下らず、まっすぐに船子村を横切れば近かろう}、石田村→一里→糠谷→伊勢原村→一里→神渡→城の内村→18丁→前波マエナミ(善波?) →切通上り10丁→下る一里→十日市場→
増屋→上の道近道→沢間→畑道一里→千村チムラ→半里下る→川筋、48瀬→一里→
↘下の道山坂ない遠い
神山村(向かい松田村) →十文字川(仮橋、酒匂川上流)越して→町屋、吉田島、延沢村
→坂道下る二里→関本→片上里、雨坪村、弘西寺村、苅岩村、一色村→一里八丁→矢倉沢
(関所)→20丁上り→16~7丁下り→地蔵堂村→険路上り一里→足柄峠(地蔵堂) →一里八丁下る→
一里で竹の下→4~5丁上り→並木通り、厩や村→一里→御殿場
→埃沢エンザワ通り→印野(光徳寺) →独鈷沢→須山口の鳥居→半里→印野から二里半で
↘本道は左:茱□(草カンムリに叟、ミ)原グミハラ、芹沢原、菱刈原、二里半遠い
十里木(9軒)→一里下り→世古(勢子)辻→上の道→大宮道
→中道、大淵村→原まま沢に下り、十里木より
→下道→吉原道
三里、大淵村→杉谷村→甲州路二里半→大宮町
↘半里→万農原
・大宮(富士宮浅間大社)から野中村、治窪村を過ぎ、峠一つ越えて羽鮒村に下る。
治窪村は沼久保のことか? だとすると野中町から沼久保へ出て、安居山越えで羽鮒に至ったようだが、正確にはどこを越えたか不明。地元の人なら分かるのかもしれない。羽鮒山にはハイキングコースがあり、展望台もある。もしかするとそのハイキングコースの一部にも重なっているかもしれない。
・次に鮒川(芝川)の急流では藤縄を張った刳船で渡って、長貫村に出ている。釜口峡の藤縄の吊り橋に度肝を抜かれている。
・内房村、塩出組、境川村を通り宍原道、これは洪水のときに使う道で、または爪生島を通りしし原道となる。水廻り通りを行くとなっているので爪生島を通り途中で山に取り付き、今はゴルフ場となっている山を越して宍原に至ったのか。細谷川とは稲瀬川のことか。
・宍原から椿峠へ登る。峠からは大所へ下りている。今は大所入口に供養塔がある。桑又川に沿い下って小川村に出る。
・小川村から山を上って板峠(榎峠のことか?) 和田嶌に下る。しけの島村(茂野島)、とつら沢村(葛沢) 、土村、(布沢村)、黒川村、(河内村、大平村)、(竜爪山)、駒曳峠、
黒川から駒曳峠へはおぼつかない危険な道だったようで、今ではさらに廃道化しているようだ。よほどの山慣れた人しか歩けないだろう。
・駒曳峠、俵峰村、俵沢村、油島村、安倍川、中沢村、桂山村、只間(唯間)村、落合村、寺尾村、内匠村、樫の木峠、
峠から俵峰へは今も道がある。俵沢へは舗装された新道となる。その付近に昔の廃道があるのだろう。中沢から安倍川や中河内川、西河内川沿いに歩いているが、河原道を通ったのか、古道があったかは不明。おそらく内匠村から白石沢に沿いに上って樫の木峠に出ている。1990年ごろこのルートは通れたが今通れるか不明。川島から林道で峠に出られるようになったため。樫の木峠直下から日向村に出る古道は林道により消失している。ただ林道の途中から古道登山ルートが一部残存している。
・日向村、藁科川、洗沢峠、峯(富士城?、平栗の枝村)、(榊尾峠?、高山・無双連山方向のことか)、真瀬マセの大橋(馬路マジ橋)、
日向で藁科川を越え、後の開拓地:畑色(この時代は未開拓)付近を通り上杉尾を通過し洗沢峠に出たと思われる。
・藤川村、小永井村(小長井)、小長井神社(城)、岸村、田代村、坂本尾沢、青部村、沢間村、堀の内村(徳山)、庄島(正島)村、田の口(田野口)村、梅島、下長尾村、麦代村(向井、原山、久保尾?)、
この辺り川根沿いの秋葉街道に当たり、そのルートそのままに通行している。(*川根沿いの秋葉街道については、「古街道を行く」鈴木茂伸、静岡新聞社、参照)
麦代村はどこの村なのだろうか?
・麦代村(向井、原山、久保尾?)、権現峠(川根本町原山と浜松市田河内水舟、家山林道)、田河内村、越木平、花島村、
権現峠(川根本町原山と浜松市田河内水舟)家山林道
権現峠は先の静岡新聞記事の推定で間違いなかろう。今は家山林道が尾根通しに通過していて峠という印象すらなかろうが、向井や田河内村に下る古道は残存している。
・越木平→花島村→右:春埜山道五十丁、杉野村
↘左:秋葉道→いさ川村(砂川) →半里→和泉平→半里→中谷→半里→平生
*なお上記の右左は私なりに考えてみると変な気がする。なぜなら村の名の順序からして南西方向に進行している(または西ないしは南向きと考えてもよい)はずだが、そうすると左に春埜山道、右に秋葉道になると思うのだが、私が変?
→半里→若之平→十丁→犬居村→左:和田ヶ谷→中沢、領家村→32丁→峯小屋、中小屋(横川
↘右:坂本道 ↘18丁→光明山
村) →只来村→50丁→山東村→48瀬→25~6丁18瀬越→二股村→小峠一つ越え→東鹿島村、船渡し場→西鹿島村→岩水村、岩水寺→宮の口→味方が原→右:都田村、初山鮭院寺、この上の山蓮華峯、前:瀬戸村、瀬戸ヶ淵→右:金指宿→気賀→引佐峠→二里→三ケ火→本坂越二里半→嵩山すせ→一里→長柄→三里→御油
*以下は松浦武四郎が考えたより合理的なルートの案として掲載されているものである。
・(案1)大井川梅島→篠原、平木□□、黒原→犬居
・(案2)上長尾→越木平、気田村、窪田村→秋葉の後山→雲名村の渡し→石打村→熊村→嶺→神沢→鳳来寺、新城
2011年09月26日
古街道研究における道のでき方の法則
古街道研究の中のフィールド・ワーク主体の古街道実地調査にかかわって知った言葉、専門用語といえば「ダウン・ムーブメント」が唯一のものであった。古街道の制度史、政治、行政、歴史に関しては、宿駅制、伝馬制、助郷など多岐にわたる概念、専門用語が数多いが、古街道を実際に再発見しようという研究では、これといったものがない。
古街道における「ダウン・ムーブメント」とは、道は古くは標高の高い所を通っているが、次第に低い所を通るようになるという意味である、とされる。これは古街道以外に登山道の変遷でより実感される。古い登山道が尾根伝いに忠実についていたのが、時代が下るにつれ、より低い所を通り、らくな通貨が可能になるというものだ。
それにしても、この「ダウン・ムーブメント」という概念は、古街道研究の中で、どのように醸成され、発展してきたのかを知らない。この歴史的流れを知りたいのだが、どのように調査していいものか、から考えるしかなさそうだ。誰か教えていただけないものだろうか。
ちなみにグーグル検索したが、まったくだめだった。
この頃の高速道路建設では、あえて人里離れた山の尾根や中腹に通すので、この概念が壊れつつある。例としては「第二東名」や「能登自動車道」である。
道のでき方には法則があることが知られている。その一つというか、それ一つしか学んでこなかった。しかもいつ誰がなぜそう言い出したかはまったく知らない。
・1.ダウン・ムーヴメントDown Movement、下降運動
道は上から下に作り変えられていくという法則。街道で考えるより登山道で考えると分かりやすい。山の尾根伝いに道を作れば山腹のがけ崩れや沢谷を渡らずに済み安全である。しかし山の尾根は最高所であるため、そこまで上ることとあとで麓へ下ることが大変であり、長距離の尾根の場合幾度もピーク(頂)とコル(鞍部、乗越し、峠)を上り下りせねばならず苦しい。時代が下ると登山道はコル同士を水平移動できるよう改善され、途中のピークに上る手間を省くようになる。もっと道路作りの土木技術が進むと、麓から尾根の向こうの別の麓へ中腹だけを通っていけるようになる。さらに発展すると麓から麓へトンネルを掘って直通になる。これがDown Movementである。
ここから先、私の勝手な考えを述べる。Down Movement以外にも道の発展の仕方があると考えるからだ。
・2.迂回路ムーヴメント、Ukairo(Roundabout、detour) Movement、迂回運動
切通しの道が深くえぐれてしまい安全に通行しにくくなると、すぐ横に迂回路、バイパス化のように新たな切通し道が開かれていく。山の峠道や登山道にある。
・3.アップ・ムーヴメントUp Movement、上昇運動
時代が下り現代の土木技術においてと道路を作る用地買収や環境配慮により、あえて麓ではなく、山の中腹や尾根伝い沿いに自動車道を作ってしまう。能登自動車道や第二東名高速道路である。
古街道における「ダウン・ムーブメント」とは、道は古くは標高の高い所を通っているが、次第に低い所を通るようになるという意味である、とされる。これは古街道以外に登山道の変遷でより実感される。古い登山道が尾根伝いに忠実についていたのが、時代が下るにつれ、より低い所を通り、らくな通貨が可能になるというものだ。
それにしても、この「ダウン・ムーブメント」という概念は、古街道研究の中で、どのように醸成され、発展してきたのかを知らない。この歴史的流れを知りたいのだが、どのように調査していいものか、から考えるしかなさそうだ。誰か教えていただけないものだろうか。
ちなみにグーグル検索したが、まったくだめだった。
この頃の高速道路建設では、あえて人里離れた山の尾根や中腹に通すので、この概念が壊れつつある。例としては「第二東名」や「能登自動車道」である。
道のでき方には法則があることが知られている。その一つというか、それ一つしか学んでこなかった。しかもいつ誰がなぜそう言い出したかはまったく知らない。
・1.ダウン・ムーヴメントDown Movement、下降運動
道は上から下に作り変えられていくという法則。街道で考えるより登山道で考えると分かりやすい。山の尾根伝いに道を作れば山腹のがけ崩れや沢谷を渡らずに済み安全である。しかし山の尾根は最高所であるため、そこまで上ることとあとで麓へ下ることが大変であり、長距離の尾根の場合幾度もピーク(頂)とコル(鞍部、乗越し、峠)を上り下りせねばならず苦しい。時代が下ると登山道はコル同士を水平移動できるよう改善され、途中のピークに上る手間を省くようになる。もっと道路作りの土木技術が進むと、麓から尾根の向こうの別の麓へ中腹だけを通っていけるようになる。さらに発展すると麓から麓へトンネルを掘って直通になる。これがDown Movementである。
ここから先、私の勝手な考えを述べる。Down Movement以外にも道の発展の仕方があると考えるからだ。
・2.迂回路ムーヴメント、Ukairo(Roundabout、detour) Movement、迂回運動
切通しの道が深くえぐれてしまい安全に通行しにくくなると、すぐ横に迂回路、バイパス化のように新たな切通し道が開かれていく。山の峠道や登山道にある。
・3.アップ・ムーヴメントUp Movement、上昇運動
時代が下り現代の土木技術においてと道路を作る用地買収や環境配慮により、あえて麓ではなく、山の中腹や尾根伝い沿いに自動車道を作ってしまう。能登自動車道や第二東名高速道路である。
2011年04月29日
大谷街道
大谷街道
大谷街道の出発点をどこと捉えるか決定打はないが、池田街道分岐点と捉えよう。今の池田街道から分岐するのが、今の大谷街道(県道大谷古庄線)の分岐出発点でもある。ただ古い池田街道は今の分岐点より30m南の路地のようであり、今の池田街道の1本南に平行して通っている。
池田街道の詳細は『古街道を行く』鈴木茂伸(静岡新聞社)の「平沢観音道、曲金コース」を参照されたい。
・寺田博士記念碑(池田1086-4)
大谷街道の出発点からはずれるが、この付近なので紹介しておく。場所は東豊田幼稚園東で川を渡った向こうである。寺田氏とは近代における近辺の有力者で郷土発展に尽力した方のようだ。この記念碑の東200mの交番前(聖一色46-1)にも寺田博士記念碑がある。
・庚申塔(池田733、池田バス停)
さて県道の大谷街道南下する。150mで消防分団を通過する。ここに「庚申塔 大正九年…」がある。ここから東200mに池田神社がある。
・池田神社
由緒あり、池田の地名になっている。隣に豊川稲荷がある。
・本覚寺(池田1379)
さて県道の南下を続ける。300mで交差点があり、本覚寺参道入口標識がある。寺へは東300mである。寺には石塔類豊富である。寺には幕末の侠客:安東文吉や徳川家康に嫌われた孕石主水、高天神城を守った岡部丹波守の墓がある。
・法伝寺(小鹿1610-3)
近年移転してきた寺である。
・龍雲寺(小鹿866)
500m南下すると、龍雲寺が見える。明治になって話し合いをして檀家が離れたため墓地だけの寺になっている。境内は月ぎめ駐車場である。曹洞宗。地蔵堂:本尊:阿弥陀如来、子安地蔵菩薩、他2基。古い石塔類が多い。「庚申供養塔」2基、石塔10基、「豊田小学校発祥の地記念碑」、「牛供養」、新・地蔵。
・小鹿氏居館跡(小鹿866)
殿屋敷といわれる龍雲寺近辺が小鹿氏の居館跡。
・伊勢神明神社(小鹿886)
150m南下し二つ池手前を東へ150m。巨木があり、古くから神社のある地と考えられる。この小鹿の地が古くから開けていたことはこの後の史跡からも分かる。創立1590年。楠(静岡県指定天然記念物)樹齢千数百年。
・二つ池(小鹿)
小鹿公園もあり、憩いの地。溜池のようだが今は公園の一部となっている。
・若一王子神社(小鹿370)
池から50mないし150m進み、堀の内バス停付近の路地を西へ向かい再度折れ曲がると付近に小さな神社がある。1625年にはすでにあったようだ。手水鉢「慶応二年」。石灯籠1基。石鳥居「大正六年」。
・山神社(小鹿)
・七面堂(小鹿)
本覚寺の境外仏堂。北原山にある。
・山の神古墳
・駿河堀の内山古墳群
・長沢地蔵(大谷448)
150m進んだ長沢川手前にある。11年4月付近を改修中らしく地蔵もない。
・日本平公園遊歩道と駐車場(小鹿2237)
街道をそれ、長沢川を東に1km詰めていくと遊歩道と駐車場の標識がある。11年3月には整備工事中であった。
・西教寺(大谷5105)
人気のない寂しい道を500m奥に進むと梅林があり、白梅がきれいに咲き梅の花の香りに包まれた。ここを過ぎると寺がある。かつて市内人宿町か新通あたりにあった寺のようだ。古い石塔類も移転されている。ちなみに寺を過ぎると下り坂となり、静岡大学グラウンド前に出て急に明るくなる。
・長沢川(小鹿と大谷の境)
西教寺手前の道を奥深く進むと長沢川上流に行ける。行くなら冬場に限る。600m奥の日本平パークウェイ手前で登山道も崩壊していて進めないが、ここまででもちょいとした冒険探検気分が味わえる。
・西教寺墓地横の尾根道、かつてのハイキングコース?かもしれない
農園の畑となっている。この尾根に沿って奥へ進むのがかつての大谷からの日本平へのハイキングコースかもしれない。だとすれば遊木の森(かつてのボーイスカウトキャンプ地)で日本平パークウェイを越える歩道橋につながり、日本平と大谷をつなぐコースだったかもしれない。なお下記のコースかもしれない。
・池ノ谷沢川(大谷)、かつてのハイキングコース?かもしれない
静大グラウンド前の自然観察実習室横の沢に沿って奥へ1km進む。道はでこぼこだが一応コンクリ舗装されている。畑に出て終点だが、かつてはこの沢奥に進め、遊木の森(かつてのボーイスカウトキャンプ地)で日本平パークウェイを越える歩道橋につながり、日本平と大谷をつなぐコースだったかもしれない。
・静岡大学、旧・大段(大谷)
静岡大学が大岩から移転する前は、大段といわれ、一面の畑であった。
・片山公民館(旧・子安堂)
静大入口交差点を静大方向の東名ガードに向かい進み、一つ目の右折路を曲がる。石塔類。「葷酒不入山門」、庚申塔「昭和五十五年」、他1基、地蔵、石塔、六地蔵「元禄五」、「記念碑 永徳寺子安堂と公民館の沿革」によれば、永徳寺開山1675年、廃寺1871年、
・片山廃寺跡(大谷)
話を長沢川の大谷街道に戻す。300m進むと東名高速道路高架橋下に出る。新・地蔵も祀られている。この辺りが片山廃寺跡である。本格的寺院で国分寺かそれに匹敵する寺院と考えられるが、決定的証拠はない。この地が古代から開けていたことは明らかである。礎石の跡などが例示されていて、建物が想像できる。
・白山神社(大谷596)
隣に神社がある。記念碑がある。
・諏訪神社(大谷4475)、古墳
400m進むと左(東)に広い通りがある。これを50m進み右の坂を上ると神社がある。古墳である。
・池ヶ谷池(大谷1424)
諏訪神社の道向かいにあり、かつての溜池である。
・宮川の子授け地蔵、庚申塔(大谷)
静大への広い取り付け道路交差点の次の狭い交差点にある。「庚申塔 大正九年 宮川區…」。
・大正寺(大谷3660)
600m進み大谷小学校を通過し、大正寺沢川を渡ると東に大正寺参道入口がある。古い石塔類もある。諏訪大明神のお堂もある。これは麻端沼の婆さんを祀ったものである。当寺は麻機の岩崎家や分家が関係する旦那寺であるため、ここに沼の婆さんを祀っているのだ。
「庚申塔 萬延元年」「庚申供養塔」「奉順礼西国四国…」、ぽっくり地蔵尊・他4基(大正寺末寺 大谷海雲寺より移転)、姿見の井戸(朝比奈弥太郎泰能が自害する前に身支度を整えた井戸である。彼は今川氏真部下で武田氏に駿府を攻められたとき氏真を掛川に逃し、婦女子を高松海岸の船に乗せるよう手はずを整えたのち、この寺で自害した。しかし婦女子は乗船できず入江の渕:上臈渕に身投げしたという。) 隣に雷が岩を引っかいたという筋模様の岩がある。
・旧大谷街道、八坂神社、大谷不動(大谷2781)
大正寺参道入口から大谷街道を30m南下すると左(東)に細い道がある。これが旧大谷街道の残存部と考えられている。薄暗い道を進むと八坂神社があり、神社の上には大谷不動が祀られるお堂もあり、アスレチック広場にもなっている。
・八坂神社(大谷)
創建不詳、棟札1672,1854年、元牛頭天王社、樹木100~300年、石鳥居:明治二十九年建造昭和六十二年再建、石灯籠:元和三1617年、慶安元1648年、手水舎:文化三1806年。
・海岸山大谷不動明王、加羅倶利堂(大谷)
参道途中に庚申塔等の石塔14基、地蔵7基が安置されている。大谷不動の由来は漁師が漁をしていて網にかかったのが石仏で、それを祀ったものだという。大谷不動の西側には地蔵堂(地蔵、大日如来)がある。歯痛封じの地蔵である。倶利伽羅堂という。石灯籠:元和二年、六地蔵、80cm×1.5mの台石。
・地蔵堂(大谷2651)
薄暗い旧大谷街道を下りきると、旧久能街道と交差する。そこに石仏が祀られている。大谷街道は久能街道に合流して終点である。なお個人的にはもっと古い久能街道はもう少し北寄りの路地だったのではないかと考えているので、ここの石仏も移転されてここにあるのだろうと勝手に考えている。
11年4月細かった道は広く付け直され周辺も区画整理されて新しい家ばかりで、旧態がほぼない。地蔵もない。
大谷街道の出発点をどこと捉えるか決定打はないが、池田街道分岐点と捉えよう。今の池田街道から分岐するのが、今の大谷街道(県道大谷古庄線)の分岐出発点でもある。ただ古い池田街道は今の分岐点より30m南の路地のようであり、今の池田街道の1本南に平行して通っている。
池田街道の詳細は『古街道を行く』鈴木茂伸(静岡新聞社)の「平沢観音道、曲金コース」を参照されたい。
・寺田博士記念碑(池田1086-4)
大谷街道の出発点からはずれるが、この付近なので紹介しておく。場所は東豊田幼稚園東で川を渡った向こうである。寺田氏とは近代における近辺の有力者で郷土発展に尽力した方のようだ。この記念碑の東200mの交番前(聖一色46-1)にも寺田博士記念碑がある。
・庚申塔(池田733、池田バス停)
さて県道の大谷街道南下する。150mで消防分団を通過する。ここに「庚申塔 大正九年…」がある。ここから東200mに池田神社がある。
・池田神社
由緒あり、池田の地名になっている。隣に豊川稲荷がある。
・本覚寺(池田1379)
さて県道の南下を続ける。300mで交差点があり、本覚寺参道入口標識がある。寺へは東300mである。寺には石塔類豊富である。寺には幕末の侠客:安東文吉や徳川家康に嫌われた孕石主水、高天神城を守った岡部丹波守の墓がある。
・法伝寺(小鹿1610-3)
近年移転してきた寺である。
・龍雲寺(小鹿866)
500m南下すると、龍雲寺が見える。明治になって話し合いをして檀家が離れたため墓地だけの寺になっている。境内は月ぎめ駐車場である。曹洞宗。地蔵堂:本尊:阿弥陀如来、子安地蔵菩薩、他2基。古い石塔類が多い。「庚申供養塔」2基、石塔10基、「豊田小学校発祥の地記念碑」、「牛供養」、新・地蔵。
・小鹿氏居館跡(小鹿866)
殿屋敷といわれる龍雲寺近辺が小鹿氏の居館跡。
・伊勢神明神社(小鹿886)
150m南下し二つ池手前を東へ150m。巨木があり、古くから神社のある地と考えられる。この小鹿の地が古くから開けていたことはこの後の史跡からも分かる。創立1590年。楠(静岡県指定天然記念物)樹齢千数百年。
・二つ池(小鹿)
小鹿公園もあり、憩いの地。溜池のようだが今は公園の一部となっている。
・若一王子神社(小鹿370)
池から50mないし150m進み、堀の内バス停付近の路地を西へ向かい再度折れ曲がると付近に小さな神社がある。1625年にはすでにあったようだ。手水鉢「慶応二年」。石灯籠1基。石鳥居「大正六年」。
・山神社(小鹿)
・七面堂(小鹿)
本覚寺の境外仏堂。北原山にある。
・山の神古墳
・駿河堀の内山古墳群
・長沢地蔵(大谷448)
150m進んだ長沢川手前にある。11年4月付近を改修中らしく地蔵もない。
・日本平公園遊歩道と駐車場(小鹿2237)
街道をそれ、長沢川を東に1km詰めていくと遊歩道と駐車場の標識がある。11年3月には整備工事中であった。
・西教寺(大谷5105)
人気のない寂しい道を500m奥に進むと梅林があり、白梅がきれいに咲き梅の花の香りに包まれた。ここを過ぎると寺がある。かつて市内人宿町か新通あたりにあった寺のようだ。古い石塔類も移転されている。ちなみに寺を過ぎると下り坂となり、静岡大学グラウンド前に出て急に明るくなる。
・長沢川(小鹿と大谷の境)
西教寺手前の道を奥深く進むと長沢川上流に行ける。行くなら冬場に限る。600m奥の日本平パークウェイ手前で登山道も崩壊していて進めないが、ここまででもちょいとした冒険探検気分が味わえる。
・西教寺墓地横の尾根道、かつてのハイキングコース?かもしれない
農園の畑となっている。この尾根に沿って奥へ進むのがかつての大谷からの日本平へのハイキングコースかもしれない。だとすれば遊木の森(かつてのボーイスカウトキャンプ地)で日本平パークウェイを越える歩道橋につながり、日本平と大谷をつなぐコースだったかもしれない。なお下記のコースかもしれない。
・池ノ谷沢川(大谷)、かつてのハイキングコース?かもしれない
静大グラウンド前の自然観察実習室横の沢に沿って奥へ1km進む。道はでこぼこだが一応コンクリ舗装されている。畑に出て終点だが、かつてはこの沢奥に進め、遊木の森(かつてのボーイスカウトキャンプ地)で日本平パークウェイを越える歩道橋につながり、日本平と大谷をつなぐコースだったかもしれない。
・静岡大学、旧・大段(大谷)
静岡大学が大岩から移転する前は、大段といわれ、一面の畑であった。
・片山公民館(旧・子安堂)
静大入口交差点を静大方向の東名ガードに向かい進み、一つ目の右折路を曲がる。石塔類。「葷酒不入山門」、庚申塔「昭和五十五年」、他1基、地蔵、石塔、六地蔵「元禄五」、「記念碑 永徳寺子安堂と公民館の沿革」によれば、永徳寺開山1675年、廃寺1871年、
・片山廃寺跡(大谷)
話を長沢川の大谷街道に戻す。300m進むと東名高速道路高架橋下に出る。新・地蔵も祀られている。この辺りが片山廃寺跡である。本格的寺院で国分寺かそれに匹敵する寺院と考えられるが、決定的証拠はない。この地が古代から開けていたことは明らかである。礎石の跡などが例示されていて、建物が想像できる。
・白山神社(大谷596)
隣に神社がある。記念碑がある。
・諏訪神社(大谷4475)、古墳
400m進むと左(東)に広い通りがある。これを50m進み右の坂を上ると神社がある。古墳である。
・池ヶ谷池(大谷1424)
諏訪神社の道向かいにあり、かつての溜池である。
・宮川の子授け地蔵、庚申塔(大谷)
静大への広い取り付け道路交差点の次の狭い交差点にある。「庚申塔 大正九年 宮川區…」。
・大正寺(大谷3660)
600m進み大谷小学校を通過し、大正寺沢川を渡ると東に大正寺参道入口がある。古い石塔類もある。諏訪大明神のお堂もある。これは麻端沼の婆さんを祀ったものである。当寺は麻機の岩崎家や分家が関係する旦那寺であるため、ここに沼の婆さんを祀っているのだ。
「庚申塔 萬延元年」「庚申供養塔」「奉順礼西国四国…」、ぽっくり地蔵尊・他4基(大正寺末寺 大谷海雲寺より移転)、姿見の井戸(朝比奈弥太郎泰能が自害する前に身支度を整えた井戸である。彼は今川氏真部下で武田氏に駿府を攻められたとき氏真を掛川に逃し、婦女子を高松海岸の船に乗せるよう手はずを整えたのち、この寺で自害した。しかし婦女子は乗船できず入江の渕:上臈渕に身投げしたという。) 隣に雷が岩を引っかいたという筋模様の岩がある。
・旧大谷街道、八坂神社、大谷不動(大谷2781)
大正寺参道入口から大谷街道を30m南下すると左(東)に細い道がある。これが旧大谷街道の残存部と考えられている。薄暗い道を進むと八坂神社があり、神社の上には大谷不動が祀られるお堂もあり、アスレチック広場にもなっている。
・八坂神社(大谷)
創建不詳、棟札1672,1854年、元牛頭天王社、樹木100~300年、石鳥居:明治二十九年建造昭和六十二年再建、石灯籠:元和三1617年、慶安元1648年、手水舎:文化三1806年。
・海岸山大谷不動明王、加羅倶利堂(大谷)
参道途中に庚申塔等の石塔14基、地蔵7基が安置されている。大谷不動の由来は漁師が漁をしていて網にかかったのが石仏で、それを祀ったものだという。大谷不動の西側には地蔵堂(地蔵、大日如来)がある。歯痛封じの地蔵である。倶利伽羅堂という。石灯籠:元和二年、六地蔵、80cm×1.5mの台石。
・地蔵堂(大谷2651)
薄暗い旧大谷街道を下りきると、旧久能街道と交差する。そこに石仏が祀られている。大谷街道は久能街道に合流して終点である。なお個人的にはもっと古い久能街道はもう少し北寄りの路地だったのではないかと考えているので、ここの石仏も移転されてここにあるのだろうと勝手に考えている。
11年4月細かった道は広く付け直され周辺も区画整理されて新しい家ばかりで、旧態がほぼない。地蔵もない。
2011年04月04日
推定平安鎌倉古道、三嶋大社~箱根・芦ノ湖高原別荘地
・推定平安鎌倉古道、三嶋大社~箱根・芦ノ湖高原別荘地、標高850m (三島市)
江戸時代の東海道による箱根越え道は今の国道1号線に付かず離れずに山中新田や山中城辺りの尾根を辿って行く道である。それ以前の道は足柄峠越えということになっている。しかし鎌倉時代の「十六夜日記」に箱根越えの記述があり、山中新田の尾根のもう1ぽん北の尾根(小沢、元山中、五輪)を通ったものと推定されている。
まず出発点であるが、三嶋大社の東側の暦を作った家(河合氏宅)前から東に進み、大場川に架かる下神川橋を渡り左カーブを道なりに進むと正面に「願成寺」がある。源頼朝所縁の寺でここからかつての箱根越えの坂道がはじまるのが分かる。道なりに奥へ進む。基本的に尾根の中心部に沿って進むものと考えればよい。鉄道高架橋(高さ1.9m制限、東に小さな天神社があるようだ)を渡り、すぐ右に曲がり道なりに進むと新幹線の高架橋を渡る。旭ヶ丘という新興住宅団地の土真ん中を突っ切って行く。この辺りから古色が失せ現代的な山の手風景となるが、この新しい尾根道は古い古道を拡幅したものと思われる。山田小中学校や老人センターを過ぎゴリラマークのゴルフ練習場向かいに古びた「元山中、青少年センター、箱根」の標識がある。その標識奥の暗い道に入る。清掃工場の裏口になるようだ。それを過ぎるととたんに道が劣化しでこぼこ道となる。暗く淋しい所を過ぎ尾根上を上って右方向に進むと畑をいくつか過ぎ、「小沢の里、トイレ←→鎌倉古道」の標識がやっとある。ただし小沢の里に下りるのは正規コースではなくトイレ休憩用であるので、道はそのまま尾根上を上って行く。広々と区画整理された畑に出る。そのまま直進すると元山中集落に越えていくことになるので、その手前を左折し尾根上を上って行く。その曲がる所の奥に地蔵石仏がある。左折し500m進むと左に「山神社」があり、「復元された平安鎌倉古道」の云われの看板がある。山神社少し先からゴルフ場用地内に標識があって古道が進んでいて、さらに先で舗装路に戻るが、柵が張られていて進むことはできない。しかし山神社奥にもピークヲ反対側から巻く別の山道があり、この山道もどうも鎌倉古道の成れの果てと思われる。山神社前の舗装路をもう300m進むと左に石階段があり、上に諏訪神社がある。これまた諏訪神社奥の堀切のような空堀は鎌倉古道の成れの果てと思われる。しかしいったんゴルフ場(グランフィールズカントリークラブ)横の舗装路に戻り、200m奥に進むと左手上に進む山道があり、標識「元山中、箱根」がある。笹や草が繁っているが、かつて道幅は1間(1.8m)あったと思われる。ここから先ほどのピークの反対側に行く別山道に分かれる分岐点もあった。300m進むと幅1mのコンクリ舗装と出会う。これは下の先ほどの舗装路から分岐し30m伸びる道でちょうどここで幅1mのコンクリ舗装が切れる。ここにも標識「元山中、箱根」がある。古道を100m進むと草の繁り方がひどくなり笹と草と蜘蛛の巣をかきわけることになる。200mもかきわけると突然幅1.8mだけ草が切れる。これまた先ほどのゴルフ場横の舗装路から草刈りして進む作業道のようだ。どうしても進みたくなければ草刈した道を右に行けばすぐに出発点につながる舗装路に出られる。草刈した道を横断しまた笹と草の中に埋没していく。500mがまんし踏み跡を辿りかき分けていくと突然道幅1.8mの扇平ハイキングコースに出る。標識に従い箱根方向を目指す。地面は赤土の溶岩で濡れていると滑りやすい。なぜ江戸期の東海道箱根路が石畳かというと、この赤土の滑りやすさとぬるぬるさのためである。300mで舗装路に出る。ここにも看板「復元された平安鎌倉古道」がある。舗装路を横断し再度古道に入る。入り口は木の柵があり、入れないかと思ったら二重になっていて人なら入れるようになっていた。おそらく二輪車進入を防ぐためだろう。道は格段に歩きやすく幅が広い。ただし赤土なのですべらないように。途中でピークを左に巻いて道が行く所があるのだが、右に巻く廃道もあり、ピークの先で合流する。古道も時代で付け替えられ左右を見渡すと幾本もの道筋がつけられている。1kmも進むと林道を横断するところが2箇所出てくる。また林道のすぐ横を通る所もある。林道を2箇所横断すると道は尾根上から沢筋になり、道に水たまりが見られる所も出てくる。芦ノ湖高原別荘地に近づいた証拠である。500m進むと前方に柵とコンクリ壁が見える。鉄塔である。その向こうに別荘がある。道をさらに100m進むと別荘地のCエリア前に出る。「鎌倉古道入口」標識がある。別荘地内をさらに上る古道はすでにない。おそらく家々の境やその先の上って行く道が古道を元にした道と推定されるが、もはや古色はない。かつて古道は別荘地になった所を上り有料道路を横断し箱根に下っていったはずだ。部分的には切通しが残存しているかもしれない。
車での帰路、小沢から清掃工場裏への道を2回間違え、3回目でやっと山田中方面へ出られた。林道の分岐点を間違えやすい。来るときは上りの右方向へ行けばよかったが、下りはそうはいかない。
江戸時代の東海道による箱根越え道は今の国道1号線に付かず離れずに山中新田や山中城辺りの尾根を辿って行く道である。それ以前の道は足柄峠越えということになっている。しかし鎌倉時代の「十六夜日記」に箱根越えの記述があり、山中新田の尾根のもう1ぽん北の尾根(小沢、元山中、五輪)を通ったものと推定されている。
まず出発点であるが、三嶋大社の東側の暦を作った家(河合氏宅)前から東に進み、大場川に架かる下神川橋を渡り左カーブを道なりに進むと正面に「願成寺」がある。源頼朝所縁の寺でここからかつての箱根越えの坂道がはじまるのが分かる。道なりに奥へ進む。基本的に尾根の中心部に沿って進むものと考えればよい。鉄道高架橋(高さ1.9m制限、東に小さな天神社があるようだ)を渡り、すぐ右に曲がり道なりに進むと新幹線の高架橋を渡る。旭ヶ丘という新興住宅団地の土真ん中を突っ切って行く。この辺りから古色が失せ現代的な山の手風景となるが、この新しい尾根道は古い古道を拡幅したものと思われる。山田小中学校や老人センターを過ぎゴリラマークのゴルフ練習場向かいに古びた「元山中、青少年センター、箱根」の標識がある。その標識奥の暗い道に入る。清掃工場の裏口になるようだ。それを過ぎるととたんに道が劣化しでこぼこ道となる。暗く淋しい所を過ぎ尾根上を上って右方向に進むと畑をいくつか過ぎ、「小沢の里、トイレ←→鎌倉古道」の標識がやっとある。ただし小沢の里に下りるのは正規コースではなくトイレ休憩用であるので、道はそのまま尾根上を上って行く。広々と区画整理された畑に出る。そのまま直進すると元山中集落に越えていくことになるので、その手前を左折し尾根上を上って行く。その曲がる所の奥に地蔵石仏がある。左折し500m進むと左に「山神社」があり、「復元された平安鎌倉古道」の云われの看板がある。山神社少し先からゴルフ場用地内に標識があって古道が進んでいて、さらに先で舗装路に戻るが、柵が張られていて進むことはできない。しかし山神社奥にもピークヲ反対側から巻く別の山道があり、この山道もどうも鎌倉古道の成れの果てと思われる。山神社前の舗装路をもう300m進むと左に石階段があり、上に諏訪神社がある。これまた諏訪神社奥の堀切のような空堀は鎌倉古道の成れの果てと思われる。しかしいったんゴルフ場(グランフィールズカントリークラブ)横の舗装路に戻り、200m奥に進むと左手上に進む山道があり、標識「元山中、箱根」がある。笹や草が繁っているが、かつて道幅は1間(1.8m)あったと思われる。ここから先ほどのピークの反対側に行く別山道に分かれる分岐点もあった。300m進むと幅1mのコンクリ舗装と出会う。これは下の先ほどの舗装路から分岐し30m伸びる道でちょうどここで幅1mのコンクリ舗装が切れる。ここにも標識「元山中、箱根」がある。古道を100m進むと草の繁り方がひどくなり笹と草と蜘蛛の巣をかきわけることになる。200mもかきわけると突然幅1.8mだけ草が切れる。これまた先ほどのゴルフ場横の舗装路から草刈りして進む作業道のようだ。どうしても進みたくなければ草刈した道を右に行けばすぐに出発点につながる舗装路に出られる。草刈した道を横断しまた笹と草の中に埋没していく。500mがまんし踏み跡を辿りかき分けていくと突然道幅1.8mの扇平ハイキングコースに出る。標識に従い箱根方向を目指す。地面は赤土の溶岩で濡れていると滑りやすい。なぜ江戸期の東海道箱根路が石畳かというと、この赤土の滑りやすさとぬるぬるさのためである。300mで舗装路に出る。ここにも看板「復元された平安鎌倉古道」がある。舗装路を横断し再度古道に入る。入り口は木の柵があり、入れないかと思ったら二重になっていて人なら入れるようになっていた。おそらく二輪車進入を防ぐためだろう。道は格段に歩きやすく幅が広い。ただし赤土なのですべらないように。途中でピークを左に巻いて道が行く所があるのだが、右に巻く廃道もあり、ピークの先で合流する。古道も時代で付け替えられ左右を見渡すと幾本もの道筋がつけられている。1kmも進むと林道を横断するところが2箇所出てくる。また林道のすぐ横を通る所もある。林道を2箇所横断すると道は尾根上から沢筋になり、道に水たまりが見られる所も出てくる。芦ノ湖高原別荘地に近づいた証拠である。500m進むと前方に柵とコンクリ壁が見える。鉄塔である。その向こうに別荘がある。道をさらに100m進むと別荘地のCエリア前に出る。「鎌倉古道入口」標識がある。別荘地内をさらに上る古道はすでにない。おそらく家々の境やその先の上って行く道が古道を元にした道と推定されるが、もはや古色はない。かつて古道は別荘地になった所を上り有料道路を横断し箱根に下っていったはずだ。部分的には切通しが残存しているかもしれない。
車での帰路、小沢から清掃工場裏への道を2回間違え、3回目でやっと山田中方面へ出られた。林道の分岐点を間違えやすい。来るときは上りの右方向へ行けばよかったが、下りはそうはいかない。
2011年03月21日
安倍七観音霊場巡りコース(静岡市駿河区、葵区、清水区)
安倍七観音霊場巡りコース(静岡市駿河区、葵区、清水区)
伝説では、僧:行基が聖武天皇(別の皇族の場合もあり)病気平癒のため、駿河の国(足久保?またはその寺の周辺の場合がある)で樟を切り倒し、七体の観音を彫り、七つの寺に納めたといわれる。
行基は奈良時代に実在した優れた僧であり、畿内をめぐったことは歴史的に確実そうである。静岡県内だけでなく全国的にも、行基開基といわれる寺院はあまたにのぼるが、静岡までには足を伸ばしていないだろう。だからといって、その寺の品位をおとしめようという意図はない。その寺がそれほど古い、あるいは格式がある、行基が目指したことをこの寺は実現したいといいたい。または行基の息のかかった者たちが開基やこの伝説にからんでいたのかもしれない。そう解釈しよう。
巡礼の順序は、特にどこからはじめるという規則性はないようなので、便宜的に西からつないでみる。静鉄タクシーの巡礼見本コースでもそうなっているが、真似してみようという意図はないので、それとは一部順序を変えてみる。主に巡礼道らしきところを紹介したいのだ。
・徳願寺(静岡市駿河区向敷地689)
北条早雲の妹:北川殿の菩提寺。古い石塔類多し。元は大窪寺といって、裏山の山頂(仏平、大久保山、小豆山)付近の扇平に寺があったという。山頂へは裏山のハイキングコースがあるので上ることができる。仏平からさらに尾根を伝い途中歓昌院坂を越えて、大鑪(金偏に戸と書いてだたらと読む、たたらは錧または鑪であり、金戸の字はない)オオダタラ不動尊まで歩いていけるが、時期は晩秋・冬・春がよかろう。私は飯間山さらに谷川峠まで足を延ばせた。
参道入口に丁石があり、階段を上ればすぐ二丁で山門である。ここに車道が横切っていて、車で境内まで行ける。
次の建穂へのコースであるが、県道を北上し牧ヶ谷で木枯らしの森を見つつ藁科川を渡るのが無難である。車でならこれになる。
ちなみに古い道を行くなら向敷地の山と平野の境目の道を選んで進むのがお勧めである。古めかしさを味わえよう。安倍川と藁科川が合流する地点に浮かぶ舟山が見える地点の、こちらの山の斜面に昔の道はあったのだろうが、今は通れないだろう。かつては舟山とこの山とはつながっていたようだ。ちなみに木枯らしの森と南の山も地質的に同一でつながっていたことが分かる。牧ヶ谷橋の所で山すそがせまっているが、この丘上の茶畑に昔の峠道らしきが通っている。
古道好きならあえて遠回りになるが、南周りを紹介する。徳願寺の参道入口から山と平野の境目を南下すると、手児の呼び坂(通称:ぬすっと坂)入口標識がある。この道を通り、北丸子の山すそに沿い龍国寺前を通過し、国道1号線に出て泉ヶ谷の柴屋寺方面を目指す。柴屋寺より奥の歓昌院の裏山越えが、歓昌院坂の古道にしてハイキングコースである。坂を越えると牧ヶ谷であり、石道標が迎えてくれる。牧ヶ谷の牧は古代の軍馬用牧場を意味するかもしれないといわれる。古めかしい田舎びた雰囲気が残っている。道を北上すれば木枯らしの森のある牧ヶ谷橋に出る。その手前左の道を山奥に行くと寺院と古墳を見られる。
牧ヶ谷橋を渡って国道362号をいったん左折(西)しまた右折(北)し北の山に向かい進めばよい。
・建穂寺タキョウジ(静岡市葵区建穂271)
建穂寺は現在廃寺で近くの建穂公民館に寺の遺品が保存されているが、そこへ行く前にかつての所在地を詣でよう。公民館より東500mの建穂神社である。神社裏手は広々した植林地になっているが、かつて坊が軒を連ねた所だろう。裏山の斜面を上っても所々に平坦地があり、建物があったことを知らしめる。裏山の中腹まで建物があったことは絵図で分かる。
さて公民館に行く。見られる一部の寺宝を見てかつての栄華をしのぶもよし、何かを感じるもよし。
かつては静岡最大の寺院だった。かつて白鳳年間とされたが現在平安時代創建とされるようだ。静岡まつりのとき、浅間神社は廿日会祭を行う、というより、歴史的順序は逆である。浅間神社に奉納される稚児の舞はこの寺の舞である。今でも建穂地区の子供が舞う。徳川家康ですらこの稚児を出迎えに寺の門前に行き、数時間待たされたという。大御所家康ですら待ち続けさせる寺だったのだ。
次の増善寺へのコースを紹介する。公民館前に石道標があり、「右 当村道 左 久住洞慶院」と刻まれている。この右・当村道が昔の巡礼道で巡礼越えという。また慈悲尾の学童が羽鳥の学校に通学した道なので学校坂とも呼ばれた。公民館前に川が流れているが、この川の上流を目指せばよい。新興住宅地と畑を過ぎると、「林道 慈悲尾線」の看板がある。古道はこの右側にあるが、もう今は寸断されていて通らないほうがよいので、林道を行く。2.5km進み180m上がると切通しの峠で、開通記念碑がある。建穂側の古道は記念碑下左に見え、慈悲尾側は切通し5m上左の倒木の中にある。慈悲尾側は明らかに廃道である。林道を下ると古道を寸断して麓に出る。橋を渡った左に増善寺が見える。
山の林道が苦手なら、安倍川西岸の県道に出て慈悲尾を目指すのが一般的だ。
・増善寺 (静岡市葵区慈悲尾302)
681年開基、1500年今川氏により再興。慈悲寺といわれた。今川氏親墓所。徳川家康とも縁が深かった。千手観音菩薩を祀る観音堂があり、前仏が置かれている。秘仏は写真によって分かる。石塔や古い墓石が多い。
次の法明寺への古道は、本堂真裏のハイキングコースを行くことになるが、まったく案内標識は無いので、寺の関係者か付近の住民に聞くしかない。本堂真裏を5分上ると新しい石標識で「観音堂跡」が立っていて、植林された平坦地だ。かつてここに寺があったのだ。また東下に下る道もある。これは椎之雄神社への道である。北奥へ上っていくと10~15分で高圧鉄塔のある峠に着く。ここに標識があり、西の尾根を上ると安倍城であることを示している。マイナーな安倍城ハイキングコースのひとつなのだ。北は西ヶ谷である。5~10分下れば茶畑奥の舗装路に出られる。あとは西ヶ谷集落をめざせばよい。
車でなら安倍川西岸の県道に出て美和中学まで進み、左折し足久保奥を目指す。
なぜ古道は川沿いではなく山越えするかであるが、川の水量が減っているときは河原を歩いたのだろうが、ひとたび水量が増えると川沿いを歩けなかったのだろう。今のようにしっかりした堤防はなく、水量も今のように水害対策が進んで少なかったわけではなく、今の倍から数倍の水量だったと思われる。
西ヶ谷から足久保へは内牧(牧は古代の官営牧場かもしれない)、中ノ郷、松崎山のいずれから山越えして足久保に行けた。内牧からはいくつかの上り口が廃道である。ただ駿府学園・狩野介貞長記念碑のある尾根から電線巡視路を上っていけば足久保側への下山路になる電線巡視路を見出せよう。しかし国土地理院地形図に記入された古い道はすでに廃道で、別な箇所に電線巡視路が付けられているので、どこにどう道が付け替えられているのか分かりづらい。地図と磁石でルートファインディングできないととても安心して歩けない。基本的に昔ながらの山道は消失している。電線巡視路の標識は数字と記号で表しているのでどこに向かうか分からないのだ。ただ山中を歩いているとここが地図上に記載された古い山道の成れの果てかと思える所がある。結論として巡礼道として古い山道は通れない。
今の自動車道を通ることにするが、なるべく山すその古そうな道を選ぶと古色ゆかしい。
狩野介貞長記念碑、宇知ノ宮神社、はるな地蔵(はるなさん)、大仙寺、白髭神社などを経て松崎山の第二東名高架下を通過する。
* なお西ヶ谷から足久保についての詳細は『美和(足久保)街道』を参照すればもっと詳しく分かる。
・法明寺 (静岡市葵区足久保奥組1043)
美和中学前バス停で左折(西)し西進する。500mほどで県道が、急に右・左に折れ曲がる所がある。札の辻と呼ばれるらしい。ここの理容院と酒屋の間に石道標がある。もう刻字は読めないが、法明寺を指し示している。ここから旧道は少しの間だけ山すそを回りこむがすぐ現県道に合流する。南叟寺手前にも少しだけ山すそ回りの旧道があり、地蔵堂がある。足久保小学校手前の村前橋を渡り川に沿って進み、急な上り坂になると石塔が出現して古色ゆかしい。この上が寺である。
安倍七観音伝説が色濃く残っていて、行基の彫った楠はこの地にあったという。
古い石塔が多い。周辺は茶畑で上は杉檜植林地。
ここから霊山寺へは現県道を下り、安倍川に出る。ここから北街道方面に出たいのだが、主なルートは2つである。
① 第二東名高架下の市道の橋を渡り直進し、鯨が池を通過し桜峠トンネルを通り、麻機に出て麻機街道(賎機山東側)を南下し浅間神社前を目指す。浅間神社東前の石鳥居をくぐり長谷通りを進み、北街道に合流し左折(西)すれば清水区方面に進める。
第二東名高架下の橋は、戦前、有料の賃取橋があったので再興したようなものである。桜峠には地蔵が祀られている。
* 『麻機街道』参照。
② 美和街道に沿って安倍口団地前を通過し狩野橋を渡り、安倍街道(賎機山西側)に出て浅間神社前を目指す。浅間神社を通過し中町交差点も直進し江川町交差点で左折(西)すると北街道で清水区方面に進める。
* 『安倍街道』参照。
北街道とは通称名で「県道 静岡 千代田 清水線」という。江戸時代の東海道より北側にほぼ平行して通っている道なのでそう呼ばれるようだ。実は江戸時代の東海道より古い中世の東海道で、鎌倉と京の都を結ぶ鎌倉街道であった。とはいっても今の自動車が通る県道は大正時代に作られたので、その近辺に付かず離れずに古道が残存していることもある。
さて北街道を西進し清水区大内に至る前の、瀬名川交差点辺りの南に浄界寺や世尊寺がある。この東西に伸びる狭い道が鎌倉街道で、ここは間の宿:瀬名川の宿である。近くには「矢射タン橋の碑」もある。この碑は、鎌倉時代初期に幕府の重鎮でありながら謀反を起こし、京に脱出を謀った梶原一族が通過する際、幕府側が矢を放った所である。ここが東海道だから通ったということだ。この近辺には梶原氏ゆかりの物事が多い。例えば北に見える山の名は「梶原山」である。彼らが自害して果てた所だからである。
・霊山寺 (静岡市清水区大内597)
大内で石道標「大内観音」が見えたら左折(北)し山を目指す。山の中腹に寺の屋根が見える。途中石塔類もあろう。北街道は都市交通網のひとつでせわしないが、大内に入りちょいとした田舎びた雰囲気が味わえる。北進し浅間神社を過ぎると駐車場があり、参道の登山道となる。七つの場所で唯一車で門前に行けない。距離300m、標高差80mである。10~20分で上れるだろう。足の弱い人は参道入口で拝めばよい。
古義真言宗、仁王門は重要文化財、開創行基といわれる、三十三曲がりの急な細い道は観音三十三身の化現を意味し、途中の6基の丁石は六波羅蜜を意味する。
この裏山の山頂は帆掛山一本松公園で標高差150mである。
次は平澤寺である。まず古道ルートを紹介するが、通れないので別ルートをあとで紹介する。北街道に出て広い瀬名川交差点に戻る。この近くのガソリンスタンドの横に消防分団がある。この裏に瀬名川公園があり、ここに石道標がある。ここから南の浄界寺や世尊寺を通って巴川に出て、川向こうの現在国道1号線(国1)の中吉田交差点に出るのが、旧竜爪街道にして平澤観音道へのルートである。しかし11年3月現在、巴川への架橋工事中でまだ橋がないので、別ルートを示す。広い瀬名川交差点を東へ1区間行くと古い瀬名川交差点の信号がある。ここを南に進むと国1に出られる。国1を西に1区間進むと中吉田交差点に着く。古道はボーリング場脇を南に進むが、今は線路を通れない。新道である交差点からまっすぐ南に進む広い道を行く。古道は道1本分東だと思いつつ進めばよい。JR線と静岡鉄道の踏み切りを渡り、静鉄線路に沿い道1本東に移動する。津島神社とやぶきた茶の記念碑があるところを南に曲がる。ここが先ほどから出てくる旧竜爪街道である。広い南幹線を渡り、次の交差点に出ると。ここの東西にはしる道が江戸時代の東海道である。ここで旧竜爪街道は終点となり、この先南に行く道が平沢観音道である。クレー射撃場、乗馬スクール、フランス料理店、平沢動物霊園の道案内があるので迷うことはないだろう。道なりに進めば田舎びた雰囲気と古い石仏にいくつか出会え、門前に達するだろう。
* 「竜爪街道」、「平沢観音道」については、『古街道を行く』鈴木茂伸(静岡新聞社)を参照すれば詳細な説明がある。
・平澤寺ヘイタクジ、平沢観音ひらさわかんのん (静岡市駿河区平沢ヒラサワ50)
和銅年間に行基が立ち寄り地蔵菩薩を彫って祀ったことによるという。718年皇子の病気平癒のため再度訪れ七体の観音菩薩を彫り、当寺を含め7体を7つの寺に祀ったという。真言宗。現在動物霊園としても人気を集めている。
次の鉄舟寺へのルートは、現在の日本平ハイキングコースにして、古い巡礼道が部分的にある。本堂裏左に朽ちかけた石道標があり、ハイキングコースを示す標識もあるので、そちらに向かう。車道をはずれ登山道となるとまた石道標があり、古めかしい巡礼道の趣きがある。絶壁の狭い道を抜け、ゴルフ場横の尾根を越す所にも石道標がある。これまでの石道標には久能寺または久能観音となっている、つまり石道標は江戸時代のものである。ルートは下に下りるが、尾根を北に向かうルートには工事中のため立ち入り禁止となっている。この北ルートは尾根伝いの清水区と駿河区の境で県立大学や県立美術館までつながっている。ここから2~3分も下ると舗装路に出る。舗装路を少し左に見ると舗装路を横断してまた山を上るハイキングコースの標識がある。これまた鉄舟寺に向かう巡礼道である。日本平観光ホテルの横に出るが、山頂を目指すわけではないので、ホテル下側の庭園の下の寂しい車道を下っていく。みかん畑の中の農道となる。この途中で村松方面を示すハイキングコース標識があり、行き止まりであることも示していよう。鉄舟寺に向かう巡礼道のハイキングコースは農場再整備で破壊されてしまった。しかしある程度たどれるので紹介する。行き止まりとなっていてもハイキングコースをしばらく行く。完全にコースが分からなくなるが、山を崩して平らにした農園の左端にはいくつもの山のがけが林立している。その中の多分もっとも左奥(東奥)のがけを10m上り一番高い所に道がついている。しばらく歩くと古い標識がそのまま残っている。標識「日本平←→村松、ハイキングコース」は数本ある。かつての鉄舟寺に向かう巡礼道である。ただ鉄舟寺の観音堂にもう100mばかりという所で耕作放棄された畑の雑草がひどく進むのをあきらめた。かつてはきれいに整備された道で周辺の畑もきれいに整備されていて、鉄舟寺の観音堂まで心地よく歩けたのだが。鉄舟寺の観音堂の右に車が通れそうなほど広い切通し道がついているが、それがこのコースである。道幅はすぐに畑のあぜ道ほどの狭さになる。
・鉄舟寺(久能寺)(静岡市清水区村松2188)
臨済宗。本尊:千手観音菩薩。飛鳥時代、久能氏により久能山に堂を建立したのにはじまる。奈良時代、行基が久能寺と号した。聖一国師が学ぶなど駿河一の学問寺として隆盛を極めた。武田信玄が駿河を支配したとき、久能山を山城(久能山城)にするため、久能寺を村松の地に移転した。幕末頃より衰退し明治2年廃寺となった。地元の郷士が山岡鉄舟をリーダーにして再興を果たし、寺名も鉄舟寺とした。
鉄舟寺(久能寺)を目指すルートで、静鉄電車狐ヶ崎駅前ジャスコイーオン横からのものがある。狐ヶ崎駅前を横切る道は江戸時代の東海道である。イーオン左に小さな沢があり、そこのたもとに石道標で「久能寺観音道」と記されている。そのみちである。ただ石道標は移転されていて、道1本分東に行くと南に向かう路地がある。これが「久能寺観音道」である。ルートは道なりに行けば鉄舟寺に着けるわけではなく、紆余曲折が多いルートとなっているが、古めかしい雰囲気を味わえるコースである。
* 『久能寺観音道』参照。
戦国期まで鉄舟寺(久能寺)は久能山にあったので、最後に久能山に詣でるのも一興であろう。足が弱い場合、車で日本平山頂へ行き、ロープウェイを使って久能山東照宮へ行く手段もある。苦労したい人は、久能山の石段を一歩一歩踏みしめればよかろう。ちなみに久能寺をしのべるものは一切ないが、かつて久能寺にいた人たちもこの眼下の景色を見ていたのかと感慨にふけることはできる。久能山東照宮は日光東照宮より知名度は落ちるが、こちらの方が先であり、家康が最初に埋葬されたのはここだ。また久能城の遺構として勘助井戸がある。ただし城が築かれたときもう勘助は亡くなっていたはずだが。
久能までの古道ルートとしては、清水区に「久能街道」があり、駿河区に「大谷街道」や葵区から駿河区にかけて「久能山東照宮道」もある。
* 『久能街道』、『大谷街道』、『久能山東照宮道』参照。
伝説では、僧:行基が聖武天皇(別の皇族の場合もあり)病気平癒のため、駿河の国(足久保?またはその寺の周辺の場合がある)で樟を切り倒し、七体の観音を彫り、七つの寺に納めたといわれる。
行基は奈良時代に実在した優れた僧であり、畿内をめぐったことは歴史的に確実そうである。静岡県内だけでなく全国的にも、行基開基といわれる寺院はあまたにのぼるが、静岡までには足を伸ばしていないだろう。だからといって、その寺の品位をおとしめようという意図はない。その寺がそれほど古い、あるいは格式がある、行基が目指したことをこの寺は実現したいといいたい。または行基の息のかかった者たちが開基やこの伝説にからんでいたのかもしれない。そう解釈しよう。
巡礼の順序は、特にどこからはじめるという規則性はないようなので、便宜的に西からつないでみる。静鉄タクシーの巡礼見本コースでもそうなっているが、真似してみようという意図はないので、それとは一部順序を変えてみる。主に巡礼道らしきところを紹介したいのだ。
・徳願寺(静岡市駿河区向敷地689)
北条早雲の妹:北川殿の菩提寺。古い石塔類多し。元は大窪寺といって、裏山の山頂(仏平、大久保山、小豆山)付近の扇平に寺があったという。山頂へは裏山のハイキングコースがあるので上ることができる。仏平からさらに尾根を伝い途中歓昌院坂を越えて、大鑪(金偏に戸と書いてだたらと読む、たたらは錧または鑪であり、金戸の字はない)オオダタラ不動尊まで歩いていけるが、時期は晩秋・冬・春がよかろう。私は飯間山さらに谷川峠まで足を延ばせた。
参道入口に丁石があり、階段を上ればすぐ二丁で山門である。ここに車道が横切っていて、車で境内まで行ける。
次の建穂へのコースであるが、県道を北上し牧ヶ谷で木枯らしの森を見つつ藁科川を渡るのが無難である。車でならこれになる。
ちなみに古い道を行くなら向敷地の山と平野の境目の道を選んで進むのがお勧めである。古めかしさを味わえよう。安倍川と藁科川が合流する地点に浮かぶ舟山が見える地点の、こちらの山の斜面に昔の道はあったのだろうが、今は通れないだろう。かつては舟山とこの山とはつながっていたようだ。ちなみに木枯らしの森と南の山も地質的に同一でつながっていたことが分かる。牧ヶ谷橋の所で山すそがせまっているが、この丘上の茶畑に昔の峠道らしきが通っている。
古道好きならあえて遠回りになるが、南周りを紹介する。徳願寺の参道入口から山と平野の境目を南下すると、手児の呼び坂(通称:ぬすっと坂)入口標識がある。この道を通り、北丸子の山すそに沿い龍国寺前を通過し、国道1号線に出て泉ヶ谷の柴屋寺方面を目指す。柴屋寺より奥の歓昌院の裏山越えが、歓昌院坂の古道にしてハイキングコースである。坂を越えると牧ヶ谷であり、石道標が迎えてくれる。牧ヶ谷の牧は古代の軍馬用牧場を意味するかもしれないといわれる。古めかしい田舎びた雰囲気が残っている。道を北上すれば木枯らしの森のある牧ヶ谷橋に出る。その手前左の道を山奥に行くと寺院と古墳を見られる。
牧ヶ谷橋を渡って国道362号をいったん左折(西)しまた右折(北)し北の山に向かい進めばよい。
・建穂寺タキョウジ(静岡市葵区建穂271)
建穂寺は現在廃寺で近くの建穂公民館に寺の遺品が保存されているが、そこへ行く前にかつての所在地を詣でよう。公民館より東500mの建穂神社である。神社裏手は広々した植林地になっているが、かつて坊が軒を連ねた所だろう。裏山の斜面を上っても所々に平坦地があり、建物があったことを知らしめる。裏山の中腹まで建物があったことは絵図で分かる。
さて公民館に行く。見られる一部の寺宝を見てかつての栄華をしのぶもよし、何かを感じるもよし。
かつては静岡最大の寺院だった。かつて白鳳年間とされたが現在平安時代創建とされるようだ。静岡まつりのとき、浅間神社は廿日会祭を行う、というより、歴史的順序は逆である。浅間神社に奉納される稚児の舞はこの寺の舞である。今でも建穂地区の子供が舞う。徳川家康ですらこの稚児を出迎えに寺の門前に行き、数時間待たされたという。大御所家康ですら待ち続けさせる寺だったのだ。
次の増善寺へのコースを紹介する。公民館前に石道標があり、「右 当村道 左 久住洞慶院」と刻まれている。この右・当村道が昔の巡礼道で巡礼越えという。また慈悲尾の学童が羽鳥の学校に通学した道なので学校坂とも呼ばれた。公民館前に川が流れているが、この川の上流を目指せばよい。新興住宅地と畑を過ぎると、「林道 慈悲尾線」の看板がある。古道はこの右側にあるが、もう今は寸断されていて通らないほうがよいので、林道を行く。2.5km進み180m上がると切通しの峠で、開通記念碑がある。建穂側の古道は記念碑下左に見え、慈悲尾側は切通し5m上左の倒木の中にある。慈悲尾側は明らかに廃道である。林道を下ると古道を寸断して麓に出る。橋を渡った左に増善寺が見える。
山の林道が苦手なら、安倍川西岸の県道に出て慈悲尾を目指すのが一般的だ。
・増善寺 (静岡市葵区慈悲尾302)
681年開基、1500年今川氏により再興。慈悲寺といわれた。今川氏親墓所。徳川家康とも縁が深かった。千手観音菩薩を祀る観音堂があり、前仏が置かれている。秘仏は写真によって分かる。石塔や古い墓石が多い。
次の法明寺への古道は、本堂真裏のハイキングコースを行くことになるが、まったく案内標識は無いので、寺の関係者か付近の住民に聞くしかない。本堂真裏を5分上ると新しい石標識で「観音堂跡」が立っていて、植林された平坦地だ。かつてここに寺があったのだ。また東下に下る道もある。これは椎之雄神社への道である。北奥へ上っていくと10~15分で高圧鉄塔のある峠に着く。ここに標識があり、西の尾根を上ると安倍城であることを示している。マイナーな安倍城ハイキングコースのひとつなのだ。北は西ヶ谷である。5~10分下れば茶畑奥の舗装路に出られる。あとは西ヶ谷集落をめざせばよい。
車でなら安倍川西岸の県道に出て美和中学まで進み、左折し足久保奥を目指す。
なぜ古道は川沿いではなく山越えするかであるが、川の水量が減っているときは河原を歩いたのだろうが、ひとたび水量が増えると川沿いを歩けなかったのだろう。今のようにしっかりした堤防はなく、水量も今のように水害対策が進んで少なかったわけではなく、今の倍から数倍の水量だったと思われる。
西ヶ谷から足久保へは内牧(牧は古代の官営牧場かもしれない)、中ノ郷、松崎山のいずれから山越えして足久保に行けた。内牧からはいくつかの上り口が廃道である。ただ駿府学園・狩野介貞長記念碑のある尾根から電線巡視路を上っていけば足久保側への下山路になる電線巡視路を見出せよう。しかし国土地理院地形図に記入された古い道はすでに廃道で、別な箇所に電線巡視路が付けられているので、どこにどう道が付け替えられているのか分かりづらい。地図と磁石でルートファインディングできないととても安心して歩けない。基本的に昔ながらの山道は消失している。電線巡視路の標識は数字と記号で表しているのでどこに向かうか分からないのだ。ただ山中を歩いているとここが地図上に記載された古い山道の成れの果てかと思える所がある。結論として巡礼道として古い山道は通れない。
今の自動車道を通ることにするが、なるべく山すその古そうな道を選ぶと古色ゆかしい。
狩野介貞長記念碑、宇知ノ宮神社、はるな地蔵(はるなさん)、大仙寺、白髭神社などを経て松崎山の第二東名高架下を通過する。
* なお西ヶ谷から足久保についての詳細は『美和(足久保)街道』を参照すればもっと詳しく分かる。
・法明寺 (静岡市葵区足久保奥組1043)
美和中学前バス停で左折(西)し西進する。500mほどで県道が、急に右・左に折れ曲がる所がある。札の辻と呼ばれるらしい。ここの理容院と酒屋の間に石道標がある。もう刻字は読めないが、法明寺を指し示している。ここから旧道は少しの間だけ山すそを回りこむがすぐ現県道に合流する。南叟寺手前にも少しだけ山すそ回りの旧道があり、地蔵堂がある。足久保小学校手前の村前橋を渡り川に沿って進み、急な上り坂になると石塔が出現して古色ゆかしい。この上が寺である。
安倍七観音伝説が色濃く残っていて、行基の彫った楠はこの地にあったという。
古い石塔が多い。周辺は茶畑で上は杉檜植林地。
ここから霊山寺へは現県道を下り、安倍川に出る。ここから北街道方面に出たいのだが、主なルートは2つである。
① 第二東名高架下の市道の橋を渡り直進し、鯨が池を通過し桜峠トンネルを通り、麻機に出て麻機街道(賎機山東側)を南下し浅間神社前を目指す。浅間神社東前の石鳥居をくぐり長谷通りを進み、北街道に合流し左折(西)すれば清水区方面に進める。
第二東名高架下の橋は、戦前、有料の賃取橋があったので再興したようなものである。桜峠には地蔵が祀られている。
* 『麻機街道』参照。
② 美和街道に沿って安倍口団地前を通過し狩野橋を渡り、安倍街道(賎機山西側)に出て浅間神社前を目指す。浅間神社を通過し中町交差点も直進し江川町交差点で左折(西)すると北街道で清水区方面に進める。
* 『安倍街道』参照。
北街道とは通称名で「県道 静岡 千代田 清水線」という。江戸時代の東海道より北側にほぼ平行して通っている道なのでそう呼ばれるようだ。実は江戸時代の東海道より古い中世の東海道で、鎌倉と京の都を結ぶ鎌倉街道であった。とはいっても今の自動車が通る県道は大正時代に作られたので、その近辺に付かず離れずに古道が残存していることもある。
さて北街道を西進し清水区大内に至る前の、瀬名川交差点辺りの南に浄界寺や世尊寺がある。この東西に伸びる狭い道が鎌倉街道で、ここは間の宿:瀬名川の宿である。近くには「矢射タン橋の碑」もある。この碑は、鎌倉時代初期に幕府の重鎮でありながら謀反を起こし、京に脱出を謀った梶原一族が通過する際、幕府側が矢を放った所である。ここが東海道だから通ったということだ。この近辺には梶原氏ゆかりの物事が多い。例えば北に見える山の名は「梶原山」である。彼らが自害して果てた所だからである。
・霊山寺 (静岡市清水区大内597)
大内で石道標「大内観音」が見えたら左折(北)し山を目指す。山の中腹に寺の屋根が見える。途中石塔類もあろう。北街道は都市交通網のひとつでせわしないが、大内に入りちょいとした田舎びた雰囲気が味わえる。北進し浅間神社を過ぎると駐車場があり、参道の登山道となる。七つの場所で唯一車で門前に行けない。距離300m、標高差80mである。10~20分で上れるだろう。足の弱い人は参道入口で拝めばよい。
古義真言宗、仁王門は重要文化財、開創行基といわれる、三十三曲がりの急な細い道は観音三十三身の化現を意味し、途中の6基の丁石は六波羅蜜を意味する。
この裏山の山頂は帆掛山一本松公園で標高差150mである。
次は平澤寺である。まず古道ルートを紹介するが、通れないので別ルートをあとで紹介する。北街道に出て広い瀬名川交差点に戻る。この近くのガソリンスタンドの横に消防分団がある。この裏に瀬名川公園があり、ここに石道標がある。ここから南の浄界寺や世尊寺を通って巴川に出て、川向こうの現在国道1号線(国1)の中吉田交差点に出るのが、旧竜爪街道にして平澤観音道へのルートである。しかし11年3月現在、巴川への架橋工事中でまだ橋がないので、別ルートを示す。広い瀬名川交差点を東へ1区間行くと古い瀬名川交差点の信号がある。ここを南に進むと国1に出られる。国1を西に1区間進むと中吉田交差点に着く。古道はボーリング場脇を南に進むが、今は線路を通れない。新道である交差点からまっすぐ南に進む広い道を行く。古道は道1本分東だと思いつつ進めばよい。JR線と静岡鉄道の踏み切りを渡り、静鉄線路に沿い道1本東に移動する。津島神社とやぶきた茶の記念碑があるところを南に曲がる。ここが先ほどから出てくる旧竜爪街道である。広い南幹線を渡り、次の交差点に出ると。ここの東西にはしる道が江戸時代の東海道である。ここで旧竜爪街道は終点となり、この先南に行く道が平沢観音道である。クレー射撃場、乗馬スクール、フランス料理店、平沢動物霊園の道案内があるので迷うことはないだろう。道なりに進めば田舎びた雰囲気と古い石仏にいくつか出会え、門前に達するだろう。
* 「竜爪街道」、「平沢観音道」については、『古街道を行く』鈴木茂伸(静岡新聞社)を参照すれば詳細な説明がある。
・平澤寺ヘイタクジ、平沢観音ひらさわかんのん (静岡市駿河区平沢ヒラサワ50)
和銅年間に行基が立ち寄り地蔵菩薩を彫って祀ったことによるという。718年皇子の病気平癒のため再度訪れ七体の観音菩薩を彫り、当寺を含め7体を7つの寺に祀ったという。真言宗。現在動物霊園としても人気を集めている。
次の鉄舟寺へのルートは、現在の日本平ハイキングコースにして、古い巡礼道が部分的にある。本堂裏左に朽ちかけた石道標があり、ハイキングコースを示す標識もあるので、そちらに向かう。車道をはずれ登山道となるとまた石道標があり、古めかしい巡礼道の趣きがある。絶壁の狭い道を抜け、ゴルフ場横の尾根を越す所にも石道標がある。これまでの石道標には久能寺または久能観音となっている、つまり石道標は江戸時代のものである。ルートは下に下りるが、尾根を北に向かうルートには工事中のため立ち入り禁止となっている。この北ルートは尾根伝いの清水区と駿河区の境で県立大学や県立美術館までつながっている。ここから2~3分も下ると舗装路に出る。舗装路を少し左に見ると舗装路を横断してまた山を上るハイキングコースの標識がある。これまた鉄舟寺に向かう巡礼道である。日本平観光ホテルの横に出るが、山頂を目指すわけではないので、ホテル下側の庭園の下の寂しい車道を下っていく。みかん畑の中の農道となる。この途中で村松方面を示すハイキングコース標識があり、行き止まりであることも示していよう。鉄舟寺に向かう巡礼道のハイキングコースは農場再整備で破壊されてしまった。しかしある程度たどれるので紹介する。行き止まりとなっていてもハイキングコースをしばらく行く。完全にコースが分からなくなるが、山を崩して平らにした農園の左端にはいくつもの山のがけが林立している。その中の多分もっとも左奥(東奥)のがけを10m上り一番高い所に道がついている。しばらく歩くと古い標識がそのまま残っている。標識「日本平←→村松、ハイキングコース」は数本ある。かつての鉄舟寺に向かう巡礼道である。ただ鉄舟寺の観音堂にもう100mばかりという所で耕作放棄された畑の雑草がひどく進むのをあきらめた。かつてはきれいに整備された道で周辺の畑もきれいに整備されていて、鉄舟寺の観音堂まで心地よく歩けたのだが。鉄舟寺の観音堂の右に車が通れそうなほど広い切通し道がついているが、それがこのコースである。道幅はすぐに畑のあぜ道ほどの狭さになる。
・鉄舟寺(久能寺)(静岡市清水区村松2188)
臨済宗。本尊:千手観音菩薩。飛鳥時代、久能氏により久能山に堂を建立したのにはじまる。奈良時代、行基が久能寺と号した。聖一国師が学ぶなど駿河一の学問寺として隆盛を極めた。武田信玄が駿河を支配したとき、久能山を山城(久能山城)にするため、久能寺を村松の地に移転した。幕末頃より衰退し明治2年廃寺となった。地元の郷士が山岡鉄舟をリーダーにして再興を果たし、寺名も鉄舟寺とした。
鉄舟寺(久能寺)を目指すルートで、静鉄電車狐ヶ崎駅前ジャスコイーオン横からのものがある。狐ヶ崎駅前を横切る道は江戸時代の東海道である。イーオン左に小さな沢があり、そこのたもとに石道標で「久能寺観音道」と記されている。そのみちである。ただ石道標は移転されていて、道1本分東に行くと南に向かう路地がある。これが「久能寺観音道」である。ルートは道なりに行けば鉄舟寺に着けるわけではなく、紆余曲折が多いルートとなっているが、古めかしい雰囲気を味わえるコースである。
* 『久能寺観音道』参照。
戦国期まで鉄舟寺(久能寺)は久能山にあったので、最後に久能山に詣でるのも一興であろう。足が弱い場合、車で日本平山頂へ行き、ロープウェイを使って久能山東照宮へ行く手段もある。苦労したい人は、久能山の石段を一歩一歩踏みしめればよかろう。ちなみに久能寺をしのべるものは一切ないが、かつて久能寺にいた人たちもこの眼下の景色を見ていたのかと感慨にふけることはできる。久能山東照宮は日光東照宮より知名度は落ちるが、こちらの方が先であり、家康が最初に埋葬されたのはここだ。また久能城の遺構として勘助井戸がある。ただし城が築かれたときもう勘助は亡くなっていたはずだが。
久能までの古道ルートとしては、清水区に「久能街道」があり、駿河区に「大谷街道」や葵区から駿河区にかけて「久能山東照宮道」もある。
* 『久能街道』、『大谷街道』、『久能山東照宮道』参照。