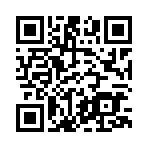2019年09月01日
葉梨街道:静岡県藤枝市
葉梨街道
・情報提供呼びかけ
今後、2016年11月以降、笹間街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
藤枝市葉梨川流域の道である。一応起点は県道215号伊久美藤枝線と旧東海道との交差点:藤枝大手とする。ここから葉梨川の上流を目指すことになる。そして反対に下流側を目指すと田中城を経て焼津駅に至るが、今回は割愛する。
*住所地は当地ではなく附近のものである場合がある。住所は現地で探す時の補助になればという思いで掲載しているためである。
大手交差点周辺の大手、本町、天王町の遺物類から紹介する。
・成田山不動寺、新護寺(藤枝市本町4丁目5-24 )
・左車神社(藤枝市本町4丁目6-14 )
・愛宕神社(藤枝市本町4丁目3-26 )
・養命寺(大手1丁目6-35 )
・源昌寺(大手1丁目14-10 )
・キリスト教会ふじえだチャペル(大手1丁目17-3 )
・向善寺(天王町1丁目5-30 )
・了善寺(天王町1丁目4-1 )
・豊受教会(天王町2丁目3- )
・地蔵堂(天王町2丁目3-41 )
・ 神社(天王町2丁目3-38 )
・翁稲荷社(天王町2丁目3-30 )
・大黒天(本町3丁目2-13 )
・ 神社(天王町2丁目9-15 )
・六角庵子育地蔵尊(天王町2丁目7-45 )
・八坂神社(天王町3丁目-16-1 )
・岳叟寺(五十海4丁目8-34 )
・原木神社(五十海4丁目3-10 )
・境橋(藤岡5丁目- )
・押切橋(時ケ谷 )
・耕雲寺(時ケ谷253 )
・智勝神社(下薮田26-37 )
・最林寺(下薮田322 )
・ 神社(時ケ谷30 )
・桜宮神社(時ケ谷30 )
・白山神社(上薮田658 )
・利勝院(上薮田669 )
・貴船神社(下之郷580 )
・長慶寺(下之郷1225 )
・延命地蔵尊(横見1361-8 )
・八幡神社(花倉332 )
・遍照寺(花倉397-1 )
・補陀落寺(花倉1038 )
・花倉城跡(花倉 )
・忠霊之碑(下之郷、中田203₋2 )
・二ノ宮神社(中ノ合711 )
・毘沙門天(中ノ合8-3 )
・准渓寺(中ノ合68 )
・連久寺(北方47 )
・白藤の滝(北方 )
・盤脚院(西方407 )
・安楽寺(北方962 )
・葉梨神社(北方962 )
・津島神社(北方1451-1 )
・西方八幡宮(西方1691-8 )
・大沢峡(西方 )
・(西方 )
☆☆☆~~~葉梨川沿い~~~
天王町周辺の遺物類から紹介する。
・六角庵子育て地蔵尊(藤枝市天王町2丁目7‐45、 )
・豊受教会(藤枝市天王町2丁目、 )
・ 神社(藤枝市天王町2丁目3-41 )
・ 神社(藤枝市天王町2丁目3-38 )
・ 神社(藤枝市天王町2丁目9-15 )
・ 翁稲荷社(藤枝市天王町2丁目3-30 )
・ 八坂神社(藤枝市天王町3丁目16-9 )
・ 大黒天(藤枝市本町3丁目2-13 )
・ 養命寺(藤枝市本町3丁目6-35 )
・ 愛宕神社(藤枝市本町4丁目3-1 )
・ 成田山新護寺(藤枝市本町4丁目5-24 )
・ 左車神社(藤枝市本町4丁目6-13 )
・ 蓮生寺(藤枝市本町1丁目3-31 )
・ 茶木稲荷神社(藤枝市本町1丁目3-18 )
・ 神社(藤枝市本町1丁目4-30 )
・ 慶全寺(藤枝市本町1丁目12-13 )
・ 大井神社(藤枝市本町1丁目12-20 )
・ 長楽寺(藤枝市本町1丁目10-12 )
・ 天満宮津島神社(藤枝市本町1丁目13-2 )
・原木神社(五十海4丁目3-10 )
・岳叟寺(五十海4丁目8-34 )
・向善寺(藤枝天王町1丁目5-30 )
・了善寺(藤枝天王町1丁目4-1 )
・蓮華寺池公園(若王子500 )
・蓮華寺池
・藤枝市郷土博物館、文学館
・ 源昌寺(藤枝市大手1丁目14-10 )
・ キリスト教会藤枝チャペル(藤枝市大手1丁目17-14 )
・ 村岡山万願寺(藤枝市郡726-1 )
・ 田中神社(藤枝市郡726-1 )
・ 姥ヶ池(藤枝市立花2丁目9-11 )
・ 田中城址(藤枝市田中1丁目37-3、藤枝市立西益津小学校、西益津中学校)
・ 下屋敷稲荷社(藤枝市田中3丁目14 )
・青山八幡宮(八幡884 )
・神の池
・耕春院(八幡967 )
・須賀神社(鬼島11-25 )
・全居寺(鬼島16 )
・観音堂(鬼島21-7 )
・本行寺(鬼島11-3 )
・ 如法寺(鬼島46 )
・ 諏訪神社(鬼島629 )
・真福寺(上当間178 )
・橘神社(上当間92 )
・ 神社(平島1702 )
・ 藤井神社(平島12‐3 )
・ 東泉寺(平島179 )
・ 光明寺(平島372 )
・ 延命地蔵尊(平島136 )
~藤枝市薮田周辺~
・智勝神社(藤枝市下薮田26-37 )
・最林寺(藤枝市下薮田322)
・桜宮神社、二つ池(時ケ谷138-17 )
・耕雲寺(時ケ谷253 )
・白山神社(上薮田658 )
・利勝院(上薮田669 )
・忠霊之碑(中田203-2 )
・延命地蔵尊、横見池(横見1501)
・貴船神社(下之郷580 )
・衣原古墳群(下之郷 )
・長慶寺(下之郷1225 )
・八幡神社神輿御休所(花倉57-16 )
・ 神社(花倉85 )
・ 八幡神社(花倉332 )
・ 徧照寺(花倉397-1 )
・補陀落寺(花倉1038 )
・花倉城(花倉 )
・二ノ宮神社(中ノ合711 )
・毘沙門天(中ノ合8-3 )
・ 潅渓寺(中ノ合68 )
・ 連久寺(北方47 )
・ 安楽寺(北方962 )
・ 葉梨神社(北方962 )
・ 盤脚院(西方407 )
・津島神社(北方1451-1 )
・西方八幡宮(西方1691-8 )
・白藤の滝
・大沢峡
・峠道
朝比奈川沿いの集落や街道に出るための道があったようだ。
・情報提供呼びかけ
今後、2016年11月以降、笹間街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
藤枝市葉梨川流域の道である。一応起点は県道215号伊久美藤枝線と旧東海道との交差点:藤枝大手とする。ここから葉梨川の上流を目指すことになる。そして反対に下流側を目指すと田中城を経て焼津駅に至るが、今回は割愛する。
*住所地は当地ではなく附近のものである場合がある。住所は現地で探す時の補助になればという思いで掲載しているためである。
大手交差点周辺の大手、本町、天王町の遺物類から紹介する。
・成田山不動寺、新護寺(藤枝市本町4丁目5-24 )
・左車神社(藤枝市本町4丁目6-14 )
・愛宕神社(藤枝市本町4丁目3-26 )
・養命寺(大手1丁目6-35 )
・源昌寺(大手1丁目14-10 )
・キリスト教会ふじえだチャペル(大手1丁目17-3 )
・向善寺(天王町1丁目5-30 )
・了善寺(天王町1丁目4-1 )
・豊受教会(天王町2丁目3- )
・地蔵堂(天王町2丁目3-41 )
・ 神社(天王町2丁目3-38 )
・翁稲荷社(天王町2丁目3-30 )
・大黒天(本町3丁目2-13 )
・ 神社(天王町2丁目9-15 )
・六角庵子育地蔵尊(天王町2丁目7-45 )
・八坂神社(天王町3丁目-16-1 )
・岳叟寺(五十海4丁目8-34 )
・原木神社(五十海4丁目3-10 )
・境橋(藤岡5丁目- )
・押切橋(時ケ谷 )
・耕雲寺(時ケ谷253 )
・智勝神社(下薮田26-37 )
・最林寺(下薮田322 )
・ 神社(時ケ谷30 )
・桜宮神社(時ケ谷30 )
・白山神社(上薮田658 )
・利勝院(上薮田669 )
・貴船神社(下之郷580 )
・長慶寺(下之郷1225 )
・延命地蔵尊(横見1361-8 )
・八幡神社(花倉332 )
・遍照寺(花倉397-1 )
・補陀落寺(花倉1038 )
・花倉城跡(花倉 )
・忠霊之碑(下之郷、中田203₋2 )
・二ノ宮神社(中ノ合711 )
・毘沙門天(中ノ合8-3 )
・准渓寺(中ノ合68 )
・連久寺(北方47 )
・白藤の滝(北方 )
・盤脚院(西方407 )
・安楽寺(北方962 )
・葉梨神社(北方962 )
・津島神社(北方1451-1 )
・西方八幡宮(西方1691-8 )
・大沢峡(西方 )
・(西方 )
☆☆☆~~~葉梨川沿い~~~
天王町周辺の遺物類から紹介する。
・六角庵子育て地蔵尊(藤枝市天王町2丁目7‐45、 )
・豊受教会(藤枝市天王町2丁目、 )
・ 神社(藤枝市天王町2丁目3-41 )
・ 神社(藤枝市天王町2丁目3-38 )
・ 神社(藤枝市天王町2丁目9-15 )
・ 翁稲荷社(藤枝市天王町2丁目3-30 )
・ 八坂神社(藤枝市天王町3丁目16-9 )
・ 大黒天(藤枝市本町3丁目2-13 )
・ 養命寺(藤枝市本町3丁目6-35 )
・ 愛宕神社(藤枝市本町4丁目3-1 )
・ 成田山新護寺(藤枝市本町4丁目5-24 )
・ 左車神社(藤枝市本町4丁目6-13 )
・ 蓮生寺(藤枝市本町1丁目3-31 )
・ 茶木稲荷神社(藤枝市本町1丁目3-18 )
・ 神社(藤枝市本町1丁目4-30 )
・ 慶全寺(藤枝市本町1丁目12-13 )
・ 大井神社(藤枝市本町1丁目12-20 )
・ 長楽寺(藤枝市本町1丁目10-12 )
・ 天満宮津島神社(藤枝市本町1丁目13-2 )
・原木神社(五十海4丁目3-10 )
・岳叟寺(五十海4丁目8-34 )
・向善寺(藤枝天王町1丁目5-30 )
・了善寺(藤枝天王町1丁目4-1 )
・蓮華寺池公園(若王子500 )
・蓮華寺池
・藤枝市郷土博物館、文学館
・ 源昌寺(藤枝市大手1丁目14-10 )
・ キリスト教会藤枝チャペル(藤枝市大手1丁目17-14 )
・ 村岡山万願寺(藤枝市郡726-1 )
・ 田中神社(藤枝市郡726-1 )
・ 姥ヶ池(藤枝市立花2丁目9-11 )
・ 田中城址(藤枝市田中1丁目37-3、藤枝市立西益津小学校、西益津中学校)
・ 下屋敷稲荷社(藤枝市田中3丁目14 )
・青山八幡宮(八幡884 )
・神の池
・耕春院(八幡967 )
・須賀神社(鬼島11-25 )
・全居寺(鬼島16 )
・観音堂(鬼島21-7 )
・本行寺(鬼島11-3 )
・ 如法寺(鬼島46 )
・ 諏訪神社(鬼島629 )
・真福寺(上当間178 )
・橘神社(上当間92 )
・ 神社(平島1702 )
・ 藤井神社(平島12‐3 )
・ 東泉寺(平島179 )
・ 光明寺(平島372 )
・ 延命地蔵尊(平島136 )
~藤枝市薮田周辺~
・智勝神社(藤枝市下薮田26-37 )
・最林寺(藤枝市下薮田322)
・桜宮神社、二つ池(時ケ谷138-17 )
・耕雲寺(時ケ谷253 )
・白山神社(上薮田658 )
・利勝院(上薮田669 )
・忠霊之碑(中田203-2 )
・延命地蔵尊、横見池(横見1501)
・貴船神社(下之郷580 )
・衣原古墳群(下之郷 )
・長慶寺(下之郷1225 )
・八幡神社神輿御休所(花倉57-16 )
・ 神社(花倉85 )
・ 八幡神社(花倉332 )
・ 徧照寺(花倉397-1 )
・補陀落寺(花倉1038 )
・花倉城(花倉 )
・二ノ宮神社(中ノ合711 )
・毘沙門天(中ノ合8-3 )
・ 潅渓寺(中ノ合68 )
・ 連久寺(北方47 )
・ 安楽寺(北方962 )
・ 葉梨神社(北方962 )
・ 盤脚院(西方407 )
・津島神社(北方1451-1 )
・西方八幡宮(西方1691-8 )
・白藤の滝
・大沢峡
・峠道
朝比奈川沿いの集落や街道に出るための道があったようだ。
2016年09月22日
高草街道、三輪街道(静岡県藤枝市岡部、焼津市)
~~~高草街道、三輪街道~~~
’14 ’15 6月
・情報提供呼びかけ
今後、高草(三輪)街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
まだきちんと一通り調べていないので、過去に立ち寄った基礎資料にすぎないが、一応今後調べ直すということで、一旦掲載する。岡部から焼津に懸けて、高草山麓の三輪街道または高草街道と呼ばれる所の基礎資料である。
~岡部~
○つたの細道(平安時代から戦国時代の東海道)
古代中世(約700~1590年頃)の東海道。古くは「宇津の山越え」とか「蔦の下道」と呼ばれ平安時代の歌人;在原業平が『伊勢物語』にこの峠道のことを書き記してから全国的に名を知られるようになった。
*これより古い古代の東海道は「日本坂峠」越えの道で、静岡市小坂の日本坂峠登山口から焼津市花沢の法華寺前に出る道である。徒歩道ハイキングコース。
・歌碑:宇津ノ谷峠
・猫石
・つたの細道公園
・石碑:蔦の細道
○木和田川の堰堤
・国登録有形文化財:1910年豪雨によって大災害が発生した。災害防止のための砂防工事を進めた。1912年から14年以かけて造られた堰堤である。木和田川の13㎞にわたり、8基の石積み堰堤を築いた。形から兜堰堤ともいう。ちょうど蔦の細道や旧東海道藤枝市岡部側に下った所の川である。上流に向かうと石積みを見られる。
○明治のトンネル
明治、大正時代1876~1930の東海道。現在みられる「レンガのトンネル」は明治29年に照明用カンテラの失火によって新たに造り替えたもので、現在は国の有形文化財に認定されている。最初のトンネルは日本で初めて通行料を取ったトンネルなので、「銭取りトンネル」と言われた。
*他の宇津ノ谷のトンネル:
・大正のトンネル、完成は昭和初期、だいぶ坂を上り、人家の隣を通過しトンネルに至る県道である。
・昭和のトンネル、現在、国1上り線側(北側)
・平成のトンネル、現在、国1下り線側、歩道が付いている(南側)
○宇津ノ谷の旧東海道(江戸時代の東海道)
天正8年1581豊臣秀吉が小田原征伐のときに大軍を通すために開拓されたと云われている。江戸時代に入り正式な東海道として参勤交代の大名をはじめ、オランダ商館長、朝鮮通信使、琉球使節や一般の旅人が明治初期まで通行しており、当時はたいへん国際色豊かな街道としてにぎわっていた。
*私見:戦国史専門の小和田哲夫氏は江戸時代の東海道を最初に整備したのは今川義元で桶狭間に軍が向かうときは、その道を使ったのではないかと推定している。
・静岡市側からだと道の駅の東側の供養塔がある所にかつては一里塚があったと推定されている。そこから川伝いに西に向かい道の駅を通過し、現在の国1南側の小さな橋「平橋たいらはし」を渡るのが、江戸時代の東海道ルートである。ここから道は北の宇津ノ谷集落に向かうため、現在の国1を渡る。ここから先は川沿いに集落を目指すと道標や地図が頻繁にあるので分かるだろう。ちなみに平橋手前で左(南)に曲がり山に入っていくのが蔦の細道である。
・慶龍寺:十団子伝説
・賀茂神社
・お羽織屋
宇津ノ谷集落から江戸時代徒歩道東海道を上っていくと、馬頭観音や地蔵堂跡を過ぎ峠越えをすると、藤枝市に入る。その先で道は舗装された所に出て舗装路を歩く。この舗装路を逆に上ると、国1トンネルの山の上の排気口の建物に出て行き止まりであるので、下るしかない。そうすると藤枝市(旧岡部町)坂下集落に出る。
○坂下地蔵堂(藤枝市旧岡部町坂下2027)
・羅経記の碑
・鼻取り地蔵
・石仏石塔
○観音堂(廻沢2589)
○松岡神社(廻沢2718)
○十石坂観音堂(岡部1179 川原町)じっこくざか
市指定文化財。入母屋造りの瓦葺の観音堂、内陣、外陣の境の格子は非常に細かい技巧が施されている。江戸時代末期の作と思われ、観音堂内に2基の厨子が安置されている。
厨子1:中央にある厨子で、宮殿造り。屋根は入母屋造り、杮葺きコケラブキで二重垂木、妻入である。彩色が施され、江戸もやや末期の作と思われる。
厨子2:観音堂の向かって右。宝形、板葺屋根、黒漆塗りで簡素ではあるが品格の高いものだ。江戸も中期以降の作と思われる。
・河野蓀園碑文:市指定文化財。河野蓀園コウノソンエンは駿府町奉行服部久エ門貞勝が駿府地誌の編纂を山梨稲川ヤマナシトウセン(江戸時代の漢学者としてその名を知られた。)に依頼した時に、岡部の属する益頭郡を担当した人である。岡部本町に住し(屋号:河野屋)、文化12年正月18日46歳で没した。彼の墓碑は稲川の撰文と書が刻まれたものだ。その撰文の要旨は彼の資性と業績が立派だったことを顕彰したものだ。建碑については彼の友人で岡部宿駅の漢学者:杉山佐十、本間春策等の友情によって立石されたものだ。
・古:石燈籠?
・石塔?
・手洗石
・萬霊塔:文政三辰年
・新:萬霊塔
*私見:観音堂は旧東海道の県道横の10m高い山裾にある。おそらくかつては山裾が川の手前まであって東海道はこの観音堂と同じ標高まで上らないと越せなかったのだろう。そこで十石坂なのだろう。現在は土木技術の進歩で、山すそを完全に除去し平坦なので気付かないが、かつては坂道だったのだ。観音堂に上れば当時の旅人の気分が味わえるだろう。
・常夜燈、祠(岡部1140 川原町)
○笠懸松(藤枝市岡部642⁻19 牛ケ谷)
笠はあり その身はいかに なりならむ あわれはかなき 天の下かな
西行(西行ものがたりより)
平安時代末期~鎌倉時代にかけての歌僧として有名な西行が、愛弟子西住と東国へと
旅をしたときに起きた悲しい物語の舞台であり、謡曲「西行西住」にまつわる場所でもある。東下りの途中、川渡しの場で武士の揉め事に巻き込まれたとき、師である西行に暴力が振るわれたのに我慢できず、西住は相手の武士を杖で殴った。しかし西行は仏に仕える身として辱めに耐える大切さを説いた後、西住を破門した。西住は師を慕って後を追うが、岡部まで来て病に倒れ、最後に体を休めた松の木に、
「西へ行く 雨夜の月や あみだ笠 影を岡部の松に残して」
と、辞世を書き残した笠を懸け、そのまま帰らぬ人となった。
西行は、東国からの帰途に立ち寄った菴で一休みしていると、戸に古い檜笠が懸っていたよくよく見てみると、西行が破門した愛弟子西住に贈った笠だった。庵主に聞いてみると、西住が歌を書き記した笠を松の木に懸け、病気により最期を迎えたことを知り、悲しんで歌ったと伝えられている。
西住法師:岡部の里人伝云、西住は西行の弟子、西行に従って東遊す。遠州天竜川に於いて西行武人の船に乗合いて及危難。西住怒って武人に敵す。於之、西住師の勘気を蒙る。西行独歩東国に赴く。西住悲難愁絶して其師に追及んとす。自足栄々として独往、岡部里に至て病て不能行。終にこの里にて卒す。傍に一松樹あり。竹笠を掛一首の辞世を残す云々。
(「駿河國新風土記」新庄道雄より)
・宝篋印塔の一部、
○三星寺(岡部650)
・四国八十八所第三拾三番
・祠:地蔵
・新:三界萬霊菩提
・枡形跡:
曲尺手(かねんて)とも言う。本陣めがけて敵がたやすく侵入できないように宿場の出入口に設けたもので、ここは道が直角に折れ曲がっている。またここには木戸と番小屋が設けられ、木戸番が毎日木戸を明け六つに開け、暮れ六つに閉じた。
○専称寺(岡部663)
・西行座像:市指定文化財彫刻、像高50㎝、西行法師の旅姿をした座像で白木彫りの作りである。像底裏に「享保十一1726年江戸の湯島天神の西にいた柑本南浦(こうしもとなんぽ)が最林寺(川原町、文化五年焼失)に奉納」の意味の銘がある。江戸時代後期の作と思われる。岡部十石坂観音堂。
・不動尊立像:市指定文化財彫刻、像高:54㎝、一木彫り立像で忿怒の形相が力強く表現されている。鎌倉前期のものといわれる。岡部立光山不動院。
2体とも当山専称寺にて保管されている。
・六地蔵+7:計13:
○立石山不動尊(岡部795⁻5)
・馬頭:女馬 大正七年
・馬頭:大正四年
・馬頭:明治廿七年
・馬頭:女馬 大正九年
・石仏
・石祠:瓦葺
○大旅籠 柏屋(岡部817)
創設:天保7年1836、大旅籠柏屋は平成12年に東海道や旅、岡部宿を楽しく学べる歴史資料館として蘇えった。
旅籠とは江戸時代の宿泊施設。柏屋はその規模から「大旅籠柏屋」といわれ、岡部宿を代表する旅籠である。柏屋を経営していた山内家は5代目良吉(天保期)以降旅籠と質屋を兼業し、田畑の集積も進め、その富を背景に代々問屋や年寄などの宿役人を勤めた。岡部宿でも屈指の名家だった。
延べ床面積約331㎡:約100坪。柏屋は文政と天保の2回、岡部宿の大火で焼失しているが、当時の『類焼見舞覚』や『諸入用之覚』等の資料によれば、天保6年1835に「棟上げ」をしているので、江戸時代後期の建物であることが分かった。
○岡部宿内野本陣跡(岡部831)、岡部宿公園、
本陣とは江戸時代に大名や旗本。幕府の役人等が使用した格式の高い宿泊施設のことで、内野家は元禄年間1688~1703に本陣職を命ぜられてから明治時代に宿場の制度が廃止になるまでの約180年間、代々本陣職を継いだ。当時の建物は残っていないが、敷地はそのまま残されていて、昭和48年には市指定史跡となった。
この内野本陣は現在、当時の建物間取りを平面表示し、歴史文化や街道のたたずまいを感じられるよう門塀をイメージ再現した「岡部宿内野本陣史跡広場」として整備されている。
・赤鳥居2
・石祠
・手洗石
・祠
・問屋場跡:
幕府専用旅行者のためにつくられた施設で、人夫や馬を常備し、次の宿場まで、旅行者や荷物を無料で継ぎ送りした。しかし公用の仕事がないときは一般旅行者や荷物を有料で送った。岡部宿には岡部本町と加宿内谷の2か所にあった。
・専念寺(岡部841)
○佐護神社:おしゃもっつぁん(内谷259⁻1):
例祭日:1月中旬日曜日、立石神社例祭:7月第3または第4土、日曜日。『岡部史談 岡部のお宮さん』より。
立石神社例祭の御神輿の御旅所(御仮屋)の守護として古来より祀られる。おしゃもっつぁんは、農耕の神、丈量(測量)の神または安産の神であったりと、様々な説がある。現社殿は昭和50年1975に神神社より拝領し、移設された。3つに仕切られた内陣の中央には、天照皇大神、向かって右が佐護神社、左が小坂で祀る秋葉さんである。
・立石神社御仮屋
・新:奉燈2
・板碑:?歌碑
・石塔:昭和六年四月竣工
・石塔:天皇在位六十周年 昭和六十一年
・25m離れた道端:石仏
・彩適空間 新緑と橘の里:田園空間整備事業 駿河岡部地区
静岡県では、農村の持つ豊かな自然、農業伝統文化等を見直し、美しい農村景観や伝統的な農業施設などを保全、復元し、この地域をまるごと「田園空間博物館」としえt、魅力ある空間に整備している。事業区域は藤枝市岡部町地域と葉梨西北地域、静岡市の宇津ノ谷地域を対象とした2市にまたがる広域的な博物館である。
沿道のみかん園、里山の自然と調和した農村生活、志太平野に広がる駿河岡部の田園 が持つ原風景を展示することにより、訪れた人や地元住民が田園の風景を楽しみながら、農業、農村に対する理解を深めることのできる遊歩道として整備された。
○正應院(内谷264₋2)
宗旨:日蓮宗総本山身延山久遠寺
名称:山号:見珠山けんじゅざん、寺号:正應院しょうおういん、
宗祖:日蓮大聖人(朝日合掌立像)
本尊:久遠本師釈迦牟尼佛(一塔両尊)
題目:南無妙法蓮華経
経典:妙法蓮華経(法華経)
教義:釈迦の説かれた最高の教えである法華経を拠り所にする。この法華経を身をもって読まれ布教された日蓮聖人を宗祖と仰ぐ。法華経の魂を題目に込められた宗祖に導かれて私たちが信心修行に励み、この教えを広めることにより、世界の平和と人類の幸福、ひいては個人の幸せにつながる教えである。
開基:大正7年佐藤政十氏が曹洞宗から日蓮宗に改宗、自宅土蔵に見珠道場開設、私財を投じて現地に本堂建立を発願する。大正13年池田本覚寺第48世身延山第81世杉田日布上人に就いて出家得度、政蔭と改名、正蔭院日勇と称す。大正15年7月1日51歳をもって遷化。
開山:大正12年佐藤敏郎氏は東京久ヶ原安詳寺第18世小島龍成上人に就いて出家得度、龍秀と改名、正應院日龍と称す。昭和14年当山住職に任命。昭和41年11月24日59歳をもって遷化。
仮本堂:昭和6年佐藤家住宅をもって当地に仮本堂、現在の客殿を建立。宗祖650遠忌法要を威大に厳修す。
寺号公称:昭和15年伊豆韮山本山本立寺塔頭正應院(永正三年1506 江川英成建立)を当地に移転、同時に宝暦11年1761建立、駿遠六庚申岡部堂(妙法勇進結社を合併する。)
第三世:昭和36年 佐藤矩夫氏は正應院開山上人に就いて出家得度、龍導と改名、正應院日曠と称す。昭和42年当山住職に任命。
本堂:昭和44年当山檀信徒の永年の願望であった本堂は開基上人発願以来50年目宮大工松浦喜和蔵、茂治氏親子により3年を費やし建立。
多寶塔:昭和54年当山開基政蔭院日勇上人第50回忌の砌、篤信家の佐藤義人氏の発願
により宮大工松浦茂治氏によって7年間を費やし造られた。和様素木造り、後松浦氏は静岡県名工に推挙される。
山門:昭和57年 当山開基政蔭院日勇上人の生家 佐藤家の先祖供養のため篤信家の佐藤久和子老女の発願により宮大工松浦茂治氏によって造られた総欅唐様四脚門造り、同時に二十間築地白塀も造られた。
庫裏:平成15年 立教開宗750年慶讃記念に合わせて当山開山85周年報恩事業として建立落成する。同時に歴代廟、永代供養廟、境内整備等の事業を完了し現在に至る。
寺宝:御曼荼羅―伝 宗祖日蓮聖人御本尊2幅、身延山歴代御本尊10余幅、
仏像―釈迦立像、十一面観音、薬師如来、不動明王、兜仏外、
書画―酒井包一 1幅外、文人書画等多数を護持、
行事:毎月朔日 威運祈願祭、1月1日元朝祝祷会、3月1日御守護神祭、特別祈祷会、7月1日御開山会、8月1日御施餓鬼会、11月1日御会式、
西國三十三観音:
多宝塔:開基、政薩院日勇の50回忌記念に篤信家の発願により作られた。和様素木造里で、建築に7年間を費やした立派なものだ。
忠霊塔:
内谷児童遊園地:
・供養塔:ひげ題目:日曠○
・新:石燈籠2
・燈籠:庭:高70㎝
・丸石
・燈籠:庭:高1.5m
・祠:狛犬2
・石仏3
・石塔?
・青面金剛童子
・石塔?
・新:燈籠
・新:地蔵2
・新:観音
・新:層塔:七重塔
・五輪塔?
○山辺の道:やまのべのみち:神神社~正應院 約90分、
岡部地区三輪、本郷、山東を廻る豊かな自然と歴史資源の豊富な散歩道で、道の脇に植えられた花や手入れの行き届いた垣、お地蔵さんにかかる頭巾、現在も使用されている常夜燈など、農村の文化や住民の郷土に対するやさしさを感じることができる場所が随所にみられる。
山辺の道は神神社から高草山の麓を通り、内谷を経て正応院にまたがるコース。奈良盆地の東、三輪山の麓を廻る「山の辺の道」になぞらえて選定した。文化財として価値のある寺院、花木やみかん畑等を見ながらハイキングが楽しめる。道筋の民家、古の面影を残す常夜燈が心の中の郷愁を呼び覚ます。
・水車小屋跡
昭和20年代までは水車小屋が存在していた三輪川。その跡地には洗い場や石積み水路などが残り、伝統的な農村景観を現在に伝える。
・大滝延命地蔵
皮膚病や目の病が治るという地蔵。
・大滝おたき(王滝)
昔、修験者が修業する場所として知られていた。
・時石
正午を知らせる石。
・潮見平
汐見平、白帆見平、シラミ平等いろいろな呼び名がある。
・雲谷
神神社では高草山を御神体としていた頃があり、「霧が停滞すると雲谷に神がおわす」という神事の名残。
・金苞園
三輪地区の温州みかん類栽培技術の普及に努めた大塚熊太郎氏は優れたみかん産地との評価に喜び、自園の一角に石碑を建て園地を金苞園と名付けた。
・「いやんばいです」:「良いお日和でございます」という意味で、天気の良い日のあいさつ。
・ふるさとみかん山
傾斜地のみかん畑を使い、伝統的なみかんの栽培技術などを展示保存し、楽しむことができる憩いの空間である。
・池の平
万葉集:えごの木、大杉、湧水池:標高350m、富士見峠、振り返り坂、戦没者慰霊碑、高草山大権現、高草山:標高501m、
○雨宮大神宮、岡部西宮神社(内谷172)おいべっさん
祭神:西宮大神(事代主命)、大国主大神、
創建:江戸時代、明和年間1764~1771と伝わる。本社は兵庫県西宮市の西宮大神社。明治12年1879には本社より祭礼、神事の覚書が出され、今でも保存、伝承されている。宮仕え、宮守は、代々榊原家で継承されている。先祖の長次郎、長太夫、亀太郎、金作の各故人が神社を支えてきた。現在は榊原福一氏である。神社と共においべっさんと呼ばれ親しまれている。商売繁盛、家内安全にとても御利益がある。例祭日:11月19日宵祭、11月20日本祭、『岡部史談 岡部のお宮さん』より
○柳沢稲荷神社:
祭神:うかのみたまのみこと宇迦之御魂命、
寛政八1796年、凶作による生活苦に喘ぐ地元民を救う思いで祀られた。最初は字小柳にあったが、明治15年1882に村社になった。大正15年1926杉山氏から土地の奉納を受け現在地に移転遷座した。杉山氏から奉納された伊豆の長八のこて絵は、町民センターおかべに保管されている。
お稲荷さんの孕石(ハラミイシ)
昔、内谷村上之町に久七、はるという仲睦まじい農民夫婦が住んでいた。子供ができないのを悲しみ、神仏に日夜祈ったが、願いは叶えられなかった。途方に暮れていたある夜、久七の夢枕にお稲荷さんが立った。本堂の傍らにある石を抱いて拝めば、願望成就するというお告げに喜んだ久七は早速にお稲荷さんへ出かけた。やがて夫婦に玉のような男の赤ちゃんが授かった。お稲荷さんはその後も近隣の悩める夫婦の願いを叶え続けたと云う。
「境内の由緒書」より。例祭日:3月第2日曜日、
○小野小町の姿見の橋(内谷160)、旧岡部宿の東海道
小野小町は絶世の美人で歌人としても有名だった。晩年に東国へ下る途中、この岡部宿に泊まったという。小町はこの橋の上に立ち止まり、夕日に映える西山の景色の美しさに見とれていたが、ふと目を橋の下の水面に移すと、そこには長旅で疲れ果てた自分の姿が映っていた。そして過ぎし昔の面影をうしなってしまった老いの身を嘆き悲しんだという。宿場の人はこの橋を「小野小町の姿見の橋」と名付けたという。
・20m東:石祠
○光泰寺(内谷424)
・木喰仏 准胝観音じゅんていかんのん菩薩立像:
像高214.5㎝、完成:寛政12年7月
准胝観音は無数の諸菩薩の母であり、延命の利益がある。2mを越す大きな身体一面に虫食い跡があり、かなり傷んでいるが堂々とした姿をしており、ぼってりした肉体をくねくねした曲線で表現された衣が包んでいる。木喰上人は寛政12年1800の6月13日より8月13にちまでまるまる2か月岡部に滞在し附近の寺々に仏像を奉斎した。このうち岡部には光泰寺2体、桂島梅林院2体、三輪十輪寺2体の計6体がある。市指定文化財。
*胝:チ、タコ、
・木喰仏 聖徳太子立像
像高111.0㎝、完成:寛政12年7月5日、この像は木喰仏の発見者民芸運動の故柳宗悦が「中期の作として蓋し最も傑出せるものの一体であろう。そうして日本に数ある太子像の中で、忘れがたいもののひとつである。」と絶賛した。静かに合掌し、瞑想するその顔は私たちに安らぎと親しみを感じさせてくれる。製作者である木喰上人は45歳の時1762木喰戒を受けるとともに日本回国の願を発し、93歳1810で没するまで休むことなく日本全国を歩き続けた。そして足をとめたほとんどの土地に仏像を残した。市指定文化財。
・○庚申 寛政□年
・馬頭:明治廿六年
・馬頭:安政五年
・祠:地蔵1、観音1、石塔1:寺門前
・献燈2:昭和三十二年
・忠魂碑
・狛犬2:昭和三十年
・奉献燈2:昭和三十年
・新:観音
・西國三十三観世音菩薩:大きい、立派、見事
・石燈籠:奉納薬師如来 享和三
・鐘楼
・石室:石仏3:地蔵1、他2
・善光寺供養塔
・薬師堂
・西國供養塔2
・石燈:寛政十一
・奉献西國三十三所
・墓石
・庚申供養(羊良)塔
・庚申供養塔
・奉納大乗~~
・三界萬霊供養(羊良) 寛政十一
・三界萬霊塔
・新:石燈籠2
・六地蔵
・不許葷酒入山門
・角柱2:高70㎝
・板碑:岡部町町会議員~~
・新:手洗石
・七面堂(内谷650)、五智如来、公園
・丸山神社(内谷山東1890⁻1)
○常昌院(内谷山東1967)
・兵隊人形:本堂内: 兵隊寺とも呼ばれ、旧志太郡下から日露戦争に出征して戦死された勇士英霊223体が当時の軍服姿で、生前在りし日そのままの姿の木像として祀られる。
・石塔:□□□十五番□□□
・石塔:□之(?塩堰)建立□□凡申憂
・供養塔:□□一国三十三所 嘉永五
・地蔵?
・供養塔:南無阿弥陀佛
○南陽寺(内谷本郷2170)
・説明版:宗派:曹洞宗、岡部町光泰寺末寺、本尊:延命地蔵菩薩、脇仏:如意輪観世音菩薩、開創:天正十七、八年1589~90頃、草創開山:茂山谷栄和尚もさんこくえい、改宗開山:大翁恵最和尚だいおうえさい、 開基:不詳、 由緒:戦国時代末、天正17年1589頃茂山谷栄によって真言宗寺院として開創された。茂山は南陽寺を建立し間もなく文禄3年1594に亡くなった。その後、寺は無住状態が続き廃寺同然となった。光泰寺2世の大翁恵最が、この寺に隠居して堂を再建し、曹洞宗の寺に改め光泰寺末寺とした。大翁は地蔵菩薩を厚く信仰していたので、延命地蔵菩薩本尊とし、諏訪明神を寺の守護神として祀り南陽寺の最高に努めた。大翁は寛永11年1635に亡くなった。嘉永6年1850には冨山和尚が雨乞いの御面を諏訪神社に奉納した。また線刻不動明王を山上に祀り村人の信仰を集めた。明治維新後、平野佐助等は20数名だった檀信徒を増やし、寺の経済的基盤を確かなものにし、明治34年1901老朽化した本堂を新築(現在)した。南陽寺は開祖がなくなった後、長い間本寺光泰寺住職による兼務が続いた。そして明治41年1908三輪十輪寺柴田実雄の弟子水谷貫禅を迎え法地寺院となった。
*諏訪神社は、大正7年に立石神社内に合祀された。
線刻不動明王は、大正末頃境内の現在地に移された、
雨乞いの御面(雨龍さん)は、今も雨乞いのときに梅花流御詠歌により祈願されている。
・新:六地蔵
・水子地蔵:
・堂:線刻不動明王、
・(梵字)庚申 昭和五十五年二月吉日建 講中
・供養塔2、
・地蔵
・立石神社(内谷本郷2248)
○多福寺(内谷本郷2360)
・寺名碑:明照山多福寺 昭和四十七年
・三界萬霊塔
・供養塔か観音?
・六地蔵
・一國順礼供養塔
・地蔵
・石塔
・南無阿弥陀佛
○ふるさとみかん山(内谷本郷)
・「家康手植の蜜柑」(静岡県指定天然記念物)の穂木を接木した小みかんの木
徳川家康が大御所として駿府城に住んでいた頃、紀州藩(和歌山県)から鉢植えみかんが献上された。家康は、このみかんを自ら、駿府城本丸に移植したと伝わる。静岡県指定天然記念物「家康手植の蜜柑」は今も駿府城公園内にあるが、このたびその穂木を接木したものを園内に移植した。このみかんは現在皆が食べている温州みかんとは違う「小みかん」という種類で、香りと酸味が強く、種が多いという特徴がある。
・静岡県産温州みかん発祥の地:岡部
古くから武家等の上流階級に珍重されたみかんだが、静岡県で栽培が本格化したのは、温州みかんの栽培が始まった江戸末期以降のことである。温州みかんは現在日本で最も普及している甘くて食べやすい種類で、県内では文化年間1804~1817に現在の藤枝市岡部地区三輪に植えられたのがはじめと伝わる。明治19年当時の志太郡長:松田寅卯氏の尽力により、みかんの栽培は広まっていき藤枝、岡部は県下でも有数のみかん産地となった。
(出展:志太郡誌、静岡県蜜柑小史)
○和田の地蔵さん(内谷本郷)
ふるさとみかん山の北隣にある
昔この場所は寺に通じる参道ではないかと云われる。馬頭観世音:天正六1578年、無縁法要塔:元禄四1691年、六地蔵菩薩等が立ち並び、地域の人々は地名から「和田の地蔵さん」と呼ぶ。馬頭観音が祀られていることから、農耕や荷物の運搬に使われた馬や牛等が、葬られ供養された場所であったと云われる。毎年8月23日に地域内の地蔵菩薩と一緒に供養されている。
・石塔:数基
・地蔵:数基
・馬頭観音:数基
・供養塔:「無縁法界 」数基
・石塔:破片いくつか
○興福寺、薬師如来(三輪471)
・薬師如来立像:市指定有形文化財、像高:83㎝、檜の一木造り
像高83.0㎝、製作者は聖徳太子と伝えられる。秘仏とされている。33年毎開帳時しか拝めない。容姿は○○円満で優美な○原仏(平安時代)の特徴を備えている。
皇極天皇三645年、東国に流行した疫病を平癒させるために、この地に大和の國の大神(おおみわ)神社の分霊が祀られたおり、奈良の興福寺の許可を得て祀ったと伝わる。またこの仏像は聖徳太子作と言い伝えられるが、円満で優美な容姿や作風は飛鳥仏よりも藤原仏(平安期代中、後期)の特徴をより多く供えている。尚この仏像は興福寺の秘仏として大切に伝えられ、33年毎開帳。次回は2018年予定。
・古い墓石7
・祠;観音:第廿六番、観音
・石祠
・地蔵:座
・廻國供養塔
・石塔:?庚申供養塔らしき見言聞ザルレリーフあり、
・馬頭観音
・水車小屋跡(三輪)
・子安観音:三輪
子安観音:建立:寛永7年7月17日庚午かのえうま1630、徳川三代将軍家光の時代で、当時この三輪の里に子供たちの疫病が大流行し難儀の挙句、子供を疫病から救うため、里の人々が講を作って、この観音を建立したと思われる。その後は疫病はもとより一切の難を逃れ子供も健やかに育つようになったと云われる。講中は15軒ある。例祭日:8月17日、子安観音は子宝、安産、子育てに御利益があると云われ、今でも御利益があったということでお菓子等を供えていく人がある。
・馬頭観音:三輪字後呂
一面二臂(顔が一つと腕が二本)で頭上に馬の頭をいただいた姿だ。馬は昔から農耕や運搬の手段として大切にされてきた。また馬は牧草を食べるように人の煩悩や厄災を食べつくし救済すると云われる。不幸にして道半ばで力尽きた馬の冥福を祈りねんごろに葬った。その供養碑が馬の安全息災と旅人の道中無事を念じ、馬頭観音として路べに立てられた。
○十輪寺(三輪925)宝珠山
・宗派:曹洞宗(禅宗)、道元禅師1200~1253、□山禅師1268~1323
・本山:永平寺(福井県)、総持寺(横浜市)
・本尊:延命地蔵菩薩
・開創:寛永元年1624
・開山:照山元春大和尚(林叟院9世)しょうざんげんしゅんだいおしょう
・開基:嘯山虎公和尚しょうざんここうおしょう
・由緒:当山はその昔小寺であったが、寛永元年1624嘯山虎公和尚が三輪村の人々の協力を得て伽藍を再建し、照山元春大和尚を拝請して結制安居ができる修行道場として格をあげ曹洞宗寺院として再興開創された。現在の諸伽藍は本堂:享和3年1803、書院:明治18年1885、山門:昭和24年1949、位牌堂:昭和55年、庫裏:平成14年、にそれぞれ築かれた。
・見どころ:木喰仏2体文化財、もくれん約350本、伝説:水石火石と山号、宝珠山のいわれ、
・年間行事:1月1日10時:新年祈祷会、2月3日節分豆まき、3月中旬頃木蓮祭り、8月4日10時半:施餓鬼、8月24日夜地蔵尊縁日、10月第4日曜日開山忌、
・月例行事:地蔵講毎月24日午後1時、座禅の会第2日曜朝8時、写経の会第4日曜午後3時、
・子安地蔵菩薩立像:像高138.0㎝、寛政12年7月12日完成、市指定彫刻。
この像は比較的大きく堂々としており、微笑した顔は心休まるもので静岡県下の木喰仏の中で傑作のひとつに数えられる。
比較的大きく堂々としたものである。顔の微笑も心休まる表情をしており、静岡県下の木喰仏の中で傑作のひとつに数えられるものである。製作者の木喰上人は45歳の時1762木喰戒を受けるとともに日本回国の願を発し、93歳1810で没するまで休むことなく日本全国を歩き続けた。そして足をとめたほとんどの土地に仏像を残している。
・虚空蔵菩薩立像:像高113.0㎝、寛政12年7月11日完成、市指定彫刻。
どこかしら遠くを見る目、笑みを浮かべた顔には底知れない知恵が秘められる。
木喰仏の晩年のものはいずれも微笑しており、どれも似ているがよく見るとみな違う。この虚空蔵菩薩は若い女性の表情をしている。どこかしら遠くを見る目、微笑みを浮かべた顔には底知れない知恵が秘められている。木喰上人は寛政12年1800の6月13日までまる2か月間岡部に滞在し附近の寺々に仏像を奉斎した。このうち岡部には十輪寺2体、内谷光泰寺2体、桂島梅林院2体の6体がある。
・沙羅樹:ナツツバキ:釈迦が涅槃に入るとき(逝去)四方の8本の内4本が悲しみで枯れたという聖樹。日本ではナツツバキを沙羅と呼ぶ。この木は伊豆修善寺の実から育てたものである。
・水琴窟:少しずつ水を流すと妙音が地中より響く。
・仏足石:釈迦の足跡を石に刻んだもの。古代インドでは仏像が作られる前の古い時代から仏足石を敬い礼拝する風習があった。日本では天平勝宝五年753に奈良の薬師寺に安置されているものが最初のものである。
・石塔
・石燈籠2
・石段
・古:墓石多数
・観音
・六地蔵
・古:墓石:宝篋印塔、五輪塔:多数
・地蔵
・観音3
・山門:周辺は前庭で自然石多数配置
○金毘羅神社(三輪925)
藤枝市岡部町三輪字佐護神ヶ谷(さごじがや)879番地 、祭神:おおものぬしのみこと大物主命、例祭日:10月10日近辺の日祭日、
創祀:文化七1810年、祭神が安置され文政九1826年に大畑仁氏の先祖により、大祭が催されたと記録にある。明治35年1902に大畑博俊氏の先祖から土地の譲渡を受け現在地に鎮座した。ここは三輪の集落のほぼ真ん中の高台(標高56.5m)にあり、駿河湾、志太平野、南アルプスが望める。地元では「こんぴらさん」と呼ばれ親しまれてきた。毎年行事は講中の上組、中組、五軒屋組、桐川組が交代で執り行い、10月には例祭を行う。前夜祭には太鼓を打ち鳴らし、翌日の例祭を集落全体に知らせたと云う。当日は赤飯(しょうゆ飯)の三角むすびが献じられ、講中の参列者や子供たちがこれをいただいたという素朴な祭りだった。岡部史談第2集「岡部のお宮さん」より
・常夜燈
○神神社みわじんじゃ(三輪1288)
祭神:おおもののぬしのおおかみ大物主大神(大国主神の和魂ニギタマ)、相殿 天照皇大神・葛城一言主神、 例祭:10月19日、 創祀:皇極天皇3年644,4月中も卯の日、
由緒:皇極天皇の御代東国に疫病が蔓延して人民が苦しみあえいだとき、先の崇神天皇の御代の吉例に倣って大和國三輪山大物主神を意富多多根古命おおたたねこのみこと26代の子孫三輪四位を神主としてこの地に祀り、大難を救ったのがこの神社創祀の由来である。
文徳天皇仁寿元年851正六位上の位を賜ってより順次叙位を重ねて、伏見天皇正応六年1293正一位を賜る。明治6年3月22日郷社に列せられた。当神社は古来本殿がなく、三ツ鳥居の奥が古代の斎庭(まつりのにわ)であった。今でも例祭等主な祭りには、お山に五対の御幣を立て、本殿と同じ神饌を上げて祀る古代祭祀の姿を残している。(藤枝市岡部町民俗無形文化財)、
特殊神饌:例祭:白おこわを献ずる、端午の節句:6月5日、茅巻(ちまき)を献ずる、
特殊建造物:三ツ鳥居(三輪鳥居)
本殿:文化八年十月、拝殿:昭和6年10月、明神鳥居:文政九年十月奉建、
山宮祭
本殿三輪鳥居奥の岩頂は、本殿ができる前、古来の○庭だ。今でも例祭など主な祭りには、お山に五対の御弊を立て、本殿と同じ神幟を揚げて祀る古代祭祀の姿を残す。
・山の神祭り
神神社飛び地境内地
2月8日、飛び地境内である高草山の中腹にある、古代そのままの「山の神の磐座」で行われる。
・三ツ鳥居
現在では大神(おおみわ)神社とここ神神社にしかない、珍しい形の鳥居。神と人の世界を区切る鳥居で、くぐって入ってはいけない、とされている。
・神神社の森:緑の森は神々の衣、静岡県ふるさとの森百選、御遷座皇極天皇三年644、
延喜式内神神社、
・笹百合:科属:ユリ科ユリ属の多年草、分布:日本にだけ自生し、本州中部地方以西から四国、九州地方に分布する。
大三輪の神様と笹百合 ~古事記「左韋と云ひき」さい~
古事記によると、三輪山から流れている狭井川のほとりに笹百合がたくさん咲いており、大三輪の神様にお仕えしていたイスケヨリ姫は、6人の御供たちを連れて笹百合をつんでいた。そこへおいでになった神武天皇は、その清楚な美しい姿の姫に一目で見初められて皇后になった。日本国第一代の皇后は笹百合が御縁で誕生した。そのため大神神社では笹百合を御神花として守り育てている。神神社でもこの吉事にならって笹百合の栽培を行っている、5月下旬から6月にかけて清楚な花を開く。
・杉之坊社:参拝所:
祭神:ひぎたかひこのかみ霊木高比古神、ひぎたかひめのかみ霊木高比賣神、
例祭:1月7日
特殊神饌:三角のおこわのおむすびを「かくれみの」の葉にくるんでお供えする。
由緒:森の鎮めの神として社殿はもたず、御神木を中心に祀られてきたが、明治34年長い間難病に苦しんできた伊久美村(現:島田市伊久美)の福井伊太郎氏が快気の御礼に小型の社殿を奉建した。現在の社殿はその曽孫にあたる高橋金子氏が平成改元を記念して奉建した。神神社の荒魂の神として、霊験あらたかな御神徳は病気、怪我、災難除けの神様として古来より厚く信仰されている。
・石鳥居・昭和五十四年
・新:石燈籠2
・忠魂碑
・石うさぎ2
・石御神燈1:天明九
・石橋
・石神燈:~~陸軍歩兵~~
・かみなり井戸(三輪1288)
昔この神神社の森にかみなりが落ちたことがあった。神はたいへん怒って、そのかみなりを捕まえて、井戸に閉じ込めて蓋をした。かみなりは「もう二度とここには堕ちませんから、どうk許してください。」といって泣いて誤った。神もさすがに可哀想になって助けてやった。雷はたいそう喜んで天に上っていった。それからはこの森は一度も雷が落ちたことがないと伝わる。宮司。
・田明神(三輪1288)
田明神は元は神ミワ神社の南方約100mの田の中の小さな祠に祀ってあったが、昭和60年1985に境内の神域に遷座した。しかし例祭は元の小さな祠跡に降神して行う。例祭は1月11日朝、日の出前に東に向けて設けられた祭壇に焼餅、干し柿を献じる。祭を終えて参列者はこれをいただいてたき火に当りながら食べる。農家ではやはり1月11日に「春田打ち」と称して一鍬起こして立てた萱の穂の根元に小さなお供え餅などを上げて祀る。農作業の行為を模倣的に演じ、実際の農耕の成就を祈念する。この地域では古くから男子の行事とされている。岡部史談第2集「岡部のお宮さん」より
~藤枝市横内~
・慈眼寺(藤枝市横内179)
・白髭神社(横内208⁻8)
・貴船神社(藤枝市旧岡部町内谷783⁻1)
・鳥居(横内51⁻1)
・石仏(横内51⁻1)
・看板、石仏(横内1-4)
・横内橋(横内1-4)
・石仏(仮宿1012)
横内橋袂。
~~~~~~
~焼津市~
○智勝神社(焼津市策牛398)
・石鳥居
・手洗石
・献燈2
・石段
・板碑
○薬師堂(焼津市策牛436)策牛集会所
・説明版:現在の建物は昭和2年村人によって建てられたもので、近年改修された。この地より西方1㎞の原の山(犬頭塚)に満願寺という寺があり、戦国中期に戦火により焼失したおり、寺の一部を移築したお堂の後に建てられたものと伝わる。本尊は薬師如来で左手に薬壺宝珠を持つ姿をしている。また十二神将を従えているが、顔面を削り取られており、時代的な謎とされる。地元の人には耳薬師として信仰され耳の不自由になった人が願をかけ、治癒したときに穴の開いた石をお果たし(御礼)に供え、今でもその石が多く残っている。このお堂の裏手には明治の始めに廃寺になった寶善寺があり、尼僧が住持していた。地元ではこの辺りを寺屋敷という。
*私見:耳の病気を治すという薬師如来の顔面が削られているのは、昔は病気を治す際、仏像の一部を削って服用すると効果があると云われたためかもしれない。耳の病気なので耳附近の顔面が削られたのかもしれない。
・おくまの石(策牛)
石には霊力が潜むと信じられ、巨石は信仰の対象とされ、当地区には「ぼたもち石」「むじな石」等があり、この「おくまの石」もそのひとつである。女性の裁縫の御守りとして、カナ糸等を奉納した。
○神龍山 長福寺(関方412)曹洞宗
・地蔵:祠、地蔵、第丗ニ番
この地蔵は元は裏の寺山山頂:104mに安置されていた。田中城の殿が検地で岡部方面より見回りに来て関方に差し掛かると急に馬が棹立ちになって暴れ、殿はスッテンコロリと落馬するという事故があった。易者に伺ったところ地蔵を山頂から降ろして読経の聞こえる所に安置するよう告げられ、現在地に祀った。地蔵の顔にイボが治った跡があると云われ、台座周りの丸石(経文石)を早朝に借りてイボをそっとなでると治ると参詣人に云われていた。縁日は8月18日で戦前は夜店が数店出てにぎわった。現在も祭りは続いている。
・経塚石
碑文:圓通懺摩法一座 奉書寫一字一禮 寶筐印陀羅尼三辺
大般若経一巻大悲神梵消神梵 大乗妙典経一般若心経佛陀
百楞厳神梵一巻大施餓鬼光明無
明和ニ乙西歳1765八月晦日回向供養 願主 義目 謹書
石数八万七千施主男女等
・供養塔
・六地蔵+1、地蔵
・地蔵、・石塔、・観音3、
・石燈籠、・手洗石
・石祠
・葷酒不入山門
・石塔
○猪之谷大明神(関方15)
・六鈴鐘出土古墳:市指定有形文化財、直径13.8㎝、厚さ0.55㎝、古墳時代後期のものと推定される。日本の古代社会においては、鏡は姿見としてではなく、呪術的な道具として考えられている。鈴についても呪術的な道具として考えられている。鈴についても呪術具祭器として使用されている。こうした祭儀用の鏡と鈴を一緒にしたのが鈴鏡で、日本特有の鏡である。この鏡はほとんど完全品で、形式のみごとなものである。内区は内行五花文を中心とし、重圏文と櫛歯文を交互に二重にまわらせている。6個の鈴が付き内2個が半面欠損しているのみで、まことに貴重な珍品である。
・ナギ:市指定天然記念物、目通り2.25m、根回り2.6m、樹高16m、枝張り5m、神社拝殿前にある雅樹で樹勢は旺盛である。ナギはマキ科の常緑高木で元来亜熱帯性植物であり、わが国では、暖地に自生する。葉脈が平行であるため、せんまいさばきともいう。
・石鳥居
・新:狛犬2
・新:手洗石
・手洗石
・石燈籠
・石室:祠:古墳前
・石段
・山の神祭り(関方)
焼津市関方地区で毎年2月8日に行われる祭り。山の神を田に迎えて、その年の豊年万作を祈る神事で、祭りのもっとも原始的な形を残している。以前は前日7日に年行事当番の青年たちが「山の神の勧進(かんじ)、何でも一升十六文」と言って集落中から米や豆等を集めて回ったが、今では行っていない。しかし年行事当番は、1,2週間も前から山道普請、祭具、お供え物の調達等、ほぼ昔からのしきたりにそって準備している。前日7日には、お供え餅(古くはしとぎ)、直会(なおらい)のごちそう(赤飯、煮豆、おから等)が作られる。
8日は早朝から龍神、幟、しめ縄、御幣(4本)、御弓(2張)、御矢(6本)等が調整される。そして午前9時ころの1番鉦で村中に祭りのふれが合図され、午前10時半頃の2番鉦で祭り行列は出発する。途中「参ろう参ろう御幣(おんべ)持って参ろう。」と、大声で唱えながら山道を上っていく。
山の神の磐座(いわくら)は、高草山の標高200mばかりの所、沢の源流部にある。神前に龍神を飾り、お神酒、餅、赤飯等を供えて参拝する。参拝が済むと2張の御弓から計6本の御矢が下に向かって放たれる。山の神はこの矢に乗って里に降り田の神となる。
この行事が済むと50mほど下の拝所で直会が行われる。この直会は神と共に食事を楽しむという意味がある。
○やいづ山の手今昔案内解説
1、 高草山山頂、標高501.4m、測量三角点設置通信各社中継アンテナ設置地点。
2、 無名戦士の碑:ソロモンの碑
3、 古木一本杉、樹齢推定300年、一本杉茶園、やまざくら群生地、大島ざくら群生地、複線索道、単線テッセン発着跡地
4、 池の平(三輪地内)湧水池、貴重な飲料水、湧水井、えごの巨木あり、
5、 しらみ平(白帆見平)岡部町との尾根境行政界、
6、 策牛山の神鎮座地(五反明)、
7、 方ノ上城址 石合山(いしゃばい山)標高230m、伝承狼煙台、天文5年1535今川義元判物写、花倉の乱、
8、 幻の池出現地(池ノ窪、池ノ段)
9、 方ノ上古墳群、経塚(問)発見地石合山山頂) 古代平安朝
10、 関方山の神奥の院 例祭2月8日、(焼津市無形文化財指定)
11、 関方山の神拝所 直会場 石切場
12、 炭焼き窯跡地(小深谷)
13、 水車(米搗き場)跡地
14、 索道荷受場跡地 茶、みかん、農産物、材木
15、 おくまの石 安産、機織り信仰の拝み石
16、 高草山登山道入口石碑 きじ屋 かやのき
17、 薬師堂 耳薬師、穴明き石、庚申塚、十二神将、百万遍数珠
18、 マンボ(県道焼津岡部線に架かる道路兼水路橋)大正9~10年工事、方の上に畑生まれる
19、 智勝神社、天正12年4月創立1588郷倉跡、共同作業所跡
20、 焼津病院、犬頭塚、策牛関方用水水門
21、 水田みかん転作地跡(昭和44年完工)
22、 清水遺跡(弥生時代)
23、 青雲寺跡
24、 奥屋敷古墳群
25、 長福寺 1660年 林叟院13世創建、本堂建立 安政7年1861 いぼ地蔵 経塚石 坂本 松雲寺より長福寺学校日新舎(明治8年~13年生徒50名)
26、 猪の谷神社、興国5年1334,4月建立、古墳時代後期人穴さん、市天然記念物、ナギの木、市文化財、六鈴鏡、
27、 高草山登山道入口石碑、山の手口2000年記念建立、関方茶工場跡(共同作業所跡)昭和20年~平成2年解散
28、 山の手会館 昭和48年新築
29、 河心改修の碑、朝比奈川改修、昭和3年建立、
30、 蝋梅の里、梅の木街道、老人クラブ管理、山の手クリニック、永田デイサービスセンター、
31、 バクダン淵伝承版:昭和20年5月19日投下、朝比奈川堤中里用水堰管理棟太平洋バクダン淵跡、
32、 ハチガシリ流水橋跡
33、 山の手桜堤、さくらまつり、2月第3または第4日曜日、東海道自転車道、
34、 朝比奈川、葉梨川、吐呂川合流点、
35、 秀水苑(老人ケアセンター)
36、 六字堤防跡、尺土管跡、策牛、関方の田園、35ha に1か所直径1尺の排水口、天保6年1835~昭和44年1969まで
37、 方の上学校日新舎:長福寺より新築に依り明治13年~19年、以後越後島尋常小学校分教室となる
38、 八王子神社:天文7年1538,9月創立、天正5年1577、
39、 方の上茶工場跡(共同作業所)
40、 法号庵、閻魔さん、侍者仏
41、 梅の木街道
42、 石切り場
43、 コミュニティーケア高草、老人福祉施設
44、 方ノ上遺跡、中世奈良時代
45、 二重堤防跡
46、 雲龍、雲渓、雨後谷間より湧き昇る雲の様子、
47、 関方、三輪埋樋切崩事件、延享3年1746、
48、 谷川(高天井川)堤跡:昭和44年土地改良により改修、
49、 太田川(新川)跡:昭和44年土地改良により改修され高草川生まれる:昭和18年学徒動員東大生により暗渠排水工事、
50、 防火用水槽:消火栓設置以前地区自衛の為設置、
隣接地:
焼津市坂本、坂本神社、林叟院、高麗福祉センター、坂本団地、藤枝市岡部町三輪、神(みわ)神社、三輪団地、
山の手地区の概況:
焼津市の西北部、藤枝市岡部町との隣接地域にあり、高草山尾根を境とし、吐呂川、朝比奈川合流点より東、朝比奈川本流の北側の地域で、東名高速焼津インターチェンジより約1㎞の所にあり、山、畑、田と自然に恵まれた地区で、現在三字合計戸数346戸人口1036人(明治24年の戸数、 方の上37戸、194人、 関方46戸、264人、 策牛34戸、227人)の昔から長い歴史と文化をもつ平和な郷である。2006年焼津市山の手未来の会創立10周年。
○方ノ上城跡(かたのかみじょう)入口
方ノ上城址 石合山(いしゃばい山)標高230m、伝承狼煙台、天文5年1535今川義元判物写、花倉の乱、
天文五1536年以前の築城で、今川氏の家督争いである花倉の乱において玄広恵□(ゲンコウエタン)方の拠点の一つであった可能性がある。
○八王子神社(方ノ上154)
○祠:地蔵、馬頭観世音(方ノ上400⁻1)、水準点
馬頭は昭和13年12月大石建立。
○法号庵(方ノ上343⁻1)
・方ノ上閻魔堂:安置:享保四1720年、当時の安置場所は現在地より北側の県道近辺の方ノ上地蔵堂に安置されていたが、県道の拡幅工事に依り現在地に移転された。
由来:赤穂浪士の敵討ちのあった元禄の世も、宝永、正徳と移り変わったある日、元吉良家のある家来が、各地流浪の末、方ノ上村の地蔵堂に堂守として住み着いたが、今まで過ごしてきた土地でも、またこの土地でも吉良家の評判が悪かった。吉良の殿様は悪くなく、自慢の殿様だと思い何とかしたいと悩んでいた。これでは吉良の殿様をはじめ、大勢の犠牲者の霊は浮かばれない、成仏できないと思い、堂守はあの世で人の生前の裁きを閻魔様にしてもらおうと考えたのが、閻魔様を作ることだった。まずはこの土地の法号庵の住職、更に地元名主へまた本寺林叟院方丈へと相談の上、江戸に上り寄附を募り立派な閻魔様を享保三年の暮れに完成させた。翌年の春、焼津湊の積問屋巻田久左衛門の船で順風に乗って運ばれ、善男善女に出迎えられて、方ノ上地蔵堂に安置された。堂守が一念発起してより5年目だった。船主巻田久左衛門は閻魔様を運んだのを慶びとして、脇立2体と鉦を寄進した。
・六地蔵
・窪なし地蔵:3
・地蔵:3
・石仏:4
・石塔:3
・五輪塔破片
・石塔
・結界石2
・祠:石塔:寺前辻にあり
○坂本神社(坂本1045⁻1)
・保存樹木:ほるとの木
・石段
・献燈2
・献燈2
・石祠:19以上多数
・手洗石
・祠
・本殿、拝殿
○林叟院(坂本1400)
市指定文化財
・経蔵:木造一重桟瓦葺、方形造り。内部は正面奥に仏壇、中央に輪蔵、格天井で4.84m
(16尺)4面である。経蔵とは一切経等の経典を納めておく蔵で20世心牛租印師が明和五1768年建造を発願し、明和八1771年に工匠石川市之丞及びその子権右衛門により上棟された。師は中央の輪蔵に一切経全6930巻を納めることを目標としたが、その一部950巻を収納できたのみと伝わる。
・鐘楼:木造入母屋造り桟瓦葺、袴腰付、二軒繁垂木ふたのきしげたるき、勾欄付こうらんつき。間口奥行共に2.83m(9.34尺)下層地貫上端かそうじぬきうわば、高さは礎石上端より丸桁がぎょう上端まで4.84mである。鐘楼は別名鐘撞堂かねつきどうとも言い、寺院の境内等で釣鐘のある堂のことを言う。この鐘楼は宝永三年1706の創建と云われてきたが、平成14年度修理の際、天保十五年1844の棟札と棟束むねづかに墨書が確認された。梵鐘を吊るすのに袴腰付形式のものはなく焼津市内では唯一つである。
・宝篋印塔:高さ約2.6m、宝篋印塔の名は「宝筐院陀羅尼」という経典を納めたことに由来する。石造塔では墓塔または供養塔として造立されたものが多い。下に基壇を置き、その上に反花座、基礎、塔身、笠の順に積み、最上部に相輪を立てている。寛政三1791年の古図に移設前の姿がえがかれているので、それ以前の建立と考えられる。
・ホルトの木:目通り3.1m、根回り4m、樹高20m、枝張り24m、で、林叟院の墓地裏にあり、樹勢は旺盛である。ホルトノキ科に属し亜熱帯原産のもので、房総半島以西の太平洋岸の暖地、特に四国、九州地方に生育するが、本県には数が少なく大木であるのは珍しい。焼津市歴史民俗資料館。
・自然石2
・角柱2
・如来
・馬頭観音2
・六地蔵+1
・祠:地蔵4
・石仏:多:地蔵、観音、墓石?
・不許葷酒入山門
・石塔2
・新:六地蔵
・歌碑&説明版石
・新:地蔵
・すぎ保存祷:大木
・山神血脈石
・石燈籠1:、2:
・石仏&石塔21:
・忠魂碑
・笛吹段古墳群(坂本)笛吹段公園
高草山中腹標高約260mに位置する。古墳時代後期の古墳で10基の横穴式石室が見つかっている。昭和58年農道の整備に伴い調査が行われ調査後はほとんど埋め戻されたが、現在2基の石室を見学できる。
・東海道標識(坂本521⁻3)
東海道とはいっても有名な東海道ではなく、東の街道を意味したと思われるが、または古代東海道の名残か? ただ焼き津辺から花沢へ行くには西に遠回りではある。
・説明版:海道には街道と垣内の2つの意味がある。やきつべのみちの海道と、東の屋敷の集落の2説がある。いづれか。
○筧沢寺(石脇上423)
・庚申供養塔
・石塔
・六地蔵
・地蔵2:立、座、
・石塔:納経寶塔
・石塔:金毘羅宮
・本堂裏に古い墓地、墓石
・新:寺名碑:曹洞宗風尾山筧澤寺入口
○高草山ハイキングコース標識説明版(石脇上528⁻1)
高草山ハイキングコース:大滝延命地蔵、正午を知らせる石「時石」、潮見平を経て高草山頂上へ、池の平遊水地、金苞園を経て戻る。駿河湾、富士山、伊豆連山、志太平野を一望する健脚向きのコース。三輪公民館~高草山山頂(潮見平コースで100分)、高草山山頂~三輪公民館(池の平コースで45分)、
・富士見峠
・鞍掛峠
○高草山
標高501.4m、農作物の宝庫であり野鳥の森としても知られる。高草山はアルカリ玄武岩から成る山で、枕状溶岩や珍しいタカラン石が見られる等地学上でも有名。大井川平野や遠くは御前崎まで眺めることができる。
・山頂:電波塔、
・祠:高草山上大神(高草権現)
○勢岩寺(石脇上600)曹洞宗 谷汲山
・弘法大師像:焼津市指定有形文化財、像高17㎝:5寸6分、内台座4㎝:1寸3分、袖張り7.5㎝:2寸5分、木喰五行上人作、小さいながらもまことに丁重に彫刻された美しい座像であり、いかにも幸福をもたらしてくれそうな微笑ましい木喰仏である。光背が常楽寺、宝積寺の物と同形式であり、台座は大日菩薩のものと同じである。製作は寛政12年1800の7月と推定される。
(背面の墨書)日本国中 木喰五行(種子)大師遍照金剛 父母安楽菩薩(花押)正作自在法門
(背面の墨書)(光明真言)(梵字)寿命日本千体(身体)ノ内 国王国中 大師遍照金剛 父母安楽 百万歳 正作 天下一自在法門 八十三才 木喰五行菩薩 (花押)
・機織り地蔵尊の由来:弘法大師の甥で、後に近江國三井寺開山になった智証大師が、円珍と呼ばれていた頃、大和國長谷寺に参詣し、一心に拝んでいると、長谷寺鎮護の神の手力雄尊が霊夢に立った。この寺の開山徳道上人が本尊を造刻したときの霊木が残っているから、この霊木で不動明王を造刻して、駿州花沢の法華寺の十二坊の一坊に納め、永く衆生を済度せよ。石脇前の泓に至れば金色の光を放ち、地蔵尊が迎えるだろう。機織りの地蔵と言い六十六番札所の二十二番と定められ、いかなる願懸も必ず利生を授けると云う。一刻も早く不動明王を刻み、駿河に下向せよ。通力自在の計らいをなさん、と言い手力雄尊は消えた。円珍は霊木で直ちに不動尊を造刻し、駿河に下った。石脇前の泓に立つと金色の光が差し、円珍を迎えた。光の消えた後、機織りの石の上には地蔵が座っていた。これぞ霊夢のお告げの通りと恭しく拝んだ。当山に本尊を納めた。この地蔵は肌身地蔵といって体内に尊像を身ごもって、子授け、安産の地蔵といわれ遠近にも比類のないものである。威徳は広大無辺いかなる難病苦難も家内安全、商売繁盛、学業成就、交通安全に至る、日々の衆生の生活を洩れることなく守り救ってくれる地蔵である。当山本尊を造刻した智証大師を金色の光を放ち迎えた地蔵を繰り返し拝んでください。
*泓=オウ、コウ、深い
・歌碑
・地蔵
・六地蔵+1
・三界萬霊塔
・石塔3
・祠
・赤鳥居、石祠
・新:十二支地蔵尊
・宝積寺(石脇下692)
・地蔵菩薩立像:木喰仏:市指定文化財:像高77㎝(2尺2寸5分)、内台座14㎝(4寸6分)、 (背面墨書)法門 増宝寿 八十三才(花押)大菩薩 木喰五行菩薩 以下不明
(背面墨書) 光明真言 (種子)正作 天一 自在法門 日本千タイノ内なり 聖朝安穏増宝寿 南無地蔵大菩薩 天下安楽興正法 寛政十二甲歳八月四日ニ成就ス 命 万 百 木喰五行 八十三才 菩薩 年 (花押)
この地蔵は左手に宝珠を持ち、右手は袂をつかんでいる。木喰仏としては珍しく、材質が桜の木である。しかもまことに慎重で、一部丸ノミが使用され、足指の爪まで掘り出されている。製作は寛政12年1800、7月と推定される。
*木喰五行上人:享保3年1718~文化7年1810、45歳の宝暦12年1762、常陸國の木喰観海上人によって木喰戒を受け、全国隈なく巡礼を行った。木喰上人は幾つかの願を持っていたが、その中でも大きな願は日本全国の神社仏閣に参拝する「日本回国」の願と、千体の仏像を彫刻してゆかりの国々寺々に供養したいという「千体仏」の願があった。この二大願を乗り越え、83歳で「日本回国」、90歳で「千体仏」の大願を果たした。木喰上人が現在の静岡県に入ったのは寛政11年1799ノ11月19日遠州の狩宿で、翌年6月13日に岡部町に入り8月13日まで2か月間滞在している。焼津市内の仏像もこの期間のものである。
・西國三十三番観世音菩薩:由来:当山石脇山寶積寺境内に安置する、これらの菩薩の尊体は今を去る180年前、人皇119代光格天皇の御代享和元年辛酉5月及び7月吉日を選んで当村並びに近郷の篤志家が先祖菩提のため、勧請建立したものである。このような33の尊体を羅列安置してある霊場は全く稀であり、その感応霊験あらたかなることは世人の良く知るところである。
・石脇山宝積寺は往古天台宗花沢法華寺寺坊の一つとして元小浜にあったが、波の為、欠損したので永禄十年、鎌倉建長寺派に属し時の庄屋原川新三郎氏が菩提の為観世音菩薩を本尊として建立、その後享和元年、近郷の寄進により西國三十三所観世音菩薩石仏尊体が安置された。しかるに昭和41年1月東名高速道路建設により本堂、墓石等移転のやむなきに至る。檀家一同一致協力5カ年の歳月を費やし以て境内の整地、本堂、庫裏の改築、墓石移転を終了、よって昭和45年3月9日落慶入仏式を挙行す。
・地蔵3
・観音
・石塔
・石塔2
・寺門前近くの参道入口に石塔あり。
○石脇浅間神社(焼津市石脇705)
・祭神:木花咲耶姫命、品陀和気命、天照大御神、・例祭日:10月10日、境内社:津島神社、・境内地477坪、
・由緒:浅間神社上り口右側に大きな岩が2つある。旗掛石または鞍掛石という。本来この2つの岩は我が国の古い信仰である神の依りつかれる磐座(いわくら)であった。この浅間神社は、延徳3年9月天下の英雄徳川家康の三河時代からの家臣であった原川新三郎氏が郷里原川村から浅間社を勧請してこの聖地の例に奉斎したものと伝えられ、明治8年2月村社に、同40年3月神饌幣帛料供進社に指定された。旧除地高2石であった。
・災害:昭和57年9月12日本県を直撃した台風18号により境内の南側階段等倒壊し多大の災害を蒙るも464名の氏子一丸となって懸命な努力を続け復旧に直進し、同年10月吉日大鳥居を再建した。
・記念碑:この神社は延徳3年5月、この地に祀られた歴史をもつが、昭和57年18号台風の強襲によって標高17mの神社境内地が大きく崩壊し、明治27年氏子の建設した拝殿等床下倒壊の危険にさらされ氏子一同苦慮していたところ、ときの区長総代等相図り浅間神社再建奉賛会を設立し昭和58年10月10日第1回総会を開催氏子一同の賛同を得て発足した。奉賛会は総会以来満2ヶ年を予定し境内高を5mに造成拡充し拝殿新築、その他諸施設等完備、昭和60年10月20日完成、落成式を挙行し、且つ氏子総代に一切の管理を移管。まことに氏子の家運並びに子孫繁栄を共に地域発展を祈願して之を建立す。
・新:石鳥居
・新:石段
・新:献燈2
・新:手洗石
・新:狛犬2
・古:石
・献燈2
・石段
・新:社名碑:
・自然石:数個
・祠:数個
○旗懸け岩(石脇下89)
・平和の碑
・この石は江戸時代、高草山周辺にたびたび狩りに来ていた徳川家康が家臣であった原川新三郎の家に立ち寄った際に、旗や鞍をかけたことからこの名がついた。また石脇という地名もこの石に由来していると云われる。
・旗掛石:当寺、岩の近くに原川新三郎氏の門前があり、家康が転化を取ってからしばしばこの辺りで鷹狩を催し、その都度原川家を訪ね、その際家康の旗を立てかけ、馬の鞍を置いたので、この名があるという。他にやきつべの小径、駒つなぎの松の名跡がある。また氏子たちで年2回大しめ飾りが行われる。
・しめ縄
岩は磐座と云われ、2つに分かれていて、おそらくその間に土師器等を割って占いをしたのだろう。古代の祭祀場といわれる。高草山の中腹にも祭祀場の磐座があり、関連があるのだろうか。
・秋葉常夜灯(石脇下875)
○石脇城跡、大日堂、八幡神社、六地蔵:説明版(石脇下906)
・石脇城跡:応仁年間1467~1469に今川義忠の妻(北側殿)の兄、伊勢新九郎長氏(後の北条早雲)が今川の客将として石脇に住まいを構えており、石脇城の築城はその後の文明年間1469~1486と推定される。北条早雲はその後、小田原城を本拠に戦国大名として世に出たので石脇城は出世の第一歩を進めた城といえる。現在曲輪跡と土塁跡が残っている。
この城は北の高崎山から南へ枝分かれする尾根の先端の標高30mの城山ジョウヤマに所在する。15世紀(室町中期頃)の駿河守護職で後の戦国大名今川氏の属城(支城)と推定され、範囲は南北約220m、東西130mと考えられる。山裾の西から南へ流れる堀川を外堀とし、山頂の第一曲輪、中腹の第二曲輪、その第二曲輪を堀切で隔てた南端の外曲輪と、附属曲輪のための土手)の痕跡が残っている。城主については記録がないが、江戸時代に編まれた地誌「駿河記」によると、文明年間1469~1486に今川義忠が伊勢新九郎盛時(後の北条早雲)を石脇に住まわせたとある。伊勢新九郎盛時は文明8年1476応仁の乱の影響で今川家の当主、上総之介義忠が遠江(御前崎市川上)の塩買坂での戦死により、次代をめぐる家督争い(内紛)が起きた際、嫡子竜王丸(後の今川上総之介氏親)を助けて活躍をした。伊勢新九郎は、この功績により富士下方一二郷(富士市城)を与えられ、延徳3年1491以後伊豆平定に乗り出し、やがて関東8か国を治めた戦国大名北条家(後北条)の基礎を築いた。
・大日堂:
・不動明王像:像高94㎝、市指定文化財、(背面の墨書)日本千タイノ内なり 正作聖朝安穏増宝寿 天一自在法門(種子)天下安楽興正法 木喰五行菩薩 八十三才 寛政十二申歳七月廿三日 本 (光明真言) 命 百 母 万 □□ (種子) 父 歳
この像は、吉祥天立像が完成した2日後にできあがった。岩座の上に踏ん張り、渦巻きとなって燃え上がる火災の中に立ち、不動の気魂を十分に表しながらも木喰仏らしい人間味が出ている。
・吉祥天立像:像高94㎝、内台座13.6㎝、市指定文化財、(背面の墨書) (種子)日本千タイノ内なり正作聖朝安穏増宝寿 天一自在法門(種子)大吉祥天女 木喰五行菩薩 天下安楽興正法 八十三才 (花押)寛政十二申歳七月廿一日ニ成就ス
吉祥天は正しくは大吉祥天女といい、福徳を司るといわれ、種々の善根を施したので美しい顔になったという。髪はふっさりと肩までかかり、親しみを感じるにこやかな童顔をしている。
*木喰五行上人と焼津:1718~1810
安永2年1773,56歳のときに日本回国と千体仏の願を起こし全国を廻り諸国に自生の仏像を奉納した。現在全国で約500体の作品が確認されている。木喰上人が当地を訪れたのは寛政12年1800上人が83歳のときで故郷である現在の山梨県へ戻る途中であった。現在焼津市には、この時造られた仏像が大日堂、勢岩寺(歴史民俗資料館で保管)、宝積寺に残っている。
・城山稲荷社:赤鳥居、祠、
・供養塔2、「奉納大乗妙典供養塔」、「庚申供養塔」
・奉献燈:竿部分
・大山祇眷属龍神神社 昭和十一年
・墓石
・六地蔵
・城山八幡宮:・石鳥居、・手洗石、・祠
・石塔:古城山全昌院址
・村はずれの細い山道
ゴロタの石道、峠を越えるとそこは隣村、昔の古道。
○八幡神社、諏訪神社(高崎409)
○鳴沢不動尊(高崎602)
○花沢城跡(高崎758)
○神明宮(吉津164)
○法華寺(花沢2)
○日本坂峠(焼津市花沢、静岡市小坂)
○須賀神社(小浜35-1)
○塩釜神社(小浜1520)
・石鳥居
○海雲寺(小浜88)
○大日堂(小浜)
○道了権現(小浜)
・砂張屋孫右衛門道標:
○虚空蔵山香集寺(浜当目)
仁王門
○弘徳院(浜当目三丁目14-7)
○那閉神社(浜当目三丁目14-13)
・鳥居(浜当目一丁目14)
○西宮神社(岡当目74⁻1)
・社名碑:供進指定村社西宮神社 昭和丗九年
・石鳥居:昭和三十九年
・手洗石
・奉請庚申供養塔 安永五
・石塔
・石祠
・祠
・献燈2:紀元二千六百年
・狛犬2:昭和期か?
○薬師堂(中里655)
○若宮八幡宮(中里1000⁻1)
・焼津市指定文化財:・若宮八幡宮棟札(長さ152.2㎝、厚さ3.6㎝、重さ5㎏)、若宮八幡宮が寛永六年1629に第2代彦根藩主井伊直孝(1590~1659)により再建されたときの棟札である。檜の一枚板の表面に黒漆を塗り、文字の部分を彫り込み白色顔料をかけている。棟札の文字は寛永の三筆として名高い松花堂昭乗の筆である。(歴史民俗資料館で保管している。)
・若宮八幡宮の石橋:(長さ152㎝、幅159㎝)、天保六年1835に架設された石橋である。通路部分は4枚のアーチ型の板石でできており、高さ約33㎝の4本の親柱には再建年月と再建に関わった者の名前が刻まれている。
・直孝公産湯の井:伊井直孝は彦根35万石の城主で徳川譜代筆頭の大名である。現:国宝彦根城は直孝の築城である。当地若宮八幡宮は寛永六年直孝が建立した。
・歌碑:「歴史きさむ 棟札のこれり 」
詠者井伊文子は井伊家39代井伊直興氏(彦根市長)の夫人で、旧琉球王家尚昌氏の長女、女子学習院本科を卒業され、歌人佐々木信綱先生の高弟であり、歌集随筆集など多数の著書がある。このたび若宮八幡宮建立350年に当り、これを記念して表題の歌を書かれたのである。また夫人は沖縄のひめゆりの塔の憂歌「ひめゆりの 石ぶみに深う ぬかづけば 平らぎを希いなむ 乙女らの声は」の詠者でもある。
・石鳥居:大正十三年、
・石鳥居:皇紀二千六百年記念
・狛犬2:平成十年
・手洗石:平成十年
・石燈籠2:
・御神燈2:日露戦役従軍者紀念、
・御神燈1:
・手洗石:慶應四歳
・祠4
・石祠
・自然石
○糧堂院、岡当目公会堂(岡当目381⁻1)
○大徳寺(浜当目一丁目3-4)日蓮宗
・石祠3、うち1つ稲荷、鏡
・マリアナ観音(浜当目三丁目16)
’14 ’15 6月
・情報提供呼びかけ
今後、高草(三輪)街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
まだきちんと一通り調べていないので、過去に立ち寄った基礎資料にすぎないが、一応今後調べ直すということで、一旦掲載する。岡部から焼津に懸けて、高草山麓の三輪街道または高草街道と呼ばれる所の基礎資料である。
~岡部~
○つたの細道(平安時代から戦国時代の東海道)
古代中世(約700~1590年頃)の東海道。古くは「宇津の山越え」とか「蔦の下道」と呼ばれ平安時代の歌人;在原業平が『伊勢物語』にこの峠道のことを書き記してから全国的に名を知られるようになった。
*これより古い古代の東海道は「日本坂峠」越えの道で、静岡市小坂の日本坂峠登山口から焼津市花沢の法華寺前に出る道である。徒歩道ハイキングコース。
・歌碑:宇津ノ谷峠
・猫石
・つたの細道公園
・石碑:蔦の細道
○木和田川の堰堤
・国登録有形文化財:1910年豪雨によって大災害が発生した。災害防止のための砂防工事を進めた。1912年から14年以かけて造られた堰堤である。木和田川の13㎞にわたり、8基の石積み堰堤を築いた。形から兜堰堤ともいう。ちょうど蔦の細道や旧東海道藤枝市岡部側に下った所の川である。上流に向かうと石積みを見られる。
○明治のトンネル
明治、大正時代1876~1930の東海道。現在みられる「レンガのトンネル」は明治29年に照明用カンテラの失火によって新たに造り替えたもので、現在は国の有形文化財に認定されている。最初のトンネルは日本で初めて通行料を取ったトンネルなので、「銭取りトンネル」と言われた。
*他の宇津ノ谷のトンネル:
・大正のトンネル、完成は昭和初期、だいぶ坂を上り、人家の隣を通過しトンネルに至る県道である。
・昭和のトンネル、現在、国1上り線側(北側)
・平成のトンネル、現在、国1下り線側、歩道が付いている(南側)
○宇津ノ谷の旧東海道(江戸時代の東海道)
天正8年1581豊臣秀吉が小田原征伐のときに大軍を通すために開拓されたと云われている。江戸時代に入り正式な東海道として参勤交代の大名をはじめ、オランダ商館長、朝鮮通信使、琉球使節や一般の旅人が明治初期まで通行しており、当時はたいへん国際色豊かな街道としてにぎわっていた。
*私見:戦国史専門の小和田哲夫氏は江戸時代の東海道を最初に整備したのは今川義元で桶狭間に軍が向かうときは、その道を使ったのではないかと推定している。
・静岡市側からだと道の駅の東側の供養塔がある所にかつては一里塚があったと推定されている。そこから川伝いに西に向かい道の駅を通過し、現在の国1南側の小さな橋「平橋たいらはし」を渡るのが、江戸時代の東海道ルートである。ここから道は北の宇津ノ谷集落に向かうため、現在の国1を渡る。ここから先は川沿いに集落を目指すと道標や地図が頻繁にあるので分かるだろう。ちなみに平橋手前で左(南)に曲がり山に入っていくのが蔦の細道である。
・慶龍寺:十団子伝説
・賀茂神社
・お羽織屋
宇津ノ谷集落から江戸時代徒歩道東海道を上っていくと、馬頭観音や地蔵堂跡を過ぎ峠越えをすると、藤枝市に入る。その先で道は舗装された所に出て舗装路を歩く。この舗装路を逆に上ると、国1トンネルの山の上の排気口の建物に出て行き止まりであるので、下るしかない。そうすると藤枝市(旧岡部町)坂下集落に出る。
○坂下地蔵堂(藤枝市旧岡部町坂下2027)
・羅経記の碑
・鼻取り地蔵
・石仏石塔
○観音堂(廻沢2589)
○松岡神社(廻沢2718)
○十石坂観音堂(岡部1179 川原町)じっこくざか
市指定文化財。入母屋造りの瓦葺の観音堂、内陣、外陣の境の格子は非常に細かい技巧が施されている。江戸時代末期の作と思われ、観音堂内に2基の厨子が安置されている。
厨子1:中央にある厨子で、宮殿造り。屋根は入母屋造り、杮葺きコケラブキで二重垂木、妻入である。彩色が施され、江戸もやや末期の作と思われる。
厨子2:観音堂の向かって右。宝形、板葺屋根、黒漆塗りで簡素ではあるが品格の高いものだ。江戸も中期以降の作と思われる。
・河野蓀園碑文:市指定文化財。河野蓀園コウノソンエンは駿府町奉行服部久エ門貞勝が駿府地誌の編纂を山梨稲川ヤマナシトウセン(江戸時代の漢学者としてその名を知られた。)に依頼した時に、岡部の属する益頭郡を担当した人である。岡部本町に住し(屋号:河野屋)、文化12年正月18日46歳で没した。彼の墓碑は稲川の撰文と書が刻まれたものだ。その撰文の要旨は彼の資性と業績が立派だったことを顕彰したものだ。建碑については彼の友人で岡部宿駅の漢学者:杉山佐十、本間春策等の友情によって立石されたものだ。
・古:石燈籠?
・石塔?
・手洗石
・萬霊塔:文政三辰年
・新:萬霊塔
*私見:観音堂は旧東海道の県道横の10m高い山裾にある。おそらくかつては山裾が川の手前まであって東海道はこの観音堂と同じ標高まで上らないと越せなかったのだろう。そこで十石坂なのだろう。現在は土木技術の進歩で、山すそを完全に除去し平坦なので気付かないが、かつては坂道だったのだ。観音堂に上れば当時の旅人の気分が味わえるだろう。
・常夜燈、祠(岡部1140 川原町)
○笠懸松(藤枝市岡部642⁻19 牛ケ谷)
笠はあり その身はいかに なりならむ あわれはかなき 天の下かな
西行(西行ものがたりより)
平安時代末期~鎌倉時代にかけての歌僧として有名な西行が、愛弟子西住と東国へと
旅をしたときに起きた悲しい物語の舞台であり、謡曲「西行西住」にまつわる場所でもある。東下りの途中、川渡しの場で武士の揉め事に巻き込まれたとき、師である西行に暴力が振るわれたのに我慢できず、西住は相手の武士を杖で殴った。しかし西行は仏に仕える身として辱めに耐える大切さを説いた後、西住を破門した。西住は師を慕って後を追うが、岡部まで来て病に倒れ、最後に体を休めた松の木に、
「西へ行く 雨夜の月や あみだ笠 影を岡部の松に残して」
と、辞世を書き残した笠を懸け、そのまま帰らぬ人となった。
西行は、東国からの帰途に立ち寄った菴で一休みしていると、戸に古い檜笠が懸っていたよくよく見てみると、西行が破門した愛弟子西住に贈った笠だった。庵主に聞いてみると、西住が歌を書き記した笠を松の木に懸け、病気により最期を迎えたことを知り、悲しんで歌ったと伝えられている。
西住法師:岡部の里人伝云、西住は西行の弟子、西行に従って東遊す。遠州天竜川に於いて西行武人の船に乗合いて及危難。西住怒って武人に敵す。於之、西住師の勘気を蒙る。西行独歩東国に赴く。西住悲難愁絶して其師に追及んとす。自足栄々として独往、岡部里に至て病て不能行。終にこの里にて卒す。傍に一松樹あり。竹笠を掛一首の辞世を残す云々。
(「駿河國新風土記」新庄道雄より)
・宝篋印塔の一部、
○三星寺(岡部650)
・四国八十八所第三拾三番
・祠:地蔵
・新:三界萬霊菩提
・枡形跡:
曲尺手(かねんて)とも言う。本陣めがけて敵がたやすく侵入できないように宿場の出入口に設けたもので、ここは道が直角に折れ曲がっている。またここには木戸と番小屋が設けられ、木戸番が毎日木戸を明け六つに開け、暮れ六つに閉じた。
○専称寺(岡部663)
・西行座像:市指定文化財彫刻、像高50㎝、西行法師の旅姿をした座像で白木彫りの作りである。像底裏に「享保十一1726年江戸の湯島天神の西にいた柑本南浦(こうしもとなんぽ)が最林寺(川原町、文化五年焼失)に奉納」の意味の銘がある。江戸時代後期の作と思われる。岡部十石坂観音堂。
・不動尊立像:市指定文化財彫刻、像高:54㎝、一木彫り立像で忿怒の形相が力強く表現されている。鎌倉前期のものといわれる。岡部立光山不動院。
2体とも当山専称寺にて保管されている。
・六地蔵+7:計13:
○立石山不動尊(岡部795⁻5)
・馬頭:女馬 大正七年
・馬頭:大正四年
・馬頭:明治廿七年
・馬頭:女馬 大正九年
・石仏
・石祠:瓦葺
○大旅籠 柏屋(岡部817)
創設:天保7年1836、大旅籠柏屋は平成12年に東海道や旅、岡部宿を楽しく学べる歴史資料館として蘇えった。
旅籠とは江戸時代の宿泊施設。柏屋はその規模から「大旅籠柏屋」といわれ、岡部宿を代表する旅籠である。柏屋を経営していた山内家は5代目良吉(天保期)以降旅籠と質屋を兼業し、田畑の集積も進め、その富を背景に代々問屋や年寄などの宿役人を勤めた。岡部宿でも屈指の名家だった。
延べ床面積約331㎡:約100坪。柏屋は文政と天保の2回、岡部宿の大火で焼失しているが、当時の『類焼見舞覚』や『諸入用之覚』等の資料によれば、天保6年1835に「棟上げ」をしているので、江戸時代後期の建物であることが分かった。
○岡部宿内野本陣跡(岡部831)、岡部宿公園、
本陣とは江戸時代に大名や旗本。幕府の役人等が使用した格式の高い宿泊施設のことで、内野家は元禄年間1688~1703に本陣職を命ぜられてから明治時代に宿場の制度が廃止になるまでの約180年間、代々本陣職を継いだ。当時の建物は残っていないが、敷地はそのまま残されていて、昭和48年には市指定史跡となった。
この内野本陣は現在、当時の建物間取りを平面表示し、歴史文化や街道のたたずまいを感じられるよう門塀をイメージ再現した「岡部宿内野本陣史跡広場」として整備されている。
・赤鳥居2
・石祠
・手洗石
・祠
・問屋場跡:
幕府専用旅行者のためにつくられた施設で、人夫や馬を常備し、次の宿場まで、旅行者や荷物を無料で継ぎ送りした。しかし公用の仕事がないときは一般旅行者や荷物を有料で送った。岡部宿には岡部本町と加宿内谷の2か所にあった。
・専念寺(岡部841)
○佐護神社:おしゃもっつぁん(内谷259⁻1):
例祭日:1月中旬日曜日、立石神社例祭:7月第3または第4土、日曜日。『岡部史談 岡部のお宮さん』より。
立石神社例祭の御神輿の御旅所(御仮屋)の守護として古来より祀られる。おしゃもっつぁんは、農耕の神、丈量(測量)の神または安産の神であったりと、様々な説がある。現社殿は昭和50年1975に神神社より拝領し、移設された。3つに仕切られた内陣の中央には、天照皇大神、向かって右が佐護神社、左が小坂で祀る秋葉さんである。
・立石神社御仮屋
・新:奉燈2
・板碑:?歌碑
・石塔:昭和六年四月竣工
・石塔:天皇在位六十周年 昭和六十一年
・25m離れた道端:石仏
・彩適空間 新緑と橘の里:田園空間整備事業 駿河岡部地区
静岡県では、農村の持つ豊かな自然、農業伝統文化等を見直し、美しい農村景観や伝統的な農業施設などを保全、復元し、この地域をまるごと「田園空間博物館」としえt、魅力ある空間に整備している。事業区域は藤枝市岡部町地域と葉梨西北地域、静岡市の宇津ノ谷地域を対象とした2市にまたがる広域的な博物館である。
沿道のみかん園、里山の自然と調和した農村生活、志太平野に広がる駿河岡部の田園 が持つ原風景を展示することにより、訪れた人や地元住民が田園の風景を楽しみながら、農業、農村に対する理解を深めることのできる遊歩道として整備された。
○正應院(内谷264₋2)
宗旨:日蓮宗総本山身延山久遠寺
名称:山号:見珠山けんじゅざん、寺号:正應院しょうおういん、
宗祖:日蓮大聖人(朝日合掌立像)
本尊:久遠本師釈迦牟尼佛(一塔両尊)
題目:南無妙法蓮華経
経典:妙法蓮華経(法華経)
教義:釈迦の説かれた最高の教えである法華経を拠り所にする。この法華経を身をもって読まれ布教された日蓮聖人を宗祖と仰ぐ。法華経の魂を題目に込められた宗祖に導かれて私たちが信心修行に励み、この教えを広めることにより、世界の平和と人類の幸福、ひいては個人の幸せにつながる教えである。
開基:大正7年佐藤政十氏が曹洞宗から日蓮宗に改宗、自宅土蔵に見珠道場開設、私財を投じて現地に本堂建立を発願する。大正13年池田本覚寺第48世身延山第81世杉田日布上人に就いて出家得度、政蔭と改名、正蔭院日勇と称す。大正15年7月1日51歳をもって遷化。
開山:大正12年佐藤敏郎氏は東京久ヶ原安詳寺第18世小島龍成上人に就いて出家得度、龍秀と改名、正應院日龍と称す。昭和14年当山住職に任命。昭和41年11月24日59歳をもって遷化。
仮本堂:昭和6年佐藤家住宅をもって当地に仮本堂、現在の客殿を建立。宗祖650遠忌法要を威大に厳修す。
寺号公称:昭和15年伊豆韮山本山本立寺塔頭正應院(永正三年1506 江川英成建立)を当地に移転、同時に宝暦11年1761建立、駿遠六庚申岡部堂(妙法勇進結社を合併する。)
第三世:昭和36年 佐藤矩夫氏は正應院開山上人に就いて出家得度、龍導と改名、正應院日曠と称す。昭和42年当山住職に任命。
本堂:昭和44年当山檀信徒の永年の願望であった本堂は開基上人発願以来50年目宮大工松浦喜和蔵、茂治氏親子により3年を費やし建立。
多寶塔:昭和54年当山開基政蔭院日勇上人第50回忌の砌、篤信家の佐藤義人氏の発願
により宮大工松浦茂治氏によって7年間を費やし造られた。和様素木造り、後松浦氏は静岡県名工に推挙される。
山門:昭和57年 当山開基政蔭院日勇上人の生家 佐藤家の先祖供養のため篤信家の佐藤久和子老女の発願により宮大工松浦茂治氏によって造られた総欅唐様四脚門造り、同時に二十間築地白塀も造られた。
庫裏:平成15年 立教開宗750年慶讃記念に合わせて当山開山85周年報恩事業として建立落成する。同時に歴代廟、永代供養廟、境内整備等の事業を完了し現在に至る。
寺宝:御曼荼羅―伝 宗祖日蓮聖人御本尊2幅、身延山歴代御本尊10余幅、
仏像―釈迦立像、十一面観音、薬師如来、不動明王、兜仏外、
書画―酒井包一 1幅外、文人書画等多数を護持、
行事:毎月朔日 威運祈願祭、1月1日元朝祝祷会、3月1日御守護神祭、特別祈祷会、7月1日御開山会、8月1日御施餓鬼会、11月1日御会式、
西國三十三観音:
多宝塔:開基、政薩院日勇の50回忌記念に篤信家の発願により作られた。和様素木造里で、建築に7年間を費やした立派なものだ。
忠霊塔:
内谷児童遊園地:
・供養塔:ひげ題目:日曠○
・新:石燈籠2
・燈籠:庭:高70㎝
・丸石
・燈籠:庭:高1.5m
・祠:狛犬2
・石仏3
・石塔?
・青面金剛童子
・石塔?
・新:燈籠
・新:地蔵2
・新:観音
・新:層塔:七重塔
・五輪塔?
○山辺の道:やまのべのみち:神神社~正應院 約90分、
岡部地区三輪、本郷、山東を廻る豊かな自然と歴史資源の豊富な散歩道で、道の脇に植えられた花や手入れの行き届いた垣、お地蔵さんにかかる頭巾、現在も使用されている常夜燈など、農村の文化や住民の郷土に対するやさしさを感じることができる場所が随所にみられる。
山辺の道は神神社から高草山の麓を通り、内谷を経て正応院にまたがるコース。奈良盆地の東、三輪山の麓を廻る「山の辺の道」になぞらえて選定した。文化財として価値のある寺院、花木やみかん畑等を見ながらハイキングが楽しめる。道筋の民家、古の面影を残す常夜燈が心の中の郷愁を呼び覚ます。
・水車小屋跡
昭和20年代までは水車小屋が存在していた三輪川。その跡地には洗い場や石積み水路などが残り、伝統的な農村景観を現在に伝える。
・大滝延命地蔵
皮膚病や目の病が治るという地蔵。
・大滝おたき(王滝)
昔、修験者が修業する場所として知られていた。
・時石
正午を知らせる石。
・潮見平
汐見平、白帆見平、シラミ平等いろいろな呼び名がある。
・雲谷
神神社では高草山を御神体としていた頃があり、「霧が停滞すると雲谷に神がおわす」という神事の名残。
・金苞園
三輪地区の温州みかん類栽培技術の普及に努めた大塚熊太郎氏は優れたみかん産地との評価に喜び、自園の一角に石碑を建て園地を金苞園と名付けた。
・「いやんばいです」:「良いお日和でございます」という意味で、天気の良い日のあいさつ。
・ふるさとみかん山
傾斜地のみかん畑を使い、伝統的なみかんの栽培技術などを展示保存し、楽しむことができる憩いの空間である。
・池の平
万葉集:えごの木、大杉、湧水池:標高350m、富士見峠、振り返り坂、戦没者慰霊碑、高草山大権現、高草山:標高501m、
○雨宮大神宮、岡部西宮神社(内谷172)おいべっさん
祭神:西宮大神(事代主命)、大国主大神、
創建:江戸時代、明和年間1764~1771と伝わる。本社は兵庫県西宮市の西宮大神社。明治12年1879には本社より祭礼、神事の覚書が出され、今でも保存、伝承されている。宮仕え、宮守は、代々榊原家で継承されている。先祖の長次郎、長太夫、亀太郎、金作の各故人が神社を支えてきた。現在は榊原福一氏である。神社と共においべっさんと呼ばれ親しまれている。商売繁盛、家内安全にとても御利益がある。例祭日:11月19日宵祭、11月20日本祭、『岡部史談 岡部のお宮さん』より
○柳沢稲荷神社:
祭神:うかのみたまのみこと宇迦之御魂命、
寛政八1796年、凶作による生活苦に喘ぐ地元民を救う思いで祀られた。最初は字小柳にあったが、明治15年1882に村社になった。大正15年1926杉山氏から土地の奉納を受け現在地に移転遷座した。杉山氏から奉納された伊豆の長八のこて絵は、町民センターおかべに保管されている。
お稲荷さんの孕石(ハラミイシ)
昔、内谷村上之町に久七、はるという仲睦まじい農民夫婦が住んでいた。子供ができないのを悲しみ、神仏に日夜祈ったが、願いは叶えられなかった。途方に暮れていたある夜、久七の夢枕にお稲荷さんが立った。本堂の傍らにある石を抱いて拝めば、願望成就するというお告げに喜んだ久七は早速にお稲荷さんへ出かけた。やがて夫婦に玉のような男の赤ちゃんが授かった。お稲荷さんはその後も近隣の悩める夫婦の願いを叶え続けたと云う。
「境内の由緒書」より。例祭日:3月第2日曜日、
○小野小町の姿見の橋(内谷160)、旧岡部宿の東海道
小野小町は絶世の美人で歌人としても有名だった。晩年に東国へ下る途中、この岡部宿に泊まったという。小町はこの橋の上に立ち止まり、夕日に映える西山の景色の美しさに見とれていたが、ふと目を橋の下の水面に移すと、そこには長旅で疲れ果てた自分の姿が映っていた。そして過ぎし昔の面影をうしなってしまった老いの身を嘆き悲しんだという。宿場の人はこの橋を「小野小町の姿見の橋」と名付けたという。
・20m東:石祠
○光泰寺(内谷424)
・木喰仏 准胝観音じゅんていかんのん菩薩立像:
像高214.5㎝、完成:寛政12年7月
准胝観音は無数の諸菩薩の母であり、延命の利益がある。2mを越す大きな身体一面に虫食い跡があり、かなり傷んでいるが堂々とした姿をしており、ぼってりした肉体をくねくねした曲線で表現された衣が包んでいる。木喰上人は寛政12年1800の6月13日より8月13にちまでまるまる2か月岡部に滞在し附近の寺々に仏像を奉斎した。このうち岡部には光泰寺2体、桂島梅林院2体、三輪十輪寺2体の計6体がある。市指定文化財。
*胝:チ、タコ、
・木喰仏 聖徳太子立像
像高111.0㎝、完成:寛政12年7月5日、この像は木喰仏の発見者民芸運動の故柳宗悦が「中期の作として蓋し最も傑出せるものの一体であろう。そうして日本に数ある太子像の中で、忘れがたいもののひとつである。」と絶賛した。静かに合掌し、瞑想するその顔は私たちに安らぎと親しみを感じさせてくれる。製作者である木喰上人は45歳の時1762木喰戒を受けるとともに日本回国の願を発し、93歳1810で没するまで休むことなく日本全国を歩き続けた。そして足をとめたほとんどの土地に仏像を残した。市指定文化財。
・○庚申 寛政□年
・馬頭:明治廿六年
・馬頭:安政五年
・祠:地蔵1、観音1、石塔1:寺門前
・献燈2:昭和三十二年
・忠魂碑
・狛犬2:昭和三十年
・奉献燈2:昭和三十年
・新:観音
・西國三十三観世音菩薩:大きい、立派、見事
・石燈籠:奉納薬師如来 享和三
・鐘楼
・石室:石仏3:地蔵1、他2
・善光寺供養塔
・薬師堂
・西國供養塔2
・石燈:寛政十一
・奉献西國三十三所
・墓石
・庚申供養(羊良)塔
・庚申供養塔
・奉納大乗~~
・三界萬霊供養(羊良) 寛政十一
・三界萬霊塔
・新:石燈籠2
・六地蔵
・不許葷酒入山門
・角柱2:高70㎝
・板碑:岡部町町会議員~~
・新:手洗石
・七面堂(内谷650)、五智如来、公園
・丸山神社(内谷山東1890⁻1)
○常昌院(内谷山東1967)
・兵隊人形:本堂内: 兵隊寺とも呼ばれ、旧志太郡下から日露戦争に出征して戦死された勇士英霊223体が当時の軍服姿で、生前在りし日そのままの姿の木像として祀られる。
・石塔:□□□十五番□□□
・石塔:□之(?塩堰)建立□□凡申憂
・供養塔:□□一国三十三所 嘉永五
・地蔵?
・供養塔:南無阿弥陀佛
○南陽寺(内谷本郷2170)
・説明版:宗派:曹洞宗、岡部町光泰寺末寺、本尊:延命地蔵菩薩、脇仏:如意輪観世音菩薩、開創:天正十七、八年1589~90頃、草創開山:茂山谷栄和尚もさんこくえい、改宗開山:大翁恵最和尚だいおうえさい、 開基:不詳、 由緒:戦国時代末、天正17年1589頃茂山谷栄によって真言宗寺院として開創された。茂山は南陽寺を建立し間もなく文禄3年1594に亡くなった。その後、寺は無住状態が続き廃寺同然となった。光泰寺2世の大翁恵最が、この寺に隠居して堂を再建し、曹洞宗の寺に改め光泰寺末寺とした。大翁は地蔵菩薩を厚く信仰していたので、延命地蔵菩薩本尊とし、諏訪明神を寺の守護神として祀り南陽寺の最高に努めた。大翁は寛永11年1635に亡くなった。嘉永6年1850には冨山和尚が雨乞いの御面を諏訪神社に奉納した。また線刻不動明王を山上に祀り村人の信仰を集めた。明治維新後、平野佐助等は20数名だった檀信徒を増やし、寺の経済的基盤を確かなものにし、明治34年1901老朽化した本堂を新築(現在)した。南陽寺は開祖がなくなった後、長い間本寺光泰寺住職による兼務が続いた。そして明治41年1908三輪十輪寺柴田実雄の弟子水谷貫禅を迎え法地寺院となった。
*諏訪神社は、大正7年に立石神社内に合祀された。
線刻不動明王は、大正末頃境内の現在地に移された、
雨乞いの御面(雨龍さん)は、今も雨乞いのときに梅花流御詠歌により祈願されている。
・新:六地蔵
・水子地蔵:
・堂:線刻不動明王、
・(梵字)庚申 昭和五十五年二月吉日建 講中
・供養塔2、
・地蔵
・立石神社(内谷本郷2248)
○多福寺(内谷本郷2360)
・寺名碑:明照山多福寺 昭和四十七年
・三界萬霊塔
・供養塔か観音?
・六地蔵
・一國順礼供養塔
・地蔵
・石塔
・南無阿弥陀佛
○ふるさとみかん山(内谷本郷)
・「家康手植の蜜柑」(静岡県指定天然記念物)の穂木を接木した小みかんの木
徳川家康が大御所として駿府城に住んでいた頃、紀州藩(和歌山県)から鉢植えみかんが献上された。家康は、このみかんを自ら、駿府城本丸に移植したと伝わる。静岡県指定天然記念物「家康手植の蜜柑」は今も駿府城公園内にあるが、このたびその穂木を接木したものを園内に移植した。このみかんは現在皆が食べている温州みかんとは違う「小みかん」という種類で、香りと酸味が強く、種が多いという特徴がある。
・静岡県産温州みかん発祥の地:岡部
古くから武家等の上流階級に珍重されたみかんだが、静岡県で栽培が本格化したのは、温州みかんの栽培が始まった江戸末期以降のことである。温州みかんは現在日本で最も普及している甘くて食べやすい種類で、県内では文化年間1804~1817に現在の藤枝市岡部地区三輪に植えられたのがはじめと伝わる。明治19年当時の志太郡長:松田寅卯氏の尽力により、みかんの栽培は広まっていき藤枝、岡部は県下でも有数のみかん産地となった。
(出展:志太郡誌、静岡県蜜柑小史)
○和田の地蔵さん(内谷本郷)
ふるさとみかん山の北隣にある
昔この場所は寺に通じる参道ではないかと云われる。馬頭観世音:天正六1578年、無縁法要塔:元禄四1691年、六地蔵菩薩等が立ち並び、地域の人々は地名から「和田の地蔵さん」と呼ぶ。馬頭観音が祀られていることから、農耕や荷物の運搬に使われた馬や牛等が、葬られ供養された場所であったと云われる。毎年8月23日に地域内の地蔵菩薩と一緒に供養されている。
・石塔:数基
・地蔵:数基
・馬頭観音:数基
・供養塔:「無縁法界 」数基
・石塔:破片いくつか
○興福寺、薬師如来(三輪471)
・薬師如来立像:市指定有形文化財、像高:83㎝、檜の一木造り
像高83.0㎝、製作者は聖徳太子と伝えられる。秘仏とされている。33年毎開帳時しか拝めない。容姿は○○円満で優美な○原仏(平安時代)の特徴を備えている。
皇極天皇三645年、東国に流行した疫病を平癒させるために、この地に大和の國の大神(おおみわ)神社の分霊が祀られたおり、奈良の興福寺の許可を得て祀ったと伝わる。またこの仏像は聖徳太子作と言い伝えられるが、円満で優美な容姿や作風は飛鳥仏よりも藤原仏(平安期代中、後期)の特徴をより多く供えている。尚この仏像は興福寺の秘仏として大切に伝えられ、33年毎開帳。次回は2018年予定。
・古い墓石7
・祠;観音:第廿六番、観音
・石祠
・地蔵:座
・廻國供養塔
・石塔:?庚申供養塔らしき見言聞ザルレリーフあり、
・馬頭観音
・水車小屋跡(三輪)
・子安観音:三輪
子安観音:建立:寛永7年7月17日庚午かのえうま1630、徳川三代将軍家光の時代で、当時この三輪の里に子供たちの疫病が大流行し難儀の挙句、子供を疫病から救うため、里の人々が講を作って、この観音を建立したと思われる。その後は疫病はもとより一切の難を逃れ子供も健やかに育つようになったと云われる。講中は15軒ある。例祭日:8月17日、子安観音は子宝、安産、子育てに御利益があると云われ、今でも御利益があったということでお菓子等を供えていく人がある。
・馬頭観音:三輪字後呂
一面二臂(顔が一つと腕が二本)で頭上に馬の頭をいただいた姿だ。馬は昔から農耕や運搬の手段として大切にされてきた。また馬は牧草を食べるように人の煩悩や厄災を食べつくし救済すると云われる。不幸にして道半ばで力尽きた馬の冥福を祈りねんごろに葬った。その供養碑が馬の安全息災と旅人の道中無事を念じ、馬頭観音として路べに立てられた。
○十輪寺(三輪925)宝珠山
・宗派:曹洞宗(禅宗)、道元禅師1200~1253、□山禅師1268~1323
・本山:永平寺(福井県)、総持寺(横浜市)
・本尊:延命地蔵菩薩
・開創:寛永元年1624
・開山:照山元春大和尚(林叟院9世)しょうざんげんしゅんだいおしょう
・開基:嘯山虎公和尚しょうざんここうおしょう
・由緒:当山はその昔小寺であったが、寛永元年1624嘯山虎公和尚が三輪村の人々の協力を得て伽藍を再建し、照山元春大和尚を拝請して結制安居ができる修行道場として格をあげ曹洞宗寺院として再興開創された。現在の諸伽藍は本堂:享和3年1803、書院:明治18年1885、山門:昭和24年1949、位牌堂:昭和55年、庫裏:平成14年、にそれぞれ築かれた。
・見どころ:木喰仏2体文化財、もくれん約350本、伝説:水石火石と山号、宝珠山のいわれ、
・年間行事:1月1日10時:新年祈祷会、2月3日節分豆まき、3月中旬頃木蓮祭り、8月4日10時半:施餓鬼、8月24日夜地蔵尊縁日、10月第4日曜日開山忌、
・月例行事:地蔵講毎月24日午後1時、座禅の会第2日曜朝8時、写経の会第4日曜午後3時、
・子安地蔵菩薩立像:像高138.0㎝、寛政12年7月12日完成、市指定彫刻。
この像は比較的大きく堂々としており、微笑した顔は心休まるもので静岡県下の木喰仏の中で傑作のひとつに数えられる。
比較的大きく堂々としたものである。顔の微笑も心休まる表情をしており、静岡県下の木喰仏の中で傑作のひとつに数えられるものである。製作者の木喰上人は45歳の時1762木喰戒を受けるとともに日本回国の願を発し、93歳1810で没するまで休むことなく日本全国を歩き続けた。そして足をとめたほとんどの土地に仏像を残している。
・虚空蔵菩薩立像:像高113.0㎝、寛政12年7月11日完成、市指定彫刻。
どこかしら遠くを見る目、笑みを浮かべた顔には底知れない知恵が秘められる。
木喰仏の晩年のものはいずれも微笑しており、どれも似ているがよく見るとみな違う。この虚空蔵菩薩は若い女性の表情をしている。どこかしら遠くを見る目、微笑みを浮かべた顔には底知れない知恵が秘められている。木喰上人は寛政12年1800の6月13日までまる2か月間岡部に滞在し附近の寺々に仏像を奉斎した。このうち岡部には十輪寺2体、内谷光泰寺2体、桂島梅林院2体の6体がある。
・沙羅樹:ナツツバキ:釈迦が涅槃に入るとき(逝去)四方の8本の内4本が悲しみで枯れたという聖樹。日本ではナツツバキを沙羅と呼ぶ。この木は伊豆修善寺の実から育てたものである。
・水琴窟:少しずつ水を流すと妙音が地中より響く。
・仏足石:釈迦の足跡を石に刻んだもの。古代インドでは仏像が作られる前の古い時代から仏足石を敬い礼拝する風習があった。日本では天平勝宝五年753に奈良の薬師寺に安置されているものが最初のものである。
・石塔
・石燈籠2
・石段
・古:墓石多数
・観音
・六地蔵
・古:墓石:宝篋印塔、五輪塔:多数
・地蔵
・観音3
・山門:周辺は前庭で自然石多数配置
○金毘羅神社(三輪925)
藤枝市岡部町三輪字佐護神ヶ谷(さごじがや)879番地 、祭神:おおものぬしのみこと大物主命、例祭日:10月10日近辺の日祭日、
創祀:文化七1810年、祭神が安置され文政九1826年に大畑仁氏の先祖により、大祭が催されたと記録にある。明治35年1902に大畑博俊氏の先祖から土地の譲渡を受け現在地に鎮座した。ここは三輪の集落のほぼ真ん中の高台(標高56.5m)にあり、駿河湾、志太平野、南アルプスが望める。地元では「こんぴらさん」と呼ばれ親しまれてきた。毎年行事は講中の上組、中組、五軒屋組、桐川組が交代で執り行い、10月には例祭を行う。前夜祭には太鼓を打ち鳴らし、翌日の例祭を集落全体に知らせたと云う。当日は赤飯(しょうゆ飯)の三角むすびが献じられ、講中の参列者や子供たちがこれをいただいたという素朴な祭りだった。岡部史談第2集「岡部のお宮さん」より
・常夜燈
○神神社みわじんじゃ(三輪1288)
祭神:おおもののぬしのおおかみ大物主大神(大国主神の和魂ニギタマ)、相殿 天照皇大神・葛城一言主神、 例祭:10月19日、 創祀:皇極天皇3年644,4月中も卯の日、
由緒:皇極天皇の御代東国に疫病が蔓延して人民が苦しみあえいだとき、先の崇神天皇の御代の吉例に倣って大和國三輪山大物主神を意富多多根古命おおたたねこのみこと26代の子孫三輪四位を神主としてこの地に祀り、大難を救ったのがこの神社創祀の由来である。
文徳天皇仁寿元年851正六位上の位を賜ってより順次叙位を重ねて、伏見天皇正応六年1293正一位を賜る。明治6年3月22日郷社に列せられた。当神社は古来本殿がなく、三ツ鳥居の奥が古代の斎庭(まつりのにわ)であった。今でも例祭等主な祭りには、お山に五対の御幣を立て、本殿と同じ神饌を上げて祀る古代祭祀の姿を残している。(藤枝市岡部町民俗無形文化財)、
特殊神饌:例祭:白おこわを献ずる、端午の節句:6月5日、茅巻(ちまき)を献ずる、
特殊建造物:三ツ鳥居(三輪鳥居)
本殿:文化八年十月、拝殿:昭和6年10月、明神鳥居:文政九年十月奉建、
山宮祭
本殿三輪鳥居奥の岩頂は、本殿ができる前、古来の○庭だ。今でも例祭など主な祭りには、お山に五対の御弊を立て、本殿と同じ神幟を揚げて祀る古代祭祀の姿を残す。
・山の神祭り
神神社飛び地境内地
2月8日、飛び地境内である高草山の中腹にある、古代そのままの「山の神の磐座」で行われる。
・三ツ鳥居
現在では大神(おおみわ)神社とここ神神社にしかない、珍しい形の鳥居。神と人の世界を区切る鳥居で、くぐって入ってはいけない、とされている。
・神神社の森:緑の森は神々の衣、静岡県ふるさとの森百選、御遷座皇極天皇三年644、
延喜式内神神社、
・笹百合:科属:ユリ科ユリ属の多年草、分布:日本にだけ自生し、本州中部地方以西から四国、九州地方に分布する。
大三輪の神様と笹百合 ~古事記「左韋と云ひき」さい~
古事記によると、三輪山から流れている狭井川のほとりに笹百合がたくさん咲いており、大三輪の神様にお仕えしていたイスケヨリ姫は、6人の御供たちを連れて笹百合をつんでいた。そこへおいでになった神武天皇は、その清楚な美しい姿の姫に一目で見初められて皇后になった。日本国第一代の皇后は笹百合が御縁で誕生した。そのため大神神社では笹百合を御神花として守り育てている。神神社でもこの吉事にならって笹百合の栽培を行っている、5月下旬から6月にかけて清楚な花を開く。
・杉之坊社:参拝所:
祭神:ひぎたかひこのかみ霊木高比古神、ひぎたかひめのかみ霊木高比賣神、
例祭:1月7日
特殊神饌:三角のおこわのおむすびを「かくれみの」の葉にくるんでお供えする。
由緒:森の鎮めの神として社殿はもたず、御神木を中心に祀られてきたが、明治34年長い間難病に苦しんできた伊久美村(現:島田市伊久美)の福井伊太郎氏が快気の御礼に小型の社殿を奉建した。現在の社殿はその曽孫にあたる高橋金子氏が平成改元を記念して奉建した。神神社の荒魂の神として、霊験あらたかな御神徳は病気、怪我、災難除けの神様として古来より厚く信仰されている。
・石鳥居・昭和五十四年
・新:石燈籠2
・忠魂碑
・石うさぎ2
・石御神燈1:天明九
・石橋
・石神燈:~~陸軍歩兵~~
・かみなり井戸(三輪1288)
昔この神神社の森にかみなりが落ちたことがあった。神はたいへん怒って、そのかみなりを捕まえて、井戸に閉じ込めて蓋をした。かみなりは「もう二度とここには堕ちませんから、どうk許してください。」といって泣いて誤った。神もさすがに可哀想になって助けてやった。雷はたいそう喜んで天に上っていった。それからはこの森は一度も雷が落ちたことがないと伝わる。宮司。
・田明神(三輪1288)
田明神は元は神ミワ神社の南方約100mの田の中の小さな祠に祀ってあったが、昭和60年1985に境内の神域に遷座した。しかし例祭は元の小さな祠跡に降神して行う。例祭は1月11日朝、日の出前に東に向けて設けられた祭壇に焼餅、干し柿を献じる。祭を終えて参列者はこれをいただいてたき火に当りながら食べる。農家ではやはり1月11日に「春田打ち」と称して一鍬起こして立てた萱の穂の根元に小さなお供え餅などを上げて祀る。農作業の行為を模倣的に演じ、実際の農耕の成就を祈念する。この地域では古くから男子の行事とされている。岡部史談第2集「岡部のお宮さん」より
~藤枝市横内~
・慈眼寺(藤枝市横内179)
・白髭神社(横内208⁻8)
・貴船神社(藤枝市旧岡部町内谷783⁻1)
・鳥居(横内51⁻1)
・石仏(横内51⁻1)
・看板、石仏(横内1-4)
・横内橋(横内1-4)
・石仏(仮宿1012)
横内橋袂。
~~~~~~
~焼津市~
○智勝神社(焼津市策牛398)
・石鳥居
・手洗石
・献燈2
・石段
・板碑
○薬師堂(焼津市策牛436)策牛集会所
・説明版:現在の建物は昭和2年村人によって建てられたもので、近年改修された。この地より西方1㎞の原の山(犬頭塚)に満願寺という寺があり、戦国中期に戦火により焼失したおり、寺の一部を移築したお堂の後に建てられたものと伝わる。本尊は薬師如来で左手に薬壺宝珠を持つ姿をしている。また十二神将を従えているが、顔面を削り取られており、時代的な謎とされる。地元の人には耳薬師として信仰され耳の不自由になった人が願をかけ、治癒したときに穴の開いた石をお果たし(御礼)に供え、今でもその石が多く残っている。このお堂の裏手には明治の始めに廃寺になった寶善寺があり、尼僧が住持していた。地元ではこの辺りを寺屋敷という。
*私見:耳の病気を治すという薬師如来の顔面が削られているのは、昔は病気を治す際、仏像の一部を削って服用すると効果があると云われたためかもしれない。耳の病気なので耳附近の顔面が削られたのかもしれない。
・おくまの石(策牛)
石には霊力が潜むと信じられ、巨石は信仰の対象とされ、当地区には「ぼたもち石」「むじな石」等があり、この「おくまの石」もそのひとつである。女性の裁縫の御守りとして、カナ糸等を奉納した。
○神龍山 長福寺(関方412)曹洞宗
・地蔵:祠、地蔵、第丗ニ番
この地蔵は元は裏の寺山山頂:104mに安置されていた。田中城の殿が検地で岡部方面より見回りに来て関方に差し掛かると急に馬が棹立ちになって暴れ、殿はスッテンコロリと落馬するという事故があった。易者に伺ったところ地蔵を山頂から降ろして読経の聞こえる所に安置するよう告げられ、現在地に祀った。地蔵の顔にイボが治った跡があると云われ、台座周りの丸石(経文石)を早朝に借りてイボをそっとなでると治ると参詣人に云われていた。縁日は8月18日で戦前は夜店が数店出てにぎわった。現在も祭りは続いている。
・経塚石
碑文:圓通懺摩法一座 奉書寫一字一禮 寶筐印陀羅尼三辺
大般若経一巻大悲神梵消神梵 大乗妙典経一般若心経佛陀
百楞厳神梵一巻大施餓鬼光明無
明和ニ乙西歳1765八月晦日回向供養 願主 義目 謹書
石数八万七千施主男女等
・供養塔
・六地蔵+1、地蔵
・地蔵、・石塔、・観音3、
・石燈籠、・手洗石
・石祠
・葷酒不入山門
・石塔
○猪之谷大明神(関方15)
・六鈴鐘出土古墳:市指定有形文化財、直径13.8㎝、厚さ0.55㎝、古墳時代後期のものと推定される。日本の古代社会においては、鏡は姿見としてではなく、呪術的な道具として考えられている。鈴についても呪術的な道具として考えられている。鈴についても呪術具祭器として使用されている。こうした祭儀用の鏡と鈴を一緒にしたのが鈴鏡で、日本特有の鏡である。この鏡はほとんど完全品で、形式のみごとなものである。内区は内行五花文を中心とし、重圏文と櫛歯文を交互に二重にまわらせている。6個の鈴が付き内2個が半面欠損しているのみで、まことに貴重な珍品である。
・ナギ:市指定天然記念物、目通り2.25m、根回り2.6m、樹高16m、枝張り5m、神社拝殿前にある雅樹で樹勢は旺盛である。ナギはマキ科の常緑高木で元来亜熱帯性植物であり、わが国では、暖地に自生する。葉脈が平行であるため、せんまいさばきともいう。
・石鳥居
・新:狛犬2
・新:手洗石
・手洗石
・石燈籠
・石室:祠:古墳前
・石段
・山の神祭り(関方)
焼津市関方地区で毎年2月8日に行われる祭り。山の神を田に迎えて、その年の豊年万作を祈る神事で、祭りのもっとも原始的な形を残している。以前は前日7日に年行事当番の青年たちが「山の神の勧進(かんじ)、何でも一升十六文」と言って集落中から米や豆等を集めて回ったが、今では行っていない。しかし年行事当番は、1,2週間も前から山道普請、祭具、お供え物の調達等、ほぼ昔からのしきたりにそって準備している。前日7日には、お供え餅(古くはしとぎ)、直会(なおらい)のごちそう(赤飯、煮豆、おから等)が作られる。
8日は早朝から龍神、幟、しめ縄、御幣(4本)、御弓(2張)、御矢(6本)等が調整される。そして午前9時ころの1番鉦で村中に祭りのふれが合図され、午前10時半頃の2番鉦で祭り行列は出発する。途中「参ろう参ろう御幣(おんべ)持って参ろう。」と、大声で唱えながら山道を上っていく。
山の神の磐座(いわくら)は、高草山の標高200mばかりの所、沢の源流部にある。神前に龍神を飾り、お神酒、餅、赤飯等を供えて参拝する。参拝が済むと2張の御弓から計6本の御矢が下に向かって放たれる。山の神はこの矢に乗って里に降り田の神となる。
この行事が済むと50mほど下の拝所で直会が行われる。この直会は神と共に食事を楽しむという意味がある。
○やいづ山の手今昔案内解説
1、 高草山山頂、標高501.4m、測量三角点設置通信各社中継アンテナ設置地点。
2、 無名戦士の碑:ソロモンの碑
3、 古木一本杉、樹齢推定300年、一本杉茶園、やまざくら群生地、大島ざくら群生地、複線索道、単線テッセン発着跡地
4、 池の平(三輪地内)湧水池、貴重な飲料水、湧水井、えごの巨木あり、
5、 しらみ平(白帆見平)岡部町との尾根境行政界、
6、 策牛山の神鎮座地(五反明)、
7、 方ノ上城址 石合山(いしゃばい山)標高230m、伝承狼煙台、天文5年1535今川義元判物写、花倉の乱、
8、 幻の池出現地(池ノ窪、池ノ段)
9、 方ノ上古墳群、経塚(問)発見地石合山山頂) 古代平安朝
10、 関方山の神奥の院 例祭2月8日、(焼津市無形文化財指定)
11、 関方山の神拝所 直会場 石切場
12、 炭焼き窯跡地(小深谷)
13、 水車(米搗き場)跡地
14、 索道荷受場跡地 茶、みかん、農産物、材木
15、 おくまの石 安産、機織り信仰の拝み石
16、 高草山登山道入口石碑 きじ屋 かやのき
17、 薬師堂 耳薬師、穴明き石、庚申塚、十二神将、百万遍数珠
18、 マンボ(県道焼津岡部線に架かる道路兼水路橋)大正9~10年工事、方の上に畑生まれる
19、 智勝神社、天正12年4月創立1588郷倉跡、共同作業所跡
20、 焼津病院、犬頭塚、策牛関方用水水門
21、 水田みかん転作地跡(昭和44年完工)
22、 清水遺跡(弥生時代)
23、 青雲寺跡
24、 奥屋敷古墳群
25、 長福寺 1660年 林叟院13世創建、本堂建立 安政7年1861 いぼ地蔵 経塚石 坂本 松雲寺より長福寺学校日新舎(明治8年~13年生徒50名)
26、 猪の谷神社、興国5年1334,4月建立、古墳時代後期人穴さん、市天然記念物、ナギの木、市文化財、六鈴鏡、
27、 高草山登山道入口石碑、山の手口2000年記念建立、関方茶工場跡(共同作業所跡)昭和20年~平成2年解散
28、 山の手会館 昭和48年新築
29、 河心改修の碑、朝比奈川改修、昭和3年建立、
30、 蝋梅の里、梅の木街道、老人クラブ管理、山の手クリニック、永田デイサービスセンター、
31、 バクダン淵伝承版:昭和20年5月19日投下、朝比奈川堤中里用水堰管理棟太平洋バクダン淵跡、
32、 ハチガシリ流水橋跡
33、 山の手桜堤、さくらまつり、2月第3または第4日曜日、東海道自転車道、
34、 朝比奈川、葉梨川、吐呂川合流点、
35、 秀水苑(老人ケアセンター)
36、 六字堤防跡、尺土管跡、策牛、関方の田園、35ha に1か所直径1尺の排水口、天保6年1835~昭和44年1969まで
37、 方の上学校日新舎:長福寺より新築に依り明治13年~19年、以後越後島尋常小学校分教室となる
38、 八王子神社:天文7年1538,9月創立、天正5年1577、
39、 方の上茶工場跡(共同作業所)
40、 法号庵、閻魔さん、侍者仏
41、 梅の木街道
42、 石切り場
43、 コミュニティーケア高草、老人福祉施設
44、 方ノ上遺跡、中世奈良時代
45、 二重堤防跡
46、 雲龍、雲渓、雨後谷間より湧き昇る雲の様子、
47、 関方、三輪埋樋切崩事件、延享3年1746、
48、 谷川(高天井川)堤跡:昭和44年土地改良により改修、
49、 太田川(新川)跡:昭和44年土地改良により改修され高草川生まれる:昭和18年学徒動員東大生により暗渠排水工事、
50、 防火用水槽:消火栓設置以前地区自衛の為設置、
隣接地:
焼津市坂本、坂本神社、林叟院、高麗福祉センター、坂本団地、藤枝市岡部町三輪、神(みわ)神社、三輪団地、
山の手地区の概況:
焼津市の西北部、藤枝市岡部町との隣接地域にあり、高草山尾根を境とし、吐呂川、朝比奈川合流点より東、朝比奈川本流の北側の地域で、東名高速焼津インターチェンジより約1㎞の所にあり、山、畑、田と自然に恵まれた地区で、現在三字合計戸数346戸人口1036人(明治24年の戸数、 方の上37戸、194人、 関方46戸、264人、 策牛34戸、227人)の昔から長い歴史と文化をもつ平和な郷である。2006年焼津市山の手未来の会創立10周年。
○方ノ上城跡(かたのかみじょう)入口
方ノ上城址 石合山(いしゃばい山)標高230m、伝承狼煙台、天文5年1535今川義元判物写、花倉の乱、
天文五1536年以前の築城で、今川氏の家督争いである花倉の乱において玄広恵□(ゲンコウエタン)方の拠点の一つであった可能性がある。
○八王子神社(方ノ上154)
○祠:地蔵、馬頭観世音(方ノ上400⁻1)、水準点
馬頭は昭和13年12月大石建立。
○法号庵(方ノ上343⁻1)
・方ノ上閻魔堂:安置:享保四1720年、当時の安置場所は現在地より北側の県道近辺の方ノ上地蔵堂に安置されていたが、県道の拡幅工事に依り現在地に移転された。
由来:赤穂浪士の敵討ちのあった元禄の世も、宝永、正徳と移り変わったある日、元吉良家のある家来が、各地流浪の末、方ノ上村の地蔵堂に堂守として住み着いたが、今まで過ごしてきた土地でも、またこの土地でも吉良家の評判が悪かった。吉良の殿様は悪くなく、自慢の殿様だと思い何とかしたいと悩んでいた。これでは吉良の殿様をはじめ、大勢の犠牲者の霊は浮かばれない、成仏できないと思い、堂守はあの世で人の生前の裁きを閻魔様にしてもらおうと考えたのが、閻魔様を作ることだった。まずはこの土地の法号庵の住職、更に地元名主へまた本寺林叟院方丈へと相談の上、江戸に上り寄附を募り立派な閻魔様を享保三年の暮れに完成させた。翌年の春、焼津湊の積問屋巻田久左衛門の船で順風に乗って運ばれ、善男善女に出迎えられて、方ノ上地蔵堂に安置された。堂守が一念発起してより5年目だった。船主巻田久左衛門は閻魔様を運んだのを慶びとして、脇立2体と鉦を寄進した。
・六地蔵
・窪なし地蔵:3
・地蔵:3
・石仏:4
・石塔:3
・五輪塔破片
・石塔
・結界石2
・祠:石塔:寺前辻にあり
○坂本神社(坂本1045⁻1)
・保存樹木:ほるとの木
・石段
・献燈2
・献燈2
・石祠:19以上多数
・手洗石
・祠
・本殿、拝殿
○林叟院(坂本1400)
市指定文化財
・経蔵:木造一重桟瓦葺、方形造り。内部は正面奥に仏壇、中央に輪蔵、格天井で4.84m
(16尺)4面である。経蔵とは一切経等の経典を納めておく蔵で20世心牛租印師が明和五1768年建造を発願し、明和八1771年に工匠石川市之丞及びその子権右衛門により上棟された。師は中央の輪蔵に一切経全6930巻を納めることを目標としたが、その一部950巻を収納できたのみと伝わる。
・鐘楼:木造入母屋造り桟瓦葺、袴腰付、二軒繁垂木ふたのきしげたるき、勾欄付こうらんつき。間口奥行共に2.83m(9.34尺)下層地貫上端かそうじぬきうわば、高さは礎石上端より丸桁がぎょう上端まで4.84mである。鐘楼は別名鐘撞堂かねつきどうとも言い、寺院の境内等で釣鐘のある堂のことを言う。この鐘楼は宝永三年1706の創建と云われてきたが、平成14年度修理の際、天保十五年1844の棟札と棟束むねづかに墨書が確認された。梵鐘を吊るすのに袴腰付形式のものはなく焼津市内では唯一つである。
・宝篋印塔:高さ約2.6m、宝篋印塔の名は「宝筐院陀羅尼」という経典を納めたことに由来する。石造塔では墓塔または供養塔として造立されたものが多い。下に基壇を置き、その上に反花座、基礎、塔身、笠の順に積み、最上部に相輪を立てている。寛政三1791年の古図に移設前の姿がえがかれているので、それ以前の建立と考えられる。
・ホルトの木:目通り3.1m、根回り4m、樹高20m、枝張り24m、で、林叟院の墓地裏にあり、樹勢は旺盛である。ホルトノキ科に属し亜熱帯原産のもので、房総半島以西の太平洋岸の暖地、特に四国、九州地方に生育するが、本県には数が少なく大木であるのは珍しい。焼津市歴史民俗資料館。
・自然石2
・角柱2
・如来
・馬頭観音2
・六地蔵+1
・祠:地蔵4
・石仏:多:地蔵、観音、墓石?
・不許葷酒入山門
・石塔2
・新:六地蔵
・歌碑&説明版石
・新:地蔵
・すぎ保存祷:大木
・山神血脈石
・石燈籠1:、2:
・石仏&石塔21:
・忠魂碑
・笛吹段古墳群(坂本)笛吹段公園
高草山中腹標高約260mに位置する。古墳時代後期の古墳で10基の横穴式石室が見つかっている。昭和58年農道の整備に伴い調査が行われ調査後はほとんど埋め戻されたが、現在2基の石室を見学できる。
・東海道標識(坂本521⁻3)
東海道とはいっても有名な東海道ではなく、東の街道を意味したと思われるが、または古代東海道の名残か? ただ焼き津辺から花沢へ行くには西に遠回りではある。
・説明版:海道には街道と垣内の2つの意味がある。やきつべのみちの海道と、東の屋敷の集落の2説がある。いづれか。
○筧沢寺(石脇上423)
・庚申供養塔
・石塔
・六地蔵
・地蔵2:立、座、
・石塔:納経寶塔
・石塔:金毘羅宮
・本堂裏に古い墓地、墓石
・新:寺名碑:曹洞宗風尾山筧澤寺入口
○高草山ハイキングコース標識説明版(石脇上528⁻1)
高草山ハイキングコース:大滝延命地蔵、正午を知らせる石「時石」、潮見平を経て高草山頂上へ、池の平遊水地、金苞園を経て戻る。駿河湾、富士山、伊豆連山、志太平野を一望する健脚向きのコース。三輪公民館~高草山山頂(潮見平コースで100分)、高草山山頂~三輪公民館(池の平コースで45分)、
・富士見峠
・鞍掛峠
○高草山
標高501.4m、農作物の宝庫であり野鳥の森としても知られる。高草山はアルカリ玄武岩から成る山で、枕状溶岩や珍しいタカラン石が見られる等地学上でも有名。大井川平野や遠くは御前崎まで眺めることができる。
・山頂:電波塔、
・祠:高草山上大神(高草権現)
○勢岩寺(石脇上600)曹洞宗 谷汲山
・弘法大師像:焼津市指定有形文化財、像高17㎝:5寸6分、内台座4㎝:1寸3分、袖張り7.5㎝:2寸5分、木喰五行上人作、小さいながらもまことに丁重に彫刻された美しい座像であり、いかにも幸福をもたらしてくれそうな微笑ましい木喰仏である。光背が常楽寺、宝積寺の物と同形式であり、台座は大日菩薩のものと同じである。製作は寛政12年1800の7月と推定される。
(背面の墨書)日本国中 木喰五行(種子)大師遍照金剛 父母安楽菩薩(花押)正作自在法門
(背面の墨書)(光明真言)(梵字)寿命日本千体(身体)ノ内 国王国中 大師遍照金剛 父母安楽 百万歳 正作 天下一自在法門 八十三才 木喰五行菩薩 (花押)
・機織り地蔵尊の由来:弘法大師の甥で、後に近江國三井寺開山になった智証大師が、円珍と呼ばれていた頃、大和國長谷寺に参詣し、一心に拝んでいると、長谷寺鎮護の神の手力雄尊が霊夢に立った。この寺の開山徳道上人が本尊を造刻したときの霊木が残っているから、この霊木で不動明王を造刻して、駿州花沢の法華寺の十二坊の一坊に納め、永く衆生を済度せよ。石脇前の泓に至れば金色の光を放ち、地蔵尊が迎えるだろう。機織りの地蔵と言い六十六番札所の二十二番と定められ、いかなる願懸も必ず利生を授けると云う。一刻も早く不動明王を刻み、駿河に下向せよ。通力自在の計らいをなさん、と言い手力雄尊は消えた。円珍は霊木で直ちに不動尊を造刻し、駿河に下った。石脇前の泓に立つと金色の光が差し、円珍を迎えた。光の消えた後、機織りの石の上には地蔵が座っていた。これぞ霊夢のお告げの通りと恭しく拝んだ。当山に本尊を納めた。この地蔵は肌身地蔵といって体内に尊像を身ごもって、子授け、安産の地蔵といわれ遠近にも比類のないものである。威徳は広大無辺いかなる難病苦難も家内安全、商売繁盛、学業成就、交通安全に至る、日々の衆生の生活を洩れることなく守り救ってくれる地蔵である。当山本尊を造刻した智証大師を金色の光を放ち迎えた地蔵を繰り返し拝んでください。
*泓=オウ、コウ、深い
・歌碑
・地蔵
・六地蔵+1
・三界萬霊塔
・石塔3
・祠
・赤鳥居、石祠
・新:十二支地蔵尊
・宝積寺(石脇下692)
・地蔵菩薩立像:木喰仏:市指定文化財:像高77㎝(2尺2寸5分)、内台座14㎝(4寸6分)、 (背面墨書)法門 増宝寿 八十三才(花押)大菩薩 木喰五行菩薩 以下不明
(背面墨書) 光明真言 (種子)正作 天一 自在法門 日本千タイノ内なり 聖朝安穏増宝寿 南無地蔵大菩薩 天下安楽興正法 寛政十二甲歳八月四日ニ成就ス 命 万 百 木喰五行 八十三才 菩薩 年 (花押)
この地蔵は左手に宝珠を持ち、右手は袂をつかんでいる。木喰仏としては珍しく、材質が桜の木である。しかもまことに慎重で、一部丸ノミが使用され、足指の爪まで掘り出されている。製作は寛政12年1800、7月と推定される。
*木喰五行上人:享保3年1718~文化7年1810、45歳の宝暦12年1762、常陸國の木喰観海上人によって木喰戒を受け、全国隈なく巡礼を行った。木喰上人は幾つかの願を持っていたが、その中でも大きな願は日本全国の神社仏閣に参拝する「日本回国」の願と、千体の仏像を彫刻してゆかりの国々寺々に供養したいという「千体仏」の願があった。この二大願を乗り越え、83歳で「日本回国」、90歳で「千体仏」の大願を果たした。木喰上人が現在の静岡県に入ったのは寛政11年1799ノ11月19日遠州の狩宿で、翌年6月13日に岡部町に入り8月13日まで2か月間滞在している。焼津市内の仏像もこの期間のものである。
・西國三十三番観世音菩薩:由来:当山石脇山寶積寺境内に安置する、これらの菩薩の尊体は今を去る180年前、人皇119代光格天皇の御代享和元年辛酉5月及び7月吉日を選んで当村並びに近郷の篤志家が先祖菩提のため、勧請建立したものである。このような33の尊体を羅列安置してある霊場は全く稀であり、その感応霊験あらたかなることは世人の良く知るところである。
・石脇山宝積寺は往古天台宗花沢法華寺寺坊の一つとして元小浜にあったが、波の為、欠損したので永禄十年、鎌倉建長寺派に属し時の庄屋原川新三郎氏が菩提の為観世音菩薩を本尊として建立、その後享和元年、近郷の寄進により西國三十三所観世音菩薩石仏尊体が安置された。しかるに昭和41年1月東名高速道路建設により本堂、墓石等移転のやむなきに至る。檀家一同一致協力5カ年の歳月を費やし以て境内の整地、本堂、庫裏の改築、墓石移転を終了、よって昭和45年3月9日落慶入仏式を挙行す。
・地蔵3
・観音
・石塔
・石塔2
・寺門前近くの参道入口に石塔あり。
○石脇浅間神社(焼津市石脇705)
・祭神:木花咲耶姫命、品陀和気命、天照大御神、・例祭日:10月10日、境内社:津島神社、・境内地477坪、
・由緒:浅間神社上り口右側に大きな岩が2つある。旗掛石または鞍掛石という。本来この2つの岩は我が国の古い信仰である神の依りつかれる磐座(いわくら)であった。この浅間神社は、延徳3年9月天下の英雄徳川家康の三河時代からの家臣であった原川新三郎氏が郷里原川村から浅間社を勧請してこの聖地の例に奉斎したものと伝えられ、明治8年2月村社に、同40年3月神饌幣帛料供進社に指定された。旧除地高2石であった。
・災害:昭和57年9月12日本県を直撃した台風18号により境内の南側階段等倒壊し多大の災害を蒙るも464名の氏子一丸となって懸命な努力を続け復旧に直進し、同年10月吉日大鳥居を再建した。
・記念碑:この神社は延徳3年5月、この地に祀られた歴史をもつが、昭和57年18号台風の強襲によって標高17mの神社境内地が大きく崩壊し、明治27年氏子の建設した拝殿等床下倒壊の危険にさらされ氏子一同苦慮していたところ、ときの区長総代等相図り浅間神社再建奉賛会を設立し昭和58年10月10日第1回総会を開催氏子一同の賛同を得て発足した。奉賛会は総会以来満2ヶ年を予定し境内高を5mに造成拡充し拝殿新築、その他諸施設等完備、昭和60年10月20日完成、落成式を挙行し、且つ氏子総代に一切の管理を移管。まことに氏子の家運並びに子孫繁栄を共に地域発展を祈願して之を建立す。
・新:石鳥居
・新:石段
・新:献燈2
・新:手洗石
・新:狛犬2
・古:石
・献燈2
・石段
・新:社名碑:
・自然石:数個
・祠:数個
○旗懸け岩(石脇下89)
・平和の碑
・この石は江戸時代、高草山周辺にたびたび狩りに来ていた徳川家康が家臣であった原川新三郎の家に立ち寄った際に、旗や鞍をかけたことからこの名がついた。また石脇という地名もこの石に由来していると云われる。
・旗掛石:当寺、岩の近くに原川新三郎氏の門前があり、家康が転化を取ってからしばしばこの辺りで鷹狩を催し、その都度原川家を訪ね、その際家康の旗を立てかけ、馬の鞍を置いたので、この名があるという。他にやきつべの小径、駒つなぎの松の名跡がある。また氏子たちで年2回大しめ飾りが行われる。
・しめ縄
岩は磐座と云われ、2つに分かれていて、おそらくその間に土師器等を割って占いをしたのだろう。古代の祭祀場といわれる。高草山の中腹にも祭祀場の磐座があり、関連があるのだろうか。
・秋葉常夜灯(石脇下875)
○石脇城跡、大日堂、八幡神社、六地蔵:説明版(石脇下906)
・石脇城跡:応仁年間1467~1469に今川義忠の妻(北側殿)の兄、伊勢新九郎長氏(後の北条早雲)が今川の客将として石脇に住まいを構えており、石脇城の築城はその後の文明年間1469~1486と推定される。北条早雲はその後、小田原城を本拠に戦国大名として世に出たので石脇城は出世の第一歩を進めた城といえる。現在曲輪跡と土塁跡が残っている。
この城は北の高崎山から南へ枝分かれする尾根の先端の標高30mの城山ジョウヤマに所在する。15世紀(室町中期頃)の駿河守護職で後の戦国大名今川氏の属城(支城)と推定され、範囲は南北約220m、東西130mと考えられる。山裾の西から南へ流れる堀川を外堀とし、山頂の第一曲輪、中腹の第二曲輪、その第二曲輪を堀切で隔てた南端の外曲輪と、附属曲輪のための土手)の痕跡が残っている。城主については記録がないが、江戸時代に編まれた地誌「駿河記」によると、文明年間1469~1486に今川義忠が伊勢新九郎盛時(後の北条早雲)を石脇に住まわせたとある。伊勢新九郎盛時は文明8年1476応仁の乱の影響で今川家の当主、上総之介義忠が遠江(御前崎市川上)の塩買坂での戦死により、次代をめぐる家督争い(内紛)が起きた際、嫡子竜王丸(後の今川上総之介氏親)を助けて活躍をした。伊勢新九郎は、この功績により富士下方一二郷(富士市城)を与えられ、延徳3年1491以後伊豆平定に乗り出し、やがて関東8か国を治めた戦国大名北条家(後北条)の基礎を築いた。
・大日堂:
・不動明王像:像高94㎝、市指定文化財、(背面の墨書)日本千タイノ内なり 正作聖朝安穏増宝寿 天一自在法門(種子)天下安楽興正法 木喰五行菩薩 八十三才 寛政十二申歳七月廿三日 本 (光明真言) 命 百 母 万 □□ (種子) 父 歳
この像は、吉祥天立像が完成した2日後にできあがった。岩座の上に踏ん張り、渦巻きとなって燃え上がる火災の中に立ち、不動の気魂を十分に表しながらも木喰仏らしい人間味が出ている。
・吉祥天立像:像高94㎝、内台座13.6㎝、市指定文化財、(背面の墨書) (種子)日本千タイノ内なり正作聖朝安穏増宝寿 天一自在法門(種子)大吉祥天女 木喰五行菩薩 天下安楽興正法 八十三才 (花押)寛政十二申歳七月廿一日ニ成就ス
吉祥天は正しくは大吉祥天女といい、福徳を司るといわれ、種々の善根を施したので美しい顔になったという。髪はふっさりと肩までかかり、親しみを感じるにこやかな童顔をしている。
*木喰五行上人と焼津:1718~1810
安永2年1773,56歳のときに日本回国と千体仏の願を起こし全国を廻り諸国に自生の仏像を奉納した。現在全国で約500体の作品が確認されている。木喰上人が当地を訪れたのは寛政12年1800上人が83歳のときで故郷である現在の山梨県へ戻る途中であった。現在焼津市には、この時造られた仏像が大日堂、勢岩寺(歴史民俗資料館で保管)、宝積寺に残っている。
・城山稲荷社:赤鳥居、祠、
・供養塔2、「奉納大乗妙典供養塔」、「庚申供養塔」
・奉献燈:竿部分
・大山祇眷属龍神神社 昭和十一年
・墓石
・六地蔵
・城山八幡宮:・石鳥居、・手洗石、・祠
・石塔:古城山全昌院址
・村はずれの細い山道
ゴロタの石道、峠を越えるとそこは隣村、昔の古道。
○八幡神社、諏訪神社(高崎409)
○鳴沢不動尊(高崎602)
○花沢城跡(高崎758)
○神明宮(吉津164)
○法華寺(花沢2)
○日本坂峠(焼津市花沢、静岡市小坂)
○須賀神社(小浜35-1)
○塩釜神社(小浜1520)
・石鳥居
○海雲寺(小浜88)
○大日堂(小浜)
○道了権現(小浜)
・砂張屋孫右衛門道標:
○虚空蔵山香集寺(浜当目)
仁王門
○弘徳院(浜当目三丁目14-7)
○那閉神社(浜当目三丁目14-13)
・鳥居(浜当目一丁目14)
○西宮神社(岡当目74⁻1)
・社名碑:供進指定村社西宮神社 昭和丗九年
・石鳥居:昭和三十九年
・手洗石
・奉請庚申供養塔 安永五
・石塔
・石祠
・祠
・献燈2:紀元二千六百年
・狛犬2:昭和期か?
○薬師堂(中里655)
○若宮八幡宮(中里1000⁻1)
・焼津市指定文化財:・若宮八幡宮棟札(長さ152.2㎝、厚さ3.6㎝、重さ5㎏)、若宮八幡宮が寛永六年1629に第2代彦根藩主井伊直孝(1590~1659)により再建されたときの棟札である。檜の一枚板の表面に黒漆を塗り、文字の部分を彫り込み白色顔料をかけている。棟札の文字は寛永の三筆として名高い松花堂昭乗の筆である。(歴史民俗資料館で保管している。)
・若宮八幡宮の石橋:(長さ152㎝、幅159㎝)、天保六年1835に架設された石橋である。通路部分は4枚のアーチ型の板石でできており、高さ約33㎝の4本の親柱には再建年月と再建に関わった者の名前が刻まれている。
・直孝公産湯の井:伊井直孝は彦根35万石の城主で徳川譜代筆頭の大名である。現:国宝彦根城は直孝の築城である。当地若宮八幡宮は寛永六年直孝が建立した。
・歌碑:「歴史きさむ 棟札のこれり 」
詠者井伊文子は井伊家39代井伊直興氏(彦根市長)の夫人で、旧琉球王家尚昌氏の長女、女子学習院本科を卒業され、歌人佐々木信綱先生の高弟であり、歌集随筆集など多数の著書がある。このたび若宮八幡宮建立350年に当り、これを記念して表題の歌を書かれたのである。また夫人は沖縄のひめゆりの塔の憂歌「ひめゆりの 石ぶみに深う ぬかづけば 平らぎを希いなむ 乙女らの声は」の詠者でもある。
・石鳥居:大正十三年、
・石鳥居:皇紀二千六百年記念
・狛犬2:平成十年
・手洗石:平成十年
・石燈籠2:
・御神燈2:日露戦役従軍者紀念、
・御神燈1:
・手洗石:慶應四歳
・祠4
・石祠
・自然石
○糧堂院、岡当目公会堂(岡当目381⁻1)
○大徳寺(浜当目一丁目3-4)日蓮宗
・石祠3、うち1つ稲荷、鏡
・マリアナ観音(浜当目三丁目16)
2016年09月22日
千葉山街道
千葉山街道
・情報提供呼びかけ
今後、2016年11月以降、笹間街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
島田市大津谷川流域の道である。一応起点は旧東海道と大津通りの交差点とする。ここから大津谷川の上流を目指すことになる。そして反対に下流側を目指すと島田駅東側を通り大井川河川敷に到達する。今回は割愛する。
☆☆☆~~~大津谷川沿い~~~
大津通り交差点周辺の遺物類から紹介する。
・大神宮(島田市本通6丁目6043⁻1 )
・ 神社(島田市本通5丁目8315 )
・福泉寺(島田市大川町4904⁻1 )
・須田神社(祇園町8498 )
・林入寺(祇園町8512⁻1 )
・日本基督教団(大津通8328⁻5 )
・道圓寺(祇園町8648⁻3 )
・長徳寺(新田町8650⁻1 )
・空性寺(新田町8664 )
・御陣屋稲荷(柳町2074 )
・快林寺(幸町2073 )
・洞源寺(大津通8594⁻1 )
・福音ルーテル教会(中河町8677⁻1 )
・天理教(中央町21-24 )
・金山神社(元島田234⁻3 )
・カトリック島田教会(中河町344 )
・三崎稲荷大明神(野田1266₋2 )
・鵜田寺(野田1195‐3 )
・白岩寺、白岩寺公園、愛宕神社(御仮屋町9957 )
・法信寺(松葉町9945 )
・八幡宮(音羽町5丁目 )
・竜雲寺(野田173 )
・釣月寺(野田178 )
・神明宮(野田925⁻1 )
・島田市中央公園、ばらの丘公園(野田1689 )
・春日神社(落合425⁻1 )
・大津忠魂社(落合112 )
・智徳寺(落合102 )
・要法寺(落合547⁻5 )
・ 堂(尾川239⁻1 )
・法蔵寺(尾川321 )
・五社神社(尾川368 )
・八幡神社(大草767 )
・慶寿寺(大草767 )
・枝垂桜:県指定天然記念物
・天徳寺(大草911 )
・石塔類( )
・千葉山智満寺、十本杉、千葉山496m(千葉254 )
☆☆☆~~~☆東光寺谷川沿い~~~
~東光寺方面~
・峠(野田、東光寺 )
・東光寺(東光寺557 )
・日吉神社(東光寺557 )
~東光寺の下流の阿知ケ谷、岸、岸町方面~
・天満天神社(阿知ケ谷616⁻1 )
・香橘寺(阿知ケ谷325 )
・西念(堂)寺(阿知ケ谷85‐1 )
・浅間神社(岸町13-1 )
・大日堂(岸 )
・養命寺(岸 )
・竜江院(岸2054 )
・西山堂(藤枝市上青島393⁻1 )
☆☆☆~~~☆伊太谷川沿い~~~
~伊太谷川下流~
・法幢寺(野田1450⁻1、中河町旗指 )
・旗指恐山地蔵尊(中河町3031⁻1 )
~伊太~
・敬信寺(伊太3050⁻1 )
・伝心寺(伊太2980 )
・左軍神社(伊太1450‐1 )
・秋葉神社(伊太1450‐1 )
・康泰寺(伊太2883⁻1 )
・三寸神社(伊太2883⁻1 )
・静居寺(伊太3083 )
・薬師庵(伊太2771 )
・慶幅寺(伊太2060 )
・地蔵堂(伊太1267⁻1 )
・八幡神社(伊太1094 )
・玉雲寺(伊太584、上伊太 )
・矢倉山311m(伊太 )
・八幡神社(伊太213₋2、田代 )
~向谷方面~
・ 神社(伊太1932 )
・水神堀(伊太1832 )
・天神宮、殉国之碑(伊太2014⁻1 )
・大井神社、忠魂碑(天神町1786 )
・水神社(天神町1786 )
・竜泉院(向谷1丁目833⁻1 )
・善光寺如来堂(三ツ合町2675⁻4 )
・稲荷神社(稲荷2丁目13-12 )
・神明宮(稲荷2丁目13-12 )
☆☆☆~~~☆相賀谷川沿い~~~
・観音堂(伊太1620、笹ヶ久保 )
・白山神社(伊太1472⁻3、笹ヶ久保 )
・赤松地蔵(相賀90⁻5、室谷 )
・赤松発電所(相賀230 )
・瑞雲寺(相賀316 )
・洞源寺(相賀1092 )
・高山白山神社(相賀1422 )
・養徳寺(相賀2260 )
☆☆☆~~~☆伊久美川沿い~~~
・川口発電所、変電所(身成983 )
・八幡神社(身成210⁻1 )
・清源寺(身成438 )
・神明宮(伊久美5750、長島 )
・津島神社(伊久美4641、犬間 )
・子の御前神社(伊久美3597、小川 )
・法泉禅寺(伊久美3803、小川 )
・祭文峠(伊久美 )
・八幡宮(伊久美2588、中平 )
・子安堂(伊久美2089、中平 )
・大井浅間神社(伊久美1014⁻1、二俣 )
・京柱峠(伊久美、二俣、 )
~出会い橋
・神社(伊久美220、白井 )
・白井公会堂(伊久美315、白井 )
・西向公会堂(伊久美1942⁻6、西向 )
・明神社(笹間下1948、西向 )
・明神社(笹間下1599、大平 )
・大平公会堂(笹間下1682、大平 )
・大森(笹間下、大森 )
・江松峠(笹間下、 )
・東海自然歩道、秋葉街道(笹間下、 )
・笑い仏(笹間下、 )
~身成川を下流に向かう~
・白井和神社(笹間下3052、上河内 )
・慈眼山阿主南寺(身成 )
~島田市伊久美、桧峠~
・峠の地蔵尊(伊久美2971、桧峠 )
峠のすぐ先は藤枝市。
・情報提供呼びかけ
今後、2016年11月以降、笹間街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
島田市大津谷川流域の道である。一応起点は旧東海道と大津通りの交差点とする。ここから大津谷川の上流を目指すことになる。そして反対に下流側を目指すと島田駅東側を通り大井川河川敷に到達する。今回は割愛する。
☆☆☆~~~大津谷川沿い~~~
大津通り交差点周辺の遺物類から紹介する。
・大神宮(島田市本通6丁目6043⁻1 )
・ 神社(島田市本通5丁目8315 )
・福泉寺(島田市大川町4904⁻1 )
・須田神社(祇園町8498 )
・林入寺(祇園町8512⁻1 )
・日本基督教団(大津通8328⁻5 )
・道圓寺(祇園町8648⁻3 )
・長徳寺(新田町8650⁻1 )
・空性寺(新田町8664 )
・御陣屋稲荷(柳町2074 )
・快林寺(幸町2073 )
・洞源寺(大津通8594⁻1 )
・福音ルーテル教会(中河町8677⁻1 )
・天理教(中央町21-24 )
・金山神社(元島田234⁻3 )
・カトリック島田教会(中河町344 )
・三崎稲荷大明神(野田1266₋2 )
・鵜田寺(野田1195‐3 )
・白岩寺、白岩寺公園、愛宕神社(御仮屋町9957 )
・法信寺(松葉町9945 )
・八幡宮(音羽町5丁目 )
・竜雲寺(野田173 )
・釣月寺(野田178 )
・神明宮(野田925⁻1 )
・島田市中央公園、ばらの丘公園(野田1689 )
・春日神社(落合425⁻1 )
・大津忠魂社(落合112 )
・智徳寺(落合102 )
・要法寺(落合547⁻5 )
・ 堂(尾川239⁻1 )
・法蔵寺(尾川321 )
・五社神社(尾川368 )
・八幡神社(大草767 )
・慶寿寺(大草767 )
・枝垂桜:県指定天然記念物
・天徳寺(大草911 )
・石塔類( )
・千葉山智満寺、十本杉、千葉山496m(千葉254 )
☆☆☆~~~☆東光寺谷川沿い~~~
~東光寺方面~
・峠(野田、東光寺 )
・東光寺(東光寺557 )
・日吉神社(東光寺557 )
~東光寺の下流の阿知ケ谷、岸、岸町方面~
・天満天神社(阿知ケ谷616⁻1 )
・香橘寺(阿知ケ谷325 )
・西念(堂)寺(阿知ケ谷85‐1 )
・浅間神社(岸町13-1 )
・大日堂(岸 )
・養命寺(岸 )
・竜江院(岸2054 )
・西山堂(藤枝市上青島393⁻1 )
☆☆☆~~~☆伊太谷川沿い~~~
~伊太谷川下流~
・法幢寺(野田1450⁻1、中河町旗指 )
・旗指恐山地蔵尊(中河町3031⁻1 )
~伊太~
・敬信寺(伊太3050⁻1 )
・伝心寺(伊太2980 )
・左軍神社(伊太1450‐1 )
・秋葉神社(伊太1450‐1 )
・康泰寺(伊太2883⁻1 )
・三寸神社(伊太2883⁻1 )
・静居寺(伊太3083 )
・薬師庵(伊太2771 )
・慶幅寺(伊太2060 )
・地蔵堂(伊太1267⁻1 )
・八幡神社(伊太1094 )
・玉雲寺(伊太584、上伊太 )
・矢倉山311m(伊太 )
・八幡神社(伊太213₋2、田代 )
~向谷方面~
・ 神社(伊太1932 )
・水神堀(伊太1832 )
・天神宮、殉国之碑(伊太2014⁻1 )
・大井神社、忠魂碑(天神町1786 )
・水神社(天神町1786 )
・竜泉院(向谷1丁目833⁻1 )
・善光寺如来堂(三ツ合町2675⁻4 )
・稲荷神社(稲荷2丁目13-12 )
・神明宮(稲荷2丁目13-12 )
☆☆☆~~~☆相賀谷川沿い~~~
・観音堂(伊太1620、笹ヶ久保 )
・白山神社(伊太1472⁻3、笹ヶ久保 )
・赤松地蔵(相賀90⁻5、室谷 )
・赤松発電所(相賀230 )
・瑞雲寺(相賀316 )
・洞源寺(相賀1092 )
・高山白山神社(相賀1422 )
・養徳寺(相賀2260 )
☆☆☆~~~☆伊久美川沿い~~~
・川口発電所、変電所(身成983 )
・八幡神社(身成210⁻1 )
・清源寺(身成438 )
・神明宮(伊久美5750、長島 )
・津島神社(伊久美4641、犬間 )
・子の御前神社(伊久美3597、小川 )
・法泉禅寺(伊久美3803、小川 )
・祭文峠(伊久美 )
・八幡宮(伊久美2588、中平 )
・子安堂(伊久美2089、中平 )
・大井浅間神社(伊久美1014⁻1、二俣 )
・京柱峠(伊久美、二俣、 )
~出会い橋
・神社(伊久美220、白井 )
・白井公会堂(伊久美315、白井 )
・西向公会堂(伊久美1942⁻6、西向 )
・明神社(笹間下1948、西向 )
・明神社(笹間下1599、大平 )
・大平公会堂(笹間下1682、大平 )
・大森(笹間下、大森 )
・江松峠(笹間下、 )
・東海自然歩道、秋葉街道(笹間下、 )
・笑い仏(笹間下、 )
~身成川を下流に向かう~
・白井和神社(笹間下3052、上河内 )
・慈眼山阿主南寺(身成 )
~島田市伊久美、桧峠~
・峠の地蔵尊(伊久美2971、桧峠 )
峠のすぐ先は藤枝市。
2016年09月22日
高根山街道:静岡県藤枝市
高根山街道
・情報提供呼びかけ
今後、2016年11月以降、笹間街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
藤枝市瀬戸川流域の道である。一応起点は県道32号藤枝黒俣線と旧東海道との交差点:上伝馬や千歳とする。ここから瀬戸川の上流を目指すことになる。そして反対に下流側を目指すと田中城や西焼津駅を経て焼津港に至るが、今回は割愛する。
上伝馬や千歳交差点周辺の藤枝1~5丁目の遺物類から紹介する。
・岡出山公園(藤枝市藤枝5丁目15 )
・忠霊塔、
・飽波神社(藤枝市藤枝5丁目15 )
・七ツ森神社(藤枝5丁目15 )
・天満宮津島神社(本町1丁目13⁻4 )
・大井神社(本町1丁目20 )
・慶全寺(本町1丁目12⁻13 )
・長楽寺(本町1丁目10‐12 )
・蓮生寺(本町1丁目3‐31 )
・茶木稲荷神社(本町1丁目3‐18 )
・大慶寺(藤枝4丁目2⁻7 )
・妙法寺(藤枝4丁目5-35 )
・勝草橋、説明版(藤枝1丁目 )
・川除地蔵尊堂(藤枝2丁目2-13 )
・川除地蔵2、馬頭観音、
・出雲大社分院(藤枝2丁目1-33 )
・手洗石、常夜燈、石、
・正定寺(藤枝2丁目3-27 )
・西光寺(藤枝3丁目10-37 )
・月見里神社(藤枝3丁目10⁻24 )
・神明神社(藤枝3丁目4-4 )
・日本キリスト教団(藤枝3丁目12-5 )
・藤枝カトリック教会(茶町1丁目2-51 )
・宗伝寺(藤枝1丁目4-27 )
・満蔵寺(稲川1丁目3-14 )
・洞雲寺(藤枝5丁目2-28 )
・若一王子神社(藤枝5丁目2 )
・鬼岩寺(藤枝3丁目16‐⒕ )
・黒犬神社(藤枝3丁目16-14 )
・萬照寺(原1287⁻6 )
・八幡宮(音羽町5丁目2 )
・茶町(茶町1~4丁目 )
・護国殿(茶町1丁目1-33 )
・西雲寺(音羽町3丁目17-9 )
・清水寺(原 )
~~~☆志太、瀬古地区:茶町の川向い~~~
・秋葉常夜灯、石仏、勝草橋説明版、(志太3丁目3-18 )
・田沼街道入口、史蹟、説明版(志太4丁目11 )
・進雄神社(志太4丁目4 )
・龍王神社(志太4丁目10-19 )
・葺中観音堂(志太4丁目6-17 )
・薬師堂(志太3丁目15-17 )
・金比羅公園、金毘羅神社、天満宮(志太3丁目19 )
・観音寺(瀬古1丁目2-1 )
・秋葉神社(瀬古1丁目2-1 )
・進雄神社(瀬古1丁目12-1 )
・志太温泉、旅館元湯(志太598⁻1⁻1 )、潮生館(志太600⁻2⁻2)
~~~~~~
・延命地蔵尊堂(堀之内929 )
・円応教(堀之内334⁻1 )
・東国寺(堀之内201 )
・龍雲寺(堀之内302₋2 )
・堀之内神社(堀之内589⁻9 )
・京塚(経塚)山245.3m(堀之内 )
~~~☆谷稲葉地区:堀之内の西~~~
・延命地蔵堂(谷稲葉429⁻5 )
・慈光院(谷稲葉931⁻3 )
・谷稲葉神社(谷稲葉720 )
・中世東海道(谷稲葉 )
・心岳寺(谷稲葉1591 )
・双子山(谷稲葉 )
~~~~~~
・寺島神社(寺島906⁻8 )
・薬師堂(寺島366 )
・大井神社(助宗1873 )
・円通院(助宗1787 )
・高山寺(瀬戸ノ谷1946、紺屋、 )
・普門寺(瀬戸ノ谷263、萩間、本郷 )
・本郷神社(瀬戸ノ谷1175₋2、本郷 )
・烏帽子形山392.7m(本郷、助宗、西方)
~~~☆滝沢、滝之谷地区:瀬戸谷の西北~~~
・八坂神社(滝沢1325 )
・竜雲寺(滝沢1498 )
・上滝沢地蔵堂(滝沢2669⁻1 )
・城山(滝之谷 )
・津島神社(滝之谷12212 )
・桧峠(滝沢、桧峠 )
・菩提山(滝沢瀬戸ノ谷 )
~~~~~~
・玉林寺(瀬戸ノ谷5874 )
・津島神社(瀬戸ノ谷12935 )
・びく石牧場(瀬戸ノ谷5658 )
・峠(瀬戸ノ谷 )
・津島神社(瀬戸ノ谷7405、市之瀬 )
多分、旧髙根山登山道開始点。
・びく石登山道(市之瀬 )
・高尾山(瀬戸ノ谷 )
・ 神社(蔵田 )
・鼻崎の大杉(蔵田 )
・高根山、石仏(蔵田 )
・高根白山神社、髙根山831m、東海自然歩道(蔵田 )
・津島神社(瀬戸ノ谷10947、大久保 )
・宇嶺の滝(瀬戸ノ谷、市之瀬 )
・情報提供呼びかけ
今後、2016年11月以降、笹間街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
藤枝市瀬戸川流域の道である。一応起点は県道32号藤枝黒俣線と旧東海道との交差点:上伝馬や千歳とする。ここから瀬戸川の上流を目指すことになる。そして反対に下流側を目指すと田中城や西焼津駅を経て焼津港に至るが、今回は割愛する。
上伝馬や千歳交差点周辺の藤枝1~5丁目の遺物類から紹介する。
・岡出山公園(藤枝市藤枝5丁目15 )
・忠霊塔、
・飽波神社(藤枝市藤枝5丁目15 )
・七ツ森神社(藤枝5丁目15 )
・天満宮津島神社(本町1丁目13⁻4 )
・大井神社(本町1丁目20 )
・慶全寺(本町1丁目12⁻13 )
・長楽寺(本町1丁目10‐12 )
・蓮生寺(本町1丁目3‐31 )
・茶木稲荷神社(本町1丁目3‐18 )
・大慶寺(藤枝4丁目2⁻7 )
・妙法寺(藤枝4丁目5-35 )
・勝草橋、説明版(藤枝1丁目 )
・川除地蔵尊堂(藤枝2丁目2-13 )
・川除地蔵2、馬頭観音、
・出雲大社分院(藤枝2丁目1-33 )
・手洗石、常夜燈、石、
・正定寺(藤枝2丁目3-27 )
・西光寺(藤枝3丁目10-37 )
・月見里神社(藤枝3丁目10⁻24 )
・神明神社(藤枝3丁目4-4 )
・日本キリスト教団(藤枝3丁目12-5 )
・藤枝カトリック教会(茶町1丁目2-51 )
・宗伝寺(藤枝1丁目4-27 )
・満蔵寺(稲川1丁目3-14 )
・洞雲寺(藤枝5丁目2-28 )
・若一王子神社(藤枝5丁目2 )
・鬼岩寺(藤枝3丁目16‐⒕ )
・黒犬神社(藤枝3丁目16-14 )
・萬照寺(原1287⁻6 )
・八幡宮(音羽町5丁目2 )
・茶町(茶町1~4丁目 )
・護国殿(茶町1丁目1-33 )
・西雲寺(音羽町3丁目17-9 )
・清水寺(原 )
~~~☆志太、瀬古地区:茶町の川向い~~~
・秋葉常夜灯、石仏、勝草橋説明版、(志太3丁目3-18 )
・田沼街道入口、史蹟、説明版(志太4丁目11 )
・進雄神社(志太4丁目4 )
・龍王神社(志太4丁目10-19 )
・葺中観音堂(志太4丁目6-17 )
・薬師堂(志太3丁目15-17 )
・金比羅公園、金毘羅神社、天満宮(志太3丁目19 )
・観音寺(瀬古1丁目2-1 )
・秋葉神社(瀬古1丁目2-1 )
・進雄神社(瀬古1丁目12-1 )
・志太温泉、旅館元湯(志太598⁻1⁻1 )、潮生館(志太600⁻2⁻2)
~~~~~~
・延命地蔵尊堂(堀之内929 )
・円応教(堀之内334⁻1 )
・東国寺(堀之内201 )
・龍雲寺(堀之内302₋2 )
・堀之内神社(堀之内589⁻9 )
・京塚(経塚)山245.3m(堀之内 )
~~~☆谷稲葉地区:堀之内の西~~~
・延命地蔵堂(谷稲葉429⁻5 )
・慈光院(谷稲葉931⁻3 )
・谷稲葉神社(谷稲葉720 )
・中世東海道(谷稲葉 )
・心岳寺(谷稲葉1591 )
・双子山(谷稲葉 )
~~~~~~
・寺島神社(寺島906⁻8 )
・薬師堂(寺島366 )
・大井神社(助宗1873 )
・円通院(助宗1787 )
・高山寺(瀬戸ノ谷1946、紺屋、 )
・普門寺(瀬戸ノ谷263、萩間、本郷 )
・本郷神社(瀬戸ノ谷1175₋2、本郷 )
・烏帽子形山392.7m(本郷、助宗、西方)
~~~☆滝沢、滝之谷地区:瀬戸谷の西北~~~
・八坂神社(滝沢1325 )
・竜雲寺(滝沢1498 )
・上滝沢地蔵堂(滝沢2669⁻1 )
・城山(滝之谷 )
・津島神社(滝之谷12212 )
・桧峠(滝沢、桧峠 )
・菩提山(滝沢瀬戸ノ谷 )
~~~~~~
・玉林寺(瀬戸ノ谷5874 )
・津島神社(瀬戸ノ谷12935 )
・びく石牧場(瀬戸ノ谷5658 )
・峠(瀬戸ノ谷 )
・津島神社(瀬戸ノ谷7405、市之瀬 )
多分、旧髙根山登山道開始点。
・びく石登山道(市之瀬 )
・高尾山(瀬戸ノ谷 )
・ 神社(蔵田 )
・鼻崎の大杉(蔵田 )
・高根山、石仏(蔵田 )
・高根白山神社、髙根山831m、東海自然歩道(蔵田 )
・津島神社(瀬戸ノ谷10947、大久保 )
・宇嶺の滝(瀬戸ノ谷、市之瀬 )
2016年09月22日
笹間街道:静岡市黒俣~島田市笹間
笹間街道
・情報提供呼びかけ
今後、2016年11月以降、笹間街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
静岡市黒俣と島田市川根の笹間を結んでいた道である。峠は市境の笹間峠である。起点は黒俣の盤龍寺と3㎞奥の東向寺の2か所である。東向寺の方がより近代に近いルートである。笹間峠を越えると川根の日掛に出て、笹間川沿いの集落に沿って下ったようだ。ただ近代以前は川沿いに集落は少なく、焼き畑農業で山の中腹以上に居住していたと思われるので、川よりだいぶ上に歩く道があったはずだ。
☆☆☆~~~黒沢川沿い~~~
黒俣の遺物類から紹介する。
・九能尾(静岡市葵区黒俣、九能尾 )
・盤龍寺(静岡市葵区黒俣1105、九能尾 )
・大渡神社(静岡市葵区黒俣1105、久能尾 )
・石仏( )
・船水弘法大師堂(黒俣1374、上和田 )
・八幡神社、白髭神社(黒俣1590、 中村 )
・東向寺(黒俣1886、中村 )
・石仏(黒俣1886、中村 )
東向寺から笹間峠に向かい上りだすとすぐにある。
・イチョウの木、神社(黒俣2181、坂野 )
坂野の県道沿いにある。
・石仏(黒俣 )
坂野と清笹峠の県道途中にある。
・清笹峠(黒俣 )
静岡市と藤枝市の境界、
・石塔( )
・笹間峠(静岡市黒俣、島田市笹間上 )
~島田市川根、笹間上~
・笹間街道(島田市笹間上 )
・林道(島田市笹間上日掛~静岡市葵区峰山)
・日掛、日限地蔵尊(笹間上2794、日掛 )
・久野地蔵尊(笹間上2629、久野 )
・久円寺(笹間上2613、久野 )
・加賀沢の滝(笹間上 )
・林道(笹間上下二俣~川根本町壱町河内 )
・無双連山1008.3m、徳山城、高山 (笹間上 )
・二俣八幡神社(笹間上1825、二俣 )
・登福寺(笹間上729、石上 )
・八幡神社(笹間上373、出本 )
・大井神社(笹間上、竹島 )
・ (笹間 )
・ (笹間 )
・一之宮神社(笹間下1176、三並 )
・龍光院(笹間下1064、三並 )
・白山神社(笹間下622、日向 )
・春日神社(笹間下396、桑ノ山 )
・笹間川ダム(笹間渡 )
・ (笹間渡 )
・情報提供呼びかけ
今後、2016年11月以降、笹間街道やその他の街道を調べようと思っていますが、何か街道沿いに関する情報がありましたら、教えていただきたいので事前資料を公開します。以下の項目に沿うこと、沿わないこと等なんでもお知らせくだされば、とても助かりますし、他の方たちにも有益だと思います。
・前文
静岡市黒俣と島田市川根の笹間を結んでいた道である。峠は市境の笹間峠である。起点は黒俣の盤龍寺と3㎞奥の東向寺の2か所である。東向寺の方がより近代に近いルートである。笹間峠を越えると川根の日掛に出て、笹間川沿いの集落に沿って下ったようだ。ただ近代以前は川沿いに集落は少なく、焼き畑農業で山の中腹以上に居住していたと思われるので、川よりだいぶ上に歩く道があったはずだ。
☆☆☆~~~黒沢川沿い~~~
黒俣の遺物類から紹介する。
・九能尾(静岡市葵区黒俣、九能尾 )
・盤龍寺(静岡市葵区黒俣1105、九能尾 )
・大渡神社(静岡市葵区黒俣1105、久能尾 )
・石仏( )
・船水弘法大師堂(黒俣1374、上和田 )
・八幡神社、白髭神社(黒俣1590、 中村 )
・東向寺(黒俣1886、中村 )
・石仏(黒俣1886、中村 )
東向寺から笹間峠に向かい上りだすとすぐにある。
・イチョウの木、神社(黒俣2181、坂野 )
坂野の県道沿いにある。
・石仏(黒俣 )
坂野と清笹峠の県道途中にある。
・清笹峠(黒俣 )
静岡市と藤枝市の境界、
・石塔( )
・笹間峠(静岡市黒俣、島田市笹間上 )
~島田市川根、笹間上~
・笹間街道(島田市笹間上 )
・林道(島田市笹間上日掛~静岡市葵区峰山)
・日掛、日限地蔵尊(笹間上2794、日掛 )
・久野地蔵尊(笹間上2629、久野 )
・久円寺(笹間上2613、久野 )
・加賀沢の滝(笹間上 )
・林道(笹間上下二俣~川根本町壱町河内 )
・無双連山1008.3m、徳山城、高山 (笹間上 )
・二俣八幡神社(笹間上1825、二俣 )
・登福寺(笹間上729、石上 )
・八幡神社(笹間上373、出本 )
・大井神社(笹間上、竹島 )
・ (笹間 )
・ (笹間 )
・一之宮神社(笹間下1176、三並 )
・龍光院(笹間下1064、三並 )
・白山神社(笹間下622、日向 )
・春日神社(笹間下396、桑ノ山 )
・笹間川ダム(笹間渡 )
・ (笹間渡 )
2016年07月28日
静岡市用宗周辺
静岡市 用宗 周辺
‘13 ’14 6、7月
・前文
だいぶ不完全な文書なうえ、所々しか調べていない基礎資料ですが、今後調べていくということで、一旦掲載します。
またブログに保存することで、手持ちのパソコンや記憶媒体がすべて破壊されても、バックアップとして利用できるからです。
◎大雲寺 昭和六十三年
○城山観音菩薩大悲閣
・庚申供養塔 享和二壬戌1802
・庚申:元禄拾三庚辰五月廿八日 奉納建立庚申、
・線刻画:佛:座像、
・新:石仏多数、
・祠:地蔵 安永七戌年、・如意輪観世音菩薩 廿七番、
・新:燈籠2、
・新:仁王像:阿形像、吽形像、
・忠霊塔、
・新:南無釈迦牟尼佛、
・新:地蔵、
・新:六地蔵、
・鐘楼、
・石祠、
○熊野神社跡地
・石鳥居;明治二十八年、
・本殿:廃屋、
○八幡神社跡地
・石鳥居:昭和二年、
・手洗石:昭和七年、
・石燈籠:笠部、
・本殿、拝殿:廃屋、
○石部神社:静岡市石部51-⒑、
祭神:天照大神あまてらすおおみかみ、祭日:10月16日、内社:津島神社:すさのうのみこと素戔嗚命、白髭神社:猿田彦命、山神社:おおやまつみのみこと大山祇命、由緒:天明元年再建とあるが、御鎮祭は近隣に古墳七基の発見や、古代から大崩海道の沿岸にあり、遥に古い時代と思われる。古くは天白社と称し、明治初年に現在の社号に改められ、明治八年村社に列した。境内社の津島神社は素戔嗚神を祀り、疫病除けの神として崇められる。氏子の信仰は今も往時も変わりなく、例祭、歳日祭、初午祭、祇園祭、七五三祭等、古くからの伝統と神社の護持発展に積極的な努力と奉仕が続けられている。昭和52年3月13日、大崩山腹「コツサ沢」鎮座の豊漁航海安全の神として崇められた白髭神社:猿田彦命と、高草山系石部「大ニヨウ」鎮座の山神社:大山祇命の両社を、遠隔地で祭祀参詣も意の如くならず、氏子の総意により本社の相殿に遷宮鎮祭した。昭和21年7月30日宗教法人令による届け出をし、昭和27年7月23日宗教法人令により、宗教法人「石部神社」の設立を登記した。静岡県神社庁神社等級規定九級社である。平成22年12月吉日。静岡市神社名鑑より作成。
・鎮魂:昭和四十七年、Ω、
・石鳥居:文化八辛未弐月吉日、
・石鳥居:大正十四年、
・石鳥居:
・猿田彦大神:大正拾四乙丑年、
・力石
・手洗石
・石塔:宝永七寅年、
・祠
・辻:祠、
○寶珠院
・地蔵堂
・新:六地蔵
・板碑
・馬頭観音菩薩
・庚申供養塔
・庚申供養塔:享保十二未年
・庚申塔:昭和五十五年
・南無阿弥陀佛
・手洗石:呉服町四丁目油屋
・祠:
・堂
・井戸ポンプ
・新:萬霊塔
○熊野神社
・城山列士供養塔
・地蔵
・石鳥居:昭和三十二年
・玉垣
・石燈籠2,2,2:文久三
・船の碇⚓、
・祠
・石塔:明治十七申年、
・御神燈:安政六未、
・石燈籠:奉納八幡宮:寛政九稔
・狛犬2、2、
・城山農道完成記念碑:平成三年
・妙見坂 五十四
・丸石
・石燈籠2:昭和三年、
・祠跡:廃
○持舟城
・説明版:築城年代不明、戦国時代の今川氏時代には築かれていたと考えられる。江戸時代の古絵図によると当地は、駿河湾に面して東・北に深く入り江が形作られた天然の良港だった。現在の静岡市駿河区用宗の地名は湊(港)を意味する「持舟」が転化したものと云われ、今も昔も漁業と深い関係を持っている。今川氏はここを水軍の拠点とすると共に西方、日本坂から駿府に侵入する敵対勢力を防ぐ城砦としても利用した。城跡は、頂上広場(標高76m)が本丸(本曲輪)、南西側の窪地に大堀切、井戸跡(曲輪)があり、その南側に二ノ丸(二の曲輪)、本丸の北側には腰曲輪があった。北側の城の下は沼地と深田が広がっていた。南側は海に近く、船溜まりと蔵屋敷があり、湊(港)と平山城の条件が整っていた。長い年月を経た今も、遺構はそのままの形で残っている。
築城から廃城までの間に、今川、武田、徳川氏によって3度の攻防戦が行われ、数百もの将兵が討死する記録が残ることは静岡周辺の他の城砦に比べても例がなく、この城の戦略的価値がいかに高かったかを物語っている。今川氏の城主「一宮出羽守随波斎いちのみやでわのかみずいはさい」は麓の青木の森に、武田氏の城主「向井伊賀守正重むかいいがのかみまさしげ」は興津清見寺に手厚く祀られている。
最後の城主、武田氏の「朝比奈駿河守」は徳川軍に城を明け渡し、多くの将兵は城下に落ち延びて生涯を全うした。やがて持舟城は徳川氏のもとで廃城となった。
後に向井氏の子孫が城跡に観音像を立てて「正重」の霊を祀った。観音像は阿耨観音あのくかんのん(マリア観音)と呼ばれ、今は用宗駅北の大雲寺に安置される。村民たちは七年に一度、御開帳を催し、将兵の慰霊と現世の平和を祈る。
*耨=ドウ、ヌ、くさぎる、のぞく。
・持舟城趾由来略誌:説明版:
今川家は代々駿河国の守護大名として駿府に在り、周辺警備の出城として、関口刑部親長に持舟城を守らせていた。この関口の娘瀬名姫(後の築山殿)と徳川家康は弘治元年結婚。この政略結婚が後年家康の生涯にとって痛恨の惨事になるとは知る由もなかった。永禄三年五月今川義元は桶狭間において織田信長の急襲に遭い敗死するや今川家の勢力は急速に退潮した。川中島で矛を収めた武田信玄は上洛の進路を東海道に求め、永禄十一年末、駿河に侵攻して、持舟城を攻略、城主一宮出羽守は兵と共に討死、城は武田勢水軍の支配下に入った。三河に勃興し遠州に勢力を拡大した徳川勢と度重なる攻防戦を繰り返し、なかでも天正七年九月の戦は最も残虐であった。それは織田信長に今川と結び謀反の疑いをかけられた家康が今川方の血を引く正室築山殿を自らの手の者に殺させ、また長子信康は二俣城中で自刃し果てた。我が妻子の無念を思う家康のやるところなきうっ憤の吐け場となり、激闘壮絶を極め武田方の城将向井伊賀守正重、甥の兵庫叔父伊兵政綱長男政勝ら悉く悲惨な討死を遂げた。後日家康は非を悔い向井叔父甥を興津清見寺に葬り、今も古式蒼然とした墓塔が同寺にある。天正八年二月再び武田氏の領有となり朝比奈駿河守が城主となった。攻防戦の終盤は天正十年二月徳川家康は織田信長と共に甲州征伐を決して浜松城を進発し、遠州、駿河の各城を抜き持舟城に迫るや朝比奈駿河守は情勢不利とみて戦わずして城を明け渡し退却あっけない幕切れとなった。家康は間もなく廃城としたので戦国ロマンを秘めた持舟城の歴史的使命は終わった。向井正重の次男正綱はたまたま城外にあって生き残り、本多作左衛門の手の者となり徳川家に仕えて船手頭となり、その四代目の子孫正興が長崎奉行勤番の折り、城山の頂上に観音像を建立した。近年麓の大雲寺に安置され直した。向井家は以後代々重臣として繁栄し、其の後裔は東京都新宿区に現住している。
・城山周辺の野鳥:
・説明版:周辺で見られる10種の野鳥。メジロ、エナガ、ウグイス、ヤマガラ、カワセミ、シジュウカラ、コゲラ、ハクセキレイ、アオバト、イソヒヨドリ、
・城山周辺の蝶:
・説明版:城山で見られる蝶の種類は25種だが、そのうち12種紹介する。
アゲハ、ジャコウアゲハ、ゴマダラチョウ、ルリタテハ、カラスアゲハ、モンキアゲハ、ツマクロヒョウモン、コミスジ、アオスジアゲハ、アオバセセリ、クロコノマチョウ、アサギマダラ、
・府中道:古来よりの大崩街道:
・説明版:當目山坂口より左につき大谷に入登れば、右は滄海に臨み、左に高草の麓の村里瀬戸川を眼下に見て勝景なり。ここは長むねと云處也。爰より数十歩過て切通あり。左の高き丘に大日堂を置、西山下は小濱村也。この切通を越れば山下海岸谷々に山畠あり。高より臨むに海岸に平地を見る。これ小濱村の蕉地也。其内に森二ヶ所あり。洞口の両處には大なる巌海中に聳立、高さ百丈餘。これに並び立つ巌五十丈餘。往昔は此巨巌の上に松一樹ありて塔之松と呼。後世枯失たり。是等を右に見て、切通より山の腰を廻り下る坂あり。七曲と云。行々麗の海岸に下る。此處を垢離取場(府在村里願望ある者、必爰に來て垢離す)と云。ここより石部村の地に隷。一軒屋の茶店(一軒屋)あり。是より礒邊巨巖石の閒を通ふ。波荒き時は通がたし。此際凡十餘町許、大崩と呼。左手の山は岩石聳えて突出、常に岩石轉倒の怖あり。右手波浪に衣をひたし、嶮難の閒道岩上より足を失て、刀劒の如くなる巌の稜に轉倒せしむとし、唯戦々兢々(恐々)たるのみ。大人君子の通べき路次には非ず。此所古へは石渡りと云と也。ここを通て石部の村落に至る。凡當目より石部へ一里餘、持舟廣野川原にかかり、国府に至る行程總て三里と云。
(補記)東照傳に、天正六1578年大神君由比蒲原に討向むとし給ひ、田中城を左に見て濱際を押通り、同八月廿二日先陣は上原清水に着す。御本陣は當目に居させ給ふと云は、則此濱道筋を通りし也。其頃は今よりは路次も廣かりしにや。『駿國雑誌一 六之巻より』四十九巻 安部正信 天保十三年1842編集
・供養塔:祠:向井伊賀守正重 天正七年九月十九日
由来記:この供養塔の向背地の城山にあった持舟城は、永禄元亀天正年間1568~1582戦国争乱の最中に生まれ、今川武田徳川など戦国大名の軍兵が互いに攻防戦を繰り広げ、数百の将兵が城と運命を共にした。ときの城将向井伊賀守正重他壮烈な散華を遂げた将士の霊を祀った。
‘13 ’14 6、7月
・前文
だいぶ不完全な文書なうえ、所々しか調べていない基礎資料ですが、今後調べていくということで、一旦掲載します。
またブログに保存することで、手持ちのパソコンや記憶媒体がすべて破壊されても、バックアップとして利用できるからです。
◎大雲寺 昭和六十三年
○城山観音菩薩大悲閣
・庚申供養塔 享和二壬戌1802
・庚申:元禄拾三庚辰五月廿八日 奉納建立庚申、
・線刻画:佛:座像、
・新:石仏多数、
・祠:地蔵 安永七戌年、・如意輪観世音菩薩 廿七番、
・新:燈籠2、
・新:仁王像:阿形像、吽形像、
・忠霊塔、
・新:南無釈迦牟尼佛、
・新:地蔵、
・新:六地蔵、
・鐘楼、
・石祠、
○熊野神社跡地
・石鳥居;明治二十八年、
・本殿:廃屋、
○八幡神社跡地
・石鳥居:昭和二年、
・手洗石:昭和七年、
・石燈籠:笠部、
・本殿、拝殿:廃屋、
○石部神社:静岡市石部51-⒑、
祭神:天照大神あまてらすおおみかみ、祭日:10月16日、内社:津島神社:すさのうのみこと素戔嗚命、白髭神社:猿田彦命、山神社:おおやまつみのみこと大山祇命、由緒:天明元年再建とあるが、御鎮祭は近隣に古墳七基の発見や、古代から大崩海道の沿岸にあり、遥に古い時代と思われる。古くは天白社と称し、明治初年に現在の社号に改められ、明治八年村社に列した。境内社の津島神社は素戔嗚神を祀り、疫病除けの神として崇められる。氏子の信仰は今も往時も変わりなく、例祭、歳日祭、初午祭、祇園祭、七五三祭等、古くからの伝統と神社の護持発展に積極的な努力と奉仕が続けられている。昭和52年3月13日、大崩山腹「コツサ沢」鎮座の豊漁航海安全の神として崇められた白髭神社:猿田彦命と、高草山系石部「大ニヨウ」鎮座の山神社:大山祇命の両社を、遠隔地で祭祀参詣も意の如くならず、氏子の総意により本社の相殿に遷宮鎮祭した。昭和21年7月30日宗教法人令による届け出をし、昭和27年7月23日宗教法人令により、宗教法人「石部神社」の設立を登記した。静岡県神社庁神社等級規定九級社である。平成22年12月吉日。静岡市神社名鑑より作成。
・鎮魂:昭和四十七年、Ω、
・石鳥居:文化八辛未弐月吉日、
・石鳥居:大正十四年、
・石鳥居:
・猿田彦大神:大正拾四乙丑年、
・力石
・手洗石
・石塔:宝永七寅年、
・祠
・辻:祠、
○寶珠院
・地蔵堂
・新:六地蔵
・板碑
・馬頭観音菩薩
・庚申供養塔
・庚申供養塔:享保十二未年
・庚申塔:昭和五十五年
・南無阿弥陀佛
・手洗石:呉服町四丁目油屋
・祠:
・堂
・井戸ポンプ
・新:萬霊塔
○熊野神社
・城山列士供養塔
・地蔵
・石鳥居:昭和三十二年
・玉垣
・石燈籠2,2,2:文久三
・船の碇⚓、
・祠
・石塔:明治十七申年、
・御神燈:安政六未、
・石燈籠:奉納八幡宮:寛政九稔
・狛犬2、2、
・城山農道完成記念碑:平成三年
・妙見坂 五十四
・丸石
・石燈籠2:昭和三年、
・祠跡:廃
○持舟城
・説明版:築城年代不明、戦国時代の今川氏時代には築かれていたと考えられる。江戸時代の古絵図によると当地は、駿河湾に面して東・北に深く入り江が形作られた天然の良港だった。現在の静岡市駿河区用宗の地名は湊(港)を意味する「持舟」が転化したものと云われ、今も昔も漁業と深い関係を持っている。今川氏はここを水軍の拠点とすると共に西方、日本坂から駿府に侵入する敵対勢力を防ぐ城砦としても利用した。城跡は、頂上広場(標高76m)が本丸(本曲輪)、南西側の窪地に大堀切、井戸跡(曲輪)があり、その南側に二ノ丸(二の曲輪)、本丸の北側には腰曲輪があった。北側の城の下は沼地と深田が広がっていた。南側は海に近く、船溜まりと蔵屋敷があり、湊(港)と平山城の条件が整っていた。長い年月を経た今も、遺構はそのままの形で残っている。
築城から廃城までの間に、今川、武田、徳川氏によって3度の攻防戦が行われ、数百もの将兵が討死する記録が残ることは静岡周辺の他の城砦に比べても例がなく、この城の戦略的価値がいかに高かったかを物語っている。今川氏の城主「一宮出羽守随波斎いちのみやでわのかみずいはさい」は麓の青木の森に、武田氏の城主「向井伊賀守正重むかいいがのかみまさしげ」は興津清見寺に手厚く祀られている。
最後の城主、武田氏の「朝比奈駿河守」は徳川軍に城を明け渡し、多くの将兵は城下に落ち延びて生涯を全うした。やがて持舟城は徳川氏のもとで廃城となった。
後に向井氏の子孫が城跡に観音像を立てて「正重」の霊を祀った。観音像は阿耨観音あのくかんのん(マリア観音)と呼ばれ、今は用宗駅北の大雲寺に安置される。村民たちは七年に一度、御開帳を催し、将兵の慰霊と現世の平和を祈る。
*耨=ドウ、ヌ、くさぎる、のぞく。
・持舟城趾由来略誌:説明版:
今川家は代々駿河国の守護大名として駿府に在り、周辺警備の出城として、関口刑部親長に持舟城を守らせていた。この関口の娘瀬名姫(後の築山殿)と徳川家康は弘治元年結婚。この政略結婚が後年家康の生涯にとって痛恨の惨事になるとは知る由もなかった。永禄三年五月今川義元は桶狭間において織田信長の急襲に遭い敗死するや今川家の勢力は急速に退潮した。川中島で矛を収めた武田信玄は上洛の進路を東海道に求め、永禄十一年末、駿河に侵攻して、持舟城を攻略、城主一宮出羽守は兵と共に討死、城は武田勢水軍の支配下に入った。三河に勃興し遠州に勢力を拡大した徳川勢と度重なる攻防戦を繰り返し、なかでも天正七年九月の戦は最も残虐であった。それは織田信長に今川と結び謀反の疑いをかけられた家康が今川方の血を引く正室築山殿を自らの手の者に殺させ、また長子信康は二俣城中で自刃し果てた。我が妻子の無念を思う家康のやるところなきうっ憤の吐け場となり、激闘壮絶を極め武田方の城将向井伊賀守正重、甥の兵庫叔父伊兵政綱長男政勝ら悉く悲惨な討死を遂げた。後日家康は非を悔い向井叔父甥を興津清見寺に葬り、今も古式蒼然とした墓塔が同寺にある。天正八年二月再び武田氏の領有となり朝比奈駿河守が城主となった。攻防戦の終盤は天正十年二月徳川家康は織田信長と共に甲州征伐を決して浜松城を進発し、遠州、駿河の各城を抜き持舟城に迫るや朝比奈駿河守は情勢不利とみて戦わずして城を明け渡し退却あっけない幕切れとなった。家康は間もなく廃城としたので戦国ロマンを秘めた持舟城の歴史的使命は終わった。向井正重の次男正綱はたまたま城外にあって生き残り、本多作左衛門の手の者となり徳川家に仕えて船手頭となり、その四代目の子孫正興が長崎奉行勤番の折り、城山の頂上に観音像を建立した。近年麓の大雲寺に安置され直した。向井家は以後代々重臣として繁栄し、其の後裔は東京都新宿区に現住している。
・城山周辺の野鳥:
・説明版:周辺で見られる10種の野鳥。メジロ、エナガ、ウグイス、ヤマガラ、カワセミ、シジュウカラ、コゲラ、ハクセキレイ、アオバト、イソヒヨドリ、
・城山周辺の蝶:
・説明版:城山で見られる蝶の種類は25種だが、そのうち12種紹介する。
アゲハ、ジャコウアゲハ、ゴマダラチョウ、ルリタテハ、カラスアゲハ、モンキアゲハ、ツマクロヒョウモン、コミスジ、アオスジアゲハ、アオバセセリ、クロコノマチョウ、アサギマダラ、
・府中道:古来よりの大崩街道:
・説明版:當目山坂口より左につき大谷に入登れば、右は滄海に臨み、左に高草の麓の村里瀬戸川を眼下に見て勝景なり。ここは長むねと云處也。爰より数十歩過て切通あり。左の高き丘に大日堂を置、西山下は小濱村也。この切通を越れば山下海岸谷々に山畠あり。高より臨むに海岸に平地を見る。これ小濱村の蕉地也。其内に森二ヶ所あり。洞口の両處には大なる巌海中に聳立、高さ百丈餘。これに並び立つ巌五十丈餘。往昔は此巨巌の上に松一樹ありて塔之松と呼。後世枯失たり。是等を右に見て、切通より山の腰を廻り下る坂あり。七曲と云。行々麗の海岸に下る。此處を垢離取場(府在村里願望ある者、必爰に來て垢離す)と云。ここより石部村の地に隷。一軒屋の茶店(一軒屋)あり。是より礒邊巨巖石の閒を通ふ。波荒き時は通がたし。此際凡十餘町許、大崩と呼。左手の山は岩石聳えて突出、常に岩石轉倒の怖あり。右手波浪に衣をひたし、嶮難の閒道岩上より足を失て、刀劒の如くなる巌の稜に轉倒せしむとし、唯戦々兢々(恐々)たるのみ。大人君子の通べき路次には非ず。此所古へは石渡りと云と也。ここを通て石部の村落に至る。凡當目より石部へ一里餘、持舟廣野川原にかかり、国府に至る行程總て三里と云。
(補記)東照傳に、天正六1578年大神君由比蒲原に討向むとし給ひ、田中城を左に見て濱際を押通り、同八月廿二日先陣は上原清水に着す。御本陣は當目に居させ給ふと云は、則此濱道筋を通りし也。其頃は今よりは路次も廣かりしにや。『駿國雑誌一 六之巻より』四十九巻 安部正信 天保十三年1842編集
・供養塔:祠:向井伊賀守正重 天正七年九月十九日
由来記:この供養塔の向背地の城山にあった持舟城は、永禄元亀天正年間1568~1582戦国争乱の最中に生まれ、今川武田徳川など戦国大名の軍兵が互いに攻防戦を繰り広げ、数百の将兵が城と運命を共にした。ときの城将向井伊賀守正重他壮烈な散華を遂げた将士の霊を祀った。
2016年06月05日
金谷街道(静岡県島田市、菊川市、牧之原市)
・前文
*住所地は目的地を探すためのものなので、分からない時は附近のものを指し示すことが多い。
*未発見や誤解曲解している箇所が多いと思われるので、コメントをいただくか、その人なりの発表方法で公表していただけると、ありがたいです。
特に牧之原台地上での発見できた石造物の少なさは、気になるので、まだたくさん未発見物があると思われます。公表されることで保存へ弾みがつくことでしょう。
~金谷街道(静岡県島田市、菊川市、牧之原市)~
現地調査:’16 4/9,10,16
~『定本静岡県の街道』より~
金谷街道は牧之原市仁王辻から島田市金谷宿までの道である。しかし今回は変則版として仁王辻から島田市金谷の諏訪原城や島田市菊川の中山新道、遠江三十三所観音霊場24番から25番への霊場道に接続するまでを紹介する。
仁王辻附近の牧之原小学校・中学校門前の東照宮からスタートする。
○東照宮神社(牧之原市東萩間2082⁻13)
・説明:徳川家康公座像:牧之原市指定 工芸品:1869明治2年徳川の家臣、福井某等20名が牧之原に移住の時江戸から持ってきて、菊川町沢水加に神社を建てて御神体とし、1942昭和17年に現在の位置に移された。座像の開眼主は日善、日宗吉、大仏師、尾崎義定と書かれている。
・コンクリ石柱2、・狛犬2、・手洗石:大正四、・石鳥居:昭和十七年、・?基準点:測量用、
ちょうど学校の正門前に神社があり、駐車場もないので正門横に乗り付け隣の神社をうろちょろすることになるが、何かしらの学校行事があるらしく、校舎の曲がり角で先生らしきが出入りする自動車を案内している。その先生が明らかに不審者として私の方に注目しているので、はやいとこ調べてすたこらさっさと逃げてきた。毎度のことながら私は不審者です。
次は同じ地区の八十原観音を見たいので、学校前を北に出て右折(東)し300m東進し、右折(南)し400m南進する。
○八十原観音(牧之原市東萩間、八十原2092)
・堂、・石碑:礎2000、・手洗石、・手洗石:明治九子年、・献燈2、、・フジ棚、
再度牧之原小学校前の交差点に戻る。北西の丸顔橋を渡り交差点に出る。ここに馬頭が祀られている。
・馬頭観音:明治三十二年五月立承(東萩間、仁王辻2360⁻1)
1.4㎞北上する。現在沢水加から上ってくる県道掛川榛原線がある。
この坂道の途中に戦争遺跡がある。下りだして1.1㎞、上りだして300mである。
・大井航空隊洞窟(菊川市沢水加)
県道から沢沿いに30m歩くと洞窟がある。どうも防空壕として掘られたようだ。牧之原台地の布引原には大井航空隊基地があった。
再度国道473号線に戻る。国道を北上するか、1本東側(100m先)の道に出る。600m北上して矢崎部品工場:布引原、矢崎206⁻1とスーパーマーケット:220⁻3の間で右折する。種苗管理センター金谷農場と谷地の間の道に右左折を繰り返して出る。出るとそこからは住宅が切れて茶畑の細尾根道を南東に道なりに500m進む。
左に標識:勝間田城跡→があり、左折(東)し茶畑を200m進む。ここで車は進めない。あとは歩きで進む。300m山道を下っていくと城跡を示す標識が出てくる。
○勝間田城跡(牧之原市勝田2160⁻1)
・説明:静岡県指定史跡:勝間田氏は、当地方を拠点とする豪族で、勝間田平三成長は鎌倉幕府の御家人となり、その子孫の長清は「夫木和歌抄」を編纂している。元弘の乱1331には、河内(大阪府)の赤坂城、千早城の攻防に一族が攻撃側と守備側の両陣営に分かれて参戦していることが記録に見える。
室町期に入り、将軍の直属軍として応永の乱1399や永享の乱1439に活躍し、応仁の乱が起るや今川氏と対立し、今川義忠の猛攻の前に1476文明8年ついに落城、一族は四散した。一説には現在の御殿場市周辺に移り住んだと伝えられる。
応永年間に勝間田定長が築城したと推定されているこの城は、中世の代表的山城で、牧之原台地に連なる尾根を巧みに利用して曲輪、土塁、堀切が設けられ、南東部の尾根には他の城跡に例を見ない鋸状の堀切が見事に残っている。文明8年の落城後、この城が再び使われたとする記録は見当たらないが、遺構からはその後に手が加えられた形跡が認められる。
・説明:勝間田氏について:勝間田氏は平安末期から室町中期まで約340年間この地方を領有した豪族である。勝間田氏が史上に登場してくるのは『保元物語』からである。
『保元物語上』に
「義朝甲の緒をしめ、即うちいでけるが、義朝馬をひかえて紅の扇を開つかいて申されけるは………相随ふ輩は誰ぞ………遠江國には横地、勝田、井八郎、駿河國には………とあり、時は保元元年1156のことである。」
平治の乱後、『吾妻鏡』に勝田平三郎成長かつまたへいさぶろうしげながというものがでてくる。成長は治承5年1181壬2月安田義定の招集に応じて史上に現れ鎌倉幕府の御家人やまた玄蕃助げんばのすけなどにもなり、以来建久6年1195まで15年間活躍した。その後健保4年1216源実朝が送った宋使節団の一行に勝田兵庫頭かつまたひょうごのかみが参加している。
建長2年1250閒院殿造営のため京に供出される材木等の分担目録の中に勝田兵庫助かつまたひょうごのすけの名が見える。鎌倉末期に参議冷泉為相の門下となった勝田長清は17300余首の歌数を収録した『夫木和歌抄』を編纂し、「下萩もかつ穂にいづる夕露に宿かりそむる秋の三日月」「置く露は袖にこぼれて夕暮れの萩の上葉に残るあきかぜ」等の秀歌を残している。
南北朝期に入ると、勝間田氏は再び史上に現れる。元弘元年1331足利尊氏に従った勝間田彦太郎入道や赤坂城の攻防で有名な楠正成に従った勝田左エ門尉直幸等が見え、南朝方、北朝方の双方に分かれて活躍していたことが分かる。正平3年1348足利尊氏は諏訪神社の笠懸の神事を行い射手に勝田能登守佐長、勝田二郎丞長直等がこれに参加している。勝田氏は足利義満の代になると、次第に中央に進出し奉公衆となり、文中元年1372勝田三河□太郎や勝田修理亮は、将軍の近習となり幕府の役人として活躍した。
室町初期の応永の乱で今川泰範の軍に加わった勝間田遠江守は、丹波の追分の合戦で討死にしている。応仁の乱で全国的に動乱化した中で、国人として生き残る道を探していた勝間田修理亮は、横地氏とともに今川義忠軍と戦い敗れ、この結果勝間田一族は四散した。
その後明応5年1496勝田播磨守が志戸呂の城主鶴見因幡守とともに城飼郡松葉城を攻め落としたが、これより後、勝間田一族は史上から姿を消してしまう。このように340年間もの長きにわたって当地を根拠地として活躍した勝間田氏は、中世の末、当地から姿を消してしまうが、敗亡当時の城と思われる勝間田、湯日、穴ヶ谷、滝堺、飯田等の城跡の他榛原町道場の清浄寺の裏手の供養塔や坂口の石雲院、中の長興寺また桃原の瑞昌院等には今も勝間田氏の位牌が残されている。
・説明:礎石建物:自然石の平坦面を表にして据え、これに柱を立てた建物。縄文時代以来の竪穴住居建物とは違い、寺院や宮殿等長年月の保存を必要とするものに限って、礎石の上に柱を立てる建築法が用いられた。
二ノ曲輪には、11棟の掘立柱建物跡と1棟の礎石建物跡が確認されている。中世の山城で、礎石を持った建物が確認されたのは非常に珍しく、当時どのような用途に使われたのか興味あるが、礎石を使った理由として、床張りで重量物例えば、兵糧米等を収納していたことが考えられる。この建物の周りには、溝が廻り、出土物としては、すり鉢、青磁、白磁、染付、天目茶碗等種類、内容とも豊富な食器が発見されている。この建物は、勝間田城の兵糧庫または貯蔵庫等の用途に使われ、城の中でもとても重要な建物だったと考えられる。
・説明:掘立柱建物ほったてはしらたてもの:土台を設けないで、直接に地面を掘って柱を立てた簡単な建物。縄文時代から弥生時代を経て、古墳時代を過ぎ奈良、平安時代まで一般の住居の基本だった竪穴住居が、生活様式の変化から掘立柱建物に変わっていた。
勝間田城跡の建物は、掘立柱建物がほとんどで、二ノ曲輪には11棟の掘立柱建物跡が確認されている。1棟の規模は平均2間×3間で、柱穴の深さは40~50㎝、穴の直径は20~25㎝だ。建物跡を掘ると、当時使われていた皿や碗、擂鉢等の食器のかけらが沢山出てきた。また建物の周辺には鉄釘や鎹カスガイが出土し、当時掘立柱建物の周辺を垣根や塀等が囲み、建物と建物を隔てていたことが分かる。特に麻ひもに通された二十数枚の銅銭(中国銭)は、当時ここに居住していた人々の所持品できっと貴重品だったに違いない。人々の暮らしぶりを垣間見る一品だ。
・説明:掘立柱建物:この掘立柱建物跡は、東西3間(5.7m)×南北3間(4.2m)の規模を持つものだが、それほどがっしりした建物ではなく、屋根も草葺きと考えられる比較的簡単なものだ。土塁等の在り方から見て、西三ノ曲輪と「馬洗い場」との間に出曲輪方向からの出入口の存在が想定され、この出入口を守る見張小屋的なものではないかと考えられる。なお多量の炭化物や焼土の在り方から見て、この建物は火災を受けている可能性がある。
出土遺物は、土師質土器、陶磁器等が出土しているが、いずれも破片で、器形の分かる物はわずかだ。また銭貨(至大通宝)が4枚出土している。至大通宝は中国の元の時代のものであり、1310年からの鋳造とされる。これら勝間田城跡からの出土品は、牧之原市榛原郷土資料館に展示してある。
・石碑:城跡寄進の碑:故村松半之助氏は郷土の豪族勝間田氏の城跡の亡失破壊を惜しみ、これを後世に伝えようと大正12年私有地1反歩を勝間田村に寄附をした。これにより城跡の本曲輪が確保されたばかりでなく城跡保存の気運を生み永く郷土の史跡として伝えることができた。
・歌碑:藤原長清:下萩もかつ穂にいづる夕露に宿かりそむる秋の三日月:玉葉集巻十四雑一、
・石柱:勝間田城址:大正十三年、・献燈2:昭和五十年、・コンクリ手洗石、・祠:神社、・石碑:勝間田城跡:昭和六十一年、
・南曲輪、土塁、堀切、本曲輪、二ノ曲輪、三ノ曲輪、西三ノ曲輪、出曲輪、
再度矢崎部品工場前まで戻り国道473号線を600m北進する。
○西光寺(嶋956⁻3)
・きく地蔵:平成19年、
国道を100m北進する。途中で県道菊川吉田線を横断する。
○大国神社(嶋955)
・石鳥居:昭和三年、・鐘、・手洗石、・石柱、・コンクリ石柱:昭和十二年、・コンクリ石柱2、・献燈2、・石柱:横倒し、
国道を300m北進する。落合刃物とアイアンドエム(株)の間の道を右折し30m進む。
・馬頭観音3(切山2968⁻1)
刻字は磨滅して読めない。所在地は後記、高塚氏より知った。
国道に戻り100m北進する。左に狭い土道が見える。
・六尺道路:県道菊川吉田線の旧道(菊川市倉沢1706⁻3:高塚氏宅と1706⁻1:鈴木氏宅の間の道)
この道がどうも現在の県道菊川吉田線の旧道にあたるようだ。土道は300mほど続くが、その先で国道473号線バイパス用地になって消滅したようだ。以前は先で坂を下り、県道吉田大東線につながっていたようだ。高塚氏談。高塚氏に感謝いたします。
~~~県道菊川吉田線~~~
金谷街道は北進するが、ここで県道菊川吉田線を進む。国道473号線の交差点からスタートする。坂を800m下っていく。途中頭上を国道473号線バイパスの高架橋がよぎっていく。
右に上っていく廃道化したコンクリ石段がある。
・かつての、高野山弘法大師堂跡地(菊川市沢水加1406⁻33)
現在は移転したか廃止したかであるようだ。頭上は先ほどのバイパス高架橋である。
さらに100m下ると大きく左カーブする。ここにかつての六尺道路は下ってきたようだ。
更に300m西に進む。右(北)上に祠がある。
・祠:神(倉沢、下倉沢)
100m西に進む。右に祠がある。
・祠:馬頭観音か、布に覆われて姿が分からない(倉沢、下倉沢)
300m西に進む。左上に祠がある。
・石祠:道祖神、・献燈(倉沢、下倉沢)
道はこの先、吉沢を通過し、途中和田から沢水加に向かう県道とも交差し、菊川駅前に達するが、金谷街道の周辺ということでここまでにする。
~~~~~~
国道473号線六尺道路前に戻る。200m北進し、左(西)120m先に六本松の公園と集会所、そして神社がある。
・神社(菊川市倉沢、六本松698)
国道に戻り2㎞北進する。猪土居交差点を過ぎ70m進むと右に入る小道がある。猪土居公民館と公園があり、神社もある。
○津島神社(島田市金谷3509)
・コンクリ石柱2、・石鳥居、・手洗石:平成二年、
国道に戻り600m北進する。右折(東)し100m先に農業用水タンクがある。
・石碑:疎水:平成十年(島田市金谷3272⁻5)
国道に戻り、国道を渡り、北200m先を目指す。
○お茶の郷(金谷3149⁻1)
・小堀遠州式日本庭園、・御茶室、・茶関係資料室、レストラン、・土産物、
・説明:小堀遠州1579~1647は、京都御所や駿府城を始めとする、江戸幕府のかかわる主だった建築工事の作事奉行を勤めて活躍した。また茶人としてもよく知れレ、島田市金谷の志戸呂窯は、遠州が諸国に好み道具を焼かせた、いわゆる遠州七窯の一つである。
そのゆかりをもって、ここに小堀遠州が営んだ庭園と建築が復元され、遠州の「綺麗さび」の世界が合成的に再現されている。
大きな①中の島を築いた築地を中心におく庭園と②築地を隔てて塀沿いに設けられて、『伊勢物語』にちなむ⓷八つ橋の流れに、寛永11年1634遠州が後水尾院の仙洞御所の東庭に作庭した姿を復元する。自然と人工、直線と曲線といった、反響的な要素がここには鮮やかな対比の中に融和しており、また平安時代の王朝文化を憧憬する趣向豊かな構成に遠州の庭園の特色が示されている。⑤書院・⑥鎖の間・⑦茶屋・⑧数寄屋からなる茶室は、書院部分に遠州が親交していた松花堂昭乗のために建てた、京都石清水八幡宮滝本坊の書院を復元して組み込んでいる以外は伏見奉行を勤めた遠州が、寛永2年1625奉行屋敷に営んだ座敷の一部を復元している。書院・鎖の間・数寄屋という3様の茶室を連ねるのは、真・行・草の茶の湯を一体的に展開した遠州の茶を反映している。書院・鎖の間の室内は、 塀や欄間・金具にいたるまでことごとくが意匠されており、この遠州において数寄屋造りとして、日本住宅におけるインテリアが、総合性をもって大成されたことが知られよう。
ここには江戸時代初期の寛永文化の粋が凝縮されている。
国道に戻って進む。左カーブしつつ北へ進むと、道は右下の金谷中心街へ下る道と、左上に進み牧之原台地状をなおも進む北進道に分かれる。今回は左上道を選ぶ。というのは金谷街道は本当は右下道がメインである。しかし今回は台地状をもっと北進したいためである。
右上道を進むとお茶の郷の東側に公園がある。
○牧之原公園(金谷3120)
・石碑:記念碑、・栄西像、・石碑2:合一之碑、杉山賞記念、・新:石畳、
直線距離150m、道の距離450mで東下に富士見展望広場がある。
また牧之原公園から道を西に横断するとお茶の郷の庭園入口になる。
牧之原公園からスタートしカーブする道なりに1.4㎞北進する。
○石碑、道しるべ(菊川?金谷1738₋2)
・芭蕉句碑:馬に寝て残夢月遠し茶の烟、・明治天皇御駐輦阯、・道しるべ類
*注:輦レン、人の引く車、天子の車、鳳輦ホウレン、
北30mに旧東海道の金谷坂の石畳があり、上りきった所に石仏類がある。
○石塔類(金谷1738₋2)
・祠:三面観音、・地蔵、・馬頭観世音、・石塔、・九十丁目 濱浜川上古右まつ
・旧東海道:金谷坂:石畳道
・説明:この石畳道は江戸時代幕府が近郷集落の助郷に命じ、東海道金谷宿と日坂宿との間にある金谷峠の坂道を旅人たちが歩きやすいように山石を敷き並べたものであると云われている。近年わずか30mを残す以外はすべてコンクリート等で舗装されていたが、平成3年町民約600名の参加を得て実施された「平成の道普請」で延長430mが復元された。今街道の石畳で往時をしのぶことができるのはこの金谷坂のほか、箱根峠、中山道十曲峠の3か所だけとなった。
・旧東海道ルート
ここから先の北進する道は旧東海道である。と言っても自動車用に拡幅され舗装されている。しかしルートは東海道そのものであろう。
400m進むと広い県道吉沢金谷線に合流する。その手前右に城跡入口がある。
○諏訪原城跡(島田市菊川、牧之原1172⁻1)
・説明:諏訪原城は武田勝頼、徳川家康時代の堀、丸馬出が良好な形で現存し、戦国時代の過程を理解するうえで重要な遺跡として国史跡指定された。
当城は天正元年1573武田勝頼が東海道沿いの牧之原台地上の金谷台に普請奉行馬場美濃守信房(信春)、その補佐を武田信豊に命じ築いたと『甲陽軍艦』等に記されている。城内に諏訪大明神を祀ったことから「諏訪原城」の名がついたと云われる。この城は大井川を境として駿河から遠江に入る交通、軍事上で重要な場所にあり、当時徳川方だった高天神城(掛川市)を攻略するための陣城(攻めの城)として、攻略後は兵站基地(軍事作戦に必要な物資や人員の移動を支援する城)としての役割を担った。
天正3年1575に、徳川家康によって攻め落とされた後「牧野城(牧野原城)」と改名され、武田方となった高天神城(掛川市)を攻略するための陣城(攻めの城)として活用された。牧野城には、今川氏真や松平家忠らが在城し、『家忠日記』には、堀普請(堀を造る土木工事)や塀普請等度重なる改修が行われたことが記されている。天正9年1581に、高天神城が落城し、翌年武田氏が滅亡するとこの城の必要性は無くなった。その後徳川家康が関東に移ったことから、天正18年1590頃廃城になったと考えられる。
・説明:諏訪原城跡:国指定史跡:諏訪原城は天正元年1573武田勝頼の臣馬場美濃守氏勝を築城奉行として金谷台に築かれた規模雄大な山城であり、当時の東海道武田領の最前線牧之原台地の東北角を占めた天然の要害であった。
遺構は、本丸、二の丸、三の丸、、大手郭帯郭、西の丸、搦手、亀甲曲輪の8郭から成る特徴のある縄張により配置形態のうえから扇城とも呼ばれた。自然堀と人工の大小堀が13本あり、いずれも深くて急斜面を呈しているが、石垣は用いられていない。武田氏の守護神である諏訪明神を城内の一角に祀ったことから諏訪原城と呼ばれたが、史料には、城の変遷を示す牧野(原)城、金谷城、扇城という呼称が見られる。
・大手口:城の表玄関に当たる所、・十二号堀:半月状水堀で三の丸を守る、長さ89.7m、幅15.3m、・壁立:壁立とは壁の如く切り立った構造を言う、特に堀と堀との直結した間隙に構え堀を伝っての直接の敵の侵入を防ぐためのもの、・三の丸:この茶園一帯が三の丸、二の丸に次ぐ一郭で食糧、武器、弾薬庫を備える重要な所、・カンカン井戸、・十五堀:規模:長さ31.0m、幅6.0m空堀、・十六号堀:規模:長さ90.0m、幅6.0m空堀、・搦手口:搦手外郭は食料、衣料、飲料水、武具等の運送に使われた主要な役割の地点、一般家庭での勝手口、裏口に相当、・天守台地:この城は山城で天守閣はなく、二層からなる矢倉(櫓)があり物見が常駐して敵の動きを監視していた、・本丸跡:本曲輪:城主の居住する所で軍政を司る所、・本曲輪虎口、・六号堀:長さ85.0m、幅14.5m空堀、この堀切は城内に谷沢(東沢)が続き自然の地形(谷沢)を利用した堀、・五号堀:この堀は三段堀といい底部は三段になっている、これは甲州流の特徴の一つで階段状になることで敵の侵入に足あり、珍しい構の空堀、長さ40.0m、幅13.0m、・二の丸:副将またはそれに準ずる武士の詰所で武器保管や他の城からの来城者の控所、武士の家屋敷もあった、・大手外丸馬出、大手曲輪、・大手南外堀、・大手北外堀、・二の曲輪大手馬出、・外堀、・二の曲輪南馬出、・二の曲輪東馬出、・二の曲輪東内馬出、・水の手曲輪、・内堀、・二の曲輪、・二の曲輪中馬出、・二の曲輪北馬出、・本曲輪、・出曲輪、・惣曲輪、・武家屋敷跡、
・墓石3:明和四年、五年、・墓石3、
・単制無縫塔4:明和、・手洗石:明治□年、・墓石3:安政二、寛延元、・祠:地蔵2、五輪塔、観音「七十番」、
諏訪神社
・板碑:諏訪原城跡県指定史跡昭和二十九年指定、・石鳥居:昭和三十四年、・庚申塔、
・石碑:今福浄閑戦死墓塚:武田方当城主、
旧東海道は県道と交差し横断すると、向こうは菊川坂入口となる。
・菊川坂(島田市菊川、牧之原1172⁻1)
・説明:菊川坂と金谷坂:江戸時代、東海道を行きかう旅人たちにとって、金谷の峠越えは、粘土質の山道であったため大変難儀をしたいた。このため近郷近在からの助郷役により石畳を敷いて旅人の難儀を救ったと云われている。この故事にちなんで菊川坂と金谷坂の石畳を平成の今、再びよみがえらせた。
菊川坂は21世紀の幕開けの事業として平成13年静岡県内の東海道21宿をはじめ、周辺地元菊川地区や町内からの助郷役の人たち500名を超えるみなさんの力で道普請に着手。平成12年の発掘調査で確認された江戸時代後期の現存する部分を含め約700mの石畳が完成した。
金谷坂は町民一人一石運動により集められた山石7万個をもって平成3年子供たちからお年寄りまで500余名の町民の力で道普請に着手、翌年3月400m余の石畳ができた。江戸時代後期の石畳そして平成の道普請のよりできた石畳に、それぞれ、昔の旅人へのあるいは平成助郷役の人たちへの思いを馳せながら、この石畳をかみしめてください。
菊川坂入口から東海道ではなく、県道を150m北進する。道祖神がある。
・石祠:道祖神
250m北進すると現在の県道島田金谷線と交差し、ラブホテルがあり、この峠を割石峠という。
・割石峠、中山新道(島田市菊川371⁻16)
そしてこの峠道(東西に横断する県道島田金谷線)はかつての旧国道1号線で、その前は日本初の有料道路、中山新道である。この峠に石塔がある。
・石仏:南無阿弥陀佛、自然石3(島田市菊川371⁻16)
この交差点を横断し北に500m進み茶畑を200m西に進むと、遠江三十三所観音霊場道の24番と25番への巡礼道と合流することになる。
・巡礼道:遠江三十三所観音霊場24番←→25番
ここで今回の金谷街道:変則版を終える。
・参考文献
・「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ‘96、
・「ゼンリン住宅地図」
・「2万5千分の1地形図」国土地理院、昭和50~平成10年代
・「2万分の1地形図」陸地測量部、明治20年代
・「静岡県 県別マップル道路地図」昭文社、’00
・「東海道 静岡県歴史の道」静岡県教育委員会、平成6年
・「日本石仏事典 第二版」庚申懇話会編、昭和55年
・「静岡県の中世城館跡」静岡県教育委員会、昭和56年
・「静岡ふしぎ里かくれ里」鈴木茂伸、静岡新聞社、’05
2016年06月05日
川崎(掛川)街道、福天権現道、大頭龍権現道(静岡県掛川市、菊川市、牧之原市)
・前文
*住所地は目的地を探すためのものなので、分からない時は附近のものを指し示すことが多い。
*未発見や誤解曲解している箇所が多いと思われるので、コメントをいただくか、その人なりの発表方法で公表していただけると、ありがたいです。
特に牧之原台地上での発見できた石造物の少なさは、気になるので、まだたくさん未発見物があると思われます。公表されることで保存へ弾みがつくことでしょう。
~川崎(掛川)街道、福天権現道、大頭龍権現道、金谷街道(静岡県掛川市、菊川市、島田市、牧之原市)~
現地調査:’16 4/9,10,16
川崎(掛川)街道は、掛川市成滝の旧東海道や、伊達方の旧東海道から南に分岐して菊川市西方の竜雲寺(福天権現)や加茂の大頭龍神社への参詣道であり、更には西方から相良坂(公文名、)潮海寺、和田を経て沢水加サバカから牧之原台地を上り仁王辻を通過し三栗原、水吞、白井追廻で左折し戸塚坂(掛川坂)を下り、戸塚橋を渡り榛原静波三丁目で旧田沼街道に接続するルートである。榛原静波の川崎はかつて港があり、海運及び海産物取引が盛んだった。榛原周辺は掛川藩領が多く、藩で徴収する年貢米や、川崎湊へ運ばれる江戸扶持米の輸送ルートであったそうだ。距離は約23㎞である。~『定本静岡県の街道』より~
金谷街道は仁王辻から金谷宿までの道である。
~川崎(掛川)街道、福天権現道、大頭龍権現道(静岡県掛川市、菊川市、牧之原市)~
~1 掛川市成滝ルート~ ナルタキ
・石道標:福天大権現 大頭龍大権現 従之大頭龍大権現□□□福天大権現□□□ 従是川崎道 行程六里(掛川市成滝96、掛川市農協JA西山口支所)
・説明版:大頭龍大権現と福天大権現の参道標である。昔は掛川宿と深い交流のあった川崎湊(現在の静波)に続く川崎街道と言って多くの人々に利用された。元の位置は約10m東にあり川崎街道起点となっている。
昔は各所への道案内として主な辻に、道標みちしるべが建てられた。そしてその道を往来する人たちの案内役を果たしていたが、最近は時代とともに次第にみうけられなくなくなってきた。西山口農協支所西角の道標は、郷土の文化遺産として、昔の時代を知る存在だ。建立時期は不明。伊達方にある道標が類似していてそちらは寛保二1742年と刻まれているので、その時期と推定される。大頭龍権現は菊川市加茂に、福天権現は菊川市西方竜雲寺境内にあるが、当時は両権現の信仰が盛んで、信者等はこの道標から裏丁通りを経てそれぞれの目的地まで歩いて行った。また川崎街道の分岐点でもあることから、堀之内、川崎湊、両方面を往来する人たちには、唯一の街道だった。なおこの道標から東へ150m直進し伊達医院角を右折すると県道37号線である。この道路は大正4年1915に建設されたが、それまではすべて菊川または川崎方面に行く人たちの当地を起点とする往来の主な役割を果たしていた。
古い記録には、「川崎街道は里道にして、本村字成滝より東海道に接続し、阿弥陀寺橋を渡り、本村字満水村の大部分を経て、満水坂を越え、隣村西方村に至る。阿弥陀寺橋、従前は掛川城主にて、簡素なる板橋を架し交通の便を図りしも、城主転任と共に村費を以て架橋せしが、少しの出水にても流失し、為に大六山などを越えざるべからざる不便もしばしばありたり。故に成滝村満水村合同し、明治4年1871,8月新規架橋す。この諸金67両2分3朱、残銭1貫4匁、この橋できた後は従前より大いに便利得たれども、数年ならずして流失するに至れり、是に於いて満水、成滝、宮脇の3村協議の上、其の筋に架橋出願許可を得て、明治9年1876より工を起こし、この8月中竣工す。橋全長21間、幅7尺、この経費金113円44銭7厘。翌月即ち明治9年9月より明治13年1880,8月まで満4年閒橋銭を申し受くることとなれり。この橋は今の所より20間ばかり下流にあたれり。」と記されている。
・いぼとり地蔵堂(成滝49⁻11)、手洗石、
創建不詳、大正2年改築、妊婦子育て中の主婦の参詣者多く、いぼとり地蔵と云われる。ガン封じに来る人も多い。
地蔵堂から阿弥陀寺にかけて道幅が狭く、古道の雰囲気を残す。
○阿弥陀寺(成滝120)
・地蔵菩薩1.2m:堂、台座0.6m、地蔵0.4m、安政大地震により当寺も損壊したため明治25年頃修復の時に、参門を南の川崎街道より入るようにしたので、同時に地蔵も境内に移し信徒等により頭を取り付け参門に祀ったと伝わる。昭和50年代に山門修築の際現在地に移された。毎月有志によりて念仏供養が行われている。それ以来地蔵は首から上のことを何でもかなえてくれる霊験あらたかな地蔵であると言い伝わる。平成10年阿弥陀寺。
・六地蔵、観音、・板碑2、・正覚山阿弥陀寺供養塔、・赤鳥居平成七年、・諸獨稲荷、・墓石:延宝九、江戸中期後期墓石、
・秋葉山常夜燈 平成六年(成滝115の裏)
‘93年版ゼンリン住宅地図では、この場所に秋葉神社となっていて狭いなりに境内がある祠のようなのだが、現在は墓地と新しい秋葉山常夜燈だけである。規模が縮小されたようだ。
~周辺~
現在の川崎街道(県道37号掛川浜岡線)の旧東海道からの起点、古道より東に150m地点である。
・石道標:□□□記念西山口村 石工有治 □□□町 □□□町 □□□町 □□□十町 □□□町(成滝395⁻4)、上部欠損
四角柱で楷書体で記入されているので近代物と思われる。
・双胎道祖神(成滝91)
この御宅の方は石造物趣味があるらしく他の石造物も設置されている。
・地蔵:祠(成滝132⁻3)
○神明神社(成滝278)
・コンクリ手洗石、・手洗石:古、・石鳥居:明治三十八年、・秋葉山常夜燈 文化十年酉七月、・石柱2:大正五年、
・新:東海道標識、祠:馬頭(成滝315₋2)
国道1号線から旧東海道へ分岐する地点。
○若宮神社(逆川336)、説明版:祭神:すさのおのみこと、おおきさぎのみこと(仁徳天皇)、例祭日:10月10日、由緒:すさのおのみことは天照大神の弟で文武に優れ出雲国を平定した神、八坂、津島、氷川等の社に祀られる。当社は池下村若宮の谷に鎮座していたが、寛永元年現在地に建立、昭和61年改修、おおきさぎのみことは人徳高く慈悲深い仁徳天皇であり、今より400年前悪病全治祈願して数日にて全治す。その神徳のありがたさに発願、氏神として合祀さる。
・石柱2:御即位紀念、・石鳥居:昭和五十七年、・シイノキ:市指定保存樹木、
・鞍骨の池(逆川422)
室町初期の南北朝期、周辺で戦があり、勝った南朝方が捕虜にした北朝の今川氏の家臣、堀越入道に鞍をつけたまま入水させ処刑したという伝説の池。
~~~
成滝の阿弥陀寺の山門前を東へ通過し山口橋に達する。上記によれば古い橋は36m下流だそうだ。山口橋を渡って現在の県道に出て満水タマリ地区を東進する。
北に山が見えだし、西満水バス停前になると、北の山に神社がある。
○高畑神社(満水538)
・石段、・コンクリ手洗石:昭和十四年、・石鳥居:昭和十四年、・祠2:津島神社、金比羅神社、・石柱2、・コンクリ献燈2:昭和拾四年:シックなシンプルデザインで美しい、
県道掛川浜岡線を東へ250m進むと北50mの山先端部に祠や堂がある。
・祠:坂東壱番観世音:新:観音:平成十四年(満水658)
東隣には堂がある。
・薬師堂:・手洗石(満水673₋2)
また県道に戻り150m東進する。北に満水公会堂がある所を左折(北)し北上する。
東に祠がある。
・祠:如意輪観世音、・手洗石:大正十一年(満水755)
また県道に戻り800m東進する。左に「思い出の家」レストランの看板があり、そこで左折(北)し、北東に進み、「思い出の家」手前でまた左折(北)し100m北上すると神社がある。
○一色神社(満水1386)
・祠、・コンクリ石段、・献燈2、・コンクリ手洗石、・石鳥居:平成十九年、・石柱2:昭和十五年、
満水地区の現在の県道を東進したが、実はこれが古道ルートではなく、満水地区の石造物紹介の為通過したようなものである。満水の古道は現在の県道やJR東海道本線、新幹線よりも南で「つま恋」より手前北の道である。
そこで一旦西満水バス停辺りまで戻り、線路下のガードをくぐり南に出て南の山(つま恋)手前の道を東進する。菊川市との境界線付近でちょっとした丘があり、線路はトンネルとなるが、道はつま恋ゲートへの道を上ることになる。おそらく古道は線路南の農家の辺りから線路沿いにトンネル上の丘を越えた(推定:満水坂)のだろうが、そこは現在道がないので、つま恋ゲートへの道で丘上を越え、満水を東進してきた先ほどまで使っていた県道に出て、右折で東進し、すぐトンネルを通過し菊川市となる。市境はトンネルとなるが無論近代の道だ。ここまで遺物類は発見なし。
トンネルをくぐり菊川市に入り200m東進すると右(南)横にJR線路が近づき隣に平行になってくる。線路向うに鳥居や祠が見える。ここから右折する道がないので、竜雲寺を過ぎてから右折することになる。そこで竜雲寺までさらに200m直進する。
○竜雲寺:福天権現(菊川市西方、田ケ谷3780⁻1)
寺の裏の県道沿いに祠がある。
・献燈2:大正四年、・堂:馬頭観世音2:平成十五年、
寺の境内地のものは以下である。
・堂:福天大権現、・観音、・三界萬霊2:施主山﨑 大正:遠江三十三所等掛川市周辺でよく見かけるものでありここにもあった、・手洗石:平成五年、・新:地蔵、・新:六地蔵、・旧:山門、
裏山石段上には稲荷神社がある。
・石祠:小稲荷多数、・コンクリ石柱2、・石鳥居:竜雲稲荷、・赤鳥居5:平成二十一年、・祠:小稲荷:多数、・狛犬の稲荷2、
伝説:昔、天狗が取付いた者がいて福天権現になったという。南の山に埋もれていた福天ゆかりの物もあるという。遠州十二坊の一つである。南の山とは田ケ谷神社のことか?
*参考『静岡ふしぎ里かくれ里』鈴木茂伸、静岡新聞社
石道標に目的地としてまで刻まれた福天権現であるが、陽春4/9土曜日、週末の昼に、境内には参詣人の姿はなく、本堂に隣接する住居棟の改築中で、大工さんたちが忙しそうに働いていた。福天権現と言ってももはや知る人も数少ないだろう。
寺門前から県道向うの南に線路下をくぐるガードがあるので通過する。
・JR高架線路橋(西方、田ケ谷3850₋2)
レンガ作りのアーチ構造でレトロであり、准文化財級である。将来は文化財だろう。
高架下ガードをくぐるとすぐ目の前に鳥居や常夜燈がある。
○田ケ谷神社(西方、田ケ谷3850₋2)
・石鳥居:大正四年、・常夜燈2:天保十衹七亥夷則下慮、・手洗石:コンクリ補修、・石段:宝暦八寅年、・祠、・本殿拝殿、
ちょうど桜がはらはらと散り際であって、散歩する人、写真撮影する人たちがいた。
鳥居前から線路沿いに300m北西進すると左(西)50m先に鳥居や祠がある。この道は線路横に直線で作られているが、線路ができる以前はもっと婉曲していたのではなかろうか。おそらく掛川市満水から満水坂を越えてきた古道はこの道に接続したのではなかろうか。残念ながらこれ以上北西進する道は現在ない。古道は完全消失したのだろう。
○神社(西方、田ケ谷)
・コンクリ石柱2、・石柱2:横倒し、・祠、・手洗石:寛政十二年、・石鳥居:大正九年、・石段:昭和六十年、・堂:子聖大権現、・常夜燈2:明治丗九年:1体はコンクリ補修、
ここから東南の大頭龍神社を目指す。
先ほどのJR線路高架ガードレンガアーチの東300mにもレンガアーチがある。
・JR高架線路橋(西方、田ケ谷3798)
線路沿いをさらに300m東南進する。菊川運動公園への標識があり、次に目指す大頭龍神社へ右折するが、その前に線路北側の遺物を紹介する。
西福寺、田ケ谷八幡神社である。『遠江三十三所観音霊場巡礼道』より一部抜粋する。
○西福寺(西方、田ケ谷3597⁻1)
・鐘、・手洗石、・祠:神、・三十三観音、・地蔵、・奉納大乗妙典、・庚申塔:田ケ谷連中、
○八幡宮(西方、田ケ谷2608)
・石柱2:昭和五年、・祠2:神、・手洗石、・石鳥居:大正九年世界戦争終局記念、
・秋葉山常夜燈:昭和十一年:センサー付き電球、
線路際の菊川運動公園への標識のある交差点で右折(南)し300m南進する。右100m先に神社がある。
○熊守神社(西方2716)
・献燈:昭和七年、・手洗石、・石鳥居:大正九年、・石柱2、
・大頭龍神社への福天権現からの最短推定ルート
熊守神社から更に南に道なりに600m進むと東名高速高架下ガードをくぐる。さらに300m道なりに南進すると直進不能になるので、その前に左折し東南進する。道なりに700m進むと川沿いの交差点の低い所に出る。ここで上る直進をやめる。
というのもこのまま直進して大頭龍神社を過ぎてしまったためである。自動車道としては一本違いの道になるのである。
大頭龍神社へはこの川沿いの低い交差点で左折し川の下流に沿って300m東進する。ここでT字路に出る。右折し東南進する。工場地帯を川に沿い300m進む。ここで広い交差点を右折し右へ左へとカーブする道を300m南進する。広い工場地帯の広い交差点を左折し300m進むと向こうに丘がある。道は直進路もあるが、道の右前方が目指す大頭龍神社であり、神社に直進路からの裏の北口はなく、入口が右(南)なので右折し丘を南に回り込む。左(東)は丘でその上に住宅が見え、右(西)は平坦で広い工場と公園になっている。途中2カ所ほど狭い上り道がある。車で上れるギリギリの道であるが、初めてならやめておこう。確かに表参道への近道ではあり、表参道沿いの住宅への道である。南に回りきると北への参道の上り道がある。
ちなみに先ほど一本違いの道のことを記入したが、その道では先ほどの低い交差点を直進し、上りきった辺りで、車では無理だが、自動車道の上りきった辺りより更に20mほど歩いて左の山上の尾根に出ると、そこが西方と加茂地区の境界線尾根である。その境界線尾根の古道に沿って400m南下し、ちょうど大頭龍神社の真西に到達した辺りで東に1㎞向かい大頭龍神社に出るというのが、福天権現からの最短古道推定ルートである。
大頭龍神社の紹介は次の「2 伊達方ルート」を述べてからにする。
~~~
~2 掛川市伊達方ルート~ ダテガタ
・石道標:福天大権現杏 、 是より 、これより ふくてんごんげん(道、ミチ?)、 寛保二 日坂町建 石屋伊 (掛川市伊達方⒕)
だいぶ刻字が読めず保存状態が成滝の物と比べよろしくない。説明版もない。
西向かいはかつてタバコ屋で一里塚跡という。
・一里塚跡(伊達方31)
・説明:一里塚は慶長9年1604江戸幕府の命により築かれた。江戸日本橋から一里4㎞ごとに塚が設けられ、松か榎を植えて目印とした。旅人にとって夏は木陰、冬は風よけとして重宝がられた。また塚の傍らには旅人の必需品が商われたほか、一服できる休憩の場であった。江戸日本橋から京都まで125里約500㎞。掛川市内には佐夜鹿、伊達方、葛川、大池の4カ所に塚が設けられていた。ここ伊達方一里塚は江戸より57番目の塚として街道の両側に築かれ、南側は現・萩田理髪店東側辺り、北側は現・三浦たばこ店屋敷辺りに設けられていた。当時塚の大きさは直径7間、高さ3間の小山で、一里山と云われた。明治33年頃取り壊されたという。
三浦たばこ店がかつての一里塚だという。現在はその西隣に一里塚石碑がある。一里塚石碑の向かいに大頭龍神社がある。と言っても祠があるだけの5m四方の空間である。しかしここから旧東海道から南に分岐する川崎街道:現在の県道菊川停車場・伊達方線の起点である。
○大頭龍神社(伊達方28⁻1)
・手洗石:摩耗して刻字不明、・石鳥居:昭和丁丑十二年一月六日建之、・石道標:大頭龍神社 従是一里十五丁 昭和五季三月建之 加藤減重、・祠:神祀、・石道標:西方村 堀ノ内駅 ニ通ズ 掛川駅ヘ約一里十四丁 堀ノ内駅へ約一里三丁 日坂村役場へ約十九丁 大正二年十月建設 東山日坂村青年會、
~周辺~
・塩井神社(伊達方、塩井川原485⁻1)
東海道と川崎街道分岐点より東に400mの国道1号線と旧東海道の分岐点辺りにある。あると言っても逆川を歩いて渡らねば神社に到達できない。橋はなく川を徒歩で歩くしかない。神社地から塩水である鉱泉が出るということである。
~~~
川崎街道の起点であるが、現在の県道分岐点なのか東20mの大きい石道標のある路地なのか判別不能である。両ルートとも南へスタートする。100m南進すると逆川に架かる豊間橋に出る。
路地側は土手に出て橋がないので、結局この橋に行き渡る。豊間橋を渡って150mほどで右(西)の水田の道へと100m西へ移動する。ちょうど西1本分の道を移動し南を目指す。水田から住宅のある道になり右(西)に小川がある。すぐにやや広い自動車道に出て横断するが、ここで横断してすぐに西へ10m進み、カーブしている路地を南に進む。伊達方1005₋2:伊藤氏宅東側を南に進む。伊藤氏宅を過ぎるとすぐに大井川用水が東西に横断している。ちょうどこの手前に祠が2つある。
○秋葉山常夜燈(木造瓦葺)、祠:庚申?(伊達方1005₋2)
大井川用水の南側は山斜面になる。その山斜面の取付きにコンクリ製祠がある。
・コンクリ製祠:地蔵2、石塔1(伊達方1005₋2)
この祠の前を東へ向かう山道と、祠の西5m地点から南に向かう山道がある。
上記の道や石仏については伊達方952:伊藤氏談。
私の勝手な推理では、東への山道は、東へ向かうと100m先で付近住民の墓地に出て道が終わるが、かつてはおそらく道が山斜面沿いにうねりながら南に続き、現在の伊達方トンネル(掛川市伊達方と菊川市西方の境)付近につながり、西方へ抜けられる道だったのではなかろうか。
西側の山道はこのまま枝尾根を抜け西側の畑地へ出られるが、また枝尾根を上り詰めることができ、そのまま枝尾根を詰めると現在の伊達方トンネル真上にも到達できる。かつてはトンネル手前の高圧鉄塔跡地辺りから南へ抜けて菊川市西方へ出られる古道があったと推定する。現在この枝尾根は悲惨であり、南に抜ける道らしきを発見できない。
そこで西方へ行くには伊達方トンネルをいったん通過するしかない。そして通過後もトンネル南西方向は工場か作業場が1つある。どうもそこの西北方向から古道が出てきて平地に下り、その工場か作業場前の道を南東に下り、現在のトンネルから下ってきた広い道と交差して南東方向に下り、西方5501:井伊谷氏宅、西方5508⁻1:黒田氏宅前の道へ下りたと思われる。
そこからは首塚様のお堂前を通り、三島神社前の道を通ったというより、西方川の反対側に古道はあったようで、反対側の山すそに沿い奉仕橋方向へ東進し奉仕橋から南東に向かう道に出て、その広い道から東へ曲がり、西方5918₋2:内田氏宅前を通り、その東先で現在は道が消失するが、山に入っていて、東の潮海寺地区の⑩成就院跡地前に出て、通りの尾根(相良往還)と呼ばれる尾根道に出たようだ。
~~~
○お堂:首塚様:説明版:所在地:沢田坂下:首から上の病には、この首塚様へ願をかけ、願い叶えば松笠や穴あき石に糸を刺し齢(年)の数ほど供えなされ。昔から願掛けすると必ず治ると遠近からの信者の参詣が後を絶たない。しかしその由来は定かではない。建武三1336年、今川範国は足利尊氏に属して武功をたて遠江守護となり以後60年が続いた。応永二十六1419年尾張の斯波氏が守護となり、その後約100年が続く。このようなことから鎌倉時代後に武威を張っていた今川方の古名族横地氏も斯波氏に属することになった。しかし今川義忠は遠江を回復せんと堀越陸奥守貞延を総大将に横地・勝間田の本拠地小笠・榛原に進撃、小夜の中山南側の海老名エビナ・影森・公文名一円が壊滅的戦場となった。士将貞延も牛頭ゴウズまで来て惨敗したと伝えられ鞍ごと池に投げ込まれたと言う。この鞍骨池伝説や海老名辺りに点在、祀られている石塔は往時を物語るものと思われる。この首塚様や堂山は、この戦の名だたる武将やかかわりのあった人たちを供養お祀りした場所と思われる。近年は霊験あらたかということで病気平癒と合格の祈願の信仰を集める。平成20年(2008)1月吉日 菊川文化財保存会鈴木利夫氏の文を基にして記入
○三島神社:・庚申塔:平成二十年、・祠3、・石柱:昭和四十一年、
右岸道300m右への道100m奥に神社がある。
広い道(公文名の市道と県道菊川停車場伊達方線)が合流する箇所に石道標がある。
・石道標:「右瀧之谷守本尊ヘ廿五丁 左東海道ヘ十五丁 堀之内駅ヘ廿七丁 大正十四年環居紀念」
~~~
ここから先は伊達方トンネルを通過して、西方に出て、西方から、大頭龍神社へ向かうルートを紹介する。それは自著:「遠江三十三所観音霊場巡礼道」のルート沿いになるので、そこからの文章を組み直して載せる。部分的に文章を追加している。
~~~*『遠江三十三所観音霊場巡礼道』より抜粋し組み立て直す~~~
また伊達方トンネルまで話を戻す。
伊達方トンネルから道を下ると、神社がある。またはトンネルを下ってくる現在の道の西の古道沿いの作業場か工場の西から南の寅尾神社に向けて細い道が付いていたかもしれない、というのも、寅尾神社前にも道らしきがあり、かつての古道かもしれないと考えられるからである。
○寅尾神社:・手洗石:昭和三年、・石柱2、・石段:御大典紀念昭和参年、・板碑、
・狛犬2、・庚申塔2:大正九年、寛政十二、
寅尾神社の南で道が分岐する。
広い道(公文名の市道と県道菊川停車場伊達方線)が合流する箇所に石道標がある。
・石道標:「右瀧之谷守本尊ヘ廿五丁 左東海道ヘ十五丁 堀之内駅ヘ廿七丁 大正十四年環居紀念」
川崎街道メインルートは潮海寺地区へ向かうが、ここから一旦、竜雲寺:福天権現や大頭龍神社へ向かうルートにして説明する。
道の合流地点から100m南へ進むと右にコンクリート擁壁がある。そこに石仏がある。
・石仏:すでに地蔵か観音か不明だが、頭部上部に細長いものがあるようなので、おそらく馬頭観音かと思われる。
100m進む。右に寺院がある。
○洞源院:・地蔵、・観音、・観音:西国三十三所安永四乙未、・手洗石、・昔の鬼瓦、・祠:神、・新四国第八十六番霊場昭和九年、・菊川地蔵尊巡り四番、・洞源院昭和五十年、
・石道標:「記念 東海道一斤八百八メートル 十六町二十間 堀之内駅ヘ二千八百三十二メートル 二十五町五十一間 大正十三年一月廿六日建之 澤田部青年團」
50m進むと東海道新幹線に達する。古道は西方川左岸沿いのようだが、道がないので右岸を迂回する。右岸道150m行って右道奥に神社がある。
○七社神社:・新:献灯2、・石鳥居:御即位紀念大正四年、・常夜灯:明治四十三年、
・石柱2:大正四年御即位紀念、平成二十三年、
右岸道50m進み右奥に神社がある。
○岡の宮神社:・石柱:大正六年、・石鳥居、
岡の宮神社の150m南の県道菊川停車場伊達方線が西方4503₋2山西茶農協製茶工場横へ東に入った路地に石仏がある。
・石仏:馬頭観世音、
右岸道を迂回したが、途中で左岸道が現れて来る。新幹線ガードから左岸道を1.2㎞進むと県道掛川浜岡線の1本北側の旧道に当たる。
福天権現へは、ここで右折(西)して、西福寺、田ケ谷八幡神社、秋葉山常夜燈を通過していくことになる。
大頭龍神社へは、遠江三十三所観音霊場の28番正法寺と同一ルートと推定されるので、先ほどの県道掛川浜岡線の一本北側の旧道で左折(東)する。北の山腹に神社がある。
○山宮神社:・板碑:大正八年、・庚申塚:明治三十年、祠3:神、
・石鳥居2:大正十五年、、献灯2:昭和四年、・祠:子育て地蔵、・手洗石、
・祠:地蔵、・板碑、・秋葉山常夜燈:木造金属葺、・石段:皇太子殿下御降誕記念、
・石柵:平成二十年、
古道的には300m東進して南下して東海道本線をくぐって28番に達するのだが、その古道は消失し、現在は線路をくぐる道はもっと400m東進しないと無いので、そちらに迂回する。28番正法寺の奥さんによればかつては石道標があったそうだ。
迂回したガード下道の100m手前東の丘上に神社がある。
・神社:・お堂、・コンクリ手洗石、南側に階段状参道があるが、草と倒木で使われていないようだ。北側は新興住宅地で道に面しているが、柵と擁壁があり、入口がない。ということは誰も祀っていないのか? ’16 2/11
県道掛川浜岡線と東海道本線に交差する所で線路をくぐる所に戻ってくる。
古道はどうも迂回せずに28番へ直に向かったようだが、現在そんな道はないので、迂回を含めガードをくぐって線路の南に出る。西の山際に28番がある。 ’16 2/11
○第二十八番 拈華山 正法寺(菊川市西方1329、にしかた)ねんかざんしょうぼうじ
創建:天正2年1574、開基:堀田正法、開山:龍雲院三世実伝宗貞和尚、本尊:聖観世音菩薩:寄木造り座像72㎝:伝行基あるいは運慶あるいは逢雲作、宗派:曹洞宗、開帳:秘仏・33年毎、縁起:
旧菊川町の寺院は森の大洞院の流れを汲むものが多い。
桐田氏私見:堀田氏は堀内氏(城飼キコウ郡:小笠郡堀之内城)で正法寺開基は堀之内重親だろう。ただ武田徳川の争乱期で寺院を開基し経営できたかは検討を要する。
安政三年1856冬失火焼失、本尊は免れる。諸堂再建は廃仏毀釈で進まず大正14年1925竣工。堀田城城主堀田正法開基で龍雲院三世実伝宗貞を招いて開創、八ツ谷観音、厄除観音、子育て、縁結び、
・鐘楼:鐘がない、戦時中供出。平成4年鋳造。
・丸い大石:「天保十四年 二十八番札所 正法寺」:参道入口、
・本堂:大正十四年落慶、
・梅古木:本堂前、
裏山は山城:堀田城または松下城、山城の輪郭が残る。中腹には円墳があったが、崩落の恐れがあり1993年発掘調査、記録保存し整地し正法寺霊園になっている。
~追加~
・堀田城(松下城):裏山には上れるし、本曲輪には標識「本曲輪」が立てられているが、他は一切ない。曲輪や堀切があり、しかも二重に切られた堀切が複数あるなどするが、そういった説明や標識類がないことが残念だ。
・円墳:霊園の中央部分らしいが、記録保存して取り壊したので一切わからない。
地元の郷土愛好家グループや教育委員会で標識や説明看板を立ててほしいものだ。
・祠:神を祀る。・供養:地蔵10、・新;献灯、・新:手洗石、・古:手洗石、
・裏山山頂:祠:秋葉山三尺坊大権現、秋葉神社 ’16 2/11
有住、駐車場有、Tel:0537-35-3612
~周辺~
東側の山上には常葉学園(大学、短大、高校、美術館)、楠木神社、菊川神社、大徳寺、公園、グラウンド、市役所、福祉施設、教育施設がある。
不本意だが古道がないので現在の自動車道を東名高速もくぐり1.5㎞進む。
途中東名高速高架をくぐる手前の東に神社がある。
○八幡神社:加茂、白岩東:・石柱2:、・手洗石:(二つ割れ)、
・石鳥居:明治十十十(廿の3本)六年、・献灯2:臺灣(台湾)高雄市織部恭市昭和十一年、・石段、・新:手洗石、・古:手洗石(割れ)、・石段、・狛犬2、
・石柵:昭和六十一年、
左折(東)し県道高瀬菊川79号線を東に800m進む。
途中北の高台に神社がある。鹿嶋神社:古墳でもある。
○鹿島神社:古墳、
・石碑:鹿島神社参道入口 平成二年、石造成記念、・鹿嶋神社表参道 平成九年、・石鳥居:明治三十九年 再建平成六年、石柱2:大正九、・新:手洗石、・石鳥居:平成二年、・石柵:平成九年、・石柱2:大正四年十月 御大典 五丁目氏子中、・石柱2:、・狛犬2:平成六年、・献灯2:平成六年、・稲荷神社:稲荷2:平成二年、・石家道祖神、
・鹿島遺跡:説明版:今から4~5千年前、縄文時代中頃(加曾利E式)の村落跡、道を隔てた北側からは宅地造成の際に二軒の縄文住居が、また遊園地の東部分からも二軒の住居跡が見つかり、土器、石斧、石器の材料の黒曜石斧が発見された。町道より境内に入るために切り取られた道しろ辺りと園地の東南部分で比較的新しい住居跡が発見された。出土土器は八斗地遺跡(旭グランド)の奈良時代のものと似ているのでおよそ同時代の村と考えられる。
・鹿島古墳:説明版:公会堂脇にある古墳は今から1400年前のかなり身分のある人の墓で、周囲には円筒埴輪は巡らされ、直刀を出土し、直径は十数メートルあったが、現在は西半分が残っている。埴輪を伴う古墳は郡下でも数カ所しかないが、そのうち旧菊川町内に3か所ある。高田ヶ原公園に2カ所。役場西の森の高田原の大徳寺前方後円墳は古代この地方の王の墓だが、この王の墓を中心に代々主な古墳がこの台地に作られ、集結している。打上台地は東寄りから南べりに八幡社の円墳まで数箇所に古墳があるが、今はほとんど消失した。この原一帯は湧水のある場所に奈良時代の家が散在し集落を形成した。菊川町の古代は、この高田原台地を中心に文化が栄えていたことを物語っている。
~~~~~
28番正法寺の参道入口に戻り、南へ300m進み右折(西)するか、南へ400m進み豆尻橋を渡り、次の道を右折するかして、西の山際に出る。西の山際で南へ進み、東名高速高架ガードをくぐる。ガードをくぐると五差路になる。左右の高速道の側道ではなく、前方右の工場への広い道でもなく、左側道と工場への広い道の間の前方左(南)の狭い道を進む。ちょうどガードをくぐったところで西方、堀田地区から加茂地区となる。西の山際に沿い300m南西へ進むと、右折(北西)し山へ登っていく道がある。
○井成神社(加茂804⁻5)井成山
・説明:井成山と三浦刑部:稲作文化が進むにつれて、今まで荒蕪の地だった白岩地帯へ水田ができたが、村の中央を流れる西方川も東へ隣接する菊川もともに、川底が低くて田へ水がのらず、干ばつのたびに稲が枯れ死するので、年貢にもさしさわり農民はいつも不作を嘆いていた。ここに三浦刑部という偉丈夫があって、これをだまって見過ごすに忍び図、決然と立って治水の路を開き、村民の苦難を救おうとしたが、当時は排他気分が盛んで許可なく他村へ立ち入ることはできぬ申し合わせがあったので、測量等には嘘や方便、狂気を装ったり、凧を揚げて糸を切り、凧を拾う振りをして隣村に立ち入ったりして、智謀の限りを尽くして、地形、距離、落差を調べ、用地は農耕にかこつけて買収する等、苦心惨憺の末、ついに潮海寺掛下から菊川の水を取り入れる企てに成功し、矢田部から潮海寺・上本所を経て半済を通り白岩・長池に通じる水路を完成した。村民は瀬波を立てる井川の水を見て、一同起死回生の思いに浸り、今もなお刑部の徳をたたえている。それ以来加茂は豊穣の地となった。
・説明:三浦刑部と加茂井水:400年前加茂村は「嫁にやるなら加茂はおよし、加茂は雲雀の遊び場所」と言われ荒れ果てていた。今川軍の武将三浦刑部は桶狭間の戦いに敗れて武士をやめ、農業を志し、清水の里から二人の息子と加茂村にやって来た。田圃の開発を決意した。加茂村は菊川、西方川に挟まれているが川の流れが低く、川の水を利用できなかった。
刑部は幾多の困難を克服して菊川の水を潮海寺村より、半済村ハンセイムラ、本所村ホンジョムラを通り加茂村に導く測量に成功した。13年の長い歳月をかけ、刑部は途中で没したが、二人の息子により井水(用水)は完成した。2千石の米が取れる加茂村が大村としてよみがえった。以後江戸時代はもとより菊川町合併まで延々と流れる井水とともに加茂村は続いた。
村人は刑部の高い志とその恩恵に感謝して、井水の全部が見えるこの山の頂に祠を建て、感謝のお祀りを4月の第一日曜日に加茂地区を挙げて盛大に行われる。なお、この神社は井水が成る「井成神社」と言い、同時にこの山を「井成山」と言う。
用水地図では、菊川の水をJR線路より北側で取水し、菊川の西側を加茂地区に分流して流していることが分かる。
・説明:加茂井水 争いの歴史:
天正九1581年、井水の工事を始める、
文禄三1594年、井水完成、
1700元禄13年、本所村が吉田領加茂村陣屋へ訴える、
1701元禄14年、本所村が幕府評定所へ訴える、
1703元禄16年、加茂村が本所村を幕府評定所へ訴える、
1704宝永元年、本所村と潮海寺村が加茂村を幕府評定所へ訴える、
幕府裁定 刻割り制
潮海寺村0時~2時、本所村2時~6時、加茂村6時~24時、
大井川用水の通水まで続いた
1761宝暦11年、井水の公平を期して総百姓が立ち会って決定した定め書きを作った
加茂村御相給定書
1788天明8年、加茂村が本所村を吉田領地方役所へ訴える
1790寛政2年、終結
1793寛政5年、村内上部落対下部落の争い
1856安政3年、神尾村、潮海寺村の鰐淵井堰の改善について争い
1857安政4年、神尾村、潮海寺村が加茂村を幕府評定所へ訴える
幕府検使が現地検分
1860万延元年、幕府の指示により示談成立
・石段:昭和十一年、・祠、・御夜燈:昭和三年、・石鳥居:大正二年、・手洗石、・金毘羅神社、・石鳥居:大正二年、・御夜燈:昭和三年、・手洗石:元治二丑年:横倒し、
神社のある山は散策コースになっていて周辺の眺めを楽しむことができる。山の名は井成山のようだ。見晴らし台もある。
井成神社への上り口の西にお堂がある。
○堂:一番山長正寺(加茂804⁻5)
・御夜燈2:昭和三年、新:昭和十年(再建?)、・石塔:菩薩、
先ほどの井成神社への参道入口に戻り、150m西進すると、大頭龍神社の大鳥居(東口)がある。
ちなみに福天権現から西周りルートで達した大頭龍神社参道入口(南口)は、ここからさらに400m南進した所である。
○大頭龍神社(加茂、白岩段944⁻1⁻1)
・説明:正一位大頭龍神社:祭神:大物主大神、大山咋大神、出雲龍神、由緒:当神社は往古より御山へ宝祚延長天下泰平国家安穏の御弊氏子崇敬者安全繁栄の御幣を立願にて相建て今日に至る。当社は桓武天皇延暦11年勧請と口碑似て伝わる。御神徳は疫病鎮護厄除縁結びにしてその福徳の神様を奉斎申上げる。現在は建立社殿は宝暦13年、文化12年の修復再建である。鳥居額:神祇管長上従二位卜部朝臣兼雄公筆、拝殿内額:徳川家達公筆、神事:七十五膳奉幣厄除篝火、昭和37年。
東口
・赤鳥居:大正九年、昭和六十三年、・永代常夜燈2:大正十四年、・石柱2:昭和五十四年、社名碑:大頭龍神社:昭和三戊辰年、
北の家の裏山に祠がある。
・祠:神、・
南口
・石柱2、・祠、・石柱2:大正四年、
南口参道入口より北へ240m、本殿前大鳥居より南に150m地点
・永代常夜燈2:文政元年戊寅十月吉日
本殿前
・祠:神、・石柱2:大正四年、・金属鳥居:文政七、・常夜燈2:昭和戊辰之秋、・永代常夜燈⒑:大正十四年、・献燈:昭和三年、・常夜燈:長谷川:文政九年、・永代常夜灯:明治四十三年、・狛犬2:昭和三戊辰、・板碑:聖徳太子、・永代常夜燈2:寛政七年、・石柱2:紀元二千六百年、・石段:文化七年、・永代常夜燈2:文化十三丙子歳、・板碑:寄附人、・板碑6:金壱百~、・手洗石:昭和二十八年、・手洗石、・永代常夜燈(3:文化十三、大正四年、2:明治四十四年、平成二十一年、文化十一)・永代三夜燈(2:文化十三、2:文化十有四年、3:文化十四年)、・常夜燈:破片、板碑2、・自然石:丸石、
桜名所であり、参道沿いは満開時素晴らしい光景だ。しかし桜満開4/9土曜日という週末の15時過ぎの晴れた日に、隣の児童公園に遊びに来た親子連れ2組、近所の人の散歩姿数人のみで、神社受付売店の神主さんも15時過ぎに帰ってしまったので、私は御朱印を貰い損ねた。16時過ぎまでいたが、他に参詣に来た人は0人。大頭龍神社と謂えばかつては遠州きっての名刹、格式ある大神社であるはずで、大鳥居や常夜燈の年号や規模からして江戸時代後期より近代までは、大いに流行っていたはずだ。だからこそ大頭龍神社への石道標があるのだし。しかし現在は静かな神社だ。神社の栄枯盛衰を見た。それにしてもこんな静かな陽春の昼下がりに満開の桜に囲まれたというのは極楽至極ともいえる。
大頭龍神社を紹介したことで、このルートの説明は終了する。次は川崎街道の菊川市西方から潮海寺へのルート説明である。
菊川市西方の奉仕橋から南東に向かう道に出て、その広い道から東へ曲がり、西方5918₋2:内田氏宅前を通り、その東先で現在は道が消失するが、山に入っていて、山坂(どうもこの坂か、次の「通りの尾根」の坂を相良坂と言ったようだ)を上って東の潮海寺地区の「⑩成就院跡」前に出て、「通りの尾根(相良往還)」と呼ばれる尾根道に出たようだ。
~~~
潮海寺地区の「⑩成就院跡」前を通過し「通りの尾根」前に出る。昔は「通りの尾根」を歩けたのだろうが、尾根に取り付くところもないほど雑草に覆われているので上るのをあきらめる。東西に延びるこの「通りの尾根」の北側と南側の平地境には、現在舗装された農道になっているので、そちらを通行する。南回りの農道では「⑪常楽院跡」の標識がある。また新幹線線路際に出て線路高架下ガード前には「⑫向田坊跡地」への案内標識もある。更に南周りを東に向かうと通りの尾根が終わる手前に「⑨中の坊跡」「へ:螢谷」の標識がある。
北回りを東に向かうと、舗装されているがかなり雑草が多く、廃道に近い。雑草を抜けると「田子谷」辺りに出て、さらに東に向かうと通りの尾根が収束しに「⑨中の坊」「へ:螢谷」のすぐ北側に出る。ここで新幹線高架下ガードを南にくぐり、東側の潮海寺への台地を南へ行きつつ上っていき、潮海寺参道入口付近に出て、潮海寺の寺の南を通過し和田へ出ることになる。
~~~
ここで一旦潮海寺地区周辺を紹介する。
潮海寺参道前の潮海寺615₋2:岩水酒店前に出る。ここから南に50m行くと東に「お祭り広場」があり、潮海寺周辺の案内図・説明版がある。
・潮海寺:説明版(潮海寺615⁻9)
・説明:潮海寺は平安時代798~1190頃寺領を中心に大いに栄えた。寺の領域は掛川の成滝から菊川の仁王辻まであったと云われ、この中に75もの寺(坊)を配し、うち潮海寺には15坊があった。
潮海寺十五坊:①学頭坊、②本善坊、⓷勝養坊、④行賢坊、⑤高塚坊、⑥小池坊、⑦法蔵坊、⑧地蔵堂、⑨中の坊、⑩成就院、⑪常楽院、⑫向田坊、⑬桜本坊、⑭梅本坊、⑮最勝坊
潮海寺八景:い:囁ささやき橋の夕照、 ろ:行賢坊 時雨、 は:塩井神社 塩井戸の浮月、 に:高塚坊 富士見、 ほ:法蔵坊 暮の鐘、 へ:中の坊 螢谷、 と:梅本坊 春霞、 ち:最勝坊 秋の月
更に南に向くと潮海寺の古い山門がある。
・潮海寺山門、仁王像(潮海寺2668⁻1)
・説明:潮海寺仁王門:菊川市指定文化財:潮海寺の始まりは天平年間、行基によって彫られた薬師如来を安置し、780宝亀11年になって寺堂が建てられたことによると伝えられる。「後拾遺往生伝」という文書には、平安時代中期の寛治年間1087~1093に多くの高僧がいたことが記されている。天正年間1573~1592と推定される古文書では、徳川家康の家臣大須賀康高により潮海寺本堂建立のため、河村郷内での用材の伐採を許されている。寺の残された棟札ムナフダによると、薬師堂が1694元禄7年、本堂が1730享保15年に建立されたことがわかるが、二王堂の棟札では年号が確認できず、現存の仁王門のものかも確定できない。ただし地元に残る写しから1705宝永二年9月と推測され、建物の年代観とおおむね合致すうr。二王堂建立の願主は阿闍梨有誉。仁王堂施主(お金を出した人)は西方村山内□□時盛、大工は西方村藤原□□□□□三郎□。仁王像の彩色施主は倉澤村山内徳左衛門、漆師は山名郡袋井町門□与次兵衛と記されている。(□は判読不明)。その記述から、堂の建立とともに仁王像に彩色が施されたようだ。
昭和32年菊川町指定建造物。平成17年1月菊川市誕生とともに菊川市指定となった。
平成元~二年度にかけて大規模な解体修理が行われた。建立当初の茅葺から瓦葺にされていた屋根は解体修理の際に銅版葺きに改めた。解体修理と同時に仁王像に関しても調査が行われ、所見では、江戸時代中期の在地仏師による作で、玉□に彩色された仁王像とは異なると考えられる。
・秋葉山常夜燈、・石段、・薬師如来:文政□□、
更に南に神社というか祠がある
・津島神社(潮海寺560⁻1)
・祠:不動明王像、・手洗石、・石塔、
南60mに祠がある。
・祠:杉葉屋根葺き、・木鳥居、
250m南進し、右折(西)120m、右に祠がある、
○祠:神(潮海寺2788⁻3)
・いくつかの五輪塔上部、・いくつかの自然石の丸石、
30m西進。
○新宮神社(潮海寺2810⁻1)
・金属鳥居:平成二十一年、・石柱2:御大典記念、・奉燈2:大正三・四年、板碑:勅忠・族忠、手洗石:明治三十年、・大木2~5、
100m西進。
○長泉寺(潮海寺2582⁻3)
・自然石、・地蔵2、・山門、・台座のみ、・馬頭?:天明八、・千部塔、・十部塔、・石塔、・庚申供養塔、・西國三十三所玉砂埋蔵供養塔:文化十三子年、・不許藝術賣買人入門、・萬霊等:寛政八、・制葷酒、・堂、
~~~
再び北の山門を過ぎておまつり広場へ戻る。
山門を過ぎておまつり広場手前の反対側の西には「⑮」がある。
・「⑮最勝坊跡」「ち:秋の月」(潮海寺2120⁻8)
⑮から西150m地点には⑭と「と」がある。
・「⑭梅本坊跡」「と:春霞」(潮海寺2659⁻1)
⑭から西150m地点には⑬がある。
・「⑬桜本坊跡」(潮海寺2655)
⑬から南西500mに⑫がある。
・「⑫向田坊跡」(潮海寺)
⑫の南西150m地点に神社がある。
・日吉神社(堀之内、宮前664⁻3)
・石柱2:昭和七年、・石鳥居:大正二年、・石段2:大正九(元)年、・献燈2:平成七年、・手洗石:平成七年、・狛犬2:平成七年、・祠:津島神社、・祠:金刀比羅神社、
潮海寺山門北の「おまつり広場」までまた戻る。
「おまつり広場」の北を目指す。まずすぐ西北の茶畑であるが、かつては地蔵があったようだが、見つからない。
・茶の木地蔵(潮海寺2120⁻7)
未発見。おまつり広場より70m北に現在の潮海寺がある。
その手前には大門があったらしい。
・大門(潮海寺2115)
かつて潮海寺の大門があったようだ。
○潮海寺:おたきあげ寺(潮海寺616)
・堂:遠州□□□大師第十二番霊場、・祠:赤鳥居、・○奉待庚申供養石塔造□:見聞言ザルレリーフ、
・「①学頭坊跡」「②本善坊跡」
真北へ300m進む。途中新幹線上の鉄橋を渡り、薬師堂、八坂神社に至る。かつてはここに巨大寺院があったようだ。
○潮海寺薬師堂(潮海寺2103⁻1)
・「い:囁ささやき橋の夕照」()
・説明:潮海寺 薬師堂:現在薬師堂が建っている所と墓地の付近にある大きな石が昔の建物の土台石と考えられ仏教文化の跡が偲ばれる。薬師堂の所にある礎石は33m前後の間隔があり縦横67個が数えられる。現在の畳を敷き詰めたとすれば百数十畳の広さをもった建物が想像される。礎石は3種類以上の物が混在している。また散在する布目瓦も平安鎌倉…と数種類がある。桓武天皇の頃、坂の上田村麿が七堂伽藍を建てたという話が残り元禄時代に再建した文書や棟札がある。そこで800年以上前からかなり大きな建物があったようで、幾度か立て直しが行われたことが偲ばれる。またこの台地一帯は山城跡であるとも言われ、立地条件も整っているし横地に対する今川氏の出城武田氏の遠州攻略には徳川方の砦として兵火にあったといわれる。昭和51年調査で薬師堂側で33個、墓地側で25個が確認、西南の墓地附近まで広がっていることが分かった。
・石燈2:明和三、・礎石4:70㎝、・鐘楼、・大円堂、・木鳥居、・自然石4:縦長、・新:十三仏:薬師は本尊で堂内にあるのでここにはない、・三面観音、・堂:金毘羅宮、・西國三十三所観音供養塔、・善光寺供養塔2、・□□□圓供養塔、・善光寺供養塔:文政□未年、・堂:弁財天、・板碑:佛天、・三十三所供養塔:文政元年、・石塔:寛政二年、・手洗石:享保十四年、
・「⓷勝養坊跡」
○八坂神社(潮海寺1959)
・説明:祭神:すさのおのみこと、例祭日:7月23日より25日、由緒:天平の中頃の創立。人皇45代聖武天皇の御代、広厳城山薬師堂山の良の頂上へ勧請し奉る。牛頭天皇と尊称し、薬師如来の御前立と定め、潮海寺の鎮守とし、なお本村氏神と尊び奉る。慶長12年造営、寛永年間造営、天保3年造営、正徳壬辰年造営、宝暦4年造営、遷宮式の棟札あり、明治4年、神仏混淆禁止の際、神仏分離して八坂神社と改称す。昭和6年1月、村社に列格す。
・説明:素戔嗚尊、大祭日:祇園祭は人々の厄を祓い農作物の豊穣を祈願する祭だ。平安時代の古式ゆかしい神輿の渡御を賑やかなお囃子にのって屋台がお供をする。屋台が仁王門の石段を下り上りするさまは実に勇壮だ。昔は毎年、京都八坂神社の祇園祭と同じ期日に行っていたが、昭和初期頃から茶の生産時期と重なるため、7月23~25日となった。27年からは3年に一度となり、更に63年からは7月23日に近い土。日を入れた3日間行われることになった。
由緒:天平の中頃740人皇45代聖武天皇の御代、廣厳山薬師堂の鎮守として、牛頭天王を境内の艮コン(東北)の方位山頂に祀った。これを「お天王さま」といって、村民の氏神とし、江戸時代末期まで栄えた。
明治4年神仏分離令によって、祭神の牛頭天王は素戔嗚尊であるとし、社名を八坂神社と改称した。神殿は仏法の守護神であるが故に薬師堂境内地を分割分離した。現在も神社と寺が同一境内地に共存すうr神仏習合の形態を留める神社は少なく往時の面影が見られる。昭和6年1月、河城村村社に列格、昭和20年敗戦により無格社となり、現在は9等級神社。
神社境内地には、合祀社「金山社、白山社、いざなぎ社、奥津社」、「金毘羅社」
祭神説明:素戔嗚尊はとても気の荒い神である。尊は高天原で天照大御神に乱暴を働き、天岩戸事件を起こして出雲の国へ追放された。そこで尊は出雲の国、簸川ヒノカワの上流に人が住んでいることを知り、鳥髪に天下って「八岐大蛇ヤマタノオロチ」を退治して櫛名田姫を救い妃にした。その子供が大国主命である。その大蛇の体内からは天の叢雲ムラクモの剣が出た。この剣を持って日本武尊は東夷征伐に行き、賊軍に焼き討ち攻めに遭ったとき、この剣で草をなぎ倒したことから、草薙の劔と呼ばれ、熱田神宮に祀られている。
・祠:中に祠5、・石柱2:大正四年、・社名碑:村社八坂神社:昭和十二年、石鳥居:昭和四十二年、・献燈2:平成十六年、・手洗石:明治□□□、・石段、
当地より東北へ200m進む。途中老人ホーム前を通過し、やや南に進む。
・「④行賢坊跡」「ろ:時雨」(潮海寺758)
北方面に150m進む。右(東)へ「は:塩井神社、塩井戸の浮月」の標識があるので、右折する。150m東進する。左(北)へ60m。
○「は:塩井神社、塩井戸の浮月」(潮海寺)
・説明:奈良時代、広く人々に知られ、南西にある潮海寺は聖武天皇の頃、潮井戸に因んで潮海寺と名付けられた。郷土の産んだ国学者:栗田土満:菊川市段平尾八幡神社官は当時の情景を「木の葉もる月の光も卯の花も桜も雪と波とこそ見れ」と歌った。当時の潮(塩)井戸は塩分を含む鉱泉が強く湧き出ていたが、安政の大地震によって地層が変化し46mほど北側から噴出するようになった。この井戸は3年に1度、7月に行う潮海寺八坂神社の祇園祭の時、お水とりの神事に用いられる。八坂神社と薬師堂は南の塩谷坂を上りきった西の森にある。
先ほどの標識まで戻る。ここからまた北を目指す。400m北進。
・「⑤高塚坊跡」「に:富士見」(潮海寺)
すぐ東側の丘頂上周辺のようだ。ちなみにこの時カモシカがいた。
700m北進し、左折(西)し600m西進する。また右折(北)し200m。右(東)に標識がある。
・「⑥小池坊跡」(潮海寺)
西進70m。
○薬師堂:奥ノ院:岩井堂(潮海寺)、水源
・献燈2、
潮海寺の巨大寺院の北端のようだ。120m西進。左折(南)400m南進。
・「⑦法蔵坊跡」「ほ:暮の鐘」()
150m南進。坂を下った所に石仏がある。
○石仏(潮海寺)
・石祠:道祖神、・「道祖神」、・地蔵、
50m南には「奥の池」である。
・「奥の池」(潮海寺)
300m南東進。橋の袂に標識がある。
・「⑧地蔵堂跡」(潮海寺)
90m東進。広い道に合流する手前に石仏がある。
・「馬頭観音」(潮海寺)「柿田」
かなり摩耗しているが馬頭である。
ここから南進すると潮海寺参道方面に近付くし、途中の250m南進し右折すると「通りの尾根:相良往還」や「⑨中の坊」「⑩成就院」「⑪常楽院」への道となる。
これで潮海寺地区の説明を終わる。
~~~
潮海寺仁王像山門参道前から津島神社横を東へ目指す。200m東進で水神橋手前に達する。この左上に神社がある。
○水神社(潮海寺)
・祠:水神社、・石碑:水神:昭和四十九年、
水神橋を渡って和田へ出るルートがある。一方で現在の潮海寺のある所を真東に進み台地を東へ下って、南の潮海寺橋を渡って和田に出るルートもある。
和田集落のJR東海道本線北側に接した所に石仏がある。
・馬頭観音:昭和十一年三月(和田36)
線路の北側を東に進み集落を抜け、大井神社方向を目指す。和田、谷田部集落の東端から東へ300mである。
○大井神社(和田426)
・秋葉山常夜燈:木造瓦葺、中の燈も木造、・祠:五輪塔、・石鳥居:明治四十年、・手洗石、・石柱:横倒し:奉御成婚和田在郷軍人會、
~~~
ここから街道は南の踏切を渡るがその前に周辺を紹介する。
大井神社前を300m東進すると吉和橋を渡る。この右(南)にJR東海道本線のレンガアーチ橋がある。
・レンガアーチ橋;
さらに300m東進する。
○西福寺(吉沢523)
・菊川地蔵巡り第七番、・自然石燈籠、・巨石3、・新:地蔵、・一石3仏:南無阿弥陀佛、・南無観世音菩薩所、・子持石、
・石道標:南無阿弥陀佛 右ハかなや 左もびい乃去涅
~~~
大井神社前に戻り、神社南側の東海道本線の和田踏切を渡り、法明寺横に出る。しかし法明寺は既に廃寺となっている。
○法明寺跡:和田公民館(和田)
・説明:法明寺の歴史と解散整理事業の概要:この地に法明寺と称する曹洞宗の寺があった。創立不詳。1623元和9年没の妙照寺4世、宝岩玄珠大和尚による開山と伝わる。
かつて法明寺は、9月2日~3日の毘沙門天のお祭りに浪曲が演じられ、夜店が出たほど賑わった。400年近く存続した寺だったが、川端玄猛住職の長期入院(平成13年没)により宗教活動ができなくなり、昭和59年に檀家が全て離檀して寺は荒れ果てた。
平成18年5月、玄猛和尚の兄が没して寺が無人になったのを期に、にわかに法明寺問題解決の取り組みについての話が持ち上がった。寺の前を通る県道吉田大東線緊急交通改善事業もその要因の一つであった。当然のことながら、この取り組みは和田区民が負う成り行きとなった。
地元選出の市議会議員、戸塚正晴氏の献身的な協力と菊川市の支援を得て、最初に取り組んだのが寺役員の再構成であった。組織の要となる、兼務住職と代表役員に、妙照寺住職の城達明師の就任承諾を得ることができ、法類に法幢寺住職、青葉茂雄師、法友に西福寺住職、末永無相師の就任受諾を得た。責任役員には信徒の資格で、北原勝、山内静、赤堀博が、干与者には岩堀和雄の就任が決まり、平成19年1月、法明寺の新たな組織が成立した。
以後、法明寺は県道拡幅工事の用地売買交渉、境内にある国有地の買収、荒れ果てた境内地の整理等を行うとともに、最終の目的である宗教法人法明寺の自主解散に向けて宗務庁と折衝を重ねた。
平成21年12月宗教法人法明寺の自主解散が承認され、平成22年5月、清算が結了して法明寺の残余財産の全てが和田地区に帰属した。
玄猛和尚のご母堂、川端明治様の遺産金相続人23名の方々から、和田地区発展のためにとの趣意で多額の寄附を賜った。この事業の推進の大きな支えとなった。平成23年3月和田法明寺解散整理事業実行委員会
・和田毘沙門堂、・法明寺鬼瓦、・旧毘沙門堂鬼瓦、
・石道標:南 沢水加ヲ経テ川崎、相良ニ通ズ 西 作道 北 本所ヲ経テ堀之内ニ通ズ 東 吉沢ヲ経テ金谷ニ通ズ 大正十二年四月 第八部青年團
この石道標は裏面を表にして固定してあり、表面は金網冊に面していて10㎝程の隙間から読むしかなく、とても読みづらい。しかし保存してあるだけでもありがたいことだ。まさにこの石道標が川崎街道があることの証明でもある。
一旦南側を東西に延びる県道菊川吉田線に出て、東へ30m進むと、南東に分岐する県道菊川榛原線(現在の川崎街道)の起点がある。ここから東南東ないしは東に向かって1.8~2.0㎞進む。沢水加公会堂が左(北)にある。その裏山には神社と墓地、堂、祠もある。
○沢水加公会堂、西宮神社、墓地、堂(沢水加725)
・板碑:殉公碑、・時計台:コンクリ製、・石柱4:大正四年、大正十三年、・大谷内竜五郎の墓、・板碑:流芳墓地、・標識:入会地奪還記念誌、
・堂:大日如来、・祠:観音4、如来1、地蔵7、地蔵の首1、
・建設沢水加青年團:大正拾弐年、
・石鳥居、・常夜燈:平成元年、・狛犬:陶製1、・手洗石:平成元年、・祠、
250m東進する。沢水加橋手前、左(北)の御宅前に標識がある。
・標識:移築された中条景昭邸(沢水加788:栗田氏宅)
沢水加橋を渡って左2軒目の加藤氏宅:沢水加902で川崎街道の古道について聞く。向かい(右)の倉庫前の植え込みに石道標があり、その前の道が山斜面に向かい延びていき斜面を上っていく。その道こそが川崎街道の古道残存部分である。地元民は軽自動車で上ってしまうようだが、私の軽自動車はスタックして進まず、加藤氏倉庫周辺に駐車させてもらった。
・石道標:東川崎相良道 北金谷道 西堀之内道
植え込みの中によくまあ保存してあったものだ。
・古道残存部分:沢水加←→仁王辻(沢水加902)
道は始めは少しだけ簡易舗装されているが、すぐに土道になる。その土道もよく観察すると、斜面に対し直に上る道とその横から斜面を斜めに斜めに上ろうとする道に分かれていることが分かる。つまり、直に上る道こそが古道であり、斜面を斜めに上る道が付け替えられた道であることが推定される。道の距離は県道分岐点から上の坂を上りきった所までで1.2㎞、標高差110mである。途中に沢水加調整池のタンクがある。
坂を上りきった所には磨滅した石仏3体がある。
・石仏3(菊川市沢水加904)
・地蔵、・石仏、・馬頭?
坂を上りきって茶畑や家々を抜け国道473号線を横断し、東へ向かうと言いたいところだが、古道や旧道は不明というか区画整理され切って直線道しかないうえ、東名高速道路相良牧之原インターチェンジ開設のため、周辺は再開発され古色がまったくなく、とりあえず東に進むしかない。東名高速道路の北側を東に進んでいく。東名のすぐ北側の側道の左(北側)に祠がある。
○こげんじ稲荷(牧之原市静谷、牧之原南2620⁻6)
・赤鳥居:平成二十三年、・祠
さらに200m東進すると、東名高速下をガードでくぐり南側に出て、県道菊川榛原線を1.1㎞東進する。
右(南)に神社がある。
○秋葉山神社(牧之原市東萩間、水吞764⁻1)
・コンクリ石柱2、・鐘40×20㎝、・石鳥居:大正十三年、・手洗石:平成十四年、・常夜燈2:平成十三年、・古木10~15、
県道へ戻り850m東進する。左(北)100m先の牧之原南一組集会所の隣に祠がある。
・祠:神、手洗石(静谷、牧之原南2519₋2)
県道に戻り550m東進する。右(南)180m先に鳥居もないが神社らしき堂がある。
・神社(白井、大久保1342)
・本殿拝殿、・鬼瓦2、
ちなみのこの辺りの地名は、東進している県道によって分けられている。というより県道がかつての境界線である。県道より北側が旧榛原町、南側が旧相良町である。合併してどちらも牧之原市である。
県道に戻り600m東進を続ける。左(北)100m先に祠がある。
・祠:地蔵3(静谷朝生)
周辺は茶畑で目印はないが、茶畑の中の祠なので多少目立つ。
県道に戻り1.5㎞東南進を続ける。旧榛原町白井、追廻地区で県道は左へ曲がり真東に進む。
・戸塚坂、掛川坂
追廻で曲がって1.5㎞程は平坦だが、そこから先は急な下り坂となる。この坂を戸塚坂とも掛川坂とも呼ぶ。400m下ると左(北)に鳥居がある。
○稲荷神社(勝俣、橋向2467⁻13)
・赤鳥居、・堂:稲荷像多数、
あと150mで下りきって、住宅街に入る。150m進むと交差点があり、右折(南)し180mで戸塚橋がある。渡って70mで静波三丁目の県道の交差点となる。ここが田沼街道との合流点である。右折(西)し田沼街道である県道を50m西進し、また右折(北)すると前方に神社がある。
○稲荷神社(静波三丁目628)
・石鳥居:昭和十一年、・コンクリ石柱2、・手洗石:明治四十年、・献燈2:昭和八年、・秋葉山常夜燈:竿部分が自然石でよい、
・石道標:
・説明:三丁目の道標:天保七丙申年1836の春に建てられ、世話人は□吉、銀蔵、太兵衛の3人で、石工は相良の藤五郎と背面に刻まれている。
この道標の特徴は、
「大井川道」は行書体で、「かけ川道」は行草体で、「さがら道」は草書体で書かれ、三面の「道」という字が異なった書体で書き分けられている。
大きさは縦横28㎝、高さ1.28m
純然たる道標である。
正面の「かけ川道」は戸塚坂を上り、大沢原から仁王辻を経て沢水加を通って堀之内から西出口に出て掛川に達する道である。
この石道標がちょうど成滝や伊達方の石道標と同じく四角柱で呼応するかのようであるが、内容や表示に共通点はそれほどない。しかし、これで川崎街道の起点、終点を指し示し灌漑深いものがある。
~~~周辺~~~
沢水加から仁王辻への古道を紹介したが、現在の県道での上り下りの道は別箇所にある。
古道から上って東の国道473号線に出る。そこで国道を北へ550m進む。そこに左へ下る県道菊川榛原線がある。下って1.1㎞、下りきる300m手前に標識がある。
・大井航空隊洞窟(菊川市沢水加)
県道から沢沿いに30mほど歩くと洞窟がある、どうも防空壕として掘られたようだ。戦争遺跡である。牧之原台地上の布引原には大井航空隊基地があった。
・参考文献
・「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ‘96、
・「ゼンリン住宅地図」
・「2万5千分の1地形図」国土地理院、昭和50~平成10年代
・「2万分の1地形図」陸地測量部、明治20年代
・「静岡県 県別マップル道路地図」昭文社、’00
・「東海道 静岡県歴史の道」静岡県教育委員会、平成6年
・「日本石仏事典 第二版」庚申懇話会編、昭和55年
・「静岡県の中世城館跡」静岡県教育委員会、昭和56年
・「静岡ふしぎ里かくれ里」鈴木茂伸、静岡新聞社、’05
*住所地は目的地を探すためのものなので、分からない時は附近のものを指し示すことが多い。
*未発見や誤解曲解している箇所が多いと思われるので、コメントをいただくか、その人なりの発表方法で公表していただけると、ありがたいです。
特に牧之原台地上での発見できた石造物の少なさは、気になるので、まだたくさん未発見物があると思われます。公表されることで保存へ弾みがつくことでしょう。
~川崎(掛川)街道、福天権現道、大頭龍権現道、金谷街道(静岡県掛川市、菊川市、島田市、牧之原市)~
現地調査:’16 4/9,10,16
川崎(掛川)街道は、掛川市成滝の旧東海道や、伊達方の旧東海道から南に分岐して菊川市西方の竜雲寺(福天権現)や加茂の大頭龍神社への参詣道であり、更には西方から相良坂(公文名、)潮海寺、和田を経て沢水加サバカから牧之原台地を上り仁王辻を通過し三栗原、水吞、白井追廻で左折し戸塚坂(掛川坂)を下り、戸塚橋を渡り榛原静波三丁目で旧田沼街道に接続するルートである。榛原静波の川崎はかつて港があり、海運及び海産物取引が盛んだった。榛原周辺は掛川藩領が多く、藩で徴収する年貢米や、川崎湊へ運ばれる江戸扶持米の輸送ルートであったそうだ。距離は約23㎞である。~『定本静岡県の街道』より~
金谷街道は仁王辻から金谷宿までの道である。
~川崎(掛川)街道、福天権現道、大頭龍権現道(静岡県掛川市、菊川市、牧之原市)~
~1 掛川市成滝ルート~ ナルタキ
・石道標:福天大権現 大頭龍大権現 従之大頭龍大権現□□□福天大権現□□□ 従是川崎道 行程六里(掛川市成滝96、掛川市農協JA西山口支所)
・説明版:大頭龍大権現と福天大権現の参道標である。昔は掛川宿と深い交流のあった川崎湊(現在の静波)に続く川崎街道と言って多くの人々に利用された。元の位置は約10m東にあり川崎街道起点となっている。
昔は各所への道案内として主な辻に、道標みちしるべが建てられた。そしてその道を往来する人たちの案内役を果たしていたが、最近は時代とともに次第にみうけられなくなくなってきた。西山口農協支所西角の道標は、郷土の文化遺産として、昔の時代を知る存在だ。建立時期は不明。伊達方にある道標が類似していてそちらは寛保二1742年と刻まれているので、その時期と推定される。大頭龍権現は菊川市加茂に、福天権現は菊川市西方竜雲寺境内にあるが、当時は両権現の信仰が盛んで、信者等はこの道標から裏丁通りを経てそれぞれの目的地まで歩いて行った。また川崎街道の分岐点でもあることから、堀之内、川崎湊、両方面を往来する人たちには、唯一の街道だった。なおこの道標から東へ150m直進し伊達医院角を右折すると県道37号線である。この道路は大正4年1915に建設されたが、それまではすべて菊川または川崎方面に行く人たちの当地を起点とする往来の主な役割を果たしていた。
古い記録には、「川崎街道は里道にして、本村字成滝より東海道に接続し、阿弥陀寺橋を渡り、本村字満水村の大部分を経て、満水坂を越え、隣村西方村に至る。阿弥陀寺橋、従前は掛川城主にて、簡素なる板橋を架し交通の便を図りしも、城主転任と共に村費を以て架橋せしが、少しの出水にても流失し、為に大六山などを越えざるべからざる不便もしばしばありたり。故に成滝村満水村合同し、明治4年1871,8月新規架橋す。この諸金67両2分3朱、残銭1貫4匁、この橋できた後は従前より大いに便利得たれども、数年ならずして流失するに至れり、是に於いて満水、成滝、宮脇の3村協議の上、其の筋に架橋出願許可を得て、明治9年1876より工を起こし、この8月中竣工す。橋全長21間、幅7尺、この経費金113円44銭7厘。翌月即ち明治9年9月より明治13年1880,8月まで満4年閒橋銭を申し受くることとなれり。この橋は今の所より20間ばかり下流にあたれり。」と記されている。
・いぼとり地蔵堂(成滝49⁻11)、手洗石、
創建不詳、大正2年改築、妊婦子育て中の主婦の参詣者多く、いぼとり地蔵と云われる。ガン封じに来る人も多い。
地蔵堂から阿弥陀寺にかけて道幅が狭く、古道の雰囲気を残す。
○阿弥陀寺(成滝120)
・地蔵菩薩1.2m:堂、台座0.6m、地蔵0.4m、安政大地震により当寺も損壊したため明治25年頃修復の時に、参門を南の川崎街道より入るようにしたので、同時に地蔵も境内に移し信徒等により頭を取り付け参門に祀ったと伝わる。昭和50年代に山門修築の際現在地に移された。毎月有志によりて念仏供養が行われている。それ以来地蔵は首から上のことを何でもかなえてくれる霊験あらたかな地蔵であると言い伝わる。平成10年阿弥陀寺。
・六地蔵、観音、・板碑2、・正覚山阿弥陀寺供養塔、・赤鳥居平成七年、・諸獨稲荷、・墓石:延宝九、江戸中期後期墓石、
・秋葉山常夜燈 平成六年(成滝115の裏)
‘93年版ゼンリン住宅地図では、この場所に秋葉神社となっていて狭いなりに境内がある祠のようなのだが、現在は墓地と新しい秋葉山常夜燈だけである。規模が縮小されたようだ。
~周辺~
現在の川崎街道(県道37号掛川浜岡線)の旧東海道からの起点、古道より東に150m地点である。
・石道標:□□□記念西山口村 石工有治 □□□町 □□□町 □□□町 □□□十町 □□□町(成滝395⁻4)、上部欠損
四角柱で楷書体で記入されているので近代物と思われる。
・双胎道祖神(成滝91)
この御宅の方は石造物趣味があるらしく他の石造物も設置されている。
・地蔵:祠(成滝132⁻3)
○神明神社(成滝278)
・コンクリ手洗石、・手洗石:古、・石鳥居:明治三十八年、・秋葉山常夜燈 文化十年酉七月、・石柱2:大正五年、
・新:東海道標識、祠:馬頭(成滝315₋2)
国道1号線から旧東海道へ分岐する地点。
○若宮神社(逆川336)、説明版:祭神:すさのおのみこと、おおきさぎのみこと(仁徳天皇)、例祭日:10月10日、由緒:すさのおのみことは天照大神の弟で文武に優れ出雲国を平定した神、八坂、津島、氷川等の社に祀られる。当社は池下村若宮の谷に鎮座していたが、寛永元年現在地に建立、昭和61年改修、おおきさぎのみことは人徳高く慈悲深い仁徳天皇であり、今より400年前悪病全治祈願して数日にて全治す。その神徳のありがたさに発願、氏神として合祀さる。
・石柱2:御即位紀念、・石鳥居:昭和五十七年、・シイノキ:市指定保存樹木、
・鞍骨の池(逆川422)
室町初期の南北朝期、周辺で戦があり、勝った南朝方が捕虜にした北朝の今川氏の家臣、堀越入道に鞍をつけたまま入水させ処刑したという伝説の池。
~~~
成滝の阿弥陀寺の山門前を東へ通過し山口橋に達する。上記によれば古い橋は36m下流だそうだ。山口橋を渡って現在の県道に出て満水タマリ地区を東進する。
北に山が見えだし、西満水バス停前になると、北の山に神社がある。
○高畑神社(満水538)
・石段、・コンクリ手洗石:昭和十四年、・石鳥居:昭和十四年、・祠2:津島神社、金比羅神社、・石柱2、・コンクリ献燈2:昭和拾四年:シックなシンプルデザインで美しい、
県道掛川浜岡線を東へ250m進むと北50mの山先端部に祠や堂がある。
・祠:坂東壱番観世音:新:観音:平成十四年(満水658)
東隣には堂がある。
・薬師堂:・手洗石(満水673₋2)
また県道に戻り150m東進する。北に満水公会堂がある所を左折(北)し北上する。
東に祠がある。
・祠:如意輪観世音、・手洗石:大正十一年(満水755)
また県道に戻り800m東進する。左に「思い出の家」レストランの看板があり、そこで左折(北)し、北東に進み、「思い出の家」手前でまた左折(北)し100m北上すると神社がある。
○一色神社(満水1386)
・祠、・コンクリ石段、・献燈2、・コンクリ手洗石、・石鳥居:平成十九年、・石柱2:昭和十五年、
満水地区の現在の県道を東進したが、実はこれが古道ルートではなく、満水地区の石造物紹介の為通過したようなものである。満水の古道は現在の県道やJR東海道本線、新幹線よりも南で「つま恋」より手前北の道である。
そこで一旦西満水バス停辺りまで戻り、線路下のガードをくぐり南に出て南の山(つま恋)手前の道を東進する。菊川市との境界線付近でちょっとした丘があり、線路はトンネルとなるが、道はつま恋ゲートへの道を上ることになる。おそらく古道は線路南の農家の辺りから線路沿いにトンネル上の丘を越えた(推定:満水坂)のだろうが、そこは現在道がないので、つま恋ゲートへの道で丘上を越え、満水を東進してきた先ほどまで使っていた県道に出て、右折で東進し、すぐトンネルを通過し菊川市となる。市境はトンネルとなるが無論近代の道だ。ここまで遺物類は発見なし。
トンネルをくぐり菊川市に入り200m東進すると右(南)横にJR線路が近づき隣に平行になってくる。線路向うに鳥居や祠が見える。ここから右折する道がないので、竜雲寺を過ぎてから右折することになる。そこで竜雲寺までさらに200m直進する。
○竜雲寺:福天権現(菊川市西方、田ケ谷3780⁻1)
寺の裏の県道沿いに祠がある。
・献燈2:大正四年、・堂:馬頭観世音2:平成十五年、
寺の境内地のものは以下である。
・堂:福天大権現、・観音、・三界萬霊2:施主山﨑 大正:遠江三十三所等掛川市周辺でよく見かけるものでありここにもあった、・手洗石:平成五年、・新:地蔵、・新:六地蔵、・旧:山門、
裏山石段上には稲荷神社がある。
・石祠:小稲荷多数、・コンクリ石柱2、・石鳥居:竜雲稲荷、・赤鳥居5:平成二十一年、・祠:小稲荷:多数、・狛犬の稲荷2、
伝説:昔、天狗が取付いた者がいて福天権現になったという。南の山に埋もれていた福天ゆかりの物もあるという。遠州十二坊の一つである。南の山とは田ケ谷神社のことか?
*参考『静岡ふしぎ里かくれ里』鈴木茂伸、静岡新聞社
石道標に目的地としてまで刻まれた福天権現であるが、陽春4/9土曜日、週末の昼に、境内には参詣人の姿はなく、本堂に隣接する住居棟の改築中で、大工さんたちが忙しそうに働いていた。福天権現と言ってももはや知る人も数少ないだろう。
寺門前から県道向うの南に線路下をくぐるガードがあるので通過する。
・JR高架線路橋(西方、田ケ谷3850₋2)
レンガ作りのアーチ構造でレトロであり、准文化財級である。将来は文化財だろう。
高架下ガードをくぐるとすぐ目の前に鳥居や常夜燈がある。
○田ケ谷神社(西方、田ケ谷3850₋2)
・石鳥居:大正四年、・常夜燈2:天保十衹七亥夷則下慮、・手洗石:コンクリ補修、・石段:宝暦八寅年、・祠、・本殿拝殿、
ちょうど桜がはらはらと散り際であって、散歩する人、写真撮影する人たちがいた。
鳥居前から線路沿いに300m北西進すると左(西)50m先に鳥居や祠がある。この道は線路横に直線で作られているが、線路ができる以前はもっと婉曲していたのではなかろうか。おそらく掛川市満水から満水坂を越えてきた古道はこの道に接続したのではなかろうか。残念ながらこれ以上北西進する道は現在ない。古道は完全消失したのだろう。
○神社(西方、田ケ谷)
・コンクリ石柱2、・石柱2:横倒し、・祠、・手洗石:寛政十二年、・石鳥居:大正九年、・石段:昭和六十年、・堂:子聖大権現、・常夜燈2:明治丗九年:1体はコンクリ補修、
ここから東南の大頭龍神社を目指す。
先ほどのJR線路高架ガードレンガアーチの東300mにもレンガアーチがある。
・JR高架線路橋(西方、田ケ谷3798)
線路沿いをさらに300m東南進する。菊川運動公園への標識があり、次に目指す大頭龍神社へ右折するが、その前に線路北側の遺物を紹介する。
西福寺、田ケ谷八幡神社である。『遠江三十三所観音霊場巡礼道』より一部抜粋する。
○西福寺(西方、田ケ谷3597⁻1)
・鐘、・手洗石、・祠:神、・三十三観音、・地蔵、・奉納大乗妙典、・庚申塔:田ケ谷連中、
○八幡宮(西方、田ケ谷2608)
・石柱2:昭和五年、・祠2:神、・手洗石、・石鳥居:大正九年世界戦争終局記念、
・秋葉山常夜燈:昭和十一年:センサー付き電球、
線路際の菊川運動公園への標識のある交差点で右折(南)し300m南進する。右100m先に神社がある。
○熊守神社(西方2716)
・献燈:昭和七年、・手洗石、・石鳥居:大正九年、・石柱2、
・大頭龍神社への福天権現からの最短推定ルート
熊守神社から更に南に道なりに600m進むと東名高速高架下ガードをくぐる。さらに300m道なりに南進すると直進不能になるので、その前に左折し東南進する。道なりに700m進むと川沿いの交差点の低い所に出る。ここで上る直進をやめる。
というのもこのまま直進して大頭龍神社を過ぎてしまったためである。自動車道としては一本違いの道になるのである。
大頭龍神社へはこの川沿いの低い交差点で左折し川の下流に沿って300m東進する。ここでT字路に出る。右折し東南進する。工場地帯を川に沿い300m進む。ここで広い交差点を右折し右へ左へとカーブする道を300m南進する。広い工場地帯の広い交差点を左折し300m進むと向こうに丘がある。道は直進路もあるが、道の右前方が目指す大頭龍神社であり、神社に直進路からの裏の北口はなく、入口が右(南)なので右折し丘を南に回り込む。左(東)は丘でその上に住宅が見え、右(西)は平坦で広い工場と公園になっている。途中2カ所ほど狭い上り道がある。車で上れるギリギリの道であるが、初めてならやめておこう。確かに表参道への近道ではあり、表参道沿いの住宅への道である。南に回りきると北への参道の上り道がある。
ちなみに先ほど一本違いの道のことを記入したが、その道では先ほどの低い交差点を直進し、上りきった辺りで、車では無理だが、自動車道の上りきった辺りより更に20mほど歩いて左の山上の尾根に出ると、そこが西方と加茂地区の境界線尾根である。その境界線尾根の古道に沿って400m南下し、ちょうど大頭龍神社の真西に到達した辺りで東に1㎞向かい大頭龍神社に出るというのが、福天権現からの最短古道推定ルートである。
大頭龍神社の紹介は次の「2 伊達方ルート」を述べてからにする。
~~~
~2 掛川市伊達方ルート~ ダテガタ
・石道標:福天大権現杏 、 是より 、これより ふくてんごんげん(道、ミチ?)、 寛保二 日坂町建 石屋伊 (掛川市伊達方⒕)
だいぶ刻字が読めず保存状態が成滝の物と比べよろしくない。説明版もない。
西向かいはかつてタバコ屋で一里塚跡という。
・一里塚跡(伊達方31)
・説明:一里塚は慶長9年1604江戸幕府の命により築かれた。江戸日本橋から一里4㎞ごとに塚が設けられ、松か榎を植えて目印とした。旅人にとって夏は木陰、冬は風よけとして重宝がられた。また塚の傍らには旅人の必需品が商われたほか、一服できる休憩の場であった。江戸日本橋から京都まで125里約500㎞。掛川市内には佐夜鹿、伊達方、葛川、大池の4カ所に塚が設けられていた。ここ伊達方一里塚は江戸より57番目の塚として街道の両側に築かれ、南側は現・萩田理髪店東側辺り、北側は現・三浦たばこ店屋敷辺りに設けられていた。当時塚の大きさは直径7間、高さ3間の小山で、一里山と云われた。明治33年頃取り壊されたという。
三浦たばこ店がかつての一里塚だという。現在はその西隣に一里塚石碑がある。一里塚石碑の向かいに大頭龍神社がある。と言っても祠があるだけの5m四方の空間である。しかしここから旧東海道から南に分岐する川崎街道:現在の県道菊川停車場・伊達方線の起点である。
○大頭龍神社(伊達方28⁻1)
・手洗石:摩耗して刻字不明、・石鳥居:昭和丁丑十二年一月六日建之、・石道標:大頭龍神社 従是一里十五丁 昭和五季三月建之 加藤減重、・祠:神祀、・石道標:西方村 堀ノ内駅 ニ通ズ 掛川駅ヘ約一里十四丁 堀ノ内駅へ約一里三丁 日坂村役場へ約十九丁 大正二年十月建設 東山日坂村青年會、
~周辺~
・塩井神社(伊達方、塩井川原485⁻1)
東海道と川崎街道分岐点より東に400mの国道1号線と旧東海道の分岐点辺りにある。あると言っても逆川を歩いて渡らねば神社に到達できない。橋はなく川を徒歩で歩くしかない。神社地から塩水である鉱泉が出るということである。
~~~
川崎街道の起点であるが、現在の県道分岐点なのか東20mの大きい石道標のある路地なのか判別不能である。両ルートとも南へスタートする。100m南進すると逆川に架かる豊間橋に出る。
路地側は土手に出て橋がないので、結局この橋に行き渡る。豊間橋を渡って150mほどで右(西)の水田の道へと100m西へ移動する。ちょうど西1本分の道を移動し南を目指す。水田から住宅のある道になり右(西)に小川がある。すぐにやや広い自動車道に出て横断するが、ここで横断してすぐに西へ10m進み、カーブしている路地を南に進む。伊達方1005₋2:伊藤氏宅東側を南に進む。伊藤氏宅を過ぎるとすぐに大井川用水が東西に横断している。ちょうどこの手前に祠が2つある。
○秋葉山常夜燈(木造瓦葺)、祠:庚申?(伊達方1005₋2)
大井川用水の南側は山斜面になる。その山斜面の取付きにコンクリ製祠がある。
・コンクリ製祠:地蔵2、石塔1(伊達方1005₋2)
この祠の前を東へ向かう山道と、祠の西5m地点から南に向かう山道がある。
上記の道や石仏については伊達方952:伊藤氏談。
私の勝手な推理では、東への山道は、東へ向かうと100m先で付近住民の墓地に出て道が終わるが、かつてはおそらく道が山斜面沿いにうねりながら南に続き、現在の伊達方トンネル(掛川市伊達方と菊川市西方の境)付近につながり、西方へ抜けられる道だったのではなかろうか。
西側の山道はこのまま枝尾根を抜け西側の畑地へ出られるが、また枝尾根を上り詰めることができ、そのまま枝尾根を詰めると現在の伊達方トンネル真上にも到達できる。かつてはトンネル手前の高圧鉄塔跡地辺りから南へ抜けて菊川市西方へ出られる古道があったと推定する。現在この枝尾根は悲惨であり、南に抜ける道らしきを発見できない。
そこで西方へ行くには伊達方トンネルをいったん通過するしかない。そして通過後もトンネル南西方向は工場か作業場が1つある。どうもそこの西北方向から古道が出てきて平地に下り、その工場か作業場前の道を南東に下り、現在のトンネルから下ってきた広い道と交差して南東方向に下り、西方5501:井伊谷氏宅、西方5508⁻1:黒田氏宅前の道へ下りたと思われる。
そこからは首塚様のお堂前を通り、三島神社前の道を通ったというより、西方川の反対側に古道はあったようで、反対側の山すそに沿い奉仕橋方向へ東進し奉仕橋から南東に向かう道に出て、その広い道から東へ曲がり、西方5918₋2:内田氏宅前を通り、その東先で現在は道が消失するが、山に入っていて、東の潮海寺地区の⑩成就院跡地前に出て、通りの尾根(相良往還)と呼ばれる尾根道に出たようだ。
~~~
○お堂:首塚様:説明版:所在地:沢田坂下:首から上の病には、この首塚様へ願をかけ、願い叶えば松笠や穴あき石に糸を刺し齢(年)の数ほど供えなされ。昔から願掛けすると必ず治ると遠近からの信者の参詣が後を絶たない。しかしその由来は定かではない。建武三1336年、今川範国は足利尊氏に属して武功をたて遠江守護となり以後60年が続いた。応永二十六1419年尾張の斯波氏が守護となり、その後約100年が続く。このようなことから鎌倉時代後に武威を張っていた今川方の古名族横地氏も斯波氏に属することになった。しかし今川義忠は遠江を回復せんと堀越陸奥守貞延を総大将に横地・勝間田の本拠地小笠・榛原に進撃、小夜の中山南側の海老名エビナ・影森・公文名一円が壊滅的戦場となった。士将貞延も牛頭ゴウズまで来て惨敗したと伝えられ鞍ごと池に投げ込まれたと言う。この鞍骨池伝説や海老名辺りに点在、祀られている石塔は往時を物語るものと思われる。この首塚様や堂山は、この戦の名だたる武将やかかわりのあった人たちを供養お祀りした場所と思われる。近年は霊験あらたかということで病気平癒と合格の祈願の信仰を集める。平成20年(2008)1月吉日 菊川文化財保存会鈴木利夫氏の文を基にして記入
○三島神社:・庚申塔:平成二十年、・祠3、・石柱:昭和四十一年、
右岸道300m右への道100m奥に神社がある。
広い道(公文名の市道と県道菊川停車場伊達方線)が合流する箇所に石道標がある。
・石道標:「右瀧之谷守本尊ヘ廿五丁 左東海道ヘ十五丁 堀之内駅ヘ廿七丁 大正十四年環居紀念」
~~~
ここから先は伊達方トンネルを通過して、西方に出て、西方から、大頭龍神社へ向かうルートを紹介する。それは自著:「遠江三十三所観音霊場巡礼道」のルート沿いになるので、そこからの文章を組み直して載せる。部分的に文章を追加している。
~~~*『遠江三十三所観音霊場巡礼道』より抜粋し組み立て直す~~~
また伊達方トンネルまで話を戻す。
伊達方トンネルから道を下ると、神社がある。またはトンネルを下ってくる現在の道の西の古道沿いの作業場か工場の西から南の寅尾神社に向けて細い道が付いていたかもしれない、というのも、寅尾神社前にも道らしきがあり、かつての古道かもしれないと考えられるからである。
○寅尾神社:・手洗石:昭和三年、・石柱2、・石段:御大典紀念昭和参年、・板碑、
・狛犬2、・庚申塔2:大正九年、寛政十二、
寅尾神社の南で道が分岐する。
広い道(公文名の市道と県道菊川停車場伊達方線)が合流する箇所に石道標がある。
・石道標:「右瀧之谷守本尊ヘ廿五丁 左東海道ヘ十五丁 堀之内駅ヘ廿七丁 大正十四年環居紀念」
川崎街道メインルートは潮海寺地区へ向かうが、ここから一旦、竜雲寺:福天権現や大頭龍神社へ向かうルートにして説明する。
道の合流地点から100m南へ進むと右にコンクリート擁壁がある。そこに石仏がある。
・石仏:すでに地蔵か観音か不明だが、頭部上部に細長いものがあるようなので、おそらく馬頭観音かと思われる。
100m進む。右に寺院がある。
○洞源院:・地蔵、・観音、・観音:西国三十三所安永四乙未、・手洗石、・昔の鬼瓦、・祠:神、・新四国第八十六番霊場昭和九年、・菊川地蔵尊巡り四番、・洞源院昭和五十年、
・石道標:「記念 東海道一斤八百八メートル 十六町二十間 堀之内駅ヘ二千八百三十二メートル 二十五町五十一間 大正十三年一月廿六日建之 澤田部青年團」
50m進むと東海道新幹線に達する。古道は西方川左岸沿いのようだが、道がないので右岸を迂回する。右岸道150m行って右道奥に神社がある。
○七社神社:・新:献灯2、・石鳥居:御即位紀念大正四年、・常夜灯:明治四十三年、
・石柱2:大正四年御即位紀念、平成二十三年、
右岸道50m進み右奥に神社がある。
○岡の宮神社:・石柱:大正六年、・石鳥居、
岡の宮神社の150m南の県道菊川停車場伊達方線が西方4503₋2山西茶農協製茶工場横へ東に入った路地に石仏がある。
・石仏:馬頭観世音、
右岸道を迂回したが、途中で左岸道が現れて来る。新幹線ガードから左岸道を1.2㎞進むと県道掛川浜岡線の1本北側の旧道に当たる。
福天権現へは、ここで右折(西)して、西福寺、田ケ谷八幡神社、秋葉山常夜燈を通過していくことになる。
大頭龍神社へは、遠江三十三所観音霊場の28番正法寺と同一ルートと推定されるので、先ほどの県道掛川浜岡線の一本北側の旧道で左折(東)する。北の山腹に神社がある。
○山宮神社:・板碑:大正八年、・庚申塚:明治三十年、祠3:神、
・石鳥居2:大正十五年、、献灯2:昭和四年、・祠:子育て地蔵、・手洗石、
・祠:地蔵、・板碑、・秋葉山常夜燈:木造金属葺、・石段:皇太子殿下御降誕記念、
・石柵:平成二十年、
古道的には300m東進して南下して東海道本線をくぐって28番に達するのだが、その古道は消失し、現在は線路をくぐる道はもっと400m東進しないと無いので、そちらに迂回する。28番正法寺の奥さんによればかつては石道標があったそうだ。
迂回したガード下道の100m手前東の丘上に神社がある。
・神社:・お堂、・コンクリ手洗石、南側に階段状参道があるが、草と倒木で使われていないようだ。北側は新興住宅地で道に面しているが、柵と擁壁があり、入口がない。ということは誰も祀っていないのか? ’16 2/11
県道掛川浜岡線と東海道本線に交差する所で線路をくぐる所に戻ってくる。
古道はどうも迂回せずに28番へ直に向かったようだが、現在そんな道はないので、迂回を含めガードをくぐって線路の南に出る。西の山際に28番がある。 ’16 2/11
○第二十八番 拈華山 正法寺(菊川市西方1329、にしかた)ねんかざんしょうぼうじ
創建:天正2年1574、開基:堀田正法、開山:龍雲院三世実伝宗貞和尚、本尊:聖観世音菩薩:寄木造り座像72㎝:伝行基あるいは運慶あるいは逢雲作、宗派:曹洞宗、開帳:秘仏・33年毎、縁起:
旧菊川町の寺院は森の大洞院の流れを汲むものが多い。
桐田氏私見:堀田氏は堀内氏(城飼キコウ郡:小笠郡堀之内城)で正法寺開基は堀之内重親だろう。ただ武田徳川の争乱期で寺院を開基し経営できたかは検討を要する。
安政三年1856冬失火焼失、本尊は免れる。諸堂再建は廃仏毀釈で進まず大正14年1925竣工。堀田城城主堀田正法開基で龍雲院三世実伝宗貞を招いて開創、八ツ谷観音、厄除観音、子育て、縁結び、
・鐘楼:鐘がない、戦時中供出。平成4年鋳造。
・丸い大石:「天保十四年 二十八番札所 正法寺」:参道入口、
・本堂:大正十四年落慶、
・梅古木:本堂前、
裏山は山城:堀田城または松下城、山城の輪郭が残る。中腹には円墳があったが、崩落の恐れがあり1993年発掘調査、記録保存し整地し正法寺霊園になっている。
~追加~
・堀田城(松下城):裏山には上れるし、本曲輪には標識「本曲輪」が立てられているが、他は一切ない。曲輪や堀切があり、しかも二重に切られた堀切が複数あるなどするが、そういった説明や標識類がないことが残念だ。
・円墳:霊園の中央部分らしいが、記録保存して取り壊したので一切わからない。
地元の郷土愛好家グループや教育委員会で標識や説明看板を立ててほしいものだ。
・祠:神を祀る。・供養:地蔵10、・新;献灯、・新:手洗石、・古:手洗石、
・裏山山頂:祠:秋葉山三尺坊大権現、秋葉神社 ’16 2/11
有住、駐車場有、Tel:0537-35-3612
~周辺~
東側の山上には常葉学園(大学、短大、高校、美術館)、楠木神社、菊川神社、大徳寺、公園、グラウンド、市役所、福祉施設、教育施設がある。
不本意だが古道がないので現在の自動車道を東名高速もくぐり1.5㎞進む。
途中東名高速高架をくぐる手前の東に神社がある。
○八幡神社:加茂、白岩東:・石柱2:、・手洗石:(二つ割れ)、
・石鳥居:明治十十十(廿の3本)六年、・献灯2:臺灣(台湾)高雄市織部恭市昭和十一年、・石段、・新:手洗石、・古:手洗石(割れ)、・石段、・狛犬2、
・石柵:昭和六十一年、
左折(東)し県道高瀬菊川79号線を東に800m進む。
途中北の高台に神社がある。鹿嶋神社:古墳でもある。
○鹿島神社:古墳、
・石碑:鹿島神社参道入口 平成二年、石造成記念、・鹿嶋神社表参道 平成九年、・石鳥居:明治三十九年 再建平成六年、石柱2:大正九、・新:手洗石、・石鳥居:平成二年、・石柵:平成九年、・石柱2:大正四年十月 御大典 五丁目氏子中、・石柱2:、・狛犬2:平成六年、・献灯2:平成六年、・稲荷神社:稲荷2:平成二年、・石家道祖神、
・鹿島遺跡:説明版:今から4~5千年前、縄文時代中頃(加曾利E式)の村落跡、道を隔てた北側からは宅地造成の際に二軒の縄文住居が、また遊園地の東部分からも二軒の住居跡が見つかり、土器、石斧、石器の材料の黒曜石斧が発見された。町道より境内に入るために切り取られた道しろ辺りと園地の東南部分で比較的新しい住居跡が発見された。出土土器は八斗地遺跡(旭グランド)の奈良時代のものと似ているのでおよそ同時代の村と考えられる。
・鹿島古墳:説明版:公会堂脇にある古墳は今から1400年前のかなり身分のある人の墓で、周囲には円筒埴輪は巡らされ、直刀を出土し、直径は十数メートルあったが、現在は西半分が残っている。埴輪を伴う古墳は郡下でも数カ所しかないが、そのうち旧菊川町内に3か所ある。高田ヶ原公園に2カ所。役場西の森の高田原の大徳寺前方後円墳は古代この地方の王の墓だが、この王の墓を中心に代々主な古墳がこの台地に作られ、集結している。打上台地は東寄りから南べりに八幡社の円墳まで数箇所に古墳があるが、今はほとんど消失した。この原一帯は湧水のある場所に奈良時代の家が散在し集落を形成した。菊川町の古代は、この高田原台地を中心に文化が栄えていたことを物語っている。
~~~~~
28番正法寺の参道入口に戻り、南へ300m進み右折(西)するか、南へ400m進み豆尻橋を渡り、次の道を右折するかして、西の山際に出る。西の山際で南へ進み、東名高速高架ガードをくぐる。ガードをくぐると五差路になる。左右の高速道の側道ではなく、前方右の工場への広い道でもなく、左側道と工場への広い道の間の前方左(南)の狭い道を進む。ちょうどガードをくぐったところで西方、堀田地区から加茂地区となる。西の山際に沿い300m南西へ進むと、右折(北西)し山へ登っていく道がある。
○井成神社(加茂804⁻5)井成山
・説明:井成山と三浦刑部:稲作文化が進むにつれて、今まで荒蕪の地だった白岩地帯へ水田ができたが、村の中央を流れる西方川も東へ隣接する菊川もともに、川底が低くて田へ水がのらず、干ばつのたびに稲が枯れ死するので、年貢にもさしさわり農民はいつも不作を嘆いていた。ここに三浦刑部という偉丈夫があって、これをだまって見過ごすに忍び図、決然と立って治水の路を開き、村民の苦難を救おうとしたが、当時は排他気分が盛んで許可なく他村へ立ち入ることはできぬ申し合わせがあったので、測量等には嘘や方便、狂気を装ったり、凧を揚げて糸を切り、凧を拾う振りをして隣村に立ち入ったりして、智謀の限りを尽くして、地形、距離、落差を調べ、用地は農耕にかこつけて買収する等、苦心惨憺の末、ついに潮海寺掛下から菊川の水を取り入れる企てに成功し、矢田部から潮海寺・上本所を経て半済を通り白岩・長池に通じる水路を完成した。村民は瀬波を立てる井川の水を見て、一同起死回生の思いに浸り、今もなお刑部の徳をたたえている。それ以来加茂は豊穣の地となった。
・説明:三浦刑部と加茂井水:400年前加茂村は「嫁にやるなら加茂はおよし、加茂は雲雀の遊び場所」と言われ荒れ果てていた。今川軍の武将三浦刑部は桶狭間の戦いに敗れて武士をやめ、農業を志し、清水の里から二人の息子と加茂村にやって来た。田圃の開発を決意した。加茂村は菊川、西方川に挟まれているが川の流れが低く、川の水を利用できなかった。
刑部は幾多の困難を克服して菊川の水を潮海寺村より、半済村ハンセイムラ、本所村ホンジョムラを通り加茂村に導く測量に成功した。13年の長い歳月をかけ、刑部は途中で没したが、二人の息子により井水(用水)は完成した。2千石の米が取れる加茂村が大村としてよみがえった。以後江戸時代はもとより菊川町合併まで延々と流れる井水とともに加茂村は続いた。
村人は刑部の高い志とその恩恵に感謝して、井水の全部が見えるこの山の頂に祠を建て、感謝のお祀りを4月の第一日曜日に加茂地区を挙げて盛大に行われる。なお、この神社は井水が成る「井成神社」と言い、同時にこの山を「井成山」と言う。
用水地図では、菊川の水をJR線路より北側で取水し、菊川の西側を加茂地区に分流して流していることが分かる。
・説明:加茂井水 争いの歴史:
天正九1581年、井水の工事を始める、
文禄三1594年、井水完成、
1700元禄13年、本所村が吉田領加茂村陣屋へ訴える、
1701元禄14年、本所村が幕府評定所へ訴える、
1703元禄16年、加茂村が本所村を幕府評定所へ訴える、
1704宝永元年、本所村と潮海寺村が加茂村を幕府評定所へ訴える、
幕府裁定 刻割り制
潮海寺村0時~2時、本所村2時~6時、加茂村6時~24時、
大井川用水の通水まで続いた
1761宝暦11年、井水の公平を期して総百姓が立ち会って決定した定め書きを作った
加茂村御相給定書
1788天明8年、加茂村が本所村を吉田領地方役所へ訴える
1790寛政2年、終結
1793寛政5年、村内上部落対下部落の争い
1856安政3年、神尾村、潮海寺村の鰐淵井堰の改善について争い
1857安政4年、神尾村、潮海寺村が加茂村を幕府評定所へ訴える
幕府検使が現地検分
1860万延元年、幕府の指示により示談成立
・石段:昭和十一年、・祠、・御夜燈:昭和三年、・石鳥居:大正二年、・手洗石、・金毘羅神社、・石鳥居:大正二年、・御夜燈:昭和三年、・手洗石:元治二丑年:横倒し、
神社のある山は散策コースになっていて周辺の眺めを楽しむことができる。山の名は井成山のようだ。見晴らし台もある。
井成神社への上り口の西にお堂がある。
○堂:一番山長正寺(加茂804⁻5)
・御夜燈2:昭和三年、新:昭和十年(再建?)、・石塔:菩薩、
先ほどの井成神社への参道入口に戻り、150m西進すると、大頭龍神社の大鳥居(東口)がある。
ちなみに福天権現から西周りルートで達した大頭龍神社参道入口(南口)は、ここからさらに400m南進した所である。
○大頭龍神社(加茂、白岩段944⁻1⁻1)
・説明:正一位大頭龍神社:祭神:大物主大神、大山咋大神、出雲龍神、由緒:当神社は往古より御山へ宝祚延長天下泰平国家安穏の御弊氏子崇敬者安全繁栄の御幣を立願にて相建て今日に至る。当社は桓武天皇延暦11年勧請と口碑似て伝わる。御神徳は疫病鎮護厄除縁結びにしてその福徳の神様を奉斎申上げる。現在は建立社殿は宝暦13年、文化12年の修復再建である。鳥居額:神祇管長上従二位卜部朝臣兼雄公筆、拝殿内額:徳川家達公筆、神事:七十五膳奉幣厄除篝火、昭和37年。
東口
・赤鳥居:大正九年、昭和六十三年、・永代常夜燈2:大正十四年、・石柱2:昭和五十四年、社名碑:大頭龍神社:昭和三戊辰年、
北の家の裏山に祠がある。
・祠:神、・
南口
・石柱2、・祠、・石柱2:大正四年、
南口参道入口より北へ240m、本殿前大鳥居より南に150m地点
・永代常夜燈2:文政元年戊寅十月吉日
本殿前
・祠:神、・石柱2:大正四年、・金属鳥居:文政七、・常夜燈2:昭和戊辰之秋、・永代常夜燈⒑:大正十四年、・献燈:昭和三年、・常夜燈:長谷川:文政九年、・永代常夜灯:明治四十三年、・狛犬2:昭和三戊辰、・板碑:聖徳太子、・永代常夜燈2:寛政七年、・石柱2:紀元二千六百年、・石段:文化七年、・永代常夜燈2:文化十三丙子歳、・板碑:寄附人、・板碑6:金壱百~、・手洗石:昭和二十八年、・手洗石、・永代常夜燈(3:文化十三、大正四年、2:明治四十四年、平成二十一年、文化十一)・永代三夜燈(2:文化十三、2:文化十有四年、3:文化十四年)、・常夜燈:破片、板碑2、・自然石:丸石、
桜名所であり、参道沿いは満開時素晴らしい光景だ。しかし桜満開4/9土曜日という週末の15時過ぎの晴れた日に、隣の児童公園に遊びに来た親子連れ2組、近所の人の散歩姿数人のみで、神社受付売店の神主さんも15時過ぎに帰ってしまったので、私は御朱印を貰い損ねた。16時過ぎまでいたが、他に参詣に来た人は0人。大頭龍神社と謂えばかつては遠州きっての名刹、格式ある大神社であるはずで、大鳥居や常夜燈の年号や規模からして江戸時代後期より近代までは、大いに流行っていたはずだ。だからこそ大頭龍神社への石道標があるのだし。しかし現在は静かな神社だ。神社の栄枯盛衰を見た。それにしてもこんな静かな陽春の昼下がりに満開の桜に囲まれたというのは極楽至極ともいえる。
大頭龍神社を紹介したことで、このルートの説明は終了する。次は川崎街道の菊川市西方から潮海寺へのルート説明である。
菊川市西方の奉仕橋から南東に向かう道に出て、その広い道から東へ曲がり、西方5918₋2:内田氏宅前を通り、その東先で現在は道が消失するが、山に入っていて、山坂(どうもこの坂か、次の「通りの尾根」の坂を相良坂と言ったようだ)を上って東の潮海寺地区の「⑩成就院跡」前に出て、「通りの尾根(相良往還)」と呼ばれる尾根道に出たようだ。
~~~
潮海寺地区の「⑩成就院跡」前を通過し「通りの尾根」前に出る。昔は「通りの尾根」を歩けたのだろうが、尾根に取り付くところもないほど雑草に覆われているので上るのをあきらめる。東西に延びるこの「通りの尾根」の北側と南側の平地境には、現在舗装された農道になっているので、そちらを通行する。南回りの農道では「⑪常楽院跡」の標識がある。また新幹線線路際に出て線路高架下ガード前には「⑫向田坊跡地」への案内標識もある。更に南周りを東に向かうと通りの尾根が終わる手前に「⑨中の坊跡」「へ:螢谷」の標識がある。
北回りを東に向かうと、舗装されているがかなり雑草が多く、廃道に近い。雑草を抜けると「田子谷」辺りに出て、さらに東に向かうと通りの尾根が収束しに「⑨中の坊」「へ:螢谷」のすぐ北側に出る。ここで新幹線高架下ガードを南にくぐり、東側の潮海寺への台地を南へ行きつつ上っていき、潮海寺参道入口付近に出て、潮海寺の寺の南を通過し和田へ出ることになる。
~~~
ここで一旦潮海寺地区周辺を紹介する。
潮海寺参道前の潮海寺615₋2:岩水酒店前に出る。ここから南に50m行くと東に「お祭り広場」があり、潮海寺周辺の案内図・説明版がある。
・潮海寺:説明版(潮海寺615⁻9)
・説明:潮海寺は平安時代798~1190頃寺領を中心に大いに栄えた。寺の領域は掛川の成滝から菊川の仁王辻まであったと云われ、この中に75もの寺(坊)を配し、うち潮海寺には15坊があった。
潮海寺十五坊:①学頭坊、②本善坊、⓷勝養坊、④行賢坊、⑤高塚坊、⑥小池坊、⑦法蔵坊、⑧地蔵堂、⑨中の坊、⑩成就院、⑪常楽院、⑫向田坊、⑬桜本坊、⑭梅本坊、⑮最勝坊
潮海寺八景:い:囁ささやき橋の夕照、 ろ:行賢坊 時雨、 は:塩井神社 塩井戸の浮月、 に:高塚坊 富士見、 ほ:法蔵坊 暮の鐘、 へ:中の坊 螢谷、 と:梅本坊 春霞、 ち:最勝坊 秋の月
更に南に向くと潮海寺の古い山門がある。
・潮海寺山門、仁王像(潮海寺2668⁻1)
・説明:潮海寺仁王門:菊川市指定文化財:潮海寺の始まりは天平年間、行基によって彫られた薬師如来を安置し、780宝亀11年になって寺堂が建てられたことによると伝えられる。「後拾遺往生伝」という文書には、平安時代中期の寛治年間1087~1093に多くの高僧がいたことが記されている。天正年間1573~1592と推定される古文書では、徳川家康の家臣大須賀康高により潮海寺本堂建立のため、河村郷内での用材の伐採を許されている。寺の残された棟札ムナフダによると、薬師堂が1694元禄7年、本堂が1730享保15年に建立されたことがわかるが、二王堂の棟札では年号が確認できず、現存の仁王門のものかも確定できない。ただし地元に残る写しから1705宝永二年9月と推測され、建物の年代観とおおむね合致すうr。二王堂建立の願主は阿闍梨有誉。仁王堂施主(お金を出した人)は西方村山内□□時盛、大工は西方村藤原□□□□□三郎□。仁王像の彩色施主は倉澤村山内徳左衛門、漆師は山名郡袋井町門□与次兵衛と記されている。(□は判読不明)。その記述から、堂の建立とともに仁王像に彩色が施されたようだ。
昭和32年菊川町指定建造物。平成17年1月菊川市誕生とともに菊川市指定となった。
平成元~二年度にかけて大規模な解体修理が行われた。建立当初の茅葺から瓦葺にされていた屋根は解体修理の際に銅版葺きに改めた。解体修理と同時に仁王像に関しても調査が行われ、所見では、江戸時代中期の在地仏師による作で、玉□に彩色された仁王像とは異なると考えられる。
・秋葉山常夜燈、・石段、・薬師如来:文政□□、
更に南に神社というか祠がある
・津島神社(潮海寺560⁻1)
・祠:不動明王像、・手洗石、・石塔、
南60mに祠がある。
・祠:杉葉屋根葺き、・木鳥居、
250m南進し、右折(西)120m、右に祠がある、
○祠:神(潮海寺2788⁻3)
・いくつかの五輪塔上部、・いくつかの自然石の丸石、
30m西進。
○新宮神社(潮海寺2810⁻1)
・金属鳥居:平成二十一年、・石柱2:御大典記念、・奉燈2:大正三・四年、板碑:勅忠・族忠、手洗石:明治三十年、・大木2~5、
100m西進。
○長泉寺(潮海寺2582⁻3)
・自然石、・地蔵2、・山門、・台座のみ、・馬頭?:天明八、・千部塔、・十部塔、・石塔、・庚申供養塔、・西國三十三所玉砂埋蔵供養塔:文化十三子年、・不許藝術賣買人入門、・萬霊等:寛政八、・制葷酒、・堂、
~~~
再び北の山門を過ぎておまつり広場へ戻る。
山門を過ぎておまつり広場手前の反対側の西には「⑮」がある。
・「⑮最勝坊跡」「ち:秋の月」(潮海寺2120⁻8)
⑮から西150m地点には⑭と「と」がある。
・「⑭梅本坊跡」「と:春霞」(潮海寺2659⁻1)
⑭から西150m地点には⑬がある。
・「⑬桜本坊跡」(潮海寺2655)
⑬から南西500mに⑫がある。
・「⑫向田坊跡」(潮海寺)
⑫の南西150m地点に神社がある。
・日吉神社(堀之内、宮前664⁻3)
・石柱2:昭和七年、・石鳥居:大正二年、・石段2:大正九(元)年、・献燈2:平成七年、・手洗石:平成七年、・狛犬2:平成七年、・祠:津島神社、・祠:金刀比羅神社、
潮海寺山門北の「おまつり広場」までまた戻る。
「おまつり広場」の北を目指す。まずすぐ西北の茶畑であるが、かつては地蔵があったようだが、見つからない。
・茶の木地蔵(潮海寺2120⁻7)
未発見。おまつり広場より70m北に現在の潮海寺がある。
その手前には大門があったらしい。
・大門(潮海寺2115)
かつて潮海寺の大門があったようだ。
○潮海寺:おたきあげ寺(潮海寺616)
・堂:遠州□□□大師第十二番霊場、・祠:赤鳥居、・○奉待庚申供養石塔造□:見聞言ザルレリーフ、
・「①学頭坊跡」「②本善坊跡」
真北へ300m進む。途中新幹線上の鉄橋を渡り、薬師堂、八坂神社に至る。かつてはここに巨大寺院があったようだ。
○潮海寺薬師堂(潮海寺2103⁻1)
・「い:囁ささやき橋の夕照」()
・説明:潮海寺 薬師堂:現在薬師堂が建っている所と墓地の付近にある大きな石が昔の建物の土台石と考えられ仏教文化の跡が偲ばれる。薬師堂の所にある礎石は33m前後の間隔があり縦横67個が数えられる。現在の畳を敷き詰めたとすれば百数十畳の広さをもった建物が想像される。礎石は3種類以上の物が混在している。また散在する布目瓦も平安鎌倉…と数種類がある。桓武天皇の頃、坂の上田村麿が七堂伽藍を建てたという話が残り元禄時代に再建した文書や棟札がある。そこで800年以上前からかなり大きな建物があったようで、幾度か立て直しが行われたことが偲ばれる。またこの台地一帯は山城跡であるとも言われ、立地条件も整っているし横地に対する今川氏の出城武田氏の遠州攻略には徳川方の砦として兵火にあったといわれる。昭和51年調査で薬師堂側で33個、墓地側で25個が確認、西南の墓地附近まで広がっていることが分かった。
・石燈2:明和三、・礎石4:70㎝、・鐘楼、・大円堂、・木鳥居、・自然石4:縦長、・新:十三仏:薬師は本尊で堂内にあるのでここにはない、・三面観音、・堂:金毘羅宮、・西國三十三所観音供養塔、・善光寺供養塔2、・□□□圓供養塔、・善光寺供養塔:文政□未年、・堂:弁財天、・板碑:佛天、・三十三所供養塔:文政元年、・石塔:寛政二年、・手洗石:享保十四年、
・「⓷勝養坊跡」
○八坂神社(潮海寺1959)
・説明:祭神:すさのおのみこと、例祭日:7月23日より25日、由緒:天平の中頃の創立。人皇45代聖武天皇の御代、広厳城山薬師堂山の良の頂上へ勧請し奉る。牛頭天皇と尊称し、薬師如来の御前立と定め、潮海寺の鎮守とし、なお本村氏神と尊び奉る。慶長12年造営、寛永年間造営、天保3年造営、正徳壬辰年造営、宝暦4年造営、遷宮式の棟札あり、明治4年、神仏混淆禁止の際、神仏分離して八坂神社と改称す。昭和6年1月、村社に列格す。
・説明:素戔嗚尊、大祭日:祇園祭は人々の厄を祓い農作物の豊穣を祈願する祭だ。平安時代の古式ゆかしい神輿の渡御を賑やかなお囃子にのって屋台がお供をする。屋台が仁王門の石段を下り上りするさまは実に勇壮だ。昔は毎年、京都八坂神社の祇園祭と同じ期日に行っていたが、昭和初期頃から茶の生産時期と重なるため、7月23~25日となった。27年からは3年に一度となり、更に63年からは7月23日に近い土。日を入れた3日間行われることになった。
由緒:天平の中頃740人皇45代聖武天皇の御代、廣厳山薬師堂の鎮守として、牛頭天王を境内の艮コン(東北)の方位山頂に祀った。これを「お天王さま」といって、村民の氏神とし、江戸時代末期まで栄えた。
明治4年神仏分離令によって、祭神の牛頭天王は素戔嗚尊であるとし、社名を八坂神社と改称した。神殿は仏法の守護神であるが故に薬師堂境内地を分割分離した。現在も神社と寺が同一境内地に共存すうr神仏習合の形態を留める神社は少なく往時の面影が見られる。昭和6年1月、河城村村社に列格、昭和20年敗戦により無格社となり、現在は9等級神社。
神社境内地には、合祀社「金山社、白山社、いざなぎ社、奥津社」、「金毘羅社」
祭神説明:素戔嗚尊はとても気の荒い神である。尊は高天原で天照大御神に乱暴を働き、天岩戸事件を起こして出雲の国へ追放された。そこで尊は出雲の国、簸川ヒノカワの上流に人が住んでいることを知り、鳥髪に天下って「八岐大蛇ヤマタノオロチ」を退治して櫛名田姫を救い妃にした。その子供が大国主命である。その大蛇の体内からは天の叢雲ムラクモの剣が出た。この剣を持って日本武尊は東夷征伐に行き、賊軍に焼き討ち攻めに遭ったとき、この剣で草をなぎ倒したことから、草薙の劔と呼ばれ、熱田神宮に祀られている。
・祠:中に祠5、・石柱2:大正四年、・社名碑:村社八坂神社:昭和十二年、石鳥居:昭和四十二年、・献燈2:平成十六年、・手洗石:明治□□□、・石段、
当地より東北へ200m進む。途中老人ホーム前を通過し、やや南に進む。
・「④行賢坊跡」「ろ:時雨」(潮海寺758)
北方面に150m進む。右(東)へ「は:塩井神社、塩井戸の浮月」の標識があるので、右折する。150m東進する。左(北)へ60m。
○「は:塩井神社、塩井戸の浮月」(潮海寺)
・説明:奈良時代、広く人々に知られ、南西にある潮海寺は聖武天皇の頃、潮井戸に因んで潮海寺と名付けられた。郷土の産んだ国学者:栗田土満:菊川市段平尾八幡神社官は当時の情景を「木の葉もる月の光も卯の花も桜も雪と波とこそ見れ」と歌った。当時の潮(塩)井戸は塩分を含む鉱泉が強く湧き出ていたが、安政の大地震によって地層が変化し46mほど北側から噴出するようになった。この井戸は3年に1度、7月に行う潮海寺八坂神社の祇園祭の時、お水とりの神事に用いられる。八坂神社と薬師堂は南の塩谷坂を上りきった西の森にある。
先ほどの標識まで戻る。ここからまた北を目指す。400m北進。
・「⑤高塚坊跡」「に:富士見」(潮海寺)
すぐ東側の丘頂上周辺のようだ。ちなみにこの時カモシカがいた。
700m北進し、左折(西)し600m西進する。また右折(北)し200m。右(東)に標識がある。
・「⑥小池坊跡」(潮海寺)
西進70m。
○薬師堂:奥ノ院:岩井堂(潮海寺)、水源
・献燈2、
潮海寺の巨大寺院の北端のようだ。120m西進。左折(南)400m南進。
・「⑦法蔵坊跡」「ほ:暮の鐘」()
150m南進。坂を下った所に石仏がある。
○石仏(潮海寺)
・石祠:道祖神、・「道祖神」、・地蔵、
50m南には「奥の池」である。
・「奥の池」(潮海寺)
300m南東進。橋の袂に標識がある。
・「⑧地蔵堂跡」(潮海寺)
90m東進。広い道に合流する手前に石仏がある。
・「馬頭観音」(潮海寺)「柿田」
かなり摩耗しているが馬頭である。
ここから南進すると潮海寺参道方面に近付くし、途中の250m南進し右折すると「通りの尾根:相良往還」や「⑨中の坊」「⑩成就院」「⑪常楽院」への道となる。
これで潮海寺地区の説明を終わる。
~~~
潮海寺仁王像山門参道前から津島神社横を東へ目指す。200m東進で水神橋手前に達する。この左上に神社がある。
○水神社(潮海寺)
・祠:水神社、・石碑:水神:昭和四十九年、
水神橋を渡って和田へ出るルートがある。一方で現在の潮海寺のある所を真東に進み台地を東へ下って、南の潮海寺橋を渡って和田に出るルートもある。
和田集落のJR東海道本線北側に接した所に石仏がある。
・馬頭観音:昭和十一年三月(和田36)
線路の北側を東に進み集落を抜け、大井神社方向を目指す。和田、谷田部集落の東端から東へ300mである。
○大井神社(和田426)
・秋葉山常夜燈:木造瓦葺、中の燈も木造、・祠:五輪塔、・石鳥居:明治四十年、・手洗石、・石柱:横倒し:奉御成婚和田在郷軍人會、
~~~
ここから街道は南の踏切を渡るがその前に周辺を紹介する。
大井神社前を300m東進すると吉和橋を渡る。この右(南)にJR東海道本線のレンガアーチ橋がある。
・レンガアーチ橋;
さらに300m東進する。
○西福寺(吉沢523)
・菊川地蔵巡り第七番、・自然石燈籠、・巨石3、・新:地蔵、・一石3仏:南無阿弥陀佛、・南無観世音菩薩所、・子持石、
・石道標:南無阿弥陀佛 右ハかなや 左もびい乃去涅
~~~
大井神社前に戻り、神社南側の東海道本線の和田踏切を渡り、法明寺横に出る。しかし法明寺は既に廃寺となっている。
○法明寺跡:和田公民館(和田)
・説明:法明寺の歴史と解散整理事業の概要:この地に法明寺と称する曹洞宗の寺があった。創立不詳。1623元和9年没の妙照寺4世、宝岩玄珠大和尚による開山と伝わる。
かつて法明寺は、9月2日~3日の毘沙門天のお祭りに浪曲が演じられ、夜店が出たほど賑わった。400年近く存続した寺だったが、川端玄猛住職の長期入院(平成13年没)により宗教活動ができなくなり、昭和59年に檀家が全て離檀して寺は荒れ果てた。
平成18年5月、玄猛和尚の兄が没して寺が無人になったのを期に、にわかに法明寺問題解決の取り組みについての話が持ち上がった。寺の前を通る県道吉田大東線緊急交通改善事業もその要因の一つであった。当然のことながら、この取り組みは和田区民が負う成り行きとなった。
地元選出の市議会議員、戸塚正晴氏の献身的な協力と菊川市の支援を得て、最初に取り組んだのが寺役員の再構成であった。組織の要となる、兼務住職と代表役員に、妙照寺住職の城達明師の就任承諾を得ることができ、法類に法幢寺住職、青葉茂雄師、法友に西福寺住職、末永無相師の就任受諾を得た。責任役員には信徒の資格で、北原勝、山内静、赤堀博が、干与者には岩堀和雄の就任が決まり、平成19年1月、法明寺の新たな組織が成立した。
以後、法明寺は県道拡幅工事の用地売買交渉、境内にある国有地の買収、荒れ果てた境内地の整理等を行うとともに、最終の目的である宗教法人法明寺の自主解散に向けて宗務庁と折衝を重ねた。
平成21年12月宗教法人法明寺の自主解散が承認され、平成22年5月、清算が結了して法明寺の残余財産の全てが和田地区に帰属した。
玄猛和尚のご母堂、川端明治様の遺産金相続人23名の方々から、和田地区発展のためにとの趣意で多額の寄附を賜った。この事業の推進の大きな支えとなった。平成23年3月和田法明寺解散整理事業実行委員会
・和田毘沙門堂、・法明寺鬼瓦、・旧毘沙門堂鬼瓦、
・石道標:南 沢水加ヲ経テ川崎、相良ニ通ズ 西 作道 北 本所ヲ経テ堀之内ニ通ズ 東 吉沢ヲ経テ金谷ニ通ズ 大正十二年四月 第八部青年團
この石道標は裏面を表にして固定してあり、表面は金網冊に面していて10㎝程の隙間から読むしかなく、とても読みづらい。しかし保存してあるだけでもありがたいことだ。まさにこの石道標が川崎街道があることの証明でもある。
一旦南側を東西に延びる県道菊川吉田線に出て、東へ30m進むと、南東に分岐する県道菊川榛原線(現在の川崎街道)の起点がある。ここから東南東ないしは東に向かって1.8~2.0㎞進む。沢水加公会堂が左(北)にある。その裏山には神社と墓地、堂、祠もある。
○沢水加公会堂、西宮神社、墓地、堂(沢水加725)
・板碑:殉公碑、・時計台:コンクリ製、・石柱4:大正四年、大正十三年、・大谷内竜五郎の墓、・板碑:流芳墓地、・標識:入会地奪還記念誌、
・堂:大日如来、・祠:観音4、如来1、地蔵7、地蔵の首1、
・建設沢水加青年團:大正拾弐年、
・石鳥居、・常夜燈:平成元年、・狛犬:陶製1、・手洗石:平成元年、・祠、
250m東進する。沢水加橋手前、左(北)の御宅前に標識がある。
・標識:移築された中条景昭邸(沢水加788:栗田氏宅)
沢水加橋を渡って左2軒目の加藤氏宅:沢水加902で川崎街道の古道について聞く。向かい(右)の倉庫前の植え込みに石道標があり、その前の道が山斜面に向かい延びていき斜面を上っていく。その道こそが川崎街道の古道残存部分である。地元民は軽自動車で上ってしまうようだが、私の軽自動車はスタックして進まず、加藤氏倉庫周辺に駐車させてもらった。
・石道標:東川崎相良道 北金谷道 西堀之内道
植え込みの中によくまあ保存してあったものだ。
・古道残存部分:沢水加←→仁王辻(沢水加902)
道は始めは少しだけ簡易舗装されているが、すぐに土道になる。その土道もよく観察すると、斜面に対し直に上る道とその横から斜面を斜めに斜めに上ろうとする道に分かれていることが分かる。つまり、直に上る道こそが古道であり、斜面を斜めに上る道が付け替えられた道であることが推定される。道の距離は県道分岐点から上の坂を上りきった所までで1.2㎞、標高差110mである。途中に沢水加調整池のタンクがある。
坂を上りきった所には磨滅した石仏3体がある。
・石仏3(菊川市沢水加904)
・地蔵、・石仏、・馬頭?
坂を上りきって茶畑や家々を抜け国道473号線を横断し、東へ向かうと言いたいところだが、古道や旧道は不明というか区画整理され切って直線道しかないうえ、東名高速道路相良牧之原インターチェンジ開設のため、周辺は再開発され古色がまったくなく、とりあえず東に進むしかない。東名高速道路の北側を東に進んでいく。東名のすぐ北側の側道の左(北側)に祠がある。
○こげんじ稲荷(牧之原市静谷、牧之原南2620⁻6)
・赤鳥居:平成二十三年、・祠
さらに200m東進すると、東名高速下をガードでくぐり南側に出て、県道菊川榛原線を1.1㎞東進する。
右(南)に神社がある。
○秋葉山神社(牧之原市東萩間、水吞764⁻1)
・コンクリ石柱2、・鐘40×20㎝、・石鳥居:大正十三年、・手洗石:平成十四年、・常夜燈2:平成十三年、・古木10~15、
県道へ戻り850m東進する。左(北)100m先の牧之原南一組集会所の隣に祠がある。
・祠:神、手洗石(静谷、牧之原南2519₋2)
県道に戻り550m東進する。右(南)180m先に鳥居もないが神社らしき堂がある。
・神社(白井、大久保1342)
・本殿拝殿、・鬼瓦2、
ちなみのこの辺りの地名は、東進している県道によって分けられている。というより県道がかつての境界線である。県道より北側が旧榛原町、南側が旧相良町である。合併してどちらも牧之原市である。
県道に戻り600m東進を続ける。左(北)100m先に祠がある。
・祠:地蔵3(静谷朝生)
周辺は茶畑で目印はないが、茶畑の中の祠なので多少目立つ。
県道に戻り1.5㎞東南進を続ける。旧榛原町白井、追廻地区で県道は左へ曲がり真東に進む。
・戸塚坂、掛川坂
追廻で曲がって1.5㎞程は平坦だが、そこから先は急な下り坂となる。この坂を戸塚坂とも掛川坂とも呼ぶ。400m下ると左(北)に鳥居がある。
○稲荷神社(勝俣、橋向2467⁻13)
・赤鳥居、・堂:稲荷像多数、
あと150mで下りきって、住宅街に入る。150m進むと交差点があり、右折(南)し180mで戸塚橋がある。渡って70mで静波三丁目の県道の交差点となる。ここが田沼街道との合流点である。右折(西)し田沼街道である県道を50m西進し、また右折(北)すると前方に神社がある。
○稲荷神社(静波三丁目628)
・石鳥居:昭和十一年、・コンクリ石柱2、・手洗石:明治四十年、・献燈2:昭和八年、・秋葉山常夜燈:竿部分が自然石でよい、
・石道標:
・説明:三丁目の道標:天保七丙申年1836の春に建てられ、世話人は□吉、銀蔵、太兵衛の3人で、石工は相良の藤五郎と背面に刻まれている。
この道標の特徴は、
「大井川道」は行書体で、「かけ川道」は行草体で、「さがら道」は草書体で書かれ、三面の「道」という字が異なった書体で書き分けられている。
大きさは縦横28㎝、高さ1.28m
純然たる道標である。
正面の「かけ川道」は戸塚坂を上り、大沢原から仁王辻を経て沢水加を通って堀之内から西出口に出て掛川に達する道である。
この石道標がちょうど成滝や伊達方の石道標と同じく四角柱で呼応するかのようであるが、内容や表示に共通点はそれほどない。しかし、これで川崎街道の起点、終点を指し示し灌漑深いものがある。
~~~周辺~~~
沢水加から仁王辻への古道を紹介したが、現在の県道での上り下りの道は別箇所にある。
古道から上って東の国道473号線に出る。そこで国道を北へ550m進む。そこに左へ下る県道菊川榛原線がある。下って1.1㎞、下りきる300m手前に標識がある。
・大井航空隊洞窟(菊川市沢水加)
県道から沢沿いに30mほど歩くと洞窟がある、どうも防空壕として掘られたようだ。戦争遺跡である。牧之原台地上の布引原には大井航空隊基地があった。
・参考文献
・「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ‘96、
・「ゼンリン住宅地図」
・「2万5千分の1地形図」国土地理院、昭和50~平成10年代
・「2万分の1地形図」陸地測量部、明治20年代
・「静岡県 県別マップル道路地図」昭文社、’00
・「東海道 静岡県歴史の道」静岡県教育委員会、平成6年
・「日本石仏事典 第二版」庚申懇話会編、昭和55年
・「静岡県の中世城館跡」静岡県教育委員会、昭和56年
・「静岡ふしぎ里かくれ里」鈴木茂伸、静岡新聞社、’05
2016年05月22日
朝比奈街道(静岡県焼津市、藤枝市、静岡市)
~朝比奈街道(静岡県焼津市、藤枝市、静岡市)~
現地調査:’16 4/23,24、29,30
・前文
本文を読み進める場合、手元に住宅地図等の地図を確認しつつ読むと分かりやすい。住宅地図がなくともグーグルやヤフーのマップ、昭文社の道路地図等でもよいと思う。
*住所地は分からない時には附近のものを記入している。正確な住所を記入することが目的ではなく、目的の場所を少しでも発見しやすくするための目安である。
個人的には文字間違いが多いかと思う。というのは丸2日がかりで打ち込んだ文章がすべて消失したので、一から打ち直していてウンザリしている。しかもすでに川崎街道は調べたのにほとんど打ち込めずに自分の記憶の方が消失しそうで早く朝比奈街道を打ち終えて、川崎街道も打ち込まねばとあせっている。ますます間違いだらけで、さらにいらいらしてくる。一旦消失した文書でも履歴とやらを探ると復活できるらしいが、パソコン苦手な私にそんな技量はない。パソコンや最新機器は嫌いです。
一応、現地で発見したもの(道、遺物類)を掲載しましたが、発見できないものも多かったと思いますので、御存じの方はぜひコメントを頂きたいです。あるいはその方なりの方法で公表していただけるとありがたいです。朝比奈街道だけではありませんが、古道や古道沿いの遺物類は片っ端から消失の危機にあると言えるでしょうから、公表されることで少しでも保存されることを願っています。
・朝比奈街道概略
朝比奈街道は『定本 静岡県の街道』によれば「焼津北を起点として、瀬戸川を渡って八楠、越後島を経て下当間に至り、広幡橋を渡って東海道と交差し、さらに仮宿村のはずれで朝比奈川の右(?左)岸に渡り、子持坂から桂島を経て宮島に至っていた。」
起点であるが、焼津北でははっきりしないが、おおむね朝比奈川は下流で瀬戸川と合流し瀬戸川として駿河湾に達し、その横に焼津港が開けている。そこで起点は焼津港とした。
~焼津市焼津漁港~
○焼津漁業協同組合焼津漁業資料館(焼津市中港二丁目6⁻13)
○宗像神社(中港五丁目18⁻16)
・コンクリ鳥居、・板碑:社碑:昭和四十七年、・手洗石:自然石かち割、
・説明版:創建不詳。昔人伝うにこの地毎年暴風雨来れ激浪打ち寄せ民家流失人命にも及ぶこと甚大なりしが或る日村民その海辺に流れ着きたる弁財天の御姿を見付けこれこそ安芸の国宗像神社の御授けと尊崇村民と計らい祭神を祀りし社殿を創建し祀りたるに霊験あらたかにして爾来波浪静まり豊漁豊作民心安泰この地今日の繁栄を期す故なり。明治三年神仏分離のため弁財天を宗像神社と改む。昭和39年焼津港築港の砌当地に移転崇敬篤き氏子の敬信により新たに社殿造営今日に至る。昭和47年
○船玉浦神社(本町一丁目16⁻1)ふなだまさん
・説明版:祭神:大錦津見命、祭礼日:7月26日、由緒:江戸時代、和歌山県、音無川上流にある船霊神社から分祀されたという。創立年月日不詳。旧焼津港の南端、明神鼻の一角にあるところから焼津港の鎮守神として「ふなだまさん」の愛称で漁民の信仰を集めてきた。例祭日には宮司が御幣を立てた小舟に乗り赤飯を盛った神餞を港外で海中に納め、海上安全、大漁を祈る古例がある。(静岡県神社庁志太支部編「志太地区神社誌」)
・社碑:昭和六十一年、・石鳥居:大正十五年、・手洗石2:大正十五年、明治廿六年、・新:猿田彦、
・石碑:焼津市古い地名:新屋:あらや旧町名 樋越 上町 中町 北町 南町 下町 新町 浜町
○青木神社(本町一丁目3⁻28)
・社碑:昭和十二年、・石鳥居:平成二年、・献燈、・新:手洗石、・自然石5、・コンクリ鹿像:昭和四年、・大木6~7本、
隣の幼稚園に・新:地蔵、
○紫雲山阿弥陀寺(本町二丁目4⁻5)
・寺名碑:平成二十四年、・六地蔵、・供養塔、・手洗石、
~その他、焼津港周辺~
・焼津神社(焼津二丁目7⁻3)
焼津の中心的神社
・普門寺(焼津六丁目9⁻16)
・貞善院(焼津六丁目11⁻⒕)
・良栄寺(焼津六丁目2⁻16)
・小泉八雲の碑(新屋425)
・護信寺弁天宮(北浜通95₋2)
・浪除八雲地蔵尊(城之腰188)
・神社:祠(城之腰176)
・常照寺(城之腰138)
・安泰寺(鰯ヶ島143)
・青峰観音(鰯ヶ島253)
近くに・記念碑
・須賀神社(焼津五丁目2⁻2)
~焼津駅北口周辺~
○昌泉院(駅北五丁目10⁻9)
・六地蔵:昭和四十七年、・無縁仏:コンクリ固め:昭和三十五年、・?供養塔、・観音、・慰霊碑、・燈籠、・狛犬、・水子地蔵、・観音、・奉納鳥大乗妙典経全部:元文五年、
・御所松(駅北五丁目10⁻9)
昌泉院横、瀬戸川河口付近の土手に赤松と黒松
○天皇神社(駅北五丁目1⁻25)
・新:社碑:、・新:玉垣、・石鳥居:昭和四十四年、・新:狛犬2、・手洗石:自然石、・自然石、・献燈2:昭和四十四年、・石碑:奉納浄水石中老会、
○大井神社(駅北二丁目5⁻13)
・社碑:昭和四十八年、・石鳥居:昭和八年、・献燈2、・狛犬2:昭和三十三年、・慰霊碑、・新:玉垣:昭和五十三年、・コンクリ石柱2、・クス、シラカシ:焼津市指定保存樹木、
・石碑:焼津市:旧地名碑:焼津北:川東 駅前小石川東 川南 駅前小石川南 舞台 西町附近 昭和55年
・説明:祭神:彌都波売命:水を司る神、猿田彦命:道の守り神、創立永禄三年、明治八年村社、明治四十年神饌幣帛供進指定社となり今日に至る。佐口社:通称:おしゃもんさん白髭神社稲荷神社を併合奉斎。永禄三年は領主今川義元が桶狭間で織田信長と戦った年で戦国末期であり、当時の虐げられた貧困の祖先たちが五穀豊穣や平和を祈ったのだろう。現在の社殿は明治41年、本殿が改築拝殿が新築された。それまでは小祠堂であっただろう。本殿拝殿は焼津市区画整理事業駅南北工区工事の際、昭和48年位置が若干移動するに当たり、更に改築が施され49年には社務所兼公会堂が落成し玉垣は53年新設された。区民有志により竣工。昭和53年。
・若宮神社(大89)
・七社神社(大村一丁目7⁻1)
・善通寺(大村一丁目19⁻4)
・用心院(大村新田317)
焼津港から瀬戸川と焼津駅の間を遡上し焼津駅北口付近に出る。駅北の大井神社付近から北西に進み県道焼津停車場仮宿線に出て、瀬戸川に架かる牛田橋を渡る。その手前に神社がある。
・神社:祠(大栄町三丁目3)
牛田橋を渡ってすぐ右折し細い道に入り、梅田川に架かる天白橋を渡り、朝比奈川土手手前で土手沿いに遡上する。すぐに国道150号線バイパスの高架下ガードをくぐり八楠の新興住宅街を遡上する。この周辺は都市計画で区画整理され、昔日の面影は消失しているが、とにもかくにも土手の1~2本手前の道を土手に沿い進むのが古道ルートに近いようだ。バイパス高架下ガードから650mで右側100m先の土手手前に寺院がある。
○正傳院(八楠460)
・六地蔵、・(梵字)庚申塚青面金剛像:平成五年:見聞言ザルレリーフ、・如来、・地蔵、・新:地蔵、・新:日切地蔵、・五輪塔、
元の道に戻り北西進するが、一旦もう一本左の道に移り北西進する。距離300mで神社である。
○加茂神社()
説明:祭神:賀茂別雷命カモワケイカヅチノミコト、例祭:10月17日ただし昭和53年以降第3日曜、創建:大化二丙午年二月646、由緒:646年2月山城国上賀茂神社より勧請したと記せる棟札あり。「総国風土記」に「箭葛柳田神社所祭祭神雙栗神也」とあり。また「諸郡神階帳」に「益津郡従五位上八楠地祇」とある。往古は賀茂神社の祭礼には神輿数台を字天白という所に行幸し神楽を奏し、字馬場田という所にて流鏑馬を行った。「賀茂神社」は山城国上賀茂神社:京都市から神の霊別雷命を祀る。上賀茂神社の例祭は賀茂祭:葵祭が有名。旧除地高:2石。明治8年1875,2月村社に列し、明治40年1907,9月神饌幣帛料供養社に列した。境内神社:末社:八坂神社:すさのおのみこと、白髭神社:さるだひこのみこと、天満社:すがわらみちざねこう、天白社:不詳、八幡神社:ほんだわけのみこと、蔵王社:不詳、佐口社:不詳、祭事:2月祈年祭、10月例大祭、11月新穀感謝祭:七五三お祝い、
・社碑:平成五年、・石鳥居:昭和十年、・献燈2:昭和五十六年、・手洗石:自然石加工、・狛犬2:昭和56年、・手洗石:草書体?江戸期、手洗石:20×40㎝:天保十、・献燈+燈の竿:文化□、奉献燈加茂大明神□□、・石塔2:明治廿八年、・大木7~10、
北西進ですぐ東名高速高架下ガードをくぐる。ガードから300mで右50mに寺院がある。
○瑞應寺(越後島114)
・寺名碑:平成四年、・手洗石:、・地蔵、・祠:青面金剛、・新:地蔵、・祠:神、・祠:地蔵、・ソテツ、・秋葉山常夜燈:文化二年、
元の道に戻り50m進む。左に越後島公会堂があり、赤鳥居が見える。
○神社(越後島183)
・木赤鳥居2、・赤祠2、・献燈:平成十二年、
この周辺は水田や畑が残り、道もやや狭く、直線ではなく昔風の曲がった道であり、古道とまではいかなくとも田舎びた旧道の雰囲気が残っている。しかし手前の八楠までは開発されていて、越後島の開発も時間の問題であろう。訪ねるなら今がラストチャンスでしょう。
200m北西進する。左折:南西進し200mで鳥居がある。途中宮前橋を渡る。
○八坂神社(焼津市越後島289)
・説明:旧駿河国益頭庄越後島村、祭神:建速須佐之男大神、由緒:往古この地の守護神、産土大神として嘉吉元年1441、御花園天皇の御代、室町中期足利義勝の頃、愛知県津島市に鎮座の旧国幣小社津島神社より分霊を勧請して創立された。本宮社と同じく元牛頭天王社ともいわれた。明治以前徳川時代までは除地高2石を有し明治8年2月には村社に列せられた。祭神は天照大御神の弟で国土経営産業開発の大神としてまた神徳は災難疫病除けの守り神招福大神と古来より篤く信仰された。境内には末社として山梨神社、八王子社、西宮社、御嶽権現社、天白神社の5社を祀る。本殿拝殿前後には樹齢500年余りの5本の大老松がそびえていたが、昭和41年大暴風雨で倒木し他も危険となり伐採した。目通り8尺。現在は2代目植樹。本殿は天和3年1683再建、外本殿は昭和47年10月再建。拝殿は昭和8年石玉垣は昭和33年、造営。境内地1035㎡。明治維新に上地され国有地化されたが昭和31年神社に譲渡。例祭は本宮津島神社では6月25日を津島祭天王祭としてあまねく世に知られているが当神社では戦前より秋農耕の収穫前近隣神社の祭礼と同じく10月16日。昭和49年。
・石鳥居:昭和四十六年、・玉垣:昭和33年、・手洗石:自然石加工、・手洗石:横倒し、石柱5:横倒し、・献燈2:平成二十二年、・大木2、・御神燈2:文化七、・狛犬2:昭和八年、
元来た道に戻り、250m北西進する。標識もないので分からないが、ここで藤枝市下当間に入る。市境から450m進むと右に下当間公園さらに奥に寺院と神社が見える。
○孝養院(藤枝市下当間542)
・寺名碑:昭和四十八年、・祠:地蔵、如来、石祠(石家道祖神)、小地蔵6、・庚申供養塔、・庚申供養塔、・自然石3~6、
○橘神社(藤枝市下当間537)
・説明:由来:天正年中1573~1592、当地の仕人五左衛門という人が奉斎したという。以来当地の守り神として現在に至っている。祭神:弟橘姫命、焼津神社(祭神:日本武尊)と由縁がある。神領除地高1石8斗9升8合を有し、明治8年2月村社列せられた。昭和28年7月8日国有境内地は無償譲渡され宗教法人として承認登記された。
祭神:弟橘姫命:美濃の穂積氏忍山宿禰の娘、日本武尊の妃となり東国平定に従ったが、走水より上総に向かう海上で暴風雨に遇い、妃の弟橘姫命は犠牲となって海神に身を捧げて尊の難を救った。尊は深く悲しみ、現在の千葉県茂原市木納町舟形山に御陵を造り弟橘姫命の櫛を納めて橘の樹2本を植えて祀ったという。
境内社:稲荷神社 倉稲魂命 稲作の守護神、御嶽神社 御鍬 農家の守護神、津島神社 素戔嗚尊 魔除け守護神、
・石鳥居:平成二十一年、・狛犬2:2012年、献燈2、・板碑、・手洗石、2:古、新:昭和五十年、・大木6~10、・神木1、
橘神社前から450m西進する。新しい石道標が電柱に立てかけられている。
・新:石道標:「しあわせ小路→」(下当間438)
50m西進すると高架下ガードをくぐり、さらに200m進むと県道焼津停車場仮宿線に出る。古道ルートは県道を横断し、県道の広幡橋の先にある狭い歩道橋で葉梨川を渡ることになる。
ただ渡る前に下当間付近の石造物を紹介する。歩道橋より先の土手沿いに寺院がある。
○観音寺(下当間1099)
・寺名碑:駿河観音霊場九番札所:昭和六十年、・六地蔵、・ソテツ、・手洗石、・地蔵:座、・地蔵:立、・奉納西國坂東秩父供養塔、・奉納大乗妙典経廻國六十六部供養天下太平國土安清:元文元、・祠:新:水子地蔵、・供養塔、・五輪塔の頭部、・三界萬霊塔:昭和四十三年、
寺の先が広幡小学校と広幡幼稚園であり、その先に石造物がある。
○忠霊塔:昭和二十八年(下当間392)
・献燈4、・狛犬2、・板碑:戦後記念碑、
忠霊塔より北東150mに小さな神社がある。
○金山神社(下当間175)
・金属鳥居、・庚申供養塔、・祠:神、・手洗石:昭和三年、
広幡橋隣の歩道橋で葉梨川を渡る。50m直進するとT字路に当る。この左右の道が江戸期東海道である。右折(北)するとすぐに法ノ橋を渡る。100m進むと現在の国道1号線との仮宿交差点に出る。東海道は交差点を斜めに横切っている。松があり、他より狭い道なので分かりやすい。
・標識:岩村藩領標示杭「是従東巖村領横内」(横内1651)
・説明:この杭は江戸時代、享保20年1735より明治維新までの135年閒岩村藩領であったことを標示した杭を再現した。岩村藩は美濃国岩村城(岐阜県恵那郡岩村町、現在岩村市)を居城とし、松平能登守が3万石の領地を持っていた。駿河国に15ヶ村、5千石分の所領地があり、横内村に陣屋(地方役所)を置いて治政を行った。
200m進むと左折(北西)である。ここに石道標がある。朝比奈街道は東海道を離れる。
・石道標:仮宿區入口 岡部町 朝比奈村 葉梨村ヘ通ズ 大正六年(横内996)
裏面は壁際固定されていて読めない。多分発起人名かと思う。
300m進むと標識がある。
・標識:小字名「評定ひょうじょう」(横内1075)
200m進む。標識がある。途中バイパス高架下ガードをくぐる。
・標識:明治の学校跡地→(横内1091)
250m進むと標識がある。
・標識:朝日山城跡→(仮宿1228⁻1)
標識から西1.2㎞先の朝日山山頂112mに稲荷神社があり、そこが中心である。
~~~~~~
一旦、朝日山城を目指し朝比奈街道ルートを外れる。
○朝日山城跡(仮宿)市指定史跡、朝日稲荷神社
西1.2㎞先の潮山200m前衛峰の山頂112m:稲荷神社を中心として築かれた岡部氏の山城。居館は神社手前の静岡大学農場のさらに手前辺りと推定されている。附近に祠や五輪塔があるようだ。城は山頂を本城に上下二段の曲輪があり、稲荷神社は下段である。たて堀、堤坪曲輪、西曲輪等がみられる。潮山とは空堀で分断されている。麓に居館があり背後に山城があるという室町初期の根古屋式の山城といわれる。室町初期に築かれ天正16年1588所領替えで廃城となった。城の弱点は西南に城より高い潮山がそびえていることだが、より高い山に城を築くことは技術力、財力、政治的情勢、必要性から考えた方がよく、廃城になったのも所領替えで、必要性が低かったのだろう。
・朝日山城:説明版:(構造及び形式等の特徴)曲輪・空堀等の遺構をよく残した山城で、その規模はおよそ東西600m、南北200mに及ぶものである。(説明事項)朝日山城は潮山(標高202m)の支峰、朝日山(別称・牛伏山、標高110m、比高約90m)頂上部を中心に造築された山城である。この山裾は、土豪として活躍したとされる、岡部氏の本拠地と伝えられることから、本城は室町時代の初め頃、この岡部氏が築いたものといわれている。このように山頂に築城し、その山麓に城主の居館地を伴う場合の城を根古屋式(詰城)と称し中世城郭の典型となっている。城は山頂の神社境内に船形で土塁によって囲まれた一ノ曲輪を中心として、ここから東に向けて階段状に曲輪を配置する。その他空堀、堀切や南曲輪・西曲輪・山下曲輪・水の手等によって構成されている。
・説明版:藤枝市仮宿1番地に所在する、岡部氏により造られた城である。この頃の岡部氏は今川氏の庇護の下、自領地を護るためのものであった。朝日山城は朝比奈川を望む海抜110mの朝日山(牛伏山)にある、山頂には室町時代初期の頃の様式の城郭遺構が残る、この城は東方山麓に居館を構えた根古屋式の城である。根古屋とは、丘陵上等に設けられた城と、その裾に屋敷が付随する城に対して付けられた名称である。朝日山城跡は一の曲輪、二の曲輪と構成されているようですが、現在この城跡は発掘調査などされていません。城跡に残る形跡は室町時代初期のものばかりではなく、一部は同時代末期の天文~永禄年間(1532~69)の頃、城郭拡張の必要(戦争)が生じたために、工事を起こしたが、完成まで至らず必要性がなくなり、途中で放棄されている。今川氏に関係する城の多くは未完成のまま残され、このうち重要な位置(海岸、街道、峠、国境)を占めるものは後に武田、徳川両氏の手により修復されている。
・絵図「朝日山城とその周辺(推定)」:(絵図に記入された文字を書き写す):潮山、村良、入野、観音前、牛伏山、朝日山城、(本丸)一ノ曲輪、二ノ曲輪、三ノ曲輪、南曲輪、竪堀、大手口、子持坂、山崎、砦居館推定地、一丁田、押場、仮宿、朝比奈川、八幡山、谷田遺跡、谷田、潮城、城山、一里山、一里塚、
「朝日山城跡の曲輪(推定)」:朝日山城は一ノ曲輪~三ノ曲輪を中心部分とします。「一ノ曲輪」;神社の裏側部分、東西57m、南北31mほどの舟形で土塁が廻る。「二ノ曲輪」;神社のある平坦地(方形)東西25m、南北31mほど。「三ノ曲輪」;二ノ曲輪の東側に階段状に下る細長い平坦部分。
「仮宿朝日山眺望」:この絵は江戸時代の終わりごろ、この朝日山からの眺望を描いたものです。文化11年(1814)紀行「山西勝地真景」より桑原藤泰。
朝日山城跡(推定)一ノ曲輪、二ノ曲輪、三の曲輪、西曲輪、空堀、通路、南曲輪、竪堀、大手口、木戸口、現在地、花倉、潮山、
・空堀跡(竪堀):説明版:この堀は、朝日山城の中で最も規模が大きく長いもの(全長110m)です。山の斜面を通って敵が侵入するのを妨げるためのものですが、このように山の斜面に沿って竪に掘った堀を竪堀といいます。
堀の種類、
堀-水堀―例・田中城(二の堀等)、駿府城等
-空堀―(空堀、竪堀、堀切) 例・朝日山城、花倉城、諏訪原城等
・空堀跡(竪堀):説明版:この附近が、堀のほぼ中央部分になります。この部分の堀幅は約20m、深さ約5mもあり非常に規模の大きな空堀といえます。
・空堀跡(竪堀):説明版:この谷の部分が人工的に掘られた空堀跡です。堀の幅はこの附近で上端が約18m(下端が約13m)深さも4mほどになります。
・一ノ曲輪:説明版:規模・東西長軸方向57m、南北短軸方向31m、形態・平面形は舟形で南側から西側の縁に沿って土塁をめぐらしています。
・板石碑:説明:朝日稲荷神社社誌、鎮座地;藤枝市仮宿字堤の坪一番地、御祭神;倉稲魂命、開創;宝永五年(1677)岡山県津山より御分霊wp勧請の伝言ありまた天野景理助右衛門名主の時、芝田金三郎催主となり創建の説あり、境内社;天満天神神社、松尾神社、権現神社、津島神社、軍人社、例祭;三月初午祭、十月五社神祭、五年毎御輿下山渡御祭、新改築関連事項;延享四年1747本社再建、寛政六年1794御輿建造、天保九年1838拝殿再建、明治八年1875村社に列する、明治十年1877本社再建、明治十九年1886御輿更新、明治四十年1908五社合祀、昭和十一年1936拝殿再建、昭和五十五年1980市史跡指定、平成三年1991本社再建、平成二十二年2010拝殿修復、平成二十九年2017五社鞘殿再建、平成三年建立、
・説明版:朝日稲荷神社:鎮座地;藤枝市仮宿一番地、朝日山城跡に鎮座 稲荷山という、本宮;伏見稲荷大社 京都市伏見、主祭神;宇迦之御魂神、宇迦とは食べ物を意味し日本人の主食である米の生育を守る神である、イナリとは稲成、稲生がなまったもので、やはり稲が立派に実るさまをいい、これが即ち稲荷という字があてられたという。赤鳥居と狐はお稲荷様の独特の風景である。赤い色は豊かさを象徴する色とされ鳥居は通るという言葉に似ているところから願い事が通るという意味があるようだ。また狐はお稲荷の使いといわれる。御祭典;毎年三月初めの土曜又は日曜、大祭典;五年目毎、大祭として神輿の下山出御神幸波御祭り、平成二十三年
・板碑、・神燈2:大正十三年、・石祠、・納札所、・石祠、・神木、・小鳥居と石祠、
・丁石:四丁目、・朝日山ビオトープ ホタルの郷、・名号碑:平成三年、・木赤鳥居2、
・献燈2:昭和四十年、・手洗石、・手洗石:大正三年、・石柱2、・稲荷2:昭和十一年、
・石柱2:昭和六十三年、平成三年、・手洗石:安政五年、・神燈2:享保十四年、
・木祠5、・宝篋印塔の頭部、・手洗石:寛政元酉年、・祠、
○南叟寺(潮995)
・寺名碑:昭和六十年、・石塔:寛…堂、・南叟延命地蔵尊、・六地蔵+1:昭和三戌、
・西国三十三所供養塔:□政□、・地蔵、・手洗石、・善光寺如来供養塔:明治十六年、
・三界萬靈塔:平成五年、・馬頭観音、
・奉納 當国三十三所善光寺如来西国三十三所 各供養塔:明治四十五年、
・□善光寺如来供養塔:大正六年、
・地蔵:祠(潮462-1)
南叟寺のある潮集落から新東名取り付け道路に出る辺りの法の川手前の微高地の丘上畑に祠と地蔵が見える。
○潮神明宮(潮407-7)
・社名碑:昭和五十五年、・金属鳥居、・御神燈2、御神燈2:明治十三年、・石段
・忠魂碑、・石祠、・木祠、・石垣、
○薬師堂(潮304-3)
・西国三十三所巡禮供養塔:寛政九年、・宝篋印塔の頭部、
隣家の潮240-1山田氏の話では、堂の名前は薬師堂、施主は現在9代目で、其の数代前の6代目辺りの与作が祀った。潮集落は昔15~6軒で潮井戸が4つあったそうだ。
’17 10/9
~~~~~~
標識:朝日山城跡→(仮宿1228⁻1)へ戻り、北へ70m進む。道が左に曲がる所に祠がある。
・祠:中組秋葉山(仮宿1189)
北西へ70mで右に寺院がある。
○用福寺(仮宿1172)
・説明:室町期引治3年1557、当時の和尚に依り開創。開山和尚は学識力量共に卓越セル禅僧で仮宿に当寺を開創後、永禄10年1567懇請され、焼津市一色の成道寺開山、永禄12年1569榛原坂部、石雲院の輪番住職を受け輪住される。永禄12年11月示寂。開山当時は駿河国今川氏勢力下にあり、1564年今川義元、桶狭間で戦死。その子氏真が家督を継ぎ、永禄8年1565常楽院を今川氏の祈願者として帰崇される。1569松平家康は今川氏の領地遠州を攻略、掛川城を明け渡される。本尊:地蔵菩薩は日限地蔵として地域の信仰を集めている。昭和59年本堂屋根を修理、昭和62年庫裏新築、平成2年位牌堂新築、平成6年境内地整備、東司建築、文殊菩薩台座新調安置。平成6年。
・寺名碑:昭和六十二年、・祠:文殊菩薩の厨子:寛政4年木製彫刻された像で明治13年再度彩色された、平成に修理された、平成6年、・手洗石:平成七年、・三界萬霊等、・新:地蔵、・自然石、・六地蔵+観音、・石碑:無心:五輪塔の頭部、・○奉供養庚申塔:人差し指を伸ばした手の甲のようで斬新な石、・奉供養西國三十三所、
550m進むと旧岡部町との境だった朝比奈川に架かる仮宿橋に至る。橋手前左30mに祠がある。
・祠:秋葉山、・秋葉山常夜燈2:平成14年(仮宿1084)
さらにこの土手沿いに西300m進むと寺院がある。
~~~~~~
・中正寺(仮宿938)
・大師堂:祠:石像、新四国第三十番慈眼山中正寺
・名号碑2:昭和六十年、 ・手洗石:新、 ・常夜燈2:新、・六地蔵:平成十三年、
・おかげさま石柱地蔵:平成八年、・祠、・常夜燈、・石塔:南無…(不明)、
この寺の南西に岡部氏関係の祠や墓石がある。
・岡部氏一族の墓:説明版:岡部氏の祖から何代かここに眠る、岡部氏の祖、藤原清綱は京より駿河の国に権守(ごんのかみ)として赴任してきた。任期が過ぎても京に帰らず、この地で帯刀してとどまる。清綱は南家出身なのでよい職に就く当てもないことが分かっていて、この地に住むことを決める。そこで権守の時、得たかもしれない伊勢内宮の御厨の職を、この地でやることになった。(岡部御厨) 平家が栄華を極めたとき、伊豆において源頼朝が挙兵したのが岡部氏がこの地にきたときであろう。清綱は頼朝の配下になり、清綱の子泰綱の時、藤原を改め岡部とし、鎌倉幕府において御家人となる。その後代々この地に住み、地域の人たちを巻き込み鎌倉幕府、今川氏と緊密な関係になった。此処の墓は鎌倉時代から、今川氏に加担した頃までのものと推察されます。したがって(1150~1530)の岡部氏の墓の檀下には万福寺の僧侶の墓もいくつか見られる。
・宝篋印塔:新:コンクリ製
・宝篋印塔:古:3、破片は多くもっと多数のものがかつてはあったのだろうが、体を成すものは3つである。
・手洗石 ’17 10/9
・仮宿白岩頭首工 ため池等整備事業 農林水産省補助(仮宿965)
説明版:ゴム引布製堰で貯水時はゴム内に空気を入れ、洪水時は空気を抜き水を流す仕組みである。
・地蔵:祠(高田993-1)
朝比奈川の土手沿いの上でちょうど土手道と高田集落への道へと分岐する辺りである。
○常楽院(高田424)
・寺名碑2:昭和四十二年、・祠、・六地蔵+観音、・新:地蔵、・永代供養塔、・新:常夜燈2、
・新:常夜燈、・新:石碑、・不許葷酒入山門:當山十一代、
・説明版:木喰上人作毘沙門天:クスノキ一木造り、一体、江戸時代、毘沙門天立像、高さ1.23m、市指定有形文化財・彫刻、「微笑仏」で知られる木喰仏のひとつで、甲冑を身に付け憤怒の相を表して邪鬼を踏みつけて立った姿の毘沙門天像である。もとは常楽院境内外の観音堂にあったが、現在は本堂に安置されている。像の背面には墨書があり、木喰が83歳で千体仏を発願した時の作で、寛政12年(1800)7月20日に完成したことが記されている。木喰仏特有の穏やかな微笑仏とはやや趣が異なり、像は厳しい表情を見せる毘沙門天であるが、木喰が最も仏像を多く作った円熟期の作品である。
木喰行道(1718~1810):享保3(1718)年に甲斐の国(山梨県)西八代郡丸畑に生まれ、宝暦12(1762)年、45歳の時常陸の国(茨城県)羅漢寺の木喰観海上人から「木喰戒」を受けた。その後日本全国を廻り千体の仏像を造ることを発願し90歳でこれを達成し、文化7(1810)年、93歳で没するまで全国各地で仏像を奉納した。寛政12(1800)年、西国を廻った帰りに藤枝・岡部・焼津の寺院に2か月間滞在し、13体の木喰仏を残した。
○高田神社(高田325-1)
・石鳥居:平成二十四年、・石段、・手洗石:昭和四十六年、・神燈の脚部と笠:明治十一年、
・神燈1、笠のみ1、・石祠、・祠、・自然石、
○観音堂、薬師堂(高田263)
・石塔:十七面観世音、・石段、・手洗石:大正十三年、・地蔵:古10、・金剛1、・獅子2、
・常夜燈3:萬延元年、・手洗石、
○日吉神社(藤枝市旧岡部町入野65-1)
・石鳥居:昭和四十一年、・石段、・杉大木、・石祠2、
・地蔵;祠(旧岡部町入野831-4)
朝比奈川に入野川が合流する手前の土手にある。
○西方寺(旧岡部町入野98)
~~~~~~
仮宿橋を渡ると前方に岡部宿の中心的神社がある。
○若宮八幡宮(岡部84⁻1)
・説明:祭神:仁徳天皇おおさざきのみこと、応神天皇ほんだわけのみこと、神功皇后おきながたらしひめのみこと、由緒:醍醐天皇、延喜8年908、8月13日駿河に下向せられて仮宿に居館を構えておられた堤中納言兼輔卿が勅に依り山城国石清水八幡宮より分霊をいただきここに祀るという、以来7郷(岡部、仮宿、内谷、横内、高田、村良、鬼島)の鎮護として里人の崇敬をえる。貞享3年1686堤中納言の子孫:岸和田城主岡部長敬によって本殿を造営された棟札があり現在に至る、明治8年郷社に列せられる、例祭:毎年9月第二土曜、日曜、
・説明:行事:神ころばし、七十五膳:3年の一度例祭の日曜に行う、市指定無形文化財:3年に一度の9月15日氏子若者(泰平衆)が白鉢巻き白下帯姿で、本殿脇の泰平所から朝比奈川を七度往復し水垢離を行い、七度半目に神輿を迎えて神事が始まる。神ころばしは泰平頭の指示で泰平衆が「お獅子の御膳」「御内膳」「お丁屋の御膳」を捧げ持ち、広場を練り歩き転びながら奉納する、次に直会用の「下敷したしき」「上敷うわしき」を同様にして納め、最後に青竹に吊るした「かめ(酒)」を奉納する。これと同時に供える「七十五膳」が伝供され、その後、神職と総代は拝殿に敷かれた下敷・上敷の上で直会を行い、この神事は終わる。
・説明:この駿河国、岡部の神社:若宮八幡宮は、山並みにも情緒があり古木もうっそうとして苔の緑もこまやかで岩の様子もたいそう神々しい。だから霞にたなびく春の一日、紅葉の美しい秋の一日は申すまでもなく、月の美しい夜、雪の降った朝など装束姿の神主さんたちがゆったりと風情を楽しむ所であったろう。このような素晴らしい所を前々から占ってお知りになっていたのであろう。我が遠い祖先、堤中納言兼輔卿は千木の形も素晴らしい立派な社殿を建てて、八幡大神を石清水より迎えて鎮めた。そもそも八幡大神とは中津彦の天皇(仲哀天皇)の皇子である品陀和気命(応神天皇)である。この方はすべてのことに賢明で慈しみの心も深いので、日本国は申すまでもなく遠く言葉の通わない韓国(新羅)までも、その威光に従ったという。八幡大神の威光は、なんとありがたい尊いことであろう。御神威は。天保15年文月(七月)正三位 維長つななが:堤中納言の子孫。
・石鳥居:明和六(昭和五十八)、雨乞い石、・玉垣、・石段、・献燈2:元文四、・手洗石、・献燈2、・献燈:寛文三、・献燈:破片いくつか、・板碑:正三位維長、大木巨木:いくつか、
橋を渡った道を左折し県道焼津森線を西に400m進む。右山斜面手前に寺院の入口があり、山道歩道が上っていく。
○萬松院(子持坂501)
・寺名碑:昭和四十六年、・自然石2、・石塔2:刻字不明、・石段、・地蔵:立、・地蔵:立:天保二子、・観音:駿河(刀3つ)志太郡山□□□村、・大日堂、・豊川茶枳尼真天覚、手洗石、・山門禁葷酒、・法界萬霊、・六地蔵+観音、・古:五輪塔:多数、・新:永代供養塔、・水子地蔵:小地蔵多数、献燈2、・新:地蔵:梅花観音80番駿河七薬師札所、
・岡部氏墓:宝篋印塔2、五輪塔1、土塀屋根瓦囲み、説明版:市指定文化財、土塀をめぐらした墓域の中に、宝篋印塔2基、五輪塔1基があり、宝篋印塔は岡部美濃守常慶ツネノリ(信綱)と出羽守(名不詳)の墓、五輪塔は常慶の子次郎右衛門正綱の墓と伝えられる。また門の扉は岡部氏の定紋である三つ巴の浮彫りが施される。岡部氏は代々今川氏に仕える有力な家臣であった。今川氏真の代に武田信玄が駿河に侵攻してきた。このとき岡部正綱は無勢ながらよく抗戦した。ついには多勢の信玄軍に敗れたが信玄はその勇猛ぶりをたたえて家臣に加えた。そして清水城(清水区本町)の守将に任じ賞金二千貫を与えたという。こののち正綱は武田軍に加わり、三方原に高天神城の攻防に徳川家康と戦闘を幾度か繰り返した。その武勇は家康の知る所となり、落城後、家康の計らいで死を免れ、家臣として招かれた。この恩情に感激した正綱、長盛父子は家康の手足となって働いた。
・富士見井戸2:説明:当寺の5代目和尚は慶長19年1614は大日如来を鋳造し、富士山頂に安置するため旅立った。寺に残った小僧は無事を案じながら井戸の水を汲もうとしたところ、仏像を背負って富士山を登っている和尚の姿が映ったため、思わず井戸に向かって手を合わせ、和尚の安全を祈った。以後この井戸を富士見の井戸という。平成17年。
寺西口は農道で車で出入りできる。その農道の石碑がある。
・石碑:松山農道:昭和五十四年(子持坂501)
西口農道から西に向かい下りていく。50mで右に馬頭がある。
・馬頭観音(子持坂501)
100m下ると板碑がある。
・板碑:開演建碑之趣旨(子持坂35)
50m下ると右に寺院と左に観光案内看板、公衆トイレがある。
○常願寺(子持坂35)
・石段・自然石、・カヤの木:天然記念物、・手洗石、・燈籠、・庚申、・燈籠、・板碑:慰霊碑、・墓石:江戸中後期の物多し、・三界萬霊塔、・六地蔵、
150m下っていく。右に長屋門が見える。
○長屋門(子持坂244):鴫谷氏宅:シギヤかシギタニか?
・説明:130年の歴史、市指定文化財、修復。
100m下ると子持坂集落内の現在の県道より古い旧道に出る。進行するには右折(西)だが、左折すると30m先に祠がある。
○大松の地蔵尊:いぼ地蔵(子持坂312)
・説明:建立安置不詳、昭和中頃まで身体にイボのできた子供は親と一緒に地蔵にイボがなくなるように祈った。祠内の小石でイボをさするとイボがなくなると云われた。治ると子供は親と一緒にお礼参りした。大松というのは祠裏に松があったからだ。
・祠:地蔵、・献燈、・新:手洗石、
子持坂には、まだ他にも紹介先があるので、大松地蔵から南西150mの神社に行く。
○熊野神社(子持坂336)
・献燈2、・コンクリ鳥居、・手洗石:安政五戊午九月、・石祠(石家道祖神)2、・献燈2:昭和五十一年、
神社から北西に300mで岡部中学である。その左手前に公園がある。
○巨石の森公園(子持坂102)
・巨石:いくつか、・裸足の散歩道、
公園から東に300mで県道焼津森線(現在の朝比奈街道)に戻れるが、その手前に地蔵堂跡地がある。
○地蔵尊(子持坂52)
・石段、・奉納西國三拾三所順禮供養塔:享(保・和)三年、西國三十三所供養塔:天保□□、・漢音、・馬頭(四角台座20㎝円形台座15㎝本体80㎝)、・地蔵、・石塔:四角柱、・破片いくつか、
県道に出て北上200mで神社である。
○浅間神社(子持坂22)
・社名碑:昭和五十一年、・石鳥居:昭和廿四年、・石段、・自然石、・イチイカシ:天然記念物、・コンクリ石柱2、・御神燈:安政四巳年、・手洗石:天保十三、・献燈:浅間宮、・秋葉山献燈2:寛政八年(平成二十二年再建)、
村良下橋を渡って村良に出る。県道の西側の山すそに神社がある。
○天満宮(村良978)
・説明:祭神:菅原道真、例祭日:10月25日、境内地220坪、境内社:津島神社、秋葉神社、弁天社、由緒:創立不詳、天明8年1788再建、明治8年村社指定、大正5年9月神饌幣帛料共進社指定、天満宮は天神さんとして全国に祀られている。京都の北野天満宮を総本社とし、その数1万社を数える。菅原道真は承知13年845生まれで、その生涯を至誠の道を垂範され、よく勉学に励まれて右大臣の高位に任ぜられた。俊才のあまり藤原時平の中傷により大宰府(九州福岡)に流された。牛車で送られる道中、牛により待ち伏せの賊の難を免れたと伝えられ、以来、牛は天神様の使いと云われ、教育の基本の象徴とされた。牛は食物を反芻して消化する。その様に繰り返して勉学せよと、教えている。天神信仰は元来農耕民族にはつきもので、天候と農業生産との関係から生まれたもので、雷電は雨をもたらし、五穀を実らせる。天神と云えば道真を指すこととなり、その威徳を偲ぶと共に文学を親しんだ神として尊敬されるようになった。江戸期には幕府が庶民の初等教育機関として全国に寺子屋を設立し、その精神的中心として道真の分霊を祀ったので、天神信仰は学神として学力向上、合格祈願の神として広く庶民に奉斎されている。
*著者注:上記の文章では江戸幕府が寺子屋を設立したかのごとくに読めるが、寺子屋は民間教育機関と歴史的に認知されている。つまり今で言えば私塾のようなものである。江戸幕府が作った教育機関として有名なのは昌平坂学問所で、各藩は武士のための藩校を設立していた。それ以外には吉田松陰が作った松下村塾や福沢諭吉が作った慶應義塾に代表されるように私塾が発達していた。現代の私塾とちょっとニュアンスが違い幅が広いかもしれない。藩の領主や重臣、代官等に設立された郷校というものもあって、武士だけでなく庶民教育を行ったものもあるようだ。
・玉垣:平成十六年、・石鳥居:昭和三年、・牛神:平成17年、・大木、・弁天、・秋葉山夜燈:慶應四戊辰1868年、・献燈:御神前:慶應三、・鬼瓦、・事業記念碑2、
神社のすぐ背後というか頭上は新東名の高架線である。
ここから山すそをめぐって400mで北の寺院に行く。
○村良薬師堂(村良574)
・吊るしびな :説明:創建:天保13年1842の記録があり、この頃建てられたと思われる。中には薬師如来が祀られている。薬師堂に長く保存されているつるし雛は地域の人たちの無病息災を祈り、薬師如来に奉納されたもので、明治38年1905と記録されたものもある。このつるし雛は毎年8月23日に行われる薬師如来の祭り「いっちょうぎり」の日に飾られるもので、つるし雛は板の竿に5本の糸で取り付け、吊るされている。平成17年。
左隣の上に寺院がある。
○大仲寺(村良574)
・庚申供養塔:天明八歳、・祠:如来、地蔵2、・手洗石2:、・石垣、・石塔、
東150mで県道に戻れる。すぐ先は村良橋である。渡って進む。橋から300m北上すると右に祠がある。
・祠:地蔵:安政四(桂島、兎島625)
すぐ東先に石段がある。
・神社:祠(桂島、兎島625)
・石段、・自然石1、
100m東に四つ角がある。そこが旧道である。かつては村良橋から北東のAIKAWA工場敷地内を旧道が北上しこの辻に出たようだ。この辻にも祠がある。
・祠:地蔵(桂島、兎島631⁻7)
水害除けで元はAIKAWA工場敷地内の中通りにあったものを移転したようだ。兎島631⁻7金子氏談。
この旧道を北東に350m進む。県道相俣岡部線に出る。ここに石道標と祠がある。
・石道標:是従葉梨村地 □□□町道 大正十五(桂島、須谷793⁻1)
○祠:北向地蔵:有縁無縁三界萬霊等、・石仏4:?観音、観音「一国三十三所」、地蔵2(桂島、須谷793⁻1)
北向地蔵は以前、県道相俣岡部線のトンネル上の貝立峠に祀られていたのだが、トンネルを切通しにした際、ここに移転されたらしい。先の金子氏談。
ここで県道を北西に400m進む。石塔がある。
・石塔:・庚申、・奉梵天帝釋青面金剛太童子(桂島、須谷834⁻1)
100m西進すると県道静岡朝比奈藤枝線(村良から北上する県道、村良で通過するのに使っていた県道)が合流する。
ここで一旦村良から北上し合流する県道で紹介するところがあるので、左折(村良方面へ南下)し150m進む。ちょうど桂島公園を過ぎて狭い水路がある所だ。
・水まんぼう:水路トンネル(桂島、須谷858⁻1)
・説明版:全長70m、幅180㎝、高さ180㎝弱であり、朝比奈川俎板渕の少し上に流れ出ている。この近くにあった字大畑の水田、二町歩が毎年のように朝比奈川、谷川川の増水により須谷川の排水ができず、稲作に被害が出たため造られた。「志太郡誌」によると貝立トンネルの竣工が明治29年1896,1月と書かれているので、おそらくその人足が水路トンネル工事にかかわったと思われる。構造は素掘りで造られ、平成に入ってから入口付近をコンクリートで補強された。平成17年。
~~~
なおここで県道相俣岡部線側の説明をしたい。岡部宿から桂島に行くルートも朝比奈街道だからである。岡部宿から川原町を過ぎ、貝立橋を渡って、現在は峠の切通しを通過する。以前はトンネルであり、更にその上に昔の峠道があり、北向地蔵も祀られていたのだが、切通しになり峠も削られたようだ。
『定本静岡県の街道』によれば、貝立峠以外に川原町から三星寺前を経て牛ヶ谷から山に上り、西の須谷に下る峠道があったようだ。以前は山上までみかん畑や茶畑だったので、明確に越えられる道筋があったのだろうが、植林地になって現在は道が荒れていると思われる。標高差80mほどのようだが、かなりの急斜面である。なお川原町から貝立団地側を通過し貝立峠に行ける道もあったようだ。
○笠懸松と西住墓(岡部、牛ヶ谷1132)
「…やがて西行は駿河国岡部宿にさしかかった。荒れ果てた小さな堂に立ち寄って一休みしているとき何気なく後ろを振り返ってみると戸に古い檜笠が掛かっていた。胸騒ぎがしてよくよく見ると過ぎた春、都で共に修業した僧の笠だった。 笠はありその身はいかになりぬらむ あはれはかなき天の下かな…」ここは歌聖として有名な西行が西住と東国へ旅をしたときに起きた悲しい物語の舞台である。「笠懸松」は右手西行山の中腹にあったが、松くい虫の被害を受け枯れた。その根元には「西住墓」と伝えられる古びた破塔がある。
○三星寺(岡部、牛ヶ谷642⁻19)
貝立橋の南150mに福寿院がある。
○福寿院(岡部、天神前356₋2)
・廃寺:堂、・庚申塔2:文化九年、?、・祠:地蔵3、・墓石:元文元年等古い物あり。
西隣も寺院である。
○永源院(岡部、天神前345)
・寺名碑:昭和四十四年、・六地蔵、・不許葷酒入山門、・地蔵、・祠:石仏:千手観音:札所第四番、
永源院の参道を南に70m進むと西の山斜面上に祠がある。
○岡部天神社(岡部、天神前361₋2)
・祠、・石段
~~~
ここで先の桂島の県道相俣岡部線と県道静岡朝比奈藤枝線が合流する所に戻る。
合流地点のすぐ西に谷川川を渡る谷橋があり、渡り、朝比奈川に沿って遡上するのが朝比奈街道である。ただここで一旦右折(北)し谷川川をさかのぼる。川沿いの新道ではなく、西の山際の旧道がよい。県道から右折して旧道を150m進むと祠がある。
・祠:地蔵:昭和四年(桂島、谷川口1036)
もう150m進むと新道に合流する。その先120m地点に石碑がある。旧道はここから右の工場敷地に向かうようだが、すでに廃道である。新道を進む。
・石碑2:谷川山、梅林院(桂島、谷川口985)
300m北上すると寺院が見える。
・祠:地蔵:説明:故鉱次郎氏は明治28年榊原家に生まれ、昭和51年9月27日、82歳の生涯を閉じた。簑笠辛苦して農業に励み、常に神仏を尊び梅林院5代に亘り身心を盡し、物心両面を惜しまず公益に率先服すること多くよく隣人に益した。老人会はその生涯を讃え集落民の協賛を得て後世まで伝えるために地蔵尊を建立した。昭和52年。
○谷川山梅林院(桂島、谷川山964)
・永代供養塔:平成十三年、・祠:神:石天板、・禁葷酒、・三界萬霊等大乗妙典十部供養塔 銘日、・祠:六地蔵+地蔵:座、・大日如来:線刻、・石段、・献燈2:寛政九、・庭用燈籠2、・新:地蔵:多数:頭部大きく可愛い、
・忠霊塔、・有縁無縁三界萬霊菩提塔:平成十八年、
・木喰仏:薬師如来立像:説明:市指定彫刻:像高95.8㎝、完成:寛政12年8月8日、背面墨書に「日本千体体ノ内ナリ天下安楽興正法」83歳花押あり満面笑みを浮かべ、豊かで大きな衣に包まれ、左手でそれを上から守っている。病気を治してくれるという薬師如来は大国人々に栄拝された。製作者である木喰上人は45歳の時1762木喰戒を受けるとともに日本回国の願を発し、93歳1810で没するまで休むことなく日本全国を歩き続けた。そして足を止めたほとんどの土地に仏像を残している。昭和47年。
・木喰仏:子安観音菩薩立像:説明:市指定彫刻、像高:96.0㎝、完成:寛政12年8月8日、背面墨書、他の一体と同じ、現在梅林院に所蔵されている二体の木喰仏はもともと神入寺にあったもので頭部の彩色はともに近年のものである。廃寺となった神入寺は檀家の総意によって梅林院境内に移され観音堂として保存されている。木喰上人は寛政12年1800、の6月13日より8月13日まで丸2か月間岡部に滞在し附近の寺々に仏像を奉斎した。このうち岡部には梅林院二体、内谷光泰寺二体、三輪十輪寺二体の六体がある。昭和47年。
・観音龍石:説明:この石は昭和35年1月、谷川山梅林院南方約300mの参道上方雑木林内に頭部のみ露出していたものを、たまたま山中に香花取りに入った某氏が見つけ、直ちに当時の梅林院住職に懇願して、この石を譲り受け自宅の庭石となすべく職人を雇い、掘り出しにかかったところが、相当深く土に埋もれているはずのこの石が、予期に反してわずかに鍬を入れたるのみにて、一人飛び出るがごとく、下の参道に落下しなおころころと回転して、道下のやわらかな畑に、でんと座ってしまった。重量1.5トンもあり運び出すのには、いかにも困難であったが、この石に魅せられた氏は、萬金を惜しまず投じようやく自宅の庭に運ぶことができた。渋味もあり何事か神秘が秘められているごとき、この石は水石に興味を持つ人々の話題の的となった。ところがその後夜毎にこの石が氏の夢枕に立って「私は谷川の観音様をお守りする龍身であり、このようなところに置かれるのはまことに不本意である。早々に観音様のそばに帰してくれ。」とのお告げがあり、氏は自分の信ずるある人に伺うに「お告げの通りいかにも観音様をお守りする龍の魂が宿っておられる御尊体である。今すぐ梅林院へお送り申し上げ末永く供養するのがよい」と言われ、驚いた氏は愛着捨てがたき神秘の謎を秘めている石なればこそ、直ちにお告げの通り梅林院境内へ奉納することにした。しかるにこの石を乗せた車が、谷川参道に入るや否やたちまち一天にわかに搔き曇り悲體戒雷ヒタイイカヅチのごとく甘露の法雨降り注ぎ萬雷鳴動して煩悩の焔が滅除された。ときはまさに昭和35年8月10日、その後氏の家では一切の災難を免れ身心快楽となり、現在では大いに家門も隆昌し安泰の生活が送られている。以来この石は観音様の御守護石としてなお一切の災難を厄除し一家の繁栄と幸福に霊験あらたかであるとして世人の信仰を得て供養され現在に至っている。昭和51年11月、駿河一国三十三ヶ所観音霊場第八番札所
・鐘楼堂:説明:建築材:40石当山森林中より、彫刻材(楠)6石殿大石芳明氏寄進、全高地上26尺、屋根幅18尺4面、廊下幅14尺4面、土台幅13尺4面、柱間8尺6寸、丸柱直径8寸七分、建立昭和56年7月、棟梁朝比奈玉取寺坂初太郎氏、記:当山は開創:長享元年1488、その昔合併により日光山神入寺より梵鐘この地に移転さる。偶大東亜戦争勃発し隆魔と化す。現在の梵鐘は当山37世の発願により、昭和30年に再鋳、鐘楼堂は寛政元年1800大工秋山傳右エ門の作である。堂宇の荒朽も甚だしくそのまま放置しておくこともできず協議の結果賛同を得て改築することになる。広く十方檀越の寄進を仰ぎ幸い名棟梁寺坂初太郎氏71歳の斤鑿キンサクにより凡そ1年間の歳月を経て完成を見る。傘下の彫刻八面は棟梁日夜辛苦の作と云われる。当山38世詩之、39世改修、平成20年5月。
○谷川と飯間の峠(藤枝市谷川、静岡市飯間)
今回谷川の奥を調べていないが、二十数年前と十数年前の記憶で記入する。谷川川に沿って3㎞北上する。途中新東名の高架下をくぐりもする。谷川と静岡市飯間の間の峠直下に車で出られる。茶畑を5分も歩いて上ると峠である。その向こうは植林地や草地で道が不明だが少し下ると道が明確になる。ただし途中耕作放棄された畑地で道が不明確になる。1㎞歩いて飯間の農道に出られた。現時点ではこの古道山道がどうなっているかは不明である。茶畑も現在整備されているかも不明である。山の畑はどんどん耕作放棄地になっていくので、歩くなら冬場をお奨めする。
なおこの峠道はかつて1351年鎌倉攻めに向かう足利尊氏が軍勢を引き連れて越えた道である。
県道の谷川口に戻り、朝比奈川に沿って遡上する。
300m進むと関谷橋がある。渡らずに前方50mを見ると鳥居が見える。
○津島神社(桂島、谷川口1107)
・石鳥居:昭和五十年、・石段、・手洗石、・石祠、・石祠(石家道祖神)、・?神木、
神社前の道を通り、丹社を経て溝口橋に抜けたが、特に遺物類は発見できなかった。
関谷橋を渡り、450m進む。祠と石道標が向かい合わせにある。
・祠:地蔵、小地蔵(桂島、関谷343⁻1)
道の向かいに2つに折れた石道標がある。
・石道標:朝比奈街道 山道ヲ経テ葉梨村ニ通ズ 里程凡ソ六千米 約一里半 昭和二年十一月 御大典記念 桂島善□會(桂島、下川原343⁻1)
正直うれしかった。朝比奈街道を調べに来て、その文字を見付けられたからである。西の山を越えると藤枝市北方の葉梨に出られたということだ。そこまでなら3㎞ほどだ。多分葉梨の中心地までなのだろう。この峠道も現在は廃道だろう。見つけるなら冬だろう。ただ地図上では途中村良を通過し農道を通るようだ。残存しているかもしれない。
・古道:桂島の観音下から葉梨の北方への山道。
国土地理院地形図では点線記入されているが現在あるかどうかは未確認。北方と桂島境の峠手前500mは一部農道ルートのようだ。
石道標から県道を300m進むと右に石燈籠がある。
・石燈籠:自然石、・丸石(桂島、下川原231⁻1)
150m進むと溝口橋に達する。この左に旧道があり、祠がある。
・祠:神(桂島、下川原102)
溝口橋を渡って100m進み右折し300m北東へ向かう。
○持珠院(羽佐間105)
・祠:六地蔵:一石二仏の三石:可愛い丸顔で首をかしげているものもある、
梅林寺の隠居寺だそうだ。地元民談。
県道に戻る手前150mで山際の旧道を通り、遡上する。120m進むと山上に石段が続く。
○天神社(羽佐間71⁻1)
・石段、・本殿・拝殿、
山際に沿って400m進む。右に石塔がある。
・石塔:刻字不明(羽佐間351)
もう300m進むと土手に達し左手に橋があり、手前に石塔類がある。
・秋葉山常夜燈:寛政九、・庚申塔2、(羽佐間160)
羽佐間橋を渡り県道は右に曲がって150m行く。右に祠がある。
・祠:馬頭観音6(羽佐間698)
馬頭観音ばかりが6つもまとめて合祀されている。この後もなぜか馬頭観音ばかりを6つ集めて祀っているものにいくつか出会うことになる。六地蔵にあやかっているのだろうか。面白い合祀方法だ。
120m進むと左に寺院の寺名碑に出会う。
○喜雲寺(羽佐間755)
・寺名碑:昭和五十一年、・新:頭部大きい地蔵、・たぬき、・地蔵2:昭和五十六年、・献燈2:、・手洗石、・鐘楼、・四角石、・燈籠:自然石:平成元年、・祠:新:地蔵:座、・新:六地蔵、
県道に戻り50m進む。右に石塔がある。
・庚申塔:明和五、・庚申□□□、・新:献燈(羽佐間698)
県道をさらに20m進むと右に櫓の模型がある。
・模型:朝比奈龍勢打上櫓:高さ3~4m(羽佐間105)
小柳津造園宅の私有地にあるようだ。
・羽佐間の古道(羽佐間675)
県道はこの先60mで殿橋を渡り殿に至るが、その前に古道で付け加えたいことがある。
羽佐間橋まで戻って、県道は殿に向かい右曲がりしていくが、県道を左折して羽佐間橋からそのまま北に向かえる道が山奥に入っていく。それが古道でもある。このまま奥に入りっぱなしではなく、狭間の一番山奥の伏見氏宅:羽佐間675まで行くと右の峠(標高差2m)を家の奥ですぐ越えられ、越えるとすぐに下降し朝比奈川に出て、川を渡り、土手沿いに現在ある龍勢打上櫓のある土手沿いに新舟に進んでいたようだ。ただ伏見氏宅横を細い山道歩道が通っていて標高差2mの峠越えができるが、そこから先は尾根沿いに上る道はあったが、下る道は雑草等ぐちゃぐちゃで発見できなかった。真冬なら強引に下りられるかもしれないが、すでに下る古道は消失しているようだ。惜しい。
この雑草ぐちゃぐちゃ部分をすっきりさせ下れる道を再整備して川まで下りられると、そこは玉露の里から川沿いに土手を整備して歩きやすくなっているうえ、岩などを配置している。その辺りの下流端に出られそうだ。そうすると伏見氏宅からの古道と玉露の里がつながるのだが残念。数少ない古道残存部なのだが。
県道の殿橋に戻り橋を渡って、殿に達する。橋から150m進むと右に増田氏宅:殿183があり、祠があるし、変わった石がいくつもある。
・祠:丸石、・馬蹄石:多(殿183)
増田氏談:この辺りは馬蹄石の産地で各家でお守りとして祀る。石仏では野田沢峠や玉露の里に観音が祀られている。
県道を50m進むと右に石塔が祀られている。
○石塔類:総善寺参道入口(殿753⁻1)
・寺名碑:新:朝比奈氏菩提寺、・農道記念碑:昭和五十年、・丸石、・古:常夜燈、・?庚申:六臂、見聞言ザルレリーフ:寛政七、
この参道で右折し300m北進し右折し300m東進する。途中寺前橋を渡る。
○総善寺(殿167)
寺名碑:昭和五十五年、・六地蔵、・地蔵、・観音:六臂、・石祠、・永代観音堂、・庭燈籠、・丸石、・新:観音、・當國善光寺四國西國秩父坂東百八拾八所供養塔 當村 明治十四年、・板碑:平和の礎、・板碑:、・献燈2:、・自然石、・鬼瓦:昭和六十年、・観世音菩薩:昭和五十八年、・献燈:平成二一年、
・「殿の虫おくり」:説明:殿地区には、山あいにしては比較的広い水田がある。そして起源は定かではないが昔から虫おくりの行事が行われている。この行事は秋ウンカが発生すると村人は松明に火をつけ行列を組み、集落全体を歩く。この時人々は「青田の虫を送れ、田の虫を送れやあ。」などと唱えながら、松明で田の面をなでるようにして虫を誘い出し焼き払った。しかしこの行事は農薬の普及により自然に行われなくなったが、昭和60年頃の町内会長、有志の人たちによって復活し、夏の一夜を楽しむようになった。現在では8月23日の夜、六地蔵尊縁日に合わせ町内会、子供会で中心になって、この行事を継承している。平成15年。
また県道に戻って西進する。100m進んで左の朝比奈川土手を見ると300m先の土手沿いに高い櫓がある。
○朝比奈龍勢花火打上櫓:無形文化財(殿167)
・説明版:歴史的な由来は定かではないが朝比奈城跡朝日山城跡又駿府城跡の位置関係から山城閒の戦略の一手段として使われた「狼煙のろし」をその起源にする説が有力である。江戸時代後期より六社神社例祭を飾る行事として又豊作を祈願して献發され、それぞれの秘曲が伝承されてきた。大東亜戦争中、中断され昭和22年農村慰安として復活、東司は柳の木などに櫓を括り付けて打ち上げられていた。昭和37年より本格的に打ち上げられ民俗文化の伝承には組織が必要と昭和53年に朝比奈龍勢保存会が設立され昭和59年、県より無形民俗文化財の選択指定を受けた。現在13の龍勢連260余名の会員を有し、歴史と文化の息づく郷土づくりのシンボルとして高さ20mの常設櫓を町助成金により建築された。平成2年。
またこの土手へは、川向こうの羽佐間の伏見氏宅から下ってきた古道が、川を渡って川のこちら岸につながっていたのである。
また県道に戻って、西進する。すぐ右(北)に公民館と公園があり、看板説明版がある。
・看板:朝比奈大龍勢:朝比奈大龍勢は、戦の狼煙の名残と考えられ、明治以前から例祭を飾る事業として打ち上げられている。静岡県内でも数箇所にしかないこの花火は、すべて地区龍勢連の手で作られ地区ごとにその技を競う。現在は2年に一度打ち上げられ、その勇壮な姿を楽しみにしている人も少なくない。
イラスト図では先頭部:ガ(ガンタ)、次いで吹き筒(フキゴ)、重心は吹き筒の長さの2.5倍部分、下方を尾という。
県道を100m西進し右折し北東進する。殿の西ノ平の集落内旧道である。100m進むと祠がある。
○祠:地蔵、・新:でか地蔵、・奉納西國三拾三所秩父三拾四所坂東三拾三所四國八拾八所文化十五(殿、西ノ平683₋2)
この祠から集落西の山上に大木があり、神を祀った祠がある。ちょうど萬年寺から朝日山城ハイキングコースを上りだすと横を通過することになる。
~野田沢~~
西の平の集落を北に抜け総善寺参道前も通過する。大野原橋や原上橋を通過するのが明治20年代のルートに近い。原上橋から300mで分岐になる。西又や岡部のリサイクル工場、小園地蔵方面へ行く西又林道が左に分岐するが、右へ行くのが野田沢ルートである。
400m進むと右に石塔がある。
・石塔:十一民平墓万(野田沢)
900m進むと野田沢橋を渡り、野田沢集落に達する。橋から350m進むと野田沢公民館前の橋袂に石塔類が苔むしている。
○石塔類(野田沢77₋2⁻1)
・庚申塔、・○奉禮観世音菩薩 西國三十三所順拝□観世音、・庚申塔:昭和五十五年、・奉善光寺如来供養:明治三年、・献燈、*自然石2の上に石塔類は固定されている。
100m進むと右に橋がありその向こうに石段がある。
○山神神社(野田沢103)
・石段、・石碑:手摺~:平成二十七年、・石鳥居:昭和三年、・手洗石:昭和六年、・祠、・拝殿本殿、
200m進む。野田沢の集落が切れる所に祠が祀られている。
・祠:笠かぶり地蔵(野田沢140)
200m進むと舗装自動車道が二手に分かれる。左が野田沢峠経由で静岡市飯間に出られる道である。ここに祠がある。
○祠:石道標:此れより右やまみち左ふちゅう寛政七年
・説明版:上記のように記されているが、寛政七年は西暦1795年で江戸時代の中期になる。この道しるべは、朝比奈から静岡市飯間を経て、駿河の府中(静岡市)へ通じる昔からの街道の一つであったことを示す遺構である。古老の話によると今川氏真が武田軍勢に追われて駿府の館から掛川城へ落ち延びる時、永禄12年1569に通った道という。現在は自動車社会になり、往来が少なくなった時期もあるが、農道整備事業により幅5.9mの快適な舗装道路となり、昔と変わらぬ物流道路としての活用が期待される。
この石道標を、よくぞしっかり保存したものだ。刻字はかなり読めなくなっているが、説明版によって分かる。将来文化財に指定されるかも。
かつてここには自動車道はなく、歩く山道があり、歩いて野田沢峠を越え飯間に出た。峠には六地蔵が祀られ、ハイキングコースとして知られていたが、自動車道ができハイキングコースになっていた古道は消失した。
祠裏の岩の中に馬頭がある。
・馬頭観音:石祠内
自動車道を上っていく。峠には新しい石碑が建立され、六地蔵は道の左擁壁上に祀られている。ちょうど静岡市と藤枝市の境界線になっている尾根沿いを1990年頃歩いて通過したことがある。その時野田沢峠も通過し六地蔵を見た。境界線尾根の道は劣化しているだろうが冬場なら歩けるかもしれない。
○石碑:山峡招き緑風爽やか、・板碑:2000年、
○六地蔵+観音:文久元酉九月日世話人増田増右エ門、
1861年。
~~~
また殿と新舟の県道に戻り、西進する。180mで右に寺院への参道となる。
○萬年寺(新舟1240⁻1)
・寺名碑:昭和四十八年、・□□□大菩薩、・萬年寺のカヤ:県指定天然記念物:根回り8m、目通り5.8m、樹高30m、根張り東西30m、南北25m、
寺の裏から朝比奈城ハイキングコースになっていて裏山に上って行ける。
○朝比奈城ハイキングコース
萬年寺から100m上っていくと殿、西ノ平集落の裏山に出る。ここに大木と祠がある。
・祠、大木
更に100m上ると石碑と石段がある。
・石碑:経塚址
更に10分も上ると山頂の平坦地で看板がある。
・朝比奈城跡
・説明版:戦国時代に岡部氏と並ぶ武将、朝比奈氏は今川、武田氏に仕え特に信置という人物は武功を上げ今川氏より感謝状を受けた戦国雑誌に「止駄郡殿村にあり今川家の功臣朝比奈某の築く所にして永禄年中まで朝比奈家代々の居城なり」とある山頂に土塁や空濠を作り居館を麓に作ったことからいわゆる「根古屋式」の城塞といえる。
空堀一つ、本曲輪が若干見られるが、城の分かりやすい遺構はハイキングコースから見付けにくいし、取りたてて紹介する標識類もない。ルート標識と山頂の城紹介看板になり、他の遺構類を紹介する標識設置が望まれる。
山頂を過ぎて20~30分下ると善能寺前に出てハイキングコースは終了である。
萬年寺入口に戻り、そこからもう20m進むと左に土手があり、馬頭が祀られている。
○馬頭観音6(新舟1240⁻1)
・馬頭:剥落しかかり、・馬頭観世音:大正六年、・馬頭:八臂:昭和四十八年:怖い形相、・南無馬頭観世音菩薩:昭和四十七年、・馬頭:大正十五年、・馬頭:八臂うち六手はレリーフで顔の形相は怖い。
県道を30m進むと右に道の駅がある。
○道の駅 玉露の里(新舟)
・昆虫館、
道の駅を過ぎてすぐ右側の家前に新しい石塔が2つある。
○石塔3(新舟1004)
・新:三界萬霊塔、・新:交通殉難者供養塔、・古:丸石
すぐ左に玉露の里に渡れる橋がある。
○玉露の里(新舟976⁻1)
・石碑:玉露の里、
・句碑:村越化石:句碑は芸術的に斬新ですぐれている。説明:村越化石は大正11年朝比奈村に生まれる。本名:英彦。昭和13年ハンセン病発病の為旧制中学校中退、昭和16年に草津の国立療養所栗生楽泉園に入園。昭和24年に大野林火先生に師事、これまで俳人協会賞、蛇笏賞の他俳壇の各賞を受賞。魂の俳人といわれる。平成3年には紫綬褒章を授賞。石刻句:「望郷の目覚む八十八夜かな」平成七年作。望郷の句は私に多い。故郷を離れてすでに久しく、見えない眼の奥にいつも故郷がある。夏も近づく八十八夜は新茶の初摘みの頃、村中が茶の香りに包まれるよき季節。生気溢るる八十八夜は望郷とともに私の好きな言葉である。村越化石。村越化石顕彰会。
・新:諸畜霊同魂碑:平成三年、・庭園:茶室庭園はこじんまりしているが素晴らしい。
・椿園、
なお玉露の里の諸蓄霊碑のある所に馬頭観音があると複数の方に言われたが、諸蓄霊碑しか見当たらないので、最近馬頭を移転して諸蓄霊碑を安置したのかもしれない。
・吊橋、
玉露の里入口の橋から県道を100m北上すると、右に神社がある。
○六社神社(新舟1018)
・社名碑:昭和六十年、・手洗石:昭和二十七年、・石鳥居:明治四十二年、・手洗石、・石鳥居:破片、・自然石:多、・石段、・大木:多、・常夜燈2:昭和六十三年、・常夜燈2:天保十一年、・忠魂碑:昭和二十七年、・板碑:忠魂碑参道、・狛犬2、・献燈4、・板碑2、「狛犬1対、「平和と鎮魂の標」
・説明版:朝比奈大龍勢:県指定無形文化財:朝比奈大龍勢は六社神社の例祭に合わせ、祭神に豊作への感謝と地域の安全・発展を祈願して奉納される花火の一種です。その呼び名は花火が轟音を響かせながら真っ赤な火の尾を引いて空に上がっていく様子が「昇天する龍の姿」に似ていることから付けられたと云われる。龍勢の起源については「戦国時代の狼煙説」と「江戸時代の猟師鉄砲試射説」とがあるが、はっきりしない。昭和53年に「朝比奈龍勢保存会」が作られ、今は13の龍勢連が加盟して各連ごとに秘伝の技術がある。隔年の10月に打ち上げられ、各連がその技術を競い合う。県内では草薙でも打ち上げられ、全国では4カ所しか行われない大変珍しい花火である。
神社から200m北上する。
○祠:・地蔵3、・馬頭1、・丸石5、・層塔(五重)(新舟233₋2)
地区の石塔類を合祀したようだ。
200m北上する。右の路地の1軒奥に常夜燈がある。
○秋葉山常夜燈:火袋辺り:昭和五十一年、竿部分:文化元子年1804(新舟175₋1)
常夜燈の火袋部分は修復され昭和の年号が刻され、竿部分は古く文化の年号が刻まれている。こうやってでも保存していることがうれしい。
県道の左側には榎橋が架かり朝比奈川を渡れる。渡ってすぐ左折し川に沿って150m南下すると祠がある。
○新舟西宮恵比寿神社(新舟522⁻1)
また榎橋に戻り左折(西)し笹川を目指す。400m進むと右(北)に行く道があり、石碑がある。岩瀧不動尊参道である。
○岩瀧山不動尊
・石碑:岩瀧不動尊参道
参道を450m進むと標識があり、右の崖下に滝があることが分かる。
・不動男女の滝
滝入口から奥に100m進む。
・岩瀧不動尊:
・岩穴ののぞき地蔵、・献燈:平成九年、・手洗石:昭和十七年、・献燈:昭和四十三年、・例祭日:10月28日、2月28日、
参道を戻り参道入口を目指す。今度は笹川を目指し450m進む。橋の袂に石塔がある。
○祠:・庚申塔:見聞言サルレリーフ:寛政?、・献燈:昭和四十三年、
200m進むと駐車場があり、笹川集落の中心部に達する。
・石祠
駐車場に説明看板がある。
・笹川集落の歴史
・説明:言い伝えによると、笹川八十八石ハイキングコースをビク石に上っていく途中に南向き傾斜面で日当たりのよい平坦な場所を「落人の段」と呼んでおり落人の忍び住むには、絶好の場所がある。ここに文治元1185年源平合戦において平家が滅亡し、平家の落人がここに住み着いたのが笹川の始まりであるといわれる。また集落の入口付近に「上の山」という山があり朝比奈川のほとんどの集落と遠くは岡部本町から焼津方面まで見渡すことができる場所があり、ここの山の背を掘割り追手を見張る場所としたと言い伝えられている。やがて時がたち世の移り変わりとともに家族も増え、落人の段から順次安住の地を求めてこの笹川の盆地に居住し笹川集落を形成した。また昔からの書紀によると駿河の国志太郡笹川村新舟とあるように笹川空さらに新舟にと住み着いたと考えられる。
・水玉神社と十四地蔵尊の由来
・説明:昔、笹川集落へホウエンさん(祈祷師のことを村人はこう呼んでいた)が、落ち延びて、この地に住み着いた人たちのために15の玉を下さった。これを氏神様として祈っていた。氏神にお参りする人々は清水の流れる堀の沢で手を清め口をすすぎ家内安全と集落の安泰発展を祈って心のよりどころとしていた。いつ頃か不明だが、突然の地震か大雨かその原因は不明だが、大きな山崩れがあり氏神である15の玉神様は埋まり何日も土砂の掘り返しを繰り返し続けたが、14の玉神様を見付けられなかった。幸い埋まらずに1体が見つけられ、この1体を水玉神社として、また見つけることができなかった玉神様は十四地蔵尊として祀られた。
駐車場のすぐ先の分岐点に石道標がある。
・石道標:瀬戸谷村十八瀬ニ通ズ 葉梨村上大澤ニ通ズ 御大典記念 昭和三年十一月新舟発起人
瀬戸谷十八瀬へはちょうどビク石登山道を指し示し、ビク石から瀬戸谷に下ればよい。上大澤へは笹川集落の水玉神社奥を尾根に取り付き山越えすると上大澤である。こちらは今となっては山道があるやらないやら。
この分岐点から左上の神社方向を目指す。
○水玉神社(新舟、笹川828)
・石段、・献燈2、・手洗石:文化十一、・十五玉伝説:上記、
○駿河一國百地蔵尊第十九番笹川十四地蔵尊、勝覚法師(新舟、笹川738)
・石祠、・観音、・手洗石、・献燈、・献燈:昭和四十三年、・十四地蔵、
・祠:勝覚法師:地蔵5:説明:勝覚法師は地元の農家の出身で取りたてて学問を納めたわけではないが、地元民の為功徳を施し、地元民の尊敬を集めた人であったようだ。没後も信仰を集め、勝覚法師として祀られるようになったようだ。
先ほどの石道標の分岐点に戻り、ビク石方向を目指す。150m進むと右の沢向うの茶工場隣に石塔がある。墓石である。
・墓石:享和三亥七月一日早世一葉童女:1803年
更に奥へ500m目指すと舗装路の終点となる。現在はここからビク石登山道であり、笹川十八石である。昔は集落尾張の家の裏山から山に取り付き尾根に出てビク石を目指したようだが、十八石を通過し手から尾根に取り付くコースになったようだ。
○笹川十八石
・表石、手洗石、赤石、三の石、ナメクジ石、ホコ石、むすび石、五色石、ラクダ石、メガネ石、こうもり石、座禅石、想像石、見上げ石、象石、がま石、コラサー石、出船入船石、こもたたき石、
・ビク石登山道:古道:笹川から笹川十八石を経てビク石山頂へ、そしてビク石から瀬戸の谷へ下れるルートである。現在はハイキングコースとして利用されている。一部は古道のままではなく道が付け替えられているようだが、およそ古道が現在でも利用されて保存されている好例であり、最も古道が残っている部分である。途中地蔵があるようだ。今回未調査。
また来た道を戻り榎橋を渡り県道に戻る。100m県道を北上する。右奥に寺院がある。県道からの参道入口に墓石や石塔がある。
○石塔、墓石(新舟137₋1)
・如来:墓石?、・萬霊塔、・墓石3:~信女、・墓石:~童子、・観音:墓石?、
○善能院(新舟271)
・寺名碑:昭和六十三年、・如来、・観音、・地蔵、・観音?、・庚申供養塔、・祠:六地蔵、・薬師堂、・禁葷酒:寛政十二、・手洗石:、・臼、
寺の裏山は朝日山城ハイキングコースで墓地で配水場でもある。裏山を100m進むと墓地手前に祠がある。
○祠:不動明王:天明元年(新舟271)
・五輪塔、・献燈、・石塔、・丸石:二段重ね、
県道を200m北上すると朝比奈川に架かる石上橋を渡り宮島の石上集落になる。更に県道を奥に目指す。石上橋から300m進むと左折し上に上っていく小道がある。50m上って右の小屋の先の奥に祠がある。
○祠:マラ地蔵(宮島、小丹原456⁻12)
・祠:マラ地蔵:一石に6組(多分男女で一組)の双体道祖神をレリーフ、横に男根石か?、丸石、8月7日の旧七夕に読経、この地域では七夕は8月7日、宮島小丹原457⁻8:前島氏奥さん談、
県道に戻る。県道沿いに石碑がある。
○板碑:記念碑(宮島、小丹原522⁻6)
記念碑から県道を400m進む。左に石碑があり、奥に大木が見える。
○大山祇神社(宮島、小丹原419⁻9)
・石道標:大山祇神社:県道沿い、・石鳥居:昭和三年、手洗石、・巨木3~5、・巨木切株、・大木5~6、
県道に戻り30mで宮島橋であり渡ると宮島の板取集落である。橋を渡ってすぐの右家に祠があり、もう1軒先にもある。
○祠:神、・祠:石塔:紀伊国川中島八兵衛:明治四十四年(宮島、板取760)、
川中島八兵衛石塔は志太郡榛原郡に偏在していて、今の藤枝市、牧之原市、焼津市、島田市周辺に分布しているようだ。詳細は『大井川町史下巻』に書かれている。これは朝比奈街道沿いの最も奥にある物ではなかろうか。
県道を150m進むと左折し朝比奈川沿いに進む道を行くと朝比奈川を渡る田島沢橋があり、渡ると、左が民宿朝比奈で右が城山不動尊方向である。右に100m向かうと田島沢に架かる橋を渡る。沢に沿ってすぐ左折し、800m奥を目指す。
○成田山城山不動尊
・祠:姫祀り、
舗装林道沿いに祠がある。ここから沢に架かる橋を渡って城山に上る。15~20分登り山の中腹の平坦地に不動尊が祀られている。
・石碑:城山観世音菩薩、・羅星庵、・祠・祠:石塔、・献燈2:平成十八年、・祠:地蔵:小多数、・地蔵、・新:自然石大石&不動明王像、・新:献燈2、・新:祠4、・新:平家の石塚、・新:地蔵、・新:源氏の石塚、
○城山:宮島城跡:△377.1m
不動尊は城山中腹の標高200m前後と思われる。この山は名の通り中世山城跡であり、宮島城といい、山頂は標高377.1mである。不動尊より上に上る道らしきはないようだが、ここから上れると山頂は近いようだ。他ルートとしては新舟の榎橋近くの新舟330:村越氏宅裏から道があるようだが、村越氏の話では途中から藪になり道は不明確だろうとのこと。また宮島の石上343村越氏宅横からも道があるようだが、付近住民によると道はないらしい。また岩瀧不動尊お堂の裏から上ればとも考えられるが、お堂の裏に道はない。せっかく中世山城があるのに行く道がないのはもったいない話だ。道を付けるとよいのだが。
また元来た朝比奈川沿いの県道に戻る。県道を300m北へ進むと寺院の参道入口になる。
○清養寺:
・寺名碑:昭和五十三年、・奉納西國三拾三所供養:文政七、・奉納西國秩父當國観世音菩薩:文政九、・善光寺詣供養塔:明治十五年、・三界萬霊等:昭和五十□□、・馬頭:明治二十一年、・馬頭:明治廿年、・観音堂、・小坊主地蔵、・四角石の碑、・水子地蔵、・六地蔵、・石、・庚申塔:昭和□四□、・庚申塔:見聞言ザルレリーフ、・丸石、・秋葉山常夜燈:文政九、
寺参道入口にはまた石道標があり、そこから寺参道の南とは逆に北へ行く山道歩道がある。
○石道標:朝比奈街道 南藁科村ニ通ズ 御大典記念昭和二 宮島
多分小園地蔵前を通過し、西又または野田沢峠越えで静岡市藁科地区へ出る道を示していたようだ。確かに現在でも小園地蔵前から自動車で西又や野田沢越えで藁科に出られる。
○古道:清養寺←→小園地蔵:距離500m、標高差50m
この山道歩道は距離500m、標高差50mを歩いて西又への道への途中の小園の地蔵がある所に出られる道である。十数年前に歩いたときはもっと道が綺麗だった。今回は歩いていないが、出入口の二カ所を見た所でも状態が劣化していると感じた。この朝比奈街道中、最も現在の街道から近い所で古道の状態を保った道が500mほどの距離で残存していると拝見する。この古道部分を失えばもはや朝比奈街道の古道は絶滅に近いだろう。この道は何とかして保存してもらえないだろうか。今回この朝比奈街道を調べブログへアップしたのも、この古道部分がどうなったか気になったので、調べたようなもので、保存を呼びかけたかったからである。もはや朝比奈街道の古道部分は消滅寸前である。
県道を150m進むと柚ノ木橋があり渡り、更に300m進むと小園橋がある。橋手前の公民館に常夜燈がある。
○秋葉山常夜燈:自然石、・丸石(宮島、小園91⁻1)
小園橋を渡る。県道は左折するが、西又への道で集落奥に向かう道を100m進むと左にお堂がある。
○芙蓉庵(宮島小園1393)
・瑠璃光山芙蓉庵薬師堂、・寺名碑:瑠璃光山:2m:文政四、・観音、・奉百番観世音菩薩、・如来、・石塔、・台座等、・○○奉供養(美良)青面金剛大菩薩:嘉永元戊申八月、・庚申供養塔:明和四丁、・自然石、・手洗石、
集落奥への道を更に100m沢沿いに奥に進む。右に橋があり鳥居が見える。
○日吉神社(宮島、小園1383)
・石垣、・木鳥居、・石祠、・大木5~6、
神社前の狭い農道を奥に詰めていく。
・古道:小園の日吉神社横農道から玉取沢への道:両方とも取付きは農道で人家がある。途中から鎌道のようだが、現在でもしっかりあるかどうかは未確認。
現在はもっと西の朝比奈川本流沿いの近又、谷倉に県道が通過しているが、昔は本流沿いに道を作りにくく、東の小園と玉取沢を結ぶ峠越え道を主要街道にして利用したのだろう。
西又へ進む県道静岡朝比奈藤枝線へ戻り、西又方面へ800m進む。石塔や祠がある。
○小園の延命地蔵尊
・説明:この地蔵尊は地元では「峠のお地蔵さん」と呼ばれ、昔から多くの人たちに親しまれてきた。いつ頃ここに祀られたか不明だが、駿河の国百地蔵の18番札所の延命地蔵尊として、今もなお多くの参拝者が訪れる。向かって右側の地蔵が初代のもので左の地蔵は昭和5年に建立され毎年9月13日には老師により法要が営まれる。そして百地蔵にはそれぞれ歌が詠まれている。「ひとすじ(一筋)に も(漏)らさで すく(掬)ふ ぐわん(願)なれば すく(救)いたまえや 南無地蔵尊」 この他岡部町内には16番「坂下の延命地蔵尊」、17番「光泰寺の地蔵菩薩」、19番「新舟の十四地蔵尊」がある。平成16年。
・祠:駿河一國百地蔵尊第十八番:地蔵4:昭和五年、昭和四十五年、・石塔、・手洗石、・秩父三拾四所供養塔:文化十年、
地蔵の裏から峠下に下って清養寺前に出る山道がある。古道で距離500m、標高差50mである。
~西又~
県道を50m進むと右に下っていく道もある。直進すると西又で、右へは岡部のリサイクル工場を経て野田沢や殿方面に行く道である。西又へ進む。
1.3㎞進むと小さい境橋があって藤枝市と静岡市の境界線になる。静岡市には一転すぐ右の工場に燈籠がある。
・自然石燈籠(静岡市西又1955)
県道を600m進むと西又集落の中心的四つ辻に出る。
2軒手前に戻り石段を上ると神社がある。
○八幡神社(静岡市西又1977)
・自然石2:二段重ね、・石段、・社殿、・祠、・サワガニ:石段に棲息、
また四辻に行き左折(北)し100m進むと右に西又公民館がある。この道向かいの左に堂がある。
○堂:三十三観音(静岡市西又2053)
・欠番:1,3,22,33番の4体で、29体があり、見事なものである。
○弓折峠(静岡市西又と玉取沢の閒)
公民館前の道を奥に1㎞進むと自動車は進めなくなるが、300m歩いて峠に行く道がある。
峠は1990年頃は茶畑だったが2002年には植林地になっていた。そして弓折峠からダイラボウに上る登山道もあったが現在はどうなっているか不明だ。
弓折峠は西又と玉取沢を結ぶ峠道である。以前2回上ったが特に遺物類はなかった。
また西又の四辻に戻り南に50m進む。堂がある。
○地蔵堂:地蔵(静岡市西又2050)
・庚申塔:天保九年戊戌十一月吉日、・観音:文政元寅年十二月吉日、・善光寺供養:明治二十二年、庚申供養塔:安永八年、・○庚申塔:昭和五十五年、
県道に戻り静岡市街方面へ進むと西又峠を越える。特に遺物類はなくダイラボウ登山口標識がある。県道のこの先は藁科である。
*西又の33観音、地蔵堂、八幡神社について教えて下さった西又1977:斉藤氏奥さんに感謝いたします。
~宮島、小園に戻る~
小園橋袂から県道相俣岡部線を朝比奈川に沿って遡上する。
芙蓉庵前から山際集落に沿って西に向かい県道に合流するのが旧道である。特に遺物類は見当たらなかった。小園橋から900mで近又橋に至る。手前右にどうも清水があるらしいが分からなかった。
○「ごとうの清水」
未発見。
橋手前のお宅にも丸石があった。
・丸石(玉取、近又30⁻1):松野氏宅
橋を渡る手前を右折し川に沿って進み、その奥の川の支流にどうも滝があるらしいが未発見。
○「近又三日滝」(玉取、近又51⁻2)
未発見。
近又橋を渡る。正面に寺院が見える。
○西楽寺(玉取、近又116⁻1)
・石段、・石塔、・献燈の竿部分、・常夜燈、・祠:地蔵、・庚申塔:明和六己年、
○青羽根への古道(玉取、近又116⁻1)
寺は山の尾根に取り付いた一段高い所に築かれており、その斜面の左側を青羽根への古道が通っている。その道は現在の青羽根への自動車道より一段高い所にあり、古道の下に新道が見える。ただし古道はこの裏の隣家:玉取153:入野氏宅で一旦おしまいのようだ。
寺の手前に保育園があり、園庭に像がある。
・二宮金次郎像:マキを背負い読書(玉取、近又121⁻1)
二宮金次郎のかつての学校での代表的な像であるが、残っているものは限定的なようだ。このまま保存する価値は十分だろう。
メイン街道は橋を渡って右だが、ここは直進して青羽根を目指す。
~青羽根~~
青羽根集落直前の自動車道沿いに石仏がある。
○馬頭観音2:明治十二年、-(青羽根、入口)
元は古道沿いにあったのだろうが、自動車道の集落入口に祀り直したのだろう。
集落に入り道を上がっていくと常夜燈がある。
○常夜燈:奉請秋葉大権現 天明五 青羽根村(青羽根716⁻1)
150m上っていくと板碑がある。
○石塔類(青羽根772)
・板碑:久志之光、・新:献燈、・手洗石、・石柱2
さらに100m上っていくと石仏がある。
○石仏:地蔵、小五輪塔2(青羽根754)
50m上り神社やハイキングコースがある方へ進む。
○新四国八十八カ所観音堂(青羽根997)
・観音堂:八十八観音、・?庚申塔、・馬頭2:顔破損、-、・庚申供養塔:宝暦七年、・手洗石:天保十三、・観音:聖観世音第二十一番、
30m進んで右のパノラマハイキングコースの道を100m進む。神社がある。
○大井神社(青羽根981)
・説明:駿河国益津郡朝比奈青羽根村に居住していた佛弟子の藤原朝臣永泰の寄進に依り建立。応仁元年亥年10月25日、願主藤原二良右衛門に依り建立、大工松山子宣。宝暦六年丙子8月、再建、神官諏訪丹波守、大工藤枝宿仁兵衛により建てられる。元治元年甲子8月27日再建。昭和12年再建。
・説明:青羽根地区は寿永四1185年、平家滅亡で、氏族存続を願いこの地に隠れ住んだ人たちの集落といわれる。仲本、村上、京、羽山、永井二家、清水の七家が集落の起源で青羽根七人衆と云われ、現在でもその子孫が家系を継承している。この大井神社は集落の護り神として青羽根村に居住していた仏弟子の藤原朝臣永泰の寄進により、応仁元1467年願主の藤原二郎衛門によって修造され、今でもその時の棟札が保存されている。その後3回ほど修造され、現在の建物は昭和12年に修造されたものである。また御神木の大杉は推定樹齢700年以上、根回り8m、樹高28mで市指定天然記念物である。志太の朝比奈村誌より。平成16年。
・木鳥居、・献燈2:安永五、・石祠2、・手洗石:大正元年、・献燈2:平成二十二年、・和合の樹、・大スギ:根回り8m、目通り5.4m、樹高28m、根張り25m
○パノラマハイキングコースにあるもの
・長塚石、・マンガン鉱山跡:採掘洞窟:すでに落盤で崩壊、・長塚峠、・麦地峠、
青羽根と市之瀬の境界尾根の峠に進む。かつての旧岡部町と旧藤枝市の境界線であった峠である。かつて「コスモス峠」という標識を見たことがあるが、正式名とは思えない。なんという峠名であろうか? 石仏もある。
○峠:?コスモス峠:青羽根と市之瀬の間
・石仏3:馬頭1、地蔵1、?1、
この尾根の南は藤枝市の市民の森△464mとなり、手前に駿河峰△489.9mがあり、市民の森の南にはビク石山△526mがある。
~~~
青羽根を終了して、県道の近又に戻る。玉取沢方向を目指す。600m進むと右に石塔がある。
○石塔類(玉取、近又351⁻1)
・庚申塔□永五□歳、・常夜燈:自然石、・?馬頭、・手洗石:内側ひょうたん型、・丸石、・花生け台2、
~谷倉~~
250m進むと落合橋に達し、谷倉集落となる。県道相俣岡部線は直進だが、左折し谷倉沢に沿って500m進むと右に寺院がある。
○梅窓寺(玉取、谷倉1328)
・地蔵、・石段、・○庚申塔:大正三年、・献燈、・六地蔵+観音:座、・石塔、・西國三十三処當國三十三処、・奉供養西國三拾三所観世音菩薩、・丸石4、・丸石:お供え餅風三重、・へそ石、・石祠、・手洗石:文化十四、
さらに30m進むと左に祠がある。
○祠:神、・献燈2:昭和四年、・手洗石(玉取、谷倉160⁻1)
70m進むと左に橋があり、その向こうにかつて畑地があったようだが荒れかかっているようだ。地元の人の話だと畑に八幡神社の祠が祀られているそうだが、探したが見つからなかった。
○?祠:八幡神社(玉取、谷倉1265₋2)
未発見。
さらに奥に150m進むと右に石塔類がある。
○石塔類(玉取、谷倉1170⁻4)
・庚申塔:大正三年、・庚申塔:明治八年、・常夜燈:自然石、
この奥は谷倉沢渓谷と呼ばれるようだ。結構奥まで人家があるようだが、古道遺物類は人家がある範囲内では見つからなかった。
~~~
落合橋まで戻る。
谷倉集落でも各家に丸石がある。
県道を200m進む。左は地域活性化センターであり、石造物がある。
○石造物(玉取、谷倉1476⁻1)
・秋葉山常夜燈:天保九:2.5m、・丸石3、・自然石:多、・新:地蔵2:頭でかくかわいい、・たまいし様、たまゆら、
この裏に神社がある。
○神明神社(玉取、谷倉1512)
・石段、・石鳥居、・石垣、・スギの大木、・他大木、
県道に戻り150m進む。
○石塔類
・祠:地蔵、・庚申塔、・献燈:自然石と金属加工の燭台、
600m進むと沢口橋手前で玉取沢右折する。
~玉取沢へ~~
180m進むと右に石塔類がある。
○石塔類
・○庚申塔、・献燈、・花生け台2、
なおも奥に350m進む。
○天狗の手洗い鉢(玉取沢1907)
・場所がはっきりしないが?多分沢崎氏宅の裏に手洗石が置かれていたようだ。
・説明版:昔法印さんを慕っていた天狗がいた。夜になると天狗は法印さんの墓に植えた大きな松の木の杖に来ては、毎晩のように太鼓を鳴らしたり、笛を吹いたりして、大変にぎやかに過ごしていた。しかしいつの間にか庄園どんの爺さん以外には声や音は聞こえても天狗の姿は見えなくなった。あまりの不思議さに近所の人たちが「そんなバカなことがあるか。」と言いあっていた。それを耳にした天狗は「それなら証に珍しいものを持ってきてやるか」と爺さんを一緒に雲に乗せて連れて行き、京都から一夜のうちに持ち帰ったのが、この手洗い鉢だという。朝比奈第一小学校編「あさひな」より、平成16年。
この玉取沢から南に入っていき峠越えすると南の小園へ抜ける古道があるようだ。ゼンリン住宅地図では細線で記入されているので道型は残存しているかもしれないが未確認。
玉取沢を東奥に詰めると自動車では行き止まりだが、歩いて西又へ抜ける弓折れ峠に至る。
○弓折峠
・西又の項目で前述している。付加すると、この山道はいまだに自動車道ではなく古道形態を残存していると言える。
~~~
県道相俣岡部線の沢口橋に戻る。
400m進むと山中(富厚里)への分岐点で、すぐ先の橋は境橋で藤枝市(旧岡部町、旧志太郡)と静岡市(旧安倍郡)の境界線である。朝比奈川を詰めると静岡市になるというのは何だか変な気がするが、志太郡と安倍郡の境なのだ。ここに石道標がある。
○石道標:御大典記念 朝比奈街道 南岡部町方面 北小布杉三野ヲ経テ川根ニ通ズ 東山中峠ヲ経テ藁科ニ通ズ
~~~
分岐点から右折(東)し600m山中集落、静岡市街方面へ進む。山中集落のお茶工場隣の山中集会所の横に石塔類がある。
○石塔(静岡市小布杉、山中2613)
・観音、・庚申:見聞言ザルレリーフ、・石塔、・一石三観音、・観音、・石塔、・地蔵、・新:献燈、・石仏、
300m進むと右上に鳥居がある。
○神社(静岡市小布杉、山中2346)
・金属鳥居、・本殿、
このすぐ上の御宅横からかつては中学生の通学路になっていた古道が峠まであった。
○古道:古い通学路(静岡市小布杉、山中2672)
40年程前までは中学生の通学路としても使われていたが、新道:自動車道が整備されて使われなくなったし、自動車道の下で沢沿いで、かなり崩壊したと思われるが、残存していれば価値ある古道と言える。富厚里峠から富厚里側に1㎞下るまでも古道があった。
山中の神社から自動車道で1.1㎞で峠である。
○富厚里峠(山中峠)
・祠:地蔵4、小地蔵12、・手洗石:大正三年、・奉納西國三拾三所巡拝供養塔:大正十四年、・開通記念碑:昭和四十六年、
峠の山中側少し手前に林道が分岐しダイラボウまで行くことができる。ダイラボウ山頂すぐ横の林道頂点には石碑がある。
・開通記念碑:平成16年3月
・ダイラボウ山頂:
・説明:昔「大らぼう」という大男がいた。富士山をつくると言って琵琶湖の土を大きなもっこに入れて運んだ。大男は富厚里山の上から水見色の高山へと一跨ぎに歩いた。その時の足跡があるので「だいらぼう」と名付けられた。木枯らしの森と下流の舟山はその時もっこからこぼれ落ちてできたものだという。中藁科小学校郷土研究クラブ。
~~~
山中と小布杉との分岐点のある境橋まで戻る。ちょうど藤枝市:志太郡と静岡市:安倍郡の境界線で境橋となっている。境橋から上流を目指す。朝比奈川の左岸:東側の道を上っていく。道のある川東側が静岡市で川西側が藤枝市である。川が境界線である。
境橋から300m上っていくと右に石塔がある。
○石塔類(静岡市小布杉1591⁻3)
・庚申塔、・庚申:安永三、・観音、
また300m上っていくと左に祠がある。
○祠:地蔵(静岡市小布杉1661) 、
さらに200~25m上っていくと右に石仏がある。
○地蔵(静岡市小布杉1697)
また400~450m上っていくと、静岡市立中藁科小学校小布杉分校がある。その手前に堂や祠がある。
○堂:弘法大師、祠:六地蔵、観音4(静岡市小布杉1756) 、
・堂:弘法大師、祠:六地蔵、観音4:當國三十三所供養塔、・奉納當國三拾三所供養塔:文化五辰十月吉日、・秩父三十四番観世音菩薩、・手洗石、
分校裏手右(南)の斜面中腹にに平戸神社があるが、地元の人に行き方を聞かないと分からない。県道沿いの茶畑からも行けるようだが標識がないので分からない。
○平戸神社(静岡市小布杉1062)
・本殿拝殿、・石垣、・金属鳥居、
分校から700m奥に詰めるとY字路に至る。右は富沢方面で左は三ツ野(三ヶ野)である。ここに石塔類がある。
○石塔類(静岡市小布杉1185)
・丸石、・西國三拾三所、・善光寺供養塔:明治、・庚申塔:明治四十一年、・庚申塔:レリーフ:文化九壬申年:1812、・庚申塔:昭和五十五年、・金属献燈:平成六年、・石塔、・當國三十三所、
○石道標(静岡市小布杉1697)
・石道標:御大典紀念 朝比奈街道 南岡部町方面 右富沢相俣川根方面 左三野ヲ経テ舟ヶ久保?
左の三野へ1.3㎞進む。右に神社がある。
○白髭神社(静岡市小布杉、三野300)
・木鳥居、・手洗石、・石段、・献燈2:昭和十年、・大木1、・大岩多数:神社裏:まるで磐座のようだ、
250m奥に進む。右に寺院がある。
○梅林寺バイリンジ(静岡市小布杉、三野319)
・観音、・西國、・西國三拾三所供養塔:天保二、・観音、・西國供養塔、・當國三拾三所供養塔、・善光寺如来:文化、・奉納西國三十三所供養塔、・「善光寺」(観音)文政元、・善光寺如来當國三十三所:文久元酉、・庚申塔:昭和五十五年、
これより奥に詰めると道がなくなるが、30年ほど前、この奥から歩いて大鈴山の南尾根の林道に出て大鈴山に上ったことがある。さらにそこから清笹峠へ歩いて抜けられた。その先の笹間峠までも歩けた。ちょうど前記の石道標のように清笹峠を経れば舟ヶ久保や笹間へ出られたはずだ。
・発電所貯水槽跡:
~~~
さて三野と富沢方面への分岐点のY字路まで戻る。今度は右の富沢方面道を進む。600m進むと小布杉最後の人家前(小布杉1303₋2:森氏宅)を通過する。更に250m進むと富沢へは右の道となり左は行き止まり林道になる。この左の行き止まり林道は後で紹介する。右の富沢方面へ進む。この道は林道富沢小布杉線となっている。行き止まり林道側が県道相俣岡部線である。1㎞進むと峠に到達する。ここに祠がある。
○祠:地蔵類(静岡市小布杉)
・祠:峠の地蔵尊:大正九、・祠:交通観音、・猪獣類諸霊位塔、・開通記念碑2:昭和六十一年、大久保山横峰林道:平成三年、
○峠:小布杉と相俣の間:未開通県道、一本杉、石仏2(静岡市小布杉)
この峠から北東への尾根を歩いて300m、標高差30mで富沢の頭に至る山頂から真西に標高差50m、距離250m歩くと、小布杉と相俣の間の峠に至る。
一般的には未開通県道と云われる。というのも昔は人が歩く道でも県道として認定されていたが、その後自動車道として整備されず、別ルートで自動車道が開通し、峠付近は廃道になってしまったからである。
小布杉側からの古道は推定されるに、先ほどの人家の(小布杉1303₋2:森氏宅)前から沢沿いに茶畑を詰め、植林地を上り、先ほどの行き止まり林道に出て、林道横の雑草だらけの崖をよじ登っていくことになるようだが、すでに20年前にも道跡は分からない。20年前には行き止まり林道を600mほど詰めて、右の林道の2mほどの雑草だらけの崖に取り付いて上ると、山道歩道の古道に出られた。急斜面の切通しの山道を100mも上ると、平坦なこの峠に出られるはずだったが、今は行き止まり林道自体が舗装されていてもぐちゃぐちゃの廃道で何が何だか分からない。また反対側の相俣側の行き止まり林道は舗装されていても廃道化している。それでも舗装路を進むと、舗装が切れて土道になる所が橋であり、この橋を渡って左の沢沿いの右に山道がかつてはついていたが、4月末にはうっそうと雑草が茂り行く手を阻んでいた。探索するなら冬場でしょう。かつても冬に上ったはずだ。ただ沢沿いに上りだし、しばらくして沢を左に渡るはずなのだが、これも標識なく迷い迷いだったはずで、20年以上経った今となっては、もっと悲惨だろうと思う。それでもこの峠道を紹介するのは、この山道が朝比奈街道の周辺部を含めて、数少ない古道残存部と考えられるからである。今となっては朝比奈街道中、わずかに残った貴重な古道である。もはや朝比奈街道の古道が全滅寸前な中で文化財級である。
この峠にはい石仏等がある。
・地蔵2:・朝比奈□□□三元恵十土 安永二□午八月日 村□□□□□□、・明治四十三年七月大森昇一連之
30年前、20年前ともにこの峠の地蔵は小さいものが1体だけだったはずで、2体あるということは、それ以後増えたということである。今回周辺入口は廃道だが、この峠を見る限り5年前あるいは10年前には近くの小布杉分校の遠足コースだったようで、壊れかけた手作り標識が設置されていた。
峠の東に不気味な枝ぶりの巨木が目についた。
・一本杉:地蔵の25m東、
付近の壊れた標識からすると「一本杉」というようだ。
なお一本杉のさらに東30m地点に切通しがあり、峠のようだ。
☆朝比奈街道沿いの古道について
朝比奈街道の古道残存部はメインルートではすでに消滅しているが、枝道の支線部分で残存している。といってもわずかばかりである。それは以下である。
1 羽佐間の古道:伏見氏宅前のわずか数メートルだけであるが、朝比奈川まで下れる道を整備し直すと玉露の里までつながるというのがよさそうだ。
2 清養寺から小園地蔵の閒:一応メインルートすぐ横から出ていて西又や野田沢、小園の分岐点の地蔵に出られて歴史を彷彿とさせる。保存価値が高い。
3 弓折峠の道:西又と玉取沢を結んでいる。
4 小布杉と相俣の峠道:未開通県道、小布杉側と相俣側どちらの林道の取付点も廃道同然で入りにくい。草刈と標識設置が望まれる。地蔵2体と一本杉が峠らしさを醸し出す。
5 古道:桂島の観音下から葉梨の北方への山道。
国土地理院地形図では点線記入されているが現在あるかどうかは未確認。北方と桂島境の峠手前500mは一部農道ルートのようだ。
6 ビク石登山道:古道:笹川から笹川十八石を経てビク石山頂へ、そしてビク石から瀬戸の谷へ下れるルートである。現在はハイキングコースとして利用されている。一部は古道のままではなく道が付け替えられているようだが、およそ古道が現在でも利用されて保存されている好例であり、最も古道が残っている部分である。
朝比奈街道中最も利用され今後も保存されるだろう最高に保存度の高い古道である。
7 古道:小園の神社横農道から玉取沢への道:両方とも取付きは農道で人家がある。途中から鎌道のようだが、現在でもしっかりあるかどうかは未確認。
現在はもっと西の朝比奈川本流沿いの近又、谷倉に県道が通過しているが、昔は本流沿いに道を作りにくく、東の小園と玉取沢を結ぶ峠越え道を主要街道にして利用したのだろう。
8 古道そのものは拡幅されてないが、焼津市越後島から藤枝市下当間、横内、仮宿周辺にはまだ古道の趣を残す風情が残っている。
もはや以上の部分ぐらいしか朝比奈街道のメインルートではないにしても支線の古道が残存していない。消滅は時間の問題だろう。
古道沿いの石塔類に関しては豊富である。各集落が積極的に合祀して残してきたのだろう。素晴らしいほど豊富な馬頭観音、庚申塔、馬蹄石、丸石、常夜燈、地蔵が残されている。ただし刻字に関しては読めないものが多くなっている。どんどん劣化していると言える。これでは石が早々にボロボロになりそうだ。おそらく酸性雨、急激な降水量、PM2.5、異常高温な真夏日の多さといった人為的で急激な気候変動が石塔を痛めつけるのだろう。
・あとがき
朝比奈川沿いに石仏が多いことは30年前から通りかかるたびに思っていた。20年ほど前、佐野敏郎氏の本「古道の石仏」を見て、いつか朝比奈川沿いの石仏をこのようにまとめたいという思いを抱いたことが、今回曲がりなりにも実現できてほっとした。しかし石仏の刻字はかなり読めなくなっていて、もっと早くやるべきだったという後悔もある。
朝比奈川沿いは石仏と古道でもっと観光化できるだろう。
○付録
・参拝の仕方
神社に貼られていた「参拝の仕方」を紹介する。
本当は地域性などで統一された方法や回数はないはずだが、昨今有名神社のやり方が全国的にマニュアルとして幅を利かせているようだ。どうもそのやり方のようだ。
参拝の仕方:
1 拝殿の前に立ち、最初に軽く会釈をする。
2 賽銭を奉納し、鈴を鳴らす。
3 祭神に向かい2回深く拝礼をする。(二礼)
4 次に両手の指先を合わせる。続いて右指先を少しずらして2回拍手をする。(二拍手)
右指先を元に戻し、左右の手のひらを合わせて祈願する。
5 祈願が済んだら両手を下げ、深く拝礼する。(一礼)
最後に軽く会釈をして下がる。
*この拝礼は一般的なもので、神社により異なる場合がある。出雲大社は4拍手だそうだ。
・六地蔵:wikipediaより
地蔵菩薩を6体祀ったもので、仏教の六道輪廻の思想から来る。全ての命は六種の世界に生まれ変わりを繰り返すというものである。
1 地獄道:檀陀地蔵(金剛願地蔵)、
2 餓鬼道:宝珠地蔵(金剛宝地蔵)、
3 畜生道:宝印地蔵(金剛悲地蔵)、
4 修羅道:持地地蔵(金剛幢地蔵)、
5 人道:除蓋障地蔵(放光王地蔵)、
6 天道:日光地蔵(預天賀地蔵)
の順になるが、名称は一定しない。持物と呼称も統一されていない。
・参考文献
・「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ‘96、
・「ゼンリン住宅地図」
・「2万5千分の1地形図」国土地理院、昭和50~平成10年代
・「2万分の1地形図」陸地測量部、明治20年代
・「静岡県 県別マップル道路地図」昭文社、’00
・「東海道 静岡県歴史の道」静岡県教育委員会、平成6年
・「日本石仏事典 第二版」庚申懇話会編、昭和55年
・「静岡県の中世城館跡」静岡県教育委員会、昭和56年
現地調査:’16 4/23,24、29,30
・前文
本文を読み進める場合、手元に住宅地図等の地図を確認しつつ読むと分かりやすい。住宅地図がなくともグーグルやヤフーのマップ、昭文社の道路地図等でもよいと思う。
*住所地は分からない時には附近のものを記入している。正確な住所を記入することが目的ではなく、目的の場所を少しでも発見しやすくするための目安である。
個人的には文字間違いが多いかと思う。というのは丸2日がかりで打ち込んだ文章がすべて消失したので、一から打ち直していてウンザリしている。しかもすでに川崎街道は調べたのにほとんど打ち込めずに自分の記憶の方が消失しそうで早く朝比奈街道を打ち終えて、川崎街道も打ち込まねばとあせっている。ますます間違いだらけで、さらにいらいらしてくる。一旦消失した文書でも履歴とやらを探ると復活できるらしいが、パソコン苦手な私にそんな技量はない。パソコンや最新機器は嫌いです。
一応、現地で発見したもの(道、遺物類)を掲載しましたが、発見できないものも多かったと思いますので、御存じの方はぜひコメントを頂きたいです。あるいはその方なりの方法で公表していただけるとありがたいです。朝比奈街道だけではありませんが、古道や古道沿いの遺物類は片っ端から消失の危機にあると言えるでしょうから、公表されることで少しでも保存されることを願っています。
・朝比奈街道概略
朝比奈街道は『定本 静岡県の街道』によれば「焼津北を起点として、瀬戸川を渡って八楠、越後島を経て下当間に至り、広幡橋を渡って東海道と交差し、さらに仮宿村のはずれで朝比奈川の右(?左)岸に渡り、子持坂から桂島を経て宮島に至っていた。」
起点であるが、焼津北でははっきりしないが、おおむね朝比奈川は下流で瀬戸川と合流し瀬戸川として駿河湾に達し、その横に焼津港が開けている。そこで起点は焼津港とした。
~焼津市焼津漁港~
○焼津漁業協同組合焼津漁業資料館(焼津市中港二丁目6⁻13)
○宗像神社(中港五丁目18⁻16)
・コンクリ鳥居、・板碑:社碑:昭和四十七年、・手洗石:自然石かち割、
・説明版:創建不詳。昔人伝うにこの地毎年暴風雨来れ激浪打ち寄せ民家流失人命にも及ぶこと甚大なりしが或る日村民その海辺に流れ着きたる弁財天の御姿を見付けこれこそ安芸の国宗像神社の御授けと尊崇村民と計らい祭神を祀りし社殿を創建し祀りたるに霊験あらたかにして爾来波浪静まり豊漁豊作民心安泰この地今日の繁栄を期す故なり。明治三年神仏分離のため弁財天を宗像神社と改む。昭和39年焼津港築港の砌当地に移転崇敬篤き氏子の敬信により新たに社殿造営今日に至る。昭和47年
○船玉浦神社(本町一丁目16⁻1)ふなだまさん
・説明版:祭神:大錦津見命、祭礼日:7月26日、由緒:江戸時代、和歌山県、音無川上流にある船霊神社から分祀されたという。創立年月日不詳。旧焼津港の南端、明神鼻の一角にあるところから焼津港の鎮守神として「ふなだまさん」の愛称で漁民の信仰を集めてきた。例祭日には宮司が御幣を立てた小舟に乗り赤飯を盛った神餞を港外で海中に納め、海上安全、大漁を祈る古例がある。(静岡県神社庁志太支部編「志太地区神社誌」)
・社碑:昭和六十一年、・石鳥居:大正十五年、・手洗石2:大正十五年、明治廿六年、・新:猿田彦、
・石碑:焼津市古い地名:新屋:あらや旧町名 樋越 上町 中町 北町 南町 下町 新町 浜町
○青木神社(本町一丁目3⁻28)
・社碑:昭和十二年、・石鳥居:平成二年、・献燈、・新:手洗石、・自然石5、・コンクリ鹿像:昭和四年、・大木6~7本、
隣の幼稚園に・新:地蔵、
○紫雲山阿弥陀寺(本町二丁目4⁻5)
・寺名碑:平成二十四年、・六地蔵、・供養塔、・手洗石、
~その他、焼津港周辺~
・焼津神社(焼津二丁目7⁻3)
焼津の中心的神社
・普門寺(焼津六丁目9⁻16)
・貞善院(焼津六丁目11⁻⒕)
・良栄寺(焼津六丁目2⁻16)
・小泉八雲の碑(新屋425)
・護信寺弁天宮(北浜通95₋2)
・浪除八雲地蔵尊(城之腰188)
・神社:祠(城之腰176)
・常照寺(城之腰138)
・安泰寺(鰯ヶ島143)
・青峰観音(鰯ヶ島253)
近くに・記念碑
・須賀神社(焼津五丁目2⁻2)
~焼津駅北口周辺~
○昌泉院(駅北五丁目10⁻9)
・六地蔵:昭和四十七年、・無縁仏:コンクリ固め:昭和三十五年、・?供養塔、・観音、・慰霊碑、・燈籠、・狛犬、・水子地蔵、・観音、・奉納鳥大乗妙典経全部:元文五年、
・御所松(駅北五丁目10⁻9)
昌泉院横、瀬戸川河口付近の土手に赤松と黒松
○天皇神社(駅北五丁目1⁻25)
・新:社碑:、・新:玉垣、・石鳥居:昭和四十四年、・新:狛犬2、・手洗石:自然石、・自然石、・献燈2:昭和四十四年、・石碑:奉納浄水石中老会、
○大井神社(駅北二丁目5⁻13)
・社碑:昭和四十八年、・石鳥居:昭和八年、・献燈2、・狛犬2:昭和三十三年、・慰霊碑、・新:玉垣:昭和五十三年、・コンクリ石柱2、・クス、シラカシ:焼津市指定保存樹木、
・石碑:焼津市:旧地名碑:焼津北:川東 駅前小石川東 川南 駅前小石川南 舞台 西町附近 昭和55年
・説明:祭神:彌都波売命:水を司る神、猿田彦命:道の守り神、創立永禄三年、明治八年村社、明治四十年神饌幣帛供進指定社となり今日に至る。佐口社:通称:おしゃもんさん白髭神社稲荷神社を併合奉斎。永禄三年は領主今川義元が桶狭間で織田信長と戦った年で戦国末期であり、当時の虐げられた貧困の祖先たちが五穀豊穣や平和を祈ったのだろう。現在の社殿は明治41年、本殿が改築拝殿が新築された。それまでは小祠堂であっただろう。本殿拝殿は焼津市区画整理事業駅南北工区工事の際、昭和48年位置が若干移動するに当たり、更に改築が施され49年には社務所兼公会堂が落成し玉垣は53年新設された。区民有志により竣工。昭和53年。
・若宮神社(大89)
・七社神社(大村一丁目7⁻1)
・善通寺(大村一丁目19⁻4)
・用心院(大村新田317)
焼津港から瀬戸川と焼津駅の間を遡上し焼津駅北口付近に出る。駅北の大井神社付近から北西に進み県道焼津停車場仮宿線に出て、瀬戸川に架かる牛田橋を渡る。その手前に神社がある。
・神社:祠(大栄町三丁目3)
牛田橋を渡ってすぐ右折し細い道に入り、梅田川に架かる天白橋を渡り、朝比奈川土手手前で土手沿いに遡上する。すぐに国道150号線バイパスの高架下ガードをくぐり八楠の新興住宅街を遡上する。この周辺は都市計画で区画整理され、昔日の面影は消失しているが、とにもかくにも土手の1~2本手前の道を土手に沿い進むのが古道ルートに近いようだ。バイパス高架下ガードから650mで右側100m先の土手手前に寺院がある。
○正傳院(八楠460)
・六地蔵、・(梵字)庚申塚青面金剛像:平成五年:見聞言ザルレリーフ、・如来、・地蔵、・新:地蔵、・新:日切地蔵、・五輪塔、
元の道に戻り北西進するが、一旦もう一本左の道に移り北西進する。距離300mで神社である。
○加茂神社()
説明:祭神:賀茂別雷命カモワケイカヅチノミコト、例祭:10月17日ただし昭和53年以降第3日曜、創建:大化二丙午年二月646、由緒:646年2月山城国上賀茂神社より勧請したと記せる棟札あり。「総国風土記」に「箭葛柳田神社所祭祭神雙栗神也」とあり。また「諸郡神階帳」に「益津郡従五位上八楠地祇」とある。往古は賀茂神社の祭礼には神輿数台を字天白という所に行幸し神楽を奏し、字馬場田という所にて流鏑馬を行った。「賀茂神社」は山城国上賀茂神社:京都市から神の霊別雷命を祀る。上賀茂神社の例祭は賀茂祭:葵祭が有名。旧除地高:2石。明治8年1875,2月村社に列し、明治40年1907,9月神饌幣帛料供養社に列した。境内神社:末社:八坂神社:すさのおのみこと、白髭神社:さるだひこのみこと、天満社:すがわらみちざねこう、天白社:不詳、八幡神社:ほんだわけのみこと、蔵王社:不詳、佐口社:不詳、祭事:2月祈年祭、10月例大祭、11月新穀感謝祭:七五三お祝い、
・社碑:平成五年、・石鳥居:昭和十年、・献燈2:昭和五十六年、・手洗石:自然石加工、・狛犬2:昭和56年、・手洗石:草書体?江戸期、手洗石:20×40㎝:天保十、・献燈+燈の竿:文化□、奉献燈加茂大明神□□、・石塔2:明治廿八年、・大木7~10、
北西進ですぐ東名高速高架下ガードをくぐる。ガードから300mで右50mに寺院がある。
○瑞應寺(越後島114)
・寺名碑:平成四年、・手洗石:、・地蔵、・祠:青面金剛、・新:地蔵、・祠:神、・祠:地蔵、・ソテツ、・秋葉山常夜燈:文化二年、
元の道に戻り50m進む。左に越後島公会堂があり、赤鳥居が見える。
○神社(越後島183)
・木赤鳥居2、・赤祠2、・献燈:平成十二年、
この周辺は水田や畑が残り、道もやや狭く、直線ではなく昔風の曲がった道であり、古道とまではいかなくとも田舎びた旧道の雰囲気が残っている。しかし手前の八楠までは開発されていて、越後島の開発も時間の問題であろう。訪ねるなら今がラストチャンスでしょう。
200m北西進する。左折:南西進し200mで鳥居がある。途中宮前橋を渡る。
○八坂神社(焼津市越後島289)
・説明:旧駿河国益頭庄越後島村、祭神:建速須佐之男大神、由緒:往古この地の守護神、産土大神として嘉吉元年1441、御花園天皇の御代、室町中期足利義勝の頃、愛知県津島市に鎮座の旧国幣小社津島神社より分霊を勧請して創立された。本宮社と同じく元牛頭天王社ともいわれた。明治以前徳川時代までは除地高2石を有し明治8年2月には村社に列せられた。祭神は天照大御神の弟で国土経営産業開発の大神としてまた神徳は災難疫病除けの守り神招福大神と古来より篤く信仰された。境内には末社として山梨神社、八王子社、西宮社、御嶽権現社、天白神社の5社を祀る。本殿拝殿前後には樹齢500年余りの5本の大老松がそびえていたが、昭和41年大暴風雨で倒木し他も危険となり伐採した。目通り8尺。現在は2代目植樹。本殿は天和3年1683再建、外本殿は昭和47年10月再建。拝殿は昭和8年石玉垣は昭和33年、造営。境内地1035㎡。明治維新に上地され国有地化されたが昭和31年神社に譲渡。例祭は本宮津島神社では6月25日を津島祭天王祭としてあまねく世に知られているが当神社では戦前より秋農耕の収穫前近隣神社の祭礼と同じく10月16日。昭和49年。
・石鳥居:昭和四十六年、・玉垣:昭和33年、・手洗石:自然石加工、・手洗石:横倒し、石柱5:横倒し、・献燈2:平成二十二年、・大木2、・御神燈2:文化七、・狛犬2:昭和八年、
元来た道に戻り、250m北西進する。標識もないので分からないが、ここで藤枝市下当間に入る。市境から450m進むと右に下当間公園さらに奥に寺院と神社が見える。
○孝養院(藤枝市下当間542)
・寺名碑:昭和四十八年、・祠:地蔵、如来、石祠(石家道祖神)、小地蔵6、・庚申供養塔、・庚申供養塔、・自然石3~6、
○橘神社(藤枝市下当間537)
・説明:由来:天正年中1573~1592、当地の仕人五左衛門という人が奉斎したという。以来当地の守り神として現在に至っている。祭神:弟橘姫命、焼津神社(祭神:日本武尊)と由縁がある。神領除地高1石8斗9升8合を有し、明治8年2月村社列せられた。昭和28年7月8日国有境内地は無償譲渡され宗教法人として承認登記された。
祭神:弟橘姫命:美濃の穂積氏忍山宿禰の娘、日本武尊の妃となり東国平定に従ったが、走水より上総に向かう海上で暴風雨に遇い、妃の弟橘姫命は犠牲となって海神に身を捧げて尊の難を救った。尊は深く悲しみ、現在の千葉県茂原市木納町舟形山に御陵を造り弟橘姫命の櫛を納めて橘の樹2本を植えて祀ったという。
境内社:稲荷神社 倉稲魂命 稲作の守護神、御嶽神社 御鍬 農家の守護神、津島神社 素戔嗚尊 魔除け守護神、
・石鳥居:平成二十一年、・狛犬2:2012年、献燈2、・板碑、・手洗石、2:古、新:昭和五十年、・大木6~10、・神木1、
橘神社前から450m西進する。新しい石道標が電柱に立てかけられている。
・新:石道標:「しあわせ小路→」(下当間438)
50m西進すると高架下ガードをくぐり、さらに200m進むと県道焼津停車場仮宿線に出る。古道ルートは県道を横断し、県道の広幡橋の先にある狭い歩道橋で葉梨川を渡ることになる。
ただ渡る前に下当間付近の石造物を紹介する。歩道橋より先の土手沿いに寺院がある。
○観音寺(下当間1099)
・寺名碑:駿河観音霊場九番札所:昭和六十年、・六地蔵、・ソテツ、・手洗石、・地蔵:座、・地蔵:立、・奉納西國坂東秩父供養塔、・奉納大乗妙典経廻國六十六部供養天下太平國土安清:元文元、・祠:新:水子地蔵、・供養塔、・五輪塔の頭部、・三界萬霊塔:昭和四十三年、
寺の先が広幡小学校と広幡幼稚園であり、その先に石造物がある。
○忠霊塔:昭和二十八年(下当間392)
・献燈4、・狛犬2、・板碑:戦後記念碑、
忠霊塔より北東150mに小さな神社がある。
○金山神社(下当間175)
・金属鳥居、・庚申供養塔、・祠:神、・手洗石:昭和三年、
広幡橋隣の歩道橋で葉梨川を渡る。50m直進するとT字路に当る。この左右の道が江戸期東海道である。右折(北)するとすぐに法ノ橋を渡る。100m進むと現在の国道1号線との仮宿交差点に出る。東海道は交差点を斜めに横切っている。松があり、他より狭い道なので分かりやすい。
・標識:岩村藩領標示杭「是従東巖村領横内」(横内1651)
・説明:この杭は江戸時代、享保20年1735より明治維新までの135年閒岩村藩領であったことを標示した杭を再現した。岩村藩は美濃国岩村城(岐阜県恵那郡岩村町、現在岩村市)を居城とし、松平能登守が3万石の領地を持っていた。駿河国に15ヶ村、5千石分の所領地があり、横内村に陣屋(地方役所)を置いて治政を行った。
200m進むと左折(北西)である。ここに石道標がある。朝比奈街道は東海道を離れる。
・石道標:仮宿區入口 岡部町 朝比奈村 葉梨村ヘ通ズ 大正六年(横内996)
裏面は壁際固定されていて読めない。多分発起人名かと思う。
300m進むと標識がある。
・標識:小字名「評定ひょうじょう」(横内1075)
200m進む。標識がある。途中バイパス高架下ガードをくぐる。
・標識:明治の学校跡地→(横内1091)
250m進むと標識がある。
・標識:朝日山城跡→(仮宿1228⁻1)
標識から西1.2㎞先の朝日山山頂112mに稲荷神社があり、そこが中心である。
~~~~~~
一旦、朝日山城を目指し朝比奈街道ルートを外れる。
○朝日山城跡(仮宿)市指定史跡、朝日稲荷神社
西1.2㎞先の潮山200m前衛峰の山頂112m:稲荷神社を中心として築かれた岡部氏の山城。居館は神社手前の静岡大学農場のさらに手前辺りと推定されている。附近に祠や五輪塔があるようだ。城は山頂を本城に上下二段の曲輪があり、稲荷神社は下段である。たて堀、堤坪曲輪、西曲輪等がみられる。潮山とは空堀で分断されている。麓に居館があり背後に山城があるという室町初期の根古屋式の山城といわれる。室町初期に築かれ天正16年1588所領替えで廃城となった。城の弱点は西南に城より高い潮山がそびえていることだが、より高い山に城を築くことは技術力、財力、政治的情勢、必要性から考えた方がよく、廃城になったのも所領替えで、必要性が低かったのだろう。
・朝日山城:説明版:(構造及び形式等の特徴)曲輪・空堀等の遺構をよく残した山城で、その規模はおよそ東西600m、南北200mに及ぶものである。(説明事項)朝日山城は潮山(標高202m)の支峰、朝日山(別称・牛伏山、標高110m、比高約90m)頂上部を中心に造築された山城である。この山裾は、土豪として活躍したとされる、岡部氏の本拠地と伝えられることから、本城は室町時代の初め頃、この岡部氏が築いたものといわれている。このように山頂に築城し、その山麓に城主の居館地を伴う場合の城を根古屋式(詰城)と称し中世城郭の典型となっている。城は山頂の神社境内に船形で土塁によって囲まれた一ノ曲輪を中心として、ここから東に向けて階段状に曲輪を配置する。その他空堀、堀切や南曲輪・西曲輪・山下曲輪・水の手等によって構成されている。
・説明版:藤枝市仮宿1番地に所在する、岡部氏により造られた城である。この頃の岡部氏は今川氏の庇護の下、自領地を護るためのものであった。朝日山城は朝比奈川を望む海抜110mの朝日山(牛伏山)にある、山頂には室町時代初期の頃の様式の城郭遺構が残る、この城は東方山麓に居館を構えた根古屋式の城である。根古屋とは、丘陵上等に設けられた城と、その裾に屋敷が付随する城に対して付けられた名称である。朝日山城跡は一の曲輪、二の曲輪と構成されているようですが、現在この城跡は発掘調査などされていません。城跡に残る形跡は室町時代初期のものばかりではなく、一部は同時代末期の天文~永禄年間(1532~69)の頃、城郭拡張の必要(戦争)が生じたために、工事を起こしたが、完成まで至らず必要性がなくなり、途中で放棄されている。今川氏に関係する城の多くは未完成のまま残され、このうち重要な位置(海岸、街道、峠、国境)を占めるものは後に武田、徳川両氏の手により修復されている。
・絵図「朝日山城とその周辺(推定)」:(絵図に記入された文字を書き写す):潮山、村良、入野、観音前、牛伏山、朝日山城、(本丸)一ノ曲輪、二ノ曲輪、三ノ曲輪、南曲輪、竪堀、大手口、子持坂、山崎、砦居館推定地、一丁田、押場、仮宿、朝比奈川、八幡山、谷田遺跡、谷田、潮城、城山、一里山、一里塚、
「朝日山城跡の曲輪(推定)」:朝日山城は一ノ曲輪~三ノ曲輪を中心部分とします。「一ノ曲輪」;神社の裏側部分、東西57m、南北31mほどの舟形で土塁が廻る。「二ノ曲輪」;神社のある平坦地(方形)東西25m、南北31mほど。「三ノ曲輪」;二ノ曲輪の東側に階段状に下る細長い平坦部分。
「仮宿朝日山眺望」:この絵は江戸時代の終わりごろ、この朝日山からの眺望を描いたものです。文化11年(1814)紀行「山西勝地真景」より桑原藤泰。
朝日山城跡(推定)一ノ曲輪、二ノ曲輪、三の曲輪、西曲輪、空堀、通路、南曲輪、竪堀、大手口、木戸口、現在地、花倉、潮山、
・空堀跡(竪堀):説明版:この堀は、朝日山城の中で最も規模が大きく長いもの(全長110m)です。山の斜面を通って敵が侵入するのを妨げるためのものですが、このように山の斜面に沿って竪に掘った堀を竪堀といいます。
堀の種類、
堀-水堀―例・田中城(二の堀等)、駿府城等
-空堀―(空堀、竪堀、堀切) 例・朝日山城、花倉城、諏訪原城等
・空堀跡(竪堀):説明版:この附近が、堀のほぼ中央部分になります。この部分の堀幅は約20m、深さ約5mもあり非常に規模の大きな空堀といえます。
・空堀跡(竪堀):説明版:この谷の部分が人工的に掘られた空堀跡です。堀の幅はこの附近で上端が約18m(下端が約13m)深さも4mほどになります。
・一ノ曲輪:説明版:規模・東西長軸方向57m、南北短軸方向31m、形態・平面形は舟形で南側から西側の縁に沿って土塁をめぐらしています。
・板石碑:説明:朝日稲荷神社社誌、鎮座地;藤枝市仮宿字堤の坪一番地、御祭神;倉稲魂命、開創;宝永五年(1677)岡山県津山より御分霊wp勧請の伝言ありまた天野景理助右衛門名主の時、芝田金三郎催主となり創建の説あり、境内社;天満天神神社、松尾神社、権現神社、津島神社、軍人社、例祭;三月初午祭、十月五社神祭、五年毎御輿下山渡御祭、新改築関連事項;延享四年1747本社再建、寛政六年1794御輿建造、天保九年1838拝殿再建、明治八年1875村社に列する、明治十年1877本社再建、明治十九年1886御輿更新、明治四十年1908五社合祀、昭和十一年1936拝殿再建、昭和五十五年1980市史跡指定、平成三年1991本社再建、平成二十二年2010拝殿修復、平成二十九年2017五社鞘殿再建、平成三年建立、
・説明版:朝日稲荷神社:鎮座地;藤枝市仮宿一番地、朝日山城跡に鎮座 稲荷山という、本宮;伏見稲荷大社 京都市伏見、主祭神;宇迦之御魂神、宇迦とは食べ物を意味し日本人の主食である米の生育を守る神である、イナリとは稲成、稲生がなまったもので、やはり稲が立派に実るさまをいい、これが即ち稲荷という字があてられたという。赤鳥居と狐はお稲荷様の独特の風景である。赤い色は豊かさを象徴する色とされ鳥居は通るという言葉に似ているところから願い事が通るという意味があるようだ。また狐はお稲荷の使いといわれる。御祭典;毎年三月初めの土曜又は日曜、大祭典;五年目毎、大祭として神輿の下山出御神幸波御祭り、平成二十三年
・板碑、・神燈2:大正十三年、・石祠、・納札所、・石祠、・神木、・小鳥居と石祠、
・丁石:四丁目、・朝日山ビオトープ ホタルの郷、・名号碑:平成三年、・木赤鳥居2、
・献燈2:昭和四十年、・手洗石、・手洗石:大正三年、・石柱2、・稲荷2:昭和十一年、
・石柱2:昭和六十三年、平成三年、・手洗石:安政五年、・神燈2:享保十四年、
・木祠5、・宝篋印塔の頭部、・手洗石:寛政元酉年、・祠、
○南叟寺(潮995)
・寺名碑:昭和六十年、・石塔:寛…堂、・南叟延命地蔵尊、・六地蔵+1:昭和三戌、
・西国三十三所供養塔:□政□、・地蔵、・手洗石、・善光寺如来供養塔:明治十六年、
・三界萬靈塔:平成五年、・馬頭観音、
・奉納 當国三十三所善光寺如来西国三十三所 各供養塔:明治四十五年、
・□善光寺如来供養塔:大正六年、
・地蔵:祠(潮462-1)
南叟寺のある潮集落から新東名取り付け道路に出る辺りの法の川手前の微高地の丘上畑に祠と地蔵が見える。
○潮神明宮(潮407-7)
・社名碑:昭和五十五年、・金属鳥居、・御神燈2、御神燈2:明治十三年、・石段
・忠魂碑、・石祠、・木祠、・石垣、
○薬師堂(潮304-3)
・西国三十三所巡禮供養塔:寛政九年、・宝篋印塔の頭部、
隣家の潮240-1山田氏の話では、堂の名前は薬師堂、施主は現在9代目で、其の数代前の6代目辺りの与作が祀った。潮集落は昔15~6軒で潮井戸が4つあったそうだ。
’17 10/9
~~~~~~
標識:朝日山城跡→(仮宿1228⁻1)へ戻り、北へ70m進む。道が左に曲がる所に祠がある。
・祠:中組秋葉山(仮宿1189)
北西へ70mで右に寺院がある。
○用福寺(仮宿1172)
・説明:室町期引治3年1557、当時の和尚に依り開創。開山和尚は学識力量共に卓越セル禅僧で仮宿に当寺を開創後、永禄10年1567懇請され、焼津市一色の成道寺開山、永禄12年1569榛原坂部、石雲院の輪番住職を受け輪住される。永禄12年11月示寂。開山当時は駿河国今川氏勢力下にあり、1564年今川義元、桶狭間で戦死。その子氏真が家督を継ぎ、永禄8年1565常楽院を今川氏の祈願者として帰崇される。1569松平家康は今川氏の領地遠州を攻略、掛川城を明け渡される。本尊:地蔵菩薩は日限地蔵として地域の信仰を集めている。昭和59年本堂屋根を修理、昭和62年庫裏新築、平成2年位牌堂新築、平成6年境内地整備、東司建築、文殊菩薩台座新調安置。平成6年。
・寺名碑:昭和六十二年、・祠:文殊菩薩の厨子:寛政4年木製彫刻された像で明治13年再度彩色された、平成に修理された、平成6年、・手洗石:平成七年、・三界萬霊等、・新:地蔵、・自然石、・六地蔵+観音、・石碑:無心:五輪塔の頭部、・○奉供養庚申塔:人差し指を伸ばした手の甲のようで斬新な石、・奉供養西國三十三所、
550m進むと旧岡部町との境だった朝比奈川に架かる仮宿橋に至る。橋手前左30mに祠がある。
・祠:秋葉山、・秋葉山常夜燈2:平成14年(仮宿1084)
さらにこの土手沿いに西300m進むと寺院がある。
~~~~~~
・中正寺(仮宿938)
・大師堂:祠:石像、新四国第三十番慈眼山中正寺
・名号碑2:昭和六十年、 ・手洗石:新、 ・常夜燈2:新、・六地蔵:平成十三年、
・おかげさま石柱地蔵:平成八年、・祠、・常夜燈、・石塔:南無…(不明)、
この寺の南西に岡部氏関係の祠や墓石がある。
・岡部氏一族の墓:説明版:岡部氏の祖から何代かここに眠る、岡部氏の祖、藤原清綱は京より駿河の国に権守(ごんのかみ)として赴任してきた。任期が過ぎても京に帰らず、この地で帯刀してとどまる。清綱は南家出身なのでよい職に就く当てもないことが分かっていて、この地に住むことを決める。そこで権守の時、得たかもしれない伊勢内宮の御厨の職を、この地でやることになった。(岡部御厨) 平家が栄華を極めたとき、伊豆において源頼朝が挙兵したのが岡部氏がこの地にきたときであろう。清綱は頼朝の配下になり、清綱の子泰綱の時、藤原を改め岡部とし、鎌倉幕府において御家人となる。その後代々この地に住み、地域の人たちを巻き込み鎌倉幕府、今川氏と緊密な関係になった。此処の墓は鎌倉時代から、今川氏に加担した頃までのものと推察されます。したがって(1150~1530)の岡部氏の墓の檀下には万福寺の僧侶の墓もいくつか見られる。
・宝篋印塔:新:コンクリ製
・宝篋印塔:古:3、破片は多くもっと多数のものがかつてはあったのだろうが、体を成すものは3つである。
・手洗石 ’17 10/9
・仮宿白岩頭首工 ため池等整備事業 農林水産省補助(仮宿965)
説明版:ゴム引布製堰で貯水時はゴム内に空気を入れ、洪水時は空気を抜き水を流す仕組みである。
・地蔵:祠(高田993-1)
朝比奈川の土手沿いの上でちょうど土手道と高田集落への道へと分岐する辺りである。
○常楽院(高田424)
・寺名碑2:昭和四十二年、・祠、・六地蔵+観音、・新:地蔵、・永代供養塔、・新:常夜燈2、
・新:常夜燈、・新:石碑、・不許葷酒入山門:當山十一代、
・説明版:木喰上人作毘沙門天:クスノキ一木造り、一体、江戸時代、毘沙門天立像、高さ1.23m、市指定有形文化財・彫刻、「微笑仏」で知られる木喰仏のひとつで、甲冑を身に付け憤怒の相を表して邪鬼を踏みつけて立った姿の毘沙門天像である。もとは常楽院境内外の観音堂にあったが、現在は本堂に安置されている。像の背面には墨書があり、木喰が83歳で千体仏を発願した時の作で、寛政12年(1800)7月20日に完成したことが記されている。木喰仏特有の穏やかな微笑仏とはやや趣が異なり、像は厳しい表情を見せる毘沙門天であるが、木喰が最も仏像を多く作った円熟期の作品である。
木喰行道(1718~1810):享保3(1718)年に甲斐の国(山梨県)西八代郡丸畑に生まれ、宝暦12(1762)年、45歳の時常陸の国(茨城県)羅漢寺の木喰観海上人から「木喰戒」を受けた。その後日本全国を廻り千体の仏像を造ることを発願し90歳でこれを達成し、文化7(1810)年、93歳で没するまで全国各地で仏像を奉納した。寛政12(1800)年、西国を廻った帰りに藤枝・岡部・焼津の寺院に2か月間滞在し、13体の木喰仏を残した。
○高田神社(高田325-1)
・石鳥居:平成二十四年、・石段、・手洗石:昭和四十六年、・神燈の脚部と笠:明治十一年、
・神燈1、笠のみ1、・石祠、・祠、・自然石、
○観音堂、薬師堂(高田263)
・石塔:十七面観世音、・石段、・手洗石:大正十三年、・地蔵:古10、・金剛1、・獅子2、
・常夜燈3:萬延元年、・手洗石、
○日吉神社(藤枝市旧岡部町入野65-1)
・石鳥居:昭和四十一年、・石段、・杉大木、・石祠2、
・地蔵;祠(旧岡部町入野831-4)
朝比奈川に入野川が合流する手前の土手にある。
○西方寺(旧岡部町入野98)
~~~~~~
仮宿橋を渡ると前方に岡部宿の中心的神社がある。
○若宮八幡宮(岡部84⁻1)
・説明:祭神:仁徳天皇おおさざきのみこと、応神天皇ほんだわけのみこと、神功皇后おきながたらしひめのみこと、由緒:醍醐天皇、延喜8年908、8月13日駿河に下向せられて仮宿に居館を構えておられた堤中納言兼輔卿が勅に依り山城国石清水八幡宮より分霊をいただきここに祀るという、以来7郷(岡部、仮宿、内谷、横内、高田、村良、鬼島)の鎮護として里人の崇敬をえる。貞享3年1686堤中納言の子孫:岸和田城主岡部長敬によって本殿を造営された棟札があり現在に至る、明治8年郷社に列せられる、例祭:毎年9月第二土曜、日曜、
・説明:行事:神ころばし、七十五膳:3年の一度例祭の日曜に行う、市指定無形文化財:3年に一度の9月15日氏子若者(泰平衆)が白鉢巻き白下帯姿で、本殿脇の泰平所から朝比奈川を七度往復し水垢離を行い、七度半目に神輿を迎えて神事が始まる。神ころばしは泰平頭の指示で泰平衆が「お獅子の御膳」「御内膳」「お丁屋の御膳」を捧げ持ち、広場を練り歩き転びながら奉納する、次に直会用の「下敷したしき」「上敷うわしき」を同様にして納め、最後に青竹に吊るした「かめ(酒)」を奉納する。これと同時に供える「七十五膳」が伝供され、その後、神職と総代は拝殿に敷かれた下敷・上敷の上で直会を行い、この神事は終わる。
・説明:この駿河国、岡部の神社:若宮八幡宮は、山並みにも情緒があり古木もうっそうとして苔の緑もこまやかで岩の様子もたいそう神々しい。だから霞にたなびく春の一日、紅葉の美しい秋の一日は申すまでもなく、月の美しい夜、雪の降った朝など装束姿の神主さんたちがゆったりと風情を楽しむ所であったろう。このような素晴らしい所を前々から占ってお知りになっていたのであろう。我が遠い祖先、堤中納言兼輔卿は千木の形も素晴らしい立派な社殿を建てて、八幡大神を石清水より迎えて鎮めた。そもそも八幡大神とは中津彦の天皇(仲哀天皇)の皇子である品陀和気命(応神天皇)である。この方はすべてのことに賢明で慈しみの心も深いので、日本国は申すまでもなく遠く言葉の通わない韓国(新羅)までも、その威光に従ったという。八幡大神の威光は、なんとありがたい尊いことであろう。御神威は。天保15年文月(七月)正三位 維長つななが:堤中納言の子孫。
・石鳥居:明和六(昭和五十八)、雨乞い石、・玉垣、・石段、・献燈2:元文四、・手洗石、・献燈2、・献燈:寛文三、・献燈:破片いくつか、・板碑:正三位維長、大木巨木:いくつか、
橋を渡った道を左折し県道焼津森線を西に400m進む。右山斜面手前に寺院の入口があり、山道歩道が上っていく。
○萬松院(子持坂501)
・寺名碑:昭和四十六年、・自然石2、・石塔2:刻字不明、・石段、・地蔵:立、・地蔵:立:天保二子、・観音:駿河(刀3つ)志太郡山□□□村、・大日堂、・豊川茶枳尼真天覚、手洗石、・山門禁葷酒、・法界萬霊、・六地蔵+観音、・古:五輪塔:多数、・新:永代供養塔、・水子地蔵:小地蔵多数、献燈2、・新:地蔵:梅花観音80番駿河七薬師札所、
・岡部氏墓:宝篋印塔2、五輪塔1、土塀屋根瓦囲み、説明版:市指定文化財、土塀をめぐらした墓域の中に、宝篋印塔2基、五輪塔1基があり、宝篋印塔は岡部美濃守常慶ツネノリ(信綱)と出羽守(名不詳)の墓、五輪塔は常慶の子次郎右衛門正綱の墓と伝えられる。また門の扉は岡部氏の定紋である三つ巴の浮彫りが施される。岡部氏は代々今川氏に仕える有力な家臣であった。今川氏真の代に武田信玄が駿河に侵攻してきた。このとき岡部正綱は無勢ながらよく抗戦した。ついには多勢の信玄軍に敗れたが信玄はその勇猛ぶりをたたえて家臣に加えた。そして清水城(清水区本町)の守将に任じ賞金二千貫を与えたという。こののち正綱は武田軍に加わり、三方原に高天神城の攻防に徳川家康と戦闘を幾度か繰り返した。その武勇は家康の知る所となり、落城後、家康の計らいで死を免れ、家臣として招かれた。この恩情に感激した正綱、長盛父子は家康の手足となって働いた。
・富士見井戸2:説明:当寺の5代目和尚は慶長19年1614は大日如来を鋳造し、富士山頂に安置するため旅立った。寺に残った小僧は無事を案じながら井戸の水を汲もうとしたところ、仏像を背負って富士山を登っている和尚の姿が映ったため、思わず井戸に向かって手を合わせ、和尚の安全を祈った。以後この井戸を富士見の井戸という。平成17年。
寺西口は農道で車で出入りできる。その農道の石碑がある。
・石碑:松山農道:昭和五十四年(子持坂501)
西口農道から西に向かい下りていく。50mで右に馬頭がある。
・馬頭観音(子持坂501)
100m下ると板碑がある。
・板碑:開演建碑之趣旨(子持坂35)
50m下ると右に寺院と左に観光案内看板、公衆トイレがある。
○常願寺(子持坂35)
・石段・自然石、・カヤの木:天然記念物、・手洗石、・燈籠、・庚申、・燈籠、・板碑:慰霊碑、・墓石:江戸中後期の物多し、・三界萬霊塔、・六地蔵、
150m下っていく。右に長屋門が見える。
○長屋門(子持坂244):鴫谷氏宅:シギヤかシギタニか?
・説明:130年の歴史、市指定文化財、修復。
100m下ると子持坂集落内の現在の県道より古い旧道に出る。進行するには右折(西)だが、左折すると30m先に祠がある。
○大松の地蔵尊:いぼ地蔵(子持坂312)
・説明:建立安置不詳、昭和中頃まで身体にイボのできた子供は親と一緒に地蔵にイボがなくなるように祈った。祠内の小石でイボをさするとイボがなくなると云われた。治ると子供は親と一緒にお礼参りした。大松というのは祠裏に松があったからだ。
・祠:地蔵、・献燈、・新:手洗石、
子持坂には、まだ他にも紹介先があるので、大松地蔵から南西150mの神社に行く。
○熊野神社(子持坂336)
・献燈2、・コンクリ鳥居、・手洗石:安政五戊午九月、・石祠(石家道祖神)2、・献燈2:昭和五十一年、
神社から北西に300mで岡部中学である。その左手前に公園がある。
○巨石の森公園(子持坂102)
・巨石:いくつか、・裸足の散歩道、
公園から東に300mで県道焼津森線(現在の朝比奈街道)に戻れるが、その手前に地蔵堂跡地がある。
○地蔵尊(子持坂52)
・石段、・奉納西國三拾三所順禮供養塔:享(保・和)三年、西國三十三所供養塔:天保□□、・漢音、・馬頭(四角台座20㎝円形台座15㎝本体80㎝)、・地蔵、・石塔:四角柱、・破片いくつか、
県道に出て北上200mで神社である。
○浅間神社(子持坂22)
・社名碑:昭和五十一年、・石鳥居:昭和廿四年、・石段、・自然石、・イチイカシ:天然記念物、・コンクリ石柱2、・御神燈:安政四巳年、・手洗石:天保十三、・献燈:浅間宮、・秋葉山献燈2:寛政八年(平成二十二年再建)、
村良下橋を渡って村良に出る。県道の西側の山すそに神社がある。
○天満宮(村良978)
・説明:祭神:菅原道真、例祭日:10月25日、境内地220坪、境内社:津島神社、秋葉神社、弁天社、由緒:創立不詳、天明8年1788再建、明治8年村社指定、大正5年9月神饌幣帛料共進社指定、天満宮は天神さんとして全国に祀られている。京都の北野天満宮を総本社とし、その数1万社を数える。菅原道真は承知13年845生まれで、その生涯を至誠の道を垂範され、よく勉学に励まれて右大臣の高位に任ぜられた。俊才のあまり藤原時平の中傷により大宰府(九州福岡)に流された。牛車で送られる道中、牛により待ち伏せの賊の難を免れたと伝えられ、以来、牛は天神様の使いと云われ、教育の基本の象徴とされた。牛は食物を反芻して消化する。その様に繰り返して勉学せよと、教えている。天神信仰は元来農耕民族にはつきもので、天候と農業生産との関係から生まれたもので、雷電は雨をもたらし、五穀を実らせる。天神と云えば道真を指すこととなり、その威徳を偲ぶと共に文学を親しんだ神として尊敬されるようになった。江戸期には幕府が庶民の初等教育機関として全国に寺子屋を設立し、その精神的中心として道真の分霊を祀ったので、天神信仰は学神として学力向上、合格祈願の神として広く庶民に奉斎されている。
*著者注:上記の文章では江戸幕府が寺子屋を設立したかのごとくに読めるが、寺子屋は民間教育機関と歴史的に認知されている。つまり今で言えば私塾のようなものである。江戸幕府が作った教育機関として有名なのは昌平坂学問所で、各藩は武士のための藩校を設立していた。それ以外には吉田松陰が作った松下村塾や福沢諭吉が作った慶應義塾に代表されるように私塾が発達していた。現代の私塾とちょっとニュアンスが違い幅が広いかもしれない。藩の領主や重臣、代官等に設立された郷校というものもあって、武士だけでなく庶民教育を行ったものもあるようだ。
・玉垣:平成十六年、・石鳥居:昭和三年、・牛神:平成17年、・大木、・弁天、・秋葉山夜燈:慶應四戊辰1868年、・献燈:御神前:慶應三、・鬼瓦、・事業記念碑2、
神社のすぐ背後というか頭上は新東名の高架線である。
ここから山すそをめぐって400mで北の寺院に行く。
○村良薬師堂(村良574)
・吊るしびな :説明:創建:天保13年1842の記録があり、この頃建てられたと思われる。中には薬師如来が祀られている。薬師堂に長く保存されているつるし雛は地域の人たちの無病息災を祈り、薬師如来に奉納されたもので、明治38年1905と記録されたものもある。このつるし雛は毎年8月23日に行われる薬師如来の祭り「いっちょうぎり」の日に飾られるもので、つるし雛は板の竿に5本の糸で取り付け、吊るされている。平成17年。
左隣の上に寺院がある。
○大仲寺(村良574)
・庚申供養塔:天明八歳、・祠:如来、地蔵2、・手洗石2:、・石垣、・石塔、
東150mで県道に戻れる。すぐ先は村良橋である。渡って進む。橋から300m北上すると右に祠がある。
・祠:地蔵:安政四(桂島、兎島625)
すぐ東先に石段がある。
・神社:祠(桂島、兎島625)
・石段、・自然石1、
100m東に四つ角がある。そこが旧道である。かつては村良橋から北東のAIKAWA工場敷地内を旧道が北上しこの辻に出たようだ。この辻にも祠がある。
・祠:地蔵(桂島、兎島631⁻7)
水害除けで元はAIKAWA工場敷地内の中通りにあったものを移転したようだ。兎島631⁻7金子氏談。
この旧道を北東に350m進む。県道相俣岡部線に出る。ここに石道標と祠がある。
・石道標:是従葉梨村地 □□□町道 大正十五(桂島、須谷793⁻1)
○祠:北向地蔵:有縁無縁三界萬霊等、・石仏4:?観音、観音「一国三十三所」、地蔵2(桂島、須谷793⁻1)
北向地蔵は以前、県道相俣岡部線のトンネル上の貝立峠に祀られていたのだが、トンネルを切通しにした際、ここに移転されたらしい。先の金子氏談。
ここで県道を北西に400m進む。石塔がある。
・石塔:・庚申、・奉梵天帝釋青面金剛太童子(桂島、須谷834⁻1)
100m西進すると県道静岡朝比奈藤枝線(村良から北上する県道、村良で通過するのに使っていた県道)が合流する。
ここで一旦村良から北上し合流する県道で紹介するところがあるので、左折(村良方面へ南下)し150m進む。ちょうど桂島公園を過ぎて狭い水路がある所だ。
・水まんぼう:水路トンネル(桂島、須谷858⁻1)
・説明版:全長70m、幅180㎝、高さ180㎝弱であり、朝比奈川俎板渕の少し上に流れ出ている。この近くにあった字大畑の水田、二町歩が毎年のように朝比奈川、谷川川の増水により須谷川の排水ができず、稲作に被害が出たため造られた。「志太郡誌」によると貝立トンネルの竣工が明治29年1896,1月と書かれているので、おそらくその人足が水路トンネル工事にかかわったと思われる。構造は素掘りで造られ、平成に入ってから入口付近をコンクリートで補強された。平成17年。
~~~
なおここで県道相俣岡部線側の説明をしたい。岡部宿から桂島に行くルートも朝比奈街道だからである。岡部宿から川原町を過ぎ、貝立橋を渡って、現在は峠の切通しを通過する。以前はトンネルであり、更にその上に昔の峠道があり、北向地蔵も祀られていたのだが、切通しになり峠も削られたようだ。
『定本静岡県の街道』によれば、貝立峠以外に川原町から三星寺前を経て牛ヶ谷から山に上り、西の須谷に下る峠道があったようだ。以前は山上までみかん畑や茶畑だったので、明確に越えられる道筋があったのだろうが、植林地になって現在は道が荒れていると思われる。標高差80mほどのようだが、かなりの急斜面である。なお川原町から貝立団地側を通過し貝立峠に行ける道もあったようだ。
○笠懸松と西住墓(岡部、牛ヶ谷1132)
「…やがて西行は駿河国岡部宿にさしかかった。荒れ果てた小さな堂に立ち寄って一休みしているとき何気なく後ろを振り返ってみると戸に古い檜笠が掛かっていた。胸騒ぎがしてよくよく見ると過ぎた春、都で共に修業した僧の笠だった。 笠はありその身はいかになりぬらむ あはれはかなき天の下かな…」ここは歌聖として有名な西行が西住と東国へ旅をしたときに起きた悲しい物語の舞台である。「笠懸松」は右手西行山の中腹にあったが、松くい虫の被害を受け枯れた。その根元には「西住墓」と伝えられる古びた破塔がある。
○三星寺(岡部、牛ヶ谷642⁻19)
貝立橋の南150mに福寿院がある。
○福寿院(岡部、天神前356₋2)
・廃寺:堂、・庚申塔2:文化九年、?、・祠:地蔵3、・墓石:元文元年等古い物あり。
西隣も寺院である。
○永源院(岡部、天神前345)
・寺名碑:昭和四十四年、・六地蔵、・不許葷酒入山門、・地蔵、・祠:石仏:千手観音:札所第四番、
永源院の参道を南に70m進むと西の山斜面上に祠がある。
○岡部天神社(岡部、天神前361₋2)
・祠、・石段
~~~
ここで先の桂島の県道相俣岡部線と県道静岡朝比奈藤枝線が合流する所に戻る。
合流地点のすぐ西に谷川川を渡る谷橋があり、渡り、朝比奈川に沿って遡上するのが朝比奈街道である。ただここで一旦右折(北)し谷川川をさかのぼる。川沿いの新道ではなく、西の山際の旧道がよい。県道から右折して旧道を150m進むと祠がある。
・祠:地蔵:昭和四年(桂島、谷川口1036)
もう150m進むと新道に合流する。その先120m地点に石碑がある。旧道はここから右の工場敷地に向かうようだが、すでに廃道である。新道を進む。
・石碑2:谷川山、梅林院(桂島、谷川口985)
300m北上すると寺院が見える。
・祠:地蔵:説明:故鉱次郎氏は明治28年榊原家に生まれ、昭和51年9月27日、82歳の生涯を閉じた。簑笠辛苦して農業に励み、常に神仏を尊び梅林院5代に亘り身心を盡し、物心両面を惜しまず公益に率先服すること多くよく隣人に益した。老人会はその生涯を讃え集落民の協賛を得て後世まで伝えるために地蔵尊を建立した。昭和52年。
○谷川山梅林院(桂島、谷川山964)
・永代供養塔:平成十三年、・祠:神:石天板、・禁葷酒、・三界萬霊等大乗妙典十部供養塔 銘日、・祠:六地蔵+地蔵:座、・大日如来:線刻、・石段、・献燈2:寛政九、・庭用燈籠2、・新:地蔵:多数:頭部大きく可愛い、
・忠霊塔、・有縁無縁三界萬霊菩提塔:平成十八年、
・木喰仏:薬師如来立像:説明:市指定彫刻:像高95.8㎝、完成:寛政12年8月8日、背面墨書に「日本千体体ノ内ナリ天下安楽興正法」83歳花押あり満面笑みを浮かべ、豊かで大きな衣に包まれ、左手でそれを上から守っている。病気を治してくれるという薬師如来は大国人々に栄拝された。製作者である木喰上人は45歳の時1762木喰戒を受けるとともに日本回国の願を発し、93歳1810で没するまで休むことなく日本全国を歩き続けた。そして足を止めたほとんどの土地に仏像を残している。昭和47年。
・木喰仏:子安観音菩薩立像:説明:市指定彫刻、像高:96.0㎝、完成:寛政12年8月8日、背面墨書、他の一体と同じ、現在梅林院に所蔵されている二体の木喰仏はもともと神入寺にあったもので頭部の彩色はともに近年のものである。廃寺となった神入寺は檀家の総意によって梅林院境内に移され観音堂として保存されている。木喰上人は寛政12年1800、の6月13日より8月13日まで丸2か月間岡部に滞在し附近の寺々に仏像を奉斎した。このうち岡部には梅林院二体、内谷光泰寺二体、三輪十輪寺二体の六体がある。昭和47年。
・観音龍石:説明:この石は昭和35年1月、谷川山梅林院南方約300mの参道上方雑木林内に頭部のみ露出していたものを、たまたま山中に香花取りに入った某氏が見つけ、直ちに当時の梅林院住職に懇願して、この石を譲り受け自宅の庭石となすべく職人を雇い、掘り出しにかかったところが、相当深く土に埋もれているはずのこの石が、予期に反してわずかに鍬を入れたるのみにて、一人飛び出るがごとく、下の参道に落下しなおころころと回転して、道下のやわらかな畑に、でんと座ってしまった。重量1.5トンもあり運び出すのには、いかにも困難であったが、この石に魅せられた氏は、萬金を惜しまず投じようやく自宅の庭に運ぶことができた。渋味もあり何事か神秘が秘められているごとき、この石は水石に興味を持つ人々の話題の的となった。ところがその後夜毎にこの石が氏の夢枕に立って「私は谷川の観音様をお守りする龍身であり、このようなところに置かれるのはまことに不本意である。早々に観音様のそばに帰してくれ。」とのお告げがあり、氏は自分の信ずるある人に伺うに「お告げの通りいかにも観音様をお守りする龍の魂が宿っておられる御尊体である。今すぐ梅林院へお送り申し上げ末永く供養するのがよい」と言われ、驚いた氏は愛着捨てがたき神秘の謎を秘めている石なればこそ、直ちにお告げの通り梅林院境内へ奉納することにした。しかるにこの石を乗せた車が、谷川参道に入るや否やたちまち一天にわかに搔き曇り悲體戒雷ヒタイイカヅチのごとく甘露の法雨降り注ぎ萬雷鳴動して煩悩の焔が滅除された。ときはまさに昭和35年8月10日、その後氏の家では一切の災難を免れ身心快楽となり、現在では大いに家門も隆昌し安泰の生活が送られている。以来この石は観音様の御守護石としてなお一切の災難を厄除し一家の繁栄と幸福に霊験あらたかであるとして世人の信仰を得て供養され現在に至っている。昭和51年11月、駿河一国三十三ヶ所観音霊場第八番札所
・鐘楼堂:説明:建築材:40石当山森林中より、彫刻材(楠)6石殿大石芳明氏寄進、全高地上26尺、屋根幅18尺4面、廊下幅14尺4面、土台幅13尺4面、柱間8尺6寸、丸柱直径8寸七分、建立昭和56年7月、棟梁朝比奈玉取寺坂初太郎氏、記:当山は開創:長享元年1488、その昔合併により日光山神入寺より梵鐘この地に移転さる。偶大東亜戦争勃発し隆魔と化す。現在の梵鐘は当山37世の発願により、昭和30年に再鋳、鐘楼堂は寛政元年1800大工秋山傳右エ門の作である。堂宇の荒朽も甚だしくそのまま放置しておくこともできず協議の結果賛同を得て改築することになる。広く十方檀越の寄進を仰ぎ幸い名棟梁寺坂初太郎氏71歳の斤鑿キンサクにより凡そ1年間の歳月を経て完成を見る。傘下の彫刻八面は棟梁日夜辛苦の作と云われる。当山38世詩之、39世改修、平成20年5月。
○谷川と飯間の峠(藤枝市谷川、静岡市飯間)
今回谷川の奥を調べていないが、二十数年前と十数年前の記憶で記入する。谷川川に沿って3㎞北上する。途中新東名の高架下をくぐりもする。谷川と静岡市飯間の間の峠直下に車で出られる。茶畑を5分も歩いて上ると峠である。その向こうは植林地や草地で道が不明だが少し下ると道が明確になる。ただし途中耕作放棄された畑地で道が不明確になる。1㎞歩いて飯間の農道に出られた。現時点ではこの古道山道がどうなっているかは不明である。茶畑も現在整備されているかも不明である。山の畑はどんどん耕作放棄地になっていくので、歩くなら冬場をお奨めする。
なおこの峠道はかつて1351年鎌倉攻めに向かう足利尊氏が軍勢を引き連れて越えた道である。
県道の谷川口に戻り、朝比奈川に沿って遡上する。
300m進むと関谷橋がある。渡らずに前方50mを見ると鳥居が見える。
○津島神社(桂島、谷川口1107)
・石鳥居:昭和五十年、・石段、・手洗石、・石祠、・石祠(石家道祖神)、・?神木、
神社前の道を通り、丹社を経て溝口橋に抜けたが、特に遺物類は発見できなかった。
関谷橋を渡り、450m進む。祠と石道標が向かい合わせにある。
・祠:地蔵、小地蔵(桂島、関谷343⁻1)
道の向かいに2つに折れた石道標がある。
・石道標:朝比奈街道 山道ヲ経テ葉梨村ニ通ズ 里程凡ソ六千米 約一里半 昭和二年十一月 御大典記念 桂島善□會(桂島、下川原343⁻1)
正直うれしかった。朝比奈街道を調べに来て、その文字を見付けられたからである。西の山を越えると藤枝市北方の葉梨に出られたということだ。そこまでなら3㎞ほどだ。多分葉梨の中心地までなのだろう。この峠道も現在は廃道だろう。見つけるなら冬だろう。ただ地図上では途中村良を通過し農道を通るようだ。残存しているかもしれない。
・古道:桂島の観音下から葉梨の北方への山道。
国土地理院地形図では点線記入されているが現在あるかどうかは未確認。北方と桂島境の峠手前500mは一部農道ルートのようだ。
石道標から県道を300m進むと右に石燈籠がある。
・石燈籠:自然石、・丸石(桂島、下川原231⁻1)
150m進むと溝口橋に達する。この左に旧道があり、祠がある。
・祠:神(桂島、下川原102)
溝口橋を渡って100m進み右折し300m北東へ向かう。
○持珠院(羽佐間105)
・祠:六地蔵:一石二仏の三石:可愛い丸顔で首をかしげているものもある、
梅林寺の隠居寺だそうだ。地元民談。
県道に戻る手前150mで山際の旧道を通り、遡上する。120m進むと山上に石段が続く。
○天神社(羽佐間71⁻1)
・石段、・本殿・拝殿、
山際に沿って400m進む。右に石塔がある。
・石塔:刻字不明(羽佐間351)
もう300m進むと土手に達し左手に橋があり、手前に石塔類がある。
・秋葉山常夜燈:寛政九、・庚申塔2、(羽佐間160)
羽佐間橋を渡り県道は右に曲がって150m行く。右に祠がある。
・祠:馬頭観音6(羽佐間698)
馬頭観音ばかりが6つもまとめて合祀されている。この後もなぜか馬頭観音ばかりを6つ集めて祀っているものにいくつか出会うことになる。六地蔵にあやかっているのだろうか。面白い合祀方法だ。
120m進むと左に寺院の寺名碑に出会う。
○喜雲寺(羽佐間755)
・寺名碑:昭和五十一年、・新:頭部大きい地蔵、・たぬき、・地蔵2:昭和五十六年、・献燈2:、・手洗石、・鐘楼、・四角石、・燈籠:自然石:平成元年、・祠:新:地蔵:座、・新:六地蔵、
県道に戻り50m進む。右に石塔がある。
・庚申塔:明和五、・庚申□□□、・新:献燈(羽佐間698)
県道をさらに20m進むと右に櫓の模型がある。
・模型:朝比奈龍勢打上櫓:高さ3~4m(羽佐間105)
小柳津造園宅の私有地にあるようだ。
・羽佐間の古道(羽佐間675)
県道はこの先60mで殿橋を渡り殿に至るが、その前に古道で付け加えたいことがある。
羽佐間橋まで戻って、県道は殿に向かい右曲がりしていくが、県道を左折して羽佐間橋からそのまま北に向かえる道が山奥に入っていく。それが古道でもある。このまま奥に入りっぱなしではなく、狭間の一番山奥の伏見氏宅:羽佐間675まで行くと右の峠(標高差2m)を家の奥ですぐ越えられ、越えるとすぐに下降し朝比奈川に出て、川を渡り、土手沿いに現在ある龍勢打上櫓のある土手沿いに新舟に進んでいたようだ。ただ伏見氏宅横を細い山道歩道が通っていて標高差2mの峠越えができるが、そこから先は尾根沿いに上る道はあったが、下る道は雑草等ぐちゃぐちゃで発見できなかった。真冬なら強引に下りられるかもしれないが、すでに下る古道は消失しているようだ。惜しい。
この雑草ぐちゃぐちゃ部分をすっきりさせ下れる道を再整備して川まで下りられると、そこは玉露の里から川沿いに土手を整備して歩きやすくなっているうえ、岩などを配置している。その辺りの下流端に出られそうだ。そうすると伏見氏宅からの古道と玉露の里がつながるのだが残念。数少ない古道残存部なのだが。
県道の殿橋に戻り橋を渡って、殿に達する。橋から150m進むと右に増田氏宅:殿183があり、祠があるし、変わった石がいくつもある。
・祠:丸石、・馬蹄石:多(殿183)
増田氏談:この辺りは馬蹄石の産地で各家でお守りとして祀る。石仏では野田沢峠や玉露の里に観音が祀られている。
県道を50m進むと右に石塔が祀られている。
○石塔類:総善寺参道入口(殿753⁻1)
・寺名碑:新:朝比奈氏菩提寺、・農道記念碑:昭和五十年、・丸石、・古:常夜燈、・?庚申:六臂、見聞言ザルレリーフ:寛政七、
この参道で右折し300m北進し右折し300m東進する。途中寺前橋を渡る。
○総善寺(殿167)
寺名碑:昭和五十五年、・六地蔵、・地蔵、・観音:六臂、・石祠、・永代観音堂、・庭燈籠、・丸石、・新:観音、・當國善光寺四國西國秩父坂東百八拾八所供養塔 當村 明治十四年、・板碑:平和の礎、・板碑:、・献燈2:、・自然石、・鬼瓦:昭和六十年、・観世音菩薩:昭和五十八年、・献燈:平成二一年、
・「殿の虫おくり」:説明:殿地区には、山あいにしては比較的広い水田がある。そして起源は定かではないが昔から虫おくりの行事が行われている。この行事は秋ウンカが発生すると村人は松明に火をつけ行列を組み、集落全体を歩く。この時人々は「青田の虫を送れ、田の虫を送れやあ。」などと唱えながら、松明で田の面をなでるようにして虫を誘い出し焼き払った。しかしこの行事は農薬の普及により自然に行われなくなったが、昭和60年頃の町内会長、有志の人たちによって復活し、夏の一夜を楽しむようになった。現在では8月23日の夜、六地蔵尊縁日に合わせ町内会、子供会で中心になって、この行事を継承している。平成15年。
また県道に戻って西進する。100m進んで左の朝比奈川土手を見ると300m先の土手沿いに高い櫓がある。
○朝比奈龍勢花火打上櫓:無形文化財(殿167)
・説明版:歴史的な由来は定かではないが朝比奈城跡朝日山城跡又駿府城跡の位置関係から山城閒の戦略の一手段として使われた「狼煙のろし」をその起源にする説が有力である。江戸時代後期より六社神社例祭を飾る行事として又豊作を祈願して献發され、それぞれの秘曲が伝承されてきた。大東亜戦争中、中断され昭和22年農村慰安として復活、東司は柳の木などに櫓を括り付けて打ち上げられていた。昭和37年より本格的に打ち上げられ民俗文化の伝承には組織が必要と昭和53年に朝比奈龍勢保存会が設立され昭和59年、県より無形民俗文化財の選択指定を受けた。現在13の龍勢連260余名の会員を有し、歴史と文化の息づく郷土づくりのシンボルとして高さ20mの常設櫓を町助成金により建築された。平成2年。
またこの土手へは、川向こうの羽佐間の伏見氏宅から下ってきた古道が、川を渡って川のこちら岸につながっていたのである。
また県道に戻って、西進する。すぐ右(北)に公民館と公園があり、看板説明版がある。
・看板:朝比奈大龍勢:朝比奈大龍勢は、戦の狼煙の名残と考えられ、明治以前から例祭を飾る事業として打ち上げられている。静岡県内でも数箇所にしかないこの花火は、すべて地区龍勢連の手で作られ地区ごとにその技を競う。現在は2年に一度打ち上げられ、その勇壮な姿を楽しみにしている人も少なくない。
イラスト図では先頭部:ガ(ガンタ)、次いで吹き筒(フキゴ)、重心は吹き筒の長さの2.5倍部分、下方を尾という。
県道を100m西進し右折し北東進する。殿の西ノ平の集落内旧道である。100m進むと祠がある。
○祠:地蔵、・新:でか地蔵、・奉納西國三拾三所秩父三拾四所坂東三拾三所四國八拾八所文化十五(殿、西ノ平683₋2)
この祠から集落西の山上に大木があり、神を祀った祠がある。ちょうど萬年寺から朝日山城ハイキングコースを上りだすと横を通過することになる。
~野田沢~~
西の平の集落を北に抜け総善寺参道前も通過する。大野原橋や原上橋を通過するのが明治20年代のルートに近い。原上橋から300mで分岐になる。西又や岡部のリサイクル工場、小園地蔵方面へ行く西又林道が左に分岐するが、右へ行くのが野田沢ルートである。
400m進むと右に石塔がある。
・石塔:十一民平墓万(野田沢)
900m進むと野田沢橋を渡り、野田沢集落に達する。橋から350m進むと野田沢公民館前の橋袂に石塔類が苔むしている。
○石塔類(野田沢77₋2⁻1)
・庚申塔、・○奉禮観世音菩薩 西國三十三所順拝□観世音、・庚申塔:昭和五十五年、・奉善光寺如来供養:明治三年、・献燈、*自然石2の上に石塔類は固定されている。
100m進むと右に橋がありその向こうに石段がある。
○山神神社(野田沢103)
・石段、・石碑:手摺~:平成二十七年、・石鳥居:昭和三年、・手洗石:昭和六年、・祠、・拝殿本殿、
200m進む。野田沢の集落が切れる所に祠が祀られている。
・祠:笠かぶり地蔵(野田沢140)
200m進むと舗装自動車道が二手に分かれる。左が野田沢峠経由で静岡市飯間に出られる道である。ここに祠がある。
○祠:石道標:此れより右やまみち左ふちゅう寛政七年
・説明版:上記のように記されているが、寛政七年は西暦1795年で江戸時代の中期になる。この道しるべは、朝比奈から静岡市飯間を経て、駿河の府中(静岡市)へ通じる昔からの街道の一つであったことを示す遺構である。古老の話によると今川氏真が武田軍勢に追われて駿府の館から掛川城へ落ち延びる時、永禄12年1569に通った道という。現在は自動車社会になり、往来が少なくなった時期もあるが、農道整備事業により幅5.9mの快適な舗装道路となり、昔と変わらぬ物流道路としての活用が期待される。
この石道標を、よくぞしっかり保存したものだ。刻字はかなり読めなくなっているが、説明版によって分かる。将来文化財に指定されるかも。
かつてここには自動車道はなく、歩く山道があり、歩いて野田沢峠を越え飯間に出た。峠には六地蔵が祀られ、ハイキングコースとして知られていたが、自動車道ができハイキングコースになっていた古道は消失した。
祠裏の岩の中に馬頭がある。
・馬頭観音:石祠内
自動車道を上っていく。峠には新しい石碑が建立され、六地蔵は道の左擁壁上に祀られている。ちょうど静岡市と藤枝市の境界線になっている尾根沿いを1990年頃歩いて通過したことがある。その時野田沢峠も通過し六地蔵を見た。境界線尾根の道は劣化しているだろうが冬場なら歩けるかもしれない。
○石碑:山峡招き緑風爽やか、・板碑:2000年、
○六地蔵+観音:文久元酉九月日世話人増田増右エ門、
1861年。
~~~
また殿と新舟の県道に戻り、西進する。180mで右に寺院への参道となる。
○萬年寺(新舟1240⁻1)
・寺名碑:昭和四十八年、・□□□大菩薩、・萬年寺のカヤ:県指定天然記念物:根回り8m、目通り5.8m、樹高30m、根張り東西30m、南北25m、
寺の裏から朝比奈城ハイキングコースになっていて裏山に上って行ける。
○朝比奈城ハイキングコース
萬年寺から100m上っていくと殿、西ノ平集落の裏山に出る。ここに大木と祠がある。
・祠、大木
更に100m上ると石碑と石段がある。
・石碑:経塚址
更に10分も上ると山頂の平坦地で看板がある。
・朝比奈城跡
・説明版:戦国時代に岡部氏と並ぶ武将、朝比奈氏は今川、武田氏に仕え特に信置という人物は武功を上げ今川氏より感謝状を受けた戦国雑誌に「止駄郡殿村にあり今川家の功臣朝比奈某の築く所にして永禄年中まで朝比奈家代々の居城なり」とある山頂に土塁や空濠を作り居館を麓に作ったことからいわゆる「根古屋式」の城塞といえる。
空堀一つ、本曲輪が若干見られるが、城の分かりやすい遺構はハイキングコースから見付けにくいし、取りたてて紹介する標識類もない。ルート標識と山頂の城紹介看板になり、他の遺構類を紹介する標識設置が望まれる。
山頂を過ぎて20~30分下ると善能寺前に出てハイキングコースは終了である。
萬年寺入口に戻り、そこからもう20m進むと左に土手があり、馬頭が祀られている。
○馬頭観音6(新舟1240⁻1)
・馬頭:剥落しかかり、・馬頭観世音:大正六年、・馬頭:八臂:昭和四十八年:怖い形相、・南無馬頭観世音菩薩:昭和四十七年、・馬頭:大正十五年、・馬頭:八臂うち六手はレリーフで顔の形相は怖い。
県道を30m進むと右に道の駅がある。
○道の駅 玉露の里(新舟)
・昆虫館、
道の駅を過ぎてすぐ右側の家前に新しい石塔が2つある。
○石塔3(新舟1004)
・新:三界萬霊塔、・新:交通殉難者供養塔、・古:丸石
すぐ左に玉露の里に渡れる橋がある。
○玉露の里(新舟976⁻1)
・石碑:玉露の里、
・句碑:村越化石:句碑は芸術的に斬新ですぐれている。説明:村越化石は大正11年朝比奈村に生まれる。本名:英彦。昭和13年ハンセン病発病の為旧制中学校中退、昭和16年に草津の国立療養所栗生楽泉園に入園。昭和24年に大野林火先生に師事、これまで俳人協会賞、蛇笏賞の他俳壇の各賞を受賞。魂の俳人といわれる。平成3年には紫綬褒章を授賞。石刻句:「望郷の目覚む八十八夜かな」平成七年作。望郷の句は私に多い。故郷を離れてすでに久しく、見えない眼の奥にいつも故郷がある。夏も近づく八十八夜は新茶の初摘みの頃、村中が茶の香りに包まれるよき季節。生気溢るる八十八夜は望郷とともに私の好きな言葉である。村越化石。村越化石顕彰会。
・新:諸畜霊同魂碑:平成三年、・庭園:茶室庭園はこじんまりしているが素晴らしい。
・椿園、
なお玉露の里の諸蓄霊碑のある所に馬頭観音があると複数の方に言われたが、諸蓄霊碑しか見当たらないので、最近馬頭を移転して諸蓄霊碑を安置したのかもしれない。
・吊橋、
玉露の里入口の橋から県道を100m北上すると、右に神社がある。
○六社神社(新舟1018)
・社名碑:昭和六十年、・手洗石:昭和二十七年、・石鳥居:明治四十二年、・手洗石、・石鳥居:破片、・自然石:多、・石段、・大木:多、・常夜燈2:昭和六十三年、・常夜燈2:天保十一年、・忠魂碑:昭和二十七年、・板碑:忠魂碑参道、・狛犬2、・献燈4、・板碑2、「狛犬1対、「平和と鎮魂の標」
・説明版:朝比奈大龍勢:県指定無形文化財:朝比奈大龍勢は六社神社の例祭に合わせ、祭神に豊作への感謝と地域の安全・発展を祈願して奉納される花火の一種です。その呼び名は花火が轟音を響かせながら真っ赤な火の尾を引いて空に上がっていく様子が「昇天する龍の姿」に似ていることから付けられたと云われる。龍勢の起源については「戦国時代の狼煙説」と「江戸時代の猟師鉄砲試射説」とがあるが、はっきりしない。昭和53年に「朝比奈龍勢保存会」が作られ、今は13の龍勢連が加盟して各連ごとに秘伝の技術がある。隔年の10月に打ち上げられ、各連がその技術を競い合う。県内では草薙でも打ち上げられ、全国では4カ所しか行われない大変珍しい花火である。
神社から200m北上する。
○祠:・地蔵3、・馬頭1、・丸石5、・層塔(五重)(新舟233₋2)
地区の石塔類を合祀したようだ。
200m北上する。右の路地の1軒奥に常夜燈がある。
○秋葉山常夜燈:火袋辺り:昭和五十一年、竿部分:文化元子年1804(新舟175₋1)
常夜燈の火袋部分は修復され昭和の年号が刻され、竿部分は古く文化の年号が刻まれている。こうやってでも保存していることがうれしい。
県道の左側には榎橋が架かり朝比奈川を渡れる。渡ってすぐ左折し川に沿って150m南下すると祠がある。
○新舟西宮恵比寿神社(新舟522⁻1)
また榎橋に戻り左折(西)し笹川を目指す。400m進むと右(北)に行く道があり、石碑がある。岩瀧不動尊参道である。
○岩瀧山不動尊
・石碑:岩瀧不動尊参道
参道を450m進むと標識があり、右の崖下に滝があることが分かる。
・不動男女の滝
滝入口から奥に100m進む。
・岩瀧不動尊:
・岩穴ののぞき地蔵、・献燈:平成九年、・手洗石:昭和十七年、・献燈:昭和四十三年、・例祭日:10月28日、2月28日、
参道を戻り参道入口を目指す。今度は笹川を目指し450m進む。橋の袂に石塔がある。
○祠:・庚申塔:見聞言サルレリーフ:寛政?、・献燈:昭和四十三年、
200m進むと駐車場があり、笹川集落の中心部に達する。
・石祠
駐車場に説明看板がある。
・笹川集落の歴史
・説明:言い伝えによると、笹川八十八石ハイキングコースをビク石に上っていく途中に南向き傾斜面で日当たりのよい平坦な場所を「落人の段」と呼んでおり落人の忍び住むには、絶好の場所がある。ここに文治元1185年源平合戦において平家が滅亡し、平家の落人がここに住み着いたのが笹川の始まりであるといわれる。また集落の入口付近に「上の山」という山があり朝比奈川のほとんどの集落と遠くは岡部本町から焼津方面まで見渡すことができる場所があり、ここの山の背を掘割り追手を見張る場所としたと言い伝えられている。やがて時がたち世の移り変わりとともに家族も増え、落人の段から順次安住の地を求めてこの笹川の盆地に居住し笹川集落を形成した。また昔からの書紀によると駿河の国志太郡笹川村新舟とあるように笹川空さらに新舟にと住み着いたと考えられる。
・水玉神社と十四地蔵尊の由来
・説明:昔、笹川集落へホウエンさん(祈祷師のことを村人はこう呼んでいた)が、落ち延びて、この地に住み着いた人たちのために15の玉を下さった。これを氏神様として祈っていた。氏神にお参りする人々は清水の流れる堀の沢で手を清め口をすすぎ家内安全と集落の安泰発展を祈って心のよりどころとしていた。いつ頃か不明だが、突然の地震か大雨かその原因は不明だが、大きな山崩れがあり氏神である15の玉神様は埋まり何日も土砂の掘り返しを繰り返し続けたが、14の玉神様を見付けられなかった。幸い埋まらずに1体が見つけられ、この1体を水玉神社として、また見つけることができなかった玉神様は十四地蔵尊として祀られた。
駐車場のすぐ先の分岐点に石道標がある。
・石道標:瀬戸谷村十八瀬ニ通ズ 葉梨村上大澤ニ通ズ 御大典記念 昭和三年十一月新舟発起人
瀬戸谷十八瀬へはちょうどビク石登山道を指し示し、ビク石から瀬戸谷に下ればよい。上大澤へは笹川集落の水玉神社奥を尾根に取り付き山越えすると上大澤である。こちらは今となっては山道があるやらないやら。
この分岐点から左上の神社方向を目指す。
○水玉神社(新舟、笹川828)
・石段、・献燈2、・手洗石:文化十一、・十五玉伝説:上記、
○駿河一國百地蔵尊第十九番笹川十四地蔵尊、勝覚法師(新舟、笹川738)
・石祠、・観音、・手洗石、・献燈、・献燈:昭和四十三年、・十四地蔵、
・祠:勝覚法師:地蔵5:説明:勝覚法師は地元の農家の出身で取りたてて学問を納めたわけではないが、地元民の為功徳を施し、地元民の尊敬を集めた人であったようだ。没後も信仰を集め、勝覚法師として祀られるようになったようだ。
先ほどの石道標の分岐点に戻り、ビク石方向を目指す。150m進むと右の沢向うの茶工場隣に石塔がある。墓石である。
・墓石:享和三亥七月一日早世一葉童女:1803年
更に奥へ500m目指すと舗装路の終点となる。現在はここからビク石登山道であり、笹川十八石である。昔は集落尾張の家の裏山から山に取り付き尾根に出てビク石を目指したようだが、十八石を通過し手から尾根に取り付くコースになったようだ。
○笹川十八石
・表石、手洗石、赤石、三の石、ナメクジ石、ホコ石、むすび石、五色石、ラクダ石、メガネ石、こうもり石、座禅石、想像石、見上げ石、象石、がま石、コラサー石、出船入船石、こもたたき石、
・ビク石登山道:古道:笹川から笹川十八石を経てビク石山頂へ、そしてビク石から瀬戸の谷へ下れるルートである。現在はハイキングコースとして利用されている。一部は古道のままではなく道が付け替えられているようだが、およそ古道が現在でも利用されて保存されている好例であり、最も古道が残っている部分である。途中地蔵があるようだ。今回未調査。
また来た道を戻り榎橋を渡り県道に戻る。100m県道を北上する。右奥に寺院がある。県道からの参道入口に墓石や石塔がある。
○石塔、墓石(新舟137₋1)
・如来:墓石?、・萬霊塔、・墓石3:~信女、・墓石:~童子、・観音:墓石?、
○善能院(新舟271)
・寺名碑:昭和六十三年、・如来、・観音、・地蔵、・観音?、・庚申供養塔、・祠:六地蔵、・薬師堂、・禁葷酒:寛政十二、・手洗石:、・臼、
寺の裏山は朝日山城ハイキングコースで墓地で配水場でもある。裏山を100m進むと墓地手前に祠がある。
○祠:不動明王:天明元年(新舟271)
・五輪塔、・献燈、・石塔、・丸石:二段重ね、
県道を200m北上すると朝比奈川に架かる石上橋を渡り宮島の石上集落になる。更に県道を奥に目指す。石上橋から300m進むと左折し上に上っていく小道がある。50m上って右の小屋の先の奥に祠がある。
○祠:マラ地蔵(宮島、小丹原456⁻12)
・祠:マラ地蔵:一石に6組(多分男女で一組)の双体道祖神をレリーフ、横に男根石か?、丸石、8月7日の旧七夕に読経、この地域では七夕は8月7日、宮島小丹原457⁻8:前島氏奥さん談、
県道に戻る。県道沿いに石碑がある。
○板碑:記念碑(宮島、小丹原522⁻6)
記念碑から県道を400m進む。左に石碑があり、奥に大木が見える。
○大山祇神社(宮島、小丹原419⁻9)
・石道標:大山祇神社:県道沿い、・石鳥居:昭和三年、手洗石、・巨木3~5、・巨木切株、・大木5~6、
県道に戻り30mで宮島橋であり渡ると宮島の板取集落である。橋を渡ってすぐの右家に祠があり、もう1軒先にもある。
○祠:神、・祠:石塔:紀伊国川中島八兵衛:明治四十四年(宮島、板取760)、
川中島八兵衛石塔は志太郡榛原郡に偏在していて、今の藤枝市、牧之原市、焼津市、島田市周辺に分布しているようだ。詳細は『大井川町史下巻』に書かれている。これは朝比奈街道沿いの最も奥にある物ではなかろうか。
県道を150m進むと左折し朝比奈川沿いに進む道を行くと朝比奈川を渡る田島沢橋があり、渡ると、左が民宿朝比奈で右が城山不動尊方向である。右に100m向かうと田島沢に架かる橋を渡る。沢に沿ってすぐ左折し、800m奥を目指す。
○成田山城山不動尊
・祠:姫祀り、
舗装林道沿いに祠がある。ここから沢に架かる橋を渡って城山に上る。15~20分登り山の中腹の平坦地に不動尊が祀られている。
・石碑:城山観世音菩薩、・羅星庵、・祠・祠:石塔、・献燈2:平成十八年、・祠:地蔵:小多数、・地蔵、・新:自然石大石&不動明王像、・新:献燈2、・新:祠4、・新:平家の石塚、・新:地蔵、・新:源氏の石塚、
○城山:宮島城跡:△377.1m
不動尊は城山中腹の標高200m前後と思われる。この山は名の通り中世山城跡であり、宮島城といい、山頂は標高377.1mである。不動尊より上に上る道らしきはないようだが、ここから上れると山頂は近いようだ。他ルートとしては新舟の榎橋近くの新舟330:村越氏宅裏から道があるようだが、村越氏の話では途中から藪になり道は不明確だろうとのこと。また宮島の石上343村越氏宅横からも道があるようだが、付近住民によると道はないらしい。また岩瀧不動尊お堂の裏から上ればとも考えられるが、お堂の裏に道はない。せっかく中世山城があるのに行く道がないのはもったいない話だ。道を付けるとよいのだが。
また元来た朝比奈川沿いの県道に戻る。県道を300m北へ進むと寺院の参道入口になる。
○清養寺:
・寺名碑:昭和五十三年、・奉納西國三拾三所供養:文政七、・奉納西國秩父當國観世音菩薩:文政九、・善光寺詣供養塔:明治十五年、・三界萬霊等:昭和五十□□、・馬頭:明治二十一年、・馬頭:明治廿年、・観音堂、・小坊主地蔵、・四角石の碑、・水子地蔵、・六地蔵、・石、・庚申塔:昭和□四□、・庚申塔:見聞言ザルレリーフ、・丸石、・秋葉山常夜燈:文政九、
寺参道入口にはまた石道標があり、そこから寺参道の南とは逆に北へ行く山道歩道がある。
○石道標:朝比奈街道 南藁科村ニ通ズ 御大典記念昭和二 宮島
多分小園地蔵前を通過し、西又または野田沢峠越えで静岡市藁科地区へ出る道を示していたようだ。確かに現在でも小園地蔵前から自動車で西又や野田沢越えで藁科に出られる。
○古道:清養寺←→小園地蔵:距離500m、標高差50m
この山道歩道は距離500m、標高差50mを歩いて西又への道への途中の小園の地蔵がある所に出られる道である。十数年前に歩いたときはもっと道が綺麗だった。今回は歩いていないが、出入口の二カ所を見た所でも状態が劣化していると感じた。この朝比奈街道中、最も現在の街道から近い所で古道の状態を保った道が500mほどの距離で残存していると拝見する。この古道部分を失えばもはや朝比奈街道の古道は絶滅に近いだろう。この道は何とかして保存してもらえないだろうか。今回この朝比奈街道を調べブログへアップしたのも、この古道部分がどうなったか気になったので、調べたようなもので、保存を呼びかけたかったからである。もはや朝比奈街道の古道部分は消滅寸前である。
県道を150m進むと柚ノ木橋があり渡り、更に300m進むと小園橋がある。橋手前の公民館に常夜燈がある。
○秋葉山常夜燈:自然石、・丸石(宮島、小園91⁻1)
小園橋を渡る。県道は左折するが、西又への道で集落奥に向かう道を100m進むと左にお堂がある。
○芙蓉庵(宮島小園1393)
・瑠璃光山芙蓉庵薬師堂、・寺名碑:瑠璃光山:2m:文政四、・観音、・奉百番観世音菩薩、・如来、・石塔、・台座等、・○○奉供養(美良)青面金剛大菩薩:嘉永元戊申八月、・庚申供養塔:明和四丁、・自然石、・手洗石、
集落奥への道を更に100m沢沿いに奥に進む。右に橋があり鳥居が見える。
○日吉神社(宮島、小園1383)
・石垣、・木鳥居、・石祠、・大木5~6、
神社前の狭い農道を奥に詰めていく。
・古道:小園の日吉神社横農道から玉取沢への道:両方とも取付きは農道で人家がある。途中から鎌道のようだが、現在でもしっかりあるかどうかは未確認。
現在はもっと西の朝比奈川本流沿いの近又、谷倉に県道が通過しているが、昔は本流沿いに道を作りにくく、東の小園と玉取沢を結ぶ峠越え道を主要街道にして利用したのだろう。
西又へ進む県道静岡朝比奈藤枝線へ戻り、西又方面へ800m進む。石塔や祠がある。
○小園の延命地蔵尊
・説明:この地蔵尊は地元では「峠のお地蔵さん」と呼ばれ、昔から多くの人たちに親しまれてきた。いつ頃ここに祀られたか不明だが、駿河の国百地蔵の18番札所の延命地蔵尊として、今もなお多くの参拝者が訪れる。向かって右側の地蔵が初代のもので左の地蔵は昭和5年に建立され毎年9月13日には老師により法要が営まれる。そして百地蔵にはそれぞれ歌が詠まれている。「ひとすじ(一筋)に も(漏)らさで すく(掬)ふ ぐわん(願)なれば すく(救)いたまえや 南無地蔵尊」 この他岡部町内には16番「坂下の延命地蔵尊」、17番「光泰寺の地蔵菩薩」、19番「新舟の十四地蔵尊」がある。平成16年。
・祠:駿河一國百地蔵尊第十八番:地蔵4:昭和五年、昭和四十五年、・石塔、・手洗石、・秩父三拾四所供養塔:文化十年、
地蔵の裏から峠下に下って清養寺前に出る山道がある。古道で距離500m、標高差50mである。
~西又~
県道を50m進むと右に下っていく道もある。直進すると西又で、右へは岡部のリサイクル工場を経て野田沢や殿方面に行く道である。西又へ進む。
1.3㎞進むと小さい境橋があって藤枝市と静岡市の境界線になる。静岡市には一転すぐ右の工場に燈籠がある。
・自然石燈籠(静岡市西又1955)
県道を600m進むと西又集落の中心的四つ辻に出る。
2軒手前に戻り石段を上ると神社がある。
○八幡神社(静岡市西又1977)
・自然石2:二段重ね、・石段、・社殿、・祠、・サワガニ:石段に棲息、
また四辻に行き左折(北)し100m進むと右に西又公民館がある。この道向かいの左に堂がある。
○堂:三十三観音(静岡市西又2053)
・欠番:1,3,22,33番の4体で、29体があり、見事なものである。
○弓折峠(静岡市西又と玉取沢の閒)
公民館前の道を奥に1㎞進むと自動車は進めなくなるが、300m歩いて峠に行く道がある。
峠は1990年頃は茶畑だったが2002年には植林地になっていた。そして弓折峠からダイラボウに上る登山道もあったが現在はどうなっているか不明だ。
弓折峠は西又と玉取沢を結ぶ峠道である。以前2回上ったが特に遺物類はなかった。
また西又の四辻に戻り南に50m進む。堂がある。
○地蔵堂:地蔵(静岡市西又2050)
・庚申塔:天保九年戊戌十一月吉日、・観音:文政元寅年十二月吉日、・善光寺供養:明治二十二年、庚申供養塔:安永八年、・○庚申塔:昭和五十五年、
県道に戻り静岡市街方面へ進むと西又峠を越える。特に遺物類はなくダイラボウ登山口標識がある。県道のこの先は藁科である。
*西又の33観音、地蔵堂、八幡神社について教えて下さった西又1977:斉藤氏奥さんに感謝いたします。
~宮島、小園に戻る~
小園橋袂から県道相俣岡部線を朝比奈川に沿って遡上する。
芙蓉庵前から山際集落に沿って西に向かい県道に合流するのが旧道である。特に遺物類は見当たらなかった。小園橋から900mで近又橋に至る。手前右にどうも清水があるらしいが分からなかった。
○「ごとうの清水」
未発見。
橋手前のお宅にも丸石があった。
・丸石(玉取、近又30⁻1):松野氏宅
橋を渡る手前を右折し川に沿って進み、その奥の川の支流にどうも滝があるらしいが未発見。
○「近又三日滝」(玉取、近又51⁻2)
未発見。
近又橋を渡る。正面に寺院が見える。
○西楽寺(玉取、近又116⁻1)
・石段、・石塔、・献燈の竿部分、・常夜燈、・祠:地蔵、・庚申塔:明和六己年、
○青羽根への古道(玉取、近又116⁻1)
寺は山の尾根に取り付いた一段高い所に築かれており、その斜面の左側を青羽根への古道が通っている。その道は現在の青羽根への自動車道より一段高い所にあり、古道の下に新道が見える。ただし古道はこの裏の隣家:玉取153:入野氏宅で一旦おしまいのようだ。
寺の手前に保育園があり、園庭に像がある。
・二宮金次郎像:マキを背負い読書(玉取、近又121⁻1)
二宮金次郎のかつての学校での代表的な像であるが、残っているものは限定的なようだ。このまま保存する価値は十分だろう。
メイン街道は橋を渡って右だが、ここは直進して青羽根を目指す。
~青羽根~~
青羽根集落直前の自動車道沿いに石仏がある。
○馬頭観音2:明治十二年、-(青羽根、入口)
元は古道沿いにあったのだろうが、自動車道の集落入口に祀り直したのだろう。
集落に入り道を上がっていくと常夜燈がある。
○常夜燈:奉請秋葉大権現 天明五 青羽根村(青羽根716⁻1)
150m上っていくと板碑がある。
○石塔類(青羽根772)
・板碑:久志之光、・新:献燈、・手洗石、・石柱2
さらに100m上っていくと石仏がある。
○石仏:地蔵、小五輪塔2(青羽根754)
50m上り神社やハイキングコースがある方へ進む。
○新四国八十八カ所観音堂(青羽根997)
・観音堂:八十八観音、・?庚申塔、・馬頭2:顔破損、-、・庚申供養塔:宝暦七年、・手洗石:天保十三、・観音:聖観世音第二十一番、
30m進んで右のパノラマハイキングコースの道を100m進む。神社がある。
○大井神社(青羽根981)
・説明:駿河国益津郡朝比奈青羽根村に居住していた佛弟子の藤原朝臣永泰の寄進に依り建立。応仁元年亥年10月25日、願主藤原二良右衛門に依り建立、大工松山子宣。宝暦六年丙子8月、再建、神官諏訪丹波守、大工藤枝宿仁兵衛により建てられる。元治元年甲子8月27日再建。昭和12年再建。
・説明:青羽根地区は寿永四1185年、平家滅亡で、氏族存続を願いこの地に隠れ住んだ人たちの集落といわれる。仲本、村上、京、羽山、永井二家、清水の七家が集落の起源で青羽根七人衆と云われ、現在でもその子孫が家系を継承している。この大井神社は集落の護り神として青羽根村に居住していた仏弟子の藤原朝臣永泰の寄進により、応仁元1467年願主の藤原二郎衛門によって修造され、今でもその時の棟札が保存されている。その後3回ほど修造され、現在の建物は昭和12年に修造されたものである。また御神木の大杉は推定樹齢700年以上、根回り8m、樹高28mで市指定天然記念物である。志太の朝比奈村誌より。平成16年。
・木鳥居、・献燈2:安永五、・石祠2、・手洗石:大正元年、・献燈2:平成二十二年、・和合の樹、・大スギ:根回り8m、目通り5.4m、樹高28m、根張り25m
○パノラマハイキングコースにあるもの
・長塚石、・マンガン鉱山跡:採掘洞窟:すでに落盤で崩壊、・長塚峠、・麦地峠、
青羽根と市之瀬の境界尾根の峠に進む。かつての旧岡部町と旧藤枝市の境界線であった峠である。かつて「コスモス峠」という標識を見たことがあるが、正式名とは思えない。なんという峠名であろうか? 石仏もある。
○峠:?コスモス峠:青羽根と市之瀬の間
・石仏3:馬頭1、地蔵1、?1、
この尾根の南は藤枝市の市民の森△464mとなり、手前に駿河峰△489.9mがあり、市民の森の南にはビク石山△526mがある。
~~~
青羽根を終了して、県道の近又に戻る。玉取沢方向を目指す。600m進むと右に石塔がある。
○石塔類(玉取、近又351⁻1)
・庚申塔□永五□歳、・常夜燈:自然石、・?馬頭、・手洗石:内側ひょうたん型、・丸石、・花生け台2、
~谷倉~~
250m進むと落合橋に達し、谷倉集落となる。県道相俣岡部線は直進だが、左折し谷倉沢に沿って500m進むと右に寺院がある。
○梅窓寺(玉取、谷倉1328)
・地蔵、・石段、・○庚申塔:大正三年、・献燈、・六地蔵+観音:座、・石塔、・西國三十三処當國三十三処、・奉供養西國三拾三所観世音菩薩、・丸石4、・丸石:お供え餅風三重、・へそ石、・石祠、・手洗石:文化十四、
さらに30m進むと左に祠がある。
○祠:神、・献燈2:昭和四年、・手洗石(玉取、谷倉160⁻1)
70m進むと左に橋があり、その向こうにかつて畑地があったようだが荒れかかっているようだ。地元の人の話だと畑に八幡神社の祠が祀られているそうだが、探したが見つからなかった。
○?祠:八幡神社(玉取、谷倉1265₋2)
未発見。
さらに奥に150m進むと右に石塔類がある。
○石塔類(玉取、谷倉1170⁻4)
・庚申塔:大正三年、・庚申塔:明治八年、・常夜燈:自然石、
この奥は谷倉沢渓谷と呼ばれるようだ。結構奥まで人家があるようだが、古道遺物類は人家がある範囲内では見つからなかった。
~~~
落合橋まで戻る。
谷倉集落でも各家に丸石がある。
県道を200m進む。左は地域活性化センターであり、石造物がある。
○石造物(玉取、谷倉1476⁻1)
・秋葉山常夜燈:天保九:2.5m、・丸石3、・自然石:多、・新:地蔵2:頭でかくかわいい、・たまいし様、たまゆら、
この裏に神社がある。
○神明神社(玉取、谷倉1512)
・石段、・石鳥居、・石垣、・スギの大木、・他大木、
県道に戻り150m進む。
○石塔類
・祠:地蔵、・庚申塔、・献燈:自然石と金属加工の燭台、
600m進むと沢口橋手前で玉取沢右折する。
~玉取沢へ~~
180m進むと右に石塔類がある。
○石塔類
・○庚申塔、・献燈、・花生け台2、
なおも奥に350m進む。
○天狗の手洗い鉢(玉取沢1907)
・場所がはっきりしないが?多分沢崎氏宅の裏に手洗石が置かれていたようだ。
・説明版:昔法印さんを慕っていた天狗がいた。夜になると天狗は法印さんの墓に植えた大きな松の木の杖に来ては、毎晩のように太鼓を鳴らしたり、笛を吹いたりして、大変にぎやかに過ごしていた。しかしいつの間にか庄園どんの爺さん以外には声や音は聞こえても天狗の姿は見えなくなった。あまりの不思議さに近所の人たちが「そんなバカなことがあるか。」と言いあっていた。それを耳にした天狗は「それなら証に珍しいものを持ってきてやるか」と爺さんを一緒に雲に乗せて連れて行き、京都から一夜のうちに持ち帰ったのが、この手洗い鉢だという。朝比奈第一小学校編「あさひな」より、平成16年。
この玉取沢から南に入っていき峠越えすると南の小園へ抜ける古道があるようだ。ゼンリン住宅地図では細線で記入されているので道型は残存しているかもしれないが未確認。
玉取沢を東奥に詰めると自動車では行き止まりだが、歩いて西又へ抜ける弓折れ峠に至る。
○弓折峠
・西又の項目で前述している。付加すると、この山道はいまだに自動車道ではなく古道形態を残存していると言える。
~~~
県道相俣岡部線の沢口橋に戻る。
400m進むと山中(富厚里)への分岐点で、すぐ先の橋は境橋で藤枝市(旧岡部町、旧志太郡)と静岡市(旧安倍郡)の境界線である。朝比奈川を詰めると静岡市になるというのは何だか変な気がするが、志太郡と安倍郡の境なのだ。ここに石道標がある。
○石道標:御大典記念 朝比奈街道 南岡部町方面 北小布杉三野ヲ経テ川根ニ通ズ 東山中峠ヲ経テ藁科ニ通ズ
~~~
分岐点から右折(東)し600m山中集落、静岡市街方面へ進む。山中集落のお茶工場隣の山中集会所の横に石塔類がある。
○石塔(静岡市小布杉、山中2613)
・観音、・庚申:見聞言ザルレリーフ、・石塔、・一石三観音、・観音、・石塔、・地蔵、・新:献燈、・石仏、
300m進むと右上に鳥居がある。
○神社(静岡市小布杉、山中2346)
・金属鳥居、・本殿、
このすぐ上の御宅横からかつては中学生の通学路になっていた古道が峠まであった。
○古道:古い通学路(静岡市小布杉、山中2672)
40年程前までは中学生の通学路としても使われていたが、新道:自動車道が整備されて使われなくなったし、自動車道の下で沢沿いで、かなり崩壊したと思われるが、残存していれば価値ある古道と言える。富厚里峠から富厚里側に1㎞下るまでも古道があった。
山中の神社から自動車道で1.1㎞で峠である。
○富厚里峠(山中峠)
・祠:地蔵4、小地蔵12、・手洗石:大正三年、・奉納西國三拾三所巡拝供養塔:大正十四年、・開通記念碑:昭和四十六年、
峠の山中側少し手前に林道が分岐しダイラボウまで行くことができる。ダイラボウ山頂すぐ横の林道頂点には石碑がある。
・開通記念碑:平成16年3月
・ダイラボウ山頂:
・説明:昔「大らぼう」という大男がいた。富士山をつくると言って琵琶湖の土を大きなもっこに入れて運んだ。大男は富厚里山の上から水見色の高山へと一跨ぎに歩いた。その時の足跡があるので「だいらぼう」と名付けられた。木枯らしの森と下流の舟山はその時もっこからこぼれ落ちてできたものだという。中藁科小学校郷土研究クラブ。
~~~
山中と小布杉との分岐点のある境橋まで戻る。ちょうど藤枝市:志太郡と静岡市:安倍郡の境界線で境橋となっている。境橋から上流を目指す。朝比奈川の左岸:東側の道を上っていく。道のある川東側が静岡市で川西側が藤枝市である。川が境界線である。
境橋から300m上っていくと右に石塔がある。
○石塔類(静岡市小布杉1591⁻3)
・庚申塔、・庚申:安永三、・観音、
また300m上っていくと左に祠がある。
○祠:地蔵(静岡市小布杉1661) 、
さらに200~25m上っていくと右に石仏がある。
○地蔵(静岡市小布杉1697)
また400~450m上っていくと、静岡市立中藁科小学校小布杉分校がある。その手前に堂や祠がある。
○堂:弘法大師、祠:六地蔵、観音4(静岡市小布杉1756) 、
・堂:弘法大師、祠:六地蔵、観音4:當國三十三所供養塔、・奉納當國三拾三所供養塔:文化五辰十月吉日、・秩父三十四番観世音菩薩、・手洗石、
分校裏手右(南)の斜面中腹にに平戸神社があるが、地元の人に行き方を聞かないと分からない。県道沿いの茶畑からも行けるようだが標識がないので分からない。
○平戸神社(静岡市小布杉1062)
・本殿拝殿、・石垣、・金属鳥居、
分校から700m奥に詰めるとY字路に至る。右は富沢方面で左は三ツ野(三ヶ野)である。ここに石塔類がある。
○石塔類(静岡市小布杉1185)
・丸石、・西國三拾三所、・善光寺供養塔:明治、・庚申塔:明治四十一年、・庚申塔:レリーフ:文化九壬申年:1812、・庚申塔:昭和五十五年、・金属献燈:平成六年、・石塔、・當國三十三所、
○石道標(静岡市小布杉1697)
・石道標:御大典紀念 朝比奈街道 南岡部町方面 右富沢相俣川根方面 左三野ヲ経テ舟ヶ久保?
左の三野へ1.3㎞進む。右に神社がある。
○白髭神社(静岡市小布杉、三野300)
・木鳥居、・手洗石、・石段、・献燈2:昭和十年、・大木1、・大岩多数:神社裏:まるで磐座のようだ、
250m奥に進む。右に寺院がある。
○梅林寺バイリンジ(静岡市小布杉、三野319)
・観音、・西國、・西國三拾三所供養塔:天保二、・観音、・西國供養塔、・當國三拾三所供養塔、・善光寺如来:文化、・奉納西國三十三所供養塔、・「善光寺」(観音)文政元、・善光寺如来當國三十三所:文久元酉、・庚申塔:昭和五十五年、
これより奥に詰めると道がなくなるが、30年ほど前、この奥から歩いて大鈴山の南尾根の林道に出て大鈴山に上ったことがある。さらにそこから清笹峠へ歩いて抜けられた。その先の笹間峠までも歩けた。ちょうど前記の石道標のように清笹峠を経れば舟ヶ久保や笹間へ出られたはずだ。
・発電所貯水槽跡:
~~~
さて三野と富沢方面への分岐点のY字路まで戻る。今度は右の富沢方面道を進む。600m進むと小布杉最後の人家前(小布杉1303₋2:森氏宅)を通過する。更に250m進むと富沢へは右の道となり左は行き止まり林道になる。この左の行き止まり林道は後で紹介する。右の富沢方面へ進む。この道は林道富沢小布杉線となっている。行き止まり林道側が県道相俣岡部線である。1㎞進むと峠に到達する。ここに祠がある。
○祠:地蔵類(静岡市小布杉)
・祠:峠の地蔵尊:大正九、・祠:交通観音、・猪獣類諸霊位塔、・開通記念碑2:昭和六十一年、大久保山横峰林道:平成三年、
○峠:小布杉と相俣の間:未開通県道、一本杉、石仏2(静岡市小布杉)
この峠から北東への尾根を歩いて300m、標高差30mで富沢の頭に至る山頂から真西に標高差50m、距離250m歩くと、小布杉と相俣の間の峠に至る。
一般的には未開通県道と云われる。というのも昔は人が歩く道でも県道として認定されていたが、その後自動車道として整備されず、別ルートで自動車道が開通し、峠付近は廃道になってしまったからである。
小布杉側からの古道は推定されるに、先ほどの人家の(小布杉1303₋2:森氏宅)前から沢沿いに茶畑を詰め、植林地を上り、先ほどの行き止まり林道に出て、林道横の雑草だらけの崖をよじ登っていくことになるようだが、すでに20年前にも道跡は分からない。20年前には行き止まり林道を600mほど詰めて、右の林道の2mほどの雑草だらけの崖に取り付いて上ると、山道歩道の古道に出られた。急斜面の切通しの山道を100mも上ると、平坦なこの峠に出られるはずだったが、今は行き止まり林道自体が舗装されていてもぐちゃぐちゃの廃道で何が何だか分からない。また反対側の相俣側の行き止まり林道は舗装されていても廃道化している。それでも舗装路を進むと、舗装が切れて土道になる所が橋であり、この橋を渡って左の沢沿いの右に山道がかつてはついていたが、4月末にはうっそうと雑草が茂り行く手を阻んでいた。探索するなら冬場でしょう。かつても冬に上ったはずだ。ただ沢沿いに上りだし、しばらくして沢を左に渡るはずなのだが、これも標識なく迷い迷いだったはずで、20年以上経った今となっては、もっと悲惨だろうと思う。それでもこの峠道を紹介するのは、この山道が朝比奈街道の周辺部を含めて、数少ない古道残存部と考えられるからである。今となっては朝比奈街道中、わずかに残った貴重な古道である。もはや朝比奈街道の古道が全滅寸前な中で文化財級である。
この峠にはい石仏等がある。
・地蔵2:・朝比奈□□□三元恵十土 安永二□午八月日 村□□□□□□、・明治四十三年七月大森昇一連之
30年前、20年前ともにこの峠の地蔵は小さいものが1体だけだったはずで、2体あるということは、それ以後増えたということである。今回周辺入口は廃道だが、この峠を見る限り5年前あるいは10年前には近くの小布杉分校の遠足コースだったようで、壊れかけた手作り標識が設置されていた。
峠の東に不気味な枝ぶりの巨木が目についた。
・一本杉:地蔵の25m東、
付近の壊れた標識からすると「一本杉」というようだ。
なお一本杉のさらに東30m地点に切通しがあり、峠のようだ。
☆朝比奈街道沿いの古道について
朝比奈街道の古道残存部はメインルートではすでに消滅しているが、枝道の支線部分で残存している。といってもわずかばかりである。それは以下である。
1 羽佐間の古道:伏見氏宅前のわずか数メートルだけであるが、朝比奈川まで下れる道を整備し直すと玉露の里までつながるというのがよさそうだ。
2 清養寺から小園地蔵の閒:一応メインルートすぐ横から出ていて西又や野田沢、小園の分岐点の地蔵に出られて歴史を彷彿とさせる。保存価値が高い。
3 弓折峠の道:西又と玉取沢を結んでいる。
4 小布杉と相俣の峠道:未開通県道、小布杉側と相俣側どちらの林道の取付点も廃道同然で入りにくい。草刈と標識設置が望まれる。地蔵2体と一本杉が峠らしさを醸し出す。
5 古道:桂島の観音下から葉梨の北方への山道。
国土地理院地形図では点線記入されているが現在あるかどうかは未確認。北方と桂島境の峠手前500mは一部農道ルートのようだ。
6 ビク石登山道:古道:笹川から笹川十八石を経てビク石山頂へ、そしてビク石から瀬戸の谷へ下れるルートである。現在はハイキングコースとして利用されている。一部は古道のままではなく道が付け替えられているようだが、およそ古道が現在でも利用されて保存されている好例であり、最も古道が残っている部分である。
朝比奈街道中最も利用され今後も保存されるだろう最高に保存度の高い古道である。
7 古道:小園の神社横農道から玉取沢への道:両方とも取付きは農道で人家がある。途中から鎌道のようだが、現在でもしっかりあるかどうかは未確認。
現在はもっと西の朝比奈川本流沿いの近又、谷倉に県道が通過しているが、昔は本流沿いに道を作りにくく、東の小園と玉取沢を結ぶ峠越え道を主要街道にして利用したのだろう。
8 古道そのものは拡幅されてないが、焼津市越後島から藤枝市下当間、横内、仮宿周辺にはまだ古道の趣を残す風情が残っている。
もはや以上の部分ぐらいしか朝比奈街道のメインルートではないにしても支線の古道が残存していない。消滅は時間の問題だろう。
古道沿いの石塔類に関しては豊富である。各集落が積極的に合祀して残してきたのだろう。素晴らしいほど豊富な馬頭観音、庚申塔、馬蹄石、丸石、常夜燈、地蔵が残されている。ただし刻字に関しては読めないものが多くなっている。どんどん劣化していると言える。これでは石が早々にボロボロになりそうだ。おそらく酸性雨、急激な降水量、PM2.5、異常高温な真夏日の多さといった人為的で急激な気候変動が石塔を痛めつけるのだろう。
・あとがき
朝比奈川沿いに石仏が多いことは30年前から通りかかるたびに思っていた。20年ほど前、佐野敏郎氏の本「古道の石仏」を見て、いつか朝比奈川沿いの石仏をこのようにまとめたいという思いを抱いたことが、今回曲がりなりにも実現できてほっとした。しかし石仏の刻字はかなり読めなくなっていて、もっと早くやるべきだったという後悔もある。
朝比奈川沿いは石仏と古道でもっと観光化できるだろう。
○付録
・参拝の仕方
神社に貼られていた「参拝の仕方」を紹介する。
本当は地域性などで統一された方法や回数はないはずだが、昨今有名神社のやり方が全国的にマニュアルとして幅を利かせているようだ。どうもそのやり方のようだ。
参拝の仕方:
1 拝殿の前に立ち、最初に軽く会釈をする。
2 賽銭を奉納し、鈴を鳴らす。
3 祭神に向かい2回深く拝礼をする。(二礼)
4 次に両手の指先を合わせる。続いて右指先を少しずらして2回拍手をする。(二拍手)
右指先を元に戻し、左右の手のひらを合わせて祈願する。
5 祈願が済んだら両手を下げ、深く拝礼する。(一礼)
最後に軽く会釈をして下がる。
*この拝礼は一般的なもので、神社により異なる場合がある。出雲大社は4拍手だそうだ。
・六地蔵:wikipediaより
地蔵菩薩を6体祀ったもので、仏教の六道輪廻の思想から来る。全ての命は六種の世界に生まれ変わりを繰り返すというものである。
1 地獄道:檀陀地蔵(金剛願地蔵)、
2 餓鬼道:宝珠地蔵(金剛宝地蔵)、
3 畜生道:宝印地蔵(金剛悲地蔵)、
4 修羅道:持地地蔵(金剛幢地蔵)、
5 人道:除蓋障地蔵(放光王地蔵)、
6 天道:日光地蔵(預天賀地蔵)
の順になるが、名称は一定しない。持物と呼称も統一されていない。
・参考文献
・「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ‘96、
・「ゼンリン住宅地図」
・「2万5千分の1地形図」国土地理院、昭和50~平成10年代
・「2万分の1地形図」陸地測量部、明治20年代
・「静岡県 県別マップル道路地図」昭文社、’00
・「東海道 静岡県歴史の道」静岡県教育委員会、平成6年
・「日本石仏事典 第二版」庚申懇話会編、昭和55年
・「静岡県の中世城館跡」静岡県教育委員会、昭和56年
2015年01月04日
小山街道コヤマカイドウ~(藤枝市~焼津市:旧大井川町)
著作権者:兵藤庄左衛門
~小山街道コヤマカイドウ~(藤枝市~焼津市:旧大井川町)
藤枝市の小山街道は、田沼街道の古形態とされる。確かに今の田沼街道の横を内陸側に寄って通じている。『定本 静岡県の街道』(郷土出版社)では藤枝市藤枝宿西入口瀬戸川西堤防で東海道から分かれ吉田町小山城下までの道である。古来は色尾越イロオゴエと云われた。中世頃に使われていたようだが開設時期は不明である。歴史に見えるのは戦国末期武田勝頼と徳川家康による田中城周辺の争奪に関して行き来されたことが分かっている。
田沼意次が相良城主になり、東海道藤枝宿から相良までの街道を整備した。これが通称「田沼街道」であるが、小山街道を整備して田沼街道になった部分と、田沼街道から外れた小山街道の部分もあった。それが藤枝市兵太夫新田以西である。
ちなみに大井川を渡った後、島田市中河に出て、吉田町小山城に向かうのだが、このルートが現在不明である。私見を述べると、おそらく中河は地名からみても、大井川の中州であるので、一刻も早く大井川の支流を含めて渡りきりたいだろうから、西岸の初倉の山麓に達したのではなかろうか。特に増水しているならなおさらである。ここから山麓の道をたどり、小山城に向かうのが水対策上は得策である。
この本文を読んでいくとき、ゼンリン等の住宅地図があると道筋が分かりやすいことを付け加えておく。筆者は古い住宅地図を古本屋で1冊千数百円で購入している。新品は1冊1~2万円しますから。或は図書館で見開きページの半分以下をコピーできます。田沼街道については「古街道を行く」等を参照してください。実地調査:’14 11月。
では道筋をたどるが、初めは田沼街道と同一であり、勝草橋周辺を含めて紹介する。
~旧東海道勝草橋周辺含む、瀬戸川東岸~
・出雲大社分院(藤枝市藤枝二丁目1番地)
・新:手洗石
・常夜灯、・石
・川除地蔵×2(藤枝市藤枝二丁目2番地 老人憩いの家)
・馬頭観音
・常夜灯、・石
~旧東海道勝草橋周辺含む、瀬戸川西岸~
・秋葉公園(藤枝市志太三丁目3番地)
・常夜灯
・地蔵、4~5基(志太三丁目13番地)瀬戸川土手沿い
・勝草橋、橋の袂に田沼街道由来版、他に勝草橋由来、
・田沼街道史蹟説明版:分岐点、(志太四丁目14番地)勝草橋西岸300m下る
ここから田沼街道分岐であり、小山街道でもある。
・周辺紹介
・龍王神社
・葦中観音堂
・塩取橋蹟(青木二丁目18番地)
・説明版:江戸時代田中藩では海岸方面から運ばれてくる塩に税金をかけ、青木地区周辺に住む元締めにその責務を負わせていた。そこに架かる橋の名が塩取橋といった。今は川筋も変わり橋もない。
*田中藩:藤枝市田中に田中城跡があり、現在は西益津小学校と中学校になっているが、一部家屋が再現されている。
・田沼街道説明版(青木二丁目1番地)
小山街道についても記載されている。この辺りは小山街道がそのまま田沼街道になった辺りで、どちらも同一路だ。
~ここで県道33号線:主要地方道藤枝大井川線:藤相田沼街道に合流する~
これが現在の田沼街道である。JR東海道本線のガード下道をくぐり、古道はまたしばらくすると分岐していくが、田沼街道は東側(左)、小山街道は反対の西側(右)である。
・稲荷:祠、・石製家型道祖神(田沼四丁目5番地)
この辺りで現在の県道:田沼街道から離れ1本西側の裏道に入っていく。
・馬頭観音 昭和十二年 大石次郎宅入口前(田沼四丁目7番地)
この辺りで馬頭観音に出くわし、古道の雰囲気を感じられる始まりである。
~新幹線ガードをくぐり150m南下する~
・八幡月夜見神社より北側 (田沼1丁目12~3丁目16~4丁目4~)
JR東海道本線南側手前で旧道の名残のような道筋の道は新たな都市計画区画整理で消失したようだ。ここから現在、田沼街道と呼ばれる県道の西側に沿って南下していく。ルートは田沼1丁目12~3丁目16~4丁目4~5丁目11~新幹線ガード下~高洲7である。
小山街道は八幡月夜見神社の横の道とされていて、ちょうどそこに出る。
・八幡月夜見神社(藤枝市高洲9)
・石鳥居:昭和三十八年、
・手洗石:文化十五
・常夜灯×2:明治四十四年
・御神前燈籠:安?
・表忠碑
・石:家:道祖神
・大嘗祭記念:平成二年
・小山街道碑:平成十年:説明
神社東側道を南下。高洲南幼稚園と高洲南小学校の間の道を南下。藤枝市上水道泉町配水場の東側を南下。栃山川土手に出て橋がないので迂回するが、川向うに道はない。大洲中学校東側の道が街道の系譜を引く道と推定する。弥左衛門と大東町の境の道である。基本的に古い街道は境界線になることが多い。焼津市(旧大井川町)に入ると、また道が消失する。少し南にある西進する道を通って大井川土手に到達して一旦終わり。
ただその道より北側の道を通って大井川土手に至る道の方が神社や寺がある。
栃山川に出ると橋がないので、200m下流の代官島橋を渡る。
・地蔵:明治四十四年(大洲四丁目2番地)代官島橋袂
大イチョウもある。隣は公園。
~公園横を100m上流へ道を進み左折し南下する。大洲中学校南の弥左衛門と大東町境の道を進む。~
・伝栄寺(大洲5丁目5番地13)
道が1~2本北にずれた位置だが周辺紹介する。おそらく伝栄寺や次項目の八幡宮前を通る道は藤枝市前島や青木方向へ進む道の古道
と思われる。
・六地蔵+1、・祠:・観音3:札所等拾五番、・地蔵4、・石燈籠4、・新:地蔵:ニコニコ、・地蔵:享保十九、・新:五重塔、・石:家:道祖神、・新:竣工記念碑2、・手洗石:穴がひょうたん型、・新:良徳観音、
・庚申塔 宝暦十(大洲五丁目15番地)
県道島田大井川線沿いにある。昔次項目の八幡宮から伝栄寺に向かう道沿いにあったようだ。
・八幡宮(焼津市上泉1403)
・説明版:14世紀中葉、川除の神として祀られた。
・石鳥居:昭和十五年、・石碑2:昭和四年:~工事、昭和十八年:□□八幡宮、・常夜灯2:昭和十五年、・コンクリ鳥居2、・石鳥居:慶應元年、・常夜灯2:昭和、・石柵:大正十五年、・狛犬2:昭和十六年、・鬼瓦、・手洗石2、明治(?三)年、天(?保)四、・祠:神6~7合祀、・手洗石:平成十三年、
・蓮性寺(上泉1199)
・近代:南無法蓮華経(?参)界萬霊、・墓石,観音,地蔵を合祀の中に「馬頭観音:昭和十三年 相草号」等が見つかる。
・板碑:老農山下幸五郎君碑銘、・石碑:父母~~昭和二十九年
寺前の通りの向こうにある。
・馬頭観音:昭和三十年代
2003年3月、大洲中学から蓮性寺辺りにかけての道沿いに昭和三十年代の高さ20~30㎝の小ぶりな馬頭観音があったが、2014年11月には見当たらなかった。
多分、'03には存在しなかった新しい道路:(東名吉田ICから直接大井川を渡り旧大井川町側の県道島田大井川線に出られる新道)が小山街道より道路1本南に作られたため、事前に移転したのではなかろうか。
ここより大井川土手近くは大規模工場等になり昔の道など存在しないし、土手沿いを見ても石仏等も見当たらない。
大井川向うの吉田町側の道は不明。
・吉田町
・小山城(吉田町片岡):(展望台として近世の天守閣:犬山城を模したといわれる)がある。戦国末期に武田・徳川両軍により激しい奪い合いが行われたことで知られる。中世山城で砦はあったろうが、近世の天守閣はまったくありえない。しかし付近の三日月堀等が残存していて中世末期の歴史資料として重要である。悲劇の城としての言い伝えもある。天守閣に歴史価値はないが、内部は吉田町資料館として一見の価値がある。
・能満寺(片岡)
・遠州七不思議に数えられる「大蘇鉄オオソテツ」が有名、吉田町きっての名刹。ちょうど小山城の麓にある。
・参考資料
「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ’90、¥16000→¥3500
「’93藤枝市 ゼンリン住宅地図」¥11500→¥1200
「’94大井川町 ゼンリン住宅地図」¥8000→¥900
「古街道を行く」鈴木茂伸、静岡新聞社、
~小山街道コヤマカイドウ~(藤枝市~焼津市:旧大井川町)
藤枝市の小山街道は、田沼街道の古形態とされる。確かに今の田沼街道の横を内陸側に寄って通じている。『定本 静岡県の街道』(郷土出版社)では藤枝市藤枝宿西入口瀬戸川西堤防で東海道から分かれ吉田町小山城下までの道である。古来は色尾越イロオゴエと云われた。中世頃に使われていたようだが開設時期は不明である。歴史に見えるのは戦国末期武田勝頼と徳川家康による田中城周辺の争奪に関して行き来されたことが分かっている。
田沼意次が相良城主になり、東海道藤枝宿から相良までの街道を整備した。これが通称「田沼街道」であるが、小山街道を整備して田沼街道になった部分と、田沼街道から外れた小山街道の部分もあった。それが藤枝市兵太夫新田以西である。
ちなみに大井川を渡った後、島田市中河に出て、吉田町小山城に向かうのだが、このルートが現在不明である。私見を述べると、おそらく中河は地名からみても、大井川の中州であるので、一刻も早く大井川の支流を含めて渡りきりたいだろうから、西岸の初倉の山麓に達したのではなかろうか。特に増水しているならなおさらである。ここから山麓の道をたどり、小山城に向かうのが水対策上は得策である。
この本文を読んでいくとき、ゼンリン等の住宅地図があると道筋が分かりやすいことを付け加えておく。筆者は古い住宅地図を古本屋で1冊千数百円で購入している。新品は1冊1~2万円しますから。或は図書館で見開きページの半分以下をコピーできます。田沼街道については「古街道を行く」等を参照してください。実地調査:’14 11月。
では道筋をたどるが、初めは田沼街道と同一であり、勝草橋周辺を含めて紹介する。
~旧東海道勝草橋周辺含む、瀬戸川東岸~
・出雲大社分院(藤枝市藤枝二丁目1番地)
・新:手洗石
・常夜灯、・石
・川除地蔵×2(藤枝市藤枝二丁目2番地 老人憩いの家)
・馬頭観音
・常夜灯、・石
~旧東海道勝草橋周辺含む、瀬戸川西岸~
・秋葉公園(藤枝市志太三丁目3番地)
・常夜灯
・地蔵、4~5基(志太三丁目13番地)瀬戸川土手沿い
・勝草橋、橋の袂に田沼街道由来版、他に勝草橋由来、
・田沼街道史蹟説明版:分岐点、(志太四丁目14番地)勝草橋西岸300m下る
ここから田沼街道分岐であり、小山街道でもある。
・周辺紹介
・龍王神社
・葦中観音堂
・塩取橋蹟(青木二丁目18番地)
・説明版:江戸時代田中藩では海岸方面から運ばれてくる塩に税金をかけ、青木地区周辺に住む元締めにその責務を負わせていた。そこに架かる橋の名が塩取橋といった。今は川筋も変わり橋もない。
*田中藩:藤枝市田中に田中城跡があり、現在は西益津小学校と中学校になっているが、一部家屋が再現されている。
・田沼街道説明版(青木二丁目1番地)
小山街道についても記載されている。この辺りは小山街道がそのまま田沼街道になった辺りで、どちらも同一路だ。
~ここで県道33号線:主要地方道藤枝大井川線:藤相田沼街道に合流する~
これが現在の田沼街道である。JR東海道本線のガード下道をくぐり、古道はまたしばらくすると分岐していくが、田沼街道は東側(左)、小山街道は反対の西側(右)である。
・稲荷:祠、・石製家型道祖神(田沼四丁目5番地)
この辺りで現在の県道:田沼街道から離れ1本西側の裏道に入っていく。
・馬頭観音 昭和十二年 大石次郎宅入口前(田沼四丁目7番地)
この辺りで馬頭観音に出くわし、古道の雰囲気を感じられる始まりである。
~新幹線ガードをくぐり150m南下する~
・八幡月夜見神社より北側 (田沼1丁目12~3丁目16~4丁目4~)
JR東海道本線南側手前で旧道の名残のような道筋の道は新たな都市計画区画整理で消失したようだ。ここから現在、田沼街道と呼ばれる県道の西側に沿って南下していく。ルートは田沼1丁目12~3丁目16~4丁目4~5丁目11~新幹線ガード下~高洲7である。
小山街道は八幡月夜見神社の横の道とされていて、ちょうどそこに出る。
・八幡月夜見神社(藤枝市高洲9)
・石鳥居:昭和三十八年、
・手洗石:文化十五
・常夜灯×2:明治四十四年
・御神前燈籠:安?
・表忠碑
・石:家:道祖神
・大嘗祭記念:平成二年
・小山街道碑:平成十年:説明
神社東側道を南下。高洲南幼稚園と高洲南小学校の間の道を南下。藤枝市上水道泉町配水場の東側を南下。栃山川土手に出て橋がないので迂回するが、川向うに道はない。大洲中学校東側の道が街道の系譜を引く道と推定する。弥左衛門と大東町の境の道である。基本的に古い街道は境界線になることが多い。焼津市(旧大井川町)に入ると、また道が消失する。少し南にある西進する道を通って大井川土手に到達して一旦終わり。
ただその道より北側の道を通って大井川土手に至る道の方が神社や寺がある。
栃山川に出ると橋がないので、200m下流の代官島橋を渡る。
・地蔵:明治四十四年(大洲四丁目2番地)代官島橋袂
大イチョウもある。隣は公園。
~公園横を100m上流へ道を進み左折し南下する。大洲中学校南の弥左衛門と大東町境の道を進む。~
・伝栄寺(大洲5丁目5番地13)
道が1~2本北にずれた位置だが周辺紹介する。おそらく伝栄寺や次項目の八幡宮前を通る道は藤枝市前島や青木方向へ進む道の古道
と思われる。
・六地蔵+1、・祠:・観音3:札所等拾五番、・地蔵4、・石燈籠4、・新:地蔵:ニコニコ、・地蔵:享保十九、・新:五重塔、・石:家:道祖神、・新:竣工記念碑2、・手洗石:穴がひょうたん型、・新:良徳観音、
・庚申塔 宝暦十(大洲五丁目15番地)
県道島田大井川線沿いにある。昔次項目の八幡宮から伝栄寺に向かう道沿いにあったようだ。
・八幡宮(焼津市上泉1403)
・説明版:14世紀中葉、川除の神として祀られた。
・石鳥居:昭和十五年、・石碑2:昭和四年:~工事、昭和十八年:□□八幡宮、・常夜灯2:昭和十五年、・コンクリ鳥居2、・石鳥居:慶應元年、・常夜灯2:昭和、・石柵:大正十五年、・狛犬2:昭和十六年、・鬼瓦、・手洗石2、明治(?三)年、天(?保)四、・祠:神6~7合祀、・手洗石:平成十三年、
・蓮性寺(上泉1199)
・近代:南無法蓮華経(?参)界萬霊、・墓石,観音,地蔵を合祀の中に「馬頭観音:昭和十三年 相草号」等が見つかる。
・板碑:老農山下幸五郎君碑銘、・石碑:父母~~昭和二十九年
寺前の通りの向こうにある。
・馬頭観音:昭和三十年代
2003年3月、大洲中学から蓮性寺辺りにかけての道沿いに昭和三十年代の高さ20~30㎝の小ぶりな馬頭観音があったが、2014年11月には見当たらなかった。
多分、'03には存在しなかった新しい道路:(東名吉田ICから直接大井川を渡り旧大井川町側の県道島田大井川線に出られる新道)が小山街道より道路1本南に作られたため、事前に移転したのではなかろうか。
ここより大井川土手近くは大規模工場等になり昔の道など存在しないし、土手沿いを見ても石仏等も見当たらない。
大井川向うの吉田町側の道は不明。
・吉田町
・小山城(吉田町片岡):(展望台として近世の天守閣:犬山城を模したといわれる)がある。戦国末期に武田・徳川両軍により激しい奪い合いが行われたことで知られる。中世山城で砦はあったろうが、近世の天守閣はまったくありえない。しかし付近の三日月堀等が残存していて中世末期の歴史資料として重要である。悲劇の城としての言い伝えもある。天守閣に歴史価値はないが、内部は吉田町資料館として一見の価値がある。
・能満寺(片岡)
・遠州七不思議に数えられる「大蘇鉄オオソテツ」が有名、吉田町きっての名刹。ちょうど小山城の麓にある。
・参考資料
「定本 静岡県の街道」郷土出版社 ’90、¥16000→¥3500
「’93藤枝市 ゼンリン住宅地図」¥11500→¥1200
「’94大井川町 ゼンリン住宅地図」¥8000→¥900
「古街道を行く」鈴木茂伸、静岡新聞社、
2014年03月22日
静岡市市街地内、静岡駅北西部
○静岡市市街地内、静岡駅北西部
調査 ’13 11~12月を含む版
まだ未調査地や不十分な個所が多いですが、いったん公開します。将来のんびりと改訂していきます。
・用語説明
・国、県、市=国、県、市指定、・有、無=有形、無形、・登=登録、・文=文化財、・天=天然記念物、・重=重要、・民=民俗、・石=石製、・家=家型、・新=近代から現代にかけて作られた新しいものと推定されるもの、・古=新しくなく古そうなもの、・欠:破損欠落しているもの、・馬頭=馬頭観世音菩薩、・コンクリ=コンクリート製、(2)=2基、
・古い用語説明
廿=20、廿の縦線3本=30、等=塔、歳‣天‣月日=年、
美良または羊良=養(美や羊ではなく羊の下は大であり美ではなく横線3本である。狼という字に似ているが、その字がパソコンで出てこない。そういった字は多く他の現代的な字に切り替えたり注を施す)、クイズ:ちなみに養がなぜ美(横線3本)や羊(下は大)と良なのかはちょっと考えるとすぐ分かります。このように漢字の部分を上下左右に組み替えることは石塔への刻字ではよくあります。彫る時の字のバランスを考慮した石工さんたちの工夫です。ちなみにある石工さんはこういう字をお寺さんの字と言っていましたが寺院で使う字ではありません。この前見た字では政を上に正、下に政の正抜きの字を彫ったものを見ました。
*「石仏事典」類を参照してください。年号や干支もこれで分かります。
・住所について
なお住所は正確に分からないものは多く、隣や付近の住居の番地号を用いているものが多い。
○静岡市市街地内、静岡駅北西部
・宝台院(常盤町2丁目13‐2)
・宝台院ほうだいいん、金米山宝台院:説明版:宝台院は、徳川家康の側室で二代将軍秀忠の生母西郷の局サイゴウノツボネ(お愛の方)の菩提寺である。西郷の局は27歳で家康に仕え、翌天正7年(1579)4月、家康の第3子秀忠を生んだ。家康38歳の時である。この頃家康にとっては、浜松城にあって、三方原の合戦、設楽原合戦、小牧長久手の合戦と、戦に明け暮れたもっとも苦難な時代であった。西郷の局は、家康の浜松城時代に仕え、苦しい浜松城の台所を仕切った文字通り糟糠ソウコウの妻であったということができる。天正14年12月、西郷の局は、長かった苦難の浜松時代を終え、名実共に東海一の実力者となった家康と共に駿府入りした。家康の陰の立役者として、献身的に仕えた西郷の局は、駿府入りと共に浜松時代の疲れが出て、天正17年5月19日、38歳の短い生涯を終わった。後年、将軍職に就いた秀忠は、母のために盛大な法要を営み、その霊を慰めた。以来、徳川300年の間、この宝台院は、徳川家の厚い保護を受けたのである。
寺宝:白本尊如来像:重要文化財、他多数。静岡市。
・徳川慶喜公謹慎之地:宝台院と徳川慶喜公:説明版:明治元年七月、第十五代将軍慶喜公、御謹慎の身となり、同月十九日水戸を出発して銚子港に到着し、同月二十一日蟠龍艦に乗船し、同月二十三日に清水港に到着しました。海路にて移動したのは、上野彰義隊の戦いの興奮も冷めない江戸を通ることが、極めて危険なことだったからでしょう。この時目付の中台信太郎(のち駿府藩町奉行)がこれを出迎え、また精鋭隊頭松岡万以下五十名の厳重な護衛がついて駿府に向かいました。慶喜公が討幕派、旧幕臣の双方から命を狙われる重要人物であった事情に加えて、無政府状態とも言うべき当時の駿府の町の状況がこのような物々しい警護体制を必要としていました。一行は当日夕刻には宝台院に入りましたが慶喜公の駿府移住は秘密裏に行われ町民には一切知らされていませんでした。慶喜公の駿府入りが町触れで知らされたのは、その五日後の二十八日のことでした。尚、宝台院を慶喜公謹慎の場所に選んだのは元若年寄大久保一翁でした。彼は駿府町奉行の経験もあってこの町を熟知しており、徳川第二代将軍秀忠公の生母西郷局が葬られた宝台院こそ慶喜公が落ち着いて過ごせる場所と考えたのでしょう。以来、精神誠意慎をされ翌明治二年九月二十八日、謹慎が解け十月五日紺屋町の元代官屋敷(現在の浮月楼)に移転されるまで、約一年余りを当山で起居されました。この謹慎の部屋は十畳と六畳の二室で、十畳の間を居間、六畳の間を次の間として使用し、当時渋沢栄一や勝海舟と面会されたのもこの六畳間でした。明治元年八月十五日、藩主亀之助(家達公)が駿府に到着した時も、先ず宝台院に参上し御霊屋に参礼の後、やはりこの部屋で対面したということです。家達公は七間町三丁目を曲がり、御輿で大手門より入城されましたが、当時まだ七歳というお年でした。現在の宝台院には、慶喜公の遺品として、キセル、カミソリ箱、急須、火鉢、本人直筆の掛軸、居間安置の観音像が残っております。静岡市。
・西郷の局供養塔、・キリシタン灯篭、・百度石、・尺八碑:明治二十三年、・板碑:燈臺寄附連名:明治三十二年、・板碑:潮田良一之碑:昭和二十二年、・板碑:俳諧師かしく坊の辞世、・新:延命地蔵尊:駿河一国百地蔵尊第三十一番、祠:稲荷大明神、・新:西国九番札所:観世音菩薩安置成田山不動尊、手洗石:長野縣信濃国諏訪郡冨士見□、・狛犬2、・地蔵、・観音、・不動明王、・新:地蔵2、・石:三○:?石垣用石、・新:狛犬2:大正十三年、・新:観音:レリーフ、・石碑:アソカ幼稚園園歌:平成二十一年、
・家康の身代わり観音:阿弥陀如来立像のこと、かつては像に傷がついていたが現代に修理したため傷は消失した。家康は本像を合戦に持って行き安置しており、自分の近くに置いた像に矢が刺さり身代わりになったと考えたというが、伝説なのか史実なのかは不明。しかも傷がなくなったそうなので、いかなる傷だったのかもなおさら不明。
ちなみに静岡市葵区、宝台院のホームページを調べると、徳川家康関係の宝物(阿弥陀如来立像、家康公の自画像、真の太刀、家康公筆「安元御賀記手習」)、三代将軍家光公筆「遠山月」二代将軍秀忠の生母・西郷の局の墓、徳川慶喜公謹慎之地、かくし坊の辞世があり、その中にキリシタン灯篭もある。説明文:「キリシタン灯篭:茶人として有名な古田織部が制作し駿府城へ奉納、徳川家康公の侍女・ジュリアおたあが信拝したという灯篭です。この灯篭は城内より静岡奉行所を経て宝台院へ移されました。」とある。
ジュリアおたあをウィキペディアで調べると生涯概略の他、文章末に「~なお、駿府時代には灯篭を作らせ瞑想していたと言い伝えられており、そのキリシタン灯篭は、現在は宝台院に移されている。」と書かれている。
これらはいかなることでしょう。日本最初のキリシタン灯篭発見が宝台院で1923(対象12)年とすると、ジュリアおたあ信拝説はそれ以後と思われますが、いったいどういう証拠があるのでしょうか。分かりません。
*私見での「キリシタン灯篭の疑問点と保存」については別項目を参照してください。文章が長くなるのでここでは割愛します。
・鎮火稲荷神社(本通5丁目1‐5)
・稲荷(2):昭和廿三年、・鳥居:コンクリ、
・津島神社(梅屋町4‐1)
・鳥居:コンクリ、・狛犬(2):昭和54年、
・説明版:津島神社:祭神:当神社の御祭神:素戔嗚尊は日本神話の中で伊弉諾尊、イザナミノミコトの御子で天照大神の□神に当たられ、荒々しい剛直な性格の神で、天照大神を天の岩戸に~~させ給われ、高天原から地上に追放されました。出雲で八岐のおろちを退治されて奇稲田姫と結婚され大蛇の尾から出た天叢雲剣~~し献上されました。また新羅に渡られ船材の樹木を持ち帰り~植林の道を教えられたと伝えられております。また、大国主命は素戔嗚尊の御愛婿であられ、出雲の地で親子二代に亘って国土の経営、産業開発にお力をいたされ、災厄と疫病を除く御徳と受福の神様として世に知られております。神話では暴風神、英雄神、農業神として語られ、氷川神社、八坂神社、熊野大社などの御祭神でもあります。
天王さん:津島神社は古くは津島牛頭天王社と言い、今日でも一般に「お天王さん」と尊称されております。これは日本には上古から民俗宗教としての祖神信仰がありましたが、仏教が伝来して次第に日本化して、その結果崇神、崇仏思想が接近し、後年明治政府が神仏分離令を発布するまで、神宮寺、寺院鎮守など神社とお寺が同居していたことと関係があるように思われますが、インドの祇園精舎の守護神であるとか、新羅の牛頭山に留まっていた素戔嗚尊の御神霊を勧請してお祀りしたとか諸説があってはっきりしません。
由緒:神社年鑑によれば天明5年(1785)創建、明治11年公称を許可とあります。古老からの言い伝えで、昔疫病が流行り疫病除けの神として勧請したと言われておりますが、歴史年表を見ると。天明3年の頃には、「7月浅間山噴火、死者2万人に及ぶ。この年未曽有の凶作、奥羽の死者数十万人に達する」 天明4年は「この年夏、秋、米価騰□して諸民飢餓し、秋よりは疫病流行して死者が多い。」 天明5年「奥州三春、凶作、琉球凶作」 天明6年「江戸開府以来の大水で死者、家屋破損が多い。この年大凶作、収穫三分の一」などとあり、疫病除けの神として素戔嗚尊を勧請したものであろうと推測されます。
沿革:天明5年 創建、明治11年 公称許可、昭和9年 本殿、拝殿、社務所等造営、昭和15年1月15日静岡大火にて焼失、昭和15年仮社殿造営、昭和30年 空襲の罹災を免れる。その後現在地に移転。昭和44年 新社殿造営、現在に至る。平成11年6月吉日。
・八朔神社(本通2丁目1‐3)
・木鳥居、・手洗石、
・静岡神明宮(屋形町13)
・石鳥居:大正十五年、・常夜灯(2):大正十五年、・石柵:大正十二年、・狛犬:大正十四年、・神社名碑:昭和八年、・道路開鑿碑:明治四拾年、
・東本願寺静岡別院(屋形町10)
・新:堂、・新:木石堂、
・大林寺(安西4丁目93)
・梶原景季と景嘉の墓:五輪塔:土水火風空、・祠:白山妙理大権現、・祠、・山門:仁王像(阿吽)、裏に風神と雷神像、・新:水子地蔵、・新:六地蔵、・石燈籠、・観音、・中世末墓石、江戸初期墓石(2)、観音風墓石(2)、・青面金剛供養塔:天明二、・法華千部塔:文政二、
・説明版:縁起:古記録によると当山は今から約800年前、鎌倉時代初期当國庵原郡高部村大内にあり、大淋寺(天台宗)といい大林寺殿贈四品榮昌福寿桑道場妙開大禅定門、姓平氏葛原親王第十四代梶原信濃守従四位少将景義四男刑部少輔朝景卿建仁元辛酉(1201)年5月3日卒を最初の開基としている。文永元(1264)年12月18日仏殿を今の柚木町に建立している(駿河記)。時移り戦国争乱期、北条早雲殿(1459)の命により、武田、今川の動静を探るため旧東海道の見張所としての城塞の寺を現在の場所に草創したのである。七堂伽藍は一万の大軍を収容でき、山門が柚木町の堤上にあり、その下に尼寺と墓地があった。寺格は法地寺中5反6畝3歩安西内新田、除地5反3畝3歩安西外新田、雑地10反あり(駿河志料)。
その後曹洞宗通幻派最乗寺門下総世寺末となり同寺五世天祐宗根和尚に嗣法する鳥道長鯨和尚天文12(1532)年癸卯12月10日寂を開山としている。三世好山宗禅和尚は慶長年間(1596)徳川家康より法門の聴聞あり。四世明室温察和尚(1624)は梶原源太景季、景嘉の墳墓を改築し、六世揚山和尚(1704)は末寺龍津の中興で、七世大鳳和尚(1688)貞享3年梵鐘鋳造の功をなし良富院の開山となる。九世槐國萬貞和尚(1716)は最勝、定林に歴住し海松、円城、雨林の3か所の開山であり、卍山道白禅師の法嗣で、徳川吉宗の釣命により、官刹長崎の皎台寺に転住し、大同庵、金泉寺を開き語録二巻を著している。十世古岳日峻、十四世一了玄画和尚も皎台寺に当寺から普住した。特に日峻は書物に参同契測海があり、海門及び月舟宗胡、独庵玄光、(辟と水で上下)山の高泉、黒瀧の潮音、槐國と共に参じた中世稀にみる高僧である。二十九世祖鳳光禅和尚は洗耳寺に歴住し明治40年七堂を再建したが、昭和20年6月19日戦火により焼失している。昭和34年三十一世光雄和尚が本堂、位牌堂、庫裏を再築している。尚開基より光雄和尚まで5回兵火に遭っている。また寺の所在は大内→安西→柚木→安西(正保元(1644)年町奉行落合氏により)に戻っている(寛政寺記及び駿河記) 昭和60年12月18日 大林寺 三十一世大鑑光雄記
・説明版:大林寺墓塔群:○梶原源太景季・景嘉の墓:源頼家(1182)の母政子の父北条時政の家来家来梶原景時(1200)が滅ぼされ、その門葉景嘉が駿河殿(徳川忠長1602)に仕え寛永9年(1632)壬申1月21日歿した。本府古図の安西4丁目南にその姓名がある。大内梶原堂の条によれば太田美濃守入道資正二男が梶原の養子となり源太政景といった。景嘉はこの後葉である。(駿河志料他)
○落合能登守小平次道次の墓(1652):長篠城攻防戦の勇者鳥居強右衛門の磔に感動した落合佐平次道久は、自分の指物に磔の図を描いて出陣し、家康に見出され、後に徳川頼宜に従って駿河衆となり、養子の道次は江戸幕府に出府し駿河奉行として由比正雪を召し捕り功あり。寛永17年より承応元年まで13年奉行として活躍した。慶安5年8月9日寂。
○安鶴の墓(1872):『諸国畸人傳』(石川淳)『駿府の安鶴』(江崎惇)により全国的に有名。
○舟川斎寺西源正勝の墓:幕府旗本天神真陽流柔術指南医士。
○小沢久七の墓:長崎で勉強し漆器界の発展に尽力した。
○小出東嶂の墓(1823~1889)画家福田半香の弟子であり書画に通じ明治6年静岡新聞を刊行す。
協力者:~略~、昭和60年12月18日、大林寺31世大鑑光雄代
・延命地蔵堂(安西5丁目114)
・堂、・秋葉山常夜灯、
ここから川根筋に抜ける川根(秋葉)街道の起点と考えられている。
*「川根(秋葉)街道」については、『古街道を行く』鈴木茂伸(静岡新聞社)をご覧ください。ただこの本すでに絶版ですので、静岡県内図書館にあるので検索するか、静岡県内の古本屋にもないので、古本屋にリクエストしていって取り扱ってもらえるとよいでしょう。
・柳町水神社(柳町135)
・木鳥居、・手洗石、・社、
・曙稲荷神社(若松町15)
・石柵:昭和十年、・石鳥居:昭和十年、・石燈籠(2):昭和十年、・石燈籠(2):昭和四十年、・稲荷(2)、・稲荷(2)、・祠、・手洗石、
・八雲神社(北番町84)
・神社名碑:昭和四十六年、・八雲神社碑、・新:狛犬(2)、・石鳥居:明治三十四年、・手洗石、・石燈籠(2):明治三十年、・北番町公園碑:昭和46年、・石塔:庚申、・石塔?、・石塔?:文政六癸未年、・若松町制四十周年:昭和三十九年、
・八雲神社御由緒:鎮座地:静岡市□番町八雲~、祭神:~~~、祭□:例祭、~~~~、創立年月日:口伝によれば応永3年創立と伝承。
往古は牛頭天王という。当国総社浅間神社に祀られていたが、戦禍に遭い別当職が簑に納め安倍郡大岩村に遷し大岩村村民の氏神として祭祀を引き継ぎたり。その後寛永の頃駿府城北番詰所の番士この地に居住し牛頭天王を崇敬し為に寛永3年大岩村よりこの地に勧請し宝永3年真言宗建穂寺末寺別当牛頭山宝積寺中興願成院智寂法印氏神として祭祀を承継す。明治3年神仏混淆廃止令により八雲神社と改称、同8年2月村社に列格、同43年6月18日神饌幣帛供進指定を受く。敗戦により国家の庇護を離れ、神社本庁設立に伴い、静岡県神社庁所属となり、氏子により祭祀を継承、現在に至る。350年を記念して建立。~以下略~
・桜森稲荷神社(土太夫町7)
・鳥居:コンクリ、・新:燈籠、・古:燈籠、・手洗石、・石:家:道祖神、
・二十六番札所、水月院(安西1丁目24)
十一面観音菩薩、
・説明版:水月堂御縁起:水月堂(通称おはつかさん)は静岡市安西1丁目南裏に位置し十一面観世音菩薩を安置し、新選府辺観音霊場(新西国)三十三か所巡礼札所中第26番にして本尊は鎌倉初期の名匠運慶の作と伝えられ国宝的存在でありました。しかし戦災(昭和20年6月20日)で焼失してしまいました。元亀年間、今を去ること400有余(405)年前、安倍郡籠鼻(今の井宮町西北部)の圓皆寺(現在は廃寺)の住僧宗文の創建で今川家の臣福島淡路守の夫人然正院智現妙本大姉の開基と伝えられています。毎月20日を以て御縁日と定め毎年3月には僧侶も招き特別大法要を続けております。 平成18年3月20日、水月堂奉賛会
・住吉神社(一番町25)
・手洗石:奉献願主府内(絞?)仲間、常夜灯:昭和六年、・石鳥居:昭和五十年、・石燈籠(2):住吉大神宮御宝前 文化十年と大正四年、・石碑:神饌幣帛供進指定中津神社 昭和十六年、
中津神社とは何? 昭和16年号なので静岡空襲か大火で消失し、戦後住吉神社と併合され、たのか?
・顕光院(研屋町45)
・馬頭(3):馬頭観音建立由来碑:昭和13年1(6)月15日正午過ぎ新富町、~~~不明
*撮影した写真不鮮明で判読困難、再度やり直す気がないのでこのままです。ごめんなさい。
おそらく内容は静岡大火と静岡空襲による戦火の災害供養のため馬頭観音を設置したと言いたいようです。
・地蔵、・南無阿弥陀仏:昭和二十六年、・地蔵(3)、・板碑:大正九年、・新:六地蔵、・三界萬霊等、・無縁堂、・平和観音堂、・庚申:文化四、・庚申:寛政二、・新観音、・新:灯篭(3)、・新:駿河一国百地蔵第一番開運成就地蔵尊、・奉納弘法大師四国八十八所 国々諸々神社供養 秩父三十三所 一国三十三所 坂東三十三所 文政四、
・くがたか橋の碑(追手町12)
かつての外堀沿いの橋の欄干だったのか。
・石塔(城内町1‐2)静岡聖母幼稚園前
全く刻字等有無不明
・石碑:青葉小(追手町4)
廃校になった青葉小学校の記念碑。
・校址碑:静岡第二尋常小學校 明治34年新設、静岡城内東小學校 大正2年 校名変更、静岡城内東尋常高等小學校 大正13年 校名変更、静岡城内東尋常小學校 昭和8年 校名変更、城内東國民學校 昭和16年校名変更 昭和20年9月5日廃校、青葉小学校 昭和29年4月設立、平成19年3月閉校、
・石碑:城濠用水 土地改良区記念碑(追手町4)
・説明版:城濠用水由来:城濠の誕生は慶長12年
~写真不鮮明で判読あきらめ~
昭和53年5月、城濠用水土地改良区
・石碑:葵文庫跡(追手町4)
・説明石碑:由来:葵文庫は大正8年静岡に縁の深い徳川家の記念事業として計画され、同14年3月28日徳川家の家紋を館名としてこの地に開館した。その特色は、江戸幕府旧蔵書の一部である「葵文庫」と3代県令関口隆吉収集にかかる「久能文庫」にあった。以来県立葵文庫は県民の図書館として、また全国的にも貴重書の宝庫として注目されその発展をみた。昭和44年市内谷田に新館が建設され、静岡県立中央図書館として移転すると、葵文庫は新たに静岡市立図書館として再出発した。しかし施設の老朽化により、昭和59年市内大岩に新築移転したため、県民に親しまれた建物は取り壊された。~~~不明
*撮影した写真に石碑終盤の文字が写っていなかったので不明としました。撮影し直すなりもう一度見に行って判読するなりの気にならないので一旦終了します。ごめんなさい。
・駿府城(駿府城公園)
・説明版:駿府城は外堀、中堀、内堀の三重の堀を持つ輪郭式の平城です。本丸を中心に回字形に本丸、二の丸、三の丸と順に配置され、中央の本丸の北西角には、五層七階(外観五層内部七階)の天守閣がありましたが、寛永十二年(1635)に焼失しています。駿府城が城郭としてその姿を見せるのは天正十三年(1585)に徳川家康が築城を開始したことに始まります。この天正期の駿府城は現在の城跡に比べると一回り小さいと考えられますが、詳細は不明です。この後江戸幕府を開いた家康が慶長十二年(1607)将軍を退き、駿府に移り住むために天正期の駿府城を「天下普請」として拡張、修築しました。当時の駿府は江戸と並ぶ政治の中心地として重要な役割を果たしていました。 平成8年3月 静岡市
・巽櫓(駿府城公園)内堀沿い たつみやぐら
巽櫓は駿府城二の丸の南東に位置する木造矩折三層二重の建物です。この巽櫓は寛永十二年(1635)城下から出た火によって延焼焼失し、寛永十五年に新たに建設されたといわれています。巽とは十二支で表した方位で辰と巳の間、即ち南東の方角をいいます。また櫓とは、一、武器を納めておくため、一、四方を展望するために設けた高楼、の役割をしたものです。巽櫓の復元は、「駿府城内外覚書」や「駿府御城惣指図」の資料をもとにしており、3年の歳月をかけ、平成元年3月に完成しました。 静岡市
・東御門(駿府城公園)ひがしごもん
東御門は駿府城二ノ丸の東に位置する主要な出入口でした。この門は二ノ丸堀(中堀)に架かる東御門橋と高麗門、櫓門、南・西の多門櫓で構成される枡形門です。東御門の前が安藤帯刀タテワキの屋敷だったことから「帯刀前御門」また、台所奉行の松下淨慶にちなんで「淨慶御門」とも呼ばれ、主に重臣たちの出入口として利用されました。東御門は寛永十二年(1635)に天守閣、御殿、巽櫓等と共に焼失し、同十五年に再建されました。復元工事は、この寛永年間の再建時の姿をめざし、復元したものです。 平成八年三月 静岡市
・坤櫓(駿府城公園)内堀沿い ひつじさるやぐら
木造二層三階。家康築城時に武器庫として利用される。寛永12年(1635)の火災で焼失。2014年4月に復元工事完了し1階は公開される。2階は非公開。
・駿府城公園内:発掘された石垣、公園内地面下には戦国期の今川館跡遺跡
駿府城は古くは今川館があったと推定される。その後徳川家康により隠居城となり、一時は大名が治めたこともあるが、長くは代官の行政所となり一部を使用したようだ。使わない部分はかなり荒廃した箇所もあるようだ。江戸時代中期以降は狐が住んでいたほど荒れていたようだ。明治期に内堀を埋立て軍隊駐屯地になった。今は公園。発掘で徳川期の石垣や使用道具類、今川氏館跡等が出土している。しかも焼かれた物が出土している。武田氏により滅ぼされ今川館は焼失したと思われるが、そのとき焼かれた物かどうかは不明。
天守閣は家康が建造したが女中の不手際で失火焼失、再建されたがまた焼失。代官時代には天守閣はなかったようだ。またそれ以外の建物や施設も代官時代に使用が縮小していったようだ。
現在みられる駿府城外側の石垣は近代以降、幾たびも修復されているので全てが江戸時代のものというわけではない。ただ一部残存しているのも確かで、家康が築城する際には全国の大名を動員したので、石垣に各大名のしるしがつけられているものがある。また各時代により石垣の積み方に特徴が出ている。
*石垣の積み方についてはネットや図書で検索してください。
・家康お手植えの蜜柑ミカンの木、
・家康銅像、
・東海道中膝栗毛弥次喜多像(追手町)内堀沿い
・説明版:十返舎一九と「東海道中膝栗毛」: 「東海道中膝栗毛」の作者十返舎一九(1765~1831)は、ここ駿河の府中(静岡市)出身で江戸文学における戯作者の第一人者であり、日本最初の本格的な職業作家といえます。1765年駿府町奉行同心、重田与八郎の長男として両替町で生まれました。本名は重田貞一、幼名を市九といいます。1783年大阪へ行き、一時は近松余七の名で浄瑠璃作家としても活躍しましたが、その後士分を捨て1794年再び庶民文化華やかな江戸に戻って戯作に道に専念し、多くの黄表紙や洒落本などを書きました。
「東海道中膝栗毛」は1802年初編(初編は「浮世道中膝栗毛」のち改題)以降毎年一編ずつ8年にわたって書き続け、1809年全8編を完結しました。この膝栗毛は爆発的人気を呼び、休む間もなく「続膝栗毛」の執筆にとりかかり、1822年の最終編までに実に21年間に及ぶ長旅の物語として空前の大ロングセラーとなりました。
物語は江戸神田の八丁堀に住む府中生まれの弥次郎兵衛(左の像)と、元役者で江尻(現清水市)出身の喜多八(右の像)という無邪気でひょうきんな主人公二人が江戸を出発して東海道を西へ向かい伊勢を経て京都、大坂へと滑稽な旅を続ける道中記で、今でも弥次喜多道中といえば楽しい旅の代名詞となっています。
当地の名物として安倍川餅やとろろ汁も登場。また府中では夜は弥勒手前の安倍川町(二丁町といった)の遊郭へ出かけたり、鞠子(現丸子)では、とびこんだ茶屋の夫婦喧嘩に巻き込まれ、名物とろろ汁を食べるどころか早々に退散したといった話が語られています。
一九は1831年没、享年67歳。墓所は東陽院(現東京都中央区勝どき)にあります。ここ府中は江戸から44里24町45間(約175㎞)19番目の宿です。
2002年2月、静岡市
・甘夏みかんの木(追手町)内堀沿い
・わさび像「わさび漬発祥の地」(追手町)内堀沿い
・説明版:わさびは370年前わが国で初めて安倍川上流有東木で栽培された。わさび漬けは今から200余年前駿府のわさび商人によってはじめて考案され幾多の人に受け継がれて改良進歩した。特に明治以後交通機関の発達により長足の発展を遂げたのである。ここに明治百年を期し先覚者の偉業を偲び感謝の誠を捧げて、この碑を建つ。昭和43年5月23日、静岡県山葵漬工業協同組合
・このわさびの像はコンクリ製で芋虫に似ていて一種のゆるキャラっぽい。あるいはシュールというべきか。宇都宮市に餃子像があるのならば静岡市にはわさび像です。
・現代アート像:指人形(追手町)内堀沿い
指人形 The fingerdoll 制作:細谷泰玆 Yasuji Hosoya 1983年
・石碑:静岡学問所跡(追手町)内堀沿い
・説明版:静岡学問所は明治維新後駿府に移ってきた徳川家(府中藩)により、藩の人材育成を目的として駿府城四ツ足御門にあった元定番屋敷内(現静岡地方合同庁舎付近)に明治元(1868)年府中学問所として創設されました。学問所には翌2年駿府が静岡に改められたことにより静岡学問所となりましたが、明治5年8月学制の施行とともに閉鎖されました。この学問所には向学心に燃える者は身分を問わず入学が許可され向山黄村、津田真一郎(真道)、中村正直(敬宇)、外山捨八(正一)など当代一流の学者により国学、漢学とともにイギリス、フランス、オランダ、ドイツの洋学も教授されました。またアメリカ人教授E.W.クラークは専門の理化学の他哲学や法学なども教えました。廃校後洋学系の教授の多くは明治政府に登用され開成学校(現東京大学の母体)の教授など学界や官界で活躍しました。静岡学問所の歴史は短期間でしたが、日本の近代教育の先駆けをなし、明治初期の中等、高等教育の最高水準の学府でありました。 静岡市教育委員会、平成元年12月
・石碑:戸田茂睡生誕之地(追手町100)とだもすい
1629~1706年、江戸時代前期の歌学者。父は徳川忠長(徳川3代将軍家光の弟、駿府城主、改易され謹慎の後自害)の付け人で、駿府城内で生まれた。
・駿府城四足御門跡(追手町)よつあしごもん
・説明版:駿府城南辺の西寄りの箇所に設けられた出入口で、東側の大手御門オオテゴモンと並び、東海道筋から城へ入る重要な出入口の一つです。三の丸堀を土橋で渡って、左手へ直角に曲がり渡櫓門ワタリヤグラモンから城内へ入る構造になっていました。 静岡市教育委員会
・大手‣追手門(追手町)
・説明版:駿府城大手御門:駿府城内に入る正面出入り口です。三の丸堀を土橋で渡って、右手へ直角に曲がり渡櫓門ワタリヤグラモンから城内へ入る構造になっていました。歩道には渡櫓門の柱礎石の位置が記されています。 静岡市教育委員会
・石垣修復説明版(追手町)
・説明版:駿府公園二の丸堀(中堀)石垣災害復旧工事完了のお知らせ:平成21年8月11日駿河湾で発生した震度6弱の地震により、駿府公園二の丸堀(中堀)の石垣が崩落しました。平成22年1月6日工事着手、平成23年3月15日工事完了、石垣の構造を説明した「石垣モデル」が駿府公園内、富士見芝生広場に設けてありますのでぜひ一度ご覧ください。静岡市。
崩落前と崩落直後、復旧後の3つの写真が並置されているので、見た目では一目で分かるようになっている。なお石垣は見えない内部構造も重要なので石垣モデルを見てください。
・静岡県庁本館(追手町9)
登録有形文化財、
・静岡市役所本館ドーム(追手町5)
登録有形文化財、
・教導石(追手町)県庁市役所前バス停
・説明版:静岡市指定有形文化財(歴史資料) 教導石きょうどうせき、指定年月日:昭和59年7月17日、所在地:静岡市追手町、所有者:静岡市、「教導石」は、明治という新しい時代を迎え、「富や知識の有無、身分の垣根を越えて互いに助け合う社会を目指す」との趣旨に賛同をした各界各層の人たちの善意をもって明治19(1885)年7月に建立されました。正面の「教導石」の文字は、旧幕臣山岡鉄太郎(鉄舟)の筆になり、本市の明治時代の数少ない歴史遺産の一つとなっています。碑の正面上部には、静岡の里程元票(札の辻)から県内各地、及び東京の日本橋や京都三条大橋までの距離を刻んであります。教導石建立の趣旨に従って碑の右側面を「尋ル方」とし、住民の相談事や何か知りたいこと、また苦情等がある人はその内容を貼り付けておくと、物事をよく知っている人や心ある人が左側面の「教ル方」に答えを寄せる、というものでした。尋ね事などのほか、店の開業広告、発明品や演説会の広告から遺失物や迷子をさがす広告なども掲示してよいことになっていました。全体の高さ:207㎝、台石の幅:107㎝、本体:高さ:177㎝、正面幅:44㎝、側面幅:38㎝、静岡市‣静岡市教育委員会
・正面:「教導石、里程(?田谷、略を上下に書く)表、駿河國沼津宿拾五里拾町余、同吉原宿拾里拾九町余、 同大宮町拾壹里拾六町、同興津宿四里拾貮町余、同清水町三里六町余、同根古屋村貮里拾九町余、同藤枝宿五里拾町余、遠江國静波町拾里貮拾九兆余、同相良町拾貮里貮拾町余、同掛川宿拾貮里拾七町余、同森町村拾六里三町余、同横須賀町拾六里三拾町」
右:「尋ル方、静岡里程元票 各地距離、東京日本橋四拾六里拾町余、神奈川縣廰三拾九里廿六町余、山梨縣廰貮拾七里拾七町、伊豆相模國堺貮拾里壹町余、伊豆國下田町三拾五里拾五町、同熱海村貮拾三里四町余、同修善寺村拾壹里二拾町、同韮山町拾九里三町余、同三島宿拾六里三拾町余」
*撮影写真不鮮明で判読困難、やり直す気がないので間違ったままですが掲載します。
左:「教ル方、同見附宿拾六里貮拾七町、同中泉村拾七里九町余、同掛塚村拾九里拾壹町、同濱松宿貮拾里拾七町余、同二俣村廿壹里廿七町余、同気賀村廿四里拾八町余、同新居宿廿四里二拾町余、遠江三河國堺廿六里(十十十)五町余、愛知縣廰四拾八里拾七町余、西京三条大橋八拾四里拾四町」
・街道研究としては近代の石道標の価値がある。
・札の辻(呉服町1丁目と2丁目の境)伊勢丹前
静岡市街の中心地は呉服町で、旧東海道も呉服町の札の辻を通過し本通り乃至は新通りに向かい直進するか曲がる交差点であり、高札等のお触書も建てられた府中宿中心の場所である。
・国・登・静岡銀行本店(旧三十五銀行)(呉服町1-10 )
国登録有形文化財、第22-0010号、この建造物は貴重な国民的財産です、文化庁。
景観重要建造物、静岡銀行本店(旧静岡三十五銀行本店) 静岡市葵区呉服町、指定第3号、平成23年9月30日、静岡市。
・静岡天満宮(中町1‐3)
・石鳥居:昭和三十一年、・神社名碑:昭和五十二年、・手洗石、・牛像、・石碑:川中天神伝説之地、黒い直径15~20㎝溶岩多数(富士山溶岩か?)、
・稲荷社祠:、・説明版:静岡天満宮末社、静銀稲荷社、御由緒:御祭神:稲荷大神、昭和20年終戦後、進駐軍が静岡に入り、大企業に立入調査を行った折、(株)静岡銀行の守護神として、社内に祀っておりました稲荷社を、直ちに撤去廃棄すべしと命ぜられ、銀行側は検討の結果、御神体を隣接する静岡天満宮(当時は天満天神社)に保管祭祀を依頼し、神社側もこれに応じて静岡天満宮末社「静銀稲荷社」として現在の場所に鎮座奉斎したのです。以来初午祭には静銀本店営業部の責任者が参拝する習わしとなったのです。御神祠:この御神祠は明治初年から昭和3年まで静岡天満宮(当時は天満天神社)の御本殿として鎮座しておりましたが、昭和4年新たに御本殿を造営するにあたり市内宮本町山下家に譲渡し同家にて同家の守護神として奉斎されていました。しかし同家の事情により、この神祠を処分することになりましたので、昭和54年2月同家より静岡天満宮の地に還御しました。これと同時に従来静岡天満宮の本殿に合祀しておりました、静銀稲荷社の御神体をこの神祠に奉斎して、今日に及んでいるのです。(昭和4年竣工の御本殿は、昭和20年6月戦災にて焼失)
・景行社祠:、・説明版:静岡天満宮攝社景行社御由緒:昌泰4年(901)1月25日菅原道真公が、無き罪により大宰府に流された。翌々日公の子息達も夫々別々の地に流され、次男景行も駿河権介に左降され、この駿河の地に流され、ここ駿河の国府に居住した。この国府は現在の静岡天満宮を中心とした一帯の地域である。その後景行の記録が定かでなく、今日に至ったので、道真公を祀る静岡天満宮を崇敬する有志が景行を祀ろうということになった。その折り、大阪市天王寺区の一行者(鎌原氏)や清水区三保の行者(日蓮宗)に「景行を祀れ」との道真公の託宣があったとのことで、平成元年春に景行社を創祀したのである。(平成20年6月25日再記)
・銅鐸:説明版:県指定文化財、奈良県北葛城郡上牧村観音山から出土したもので、銅製で耳がなくたすき形の模様がある。高さ19.7㎝、底の長径15.1㎝、短径11.5㎝、保管:登呂考古館、明治百年紀念、静岡県文化財保存協会、
・尼ヶ崎稲荷神社(中町37‐1)
・石柵、・手洗石:昭和六十年、・石燈籠(2):平成十九年、・稲荷(2)、
・説明版:尼ヶ崎稲荷神社の由来:元尼崎又右衛門という富商邸内にありました。家康に召されて駿府に移り、はじめ本通り五丁目に宅地を賜りそこを十軒町と言ったが、慶長14年四ツ足御門町(現中町)に替地を賜ったと言われています。尚金座町稲荷神社(後藤稲荷神社)がこのすぐ裏手にあり慶長の頃、駿府上魚町(現金座町日銀)で小判を鋳造した後藤庄三郎光次邸があった所でもあります。又銀座町は現在の東京銀座にお移されております。
・説明版:四ツ足御門と中町の由来:四ツ足御門町の町名は非常に地位の高い町名でありました。今の中町の所から駿府城に入ったあたりに駿府城の四ツ足御門がありましたので、この町名となったのです。さらにこれを遡れば、その昔、大化の改新に伴い今の長谷町付近に国府が置かれた頃、この中町付近に国庁の四ツ足御門があったからという説があります。その説によれば四ツ足の名は千数百年の歴史を飾る由緒ある町名であります。現在、中町という町名になったのは、四ツ足といえば獣類に通じ快い町名とは聞こえないということで、大正4年11月10日「静岡市の中心」ということで中町と改称されたのであります。 平成23年3月15日 春季大祭
・上魚町碑(金座町1)かみうおちょう
・説明版:上魚町は徳川家康の大御所時代には、中央の通りを挟んで南側を後藤庄三郎光次が拝領し、光次が江戸に移るまではここを金座として「駿河小判」と呼ばれる金貨を鋳造していました。また北側は駿府城築城の作事方中井正清が拝領していました。「駿国雑誌」によれば、家康の在城の時、下魚町から魚商人を移住させたとされ、町の南側には魚問屋、北側には青物問屋が軒を連ね、さながら「流通センター」のような役割を果たしていました。元禄5(1692)年の「駿府町数・家数・人数覚帳」によると、当時の上魚町は、南側が家数38軒、人数203人、北側が家数4軒、人数70人でした。上魚町は昭和3年に金座町となりましたが、それ以後も「かみんだな(上の店)」と呼ばれていました。
・金座稲荷神社(金座町49)
・手洗石:昭和六十二年、・常夜灯:昭和六十二年、・金座碑:昭和三十年:
日本銀行静岡支店からこの金座神社界隈はかつての金座で小判等を鋳造していた。
・説明版:お金の神様、金座稲荷神社御由緒、創建:慶長11(1606)年、御祭神:稲荷大神、秋葉大神、当神社は後藤庄三郎光次が徳川家康公の命を奉じ駿府、上魚町(現在の金座町)に金座を開設し小判の鋳造を始めるに際し金座の守護神として御二柱を祀ったのが起源であります。以来400年、上魚町の産土神として祀られ、その霊験洵にあらたかなる為、「お金の神、金運の神様」として広く崇敬を集め、通称「後藤稲荷」として親しまれてまいりました。その後幾多の変遷を経て、昭和62年5月23日、当所へ遷座致しました。尚金座町という町名は、歴史的事実にもとづいた町名としては全国で唯一のものであります。昭和63年11月吉日、金座稲荷神社。
・戸塚歯科医院跡(本通1丁目3‐2)
かつて戸塚氏は郷土史家として静岡近辺の野仏や民間習俗の研究で知られていた。氏の本は私にとっても貴重な資料である。
・奥津宮神社(車町26)
・新:石灯篭、・庚申供養塔:文政三庚辰年、・石鳥居:昭和二十六年、・石柵:平成四年、・欠:庚申:安政七、・欠:庚申供養塔:文政五壬午年、・観音堂、・欠:奉寄進石燈:寛文(?政)九年
・石碑:説明:奥津彦神社、静岡市葵区車町26鎮座、祭神:火産霊神、奥津彦神、奥津媛神。由緒:神社の創立年月不明。社伝に駿河国の守護今川範国の子今川了俊深くこの神々を崇敬して邸内に奉祀してあったが、その子今川仲秋に政治の要諦を教えると共に「よくこの神を信仰せよ」と御神体を授ける。仲秋はよく父の教えを守り身を慎み祭祀を怠けたらず善政を行いやがて立身して遠江守護、尾張守護等を歴任した。仲秋は一の世を去るに臨みてその家臣に命じて御神体をこの地に祀らしめ三宝荒神社と称したと伝えられている。三宝荒神社は明治元年の神仏分離令に依り奥津彦神社と改称された。又三宝荒神社の別当用触山守源寺は昔から駿府の会所に使用され町々へのお触れ通達はここから出したので用触山の名がつけられた。御神徳:火の神様である炊事キッチンの守り神である。火の神信仰は火難を免れ病難を防ぐ。祭日:2月28日、9月28日、12月28日
・願勝寺(車町50)
・新:双体道祖神
・金剛院(八千代町17)
・石:家:道祖神
・秋葉山常夜灯(馬場町)
中町交差点に市・有民・中町秋葉山常夜灯、上部は木造で彫りが見事、下部は石造、・赤鳥居:コンクリート製、
・山田長政像(宮ケ崎町100)
馬場町は伝山田長政屋敷跡といわれる。
・二瀬川神社(馬場町65)
・石灯籠(2基):明治四年、・手洗石:古そうで年号等もありそうだが見えない位置に安置されていて判読不能。
・説明版:二瀬川神社、静岡市葵区馬場町65番地、祭神名:保食神うけもちの神、多紀理比賣神たぎりひめの神、例祭日:9月15日、社殿工作物:本殿3.3平方m、拝殿6.6平方m、境内地:132平方m、氏子戸数297戸、神職名:宮司:鈴木巌夫、禰宜:鈴木哲夫、責任役員名:小川保、鍋田治夫、由緒:創建年月不詳、昭和20年6月の戦災により焼失、昭和25年9月都市計画区画整理により現在地に移転し、以前120坪の地が40坪に削減され、その境内地に町内会館を建設したため実質は更に三分の一となって、極めて不遇な道を経過した神社といえる。静岡県神社庁神社等級規定13等級社である。年間スケジュール:祭旦祭:1月1日、初午祭:2月2の午の日(二の午祭)、夏祭:5月15日、例祭:9月15日、神輿清祓祭:例祭前後の土曜又は日曜日、
・報土寺(宮ケ崎町110)
・石塔:新:南無阿弥陀仏、・新:六地蔵(杉村隆風)、・新:無縁萬霊之塔、
・石碑:新:養国寺慰霊之碑 平成十九年、説明版:報土寺の末寺で安翁山丹龍院養国寺という浄土宗の寺が本通7丁目74番地にありました。開基は寛正6年(1466)で開山は松漣社貞誉王山上人還阿和尚であります。その後は報土寺の末寺となり歴代の当山住職が兼務住職となり、本通りの人たちと供に養国寺を護持してきましたが、昭和20年6月19日の静岡大空襲により堂宇すべて廃墟と期しました。その後、報土寺が戦後復興を進めていく中、昭和27年、養国寺は本寺である報土寺に合併されることとなりました。開基よりおよそ550年、養国寺の歴代住職をはじめ信徒の方々、本通り7丁目の方々、その他養国寺の護持の為にご協力を頂いた多くの善男善女の方々に心より御礼申し上げ、ここに慰霊の碑を建立致します。
平成19年8月、報土寺住職 泰誉博隆
・石碑:新:南無阿弥陀仏 大正十余年、説明版:経に曰く至心信楽即得往生~~~以下略~~~
~~~大正十余年
・新:冷泉為和の歌碑:冷泉為和の歌碑についての由来:報土寺の本堂前に戦国時代宮廷歌壇の第一人者冷泉為和の歌碑が建てられた。為和は歌聖藤原定家の直系冷泉家第7代の当主である。当時応仁の乱(1467~77)後の荒廃した京都を逃れて駿府に流寓した公家殿上人はかなりの数にのぼっていた。権大納言冷泉為和もそうした中の一人であった。その為和が駿府滞在中我が報土寺において歌会を催すこと9回、11首の和歌を詠んでいる。それは、「今川為和集」の中に歴然としるされている。報土寺境内にある歌碑に彫られた和歌はその中の天文12年(1543)5月2日の歌会の折りのもので、
松契還年
代々かけて 軒のかわらに むす苔も 緑あらそふ 松の気だかさ (為和)
この歌の題の「還年」は長寿をいうので軒の瓦が苔むすといえば1年や2年のことではない。何代という長い年月を栄え続けてきた証で、それと競うように枝を伸ばした松の緑の気品のある美しさを讃えて長寿を祝う歌とした手腕はさすがである。(文責 長倉智恵雄)
・一加番稲荷神社(鷹匠1丁目8)
・石鳥居:昭和三十七年五月、・石稲荷2:昭和五十一年、石柵:昭和五十八年、・手洗石:昭和五十六年、・コンクリ石塔:昭和壬子二月、・石碑:神社名:新、
・説明版:当神社の御祭神は、保食大神ウケモモノオオカミ、御別名を豊宇気比売神トヨウケヒメノカミ、また食稲霊神ウカノタマノカミと申し上げ、稲、五穀の御霊神と尊まれ、衣食住の神、商売繁盛、厄除開運、無病息災、延命長寿の守護神として広く信仰されている神である。
当社鎮座の由来は寛永八年(1631)駿府城主駿河大納言忠長卿(二代将軍秀忠公の第3子)が三代将軍家光(兄)の勘気を受けて甲斐に蟄居の後は、幕府は駿河を直轄領とし、城主を置かず重臣の内から駿府城代を任命して庶政を綜理せしめ、城代を輔けて城外の守衛に当たらせるために在番一年の役として加番を勤番させることとし、紺屋町に一加番屋敷を設けた。(これを紺屋町加番或は町口加番屋敷という)初代一加番に信州飯田城主五万五千石脇坂淡路守安元が寛永九年(1632)12月に仰せ付けられ着任した。この加番開設にあたり3200余坪の屋敷内の浄地を選び社殿を建て寛永十年(1633)山城国伏見稲荷神社の分霊を勧請し、駿府一加番の守護神として鎮斎したのが当神社の創祀と伝えられている。慶安四年(1651)由井正雪の乱があり、一加番は府城に近い横内御門前(現在の鷹匠一丁目)に移され、これに伴い当稲荷神社も新屋敷内に遷宮された。斯くて創祀以来文久元年(1861)に至る迄約230年間歴代の加番は折々に鳥居、燈籠等を献納し、年々の祭祀を厳修して、崇敬の誠をつくしてきた。
明治維新に至り加番屋敷廃邸後は、鷹匠町一丁目の産土神として、明治11年政府より存置が許可されて、一般市民の崇敬の神社となった。昭和20年6月戦災により社殿、工作物悉く焼失した。戦後氏子の奉賛により復興し、地域の区画も整理されて面目を一新し、当神社の信仰は市の内外に広まるに至った。
祭典:例祭5月5日、歳旦祭:1月1日、節分会:2月3日、秋祭:11月25日。
昭和63年5月 奉納:松浦元男
・二加番稲荷神社(西草深町4)
もとは駿府城の警護用番所でもっと敷地も広く馬場等もあったが、今はそこの祠があった部分のみに神社がある。周辺は住宅地でキリスト教会やNHKビルがある。そこもかつては敷地内だったはず。
・村本喜代作先生明徳碑文:翁は西草深町520世帯の町内会長として20年にわたる長き間、社会公共のため奉仕せられた功績は甚大である。当二加番稲荷神社は戦災により灰燼化し瓦礫の中に樹木を植え社殿を再建し自ら責任役員となり神社を中心に民福をはかり明朗な社会環境造成に盡くす。又政教社雨声会を起し政治経済文学史話等の講演を行うこと実に250余回、其の間先生の薫陶を受けた方の中には名政治家も現はる。ここに村本喜代作先生を後世に伝えるため西草深町内会神社総代会雨声会の有志相謀り明徳碑を建立する。昭和55年3月、~以下略~
・手洗石:文化(五)九年(戌辰)壬申歳、・神社名石碑:昭和四十三年、・石灯籠:天保十五甲辰、・石鳥居:昭和四十六年、・石柵:昭和四十八年、・?石灯籠の一部:元文四巳未、・?石塔:崩れて成れの果て、
・説明版:二加番稲荷神社:祭神三社:豊受毘賣命トヨウケヒメノミコト穀物の神 商業あきないの神、猿田彦命サルタヒコノミコトお祓いの神、天鈿女命アメノウヅメノミコト神楽の創始芸能の神、由緒:駿府城は寛永8年以後は城主を置かず「城代」によって統治され、城外守衛のため「加番」という役が置かれた。当所は二加番屋敷の跡で、その守護神として稲荷神社が祀られた。当社を鷹森稲荷と称されたのは、この附近を流れた安倍川のほとりに鷹が集った森があった故という。一加番(鷹匠1丁目)三加番にも夫々稲荷神社が奉祭されている。明治維新後は西草深町の産土神として遠近より崇敬されて今日に至った。加番屋敷には馬場、的場、火の見櫓などがあり、その略図を裏面に記した。歳旦祭 1月1日 春祭 初午 春分の日 秋祭 秋分の日
・裏面:二加番屋敷略図:外堀に面した現在はNHK静岡放送局から付近一帯の住宅地も含む広大な屋敷であることが分かる。外堀側77間(138.6m)、奥行き42間(75.6m)、面積10478.16平方m、3175坪。
・三加番稲荷神社(東草深町11)
・石碑:神社名:昭和三十八年九月、・石柵:平成九年、・石鳥居:安政六巳未二月初午、旗指石:奉献安藤杢(木の下は工ではなく立つ)之助源有(有るの下は月ではなく且つ)剛、・手洗石:安政(正の下に久)□□□二月、・手洗石:?、・石塔:寄進~~~、・石(埋)、・礎石2?、・石燈籠2:、・倒れた石燈籠:稲荷大明神 廣舟(止の下は舟) 文化三丙寅三月初午、
・説明版:祭神:保食大神ウケモチノオオカミ、祭日:春祭:春分の日、秋祭:秋分の日、由緒:寛永八年(1631)に駿府城主徳川忠長が将軍の勘気に触れ蟄居を命ぜられての後は駿河国は幕府の直轄領となり、駿府城には城主を置かず城代定番が勤める番城となり定番の下に小大名または旗本の中から加番を勤番せしめ城外の警備に当たらしめた。慶安四年(1651)に由井正雪の反乱があっての後は、従来の一、二加番に加えて三加番が増設され、東草深にその屋敷を設けると共に邸内の守護神として、この三加番稲荷神社を鎮祭した。代々の加番は深く崇敬して毎年二月初午に盛大な祭典を行い、また石燈籠鳥居等も数多く奉納された。
明治維新に至り加番屋敷廃邸後は、東草深三ヶ町の鎮守となり、明治11年3月政府公認の神社として存置を許可された。後に水落町二丁目も氏子に加わり一般町家、遠近の人々から深く信仰されるに至った。
御神徳:保食大神は伊勢の外宮に奉祀する豊受大神と御同神で人間生活に一番必要な食糧と衣料をお恵み下さる神である。古歌に「朝夕の箸とるごとに保食の神の恵みを思え世の人とあう」また福徳円満の神、商売繁盛の神として最も信仰される神である。
・草深界隈の古い洋館類、キリスト教会等(西草深町、東草深町)
‘13現在、(西草深町15番)西草深眼科(かつての中島医院)が洋館の趣をとどめている。他にもあったのだがだいぶ減少した。教会も現代建築のビルに改築され古式ゆかしさは消失した。
静岡英和女学院(西草深町8)はねむの木学園創設者:宮城まり子出身校である。
クラシック音楽愛好家には一時期全国的に知られていたのが青島ホール(西草深町16‐3) である。
・西草深公園(西草深町27)
・説明版:西草深と徳川慶喜公:草深町は駿府九十六ヶ町の一つで、現在の西草深公園の東側に、二筋の通りに面して一画を占めていました。明治6年(1873)に一帯の武家屋敷を含めて西草深町となり、昭和44年に御器屋町ゴキヤチョウなどを併せて現在に至っています。駿府城に近い草深町の近辺には慶安4年(1651)に駿府城の警護や城下の治安維持にあたった加番の一つ二加番や与力、同心などの武家屋敷が配置されていました。草深地区には江戸時代初期に徳川家康公に仕えた儒者、林羅山の屋敷があり、また明治維新期には静岡学問所頭ガクモンジョガシラであった向山黄村ムコウヤマコウソンをはじめとする学問所の著名な学者が多数居住していました。西草深公園には浅間神社の社家シャケの屋敷があり、明治2年(1869)6月に静岡藩主となった徳川家達イエサト公が社家新宮兵部シングウヒョウブの屋敷に移り住みました。
徳川幕府第15代将軍徳川慶喜公は、大政奉還の後、慶應4年(1868)2月から謹慎生活に入り、同年7月に駿府の宝台院に移り住みました。宝台院での謹慎生活が解かれた慶喜公は、明治2年(1869)に紺屋町コウヤマチの元駿府代官屋敷に移り、更に明治21年には西草深町に屋敷を構えましたが、東京に戻る明治30年まで政治の世界を離れ、一市民として過ごしました。静岡での慶喜公は、狩りや写真を好み、油絵をたしなみ、明治10年代から自転車を購入して市内を乗り回って市民の話題になるなど、多種多様な趣味と共に西洋的な生活を謳歌した当時の最先端を行く文化人でもありました。中でも静岡で修得した写真撮影の技術から生まれた作品は、各地の風景、生活ぶりを伝える貴重な歴史資料ともなっています。慶喜公が、東京に戻った後の徳川邸は葵ホテルとなり、更に明治37年には日露戦争の捕虜収容所の一つとして使われましたが、同38年に施設内から出火し焼失してしまいました。
・説明版:万葉歌碑:焼津邊 吾去鹿歯 駿河奈流 阿倍乃市道尓 相之兒等羽裳
春日蔵首老 焼き津辺にわが行きしかば駿河なる安倍の市道に逢いし児らはも
万葉集は日本最古の歌集で奈良時代
~~~不明、
昭和36年
*写真不鮮明で判読困難
以下は、インターネット検索「万葉集巻3、れんだいこ」より引用
「万葉集、巻3、No.284、春日蔵首老かすがのくらびとおゆ、作歌
焼き津辺=静岡県焼津市辺り、阿倍=静岡市安倍、安倍川の安倍、市道=イチジ、市場が開かれていた道、焼津方面に赴いた際、安倍の市で出会った娘たちを思い出して懐かしがっている歌。これを男女が市に集まって乱舞した、いわゆる歌垣の際の思い出ととってもよかろうが、そうとらなくても単純に美しく楽しげだった娘らを思い出しての歌として一向に差支えない。」
私見:この短歌から静岡市(安倍の市)がすでに奈良時代に賑わっていたことが分かる。
・石鳥居
浅間神社前、麻機街道と長谷通りの分岐点
・浅間神社(静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町102-1)
・交番裏の賤機山を上るとすぐ賤機山古墳がある。もう少し上に麓山神社がある。さらに上に一本松・5世紀の古墳がある。さらに上ると浅間山山頂(△140m)で舗装路はなくなり、あとは山道となる。その先に空堀(地獄谷)があり、さらに先に賤機山城址(△173m)と光明地蔵となる。
浅間神社境内遺跡跡。国・重文・浅間神社社殿。石造物でも石灯籠等、市内最古級のものが多い。
国・登・遍界山不去来庵本堂。
・西蔵寺(片羽町79)
・三界萬霊等、・庚申塔、・地蔵、・新:観音、・手洗い石、・新:灯篭、
・元三大師延命地蔵(安倍町23)
・地蔵:
・瑞光寺(安西1丁目100‐1)
・石塔:文正夂(政)十三年庚寅八月、・?観音:元文五庚申、・板碑:山梨易司翁彰功碑 大正八年、・板碑:佐久間翁叟先生碑、・新:有縁無縁三界萬霊、・お花塚 石州流生花家元~~昭和十三年、・如来(4):片足膝立ち座位、・地蔵(4)、・地蔵、・同一様式の観音約80基(三十三所観音3つ分で不足分は消失か、いくつかには二十六番等の番号が読み取れる)、
*文政の政を正夂と刻字してあるのか?
・然正院(安西1丁目103)
・新:六地蔵、・新:水子供養塔(2)、
・末広中(末広町)
かつて高等女学校があった。
・神明宮(神明町54)
・木鳥居、・常夜灯(2):昭和十五年、・石柵:昭和十五年、・狛犬(2):昭和十五年、・神社名碑:平成二年、
調査 ’13 11~12月を含む版
まだ未調査地や不十分な個所が多いですが、いったん公開します。将来のんびりと改訂していきます。
・用語説明
・国、県、市=国、県、市指定、・有、無=有形、無形、・登=登録、・文=文化財、・天=天然記念物、・重=重要、・民=民俗、・石=石製、・家=家型、・新=近代から現代にかけて作られた新しいものと推定されるもの、・古=新しくなく古そうなもの、・欠:破損欠落しているもの、・馬頭=馬頭観世音菩薩、・コンクリ=コンクリート製、(2)=2基、
・古い用語説明
廿=20、廿の縦線3本=30、等=塔、歳‣天‣月日=年、
美良または羊良=養(美や羊ではなく羊の下は大であり美ではなく横線3本である。狼という字に似ているが、その字がパソコンで出てこない。そういった字は多く他の現代的な字に切り替えたり注を施す)、クイズ:ちなみに養がなぜ美(横線3本)や羊(下は大)と良なのかはちょっと考えるとすぐ分かります。このように漢字の部分を上下左右に組み替えることは石塔への刻字ではよくあります。彫る時の字のバランスを考慮した石工さんたちの工夫です。ちなみにある石工さんはこういう字をお寺さんの字と言っていましたが寺院で使う字ではありません。この前見た字では政を上に正、下に政の正抜きの字を彫ったものを見ました。
*「石仏事典」類を参照してください。年号や干支もこれで分かります。
・住所について
なお住所は正確に分からないものは多く、隣や付近の住居の番地号を用いているものが多い。
○静岡市市街地内、静岡駅北西部
・宝台院(常盤町2丁目13‐2)
・宝台院ほうだいいん、金米山宝台院:説明版:宝台院は、徳川家康の側室で二代将軍秀忠の生母西郷の局サイゴウノツボネ(お愛の方)の菩提寺である。西郷の局は27歳で家康に仕え、翌天正7年(1579)4月、家康の第3子秀忠を生んだ。家康38歳の時である。この頃家康にとっては、浜松城にあって、三方原の合戦、設楽原合戦、小牧長久手の合戦と、戦に明け暮れたもっとも苦難な時代であった。西郷の局は、家康の浜松城時代に仕え、苦しい浜松城の台所を仕切った文字通り糟糠ソウコウの妻であったということができる。天正14年12月、西郷の局は、長かった苦難の浜松時代を終え、名実共に東海一の実力者となった家康と共に駿府入りした。家康の陰の立役者として、献身的に仕えた西郷の局は、駿府入りと共に浜松時代の疲れが出て、天正17年5月19日、38歳の短い生涯を終わった。後年、将軍職に就いた秀忠は、母のために盛大な法要を営み、その霊を慰めた。以来、徳川300年の間、この宝台院は、徳川家の厚い保護を受けたのである。
寺宝:白本尊如来像:重要文化財、他多数。静岡市。
・徳川慶喜公謹慎之地:宝台院と徳川慶喜公:説明版:明治元年七月、第十五代将軍慶喜公、御謹慎の身となり、同月十九日水戸を出発して銚子港に到着し、同月二十一日蟠龍艦に乗船し、同月二十三日に清水港に到着しました。海路にて移動したのは、上野彰義隊の戦いの興奮も冷めない江戸を通ることが、極めて危険なことだったからでしょう。この時目付の中台信太郎(のち駿府藩町奉行)がこれを出迎え、また精鋭隊頭松岡万以下五十名の厳重な護衛がついて駿府に向かいました。慶喜公が討幕派、旧幕臣の双方から命を狙われる重要人物であった事情に加えて、無政府状態とも言うべき当時の駿府の町の状況がこのような物々しい警護体制を必要としていました。一行は当日夕刻には宝台院に入りましたが慶喜公の駿府移住は秘密裏に行われ町民には一切知らされていませんでした。慶喜公の駿府入りが町触れで知らされたのは、その五日後の二十八日のことでした。尚、宝台院を慶喜公謹慎の場所に選んだのは元若年寄大久保一翁でした。彼は駿府町奉行の経験もあってこの町を熟知しており、徳川第二代将軍秀忠公の生母西郷局が葬られた宝台院こそ慶喜公が落ち着いて過ごせる場所と考えたのでしょう。以来、精神誠意慎をされ翌明治二年九月二十八日、謹慎が解け十月五日紺屋町の元代官屋敷(現在の浮月楼)に移転されるまで、約一年余りを当山で起居されました。この謹慎の部屋は十畳と六畳の二室で、十畳の間を居間、六畳の間を次の間として使用し、当時渋沢栄一や勝海舟と面会されたのもこの六畳間でした。明治元年八月十五日、藩主亀之助(家達公)が駿府に到着した時も、先ず宝台院に参上し御霊屋に参礼の後、やはりこの部屋で対面したということです。家達公は七間町三丁目を曲がり、御輿で大手門より入城されましたが、当時まだ七歳というお年でした。現在の宝台院には、慶喜公の遺品として、キセル、カミソリ箱、急須、火鉢、本人直筆の掛軸、居間安置の観音像が残っております。静岡市。
・西郷の局供養塔、・キリシタン灯篭、・百度石、・尺八碑:明治二十三年、・板碑:燈臺寄附連名:明治三十二年、・板碑:潮田良一之碑:昭和二十二年、・板碑:俳諧師かしく坊の辞世、・新:延命地蔵尊:駿河一国百地蔵尊第三十一番、祠:稲荷大明神、・新:西国九番札所:観世音菩薩安置成田山不動尊、手洗石:長野縣信濃国諏訪郡冨士見□、・狛犬2、・地蔵、・観音、・不動明王、・新:地蔵2、・石:三○:?石垣用石、・新:狛犬2:大正十三年、・新:観音:レリーフ、・石碑:アソカ幼稚園園歌:平成二十一年、
・家康の身代わり観音:阿弥陀如来立像のこと、かつては像に傷がついていたが現代に修理したため傷は消失した。家康は本像を合戦に持って行き安置しており、自分の近くに置いた像に矢が刺さり身代わりになったと考えたというが、伝説なのか史実なのかは不明。しかも傷がなくなったそうなので、いかなる傷だったのかもなおさら不明。
ちなみに静岡市葵区、宝台院のホームページを調べると、徳川家康関係の宝物(阿弥陀如来立像、家康公の自画像、真の太刀、家康公筆「安元御賀記手習」)、三代将軍家光公筆「遠山月」二代将軍秀忠の生母・西郷の局の墓、徳川慶喜公謹慎之地、かくし坊の辞世があり、その中にキリシタン灯篭もある。説明文:「キリシタン灯篭:茶人として有名な古田織部が制作し駿府城へ奉納、徳川家康公の侍女・ジュリアおたあが信拝したという灯篭です。この灯篭は城内より静岡奉行所を経て宝台院へ移されました。」とある。
ジュリアおたあをウィキペディアで調べると生涯概略の他、文章末に「~なお、駿府時代には灯篭を作らせ瞑想していたと言い伝えられており、そのキリシタン灯篭は、現在は宝台院に移されている。」と書かれている。
これらはいかなることでしょう。日本最初のキリシタン灯篭発見が宝台院で1923(対象12)年とすると、ジュリアおたあ信拝説はそれ以後と思われますが、いったいどういう証拠があるのでしょうか。分かりません。
*私見での「キリシタン灯篭の疑問点と保存」については別項目を参照してください。文章が長くなるのでここでは割愛します。
・鎮火稲荷神社(本通5丁目1‐5)
・稲荷(2):昭和廿三年、・鳥居:コンクリ、
・津島神社(梅屋町4‐1)
・鳥居:コンクリ、・狛犬(2):昭和54年、
・説明版:津島神社:祭神:当神社の御祭神:素戔嗚尊は日本神話の中で伊弉諾尊、イザナミノミコトの御子で天照大神の□神に当たられ、荒々しい剛直な性格の神で、天照大神を天の岩戸に~~させ給われ、高天原から地上に追放されました。出雲で八岐のおろちを退治されて奇稲田姫と結婚され大蛇の尾から出た天叢雲剣~~し献上されました。また新羅に渡られ船材の樹木を持ち帰り~植林の道を教えられたと伝えられております。また、大国主命は素戔嗚尊の御愛婿であられ、出雲の地で親子二代に亘って国土の経営、産業開発にお力をいたされ、災厄と疫病を除く御徳と受福の神様として世に知られております。神話では暴風神、英雄神、農業神として語られ、氷川神社、八坂神社、熊野大社などの御祭神でもあります。
天王さん:津島神社は古くは津島牛頭天王社と言い、今日でも一般に「お天王さん」と尊称されております。これは日本には上古から民俗宗教としての祖神信仰がありましたが、仏教が伝来して次第に日本化して、その結果崇神、崇仏思想が接近し、後年明治政府が神仏分離令を発布するまで、神宮寺、寺院鎮守など神社とお寺が同居していたことと関係があるように思われますが、インドの祇園精舎の守護神であるとか、新羅の牛頭山に留まっていた素戔嗚尊の御神霊を勧請してお祀りしたとか諸説があってはっきりしません。
由緒:神社年鑑によれば天明5年(1785)創建、明治11年公称を許可とあります。古老からの言い伝えで、昔疫病が流行り疫病除けの神として勧請したと言われておりますが、歴史年表を見ると。天明3年の頃には、「7月浅間山噴火、死者2万人に及ぶ。この年未曽有の凶作、奥羽の死者数十万人に達する」 天明4年は「この年夏、秋、米価騰□して諸民飢餓し、秋よりは疫病流行して死者が多い。」 天明5年「奥州三春、凶作、琉球凶作」 天明6年「江戸開府以来の大水で死者、家屋破損が多い。この年大凶作、収穫三分の一」などとあり、疫病除けの神として素戔嗚尊を勧請したものであろうと推測されます。
沿革:天明5年 創建、明治11年 公称許可、昭和9年 本殿、拝殿、社務所等造営、昭和15年1月15日静岡大火にて焼失、昭和15年仮社殿造営、昭和30年 空襲の罹災を免れる。その後現在地に移転。昭和44年 新社殿造営、現在に至る。平成11年6月吉日。
・八朔神社(本通2丁目1‐3)
・木鳥居、・手洗石、
・静岡神明宮(屋形町13)
・石鳥居:大正十五年、・常夜灯(2):大正十五年、・石柵:大正十二年、・狛犬:大正十四年、・神社名碑:昭和八年、・道路開鑿碑:明治四拾年、
・東本願寺静岡別院(屋形町10)
・新:堂、・新:木石堂、
・大林寺(安西4丁目93)
・梶原景季と景嘉の墓:五輪塔:土水火風空、・祠:白山妙理大権現、・祠、・山門:仁王像(阿吽)、裏に風神と雷神像、・新:水子地蔵、・新:六地蔵、・石燈籠、・観音、・中世末墓石、江戸初期墓石(2)、観音風墓石(2)、・青面金剛供養塔:天明二、・法華千部塔:文政二、
・説明版:縁起:古記録によると当山は今から約800年前、鎌倉時代初期当國庵原郡高部村大内にあり、大淋寺(天台宗)といい大林寺殿贈四品榮昌福寿桑道場妙開大禅定門、姓平氏葛原親王第十四代梶原信濃守従四位少将景義四男刑部少輔朝景卿建仁元辛酉(1201)年5月3日卒を最初の開基としている。文永元(1264)年12月18日仏殿を今の柚木町に建立している(駿河記)。時移り戦国争乱期、北条早雲殿(1459)の命により、武田、今川の動静を探るため旧東海道の見張所としての城塞の寺を現在の場所に草創したのである。七堂伽藍は一万の大軍を収容でき、山門が柚木町の堤上にあり、その下に尼寺と墓地があった。寺格は法地寺中5反6畝3歩安西内新田、除地5反3畝3歩安西外新田、雑地10反あり(駿河志料)。
その後曹洞宗通幻派最乗寺門下総世寺末となり同寺五世天祐宗根和尚に嗣法する鳥道長鯨和尚天文12(1532)年癸卯12月10日寂を開山としている。三世好山宗禅和尚は慶長年間(1596)徳川家康より法門の聴聞あり。四世明室温察和尚(1624)は梶原源太景季、景嘉の墳墓を改築し、六世揚山和尚(1704)は末寺龍津の中興で、七世大鳳和尚(1688)貞享3年梵鐘鋳造の功をなし良富院の開山となる。九世槐國萬貞和尚(1716)は最勝、定林に歴住し海松、円城、雨林の3か所の開山であり、卍山道白禅師の法嗣で、徳川吉宗の釣命により、官刹長崎の皎台寺に転住し、大同庵、金泉寺を開き語録二巻を著している。十世古岳日峻、十四世一了玄画和尚も皎台寺に当寺から普住した。特に日峻は書物に参同契測海があり、海門及び月舟宗胡、独庵玄光、(辟と水で上下)山の高泉、黒瀧の潮音、槐國と共に参じた中世稀にみる高僧である。二十九世祖鳳光禅和尚は洗耳寺に歴住し明治40年七堂を再建したが、昭和20年6月19日戦火により焼失している。昭和34年三十一世光雄和尚が本堂、位牌堂、庫裏を再築している。尚開基より光雄和尚まで5回兵火に遭っている。また寺の所在は大内→安西→柚木→安西(正保元(1644)年町奉行落合氏により)に戻っている(寛政寺記及び駿河記) 昭和60年12月18日 大林寺 三十一世大鑑光雄記
・説明版:大林寺墓塔群:○梶原源太景季・景嘉の墓:源頼家(1182)の母政子の父北条時政の家来家来梶原景時(1200)が滅ぼされ、その門葉景嘉が駿河殿(徳川忠長1602)に仕え寛永9年(1632)壬申1月21日歿した。本府古図の安西4丁目南にその姓名がある。大内梶原堂の条によれば太田美濃守入道資正二男が梶原の養子となり源太政景といった。景嘉はこの後葉である。(駿河志料他)
○落合能登守小平次道次の墓(1652):長篠城攻防戦の勇者鳥居強右衛門の磔に感動した落合佐平次道久は、自分の指物に磔の図を描いて出陣し、家康に見出され、後に徳川頼宜に従って駿河衆となり、養子の道次は江戸幕府に出府し駿河奉行として由比正雪を召し捕り功あり。寛永17年より承応元年まで13年奉行として活躍した。慶安5年8月9日寂。
○安鶴の墓(1872):『諸国畸人傳』(石川淳)『駿府の安鶴』(江崎惇)により全国的に有名。
○舟川斎寺西源正勝の墓:幕府旗本天神真陽流柔術指南医士。
○小沢久七の墓:長崎で勉強し漆器界の発展に尽力した。
○小出東嶂の墓(1823~1889)画家福田半香の弟子であり書画に通じ明治6年静岡新聞を刊行す。
協力者:~略~、昭和60年12月18日、大林寺31世大鑑光雄代
・延命地蔵堂(安西5丁目114)
・堂、・秋葉山常夜灯、
ここから川根筋に抜ける川根(秋葉)街道の起点と考えられている。
*「川根(秋葉)街道」については、『古街道を行く』鈴木茂伸(静岡新聞社)をご覧ください。ただこの本すでに絶版ですので、静岡県内図書館にあるので検索するか、静岡県内の古本屋にもないので、古本屋にリクエストしていって取り扱ってもらえるとよいでしょう。
・柳町水神社(柳町135)
・木鳥居、・手洗石、・社、
・曙稲荷神社(若松町15)
・石柵:昭和十年、・石鳥居:昭和十年、・石燈籠(2):昭和十年、・石燈籠(2):昭和四十年、・稲荷(2)、・稲荷(2)、・祠、・手洗石、
・八雲神社(北番町84)
・神社名碑:昭和四十六年、・八雲神社碑、・新:狛犬(2)、・石鳥居:明治三十四年、・手洗石、・石燈籠(2):明治三十年、・北番町公園碑:昭和46年、・石塔:庚申、・石塔?、・石塔?:文政六癸未年、・若松町制四十周年:昭和三十九年、
・八雲神社御由緒:鎮座地:静岡市□番町八雲~、祭神:~~~、祭□:例祭、~~~~、創立年月日:口伝によれば応永3年創立と伝承。
往古は牛頭天王という。当国総社浅間神社に祀られていたが、戦禍に遭い別当職が簑に納め安倍郡大岩村に遷し大岩村村民の氏神として祭祀を引き継ぎたり。その後寛永の頃駿府城北番詰所の番士この地に居住し牛頭天王を崇敬し為に寛永3年大岩村よりこの地に勧請し宝永3年真言宗建穂寺末寺別当牛頭山宝積寺中興願成院智寂法印氏神として祭祀を承継す。明治3年神仏混淆廃止令により八雲神社と改称、同8年2月村社に列格、同43年6月18日神饌幣帛供進指定を受く。敗戦により国家の庇護を離れ、神社本庁設立に伴い、静岡県神社庁所属となり、氏子により祭祀を継承、現在に至る。350年を記念して建立。~以下略~
・桜森稲荷神社(土太夫町7)
・鳥居:コンクリ、・新:燈籠、・古:燈籠、・手洗石、・石:家:道祖神、
・二十六番札所、水月院(安西1丁目24)
十一面観音菩薩、
・説明版:水月堂御縁起:水月堂(通称おはつかさん)は静岡市安西1丁目南裏に位置し十一面観世音菩薩を安置し、新選府辺観音霊場(新西国)三十三か所巡礼札所中第26番にして本尊は鎌倉初期の名匠運慶の作と伝えられ国宝的存在でありました。しかし戦災(昭和20年6月20日)で焼失してしまいました。元亀年間、今を去ること400有余(405)年前、安倍郡籠鼻(今の井宮町西北部)の圓皆寺(現在は廃寺)の住僧宗文の創建で今川家の臣福島淡路守の夫人然正院智現妙本大姉の開基と伝えられています。毎月20日を以て御縁日と定め毎年3月には僧侶も招き特別大法要を続けております。 平成18年3月20日、水月堂奉賛会
・住吉神社(一番町25)
・手洗石:奉献願主府内(絞?)仲間、常夜灯:昭和六年、・石鳥居:昭和五十年、・石燈籠(2):住吉大神宮御宝前 文化十年と大正四年、・石碑:神饌幣帛供進指定中津神社 昭和十六年、
中津神社とは何? 昭和16年号なので静岡空襲か大火で消失し、戦後住吉神社と併合され、たのか?
・顕光院(研屋町45)
・馬頭(3):馬頭観音建立由来碑:昭和13年1(6)月15日正午過ぎ新富町、~~~不明
*撮影した写真不鮮明で判読困難、再度やり直す気がないのでこのままです。ごめんなさい。
おそらく内容は静岡大火と静岡空襲による戦火の災害供養のため馬頭観音を設置したと言いたいようです。
・地蔵、・南無阿弥陀仏:昭和二十六年、・地蔵(3)、・板碑:大正九年、・新:六地蔵、・三界萬霊等、・無縁堂、・平和観音堂、・庚申:文化四、・庚申:寛政二、・新観音、・新:灯篭(3)、・新:駿河一国百地蔵第一番開運成就地蔵尊、・奉納弘法大師四国八十八所 国々諸々神社供養 秩父三十三所 一国三十三所 坂東三十三所 文政四、
・くがたか橋の碑(追手町12)
かつての外堀沿いの橋の欄干だったのか。
・石塔(城内町1‐2)静岡聖母幼稚園前
全く刻字等有無不明
・石碑:青葉小(追手町4)
廃校になった青葉小学校の記念碑。
・校址碑:静岡第二尋常小學校 明治34年新設、静岡城内東小學校 大正2年 校名変更、静岡城内東尋常高等小學校 大正13年 校名変更、静岡城内東尋常小學校 昭和8年 校名変更、城内東國民學校 昭和16年校名変更 昭和20年9月5日廃校、青葉小学校 昭和29年4月設立、平成19年3月閉校、
・石碑:城濠用水 土地改良区記念碑(追手町4)
・説明版:城濠用水由来:城濠の誕生は慶長12年
~写真不鮮明で判読あきらめ~
昭和53年5月、城濠用水土地改良区
・石碑:葵文庫跡(追手町4)
・説明石碑:由来:葵文庫は大正8年静岡に縁の深い徳川家の記念事業として計画され、同14年3月28日徳川家の家紋を館名としてこの地に開館した。その特色は、江戸幕府旧蔵書の一部である「葵文庫」と3代県令関口隆吉収集にかかる「久能文庫」にあった。以来県立葵文庫は県民の図書館として、また全国的にも貴重書の宝庫として注目されその発展をみた。昭和44年市内谷田に新館が建設され、静岡県立中央図書館として移転すると、葵文庫は新たに静岡市立図書館として再出発した。しかし施設の老朽化により、昭和59年市内大岩に新築移転したため、県民に親しまれた建物は取り壊された。~~~不明
*撮影した写真に石碑終盤の文字が写っていなかったので不明としました。撮影し直すなりもう一度見に行って判読するなりの気にならないので一旦終了します。ごめんなさい。
・駿府城(駿府城公園)
・説明版:駿府城は外堀、中堀、内堀の三重の堀を持つ輪郭式の平城です。本丸を中心に回字形に本丸、二の丸、三の丸と順に配置され、中央の本丸の北西角には、五層七階(外観五層内部七階)の天守閣がありましたが、寛永十二年(1635)に焼失しています。駿府城が城郭としてその姿を見せるのは天正十三年(1585)に徳川家康が築城を開始したことに始まります。この天正期の駿府城は現在の城跡に比べると一回り小さいと考えられますが、詳細は不明です。この後江戸幕府を開いた家康が慶長十二年(1607)将軍を退き、駿府に移り住むために天正期の駿府城を「天下普請」として拡張、修築しました。当時の駿府は江戸と並ぶ政治の中心地として重要な役割を果たしていました。 平成8年3月 静岡市
・巽櫓(駿府城公園)内堀沿い たつみやぐら
巽櫓は駿府城二の丸の南東に位置する木造矩折三層二重の建物です。この巽櫓は寛永十二年(1635)城下から出た火によって延焼焼失し、寛永十五年に新たに建設されたといわれています。巽とは十二支で表した方位で辰と巳の間、即ち南東の方角をいいます。また櫓とは、一、武器を納めておくため、一、四方を展望するために設けた高楼、の役割をしたものです。巽櫓の復元は、「駿府城内外覚書」や「駿府御城惣指図」の資料をもとにしており、3年の歳月をかけ、平成元年3月に完成しました。 静岡市
・東御門(駿府城公園)ひがしごもん
東御門は駿府城二ノ丸の東に位置する主要な出入口でした。この門は二ノ丸堀(中堀)に架かる東御門橋と高麗門、櫓門、南・西の多門櫓で構成される枡形門です。東御門の前が安藤帯刀タテワキの屋敷だったことから「帯刀前御門」また、台所奉行の松下淨慶にちなんで「淨慶御門」とも呼ばれ、主に重臣たちの出入口として利用されました。東御門は寛永十二年(1635)に天守閣、御殿、巽櫓等と共に焼失し、同十五年に再建されました。復元工事は、この寛永年間の再建時の姿をめざし、復元したものです。 平成八年三月 静岡市
・坤櫓(駿府城公園)内堀沿い ひつじさるやぐら
木造二層三階。家康築城時に武器庫として利用される。寛永12年(1635)の火災で焼失。2014年4月に復元工事完了し1階は公開される。2階は非公開。
・駿府城公園内:発掘された石垣、公園内地面下には戦国期の今川館跡遺跡
駿府城は古くは今川館があったと推定される。その後徳川家康により隠居城となり、一時は大名が治めたこともあるが、長くは代官の行政所となり一部を使用したようだ。使わない部分はかなり荒廃した箇所もあるようだ。江戸時代中期以降は狐が住んでいたほど荒れていたようだ。明治期に内堀を埋立て軍隊駐屯地になった。今は公園。発掘で徳川期の石垣や使用道具類、今川氏館跡等が出土している。しかも焼かれた物が出土している。武田氏により滅ぼされ今川館は焼失したと思われるが、そのとき焼かれた物かどうかは不明。
天守閣は家康が建造したが女中の不手際で失火焼失、再建されたがまた焼失。代官時代には天守閣はなかったようだ。またそれ以外の建物や施設も代官時代に使用が縮小していったようだ。
現在みられる駿府城外側の石垣は近代以降、幾たびも修復されているので全てが江戸時代のものというわけではない。ただ一部残存しているのも確かで、家康が築城する際には全国の大名を動員したので、石垣に各大名のしるしがつけられているものがある。また各時代により石垣の積み方に特徴が出ている。
*石垣の積み方についてはネットや図書で検索してください。
・家康お手植えの蜜柑ミカンの木、
・家康銅像、
・東海道中膝栗毛弥次喜多像(追手町)内堀沿い
・説明版:十返舎一九と「東海道中膝栗毛」: 「東海道中膝栗毛」の作者十返舎一九(1765~1831)は、ここ駿河の府中(静岡市)出身で江戸文学における戯作者の第一人者であり、日本最初の本格的な職業作家といえます。1765年駿府町奉行同心、重田与八郎の長男として両替町で生まれました。本名は重田貞一、幼名を市九といいます。1783年大阪へ行き、一時は近松余七の名で浄瑠璃作家としても活躍しましたが、その後士分を捨て1794年再び庶民文化華やかな江戸に戻って戯作に道に専念し、多くの黄表紙や洒落本などを書きました。
「東海道中膝栗毛」は1802年初編(初編は「浮世道中膝栗毛」のち改題)以降毎年一編ずつ8年にわたって書き続け、1809年全8編を完結しました。この膝栗毛は爆発的人気を呼び、休む間もなく「続膝栗毛」の執筆にとりかかり、1822年の最終編までに実に21年間に及ぶ長旅の物語として空前の大ロングセラーとなりました。
物語は江戸神田の八丁堀に住む府中生まれの弥次郎兵衛(左の像)と、元役者で江尻(現清水市)出身の喜多八(右の像)という無邪気でひょうきんな主人公二人が江戸を出発して東海道を西へ向かい伊勢を経て京都、大坂へと滑稽な旅を続ける道中記で、今でも弥次喜多道中といえば楽しい旅の代名詞となっています。
当地の名物として安倍川餅やとろろ汁も登場。また府中では夜は弥勒手前の安倍川町(二丁町といった)の遊郭へ出かけたり、鞠子(現丸子)では、とびこんだ茶屋の夫婦喧嘩に巻き込まれ、名物とろろ汁を食べるどころか早々に退散したといった話が語られています。
一九は1831年没、享年67歳。墓所は東陽院(現東京都中央区勝どき)にあります。ここ府中は江戸から44里24町45間(約175㎞)19番目の宿です。
2002年2月、静岡市
・甘夏みかんの木(追手町)内堀沿い
・わさび像「わさび漬発祥の地」(追手町)内堀沿い
・説明版:わさびは370年前わが国で初めて安倍川上流有東木で栽培された。わさび漬けは今から200余年前駿府のわさび商人によってはじめて考案され幾多の人に受け継がれて改良進歩した。特に明治以後交通機関の発達により長足の発展を遂げたのである。ここに明治百年を期し先覚者の偉業を偲び感謝の誠を捧げて、この碑を建つ。昭和43年5月23日、静岡県山葵漬工業協同組合
・このわさびの像はコンクリ製で芋虫に似ていて一種のゆるキャラっぽい。あるいはシュールというべきか。宇都宮市に餃子像があるのならば静岡市にはわさび像です。
・現代アート像:指人形(追手町)内堀沿い
指人形 The fingerdoll 制作:細谷泰玆 Yasuji Hosoya 1983年
・石碑:静岡学問所跡(追手町)内堀沿い
・説明版:静岡学問所は明治維新後駿府に移ってきた徳川家(府中藩)により、藩の人材育成を目的として駿府城四ツ足御門にあった元定番屋敷内(現静岡地方合同庁舎付近)に明治元(1868)年府中学問所として創設されました。学問所には翌2年駿府が静岡に改められたことにより静岡学問所となりましたが、明治5年8月学制の施行とともに閉鎖されました。この学問所には向学心に燃える者は身分を問わず入学が許可され向山黄村、津田真一郎(真道)、中村正直(敬宇)、外山捨八(正一)など当代一流の学者により国学、漢学とともにイギリス、フランス、オランダ、ドイツの洋学も教授されました。またアメリカ人教授E.W.クラークは専門の理化学の他哲学や法学なども教えました。廃校後洋学系の教授の多くは明治政府に登用され開成学校(現東京大学の母体)の教授など学界や官界で活躍しました。静岡学問所の歴史は短期間でしたが、日本の近代教育の先駆けをなし、明治初期の中等、高等教育の最高水準の学府でありました。 静岡市教育委員会、平成元年12月
・石碑:戸田茂睡生誕之地(追手町100)とだもすい
1629~1706年、江戸時代前期の歌学者。父は徳川忠長(徳川3代将軍家光の弟、駿府城主、改易され謹慎の後自害)の付け人で、駿府城内で生まれた。
・駿府城四足御門跡(追手町)よつあしごもん
・説明版:駿府城南辺の西寄りの箇所に設けられた出入口で、東側の大手御門オオテゴモンと並び、東海道筋から城へ入る重要な出入口の一つです。三の丸堀を土橋で渡って、左手へ直角に曲がり渡櫓門ワタリヤグラモンから城内へ入る構造になっていました。 静岡市教育委員会
・大手‣追手門(追手町)
・説明版:駿府城大手御門:駿府城内に入る正面出入り口です。三の丸堀を土橋で渡って、右手へ直角に曲がり渡櫓門ワタリヤグラモンから城内へ入る構造になっていました。歩道には渡櫓門の柱礎石の位置が記されています。 静岡市教育委員会
・石垣修復説明版(追手町)
・説明版:駿府公園二の丸堀(中堀)石垣災害復旧工事完了のお知らせ:平成21年8月11日駿河湾で発生した震度6弱の地震により、駿府公園二の丸堀(中堀)の石垣が崩落しました。平成22年1月6日工事着手、平成23年3月15日工事完了、石垣の構造を説明した「石垣モデル」が駿府公園内、富士見芝生広場に設けてありますのでぜひ一度ご覧ください。静岡市。
崩落前と崩落直後、復旧後の3つの写真が並置されているので、見た目では一目で分かるようになっている。なお石垣は見えない内部構造も重要なので石垣モデルを見てください。
・静岡県庁本館(追手町9)
登録有形文化財、
・静岡市役所本館ドーム(追手町5)
登録有形文化財、
・教導石(追手町)県庁市役所前バス停
・説明版:静岡市指定有形文化財(歴史資料) 教導石きょうどうせき、指定年月日:昭和59年7月17日、所在地:静岡市追手町、所有者:静岡市、「教導石」は、明治という新しい時代を迎え、「富や知識の有無、身分の垣根を越えて互いに助け合う社会を目指す」との趣旨に賛同をした各界各層の人たちの善意をもって明治19(1885)年7月に建立されました。正面の「教導石」の文字は、旧幕臣山岡鉄太郎(鉄舟)の筆になり、本市の明治時代の数少ない歴史遺産の一つとなっています。碑の正面上部には、静岡の里程元票(札の辻)から県内各地、及び東京の日本橋や京都三条大橋までの距離を刻んであります。教導石建立の趣旨に従って碑の右側面を「尋ル方」とし、住民の相談事や何か知りたいこと、また苦情等がある人はその内容を貼り付けておくと、物事をよく知っている人や心ある人が左側面の「教ル方」に答えを寄せる、というものでした。尋ね事などのほか、店の開業広告、発明品や演説会の広告から遺失物や迷子をさがす広告なども掲示してよいことになっていました。全体の高さ:207㎝、台石の幅:107㎝、本体:高さ:177㎝、正面幅:44㎝、側面幅:38㎝、静岡市‣静岡市教育委員会
・正面:「教導石、里程(?田谷、略を上下に書く)表、駿河國沼津宿拾五里拾町余、同吉原宿拾里拾九町余、 同大宮町拾壹里拾六町、同興津宿四里拾貮町余、同清水町三里六町余、同根古屋村貮里拾九町余、同藤枝宿五里拾町余、遠江國静波町拾里貮拾九兆余、同相良町拾貮里貮拾町余、同掛川宿拾貮里拾七町余、同森町村拾六里三町余、同横須賀町拾六里三拾町」
右:「尋ル方、静岡里程元票 各地距離、東京日本橋四拾六里拾町余、神奈川縣廰三拾九里廿六町余、山梨縣廰貮拾七里拾七町、伊豆相模國堺貮拾里壹町余、伊豆國下田町三拾五里拾五町、同熱海村貮拾三里四町余、同修善寺村拾壹里二拾町、同韮山町拾九里三町余、同三島宿拾六里三拾町余」
*撮影写真不鮮明で判読困難、やり直す気がないので間違ったままですが掲載します。
左:「教ル方、同見附宿拾六里貮拾七町、同中泉村拾七里九町余、同掛塚村拾九里拾壹町、同濱松宿貮拾里拾七町余、同二俣村廿壹里廿七町余、同気賀村廿四里拾八町余、同新居宿廿四里二拾町余、遠江三河國堺廿六里(十十十)五町余、愛知縣廰四拾八里拾七町余、西京三条大橋八拾四里拾四町」
・街道研究としては近代の石道標の価値がある。
・札の辻(呉服町1丁目と2丁目の境)伊勢丹前
静岡市街の中心地は呉服町で、旧東海道も呉服町の札の辻を通過し本通り乃至は新通りに向かい直進するか曲がる交差点であり、高札等のお触書も建てられた府中宿中心の場所である。
・国・登・静岡銀行本店(旧三十五銀行)(呉服町1-10 )
国登録有形文化財、第22-0010号、この建造物は貴重な国民的財産です、文化庁。
景観重要建造物、静岡銀行本店(旧静岡三十五銀行本店) 静岡市葵区呉服町、指定第3号、平成23年9月30日、静岡市。
・静岡天満宮(中町1‐3)
・石鳥居:昭和三十一年、・神社名碑:昭和五十二年、・手洗石、・牛像、・石碑:川中天神伝説之地、黒い直径15~20㎝溶岩多数(富士山溶岩か?)、
・稲荷社祠:、・説明版:静岡天満宮末社、静銀稲荷社、御由緒:御祭神:稲荷大神、昭和20年終戦後、進駐軍が静岡に入り、大企業に立入調査を行った折、(株)静岡銀行の守護神として、社内に祀っておりました稲荷社を、直ちに撤去廃棄すべしと命ぜられ、銀行側は検討の結果、御神体を隣接する静岡天満宮(当時は天満天神社)に保管祭祀を依頼し、神社側もこれに応じて静岡天満宮末社「静銀稲荷社」として現在の場所に鎮座奉斎したのです。以来初午祭には静銀本店営業部の責任者が参拝する習わしとなったのです。御神祠:この御神祠は明治初年から昭和3年まで静岡天満宮(当時は天満天神社)の御本殿として鎮座しておりましたが、昭和4年新たに御本殿を造営するにあたり市内宮本町山下家に譲渡し同家にて同家の守護神として奉斎されていました。しかし同家の事情により、この神祠を処分することになりましたので、昭和54年2月同家より静岡天満宮の地に還御しました。これと同時に従来静岡天満宮の本殿に合祀しておりました、静銀稲荷社の御神体をこの神祠に奉斎して、今日に及んでいるのです。(昭和4年竣工の御本殿は、昭和20年6月戦災にて焼失)
・景行社祠:、・説明版:静岡天満宮攝社景行社御由緒:昌泰4年(901)1月25日菅原道真公が、無き罪により大宰府に流された。翌々日公の子息達も夫々別々の地に流され、次男景行も駿河権介に左降され、この駿河の地に流され、ここ駿河の国府に居住した。この国府は現在の静岡天満宮を中心とした一帯の地域である。その後景行の記録が定かでなく、今日に至ったので、道真公を祀る静岡天満宮を崇敬する有志が景行を祀ろうということになった。その折り、大阪市天王寺区の一行者(鎌原氏)や清水区三保の行者(日蓮宗)に「景行を祀れ」との道真公の託宣があったとのことで、平成元年春に景行社を創祀したのである。(平成20年6月25日再記)
・銅鐸:説明版:県指定文化財、奈良県北葛城郡上牧村観音山から出土したもので、銅製で耳がなくたすき形の模様がある。高さ19.7㎝、底の長径15.1㎝、短径11.5㎝、保管:登呂考古館、明治百年紀念、静岡県文化財保存協会、
・尼ヶ崎稲荷神社(中町37‐1)
・石柵、・手洗石:昭和六十年、・石燈籠(2):平成十九年、・稲荷(2)、
・説明版:尼ヶ崎稲荷神社の由来:元尼崎又右衛門という富商邸内にありました。家康に召されて駿府に移り、はじめ本通り五丁目に宅地を賜りそこを十軒町と言ったが、慶長14年四ツ足御門町(現中町)に替地を賜ったと言われています。尚金座町稲荷神社(後藤稲荷神社)がこのすぐ裏手にあり慶長の頃、駿府上魚町(現金座町日銀)で小判を鋳造した後藤庄三郎光次邸があった所でもあります。又銀座町は現在の東京銀座にお移されております。
・説明版:四ツ足御門と中町の由来:四ツ足御門町の町名は非常に地位の高い町名でありました。今の中町の所から駿府城に入ったあたりに駿府城の四ツ足御門がありましたので、この町名となったのです。さらにこれを遡れば、その昔、大化の改新に伴い今の長谷町付近に国府が置かれた頃、この中町付近に国庁の四ツ足御門があったからという説があります。その説によれば四ツ足の名は千数百年の歴史を飾る由緒ある町名であります。現在、中町という町名になったのは、四ツ足といえば獣類に通じ快い町名とは聞こえないということで、大正4年11月10日「静岡市の中心」ということで中町と改称されたのであります。 平成23年3月15日 春季大祭
・上魚町碑(金座町1)かみうおちょう
・説明版:上魚町は徳川家康の大御所時代には、中央の通りを挟んで南側を後藤庄三郎光次が拝領し、光次が江戸に移るまではここを金座として「駿河小判」と呼ばれる金貨を鋳造していました。また北側は駿府城築城の作事方中井正清が拝領していました。「駿国雑誌」によれば、家康の在城の時、下魚町から魚商人を移住させたとされ、町の南側には魚問屋、北側には青物問屋が軒を連ね、さながら「流通センター」のような役割を果たしていました。元禄5(1692)年の「駿府町数・家数・人数覚帳」によると、当時の上魚町は、南側が家数38軒、人数203人、北側が家数4軒、人数70人でした。上魚町は昭和3年に金座町となりましたが、それ以後も「かみんだな(上の店)」と呼ばれていました。
・金座稲荷神社(金座町49)
・手洗石:昭和六十二年、・常夜灯:昭和六十二年、・金座碑:昭和三十年:
日本銀行静岡支店からこの金座神社界隈はかつての金座で小判等を鋳造していた。
・説明版:お金の神様、金座稲荷神社御由緒、創建:慶長11(1606)年、御祭神:稲荷大神、秋葉大神、当神社は後藤庄三郎光次が徳川家康公の命を奉じ駿府、上魚町(現在の金座町)に金座を開設し小判の鋳造を始めるに際し金座の守護神として御二柱を祀ったのが起源であります。以来400年、上魚町の産土神として祀られ、その霊験洵にあらたかなる為、「お金の神、金運の神様」として広く崇敬を集め、通称「後藤稲荷」として親しまれてまいりました。その後幾多の変遷を経て、昭和62年5月23日、当所へ遷座致しました。尚金座町という町名は、歴史的事実にもとづいた町名としては全国で唯一のものであります。昭和63年11月吉日、金座稲荷神社。
・戸塚歯科医院跡(本通1丁目3‐2)
かつて戸塚氏は郷土史家として静岡近辺の野仏や民間習俗の研究で知られていた。氏の本は私にとっても貴重な資料である。
・奥津宮神社(車町26)
・新:石灯篭、・庚申供養塔:文政三庚辰年、・石鳥居:昭和二十六年、・石柵:平成四年、・欠:庚申:安政七、・欠:庚申供養塔:文政五壬午年、・観音堂、・欠:奉寄進石燈:寛文(?政)九年
・石碑:説明:奥津彦神社、静岡市葵区車町26鎮座、祭神:火産霊神、奥津彦神、奥津媛神。由緒:神社の創立年月不明。社伝に駿河国の守護今川範国の子今川了俊深くこの神々を崇敬して邸内に奉祀してあったが、その子今川仲秋に政治の要諦を教えると共に「よくこの神を信仰せよ」と御神体を授ける。仲秋はよく父の教えを守り身を慎み祭祀を怠けたらず善政を行いやがて立身して遠江守護、尾張守護等を歴任した。仲秋は一の世を去るに臨みてその家臣に命じて御神体をこの地に祀らしめ三宝荒神社と称したと伝えられている。三宝荒神社は明治元年の神仏分離令に依り奥津彦神社と改称された。又三宝荒神社の別当用触山守源寺は昔から駿府の会所に使用され町々へのお触れ通達はここから出したので用触山の名がつけられた。御神徳:火の神様である炊事キッチンの守り神である。火の神信仰は火難を免れ病難を防ぐ。祭日:2月28日、9月28日、12月28日
・願勝寺(車町50)
・新:双体道祖神
・金剛院(八千代町17)
・石:家:道祖神
・秋葉山常夜灯(馬場町)
中町交差点に市・有民・中町秋葉山常夜灯、上部は木造で彫りが見事、下部は石造、・赤鳥居:コンクリート製、
・山田長政像(宮ケ崎町100)
馬場町は伝山田長政屋敷跡といわれる。
・二瀬川神社(馬場町65)
・石灯籠(2基):明治四年、・手洗石:古そうで年号等もありそうだが見えない位置に安置されていて判読不能。
・説明版:二瀬川神社、静岡市葵区馬場町65番地、祭神名:保食神うけもちの神、多紀理比賣神たぎりひめの神、例祭日:9月15日、社殿工作物:本殿3.3平方m、拝殿6.6平方m、境内地:132平方m、氏子戸数297戸、神職名:宮司:鈴木巌夫、禰宜:鈴木哲夫、責任役員名:小川保、鍋田治夫、由緒:創建年月不詳、昭和20年6月の戦災により焼失、昭和25年9月都市計画区画整理により現在地に移転し、以前120坪の地が40坪に削減され、その境内地に町内会館を建設したため実質は更に三分の一となって、極めて不遇な道を経過した神社といえる。静岡県神社庁神社等級規定13等級社である。年間スケジュール:祭旦祭:1月1日、初午祭:2月2の午の日(二の午祭)、夏祭:5月15日、例祭:9月15日、神輿清祓祭:例祭前後の土曜又は日曜日、
・報土寺(宮ケ崎町110)
・石塔:新:南無阿弥陀仏、・新:六地蔵(杉村隆風)、・新:無縁萬霊之塔、
・石碑:新:養国寺慰霊之碑 平成十九年、説明版:報土寺の末寺で安翁山丹龍院養国寺という浄土宗の寺が本通7丁目74番地にありました。開基は寛正6年(1466)で開山は松漣社貞誉王山上人還阿和尚であります。その後は報土寺の末寺となり歴代の当山住職が兼務住職となり、本通りの人たちと供に養国寺を護持してきましたが、昭和20年6月19日の静岡大空襲により堂宇すべて廃墟と期しました。その後、報土寺が戦後復興を進めていく中、昭和27年、養国寺は本寺である報土寺に合併されることとなりました。開基よりおよそ550年、養国寺の歴代住職をはじめ信徒の方々、本通り7丁目の方々、その他養国寺の護持の為にご協力を頂いた多くの善男善女の方々に心より御礼申し上げ、ここに慰霊の碑を建立致します。
平成19年8月、報土寺住職 泰誉博隆
・石碑:新:南無阿弥陀仏 大正十余年、説明版:経に曰く至心信楽即得往生~~~以下略~~~
~~~大正十余年
・新:冷泉為和の歌碑:冷泉為和の歌碑についての由来:報土寺の本堂前に戦国時代宮廷歌壇の第一人者冷泉為和の歌碑が建てられた。為和は歌聖藤原定家の直系冷泉家第7代の当主である。当時応仁の乱(1467~77)後の荒廃した京都を逃れて駿府に流寓した公家殿上人はかなりの数にのぼっていた。権大納言冷泉為和もそうした中の一人であった。その為和が駿府滞在中我が報土寺において歌会を催すこと9回、11首の和歌を詠んでいる。それは、「今川為和集」の中に歴然としるされている。報土寺境内にある歌碑に彫られた和歌はその中の天文12年(1543)5月2日の歌会の折りのもので、
松契還年
代々かけて 軒のかわらに むす苔も 緑あらそふ 松の気だかさ (為和)
この歌の題の「還年」は長寿をいうので軒の瓦が苔むすといえば1年や2年のことではない。何代という長い年月を栄え続けてきた証で、それと競うように枝を伸ばした松の緑の気品のある美しさを讃えて長寿を祝う歌とした手腕はさすがである。(文責 長倉智恵雄)
・一加番稲荷神社(鷹匠1丁目8)
・石鳥居:昭和三十七年五月、・石稲荷2:昭和五十一年、石柵:昭和五十八年、・手洗石:昭和五十六年、・コンクリ石塔:昭和壬子二月、・石碑:神社名:新、
・説明版:当神社の御祭神は、保食大神ウケモモノオオカミ、御別名を豊宇気比売神トヨウケヒメノカミ、また食稲霊神ウカノタマノカミと申し上げ、稲、五穀の御霊神と尊まれ、衣食住の神、商売繁盛、厄除開運、無病息災、延命長寿の守護神として広く信仰されている神である。
当社鎮座の由来は寛永八年(1631)駿府城主駿河大納言忠長卿(二代将軍秀忠公の第3子)が三代将軍家光(兄)の勘気を受けて甲斐に蟄居の後は、幕府は駿河を直轄領とし、城主を置かず重臣の内から駿府城代を任命して庶政を綜理せしめ、城代を輔けて城外の守衛に当たらせるために在番一年の役として加番を勤番させることとし、紺屋町に一加番屋敷を設けた。(これを紺屋町加番或は町口加番屋敷という)初代一加番に信州飯田城主五万五千石脇坂淡路守安元が寛永九年(1632)12月に仰せ付けられ着任した。この加番開設にあたり3200余坪の屋敷内の浄地を選び社殿を建て寛永十年(1633)山城国伏見稲荷神社の分霊を勧請し、駿府一加番の守護神として鎮斎したのが当神社の創祀と伝えられている。慶安四年(1651)由井正雪の乱があり、一加番は府城に近い横内御門前(現在の鷹匠一丁目)に移され、これに伴い当稲荷神社も新屋敷内に遷宮された。斯くて創祀以来文久元年(1861)に至る迄約230年間歴代の加番は折々に鳥居、燈籠等を献納し、年々の祭祀を厳修して、崇敬の誠をつくしてきた。
明治維新に至り加番屋敷廃邸後は、鷹匠町一丁目の産土神として、明治11年政府より存置が許可されて、一般市民の崇敬の神社となった。昭和20年6月戦災により社殿、工作物悉く焼失した。戦後氏子の奉賛により復興し、地域の区画も整理されて面目を一新し、当神社の信仰は市の内外に広まるに至った。
祭典:例祭5月5日、歳旦祭:1月1日、節分会:2月3日、秋祭:11月25日。
昭和63年5月 奉納:松浦元男
・二加番稲荷神社(西草深町4)
もとは駿府城の警護用番所でもっと敷地も広く馬場等もあったが、今はそこの祠があった部分のみに神社がある。周辺は住宅地でキリスト教会やNHKビルがある。そこもかつては敷地内だったはず。
・村本喜代作先生明徳碑文:翁は西草深町520世帯の町内会長として20年にわたる長き間、社会公共のため奉仕せられた功績は甚大である。当二加番稲荷神社は戦災により灰燼化し瓦礫の中に樹木を植え社殿を再建し自ら責任役員となり神社を中心に民福をはかり明朗な社会環境造成に盡くす。又政教社雨声会を起し政治経済文学史話等の講演を行うこと実に250余回、其の間先生の薫陶を受けた方の中には名政治家も現はる。ここに村本喜代作先生を後世に伝えるため西草深町内会神社総代会雨声会の有志相謀り明徳碑を建立する。昭和55年3月、~以下略~
・手洗石:文化(五)九年(戌辰)壬申歳、・神社名石碑:昭和四十三年、・石灯籠:天保十五甲辰、・石鳥居:昭和四十六年、・石柵:昭和四十八年、・?石灯籠の一部:元文四巳未、・?石塔:崩れて成れの果て、
・説明版:二加番稲荷神社:祭神三社:豊受毘賣命トヨウケヒメノミコト穀物の神 商業あきないの神、猿田彦命サルタヒコノミコトお祓いの神、天鈿女命アメノウヅメノミコト神楽の創始芸能の神、由緒:駿府城は寛永8年以後は城主を置かず「城代」によって統治され、城外守衛のため「加番」という役が置かれた。当所は二加番屋敷の跡で、その守護神として稲荷神社が祀られた。当社を鷹森稲荷と称されたのは、この附近を流れた安倍川のほとりに鷹が集った森があった故という。一加番(鷹匠1丁目)三加番にも夫々稲荷神社が奉祭されている。明治維新後は西草深町の産土神として遠近より崇敬されて今日に至った。加番屋敷には馬場、的場、火の見櫓などがあり、その略図を裏面に記した。歳旦祭 1月1日 春祭 初午 春分の日 秋祭 秋分の日
・裏面:二加番屋敷略図:外堀に面した現在はNHK静岡放送局から付近一帯の住宅地も含む広大な屋敷であることが分かる。外堀側77間(138.6m)、奥行き42間(75.6m)、面積10478.16平方m、3175坪。
・三加番稲荷神社(東草深町11)
・石碑:神社名:昭和三十八年九月、・石柵:平成九年、・石鳥居:安政六巳未二月初午、旗指石:奉献安藤杢(木の下は工ではなく立つ)之助源有(有るの下は月ではなく且つ)剛、・手洗石:安政(正の下に久)□□□二月、・手洗石:?、・石塔:寄進~~~、・石(埋)、・礎石2?、・石燈籠2:、・倒れた石燈籠:稲荷大明神 廣舟(止の下は舟) 文化三丙寅三月初午、
・説明版:祭神:保食大神ウケモチノオオカミ、祭日:春祭:春分の日、秋祭:秋分の日、由緒:寛永八年(1631)に駿府城主徳川忠長が将軍の勘気に触れ蟄居を命ぜられての後は駿河国は幕府の直轄領となり、駿府城には城主を置かず城代定番が勤める番城となり定番の下に小大名または旗本の中から加番を勤番せしめ城外の警備に当たらしめた。慶安四年(1651)に由井正雪の反乱があっての後は、従来の一、二加番に加えて三加番が増設され、東草深にその屋敷を設けると共に邸内の守護神として、この三加番稲荷神社を鎮祭した。代々の加番は深く崇敬して毎年二月初午に盛大な祭典を行い、また石燈籠鳥居等も数多く奉納された。
明治維新に至り加番屋敷廃邸後は、東草深三ヶ町の鎮守となり、明治11年3月政府公認の神社として存置を許可された。後に水落町二丁目も氏子に加わり一般町家、遠近の人々から深く信仰されるに至った。
御神徳:保食大神は伊勢の外宮に奉祀する豊受大神と御同神で人間生活に一番必要な食糧と衣料をお恵み下さる神である。古歌に「朝夕の箸とるごとに保食の神の恵みを思え世の人とあう」また福徳円満の神、商売繁盛の神として最も信仰される神である。
・草深界隈の古い洋館類、キリスト教会等(西草深町、東草深町)
‘13現在、(西草深町15番)西草深眼科(かつての中島医院)が洋館の趣をとどめている。他にもあったのだがだいぶ減少した。教会も現代建築のビルに改築され古式ゆかしさは消失した。
静岡英和女学院(西草深町8)はねむの木学園創設者:宮城まり子出身校である。
クラシック音楽愛好家には一時期全国的に知られていたのが青島ホール(西草深町16‐3) である。
・西草深公園(西草深町27)
・説明版:西草深と徳川慶喜公:草深町は駿府九十六ヶ町の一つで、現在の西草深公園の東側に、二筋の通りに面して一画を占めていました。明治6年(1873)に一帯の武家屋敷を含めて西草深町となり、昭和44年に御器屋町ゴキヤチョウなどを併せて現在に至っています。駿府城に近い草深町の近辺には慶安4年(1651)に駿府城の警護や城下の治安維持にあたった加番の一つ二加番や与力、同心などの武家屋敷が配置されていました。草深地区には江戸時代初期に徳川家康公に仕えた儒者、林羅山の屋敷があり、また明治維新期には静岡学問所頭ガクモンジョガシラであった向山黄村ムコウヤマコウソンをはじめとする学問所の著名な学者が多数居住していました。西草深公園には浅間神社の社家シャケの屋敷があり、明治2年(1869)6月に静岡藩主となった徳川家達イエサト公が社家新宮兵部シングウヒョウブの屋敷に移り住みました。
徳川幕府第15代将軍徳川慶喜公は、大政奉還の後、慶應4年(1868)2月から謹慎生活に入り、同年7月に駿府の宝台院に移り住みました。宝台院での謹慎生活が解かれた慶喜公は、明治2年(1869)に紺屋町コウヤマチの元駿府代官屋敷に移り、更に明治21年には西草深町に屋敷を構えましたが、東京に戻る明治30年まで政治の世界を離れ、一市民として過ごしました。静岡での慶喜公は、狩りや写真を好み、油絵をたしなみ、明治10年代から自転車を購入して市内を乗り回って市民の話題になるなど、多種多様な趣味と共に西洋的な生活を謳歌した当時の最先端を行く文化人でもありました。中でも静岡で修得した写真撮影の技術から生まれた作品は、各地の風景、生活ぶりを伝える貴重な歴史資料ともなっています。慶喜公が、東京に戻った後の徳川邸は葵ホテルとなり、更に明治37年には日露戦争の捕虜収容所の一つとして使われましたが、同38年に施設内から出火し焼失してしまいました。
・説明版:万葉歌碑:焼津邊 吾去鹿歯 駿河奈流 阿倍乃市道尓 相之兒等羽裳
春日蔵首老 焼き津辺にわが行きしかば駿河なる安倍の市道に逢いし児らはも
万葉集は日本最古の歌集で奈良時代
~~~不明、
昭和36年
*写真不鮮明で判読困難
以下は、インターネット検索「万葉集巻3、れんだいこ」より引用
「万葉集、巻3、No.284、春日蔵首老かすがのくらびとおゆ、作歌
焼き津辺=静岡県焼津市辺り、阿倍=静岡市安倍、安倍川の安倍、市道=イチジ、市場が開かれていた道、焼津方面に赴いた際、安倍の市で出会った娘たちを思い出して懐かしがっている歌。これを男女が市に集まって乱舞した、いわゆる歌垣の際の思い出ととってもよかろうが、そうとらなくても単純に美しく楽しげだった娘らを思い出しての歌として一向に差支えない。」
私見:この短歌から静岡市(安倍の市)がすでに奈良時代に賑わっていたことが分かる。
・石鳥居
浅間神社前、麻機街道と長谷通りの分岐点
・浅間神社(静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町102-1)
・交番裏の賤機山を上るとすぐ賤機山古墳がある。もう少し上に麓山神社がある。さらに上に一本松・5世紀の古墳がある。さらに上ると浅間山山頂(△140m)で舗装路はなくなり、あとは山道となる。その先に空堀(地獄谷)があり、さらに先に賤機山城址(△173m)と光明地蔵となる。
浅間神社境内遺跡跡。国・重文・浅間神社社殿。石造物でも石灯籠等、市内最古級のものが多い。
国・登・遍界山不去来庵本堂。
・西蔵寺(片羽町79)
・三界萬霊等、・庚申塔、・地蔵、・新:観音、・手洗い石、・新:灯篭、
・元三大師延命地蔵(安倍町23)
・地蔵:
・瑞光寺(安西1丁目100‐1)
・石塔:文正夂(政)十三年庚寅八月、・?観音:元文五庚申、・板碑:山梨易司翁彰功碑 大正八年、・板碑:佐久間翁叟先生碑、・新:有縁無縁三界萬霊、・お花塚 石州流生花家元~~昭和十三年、・如来(4):片足膝立ち座位、・地蔵(4)、・地蔵、・同一様式の観音約80基(三十三所観音3つ分で不足分は消失か、いくつかには二十六番等の番号が読み取れる)、
*文政の政を正夂と刻字してあるのか?
・然正院(安西1丁目103)
・新:六地蔵、・新:水子供養塔(2)、
・末広中(末広町)
かつて高等女学校があった。
・神明宮(神明町54)
・木鳥居、・常夜灯(2):昭和十五年、・石柵:昭和十五年、・狛犬(2):昭和十五年、・神社名碑:平成二年、